『週刊朝日』休刊号で追憶にふける ― 2023年06月01日
『週刊朝日』の休刊号('23.6.9)が出た。101年続いた週刊誌の終焉である。発行部数150万部を超えたこともあったが、最近は8万部を切っていたそうだ(実売部数4万5千ともいう)。
私は60年以上『週刊朝日』に接してきた。親が定期購読していたので、子供の頃から身近な週刊誌だった。社会人になり、実家を離れてしばらくは断続的に読んでいた。いつ頃からか自ら定期購読するようになった。以前は新聞販売店が配達してくれたが、いつしか郵送になり、現在まで続いている。
いまや稀少な残存定期購読者のひとりだが、熱心な読者とは言えない。最近の『週刊朝日』はあまり面白くなく、読むページが少ない。購読を止めようと思いつつずるずると引き延ばしているうちに休刊になってしまった。
いざ休刊となると、やはり感慨深い。記憶の底をさぐると過去のいろいろな記事が浮かんでくる。
休刊号には『「ジャンプしてください!」と著名人に無茶振り』と題した過去の企画記事の紹介がある。60年前の1963年、私が中学2年の頃の記事だ。懐かしい。うさぎ年にちなんだ「ジャンプ'63」という企画で、多くの著名人がジャンプした写真を並べていた。休刊号に載っている岡潔のジャンプ写真もよく憶えている。本田宗一郎はバイクでジャンプしていて、ズルイと感じたのを思い出した。
いまも『週刊朝日』の手柄だと思うのは、スプーン曲げのトリックをカメラで暴いた記事だ。超能力を否定する痛快な内容だった。調べてみると1974年5月、私が社会人2年目の頃の記事だ。
連載小説もいくつか読んだ。記憶に残る最も古い連載小説は城山三郎の『イチかバチか』だ。単行本刊行が1962年だから連載は私が中学1年の頃だと思う。梶山季之の『夜の配当』 は中学2年の頃だ。山崎豊子の『仮装集団』は高校生の頃の連載、その後が松本清張の『黒の様式』だった。
『週刊朝日』の連載小説にはもっと有名な作品が多くある(『飢餓海峡』『さぶ』『世に棲む日々』『官僚たちの夏』など)。だが、なぜか私が連載で読んだ記憶が鮮明なのは比較的マイナーな上記4作なのである。
マイナーと言えば、やなせたかしの連載マンガ『ボウ氏』も懐かしい。これは、切り抜きをいまも保存している。「百万円懸賞連載マンガ」の入選作だからマイナーと言うのは不適切かもしれないが、その後のやなせ氏の活躍から見れば注目度は低いと思う。
私は60年以上『週刊朝日』に接してきた。親が定期購読していたので、子供の頃から身近な週刊誌だった。社会人になり、実家を離れてしばらくは断続的に読んでいた。いつ頃からか自ら定期購読するようになった。以前は新聞販売店が配達してくれたが、いつしか郵送になり、現在まで続いている。
いまや稀少な残存定期購読者のひとりだが、熱心な読者とは言えない。最近の『週刊朝日』はあまり面白くなく、読むページが少ない。購読を止めようと思いつつずるずると引き延ばしているうちに休刊になってしまった。
いざ休刊となると、やはり感慨深い。記憶の底をさぐると過去のいろいろな記事が浮かんでくる。
休刊号には『「ジャンプしてください!」と著名人に無茶振り』と題した過去の企画記事の紹介がある。60年前の1963年、私が中学2年の頃の記事だ。懐かしい。うさぎ年にちなんだ「ジャンプ'63」という企画で、多くの著名人がジャンプした写真を並べていた。休刊号に載っている岡潔のジャンプ写真もよく憶えている。本田宗一郎はバイクでジャンプしていて、ズルイと感じたのを思い出した。
いまも『週刊朝日』の手柄だと思うのは、スプーン曲げのトリックをカメラで暴いた記事だ。超能力を否定する痛快な内容だった。調べてみると1974年5月、私が社会人2年目の頃の記事だ。
連載小説もいくつか読んだ。記憶に残る最も古い連載小説は城山三郎の『イチかバチか』だ。単行本刊行が1962年だから連載は私が中学1年の頃だと思う。梶山季之の『夜の配当』 は中学2年の頃だ。山崎豊子の『仮装集団』は高校生の頃の連載、その後が松本清張の『黒の様式』だった。
『週刊朝日』の連載小説にはもっと有名な作品が多くある(『飢餓海峡』『さぶ』『世に棲む日々』『官僚たちの夏』など)。だが、なぜか私が連載で読んだ記憶が鮮明なのは比較的マイナーな上記4作なのである。
マイナーと言えば、やなせたかしの連載マンガ『ボウ氏』も懐かしい。これは、切り抜きをいまも保存している。「百万円懸賞連載マンガ」の入選作だからマイナーと言うのは不適切かもしれないが、その後のやなせ氏の活躍から見れば注目度は低いと思う。
突然、世界文学全集の『レベッカ』を読んだ ― 2023年06月03日
いずれ読みたい世界文学や、いつの日かの再読を楽しみにしている小説は少なくない。それらをさしおいて突然、古い世界文学全集所収の『レベッカ』を読んた。
『レベッカ』(デュ・モーリア/大久保康雄訳/河出書房新社/1960.7)
河出書房の「世界文学全集 グリーン版」は私が子供の頃から家にあった。実家を処分するときに引き取ったので、わが書架の奥に眠っている。
本書を読んだきっかけは、日経新聞夕刊(2023.5.24)に載った松浦寿輝氏のコラムである。「懐かしい本」と題して、中学2年のときに読んだ『レベッカ』を挙げている。「上下段にびっしり活字が組まれた」全集本は、「大人の小説」初体験だったそうだ。松浦氏は「幸福な出会いではあった。そのとき教えてもらった小説の物語というものの悦楽が、以後のわたしの人生を決定することになったからである」と語っている。
私は中学生のとき、世界文学全集の『大地(上)(下)』(パール・バック)で、松浦氏に似た「大人の小説」初体験をした。だが『レベッカ』は関心外で、これまで読もうと思ったことがなかった。
松浦氏のコラムを読んで、中学生の頃から背表紙だけは眺めていた『レベッカ』が急に気がかりになった。74歳の高齢者が中学生のような読書体験をできるとは思わないが、この小説を読みたくなった。
私の事前のイメージは、女性作家によるゴシック・ロマンらしい、ヒチコックが映画化したのだから面白そうだ、という程度だった。それ以上の予備知識はなっかた。
2段組470ページをほぼ一日で一気に読んだ。ホラー、ミステリー、ラブロマンスの要素がまざった面白い小説である。若い女性の一人称叙述は事実と想像と妄想が混在していて少々不気味でもある。中学生のときに読めば、より大きな感慨を抱いたと思う。
よくできた物語だが、レベッカ(小説上では故人)をはじめ登場人物たちの造形がいまひとつピンと来ない。人物像の陰影をもっと魅力的に表現できないかと思った。
この小説の最大の魅力はマンダレイという舞台設定である。海に面した森の中の城のような大邸宅は大時代的だ。多くの使用人を抱える領主の後妻になった若い娘というお伽噺のような状況を、20世紀の物語として面白く書き込んでいる。
作者は1907年生まれ、私から見れば祖母の世代で、ギリギリ同時代作家に近い。だが、19世紀の文学を読んでいる気分になる。世界文学全集に収録されていることと相まって古風な魅力を湛えた小説だと感じた。
『レベッカ』(デュ・モーリア/大久保康雄訳/河出書房新社/1960.7)
河出書房の「世界文学全集 グリーン版」は私が子供の頃から家にあった。実家を処分するときに引き取ったので、わが書架の奥に眠っている。
本書を読んだきっかけは、日経新聞夕刊(2023.5.24)に載った松浦寿輝氏のコラムである。「懐かしい本」と題して、中学2年のときに読んだ『レベッカ』を挙げている。「上下段にびっしり活字が組まれた」全集本は、「大人の小説」初体験だったそうだ。松浦氏は「幸福な出会いではあった。そのとき教えてもらった小説の物語というものの悦楽が、以後のわたしの人生を決定することになったからである」と語っている。
私は中学生のとき、世界文学全集の『大地(上)(下)』(パール・バック)で、松浦氏に似た「大人の小説」初体験をした。だが『レベッカ』は関心外で、これまで読もうと思ったことがなかった。
松浦氏のコラムを読んで、中学生の頃から背表紙だけは眺めていた『レベッカ』が急に気がかりになった。74歳の高齢者が中学生のような読書体験をできるとは思わないが、この小説を読みたくなった。
私の事前のイメージは、女性作家によるゴシック・ロマンらしい、ヒチコックが映画化したのだから面白そうだ、という程度だった。それ以上の予備知識はなっかた。
2段組470ページをほぼ一日で一気に読んだ。ホラー、ミステリー、ラブロマンスの要素がまざった面白い小説である。若い女性の一人称叙述は事実と想像と妄想が混在していて少々不気味でもある。中学生のときに読めば、より大きな感慨を抱いたと思う。
よくできた物語だが、レベッカ(小説上では故人)をはじめ登場人物たちの造形がいまひとつピンと来ない。人物像の陰影をもっと魅力的に表現できないかと思った。
この小説の最大の魅力はマンダレイという舞台設定である。海に面した森の中の城のような大邸宅は大時代的だ。多くの使用人を抱える領主の後妻になった若い娘というお伽噺のような状況を、20世紀の物語として面白く書き込んでいる。
作者は1907年生まれ、私から見れば祖母の世代で、ギリギリ同時代作家に近い。だが、19世紀の文学を読んでいる気分になる。世界文学全集に収録されていることと相まって古風な魅力を湛えた小説だと感じた。
視点転換で新鮮な景色を見せてくれる『ペルシア帝国』 ― 2023年06月05日
2年前の刊行時に購入し、そのまま積んでいた新書をやっと読んだ。
『ペルシア帝国』(青木健/講談社現代新書)
青木氏の著書を読むのは『マニ教』に続いて2冊目である。随所に著者のツッコミや感慨吐露コメントを挿入した語り口は魅力的だ。
だが、私にとって本書はさほど読みやすくはなかった。概説書とは言え、かなり細かい事柄に踏み込んでいる。私の知らない固有名詞が頻出する。私にはややレベルの高い概説書である。巻末の「補論 研究ガイド」などは、研究者の卵を対象にしているように見える。
本書のいう「ペルシア帝国」とはハカーマニシュ朝(アケメネス朝)とサーサーン朝を指す。この二つの王朝に絞った概説である。
本書は固有名詞を原音(だと思う)で表記している。私たちが慣れているギリシア語表記(だと思う)とはかなり違う。いくつか例示してみる。カッコ内がギリシア語だ。
ハカーマニシュ朝(アケメネス朝)
アルシャク朝(アルケサス朝)
クールシュ2世(キュロス2世)
カンブージヤ(カンビュセス)
クシャヤールシャン(クセルクセス)
ダーラヤワシュ(ダレイオス)
テースィフォーン(クテシフォン)
・・・・・・
研究者の世界では原音表記が原則なのだろう。西欧中心の見方を変えるのには賛同できる。だが、歴史書で常に固有名詞に悩まされている身には、やっと馴染んだ固有名詞が別表記になっていると混乱する。頭の中でいちいち変換しながら読み進めるのは難儀だ。とは言え、本書を読了する頃には少しだけ原音表記に慣れてきた。
原音表記はペルシア帝国に関する固有名詞だけで、ハカーマニシュ朝を滅ぼしたあの大王は「アレクサンダー3世」と表記している。アレクサンドロスでもイスカンダルでもないのが面白い。
本書が扱うハカーマニシュ朝とサーサーン朝は、高校世界史の教科書では4ページ足らず、それをじっくり1冊で解説している。私には未知の事柄ばかりで、驚くべき内容も随所にある(皇帝の親族大虐殺、マズダー教とゾロアスター教の違いなどなど)。
ハカーマニシュ朝はアレクサンダーに滅ぼされ、サーサーン朝はアラブ(イスラム)に滅ぼされたと記憶していた。しかし、本書によれば事情は単純ではない。
ハカーマニシュ朝はアレクサンダーに侵攻された頃にはすでにガタガタ、ダーラヤワシュ3世(ダレイオス3世)自身がはなはだ出自のあやしい人物だったそうだ。サーサーン朝もアラブが来る前にすでに死に体だったらしい。初めて知った。
本書によってあらためて認識したのは、視点が変われば景色が変わるということだ。あたりまえかもしれない。だが、視点を変えるのはさほど容易ではない。
よく考えると、私の頭の中でのペルシア帝国のイメージの大部分はギリシア・ローマ史、ビザンツ史、イスラム史のなかで形成されてきたと思う。
ハカーマニシュ朝といえばギリシアとの戦争とアレクサンダーの征服が思い浮かぶ。サーサーン朝はローマ帝国やビザンツ帝国の東方をおびやかすライバルであり、正統カリフ時代のアラブに滅ぼされた帝国である。常に「相手方」のイメージなのだ。本書ではそれが逆転する。ギリシア、ローマ、ビザンツ、アラブなどが「相手方」になる。それも辺境の地の遠い存在である。新鮮な景色だ。
ハカーマニシュ朝やサーサーン朝にとって、辺境の地の騒擾も大変ではあるが、内情のあれこれの方が重要である。本書を読んでいると、ご近所つきあいで表向きの外面しか知らなかった家庭に入り込んで、その内実を知ってしまった気分になる。どこの家庭も複雑な事情をかかえて大変だなあと思ってしまう。
ペルシア帝国を身内に感じるられる歴史書である。
『ペルシア帝国』(青木健/講談社現代新書)
青木氏の著書を読むのは『マニ教』に続いて2冊目である。随所に著者のツッコミや感慨吐露コメントを挿入した語り口は魅力的だ。
だが、私にとって本書はさほど読みやすくはなかった。概説書とは言え、かなり細かい事柄に踏み込んでいる。私の知らない固有名詞が頻出する。私にはややレベルの高い概説書である。巻末の「補論 研究ガイド」などは、研究者の卵を対象にしているように見える。
本書のいう「ペルシア帝国」とはハカーマニシュ朝(アケメネス朝)とサーサーン朝を指す。この二つの王朝に絞った概説である。
本書は固有名詞を原音(だと思う)で表記している。私たちが慣れているギリシア語表記(だと思う)とはかなり違う。いくつか例示してみる。カッコ内がギリシア語だ。
ハカーマニシュ朝(アケメネス朝)
アルシャク朝(アルケサス朝)
クールシュ2世(キュロス2世)
カンブージヤ(カンビュセス)
クシャヤールシャン(クセルクセス)
ダーラヤワシュ(ダレイオス)
テースィフォーン(クテシフォン)
・・・・・・
研究者の世界では原音表記が原則なのだろう。西欧中心の見方を変えるのには賛同できる。だが、歴史書で常に固有名詞に悩まされている身には、やっと馴染んだ固有名詞が別表記になっていると混乱する。頭の中でいちいち変換しながら読み進めるのは難儀だ。とは言え、本書を読了する頃には少しだけ原音表記に慣れてきた。
原音表記はペルシア帝国に関する固有名詞だけで、ハカーマニシュ朝を滅ぼしたあの大王は「アレクサンダー3世」と表記している。アレクサンドロスでもイスカンダルでもないのが面白い。
本書が扱うハカーマニシュ朝とサーサーン朝は、高校世界史の教科書では4ページ足らず、それをじっくり1冊で解説している。私には未知の事柄ばかりで、驚くべき内容も随所にある(皇帝の親族大虐殺、マズダー教とゾロアスター教の違いなどなど)。
ハカーマニシュ朝はアレクサンダーに滅ぼされ、サーサーン朝はアラブ(イスラム)に滅ぼされたと記憶していた。しかし、本書によれば事情は単純ではない。
ハカーマニシュ朝はアレクサンダーに侵攻された頃にはすでにガタガタ、ダーラヤワシュ3世(ダレイオス3世)自身がはなはだ出自のあやしい人物だったそうだ。サーサーン朝もアラブが来る前にすでに死に体だったらしい。初めて知った。
本書によってあらためて認識したのは、視点が変われば景色が変わるということだ。あたりまえかもしれない。だが、視点を変えるのはさほど容易ではない。
よく考えると、私の頭の中でのペルシア帝国のイメージの大部分はギリシア・ローマ史、ビザンツ史、イスラム史のなかで形成されてきたと思う。
ハカーマニシュ朝といえばギリシアとの戦争とアレクサンダーの征服が思い浮かぶ。サーサーン朝はローマ帝国やビザンツ帝国の東方をおびやかすライバルであり、正統カリフ時代のアラブに滅ぼされた帝国である。常に「相手方」のイメージなのだ。本書ではそれが逆転する。ギリシア、ローマ、ビザンツ、アラブなどが「相手方」になる。それも辺境の地の遠い存在である。新鮮な景色だ。
ハカーマニシュ朝やサーサーン朝にとって、辺境の地の騒擾も大変ではあるが、内情のあれこれの方が重要である。本書を読んでいると、ご近所つきあいで表向きの外面しか知らなかった家庭に入り込んで、その内実を知ってしまった気分になる。どこの家庭も複雑な事情をかかえて大変だなあと思ってしまう。
ペルシア帝国を身内に感じるられる歴史書である。
猿之助不在の「六月大歌舞伎」を観た ― 2023年06月08日
歌舞伎座で「六月大歌舞伎」の昼の部と夜の部を通しで観た。当初は夜の部のみを観る予定だった。目当ては片岡仁左衛門の「いがみの権太」である。猿之助事件が発生し、猿之助が出演予定だった昼の部は代役で上演していると知り、昼の部も観たくなった。昼の部、夜の部ともに満席ではなく、チケットは容易に入手できた。
演目は以下の通りである。
[昼の部]
傾城反魂香
(土佐将監閑居)(浮世又平住家)
児雷也
扇獅子
[夜の部]
義経千本桜
(木の実)(小金吾討死)(すし屋)(川連法眼館)
猿之助出演予定だった「傾城反魂香」は私には未知の演目、わが本棚の『名作歌舞伎全集 第1巻 近松門左衛門集』を確認すると、しっかり冒頭に載っていた。チラシには「三代猿之助四十八撰の内」とある。市川中車と猿之助が主役夫婦(猿之助が女房)の予定だったが、猿之助に代わって中村壱太郎が中車の女房を演じた。
芝居を観て、歌舞伎は主役級の役でも違和感なく代役が可能なのだとあらためて感心した。歌舞伎役者は誰でもがどの役でも演じることができると聞いたことがある。真偽のほどはわからない。
「傾城反魂香」は吃りの絵師(中車)の話である。気迫を込めて絵に描いた動物や人物が実体化したり、絵から出てきた虎を気迫の筆で消去するという仕掛けが楽しい。
「義経千本桜」の前半、片岡仁左衛門(80歳)の「いがみの権太」は色気があって声も姿も素晴らしい。私がこの役者の歌舞伎を初めて観たのは40年近く昔(当時は片岡孝夫)だと思う。その頃とあまり変わっていないのに驚く。
この芝居で仁左衛門(80歳)、片岡孝太郎(55歳)、片岡千之助(23歳)の親子孫三代が共演している。役者の実年齢は役の年齢と無関係なのだ。芝居の魔術だと思う。
「義経千本桜」の後半は狐忠信の話である。狐忠信は過去にいくつか観ている。尾上松緑の狐忠信は、私の記憶にある芝居とは少し印象が違い、新鮮だった。
狐忠信を観ながら、猿之助の狐忠信を思い出した。建て替えた歌舞伎座に猿之助が初めて出演した時の演目が「川連法眼館」だった。猿之助だから宙乗りがある。それを観たくてチケットをゲットした。もちろん、松緑の狐忠信は空を飛ばないが、松緑のラストシーンを観ながら猿之助が二重写しになった。
演目は以下の通りである。
[昼の部]
傾城反魂香
(土佐将監閑居)(浮世又平住家)
児雷也
扇獅子
[夜の部]
義経千本桜
(木の実)(小金吾討死)(すし屋)(川連法眼館)
猿之助出演予定だった「傾城反魂香」は私には未知の演目、わが本棚の『名作歌舞伎全集 第1巻 近松門左衛門集』を確認すると、しっかり冒頭に載っていた。チラシには「三代猿之助四十八撰の内」とある。市川中車と猿之助が主役夫婦(猿之助が女房)の予定だったが、猿之助に代わって中村壱太郎が中車の女房を演じた。
芝居を観て、歌舞伎は主役級の役でも違和感なく代役が可能なのだとあらためて感心した。歌舞伎役者は誰でもがどの役でも演じることができると聞いたことがある。真偽のほどはわからない。
「傾城反魂香」は吃りの絵師(中車)の話である。気迫を込めて絵に描いた動物や人物が実体化したり、絵から出てきた虎を気迫の筆で消去するという仕掛けが楽しい。
「義経千本桜」の前半、片岡仁左衛門(80歳)の「いがみの権太」は色気があって声も姿も素晴らしい。私がこの役者の歌舞伎を初めて観たのは40年近く昔(当時は片岡孝夫)だと思う。その頃とあまり変わっていないのに驚く。
この芝居で仁左衛門(80歳)、片岡孝太郎(55歳)、片岡千之助(23歳)の親子孫三代が共演している。役者の実年齢は役の年齢と無関係なのだ。芝居の魔術だと思う。
「義経千本桜」の後半は狐忠信の話である。狐忠信は過去にいくつか観ている。尾上松緑の狐忠信は、私の記憶にある芝居とは少し印象が違い、新鮮だった。
狐忠信を観ながら、猿之助の狐忠信を思い出した。建て替えた歌舞伎座に猿之助が初めて出演した時の演目が「川連法眼館」だった。猿之助だから宙乗りがある。それを観たくてチケットをゲットした。もちろん、松緑の狐忠信は空を飛ばないが、松緑のラストシーンを観ながら猿之助が二重写しになった。
複雑であることを再認識させられる『バルカンの歴史』 ― 2023年06月10日
昨年夏からビザンツ史の本を断続的に何冊か読んできた。多少はビザンツ史が身近になった。先日読んだ『ペルシア帝国』はビザンツから見て東方だったので、今度は西方の『バルカンの歴史』を読んだ。ビザンツは東方にも西方にも悩まされていたのだ。
『図説バルカンの歴史』(柴宜弘/ふくろうの本/河出書房新社)
河出の「ふくろうの本」は写真や図版をほぼ全ページに配した親しみやすい本だ。本書を読む気になったのは短時間で読めると思ったからである。
本書を読了し、何とゴチャゴチャ複雑な歴史だとため息が出た。あらためて複雑さの淵源と複雑度が増大している現状を知った。頭の中はゴチャゴチャのままで、「複雑だ」ということだけを了解した感じだ。
古代から中世にかけてのブルガリアやハンガリーの状況を知りたい――それが、本書を読むそもそもの動機だった。第一次ブルガリア帝国(681-1018)や第ニ次ブルガリア帝国(1187-1396)の様子はある程度わかったが、ハンガリーについて本書は簡単にしか触れていない。
著者は、バルカンの範囲について次のように述べている。
「バルカンをたんなる地理的範囲と捉えるのではなく、歴史的なものとして考える。つまり、歴史的にビザンツ帝国とオスマン帝国の影響を強く受けた地域と規定しておきたい。したがって、オスマン帝国の支配を一時的にしか受けなかったハンガリーについては除外されるが、ルーマニアは含まれる。旧ユーゴスラヴィアから独立したスロヴェニアも原則として除かれることになる。」
地域の歴史を捉えるうえでの明解な考え方だ。この考え方だけでも、多少はゴチャゴチャが整理できる。この地域の歴史は、周辺の勢力とのせめぎあいだ。ビザンツ帝国やオスマン帝国だけでなく、ハプスブルク帝国やロシアの影響も大きい。隣接していないドイツ、フランス、英国なども影響を及ぼしている。
本書は全体の半分以上が19世紀以降、つまり近現代史である。古代や中世への関心から本書を手した私の期待とは少しズレている。だが、満足できる内容だった。きちんと把握できていなかった近現代のバルカンの状況を多少はイメージできた。
近代以降のバルカン史は「民族意識」がどうに作られてきたかの歴史である。さまざまな民族意識をもつ人々が地理的に棲み分けずに混在している――それがバルカンの問題である。民族意識の形成が人々を不幸にしているようにも思えてしまう。
ナショナリズムとは「想像の共同体」の産物であり、民族意識の形成に利用・活用されるのが歴史である。だから、バルカンの近代を捉えるには古代や中世の歴史を知らなければならない。
民族意識はいつかは克服すべきものだと思う。と言っても、人間の集団である社会の維持に何等かの「想像の共同体」は必須にも思える。バルカンのゴチャゴチャは、この地域の特殊性というよりは、集団で行動する人間が抱える普遍的課題に思えてきた。
『図説バルカンの歴史』(柴宜弘/ふくろうの本/河出書房新社)
河出の「ふくろうの本」は写真や図版をほぼ全ページに配した親しみやすい本だ。本書を読む気になったのは短時間で読めると思ったからである。
本書を読了し、何とゴチャゴチャ複雑な歴史だとため息が出た。あらためて複雑さの淵源と複雑度が増大している現状を知った。頭の中はゴチャゴチャのままで、「複雑だ」ということだけを了解した感じだ。
古代から中世にかけてのブルガリアやハンガリーの状況を知りたい――それが、本書を読むそもそもの動機だった。第一次ブルガリア帝国(681-1018)や第ニ次ブルガリア帝国(1187-1396)の様子はある程度わかったが、ハンガリーについて本書は簡単にしか触れていない。
著者は、バルカンの範囲について次のように述べている。
「バルカンをたんなる地理的範囲と捉えるのではなく、歴史的なものとして考える。つまり、歴史的にビザンツ帝国とオスマン帝国の影響を強く受けた地域と規定しておきたい。したがって、オスマン帝国の支配を一時的にしか受けなかったハンガリーについては除外されるが、ルーマニアは含まれる。旧ユーゴスラヴィアから独立したスロヴェニアも原則として除かれることになる。」
地域の歴史を捉えるうえでの明解な考え方だ。この考え方だけでも、多少はゴチャゴチャが整理できる。この地域の歴史は、周辺の勢力とのせめぎあいだ。ビザンツ帝国やオスマン帝国だけでなく、ハプスブルク帝国やロシアの影響も大きい。隣接していないドイツ、フランス、英国なども影響を及ぼしている。
本書は全体の半分以上が19世紀以降、つまり近現代史である。古代や中世への関心から本書を手した私の期待とは少しズレている。だが、満足できる内容だった。きちんと把握できていなかった近現代のバルカンの状況を多少はイメージできた。
近代以降のバルカン史は「民族意識」がどうに作られてきたかの歴史である。さまざまな民族意識をもつ人々が地理的に棲み分けずに混在している――それがバルカンの問題である。民族意識の形成が人々を不幸にしているようにも思えてしまう。
ナショナリズムとは「想像の共同体」の産物であり、民族意識の形成に利用・活用されるのが歴史である。だから、バルカンの近代を捉えるには古代や中世の歴史を知らなければならない。
民族意識はいつかは克服すべきものだと思う。と言っても、人間の集団である社会の維持に何等かの「想像の共同体」は必須にも思える。バルカンのゴチャゴチャは、この地域の特殊性というよりは、集団で行動する人間が抱える普遍的課題に思えてきた。
映画原作の芝居『パラサイト』を観て映画『天国と地獄』を想起 ― 2023年06月12日
新宿の歌舞伎町タワーにできたシアターミラノ座のオープニング公演『パラサイト』(台本・演出:鄭義信、出演:古田新太、宮沢氷魚、伊藤沙莉、江口のりこ、他)を観た。映画『パラサイト 半地下の家族』が原作である。あの有名映画をどう舞台化するのか興味があった。
思った以上に映画に忠実な芝居だった。格差社会や家族の絆に関しては映画よりメッセージ性が強い。映画以上にコミカルなシーンも多い。
舞台では日本の関西の話にしている。時代は1995年、阪神淡路大震災の年だ。映画で「半地下」だった住宅は、高い堤防の脇の川床より低い猥雑な地域の零細な家屋になっている。立体的な舞台装置は家族の空間だけでなく地域環境も表現している。
この芝居で関心したのは舞台装置である。きちんと作り込んだ壮大な舞台装置だ。場面は「零細な家屋」「金持ちの邸宅」「邸宅の地下室」の三つ、それが回り舞台でスムーズに転換する。大劇場にふさわしい仕掛けである。
金持ちの邸宅は高台にあり、背景の巨大カーテンを上げると神戸の町をはるかに見下ろせる。見下ろす町の映像に迫力がある。低地に住む貧困層と高台に住む富裕層という対比を鮮やかに表現している。黒澤明の古い映画『天国と地獄』を想起した。
映画では半地下の家は洪水被害に合う。舞台では震災で焼失する。高台の邸宅は揺れも少なく殆ど被害を受けない(これは実話に基づいているらしい)。邸宅の巨大なガラス戸からは、あちこちから煙が上がる神戸の町を俯瞰できる。壮観である。
終盤の金持ちの息子の誕生パーティ・シーン(このパーティは惨劇の場になる)は、映画ではガーデン・パーティだった。舞台では邸宅の室内パーティだ。大人たちが仮装してうかれている背景は、巨大なガラス戸から見下す神戸の町である。その町は依然として燃え上がっている。燃える町とパーティ、演劇らしい印象的なシーンだ。このシーンは映画を超えていると思った。
思った以上に映画に忠実な芝居だった。格差社会や家族の絆に関しては映画よりメッセージ性が強い。映画以上にコミカルなシーンも多い。
舞台では日本の関西の話にしている。時代は1995年、阪神淡路大震災の年だ。映画で「半地下」だった住宅は、高い堤防の脇の川床より低い猥雑な地域の零細な家屋になっている。立体的な舞台装置は家族の空間だけでなく地域環境も表現している。
この芝居で関心したのは舞台装置である。きちんと作り込んだ壮大な舞台装置だ。場面は「零細な家屋」「金持ちの邸宅」「邸宅の地下室」の三つ、それが回り舞台でスムーズに転換する。大劇場にふさわしい仕掛けである。
金持ちの邸宅は高台にあり、背景の巨大カーテンを上げると神戸の町をはるかに見下ろせる。見下ろす町の映像に迫力がある。低地に住む貧困層と高台に住む富裕層という対比を鮮やかに表現している。黒澤明の古い映画『天国と地獄』を想起した。
映画では半地下の家は洪水被害に合う。舞台では震災で焼失する。高台の邸宅は揺れも少なく殆ど被害を受けない(これは実話に基づいているらしい)。邸宅の巨大なガラス戸からは、あちこちから煙が上がる神戸の町を俯瞰できる。壮観である。
終盤の金持ちの息子の誕生パーティ・シーン(このパーティは惨劇の場になる)は、映画ではガーデン・パーティだった。舞台では邸宅の室内パーティだ。大人たちが仮装してうかれている背景は、巨大なガラス戸から見下す神戸の町である。その町は依然として燃え上がっている。燃える町とパーティ、演劇らしい印象的なシーンだ。このシーンは映画を超えていると思った。
ディティールを楽しめる『吸血鬼ドラキュラ』 ― 2023年06月14日
高校2年のとき(57年前)に古本で入手したまま未読だった『吸血鬼ドラキュラ』を読んだ。表紙は破れ、中身が黄ばんだ文庫本である。巻末のメモで購入年がわかった。
『吸血鬼ドラキュラ』(ブラム・ストーカー/平井呈一訳/創元推理文庫)
こんな昔の本を読む気になったのは、先日読んだ『バルカンの歴史』がこの小説に言及していたからである。ドラキュラのモデルは15世紀ワラキア公国のヴラド公である。法律に違反した者に串刺し刑を科すことが多かったので異名は串刺公、オスマン帝国と戦った英雄でもある。
アイルランドの作家ブラム・ストーカーがスラヴの吸血鬼伝説とヴラド公を結びつけた『吸血鬼ドラキュラ』を刊行したのは1897年、19世紀末である。
高校生の私が本書を読みかけにしたのは、読みにくかったからだと思う。十字架とニンニクが苦手な吸血鬼を、棺桶で眠っているときに胸に杭を打ち込んで退治する――それだけの話だとわかっているので、読むまでもないと放り出したのかもしれない。
57年ぶりの『吸血鬼ドラキュラ』は楽しみながら読み進めることができた。この小説は、複数の登場人物による手紙や日記の集成という構成である。日記には速記文字で書かれたものや蝋管蓄音機に録音されたものもある。日記に新聞記事が挿入されていたり、手書き日記をタイプライターで複写したりもする。この小説は、多様なドキュメントを日付順に整理したファイルなのだ。作者の工夫が面白い。
冒頭は、東欧の未知の地トランシルヴァニアに出張した英国の若い弁理士の日記である。ドラキュラ伯爵の居城に招かれて異郷を旅する記録に引き込まれる。彼の地の歴史や風俗への言及も興味深い。大時代的な雰囲気もいい。
だが、ふと思う。この小説は、57年前の高校生の私には退屈で難儀だったかもしれない。思わせぶりなシーンは多く、ストーリーの進行が遅いのだ。手紙や日記の繰り返しを「物語のふくらみ」と感じれば楽しめるが、冗長と感じると退屈かもしれない。荒唐無稽でバカげた話にうんざりする可能性もある。
この小説に出てくる地名の大半は、高校生の私には未知の地名だったと思う。いまの私は、高校生の頃よりは歴史や地理を知っているので、地名からイメージが広がる。未知の地名が小説に出てくれば調べる。ネットのおかげで調べやすいし地図帳もいくつかある。だが、57年前の私は、おそらく未知の地名を気にせず、ストーリーを追って読み進めるだろう。
この小説に登場する地名の多くはトランシルヴァニア周辺と英国であり、この二つの地域を結ぶ海路や鉄道も出てくる。地名を確認しながら登場人物の移動を地図で追うのが楽しい。
主要人物の教授がロンドンとオランダを容易に行き来しているのにも驚いた。19世紀末の交通事情に興味がわく。本書に登場するリヴァプールという地名は、イングランド西岸の港町だとすると違和感がある。いろいろ調べて、ロンドン市内にリヴァプール・ストリートという駅があると判明して得心した。年を取ると、そんな些末な所に読書の楽しみを見いだすのである。
太宰治の『新ハムレット』は面倒くさい人々の悲喜劇 ― 2023年06月16日
パルコ劇場で『新ハムレット』(作:太宰治、上演台本・演出:五戸真理枝、出演:木村達成、島崎遥香、加藤諒、駒井健介、池田成志、松下由樹、平田満)を観た。
『新ハムレット』は太宰治の最初の書き下ろし長編小説である。刊行は1941年7月、この年の12月には太平洋戦争が始まる。あんな時代にこんな本が出ていたのだ。
私は昨年、「戯曲リーディング『ハムレット』」 を観たの機に少々ハムレットづいた。数十年ぶりに『新ハムレット』 を再読し、『謎解き『ハムレット』』 (河合祥一郎)を読んだ。今年3月に野村萬斎演出『ハムレット』 を観て一段落と思っていたが、思いがけなく『新ハムレット』まで観ることができた。
『新ハムレット』は会話だけの戯曲風小説である。太宰治は「はしがき」で「戯曲のつもりで書いたのではない」と明言している。会話と言っても太宰風の饒舌で奔放な語りが多い。この小説を読んだとき、舞台化するのは至難だろうと感じた。
今回の舞台、導入部が面白い。「スマホの電源を切ってください」の場内アナウンスで芝居が始まっていた。アナウンスしていたのはポローニヤスで、舞台中央でスマホを操作しているハムレットをたしなめる。続いて「はしがき」(文庫本3頁ほど)の朗読が始まる。「こんなものが出来ました、というより他に仕様がない。」の書き出しから「作者の力量が、これだけしかないのだ。じたばた自己弁解してみたところで、はじまらぬ。昭和16年夏」で終わる「はしがき」を役者全員がリレー形式で読み上げる。
太宰治の世界に引き込んでいく見事な導入である。ハムレットだけでなく、すべての登場人物が太宰治的な面倒くさい人物の世界である。大人と若者が互いのいやらしさを指摘しあう。両者に大きな違いは感じられない。と言っても、ハムレットはスマホをいじるだけでなく「馬鹿だ 馬鹿だ 馬鹿だ 馬鹿だ 馬鹿だ」とラップを歌ったりもするのだが……。
この舞台を観て、時局とは無縁に思えた『新ハムレット』に戦争が反映されていると気づいた。終盤に出てくるデンマーク対ノルウェイの戦争は、直前に迫った太平洋戦争を思わせる。そんな時代のなかに生きる家族のそれぞれが、アレコレ悩む姿を描いた悲喜劇である。
『新ハムレット』は太宰治の最初の書き下ろし長編小説である。刊行は1941年7月、この年の12月には太平洋戦争が始まる。あんな時代にこんな本が出ていたのだ。
私は昨年、「戯曲リーディング『ハムレット』」 を観たの機に少々ハムレットづいた。数十年ぶりに『新ハムレット』 を再読し、『謎解き『ハムレット』』 (河合祥一郎)を読んだ。今年3月に野村萬斎演出『ハムレット』 を観て一段落と思っていたが、思いがけなく『新ハムレット』まで観ることができた。
『新ハムレット』は会話だけの戯曲風小説である。太宰治は「はしがき」で「戯曲のつもりで書いたのではない」と明言している。会話と言っても太宰風の饒舌で奔放な語りが多い。この小説を読んだとき、舞台化するのは至難だろうと感じた。
今回の舞台、導入部が面白い。「スマホの電源を切ってください」の場内アナウンスで芝居が始まっていた。アナウンスしていたのはポローニヤスで、舞台中央でスマホを操作しているハムレットをたしなめる。続いて「はしがき」(文庫本3頁ほど)の朗読が始まる。「こんなものが出来ました、というより他に仕様がない。」の書き出しから「作者の力量が、これだけしかないのだ。じたばた自己弁解してみたところで、はじまらぬ。昭和16年夏」で終わる「はしがき」を役者全員がリレー形式で読み上げる。
太宰治の世界に引き込んでいく見事な導入である。ハムレットだけでなく、すべての登場人物が太宰治的な面倒くさい人物の世界である。大人と若者が互いのいやらしさを指摘しあう。両者に大きな違いは感じられない。と言っても、ハムレットはスマホをいじるだけでなく「馬鹿だ 馬鹿だ 馬鹿だ 馬鹿だ 馬鹿だ」とラップを歌ったりもするのだが……。
この舞台を観て、時局とは無縁に思えた『新ハムレット』に戦争が反映されていると気づいた。終盤に出てくるデンマーク対ノルウェイの戦争は、直前に迫った太平洋戦争を思わせる。そんな時代のなかに生きる家族のそれぞれが、アレコレ悩む姿を描いた悲喜劇である。
57年寝かした『フランケンシュタイン』を読了 ― 2023年06月18日
先日、57年前の高校時代に古本で入手したまま未読だった『吸血鬼ドラキュラ』
を読了し、同じ頃に古本で入手したもうひとつの未読本『フランケンシュタイン』を思い出した。ドラキュラを読んだのを機に、この未読文庫本も読んだ。
『フランケンシュタイン』(シェリー夫人/山本政喜訳/角川文庫)
高校生の頃、この小説に関する雑学的知識は仕入れていた。「作者は詩人シェリーの妻(この翻訳の作者名はシェリー夫人! メアリー・シェリーではない」「バイロンとシェリーとその妻の三人の夜話がきっかけで生まれ小説」「フランケンシュタインは怪物の名ではなく、それを創った人の名」「映画などで広まっているフランケンシュタインのイメージは小説とは違う」といった知識である。
そんな知識を前提に本書に取り組んだ高校生の私は、あえなく挫折した。19世紀文学の回りくどい進行につきあう忍耐力がなかったのだと思う。74歳の私は57年寝かせた本書を面白く読了した。
率直な読後感は「フランケンシュタインってこんなに意外でヘンな話だったのか」である。SF的要素は少なく、かなり文学的である。怪物もそれを創ったヴィクトル・フランケンシュタインも思考や行動がかなりヘンだ。ツッコミ所はいろいろある。状況や情景の描写は細やかで、引き込まれる。暗喩小説にも感じられた。
怪物が内省的で知的なのには驚いた。創られた当初は無知な文盲で、創造主から見捨てられても短期間で言語をマスターする。『失楽園』『プルタークの伝記』『ヴェルテルの悲しみ』を読みこなし、いろいろ考察する。どれも読んでいない私(『プルターク』は一部だけ読んだが)は、己がこの怪物より知的に劣っているのかと歎息した。
本書の記述は入れ子になっている。北極圏でフランケンシュタインを発見したウォルトンの姉あての手紙、その手紙に挿入されたフランシュタインの語り(これがメイン)、その語りに挿入された怪物の告白と糾弾――の三重構造である。
この「語り」を読んでいる途中、怪物はフランケンシュタインにだけ見える妄想であって、実在しないのではと思えることもあった。創造主と怪物がジキルとハイドの関係に感じられたのだ。もちろん、そんな展開にはならないのだが……。
『フランケンシュタイン』(シェリー夫人/山本政喜訳/角川文庫)
高校生の頃、この小説に関する雑学的知識は仕入れていた。「作者は詩人シェリーの妻(この翻訳の作者名はシェリー夫人! メアリー・シェリーではない」「バイロンとシェリーとその妻の三人の夜話がきっかけで生まれ小説」「フランケンシュタインは怪物の名ではなく、それを創った人の名」「映画などで広まっているフランケンシュタインのイメージは小説とは違う」といった知識である。
そんな知識を前提に本書に取り組んだ高校生の私は、あえなく挫折した。19世紀文学の回りくどい進行につきあう忍耐力がなかったのだと思う。74歳の私は57年寝かせた本書を面白く読了した。
率直な読後感は「フランケンシュタインってこんなに意外でヘンな話だったのか」である。SF的要素は少なく、かなり文学的である。怪物もそれを創ったヴィクトル・フランケンシュタインも思考や行動がかなりヘンだ。ツッコミ所はいろいろある。状況や情景の描写は細やかで、引き込まれる。暗喩小説にも感じられた。
怪物が内省的で知的なのには驚いた。創られた当初は無知な文盲で、創造主から見捨てられても短期間で言語をマスターする。『失楽園』『プルタークの伝記』『ヴェルテルの悲しみ』を読みこなし、いろいろ考察する。どれも読んでいない私(『プルターク』は一部だけ読んだが)は、己がこの怪物より知的に劣っているのかと歎息した。
本書の記述は入れ子になっている。北極圏でフランケンシュタインを発見したウォルトンの姉あての手紙、その手紙に挿入されたフランシュタインの語り(これがメイン)、その語りに挿入された怪物の告白と糾弾――の三重構造である。
この「語り」を読んでいる途中、怪物はフランケンシュタインにだけ見える妄想であって、実在しないのではと思えることもあった。創造主と怪物がジキルとハイドの関係に感じられたのだ。もちろん、そんな展開にはならないのだが……。
『フランケンシュタイン』を精読した気分になる『批評理論入門』 ― 2023年06月20日
57年寝かせた『フランケンシュタイン』を読了した後、ネット検索で次の新書を見つけた。『フランケンシュタイン』を題材にした批評入門らしい。あの小説をどう読み解くのか興味がわき、入手・読了した。
『批評理論入門:『フランケンシュタイン』解剖講義』(廣野由美子/中公新書)
著者は英文学の大学教授、本書は以下の批評理論を紹介・解説している。
「伝統的批評」「ジャンル批評」「読者反応批評」「脱構築批評」「精神分析批評」「フェミニズム批評」「ジェンダー批評」「マルクス主義批評」「文化批評」「ポストコロニアル批評」「新歴史主義」「文体論的批評」「透明な批評」
大学の講義のような目次を見ると『文学部唯野教授』(筒井康隆)を想起する。私は批評理論を勉強したいのではない。『フランケンシュタイン』をどう批評しているかに興味があるだけだ。そんな私にも読みやすかった。
著者は多様な批評理論を『フランケンシュタイン』を題材に解説している。さまざまな切り口の『フランケンシュタイン』批評集とも言える。あの小説を読んだ直後に本書を読んだので、『フランケンシュタイン』をていねいに再読した気分になった。
私が『フランケンシュタイン』でヘンだと感じた部分やツッコミ所の掘り下げもある。複数の語りの入れ子構造になっているこの小説の語り手たちを「信頼できない語り手」と見なせば、小説が紡ぎ出すイメージがよりクリアになった。
著者がこの小説に関して指摘している事柄の大半は、私が気づかなかった事柄である。そのすべてに共感できたわけではないが、小説とはかくも多様な読み方ができるのかと感服した。
作者メアリー・シェリーについての興味深い伝記的情報を得られたのも収穫だった。彼女がこの小説を書いたのは19歳のとき、すでにシェリーの子を出産していたが、まだ妻ではなく不倫関係だったそうだ。驚いた。
『批評理論入門:『フランケンシュタイン』解剖講義』(廣野由美子/中公新書)
著者は英文学の大学教授、本書は以下の批評理論を紹介・解説している。
「伝統的批評」「ジャンル批評」「読者反応批評」「脱構築批評」「精神分析批評」「フェミニズム批評」「ジェンダー批評」「マルクス主義批評」「文化批評」「ポストコロニアル批評」「新歴史主義」「文体論的批評」「透明な批評」
大学の講義のような目次を見ると『文学部唯野教授』(筒井康隆)を想起する。私は批評理論を勉強したいのではない。『フランケンシュタイン』をどう批評しているかに興味があるだけだ。そんな私にも読みやすかった。
著者は多様な批評理論を『フランケンシュタイン』を題材に解説している。さまざまな切り口の『フランケンシュタイン』批評集とも言える。あの小説を読んだ直後に本書を読んだので、『フランケンシュタイン』をていねいに再読した気分になった。
私が『フランケンシュタイン』でヘンだと感じた部分やツッコミ所の掘り下げもある。複数の語りの入れ子構造になっているこの小説の語り手たちを「信頼できない語り手」と見なせば、小説が紡ぎ出すイメージがよりクリアになった。
著者がこの小説に関して指摘している事柄の大半は、私が気づかなかった事柄である。そのすべてに共感できたわけではないが、小説とはかくも多様な読み方ができるのかと感服した。
作者メアリー・シェリーについての興味深い伝記的情報を得られたのも収穫だった。彼女がこの小説を書いたのは19歳のとき、すでにシェリーの子を出産していたが、まだ妻ではなく不倫関係だったそうだ。驚いた。




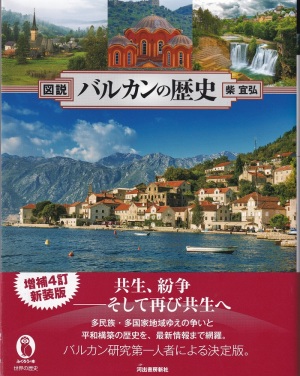



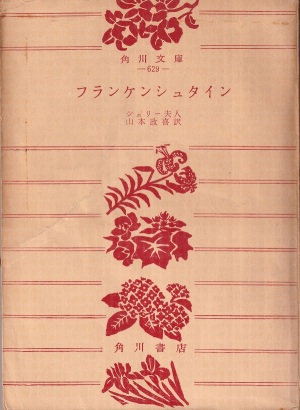

最近のコメント