『桐島です』は逃亡生活を坦々と描いていた ― 2025年07月08日
新宿武蔵野館で『桐島です』(監督:高橋伴明、脚本:梶原阿貴、出演:毎熊克哉、奥野瑛太、北香那、他)を観た。連続企業爆破事件指名手配犯・桐島聡を描いた映画である。彼は昨年(2024年)1月、病床で「私は桐島聡です」と名乗り、その4日後にガンで逝った。
あの衝撃的な「名乗り」を契機に制作された映画には、4カ月前に公開された足立正生監督の『逃走』もある。神奈川県藤沢市で市井の人として入院・死亡した桐島の49年に及ぶ逃亡生活の実態の大半は不明である。それ故に映画監督たちの想像力を駆り立てるのだと思う。
『桐島です』は『逃走』とはかなりテイストの違う映画だった。足立監督は「逃走貫徹=闘争貫徹」という明瞭なコンセプトのもとに桐島の心象風景や妄想の映像を交えて逃亡生活を描いた。高橋監督は桐島を社会的正義感がやや強い等身大の普通の人間と捉え、怒濤の青春とその後の日常を坦々と描いている。
この映画のキーワードは「時代遅れ」である。もちろん「時代遅れで何が悪い」という、時代に対する反骨を秘めている。それは、「こんな日本にしてしまってゴメン」という忸怩たる思いにつながる。世代の思いの反映だと感じる。
『桐島です』と『逃走』の両方に、桐島が本屋で『棺一基 大道寺将司全句集』(2012年発行)を手にするシーンがある。桐島の遺品にこの本があったかどうかは知らないが、あり得た場面に思える。両方の映画では、大道寺将司(死刑囚。2017年獄死)が獄中で詠んだ俳句数篇を読み上げる。私の曖昧な記憶では、選ばれた句は二つの映画でかなり異なっていた気がする。機会があれば確認したい。
『桐島です』で印象に残ったシーンがある。桐島は宇賀神寿一と共に指名手配され、別々に逃走する。二人は再会の月日と場所を決めていたが、再会を果たせないまま宇賀神が逮捕される。桐島は『棺一基』の注釈を読んで宇賀神が刑期を終えて出所していると知り、かつて再会を約束した9月9日に約束の場所に赴く。その日、齢を重ねた二人は互いに気づかないままにすれ違う。フィクションだろうが心に残る。
ラストシーンも印象的だ。映画は、病床で「私は桐島聡です」と名乗った後の騒動を描かず、不思議な場面転換になる。中東と思われる塹壕の中で、老いた女性闘士(高橋恵子)が、スマホに届いたメッセージを見てつぶやく。「桐島くん、おつかれさま」と。
足立正生監督へのオマージュだろうか。
あの衝撃的な「名乗り」を契機に制作された映画には、4カ月前に公開された足立正生監督の『逃走』もある。神奈川県藤沢市で市井の人として入院・死亡した桐島の49年に及ぶ逃亡生活の実態の大半は不明である。それ故に映画監督たちの想像力を駆り立てるのだと思う。
『桐島です』は『逃走』とはかなりテイストの違う映画だった。足立監督は「逃走貫徹=闘争貫徹」という明瞭なコンセプトのもとに桐島の心象風景や妄想の映像を交えて逃亡生活を描いた。高橋監督は桐島を社会的正義感がやや強い等身大の普通の人間と捉え、怒濤の青春とその後の日常を坦々と描いている。
この映画のキーワードは「時代遅れ」である。もちろん「時代遅れで何が悪い」という、時代に対する反骨を秘めている。それは、「こんな日本にしてしまってゴメン」という忸怩たる思いにつながる。世代の思いの反映だと感じる。
『桐島です』と『逃走』の両方に、桐島が本屋で『棺一基 大道寺将司全句集』(2012年発行)を手にするシーンがある。桐島の遺品にこの本があったかどうかは知らないが、あり得た場面に思える。両方の映画では、大道寺将司(死刑囚。2017年獄死)が獄中で詠んだ俳句数篇を読み上げる。私の曖昧な記憶では、選ばれた句は二つの映画でかなり異なっていた気がする。機会があれば確認したい。
『桐島です』で印象に残ったシーンがある。桐島は宇賀神寿一と共に指名手配され、別々に逃走する。二人は再会の月日と場所を決めていたが、再会を果たせないまま宇賀神が逮捕される。桐島は『棺一基』の注釈を読んで宇賀神が刑期を終えて出所していると知り、かつて再会を約束した9月9日に約束の場所に赴く。その日、齢を重ねた二人は互いに気づかないままにすれ違う。フィクションだろうが心に残る。
ラストシーンも印象的だ。映画は、病床で「私は桐島聡です」と名乗った後の騒動を描かず、不思議な場面転換になる。中東と思われる塹壕の中で、老いた女性闘士(高橋恵子)が、スマホに届いたメッセージを見てつぶやく。「桐島くん、おつかれさま」と。
足立正生監督へのオマージュだろうか。
話題の映画『国宝』を観て、原作本も読んだ ― 2025年06月29日
歌舞伎の世界を描いた話題の映画『国宝』(監督:李相日、原作:吉田修一、出演:吉沢亮、横浜流星、高畑充希、寺島しのぶ、渡辺謙、他)を観た。吉沢亮と横浜流星が演じる女形歌舞伎役者の姿が見事だと評判である。映画を観て、評判通りだと思った。
主人公・喜久雄(吉沢亮)は長崎のヤクザの親分の息子である。抗争で父を殺され、上方歌舞伎の名門・花井半二郎に引き取られ、半次郎の息子・俊介(横浜流星)と共に歌舞伎役者として育てられる。二人は同い年だ。
14歳の喜久雄が紆余曲折のすえ人間国宝にまで上り詰める約半世紀の物語である。2時間55分の映画を退屈することなく観た。上映時間は長いが、扱う時間も長い。少年があっという間に老人になっていく話なので、やや目まぐるしく、駆け足にも感じられる。
この映画には二人の役者が歌舞伎を演じる場面が多い。吉沢亮と横浜流星は1年以上稽古したそうだ。私はこの10年ばかり、年に数回ほど歌舞伎を観てきた素人である。歌舞伎役者の良し悪しがわかるわけではないが、二人の女形には感心した。二人が演じる歌舞伎シーンになると、観客席の私もつい緊張して見入ってしまい、その出来栄えにホッとする。
歌舞伎の舞台の裏側を描いているのもこの映画の魅力だ。楽屋や舞台裏の情景が興味深いし、せり上がりや花道を観客目線ではなく役者目線でとらえた映像も新鮮だ。歌舞伎座(と思しき劇場)の満員の観客席を舞台側から見た光景に感動した。
印象に残る場面が多い映画だが、半世紀にわたる話なので、シノプシスを見せられただけという気分にもなる。
多少の物足りなさを感じたので、映画館を出た後、本屋に寄って原作本を購入し、上下2巻を一気に読了した。
『国宝(上)(下)』(吉田修一/朝日文庫)
原作には映画ではわかりにくかった展開も書き込まれている。とは言え、半世紀にわたる歌舞伎役者の波乱に富んだ人生を描くには、上下2冊の分量でも、かなりの省略と飛躍が必要である。面白いが、やや駆け足の長編だった。
小説のなかで印象に残る会話の多くが映画に反映されているのには感心した。映画は、小説が描く世界の魅力を十全に取り込んでいると思う。
さて、映画と小説、どちらが面白いか。私には判断できない。一般的には原作の面白さを超えた映画は少ないと思うが『国宝』のケースは何とも言えない。映画には映画でしか感得できない味わいがあり、小説には小説でしか得られない面白さがある。映画と小説はジャンルの違う作品だという当然のことを再確認するしかない。
主人公・喜久雄(吉沢亮)は長崎のヤクザの親分の息子である。抗争で父を殺され、上方歌舞伎の名門・花井半二郎に引き取られ、半次郎の息子・俊介(横浜流星)と共に歌舞伎役者として育てられる。二人は同い年だ。
14歳の喜久雄が紆余曲折のすえ人間国宝にまで上り詰める約半世紀の物語である。2時間55分の映画を退屈することなく観た。上映時間は長いが、扱う時間も長い。少年があっという間に老人になっていく話なので、やや目まぐるしく、駆け足にも感じられる。
この映画には二人の役者が歌舞伎を演じる場面が多い。吉沢亮と横浜流星は1年以上稽古したそうだ。私はこの10年ばかり、年に数回ほど歌舞伎を観てきた素人である。歌舞伎役者の良し悪しがわかるわけではないが、二人の女形には感心した。二人が演じる歌舞伎シーンになると、観客席の私もつい緊張して見入ってしまい、その出来栄えにホッとする。
歌舞伎の舞台の裏側を描いているのもこの映画の魅力だ。楽屋や舞台裏の情景が興味深いし、せり上がりや花道を観客目線ではなく役者目線でとらえた映像も新鮮だ。歌舞伎座(と思しき劇場)の満員の観客席を舞台側から見た光景に感動した。
印象に残る場面が多い映画だが、半世紀にわたる話なので、シノプシスを見せられただけという気分にもなる。
多少の物足りなさを感じたので、映画館を出た後、本屋に寄って原作本を購入し、上下2巻を一気に読了した。
『国宝(上)(下)』(吉田修一/朝日文庫)
原作には映画ではわかりにくかった展開も書き込まれている。とは言え、半世紀にわたる歌舞伎役者の波乱に富んだ人生を描くには、上下2冊の分量でも、かなりの省略と飛躍が必要である。面白いが、やや駆け足の長編だった。
小説のなかで印象に残る会話の多くが映画に反映されているのには感心した。映画は、小説が描く世界の魅力を十全に取り込んでいると思う。
さて、映画と小説、どちらが面白いか。私には判断できない。一般的には原作の面白さを超えた映画は少ないと思うが『国宝』のケースは何とも言えない。映画には映画でしか感得できない味わいがあり、小説には小説でしか得られない面白さがある。映画と小説はジャンルの違う作品だという当然のことを再確認するしかない。
桐島聡の49年に想像力を馳せた映画『逃走』 ― 2025年03月21日
ユーロスペースで映画『逃走』(監督・脚本:足立正生、主演:古舘寛治、杉田雷麟、他)を観た。連続企業爆破事件で指名手配された桐島聡を描いた映画である。
連続企業爆破事件(1974~1975年)を起こした東アジア反日武装戦線は「狼」「大地の牙」「さそり」の三グループから成る。メンバーの大半は1975年5月に一斉逮捕された。「さそり」の一員だった宇賀神寿一と桐島聡は一斉逮捕を免れて逃走。指名手配される。宇賀神寿一は7年後の1982年に逮捕された。
そして、昨年(2024年)1月、驚きのニュースが流れた。末期ガンで入院している内田洋という男が、自分は桐島聡だと名乗り出たのである。その4日後、男は入院中の病院で死亡した。享年70歳。警視庁はDNA鑑定などから、死亡した男は桐島聡本人と断定した。
このニュースに接してすぐに映画化を考えた足立正生監督(85歳)は、1年足らずで公開にこぎつけた。老監督のフットワークに感心する。
桐島聡の近年の生活については周辺から取材できるが、49年に及ぶ逃走生活には不明の部分が多い。映画『逃走』は、事実をベースにしたフィクションである。桐島聡が抱いたかもしれない心象風景や妄想も織り込んでいる。
よくできた面白い映画だった。桐島聡の後半生を、逃走=闘争ととらえている。末期の病床での名乗りは、逃走貫徹=闘争貫徹を仲間たち伝えるメッセージだった。明解な解釈である。と言っても、49年の逃走人生には悲哀も葛藤もある。日常的な実生活に、妄想世界での別の自分との自問自答や時間を超えた仲間との会話のシーンが重なり、逃走=闘争の日々の姿が重層的に浮かび上がってくる。
桐島聡の指名手配写真は印象的な笑顔だ。逃走を開始した直後、指名手配写真を見た桐島聡は「笑顔禁止」だと自分に言い聞かせる。その滑稽な決意が面白い。「日本中にいつも笑顔をありがとう」という台詞には笑えた。
連続企業爆破事件のリーダたちは私とほぼ同世代で、桐島聡は6歳下だ。往時茫々の思いにとらわれる。だが、私より9歳上の足立正生監督は現役で活躍している。
私たちの学生時代(半世紀以上昔)、足立正生はある種のスター映画人だった。映画を撮るためにパレスチナに行き、日本赤軍の創設に関わり、国際指名手配される。22年に及ぶ海外生活の後、レバノンで逮捕・収監され、3年の禁固刑を終えて帰国(強制送還)する。表現者と実践者が融合した特異な人だ。そんな人が85歳になっても意気軒高なのである。当方も背筋を伸ばさねばという気になる。
連続企業爆破事件(1974~1975年)を起こした東アジア反日武装戦線は「狼」「大地の牙」「さそり」の三グループから成る。メンバーの大半は1975年5月に一斉逮捕された。「さそり」の一員だった宇賀神寿一と桐島聡は一斉逮捕を免れて逃走。指名手配される。宇賀神寿一は7年後の1982年に逮捕された。
そして、昨年(2024年)1月、驚きのニュースが流れた。末期ガンで入院している内田洋という男が、自分は桐島聡だと名乗り出たのである。その4日後、男は入院中の病院で死亡した。享年70歳。警視庁はDNA鑑定などから、死亡した男は桐島聡本人と断定した。
このニュースに接してすぐに映画化を考えた足立正生監督(85歳)は、1年足らずで公開にこぎつけた。老監督のフットワークに感心する。
桐島聡の近年の生活については周辺から取材できるが、49年に及ぶ逃走生活には不明の部分が多い。映画『逃走』は、事実をベースにしたフィクションである。桐島聡が抱いたかもしれない心象風景や妄想も織り込んでいる。
よくできた面白い映画だった。桐島聡の後半生を、逃走=闘争ととらえている。末期の病床での名乗りは、逃走貫徹=闘争貫徹を仲間たち伝えるメッセージだった。明解な解釈である。と言っても、49年の逃走人生には悲哀も葛藤もある。日常的な実生活に、妄想世界での別の自分との自問自答や時間を超えた仲間との会話のシーンが重なり、逃走=闘争の日々の姿が重層的に浮かび上がってくる。
桐島聡の指名手配写真は印象的な笑顔だ。逃走を開始した直後、指名手配写真を見た桐島聡は「笑顔禁止」だと自分に言い聞かせる。その滑稽な決意が面白い。「日本中にいつも笑顔をありがとう」という台詞には笑えた。
連続企業爆破事件のリーダたちは私とほぼ同世代で、桐島聡は6歳下だ。往時茫々の思いにとらわれる。だが、私より9歳上の足立正生監督は現役で活躍している。
私たちの学生時代(半世紀以上昔)、足立正生はある種のスター映画人だった。映画を撮るためにパレスチナに行き、日本赤軍の創設に関わり、国際指名手配される。22年に及ぶ海外生活の後、レバノンで逮捕・収監され、3年の禁固刑を終えて帰国(強制送還)する。表現者と実践者が融合した特異な人だ。そんな人が85歳になっても意気軒高なのである。当方も背筋を伸ばさねばという気になる。
映画『敵』の影の主役は屋敷 ― 2025年02月09日
テアトル新宿で映画『敵』(原作:筒井康隆、監督・脚本:吉田大八、主演:長塚京三)を観た。この監督の映画を観るのは『美しい星』、『騙し絵の牙』に続いて3本目である。映画を観る直前に筒井氏の原作を再読したので、原作の雰囲気と比較しつつの映画鑑賞になった。
上映後にはトークイベンがあった。吉田大八監督に若手の奥山由之氏(映画監督、写真家)がインタビューする形のトークだった。吉田監督は「原作にかなり忠実な映画です。スピリットでは…」と語っていた。その通りだとは思うが、当然ながら映画表現は小説表現とは異なる。
10年前に退職した元大学教授・渡辺儀助の生活を描いたこの映画はモノクロである。儀助が一人で暮らしている古い屋敷がモノクロにマッチしている。冒頭、儀助の起床、朝食の支度、朝食、歯磨き、洗濯、掃除、講演依頼電話への対応、パソコンを使った原稿執筆などの場面が坦々と流れる。原作小説の端正な世界引き込まれて行く心地よさを感じた。
原作の小説では、薄い膜を通した回想のような世界を感じた。映画は即物的表現がメインである。映像からは具体的でリアルな感触が伝わってくる。米を研ぐ手慣れた様子に感心し、朝食の咀嚼に美味を感じた。この映画に出てくる食べ物は美味しそうに見える。儀助が自身の生活演出に満足しているように見えるからだろう。
原作で75歳だった儀助が映画では77歳である。小説の儀助は私より1つ年下だが映画では1つ上だ。何故か得心する。この二十数年の社会の高齢化シフトを反映しているのだろう。
原作を改変した箇所はいくつかあり、それぞれに納得できて面白い。儀助の従兄弟の長子・渡辺槙男が最後に登場するのには驚いた。原作では名前が出てくるだけの人物である。渡辺槙男を登場させたのは、儀助の屋敷の相続人に指定されたからである。
吉田監督がトークでも述べていたが、この映画では屋敷のウエイトが高い。古い屋敷には記憶が多重的に刻み込まれている。畳み込まれた時間が錯綜的に流れる不思議な空間である。映画『敵』はそんな時空を表現した作品になっている。
上映後にはトークイベンがあった。吉田大八監督に若手の奥山由之氏(映画監督、写真家)がインタビューする形のトークだった。吉田監督は「原作にかなり忠実な映画です。スピリットでは…」と語っていた。その通りだとは思うが、当然ながら映画表現は小説表現とは異なる。
10年前に退職した元大学教授・渡辺儀助の生活を描いたこの映画はモノクロである。儀助が一人で暮らしている古い屋敷がモノクロにマッチしている。冒頭、儀助の起床、朝食の支度、朝食、歯磨き、洗濯、掃除、講演依頼電話への対応、パソコンを使った原稿執筆などの場面が坦々と流れる。原作小説の端正な世界引き込まれて行く心地よさを感じた。
原作の小説では、薄い膜を通した回想のような世界を感じた。映画は即物的表現がメインである。映像からは具体的でリアルな感触が伝わってくる。米を研ぐ手慣れた様子に感心し、朝食の咀嚼に美味を感じた。この映画に出てくる食べ物は美味しそうに見える。儀助が自身の生活演出に満足しているように見えるからだろう。
原作で75歳だった儀助が映画では77歳である。小説の儀助は私より1つ年下だが映画では1つ上だ。何故か得心する。この二十数年の社会の高齢化シフトを反映しているのだろう。
原作を改変した箇所はいくつかあり、それぞれに納得できて面白い。儀助の従兄弟の長子・渡辺槙男が最後に登場するのには驚いた。原作では名前が出てくるだけの人物である。渡辺槙男を登場させたのは、儀助の屋敷の相続人に指定されたからである。
吉田監督がトークでも述べていたが、この映画では屋敷のウエイトが高い。古い屋敷には記憶が多重的に刻み込まれている。畳み込まれた時間が錯綜的に流れる不思議な空間である。映画『敵』はそんな時空を表現した作品になっている。
『シビル・ウォー』は米国の内戦を追う戦場カメラマンの話 ― 2024年11月28日
映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を那覇市のシネマパレットで観た。現代の米国が内戦に突入した世界を描いた架空の同時代戦争映画だ。
カリフォルニアとテキサスを中心とするWF(西部勢力)と政府軍の内戦状況のなか、女性戦場カメラマンら4人のジャーナリストが大統領インタビューというスクープのために車でワシントンDCを目指す話である。内戦で荒廃した世界のロードームービーの趣がある。
戦闘場面だけでなく無政府状態での私刑や大量虐殺が描かれていて、現代世界で内戦が勃発したときの悲惨さが伝わってくる。
内戦の原因などは語られていない。半世紀以上昔に筒井康隆氏が描いた『東海道戦争』の開戦理由は「東京が攻めてくるから」「大阪が攻めてくるから」だった。内戦とは防衛と攻撃がないまぜになりやすいのかもしれない。
この映画で面白いと思ったのは、内戦下にあって「あえて内戦を見ない」という態度をとる人や町が存在することだ。中立や無関心とは少し違うように思う。積極的に殻にこもるという生き方であり、そのためには殻が頑丈でなければならない。現代的な態度のひとつかもしれない。
映画を観ながら、戦場カメラマンとは不思議な仕事だとあらためて思った。大きな成果をあげた戦場カメラマンは多いし、戦場で命を落としたカメラマンも少なくない。戦場の実情を伝え、平和に資するのが彼らの使命だと思うが、過酷な仕事である。戦場カメラマンという仕事がなくなる世界になればいいはずだが、当分は無理だろう。戦場カメラマンがいなくなり、戦場だけが残る――そんな世界になると恐ろしい。
カリフォルニアとテキサスを中心とするWF(西部勢力)と政府軍の内戦状況のなか、女性戦場カメラマンら4人のジャーナリストが大統領インタビューというスクープのために車でワシントンDCを目指す話である。内戦で荒廃した世界のロードームービーの趣がある。
戦闘場面だけでなく無政府状態での私刑や大量虐殺が描かれていて、現代世界で内戦が勃発したときの悲惨さが伝わってくる。
内戦の原因などは語られていない。半世紀以上昔に筒井康隆氏が描いた『東海道戦争』の開戦理由は「東京が攻めてくるから」「大阪が攻めてくるから」だった。内戦とは防衛と攻撃がないまぜになりやすいのかもしれない。
この映画で面白いと思ったのは、内戦下にあって「あえて内戦を見ない」という態度をとる人や町が存在することだ。中立や無関心とは少し違うように思う。積極的に殻にこもるという生き方であり、そのためには殻が頑丈でなければならない。現代的な態度のひとつかもしれない。
映画を観ながら、戦場カメラマンとは不思議な仕事だとあらためて思った。大きな成果をあげた戦場カメラマンは多いし、戦場で命を落としたカメラマンも少なくない。戦場の実情を伝え、平和に資するのが彼らの使命だと思うが、過酷な仕事である。戦場カメラマンという仕事がなくなる世界になればいいはずだが、当分は無理だろう。戦場カメラマンがいなくなり、戦場だけが残る――そんな世界になると恐ろしい。
映画『箱男 The Box Man』は意外に原作通り ― 2024年09月05日
渋谷のユーロスペースで映画『箱男 The Box Man』(原作:安部公房、監督:石井岳龍、出演:永瀬正敏、浅野忠信、佐藤浩市、白本彩奈、他)を観た。
ロビーに箱男の段ボール箱を置いていた。かなりボロボロなので、箱男の残骸にも見える。実物の段ボール箱は意外に大きく、存在感があり、かなり不気味である。
32年前、安部公房は石井監督に「娯楽映画にしてほしい」と言ったそうだ。この映画は、27年前に撮影直前になって制作中止となり、石井監督の執念の持続で安部公房生誕100年の今年、公開にこぎつけた。
どう作れば、あのメタフィクション的で難解な『箱男』が娯楽映画になるのだろうかと思いながら映画館に足を運んだ。観終えて、娯楽映画になっているかは疑問だった。箱男(永瀬正敏)と贋箱男(浅野忠信)の格闘シーンや軍医(佐藤浩市)の奇怪なふるまいなど、娯楽映画的に楽しめるシーンは多い。だが、原作と同様に話が迷路になっていて、わけがわからなくなってくる。
原作では「記録(小説『箱男』の本文?)」の書き手がだれかが不分明になっていき、この箇所の映画表現は困難だと思った。ところが、映画でもその部分を取り入れている。箱男とは見る存在ではなく記録する存在である、との認識にはナルホドと思った。
原作の登場人物は「葉子」以外は記号化されていて、そもそも別人なのか同一人物なのかも怪しくなる。俳優が演じる映画では、「わたし」「贋医者」「軍医」を個別の肉体が表現するので、多少はくっきりする。
そして、この映画は私が想定した以上に原作に忠実に作られていると感じた。原作の解釈のひとつの提示であり、あの小説を読み解く大きな手助けにもなる。その意味では、かなり重要な映画だと思う。
安部公房が「娯楽映画にしてほしい」と述べたのは、『箱男』には娯楽映画になる要素が潜んでいると考えたからだろう。その視点での読み解きのヒントを与えてくれるのが、この映画である。
映画を観終えて、ロビーの段ボールの残骸を眺め、箱男とは抜け殻かもしれないとも感じた。
ロビーに箱男の段ボール箱を置いていた。かなりボロボロなので、箱男の残骸にも見える。実物の段ボール箱は意外に大きく、存在感があり、かなり不気味である。
32年前、安部公房は石井監督に「娯楽映画にしてほしい」と言ったそうだ。この映画は、27年前に撮影直前になって制作中止となり、石井監督の執念の持続で安部公房生誕100年の今年、公開にこぎつけた。
どう作れば、あのメタフィクション的で難解な『箱男』が娯楽映画になるのだろうかと思いながら映画館に足を運んだ。観終えて、娯楽映画になっているかは疑問だった。箱男(永瀬正敏)と贋箱男(浅野忠信)の格闘シーンや軍医(佐藤浩市)の奇怪なふるまいなど、娯楽映画的に楽しめるシーンは多い。だが、原作と同様に話が迷路になっていて、わけがわからなくなってくる。
原作では「記録(小説『箱男』の本文?)」の書き手がだれかが不分明になっていき、この箇所の映画表現は困難だと思った。ところが、映画でもその部分を取り入れている。箱男とは見る存在ではなく記録する存在である、との認識にはナルホドと思った。
原作の登場人物は「葉子」以外は記号化されていて、そもそも別人なのか同一人物なのかも怪しくなる。俳優が演じる映画では、「わたし」「贋医者」「軍医」を個別の肉体が表現するので、多少はくっきりする。
そして、この映画は私が想定した以上に原作に忠実に作られていると感じた。原作の解釈のひとつの提示であり、あの小説を読み解く大きな手助けにもなる。その意味では、かなり重要な映画だと思う。
安部公房が「娯楽映画にしてほしい」と述べたのは、『箱男』には娯楽映画になる要素が潜んでいると考えたからだろう。その視点での読み解きのヒントを与えてくれるのが、この映画である。
映画を観終えて、ロビーの段ボールの残骸を眺め、箱男とは抜け殻かもしれないとも感じた。
映画字幕をめぐるアレコレは面白い ― 2024年08月22日
映画字幕翻訳者が書いたドストエフスキー紹介本『ひらけ! ドスワールド』の軽妙な文章が面白かったので、同じ著者の次のエッセイを読んだ。
『字幕屋のホンネ:映画は日本語訳こそが面白い』(太田直子/知恵の森文庫/光文社/2019.2)
映画字幕翻訳にまつわるアレコレを暴露したエッセイである。身近に接している映画字幕の背景に私の知らないさまざまな事情があると知り、「へぇー」と思いながら楽しく読了した。
本書の原題は『字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ』(2007年刊)で、著者の最初の本である。著者は2016年に56歳で亡くなっている。著者の死後3年の文庫化にあたって改題している。
私は原題の方がいいと思う。内容にもマッチしている。生前の著者は改題を承知していたのだろうか。文庫化にあたって、版元が独自の営業的判断で改題したのかもしれない。原題は一部の人にはウケるかもしれないが、何を言いたいのかわかりにくい。そもそも長すぎる。多くの読者に売るには、もっと短くてわかりやすい題名がいいと、誰かが判断した可能性もある。
――こんなことを考えたのは、売り手のオトナの事情のアレコレがもたらすアレコレが、著者が本書で描いている字幕をめぐる状況とパラレルだと感じたからである。入れ子細工のようで面白い。
映画字幕にはさまざまな制約があり、俳優の台詞をそのまま翻訳しているわけではない。一画面で容易に読み取れる字数制限があるのは当然だが、それ以外にもさまざまな制約があると知った。台詞のない余韻画面にまで字幕を要求されることもあるそうだ。
いずれにしても、いかに少ない文字数で過不足なく伝えるかの技術は興味深い。文章を、より「わかりやすく」、より「短く」する技術は重要で有用だと思う。
本書は、字幕をネタに現代の日本語へのいろいろな違和感も提示している。「そんなに叫んでどうするの~「!」の話」では「!」の多用への苦言を呈している。にもかかわらず、本書の章題では「!」を連発し、本書(原版)の後に出した本のタイトルは『ひらけ! ドスワールド』だ。
著者のそんなところにも面白さを感じる。
『字幕屋のホンネ:映画は日本語訳こそが面白い』(太田直子/知恵の森文庫/光文社/2019.2)
映画字幕翻訳にまつわるアレコレを暴露したエッセイである。身近に接している映画字幕の背景に私の知らないさまざまな事情があると知り、「へぇー」と思いながら楽しく読了した。
本書の原題は『字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ』(2007年刊)で、著者の最初の本である。著者は2016年に56歳で亡くなっている。著者の死後3年の文庫化にあたって改題している。
私は原題の方がいいと思う。内容にもマッチしている。生前の著者は改題を承知していたのだろうか。文庫化にあたって、版元が独自の営業的判断で改題したのかもしれない。原題は一部の人にはウケるかもしれないが、何を言いたいのかわかりにくい。そもそも長すぎる。多くの読者に売るには、もっと短くてわかりやすい題名がいいと、誰かが判断した可能性もある。
――こんなことを考えたのは、売り手のオトナの事情のアレコレがもたらすアレコレが、著者が本書で描いている字幕をめぐる状況とパラレルだと感じたからである。入れ子細工のようで面白い。
映画字幕にはさまざまな制約があり、俳優の台詞をそのまま翻訳しているわけではない。一画面で容易に読み取れる字数制限があるのは当然だが、それ以外にもさまざまな制約があると知った。台詞のない余韻画面にまで字幕を要求されることもあるそうだ。
いずれにしても、いかに少ない文字数で過不足なく伝えるかの技術は興味深い。文章を、より「わかりやすく」、より「短く」する技術は重要で有用だと思う。
本書は、字幕をネタに現代の日本語へのいろいろな違和感も提示している。「そんなに叫んでどうするの~「!」の話」では「!」の多用への苦言を呈している。にもかかわらず、本書の章題では「!」を連発し、本書(原版)の後に出した本のタイトルは『ひらけ! ドスワールド』だ。
著者のそんなところにも面白さを感じる。
映画『PERFECT DAYS』の主役は公共トイレか? ― 2024年02月27日
役所広司がカンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞して話題になった映画『PERFECT DAYS』(監督:ヴィム・ヴェンダース)を観た。公共トイレ清掃員の日常を淡々と描いた映画と聞いていたので、観る前から一定のイメージが頭の中にあった。そのイメージからさほど逸れない想定通りの映画だった。
一人暮らしの中年のトイレ清掃員の早朝の目覚めで映画は始まる。朝のルーティンを経て軽のワンボックスカーで現場に出勤、いくつかのトイレの清掃を終えて帰宅し、自転車で開店直後の銭湯に行って湯に浸かり、小さな居酒屋で軽く一杯飲む。帰宅後、就寝前に布団に寝そべったまま少々の読書、やがて本を閉じて消灯、眠りにつく。
そんな日常の繰り返しを表現するだけで映画になるのかと心配になる。小さな出来事はいろいろあっても、物語が展開されるわけではない。でも、退屈することなく観終えた。人生とは小さな出来事の繰り返し――という当然のことを突き付けられ気分になる。
この映画で驚いたのは、公共トイレが綺麗なことである。どれもデザインが凝っている。主役はこれらの公共トイレかもしれない。
一人暮らしの中年のトイレ清掃員の早朝の目覚めで映画は始まる。朝のルーティンを経て軽のワンボックスカーで現場に出勤、いくつかのトイレの清掃を終えて帰宅し、自転車で開店直後の銭湯に行って湯に浸かり、小さな居酒屋で軽く一杯飲む。帰宅後、就寝前に布団に寝そべったまま少々の読書、やがて本を閉じて消灯、眠りにつく。
そんな日常の繰り返しを表現するだけで映画になるのかと心配になる。小さな出来事はいろいろあっても、物語が展開されるわけではない。でも、退屈することなく観終えた。人生とは小さな出来事の繰り返し――という当然のことを突き付けられ気分になる。
この映画で驚いたのは、公共トイレが綺麗なことである。どれもデザインが凝っている。主役はこれらの公共トイレかもしれない。
映画『ナポレオン』はアッと言う間の2時間半 ― 2024年01月07日
公開中の映画『ナポレオン』(監督:リドリー・スコット、主演:ホアキン・フェニックス)を観た。2時間半を超える大作、戦闘シーンは大迫力だ。ダヴィドの絵画を動画で再現した戴冠式も見ごたえがある。ナポレオンの事蹟を2時間半で綴るのだからダイジェストにならざるを得ないが、ナポレオン時代の壮大な絵巻物を観た気分である。
昨年末、ナポレオン関連の本数冊(岩波新書、世界史リブレットなど)を読んだばかかりなので、私の頭の中に一定のナポレオンのイメージができている。映画のナポレオンは、そのイメージとは少し異なっていた。歴史研究者と映画製作者との切り口の違いをあらためて認識し、それを面白く感じた。
ナポレオンとジョゼフィーヌを中心に据えた映画である。ナポレオンが軍人として頭角を現していく頃からセントヘレナ島で没するまでの二十数年を、ナポレオンのジョゼフィーヌへの思いに焦点を当てて描いている。
エジプト遠征の途中でナポレオンが少人数で帰国した主因を、ジョゼフィーヌの浮気を知ったことにしている。ナポレオンがエルバ島に流されたとき、すでにジョゼフィーヌを離婚しオーストリア皇女と再婚しているが、エルバ島脱出を決意するのは、ジョゼフィーヌとロシア皇帝の交際の報に接して怒りに燃えたせいにしている。ワーテルローで敗れた遠因をジョゼフィーヌの死を知った失意としているようにも見える。映画らしい目のつけ所だと感心した。史実にどれだけ近いか遠いか、私にはわからないが。
昨年末、ナポレオン関連の本数冊(岩波新書、世界史リブレットなど)を読んだばかかりなので、私の頭の中に一定のナポレオンのイメージができている。映画のナポレオンは、そのイメージとは少し異なっていた。歴史研究者と映画製作者との切り口の違いをあらためて認識し、それを面白く感じた。
ナポレオンとジョゼフィーヌを中心に据えた映画である。ナポレオンが軍人として頭角を現していく頃からセントヘレナ島で没するまでの二十数年を、ナポレオンのジョゼフィーヌへの思いに焦点を当てて描いている。
エジプト遠征の途中でナポレオンが少人数で帰国した主因を、ジョゼフィーヌの浮気を知ったことにしている。ナポレオンがエルバ島に流されたとき、すでにジョゼフィーヌを離婚しオーストリア皇女と再婚しているが、エルバ島脱出を決意するのは、ジョゼフィーヌとロシア皇帝の交際の報に接して怒りに燃えたせいにしている。ワーテルローで敗れた遠因をジョゼフィーヌの死を知った失意としているようにも見える。映画らしい目のつけ所だと感心した。史実にどれだけ近いか遠いか、私にはわからないが。
『北北西に進路を取れ』の「北北西」の謎 ― 2023年11月26日
ヒッチコックの有名映画はいくつか観ているが、1959年の『北北西に進路を取れ』は未見だった。タイトルは航海映画を思わせるのに、映画のなかに「北北西」が出てこないとは聞いていた。いずれ観ようと、テレビ放映を録画していたのを、ついに観た(録画したまま未見の映画は数十本、いつになったら観るのか自分でも不明)。
別人に間違えられた広告マンが謎の組織に追いかけられる話である。74年前の映画だから冗長に感じる部分もあるが、飽きることなく楽しめた。往年の米国の雰囲気を感得できるのがうれしい。
問題はタイトルである。『謎解き「ハムレット」』という本には次の記述がある。
「ハムレットが「俺の気が狂うのは北北西の風が吹くときだけだ。南風なら、鷹の子と糸鋸の区別はつく」といったわけのわからない台詞を言うのも、ギルデンスターンらを煙に巻くための佯狂だ。この台詞から題名を借りたアルフレッド・ヒッチコック監督の映画『北北西に進路を取れ』は、ある日突然ひとりの男が不可解な事件に巻きこまれてしまう不条理を描くものだが、この映画と同様に、狂っているのは主人公ではなくて、彼の陥った状況のほうかもしれない。」
ネットで調べると、このタイトルがハムレット由来というのはひとつの説にすぎないようだ。
映画の原題は"North by Northwest"、実在しない方位だそうだ。北北西は"North Northwest"である。ハムレットも"North Northwest"と言っている。byを使った"Northwest by North"という方位はあり、これは北西と北北西の間の方向になる。
ヒッチコックは、"North by Northwest"がコンパスに実在しないことをふまえて「タイトルがこの映画の全体を象徴している」と述べているが、公開後の後付けの弁の可能性がある。
このタイトルは"North Northwest"のつもりで間違えたかのだろうか。何らかの効果を考えてあえて"North by Northwest"としたのだろうか。ネイティブの意見を聞いてみたい。
別人に間違えられた広告マンが謎の組織に追いかけられる話である。74年前の映画だから冗長に感じる部分もあるが、飽きることなく楽しめた。往年の米国の雰囲気を感得できるのがうれしい。
問題はタイトルである。『謎解き「ハムレット」』という本には次の記述がある。
「ハムレットが「俺の気が狂うのは北北西の風が吹くときだけだ。南風なら、鷹の子と糸鋸の区別はつく」といったわけのわからない台詞を言うのも、ギルデンスターンらを煙に巻くための佯狂だ。この台詞から題名を借りたアルフレッド・ヒッチコック監督の映画『北北西に進路を取れ』は、ある日突然ひとりの男が不可解な事件に巻きこまれてしまう不条理を描くものだが、この映画と同様に、狂っているのは主人公ではなくて、彼の陥った状況のほうかもしれない。」
ネットで調べると、このタイトルがハムレット由来というのはひとつの説にすぎないようだ。
映画の原題は"North by Northwest"、実在しない方位だそうだ。北北西は"North Northwest"である。ハムレットも"North Northwest"と言っている。byを使った"Northwest by North"という方位はあり、これは北西と北北西の間の方向になる。
ヒッチコックは、"North by Northwest"がコンパスに実在しないことをふまえて「タイトルがこの映画の全体を象徴している」と述べているが、公開後の後付けの弁の可能性がある。
このタイトルは"North Northwest"のつもりで間違えたかのだろうか。何らかの効果を考えてあえて"North by Northwest"としたのだろうか。ネイティブの意見を聞いてみたい。




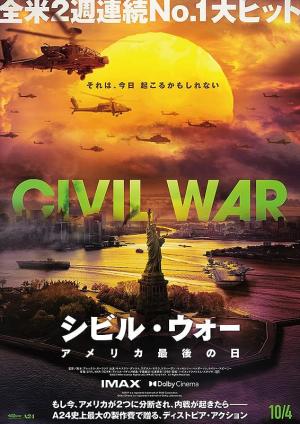





最近のコメント