ビザンツのしたたかな強さを語る『ビザンツ帝国生存戦略の一千年』 ― 2024年04月10日
先日読んだビザンツ史家による『ヨーロッパ史』はヨーロッパ史の精神的ベースとしてのビザンツを論じていたが、やや抽象的・哲学的で私には難解だった。一昨年から昨年前半にかけてビザンツ史がマイブームになり十数冊の一般書を読んだが、すでに記憶が薄れかけている。
読んだ本の内容を忘れるのは仕方ないが、多少でも記憶を掘りおこす心づもりで次の本を読んだ。
『ビザンツ帝国生存戦略の一千年』(ジョナサン・ハリス/井上浩一訳/白水社)
著者は英国のビザンツ史研究者、約350頁の本書はビザンツ帝国の通史である。コンスタンティヌス大帝(在306-337)の時代から1453年のコンスタンティノープル陥落までの1000年を、どの時代にも満遍なく目配りして記述している。記述は面白く、読みにくくはないが、読了には思いのほかの時間を要した。さまざまな事象が繰り返される1000年の通史を読むのは疲れる。ぐったりした。
著者は序章で、ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において、ビザンツ帝国の「臆病と内紛」を強調していると指摘している。ギボン再読中の私も著者に共感する。18世紀啓蒙主義(ギボン)に限らず西欧のビザンツ観には偏見がある。「臆病と内紛」だけの帝国が1000年も持続するだろうか。本書は、ビザンツが1000年も続いた理由を解き明かす通史である。1000年続くには、したたかな生存戦略があった。書名通りの内容の本だった。
帝国は軍事力だけでは維持できない。さまざまな外敵に囲まれ、首都の皇帝や官僚、地方の軍人貴族たちの緊張関係のなかで帝国を持続させるには、軍事力に加えて財力や文化の力(宗教?)をベースにした政治力が必要である。簒奪の繰り返しにも見えるビザンツ史には、複雑に変動する歴史の面白さがある。
本書終章の末尾を引用する。
「ビザンツ帝国は絶えず国境に押し寄せる人の波を、みずからの利益に変えようと努力した。そのために、お互いを戦わせたり、一部の者を国境内に取り込んでみずからの人的資源を強化したり、自分たちの宗教や文化に同化させたりした。(…)ビザンツ帝国の最大の遺産は、もっとも厳しい逆境にあっても、他者をなじませ統合する能力にこそ、社会の強さがあるという教訓である。」
いくつかの本が、ビザンツへの偏見として「権謀術数」「お追従者」「画一的」「官僚的」「軟弱」「複雑怪奇」などを挙げていた。考えてみれば、これらの偏見は皮相的で浅薄なビザンツ観であり、その背後にあるリアルな戦略という本質が見えていなかったにすぎない。本書を読んで、そう認識した。
読んだ本の内容を忘れるのは仕方ないが、多少でも記憶を掘りおこす心づもりで次の本を読んだ。
『ビザンツ帝国生存戦略の一千年』(ジョナサン・ハリス/井上浩一訳/白水社)
著者は英国のビザンツ史研究者、約350頁の本書はビザンツ帝国の通史である。コンスタンティヌス大帝(在306-337)の時代から1453年のコンスタンティノープル陥落までの1000年を、どの時代にも満遍なく目配りして記述している。記述は面白く、読みにくくはないが、読了には思いのほかの時間を要した。さまざまな事象が繰り返される1000年の通史を読むのは疲れる。ぐったりした。
著者は序章で、ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において、ビザンツ帝国の「臆病と内紛」を強調していると指摘している。ギボン再読中の私も著者に共感する。18世紀啓蒙主義(ギボン)に限らず西欧のビザンツ観には偏見がある。「臆病と内紛」だけの帝国が1000年も持続するだろうか。本書は、ビザンツが1000年も続いた理由を解き明かす通史である。1000年続くには、したたかな生存戦略があった。書名通りの内容の本だった。
帝国は軍事力だけでは維持できない。さまざまな外敵に囲まれ、首都の皇帝や官僚、地方の軍人貴族たちの緊張関係のなかで帝国を持続させるには、軍事力に加えて財力や文化の力(宗教?)をベースにした政治力が必要である。簒奪の繰り返しにも見えるビザンツ史には、複雑に変動する歴史の面白さがある。
本書終章の末尾を引用する。
「ビザンツ帝国は絶えず国境に押し寄せる人の波を、みずからの利益に変えようと努力した。そのために、お互いを戦わせたり、一部の者を国境内に取り込んでみずからの人的資源を強化したり、自分たちの宗教や文化に同化させたりした。(…)ビザンツ帝国の最大の遺産は、もっとも厳しい逆境にあっても、他者をなじませ統合する能力にこそ、社会の強さがあるという教訓である。」
いくつかの本が、ビザンツへの偏見として「権謀術数」「お追従者」「画一的」「官僚的」「軟弱」「複雑怪奇」などを挙げていた。考えてみれば、これらの偏見は皮相的で浅薄なビザンツ観であり、その背後にあるリアルな戦略という本質が見えていなかったにすぎない。本書を読んで、そう認識した。
『ヨーロッパ史』は、やや抽象的な歴史エッセイ ― 2024年03月31日
『ヨーロッパ史:拡大と統合の力学』(大月康弘/岩波新書)
朝日新聞(2024.3.23)の書評で、ビザンツ史の専門家が書いた本書を「西欧中心の歴史観に異議を唱える」と紹介していた。それを読んで、すぐに購入した。
私は一昨年からビザンツ史の本を何冊か読み、よく知らなかったこの「帝国」の面白さに魅せられている。また、西欧中心歴史観の見直しは、高齢の私が歴史書を読む際のテーマの一つだ。だから、大きな期待を抱いて本書を読み始めた。だが、思った以上の難物だった。
本書は「ヨーロッパ史とは何か」というやや抽象的な課題を論じていて、キー概念は「キリスト教ローマ帝国」である。ビザンツ帝国が自らを「ローマ帝国」と自認していたことをベースに、古代末期から中世・近代・現代に至るヨーロッパを支えてきた観念を「キリスト教ローマ帝国」という捉え方で論じている。
「時代精神」「キリスト教的時間意識」「終末意識」などの抽象概念や「当為」といった哲学用語が多く、すらすらとは読めない。私の知らない歴史研究者たちの言説紹介も多い。かなり専門的でやや難解な歴史エッセイである。断片的には面白い話も多いが全体像をつかみ難い。いずれ、覚悟して再読れば理解が深まるかもしれない。
本書が描くヨーロッパの原点は「キリスト教ローマ帝国」としてのビザンツ帝国であり、それとフランク王国の登場やアラブ・イスラムの侵入が絡んで「キリスト教ローマ帝国」たるヨーロッパ史が始まるというストーリーになっている。
著者は「おわりに」で次のように述べている。
「ヨーロッパといえば、イギリス、フランス、ドイツと三つの国を挙げる人は多い。これにイタリアを加え、あるいはスペインを含めたいと思うことだろう。私であれば、すでに第3章で述べたように、東欧、ギリシア、トルコ、またキプロスなども当然ながらキリスト教世界としての基層を共有する「ヨーロッパ」だ、としたいところである。」
1453年、コンスタンティノープルを陥したオスマン帝国のメフメト2世は、帝都侵入後「ルーム・カエサル」と称したそうだ。本書でそれを知って驚いた。
朝日新聞(2024.3.23)の書評で、ビザンツ史の専門家が書いた本書を「西欧中心の歴史観に異議を唱える」と紹介していた。それを読んで、すぐに購入した。
私は一昨年からビザンツ史の本を何冊か読み、よく知らなかったこの「帝国」の面白さに魅せられている。また、西欧中心歴史観の見直しは、高齢の私が歴史書を読む際のテーマの一つだ。だから、大きな期待を抱いて本書を読み始めた。だが、思った以上の難物だった。
本書は「ヨーロッパ史とは何か」というやや抽象的な課題を論じていて、キー概念は「キリスト教ローマ帝国」である。ビザンツ帝国が自らを「ローマ帝国」と自認していたことをベースに、古代末期から中世・近代・現代に至るヨーロッパを支えてきた観念を「キリスト教ローマ帝国」という捉え方で論じている。
「時代精神」「キリスト教的時間意識」「終末意識」などの抽象概念や「当為」といった哲学用語が多く、すらすらとは読めない。私の知らない歴史研究者たちの言説紹介も多い。かなり専門的でやや難解な歴史エッセイである。断片的には面白い話も多いが全体像をつかみ難い。いずれ、覚悟して再読れば理解が深まるかもしれない。
本書が描くヨーロッパの原点は「キリスト教ローマ帝国」としてのビザンツ帝国であり、それとフランク王国の登場やアラブ・イスラムの侵入が絡んで「キリスト教ローマ帝国」たるヨーロッパ史が始まるというストーリーになっている。
著者は「おわりに」で次のように述べている。
「ヨーロッパといえば、イギリス、フランス、ドイツと三つの国を挙げる人は多い。これにイタリアを加え、あるいはスペインを含めたいと思うことだろう。私であれば、すでに第3章で述べたように、東欧、ギリシア、トルコ、またキプロスなども当然ながらキリスト教世界としての基層を共有する「ヨーロッパ」だ、としたいところである。」
1453年、コンスタンティノープルを陥したオスマン帝国のメフメト2世は、帝都侵入後「ルーム・カエサル」と称したそうだ。本書でそれを知って驚いた。
大河ドラマ『光の君へ』の藤原実資への興味がわいた ― 2024年03月10日
私はNHKの大河ドラマの大半は見ていないが、今年の『光の君へ』は視聴を続けている。舞台が平安時代で紫式部が主人公という意外性に興味を抱いたからである。と言っても、藤原道長や紫式部についてほとんど知らない。源氏物語は口語訳すら読んだことはない。
ドラマは現代的で意外に面白い。かなりフィクションを盛り込んでいると感じるが、そもそもの史実を知らないので、どこまで史実を踏まえているかわからない。で、このドラマの時代考証を担当した研究者が著した次の新書を読んだ。
「紫式部と藤原道長」(倉本一宏/講談社現代新書)
著者は「はじめに」で次のように述べている。
「紫式部と道長が2024年の大河ドラマの主人公になることが決まったとき、平安時代を研究する者として、この時代の歴史にもやっと日が当たる時が来たと喜んだものである(その直後、喜んでばかりいられないことになってしまったが)。しかし、ドラマのストーリーが独り歩きして、紫式部と道長が実際にドラマで描かれるような人物であったと誤解さるのは、如何なものかとは思う。この本では、ここまでは史実であるという紫式部と道長のリアルな姿を、明らかにしていきたい。」
本書は一次史料で確認できる紫式部と藤原道長の姿を描いている。同時代に紫式部や道長に実際に接した人が残した史料から推測される二人のイメージは、ドラマとはかなり異なる。
ドラマは少年少女時代の道長と紫式部の出会いを描いているが、著者は次のように指摘している。
「五男とはいえ摂関家の子息である道長と無官の貧乏学者の女である紫式部が幼少期に顔を合わせた可能性は、ほぼゼロといったところであるが。」
史実で確認できない部分を想像力で膨らませるのが歴史ドラマの醍醐味だから、若い紫式部と道長が互いに引かれ合う設定はいいと思う。と言うか、そうでなければ物語は始まらない。
だが、本書によって紫式部が親子ほど年の離れた年長の藤原宣孝と結婚すると知って驚いた。ドラマの藤原宣孝は紫式部の父を時々訪れる気さくなオジサンで、佐々木蔵之介が演じている。今後、このオジサンが吉高由里子演じる紫式部に求婚する展開になるとは想像し難いが、史実を変えるわけにはいかないだろう。
本書には、藤原実資の記した日記『小右記』からの引用が多い。藤原実資はドラマでも日記を書き続ける不平不満の貴族として登場する。この人物は、この先長く道長や紫式部の生涯に付き合っていくことになるようだ。ドラマを観るうえで、実資への興味が大きくなった。
ドラマは現代的で意外に面白い。かなりフィクションを盛り込んでいると感じるが、そもそもの史実を知らないので、どこまで史実を踏まえているかわからない。で、このドラマの時代考証を担当した研究者が著した次の新書を読んだ。
「紫式部と藤原道長」(倉本一宏/講談社現代新書)
著者は「はじめに」で次のように述べている。
「紫式部と道長が2024年の大河ドラマの主人公になることが決まったとき、平安時代を研究する者として、この時代の歴史にもやっと日が当たる時が来たと喜んだものである(その直後、喜んでばかりいられないことになってしまったが)。しかし、ドラマのストーリーが独り歩きして、紫式部と道長が実際にドラマで描かれるような人物であったと誤解さるのは、如何なものかとは思う。この本では、ここまでは史実であるという紫式部と道長のリアルな姿を、明らかにしていきたい。」
本書は一次史料で確認できる紫式部と藤原道長の姿を描いている。同時代に紫式部や道長に実際に接した人が残した史料から推測される二人のイメージは、ドラマとはかなり異なる。
ドラマは少年少女時代の道長と紫式部の出会いを描いているが、著者は次のように指摘している。
「五男とはいえ摂関家の子息である道長と無官の貧乏学者の女である紫式部が幼少期に顔を合わせた可能性は、ほぼゼロといったところであるが。」
史実で確認できない部分を想像力で膨らませるのが歴史ドラマの醍醐味だから、若い紫式部と道長が互いに引かれ合う設定はいいと思う。と言うか、そうでなければ物語は始まらない。
だが、本書によって紫式部が親子ほど年の離れた年長の藤原宣孝と結婚すると知って驚いた。ドラマの藤原宣孝は紫式部の父を時々訪れる気さくなオジサンで、佐々木蔵之介が演じている。今後、このオジサンが吉高由里子演じる紫式部に求婚する展開になるとは想像し難いが、史実を変えるわけにはいかないだろう。
本書には、藤原実資の記した日記『小右記』からの引用が多い。藤原実資はドラマでも日記を書き続ける不平不満の貴族として登場する。この人物は、この先長く道長や紫式部の生涯に付き合っていくことになるようだ。ドラマを観るうえで、実資への興味が大きくなった。
『地中海の十字路=シチリアの歴史』を読んで沖縄を連想 ― 2024年03月06日
私は6年前にシチリアの古跡を巡るツアーに参加した。それに先立ってシチリア史の概説書を何冊か読んだ。だが、6年前に読んだ本の内容の大半は蒸発していて、シチリア史の何層にも堆積した複雑さの漠然たる印象が残っているだけだ。
あの複雑なシチリア史の復習をしようと思い、次の本を読んだ。1943年生まれの研究者による5年前の本である。
『地中海の十字路=シチリアの歴史』(藤澤房俊/講談社選書メチエ)
本書は、紀元前8世紀のギリシア植民市から20世紀の第2次世界大戦終結までのシチリア史を要領よく描いている。読了して、シチリアの歴史の複雑さと面白さをあらためて認識した。
ざっくり言えば1282年の「シチリアの晩禱」事件までは活気があり、それ以降は沈滞と翻弄の時代に思える。
シチリアと言えば、塩野七生が『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』で魅力的に描いたフェデリーコ2世が思い浮かぶ。「世界の驚異」と呼ばれた13世紀のこの皇帝に、本書はかなりのページを割き、その事績には神話・俗説も多いと述べている。フェデリーコ2世の施策(都市反乱の弾圧など)がイタリアの南北問題の歴史的要因の一つになったとも指摘している。意外な指摘だ。
18世紀末にシチリアを「再発見」したのは『イタリア紀行』を著したゲーテである。その再発見はオリエンタリズムであり、シチリア人にとっては「シチリアに無知なヨーロッパ人」の再発見だった、との見解が面白い。
マルクスもシチリア史に言及しているそうだ。マルクスは、以下のように要領よくまとめている。
「シチリア人は南と北のあらゆる人種が混血したものである。まず、原住民のシカーニ人、フェニキア人、カルタゴ人、ギリシア人、そして売買あるいは戦争によって世界各地からシチリアに連れてこられた奴隷、さらにアラブ人、ノルマン人、イタリア人との混血である。シチリア人は、あらゆる転変と推移の間にも、自らの自由のために戦ってきたし、戦い続けている。」
シチリアは歴史的に何度か独立を試みているが、現在はイタリアの特別自治州である。海に囲まれたシチリアの歴史は、海からやって来る「よそ者」に次々に支配・翻弄される歴史だった。最後にやって来た「よそ者」は第2次世界大戦末期の米英連合軍である。
私は現在、沖縄滞在中で、本書を沖縄で読んだ。そのせいか、シチリアと沖縄が二重写しになった。
あの複雑なシチリア史の復習をしようと思い、次の本を読んだ。1943年生まれの研究者による5年前の本である。
『地中海の十字路=シチリアの歴史』(藤澤房俊/講談社選書メチエ)
本書は、紀元前8世紀のギリシア植民市から20世紀の第2次世界大戦終結までのシチリア史を要領よく描いている。読了して、シチリアの歴史の複雑さと面白さをあらためて認識した。
ざっくり言えば1282年の「シチリアの晩禱」事件までは活気があり、それ以降は沈滞と翻弄の時代に思える。
シチリアと言えば、塩野七生が『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』で魅力的に描いたフェデリーコ2世が思い浮かぶ。「世界の驚異」と呼ばれた13世紀のこの皇帝に、本書はかなりのページを割き、その事績には神話・俗説も多いと述べている。フェデリーコ2世の施策(都市反乱の弾圧など)がイタリアの南北問題の歴史的要因の一つになったとも指摘している。意外な指摘だ。
18世紀末にシチリアを「再発見」したのは『イタリア紀行』を著したゲーテである。その再発見はオリエンタリズムであり、シチリア人にとっては「シチリアに無知なヨーロッパ人」の再発見だった、との見解が面白い。
マルクスもシチリア史に言及しているそうだ。マルクスは、以下のように要領よくまとめている。
「シチリア人は南と北のあらゆる人種が混血したものである。まず、原住民のシカーニ人、フェニキア人、カルタゴ人、ギリシア人、そして売買あるいは戦争によって世界各地からシチリアに連れてこられた奴隷、さらにアラブ人、ノルマン人、イタリア人との混血である。シチリア人は、あらゆる転変と推移の間にも、自らの自由のために戦ってきたし、戦い続けている。」
シチリアは歴史的に何度か独立を試みているが、現在はイタリアの特別自治州である。海に囲まれたシチリアの歴史は、海からやって来る「よそ者」に次々に支配・翻弄される歴史だった。最後にやって来た「よそ者」は第2次世界大戦末期の米英連合軍である。
私は現在、沖縄滞在中で、本書を沖縄で読んだ。そのせいか、シチリアと沖縄が二重写しになった。
『物語としての旧約聖書』の読み解きが興味深い ― 2024年03月02日
『ビジュアル版 聖書物語』に続いて次の関連書を読んだ。今年1月に出た新刊である。
『物語としての旧約聖書:人類史に何をもたらしたか』(月本昭男/NHKブックス)
私には本書はやや専門的に感じられた。読者が旧約聖書の内容をある程度把握していることを前提にしているように思える。旧約聖書の多様な解釈にウエイトを置いた本である。私は『聖書物語』を読んだばかりだったおかげで、何とか興味深く読了できた。
天地創造から楽園追放、ノアの洪水、アブラハム、出エジプトを経てカナン定住に至るまでの物語とその解釈が、特に面白かった。
アブラハムが神から愛児イサクを犠牲に献げと命じられて応じる話は、普通に考えれば奇怪である。著者は、この話がどのように解釈されてきたかをいろいろ紹介している。キルケゴールの「そのような不条理を『おそれとおののき』をもって受けとめること、そこにこそ神信仰の本質がある」という見解には「へぇー」と感心した。不条理の哲学だろうか。理解できたわけではない。
出エジプトが史実かどうかは不明だが、その後、イスラエルの民は「約束の地」カナンに定住する。「約束の地」と言ってもそこには先住者がいるのだから穏当ではない。旧約聖書の記述からは「軍事征服説」と「平和浸透説」の二つの解釈が成り立つそうだ。その他に社会学的視座から、貧農層が都市支配から「引き揚げた」という説や貧農層が「反乱」したという説もあるそうだ。
旧約聖書にたたみこまれているもの、反映されている「何か」を読み解く話はスリリングで面白い。
本書を読んで、私の印象に残った旧約聖書の性格は次の三点である。
・唯一神への信仰を強く主張している
・歴史観は因果応報思想である
・記述には矛盾も多く複眼的である
著者が述べているように、オリエントの強大国に翻弄され続けた弱小の民が残した旧約聖書が後世のキリスト教やイスラム教を生み出すことになるのは逆説的な現象である。その不思議に感慨をおぼえざるを得ない。
『物語としての旧約聖書:人類史に何をもたらしたか』(月本昭男/NHKブックス)
私には本書はやや専門的に感じられた。読者が旧約聖書の内容をある程度把握していることを前提にしているように思える。旧約聖書の多様な解釈にウエイトを置いた本である。私は『聖書物語』を読んだばかりだったおかげで、何とか興味深く読了できた。
天地創造から楽園追放、ノアの洪水、アブラハム、出エジプトを経てカナン定住に至るまでの物語とその解釈が、特に面白かった。
アブラハムが神から愛児イサクを犠牲に献げと命じられて応じる話は、普通に考えれば奇怪である。著者は、この話がどのように解釈されてきたかをいろいろ紹介している。キルケゴールの「そのような不条理を『おそれとおののき』をもって受けとめること、そこにこそ神信仰の本質がある」という見解には「へぇー」と感心した。不条理の哲学だろうか。理解できたわけではない。
出エジプトが史実かどうかは不明だが、その後、イスラエルの民は「約束の地」カナンに定住する。「約束の地」と言ってもそこには先住者がいるのだから穏当ではない。旧約聖書の記述からは「軍事征服説」と「平和浸透説」の二つの解釈が成り立つそうだ。その他に社会学的視座から、貧農層が都市支配から「引き揚げた」という説や貧農層が「反乱」したという説もあるそうだ。
旧約聖書にたたみこまれているもの、反映されている「何か」を読み解く話はスリリングで面白い。
本書を読んで、私の印象に残った旧約聖書の性格は次の三点である。
・唯一神への信仰を強く主張している
・歴史観は因果応報思想である
・記述には矛盾も多く複眼的である
著者が述べているように、オリエントの強大国に翻弄され続けた弱小の民が残した旧約聖書が後世のキリスト教やイスラム教を生み出すことになるのは逆説的な現象である。その不思議に感慨をおぼえざるを得ない。
『聖書物語』(木崎さと子)は神へのツッコミが面白い ― 2024年02月29日
先日、『ユダヤ人は、いつユダヤ人になったのか』を読み、自分が旧約聖書について無知だと認識し、かなり以前に入手したまま未読だった次の本を読んだ。
『ビジュアル版 聖書物語』(木崎さと子/講談社)
文学者の視点で聖書の内容を物語風に紹介した本である。前半の約三分の二が旧約聖書、後半の約三分の一が新約聖書だ。著者は1939年生まれの芥川賞作家、43歳でカトリックの受洗をしている。
聖書は超有名本だから目を通しておかねばと若い頃から思っていた。旧約の『創世記』『出エジプト記』、新約の『マタイ伝』だけは読んでいるはずだが、内容をよくおぼえていない。齢を重ね、いまさら聖書に取り組もうという気力は失せ、木崎氏の『聖書物語』が手頃と思って入手したのが数年前。それをやっと読了したのである。
私にとって旧約聖書のイメージは、小学生の頃に観た映画『十戒』のモーゼである。だが、あれは旧約のほんの一部に過ぎず、旧約の大半はおよそ千年にわたるイスラエル人の歴史を延々と語っているようだ。
本書を読んでいて、旧約のどこが「聖書」なのだろうという気がした。ありがたい教えを説いている書とは思えないのである。そこに面白さがあるのかもしれない。
旧約は史書ではなく伝説の集成に近く、人類の愚行を言い伝える書のように思える。その愚行はかなりゴチャゴチャしていて、頭に入りにくい。ざっくり言えば、人間は神への信仰と裏切りを繰り返し、神はそんな人間を懲らしめることを繰り返しているのである。
著者はキリスト教徒ではあるが、本書では神に対するかなり辛辣なツッコミが随所にある。聖者や預言者たちの言動に現代人の感覚から違和感を表明している箇所もある。私には、そんなところが面白かった。
後半の新約聖書はイエスの伝記という体裁で、かなりすっきりしていて読みやすい。個別の福音書それぞれを解説するのではなく、「マタイ」「マルコ」「ルカ」および「ヨハネ」による福音書をベースに、イエスの生誕から復活までの言動を解説し、それぞれの福音書における表現の違いを指摘している。初心者に親切な解説だ。
新約聖書はイエスの復活で終わるのではなく、その後のパウロによる宣教の旅があり、さらにはヨハネの黙示録もある。これらも簡潔に解説していて、なるほどと思った。
本書を読んで、私が何となく知っている故事や格言の多くが聖書由来だと知った。西欧キリスト教文化圏の人々の思考のベースを把握するには、旧約聖書・新約聖書の基本的な知識が必須だとあらためて認識した。
『ビジュアル版 聖書物語』(木崎さと子/講談社)
文学者の視点で聖書の内容を物語風に紹介した本である。前半の約三分の二が旧約聖書、後半の約三分の一が新約聖書だ。著者は1939年生まれの芥川賞作家、43歳でカトリックの受洗をしている。
聖書は超有名本だから目を通しておかねばと若い頃から思っていた。旧約の『創世記』『出エジプト記』、新約の『マタイ伝』だけは読んでいるはずだが、内容をよくおぼえていない。齢を重ね、いまさら聖書に取り組もうという気力は失せ、木崎氏の『聖書物語』が手頃と思って入手したのが数年前。それをやっと読了したのである。
私にとって旧約聖書のイメージは、小学生の頃に観た映画『十戒』のモーゼである。だが、あれは旧約のほんの一部に過ぎず、旧約の大半はおよそ千年にわたるイスラエル人の歴史を延々と語っているようだ。
本書を読んでいて、旧約のどこが「聖書」なのだろうという気がした。ありがたい教えを説いている書とは思えないのである。そこに面白さがあるのかもしれない。
旧約は史書ではなく伝説の集成に近く、人類の愚行を言い伝える書のように思える。その愚行はかなりゴチャゴチャしていて、頭に入りにくい。ざっくり言えば、人間は神への信仰と裏切りを繰り返し、神はそんな人間を懲らしめることを繰り返しているのである。
著者はキリスト教徒ではあるが、本書では神に対するかなり辛辣なツッコミが随所にある。聖者や預言者たちの言動に現代人の感覚から違和感を表明している箇所もある。私には、そんなところが面白かった。
後半の新約聖書はイエスの伝記という体裁で、かなりすっきりしていて読みやすい。個別の福音書それぞれを解説するのではなく、「マタイ」「マルコ」「ルカ」および「ヨハネ」による福音書をベースに、イエスの生誕から復活までの言動を解説し、それぞれの福音書における表現の違いを指摘している。初心者に親切な解説だ。
新約聖書はイエスの復活で終わるのではなく、その後のパウロによる宣教の旅があり、さらにはヨハネの黙示録もある。これらも簡潔に解説していて、なるほどと思った。
本書を読んで、私が何となく知っている故事や格言の多くが聖書由来だと知った。西欧キリスト教文化圏の人々の思考のベースを把握するには、旧約聖書・新約聖書の基本的な知識が必須だとあらためて認識した。
バビロニア捕囚が聖書とユダヤ人を作った…… ― 2024年02月10日
NHK出版から「世界史のリテラシー」というシリーズが刊行されている。教養番組のテキストのような形のムックである。そのなかの一冊を読んだ。
『ユダヤ人は、いつユダヤ人になったのか:バビロニア捕囚』(長谷川修一/世界史のリテラシー/NHK出版)
薄い本だから集中すれば1日で読めると思っていたが、想定外に時間がかかってしまった。半分近くまで読んで、雑事にかまけて数日おいて再開しようとしたが、それまで読んだ内容が頭から消えかかっていた。頭に入ってなかったのだ。仕方なく、最初から読み返した。
著者は、ユダヤ人のアイデンティティの源泉はバビロニア捕囚にあるとし、バビロニア捕囚とは何であったかを追究している(バビロン捕囚でなくバビロニア捕囚なのは歴史学的な視点)。
本書が私にとって読みやすくなかったのは、旧約聖書の内容をほとんど知らないからである。登場する人物にも馴染みがない。古代オリエント史やバビロニア捕囚の概要は把握しているつもりだったが、旧約聖書はきちんと読んでいない。
旧約学の専門家である著者は、本書において「旧約聖書」を「ヘブライ語聖書」と記述している。より中立的だからだ。確かに「旧約」という呼び方はキリスト教の視点だ。「新約」も「ギリシア語聖書」と呼ぶ方がいいかもしれないが、キリストがギリシア語を話したわけではないし……。
紀元前6世紀、ユダヤ人が南レヴァント(パレスチナ)の故地からバビロニア(現在のイラク)へ移住させられたというバビロニア捕囚という出来事について、同時代史料は少ないそうだ。バビロニア捕囚を詳しく述べているのはヘブライ語聖書である。
しかし、聖書の内容をそのまま史実と見なすことはできない。聖書を史料として参照するには史料批判が必要である。聖書の記述の背後にどんな史実があったかを、他の史料や考古学上の発見と突き合わせて推測するのだ。本書からは、聖書の史料批判的な読み方の面白さが伝わってくる。
征服者が支配地の住人の一部を強制的に移住させるのはよくある話で、バビロニア捕囚という出来事は古代オリエント史においてワン・オブ・ゼムの小事件に過ぎない。この2500年以上前の小事件が、現代にまで続く「ユダヤ人」を作ったそうだ。人間の集団が作り出す想像力の威力と、その持続力とをあらためて認識した。
『ユダヤ人は、いつユダヤ人になったのか:バビロニア捕囚』(長谷川修一/世界史のリテラシー/NHK出版)
薄い本だから集中すれば1日で読めると思っていたが、想定外に時間がかかってしまった。半分近くまで読んで、雑事にかまけて数日おいて再開しようとしたが、それまで読んだ内容が頭から消えかかっていた。頭に入ってなかったのだ。仕方なく、最初から読み返した。
著者は、ユダヤ人のアイデンティティの源泉はバビロニア捕囚にあるとし、バビロニア捕囚とは何であったかを追究している(バビロン捕囚でなくバビロニア捕囚なのは歴史学的な視点)。
本書が私にとって読みやすくなかったのは、旧約聖書の内容をほとんど知らないからである。登場する人物にも馴染みがない。古代オリエント史やバビロニア捕囚の概要は把握しているつもりだったが、旧約聖書はきちんと読んでいない。
旧約学の専門家である著者は、本書において「旧約聖書」を「ヘブライ語聖書」と記述している。より中立的だからだ。確かに「旧約」という呼び方はキリスト教の視点だ。「新約」も「ギリシア語聖書」と呼ぶ方がいいかもしれないが、キリストがギリシア語を話したわけではないし……。
紀元前6世紀、ユダヤ人が南レヴァント(パレスチナ)の故地からバビロニア(現在のイラク)へ移住させられたというバビロニア捕囚という出来事について、同時代史料は少ないそうだ。バビロニア捕囚を詳しく述べているのはヘブライ語聖書である。
しかし、聖書の内容をそのまま史実と見なすことはできない。聖書を史料として参照するには史料批判が必要である。聖書の記述の背後にどんな史実があったかを、他の史料や考古学上の発見と突き合わせて推測するのだ。本書からは、聖書の史料批判的な読み方の面白さが伝わってくる。
征服者が支配地の住人の一部を強制的に移住させるのはよくある話で、バビロニア捕囚という出来事は古代オリエント史においてワン・オブ・ゼムの小事件に過ぎない。この2500年以上前の小事件が、現代にまで続く「ユダヤ人」を作ったそうだ。人間の集団が作り出す想像力の威力と、その持続力とをあらためて認識した。
古典文学を通して世界史散策 ― 2024年01月09日
『20の古典で読み解く世界史』(本村凌二/PHP研究所)
ローマ史家・本村凌二氏による本書は、数年前に同じ出版社から出た『教養としてのローマ史/世界史』と同じ造本、テイストも似ている。読みやすい歴史エッセイだ。
20の古典の概要を紹介し、歴史家の眼でコメントしている。結末の紹介は避け、原典を読むよう促すが、やはり、すでに読んだ作品に関する話の方が興味深く読める。
本書が取り上げる20の古典のうち、私が読んでいるのは次の12点だ(冒頭数字は本書目次にある番号)。
『05 神曲』
『07 ドン・キホーテ』
『09 ハムレット』
『10 ロビンソン・クルーソー』
『11 ファウスト』
『12 ゴリオ爺さん』
『14 戦争と平和』
『15 カラマーゾフの兄弟』
『16 夜明け前』
『18 阿Q正伝』
『19 武器よさらば』
『20 ペスト』
古典とは若いうちの読むものだと思っていたが、この12点のうち青字の9点は60歳を過ぎて読んだ(『ハムレット』『カラマーゾフの兄弟』は再読or再々読)。若い頃にさほど古典に親しまなかったということである。私は61歳になった2010年以降は読了本の記録をExcelに残しているので、この十数年に読んだ本は検索できるのだ。
実は、本書を購入したのは昨年夏である。それ以降に読んだ数冊は本書を機に読んだ。本書を読む前に、かねてから気がかりだった名作を読もうと思ったのだ。
いずれにしても、本書によって、ささやかなわが読書体験のたな卸しをした気分になった。読書体験も時々反芻しないと忘却の沼底に沈んでしまう。
未読本は次の8点だ。
『01 イリアス/オデュセイア』
『02 史記列伝』
『03 英雄伝』
『04 三国志演義』
『06 デカメロン』
『08 アラビアンナイト』
『13 大いなる遺産』
『17 山猫』
「01」は『イリアス』だけ読んでいる。本書の紹介を読んで『オデュセイア』も読みたくなったが、この叙事詩は耳で訊きたい。著者は学生に英語版CDを訊かせているそうだ。いのつ日か、日本語オーディオ版が出るのを期待したい。
「02」の史記は入門書のダイジェストを読んだので、とりあえずそれ満足している。原典に挑戦する意欲はない。
「03」の『プルタルコス 英雄伝』は何篇かを拾い読みした。いずれ、ちくま学芸文庫版(全3冊)を読むつもりだが、いつになるかわからない。
「04」の三国志に関しては、十数年前に吉川英治版と北方謙三版を読んだので、『三国志演義』にまで手を伸ばす元気はない。
『06 デカメロン』は、2020年のコロナ禍の蟄居時代に読もうと思ったことがあるが、すでに機を逸っしてしまった。
『08 アラビアンナイト』に関しては、半世紀以上昔の学生時代に河出書房から出たバートン版『千夜一夜物語』(全10巻)を入手して拾い読みした。全巻読破はしていない。本書によって、西洋人編纂の『千夜一夜物語』が「好色にして残虐」を強調しているのは植民地支配正当化の反映だと知った。いつの日か読み返すことがあれば、留意すべきだ。
『13 大いなる遺産』は、本書の紹介に惹かれ、読みたくなった。
『17 山猫』は映画を観たので、それでいいかと思う。
これらの名作のなかで著者にとってのナンバーワンは『カラマーゾフの兄弟』だそうだ。私も同意見だ。
バルザックに関しては『21世紀の資本』の著者・ピケティの見解も紹介し、「人間喜劇」で19世紀の社会を丸ごと描いたのが歴史家にとって魅力だと述べている。ロンドンで資本論を執筆中のマルクスにとって、バルザックの小説は実社会の報告書だったと聞いたこともある。フィクションの力はあなどれない――本書全体を通して、あらためてそう感じる。
ローマ史家・本村凌二氏による本書は、数年前に同じ出版社から出た『教養としてのローマ史/世界史』と同じ造本、テイストも似ている。読みやすい歴史エッセイだ。
20の古典の概要を紹介し、歴史家の眼でコメントしている。結末の紹介は避け、原典を読むよう促すが、やはり、すでに読んだ作品に関する話の方が興味深く読める。
本書が取り上げる20の古典のうち、私が読んでいるのは次の12点だ(冒頭数字は本書目次にある番号)。
『05 神曲』
『07 ドン・キホーテ』
『09 ハムレット』
『10 ロビンソン・クルーソー』
『11 ファウスト』
『12 ゴリオ爺さん』
『14 戦争と平和』
『15 カラマーゾフの兄弟』
『16 夜明け前』
『18 阿Q正伝』
『19 武器よさらば』
『20 ペスト』
古典とは若いうちの読むものだと思っていたが、この12点のうち青字の9点は60歳を過ぎて読んだ(『ハムレット』『カラマーゾフの兄弟』は再読or再々読)。若い頃にさほど古典に親しまなかったということである。私は61歳になった2010年以降は読了本の記録をExcelに残しているので、この十数年に読んだ本は検索できるのだ。
実は、本書を購入したのは昨年夏である。それ以降に読んだ数冊は本書を機に読んだ。本書を読む前に、かねてから気がかりだった名作を読もうと思ったのだ。
いずれにしても、本書によって、ささやかなわが読書体験のたな卸しをした気分になった。読書体験も時々反芻しないと忘却の沼底に沈んでしまう。
未読本は次の8点だ。
『01 イリアス/オデュセイア』
『02 史記列伝』
『03 英雄伝』
『04 三国志演義』
『06 デカメロン』
『08 アラビアンナイト』
『13 大いなる遺産』
『17 山猫』
「01」は『イリアス』だけ読んでいる。本書の紹介を読んで『オデュセイア』も読みたくなったが、この叙事詩は耳で訊きたい。著者は学生に英語版CDを訊かせているそうだ。いのつ日か、日本語オーディオ版が出るのを期待したい。
「02」の史記は入門書のダイジェストを読んだので、とりあえずそれ満足している。原典に挑戦する意欲はない。
「03」の『プルタルコス 英雄伝』は何篇かを拾い読みした。いずれ、ちくま学芸文庫版(全3冊)を読むつもりだが、いつになるかわからない。
「04」の三国志に関しては、十数年前に吉川英治版と北方謙三版を読んだので、『三国志演義』にまで手を伸ばす元気はない。
『06 デカメロン』は、2020年のコロナ禍の蟄居時代に読もうと思ったことがあるが、すでに機を逸っしてしまった。
『08 アラビアンナイト』に関しては、半世紀以上昔の学生時代に河出書房から出たバートン版『千夜一夜物語』(全10巻)を入手して拾い読みした。全巻読破はしていない。本書によって、西洋人編纂の『千夜一夜物語』が「好色にして残虐」を強調しているのは植民地支配正当化の反映だと知った。いつの日か読み返すことがあれば、留意すべきだ。
『13 大いなる遺産』は、本書の紹介に惹かれ、読みたくなった。
『17 山猫』は映画を観たので、それでいいかと思う。
これらの名作のなかで著者にとってのナンバーワンは『カラマーゾフの兄弟』だそうだ。私も同意見だ。
バルザックに関しては『21世紀の資本』の著者・ピケティの見解も紹介し、「人間喜劇」で19世紀の社会を丸ごと描いたのが歴史家にとって魅力だと述べている。ロンドンで資本論を執筆中のマルクスにとって、バルザックの小説は実社会の報告書だったと聞いたこともある。フィクションの力はあなどれない――本書全体を通して、あらためてそう感じる。
さらに、ナポレオン本を読んだ ― 2023年12月24日
岩波新書の『ナポレオン』
に続いて次の2冊を読んだ。
『ナポレオン:英雄か独裁者か』(上垣豊/世界史リブレット人/山川出版社)
『図説ナポレオン:政治と戦争』(松蔦明男/ふくろうの本/河出書房新社)
前者リブレットはナポレオンの生涯を論評を交えつつ紹介していて読みやすい。ナポレオンには戦さ上手の将軍というイメージがあるが、ほとんど負けに近い戦さも多く、ブリューメル18日のクーデターもあやうく失敗するところだった。自己演出力に長けた強運の人だったようだ。
ロゼッタ・ストーンと言えばナポレオンである。それがなぜ大英博物館にあるのか不思議だったが、このリブレットで疑問が解消した。ナポレオンの脱出でエジプトに取り残された遠征軍が撤退したため、イギリス軍に奪われたのだ。
このリブレットで興味深かったのは、独裁と共和政が矛盾するとは考えられていなかったという指摘である。共和政の古代ローマにも独裁官制度があった。ナポレオンが皇帝になったときの憲法には「共和国政府はフランス人の皇帝という称号をもつ皇帝に託される」とあるそうだ。帝政の共和国だったのだ!?
後者の図説は写真の多い本だが、思いのほか歯ごたえがあった。評伝スタイルではなく、「ナポレオンの人物像」「ナポレオンと政治」「ナポレオンとフランス経済」「ナポレオンと宗教」「ナポレオンと戦争」などテーマごとに解説している。ナポレオンを社会史で捉える試みのようだ。従来の考え方に対して最近の学説を紹介するというスタイルが多く、やや専門的である。
ナポレオンが大陸封鎖をしても、イギリスの貴族はフランス産の高級ワインを飲んでいたという話を初めて知った。イギリス貴族とフランス醸造業者の利害が一致し、中立国商船を使った貿易が続いていたのだ。
ナポレオンがジョセフィーヌを離婚し、オーストリアの公女マリア・ルイサと再婚した件については、ナポレオンの威力に圧されてハプスブルク家が人身御供を出したとされてきたそうだ。だが本書(図説)は、結婚政策で知られるハプスブルク外交のナポレオン弱体化をねらった策だったとの見方を紹介している。面白い。
『ナポレオン:英雄か独裁者か』(上垣豊/世界史リブレット人/山川出版社)
『図説ナポレオン:政治と戦争』(松蔦明男/ふくろうの本/河出書房新社)
前者リブレットはナポレオンの生涯を論評を交えつつ紹介していて読みやすい。ナポレオンには戦さ上手の将軍というイメージがあるが、ほとんど負けに近い戦さも多く、ブリューメル18日のクーデターもあやうく失敗するところだった。自己演出力に長けた強運の人だったようだ。
ロゼッタ・ストーンと言えばナポレオンである。それがなぜ大英博物館にあるのか不思議だったが、このリブレットで疑問が解消した。ナポレオンの脱出でエジプトに取り残された遠征軍が撤退したため、イギリス軍に奪われたのだ。
このリブレットで興味深かったのは、独裁と共和政が矛盾するとは考えられていなかったという指摘である。共和政の古代ローマにも独裁官制度があった。ナポレオンが皇帝になったときの憲法には「共和国政府はフランス人の皇帝という称号をもつ皇帝に託される」とあるそうだ。帝政の共和国だったのだ!?
後者の図説は写真の多い本だが、思いのほか歯ごたえがあった。評伝スタイルではなく、「ナポレオンの人物像」「ナポレオンと政治」「ナポレオンとフランス経済」「ナポレオンと宗教」「ナポレオンと戦争」などテーマごとに解説している。ナポレオンを社会史で捉える試みのようだ。従来の考え方に対して最近の学説を紹介するというスタイルが多く、やや専門的である。
ナポレオンが大陸封鎖をしても、イギリスの貴族はフランス産の高級ワインを飲んでいたという話を初めて知った。イギリス貴族とフランス醸造業者の利害が一致し、中立国商船を使った貿易が続いていたのだ。
ナポレオンがジョセフィーヌを離婚し、オーストリアの公女マリア・ルイサと再婚した件については、ナポレオンの威力に圧されてハプスブルク家が人身御供を出したとされてきたそうだ。だが本書(図説)は、結婚政策で知られるハプスブルク外交のナポレオン弱体化をねらった策だったとの見方を紹介している。面白い。
岩波新書の『ナポレオン』は読みやすくて面白い ― 2023年12月20日
フランス革命の概説書(『革命と皇帝』、『フランス革命』)を読んだ流れでナポレオンの本を読んだ。いま公開中の映画『ナポレオン』の影響もある。近いうちにこの映画を観たいと思っている。
『ナポレオン:最後の専制君主、最初の近代政治家』(杉本淑彦/岩波新書)
研究者による読みやすい評伝である。「はじめに」で次のように述べている。
「本書は、歴史研究のこれまでの成果を取り入れながら、文学者のひそみにならい、人物の心理に踏みこもうとした。したがって、歴史研究では忌避されることが多い、おもしろさが先だっている裏話や逸話も、あえて取り上げた。」
ナポレオンは普通は4年程かかる士官学校を11カ月という最短記録で卒業し、16歳で少尉になる。勤勉で優秀だったが、経済的事情で早く任官したらしい。数学が得意で歴史書を耽読、文学や美術への関心は薄かった。ヴォルテール、モンテスキュー、ルソーなど啓蒙思想家の著作を読んでいる。
本書は冒頭で、近代民主主義論の古典と評価されるルソーの『社会契約論』を紹介し、ルソーの「一般意思」が「独裁」につながる可能性を指摘している。フランス革命の継承・伝道から独裁に至ったナポレオンは、彼が若い頃に読んだルソーの思想を体現したのかもしれない。
ナポレオンは「時代に遅れていると同時に、時代に先駆けてもいた人物」と評される。本書は、サブタイトル「最後の専制君主、最初の近代政治家」にあるように、評価が錯綜する人物の生涯を逸話をまじえて興味深く描いている。
肖像画などの絵画を自己宣伝に利用した話が面白い。初期の肖像画『アルレコ橋のボナパルト将軍』を発注したのはジョセフィーヌで、当初、ナポレオンは乗り気でなかったらしい。ナポレオンが熱愛して結婚した年長の貴族婦人ジョセフィーヌは、若い夫を政界に売り込むプロデューサーだった。
ジョセフィーヌを含めて当時の貴族社会の女性に愛人が多いのにあきれるが、本書の次の指摘を読んで納得した。
「夫とはべつに愛人を持つというのは、彼女が育ったフランス貴族社会では特段とがめられることでもなかった」
考えてみれば、バルザックの小説はどれもそんな世界だった。そんな貴族社会に馴染んでいなかった新参者には大変な世界だったのかもしれない。エルバ島の領主に封じられたナポレオンは、エルバ島を訪れた愛人を追い返して、2番目の妻マリー=ルイーズ(ハプスブルク家皇女)の到着を待つ。だが、マリーは護衛の貴族と愛人関係になりエルバ島行きを取りやめる。ナポレオンがちょっと気の毒になる。
『ナポレオン:最後の専制君主、最初の近代政治家』(杉本淑彦/岩波新書)
研究者による読みやすい評伝である。「はじめに」で次のように述べている。
「本書は、歴史研究のこれまでの成果を取り入れながら、文学者のひそみにならい、人物の心理に踏みこもうとした。したがって、歴史研究では忌避されることが多い、おもしろさが先だっている裏話や逸話も、あえて取り上げた。」
ナポレオンは普通は4年程かかる士官学校を11カ月という最短記録で卒業し、16歳で少尉になる。勤勉で優秀だったが、経済的事情で早く任官したらしい。数学が得意で歴史書を耽読、文学や美術への関心は薄かった。ヴォルテール、モンテスキュー、ルソーなど啓蒙思想家の著作を読んでいる。
本書は冒頭で、近代民主主義論の古典と評価されるルソーの『社会契約論』を紹介し、ルソーの「一般意思」が「独裁」につながる可能性を指摘している。フランス革命の継承・伝道から独裁に至ったナポレオンは、彼が若い頃に読んだルソーの思想を体現したのかもしれない。
ナポレオンは「時代に遅れていると同時に、時代に先駆けてもいた人物」と評される。本書は、サブタイトル「最後の専制君主、最初の近代政治家」にあるように、評価が錯綜する人物の生涯を逸話をまじえて興味深く描いている。
肖像画などの絵画を自己宣伝に利用した話が面白い。初期の肖像画『アルレコ橋のボナパルト将軍』を発注したのはジョセフィーヌで、当初、ナポレオンは乗り気でなかったらしい。ナポレオンが熱愛して結婚した年長の貴族婦人ジョセフィーヌは、若い夫を政界に売り込むプロデューサーだった。
ジョセフィーヌを含めて当時の貴族社会の女性に愛人が多いのにあきれるが、本書の次の指摘を読んで納得した。
「夫とはべつに愛人を持つというのは、彼女が育ったフランス貴族社会では特段とがめられることでもなかった」
考えてみれば、バルザックの小説はどれもそんな世界だった。そんな貴族社会に馴染んでいなかった新参者には大変な世界だったのかもしれない。エルバ島の領主に封じられたナポレオンは、エルバ島を訪れた愛人を追い返して、2番目の妻マリー=ルイーズ(ハプスブルク家皇女)の到着を待つ。だが、マリーは護衛の貴族と愛人関係になりエルバ島行きを取りやめる。ナポレオンがちょっと気の毒になる。

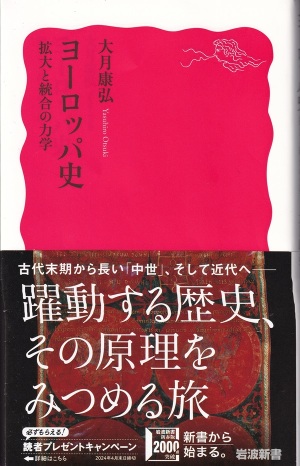
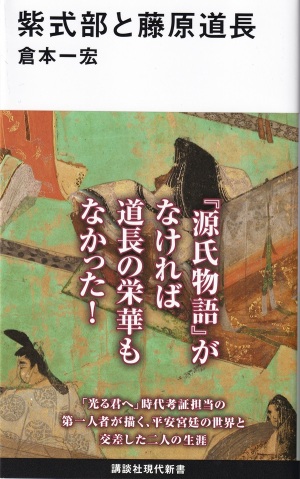
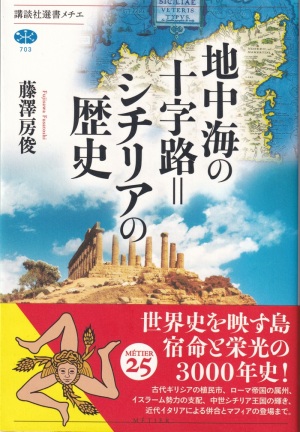





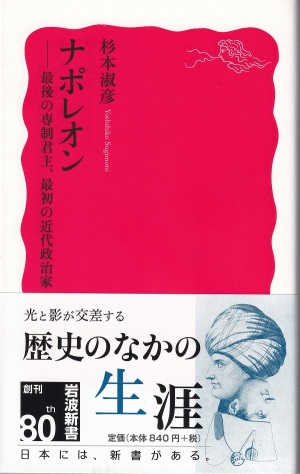
最近のコメント