シャーロック・ホームズ全編読み返し第3弾(終) ― 2024年05月01日
先月から始めたシャーロック・ホームズ全9冊読み返し計画、第1弾の初期3冊、脂の乗った中期3冊に続いて次の後期3冊を読了し、全60編読み返しを完了した。
『恐怖の谷』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)
『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)
『シャーロック・ホームズの事件簿』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)
『恐怖の谷』は長編、『…最後の挨拶』は短編7編、『…事件簿』は短編12編だ。いずれも昔読んだ作品のはずだが、ほとんどの内容を失念していて、初読と同じようなワクワク・ドキドキ読書だった。
長編『恐怖の谷』は『緋色の研究』『四つの署名』と似た二部構成で、前半で事件は一応解決し、後半は事件の元にになった過去の物語になる。『恐怖の谷』は一部だけでなく二部にも謎解きの要素があり、独立した二つの面白い小説を読んだ気分になる。だがその分、前半と後半の繋がりがやや希薄に感じられる。
あらためて気づいたのは『恐怖の谷』がモリアーティ教授絡みの話になっている点だ。モリアーティが登場するのは『最後の事件』と『空き家の冒険』だけと思っていたが、『恐怖の谷』は『最後の事件』以前の時代設定で、物語の背後にモリアーティの影がある。やや無理にモリアーティに言及しているようにも感じるが、犯罪界のナポレオンの実在性を強調したいドイルの工夫だろう。
『…最後の挨拶』と『…事件簿』には「まえがき」がついている。前者はワトソン、後者はドイルによるものだ。昔読んだ新潮文庫版に「まえがき」はなかった。トクした気分になった。
大半の短編の内容は失念していたが『瀕死の探偵』だけはよく憶えていた。小学生の時に初めて読んだホームス物だからである。講談社の『少年少女世界文学全集』には『緋色の研究』と『瀕死の探偵』が収録されていて、この2編が私のホームズ初体験だった。最も昔に読んだものが最も印象深く残っているという記憶のメカニズムの不思議を感じた。
『…最後の挨拶』の末尾の短編『最後の挨拶』には「シャーロック・ホームズのエピローグ」のサブタイトルが付いている。ワトソンの語りではなく三人称の短編だ。時代は第一次大戦直前、高齢者になったホームズとワトソンが往年を彷彿とさせる活躍をする。愛国プロパガンダ的物語で、ホームズが別れの挨拶をするわけではない。
ドイルは『…最後の挨拶』で打ち止めのつもりだったのかもしれないが、その後も『…事件簿』に収録される短編を書き続ける。この短編集にはホームズが語る物語が2編、三人称の物語が1編ある。
ホームス物60編を読み返し、中学生時代にホームズの短編集を読みふけって夜更かしした記憶がよみがえってきた。今晩はここでやめようと思いつつ、次の短編も読みたくなり、睡眠時間が短くなっていった。75歳になって読み返しても、やはり似たような読書体験になった。ドイルのストーリー・テラーとしての力量を再認識した。
『恐怖の谷』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)
『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)
『シャーロック・ホームズの事件簿』(コナン・ドイル/日暮雅道訳/光文社文庫)
『恐怖の谷』は長編、『…最後の挨拶』は短編7編、『…事件簿』は短編12編だ。いずれも昔読んだ作品のはずだが、ほとんどの内容を失念していて、初読と同じようなワクワク・ドキドキ読書だった。
長編『恐怖の谷』は『緋色の研究』『四つの署名』と似た二部構成で、前半で事件は一応解決し、後半は事件の元にになった過去の物語になる。『恐怖の谷』は一部だけでなく二部にも謎解きの要素があり、独立した二つの面白い小説を読んだ気分になる。だがその分、前半と後半の繋がりがやや希薄に感じられる。
あらためて気づいたのは『恐怖の谷』がモリアーティ教授絡みの話になっている点だ。モリアーティが登場するのは『最後の事件』と『空き家の冒険』だけと思っていたが、『恐怖の谷』は『最後の事件』以前の時代設定で、物語の背後にモリアーティの影がある。やや無理にモリアーティに言及しているようにも感じるが、犯罪界のナポレオンの実在性を強調したいドイルの工夫だろう。
『…最後の挨拶』と『…事件簿』には「まえがき」がついている。前者はワトソン、後者はドイルによるものだ。昔読んだ新潮文庫版に「まえがき」はなかった。トクした気分になった。
大半の短編の内容は失念していたが『瀕死の探偵』だけはよく憶えていた。小学生の時に初めて読んだホームス物だからである。講談社の『少年少女世界文学全集』には『緋色の研究』と『瀕死の探偵』が収録されていて、この2編が私のホームズ初体験だった。最も昔に読んだものが最も印象深く残っているという記憶のメカニズムの不思議を感じた。
『…最後の挨拶』の末尾の短編『最後の挨拶』には「シャーロック・ホームズのエピローグ」のサブタイトルが付いている。ワトソンの語りではなく三人称の短編だ。時代は第一次大戦直前、高齢者になったホームズとワトソンが往年を彷彿とさせる活躍をする。愛国プロパガンダ的物語で、ホームズが別れの挨拶をするわけではない。
ドイルは『…最後の挨拶』で打ち止めのつもりだったのかもしれないが、その後も『…事件簿』に収録される短編を書き続ける。この短編集にはホームズが語る物語が2編、三人称の物語が1編ある。
ホームス物60編を読み返し、中学生時代にホームズの短編集を読みふけって夜更かしした記憶がよみがえってきた。今晩はここでやめようと思いつつ、次の短編も読みたくなり、睡眠時間が短くなっていった。75歳になって読み返しても、やはり似たような読書体験になった。ドイルのストーリー・テラーとしての力量を再認識した。
『帰れない男』は不気味な屋敷のやや古風な心理劇 ― 2024年05月03日
本多劇場で『帰れない男~慰留と斡旋の攻防~』(作・演出:倉持裕、出演:林遣都、藤間爽子、柄本時生、山崎一、他)を観た。倉持裕氏の芝居を観るのは一昨年の『お勢、断行』に続いて2本目だと思う。
舞台は大正末期か昭和初期の立派な屋敷の客間である。道路で馬に踏まれそうになった若い女性を助けた男が、女性の屋敷に招かれ、すぐに帰るつもりだったのに宿泊し、そのまま屋敷から帰れなくなる。この男、妻もいる作家だが、屋敷の客間に居ついたまま小説の執筆もする。友人が迎えに来ても、やはり帰ることができない。
日経新聞の劇評(2024.4.26夕刊)に、「明治大正の短編小説を読んだような心持ちになる」「内田百閒の小説に想を得たとかで…」などとあったので、鈴木清順監督の映画『ツィゴイネルワイゼン』のような超現実的な幻想譚を期待した。
男が帰れなくなる過程を描いた前半に惹かれたが、私が想像した話とはやや異なる心理劇だった。年配の実業家と若い後妻(元・女給)と作家、さらには作家の友人や作家の妻(舞台には登場しない)も絡んでくる。確かに明治大正の短編小説の雰囲気が色濃く漂う心理劇であり、やや怪奇でもある。だが、期待したほど超現実的ではなかった。
物語は超現実的でないとしても、舞台設定には超現実的な魅力がある。玄関の音は聞こえるのに、玄関から客間までは遠い。屋敷は迷路のようで、来客が帰るとき、案内なしで玄関に戻るのは難しい。客間の背景になる中庭の向こうは賑やかな宴会場で、客の影が見える。宴会はいつの間にか始まり、いつの間にか終わる。それが繰り返される。秀逸な背景だ。時に中庭に人が現れることがあり、不気味である。
物語の展開ももう少し不気味にできたのは、と思えた。
舞台は大正末期か昭和初期の立派な屋敷の客間である。道路で馬に踏まれそうになった若い女性を助けた男が、女性の屋敷に招かれ、すぐに帰るつもりだったのに宿泊し、そのまま屋敷から帰れなくなる。この男、妻もいる作家だが、屋敷の客間に居ついたまま小説の執筆もする。友人が迎えに来ても、やはり帰ることができない。
日経新聞の劇評(2024.4.26夕刊)に、「明治大正の短編小説を読んだような心持ちになる」「内田百閒の小説に想を得たとかで…」などとあったので、鈴木清順監督の映画『ツィゴイネルワイゼン』のような超現実的な幻想譚を期待した。
男が帰れなくなる過程を描いた前半に惹かれたが、私が想像した話とはやや異なる心理劇だった。年配の実業家と若い後妻(元・女給)と作家、さらには作家の友人や作家の妻(舞台には登場しない)も絡んでくる。確かに明治大正の短編小説の雰囲気が色濃く漂う心理劇であり、やや怪奇でもある。だが、期待したほど超現実的ではなかった。
物語は超現実的でないとしても、舞台設定には超現実的な魅力がある。玄関の音は聞こえるのに、玄関から客間までは遠い。屋敷は迷路のようで、来客が帰るとき、案内なしで玄関に戻るのは難しい。客間の背景になる中庭の向こうは賑やかな宴会場で、客の影が見える。宴会はいつの間にか始まり、いつの間にか終わる。それが繰り返される。秀逸な背景だ。時に中庭に人が現れることがあり、不気味である。
物語の展開ももう少し不気味にできたのは、と思えた。
ホームズの架空伝記は思った以上に大胆だった ― 2024年05月05日
先月、シャーロック・ホームスの全60編(初期の長編2冊と短編集1冊、中期の短編集2冊と長編1冊、後期の短編集2冊と長編1冊)を読み返した。その残像が頭にあるうちに次の架空伝記を読んだ。
『シャーロック・ホームズ ガス燈に浮かぶその生涯』(ベアリング=グールド/小林司・東山あかね訳/講談社)
本書を購入したのは45年前、私が29歳のとき(1979.2)だ。あの頃、『名探偵読本シャーロック・ホームズ』(小林司・東山あかね編)というムックを読んだのがきっかけで、中学生時代に読んだホームズへの思いが高揚し、ホームズ関連本を何冊か集中的に読んだ。だが、この伝記はパラパラと拾い読みしただけで、通読していない。ホームズ全編を読み返したうえで読むべきだと考えたのだ。で、半世紀近くの年月が経過してしまった。
グールドは、全60の事件の発生時期を確定させたホームズ研究家である。上記のムックはグールド説に従った順番で60の物語を解説していた。1話1頁のこの解説はシャーロキアンならではの楽しいツッコミが面白かった。
グールドはシャーロキアンだから、ホームズやワトソンを実在の人物として研究を進めている。ワトソンが残した記録にある年代にはつじつまがあわないものがあり、実在しない地名もある。何等かの事情で事実をズラして発表しているのだろうが、誤記の可能性もある。60編の正典を基にその背後にある事実を追究した成果が本書である。
本書は私が想定した以上に大胆で強引な伝記だった。全60編では語られていない「驚きの事実」が次々に出てくる。そのいくつかを以下に紹介する。
・モリアティはホームズの家庭教師だった。
・ホームズはオックスフォードとケンブリッジ、両方の大学で学んだ。
・ホームズは25歳頃、大学時代の友人に誘われてシェイクスピア劇の俳優になり、8カ月ほどのアメリカ公演に参加している。
・ワトソンはホームズとの共同生活を始めた後、アメリカ在住の弟が病気になったので、ホームズから借金して渡米する。弟は回復するが、ホームズへの借金返済のためサンフランシスコで医院を開業し、結婚もする。その後、妻とともにイギリスに戻るが、妻は早世する。
・実は「切り裂きジャック事件」もホームズとワトソンが解決していた。犯人が警察関係者だったため公表されなかった。
・ホームズは失踪期間中にモンテネグロでアイリーン・アドラーと一時同棲していた。
・ホームズは失踪期間中にエレベスト登山を試み、雪男を探索した。
・ホームズは失踪期間中にチベットで仏教の影響を大きく受けた。
・ワトソンの2回目の結婚相手は『四つの署名』のメアリー・モースタンだが、彼女も早世する。その後、ワトソンは3回目の結婚をする。
・ホームズは第一次世界大戦も第二次世界大戦も経験し、1957年に103歳で亡くなった。長命の秘訣は養蜂にあった。
信じがたい話も多いが、さまざまな研究成果に基づいた「事実」らしい。この架空伝記にはコナン・ドイルも登場する。ドイルはワトソンの友人で出版の仲介者という位置づけである。虚実混ざったもっともらしい注釈もかなり挿入されている。ホームズ物語全60編のつじつまを合わせて伝記を紡ぐ力業は楽しいだろうなあと想像した。
『シャーロック・ホームズ ガス燈に浮かぶその生涯』(ベアリング=グールド/小林司・東山あかね訳/講談社)
本書を購入したのは45年前、私が29歳のとき(1979.2)だ。あの頃、『名探偵読本シャーロック・ホームズ』(小林司・東山あかね編)というムックを読んだのがきっかけで、中学生時代に読んだホームズへの思いが高揚し、ホームズ関連本を何冊か集中的に読んだ。だが、この伝記はパラパラと拾い読みしただけで、通読していない。ホームズ全編を読み返したうえで読むべきだと考えたのだ。で、半世紀近くの年月が経過してしまった。
グールドは、全60の事件の発生時期を確定させたホームズ研究家である。上記のムックはグールド説に従った順番で60の物語を解説していた。1話1頁のこの解説はシャーロキアンならではの楽しいツッコミが面白かった。
グールドはシャーロキアンだから、ホームズやワトソンを実在の人物として研究を進めている。ワトソンが残した記録にある年代にはつじつまがあわないものがあり、実在しない地名もある。何等かの事情で事実をズラして発表しているのだろうが、誤記の可能性もある。60編の正典を基にその背後にある事実を追究した成果が本書である。
本書は私が想定した以上に大胆で強引な伝記だった。全60編では語られていない「驚きの事実」が次々に出てくる。そのいくつかを以下に紹介する。
・モリアティはホームズの家庭教師だった。
・ホームズはオックスフォードとケンブリッジ、両方の大学で学んだ。
・ホームズは25歳頃、大学時代の友人に誘われてシェイクスピア劇の俳優になり、8カ月ほどのアメリカ公演に参加している。
・ワトソンはホームズとの共同生活を始めた後、アメリカ在住の弟が病気になったので、ホームズから借金して渡米する。弟は回復するが、ホームズへの借金返済のためサンフランシスコで医院を開業し、結婚もする。その後、妻とともにイギリスに戻るが、妻は早世する。
・実は「切り裂きジャック事件」もホームズとワトソンが解決していた。犯人が警察関係者だったため公表されなかった。
・ホームズは失踪期間中にモンテネグロでアイリーン・アドラーと一時同棲していた。
・ホームズは失踪期間中にエレベスト登山を試み、雪男を探索した。
・ホームズは失踪期間中にチベットで仏教の影響を大きく受けた。
・ワトソンの2回目の結婚相手は『四つの署名』のメアリー・モースタンだが、彼女も早世する。その後、ワトソンは3回目の結婚をする。
・ホームズは第一次世界大戦も第二次世界大戦も経験し、1957年に103歳で亡くなった。長命の秘訣は養蜂にあった。
信じがたい話も多いが、さまざまな研究成果に基づいた「事実」らしい。この架空伝記にはコナン・ドイルも登場する。ドイルはワトソンの友人で出版の仲介者という位置づけである。虚実混ざったもっともらしい注釈もかなり挿入されている。ホームズ物語全60編のつじつまを合わせて伝記を紡ぐ力業は楽しいだろうなあと想像した。
紅テントの『泥人魚』は唐十郎追悼公演になった ― 2024年05月07日
3日前(2024.5.4)唐十郎が亡くなった。84歳だった。訃報を知ったのは一昨日(5月5日)、唐十郎の戯曲『泥人魚』を読んだ直後だった。私は半世紀前に紅テント(状況劇場)に魅せられ何度も足を運んだ。唐十郎の訃報に時代の変転を感じる。
戯曲『泥人魚』は観劇準備のために読んだ。劇団唐組が『泥人魚』を再演(初演は2003年)すると知り、チケットを手配した。花園神社での初日は2024年5月5日、唐十郎逝去の翌日だった。私は昨日(5月6日)の公演を観た。
私は3年前、シアターコクーン公演の『泥人魚』(演出:金守珍、出演:宮沢りえ、風間杜夫、他)を観ている。あのときは戯曲を読んでいなかった。もちろん、それでも十分に面白かった。今回は事前に戯曲を読んで、多少は「わかった気分」を増やそうと思い、戯曲を古書で入手した。
戯曲のオビには「読売文学賞、紀伊国屋演劇賞、鶴屋南北戯曲賞トリプル受賞」とある。3年前に観た芝居の戯曲を読むのだから頭に入りやすいだろうと思ったが、そうでなっかた。観劇の記憶は薄れていて、漫然と読んでいると、わけがわからなくなる。この戯曲には伊東静雄の詩、島尾敏雄の小説などが登場するので、伊東静雄の詩を確認し、島尾敏雄の『島の果て』を読み返した。
『泥人魚』は諫早湾のギロチン堤防がモチーフだとは承知しているが、戯曲の「あとがき」には少々驚いた。朝日新聞の諫早通信局を通して現地取材した様子や戯曲発想の発火点になった事物について具体的に記述している。唐十郎の妄想世界の根にあるリアリズムが意外に深いと知った。
ギロチン堤防を巡る実情を知り、伊東静雄の詩、島尾敏雄の小説などを確認したうえで戯曲を再読すると、これらの素材を唐十郎の言葉で書き替えているのが確認できた。戯曲に散りばめられている様々な素材(伊東静雄、島尾敏雄、浦上天主堂、人間魚雷、天草四郎、他)を強引にデフォルメしたうえで、一貫性のあるイメージに収斂させていると気づいた。
その「気づき」は観劇によって強固になった。戯曲を繰り返し読んでもわからないことが、役者たちの台詞で聞いているとすっきりわかってくる。唐十郎の芝居は「よくわからないが面白い」という感想を抱くことが多い、だが、役者が演ずる姿を観て、『泥人魚』はかなり明晰な芝居だと感じた。
現地取材に基づいた芝居で、長崎や諫早を想起させる素材を多用しているにもかかわらず、芝居の舞台は東京のブリキ加工店になっている。これも暗示的だ。ギロチン堤防や登場人物たちの葛藤の普遍性が浮き上がってくる。
終演後の恒例の役者紹介の後、客席の照明を落とした暗闇の中、唐十郎の歌声が流れた。「ある夕方のこと 風がおいらに伝えたさ この町の果てで あの子が死にかけているていると…」――『さすらいの唄』だ。劇中で聞いた記憶はないが、LPレコード『唐十郎 四角いジャングルで唄う』で繰り返し聞いた懐かしい唄である。暗闇のなかで唐十郎の若くて力強い唄声をじっと聞いていると、目頭が熱くなってきた。
戯曲『泥人魚』は観劇準備のために読んだ。劇団唐組が『泥人魚』を再演(初演は2003年)すると知り、チケットを手配した。花園神社での初日は2024年5月5日、唐十郎逝去の翌日だった。私は昨日(5月6日)の公演を観た。
私は3年前、シアターコクーン公演の『泥人魚』(演出:金守珍、出演:宮沢りえ、風間杜夫、他)を観ている。あのときは戯曲を読んでいなかった。もちろん、それでも十分に面白かった。今回は事前に戯曲を読んで、多少は「わかった気分」を増やそうと思い、戯曲を古書で入手した。
戯曲のオビには「読売文学賞、紀伊国屋演劇賞、鶴屋南北戯曲賞トリプル受賞」とある。3年前に観た芝居の戯曲を読むのだから頭に入りやすいだろうと思ったが、そうでなっかた。観劇の記憶は薄れていて、漫然と読んでいると、わけがわからなくなる。この戯曲には伊東静雄の詩、島尾敏雄の小説などが登場するので、伊東静雄の詩を確認し、島尾敏雄の『島の果て』を読み返した。
『泥人魚』は諫早湾のギロチン堤防がモチーフだとは承知しているが、戯曲の「あとがき」には少々驚いた。朝日新聞の諫早通信局を通して現地取材した様子や戯曲発想の発火点になった事物について具体的に記述している。唐十郎の妄想世界の根にあるリアリズムが意外に深いと知った。
ギロチン堤防を巡る実情を知り、伊東静雄の詩、島尾敏雄の小説などを確認したうえで戯曲を再読すると、これらの素材を唐十郎の言葉で書き替えているのが確認できた。戯曲に散りばめられている様々な素材(伊東静雄、島尾敏雄、浦上天主堂、人間魚雷、天草四郎、他)を強引にデフォルメしたうえで、一貫性のあるイメージに収斂させていると気づいた。
その「気づき」は観劇によって強固になった。戯曲を繰り返し読んでもわからないことが、役者たちの台詞で聞いているとすっきりわかってくる。唐十郎の芝居は「よくわからないが面白い」という感想を抱くことが多い、だが、役者が演ずる姿を観て、『泥人魚』はかなり明晰な芝居だと感じた。
現地取材に基づいた芝居で、長崎や諫早を想起させる素材を多用しているにもかかわらず、芝居の舞台は東京のブリキ加工店になっている。これも暗示的だ。ギロチン堤防や登場人物たちの葛藤の普遍性が浮き上がってくる。
終演後の恒例の役者紹介の後、客席の照明を落とした暗闇の中、唐十郎の歌声が流れた。「ある夕方のこと 風がおいらに伝えたさ この町の果てで あの子が死にかけているていると…」――『さすらいの唄』だ。劇中で聞いた記憶はないが、LPレコード『唐十郎 四角いジャングルで唄う』で繰り返し聞いた懐かしい唄である。暗闇のなかで唐十郎の若くて力強い唄声をじっと聞いていると、目頭が熱くなってきた。
小室直樹『日本人のための宗教原論』は頭がクラクラする奇書 ― 2024年05月09日
橋爪大三郎氏の宗教社会学入門書『世界は四大文明でできている』を読み、橋爪氏の師匠にしてケタ外れの学者・小室直樹の宗教入門書を思い出した。かなり以前に入手したまま積んでいた本である。
『日本人のための宗教原論』(小室直樹/徳間書店/2000.6)
比較宗教学のような内容で、キリスト教、仏教、イスラム教、儒教を縦横に語っている。面白いが易しくはない。目から鱗の話も多い。終盤は日本の現状を憂う怪気炎になり、頭がクラクラしてくる。勉強になるが奇書に近い。
小室直樹という在野の学究については、11年前に読んだ『小室直樹の世界』(橋爪大三郎編著)によって奇矯な怪人のイメージが脳裏に焼き付いている。橋爪大三郎、宮台真司、大澤真幸をはじめ錚々たる学者が薫陶を受けた人物である。
京大で数学、阪大大学院で経済学を学んだ後、フルブライト留学生として渡米、ミシガン大、MIT、ハーバードで研究し、帰国後は東大の法学政治学研究科に入る。その後始めた自主ゼミで、若い研究者たちに経済学、法社会学、比較宗教学、線型代数学、統計学、抽象代数学、解析学などを幅広く教授したそうだ。
宗教入門書である本書にも突如として数学・物理学・経済学などが顔を出す。例えば仏教の唯識論や「空(くう)」の解説に「質点の力学」「ケインズ・モデル」「非ユークリッド幾何学」を援用している。
マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の援用も多く、宗教社会学に沿った解説になっている。私はヴェーバーのキリスト教に関する考察をほとんど理解できなかったが、本書を熟読したうえでヴェーバーに再挑戦すれば多少は理解が深まるかもしれない。そんな機会は巡ってこないと思うが…
それにしても、キリスト教に関する次のような解説は鋭い。
「救世主による新契約(契約の更改)とは世界(秩序)を根底からくつがえし、賤民が主となるという思想である。革命思想の事始めであり、資本主義・デモクラシー・近代法を生み、また、マルクシズムの根源ともなった。」
著者は、キリスト教の根本教義は「救世主の受難」だと指摘し、キリストの贖罪死によって無条件、無限の愛(アガペー)が発動、原罪は赦されたという教義を「摩訶不思議」と形容している。確かに不思議な教義だと思う。
四つの宗教を比較解説した本書は、キリスト教のキーワードは「予定説」、仏教のキーワードは「空(くう)」、イスラム教のキーワードは「コーラン」、儒教のキーワードは「官僚制度」としている。わかりやすい。
特に「予定説」と「空(くう)」について力を入れて詳しく解説している。これは難解である。わかりやすいとは言えない。
中世において、イスラム教国の学問レベルはヨーロッパのキリスト教国を凌駕していた。しかし、近代における資本主義化では遅れをとる。著者は、キリスト教が近代を作った宗教的要因を、パウロが「内面(信仰)と外面(行動)」を峻別したことにあると指摘している。慧眼だと思った。
『日本人のための宗教原論』(小室直樹/徳間書店/2000.6)
比較宗教学のような内容で、キリスト教、仏教、イスラム教、儒教を縦横に語っている。面白いが易しくはない。目から鱗の話も多い。終盤は日本の現状を憂う怪気炎になり、頭がクラクラしてくる。勉強になるが奇書に近い。
小室直樹という在野の学究については、11年前に読んだ『小室直樹の世界』(橋爪大三郎編著)によって奇矯な怪人のイメージが脳裏に焼き付いている。橋爪大三郎、宮台真司、大澤真幸をはじめ錚々たる学者が薫陶を受けた人物である。
京大で数学、阪大大学院で経済学を学んだ後、フルブライト留学生として渡米、ミシガン大、MIT、ハーバードで研究し、帰国後は東大の法学政治学研究科に入る。その後始めた自主ゼミで、若い研究者たちに経済学、法社会学、比較宗教学、線型代数学、統計学、抽象代数学、解析学などを幅広く教授したそうだ。
宗教入門書である本書にも突如として数学・物理学・経済学などが顔を出す。例えば仏教の唯識論や「空(くう)」の解説に「質点の力学」「ケインズ・モデル」「非ユークリッド幾何学」を援用している。
マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の援用も多く、宗教社会学に沿った解説になっている。私はヴェーバーのキリスト教に関する考察をほとんど理解できなかったが、本書を熟読したうえでヴェーバーに再挑戦すれば多少は理解が深まるかもしれない。そんな機会は巡ってこないと思うが…
それにしても、キリスト教に関する次のような解説は鋭い。
「救世主による新契約(契約の更改)とは世界(秩序)を根底からくつがえし、賤民が主となるという思想である。革命思想の事始めであり、資本主義・デモクラシー・近代法を生み、また、マルクシズムの根源ともなった。」
著者は、キリスト教の根本教義は「救世主の受難」だと指摘し、キリストの贖罪死によって無条件、無限の愛(アガペー)が発動、原罪は赦されたという教義を「摩訶不思議」と形容している。確かに不思議な教義だと思う。
四つの宗教を比較解説した本書は、キリスト教のキーワードは「予定説」、仏教のキーワードは「空(くう)」、イスラム教のキーワードは「コーラン」、儒教のキーワードは「官僚制度」としている。わかりやすい。
特に「予定説」と「空(くう)」について力を入れて詳しく解説している。これは難解である。わかりやすいとは言えない。
中世において、イスラム教国の学問レベルはヨーロッパのキリスト教国を凌駕していた。しかし、近代における資本主義化では遅れをとる。著者は、キリスト教が近代を作った宗教的要因を、パウロが「内面(信仰)と外面(行動)」を峻別したことにあると指摘している。慧眼だと思った。
唐十郎を追悼して『唐十郎の劇世界』を読んだ ― 2024年05月11日
先週亡くなった唐十郎を追悼する気分で次の本を読んだ。
『唐十郎の劇世界』(扇田昭彦/右文書院/2007.1)
朝日新聞の演劇記者だった扇田昭彦が新聞や雑誌に書いた唐十郎関連の記事93編の集成である。かなり以前に入手し、いくつかの記事を拾い読みしていたが、今回、頭から通して読んだ。
扇田昭彦は唐十郎と同じ1940年生まれ(学年は唐十郎が一つ上)で、2015年に亡くなった。本書収録記事の発表年は1970年から2006年にわたるが、大半は1970~80年代だ。古い記事をまとめて読むと往時にタイムスリップする。私にとって懐かしいのは、観劇の記憶がよみがえってくる1970年代の劇評だ。
2年前に読んだ『唐十郎のせりふ』は私が観ていない2000年代の作品を論じていて、多少の隔靴掻痒の感があった。本書はどっぷりと観劇記憶を追体験できる。
1970年代、朝日新聞には状況劇場を高く評価する劇評がよく載った。その筆者が扇田記者だとは承知していた。客が押し寄せてテントにギュウギュウ詰めにされ、朝日新聞があんな劇評を載せるからだと逆恨みしたこともある。
あの頃、扇田記者も唐十郎も三十代、観客の私は二十代だった。本書所収の1982年の記事に次のような記述がある。
「私が多少むきになって小劇場の動きをクローズアップしはじめたのは、これこそがいま本当に演劇と呼びうるものだと思ったからであると同時に、これら小劇場に対する一般の演劇的理解の浅さにいささか憤慨したからである。」
本書をまとめて読むと、アングラと呼ばれた小劇場の興隆と帰趨、そしてさまざまな世代交代を一望した気分になる。感慨深い。
私が唐十郎の世界に引きずり込まれたのは1969年12月だった。その年の夏、古書店で戯曲集『ジョン・シルバー』を購入しているから多少の関心はあったが、1969年12月封切りの映画『新宿泥棒日記』が衝撃的だった。唐十郎の怪しさに惹かれた。その直後、季節外れの大学祭に招いた状況劇場一党の歌謡ショーで四谷シモンの妖しさに陶酔し、すぐに紅テントに駆け付けた。上演中の『少女都市』観て、麿赤児の怪演に度肝を抜かれた。
それ以来、紅テントに通うようになった。いつどこで何を観たか、もはや記憶はあいまいだ。ハーメルンの笛吹き男に誘われるように、渋谷・吉祥寺・上野・月島埠頭の石炭船・夢の島・大久保のロケット工場・青山墓地・下北沢・新宿西口などに立つ紅テントに足を運んだ。
古いメモなどを頼りに記憶をたどると、私が最後に観た紅テント(状況劇場)の芝居は1979年5月の『犬狼都市』のようだ。1969年から1979年までの10年間に14本の状況劇場公演を観ている。他に状況劇場以外で上演した唐十郎の芝居も何本か観ている。だが、1980年代以降はほとんど芝居を観なくなった。言い訳めくが、三十代後半からは仕事も忙しくなり、観劇に時間を割く余裕がなくなった。
1988年、状況劇場は解散する。その後、唐十郎は紅テントの劇団唐組を立ち上げたと聞いていたが、その紅テントに足を運ぶことはなかった。
それから長い年月が経過し、自由の身となった私は、2018年5月には47年ぶりに紅テントで劇団唐組の『吸血姫』を観た。47年前に一緒に観劇した友人との再びの観劇という不思議な体験だった。客席に唐十郎と麿赤児が並んで座っているの発見し、感激した。
その後、唐十郎の芝居を再び観るようになった。あちこちで上演される機会が多いからだ。場所も大劇場からテントまでさまざまである。本書は、唐十郎の次の述懐を紹介している。
「テントはスケールの大きな役者が育つ空間。テントがないと、ぼくは戯曲を書きたいとは思わない」
先週、花園神社境内の紅テント公演『泥人魚』で、役者たちの汗やツバが目の前を飛ぶ熱演に接した。あらためて、唐十郎の生涯にわたるテント芝居への執着に敬服する。
『唐十郎の劇世界』(扇田昭彦/右文書院/2007.1)
朝日新聞の演劇記者だった扇田昭彦が新聞や雑誌に書いた唐十郎関連の記事93編の集成である。かなり以前に入手し、いくつかの記事を拾い読みしていたが、今回、頭から通して読んだ。
扇田昭彦は唐十郎と同じ1940年生まれ(学年は唐十郎が一つ上)で、2015年に亡くなった。本書収録記事の発表年は1970年から2006年にわたるが、大半は1970~80年代だ。古い記事をまとめて読むと往時にタイムスリップする。私にとって懐かしいのは、観劇の記憶がよみがえってくる1970年代の劇評だ。
2年前に読んだ『唐十郎のせりふ』は私が観ていない2000年代の作品を論じていて、多少の隔靴掻痒の感があった。本書はどっぷりと観劇記憶を追体験できる。
1970年代、朝日新聞には状況劇場を高く評価する劇評がよく載った。その筆者が扇田記者だとは承知していた。客が押し寄せてテントにギュウギュウ詰めにされ、朝日新聞があんな劇評を載せるからだと逆恨みしたこともある。
あの頃、扇田記者も唐十郎も三十代、観客の私は二十代だった。本書所収の1982年の記事に次のような記述がある。
「私が多少むきになって小劇場の動きをクローズアップしはじめたのは、これこそがいま本当に演劇と呼びうるものだと思ったからであると同時に、これら小劇場に対する一般の演劇的理解の浅さにいささか憤慨したからである。」
本書をまとめて読むと、アングラと呼ばれた小劇場の興隆と帰趨、そしてさまざまな世代交代を一望した気分になる。感慨深い。
私が唐十郎の世界に引きずり込まれたのは1969年12月だった。その年の夏、古書店で戯曲集『ジョン・シルバー』を購入しているから多少の関心はあったが、1969年12月封切りの映画『新宿泥棒日記』が衝撃的だった。唐十郎の怪しさに惹かれた。その直後、季節外れの大学祭に招いた状況劇場一党の歌謡ショーで四谷シモンの妖しさに陶酔し、すぐに紅テントに駆け付けた。上演中の『少女都市』観て、麿赤児の怪演に度肝を抜かれた。
それ以来、紅テントに通うようになった。いつどこで何を観たか、もはや記憶はあいまいだ。ハーメルンの笛吹き男に誘われるように、渋谷・吉祥寺・上野・月島埠頭の石炭船・夢の島・大久保のロケット工場・青山墓地・下北沢・新宿西口などに立つ紅テントに足を運んだ。
古いメモなどを頼りに記憶をたどると、私が最後に観た紅テント(状況劇場)の芝居は1979年5月の『犬狼都市』のようだ。1969年から1979年までの10年間に14本の状況劇場公演を観ている。他に状況劇場以外で上演した唐十郎の芝居も何本か観ている。だが、1980年代以降はほとんど芝居を観なくなった。言い訳めくが、三十代後半からは仕事も忙しくなり、観劇に時間を割く余裕がなくなった。
1988年、状況劇場は解散する。その後、唐十郎は紅テントの劇団唐組を立ち上げたと聞いていたが、その紅テントに足を運ぶことはなかった。
それから長い年月が経過し、自由の身となった私は、2018年5月には47年ぶりに紅テントで劇団唐組の『吸血姫』を観た。47年前に一緒に観劇した友人との再びの観劇という不思議な体験だった。客席に唐十郎と麿赤児が並んで座っているの発見し、感激した。
その後、唐十郎の芝居を再び観るようになった。あちこちで上演される機会が多いからだ。場所も大劇場からテントまでさまざまである。本書は、唐十郎の次の述懐を紹介している。
「テントはスケールの大きな役者が育つ空間。テントがないと、ぼくは戯曲を書きたいとは思わない」
先週、花園神社境内の紅テント公演『泥人魚』で、役者たちの汗やツバが目の前を飛ぶ熱演に接した。あらためて、唐十郎の生涯にわたるテント芝居への執着に敬服する。
吉田羊主演の『ハムレットQ1』はテンポがいい芝居 ― 2024年05月13日
パルコ劇場でシェイクスピアの『ハムレットQ1』(訳:松岡和子、演出:森新太郎、出演:吉田羊、飯豊まりえ、吉田栄作、他)を観た。
『ハムレット』にはQ1、Q2、F1という三種類の原本があるそうだ。現在はQ2とF1の折衷版を使うことが多く、Q2やF1より短いQ1は不完全な版とされているらしい。しかし、今回の上演は、ほとんど上演されないQ1をあえて使っている。だから、タイトルは『ハムレットQ1』なのだ。
昨年観た河合祥一郎訳・野村萬斎演出の『ハムレット』の上演時間は3時間15分(休憩時間を除く)だったが、今回の『ハムレットQ1』は2時間30分(休憩時間を除く)だった。展開がスピーディでハムレットの長台詞も少ない。
森新太郎演出・吉田羊主演のパルコ劇場でのシェイクスピア劇は3年前の『ジュリアス・シーザー』に続いて2本目である。『ジュリアス・シーザー』は出演者が全員女優というユニークだ趣向だった。今回は、ハムレットを吉田羊が演じ、廷臣を演じる女優もいるが、概ね男性を男優、女性を女優が演じている。
ハムレット役の吉田羊には、まったく違和感がない。若い王子とは中性的存在なのかもしれない。ハムレットが狂気を演じるとき、急にコミカルな高音の女性の声に変貌するのが面白い。笑えるハムレットである。テンポのいい展開も心地いい。主要人物がみな死んでしまう終幕に向かってどんどん突き進んでいく印象の舞台だった。
抽象的な造形のモノトーンの舞台装置は開幕から終幕まで変化しない。王宮も墓場も同じである。墓場にこそふさわしい舞台の上で物語が進行しているように見えてくる。
ハムレットの衣装はシンプルな黒いマントだが、他の役者たちは現代の服装である。クローディアス(吉田栄作)はネクタイ&スーツに王冠を被って登場する。そのチグハグな姿は、王冠にふわしくないと揶揄しているようにも見える。クローディアスを小心な男に描いた舞台である。
『ハムレット』にはQ1、Q2、F1という三種類の原本があるそうだ。現在はQ2とF1の折衷版を使うことが多く、Q2やF1より短いQ1は不完全な版とされているらしい。しかし、今回の上演は、ほとんど上演されないQ1をあえて使っている。だから、タイトルは『ハムレットQ1』なのだ。
昨年観た河合祥一郎訳・野村萬斎演出の『ハムレット』の上演時間は3時間15分(休憩時間を除く)だったが、今回の『ハムレットQ1』は2時間30分(休憩時間を除く)だった。展開がスピーディでハムレットの長台詞も少ない。
森新太郎演出・吉田羊主演のパルコ劇場でのシェイクスピア劇は3年前の『ジュリアス・シーザー』に続いて2本目である。『ジュリアス・シーザー』は出演者が全員女優というユニークだ趣向だった。今回は、ハムレットを吉田羊が演じ、廷臣を演じる女優もいるが、概ね男性を男優、女性を女優が演じている。
ハムレット役の吉田羊には、まったく違和感がない。若い王子とは中性的存在なのかもしれない。ハムレットが狂気を演じるとき、急にコミカルな高音の女性の声に変貌するのが面白い。笑えるハムレットである。テンポのいい展開も心地いい。主要人物がみな死んでしまう終幕に向かってどんどん突き進んでいく印象の舞台だった。
抽象的な造形のモノトーンの舞台装置は開幕から終幕まで変化しない。王宮も墓場も同じである。墓場にこそふさわしい舞台の上で物語が進行しているように見えてくる。
ハムレットの衣装はシンプルな黒いマントだが、他の役者たちは現代の服装である。クローディアス(吉田栄作)はネクタイ&スーツに王冠を被って登場する。そのチグハグな姿は、王冠にふわしくないと揶揄しているようにも見える。クローディアスを小心な男に描いた舞台である。
『ホームズとワトソン:友情の研究』は哀感漂う架空伝記 ― 2024年05月15日
先月、シャーロック・ホームズ全編を読み返したのを機に、ホームズの架空伝記『シャーロック・ホームズ ガス燈に浮かぶその生涯』(グールド)を読んだ。ホームズの伝記は他にもいくつかあり、もう1冊ぐらい読んでおこうと思い、次の伝記を読んだ。
『ホームズとワトソン:友情の研究』(ジューン・トムスン/押田由起訳/創元推理文庫)
本書の著者は英国の女流推理作家で、ワトソンが語らなかったホームズの事件を題材にした物語を多く書いているそうだ。本書は、ホームズとワトソンとの関わりに焦点を当てた架空伝記である。
世界で一番有名なフィクションの人物はシャーロック・ホームズだと聞いたことがある。だとすれば、二番目はワトソンだろう。ワトソンという絶妙な相棒&語り手によってホームズは魅力的な存在になった。ホームズ全編を読み返しているとき、ホームズ物の面白さは、謎解きや冒険ではなくホームズとワトソンの掛け合いにあると感じた。
グールドの架空伝記は奔放で破天荒だったが、本書はかなり抑制的・禁欲的である。あくまで聖典60編を一次史料とし、聖典から推測できない事項の断定を避けている。グールドの伝記より本書の方が面白い。ホームズ像に陰影があり、哀感さえ漂う。
著者はホームズは躁鬱病だとしている。それは大空白時代(1891年の『最後の事件』から1894年の『空家の冒険』まで)の後も継続している。グールドは大空白時代以降、ホームズはコカイン依存を克服したとしているが、本書では克服できていない。
『最後の事件』においてホームズが失踪を決意した動機の追究が面白い。『空家の冒険』でホームズがワトソンに語った動機に無理があるのは確かだ。著者は、躁鬱病だったホームズが抱いた「自分自身から逃げ出して、まったく新しい人格をつくりだしたいという無意識の衝動」を指摘している。
本書の肝はホームズとワトソンの関係の分析である。ホームズのワトソンへの支配欲、それを受け容れるワトソンという相互依存的な「友情」という指摘は説得的だ。そんな関係だから、ワトソンの結婚に冷淡なホームズに哀感が漂う。
グールドはワトソン3回結婚説だが、本書は2回結婚説である。『四つの署名』のメアリ・モースタンが1回目で、彼女は大空白時代に亡くなる。2回目の相手は、何と『ソア橋の怪事件』のグレース・ダンバーだとしている。聖典のみを手掛かりにした緻密な推論に感心した。
『ホームズとワトソン:友情の研究』(ジューン・トムスン/押田由起訳/創元推理文庫)
本書の著者は英国の女流推理作家で、ワトソンが語らなかったホームズの事件を題材にした物語を多く書いているそうだ。本書は、ホームズとワトソンとの関わりに焦点を当てた架空伝記である。
世界で一番有名なフィクションの人物はシャーロック・ホームズだと聞いたことがある。だとすれば、二番目はワトソンだろう。ワトソンという絶妙な相棒&語り手によってホームズは魅力的な存在になった。ホームズ全編を読み返しているとき、ホームズ物の面白さは、謎解きや冒険ではなくホームズとワトソンの掛け合いにあると感じた。
グールドの架空伝記は奔放で破天荒だったが、本書はかなり抑制的・禁欲的である。あくまで聖典60編を一次史料とし、聖典から推測できない事項の断定を避けている。グールドの伝記より本書の方が面白い。ホームズ像に陰影があり、哀感さえ漂う。
著者はホームズは躁鬱病だとしている。それは大空白時代(1891年の『最後の事件』から1894年の『空家の冒険』まで)の後も継続している。グールドは大空白時代以降、ホームズはコカイン依存を克服したとしているが、本書では克服できていない。
『最後の事件』においてホームズが失踪を決意した動機の追究が面白い。『空家の冒険』でホームズがワトソンに語った動機に無理があるのは確かだ。著者は、躁鬱病だったホームズが抱いた「自分自身から逃げ出して、まったく新しい人格をつくりだしたいという無意識の衝動」を指摘している。
本書の肝はホームズとワトソンの関係の分析である。ホームズのワトソンへの支配欲、それを受け容れるワトソンという相互依存的な「友情」という指摘は説得的だ。そんな関係だから、ワトソンの結婚に冷淡なホームズに哀感が漂う。
グールドはワトソン3回結婚説だが、本書は2回結婚説である。『四つの署名』のメアリ・モースタンが1回目で、彼女は大空白時代に亡くなる。2回目の相手は、何と『ソア橋の怪事件』のグレース・ダンバーだとしている。聖典のみを手掛かりにした緻密な推論に感心した。
『ディアナの森』は地理的紀行が知的迷宮に変転する書 ― 2024年05月18日
一昨年12月、89歳で亡くなった前田耕作先生の次の本を読んだ。先生の尊称を付すのは、カルチャーセンターなどで講義をいくつか受講し、一緒にシチリア旅行をしたこともあり、前田先生と表記しないとしっくりこないからである。
『ディアナの森:ユーロアジア歴史紀行』(前田耕作/せりか書房/1998.7)
本書は互いに絡みあった20編のエセー集成である。私はかなり以前に本書を購入したが、何編かを拾い読みしただけだった。研究者の随想なので未知の固有名詞が頻出し、サラサラとは読めなかったのだ。今回、意を決して頭から通して読んだ。
前田先生は「あとがき」で次のように述べている。
「文字通りのエセー、私語、試考の類で、私の漂流ぶり、パラムナード(漂歩)のさまをより多くの人にみてもらおうと書きかさねたものである。これらのエセーの間隙に書いた『バクトリア王国の興亡』と『宗祖ゾロアスター』とを合わせて読んでいただければ、私が奈辺を漂っているか、およそ察していただけよう。」
昨年2月に開催された追悼シンポジウム「前田耕作先生の業績を語る会」で、後輩学者の一人が「<夢想・歴史・神話/宗教>を結ぶ“前田学”」ということを語っていた。私に難しいことはわからないが、本書によってあらためて、さまざまな遺物や遺跡をベースにアジア・ヨーロッパの異文化交流や精神史を追究した人だったと思った。
ギボンやプルタルコスの史書の講義のとき、先生は史書に出て来る地名をいちいち地図で確認しながら話を進め、その地を訪れた逸話に触れることも多かった。先生の行動範囲の広さに驚いた。古跡巡りの旅行をご一緒したとき「何も残っていなくても、その現場に立ってみることが大事だ」とおっしゃっていた。現場に立てば、書斎で得られないものが見えてくるのだと思う。
「ユーロアジア歴史紀行」のサブタイトルがある本書は、地理的紀行が時間紀行と脳内紀行に変転していくエセー集である。旅行譚のつもりで読み始めるといつの間にやら知的時空の迷宮に引きずりこまれ、知識も知力も乏しい私は途方に暮れそうになる。そんな体験にも一種の心地よさがあり、前田先生の後ろ姿を遠く眺めながら漂流している気分になる。本書に現場の空気が流れているせいだろう。
本書には多くの学者の名が出てくる。私の知らない人が多い。頻出するのは『金枝篇』のフレイザーである。原始宗教・儀礼・神話・習慣などを比較研究した『金枝篇』を私は読んだことがない。大部な書だから読む予定もない。面白そうな世界だろうとは思うが、底なし沼のようでもあり、近づくのがこわい。
『ディアナの森:ユーロアジア歴史紀行』(前田耕作/せりか書房/1998.7)
本書は互いに絡みあった20編のエセー集成である。私はかなり以前に本書を購入したが、何編かを拾い読みしただけだった。研究者の随想なので未知の固有名詞が頻出し、サラサラとは読めなかったのだ。今回、意を決して頭から通して読んだ。
前田先生は「あとがき」で次のように述べている。
「文字通りのエセー、私語、試考の類で、私の漂流ぶり、パラムナード(漂歩)のさまをより多くの人にみてもらおうと書きかさねたものである。これらのエセーの間隙に書いた『バクトリア王国の興亡』と『宗祖ゾロアスター』とを合わせて読んでいただければ、私が奈辺を漂っているか、およそ察していただけよう。」
昨年2月に開催された追悼シンポジウム「前田耕作先生の業績を語る会」で、後輩学者の一人が「<夢想・歴史・神話/宗教>を結ぶ“前田学”」ということを語っていた。私に難しいことはわからないが、本書によってあらためて、さまざまな遺物や遺跡をベースにアジア・ヨーロッパの異文化交流や精神史を追究した人だったと思った。
ギボンやプルタルコスの史書の講義のとき、先生は史書に出て来る地名をいちいち地図で確認しながら話を進め、その地を訪れた逸話に触れることも多かった。先生の行動範囲の広さに驚いた。古跡巡りの旅行をご一緒したとき「何も残っていなくても、その現場に立ってみることが大事だ」とおっしゃっていた。現場に立てば、書斎で得られないものが見えてくるのだと思う。
「ユーロアジア歴史紀行」のサブタイトルがある本書は、地理的紀行が時間紀行と脳内紀行に変転していくエセー集である。旅行譚のつもりで読み始めるといつの間にやら知的時空の迷宮に引きずりこまれ、知識も知力も乏しい私は途方に暮れそうになる。そんな体験にも一種の心地よさがあり、前田先生の後ろ姿を遠く眺めながら漂流している気分になる。本書に現場の空気が流れているせいだろう。
本書には多くの学者の名が出てくる。私の知らない人が多い。頻出するのは『金枝篇』のフレイザーである。原始宗教・儀礼・神話・習慣などを比較研究した『金枝篇』を私は読んだことがない。大部な書だから読む予定もない。面白そうな世界だろうとは思うが、底なし沼のようでもあり、近づくのがこわい。
別役実とつかこうへいを繋ぐ『象』を観た ― 2024年05月20日
上野ストアハウスという小さな劇場で9PROJECT公演『象』(作:別役実、演出:渡辺和徳、出演:小川智之、井上裕朗、高野愛、浦島三太朗、瑠音)を観た。
別役実の初期有名作品『象』は戯曲を読んだはずだが舞台を観ていない。半世紀以上昔の学生時代、別役実は気がかりな劇作家だったが、舞台は観ていない。その心残りのせいか、今頃になって、別役作品の上演があれば、観たくなるのだ。
「9PROJECT」という演劇ユニーットを今回初めて知った。「北区つかこうへい劇団」出身者が、つかこうへい作品を上演するために立ち上げたそうだ。その9PROJECTがなぜ別役実の作品を上演するのか。つかこうへいが別役実の『象』にインスパイアされていたからである。チラシにはつかこうへいの次の言葉を掲載している。
「別役実さんは、私の最も尊敬する人である。(中略)『初級化革命講座飛龍伝』は、『象』の盗作だし、他にも『郵便屋さんちょっと』など盗作ばかりである。」
私は別役実やつかこうへいの芝居もさほど観ていないし、つかこうへいの戯曲はほとんど読んでいない。そんな乏しい経験で語るのは気が引けるが、別役実とつかこうへいの繋がりを感じたことはなかった。『飛龍伝』の舞台は観ているが、別役実を連想することはなかった。
しかし、今回の『象』を観て、これは確かにつかこうへいに通じる舞台だと思った。少しアレンジすれば、つかこうへい作品としてもおかしくないかもしれない。いままでの私の読みの浅さを知った。
『象』は別役実作品には珍しく「被爆者」「原水爆禁止大会」など具体名が出てくる。もちろんリアリズムの芝居ではなく、不思議な空間の不条理劇である。背中のケロイドを見世物にして喝采を浴びることにこだわる主人公は、つかこうへい的だ。だが、静謐で沈鬱な空気が流れている。
『象』の初演は、別役実25歳のときの1962年である(自由舞台=後の早稲田小劇場で上演)。つかこうへいは14歳の中学生だった。私はつかこうへいと同い年だが、別役実の名を知ったのは大学時代の1970年頃だと思う。
私より11歳年長の別役実は60年安保世代である。政治の季節が終わったであろう1962年発表『象』の舞台を観て、「終わった」という当時の空気が色濃く刻印されているように感じた。
別役実の初期有名作品『象』は戯曲を読んだはずだが舞台を観ていない。半世紀以上昔の学生時代、別役実は気がかりな劇作家だったが、舞台は観ていない。その心残りのせいか、今頃になって、別役作品の上演があれば、観たくなるのだ。
「9PROJECT」という演劇ユニーットを今回初めて知った。「北区つかこうへい劇団」出身者が、つかこうへい作品を上演するために立ち上げたそうだ。その9PROJECTがなぜ別役実の作品を上演するのか。つかこうへいが別役実の『象』にインスパイアされていたからである。チラシにはつかこうへいの次の言葉を掲載している。
「別役実さんは、私の最も尊敬する人である。(中略)『初級化革命講座飛龍伝』は、『象』の盗作だし、他にも『郵便屋さんちょっと』など盗作ばかりである。」
私は別役実やつかこうへいの芝居もさほど観ていないし、つかこうへいの戯曲はほとんど読んでいない。そんな乏しい経験で語るのは気が引けるが、別役実とつかこうへいの繋がりを感じたことはなかった。『飛龍伝』の舞台は観ているが、別役実を連想することはなかった。
しかし、今回の『象』を観て、これは確かにつかこうへいに通じる舞台だと思った。少しアレンジすれば、つかこうへい作品としてもおかしくないかもしれない。いままでの私の読みの浅さを知った。
『象』は別役実作品には珍しく「被爆者」「原水爆禁止大会」など具体名が出てくる。もちろんリアリズムの芝居ではなく、不思議な空間の不条理劇である。背中のケロイドを見世物にして喝采を浴びることにこだわる主人公は、つかこうへい的だ。だが、静謐で沈鬱な空気が流れている。
『象』の初演は、別役実25歳のときの1962年である(自由舞台=後の早稲田小劇場で上演)。つかこうへいは14歳の中学生だった。私はつかこうへいと同い年だが、別役実の名を知ったのは大学時代の1970年頃だと思う。
私より11歳年長の別役実は60年安保世代である。政治の季節が終わったであろう1962年発表『象』の舞台を観て、「終わった」という当時の空気が色濃く刻印されているように感じた。


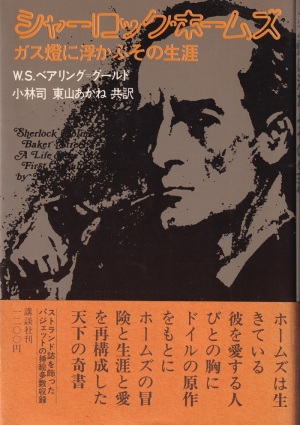

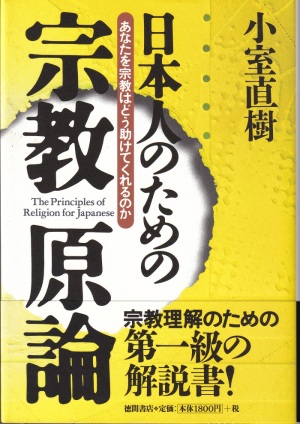





最近のコメント