「沖縄の貧困問題」から想定外の世界に展開する書 ― 2021年11月08日
那覇市の書店の店頭に並んでいた『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』という本をタイトルに惹かれて手に取った。冒頭部分の著者の体験談と困惑が非常に興味深く、先を読みたくなって購入した。
『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』(樋口耕太郎/光文社新書)
1965年生まれの著者は沖縄出身ではないが、16年前から沖縄で暮らしているそうだ。巻末の著者略歴によれば、筑波大学卒業後野村證券に入社し、米国に赴任しニューヨーク大学でMBAを取得、不動産トレーディング会社に転身し金融事業を統括、現在は事業再生会社の社長で沖縄大学の准教授も務めている。この経歴から、事業経営のかたわら大学での講義もこなす頭脳明晰な辣腕事業家をイメージし、そんな人の目で沖縄の問題点を剔出した本だろうと思った。
本書の前半はそんな予感通りの内容で、次々に紹介される興味深い実情に「へぇー」と思いながらスラスラと読み進めた。だが、後半になると次第に趣が変わってきて、私の当初の想定から大きく隔たった世界にひきずりこまれた。経済の話のつもりで読み進めていると、いつの間にか哲学的になり「幸福論」の話になっていた。期待外れだったわけではない。この世の困難に立ちすくむ思いにとらわれた。
沖縄に魅せられている本土人は多いが、沖縄には多くの謎があり、問題点も多い。県民所得は全国最下位で、貧困率も突出している。自殺率や教員の鬱なども全国の他の地域を圧倒している。その根本原因は何か……その追究が本書のテーマであり、著者は、沖縄の社会や沖縄の人々の心性に原因があるとしている。
単純に要約すれば、社会の同調圧力が問題であり、人々に自尊心がないのが問題である。その解決は容易でないが、著者は「人が本当に自分自身を愛すること」「人への関心ではなく、人の関心への関心をもつこと」が重要だと説き「愛の経営」を提唱する。その姿は修道士か伝道師のようでもある。
また、本書後半には著者自身の人生の転機も語っていて、それは回心(えしん)談でもあり、興味深い。
そして巻末で、本書が提示した沖縄問題は日本問題でもあると明言している。「日本の沖縄」は「世界の日本」なのだ。われわれすべてが、やっかいな課題に取り組まねばならないということである。
『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』(樋口耕太郎/光文社新書)
1965年生まれの著者は沖縄出身ではないが、16年前から沖縄で暮らしているそうだ。巻末の著者略歴によれば、筑波大学卒業後野村證券に入社し、米国に赴任しニューヨーク大学でMBAを取得、不動産トレーディング会社に転身し金融事業を統括、現在は事業再生会社の社長で沖縄大学の准教授も務めている。この経歴から、事業経営のかたわら大学での講義もこなす頭脳明晰な辣腕事業家をイメージし、そんな人の目で沖縄の問題点を剔出した本だろうと思った。
本書の前半はそんな予感通りの内容で、次々に紹介される興味深い実情に「へぇー」と思いながらスラスラと読み進めた。だが、後半になると次第に趣が変わってきて、私の当初の想定から大きく隔たった世界にひきずりこまれた。経済の話のつもりで読み進めていると、いつの間にか哲学的になり「幸福論」の話になっていた。期待外れだったわけではない。この世の困難に立ちすくむ思いにとらわれた。
沖縄に魅せられている本土人は多いが、沖縄には多くの謎があり、問題点も多い。県民所得は全国最下位で、貧困率も突出している。自殺率や教員の鬱なども全国の他の地域を圧倒している。その根本原因は何か……その追究が本書のテーマであり、著者は、沖縄の社会や沖縄の人々の心性に原因があるとしている。
単純に要約すれば、社会の同調圧力が問題であり、人々に自尊心がないのが問題である。その解決は容易でないが、著者は「人が本当に自分自身を愛すること」「人への関心ではなく、人の関心への関心をもつこと」が重要だと説き「愛の経営」を提唱する。その姿は修道士か伝道師のようでもある。
また、本書後半には著者自身の人生の転機も語っていて、それは回心(えしん)談でもあり、興味深い。
そして巻末で、本書が提示した沖縄問題は日本問題でもあると明言している。「日本の沖縄」は「世界の日本」なのだ。われわれすべてが、やっかいな課題に取り組まねばならないということである。
『ダム・ウェイター』は不可思議な芝居 ― 2021年11月10日
墨田区の大横川親水公園沿いにある「すみだパークシアター倉」という小劇場でハロルド・ピンターの『ダム・ウェイター』(演出:タカイアキフミ、出演:大野瑞生、横田龍儀)を観た。
半世紀以上昔の大学時代に、演劇の道に進んだ高校同級の友人から『ダム・ウェイター』という芝居がスゴイと聞いたことがある。記憶に残っているのは意味不明の『ダム・ウェイター』というタイトルだけで、どんな内容かは知らないままに半世紀が経過した。
3年前、新国立劇場小劇場でハロルド・ピンターの 『誰もいない国』を観たとき、『ダム・ウェイター』がこのノーベル文学賞作家の作品だと知ったが、タイトルの意味も内容も不明のままだった。今回、『ダム・ウェイター』が上演されると知って早速チケットを購入した。
チケット入手後、たまたま手元の『安部公房全集』をめくっていて、その第24巻に安部公房翻案の『ダム・ウェイター』が収録されているのに気づいた。1973年に安部公房の翻案・演出で安部公房スタジオが『ダム・ウェイター』を上演していたのだ。
事前に安部公房の翻案戯曲を読めたので、およその内容はわかった。解釈困難、意味不明の劇である。タイトルの意味はわかった。直接的には「料理昇降機(リフト)」のことで「唖の給仕」「馬鹿な給仕」「無言の待ち人」なども暗示している。
当然ながら、戯曲を読む体験と観劇という体験は大きく異なる。あのモヤモヤした戯曲を生身の役者が演ずる様を眼前にすると、不可思議な状況の緊迫感とおかしさがヒシヒシと伝わってくる。
この芝居の登場人物は二人の殺し屋、場所はベッドが二つある地下室、二人はそこで何かを待っている。待っているのは、上からの指示のようでもあり、ターゲットの犠牲者のようでもある。この地下室には上階とつながる料理昇降機があり、注文書や料理のやり取りができる。へんてこな設定である。
二人の殺し屋は兄貴分と弟分という関係で、この二人の会話だけで芝居は進行する。二人の意思とは関係なく作動する料理昇降機の不気味さは、戯曲ではさほど感じなかったが、舞台からはダイレクトに伝わってくる。作動するとき響く異様に大きな音が神経に触るし、小さな扉の向こうに何かが潜んでいる気配が怖い。
今回の公演は上演ごとに二人の役者が入れ替わる設定である。それはチラシで了解していたが、実は単に役者が交替するだけでなく、演出も異なっているようだ。「シンプルバージョン」と「アレンジバージョン」を交互に上演しているのだ。私が観たのは「シンプルバージョン」の方だった。「アレンジバージョン」も気がかりだが、私が観劇したのは最終日だったので再訪は無理だ。どんなアレンジがあり得るか、自分で想像してみるのも楽しい。
半世紀以上昔の大学時代に、演劇の道に進んだ高校同級の友人から『ダム・ウェイター』という芝居がスゴイと聞いたことがある。記憶に残っているのは意味不明の『ダム・ウェイター』というタイトルだけで、どんな内容かは知らないままに半世紀が経過した。
3年前、新国立劇場小劇場でハロルド・ピンターの 『誰もいない国』を観たとき、『ダム・ウェイター』がこのノーベル文学賞作家の作品だと知ったが、タイトルの意味も内容も不明のままだった。今回、『ダム・ウェイター』が上演されると知って早速チケットを購入した。
チケット入手後、たまたま手元の『安部公房全集』をめくっていて、その第24巻に安部公房翻案の『ダム・ウェイター』が収録されているのに気づいた。1973年に安部公房の翻案・演出で安部公房スタジオが『ダム・ウェイター』を上演していたのだ。
事前に安部公房の翻案戯曲を読めたので、およその内容はわかった。解釈困難、意味不明の劇である。タイトルの意味はわかった。直接的には「料理昇降機(リフト)」のことで「唖の給仕」「馬鹿な給仕」「無言の待ち人」なども暗示している。
当然ながら、戯曲を読む体験と観劇という体験は大きく異なる。あのモヤモヤした戯曲を生身の役者が演ずる様を眼前にすると、不可思議な状況の緊迫感とおかしさがヒシヒシと伝わってくる。
この芝居の登場人物は二人の殺し屋、場所はベッドが二つある地下室、二人はそこで何かを待っている。待っているのは、上からの指示のようでもあり、ターゲットの犠牲者のようでもある。この地下室には上階とつながる料理昇降機があり、注文書や料理のやり取りができる。へんてこな設定である。
二人の殺し屋は兄貴分と弟分という関係で、この二人の会話だけで芝居は進行する。二人の意思とは関係なく作動する料理昇降機の不気味さは、戯曲ではさほど感じなかったが、舞台からはダイレクトに伝わってくる。作動するとき響く異様に大きな音が神経に触るし、小さな扉の向こうに何かが潜んでいる気配が怖い。
今回の公演は上演ごとに二人の役者が入れ替わる設定である。それはチラシで了解していたが、実は単に役者が交替するだけでなく、演出も異なっているようだ。「シンプルバージョン」と「アレンジバージョン」を交互に上演しているのだ。私が観たのは「シンプルバージョン」の方だった。「アレンジバージョン」も気がかりだが、私が観劇したのは最終日だったので再訪は無理だ。どんなアレンジがあり得るか、自分で想像してみるのも楽しい。
沖縄復帰から約半世紀の体験的世相史 ― 2021年11月13日
那覇市の書店の店頭に地産本のベストセラーとして積まれていた次の新書を読んだ。
『増補改訂 ぼくの沖縄〈復帰後〉史プラス』(新城和博/ボーダー新書/ボーダーインク)
本書の版元ボーダーインクは那覇市の出版社で、本書の著者はその設立に関わった人である。1963年那覇市生まれの著者・新城和博氏は琉球大学卒業後、福岡で就職するが1か月で沖縄に戻り、その後は沖縄で活躍している編集者である。地元の新聞へ寄稿するコラムニストでラジオやテレビにも出演し、多数の著書がある。
本書は沖縄タイムスに連載した「沖縄復帰後史 我らの時代のフォークロア」をまとめたもので、それぞれの時代のトピックを語るコラム集成である。連載は2012年に終了し、本書初版は2014年に刊行、その後の2020年までのトピックを追加したのが、この増補改訂版である。2020年8月第2刷の本書には、首里城焼失や新型コロナウイルスの話も載っている。
この半世紀の間に沖縄ではさまざまな出来事があった。現地の人がそれをどんな気分で体験してきたか、その時々の空気が伝わってくる本である。
沖縄の本土復帰は1972年(来年で50年だ)、著者は9歳の小学生だった。それから約半世紀の間に著者が体験したアレコレの思い出を積み上げた本書は、読みやすい沖縄世相史・文化史である。各コラムの末尾に註釈と出来事年表があり、私のような部外者には勉強になる。
海洋博、具志堅用高、喜納昌吉、安室奈美恵、沖縄サミット、高校野球、オスプレイなど話題は多岐にわたる。知事選や県民集会の話題も多い。著者は太田昌秀革新県政支持、辺野古移転反対、オール沖縄の翁長知事、玉城知事支援であり、その時々の心情を率直に語っている。人によって考えはさまざまだろうが、沖縄の人々の平均的な思いを反映していると感じた。
面白く思ったのは首里城の見方である。1992年に首里城が復元オープンしたとき、「ハリボテでしょう」という意見に著者は共鳴していたそうだ。でも、復元作業に携わった人の苦労を知るにつけ、首里城の意義も理解するようになる。そして27年後、首里城焼失を眼前にしたとき、首里城は27年かけて沖縄のシンボルになっていたと気づき、焼失したことによって存在感が増したと感じるのである。
『増補改訂 ぼくの沖縄〈復帰後〉史プラス』(新城和博/ボーダー新書/ボーダーインク)
本書の版元ボーダーインクは那覇市の出版社で、本書の著者はその設立に関わった人である。1963年那覇市生まれの著者・新城和博氏は琉球大学卒業後、福岡で就職するが1か月で沖縄に戻り、その後は沖縄で活躍している編集者である。地元の新聞へ寄稿するコラムニストでラジオやテレビにも出演し、多数の著書がある。
本書は沖縄タイムスに連載した「沖縄復帰後史 我らの時代のフォークロア」をまとめたもので、それぞれの時代のトピックを語るコラム集成である。連載は2012年に終了し、本書初版は2014年に刊行、その後の2020年までのトピックを追加したのが、この増補改訂版である。2020年8月第2刷の本書には、首里城焼失や新型コロナウイルスの話も載っている。
この半世紀の間に沖縄ではさまざまな出来事があった。現地の人がそれをどんな気分で体験してきたか、その時々の空気が伝わってくる本である。
沖縄の本土復帰は1972年(来年で50年だ)、著者は9歳の小学生だった。それから約半世紀の間に著者が体験したアレコレの思い出を積み上げた本書は、読みやすい沖縄世相史・文化史である。各コラムの末尾に註釈と出来事年表があり、私のような部外者には勉強になる。
海洋博、具志堅用高、喜納昌吉、安室奈美恵、沖縄サミット、高校野球、オスプレイなど話題は多岐にわたる。知事選や県民集会の話題も多い。著者は太田昌秀革新県政支持、辺野古移転反対、オール沖縄の翁長知事、玉城知事支援であり、その時々の心情を率直に語っている。人によって考えはさまざまだろうが、沖縄の人々の平均的な思いを反映していると感じた。
面白く思ったのは首里城の見方である。1992年に首里城が復元オープンしたとき、「ハリボテでしょう」という意見に著者は共鳴していたそうだ。でも、復元作業に携わった人の苦労を知るにつけ、首里城の意義も理解するようになる。そして27年後、首里城焼失を眼前にしたとき、首里城は27年かけて沖縄のシンボルになっていたと気づき、焼失したことによって存在感が増したと感じるのである。
井上靖の西域短篇『楼蘭』を読んだ ― 2021年11月17日
私にとって井上靖は遠い記憶の中の作家だ。半世紀以上昔の中学・高校時代に読んだいくつかの小説に感銘を受けたが、その後は関心外の作家だった。齢を重ねてシルクロード史に関心を抱くようになり、井上靖の「西域モノ」が気がかりになり未読の『楼蘭』を読んだ。
『楼蘭』(井上靖/新潮文庫)
本書は12篇の短篇集である。『楼蘭』は『敦煌』のような長編小説ではなく50頁ほどの短篇である。いまや敦煌は人々が押しよせる観光地になっているらしいが、タクラマカン砂漠に埋もれた楼蘭はいまだに秘境であり、ロマンあふれる謎を秘めている。
短篇『楼蘭』はエッセイ風の叙事詩的年代記で、古代人が波乱万丈を繰り広げる物語ではない。結末部では1500年周期で移動するヘディンの「さまよえる湖」に言及し、悠久の時間を超えて現代と古代をつなでいる。「さまよえる湖」に魅せられていた高校生の頃にこの小説を読んでいれば、うっとりと感動したと思う。だが、「さまよえる湖」が否定されている現在の読後感は多少しらける。でも、楼蘭や鄯善に関する具体的なイメージを紡ぐことができた。
この短篇集で不意打ちだったのは『異域の人』である。私はこの短篇を高校1年の時に読んでいる。自発的に読んだのではない。古典の授業中に若い教師が「井上靖の『異域の人』は最後の文章がいい」と語ったので、角川文庫の薄い短篇集『異域の人』を買って読んだのである。その短篇のラストの「むなしさ」の印象はかすかに残っている。だが、小説の内容はまったく失念している。(あの教師は、後に国立劇場研究員を経て千葉大教授になった、高名な歌舞伎研究者・服部幸雄先生である)
今回、半世紀以上を経て『異域の人』を再読し、この小説が班超の話だとあらためて知った。高校1年のときにこの小説をどう読んだかの記憶は全くよみがえってこない。当時、班超の名を知っていたはずがない。背伸びし無理して読んだのだろう。ラストの印象は半世紀以上昔とさはど変わらない。この半世紀が長いようにも短いようにも思える。
『楼蘭』(井上靖/新潮文庫)
本書は12篇の短篇集である。『楼蘭』は『敦煌』のような長編小説ではなく50頁ほどの短篇である。いまや敦煌は人々が押しよせる観光地になっているらしいが、タクラマカン砂漠に埋もれた楼蘭はいまだに秘境であり、ロマンあふれる謎を秘めている。
短篇『楼蘭』はエッセイ風の叙事詩的年代記で、古代人が波乱万丈を繰り広げる物語ではない。結末部では1500年周期で移動するヘディンの「さまよえる湖」に言及し、悠久の時間を超えて現代と古代をつなでいる。「さまよえる湖」に魅せられていた高校生の頃にこの小説を読んでいれば、うっとりと感動したと思う。だが、「さまよえる湖」が否定されている現在の読後感は多少しらける。でも、楼蘭や鄯善に関する具体的なイメージを紡ぐことができた。
この短篇集で不意打ちだったのは『異域の人』である。私はこの短篇を高校1年の時に読んでいる。自発的に読んだのではない。古典の授業中に若い教師が「井上靖の『異域の人』は最後の文章がいい」と語ったので、角川文庫の薄い短篇集『異域の人』を買って読んだのである。その短篇のラストの「むなしさ」の印象はかすかに残っている。だが、小説の内容はまったく失念している。(あの教師は、後に国立劇場研究員を経て千葉大教授になった、高名な歌舞伎研究者・服部幸雄先生である)
今回、半世紀以上を経て『異域の人』を再読し、この小説が班超の話だとあらためて知った。高校1年のときにこの小説をどう読んだかの記憶は全くよみがえってこない。当時、班超の名を知っていたはずがない。背伸びし無理して読んだのだろう。ラストの印象は半世紀以上昔とさはど変わらない。この半世紀が長いようにも短いようにも思える。
井上靖はソグド人遺跡「ペンジケント」を書いていた ― 2021年11月19日
井上靖の短篇集『楼蘭』に続いて短篇種『崑崙の玉/漂流』を読んだ。
『崑崙の玉/漂流』(井上靖/講談社文芸文庫)
本書には10篇が収録されている。井上靖の「西域モノ」をチェックしておこうとひも解いたが、中国や中央アジアを舞台にした小説は表題作を含めて3篇だけだ。
『崑崙の玉』という題名は、数年前に再放送で観たNHKのシルクロードで新疆ウイグル自治区のホータン(于闐)を紹介する際に言及があり、それ以来気がかりだった。ホータンは古代から玉(ぎょく)の産地として有名で、その玉は「ホータンの玉」あるいは「崑崙の玉」と呼ばれたそうだ。テレビには、いまも(取材時の1980年頃)も農作業の片手間に河原で玉を探す人の姿が映っていた。
『崑崙の玉』は千年以上昔の五代時代の物語である。玉を探し求める話だと思って読み始めたが、途中から黄河の水源を探る話になり、ロブ湖がからんでくる。遠い時代の遠い地理を多少は身近に感じることができ、面白かった。
この短篇集で感激したのは別の西域モノ『古代ペンジケント』である。私は2年前にタジキスタンの ペンジケント遺跡を訪問している。ペンジケントはソグド人の都市遺跡である。ソグド人に関心があった私は、旅行前にペンジケントに関する資料を集めて目を通したが、この小説の存在は知らなかった。迂闊だった。
本書の目次を開いたとき「古代ペンジケント」という文字が目に飛び込み、驚いた。この小説は井上靖を思わせる「私」がペンジケントを訪れる話である。小説ではなく紀行文かなと思いながら読み進めたが、やはり小説だった(実話の可能性がないわけではないが…)。
巻末の年譜を見ると井上靖は1965年(58歳)にソ連領中央アジアを旅行している。その際にペンジケントに行ったのだろう。
この小説のメインは、現地ガイド(本職はタイル業、考古学が趣味で発掘の手伝いをしている青年)の大演説である。それはソグド人の歴史物語であり、発掘物語でもある。その基本的内容は史料に基づいたもので、とても勉強になった。半世紀以上昔に井上靖はこんなにわかりやすい「史料解説」を書いていたのだ。
つくづく、一昨年の旅行の前にこの小説を読んでおけば、と悔やまれる。
『崑崙の玉/漂流』(井上靖/講談社文芸文庫)
本書には10篇が収録されている。井上靖の「西域モノ」をチェックしておこうとひも解いたが、中国や中央アジアを舞台にした小説は表題作を含めて3篇だけだ。
『崑崙の玉』という題名は、数年前に再放送で観たNHKのシルクロードで新疆ウイグル自治区のホータン(于闐)を紹介する際に言及があり、それ以来気がかりだった。ホータンは古代から玉(ぎょく)の産地として有名で、その玉は「ホータンの玉」あるいは「崑崙の玉」と呼ばれたそうだ。テレビには、いまも(取材時の1980年頃)も農作業の片手間に河原で玉を探す人の姿が映っていた。
『崑崙の玉』は千年以上昔の五代時代の物語である。玉を探し求める話だと思って読み始めたが、途中から黄河の水源を探る話になり、ロブ湖がからんでくる。遠い時代の遠い地理を多少は身近に感じることができ、面白かった。
この短篇集で感激したのは別の西域モノ『古代ペンジケント』である。私は2年前にタジキスタンの ペンジケント遺跡を訪問している。ペンジケントはソグド人の都市遺跡である。ソグド人に関心があった私は、旅行前にペンジケントに関する資料を集めて目を通したが、この小説の存在は知らなかった。迂闊だった。
本書の目次を開いたとき「古代ペンジケント」という文字が目に飛び込み、驚いた。この小説は井上靖を思わせる「私」がペンジケントを訪れる話である。小説ではなく紀行文かなと思いながら読み進めたが、やはり小説だった(実話の可能性がないわけではないが…)。
巻末の年譜を見ると井上靖は1965年(58歳)にソ連領中央アジアを旅行している。その際にペンジケントに行ったのだろう。
この小説のメインは、現地ガイド(本職はタイル業、考古学が趣味で発掘の手伝いをしている青年)の大演説である。それはソグド人の歴史物語であり、発掘物語でもある。その基本的内容は史料に基づいたもので、とても勉強になった。半世紀以上昔に井上靖はこんなにわかりやすい「史料解説」を書いていたのだ。
つくづく、一昨年の旅行の前にこの小説を読んでおけば、と悔やまれる。
米国占領下の沖縄が舞台のエンタメ『宝島』は伝説談のようだ ― 2021年11月22日
那覇市の古本屋で入手した次の小説を読んだ。
『宝島』(真藤順丈/講談社)
2年前の直木賞受賞でこの小説を知り、戦後沖縄を舞台にしたメルヘン風の悪童物語というイメージを抱いていた。開高健の『日本三文オペラ』や小松左京の『日本アパッチ族』のようなバイタリティあふれる小説を予感した。私の予感は半分当たり、半分はずれた。
米軍基地からの窃盗団「戦果アギャー(戦果をあげる者)」をめぐるこの物語は、予感した以上に軽快にブッ飛んでいて、予感した以上にシリアスだった。、沖縄方言満載の不思議な一千枚である。
著者は東京出身だそうだが、それを知らずに読むと、作者を沖縄出身と思い込んだだろう(沖縄の人がどう感じるかは不明だが)。会話部分だけでなく地の文章も沖縄方言があふれている。この奇妙な「語り」の随所にカッコつきのツッコミが挿入されていて、読み始めてしばらくは、この「語り手」は何者だろうと気になった。やがて、それは自称「語り部」だと気づく。それも、集合的な語り部らしいのである。神話や伝説の雰囲気が漂う面白い手法だ。
主な登場人物の名もどこか神話的だ。オンちゃん、グスク、レイ、ヤマコ、ウタなどである。漢字名の人物も登場する。そのほとんどは実在の人物で、瀬長亀次郎(沖縄人民党書記長→那覇市長→衆議院議員)、屋良朝苗(沖縄教職員会長→行政主席→沖縄県知事)、喜捨場朝信(ヤクザの親分)、又吉世喜(ヤクザの親分)などである。これらのカタカナ名と漢字名の人物が入り混じって物語が展開していく。
そんな物語は1952年から1972年までのアメリカ占領下の沖縄、つまり「アメリカ世」の沖縄の歴史と沖縄の人々の感性をダイレクトに反映している。米軍機墜落事故やコザ暴動も出てくる。占領下の20年という時間は新生児が成年になるまでの濃密な時間であり、沖縄の人民史を伝説のように語る小説である。
『宝島』(真藤順丈/講談社)
2年前の直木賞受賞でこの小説を知り、戦後沖縄を舞台にしたメルヘン風の悪童物語というイメージを抱いていた。開高健の『日本三文オペラ』や小松左京の『日本アパッチ族』のようなバイタリティあふれる小説を予感した。私の予感は半分当たり、半分はずれた。
米軍基地からの窃盗団「戦果アギャー(戦果をあげる者)」をめぐるこの物語は、予感した以上に軽快にブッ飛んでいて、予感した以上にシリアスだった。、沖縄方言満載の不思議な一千枚である。
著者は東京出身だそうだが、それを知らずに読むと、作者を沖縄出身と思い込んだだろう(沖縄の人がどう感じるかは不明だが)。会話部分だけでなく地の文章も沖縄方言があふれている。この奇妙な「語り」の随所にカッコつきのツッコミが挿入されていて、読み始めてしばらくは、この「語り手」は何者だろうと気になった。やがて、それは自称「語り部」だと気づく。それも、集合的な語り部らしいのである。神話や伝説の雰囲気が漂う面白い手法だ。
主な登場人物の名もどこか神話的だ。オンちゃん、グスク、レイ、ヤマコ、ウタなどである。漢字名の人物も登場する。そのほとんどは実在の人物で、瀬長亀次郎(沖縄人民党書記長→那覇市長→衆議院議員)、屋良朝苗(沖縄教職員会長→行政主席→沖縄県知事)、喜捨場朝信(ヤクザの親分)、又吉世喜(ヤクザの親分)などである。これらのカタカナ名と漢字名の人物が入り混じって物語が展開していく。
そんな物語は1952年から1972年までのアメリカ占領下の沖縄、つまり「アメリカ世」の沖縄の歴史と沖縄の人々の感性をダイレクトに反映している。米軍機墜落事故やコザ暴動も出てくる。占領下の20年という時間は新生児が成年になるまでの濃密な時間であり、沖縄の人民史を伝説のように語る小説である。
青木繁の『海の幸』から派生した森村泰昌の歴史パノラマを観た ― 2021年11月24日
アーティゾン美術館で『M式「海の幸」森村泰昌:ワタシガタリの神話』という展示を観た。この美術館は元ブリヂストン美術館で、2年前に京橋の高層ビルにオープンした。写真撮影原則OKなのがいい。
森村泰昌氏は名画の人物や有名人に扮したセルフポートレート写真で名高い美術家である。新聞や雑誌で森村氏の奇怪な作品を知り、いつか観たいと思っていた。現物作品を眼前にすると、やはり迫力を感じる。
今回、森村氏が扮するのは青木繁の『海の幸』である。この美術館が所蔵する本物の『海の幸』をはじめ青木繁の作品数点も同時に展示している。面白い企画だ。青木繁に扮した森村氏が、28歳で夭逝した青木繁に語りかける『ワタシガタリの神話』という動画作品を会場内で上演している。
10人の人物が描かれた『海の幸』の森村版には10点のバージョンがある。作中人物に扮した10人の森村氏が登場するオリジナルに似せた作品の他にさまざまな興味深い作品を展示している。『海の幸』は1904年(明治37年)の作品で、森村版はその後の歴史を反映する仕掛けになっている。1964年の東京オリンピック開会式や1960年代末のゲバ棒学生群像などもあり、現代史のパノラマのようだ。
これら10点のタイトルも興味深い。『假象の創造』『それから』『パノラマ島綺譚』『暗い絵』『復活の日1』『われらの時代』『復活の日2』『モードの迷宮』『たそがれに還る』『豊穣の海』である。私の読んだ小説ばかりでうれしくなった。わからなかったのは『假象の創造』と『モードの迷宮』で、調べてみると前者は青木繁の文集のタイトル、後者は鷲田清一の著作名だった。それにしても、光瀬龍の『たそがれに還る』に出会えたのは驚きだった。
オリジナルと似たポーズの作品もあるが、そうでないものもある。戦争場面のバージョン『暗い絵』が藤田嗣治の戦争画『アッツ島玉砕』を模しているのはわかったが、他はよくわからなかった。何かを模しているのだろうと思うが。
最後から2枚目は途上人物が4人に減少し、最後の1枚は一人だけになってしまう。その一人は人間なのか非人類なのかよくわからない。地球の未来の暗示だと思う。
森村泰昌氏は名画の人物や有名人に扮したセルフポートレート写真で名高い美術家である。新聞や雑誌で森村氏の奇怪な作品を知り、いつか観たいと思っていた。現物作品を眼前にすると、やはり迫力を感じる。
今回、森村氏が扮するのは青木繁の『海の幸』である。この美術館が所蔵する本物の『海の幸』をはじめ青木繁の作品数点も同時に展示している。面白い企画だ。青木繁に扮した森村氏が、28歳で夭逝した青木繁に語りかける『ワタシガタリの神話』という動画作品を会場内で上演している。
10人の人物が描かれた『海の幸』の森村版には10点のバージョンがある。作中人物に扮した10人の森村氏が登場するオリジナルに似せた作品の他にさまざまな興味深い作品を展示している。『海の幸』は1904年(明治37年)の作品で、森村版はその後の歴史を反映する仕掛けになっている。1964年の東京オリンピック開会式や1960年代末のゲバ棒学生群像などもあり、現代史のパノラマのようだ。
これら10点のタイトルも興味深い。『假象の創造』『それから』『パノラマ島綺譚』『暗い絵』『復活の日1』『われらの時代』『復活の日2』『モードの迷宮』『たそがれに還る』『豊穣の海』である。私の読んだ小説ばかりでうれしくなった。わからなかったのは『假象の創造』と『モードの迷宮』で、調べてみると前者は青木繁の文集のタイトル、後者は鷲田清一の著作名だった。それにしても、光瀬龍の『たそがれに還る』に出会えたのは驚きだった。
オリジナルと似たポーズの作品もあるが、そうでないものもある。戦争場面のバージョン『暗い絵』が藤田嗣治の戦争画『アッツ島玉砕』を模しているのはわかったが、他はよくわからなかった。何かを模しているのだろうと思うが。
最後から2枚目は途上人物が4人に減少し、最後の1枚は一人だけになってしまう。その一人は人間なのか非人類なのかよくわからない。地球の未来の暗示だと思う。
キタイ(契丹)と平将門のつながりに驚いた ― 2021年11月26日
モンゴル史研究の第一人者・杉山正明氏の次の本を読んだ。
『疾駆する草原の征服者』(杉山正明/中国の歴史08/講談社)
講談社の叢書「中国の歴史」の第8巻で2005年刊行である。今年になって講談社学術文庫になったが、私が読んだのは昨年入手したハードカバーである。
安禄山の挙兵からモンゴル帝国解体まで、8世紀半ばから14世紀半ばまでの約600年の中国史を描いている。中華王朝史観・西欧中心史観の見直しを提唱する杉山氏の歴史書だから、中国「正史」のバイアスを批判的に検討し、世界史的視点を提示している。
巻末に主要人物略伝がある。取り上げているのは安禄山(安史の乱)、安思明(安史の乱)、耶律阿保機(キタイ帝国)、朱全忠(後梁)、李克用(沙陀軍閥)、李存勗(沙陀軍閥)、耶律突欲(キタイ皇子)、チンギス・カン(モンゴル帝国)、クビライ(モンゴル帝国)の9人で、本書は彼らの活躍を中心に600年の中国史を描いている。
本書が扱うスパンは高校世界史では「唐・五代十国・宋・金・南宋・元」と憶える時代だが、杉山氏はそのような中国「王朝」に基づく見方では歴史の実態を見誤ると警告している。これらの「国」はワンノブゼムに過ぎず、その周囲には対等あるいはより強力な「国」がいくつも存在し、それらが多元的に盛衰をくり返していたのだ。
特に唐に関して、日本人は唐を大王朝と特別視する傾向があるが、唐が「世界帝国」だったのは初期の一瞬との指摘に、大唐にロマンを感じている私はドキッとした。
これまでに私が読んだ杉山氏の著作はモンゴルがメインだったが、本書はそれ以前がメインで、「キタイ(契丹)vs 沙陀」にかなりのページを費やしている。史料が少なく不明の点も多いキタイの記述に力点をおき、現地調査の報告も収録している。
私が驚いたのは、平将門の乱(939年)とキタイを関連付けている点だ。乱を起こした将門は奏状で、おのれの正統性を支える事例としてキタイの阿保機による渤海国接収(926年)に言及しているそうだ。大陸や半島における「時代」急変の震動が日本にも伝わり、平将門や藤原純友の「反乱」につながった――杉山氏はそんな推測を述べている。ダイナミックな見方である。
また、『資治通鑑』を執筆した宋の司馬光を「心性は子ども」「浅知恵がみじめ」などと徹底的に批判しているのが面白い。漢文の史書がいかに事実を歪曲しているかの指摘であり、史書の読み方の難しさを感じた。同時に現代にも通じる「歴史認識」の危うさや難しさに思いを馳せた。
『疾駆する草原の征服者』(杉山正明/中国の歴史08/講談社)
講談社の叢書「中国の歴史」の第8巻で2005年刊行である。今年になって講談社学術文庫になったが、私が読んだのは昨年入手したハードカバーである。
安禄山の挙兵からモンゴル帝国解体まで、8世紀半ばから14世紀半ばまでの約600年の中国史を描いている。中華王朝史観・西欧中心史観の見直しを提唱する杉山氏の歴史書だから、中国「正史」のバイアスを批判的に検討し、世界史的視点を提示している。
巻末に主要人物略伝がある。取り上げているのは安禄山(安史の乱)、安思明(安史の乱)、耶律阿保機(キタイ帝国)、朱全忠(後梁)、李克用(沙陀軍閥)、李存勗(沙陀軍閥)、耶律突欲(キタイ皇子)、チンギス・カン(モンゴル帝国)、クビライ(モンゴル帝国)の9人で、本書は彼らの活躍を中心に600年の中国史を描いている。
本書が扱うスパンは高校世界史では「唐・五代十国・宋・金・南宋・元」と憶える時代だが、杉山氏はそのような中国「王朝」に基づく見方では歴史の実態を見誤ると警告している。これらの「国」はワンノブゼムに過ぎず、その周囲には対等あるいはより強力な「国」がいくつも存在し、それらが多元的に盛衰をくり返していたのだ。
特に唐に関して、日本人は唐を大王朝と特別視する傾向があるが、唐が「世界帝国」だったのは初期の一瞬との指摘に、大唐にロマンを感じている私はドキッとした。
これまでに私が読んだ杉山氏の著作はモンゴルがメインだったが、本書はそれ以前がメインで、「キタイ(契丹)vs 沙陀」にかなりのページを費やしている。史料が少なく不明の点も多いキタイの記述に力点をおき、現地調査の報告も収録している。
私が驚いたのは、平将門の乱(939年)とキタイを関連付けている点だ。乱を起こした将門は奏状で、おのれの正統性を支える事例としてキタイの阿保機による渤海国接収(926年)に言及しているそうだ。大陸や半島における「時代」急変の震動が日本にも伝わり、平将門や藤原純友の「反乱」につながった――杉山氏はそんな推測を述べている。ダイナミックな見方である。
また、『資治通鑑』を執筆した宋の司馬光を「心性は子ども」「浅知恵がみじめ」などと徹底的に批判しているのが面白い。漢文の史書がいかに事実を歪曲しているかの指摘であり、史書の読み方の難しさを感じた。同時に現代にも通じる「歴史認識」の危うさや難しさに思いを馳せた。
4人の役者の役が目まぐるしく変転する『叔母との旅』 ― 2021年11月28日
サンシャイン劇場で加藤健一事務所の『叔母との旅』(原作:グレアム・グリーン、脚色:ジャイルズ・ハヴァガル、演出:鵜山仁、出演:加藤健一、雨宮良、清水明彦、加藤義宗)を観た。
加藤健一事務所の芝居は大昔に一度観たきりで、久々である。加藤健一は私より1歳下の1949年生まれ72歳だ。いまだ元気で若いのを確認し、なぜかホッとした。
軽快なコメディを予感して劇場に赴き、確かにそうではあったが、かなり特異な仕掛けに驚いた。原作はグレアム・グリーンの小説(私は未読)なので渋いユーモアがある。脚色が特異なのだ。
会話だけでなく、地の文章も役者が語る作りになっている。語り手は主人公のヘンリー・プリングで、朗読劇のようでもある。登場する役者は4人だけで、4人が地の文と「科白&演技」を分担し、それが目まぐるしく変転する。一人が何人もの役を演じるだけでなく、4人が交替で一人の人物を演じたりもする。時には黒子にもなる。冒頭部分だけの仕掛けかと思ったが、これが最後まで続いた。
チラシを見たとき、『叔母との旅』というタイトルなのに出演は男優4人だけなので、「叔母」は登場しない芝居かと思った。しかし「叔母」だけでなく何人かの女性がしっかり舞台に登場する。それを男優たちが「語り」の合間に演じるのである。一人で何役もこなす「落語」のように語りながら、複数の役者が役を交替しながら舞台を動き回る芝居である。演じる役者も大変だろうが観る方も混乱しそうになる。この面白い仕掛けを、最後まで飽きることなく堪能できた。
大筋は、銀行を定年退職した50代の主人公(ロンドン在住)が、母親の葬儀で初めて対面した奔放な叔母(母の妹)に振り回されて、イスタンブール、アルゼンチン、パラグアイなどを旅する話である。その中で主人公の心境が次第に変化していく。ハッピーエンドではあるが、本当にこれで大丈夫なのかという気もする。
加藤健一事務所の芝居は大昔に一度観たきりで、久々である。加藤健一は私より1歳下の1949年生まれ72歳だ。いまだ元気で若いのを確認し、なぜかホッとした。
軽快なコメディを予感して劇場に赴き、確かにそうではあったが、かなり特異な仕掛けに驚いた。原作はグレアム・グリーンの小説(私は未読)なので渋いユーモアがある。脚色が特異なのだ。
会話だけでなく、地の文章も役者が語る作りになっている。語り手は主人公のヘンリー・プリングで、朗読劇のようでもある。登場する役者は4人だけで、4人が地の文と「科白&演技」を分担し、それが目まぐるしく変転する。一人が何人もの役を演じるだけでなく、4人が交替で一人の人物を演じたりもする。時には黒子にもなる。冒頭部分だけの仕掛けかと思ったが、これが最後まで続いた。
チラシを見たとき、『叔母との旅』というタイトルなのに出演は男優4人だけなので、「叔母」は登場しない芝居かと思った。しかし「叔母」だけでなく何人かの女性がしっかり舞台に登場する。それを男優たちが「語り」の合間に演じるのである。一人で何役もこなす「落語」のように語りながら、複数の役者が役を交替しながら舞台を動き回る芝居である。演じる役者も大変だろうが観る方も混乱しそうになる。この面白い仕掛けを、最後まで飽きることなく堪能できた。
大筋は、銀行を定年退職した50代の主人公(ロンドン在住)が、母親の葬儀で初めて対面した奔放な叔母(母の妹)に振り回されて、イスタンブール、アルゼンチン、パラグアイなどを旅する話である。その中で主人公の心境が次第に変化していく。ハッピーエンドではあるが、本当にこれで大丈夫なのかという気もする。
多元複合の世界国家モンゴルを描いた『大モンゴルの世界』 ― 2021年11月30日
『疾駆する草原の征服者』に続いて同じ著者の次の本を読んだ。
『大モンゴルの世界:陸と海の巨大帝国』(杉山正明/角川ソフィア文庫)
杉山正明氏の本を読むのは8冊目である。年のせいか、本を読んでも少し時間が経てばその内容の大半が蒸発する。特に歴史書は、アレコレの事象が頭の中でゴチャゴチャに霞んでいく傾向が強い。再読、再々読すればいいのだが、類書を読む方が目先が変わって楽しい。だから、本書を読んだ。
この文庫版の原著は1992年刊行、著者の一般向け概説書では最も古いものだ。獰猛な破壊者モンゴルという見方を否定し、13世紀のクビライ朝によってユーラシアの東西をつなぐ「世界史」が登場したという著者の見解を過不足なく展開している。
チンギス・カンからクビライ朝に至る13~14世紀が中心だが、それ以前の遊牧の起源や草原国家の解説から書き起こし、それ以降の明、清、ティムール、ムガル、オスマン、ロシアにまで言及している。人類の世界史の基盤を俯瞰した気分になる。
本書であらためて認識したのはモンゴルとは民族の名でも人種の名でもないという見解である。それが民族や人種を指すようになったのは近代になってからだ。
遊牧民はいくつもの人間のかたまりとして行動し、そのかたまりが離合集散を繰り返す。もともとは小さな部族集団だったモンゴルは、チンギスの登場によって他の多くの部族集団を統合し「大モンゴル国」を形成する。その集団にはトルコ系やモンゴル系などの雑多な人々がいた。杉山氏は「大モンゴル国」を多元複合の世界国家と述べている。それは、われわれが知っている近代の「帝国」とはかなり違うイメージの世界国家だったと思われる。
中央ユーラシアの歴史を眺めるとき、さまざまの国や人間集団をモンゴル系、トルコ系、イラン系、チベット系などと分別したくなる。それは無意味ではないと思うが、あまり重視すると近代人の偏見で歴史を観ることになりそうだ。
人種とは別の「人間のかたまり」が西へ東へ(あるいは南へ北へ)移動しながら離合集散・融合拡散を繰り返し、争乱の時代や大帝国の時代を織りなしてきた――そんな、ダイナミックなイメージで歴史を捉えたい。本書を読んで、そんなことを考えた。
『大モンゴルの世界:陸と海の巨大帝国』(杉山正明/角川ソフィア文庫)
杉山正明氏の本を読むのは8冊目である。年のせいか、本を読んでも少し時間が経てばその内容の大半が蒸発する。特に歴史書は、アレコレの事象が頭の中でゴチャゴチャに霞んでいく傾向が強い。再読、再々読すればいいのだが、類書を読む方が目先が変わって楽しい。だから、本書を読んだ。
この文庫版の原著は1992年刊行、著者の一般向け概説書では最も古いものだ。獰猛な破壊者モンゴルという見方を否定し、13世紀のクビライ朝によってユーラシアの東西をつなぐ「世界史」が登場したという著者の見解を過不足なく展開している。
チンギス・カンからクビライ朝に至る13~14世紀が中心だが、それ以前の遊牧の起源や草原国家の解説から書き起こし、それ以降の明、清、ティムール、ムガル、オスマン、ロシアにまで言及している。人類の世界史の基盤を俯瞰した気分になる。
本書であらためて認識したのはモンゴルとは民族の名でも人種の名でもないという見解である。それが民族や人種を指すようになったのは近代になってからだ。
遊牧民はいくつもの人間のかたまりとして行動し、そのかたまりが離合集散を繰り返す。もともとは小さな部族集団だったモンゴルは、チンギスの登場によって他の多くの部族集団を統合し「大モンゴル国」を形成する。その集団にはトルコ系やモンゴル系などの雑多な人々がいた。杉山氏は「大モンゴル国」を多元複合の世界国家と述べている。それは、われわれが知っている近代の「帝国」とはかなり違うイメージの世界国家だったと思われる。
中央ユーラシアの歴史を眺めるとき、さまざまの国や人間集団をモンゴル系、トルコ系、イラン系、チベット系などと分別したくなる。それは無意味ではないと思うが、あまり重視すると近代人の偏見で歴史を観ることになりそうだ。
人種とは別の「人間のかたまり」が西へ東へ(あるいは南へ北へ)移動しながら離合集散・融合拡散を繰り返し、争乱の時代や大帝国の時代を織りなしてきた――そんな、ダイナミックなイメージで歴史を捉えたい。本書を読んで、そんなことを考えた。


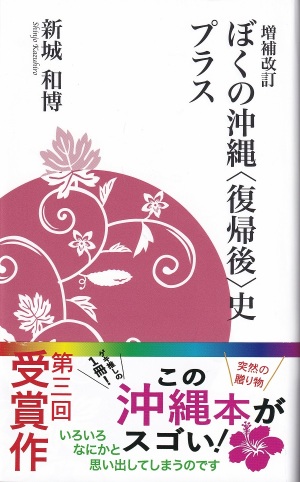
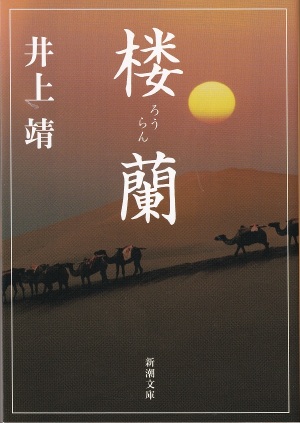

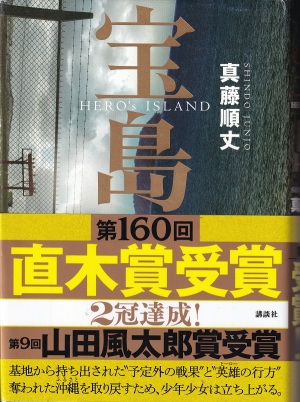



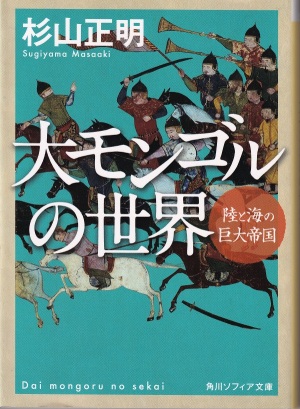
最近のコメント