多元複合の世界国家モンゴルを描いた『大モンゴルの世界』 ― 2021年11月30日
『疾駆する草原の征服者』に続いて同じ著者の次の本を読んだ。
『大モンゴルの世界:陸と海の巨大帝国』(杉山正明/角川ソフィア文庫)
杉山正明氏の本を読むのは8冊目である。年のせいか、本を読んでも少し時間が経てばその内容の大半が蒸発する。特に歴史書は、アレコレの事象が頭の中でゴチャゴチャに霞んでいく傾向が強い。再読、再々読すればいいのだが、類書を読む方が目先が変わって楽しい。だから、本書を読んだ。
この文庫版の原著は1992年刊行、著者の一般向け概説書では最も古いものだ。獰猛な破壊者モンゴルという見方を否定し、13世紀のクビライ朝によってユーラシアの東西をつなぐ「世界史」が登場したという著者の見解を過不足なく展開している。
チンギス・カンからクビライ朝に至る13~14世紀が中心だが、それ以前の遊牧の起源や草原国家の解説から書き起こし、それ以降の明、清、ティムール、ムガル、オスマン、ロシアにまで言及している。人類の世界史の基盤を俯瞰した気分になる。
本書であらためて認識したのはモンゴルとは民族の名でも人種の名でもないという見解である。それが民族や人種を指すようになったのは近代になってからだ。
遊牧民はいくつもの人間のかたまりとして行動し、そのかたまりが離合集散を繰り返す。もともとは小さな部族集団だったモンゴルは、チンギスの登場によって他の多くの部族集団を統合し「大モンゴル国」を形成する。その集団にはトルコ系やモンゴル系などの雑多な人々がいた。杉山氏は「大モンゴル国」を多元複合の世界国家と述べている。それは、われわれが知っている近代の「帝国」とはかなり違うイメージの世界国家だったと思われる。
中央ユーラシアの歴史を眺めるとき、さまざまの国や人間集団をモンゴル系、トルコ系、イラン系、チベット系などと分別したくなる。それは無意味ではないと思うが、あまり重視すると近代人の偏見で歴史を観ることになりそうだ。
人種とは別の「人間のかたまり」が西へ東へ(あるいは南へ北へ)移動しながら離合集散・融合拡散を繰り返し、争乱の時代や大帝国の時代を織りなしてきた――そんな、ダイナミックなイメージで歴史を捉えたい。本書を読んで、そんなことを考えた。
『大モンゴルの世界:陸と海の巨大帝国』(杉山正明/角川ソフィア文庫)
杉山正明氏の本を読むのは8冊目である。年のせいか、本を読んでも少し時間が経てばその内容の大半が蒸発する。特に歴史書は、アレコレの事象が頭の中でゴチャゴチャに霞んでいく傾向が強い。再読、再々読すればいいのだが、類書を読む方が目先が変わって楽しい。だから、本書を読んだ。
この文庫版の原著は1992年刊行、著者の一般向け概説書では最も古いものだ。獰猛な破壊者モンゴルという見方を否定し、13世紀のクビライ朝によってユーラシアの東西をつなぐ「世界史」が登場したという著者の見解を過不足なく展開している。
チンギス・カンからクビライ朝に至る13~14世紀が中心だが、それ以前の遊牧の起源や草原国家の解説から書き起こし、それ以降の明、清、ティムール、ムガル、オスマン、ロシアにまで言及している。人類の世界史の基盤を俯瞰した気分になる。
本書であらためて認識したのはモンゴルとは民族の名でも人種の名でもないという見解である。それが民族や人種を指すようになったのは近代になってからだ。
遊牧民はいくつもの人間のかたまりとして行動し、そのかたまりが離合集散を繰り返す。もともとは小さな部族集団だったモンゴルは、チンギスの登場によって他の多くの部族集団を統合し「大モンゴル国」を形成する。その集団にはトルコ系やモンゴル系などの雑多な人々がいた。杉山氏は「大モンゴル国」を多元複合の世界国家と述べている。それは、われわれが知っている近代の「帝国」とはかなり違うイメージの世界国家だったと思われる。
中央ユーラシアの歴史を眺めるとき、さまざまの国や人間集団をモンゴル系、トルコ系、イラン系、チベット系などと分別したくなる。それは無意味ではないと思うが、あまり重視すると近代人の偏見で歴史を観ることになりそうだ。
人種とは別の「人間のかたまり」が西へ東へ(あるいは南へ北へ)移動しながら離合集散・融合拡散を繰り返し、争乱の時代や大帝国の時代を織りなしてきた――そんな、ダイナミックなイメージで歴史を捉えたい。本書を読んで、そんなことを考えた。
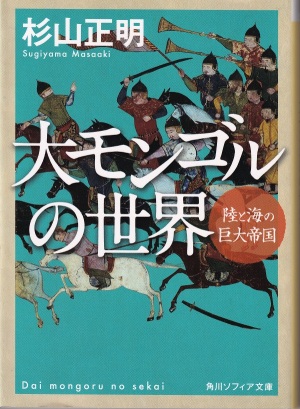
最近のコメント