なぜ進軍を続けたかを問う『獅子王アレクサンドロス』 ― 2023年08月02日
『新トロイア物語』に続いて同じ著者の次の古代史小説を読んだ。
『獅子王アレクサンドロス』(阿刀田高/講談社文庫)
少年アレクサンドロスが家庭教師アリストテレスに出会うシーンに始まり、32歳の若さでバビロンで病死(前323年)するまでを描いた一代記である。21歳で東征を開始したアレクサンドロスは、アケメネス朝ペルシアを滅ぼしても進軍をやめず、インダス河を越えてガンジス河を目指す。だが、帰郷を望む兵士らの声を容れて引き返す途中で客死――ひたすら進軍の生涯だった。
アレクサンドロスを描いた本や映画は多い。数年前に読んだ『ギリシア人の物語Ⅲ』(塩野七生)のアレクサンドロスは魅力的だった。今年になって読んだ『アレクサンドロスの征服と神話』や『文明の道① アレクサンドロスの時代』はアレクサンドロスを多面的に捉えていて印象深かった。
阿刀田氏は、何故にアレクサンドロスがひたすら進軍し続けたのか、という問いをベースに物語を展開している。アレクサンドロスには侵略者と知性人の両面があった。進軍を続けたのは、真なるものを追究したい、世界の果てを見極めたいという衝動であり、その追究心はアリストテレスに培われたとしている。
アレクソンドロスとアリストテレスの関係については、森谷公俊氏が『アレクサンドロスの征服と神話』のなかで「完全なすれ違い終わったのではなかろうか」と述べていた。アリストテレスはギリシアの枠内に留まり、アレクサンドロスはその枠を超えていたという見解である。
獅子王は政治の実践では政治学者(哲学者)の構想の枠を超えたが、彼方を目指す探究心においては哲学者の弟子だった、ということかもしれない。
『獅子王アレクサンドロス』(阿刀田高/講談社文庫)
少年アレクサンドロスが家庭教師アリストテレスに出会うシーンに始まり、32歳の若さでバビロンで病死(前323年)するまでを描いた一代記である。21歳で東征を開始したアレクサンドロスは、アケメネス朝ペルシアを滅ぼしても進軍をやめず、インダス河を越えてガンジス河を目指す。だが、帰郷を望む兵士らの声を容れて引き返す途中で客死――ひたすら進軍の生涯だった。
アレクサンドロスを描いた本や映画は多い。数年前に読んだ『ギリシア人の物語Ⅲ』(塩野七生)のアレクサンドロスは魅力的だった。今年になって読んだ『アレクサンドロスの征服と神話』や『文明の道① アレクサンドロスの時代』はアレクサンドロスを多面的に捉えていて印象深かった。
阿刀田氏は、何故にアレクサンドロスがひたすら進軍し続けたのか、という問いをベースに物語を展開している。アレクサンドロスには侵略者と知性人の両面があった。進軍を続けたのは、真なるものを追究したい、世界の果てを見極めたいという衝動であり、その追究心はアリストテレスに培われたとしている。
アレクソンドロスとアリストテレスの関係については、森谷公俊氏が『アレクサンドロスの征服と神話』のなかで「完全なすれ違い終わったのではなかろうか」と述べていた。アリストテレスはギリシアの枠内に留まり、アレクサンドロスはその枠を超えていたという見解である。
獅子王は政治の実践では政治学者(哲学者)の構想の枠を超えたが、彼方を目指す探究心においては哲学者の弟子だった、ということかもしれない。
古代メキシコの遺物には独特の魅力がある ― 2023年08月04日
東京国立博物館で開催中の『特別展古代メキシコ』を観た。マヤ文明、アステカ文明、テオティワカン文明の遺物を展示している。
古代メキシコ文明や南米のインカ文明は、私の頭の中では世界史の一部というよりはSFの世界に近い。これらの文明については、歴史書ではなくSFや伝奇読み物で接する機会が多かったからだ。そんなイメージが大いなる偏見だとは自覚している。
東西に広がるユーラシア大陸に発生した四つの文明(中国、インダス、メソポタミア、エジプト)は互いの交流もあったし、それを継承した後世の新たな文明・文化が思い浮かぶ。しかし、南北に広がるアメリカ大陸で発生した文明は、互いの交流はあったにせよ全体として孤立し、それを受け継いだ文明はないと思える。スペインのコンキスタドール(要は銃と病原菌)によって滅ぼされた「絶滅文明」である。
そんな絶命文明の遺物には、ユーラシアの文明とは異質の独特の魅力がある。展示されてている土器やマスクや石像の多くは、大胆かつおおらかな造形で、ユーモラスでもある。生命力を感じる。遺物のなかには人身供犠に関連したものもあるらしい。生贄と生命力の結びつきに文明の不思議がある。
「死のディスク石彫」は太陽の中央に舌を出した髑髏を配置した巨大な造形だ。西に沈んで東から上ってくるまでの間の「沈んだ(死んだ)太陽」の姿を表し、死と再生を暗示しているそうだ。変に理屈っぽい造形にSFを感じた。
古代メキシコ文明や南米のインカ文明は、私の頭の中では世界史の一部というよりはSFの世界に近い。これらの文明については、歴史書ではなくSFや伝奇読み物で接する機会が多かったからだ。そんなイメージが大いなる偏見だとは自覚している。
東西に広がるユーラシア大陸に発生した四つの文明(中国、インダス、メソポタミア、エジプト)は互いの交流もあったし、それを継承した後世の新たな文明・文化が思い浮かぶ。しかし、南北に広がるアメリカ大陸で発生した文明は、互いの交流はあったにせよ全体として孤立し、それを受け継いだ文明はないと思える。スペインのコンキスタドール(要は銃と病原菌)によって滅ぼされた「絶滅文明」である。
そんな絶命文明の遺物には、ユーラシアの文明とは異質の独特の魅力がある。展示されてている土器やマスクや石像の多くは、大胆かつおおらかな造形で、ユーモラスでもある。生命力を感じる。遺物のなかには人身供犠に関連したものもあるらしい。生贄と生命力の結びつきに文明の不思議がある。
「死のディスク石彫」は太陽の中央に舌を出した髑髏を配置した巨大な造形だ。西に沈んで東から上ってくるまでの間の「沈んだ(死んだ)太陽」の姿を表し、死と再生を暗示しているそうだ。変に理屈っぽい造形にSFを感じた。
ソグド人と吉備真備が活躍する歴史小説『ふりさけ見れば』 ― 2023年08月06日
『ふりさけ見れば(上)(下)』(安部龍太郎/日本経済新聞出版)
日経新聞連載中(2021年7月~2023年2月)から注目していた歴史小説である。連載を読みながら、単行本になったらじっくり読みかえそうと思っていた。この小説に注目した理由は以下の通りだ。
(1) ソグド人が活躍する。ソグド人は5年程前から私の関心事項。
(2) 吉備真備が活躍する。吉備真備は3年程前から私の関心事項。
(3) 私にとっては新しい歴史知識が盛り込まれている。
タイトルが示すとおり阿部仲麻呂を描いた歴史小説である。遣唐使留学生として唐に渡り、帰国を果たせなかった人物だ。仲麻呂と同時に入唐した吉備真備も活躍する。単行本で一気に読み返すと真備の印象が強い。仲麻呂と真備、二人が主人公の歴史小説と言える。
物語は、二人が唐で18年の年月を過ごした時点に始まる。遣唐使船が来航し、真備は帰国の途につくが仲麻呂は唐に残る。その後、紆余曲折を経て二人が生涯を終えるまでの約半世紀を描いている(仲麻呂は770年に70歳で死去、真備は775年に80歳で死去)。史実をベースにした大いなるフィクションである。やや不自然に感じる展開もあるが、ラストでは往時茫々の感慨がわいた。
私にとっては、ストーリーよりもディティールを楽しむ小説だった。多くのソグド人がさまざまな立場で活躍するのが面白い。最近の高校世界史の教科書にはソグド人が登場するそうだが、私がソグド人を知ったのは数年前だ。『シルクロードと唐帝国』や『ソグド商人の歴史』などを読んで関心が高まった。ソグド人に関する一般向け概説書が出版されないかと期待している。この歴史小説が呼び水になればいいのだが。
ソグド人への関心から松本清張の『眩人』を読み、吉備真備への興味がわいた。『吉備真備』や『吉備真備の世界』によって、一応の伝記的事柄を知った。残された史料が少なく、詳細がわからない人物である。フィクションの世界では『天平の甍』や『火の鳥』でイヤミなインテリに描かれている。テレビドラマ『大仏開眼』は真備をかなり美化していた。
『ふりさけ見れば』の真備は、真面目な秀才・仲麻呂と対称的な世故に長けた出世主義の俗物に描かれている。だが、しだいに行動的な辣腕家と理念型政治家をミックスした魅力的な人物になっていく。好感がもてた。
吉備真備は詩歌をものせず、文章なども残っていない。ところが2019年12月、真備の書とされる墓誌が中国で発見されてニュースになった。『ふりさけ見れば』は、この墓誌に関する経緯もしっかり書き込んでいる。また、2004年になって新たに存在が確認された遣唐使留学生・井真成も登場する。まさに、21世紀の歴史小説である。
日経新聞連載中(2021年7月~2023年2月)から注目していた歴史小説である。連載を読みながら、単行本になったらじっくり読みかえそうと思っていた。この小説に注目した理由は以下の通りだ。
(1) ソグド人が活躍する。ソグド人は5年程前から私の関心事項。
(2) 吉備真備が活躍する。吉備真備は3年程前から私の関心事項。
(3) 私にとっては新しい歴史知識が盛り込まれている。
タイトルが示すとおり阿部仲麻呂を描いた歴史小説である。遣唐使留学生として唐に渡り、帰国を果たせなかった人物だ。仲麻呂と同時に入唐した吉備真備も活躍する。単行本で一気に読み返すと真備の印象が強い。仲麻呂と真備、二人が主人公の歴史小説と言える。
物語は、二人が唐で18年の年月を過ごした時点に始まる。遣唐使船が来航し、真備は帰国の途につくが仲麻呂は唐に残る。その後、紆余曲折を経て二人が生涯を終えるまでの約半世紀を描いている(仲麻呂は770年に70歳で死去、真備は775年に80歳で死去)。史実をベースにした大いなるフィクションである。やや不自然に感じる展開もあるが、ラストでは往時茫々の感慨がわいた。
私にとっては、ストーリーよりもディティールを楽しむ小説だった。多くのソグド人がさまざまな立場で活躍するのが面白い。最近の高校世界史の教科書にはソグド人が登場するそうだが、私がソグド人を知ったのは数年前だ。『シルクロードと唐帝国』や『ソグド商人の歴史』などを読んで関心が高まった。ソグド人に関する一般向け概説書が出版されないかと期待している。この歴史小説が呼び水になればいいのだが。
ソグド人への関心から松本清張の『眩人』を読み、吉備真備への興味がわいた。『吉備真備』や『吉備真備の世界』によって、一応の伝記的事柄を知った。残された史料が少なく、詳細がわからない人物である。フィクションの世界では『天平の甍』や『火の鳥』でイヤミなインテリに描かれている。テレビドラマ『大仏開眼』は真備をかなり美化していた。
『ふりさけ見れば』の真備は、真面目な秀才・仲麻呂と対称的な世故に長けた出世主義の俗物に描かれている。だが、しだいに行動的な辣腕家と理念型政治家をミックスした魅力的な人物になっていく。好感がもてた。
吉備真備は詩歌をものせず、文章なども残っていない。ところが2019年12月、真備の書とされる墓誌が中国で発見されてニュースになった。『ふりさけ見れば』は、この墓誌に関する経緯もしっかり書き込んでいる。また、2004年になって新たに存在が確認された遣唐使留学生・井真成も登場する。まさに、21世紀の歴史小説である。
今年はインゲン不作 ― 2023年08月08日
12世紀のビザンツ帝国を分析した『ビザンツ 幻影の世界帝国』 ― 2023年08月10日
昨年の夏から秋にかけてビザンツ帝国がマイブームになり、10冊ほどの概説書を読み、とりえあず一段落のつもりだった。だが、次の本を入手したまま読み残していたのを思い出した。読み始めると面白く、一気に読了できた。
『ビザンツ 幻影の世界帝国』(根津由喜夫/講談社選書メチエ/1999.4)
千年続いたビザンツ帝国の後期、コムネノス朝第三代皇帝マヌエル1世(在1143-1180)の時代を描いた歴史書である。私は、概説書10冊でビザンツ史を多少はイメージできるつもりだった。だが、マヌエル1世と言われてもピンと来ない。「西欧かぶれの皇帝」と聞いて、そう言えばそんな皇帝がいたような気がすると思った。
12世紀にウエイトをおいたビザンツ本を読むのは初めてである。本書によって、ビザンツ史のイメージが補完され、マヌエル1世の姿が少しクリアになった。
ビザンツ帝国は古代ローマ帝国の承継を自認している帝国である。しかし、賢帝の2世紀と十字軍の12世紀とでは時代が異なる。周辺にさまざまな勢力があり、ビザンツ帝国の領土は縮小している。といっても、コンスタンティノープルは世界の富を集めた魅惑的な国際都市として繁栄している。
マヌエル1世は、そんな12世紀のビザンツを「世界帝国」として演出した人物であり、それは「幻影の世界帝国」「虚構の世界帝国」だった――本書はそんな視点でマヌエル1世の統治や施策を分析している。スリリングな論旨展開に魅了された。著者は次のように表現している。
「マヌエル帝によって、細心の注意を払って構築された、ビザンツを核とするこの国際秩序は、精巧なガラス細工のような繊細さと華麗さを併せもつ、虚構の世界帝国だったのである。」
幻影や虚構は無意味なものとは限らない。世の中を動かすのは物理的な力だけではない。幻影や虚構を作り出す力の役割も大きいと思う。
【以下、私的メモ】
久々にビザンツ本を読み、以前に読んだ本の内容の多くを失念していると再認識した。これまでに読んだビザンツ本の一覧表を作り、いつの日かの再読の手引きとする。
『ビザンツ帝国』中谷功治
『図説ビザンツ帝国』根津由喜夫
『ビザンツとスラブ』井上浩一・栗生沢猛夫
『生き残った帝国ビザンティン』井上浩一
『ビザンツの国家と社会』根津由喜夫
『ビザンツ帝国史』ポール・ルメルル
『ビザンツと東欧世界』鳥山成人
『ビサンツ 驚くべき中世帝国』ジュディス・ヘリン
『ビザンツ皇妃列伝』井上浩一
『黄金のビザンティン帝国』ミシェル・カプラン
『コンスタンティノープル千年』渡辺金一
『ビザンツ 幻影の世界帝国』(根津由喜夫/講談社選書メチエ/1999.4)
千年続いたビザンツ帝国の後期、コムネノス朝第三代皇帝マヌエル1世(在1143-1180)の時代を描いた歴史書である。私は、概説書10冊でビザンツ史を多少はイメージできるつもりだった。だが、マヌエル1世と言われてもピンと来ない。「西欧かぶれの皇帝」と聞いて、そう言えばそんな皇帝がいたような気がすると思った。
12世紀にウエイトをおいたビザンツ本を読むのは初めてである。本書によって、ビザンツ史のイメージが補完され、マヌエル1世の姿が少しクリアになった。
ビザンツ帝国は古代ローマ帝国の承継を自認している帝国である。しかし、賢帝の2世紀と十字軍の12世紀とでは時代が異なる。周辺にさまざまな勢力があり、ビザンツ帝国の領土は縮小している。といっても、コンスタンティノープルは世界の富を集めた魅惑的な国際都市として繁栄している。
マヌエル1世は、そんな12世紀のビザンツを「世界帝国」として演出した人物であり、それは「幻影の世界帝国」「虚構の世界帝国」だった――本書はそんな視点でマヌエル1世の統治や施策を分析している。スリリングな論旨展開に魅了された。著者は次のように表現している。
「マヌエル帝によって、細心の注意を払って構築された、ビザンツを核とするこの国際秩序は、精巧なガラス細工のような繊細さと華麗さを併せもつ、虚構の世界帝国だったのである。」
幻影や虚構は無意味なものとは限らない。世の中を動かすのは物理的な力だけではない。幻影や虚構を作り出す力の役割も大きいと思う。
【以下、私的メモ】
久々にビザンツ本を読み、以前に読んだ本の内容の多くを失念していると再認識した。これまでに読んだビザンツ本の一覧表を作り、いつの日かの再読の手引きとする。
『ビザンツ帝国』中谷功治
『図説ビザンツ帝国』根津由喜夫
『ビザンツとスラブ』井上浩一・栗生沢猛夫
『生き残った帝国ビザンティン』井上浩一
『ビザンツの国家と社会』根津由喜夫
『ビザンツ帝国史』ポール・ルメルル
『ビザンツと東欧世界』鳥山成人
『ビサンツ 驚くべき中世帝国』ジュディス・ヘリン
『ビザンツ皇妃列伝』井上浩一
『黄金のビザンティン帝国』ミシェル・カプラン
『コンスタンティノープル千年』渡辺金一
『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』は教育的啓蒙書 ― 2023年08月12日
『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』(小野寺拓也、田野大輔/岩波ブックレット)
新聞広告でタイトルを見たとき、えげつなさを感じた。でも、読んでみたくなるタイトルだ。読みやすそうな小冊子なのでネットで注文した。入手した翌日(2023.8.6)の朝日新聞文化欄に本書の記事が載っていた。異例の反響で品切れ書店続出だそうだ。
ユダヤ人虐殺をはじめ多くの「悪いこと」をナチスがやったのは確かだ。だが、事績を「悪い」「良い」の二面だけで評価するのは短絡で、多くの事績は多面的に捉えざるを得ないと思う。だから、本書のタイトルに違和感をおぼえた。
本書を読んで、こんなタイトルにした意味がわかった。私は知らなかったが、ネットでは「ナチスは良いこともした」と主張する人が増えているそうだ。緻密な議論ではなく、中二病的な単純逆張り主張である。本書は、そんな雑駁な半可通に対する歴史研究者の啓蒙的で教育的な解説書なのだ。
ナチスのやった「良いこと」として、本書は次のような事例をあげている。
「アウトバーンを作った」
「失業率を低下させた」
「経済を建て直した」
「歓喜力行団で誰でも旅行に行けるようにした」
「有給休暇を拡充した」
「禁煙政策を進めた」
「先進的な環境政策をとった」
一見「良いこと」に見えるこれらの事績の実態や結果を検討し、結局は「良いこと」ではなかった、と結論づけている。
私はナチス関連の本を多少は読んできた。上記の事績の大半についても、いくつかの本で否定的評価を把握していたので、著者たちの結論に納得した。
本書によって新たに知った事象も少なくない。ナチ体制がユダヤ人識別のためにIBMのパンチカードを利用していたとは知らなかった。戦後、1956-57年のアメリカで、30%近くのホテルが「ユダヤ人客お断り」だったとは初めて知った。
本書が描出したのは「国民社会主義」というナチ体制が目指した「民族体」の姿であり、「良いこと」とされた事象の多くは、軍事力強化と民族浄化政策とプロパガンダが作り出した仇花だった。破綻せざるを得ない幻影である。
新聞広告でタイトルを見たとき、えげつなさを感じた。でも、読んでみたくなるタイトルだ。読みやすそうな小冊子なのでネットで注文した。入手した翌日(2023.8.6)の朝日新聞文化欄に本書の記事が載っていた。異例の反響で品切れ書店続出だそうだ。
ユダヤ人虐殺をはじめ多くの「悪いこと」をナチスがやったのは確かだ。だが、事績を「悪い」「良い」の二面だけで評価するのは短絡で、多くの事績は多面的に捉えざるを得ないと思う。だから、本書のタイトルに違和感をおぼえた。
本書を読んで、こんなタイトルにした意味がわかった。私は知らなかったが、ネットでは「ナチスは良いこともした」と主張する人が増えているそうだ。緻密な議論ではなく、中二病的な単純逆張り主張である。本書は、そんな雑駁な半可通に対する歴史研究者の啓蒙的で教育的な解説書なのだ。
ナチスのやった「良いこと」として、本書は次のような事例をあげている。
「アウトバーンを作った」
「失業率を低下させた」
「経済を建て直した」
「歓喜力行団で誰でも旅行に行けるようにした」
「有給休暇を拡充した」
「禁煙政策を進めた」
「先進的な環境政策をとった」
一見「良いこと」に見えるこれらの事績の実態や結果を検討し、結局は「良いこと」ではなかった、と結論づけている。
私はナチス関連の本を多少は読んできた。上記の事績の大半についても、いくつかの本で否定的評価を把握していたので、著者たちの結論に納得した。
本書によって新たに知った事象も少なくない。ナチ体制がユダヤ人識別のためにIBMのパンチカードを利用していたとは知らなかった。戦後、1956-57年のアメリカで、30%近くのホテルが「ユダヤ人客お断り」だったとは初めて知った。
本書が描出したのは「国民社会主義」というナチ体制が目指した「民族体」の姿であり、「良いこと」とされた事象の多くは、軍事力強化と民族浄化政策とプロパガンダが作り出した仇花だった。破綻せざるを得ない幻影である。
パルコ劇場の『桜の園』はユニークな舞台だった ― 2023年08月14日
パルコ劇場でチェーホフの『桜の園』(演出:ショーン・ホームズ、出演:原田美枝子、八嶋智人、他)を観た。
没落しているのに金銭をバラまく習慣をやめられないラネーフスカヤ夫人の話は、子供の頃から聞いていた。その頃、テレビで舞台中継を観たような気もする。戯曲は学生時代に読んだ。実際の舞台を観たのは2015年の公演(出演:田中裕子、柄本佑)が初めてで、今回が2回目である。
演出は、昨年観た『セールスマンの死』と同じイギリス人演出家だ。あの舞台がユニークだったので今回も期待した。
舞台の上には巨大な四角い筒が横たわっている。その巨大筒は何本かのロープで吊られている。今にも擦り切れそうな危うげで粗末ななロープである。この筒が吊り上げられていき、中から登場人物が現れて開幕する。
芝居は宙吊りの巨大筒の下で進行する。ダモクレスの剣である。そしてラスト、屋敷に取り残されて横たわったた老僕(フィールス:村井國夫)の上に巨大筒がゆっくり降りてきて終幕になる。人の世の転変を俯瞰するような舞台だ。
舞踏会のシーンが奇抜な仮装ドンチャン乱舞になっているのに驚いた。家庭教師のシャルロッタ(川上友里)は破天荒だ。『桜の園』と言えば、遠くから聞こえる斧の音が哀切だが、この舞台ではチェンソーの騒音になっている。登場人物たちの言動の多くは、よく考えれば滑稽である。未来を語る大学生の言説も幼稚な夢想に聞こえる。
『桜の園』は苦い喜劇だと思った。
没落しているのに金銭をバラまく習慣をやめられないラネーフスカヤ夫人の話は、子供の頃から聞いていた。その頃、テレビで舞台中継を観たような気もする。戯曲は学生時代に読んだ。実際の舞台を観たのは2015年の公演(出演:田中裕子、柄本佑)が初めてで、今回が2回目である。
演出は、昨年観た『セールスマンの死』と同じイギリス人演出家だ。あの舞台がユニークだったので今回も期待した。
舞台の上には巨大な四角い筒が横たわっている。その巨大筒は何本かのロープで吊られている。今にも擦り切れそうな危うげで粗末ななロープである。この筒が吊り上げられていき、中から登場人物が現れて開幕する。
芝居は宙吊りの巨大筒の下で進行する。ダモクレスの剣である。そしてラスト、屋敷に取り残されて横たわったた老僕(フィールス:村井國夫)の上に巨大筒がゆっくり降りてきて終幕になる。人の世の転変を俯瞰するような舞台だ。
舞踏会のシーンが奇抜な仮装ドンチャン乱舞になっているのに驚いた。家庭教師のシャルロッタ(川上友里)は破天荒だ。『桜の園』と言えば、遠くから聞こえる斧の音が哀切だが、この舞台ではチェンソーの騒音になっている。登場人物たちの言動の多くは、よく考えれば滑稽である。未来を語る大学生の言説も幼稚な夢想に聞こえる。
『桜の園』は苦い喜劇だと思った。
シーラッハの孫の『犯罪』はとても面白い ― 2023年08月16日
妙なきっかけで次のミステリー短篇集を読んだ。
『犯罪』(フェルディナンド・フォン・シーラッハ、酒寄進一訳/創元推理文庫)
先日、中公新書の『ヒトラー・ユーゲント』を読んだとき、ヒトラー・ユーゲントの指導者として名高いシーラッハを検索して、孫が作家になったと知った。シーラッハの孫がどんな小説を書いているのだろうという野次馬的関心で本書を古書で入手した。
オビには「2012年本屋大賞翻訳小説部門1位」とある。作者は弁護士として活躍しながら小説を書いているそうだ。冒頭の1篇で坦々とした不思議な味わいに惹かれ、全11篇を面白く読了した。得した気分である。
犯罪実録集のような短篇集で、どれにも弁護士の「私」が登場する。だから、弁護士が自分が扱った犯罪の記録を語っているように見える。だが、全くのフィクションだと思う(多少は実例がヒントかもしれないが)。犯罪を犯した人物の切なさが伝わってくる話が多い。
読者を引き込んでいく文体がいい。基本は神の視点の三人称だ。なのに、途中で担当弁護士の「私」が控えめに出てくる。「神の眼の三人称」と「控えめな一人称」がないまぜになった不思議な叙述に独特の魅力がある。
本書に祖父の影を感じる箇所はない。「正当防衛」という短篇の冒頭に鈎十字(ハーケンクロイツ)の刺青をしたヤクザが登場したので、読者の私はドキッとした。
【以下、ネタバレあり】
「サマータイム」という短篇のラストが理解できなくて悩んだ。誰が真犯人かが不明瞭なまま幕になる話である。裁判の終盤で、監視カメラの時刻がサマータイムに変更されていなかったことを弁護士が指摘し、容疑者が犯人である可能性が減少して無罪になる。裁判から数カ月後、定年退職した判事がふいに「時間をめぐる真相」に気づくが、再審請求には不十分だと思う。判事が何に気づいたのか、いろいろ考えてもわからない。ネット検索すると判明した。気づかなかった自分の頭を殴りたくなった。サマータイムでずれる方向が逆なのに、弁護士の弁舌に惑わされていたのだ。
『犯罪』(フェルディナンド・フォン・シーラッハ、酒寄進一訳/創元推理文庫)
先日、中公新書の『ヒトラー・ユーゲント』を読んだとき、ヒトラー・ユーゲントの指導者として名高いシーラッハを検索して、孫が作家になったと知った。シーラッハの孫がどんな小説を書いているのだろうという野次馬的関心で本書を古書で入手した。
オビには「2012年本屋大賞翻訳小説部門1位」とある。作者は弁護士として活躍しながら小説を書いているそうだ。冒頭の1篇で坦々とした不思議な味わいに惹かれ、全11篇を面白く読了した。得した気分である。
犯罪実録集のような短篇集で、どれにも弁護士の「私」が登場する。だから、弁護士が自分が扱った犯罪の記録を語っているように見える。だが、全くのフィクションだと思う(多少は実例がヒントかもしれないが)。犯罪を犯した人物の切なさが伝わってくる話が多い。
読者を引き込んでいく文体がいい。基本は神の視点の三人称だ。なのに、途中で担当弁護士の「私」が控えめに出てくる。「神の眼の三人称」と「控えめな一人称」がないまぜになった不思議な叙述に独特の魅力がある。
本書に祖父の影を感じる箇所はない。「正当防衛」という短篇の冒頭に鈎十字(ハーケンクロイツ)の刺青をしたヤクザが登場したので、読者の私はドキッとした。
【以下、ネタバレあり】
「サマータイム」という短篇のラストが理解できなくて悩んだ。誰が真犯人かが不明瞭なまま幕になる話である。裁判の終盤で、監視カメラの時刻がサマータイムに変更されていなかったことを弁護士が指摘し、容疑者が犯人である可能性が減少して無罪になる。裁判から数カ月後、定年退職した判事がふいに「時間をめぐる真相」に気づくが、再審請求には不十分だと思う。判事が何に気づいたのか、いろいろ考えてもわからない。ネット検索すると判明した。気づかなかった自分の頭を殴りたくなった。サマータイムでずれる方向が逆なのに、弁護士の弁舌に惑わされていたのだ。


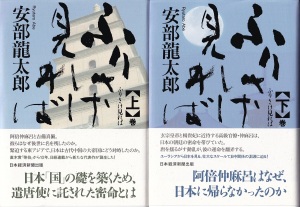


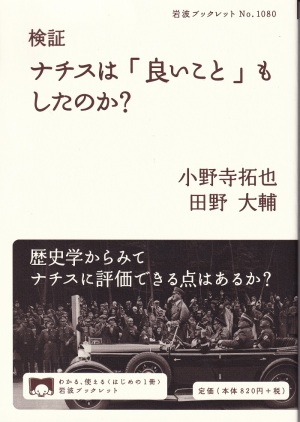


最近のコメント