『グッドラック、ハリウッド』を観て年長者の若者観の不思議を感じた ― 2023年04月02日
本多劇場で加藤健一事務所公演『グッドラック、ハリウッド』(作:リー・カルチェイム、訳:小田島恒志、演出:日澤雄介、出演:加藤健一、関口アナン、加藤忍)を観た。
よくできたヒューマン・コメディである。世代交代の葛藤と苦さを巧みに描いている。作者は1938年生まれの米国の劇作家、この芝居の初演は1988年、映画『ダイ・ハード』公開の年だそうだ。
主人公はハリウッドの往年の名監督&脚本家のボビー(加藤健一)、舞台はボビーの事務所である。デスクの上には輪のついたロープが垂れ下がっている。デスクの上に立ったボビーが首を輪に突っ込んだとき、突然ドアが開く。ハリウッドにやって来たばかりの若き脚本家デニス(関口アナン)が部屋を間違えたのである。
この冒頭シーンは面白い。往年の名監督ボビーは、自分の脚本を受け容れない現状に悲観して首を吊ろうとしたのか、あるいは新作のアイデアを紡ぐために自ら演じていたのか。ここから、ボビーとデニスの共同作業が始まる。
ボビーは若きデニスの黒子に徹し、その若さを借りて自身の熟達の作品を世に出して復活を図ろうと企てるのだ。デニスの作品として完成した映画は脚光を浴びる。だが……というストーリーである。
ボビーは64歳の設定、演じる加藤健一は73歳(私より1歳若い)だ。よく通る張りのある発声は年を感じさせない。見事な熱演である。
この芝居でも暗示しているが、「近ごろの若い者は嘆かわしい」という年長者の慨嘆はいつの時代にも繰り返されてきた。古代の遺跡にもそんな慨嘆が残っているそうだ。
そうだとわかっていても、74歳の私はボビーに感情移入したくなる。若者たちに不甲斐なさを感じるのは老化なのか。永遠に慨嘆を繰り返す人間の性は不思議である。自分では、繰り返しているとは思いにくい。
よくできたヒューマン・コメディである。世代交代の葛藤と苦さを巧みに描いている。作者は1938年生まれの米国の劇作家、この芝居の初演は1988年、映画『ダイ・ハード』公開の年だそうだ。
主人公はハリウッドの往年の名監督&脚本家のボビー(加藤健一)、舞台はボビーの事務所である。デスクの上には輪のついたロープが垂れ下がっている。デスクの上に立ったボビーが首を輪に突っ込んだとき、突然ドアが開く。ハリウッドにやって来たばかりの若き脚本家デニス(関口アナン)が部屋を間違えたのである。
この冒頭シーンは面白い。往年の名監督ボビーは、自分の脚本を受け容れない現状に悲観して首を吊ろうとしたのか、あるいは新作のアイデアを紡ぐために自ら演じていたのか。ここから、ボビーとデニスの共同作業が始まる。
ボビーは若きデニスの黒子に徹し、その若さを借りて自身の熟達の作品を世に出して復活を図ろうと企てるのだ。デニスの作品として完成した映画は脚光を浴びる。だが……というストーリーである。
ボビーは64歳の設定、演じる加藤健一は73歳(私より1歳若い)だ。よく通る張りのある発声は年を感じさせない。見事な熱演である。
この芝居でも暗示しているが、「近ごろの若い者は嘆かわしい」という年長者の慨嘆はいつの時代にも繰り返されてきた。古代の遺跡にもそんな慨嘆が残っているそうだ。
そうだとわかっていても、74歳の私はボビーに感情移入したくなる。若者たちに不甲斐なさを感じるのは老化なのか。永遠に慨嘆を繰り返す人間の性は不思議である。自分では、繰り返しているとは思いにくい。
今年もジャガイモを植え付けた ― 2023年04月04日
八ヶ岳南麓の山小屋でジャガイモを植え付けた。落葉と雑草に埋まった元の畑を整備し、耕し、畝を作り、種イモを並べ、肥料を入れ、土を被せる――かなりの労働である。腰を労りながら、休み休みの作業だった。
思い返せば、この山小屋で初めてジャガイモを植えたのは11年前、それ以来ほぼ毎年(コロナの2021年以外)、ジャガイモをつくっている。うかうかと11年の歳月が流れた。
10年も続けたにしては、一向に野菜づくりの技術が進歩した気がしない。昔はいくつかの野菜に挑戦したが、この数年はジャガイモとインゲンだけになった。惰性のようにジャガイモとインゲンをつくっているのは、比較的簡単だからだ。月に1~2度しか畑に行かない手抜き作業でも何とか収穫できるのが不思議である。
私は74歳、いつまで車を運転できるかわからない。畑のために、車でわざわざ東京から八ヶ岳へ行く意味もよくわからなくなってきたし、農作業も面倒になってきた。やめ時を考えているのだが、なかなか踏ん切りがつかない。人生とはその日暮らしである。
思い返せば、この山小屋で初めてジャガイモを植えたのは11年前、それ以来ほぼ毎年(コロナの2021年以外)、ジャガイモをつくっている。うかうかと11年の歳月が流れた。
10年も続けたにしては、一向に野菜づくりの技術が進歩した気がしない。昔はいくつかの野菜に挑戦したが、この数年はジャガイモとインゲンだけになった。惰性のようにジャガイモとインゲンをつくっているのは、比較的簡単だからだ。月に1~2度しか畑に行かない手抜き作業でも何とか収穫できるのが不思議である。
私は74歳、いつまで車を運転できるかわからない。畑のために、車でわざわざ東京から八ヶ岳へ行く意味もよくわからなくなってきたし、農作業も面倒になってきた。やめ時を考えているのだが、なかなか踏ん切りがつかない。人生とはその日暮らしである。
中高年4人兄弟の配役の妙『帰ってきたマイ・ブラザー』 ― 2023年04月06日
世田谷パブリックシアターで『帰ってきたマイ・ブラザー』(作:マギー、演出:小林顕作、出演:水谷豊、段田安則、高橋克実、堤真一、池谷のぶえ、峰村リエ、寺脇康文)を観た。演劇の楽しさを満喫できるエンタメ劇である。
40年以上昔に大ヒット曲を1本出しただけで消えた4人兄弟のコーラス・グループが、元マネージャーと長男の主導で再結成を図る話だ。時代は2023年春、つまり「いま」である。「コロナで大変だった」などの台詞も出てくる。
場所は復活コンサート直前のホールの楽屋、なぜかそれは浦賀の客席300のホール、ペリー来航の神奈川県の浦賀である。
4人兄弟の役者たちが豪華だ。長男・水谷豊(70歳)、次男・段田安則(66歳)、三男・高橋克実(62歳)、四男・堤真一(58歳)と、ちょうど4歳ずつ離れている。長男と四男は12歳違いだ。役者にアテ書きした台本だそうだ。4人兄弟の性格・雰囲気・年齢が4人の役者にマッチしている。
兄弟がデビューしたとき、四男は16歳だった。解散までの活動期間は2年だから、四男役の堤真一の実年齢とぴったり一致する。さほど似ているとも思えない4人の役者が、それぞれに齢を重ねた本物の兄弟に見えてくる。
芸能界を離れてからの40年間、一般の社会人として別々の人生を歩んできた4人兄弟が久々に再会する、という設定がいい。面白そうなドラマの始まりを予感させる。期待通りの面白い展開だった。ラストの4人のコーラスはサマになっていたし、カーテンコールでの出演者全員(7人)によるノリノリのGSナツメロも楽しかった。
40年以上昔に大ヒット曲を1本出しただけで消えた4人兄弟のコーラス・グループが、元マネージャーと長男の主導で再結成を図る話だ。時代は2023年春、つまり「いま」である。「コロナで大変だった」などの台詞も出てくる。
場所は復活コンサート直前のホールの楽屋、なぜかそれは浦賀の客席300のホール、ペリー来航の神奈川県の浦賀である。
4人兄弟の役者たちが豪華だ。長男・水谷豊(70歳)、次男・段田安則(66歳)、三男・高橋克実(62歳)、四男・堤真一(58歳)と、ちょうど4歳ずつ離れている。長男と四男は12歳違いだ。役者にアテ書きした台本だそうだ。4人兄弟の性格・雰囲気・年齢が4人の役者にマッチしている。
兄弟がデビューしたとき、四男は16歳だった。解散までの活動期間は2年だから、四男役の堤真一の実年齢とぴったり一致する。さほど似ているとも思えない4人の役者が、それぞれに齢を重ねた本物の兄弟に見えてくる。
芸能界を離れてからの40年間、一般の社会人として別々の人生を歩んできた4人兄弟が久々に再会する、という設定がいい。面白そうなドラマの始まりを予感させる。期待通りの面白い展開だった。ラストの4人のコーラスはサマになっていたし、カーテンコールでの出演者全員(7人)によるノリノリのGSナツメロも楽しかった。
ユーラシア史的視野の『軍と兵士のローマ帝国』 ― 2023年04月08日
1973年生まれの歴史研究者・井上文則氏の新刊新書を読んだ。
『軍と兵士のローマ帝国』(井上文則/岩波新書/2023.3)
本書の新聞広告を見て、すぐに購入しようと思った。以前に読んだ井上文則氏の『シルクロードとローマ帝国の興亡』(文春新書)や『岩波講座 世界歴史』収録の論文がとても面白かったからである。
ローマ史では軍が新たな皇帝を決める場面が多い。ローマ帝国において軍が大きな影響力をもっていたのはわかるが、そのローマ軍がどのような人々で構成されていたのか、私には具体的なイメージがなかった。
ローマ史を軍事の視点で概説した本書によって、ローマ軍の実態と変遷の概要をつかむことができ、ローマ史のイメージが少しくっきりした。あらためて、ローマ帝国が軍事帝国だったと認識した。
共和政時代のローマ軍は武装を自弁できる有産市民で編成する市民軍だった。第二次ポエニ戦争(BC218-201)の頃から常備軍化が始まり、初代皇帝アウグストゥスの時代には常備軍となり、ローマ軍は給与を支払われる職業軍人になる。
その後、属州駐留軍とは別に機動軍を編成、機動軍は地方にも配され、辺境防衛軍と協力して帝国を防衛する。やがて、兵員確保のために異民族をローマ軍に取り込むようになり、ローマ軍(特に機動軍)の異民族化が進んでいく。
異民族の襲来を防ぐローマ軍に異民族がいて大丈夫かとも思うが、士気に問題はなかったらしい。異民族 vs 異民族でもきちんと戦うのである。時代が進むと、機動軍とは別に異民族集団をそのまま同盟部族軍として動員するようになる。同盟部族軍には帝国の領土内に居住地が与えられた。
ローマ軍が同盟部族軍に依存せざるを得なくなって行く経過も興味深いが、本書で最も面白いのは「終章 ローマ軍再論――ユーラシア史のなかで」である。常備軍の維持に必要な膨大な経費はシルクロード交易の収益で負担していたという説を展開している。前著『シルクロードとローマ帝国の興亡』の内容にも重なり、数値的な裏付けにも説得力がある。
仮説とは言え、シルクロード交易や気候変動によってローマ軍の変遷を説明する明解さに目を見張った。要点は、シルクロード交易の収益があった時期は常備軍を維持でき、それがなくなると常備軍の維持が難しくなり、軍の異民族化が進んだ、ということである。財源がなくなれば、土地を提供して同盟部族軍を引き入れることになる。同盟部族軍の導入は民族移動の波の一部を軍事的に柔軟に吸収し、西ローマ帝国滅亡を先延ばしにしたという説にナルホドと思った。
著者は、東ローマ帝国が生き延びた理由やヘレニズム世界とローマ帝国の関係についても分析している。マクロな視点で歴史を眺める面白さを味わえた。
『軍と兵士のローマ帝国』(井上文則/岩波新書/2023.3)
本書の新聞広告を見て、すぐに購入しようと思った。以前に読んだ井上文則氏の『シルクロードとローマ帝国の興亡』(文春新書)や『岩波講座 世界歴史』収録の論文がとても面白かったからである。
ローマ史では軍が新たな皇帝を決める場面が多い。ローマ帝国において軍が大きな影響力をもっていたのはわかるが、そのローマ軍がどのような人々で構成されていたのか、私には具体的なイメージがなかった。
ローマ史を軍事の視点で概説した本書によって、ローマ軍の実態と変遷の概要をつかむことができ、ローマ史のイメージが少しくっきりした。あらためて、ローマ帝国が軍事帝国だったと認識した。
共和政時代のローマ軍は武装を自弁できる有産市民で編成する市民軍だった。第二次ポエニ戦争(BC218-201)の頃から常備軍化が始まり、初代皇帝アウグストゥスの時代には常備軍となり、ローマ軍は給与を支払われる職業軍人になる。
その後、属州駐留軍とは別に機動軍を編成、機動軍は地方にも配され、辺境防衛軍と協力して帝国を防衛する。やがて、兵員確保のために異民族をローマ軍に取り込むようになり、ローマ軍(特に機動軍)の異民族化が進んでいく。
異民族の襲来を防ぐローマ軍に異民族がいて大丈夫かとも思うが、士気に問題はなかったらしい。異民族 vs 異民族でもきちんと戦うのである。時代が進むと、機動軍とは別に異民族集団をそのまま同盟部族軍として動員するようになる。同盟部族軍には帝国の領土内に居住地が与えられた。
ローマ軍が同盟部族軍に依存せざるを得なくなって行く経過も興味深いが、本書で最も面白いのは「終章 ローマ軍再論――ユーラシア史のなかで」である。常備軍の維持に必要な膨大な経費はシルクロード交易の収益で負担していたという説を展開している。前著『シルクロードとローマ帝国の興亡』の内容にも重なり、数値的な裏付けにも説得力がある。
仮説とは言え、シルクロード交易や気候変動によってローマ軍の変遷を説明する明解さに目を見張った。要点は、シルクロード交易の収益があった時期は常備軍を維持でき、それがなくなると常備軍の維持が難しくなり、軍の異民族化が進んだ、ということである。財源がなくなれば、土地を提供して同盟部族軍を引き入れることになる。同盟部族軍の導入は民族移動の波の一部を軍事的に柔軟に吸収し、西ローマ帝国滅亡を先延ばしにしたという説にナルホドと思った。
著者は、東ローマ帝国が生き延びた理由やヘレニズム世界とローマ帝国の関係についても分析している。マクロな視点で歴史を眺める面白さを味わえた。
『ブレイキング・ザ・コード』のチューリングは溌剌としている ― 2023年04月10日
シアタートラムで『ブレイキング・ザ・コード』(作:ヒュー・ホワイトモア、訳:小田島創志、演出:稲葉賀恵、出演:亀田佳明・他)を観た。
ナチスのエニグマ暗号を解読、コンピュータや人工知能の先駆的研究で知られる英国の数学者アラン・チューリングを描いた芝居である。
私がチューリングの名を知ったのは約40年前、社会人になって始めたコンピュータの勉強の一環で情報科学の入門書(北川敏男著『情報科学的世界像』1977.6)を読んだときだ。この本に載っていたチューリングの端正な肖像写真が印象に残った。写真のキャプション「学界の期待をにないながら、謎の自殺」が焼き付いたのである。
自殺の経緯を知ったのは、2014年公開の映画『イミテーション・ゲーム』を観たときだと思う(その前だったかもしれない…)。チューリングは同性愛者で、当時の英国で同性愛は犯罪だった(1967年まで)。1952年に同性愛行為で逮捕され、女性ホルモン投与治療を受ける。1954年に41歳で死去、検死で青酸カリによる自殺とされる。
戦後、チューリングは大学に戻り、コンピュータ科学を開拓する卓越した研究を続ける。だが、エニグマ解読は長いあいだ国家機密だったので、当時の人々は、彼の多大な業績を知らなかった。
映画『イミテーション・ゲーム』の冒頭は1952年のチューリング逮捕のシーンで、その取り調べの過程で過去のエニグマ解読の物語が展開していく。芝居『ブレイキング・ザ・コード』の冒頭も1952年の警察署での取り調べシーンだ。そこに過去の出来事が重なって来る。
映画に似ていると感じたのは冒頭だけで、芝居は映画とは異なる切り口でチューリングを描いている。映画はエニグマ解読を巡る話がメインだが、芝居は同性愛を含めたチューリングの生活と真情に焦点をあてている。この芝居の初演は1986年(ロンドン)、芝居の方が映画よりかなり先なのだ。
芝居のラストで、チューリングの死を事故死だと主張する母親が「あの子が、自殺する子に見えますか」と語る。観客は、この台詞に同感したくなる。この芝居のチューリングは、自己中心的であるにしても溌剌としている。同性愛に関しても悪びれる様子はあまりない。社会の桎梏に立ち向かっている闘士のようにも見える。そこに、上演の現代性を感じた。
この芝居の翻訳者・小田島創志は、先日観た『グッドラック、ハリウッド』を翻訳した小田島恒志(小田島雄志の息子)の息子、つまり小田島雄志の孫だ。戯曲翻訳三代は素晴らしい。だが、何となく社会の流動性が失われつつあるようも感じる。小田島三代に何の咎もないが。
ナチスのエニグマ暗号を解読、コンピュータや人工知能の先駆的研究で知られる英国の数学者アラン・チューリングを描いた芝居である。
私がチューリングの名を知ったのは約40年前、社会人になって始めたコンピュータの勉強の一環で情報科学の入門書(北川敏男著『情報科学的世界像』1977.6)を読んだときだ。この本に載っていたチューリングの端正な肖像写真が印象に残った。写真のキャプション「学界の期待をにないながら、謎の自殺」が焼き付いたのである。
自殺の経緯を知ったのは、2014年公開の映画『イミテーション・ゲーム』を観たときだと思う(その前だったかもしれない…)。チューリングは同性愛者で、当時の英国で同性愛は犯罪だった(1967年まで)。1952年に同性愛行為で逮捕され、女性ホルモン投与治療を受ける。1954年に41歳で死去、検死で青酸カリによる自殺とされる。
戦後、チューリングは大学に戻り、コンピュータ科学を開拓する卓越した研究を続ける。だが、エニグマ解読は長いあいだ国家機密だったので、当時の人々は、彼の多大な業績を知らなかった。
映画『イミテーション・ゲーム』の冒頭は1952年のチューリング逮捕のシーンで、その取り調べの過程で過去のエニグマ解読の物語が展開していく。芝居『ブレイキング・ザ・コード』の冒頭も1952年の警察署での取り調べシーンだ。そこに過去の出来事が重なって来る。
映画に似ていると感じたのは冒頭だけで、芝居は映画とは異なる切り口でチューリングを描いている。映画はエニグマ解読を巡る話がメインだが、芝居は同性愛を含めたチューリングの生活と真情に焦点をあてている。この芝居の初演は1986年(ロンドン)、芝居の方が映画よりかなり先なのだ。
芝居のラストで、チューリングの死を事故死だと主張する母親が「あの子が、自殺する子に見えますか」と語る。観客は、この台詞に同感したくなる。この芝居のチューリングは、自己中心的であるにしても溌剌としている。同性愛に関しても悪びれる様子はあまりない。社会の桎梏に立ち向かっている闘士のようにも見える。そこに、上演の現代性を感じた。
この芝居の翻訳者・小田島創志は、先日観た『グッドラック、ハリウッド』を翻訳した小田島恒志(小田島雄志の息子)の息子、つまり小田島雄志の孫だ。戯曲翻訳三代は素晴らしい。だが、何となく社会の流動性が失われつつあるようも感じる。小田島三代に何の咎もないが。
碩学二人のの掛け合いが面白い『集中講義! ギリシア・ローマ』 ― 2023年04月12日
5年前に出た次の新書を読んだ。
『集中講義! ギリシア・ローマ』(桜井万里子・本村凌二/ちくま新書)
二人の碩学によるカルチャーセンターでの講義・対談を書籍にまとめたものである。ギリシアとローマを混ぜて論じた本書によって、あらためてギリシア・ローマを混然一体として把握することの面白さと重要性を認識した。
ギリシア史の桜井万里子氏は1943年生まれ、ローマ史の本村凌二氏は1947年生まれ、この二人の20年以上前の共著『中公版 世界の歴史⑤ ギリシアとローマ』を読んだのは7年前だ。本書を読んでいて、あの本の付録月報の鼎談(著者二人+阿刀田高氏)の続きを読んでいる気分になった。
本書の対談部分の二人の掛け合いが面白い。ローマ視点の本村氏の少々踏み込んだ発言をギリシア視点の桜井氏がやんわりたしなめ、両者が歩み寄りながら進行する雰囲気の対談である。
たとえば、本村氏が「ローマの戦争は正攻法」と述べると桜井氏は「ローマ人に策略・陥穽がなかったとは信じがたい」と返す。本村氏が「歴史家ポリュビオス(ギリシア人)が、ローマ人は敬虔だと述べている」と指摘すると、桜井氏は「敬虔な心の表明の仕方は多様で、ギリシア人も十分に敬虔だった」と返す。本村氏が「ギリシアがローマのように大国・帝国をつくる方向に行かなかったのは、政治状況や自然環境のせいだろうか」と尋ねると、桜井氏は「ギリシア人には大国・帝国をつくる発想がなかったのでは」と答える。
両者が共に認めるのは、ギリシアは寛大さに欠け、ローマは寛容だったという点である。
ギリシアとローマは時代的に前後関係にあるのではなく、重なった時期(ギリシアはローマの植民地になるが)が長い。ローマの共和政開始(前509年)は、ギリシアの民主政確立(前508年)より1年早いという本村氏の指摘には驚いた。まさに並列だったのだ。
また、桜井氏は『黒いアテナ』などにも言及しつつ、オリエント文明のギリシア文明への影響を強調している。ローマはギリシアの影響を強く受けているのだから、ローマをオリエント文明の辺境と捉えることもできるわけだ。
『集中講義! ギリシア・ローマ』(桜井万里子・本村凌二/ちくま新書)
二人の碩学によるカルチャーセンターでの講義・対談を書籍にまとめたものである。ギリシアとローマを混ぜて論じた本書によって、あらためてギリシア・ローマを混然一体として把握することの面白さと重要性を認識した。
ギリシア史の桜井万里子氏は1943年生まれ、ローマ史の本村凌二氏は1947年生まれ、この二人の20年以上前の共著『中公版 世界の歴史⑤ ギリシアとローマ』を読んだのは7年前だ。本書を読んでいて、あの本の付録月報の鼎談(著者二人+阿刀田高氏)の続きを読んでいる気分になった。
本書の対談部分の二人の掛け合いが面白い。ローマ視点の本村氏の少々踏み込んだ発言をギリシア視点の桜井氏がやんわりたしなめ、両者が歩み寄りながら進行する雰囲気の対談である。
たとえば、本村氏が「ローマの戦争は正攻法」と述べると桜井氏は「ローマ人に策略・陥穽がなかったとは信じがたい」と返す。本村氏が「歴史家ポリュビオス(ギリシア人)が、ローマ人は敬虔だと述べている」と指摘すると、桜井氏は「敬虔な心の表明の仕方は多様で、ギリシア人も十分に敬虔だった」と返す。本村氏が「ギリシアがローマのように大国・帝国をつくる方向に行かなかったのは、政治状況や自然環境のせいだろうか」と尋ねると、桜井氏は「ギリシア人には大国・帝国をつくる発想がなかったのでは」と答える。
両者が共に認めるのは、ギリシアは寛大さに欠け、ローマは寛容だったという点である。
ギリシアとローマは時代的に前後関係にあるのではなく、重なった時期(ギリシアはローマの植民地になるが)が長い。ローマの共和政開始(前509年)は、ギリシアの民主政確立(前508年)より1年早いという本村氏の指摘には驚いた。まさに並列だったのだ。
また、桜井氏は『黒いアテナ』などにも言及しつつ、オリエント文明のギリシア文明への影響を強調している。ローマはギリシアの影響を強く受けているのだから、ローマをオリエント文明の辺境と捉えることもできるわけだ。
天才小学4年生のおかげで昔のSFを読了 ― 2023年04月14日
33年前(1990年)のSF大賞受賞作を読んだ。
『アド・バード』(椎名誠/集英社文庫)
椎名誠氏のエッセイや自伝的長編は何冊も面白く読んできた。このSF小説も気がかりだったが、つい読みそびれていた。そんな昔の作品を読んだのは、新聞で天才棋士・藤井聡太の少年時代に関する記事を読んだからである。
その記事には、藤井聡太が小学4年のときに「名人をこす」と書いた自己紹介カードの写真が載っていた。そこには「最近読んで面白かった本」として「1.海賊と呼ばれた男(百田尚樹)」「2.深夜特急(沢木耕太郎)」「3.アド・バード(椎名誠)」をあげていた。すべて大人の本だ。その早熟に驚いた。私が小学4年の頃に読んでいたのは、せいぜい『少年少女世界文学全集』だった。
藤井少年があげた1位と2位は私も読んでいるが、3位の『アド・バード』は気がかりな未読本だ。癪に障る。74歳の凡人ジイサンが天才小学4年生と張り合ってどうするとも思うが、あたふたとネット古書店で『アド・バード』を入手し、読了した。
文庫本で560頁強の長編SFである。若い兄弟が父の消息を求めて異形の未来世界を旅する冒険譚――と言えばオーソドックスな物語の構図だが、ディティールの濃密な描写に驚いた。広告デストピアのオモロSFを想定していたが、私の予断をはるかに超えたディープな世界の話だ。壊れた未来世界を見事に描いている。
世界を牛耳る二大勢力の熾烈な広告合戦の果てに廃墟となった世界に、次からつぎへと奇怪な動植物や機械が登場してくる。生物(?)の多くは生物と機械を化合したバイオ化合物なのである。その名前をいくつか列挙してみる。
ヒゾムシ、ハリフクミ、赤舌、カニクイドリ、ワナナキ、地ばしり、シダレカズラ、セイヨウシナノキ、ハキリトビアリ、インドカネタタキ、アワフキフクロガエル、ヒコネズミ、ツノダシ、ヒトスジスミレイカ、アカグチ・・・・・
これら異形の「生物」たちの姿形を具体的に想像しながら読み進めるのは、脳味噌が干からびかけている老人にはかなりの負担である。図鑑を貼付してほしいと思った。小学4年のみずみずしい頭なら、心ときめかせて柔軟な空想力で未知の生物の姿形を奔放に紡ぎ出せるかもしれない。本書を小学4年で読んだ藤井少年がうらやましくなった。
『アド・バード』(椎名誠/集英社文庫)
椎名誠氏のエッセイや自伝的長編は何冊も面白く読んできた。このSF小説も気がかりだったが、つい読みそびれていた。そんな昔の作品を読んだのは、新聞で天才棋士・藤井聡太の少年時代に関する記事を読んだからである。
その記事には、藤井聡太が小学4年のときに「名人をこす」と書いた自己紹介カードの写真が載っていた。そこには「最近読んで面白かった本」として「1.海賊と呼ばれた男(百田尚樹)」「2.深夜特急(沢木耕太郎)」「3.アド・バード(椎名誠)」をあげていた。すべて大人の本だ。その早熟に驚いた。私が小学4年の頃に読んでいたのは、せいぜい『少年少女世界文学全集』だった。
藤井少年があげた1位と2位は私も読んでいるが、3位の『アド・バード』は気がかりな未読本だ。癪に障る。74歳の凡人ジイサンが天才小学4年生と張り合ってどうするとも思うが、あたふたとネット古書店で『アド・バード』を入手し、読了した。
文庫本で560頁強の長編SFである。若い兄弟が父の消息を求めて異形の未来世界を旅する冒険譚――と言えばオーソドックスな物語の構図だが、ディティールの濃密な描写に驚いた。広告デストピアのオモロSFを想定していたが、私の予断をはるかに超えたディープな世界の話だ。壊れた未来世界を見事に描いている。
世界を牛耳る二大勢力の熾烈な広告合戦の果てに廃墟となった世界に、次からつぎへと奇怪な動植物や機械が登場してくる。生物(?)の多くは生物と機械を化合したバイオ化合物なのである。その名前をいくつか列挙してみる。
ヒゾムシ、ハリフクミ、赤舌、カニクイドリ、ワナナキ、地ばしり、シダレカズラ、セイヨウシナノキ、ハキリトビアリ、インドカネタタキ、アワフキフクロガエル、ヒコネズミ、ツノダシ、ヒトスジスミレイカ、アカグチ・・・・・
これら異形の「生物」たちの姿形を具体的に想像しながら読み進めるのは、脳味噌が干からびかけている老人にはかなりの負担である。図鑑を貼付してほしいと思った。小学4年のみずみずしい頭なら、心ときめかせて柔軟な空想力で未知の生物の姿形を奔放に紡ぎ出せるかもしれない。本書を小学4年で読んだ藤井少年がうらやましくなった。
舞踏と融合した『毛皮のマリー』は妖艶で猥雑な活人画 ― 2023年04月16日
座・高円寺でB機関ファイナル公演『毛皮のマリー』(作:寺山修司、演出:点滅、出演:葛たか喜代、他)を観た。
1967年初演の『毛皮のマリー』は、寺山修司が美輪明宏(当時は丸山明宏・32歳)にあて書きした芝居である。私は初演を観ていないが、初演から49年後に美輪明宏が演じた『毛皮のマリー』(新国立劇場)を観た。7年前に観たその舞台の化物屋敷的な印象は残っている。だがストーリーはほとんど失念している。
今回『毛皮のマリー』を観ようと思ったのは、ほとんど失念してしまった芝居のストーリーを確認したくなったからだ。B機関は私には未知の劇団である。舞踏的手法を演劇に取り入れた舞台を追究してきたそうだ。
私には7年ぶりの『毛皮のマリー』を、ほとんど初見の印象で最後まで観た。冒頭は40歳の男娼マリーの入浴シーン、下男にすね毛やわき毛を剃らせている。マリーには同居の美少年がいて、自身を「お母さん」と呼ばせている。マリーは美少年の部屋に珍しい蝶を放ち、美少年は室内で蝶を採取し、標本を作る……そんな設定の芝居である。
この芝居、開場は開演30分前だった。開場してすぐに入場すると、舞台にはすでに4人の異様な姿の人物がいた。最初は彫刻のように見えた4人はゆっくりと舞踏をしていた。それは開演まで続いた。開演前から始まっていた暗黒舞踏は、開演後にも断続的に継続する。確かに舞踏と演劇が融合した妖艶で猥雑な舞台である。
美輪明宏が演じたマリーをどんな役者が演じるのだろうと少々心配だったが、マリーを演じた葛たか喜代は十分に妖艶奇怪で、美輪明宏に遜色ないと思えた。
7年前に観たとき、ストーリー展開よりもサイケで猥雑な活人画のような情景が印象に残った。今回の舞台は、それ以上に「絵」が素晴らしい。舞台装置は夢幻的異世界を現出させ、そのなかで演じ舞踏する役者たちの妖しく蠱惑的な動きが壮大な「絵」を次々に見せてくれる。
1967年初演の『毛皮のマリー』は、寺山修司が美輪明宏(当時は丸山明宏・32歳)にあて書きした芝居である。私は初演を観ていないが、初演から49年後に美輪明宏が演じた『毛皮のマリー』(新国立劇場)を観た。7年前に観たその舞台の化物屋敷的な印象は残っている。だがストーリーはほとんど失念している。
今回『毛皮のマリー』を観ようと思ったのは、ほとんど失念してしまった芝居のストーリーを確認したくなったからだ。B機関は私には未知の劇団である。舞踏的手法を演劇に取り入れた舞台を追究してきたそうだ。
私には7年ぶりの『毛皮のマリー』を、ほとんど初見の印象で最後まで観た。冒頭は40歳の男娼マリーの入浴シーン、下男にすね毛やわき毛を剃らせている。マリーには同居の美少年がいて、自身を「お母さん」と呼ばせている。マリーは美少年の部屋に珍しい蝶を放ち、美少年は室内で蝶を採取し、標本を作る……そんな設定の芝居である。
この芝居、開場は開演30分前だった。開場してすぐに入場すると、舞台にはすでに4人の異様な姿の人物がいた。最初は彫刻のように見えた4人はゆっくりと舞踏をしていた。それは開演まで続いた。開演前から始まっていた暗黒舞踏は、開演後にも断続的に継続する。確かに舞踏と演劇が融合した妖艶で猥雑な舞台である。
美輪明宏が演じたマリーをどんな役者が演じるのだろうと少々心配だったが、マリーを演じた葛たか喜代は十分に妖艶奇怪で、美輪明宏に遜色ないと思えた。
7年前に観たとき、ストーリー展開よりもサイケで猥雑な活人画のような情景が印象に残った。今回の舞台は、それ以上に「絵」が素晴らしい。舞台装置は夢幻的異世界を現出させ、そのなかで演じ舞踏する役者たちの妖しく蠱惑的な動きが壮大な「絵」を次々に見せてくれる。
ギリシア以前を知るために『古代オリエント全史』を読んだ ― 2023年04月19日
ギリシアとローマを語る『集中講義! ギリシア・ローマ』を読んで、ギリシア文明はオリエント文明の辺境だというイメージが湧いた。だが、肝心のオリエント文明の姿が私には不明瞭である。そんな気分のとき、半年前に出た次の新書を書店で見つけ、手頃な本だと思って購入・読了した。
『古代オリエント全史』(小林登志子/中公新書/2022.11)
本書を読む前に、基礎知識確認のため山川の教科書『詳説世界史B』の「古代オリエントの世界」という項目(約11頁)を読んだ。この教科書は以前に一度読んでいるはずだが、失念している事柄が多い。
高校世界史で11頁の歴史が本書では300頁弱に膨らんでいる。私には未知の地名や人名が頻出する。それでも何とか読了できたのは、充実した索引のおかげだ。数頁前に読んだ固有名詞も混乱するわが頭には、索引を参照しながらの読書が有益だった。
ギリシア文明の淵源を確かめたいという動機で読んだ本書、私の期待通りの内容で勉強になった。オリエントこそが文明がはじまった場所だと、あらためて確認できた。
オリエントとは、現在のエジプト、イスラエル、ヨルダン、レバノン、シリア、トルコ、イラク、イランのあたりである。著者は古代オリエントをメソポタミア、シリア、アナトリア(小アジア)、エジプト、イランの五地域にわけて解説している。
この五地域を「本流のメソポタミア」「草刈り場のシリア」「最古印欧語族のアナトリア」「偉大な傍流エジプト」「新参の大統一者イラン」とメリハリをつけて歴史をたどっている。理解しやすい。
古代オリエント史はアレクサンドロスの東征で終わる。興味深いのは、そのアレクサンドロスの評価だ。著者は次のように述べている。
「古代オリエント世界の住人にとってのアレクサンドロスは外国からの侵入者であり、戦場での戦闘行為だけでなく、住民に対しての殺戮や掠奪などもおこなっている。アレクサンドロスの都市建設はギリシア人のためであり、オリエントの住民のためではなかった。」
また、欧州共通教科書のアレクサンドロス評価に対しては「征服を過大に評価、正当化することで、現代にいたるまでユーロッパ勢力のアジア侵攻を正当化する歴史観に、本書は与しない」と批判的だ。
やはり、文明化されたオリエントにとってギリシアは西の果ての野蛮な脅威だったように思える。ペロポネス戦争で疲弊したギリシア人のなかにはペルシアの傭兵になる者も多かったそうだ。
残念なのは、オリエント世界(その中心のメソポタミア)にヘロドトスや司馬遷がいなかったことだ。文字は遠い昔からあったのに歴史書は残っていない。そのことについても著者は考察している。
本書の終章では、古代オリエント史終焉から現代にいたるまでのこの地域の歴史を駆け足で概説している。文明・文化の創出と伝播の変遷が概観でき、現代と古代オリエントのつながりが浮かびあがってくる。
本書のあとがきで著者が三笠宮崇仁に触れているのを読み、8年前に『ここに歴史はじまる』(三笠宮崇仁)を読んだのを思い出した。その本を引っ張り出して確認すると、本書と重なる歴史概説である。8年前に読んだ内容の大半が頭から蒸発していたのが悲しい。
『古代オリエント全史』(小林登志子/中公新書/2022.11)
本書を読む前に、基礎知識確認のため山川の教科書『詳説世界史B』の「古代オリエントの世界」という項目(約11頁)を読んだ。この教科書は以前に一度読んでいるはずだが、失念している事柄が多い。
高校世界史で11頁の歴史が本書では300頁弱に膨らんでいる。私には未知の地名や人名が頻出する。それでも何とか読了できたのは、充実した索引のおかげだ。数頁前に読んだ固有名詞も混乱するわが頭には、索引を参照しながらの読書が有益だった。
ギリシア文明の淵源を確かめたいという動機で読んだ本書、私の期待通りの内容で勉強になった。オリエントこそが文明がはじまった場所だと、あらためて確認できた。
オリエントとは、現在のエジプト、イスラエル、ヨルダン、レバノン、シリア、トルコ、イラク、イランのあたりである。著者は古代オリエントをメソポタミア、シリア、アナトリア(小アジア)、エジプト、イランの五地域にわけて解説している。
この五地域を「本流のメソポタミア」「草刈り場のシリア」「最古印欧語族のアナトリア」「偉大な傍流エジプト」「新参の大統一者イラン」とメリハリをつけて歴史をたどっている。理解しやすい。
古代オリエント史はアレクサンドロスの東征で終わる。興味深いのは、そのアレクサンドロスの評価だ。著者は次のように述べている。
「古代オリエント世界の住人にとってのアレクサンドロスは外国からの侵入者であり、戦場での戦闘行為だけでなく、住民に対しての殺戮や掠奪などもおこなっている。アレクサンドロスの都市建設はギリシア人のためであり、オリエントの住民のためではなかった。」
また、欧州共通教科書のアレクサンドロス評価に対しては「征服を過大に評価、正当化することで、現代にいたるまでユーロッパ勢力のアジア侵攻を正当化する歴史観に、本書は与しない」と批判的だ。
やはり、文明化されたオリエントにとってギリシアは西の果ての野蛮な脅威だったように思える。ペロポネス戦争で疲弊したギリシア人のなかにはペルシアの傭兵になる者も多かったそうだ。
残念なのは、オリエント世界(その中心のメソポタミア)にヘロドトスや司馬遷がいなかったことだ。文字は遠い昔からあったのに歴史書は残っていない。そのことについても著者は考察している。
本書の終章では、古代オリエント史終焉から現代にいたるまでのこの地域の歴史を駆け足で概説している。文明・文化の創出と伝播の変遷が概観でき、現代と古代オリエントのつながりが浮かびあがってくる。
本書のあとがきで著者が三笠宮崇仁に触れているのを読み、8年前に『ここに歴史はじまる』(三笠宮崇仁)を読んだのを思い出した。その本を引っ張り出して確認すると、本書と重なる歴史概説である。8年前に読んだ内容の大半が頭から蒸発していたのが悲しい。
挿絵満載の『痴愚神礼賛』は面白い ― 2023年04月23日
16世紀宗教改革に関する文章を読んでいてエラスムスへの興味がわいた。で、次の代表作を入手・読了した。
『痴愚神礼賛』(エラスムス/沓掛良彦訳/中公文庫)
エラスムスは16世紀最大の人文主義者と言われている。カトリックの腐敗を風刺した本書が起爆剤となってルターの宗教改革が始まった。だが、過激な宗教改革に批判的だったエラスムスはカトリックから離れない。新旧両派から非難されて孤立する。面白い立ち位置だ。
本書を読もうと思ったのは、エラスムスが1週間足らずで一気に本書を書き上げたと知ったからだ。短期間で書いたものなら短期間で読めそうだ、と勝手に思い込んだのだ。古典と言っても風刺文学なら読みやすかろうとも予感した。
ラテン語原典訳の本書、本体部分は約200頁、注が約100頁である。注を頻繁に参照しながらの読書はわずらわしい。だが、ギリシア・ローマの神話や古典を踏まえた表現が多いので、読み進めるには注が頼りになった。
本書は痴愚神が聴衆に演説する形の一人称で書かれている。痴愚神とは「痴愚というめぐみ」を人々にわけへだてなく与える女神である。『痴愚神礼賛』とは痴愚女神の自画自賛の長広舌である。かなり愉快な演説だ。
本文には16世紀原典の図版と思しき挿絵が80点以上載っていて、これを眺めるだけでも楽しい。なかには意味不明の絵もある。だが、巻末にすべての図版のタイトルがあり、それを参照するとほぼ理解できる。
痴愚女神の自画自賛の大半は「愚かな者は幸せである」という主旨であり、的を射てる点もあって面白い。後段になって修道士、教皇、枢機卿らの愚かさあげつらう。この箇所が宗教改革の契機になったのかと納得できる。終盤は痴愚や狂気に関するキリスト教談義になり、エラスムス自身が語っている趣になる。締めくくりでは再び痴愚女神の口調になって降壇する。
宗教改革の歴史を読んでいると、ルター派やカルヴァン派には現代のタリバンやISに似た過剰な原理主義も感じる。また、宗教改革の背景には宗教とは別次元の勢力争いもあったようだ。改革派対守旧派という単純な構図ではないのだ。
書斎人だったエラスムスは戦争を否定する平和主義者で、教会の分裂や宗教戦争を望んでいなかった。ルターが自分を尊敬していると知り、ルターを支援しようともするが、その過激化にはついて行けず訣別する。『痴愚神礼賛』で自身を揶揄された教皇(レオ10世)は本書を読んで笑い転げたそうだが、カトリック側からもエラスムスは不逞の人物とみなされ、著書は禁書にされる。
エラスムスについて知ると「宗教は強し、理性は弱し」という苦い感慨がわく。
『痴愚神礼賛』(エラスムス/沓掛良彦訳/中公文庫)
エラスムスは16世紀最大の人文主義者と言われている。カトリックの腐敗を風刺した本書が起爆剤となってルターの宗教改革が始まった。だが、過激な宗教改革に批判的だったエラスムスはカトリックから離れない。新旧両派から非難されて孤立する。面白い立ち位置だ。
本書を読もうと思ったのは、エラスムスが1週間足らずで一気に本書を書き上げたと知ったからだ。短期間で書いたものなら短期間で読めそうだ、と勝手に思い込んだのだ。古典と言っても風刺文学なら読みやすかろうとも予感した。
ラテン語原典訳の本書、本体部分は約200頁、注が約100頁である。注を頻繁に参照しながらの読書はわずらわしい。だが、ギリシア・ローマの神話や古典を踏まえた表現が多いので、読み進めるには注が頼りになった。
本書は痴愚神が聴衆に演説する形の一人称で書かれている。痴愚神とは「痴愚というめぐみ」を人々にわけへだてなく与える女神である。『痴愚神礼賛』とは痴愚女神の自画自賛の長広舌である。かなり愉快な演説だ。
本文には16世紀原典の図版と思しき挿絵が80点以上載っていて、これを眺めるだけでも楽しい。なかには意味不明の絵もある。だが、巻末にすべての図版のタイトルがあり、それを参照するとほぼ理解できる。
痴愚女神の自画自賛の大半は「愚かな者は幸せである」という主旨であり、的を射てる点もあって面白い。後段になって修道士、教皇、枢機卿らの愚かさあげつらう。この箇所が宗教改革の契機になったのかと納得できる。終盤は痴愚や狂気に関するキリスト教談義になり、エラスムス自身が語っている趣になる。締めくくりでは再び痴愚女神の口調になって降壇する。
宗教改革の歴史を読んでいると、ルター派やカルヴァン派には現代のタリバンやISに似た過剰な原理主義も感じる。また、宗教改革の背景には宗教とは別次元の勢力争いもあったようだ。改革派対守旧派という単純な構図ではないのだ。
書斎人だったエラスムスは戦争を否定する平和主義者で、教会の分裂や宗教戦争を望んでいなかった。ルターが自分を尊敬していると知り、ルターを支援しようともするが、その過激化にはついて行けず訣別する。『痴愚神礼賛』で自身を揶揄された教皇(レオ10世)は本書を読んで笑い転げたそうだが、カトリック側からもエラスムスは不逞の人物とみなされ、著書は禁書にされる。
エラスムスについて知ると「宗教は強し、理性は弱し」という苦い感慨がわく。



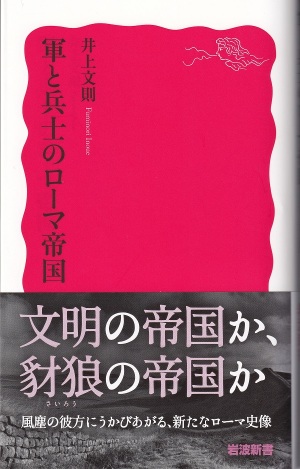

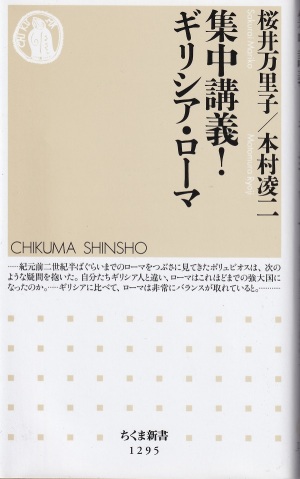



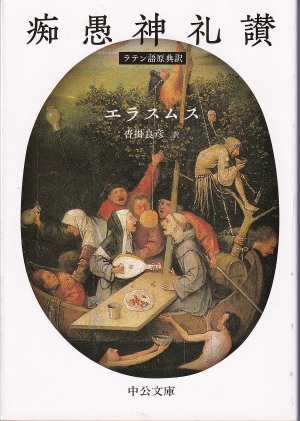
最近のコメント