北里柴三郎の伝記は面白い ― 2024年03月08日
先日、北里研究所の関係者と面談する機会があった。そのときまで、北里研究所とは北里大学内の研究機関だと思っていた。しかし、逆だった。北里研究所のもとに北里大学や北里病院などの諸機関があるそうだ。北里柴三郎が設立したのは北里研究所であり、それがそもそもの母体だと知った。そんなきっかけでこの偉人について知りたくなり、伝記を読んだ。
『北里柴三郎:雷(ドンネル)と呼ばれた男(上)(下)』(山崎光男/中公文庫)
本書は2003年刊行の単行本の文庫版(2007年)である。著者は、医学・薬学分野の作品が多い小説家である。今年の夏、千円札の肖像が野口英世から北里柴三郎に代わるが、それに当て込んだ本ではない。
北里柴三郎については子供時代に偉人の一人として習っただけで、詳しくは知らなかった。第1回ノーベル賞受賞の可能性があったが、東洋人なので受賞を逸したという話を聞いたことはある。本書を読んで、北里柴三郎の業績と疾風怒涛の生涯を知った。第1回ノーベル賞に関する著者の見解も納得できた。とても面白い伝記である。
細菌学と言えばコッホの名が浮かぶ。柴三郎はベルリンに留学し、コッホの門下生になる。単なる弟子ではなく、優秀な共同研究者としてコッホから高く評価される。同じ時期の留学生・森林太郎とはかなり異なる。柴三郎の方が研究熱心だ。
柴三郎はケンブリッジなど英米の大学から「研究所長に…」と要請されるが、国費留学生なので帰国する。しかし、帰国しても能力を活かす場がない。柴三郎の留学時代から「東大vs北里」という感情的対立があったからである。妬みが絡んだ対立という図式は、よくある光景だ。
やがて、福沢諭吉や内務官僚らの支援で柴三郎のための私立伝染病研究所が設立され、その後、国立の研究所になる。柴三郎は伝染病研究所の所長として39歳から61歳まで活躍する。
しかし、柴三郎が61歳のとき、政治家らの思惑で伝染病研究所は唐突に文部省に移管され東大付属となる。柴三郎は辞任し、自ら北里研究所を設立する。そのとき、研究員らも柴三郎と行動を共にする。研究員は残留すると目論んでいた東大側はあわてる。このくだりの経緯は小説のように面白い。現在の北里研究所の由来がよくわかった。
『北里柴三郎:雷(ドンネル)と呼ばれた男(上)(下)』(山崎光男/中公文庫)
本書は2003年刊行の単行本の文庫版(2007年)である。著者は、医学・薬学分野の作品が多い小説家である。今年の夏、千円札の肖像が野口英世から北里柴三郎に代わるが、それに当て込んだ本ではない。
北里柴三郎については子供時代に偉人の一人として習っただけで、詳しくは知らなかった。第1回ノーベル賞受賞の可能性があったが、東洋人なので受賞を逸したという話を聞いたことはある。本書を読んで、北里柴三郎の業績と疾風怒涛の生涯を知った。第1回ノーベル賞に関する著者の見解も納得できた。とても面白い伝記である。
細菌学と言えばコッホの名が浮かぶ。柴三郎はベルリンに留学し、コッホの門下生になる。単なる弟子ではなく、優秀な共同研究者としてコッホから高く評価される。同じ時期の留学生・森林太郎とはかなり異なる。柴三郎の方が研究熱心だ。
柴三郎はケンブリッジなど英米の大学から「研究所長に…」と要請されるが、国費留学生なので帰国する。しかし、帰国しても能力を活かす場がない。柴三郎の留学時代から「東大vs北里」という感情的対立があったからである。妬みが絡んだ対立という図式は、よくある光景だ。
やがて、福沢諭吉や内務官僚らの支援で柴三郎のための私立伝染病研究所が設立され、その後、国立の研究所になる。柴三郎は伝染病研究所の所長として39歳から61歳まで活躍する。
しかし、柴三郎が61歳のとき、政治家らの思惑で伝染病研究所は唐突に文部省に移管され東大付属となる。柴三郎は辞任し、自ら北里研究所を設立する。そのとき、研究員らも柴三郎と行動を共にする。研究員は残留すると目論んでいた東大側はあわてる。このくだりの経緯は小説のように面白い。現在の北里研究所の由来がよくわかった。
今年は安部公房生誕100年 ― 2024年02月25日
『芸術新潮 2024年3月号』は安部公房特集である。表紙に「生誕100年記念特集 わたしたちには安部公房が必要だ」とある。私は安部公房ファンだった。全集も購入した。だから、この雑誌をすぐに購入した。
安部公房の作品はほぼすべて読んでいるはずだが、この10年、再読はしていないと思う。だから、現在も安部公房ファンかは微妙である。一昨年出た『壁とともに生きる:わたしと「安部公房」』(ヤマザキマリ)などは面白く読んだ。私にとって気がかりな作家であり続けているのは確かだ。
『芸術新潮』の安部公房特集は約60ページ、雑誌の半分を占めている。解説記事の他に安部公房のエッセイ6編を収録、関連写真も多数載っている。安部公房自身が撮影した『都市を盗る』と題する写真もある。どれも私には懐かしい写真ばかりで、久々に安部公房世界に浸った。
この特集に接して、都市という状況への安部公房のこだわりをあらためて認識した。先日、『箱男』映画化の新聞記事を読んだ。この特集には、その映画の石井岳龍監督のインタビュー記事も載っている。すでに映画は完成し、公開準備中のようだ。
10年前、山口果林の『安部公房とわたし』を読んだとき、『箱男』を再読せねばと思った。だが、果たしていない。映画を観る前には再読したい。生誕100年をむかえ、安部公房への注目が集まればうれしい。いずれ、再挑戦したい作家である。
安部公房の作品はほぼすべて読んでいるはずだが、この10年、再読はしていないと思う。だから、現在も安部公房ファンかは微妙である。一昨年出た『壁とともに生きる:わたしと「安部公房」』(ヤマザキマリ)などは面白く読んだ。私にとって気がかりな作家であり続けているのは確かだ。
『芸術新潮』の安部公房特集は約60ページ、雑誌の半分を占めている。解説記事の他に安部公房のエッセイ6編を収録、関連写真も多数載っている。安部公房自身が撮影した『都市を盗る』と題する写真もある。どれも私には懐かしい写真ばかりで、久々に安部公房世界に浸った。
この特集に接して、都市という状況への安部公房のこだわりをあらためて認識した。先日、『箱男』映画化の新聞記事を読んだ。この特集には、その映画の石井岳龍監督のインタビュー記事も載っている。すでに映画は完成し、公開準備中のようだ。
10年前、山口果林の『安部公房とわたし』を読んだとき、『箱男』を再読せねばと思った。だが、果たしていない。映画を観る前には再読したい。生誕100年をむかえ、安部公房への注目が集まればうれしい。いずれ、再挑戦したい作家である。
吉本隆明の老人本は独演会のようだ ― 2023年12月30日
老いた吉本隆明を長女が語った『隆明だもの』を読み、書架に眠っていた次の2冊を読む気になった。
『老いの超え方』(吉本隆明/朝日新聞社/2006.5)
『老いの幸福論』(吉本隆明/青春新書/青春出版社/2011.4)
前者は刊行直後(17年前)に入手し、拾い読みしただけだ。後者は、十年ほど前に知り合いの高齢女性(私より十数歳上)から「読んだ」と聞いたのを機に入手したが、積んだままだった。
この2冊が未読だったのは、いずれ「老い」が切実になってから読めばいいと思ったからである。前者を入手したとき私は57歳、老いにさほどの関心はなかった。
先月、私は後期高齢者になった。そろそろ、老いを考えねばならない時期かもしれない。そう思ってこの2冊を読んだが、老いを超える心構えができたとは言えない。もとより、これらはハウツー本ではない。吉本隆明翁独演会の趣がある。
吉本隆明は2012年に87歳で逝った。『老いの超え方』は81歳のときの著作、『老いの幸福論』の刊行は86歳のときだ。まず前者を読んだ。「身体」「社会」「思想」「死」をテーマにした4部構成のインタビューである。一問一答もあり、読みやすい。日常生活を撮影した写真が多く載っている。ヨボっていても元気そうだ。
テーマごとのおしゃべりの後に「語録集」がある。過去の著作からの抜粋集成である。親切な編集だ。この「語録集」には2001年の『幸福論』からの抜粋が多い。気になって調べると、『幸福論』は『老いの幸福論』と同じだった。2001年刊行の『幸福論』を2011年に新書化する際に『老いの幸福論』と改題し「新書化にあたってのあとがき」を付加していたのだ。それなら『老いの幸福論』から読むべきだったと思った。
『老いの超え方』では、一番の関心ごとを訊かれて次のように応じている。
「一番関心が集約されていることはどこかというと、かかる状態が老いというかたちなのかと、われながらびくりしたり、新しく考えることが出てきたりということがあります。老人というのは何なんだ、どういうことが解決がつく部分でどういうことが解決が付かない部分なのか、考え抜いた部分と結局分からない部分が入り交じっていますが、一般のご老人たちが口にしないことを言い尽くしてみたいと思っています。けれども言い尽くせない、分からないなということが多いです。」
吉本世代とは、世の中の課題に出会ったとき、つい、吉本隆明ならどう考えるだろうかと思ってしまう世代である。『老いの超え方』は、そんな読者に向けた「老い」の現場レポートである。
『老いの幸福論』のエッセンスは『老いの超え方』の「語録集」で紹介されている。だから『老いの幸福論』は再読気分で読み進めた。そんな既視感以上に繰り返しが多い。口述をまとめる際に編集者が整理しているとは思うが、あらためて年寄りの話は繰り返しが多くてくどいと感じた。
でも、『老いの幸福論』には「老い」とは関係が薄い興味深い話題も多く、面白く読んだ。自身の結婚の際の事情をかなり赤裸々に語っている。溺れたときの体験談もある。娘たちの教育・進学などにつても具体的にしゃべっている。次女の吉本ばななに関して、最初は「親の七光り」と言われたが、すぐに逆転してこちらが「子どもの七光り」になったと語っている。楽しい自覚だ。
『老いの超え方』(吉本隆明/朝日新聞社/2006.5)
『老いの幸福論』(吉本隆明/青春新書/青春出版社/2011.4)
前者は刊行直後(17年前)に入手し、拾い読みしただけだ。後者は、十年ほど前に知り合いの高齢女性(私より十数歳上)から「読んだ」と聞いたのを機に入手したが、積んだままだった。
この2冊が未読だったのは、いずれ「老い」が切実になってから読めばいいと思ったからである。前者を入手したとき私は57歳、老いにさほどの関心はなかった。
先月、私は後期高齢者になった。そろそろ、老いを考えねばならない時期かもしれない。そう思ってこの2冊を読んだが、老いを超える心構えができたとは言えない。もとより、これらはハウツー本ではない。吉本隆明翁独演会の趣がある。
吉本隆明は2012年に87歳で逝った。『老いの超え方』は81歳のときの著作、『老いの幸福論』の刊行は86歳のときだ。まず前者を読んだ。「身体」「社会」「思想」「死」をテーマにした4部構成のインタビューである。一問一答もあり、読みやすい。日常生活を撮影した写真が多く載っている。ヨボっていても元気そうだ。
テーマごとのおしゃべりの後に「語録集」がある。過去の著作からの抜粋集成である。親切な編集だ。この「語録集」には2001年の『幸福論』からの抜粋が多い。気になって調べると、『幸福論』は『老いの幸福論』と同じだった。2001年刊行の『幸福論』を2011年に新書化する際に『老いの幸福論』と改題し「新書化にあたってのあとがき」を付加していたのだ。それなら『老いの幸福論』から読むべきだったと思った。
『老いの超え方』では、一番の関心ごとを訊かれて次のように応じている。
「一番関心が集約されていることはどこかというと、かかる状態が老いというかたちなのかと、われながらびくりしたり、新しく考えることが出てきたりということがあります。老人というのは何なんだ、どういうことが解決がつく部分でどういうことが解決が付かない部分なのか、考え抜いた部分と結局分からない部分が入り交じっていますが、一般のご老人たちが口にしないことを言い尽くしてみたいと思っています。けれども言い尽くせない、分からないなということが多いです。」
吉本世代とは、世の中の課題に出会ったとき、つい、吉本隆明ならどう考えるだろうかと思ってしまう世代である。『老いの超え方』は、そんな読者に向けた「老い」の現場レポートである。
『老いの幸福論』のエッセンスは『老いの超え方』の「語録集」で紹介されている。だから『老いの幸福論』は再読気分で読み進めた。そんな既視感以上に繰り返しが多い。口述をまとめる際に編集者が整理しているとは思うが、あらためて年寄りの話は繰り返しが多くてくどいと感じた。
でも、『老いの幸福論』には「老い」とは関係が薄い興味深い話題も多く、面白く読んだ。自身の結婚の際の事情をかなり赤裸々に語っている。溺れたときの体験談もある。娘たちの教育・進学などにつても具体的にしゃべっている。次女の吉本ばななに関して、最初は「親の七光り」と言われたが、すぐに逆転してこちらが「子どもの七光り」になったと語っている。楽しい自覚だ。
娘が父を語った『隆明だもの』は辛辣で面白い ― 2023年12月26日
「戦後最大の思想家」とも言われる吉本隆明の長女でマンガ家のハルノ宵子が父親を語った『隆明だもの』を読んだ。
『隆明だもの』(ハルノ宵子/晶文社)
吉本隆明全集(2014年刊行開始。既刊33巻。全39巻予定)の月報に載せた文章を中心にまとめたもので、吉本ばなな(次女)との姉妹対談も収録している。オビには「故人を讃えない、型破りな追悼録。」とある。「あとがき」の冒頭は次の通りだ。
「イヤ~…ヒドイ娘ですね。吉本主義者の方々の、幻想粉砕してますね。」
本書には「吉本世代」や「吉本主義者」という言葉が出てくる。娘から見れば思想家もただの面倒なオヤジであり、見方が辛辣になるのは当然である。むしろ、著者が高校生の頃から父の著書に接していたことに感心した。「(『共同幻想論』などを)斜め読みしたけど、何にもわかりません」と語っているが、父親をリスペクトするいい娘だったように思える。
私は吉本世代である。吉本主義者ではない。学生時代から吉本隆明の著作に多少は接してきたが、理解できたとは思えない。2012年に吉本隆明が87歳で逝去した直後には「マチウ書詩論」を再読し、吉本隆明を少し読み返そうと思った。思っただけで実行していない。
そんな私にとって、本書はとても面白かった。吉本隆明は晩年、糖尿病で目が見えにくくなり、身体も不自由だった。膨大な著作を残しているが、後半生の著作は口述や対談である。著者によれば、晩年の吉本隆明にはボケ特有の言動があったそうだ。ボケていても口述本は可能だった。著者は次のように述べている。
「一方父は、他人から見れば最後まで一見マトモだったと思う。インタビューなどにも、事実誤認はあるものの(それは昔からだけど)そこそこマトモに答えていたし、元々父の著作を分かりづらくさせていた、表現の“飛躍”の度合が増して、ますます誤解されやすくなっていたが、思考にブレはなかった。」
ナルホドと思った。父のことがよくわかっている。
吉本隆明の娘で想起するのは、1960年代末の替歌の次の一節だ。
吉本おやじは 生活おやじ
子供をひきつれ
はくさい にんじん 値切る
(元歌「お馬の親子」。『戯歌番外地(三一新書)』より)
吉本隆明は、病弱の妻に代わって料理を作っていたという話をどこかに書いていた。しかし、娘の証言では、病気のときに父が作ってくれた卵酒やクリームシチューは酷い代物で、とても口にできなかったそうだ。
『隆明だもの』(ハルノ宵子/晶文社)
吉本隆明全集(2014年刊行開始。既刊33巻。全39巻予定)の月報に載せた文章を中心にまとめたもので、吉本ばなな(次女)との姉妹対談も収録している。オビには「故人を讃えない、型破りな追悼録。」とある。「あとがき」の冒頭は次の通りだ。
「イヤ~…ヒドイ娘ですね。吉本主義者の方々の、幻想粉砕してますね。」
本書には「吉本世代」や「吉本主義者」という言葉が出てくる。娘から見れば思想家もただの面倒なオヤジであり、見方が辛辣になるのは当然である。むしろ、著者が高校生の頃から父の著書に接していたことに感心した。「(『共同幻想論』などを)斜め読みしたけど、何にもわかりません」と語っているが、父親をリスペクトするいい娘だったように思える。
私は吉本世代である。吉本主義者ではない。学生時代から吉本隆明の著作に多少は接してきたが、理解できたとは思えない。2012年に吉本隆明が87歳で逝去した直後には「マチウ書詩論」を再読し、吉本隆明を少し読み返そうと思った。思っただけで実行していない。
そんな私にとって、本書はとても面白かった。吉本隆明は晩年、糖尿病で目が見えにくくなり、身体も不自由だった。膨大な著作を残しているが、後半生の著作は口述や対談である。著者によれば、晩年の吉本隆明にはボケ特有の言動があったそうだ。ボケていても口述本は可能だった。著者は次のように述べている。
「一方父は、他人から見れば最後まで一見マトモだったと思う。インタビューなどにも、事実誤認はあるものの(それは昔からだけど)そこそこマトモに答えていたし、元々父の著作を分かりづらくさせていた、表現の“飛躍”の度合が増して、ますます誤解されやすくなっていたが、思考にブレはなかった。」
ナルホドと思った。父のことがよくわかっている。
吉本隆明の娘で想起するのは、1960年代末の替歌の次の一節だ。
吉本おやじは 生活おやじ
子供をひきつれ
はくさい にんじん 値切る
(元歌「お馬の親子」。『戯歌番外地(三一新書)』より)
吉本隆明は、病弱の妻に代わって料理を作っていたという話をどこかに書いていた。しかし、娘の証言では、病気のときに父が作ってくれた卵酒やクリームシチューは酷い代物で、とても口にできなかったそうだ。
SF第1世代作家の豊田有恒氏逝去 ― 2023年12月06日
本日(2023.12.6)の朝刊にSF作家・豊田有恒氏の訃報が載っていた。行年85歳。私が高校生の頃から親しんでいたSF第1世代の作家だ。私にとってのSF作家は小松左京、星新一、筒井康隆、光瀬龍、眉村卓、豊田有恒、平井和正、半村良ら第1世代の作家だ。筒井康隆氏以外はみな逝ってしまった。
豊田氏の訃報を見て、筒井康隆氏の最新刊『カーテンコール』刊行後でよかったと思った。この掌編集収録の「プレイバック」(初出は『新潮』2022.2)は検査入院中の作者の元を小説の主人公らが次々に訪れる話である。最後に、小松左京や星新一をはじめ亡くなったSF作家連中がどやどやと押しかけてくる。その中ににひとりだけ存命中の豊田有恒氏が混ざっている。その様子を次のように描写している。
「彼は自分がどうしてここにいるのかわからぬという戸惑いを表情に漂わせて周囲を見まわしている。」
この一節を読んで、私は笑ってしまった。
私は、豊田氏の初期作品は読んでいるが、その後、継続的に読んできたとは言えない。だが、4年前に出た『日本SF誕生』や『小松左京マガジン』に連載(2011~2013年、10回)した「メタボ解消に大学教授」などの晩年のエッセイを楽しく読んだ。
また、今年の夏に東京国立博物館で開催された『特別展古代メキシコ』に行った直後、久々に初期作品の『アステカに吹く風』を再読した。
豊田氏の訃報を見て、筒井康隆氏の最新刊『カーテンコール』刊行後でよかったと思った。この掌編集収録の「プレイバック」(初出は『新潮』2022.2)は検査入院中の作者の元を小説の主人公らが次々に訪れる話である。最後に、小松左京や星新一をはじめ亡くなったSF作家連中がどやどやと押しかけてくる。その中ににひとりだけ存命中の豊田有恒氏が混ざっている。その様子を次のように描写している。
「彼は自分がどうしてここにいるのかわからぬという戸惑いを表情に漂わせて周囲を見まわしている。」
この一節を読んで、私は笑ってしまった。
私は、豊田氏の初期作品は読んでいるが、その後、継続的に読んできたとは言えない。だが、4年前に出た『日本SF誕生』や『小松左京マガジン』に連載(2011~2013年、10回)した「メタボ解消に大学教授」などの晩年のエッセイを楽しく読んだ。
また、今年の夏に東京国立博物館で開催された『特別展古代メキシコ』に行った直後、久々に初期作品の『アステカに吹く風』を再読した。
ブッダは合理的でプラグマティックな考えの経験論者 ― 2023年11月23日
『ブッダが説いた幸せな生き方』(今枝由郎/岩波新書/2021.5)
さる人からいい本だと紹介されて購入したのが2年前、『ゆかいな仏教』を読んで未読の本書を思い出した。『ゆかいな~』がゴチャゴチャと難解なのに比べて本書はわかりやすい。わかりやす過ぎるぐらいだ。
著者は1947年生まれのチベット歴史文献研究者、フランスの研究機関に長く在籍し、ブータンの国立図書館顧問として現地に10年在み、現在は日本在住らしい。
著者は、日本の仏教をブッダの教えからかけはなれた「奇形」とし、もしブッダが日本仏教の現状を知ったら、まちがいなく「私は『仏教徒』ではない」と言うだろうと述べている。
紀元前5世紀頃、シッダールタが「覚り」を得てブッダとなり、仏教を開いた。著者は「覚り」という言葉を使わず、一貫して「目覚めた人」ブッダと表現している。
ブッダは人々に乞われて「目覚めた人」になる方策を語る。その教えは数世紀にわたって口承で伝えられ、初めて文字になったのはブッダから約500年後の紀元前後のパーリ語の記録である。その後、サンスクリット語で記されるようになる。経典の原文はサンスクリット語と思っていたが、それ以前にパーリ語があったとは知らなかった。
著者は、ブッダ自身のことばに可能な限り近づくため、主にパーリ語のテキストに基づいて本書を著している。著者が長年研究してきたチベット・ブータン仏教も著者の見解に反映されていて「多分に個人的な「仏教」理解です」とことわっている。
本書が紹介するブッダの教えは難解な哲学ではなく、自己啓発セミナーの指南のようだ。わかりやすいが、容易に実践できるわけではない。ブッダに関する次の指摘が意外だった。
「ブッダは経験論者で、生涯を通じてすべて自分で経験したことだけを話す人であり、思弁的、形而上学的なことがらはいっさい問題にしませんでした。」
ブッダは徹底した合理主義者でプラグマティックな考え方をしたとも述べている。その教えを簡単にまとめることはできないが、ある種の精神修養を説いている感じだ。
仏教において「目覚めた人」になる(さとりをひらく)のは至難だとのイメージがある。だが、ブッダが生きた時代には、多くの弟子たちが「目覚めた人」になったそうだ。後世になって、「目覚めた人」になるのはとっても困難と見なされるようになったらしい。ありそうな話だ。
著者は、ニーチェやアインシュタインの次のような言葉も紹介している。
「仏教は、歴史が我々に提示してくれる、唯一の真に実証科学的宗教である(ニーチェ)」
「仏教は、近代科学と両立可能な唯一の宗教である(アインシュタイン)」
私は宗教にさほどの関心はないが、仏教に期待してもいいのかな、と思わせる本である。
さる人からいい本だと紹介されて購入したのが2年前、『ゆかいな仏教』を読んで未読の本書を思い出した。『ゆかいな~』がゴチャゴチャと難解なのに比べて本書はわかりやすい。わかりやす過ぎるぐらいだ。
著者は1947年生まれのチベット歴史文献研究者、フランスの研究機関に長く在籍し、ブータンの国立図書館顧問として現地に10年在み、現在は日本在住らしい。
著者は、日本の仏教をブッダの教えからかけはなれた「奇形」とし、もしブッダが日本仏教の現状を知ったら、まちがいなく「私は『仏教徒』ではない」と言うだろうと述べている。
紀元前5世紀頃、シッダールタが「覚り」を得てブッダとなり、仏教を開いた。著者は「覚り」という言葉を使わず、一貫して「目覚めた人」ブッダと表現している。
ブッダは人々に乞われて「目覚めた人」になる方策を語る。その教えは数世紀にわたって口承で伝えられ、初めて文字になったのはブッダから約500年後の紀元前後のパーリ語の記録である。その後、サンスクリット語で記されるようになる。経典の原文はサンスクリット語と思っていたが、それ以前にパーリ語があったとは知らなかった。
著者は、ブッダ自身のことばに可能な限り近づくため、主にパーリ語のテキストに基づいて本書を著している。著者が長年研究してきたチベット・ブータン仏教も著者の見解に反映されていて「多分に個人的な「仏教」理解です」とことわっている。
本書が紹介するブッダの教えは難解な哲学ではなく、自己啓発セミナーの指南のようだ。わかりやすいが、容易に実践できるわけではない。ブッダに関する次の指摘が意外だった。
「ブッダは経験論者で、生涯を通じてすべて自分で経験したことだけを話す人であり、思弁的、形而上学的なことがらはいっさい問題にしませんでした。」
ブッダは徹底した合理主義者でプラグマティックな考え方をしたとも述べている。その教えを簡単にまとめることはできないが、ある種の精神修養を説いている感じだ。
仏教において「目覚めた人」になる(さとりをひらく)のは至難だとのイメージがある。だが、ブッダが生きた時代には、多くの弟子たちが「目覚めた人」になったそうだ。後世になって、「目覚めた人」になるのはとっても困難と見なされるようになったらしい。ありそうな話だ。
著者は、ニーチェやアインシュタインの次のような言葉も紹介している。
「仏教は、歴史が我々に提示してくれる、唯一の真に実証科学的宗教である(ニーチェ)」
「仏教は、近代科学と両立可能な唯一の宗教である(アインシュタイン)」
私は宗教にさほどの関心はないが、仏教に期待してもいいのかな、と思わせる本である。
やはり、アタテュルクは興味深い人物だ ― 2023年11月12日
私がトルコ観光をしたのは15年前だ。街のいたる所で建国の父アタテュルクの肖像や彫像に接し、アタテュルク像のマグネットを何種類か買った。それはわが家の冷蔵庫に貼ってあり、ほぼ毎日目に入る。だから、旧い知り合いのような気がする。
書店の新刊コーナーで次の新書を見たとき、いつも肖像を見ているアタテュルクの事績について高校世界史程度の知識しかないと思い至り、躊躇なく購入した。
『ケマル・アタテュルク:オスマン帝国の英傑、トルコ建国の父』(小笠原弘幸/中公新書/2023.10)
購入後、2年前に読んだ『オスマン帝国』(中公新書)と同じ著者だと気づいた。あの本の終盤と本書の序盤がつながっていて、オスマン帝国終焉の様子をあらためて確認できた。
トルコ革命を主導、トルコ共和国初代大統領になったアタテュルクは英雄・偉人のイメージが強い。本書は、そんなアタテュルクの実像に近い姿を描いていて、とても面白い。強烈なカリスマ創業社長の一代記のようだ。カリスマとは周辺の人々にとって、やっかいな存在である。振り回される側の苦労は絶えない。
本書に食指が動いた理由のひとつは、先日読んだ『イスラム飲酒紀行』だ。あの本の著者はアタテュルクを「世界史上でも稀に見る活動的なアル中独裁者」と書いていた。その真偽を確かめればと思った。本書にアタテュルクの飲酒に関する記述は多いが、アル中とは書いてない。大統領になった晩年、来客や側近と朝までラク(ブドウの蒸留酒)を飲みながら議論・歓談を続け、早朝に就寝、執務は午後からだったそうだ。
アタテュルク(父なるトルコ人)という姓は晩年に議会から贈られたもので、出生時の名はムスタファ、あだ名がケマル(完璧な)、長くムスタファ・ケマルと呼ばれた。優秀で勉強熱心な軍人だった。トルコ革命は彼ひとりの事業ではなく、多くのライバルや同僚がいた。離反した支持者も少なくない。だが、権力闘争に勝ち残って指導者となる。本書で、その過程を初めて知った。かなりゴチャゴチャしている。
彼が勝ち残った理由はいろいろあるが、明確な理念をもっていたことが一番だと思われる。それは政教分離の世俗主義、近代化という理念である。トルコ民族主義という理念も大きい。
本書の終章「アタテュルクの遺産」では、2023年(今年だ)のエルドアン大統領再選にまで言及している。エルドアンは、アタテュルクが博物館に転用した聖ソフィア大聖堂を元のモスクに戻した。著者は次の文章で本書を締めくくっている。
「アタテュルクが描いたトルコ共和国の理念が、いま大きく変容しつつあるのは明らかである。建国して2世紀目に踏み出そうとしているトルコにおいて、アタテュルクの遺産は、どのように受け継がれてゆくのだろうか。」
書店の新刊コーナーで次の新書を見たとき、いつも肖像を見ているアタテュルクの事績について高校世界史程度の知識しかないと思い至り、躊躇なく購入した。
『ケマル・アタテュルク:オスマン帝国の英傑、トルコ建国の父』(小笠原弘幸/中公新書/2023.10)
購入後、2年前に読んだ『オスマン帝国』(中公新書)と同じ著者だと気づいた。あの本の終盤と本書の序盤がつながっていて、オスマン帝国終焉の様子をあらためて確認できた。
トルコ革命を主導、トルコ共和国初代大統領になったアタテュルクは英雄・偉人のイメージが強い。本書は、そんなアタテュルクの実像に近い姿を描いていて、とても面白い。強烈なカリスマ創業社長の一代記のようだ。カリスマとは周辺の人々にとって、やっかいな存在である。振り回される側の苦労は絶えない。
本書に食指が動いた理由のひとつは、先日読んだ『イスラム飲酒紀行』だ。あの本の著者はアタテュルクを「世界史上でも稀に見る活動的なアル中独裁者」と書いていた。その真偽を確かめればと思った。本書にアタテュルクの飲酒に関する記述は多いが、アル中とは書いてない。大統領になった晩年、来客や側近と朝までラク(ブドウの蒸留酒)を飲みながら議論・歓談を続け、早朝に就寝、執務は午後からだったそうだ。
アタテュルク(父なるトルコ人)という姓は晩年に議会から贈られたもので、出生時の名はムスタファ、あだ名がケマル(完璧な)、長くムスタファ・ケマルと呼ばれた。優秀で勉強熱心な軍人だった。トルコ革命は彼ひとりの事業ではなく、多くのライバルや同僚がいた。離反した支持者も少なくない。だが、権力闘争に勝ち残って指導者となる。本書で、その過程を初めて知った。かなりゴチャゴチャしている。
彼が勝ち残った理由はいろいろあるが、明確な理念をもっていたことが一番だと思われる。それは政教分離の世俗主義、近代化という理念である。トルコ民族主義という理念も大きい。
本書の終章「アタテュルクの遺産」では、2023年(今年だ)のエルドアン大統領再選にまで言及している。エルドアンは、アタテュルクが博物館に転用した聖ソフィア大聖堂を元のモスクに戻した。著者は次の文章で本書を締めくくっている。
「アタテュルクが描いたトルコ共和国の理念が、いま大きく変容しつつあるのは明らかである。建国して2世紀目に踏み出そうとしているトルコにおいて、アタテュルクの遺産は、どのように受け継がれてゆくのだろうか。」
台湾現代史の変動に翻弄される人生の記録 ― 2023年10月08日
『台湾の少年(1)(2)(3)(4)』(游珮芸、周見信/倉本知明訳/岩波書店)
台湾マンガである。昨年7月から今年1月にかけて翻訳版が刊行された。蔡焜霖という実在の人物の一代記に台湾現代史を反映させた大河マンガだ。読み応えがある。
蔡焜霖は1930年、日本統治下の台湾台中で生まれ、読書好きの青年となる。蒋介石政権の恐怖政治時代の1950年、20歳の時に無実の罪で逮捕され、離島の収容所で10年の刑期を過ごす。その後、紆余曲折や浮沈はあるものの、児童書出版や広告の世界で活躍し、現在は白色テロ時代の政治犯の名誉回復活動や人権教育に携わっている――そんな人の一代記マンガである。
全4巻の各巻のサブタイトルは「1 統治時代生まれ」「2 収容所島の十年」「3 戒厳令下の編集者」「4 民主化の時代へ」となっている。
私が台湾に関心を抱いたのは6年前だ。『台湾:四百年の歴史と展望』、『台湾とは何か』、『台湾海峡一九四九』をはじめ何冊かの関連書を読み、4泊の観光旅行にも行った。
複雑で波瀾に満ちた台湾現代史の概要をある程度は把握しているつもりだった。だが、本書を読むまで、蒋介石政権下の白色テロの苛烈な実態に思いを寄せることはなかった。火焼島の収容所も知らなかった。高校の読書会に参加しただけで懲役10年、少し逆らえばすぐに銃殺、軍や警察の方針は「百人を誤殺しても一人の犯人逃すな」だったという。毛沢東思想浸透への強い怖れがあったにしても、ひどい話だ。
最終巻は民主化の時代であり、主人公が晩年を迎えてのハッピーエンドという雰囲気も漂う。だが、現実の世界はそう言い切れないのが悲しい。台湾の未来は不透明だ。
主人公の以下の述懐が印象に残った。
「1989年に天安門事件が起こるまで、ぼくは中国が台湾よりも開放的な国だと思っていたんです。」「大切なのは革命そのものではなく、平和裏に行われる改革なんです。それは会社も国家も同じで、それこそが正しい道なんです。」
台湾マンガである。昨年7月から今年1月にかけて翻訳版が刊行された。蔡焜霖という実在の人物の一代記に台湾現代史を反映させた大河マンガだ。読み応えがある。
蔡焜霖は1930年、日本統治下の台湾台中で生まれ、読書好きの青年となる。蒋介石政権の恐怖政治時代の1950年、20歳の時に無実の罪で逮捕され、離島の収容所で10年の刑期を過ごす。その後、紆余曲折や浮沈はあるものの、児童書出版や広告の世界で活躍し、現在は白色テロ時代の政治犯の名誉回復活動や人権教育に携わっている――そんな人の一代記マンガである。
全4巻の各巻のサブタイトルは「1 統治時代生まれ」「2 収容所島の十年」「3 戒厳令下の編集者」「4 民主化の時代へ」となっている。
私が台湾に関心を抱いたのは6年前だ。『台湾:四百年の歴史と展望』、『台湾とは何か』、『台湾海峡一九四九』をはじめ何冊かの関連書を読み、4泊の観光旅行にも行った。
複雑で波瀾に満ちた台湾現代史の概要をある程度は把握しているつもりだった。だが、本書を読むまで、蒋介石政権下の白色テロの苛烈な実態に思いを寄せることはなかった。火焼島の収容所も知らなかった。高校の読書会に参加しただけで懲役10年、少し逆らえばすぐに銃殺、軍や警察の方針は「百人を誤殺しても一人の犯人逃すな」だったという。毛沢東思想浸透への強い怖れがあったにしても、ひどい話だ。
最終巻は民主化の時代であり、主人公が晩年を迎えてのハッピーエンドという雰囲気も漂う。だが、現実の世界はそう言い切れないのが悲しい。台湾の未来は不透明だ。
主人公の以下の述懐が印象に残った。
「1989年に天安門事件が起こるまで、ぼくは中国が台湾よりも開放的な国だと思っていたんです。」「大切なのは革命そのものではなく、平和裏に行われる改革なんです。それは会社も国家も同じで、それこそが正しい道なんです。」
ソグド人と吉備真備が活躍する歴史小説『ふりさけ見れば』 ― 2023年08月06日
『ふりさけ見れば(上)(下)』(安部龍太郎/日本経済新聞出版)
日経新聞連載中(2021年7月~2023年2月)から注目していた歴史小説である。連載を読みながら、単行本になったらじっくり読みかえそうと思っていた。この小説に注目した理由は以下の通りだ。
(1) ソグド人が活躍する。ソグド人は5年程前から私の関心事項。
(2) 吉備真備が活躍する。吉備真備は3年程前から私の関心事項。
(3) 私にとっては新しい歴史知識が盛り込まれている。
タイトルが示すとおり阿部仲麻呂を描いた歴史小説である。遣唐使留学生として唐に渡り、帰国を果たせなかった人物だ。仲麻呂と同時に入唐した吉備真備も活躍する。単行本で一気に読み返すと真備の印象が強い。仲麻呂と真備、二人が主人公の歴史小説と言える。
物語は、二人が唐で18年の年月を過ごした時点に始まる。遣唐使船が来航し、真備は帰国の途につくが仲麻呂は唐に残る。その後、紆余曲折を経て二人が生涯を終えるまでの約半世紀を描いている(仲麻呂は770年に70歳で死去、真備は775年に80歳で死去)。史実をベースにした大いなるフィクションである。やや不自然に感じる展開もあるが、ラストでは往時茫々の感慨がわいた。
私にとっては、ストーリーよりもディティールを楽しむ小説だった。多くのソグド人がさまざまな立場で活躍するのが面白い。最近の高校世界史の教科書にはソグド人が登場するそうだが、私がソグド人を知ったのは数年前だ。『シルクロードと唐帝国』や『ソグド商人の歴史』などを読んで関心が高まった。ソグド人に関する一般向け概説書が出版されないかと期待している。この歴史小説が呼び水になればいいのだが。
ソグド人への関心から松本清張の『眩人』を読み、吉備真備への興味がわいた。『吉備真備』や『吉備真備の世界』によって、一応の伝記的事柄を知った。残された史料が少なく、詳細がわからない人物である。フィクションの世界では『天平の甍』や『火の鳥』でイヤミなインテリに描かれている。テレビドラマ『大仏開眼』は真備をかなり美化していた。
『ふりさけ見れば』の真備は、真面目な秀才・仲麻呂と対称的な世故に長けた出世主義の俗物に描かれている。だが、しだいに行動的な辣腕家と理念型政治家をミックスした魅力的な人物になっていく。好感がもてた。
吉備真備は詩歌をものせず、文章なども残っていない。ところが2019年12月、真備の書とされる墓誌が中国で発見されてニュースになった。『ふりさけ見れば』は、この墓誌に関する経緯もしっかり書き込んでいる。また、2004年になって新たに存在が確認された遣唐使留学生・井真成も登場する。まさに、21世紀の歴史小説である。
日経新聞連載中(2021年7月~2023年2月)から注目していた歴史小説である。連載を読みながら、単行本になったらじっくり読みかえそうと思っていた。この小説に注目した理由は以下の通りだ。
(1) ソグド人が活躍する。ソグド人は5年程前から私の関心事項。
(2) 吉備真備が活躍する。吉備真備は3年程前から私の関心事項。
(3) 私にとっては新しい歴史知識が盛り込まれている。
タイトルが示すとおり阿部仲麻呂を描いた歴史小説である。遣唐使留学生として唐に渡り、帰国を果たせなかった人物だ。仲麻呂と同時に入唐した吉備真備も活躍する。単行本で一気に読み返すと真備の印象が強い。仲麻呂と真備、二人が主人公の歴史小説と言える。
物語は、二人が唐で18年の年月を過ごした時点に始まる。遣唐使船が来航し、真備は帰国の途につくが仲麻呂は唐に残る。その後、紆余曲折を経て二人が生涯を終えるまでの約半世紀を描いている(仲麻呂は770年に70歳で死去、真備は775年に80歳で死去)。史実をベースにした大いなるフィクションである。やや不自然に感じる展開もあるが、ラストでは往時茫々の感慨がわいた。
私にとっては、ストーリーよりもディティールを楽しむ小説だった。多くのソグド人がさまざまな立場で活躍するのが面白い。最近の高校世界史の教科書にはソグド人が登場するそうだが、私がソグド人を知ったのは数年前だ。『シルクロードと唐帝国』や『ソグド商人の歴史』などを読んで関心が高まった。ソグド人に関する一般向け概説書が出版されないかと期待している。この歴史小説が呼び水になればいいのだが。
ソグド人への関心から松本清張の『眩人』を読み、吉備真備への興味がわいた。『吉備真備』や『吉備真備の世界』によって、一応の伝記的事柄を知った。残された史料が少なく、詳細がわからない人物である。フィクションの世界では『天平の甍』や『火の鳥』でイヤミなインテリに描かれている。テレビドラマ『大仏開眼』は真備をかなり美化していた。
『ふりさけ見れば』の真備は、真面目な秀才・仲麻呂と対称的な世故に長けた出世主義の俗物に描かれている。だが、しだいに行動的な辣腕家と理念型政治家をミックスした魅力的な人物になっていく。好感がもてた。
吉備真備は詩歌をものせず、文章なども残っていない。ところが2019年12月、真備の書とされる墓誌が中国で発見されてニュースになった。『ふりさけ見れば』は、この墓誌に関する経緯もしっかり書き込んでいる。また、2004年になって新たに存在が確認された遣唐使留学生・井真成も登場する。まさに、21世紀の歴史小説である。
森村誠一は『忠臣蔵』と『新選組』を書いた国民作家 ― 2023年07月31日
森村誠一が先週(2023/7/24)、90歳で亡くなった。『高層の死角』や『人間の証明』をはじめ、都会的でテンポのいいミステリーは面白かった。『悪魔の飽食』シリーズは衝撃的だった。私には「忠臣蔵と新選組の両方を書いた作家」の印象が強い。
私は忠臣蔵にハマッた時期があり、新選組にハマッた時期もある。自分では忠臣蔵ファンであり、新選組ファンだと思っている。この二つは史実とフィクションが織りなす虚実の世界が面白い。
忠臣蔵や新選組を題材にした小説は数え切れない。私はそのほんの一部を読んだだけだが、この両方ともを長編で描いた作家が少ないのを意外に感じている。見落としもあるだろうが、吉川英治は忠臣蔵だけ、司馬遼太郎は新選組だけだ。
森村誠一は両方を書いている。どちらも週刊朝日連載の長編である(『忠臣蔵』は1984.6.8~1985.5.31、『新選組』は1989.10.6~1990.8.31)。
忠臣蔵と新選組は日本人の琴線に触れる双璧であり、多くの人にとってポピュラーな存在である。この2作品を残した故に、森村誠一は国民作家と呼べる――そう思った。
この「国民作家」の訃報に接したとき、大多数の人々と同様に忠臣蔵と新選組が好きな私は、つくづく自分が平均的日本人だと悟った。
私は忠臣蔵にハマッた時期があり、新選組にハマッた時期もある。自分では忠臣蔵ファンであり、新選組ファンだと思っている。この二つは史実とフィクションが織りなす虚実の世界が面白い。
忠臣蔵や新選組を題材にした小説は数え切れない。私はそのほんの一部を読んだだけだが、この両方ともを長編で描いた作家が少ないのを意外に感じている。見落としもあるだろうが、吉川英治は忠臣蔵だけ、司馬遼太郎は新選組だけだ。
森村誠一は両方を書いている。どちらも週刊朝日連載の長編である(『忠臣蔵』は1984.6.8~1985.5.31、『新選組』は1989.10.6~1990.8.31)。
忠臣蔵と新選組は日本人の琴線に触れる双璧であり、多くの人にとってポピュラーな存在である。この2作品を残した故に、森村誠一は国民作家と呼べる――そう思った。
この「国民作家」の訃報に接したとき、大多数の人々と同様に忠臣蔵と新選組が好きな私は、つくづく自分が平均的日本人だと悟った。


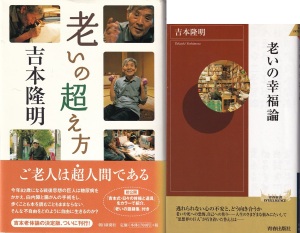


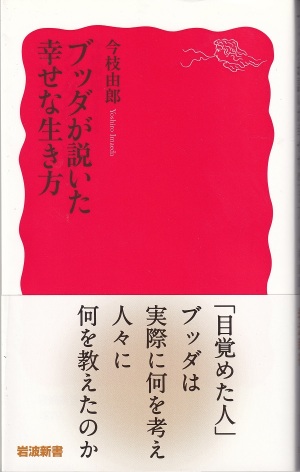
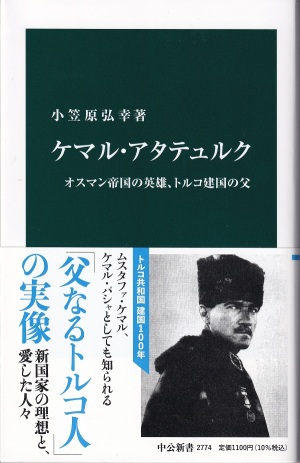

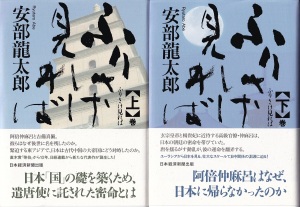

最近のコメント