『ヨーロッパ史』は、やや抽象的な歴史エッセイ ― 2024年03月31日
『ヨーロッパ史:拡大と統合の力学』(大月康弘/岩波新書)
朝日新聞(2024.3.23)の書評で、ビザンツ史の専門家が書いた本書を「西欧中心の歴史観に異議を唱える」と紹介していた。それを読んで、すぐに購入した。
私は一昨年からビザンツ史の本を何冊か読み、よく知らなかったこの「帝国」の面白さに魅せられている。また、西欧中心歴史観の見直しは、高齢の私が歴史書を読む際のテーマの一つだ。だから、大きな期待を抱いて本書を読み始めた。だが、思った以上の難物だった。
本書は「ヨーロッパ史とは何か」というやや抽象的な課題を論じていて、キー概念は「キリスト教ローマ帝国」である。ビザンツ帝国が自らを「ローマ帝国」と自認していたことをベースに、古代末期から中世・近代・現代に至るヨーロッパを支えてきた観念を「キリスト教ローマ帝国」という捉え方で論じている。
「時代精神」「キリスト教的時間意識」「終末意識」などの抽象概念や「当為」といった哲学用語が多く、すらすらとは読めない。私の知らない歴史研究者たちの言説紹介も多い。かなり専門的でやや難解な歴史エッセイである。断片的には面白い話も多いが全体像をつかみ難い。いずれ、覚悟して再読すれば理解が深まるかもしれない。
本書が描くヨーロッパの原点は「キリスト教ローマ帝国」としてのビザンツ帝国であり、それとフランク王国の登場やアラブ・イスラムの侵入が絡んで「キリスト教ローマ帝国」たるヨーロッパ史が始まるというストーリーになっている。
著者は「おわりに」で次のように述べている。
「ヨーロッパといえば、イギリス、フランス、ドイツと三つの国を挙げる人は多い。これにイタリアを加え、あるいはスペインを含めたいと思うことだろう。私であれば、すでに第3章で述べたように、東欧、ギリシア、トルコ、またキプロスなども当然ながらキリスト教世界としての基層を共有する「ヨーロッパ」だ、としたいところである。」
1453年、コンスタンティノープルを陥したオスマン帝国のメフメト2世は、帝都侵入後「ルーム・カエサル」と称したそうだ。本書でそれを知って驚いた。
朝日新聞(2024.3.23)の書評で、ビザンツ史の専門家が書いた本書を「西欧中心の歴史観に異議を唱える」と紹介していた。それを読んで、すぐに購入した。
私は一昨年からビザンツ史の本を何冊か読み、よく知らなかったこの「帝国」の面白さに魅せられている。また、西欧中心歴史観の見直しは、高齢の私が歴史書を読む際のテーマの一つだ。だから、大きな期待を抱いて本書を読み始めた。だが、思った以上の難物だった。
本書は「ヨーロッパ史とは何か」というやや抽象的な課題を論じていて、キー概念は「キリスト教ローマ帝国」である。ビザンツ帝国が自らを「ローマ帝国」と自認していたことをベースに、古代末期から中世・近代・現代に至るヨーロッパを支えてきた観念を「キリスト教ローマ帝国」という捉え方で論じている。
「時代精神」「キリスト教的時間意識」「終末意識」などの抽象概念や「当為」といった哲学用語が多く、すらすらとは読めない。私の知らない歴史研究者たちの言説紹介も多い。かなり専門的でやや難解な歴史エッセイである。断片的には面白い話も多いが全体像をつかみ難い。いずれ、覚悟して再読すれば理解が深まるかもしれない。
本書が描くヨーロッパの原点は「キリスト教ローマ帝国」としてのビザンツ帝国であり、それとフランク王国の登場やアラブ・イスラムの侵入が絡んで「キリスト教ローマ帝国」たるヨーロッパ史が始まるというストーリーになっている。
著者は「おわりに」で次のように述べている。
「ヨーロッパといえば、イギリス、フランス、ドイツと三つの国を挙げる人は多い。これにイタリアを加え、あるいはスペインを含めたいと思うことだろう。私であれば、すでに第3章で述べたように、東欧、ギリシア、トルコ、またキプロスなども当然ながらキリスト教世界としての基層を共有する「ヨーロッパ」だ、としたいところである。」
1453年、コンスタンティノープルを陥したオスマン帝国のメフメト2世は、帝都侵入後「ルーム・カエサル」と称したそうだ。本書でそれを知って驚いた。
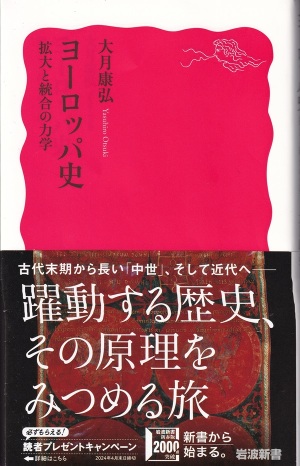
最近のコメント