2024下半期に読んだ本のマイ・ベスト3 ― 2025年01月03日
2024年下半期に読んだ本のマイ・ベスト3を選んだ。
『安部公房:消しゴムで書く』(鳥羽耕史/ミネルヴァ書房)
『ノルマン騎士の地中海興亡史』(山辺規子/白水Uブックス)
『日本に古代はあったのか』(井上章一/角川選書)
2024年は安部公房生誕100年だった。『安部公房:消しゴムで書く』は生誕100年の年に刊行された秀逸な評伝だった。他の2冊はかなり以前に出た本だが、最近の私の関心に合致した。
『安部公房:消しゴムで書く』(鳥羽耕史/ミネルヴァ書房)
『ノルマン騎士の地中海興亡史』(山辺規子/白水Uブックス)
『日本に古代はあったのか』(井上章一/角川選書)
2024年は安部公房生誕100年だった。『安部公房:消しゴムで書く』は生誕100年の年に刊行された秀逸な評伝だった。他の2冊はかなり以前に出た本だが、最近の私の関心に合致した。
2024年に読んだ本のマイ・ベスト3 ― 2025年01月03日
昨年読んだ本の前半ベスト3と後半ベスト3の計6点から、2024年に読んだ本のベスト3を選んだ。前半・後半に分けるのは、わが記憶力の射程が6カ月程度だからである。ということは、過去1年を振り返ったとしても6カ月以上彼方は曖昧なので、年間通しての評価はナンセンスかもしれないが、◎を付した赤字が年間ベスト3である。
◎『ダーウィンの呪い』(千葉聡/講談社現代新書)
『十二世紀ルネサンス』(伊東俊太郎/講談社学術文庫)
『封建制の文明史観:近代化をもたらした歴史の遺産』(今谷明/PHP新書)
◎『安部公房:消しゴムで書く』(鳥羽耕史/ミネルヴァ書房)
『ノルマン騎士の地中海興亡史』(山辺規子/白水Uブックス)
◎『日本に古代はあったのか』(井上章一/角川選書)
《過去のベスト3》
2020年に読んだ本のベスト3
2021年に読んだ本のベスト3
2022年に読んだ本のベスト3
2023年に読んだ本のベスト3
◎『ダーウィンの呪い』(千葉聡/講談社現代新書)
『十二世紀ルネサンス』(伊東俊太郎/講談社学術文庫)
『封建制の文明史観:近代化をもたらした歴史の遺産』(今谷明/PHP新書)
◎『安部公房:消しゴムで書く』(鳥羽耕史/ミネルヴァ書房)
『ノルマン騎士の地中海興亡史』(山辺規子/白水Uブックス)
◎『日本に古代はあったのか』(井上章一/角川選書)
《過去のベスト3》
2020年に読んだ本のベスト3
2021年に読んだ本のベスト3
2022年に読んだ本のベスト3
2023年に読んだ本のベスト3
『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル』は記述が細かい ― 2025年01月06日
1カ月以上前に読み始めた次の本を、年明けになってやっと読み終えた。
『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル(上)(下)』(船橋洋一/文藝春秋)
著者は本書を「調査報道であり、ノンフィクションである」と述べている。第2次安倍政権(2012年12月~2020年9月)の思考と行動を、おびただしい人数の関係者へのインタビューをベースに描いている。安倍晋三本人にも、退陣後2年弱のあいだに19回インタビューしたそうだ。労作である。
安倍晋三に関しては、以前に『安倍三代』(青木理)や『安倍晋三の正体』(適菜収)などを読んだ。いずれも安倍晋三に批判的な内容であり、私はこれらの著作に共感している。安倍政権を評価する気にはなれない。
にもかかわらず本書を読もうと思ったのは、著者が元・朝日新聞社主筆の船橋洋一氏だからである。船橋氏の著作は以前にいくつか読んだことがある。安倍政権に批判的だった朝日新聞の元・主筆が安倍政権をどのように描いているのかに興味がわいたのだ。
上下巻で約1200頁の本書は、「アベノミクス」「戦後70年首相談話」「プーチン」「トランプ」など約20のテーマごとに、政権中枢がどんな動きをしてきたかを細かく描いている。細かい話になると頭がついて行くのが難しくなり、読むのに時間を要した。何とか読了できたのは、やはり面白いからである。「へぇー」と感じる興味深い話がいろいろ出てくる。
本書は関係者の証言に基づいた事実を坦々と描写しているが、取材対象の多くは政権に関わった人物である。だから功罪の「罪」よりは「功」にウエイトがかかり、全体としては安倍政権をかなり評価している印象を受ける。
最終章の「戦後終章」は著者による安倍政権総括である。著者は次のように述べている。
「この政権は、国のあるべき構想を明確にし、そのための政治課題を設定し、それを能動的に遂行しようとするきわめて理念的かつ行動的な政治において際立っていた。」
「安倍時代、日本の政治は欧米民主国家の多くで起こったような「極端な党派性のポピュリスト的罠」に嵌ることはなかった。」
「この政権は、第1次政権の失敗の歴史からよく学んだ。その本質は、このリアリズムの政治のありようということだったかもしれない。そして、それが憲政史上最長の政権をつくった最大の秘訣だっただろう。」
船橋氏が描出した安倍晋三は、信念と使命を追究しつつも柔軟性をもったリアリズムの政治家である。青木理氏は『安倍三代』で安倍晋三を「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」としていた。適菜収氏は『安倍晋三回顧録』から見えるものは「安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ」と書いていた。これら批判的な安部晋三像と船橋氏が本書で描いた安倍晋三像は矛盾するだろうか。私は、必ずしも矛盾しないと思う。
本書のタイトル「宿命の子」は安倍晋三の母親・洋子(岸信介の娘。安倍晋太郎の妻)が息子について語った言葉である。岸信介の孫、安倍晋太郎の息子として生まれた凡庸で空疎なオボッチャマが、後天的に無理やりに「信念」や「使命」を自身に注入した――それが「宿命の子」だと思える。元が空疎だから可塑性はある。育ちのよさには、先天的な人たらしの魅力(愛嬌)があったのかもしれない。言葉が軽く、饒舌で、雑談の名手だったそうだ。
コロナ禍の頃に関する次の記述が印象に残った。
「萩生田は、コロナ危機の中で、安倍の体力と気力の弱まりを感じた。海外にも行けない。ゴルフもできない。みんなでワイワワイガヤガヤできない。」
外交やゴルフ、ワイワイガヤガヤが政権維持の気力の源泉だとすると、人間味を感じる。
『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル(上)(下)』(船橋洋一/文藝春秋)
著者は本書を「調査報道であり、ノンフィクションである」と述べている。第2次安倍政権(2012年12月~2020年9月)の思考と行動を、おびただしい人数の関係者へのインタビューをベースに描いている。安倍晋三本人にも、退陣後2年弱のあいだに19回インタビューしたそうだ。労作である。
安倍晋三に関しては、以前に『安倍三代』(青木理)や『安倍晋三の正体』(適菜収)などを読んだ。いずれも安倍晋三に批判的な内容であり、私はこれらの著作に共感している。安倍政権を評価する気にはなれない。
にもかかわらず本書を読もうと思ったのは、著者が元・朝日新聞社主筆の船橋洋一氏だからである。船橋氏の著作は以前にいくつか読んだことがある。安倍政権に批判的だった朝日新聞の元・主筆が安倍政権をどのように描いているのかに興味がわいたのだ。
上下巻で約1200頁の本書は、「アベノミクス」「戦後70年首相談話」「プーチン」「トランプ」など約20のテーマごとに、政権中枢がどんな動きをしてきたかを細かく描いている。細かい話になると頭がついて行くのが難しくなり、読むのに時間を要した。何とか読了できたのは、やはり面白いからである。「へぇー」と感じる興味深い話がいろいろ出てくる。
本書は関係者の証言に基づいた事実を坦々と描写しているが、取材対象の多くは政権に関わった人物である。だから功罪の「罪」よりは「功」にウエイトがかかり、全体としては安倍政権をかなり評価している印象を受ける。
最終章の「戦後終章」は著者による安倍政権総括である。著者は次のように述べている。
「この政権は、国のあるべき構想を明確にし、そのための政治課題を設定し、それを能動的に遂行しようとするきわめて理念的かつ行動的な政治において際立っていた。」
「安倍時代、日本の政治は欧米民主国家の多くで起こったような「極端な党派性のポピュリスト的罠」に嵌ることはなかった。」
「この政権は、第1次政権の失敗の歴史からよく学んだ。その本質は、このリアリズムの政治のありようということだったかもしれない。そして、それが憲政史上最長の政権をつくった最大の秘訣だっただろう。」
船橋氏が描出した安倍晋三は、信念と使命を追究しつつも柔軟性をもったリアリズムの政治家である。青木理氏は『安倍三代』で安倍晋三を「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」としていた。適菜収氏は『安倍晋三回顧録』から見えるものは「安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ」と書いていた。これら批判的な安部晋三像と船橋氏が本書で描いた安倍晋三像は矛盾するだろうか。私は、必ずしも矛盾しないと思う。
本書のタイトル「宿命の子」は安倍晋三の母親・洋子(岸信介の娘。安倍晋太郎の妻)が息子について語った言葉である。岸信介の孫、安倍晋太郎の息子として生まれた凡庸で空疎なオボッチャマが、後天的に無理やりに「信念」や「使命」を自身に注入した――それが「宿命の子」だと思える。元が空疎だから可塑性はある。育ちのよさには、先天的な人たらしの魅力(愛嬌)があったのかもしれない。言葉が軽く、饒舌で、雑談の名手だったそうだ。
コロナ禍の頃に関する次の記述が印象に残った。
「萩生田は、コロナ危機の中で、安倍の体力と気力の弱まりを感じた。海外にも行けない。ゴルフもできない。みんなでワイワワイガヤガヤできない。」
外交やゴルフ、ワイワイガヤガヤが政権維持の気力の源泉だとすると、人間味を感じる。
済州島四・三事件を題材にした『別れを告げない』は幻想譚 ― 2025年01月09日
ハン・ガン(2024年ノーベル文学賞)の『菜食主義者』、『少年が来る』に続いて次の長編を読んだ。
『別れを告げない』(ハン・ガン/斎藤真理子訳/白水社)
先月読んだ『少年が来る』は光州事件を題材にしていた。2021年に発表した本書は、済州島四・三事件を扱っている。私には未知の事件なので、事前にネットで検索し、この虐殺事件のあらましを調べた。
済州島四・三事件とは、李承晩政権下の1948年4月3日に済州島で起こった島民蜂起をきっかけに発生した一連の島民虐殺事件である。犠牲者数は1万数千人から8万人まで諸説あり、済州島の村々の70%が焼き尽くされたそうだ。恐怖から多くの住民の島外へ脱出し、島の人口は約28万から一時は3万人弱にまで激減したという。
本書巻末の「訳者あとがき」にも、かなり詳細な事件の解説が載っている。それによれば、この事件は「大韓民国の建国を妨害しようとした共産暴動」とされ、多数の無実の民間人が国家公権力によって虐殺された事実は隠ぺいされた。沈黙を強いられた虐殺事件となったのだ。
この小説は済州島四・三事件をストレートに描いているわけではない。設定は現代であり、この事件を体験した世代の娘が、父や母の体験を追憶する話である。この娘は私の友人である。私は作家である。K事件(光州事件だろう)の本を書いて精神的に疲弊している。友人は元・映像作家で、現在は済州島に工房をもつ家具職人になっている。著者を連想させる私と友人の奇妙な絡みで物語が進行する。
かなりニューロティックで、ぞくぞくする話である。幻想的でもある。途中から私と友人が生きている人物なのか霊魂なのか定かでなくなってくる。こんな形の小説になっているのは、「追憶」という行為の難儀を表しているのかもしれない。
『別れを告げない』というタイトルも不思議である。小説のなかには次のような会話がある。
「別れの挨拶をしないだけ? 本当に別れないという意味?」
「完成しないということかな、別れが?」
追憶や追悼に終わりはない、ということのようだ。
『別れを告げない』(ハン・ガン/斎藤真理子訳/白水社)
先月読んだ『少年が来る』は光州事件を題材にしていた。2021年に発表した本書は、済州島四・三事件を扱っている。私には未知の事件なので、事前にネットで検索し、この虐殺事件のあらましを調べた。
済州島四・三事件とは、李承晩政権下の1948年4月3日に済州島で起こった島民蜂起をきっかけに発生した一連の島民虐殺事件である。犠牲者数は1万数千人から8万人まで諸説あり、済州島の村々の70%が焼き尽くされたそうだ。恐怖から多くの住民の島外へ脱出し、島の人口は約28万から一時は3万人弱にまで激減したという。
本書巻末の「訳者あとがき」にも、かなり詳細な事件の解説が載っている。それによれば、この事件は「大韓民国の建国を妨害しようとした共産暴動」とされ、多数の無実の民間人が国家公権力によって虐殺された事実は隠ぺいされた。沈黙を強いられた虐殺事件となったのだ。
この小説は済州島四・三事件をストレートに描いているわけではない。設定は現代であり、この事件を体験した世代の娘が、父や母の体験を追憶する話である。この娘は私の友人である。私は作家である。K事件(光州事件だろう)の本を書いて精神的に疲弊している。友人は元・映像作家で、現在は済州島に工房をもつ家具職人になっている。著者を連想させる私と友人の奇妙な絡みで物語が進行する。
かなりニューロティックで、ぞくぞくする話である。幻想的でもある。途中から私と友人が生きている人物なのか霊魂なのか定かでなくなってくる。こんな形の小説になっているのは、「追憶」という行為の難儀を表しているのかもしれない。
『別れを告げない』というタイトルも不思議である。小説のなかには次のような会話がある。
「別れの挨拶をしないだけ? 本当に別れないという意味?」
「完成しないということかな、別れが?」
追憶や追悼に終わりはない、ということのようだ。
『シニア右翼』を読んでネットの歴史をふりかえった ― 2025年01月11日
約2年前に出た次の新書をネット書店で購入して読んだ。
『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)
2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。
著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。
最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。
著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。
本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。
著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。ここで言う「彼ら」の世代は、著者の親にあたる私たちベビーブーマーになるようだ。
後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私はギクリとさせられる。近現代史は常に目前の課題である。
前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。
『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)
2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。
著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。
最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。
著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。
本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。
著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。ここで言う「彼ら」の世代は、著者の親にあたる私たちベビーブーマーになるようだ。
後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私はギクリとさせられる。近現代史は常に目前の課題である。
前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。
70歳になった渡辺えりの芝居2本を連続観劇 ― 2025年01月14日
本多劇場で上演中の「渡辺えり古稀記念2作連続公演」を観た。『りぼん』と『鯨よ!私の手に乗れ』の2作を、ほぼ交互に上演している。2作とも作・演出は渡辺えり。役者の大半は重複している。
『りぼん』は上演時間3時間(休憩15分を含む)、『鯨よ!私の手に乗れ』は上演時間2時間(休憩なし)である。昼と夜の公演を続けて観れば1日での観劇も可能だが、私は2日にわけて観た。
この芝居の登場人物は43人である。全員が舞台に立つ集団シーンもある。出演者が多いので役者名を挙げるのは省略する(チラシの周囲に載っている)。
『りぼん』の初演は2003年、『鯨よ!私の手に乗れ』の初演は2017年である。私は今回の公演が初見である。私が渡辺えり作の芝居を観たのは2022年上演の『私の恋人 beyond』が最初である。
2つの戯曲はいずれも「戯曲デジタルアーカイブ」で読むことができる。観劇前に読もうと思ったがはたせず、冒頭部分を読んだだけで劇場に足を運んだ。
『りぼん』の冒頭、大勢の修学旅行の中学生が登場する。山形から横浜に来た修学旅行生である。時代は1964年の東京オリンピックの直前のようだが、現代の目で見ると終戦直後のようにも感じられる。この騒々しい修学旅行生たちのフォークダンス・シーンが印象深い。アップテンポに編曲しているので、時間の奔流と懐かしさを同時に感じた。
中学生たちがあやしげな墓地を発見するところから、時代と空間が錯綜する壮大な舞台が展開する。終戦直後の娼婦、「浜のメリー」を連想させる男娼、青山の同潤会アパート、口からリボンを吐く男などなどが登場し、関東大震災から同潤会アパート取り壊しの現代までの時間が錯綜する。
やがて、冒頭の中学生の集団を含む登場人物の多くは、現代史の記憶の底から出てきた死者だと気づかされる。家族の歴史のなかに多様な事物を盛り込んだ舞台だ。
『鯨よ!私の手に乗れ』は地方の介護施設の老人たちを巡る追憶再生の物語である。渡辺えりの家族をモデルにしている。渡辺えりと思しき人物(演じるのは本人ではない)も活躍する。家族物語のようでありながら、次第に幻想の世界が広がり、舞台に巨大な鯨も登場する。渡辺えりワールドだ。
渡辺えり、70歳。まだまだ溌剌としていて元気だ。
『りぼん』は上演時間3時間(休憩15分を含む)、『鯨よ!私の手に乗れ』は上演時間2時間(休憩なし)である。昼と夜の公演を続けて観れば1日での観劇も可能だが、私は2日にわけて観た。
この芝居の登場人物は43人である。全員が舞台に立つ集団シーンもある。出演者が多いので役者名を挙げるのは省略する(チラシの周囲に載っている)。
『りぼん』の初演は2003年、『鯨よ!私の手に乗れ』の初演は2017年である。私は今回の公演が初見である。私が渡辺えり作の芝居を観たのは2022年上演の『私の恋人 beyond』が最初である。
2つの戯曲はいずれも「戯曲デジタルアーカイブ」で読むことができる。観劇前に読もうと思ったがはたせず、冒頭部分を読んだだけで劇場に足を運んだ。
『りぼん』の冒頭、大勢の修学旅行の中学生が登場する。山形から横浜に来た修学旅行生である。時代は1964年の東京オリンピックの直前のようだが、現代の目で見ると終戦直後のようにも感じられる。この騒々しい修学旅行生たちのフォークダンス・シーンが印象深い。アップテンポに編曲しているので、時間の奔流と懐かしさを同時に感じた。
中学生たちがあやしげな墓地を発見するところから、時代と空間が錯綜する壮大な舞台が展開する。終戦直後の娼婦、「浜のメリー」を連想させる男娼、青山の同潤会アパート、口からリボンを吐く男などなどが登場し、関東大震災から同潤会アパート取り壊しの現代までの時間が錯綜する。
やがて、冒頭の中学生の集団を含む登場人物の多くは、現代史の記憶の底から出てきた死者だと気づかされる。家族の歴史のなかに多様な事物を盛り込んだ舞台だ。
『鯨よ!私の手に乗れ』は地方の介護施設の老人たちを巡る追憶再生の物語である。渡辺えりの家族をモデルにしている。渡辺えりと思しき人物(演じるのは本人ではない)も活躍する。家族物語のようでありながら、次第に幻想の世界が広がり、舞台に巨大な鯨も登場する。渡辺えりワールドだ。
渡辺えり、70歳。まだまだ溌剌としていて元気だ。
キャベツ高騰で筒井康隆氏の初期短編を想起 ― 2025年01月16日
キャベツが高騰し、いまや高級品になっているとのニュースに接し、筒井康隆氏の初期短編「下の世界」を想起した。
私は筒井康隆氏のファンで、ほぼ全作品をほぼリアルタイムで読んできた――と思う。そんな私が最初に読んだ筒井作品が「下の世界」である。1964年3月発行の『別冊宝石 特集・世界のSF』に載っていた。当時、私は高校1年だった。「下の世界」は、1冊すべてSFの別冊宝石のなかで記憶に残る作品だった。高級品となったキャベツのシーンが印象深かった。(この作品の初出は1963.5の『NULL』9号)
「下の世界」は極端な格差社会になった未来を描いている。社会は「上の世界(精神階級)」と「下の世界(肉体階級)」に分かれ、「少し前までは、この両階級の間での主従関係以外の交際や、まして恋愛などはご法度だった。だが今ではご法度以前に――性交不能じゃ」という状態になっている。
そんな時代の「下の世界」に生まれた若者が主人公である。この世界でキャベツは高級食材である。闇でしか入手できない。主人公が競技会に出場する前夜、母親が彼のためにキャベツを用意する。キャベツをめぐる食卓シーンは私の脳味噌に深く刻印された。その後しばらくは、キャベツを食べるたびに「下の世界」を思い出した。読んでから60年以上経ったいまでも、たまに思い浮かべる。だから、キャベツ高騰のニュースに反応してしまったのだ。
「下の世界」を読んだ高校生の私はその後、「SFマガジン」などに載る筒井作品をむさぼるように読んだ。ハヤカワSFシリーズで第1短編集『東海道戦争』(1965.10)が出たときにはすぐに購入した。この短編集に「下の世界」は収録されていなかった。ハヤカワSFシリーズの第2短編集『ベトナム観光公社』(1967.6)にも、文藝春秋から出た『アフリカの爆弾』(1968.3)にも収録されていなかった。筒井作品としては重くて暗いので、短編集収録が見送られたのだろうと思った。
1968年頃から筒井康隆氏は売れっ子作家になり、多くの作品集が次々に刊行されたが、それらの作品集にも「下の世界」は収録されなかった。葬られた作品かなと感じていたが、1973年2月刊行の角川文庫版『わがよき狼(ウルフ)』に「下の世界」が収録された。この文庫の目次を見て、わがファースト・コンタクトの筒井作品が9年ぶりに日の目を見たという感慨がわいた。ずいぶん昔の思い出だ。
私は筒井康隆氏のファンで、ほぼ全作品をほぼリアルタイムで読んできた――と思う。そんな私が最初に読んだ筒井作品が「下の世界」である。1964年3月発行の『別冊宝石 特集・世界のSF』に載っていた。当時、私は高校1年だった。「下の世界」は、1冊すべてSFの別冊宝石のなかで記憶に残る作品だった。高級品となったキャベツのシーンが印象深かった。(この作品の初出は1963.5の『NULL』9号)
「下の世界」は極端な格差社会になった未来を描いている。社会は「上の世界(精神階級)」と「下の世界(肉体階級)」に分かれ、「少し前までは、この両階級の間での主従関係以外の交際や、まして恋愛などはご法度だった。だが今ではご法度以前に――性交不能じゃ」という状態になっている。
そんな時代の「下の世界」に生まれた若者が主人公である。この世界でキャベツは高級食材である。闇でしか入手できない。主人公が競技会に出場する前夜、母親が彼のためにキャベツを用意する。キャベツをめぐる食卓シーンは私の脳味噌に深く刻印された。その後しばらくは、キャベツを食べるたびに「下の世界」を思い出した。読んでから60年以上経ったいまでも、たまに思い浮かべる。だから、キャベツ高騰のニュースに反応してしまったのだ。
「下の世界」を読んだ高校生の私はその後、「SFマガジン」などに載る筒井作品をむさぼるように読んだ。ハヤカワSFシリーズで第1短編集『東海道戦争』(1965.10)が出たときにはすぐに購入した。この短編集に「下の世界」は収録されていなかった。ハヤカワSFシリーズの第2短編集『ベトナム観光公社』(1967.6)にも、文藝春秋から出た『アフリカの爆弾』(1968.3)にも収録されていなかった。筒井作品としては重くて暗いので、短編集収録が見送られたのだろうと思った。
1968年頃から筒井康隆氏は売れっ子作家になり、多くの作品集が次々に刊行されたが、それらの作品集にも「下の世界」は収録されなかった。葬られた作品かなと感じていたが、1973年2月刊行の角川文庫版『わがよき狼(ウルフ)』に「下の世界」が収録された。この文庫の目次を見て、わがファースト・コンタクトの筒井作品が9年ぶりに日の目を見たという感慨がわいた。ずいぶん昔の思い出だ。
西部邁の最後の書を読んだ ― 2025年01月18日
西部邁が自死したのは2~3年前のように感じていたが、調べてみると2018年1月21日、7年前だった。齢を重ねると日々の流れが速くなる。
西部邁の自死1カ月前に出た『保守の真髄』を死の直後に読み、その本が最後の書だと思っていた。だが、その後にさらに1冊出していると知り、入手して読んだ。
『保守の遺言:JAP.COM衰微の状況』(西部邁/平凡社新書/2018.2.27)
本書の「あとがき」の日付は2018年1月15日、自死の6日前である。刊行は自死から約1カ月後だ。序文には「僕はこれが最後の著作と銘打ちつつすでに二つの書物を出版してしまった。だから、何事も三度めなので、もう嘘はないとことわりつつ…」とある。
先日読んだ『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル』で本書を知った。安倍晋三が保守系言論人からも批判された事例として本書からの引用が載っていた。著者は安倍首相をプラグマティストではなくプラクティカリスト(実際主義者)としている。それはオポチュニスト(状況適応主義)、オケージョナリスト(機会に反応するのを旨とするやり方)の別名であり、「現在に関する視界が狭い」「未来に関する視野が短い」という特徴があるそうだ。
本書にはカタカナ語が頻出し、しばしばその語源解説に及ぶ。訳語の不適切の指摘も多い。著者の芸風である。マスを「大衆」と呼ぶのは間違いで「大量人」と呼ぶべきといった言説である。コモディテイ(商品)を論じる際、古代ローマ皇帝コモドゥスを思い起こすべきだとしているのには驚いた。コモデゥスが愚帝とは承知しているが、私には了解不能で、やり過ぎではないかと感じた。
衒学的で粘っこいニシベ節には辟易することも多いが、独特の魅力も感じる。共感と反発がないまぜになる。この新書を通読した読後感は、共感3割、反感3割、理解困難4割といったところだ。悩ましい本である。著者が持論を述べた部分を引用する。
「僕の持論をここで繰り返させてもらうと、自由と秩序のあいだの平衡としての「活力」、平等と格差のあいだの平衡としての「公正」、博愛と競合のあいだの平衡としての「節度」そして合理と感情のあいだの平衡としての「良識」、この四副対の規範の(現下の状況における)具体的な姿、それがクライテリオン(複数でクライテリア)ということなのだ。」
遺言と銘打った本書のトーンは諦観である。「明るく諦観しているにすぎない」という言葉が印象深い。
西部邁の自死1カ月前に出た『保守の真髄』を死の直後に読み、その本が最後の書だと思っていた。だが、その後にさらに1冊出していると知り、入手して読んだ。
『保守の遺言:JAP.COM衰微の状況』(西部邁/平凡社新書/2018.2.27)
本書の「あとがき」の日付は2018年1月15日、自死の6日前である。刊行は自死から約1カ月後だ。序文には「僕はこれが最後の著作と銘打ちつつすでに二つの書物を出版してしまった。だから、何事も三度めなので、もう嘘はないとことわりつつ…」とある。
先日読んだ『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル』で本書を知った。安倍晋三が保守系言論人からも批判された事例として本書からの引用が載っていた。著者は安倍首相をプラグマティストではなくプラクティカリスト(実際主義者)としている。それはオポチュニスト(状況適応主義)、オケージョナリスト(機会に反応するのを旨とするやり方)の別名であり、「現在に関する視界が狭い」「未来に関する視野が短い」という特徴があるそうだ。
本書にはカタカナ語が頻出し、しばしばその語源解説に及ぶ。訳語の不適切の指摘も多い。著者の芸風である。マスを「大衆」と呼ぶのは間違いで「大量人」と呼ぶべきといった言説である。コモディテイ(商品)を論じる際、古代ローマ皇帝コモドゥスを思い起こすべきだとしているのには驚いた。コモデゥスが愚帝とは承知しているが、私には了解不能で、やり過ぎではないかと感じた。
衒学的で粘っこいニシベ節には辟易することも多いが、独特の魅力も感じる。共感と反発がないまぜになる。この新書を通読した読後感は、共感3割、反感3割、理解困難4割といったところだ。悩ましい本である。著者が持論を述べた部分を引用する。
「僕の持論をここで繰り返させてもらうと、自由と秩序のあいだの平衡としての「活力」、平等と格差のあいだの平衡としての「公正」、博愛と競合のあいだの平衡としての「節度」そして合理と感情のあいだの平衡としての「良識」、この四副対の規範の(現下の状況における)具体的な姿、それがクライテリオン(複数でクライテリア)ということなのだ。」
遺言と銘打った本書のトーンは諦観である。「明るく諦観しているにすぎない」という言葉が印象深い。


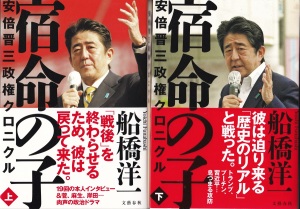
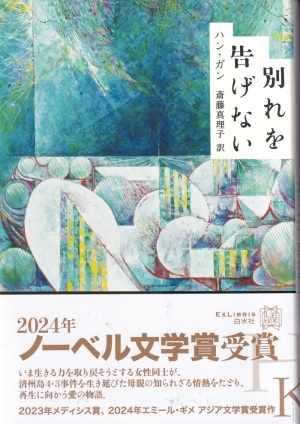
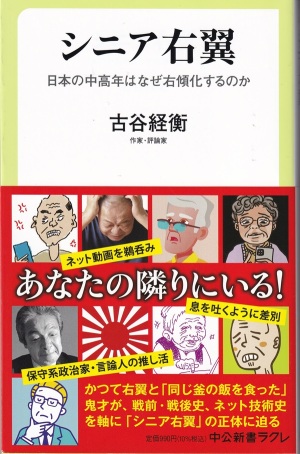



最近のコメント