耶律楚材が気の毒に思えてくる『耶律楚材とその時代』 ― 2022年01月02日
先日読んだ堺屋太一の
『世界を創った男チンギス・ハン』と井上靖の
『蒼き狼』には耶律楚材という人物が少しだけ登場する。私はこの人物についてほとんど知らなかったが、ネット検索で次の2点を知った。
(1)チンギス・カンのブレーンとして活躍した人気の高い人物である
(2)杉山正明氏は従来の耶律楚材像を否定し、たいした人物ではないと主張している
堺屋太一の小説の注釈には杉山正明氏の名が何度か出てくる。小説のなかでは耶律楚材を次のように描いている。
「チンギス・ハンは、自己顕示欲の強いこの男に利用価値を見出した。占卜を装ってわが意のあるところを発言させれば、政策遂行の役に立つ。」
半世紀以上昔の『蒼き狼』では耶律楚材を、チンギス・カンが一目おく知的「教師」のように描いている。
チンギス・カンに関する小説2冊を読んだのを機に、杉山正明氏の次の本を読んだ。25年前に出た本である。
『耶律楚材とその時代』(杉山正明/中国歴史人物選/白帝社/1997.7)
従来の耶律楚材のイメージがいかに歪められているかをあばいた本である。耶律楚材に肯定的なイメージをもっている人にとってはショッキングな内容だと思う。耶律楚材に関して何のイメージもない無知な私にも面白く読めた。
モンゴルに征服された金国の官吏だった耶律楚材は、チンギス・カンの側近として重用され、宰相にまで登りつめ、モンゴルの蛮行を諫める役割を果たした――それが従来の耶律楚材の人物像のようだ。杉山正明氏は、そんな経歴は真っ赤な嘘で、耶律楚材はモンゴルの一介の書記で、占い師にすぎないとしている。
では、なぜ「真っ赤な嘘」が後世に伝わったのか、杉山正明氏はその仕掛けを多角的に解き明かしている。面白くてスリリングである。説得力のある内容だと思うが、門外漢の私が杉山正明氏の見解を評価できるわけではない。本書がどう評価されているかも知らない。
本書によれば、「真っ赤の嘘」がまかり通ってきた責任は耶律楚材本人とその子息、そして漢族の史家たちにある。それにしても、杉山正明氏の舌鋒はするどい。耶律楚材の品性や人間性もあげつらている。批判されて当然にも思えるが、コテンパンの耶律楚材が少し気の毒になってくる。
(1)チンギス・カンのブレーンとして活躍した人気の高い人物である
(2)杉山正明氏は従来の耶律楚材像を否定し、たいした人物ではないと主張している
堺屋太一の小説の注釈には杉山正明氏の名が何度か出てくる。小説のなかでは耶律楚材を次のように描いている。
「チンギス・ハンは、自己顕示欲の強いこの男に利用価値を見出した。占卜を装ってわが意のあるところを発言させれば、政策遂行の役に立つ。」
半世紀以上昔の『蒼き狼』では耶律楚材を、チンギス・カンが一目おく知的「教師」のように描いている。
チンギス・カンに関する小説2冊を読んだのを機に、杉山正明氏の次の本を読んだ。25年前に出た本である。
『耶律楚材とその時代』(杉山正明/中国歴史人物選/白帝社/1997.7)
従来の耶律楚材のイメージがいかに歪められているかをあばいた本である。耶律楚材に肯定的なイメージをもっている人にとってはショッキングな内容だと思う。耶律楚材に関して何のイメージもない無知な私にも面白く読めた。
モンゴルに征服された金国の官吏だった耶律楚材は、チンギス・カンの側近として重用され、宰相にまで登りつめ、モンゴルの蛮行を諫める役割を果たした――それが従来の耶律楚材の人物像のようだ。杉山正明氏は、そんな経歴は真っ赤な嘘で、耶律楚材はモンゴルの一介の書記で、占い師にすぎないとしている。
では、なぜ「真っ赤な嘘」が後世に伝わったのか、杉山正明氏はその仕掛けを多角的に解き明かしている。面白くてスリリングである。説得力のある内容だと思うが、門外漢の私が杉山正明氏の見解を評価できるわけではない。本書がどう評価されているかも知らない。
本書によれば、「真っ赤の嘘」がまかり通ってきた責任は耶律楚材本人とその子息、そして漢族の史家たちにある。それにしても、杉山正明氏の舌鋒はするどい。耶律楚材の品性や人間性もあげつらている。批判されて当然にも思えるが、コテンパンの耶律楚材が少し気の毒になってくる。
ローマ帝国末期の女性哲学者ヒュパティアの本が出た ― 2022年01月04日
11年前に観た
映画『アレクサンドリア』でヒュパティアという名を知った。ローマ帝国末期のアレクサンドリアで活躍し、キリスト教の暴徒に虐殺された美貌の数学者・天文学者である。衝撃的な映画だった。彼女についてもっと知りたいと思った。
その後、ローマ史関係の本をいくつか読んできたが、ヒュパティアに触れているのは、私の記憶に残っている限りではギボンの『ローマ帝国衰亡史』と本村凌二氏の『地中海世界とローマ帝国』ぐらいで、さほど詳しいことはわからなかった。
先月末、小さな新聞広告で『ヒュパティア』という本が出ていると知った。早速入手し、年初に読了した。
『ヒュパティア:後期ローマ帝国の女性知識人』(エドワード・J・ワッソ/中西恭子訳/白水社)
著者は米国の研究者で原著の出版は2017年、訳書は2021年11月20日発行、私が入手したのは2021年12月25日発行の2刷である。売れているようだ。
ヒュパティアの評伝だが、哲学史のやや専門的な話も出てくる。ヒュパティアは新プラトン主義の哲学者の一人だった。新プラトン主義が何たるかを知らない門外漢には当時の学派のアレコレの話は少々難しい。大急ぎで俄か知識を仕入れながら読み進めた。
映画のヒュパティアは天文学者のイメージが強かったが、本書が描くヒュパティアはエリート男性たちに哲学を講じる学校の学頭である。当時の哲学は数学・天文学・神学などを包摂する学問で、人間や社会や国家のあるべき姿を示す指標だったようだ(現在でも、そうかもしれないが)。
映画の印象で、伝統宗教とキリスト教が対立するなかで前者に与するヒュパティアが虐殺されたと感じていたが、本書を読むとそんなに単純な構図ではなさそうだ。
ヒュパティアの教え子にはキリスト教徒も多く、彼らは彼女の教えを糧にして行政や教会の要職についている。彼女の新プラトン主義哲学はキリスト教の神学と対立しない方向性があったようだ。非常に優秀な人で、アレクサンドリアのエリートたちへの影響力も大きかった。女性である故の活動の制約を乗り越えて活躍した知識人である。だから、フェミニズムのアイコンにもなる。
本書で最も面白かったのは終章の「近代の象徴」である。私は映画を観るまでヒュパティアを知らなかったが、西欧では有名な女性だったようだ。この章では、これまでにヒュパティアがどのように描かれたきたかを紹介し、実像との乖離を検討している。
あの映画についても「アレハンドロ・アメナーバルの2009年の映画《アゴラ》〔邦題《アレクサンドリア》〕ほど広く一般に影響を与えたものはなかった。」とし、かなり詳しく論じている。彼女の衝撃的な死に着目しすぎると、彼女の業績や歴史の流れへの検討が希薄になり、歴史の実相を見誤る――著者はそう主張しているのだと思う。
その後、ローマ史関係の本をいくつか読んできたが、ヒュパティアに触れているのは、私の記憶に残っている限りではギボンの『ローマ帝国衰亡史』と本村凌二氏の『地中海世界とローマ帝国』ぐらいで、さほど詳しいことはわからなかった。
先月末、小さな新聞広告で『ヒュパティア』という本が出ていると知った。早速入手し、年初に読了した。
『ヒュパティア:後期ローマ帝国の女性知識人』(エドワード・J・ワッソ/中西恭子訳/白水社)
著者は米国の研究者で原著の出版は2017年、訳書は2021年11月20日発行、私が入手したのは2021年12月25日発行の2刷である。売れているようだ。
ヒュパティアの評伝だが、哲学史のやや専門的な話も出てくる。ヒュパティアは新プラトン主義の哲学者の一人だった。新プラトン主義が何たるかを知らない門外漢には当時の学派のアレコレの話は少々難しい。大急ぎで俄か知識を仕入れながら読み進めた。
映画のヒュパティアは天文学者のイメージが強かったが、本書が描くヒュパティアはエリート男性たちに哲学を講じる学校の学頭である。当時の哲学は数学・天文学・神学などを包摂する学問で、人間や社会や国家のあるべき姿を示す指標だったようだ(現在でも、そうかもしれないが)。
映画の印象で、伝統宗教とキリスト教が対立するなかで前者に与するヒュパティアが虐殺されたと感じていたが、本書を読むとそんなに単純な構図ではなさそうだ。
ヒュパティアの教え子にはキリスト教徒も多く、彼らは彼女の教えを糧にして行政や教会の要職についている。彼女の新プラトン主義哲学はキリスト教の神学と対立しない方向性があったようだ。非常に優秀な人で、アレクサンドリアのエリートたちへの影響力も大きかった。女性である故の活動の制約を乗り越えて活躍した知識人である。だから、フェミニズムのアイコンにもなる。
本書で最も面白かったのは終章の「近代の象徴」である。私は映画を観るまでヒュパティアを知らなかったが、西欧では有名な女性だったようだ。この章では、これまでにヒュパティアがどのように描かれたきたかを紹介し、実像との乖離を検討している。
あの映画についても「アレハンドロ・アメナーバルの2009年の映画《アゴラ》〔邦題《アレクサンドリア》〕ほど広く一般に影響を与えたものはなかった。」とし、かなり詳しく論じている。彼女の衝撃的な死に着目しすぎると、彼女の業績や歴史の流れへの検討が希薄になり、歴史の実相を見誤る――著者はそう主張しているのだと思う。
2021年に読んだ本のベスト3 ― 2022年01月06日
昨年前半(1~6月)に読んだ本のベスト3は半年前に選定した。年が明けたので後半のベスト3を選定し、前半・後半の6点から年間ベスト3を選んだ。
2021年後半(7月から12月)に読んだ本のベスト3
『シルクロードとローマ帝国の興亡』(井上文則/文春新書)
『ローマ五賢帝:「輝ける世紀」の虚像と実像』(南川高志/講談社学術文庫)
『青きドナウの乱痴気:ウィーン1948年』(良知力/平凡社ライブラリー)
2021年に読んだ本の年間ベスト3
◎『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満)
◎『シルクロードとローマ帝国の興亡』(井上文則/文春新書)
◎『青きドナウの乱痴気:ウィーン1948年』(良知力/平凡社ライブラリー)
こんなふうにベスト3を選ぶのは、どんどん霞んでいく読んだ本の記憶を多少なりとも留めたいからである。年の前半・後半の2段階選定にするのは、半年以上前に読んだ本の記憶を呼び戻すのが難しくなる可能性があるからだ。なら、半年ごとのベスト3だけでいいような気もするが、やはり「年間ベスト3」の方が気分が盛り上がる。
将来、「過去5年のベスト3」や「過去10年のベスト3」を選びたくなるかもしれないが、10年前に読んだ本の内容など蒸発している可能性が高い。
2021年後半(7月から12月)に読んだ本のベスト3
『シルクロードとローマ帝国の興亡』(井上文則/文春新書)
『ローマ五賢帝:「輝ける世紀」の虚像と実像』(南川高志/講談社学術文庫)
『青きドナウの乱痴気:ウィーン1948年』(良知力/平凡社ライブラリー)
2021年に読んだ本の年間ベスト3
◎『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満)
◎『シルクロードとローマ帝国の興亡』(井上文則/文春新書)
◎『青きドナウの乱痴気:ウィーン1948年』(良知力/平凡社ライブラリー)
こんなふうにベスト3を選ぶのは、どんどん霞んでいく読んだ本の記憶を多少なりとも留めたいからである。年の前半・後半の2段階選定にするのは、半年以上前に読んだ本の記憶を呼び戻すのが難しくなる可能性があるからだ。なら、半年ごとのベスト3だけでいいような気もするが、やはり「年間ベスト3」の方が気分が盛り上がる。
将来、「過去5年のベスト3」や「過去10年のベスト3」を選びたくなるかもしれないが、10年前に読んだ本の内容など蒸発している可能性が高い。
「岩波講座 世界歴史」の第3巻『ローマ帝国と西アジア』を読んだ ― 2022年01月08日
昨秋から刊行が始まった
「岩波講座 世界歴史」の第3回配本を読了した。
『ローマ帝国と西アジア 前3~7世紀(岩波講座世界歴史03)』(岩波書店)
この巻は10編の論文と5編のコラムを収録している。従来の「岩波講座」は函入りで、月報を挟み込んでいたが、今回の「岩波講座」は函なしで月報もない。随所に挿入されている見開きのコラムは月報の代替だと思う。挟み込みの月報は紛失しやすいので、この方がいい。
この巻の巻頭論文の筆者は南川高志氏である。私はこれまでに南川高志氏の著書を3冊( 『新・ローマ帝国衰亡史』『ユリアヌス:逸脱のローマ皇帝』 『ローマ五賢帝』)読んでいて、どれも面白かった。巻頭論文を読んでいると、いくつかの箇所で過去に読んだ3冊の記憶が少し甦ってきて、多少は理解の助けになった。
巻頭論文(展望)のタイトルは「ローマ帝国と西アジア:帝国ローマの盛衰と西アジア大国の躍動」である。ローマ帝国史を西アジアとからめて概説し、その後の時代が古代ローマ帝国をどう捉えてきたかを検証し、研究の現況も簡潔に報告している。
巻頭論文は巻全体の総括的解説でもあり、この巻が扱う時間と空間の意味を明解に述べている。本書が扱う時代区分(前3~7世紀)はローマが「帝国」になった時期から「帝国」でなくなるまでの期間である。ローマの「帝国」としての歴史とは、世界史的意義で捉えるローマ史である。
過去に2回刊行された「岩波講座 世界歴史」は、ローマとギリシアを「古典古代」の「地中海世界」とまとめて1巻とし、西アジアへの視点は希薄だったそうだ。「古典古代」「地中海世界」という西欧の価値観に偏った見方を超えたのが今回の新機軸である。ナルホドと納得した。ローマ帝国史が中央ユーラシア史やイスラム史に連結して見えてくる。この巻頭論文では最終節の「ローマ帝国の記憶と表象」が面白かった。
本書収録の各論文は門外漢の私には目新しい事項や難解な事項が多い。研究者たちがどんな課題に取り組んでいるかを覗うことはできた。
実は、本書を手に取る前から注目していた論文が一つあった。井上文則氏の「三世紀の危機とシルクロード交易の盛衰」である。昨年8月に興味深く読んだ 『シルクロードとローマ帝国の興亡』(井上文則/文春新書)の「あとがき」で、井上文則氏が「岩波講座」掲載予定の本論文を予告していたからである。
井上氏の20ページほどの論文は基本的には文春新書の内容と同じである。あらためて感銘を受けた。「三世紀の危機」をローマの軍人皇帝時代の状況と捉えるのではなく、ユーラシア大陸全体を見据えた世界史的な状況と見なしている。地球規模の気候変動を背景に、中国の様子とも連動させた見方が雄大である。シルクロードによる交易の重要性への着目も説得的で、ローマ帝国衰亡につながるひとつの要因を提起している。この巻の白眉だと思う。
『ローマ帝国と西アジア 前3~7世紀(岩波講座世界歴史03)』(岩波書店)
この巻は10編の論文と5編のコラムを収録している。従来の「岩波講座」は函入りで、月報を挟み込んでいたが、今回の「岩波講座」は函なしで月報もない。随所に挿入されている見開きのコラムは月報の代替だと思う。挟み込みの月報は紛失しやすいので、この方がいい。
この巻の巻頭論文の筆者は南川高志氏である。私はこれまでに南川高志氏の著書を3冊( 『新・ローマ帝国衰亡史』『ユリアヌス:逸脱のローマ皇帝』 『ローマ五賢帝』)読んでいて、どれも面白かった。巻頭論文を読んでいると、いくつかの箇所で過去に読んだ3冊の記憶が少し甦ってきて、多少は理解の助けになった。
巻頭論文(展望)のタイトルは「ローマ帝国と西アジア:帝国ローマの盛衰と西アジア大国の躍動」である。ローマ帝国史を西アジアとからめて概説し、その後の時代が古代ローマ帝国をどう捉えてきたかを検証し、研究の現況も簡潔に報告している。
巻頭論文は巻全体の総括的解説でもあり、この巻が扱う時間と空間の意味を明解に述べている。本書が扱う時代区分(前3~7世紀)はローマが「帝国」になった時期から「帝国」でなくなるまでの期間である。ローマの「帝国」としての歴史とは、世界史的意義で捉えるローマ史である。
過去に2回刊行された「岩波講座 世界歴史」は、ローマとギリシアを「古典古代」の「地中海世界」とまとめて1巻とし、西アジアへの視点は希薄だったそうだ。「古典古代」「地中海世界」という西欧の価値観に偏った見方を超えたのが今回の新機軸である。ナルホドと納得した。ローマ帝国史が中央ユーラシア史やイスラム史に連結して見えてくる。この巻頭論文では最終節の「ローマ帝国の記憶と表象」が面白かった。
本書収録の各論文は門外漢の私には目新しい事項や難解な事項が多い。研究者たちがどんな課題に取り組んでいるかを覗うことはできた。
実は、本書を手に取る前から注目していた論文が一つあった。井上文則氏の「三世紀の危機とシルクロード交易の盛衰」である。昨年8月に興味深く読んだ 『シルクロードとローマ帝国の興亡』(井上文則/文春新書)の「あとがき」で、井上文則氏が「岩波講座」掲載予定の本論文を予告していたからである。
井上氏の20ページほどの論文は基本的には文春新書の内容と同じである。あらためて感銘を受けた。「三世紀の危機」をローマの軍人皇帝時代の状況と捉えるのではなく、ユーラシア大陸全体を見据えた世界史的な状況と見なしている。地球規模の気候変動を背景に、中国の様子とも連動させた見方が雄大である。シルクロードによる交易の重要性への着目も説得的で、ローマ帝国衰亡につながるひとつの要因を提起している。この巻の白眉だと思う。
初春歌舞『南総里見八犬伝』で正月気分 ― 2022年01月10日
国立劇場大劇場で初春歌舞伎公演『南総里見八犬伝』を観た。昨秋、文化勲章を受章した尾上菊五郎を中心にした正月らしい華やかな舞台で目出度い気分になる。ドローンを模して新春を寿ぐ場面なども挿入されていた。
馬琴の八犬伝は長大な物語である。私は小学生時代に子供向けのダイジェストを読んで魅了された。いつの日か原文で全編を読んでみたいと思っているが、まだ果たしていない。原典を読んでいない身で語るのはおこがましいが、あの長編物語を3時間程度の舞台にするのは容易ではない。観客があらかじめ大筋を承知しているのを前提の名場面集のようになるのは仕方ない(多くの歌舞伎がそんな舞台ではあるが)。
私が子供心に『八犬伝』に惹かれたのは、物語の進展にともなって不思議な水晶玉を持つ8人が徐々に集まって来るところにあった。歌舞伎の八犬伝も基本的にはそんな作りになっているが、8人それぞれの物語を3時間で展開するのは難しく、かなり端折ってあわただしく8人集合にもっていくことになる。8人集合の情景を最終場面だけでなく序幕の幕切れにも入れているのは工夫だと思った。
馬琴の八犬伝は長大な物語である。私は小学生時代に子供向けのダイジェストを読んで魅了された。いつの日か原文で全編を読んでみたいと思っているが、まだ果たしていない。原典を読んでいない身で語るのはおこがましいが、あの長編物語を3時間程度の舞台にするのは容易ではない。観客があらかじめ大筋を承知しているのを前提の名場面集のようになるのは仕方ない(多くの歌舞伎がそんな舞台ではあるが)。
私が子供心に『八犬伝』に惹かれたのは、物語の進展にともなって不思議な水晶玉を持つ8人が徐々に集まって来るところにあった。歌舞伎の八犬伝も基本的にはそんな作りになっているが、8人それぞれの物語を3時間で展開するのは難しく、かなり端折ってあわただしく8人集合にもっていくことになる。8人集合の情景を最終場面だけでなく序幕の幕切れにも入れているのは工夫だと思った。
中原清一郎(外岡秀俊)の『カノン』は不思議なSF ― 2022年01月13日
年明けの朝刊に外岡秀俊氏の訃報が載っていた。1976年、東大在学中に『北帰行』で文藝賞を受賞するも、作家の道には進まず1977年に朝日新聞社に入社、記者としてのキャリアを積み上げ編集局長を務めた後、早期退職した人である。私より5歳下で享年68歳だった。
1976年、私は社会人3年目の27歳だった。外岡氏の受賞作を掲載した「文藝 1976年12月号」はいまも書架に残っている。小説の内容はほとんど失念しているが強烈な印象は残っている。共感はしなかったが感心した。難しい漢字が多い生硬な文章から「生真面目さ」が伝わってきた。「新しい作家」とは感じなかったが不思議な迫力に圧倒された。
同じ1976年、外岡氏の受賞の半年前、武蔵野美大在学中の村上龍氏が『限りなく透明に近いブルー』で群像新人賞を受賞し、鮮烈にデビューした。村上龍氏には「新しい作家」を感じた。
外岡秀俊氏の訃報に接した後、彼が新聞社退職後に中原清一郎という名で小説を発表していたと知った。どんな小説を書いたのだろうと興味がわき、次の文庫本を入手して読んだ。
『カノン』(中原清一郎/河出文庫)
読みだしたらやめられず一気に読んだ。人の精神と肉体が入れ替わるという、よくあるパターンの話でエンタメに近いが、かなりシリアスである。「あの『北帰行』の作家が捌けたものだ」という感慨と「やはり『北帰行』の作家だな」という印象がないまぜになる。
2014年発表のこの小説は近未来小説である。脳間海馬移植手術が実現した社会で、日本で2例目のその手術を受ける人を描いている。超常現象による精神と肉体の交換ではなく、さまざまな医学的課題や法的課題をクリアした上で、人の記憶を司る海馬を手術で交換するという設定がSFとしても面白い。本人同士の意思で精神と肉体の交換ができるのがミソだ。
末期がんで死を宣告された人が自分の意識(記憶)を健康な肉体に移植して延命したいと願うのはわかる。しかし、健康な肉体を提供して、自分の意識(記憶)を死に行く肉体に移植したいと思う人がいなければ脳間海馬移植手術は成立しない。そんな人がいるだろうか。
この小説では、記憶が直近の過去から遠い過去に向かって次第に消えていくという病(海馬の障害)に冒さされた32歳の女性(夫と4歳の息子がいる)が、今後の息子の養育を考えて移植を希望するという設定である。かなり無理筋だと思うが、著者はそれを説得的にていねいに書き込んでいる。
海馬交換の相手は 58歳の男性、広告代理店の部長代理で余命1年と宣告されている。つまり、32歳の女性の肉体に58歳の男性の精神が入り、幼い子供と夫のいる家庭生活を始める物語である。かなりキツイ話だ。
ドタバタ喜劇になってもおかしくない状況である。それを真面目に厳粛に展開し、感動的な物語に仕立てている。作家の力量を感じる。たいしたものだと感心した。
この小説がどの程度まで最近の脳科学をふまえているかはよくわからない。脳の働きは脳だけで完結できるものではなく末端器官との連関に支えられていて、人の意識や心がどのように発生するかは不明という考えに基づいているように思われる。興味深いテーマである。惜しい作家が早逝したと悔やまれる。
1976年、私は社会人3年目の27歳だった。外岡氏の受賞作を掲載した「文藝 1976年12月号」はいまも書架に残っている。小説の内容はほとんど失念しているが強烈な印象は残っている。共感はしなかったが感心した。難しい漢字が多い生硬な文章から「生真面目さ」が伝わってきた。「新しい作家」とは感じなかったが不思議な迫力に圧倒された。
同じ1976年、外岡氏の受賞の半年前、武蔵野美大在学中の村上龍氏が『限りなく透明に近いブルー』で群像新人賞を受賞し、鮮烈にデビューした。村上龍氏には「新しい作家」を感じた。
外岡秀俊氏の訃報に接した後、彼が新聞社退職後に中原清一郎という名で小説を発表していたと知った。どんな小説を書いたのだろうと興味がわき、次の文庫本を入手して読んだ。
『カノン』(中原清一郎/河出文庫)
読みだしたらやめられず一気に読んだ。人の精神と肉体が入れ替わるという、よくあるパターンの話でエンタメに近いが、かなりシリアスである。「あの『北帰行』の作家が捌けたものだ」という感慨と「やはり『北帰行』の作家だな」という印象がないまぜになる。
2014年発表のこの小説は近未来小説である。脳間海馬移植手術が実現した社会で、日本で2例目のその手術を受ける人を描いている。超常現象による精神と肉体の交換ではなく、さまざまな医学的課題や法的課題をクリアした上で、人の記憶を司る海馬を手術で交換するという設定がSFとしても面白い。本人同士の意思で精神と肉体の交換ができるのがミソだ。
末期がんで死を宣告された人が自分の意識(記憶)を健康な肉体に移植して延命したいと願うのはわかる。しかし、健康な肉体を提供して、自分の意識(記憶)を死に行く肉体に移植したいと思う人がいなければ脳間海馬移植手術は成立しない。そんな人がいるだろうか。
この小説では、記憶が直近の過去から遠い過去に向かって次第に消えていくという病(海馬の障害)に冒さされた32歳の女性(夫と4歳の息子がいる)が、今後の息子の養育を考えて移植を希望するという設定である。かなり無理筋だと思うが、著者はそれを説得的にていねいに書き込んでいる。
海馬交換の相手は 58歳の男性、広告代理店の部長代理で余命1年と宣告されている。つまり、32歳の女性の肉体に58歳の男性の精神が入り、幼い子供と夫のいる家庭生活を始める物語である。かなりキツイ話だ。
ドタバタ喜劇になってもおかしくない状況である。それを真面目に厳粛に展開し、感動的な物語に仕立てている。作家の力量を感じる。たいしたものだと感心した。
この小説がどの程度まで最近の脳科学をふまえているかはよくわからない。脳の働きは脳だけで完結できるものではなく末端器官との連関に支えられていて、人の意識や心がどのように発生するかは不明という考えに基づいているように思われる。興味深いテーマである。惜しい作家が早逝したと悔やまれる。
沖縄の歴史と状況を収斂させた舞台 ― 2022年01月16日
東京芸術劇場プレイハウスで『hana 1970、コザが燃えた日』(作:畑澤聖悟、演出:栗山民也、出演:松山ケンイチ、余貴美子、他)を観た。
今年は沖縄返還50周年である。50年という月日は長い。この半世紀で沖縄は変わったかもしれないが、米軍基地の島というベースは変わっていない。時間だけが無為に流れたようにも感じる。
沖縄返還50周年の年頭上演のこの芝居は、そんな沖縄の状況を想起させる。タイトルが明示しているように、舞台の日時はコザ暴動が発生した1970年12月20日未明である。場所はコザにある米軍兵相手の「hana」という酒場兼質屋である。1幕1時間40分休憩なしのこの芝居は、酒場が閉店した深夜0時過ぎ(まだ暴動は発生していない)に始まり、実時間(100分)で幕切れまで進行する。
暴動はhanaの窓の外で繰り広げられる出来事であり、暴動そのものを描いた芝居ではない。暴動は象徴的な背景である。この芝居はhanaを巡る人々によって、hanaという場所に沖縄の歴史と状況を収斂させている。濃縮された舞台である。この店の関係者と閉店後も出入りする人、つまり全登場人物を列挙すると以下の通りだ。
女主人、居候の男(女主人の事実上の亭主)、女主人の娘(二十歳前)、女主人の長男(ヤクザ)、女主人の次男(教員)、次男の同僚の教員、同僚教員の知り合いのカメラマン(本土からの旅行者)、米軍の脱走兵(女主人に匿われている)、以上8人である。女主人と長男、次男は互いに血のつながりはなく、実子の娘は幽霊だ。この8人の取り合わせに感心した。歴史と状況のあれこれを十全に8人に反映させている。hanaの深夜の100分に沖縄の時空が詰め込まれている。
舞台奥、hanaの窓外で店名を示すネオン看板は芝居の間は消えている。閉店後の話だから当然である。そのネオン看板がカーテンコールの時には点灯していた。何故か感動した。
今年は沖縄返還50周年である。50年という月日は長い。この半世紀で沖縄は変わったかもしれないが、米軍基地の島というベースは変わっていない。時間だけが無為に流れたようにも感じる。
沖縄返還50周年の年頭上演のこの芝居は、そんな沖縄の状況を想起させる。タイトルが明示しているように、舞台の日時はコザ暴動が発生した1970年12月20日未明である。場所はコザにある米軍兵相手の「hana」という酒場兼質屋である。1幕1時間40分休憩なしのこの芝居は、酒場が閉店した深夜0時過ぎ(まだ暴動は発生していない)に始まり、実時間(100分)で幕切れまで進行する。
暴動はhanaの窓の外で繰り広げられる出来事であり、暴動そのものを描いた芝居ではない。暴動は象徴的な背景である。この芝居はhanaを巡る人々によって、hanaという場所に沖縄の歴史と状況を収斂させている。濃縮された舞台である。この店の関係者と閉店後も出入りする人、つまり全登場人物を列挙すると以下の通りだ。
女主人、居候の男(女主人の事実上の亭主)、女主人の娘(二十歳前)、女主人の長男(ヤクザ)、女主人の次男(教員)、次男の同僚の教員、同僚教員の知り合いのカメラマン(本土からの旅行者)、米軍の脱走兵(女主人に匿われている)、以上8人である。女主人と長男、次男は互いに血のつながりはなく、実子の娘は幽霊だ。この8人の取り合わせに感心した。歴史と状況のあれこれを十全に8人に反映させている。hanaの深夜の100分に沖縄の時空が詰め込まれている。
舞台奥、hanaの窓外で店名を示すネオン看板は芝居の間は消えている。閉店後の話だから当然である。そのネオン看板がカーテンコールの時には点灯していた。何故か感動した。
スエトニウスの『ローマ皇帝伝』はゴシップ集?! ― 2022年01月19日
昨年夏、SF作家アシモフの
ローマ史解説本を面白く読んだ。そのなかで歴史家スエトニウスの『ローマ皇帝伝』に関する次の記述が印象に残った。
『これは(…)11人の皇帝に関するゴシップ風の伝記であった。スエトニウスは醜聞に属する話を繰り返すのが好きで、いまの歴史家なら単なる噂ばなしとして省いてしまうような記述がかなり含まれている。しかし、彼の文体は平易であり、そのこまごまと語り伝える暴露記事は、当時はもちろん今でもこの本を人気のある読み物にしている。』
この記述で、いずれスエトニウスを読んでみたいと思った。年が明けて、やっとひもといた。
『ローマ皇帝伝(上)』(スエトニウス/国原吉之助訳/岩波文庫)
この上巻が取り上げるのはカエサル、アウグストゥス、ティベリウスの3人、帝政ローマを確立した大立者カエサル、帝国の統治を盤石にした初代皇帝アウグストゥス、それを受け継いだ二代目皇帝ティベリウスの皇帝伝である。ただし、「皇帝」という言葉はタイトルにあるだけで、本文には出てこない。主に「元首」を使っている。実態は皇帝でも「皇帝」という概念が言葉や概念が歴史的に後付けだからだ。
この「皇帝伝」は確かにゴシップ集の趣がある。現在の週刊誌の皇室記事以上にあけすけで、性癖の話題も多い。皇帝についてここまで書いていいのかと感嘆するが、スエトニウスの時代の人々にとって、皇帝とはそういう存在だったのだとも思える。
スエトニウスが生まれたのは70年頃で、トライヤヌス帝やハドリアヌス帝の時代の歴史家である。彼にとってカエサルは170年前の人であり、ティベリウスでも110年以上前の人だ。1948年生まれの私が江戸時代の人物を語っているような時間感覚だ。
だが、この皇帝伝を読んでいると同時代のルポライターの週刊誌記事を読んでいる気分になる。皇帝周辺の人々から仕入れた噂ばなしを披露するような趣もある。そんな噂が後世にまで伝わっていたのだろうが、100年以上昔の話となると、どれほど尾ひれがついているのか判然としない。でも、面白いのは確かだ。
本書を読んでいてナルホドと思ったのは、ローマの聖なる炉床を守るウェスタの聖女に関する次の記述である。
「ウェスタ聖女が亡くなって代わりの処女を採用せねばならなくなったとき、多くの親が自分の娘に籤があたらぬように、いろいろと裏で工作していた」
特権的な女性神官職の実態が垣間見え、スエトニウスの率直な記述に親しみがわく。
本書が取り上げるカエサル、アウグストゥス、ティベリウスと並べると、時代が下がるに従って皇帝の性格が陽から陰に移っていくのが興味深い。陽気大胆から周到沈着を経て陰鬱残酷へと移ろっていく。皇帝の性格であって時代相ではないのだが。
『これは(…)11人の皇帝に関するゴシップ風の伝記であった。スエトニウスは醜聞に属する話を繰り返すのが好きで、いまの歴史家なら単なる噂ばなしとして省いてしまうような記述がかなり含まれている。しかし、彼の文体は平易であり、そのこまごまと語り伝える暴露記事は、当時はもちろん今でもこの本を人気のある読み物にしている。』
この記述で、いずれスエトニウスを読んでみたいと思った。年が明けて、やっとひもといた。
『ローマ皇帝伝(上)』(スエトニウス/国原吉之助訳/岩波文庫)
この上巻が取り上げるのはカエサル、アウグストゥス、ティベリウスの3人、帝政ローマを確立した大立者カエサル、帝国の統治を盤石にした初代皇帝アウグストゥス、それを受け継いだ二代目皇帝ティベリウスの皇帝伝である。ただし、「皇帝」という言葉はタイトルにあるだけで、本文には出てこない。主に「元首」を使っている。実態は皇帝でも「皇帝」という概念が言葉や概念が歴史的に後付けだからだ。
この「皇帝伝」は確かにゴシップ集の趣がある。現在の週刊誌の皇室記事以上にあけすけで、性癖の話題も多い。皇帝についてここまで書いていいのかと感嘆するが、スエトニウスの時代の人々にとって、皇帝とはそういう存在だったのだとも思える。
スエトニウスが生まれたのは70年頃で、トライヤヌス帝やハドリアヌス帝の時代の歴史家である。彼にとってカエサルは170年前の人であり、ティベリウスでも110年以上前の人だ。1948年生まれの私が江戸時代の人物を語っているような時間感覚だ。
だが、この皇帝伝を読んでいると同時代のルポライターの週刊誌記事を読んでいる気分になる。皇帝周辺の人々から仕入れた噂ばなしを披露するような趣もある。そんな噂が後世にまで伝わっていたのだろうが、100年以上昔の話となると、どれほど尾ひれがついているのか判然としない。でも、面白いのは確かだ。
本書を読んでいてナルホドと思ったのは、ローマの聖なる炉床を守るウェスタの聖女に関する次の記述である。
「ウェスタ聖女が亡くなって代わりの処女を採用せねばならなくなったとき、多くの親が自分の娘に籤があたらぬように、いろいろと裏で工作していた」
特権的な女性神官職の実態が垣間見え、スエトニウスの率直な記述に親しみがわく。
本書が取り上げるカエサル、アウグストゥス、ティベリウスと並べると、時代が下がるに従って皇帝の性格が陽から陰に移っていくのが興味深い。陽気大胆から周到沈着を経て陰鬱残酷へと移ろっていく。皇帝の性格であって時代相ではないのだが。
人物像のゆらぎが面白いスエトニウスの『ローマ皇帝伝(下)』 ― 2022年01月21日
スエトニウスの『ローマ皇帝伝(上)』に続いて下巻を読んだ。
『ローマ皇帝伝(下)』(スエトニウス/国原吉之助訳/岩波文庫)
下巻はカリグラ、クラウディウス、ネロ、ガルバ、オト、ウィステリウス、ウェスパシアニス、ティトゥス、ドミティアヌスの9人の皇帝伝で、次第にスエトニウスが生きた時代に近づいてくる。
最後のドミティアヌスが亡くなったとき、スエトニウスは20代半ばだから同時代人とも言える。しかし、時代が下るに従って記述は簡略になる。ネロまでの3人は一人で1巻だが、後の6人は3人ずつで1巻という扱いになっている。評価が定まった昔の人物は書きやすいが、直近の人物には書きにくい事情があるのかと勘繰りたくなる。
上巻の3人(カエサル、アウグストゥス、ティベリウス)に比べれば下巻の皇帝たちは軽量級で悪帝と言われる皇帝が何人もいる。スエトニウスは歴史ではなく人物を描いている。読者が大筋の歴史を知っているのが前提の書き方である。だから、事前に別の資料で各皇帝の略歴を確認したうえで本書を読んだ。
この皇帝ゴシップ集は皇帝たちの風貌描写がかなり露骨で、誰もが強欲・残酷・色情狂・放埓な人物に見えてくる。善行や業績も紹介しているので人物像が混乱する。そこが面白いとも言える。
ネロの評価もよくわからない。悪帝として描き、その死を知った世間の人が喜んではしゃいだと書く一方で、彼の墓に花を飾る人が後を絶たなかったとも述べている。後の皇帝(オトなど)によるネロ評価の事業も紹介している。時代の雰囲気がよくわからないが、現実とはチグハグなものだろうと思う。
この皇帝伝には、予知夢・予兆・予言・超常現象などが頻出する。噂ばなしを集めればこうなるのだろう。現代でも占いは廃れていないので、スエトニウスを荒唐無稽と見下すことはできない。
『ローマ皇帝伝(下)』(スエトニウス/国原吉之助訳/岩波文庫)
下巻はカリグラ、クラウディウス、ネロ、ガルバ、オト、ウィステリウス、ウェスパシアニス、ティトゥス、ドミティアヌスの9人の皇帝伝で、次第にスエトニウスが生きた時代に近づいてくる。
最後のドミティアヌスが亡くなったとき、スエトニウスは20代半ばだから同時代人とも言える。しかし、時代が下るに従って記述は簡略になる。ネロまでの3人は一人で1巻だが、後の6人は3人ずつで1巻という扱いになっている。評価が定まった昔の人物は書きやすいが、直近の人物には書きにくい事情があるのかと勘繰りたくなる。
上巻の3人(カエサル、アウグストゥス、ティベリウス)に比べれば下巻の皇帝たちは軽量級で悪帝と言われる皇帝が何人もいる。スエトニウスは歴史ではなく人物を描いている。読者が大筋の歴史を知っているのが前提の書き方である。だから、事前に別の資料で各皇帝の略歴を確認したうえで本書を読んだ。
この皇帝ゴシップ集は皇帝たちの風貌描写がかなり露骨で、誰もが強欲・残酷・色情狂・放埓な人物に見えてくる。善行や業績も紹介しているので人物像が混乱する。そこが面白いとも言える。
ネロの評価もよくわからない。悪帝として描き、その死を知った世間の人が喜んではしゃいだと書く一方で、彼の墓に花を飾る人が後を絶たなかったとも述べている。後の皇帝(オトなど)によるネロ評価の事業も紹介している。時代の雰囲気がよくわからないが、現実とはチグハグなものだろうと思う。
この皇帝伝には、予知夢・予兆・予言・超常現象などが頻出する。噂ばなしを集めればこうなるのだろう。現代でも占いは廃れていないので、スエトニウスを荒唐無稽と見下すことはできない。
『大唐帝国』(宮崎市定)は見たてが秀逸 ― 2022年01月25日
ずいぶん昔から「いずれ読もう」と気になっていた次の歴史概説書をついに読んだ。
『大唐帝国(世界の歴史7)』(宮崎市定/河出書房)
半世紀以上昔に河出書房から出た歴史叢書の1冊である。30年ぐらい前に全24巻を古書で安価に入手し、その何冊かは読んだが本書は未読だった。
この巻の刊行は1968年11月、かなり昔だが、後に河出文庫や中公文庫に収録され、いまでも文庫本で入手できる。碩学の名著なのだと思う。
1901年生まれの宮崎市定は戦時中に京大教授になっている。67歳のときに出た本書を読んでいると、老教授の闊達な史談を拝聴している気分になる。
書名は「大唐帝国」だが唐に関する記述は後ろの約2割、後漢滅亡以降から唐にいたるまでの記述がメインで、著者は本書が扱う時代を「中国の中世」としている。この時代の王朝を羅列すると以下の通りだ。
魏、蜀、呉、西晋、東晋、宋、斉、梁、陳、五胡十六国、北魏、東魏、西魏、北斉、北周、隋、唐
ここで五胡十六国と一括した国も本書では個別に登場する。中国史が不得手な私は、未知の地名と人名のオンパレードに悩まされた。それでも面白く読めたのは、宮崎節とでも言いたくなる語り口の魅力と、虫の目と鳥の目の絶妙なバランスのおかげである。小説のような情景描写と大きな時代把握がないまぜになっている。
漢滅亡後の混乱の時代をローマ帝国末期になぞらえているのがわかりやすい。カエサルの『ガリア戦記』を読んだとき、おびただしい数の蛮族名に悩まされたが、中国史に登場する部族名や国名の多さも似ている。人間の集団が織りなすものは似て当然か。
面白いなと感心したのは、北魏をメロヴィンガ朝フランク王国、唐をカール大帝のカロリング朝フランク王国に見立てている点である。中世の意味が少し見えてくる。
その他にも興味深い「見たて」が頻出する。則天武后による粛清以降の唐と終戦後日本に共通点があると指摘しているのには驚いた。旧勢力一掃で自由に人材登用ができた点、軍備を外注にして財政にウエイトを置いた点などである。
本書にはヤバイと思われる表現も出てくる。古い映画のテレビ放映の際に出る「現代では不適切な表現がありますが、作者の意図を尊重してそのまま放送します」に似た感じだ。北方遊牧民を野蛮人と見下し、安禄山の兵を「西方イラン系や北方遊牧民族出身の異国人が多く、中国人に対しては情も容赦もない」と描いている。ウイグル族の闇商人を戦後日本の第三国人や第一次大戦後ドイツのユダヤ人の闇屋と重ねる表現もある。
とは言うものの、雄渾な歴史概説書である。
================
〔追記〕
上記の文章を書いて数日後、中公文庫版『大唐帝国』(1988.9.10初版
2018.8.25改版)を手にした。巻末に以下の編集部コメントが載っていた。
「本書には、今日の人権意識からみて不適切と思われる表現が使用されていますが、本書が書かれた時代背景、および著者が故人であることを考慮し、発表時のままとしました。(編集部)」
〔追記2〕
本書函カバーの人物、どこにも説明表記がない。唐の太宗、高宗、玄宗のいずれかと推測したが、違っていた。画像検索によって「西晋の初代皇帝・司馬炎(武帝)」と判明した。
『大唐帝国(世界の歴史7)』(宮崎市定/河出書房)
半世紀以上昔に河出書房から出た歴史叢書の1冊である。30年ぐらい前に全24巻を古書で安価に入手し、その何冊かは読んだが本書は未読だった。
この巻の刊行は1968年11月、かなり昔だが、後に河出文庫や中公文庫に収録され、いまでも文庫本で入手できる。碩学の名著なのだと思う。
1901年生まれの宮崎市定は戦時中に京大教授になっている。67歳のときに出た本書を読んでいると、老教授の闊達な史談を拝聴している気分になる。
書名は「大唐帝国」だが唐に関する記述は後ろの約2割、後漢滅亡以降から唐にいたるまでの記述がメインで、著者は本書が扱う時代を「中国の中世」としている。この時代の王朝を羅列すると以下の通りだ。
魏、蜀、呉、西晋、東晋、宋、斉、梁、陳、五胡十六国、北魏、東魏、西魏、北斉、北周、隋、唐
ここで五胡十六国と一括した国も本書では個別に登場する。中国史が不得手な私は、未知の地名と人名のオンパレードに悩まされた。それでも面白く読めたのは、宮崎節とでも言いたくなる語り口の魅力と、虫の目と鳥の目の絶妙なバランスのおかげである。小説のような情景描写と大きな時代把握がないまぜになっている。
漢滅亡後の混乱の時代をローマ帝国末期になぞらえているのがわかりやすい。カエサルの『ガリア戦記』を読んだとき、おびただしい数の蛮族名に悩まされたが、中国史に登場する部族名や国名の多さも似ている。人間の集団が織りなすものは似て当然か。
面白いなと感心したのは、北魏をメロヴィンガ朝フランク王国、唐をカール大帝のカロリング朝フランク王国に見立てている点である。中世の意味が少し見えてくる。
その他にも興味深い「見たて」が頻出する。則天武后による粛清以降の唐と終戦後日本に共通点があると指摘しているのには驚いた。旧勢力一掃で自由に人材登用ができた点、軍備を外注にして財政にウエイトを置いた点などである。
本書にはヤバイと思われる表現も出てくる。古い映画のテレビ放映の際に出る「現代では不適切な表現がありますが、作者の意図を尊重してそのまま放送します」に似た感じだ。北方遊牧民を野蛮人と見下し、安禄山の兵を「西方イラン系や北方遊牧民族出身の異国人が多く、中国人に対しては情も容赦もない」と描いている。ウイグル族の闇商人を戦後日本の第三国人や第一次大戦後ドイツのユダヤ人の闇屋と重ねる表現もある。
とは言うものの、雄渾な歴史概説書である。
================
〔追記〕
上記の文章を書いて数日後、中公文庫版『大唐帝国』(1988.9.10初版
2018.8.25改版)を手にした。巻末に以下の編集部コメントが載っていた。
「本書には、今日の人権意識からみて不適切と思われる表現が使用されていますが、本書が書かれた時代背景、および著者が故人であることを考慮し、発表時のままとしました。(編集部)」
〔追記2〕
本書函カバーの人物、どこにも説明表記がない。唐の太宗、高宗、玄宗のいずれかと推測したが、違っていた。画像検索によって「西晋の初代皇帝・司馬炎(武帝)」と判明した。

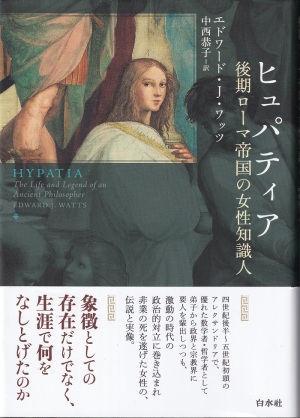

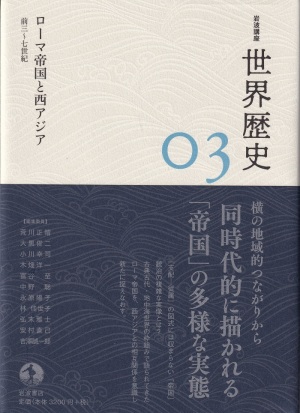



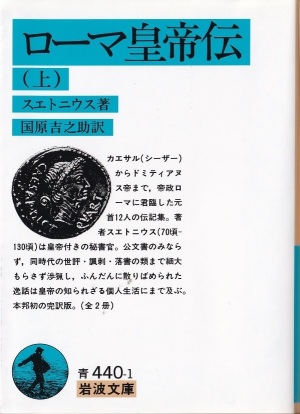


最近のコメント