中国古代史は故事・四字熟語のルーツ ― 2022年02月01日
私はシルクロードや中央ユーラシア史に関心があるのに、中国古代史は苦手だ。両者は深く関連しているので、中国古代史を敬遠し続けるわけにもいかず、『大唐帝国』(宮崎市定)を読んだのを機に次の概説書を読んだ。
『中華文明の誕生(世界の歴史2)』(尾形勇・平勢隆郎/中央公論社/1998.5)
本書は中国の新石器時代から三国時代までを扱い、2部構成になっている。王朝を羅列すれば以下の通りだ。
殷、周、東周、春秋戦国、秦、前漢、新、後漢、魏、蜀、呉
平勢氏執筆の第1部が春秋戦国まで、尾形氏執筆の第2部が秦以降になっている。
第1部はやや専門的な暦に関する議論が多く、私には難しかった。史書が記述する王の即位時期と暦に関する詳細な検討によって年号のズレを提示していて、スリリングだが十全には理解できなかった。歴史の実相を解明しようとする研究者の熱気が伝わってくる。史書に粉飾があるのはわかる。
第2部では古代史を叙述しつつ遺跡の現状も語っていて興味深い。始皇帝陵の地下の宮殿の発掘調査が行われていないのは、過去の記録からみて「盗掘ずみ」で何もないと推察されるからだそうだ。なるほどと思いつつも不思議な気がする。きっと、発掘するべき場所が他にも多いのだろう。
本書が扱う春秋戦国時代には数多くの国が存在する。戦国の七雄は秦、魏、趙、燕、斉、韓、楚で、その他にも晋、周、曹、鄭、衛、魯、宋、呉、越などイロイロあり、その位置や盛衰を歴史地図で確認するのは大変である。歴史書を読むとき、位置がわからない地名はなるべく地図で確認するよう心掛けている。もちろん、不明なときは読み飛ばす。
本書で、春秋戦国の国は「面(領域)」ではなく「点(都市)」と知って蒙を啓かれた。「点」の争奪戦なので飛び地もできる。地図上の「面」にこだわらない方がいいのである。
春秋戦国は諸氏百家の時代である。本書にも「奇貨居くべし」「鶏鳴狗盗」「宋襄の仁」「鼎の軽重」などの言葉が出てくる。多くの故事や四字熟語のルーツがこの時代にあると思い至り、春秋戦国への興味が少し高まった。
『中華文明の誕生(世界の歴史2)』(尾形勇・平勢隆郎/中央公論社/1998.5)
本書は中国の新石器時代から三国時代までを扱い、2部構成になっている。王朝を羅列すれば以下の通りだ。
殷、周、東周、春秋戦国、秦、前漢、新、後漢、魏、蜀、呉
平勢氏執筆の第1部が春秋戦国まで、尾形氏執筆の第2部が秦以降になっている。
第1部はやや専門的な暦に関する議論が多く、私には難しかった。史書が記述する王の即位時期と暦に関する詳細な検討によって年号のズレを提示していて、スリリングだが十全には理解できなかった。歴史の実相を解明しようとする研究者の熱気が伝わってくる。史書に粉飾があるのはわかる。
第2部では古代史を叙述しつつ遺跡の現状も語っていて興味深い。始皇帝陵の地下の宮殿の発掘調査が行われていないのは、過去の記録からみて「盗掘ずみ」で何もないと推察されるからだそうだ。なるほどと思いつつも不思議な気がする。きっと、発掘するべき場所が他にも多いのだろう。
本書が扱う春秋戦国時代には数多くの国が存在する。戦国の七雄は秦、魏、趙、燕、斉、韓、楚で、その他にも晋、周、曹、鄭、衛、魯、宋、呉、越などイロイロあり、その位置や盛衰を歴史地図で確認するのは大変である。歴史書を読むとき、位置がわからない地名はなるべく地図で確認するよう心掛けている。もちろん、不明なときは読み飛ばす。
本書で、春秋戦国の国は「面(領域)」ではなく「点(都市)」と知って蒙を啓かれた。「点」の争奪戦なので飛び地もできる。地図上の「面」にこだわらない方がいいのである。
春秋戦国は諸氏百家の時代である。本書にも「奇貨居くべし」「鶏鳴狗盗」「宋襄の仁」「鼎の軽重」などの言葉が出てくる。多くの故事や四字熟語のルーツがこの時代にあると思い至り、春秋戦国への興味が少し高まった。
中国と朝鮮のゴチャゴチャした時代の歴史を読んだ ― 2022年02月04日
『中華文明の誕生(世界の歴史2)』に続いて、時代がつながる次の巻を読んだ。
『隋唐帝国と古代朝鮮(世界の歴史6)』(礪波護・武田幸男/中央公論社/1997.1)
前半6割の西晋から唐までは礪波護氏が執筆、後半4割の朝鮮先史時代から新羅・渤海までは武田幸男氏が執筆している。
前半は先日読んだばかりの『大唐帝国』(宮崎市定)の時代と重なり、頭に入りやすい。後半の古代朝鮮史は私には未知の世界なので読むのに苦労した。
西晋から隋唐に至るまでの王朝は南北に分裂していて複雑だ。南は東晋、宋、斉、梁、陳、北は五胡十六国、北魏、東魏、西魏、北斉、北周と続き、隋が南北を統一する。似たような国名がゴチャゴチャ続く分裂時代を頭に入れるのは大変だ。受験生でなくてよかったと思う。
南北に分かれた時代、北は五胡(匈奴・鮮卑・羯・氐・羌)など北方遊牧民系の非漢族の王朝で、南は漢族系の王朝だ。南北を統一した隋唐は北の鮮卑族拓跋部だと知ったのは比較的最近で、それまで私は隋唐は漢族の王朝だと思っていた。
本書を読むと、この問題のややこしさがわかる。著者は初めの方で次のように述べている。
「隋王朝の皇室楊氏や唐王朝の皇室李氏が、はたして名門の漢族なのか、あるいは鮮卑族なのか、という問題については、後章であらためて取り上げる。」
確かに後章でいろいろな史実を紹介しているが、明解な結論を述べているようには思えない。隋や唐の皇室は漢族の名門貴族に連なっているようにふるまい、史書の書き換えなどもしている。周囲からはミエミエだったらしいが。
混血もあっただろうし、この時代に「民族」があったわけではない。民族はなくても貴族はあった。おのれの血統を高貴なものに粉飾する欲求は古代から連綿と続いているようだ。
本書後半の古代朝鮮史はややこしくて、あまり頭に入っていない。中国から流れてきた人々や地元の人々が織りなす歴史はかなり複雑だ。内部紛争と外圧が絡んだ合従連衡のくり返しはどの時代のどの地域でも共通の事象に思われる。
あらためて認識したのは、古代朝鮮が古代日本とかなり密接に絡まっていることだ。百済経由の仏教伝来や白村江の戦いの他にも興味深い話がいろいろある。日本の前方後円墳とそっくりの墓が、朝鮮の南部で10基あまり確認されているそうだ。
『隋唐帝国と古代朝鮮(世界の歴史6)』(礪波護・武田幸男/中央公論社/1997.1)
前半6割の西晋から唐までは礪波護氏が執筆、後半4割の朝鮮先史時代から新羅・渤海までは武田幸男氏が執筆している。
前半は先日読んだばかりの『大唐帝国』(宮崎市定)の時代と重なり、頭に入りやすい。後半の古代朝鮮史は私には未知の世界なので読むのに苦労した。
西晋から隋唐に至るまでの王朝は南北に分裂していて複雑だ。南は東晋、宋、斉、梁、陳、北は五胡十六国、北魏、東魏、西魏、北斉、北周と続き、隋が南北を統一する。似たような国名がゴチャゴチャ続く分裂時代を頭に入れるのは大変だ。受験生でなくてよかったと思う。
南北に分かれた時代、北は五胡(匈奴・鮮卑・羯・氐・羌)など北方遊牧民系の非漢族の王朝で、南は漢族系の王朝だ。南北を統一した隋唐は北の鮮卑族拓跋部だと知ったのは比較的最近で、それまで私は隋唐は漢族の王朝だと思っていた。
本書を読むと、この問題のややこしさがわかる。著者は初めの方で次のように述べている。
「隋王朝の皇室楊氏や唐王朝の皇室李氏が、はたして名門の漢族なのか、あるいは鮮卑族なのか、という問題については、後章であらためて取り上げる。」
確かに後章でいろいろな史実を紹介しているが、明解な結論を述べているようには思えない。隋や唐の皇室は漢族の名門貴族に連なっているようにふるまい、史書の書き換えなどもしている。周囲からはミエミエだったらしいが。
混血もあっただろうし、この時代に「民族」があったわけではない。民族はなくても貴族はあった。おのれの血統を高貴なものに粉飾する欲求は古代から連綿と続いているようだ。
本書後半の古代朝鮮史はややこしくて、あまり頭に入っていない。中国から流れてきた人々や地元の人々が織りなす歴史はかなり複雑だ。内部紛争と外圧が絡んだ合従連衡のくり返しはどの時代のどの地域でも共通の事象に思われる。
あらためて認識したのは、古代朝鮮が古代日本とかなり密接に絡まっていることだ。百済経由の仏教伝来や白村江の戦いの他にも興味深い話がいろいろある。日本の前方後円墳とそっくりの墓が、朝鮮の南部で10基あまり確認されているそうだ。
『暁の宇品』は、やはり傑作だった ― 2022年02月07日
大佛次郎賞を昨年末に受賞した次の作品を読んだ。
『暁の宇品:陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』(堀川恵子/講談社)
作者の堀川恵子氏はノンフィクション賞総ナメの作家である。私は10年近く前に『永山則夫:封印された鑑定記録』を読んで感動したが、他の作品は未読で、本書が2冊目になる。評判通りの傑作だった。
本書を読むまで「宇品」という地名も「陸軍船舶司令部」の存在も「暁部隊」なる名称も知らなかった。本書によってこれら未知の事項を知った。だが、新たな知見を得たのが収穫ではない。そんなことを超えた面白さが本書にある。
かつての陸軍には兵士・兵器・物資の海上輸送を担当する部署があった。海軍は輸送の護衛をするだけで、船舶の調達・輸送・上陸作戦などは陸軍の仕事だった。海外に兵士を送り出す拠点が広島市の港湾地区・宇品で、輸送を統括したのが陸軍船舶司令部である。陸軍の船舶部隊は暁部隊と呼ばれていた。
この船舶部隊を扱った本書は日本軍の弱点と言われた兵站の話であり、日本軍の失敗の記録である。失敗の事情や原因を指摘する本は多い。本書もその一つかもしれないが、失敗を避けようと奮闘した忘れられた人物を掘り起こした物語である。かなり感動する。それだけでなく、この物語は「なぜ原爆は広島に落とされたのか」という問いへのひとつの回答になっている。さらに、原爆投下直後の宇品の司令官の「異常に適格な救援活動」の謎も解明している。何重にも絡まった謎を解き明かすスリリングなノンフィクションである。
本書を読んであらためて認識したのは、戦争とはとてつもなく大変で複雑な巨大プロジェクトであり、それを遂行するには入念で詳細な段取りが必要だということである。安易に始めてナントカナルものではない。もちろん、入念に準備をすれば開戦していいという話ではない。戦争遂行の詳細を冷静に推測すれば、おのずと戦争を避けるという選択になると信じたい。それが理性だと思う。
『暁の宇品:陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』(堀川恵子/講談社)
作者の堀川恵子氏はノンフィクション賞総ナメの作家である。私は10年近く前に『永山則夫:封印された鑑定記録』を読んで感動したが、他の作品は未読で、本書が2冊目になる。評判通りの傑作だった。
本書を読むまで「宇品」という地名も「陸軍船舶司令部」の存在も「暁部隊」なる名称も知らなかった。本書によってこれら未知の事項を知った。だが、新たな知見を得たのが収穫ではない。そんなことを超えた面白さが本書にある。
かつての陸軍には兵士・兵器・物資の海上輸送を担当する部署があった。海軍は輸送の護衛をするだけで、船舶の調達・輸送・上陸作戦などは陸軍の仕事だった。海外に兵士を送り出す拠点が広島市の港湾地区・宇品で、輸送を統括したのが陸軍船舶司令部である。陸軍の船舶部隊は暁部隊と呼ばれていた。
この船舶部隊を扱った本書は日本軍の弱点と言われた兵站の話であり、日本軍の失敗の記録である。失敗の事情や原因を指摘する本は多い。本書もその一つかもしれないが、失敗を避けようと奮闘した忘れられた人物を掘り起こした物語である。かなり感動する。それだけでなく、この物語は「なぜ原爆は広島に落とされたのか」という問いへのひとつの回答になっている。さらに、原爆投下直後の宇品の司令官の「異常に適格な救援活動」の謎も解明している。何重にも絡まった謎を解き明かすスリリングなノンフィクションである。
本書を読んであらためて認識したのは、戦争とはとてつもなく大変で複雑な巨大プロジェクトであり、それを遂行するには入念で詳細な段取りが必要だということである。安易に始めてナントカナルものではない。もちろん、入念に準備をすれば開戦していいという話ではない。戦争遂行の詳細を冷静に推測すれば、おのずと戦争を避けるという選択になると信じたい。それが理性だと思う。
日本が開発した上陸用舟艇「大発」 ― 2022年02月09日
先日読んだ
『暁の宇品』には陸軍船舶司令部の技術者たちが上陸用舟艇を開発する話が出てくる。従来、兵士や物資を輸送船から海岸に陸揚げするには手漕ぎの木舟を使っていた。これをエンジン付きの鉄舟に転換する開発である。
そして大発(大発動艇)が完成し、1932年の上海事変で初めて実戦に使用される。これは「鉄製の自走舟艇を主力に使っての師団規模の上陸作戦としては世界初の成功例」として世界の軍事関係者の関心を集めた。米国海軍情報部は「日本は艦隊から海岸の攻撃要領を完全に開発した最初の大国」と認めていたそうだ。
意外な話だった。上陸用舟艇と言えば映画「史上最大の作戦」のノルマンジー上陸の映像が頭に浮かび、やはり米国軍の装備はスゴイという印象を抱いていた。しかし、太平洋戦争開戦前の時点では日本の技術が米国を凌駕していたのだ。『暁の宇品』の著者は「このとき(1939年頃)が頂点であった」と述べている。
大発とはどんな船だったのだろうと興味を抱き、ネット検索し、いくつかの写真を見た。そして、ハッとした。私は13年前に大発の残骸の実物を見たことがあったのだ。
2009年1月、パプアニューギニアの ラバウルを訪問し、戦跡を巡った。戦車やゼロ戦の残骸が印象に残っている。あのとき、海岸の洞穴に残された鉄製の小さな船舶の残骸も見た。それが大発だったのだ。当時は、この船の用途も知らず「みすぼらしい船だなあ。こんな小さな船で戦っていたのか」と思った。あの船が一時は世界先端だったとは驚きである。13年前に撮影した写真を引っぱりだし、感慨を新たにした。
そして大発(大発動艇)が完成し、1932年の上海事変で初めて実戦に使用される。これは「鉄製の自走舟艇を主力に使っての師団規模の上陸作戦としては世界初の成功例」として世界の軍事関係者の関心を集めた。米国海軍情報部は「日本は艦隊から海岸の攻撃要領を完全に開発した最初の大国」と認めていたそうだ。
意外な話だった。上陸用舟艇と言えば映画「史上最大の作戦」のノルマンジー上陸の映像が頭に浮かび、やはり米国軍の装備はスゴイという印象を抱いていた。しかし、太平洋戦争開戦前の時点では日本の技術が米国を凌駕していたのだ。『暁の宇品』の著者は「このとき(1939年頃)が頂点であった」と述べている。
大発とはどんな船だったのだろうと興味を抱き、ネット検索し、いくつかの写真を見た。そして、ハッとした。私は13年前に大発の残骸の実物を見たことがあったのだ。
2009年1月、パプアニューギニアの ラバウルを訪問し、戦跡を巡った。戦車やゼロ戦の残骸が印象に残っている。あのとき、海岸の洞穴に残された鉄製の小さな船舶の残骸も見た。それが大発だったのだ。当時は、この船の用途も知らず「みすぼらしい船だなあ。こんな小さな船で戦っていたのか」と思った。あの船が一時は世界先端だったとは驚きである。13年前に撮影した写真を引っぱりだし、感慨を新たにした。
大河ドラマの時代考証降板の呉座勇一の『頼朝と義時』 ― 2022年02月11日
NHKの大河ドラマは滅多に観ないが、先月から始まった『鎌倉殿の13人』は観ている。初回だけと思って観たのがコミカルな面白さに惹かれ、つい観続けている。鎌倉時代に特に関心はなく、さほどの知識もない。で、次の新書を読んだ。
『頼朝と義時:武家政権の誕生』(呉座勇一/講談社現代新書)
著者は数年前のベストセラー 『応仁の乱』 で有名な若手研究者だ。本書「あとがき」で驚いた。呉座勇一氏は『鎌倉殿の13人』の時代考証依頼がきっかけで本書を執筆、「不祥事」で時代考証を降板したそうだ。「あとがき」で次のように述べている。
〔本書執筆の最中、私の愚行により『鎌倉殿の13人』の時代考証を降板することになった。多くの方の心を傷つけ、多くの関係者にご迷惑をかけた以上、本書の刊行を断念することも考えた。〕
何があったのだろうと野次馬気分でネット検索した。表面的なことしかわからないが、研究者たちの狭いSNSで誹謗・イジメのようなことがあったようだ。人間社会は十年一日いや千年一日である。
閑話休題。本書によって頼朝と義時をクローズアップする意味がわかり、あらためてこの時代の面白さを知った。貴族の世が武士の時代が変わる歴史変動の物語である。次の記述が印象的だ。
〔源頼朝は鎌倉幕府を築いたが、頼朝の自己規制によって幕府は朝廷の下部機関に留まった。朝廷と幕府の力関係を劇的に転換させるには、もう一人の人物が必要だった。それが北条義時である。〕
半世紀以上昔の受験勉強の頃から北条氏の執権の似たような名前に悩まされ、頭の中でゴチャゴチャしていた。本書によって義時を何とか識別できるようになった。
だが、大河ドラマへの新たな疑念がわいた。「13人」にウエイトを置くのだろうか。有力御家人13人の合議制は、本書を読む限りではさほどの意義はない。
むしろ気になるのは源実朝である。本書は実朝を傀儡以上に評価をしている。大河ドラマ後半の重要人物になってしかるべきだと思う。頼朝と政子の子、頼家・大姫の役者は発表されているのに、なぜか実朝が抜けている。まったくの脇役扱いになるのだろうか。かつて、太宰治・小林秀雄・吉本隆明らが魅力的に描いた実朝を三谷幸喜はあえてスルーするのか、気がかりである。
『頼朝と義時:武家政権の誕生』(呉座勇一/講談社現代新書)
著者は数年前のベストセラー 『応仁の乱』 で有名な若手研究者だ。本書「あとがき」で驚いた。呉座勇一氏は『鎌倉殿の13人』の時代考証依頼がきっかけで本書を執筆、「不祥事」で時代考証を降板したそうだ。「あとがき」で次のように述べている。
〔本書執筆の最中、私の愚行により『鎌倉殿の13人』の時代考証を降板することになった。多くの方の心を傷つけ、多くの関係者にご迷惑をかけた以上、本書の刊行を断念することも考えた。〕
何があったのだろうと野次馬気分でネット検索した。表面的なことしかわからないが、研究者たちの狭いSNSで誹謗・イジメのようなことがあったようだ。人間社会は十年一日いや千年一日である。
閑話休題。本書によって頼朝と義時をクローズアップする意味がわかり、あらためてこの時代の面白さを知った。貴族の世が武士の時代が変わる歴史変動の物語である。次の記述が印象的だ。
〔源頼朝は鎌倉幕府を築いたが、頼朝の自己規制によって幕府は朝廷の下部機関に留まった。朝廷と幕府の力関係を劇的に転換させるには、もう一人の人物が必要だった。それが北条義時である。〕
半世紀以上昔の受験勉強の頃から北条氏の執権の似たような名前に悩まされ、頭の中でゴチャゴチャしていた。本書によって義時を何とか識別できるようになった。
だが、大河ドラマへの新たな疑念がわいた。「13人」にウエイトを置くのだろうか。有力御家人13人の合議制は、本書を読む限りではさほどの意義はない。
むしろ気になるのは源実朝である。本書は実朝を傀儡以上に評価をしている。大河ドラマ後半の重要人物になってしかるべきだと思う。頼朝と政子の子、頼家・大姫の役者は発表されているのに、なぜか実朝が抜けている。まったくの脇役扱いになるのだろうか。かつて、太宰治・小林秀雄・吉本隆明らが魅力的に描いた実朝を三谷幸喜はあえてスルーするのか、気がかりである。
『中国のあけぼの(世界の歴史3)』を読んで想起したこと ― 2022年02月13日
このところ、中国史を何冊か読んで頭が中国史モードになっている。この機に、未読だった古い概説書を読んだ。
『中国のあけぼの(世界の歴史3)』(貝塚茂樹/河出書房/1968.5)
先日読んだ『大唐帝国(世界の歴史7)』の前の時代、先史時代から漢滅亡までを扱った巻である。読んだばかりの『中華文明の誕生(中公版・世界の歴史2)』と重なるので頭に入りやすかった。
著者は高名な貝塚茂樹となっているが、冒頭約40ページが貝塚茂樹の執筆で、大半は大島利一の執筆である。本書の河出文庫版は貝塚茂樹・大島利一共著になっている。
春秋戦国の歴史は、やはり面白い。東西南北に散在するさまざまな小国がせめぎ合うなかで、田舎の秦が台頭して統一をはたす物語である。秦から漢へ移行する混乱期の劉邦・項羽の話も面白い。この時代が虚実不明の有名エピソードにあふれているのも面白さの一因である。漢字文化圏の故事来歴物語の趣に惹かれてしまう。
本書刊行の1968年、中国は文化革命の最中、日本では学園闘争まっさかりだった。本書を読んでいて、ふいに故・高橋和巳を想起する場面が2ヵ所あった。
一つは『わが心は石にあらず』だ。高橋和巳がこの長編のタイトルを中国の詩から取っているとは知っていたが、それ以上の知識はなかった。本書で「わが心は石にあらねば、転がすべからず、わが心は席(むしろ)にあらねば、巻くべからず」の引用に出会い、このタイトルの意味を誤解していたと感じた。作者が女性だと知って驚いた。
もう一つは「党錮の禍」である。本書挟み込みの月報には京大助教授・高橋和巳の「党錮の禍」に関する解説的エッセイが載っている。本文を読む前に月報を読み、何やらゴチャゴチャした出来事だなと思った。要は宦官と反宦官官僚との争いである。本文の「党錮の禍」の箇所を読んでいて「清流」「濁流」という言葉に出会い、ハッとした。高橋和巳が『わが解体』で苦しげに述べた「清宮教授」という言葉を連想したのだ。調べてみると「清宮」「濁宮」は清末の言葉だから直接の関連はない。
連想ついでに年譜を調べてみた。月報にエッセイを寄せた本書刊行が1968年5月、その翌年の『文芸』1969年6月号から3回にわたって『わが解体』を連載し、1970年3月に京大助教授を辞職している。逝去は1年後の1971年5月、享年39歳だった。
本書の内容とはほとんど関係ないが、本書がきっかけでそんな昔日を思い出した。
『中国のあけぼの(世界の歴史3)』(貝塚茂樹/河出書房/1968.5)
先日読んだ『大唐帝国(世界の歴史7)』の前の時代、先史時代から漢滅亡までを扱った巻である。読んだばかりの『中華文明の誕生(中公版・世界の歴史2)』と重なるので頭に入りやすかった。
著者は高名な貝塚茂樹となっているが、冒頭約40ページが貝塚茂樹の執筆で、大半は大島利一の執筆である。本書の河出文庫版は貝塚茂樹・大島利一共著になっている。
春秋戦国の歴史は、やはり面白い。東西南北に散在するさまざまな小国がせめぎ合うなかで、田舎の秦が台頭して統一をはたす物語である。秦から漢へ移行する混乱期の劉邦・項羽の話も面白い。この時代が虚実不明の有名エピソードにあふれているのも面白さの一因である。漢字文化圏の故事来歴物語の趣に惹かれてしまう。
本書刊行の1968年、中国は文化革命の最中、日本では学園闘争まっさかりだった。本書を読んでいて、ふいに故・高橋和巳を想起する場面が2ヵ所あった。
一つは『わが心は石にあらず』だ。高橋和巳がこの長編のタイトルを中国の詩から取っているとは知っていたが、それ以上の知識はなかった。本書で「わが心は石にあらねば、転がすべからず、わが心は席(むしろ)にあらねば、巻くべからず」の引用に出会い、このタイトルの意味を誤解していたと感じた。作者が女性だと知って驚いた。
もう一つは「党錮の禍」である。本書挟み込みの月報には京大助教授・高橋和巳の「党錮の禍」に関する解説的エッセイが載っている。本文を読む前に月報を読み、何やらゴチャゴチャした出来事だなと思った。要は宦官と反宦官官僚との争いである。本文の「党錮の禍」の箇所を読んでいて「清流」「濁流」という言葉に出会い、ハッとした。高橋和巳が『わが解体』で苦しげに述べた「清宮教授」という言葉を連想したのだ。調べてみると「清宮」「濁宮」は清末の言葉だから直接の関連はない。
連想ついでに年譜を調べてみた。月報にエッセイを寄せた本書刊行が1968年5月、その翌年の『文芸』1969年6月号から3回にわたって『わが解体』を連載し、1970年3月に京大助教授を辞職している。逝去は1年後の1971年5月、享年39歳だった。
本書の内容とはほとんど関係ないが、本書がきっかけでそんな昔日を思い出した。
『史記』のサワリを撫でてみた ― 2022年02月15日
中国古代史の概説書を読んでいると『史記』の重要性を感じざるを得ない。しかし私は、いまのところ『史記』に挑戦する気力はない。で、手軽そうな次の新書を読んだ。
『史記:中国古代の人びと』(貝塚茂樹/中公新書)
初版は1963年5月と古い。手元にあるのは2004年5月の75版だ。予想以上に面白かった。著者は「まえがき」で次のように述べている。
〔この本は史記の抄訳、それも思いきった現代語訳であると同時に、司馬遷がぼんやりと微妙な形で表現した歴史観に近代的な照明をあたえることによって解釈をほどこそうとするものである。〕
まさに、この宣言通りの内容だった。「思いきった現代語訳」でサワリを紹介しながら、わかりやすい解説を展開している。碩学の闊達な座談を拝聴している気分になる。
大史令だった司馬遷は李陵の禍で宮刑(去勢で宦官にされる)に処せられる。それでも『史記』を書き続ける。本書の冒頭は、そんな司馬遷の真情を綴った「ある死刑囚にあたえる手紙」の紹介である。迫力ある内容に引き込まれた。
司馬遷像を表す手紙の紹介に続いて、史記本文の解説になる。史記の全貌は巻末の「史記全巻名」一覧表で紹介している。全130巻(12本紀、8書、10表、30世家、70列伝)の題名のリストである。本書で扱った巻には*がついている。それは、3本紀、1表、3世家、15列伝で計22巻となる。
どの紹介も興味深いが、商鞅・蘇秦・孟嘗君・陳勝などの話が面白い。史記は歴史に残る有名人を記述した書と思っていたが、循吏列伝・游陜列伝・貨殖列伝・酷吏列伝などでは庶民に近い人物を描いている。これらの列伝は、その題名の意味を想像するだけでも不思議な気分になる。史記には社会史や経済史の要素もあるようだ。
本書で史記のサワリを知ったうえで巻末の全130巻のリストを眺めると、史記の大きさを多少は感得した気分になる。
『史記:中国古代の人びと』(貝塚茂樹/中公新書)
初版は1963年5月と古い。手元にあるのは2004年5月の75版だ。予想以上に面白かった。著者は「まえがき」で次のように述べている。
〔この本は史記の抄訳、それも思いきった現代語訳であると同時に、司馬遷がぼんやりと微妙な形で表現した歴史観に近代的な照明をあたえることによって解釈をほどこそうとするものである。〕
まさに、この宣言通りの内容だった。「思いきった現代語訳」でサワリを紹介しながら、わかりやすい解説を展開している。碩学の闊達な座談を拝聴している気分になる。
大史令だった司馬遷は李陵の禍で宮刑(去勢で宦官にされる)に処せられる。それでも『史記』を書き続ける。本書の冒頭は、そんな司馬遷の真情を綴った「ある死刑囚にあたえる手紙」の紹介である。迫力ある内容に引き込まれた。
司馬遷像を表す手紙の紹介に続いて、史記本文の解説になる。史記の全貌は巻末の「史記全巻名」一覧表で紹介している。全130巻(12本紀、8書、10表、30世家、70列伝)の題名のリストである。本書で扱った巻には*がついている。それは、3本紀、1表、3世家、15列伝で計22巻となる。
どの紹介も興味深いが、商鞅・蘇秦・孟嘗君・陳勝などの話が面白い。史記は歴史に残る有名人を記述した書と思っていたが、循吏列伝・游陜列伝・貨殖列伝・酷吏列伝などでは庶民に近い人物を描いている。これらの列伝は、その題名の意味を想像するだけでも不思議な気分になる。史記には社会史や経済史の要素もあるようだ。
本書で史記のサワリを知ったうえで巻末の全130巻のリストを眺めると、史記の大きさを多少は感得した気分になる。
半世紀ぶりに読了した『司馬遷 史記の世界』は気迫の作品 ― 2022年02月17日
貝塚茂樹の『史記』(中公新書)で、冒頭の司馬遷の手紙の部分を読んでいて、かすかなデジャブがわいた。やがて、それが武田泰淳だと思い至った。
若い頃、武田泰淳の小説何編かを興味深く読んだ。彼の重要作品が『司馬遷 史記の世界』だと知り、入手して読み始めたが、あえなく挫折した。冒頭の印象深いフレーズ「司馬遷は生き恥をさらした男である」だけが半世紀を経ても残っている。
貝塚茂樹が冒頭で紹介した「手紙」は、武田泰淳も冒頭で引用していた。そんな記憶が少しよみがえり、書架の奥から探し出した古い本に、あらためてチャレンジした。
『司馬遷 史記の世界』(武田泰淳/講談社)
本書には自序が六つ載っている。初版刊行は著者31歳の戦時中だ。後に何度も改版され、そのつど自序を追加している。自序の日付を古い順に示すと「昭和17年12月」「昭和23年6月末日」「昭和27年6月16日」「昭和34年1月10日」「昭和35年12月」「1965年」となる。読み継がれる名著の証だと思う。
半世紀ぶりに手にした本書、今回は何とか読了した。事前に多少ながらも史記のサワリに触れていたので興味が持続し、読み進めることができた。かなり難儀だった。
「第1篇 司馬遷傳」はともかく、メインの「第2篇「史記」の世界構造」は読みやすくはない。史記が表現する世界を縦横に論じていて、史記の概要が頭に入っていないと論についていくのが難しい。
だから、本書を理解したと言えない。だが、面白さは感じ取れた。気負った奔放な文体から、学者ではなく作家の貌が見える。何かを目指して飛翔する思考を巧みなレトリックで追いかける文章である。
武田泰淳が史記に託して追究しているのは「世界」把握だ。歴史を時間だけでなく空間として捉え、中心と周縁のせめぎあいを、人間主体に追究する――よくはわからないが、そんな論述の書である。果敢に挑戦する若気の気迫が伝わってくる。
若い頃、武田泰淳の小説何編かを興味深く読んだ。彼の重要作品が『司馬遷 史記の世界』だと知り、入手して読み始めたが、あえなく挫折した。冒頭の印象深いフレーズ「司馬遷は生き恥をさらした男である」だけが半世紀を経ても残っている。
貝塚茂樹が冒頭で紹介した「手紙」は、武田泰淳も冒頭で引用していた。そんな記憶が少しよみがえり、書架の奥から探し出した古い本に、あらためてチャレンジした。
『司馬遷 史記の世界』(武田泰淳/講談社)
本書には自序が六つ載っている。初版刊行は著者31歳の戦時中だ。後に何度も改版され、そのつど自序を追加している。自序の日付を古い順に示すと「昭和17年12月」「昭和23年6月末日」「昭和27年6月16日」「昭和34年1月10日」「昭和35年12月」「1965年」となる。読み継がれる名著の証だと思う。
半世紀ぶりに手にした本書、今回は何とか読了した。事前に多少ながらも史記のサワリに触れていたので興味が持続し、読み進めることができた。かなり難儀だった。
「第1篇 司馬遷傳」はともかく、メインの「第2篇「史記」の世界構造」は読みやすくはない。史記が表現する世界を縦横に論じていて、史記の概要が頭に入っていないと論についていくのが難しい。
だから、本書を理解したと言えない。だが、面白さは感じ取れた。気負った奔放な文体から、学者ではなく作家の貌が見える。何かを目指して飛翔する思考を巧みなレトリックで追いかける文章である。
武田泰淳が史記に託して追究しているのは「世界」把握だ。歴史を時間だけでなく空間として捉え、中心と周縁のせめぎあいを、人間主体に追究する――よくはわからないが、そんな論述の書である。果敢に挑戦する若気の気迫が伝わってくる。
張騫は司馬遷の親の世代の人 ― 2022年02月19日
中国史の本を続けて読んでいて、積ん読になっていた次の本も読んだ。
『張騫とシルクロード』(長沢和俊/清水書院)
前半は張騫の伝記、後半は張騫が開いたシルクロード概説だ。漢の時代のシルクロードがメインで、最盛期の唐までは射程に入れていない。4世紀頃までの西域史である。
最近読んだ中国古代史の概説書で前漢・新・後漢の姿が多少はくっきりしてきたが、漢人中心の歴史概説だから北方や西方の様子がぼやける。本書は匈奴や鮮卑の動向を描く西域史で、中国古代史を補完できた。
張騫は前漢・武帝の時代の人である。司馬遷も武帝の時代だ。二人とも正確な生年は不明だが、張騫は司馬遷より一世代ほど上のようだ。張騫が西域へ旅立ったのは、おそらく司馬遷が生まれた頃で、『史記』執筆時にはすでに張騫は没している。張騫の事績は司馬遷の『史記・大宛列伝』によって後世に伝わっている。
千年を越える太古以降の歴史を描いた『史記』が、伝説も含めた過去の記録の集成であると同時に、司馬遷が生きた同時代史でもあると気づいた。スゴイと思う。
張騫は武帝の命で、対・匈奴の連衡交渉のため大月氏(ソグディアナ)へ旅立つ。往路で匈奴の虜囚として十年、帰路でも匈奴の虜囚として1年余りを過ごし、13年にわたる旅になった。百余人で出発して帰ってきたのは二人、ただし虜囚時代に得た匈奴の妻も同行していた。著者の次の記述が印象深い。
「張騫は身体は大きく、その性格は寛大で人を信じ、その性格は蛮夷もこれを愛するほどであった。彼が胡妻をつれ帰ったということは、その温かい人となりをよく物語っている。」
帰国後は重用されるも、いろいろあり、さらなる西域への遣使も勤める。著者は張騫を次のように総括している。
「張騫の生涯は派手ではあるが華やかではなく。自らは報いられることあまりに少ない晩年であった。(…)彼の遣使は、直接の目的は達成できなかったものの、それから引き起こされた第二義的な影響は、また実に大きかった。(…)やがて西域、とくに西トルキスタン諸国との、はなやかな東西交易が開花してゆくのである。」
現在、張騫は切手になり、世界遺産シルクロードの起点に銅像が立っているそうだ。
『張騫とシルクロード』(長沢和俊/清水書院)
前半は張騫の伝記、後半は張騫が開いたシルクロード概説だ。漢の時代のシルクロードがメインで、最盛期の唐までは射程に入れていない。4世紀頃までの西域史である。
最近読んだ中国古代史の概説書で前漢・新・後漢の姿が多少はくっきりしてきたが、漢人中心の歴史概説だから北方や西方の様子がぼやける。本書は匈奴や鮮卑の動向を描く西域史で、中国古代史を補完できた。
張騫は前漢・武帝の時代の人である。司馬遷も武帝の時代だ。二人とも正確な生年は不明だが、張騫は司馬遷より一世代ほど上のようだ。張騫が西域へ旅立ったのは、おそらく司馬遷が生まれた頃で、『史記』執筆時にはすでに張騫は没している。張騫の事績は司馬遷の『史記・大宛列伝』によって後世に伝わっている。
千年を越える太古以降の歴史を描いた『史記』が、伝説も含めた過去の記録の集成であると同時に、司馬遷が生きた同時代史でもあると気づいた。スゴイと思う。
張騫は武帝の命で、対・匈奴の連衡交渉のため大月氏(ソグディアナ)へ旅立つ。往路で匈奴の虜囚として十年、帰路でも匈奴の虜囚として1年余りを過ごし、13年にわたる旅になった。百余人で出発して帰ってきたのは二人、ただし虜囚時代に得た匈奴の妻も同行していた。著者の次の記述が印象深い。
「張騫は身体は大きく、その性格は寛大で人を信じ、その性格は蛮夷もこれを愛するほどであった。彼が胡妻をつれ帰ったということは、その温かい人となりをよく物語っている。」
帰国後は重用されるも、いろいろあり、さらなる西域への遣使も勤める。著者は張騫を次のように総括している。
「張騫の生涯は派手ではあるが華やかではなく。自らは報いられることあまりに少ない晩年であった。(…)彼の遣使は、直接の目的は達成できなかったものの、それから引き起こされた第二義的な影響は、また実に大きかった。(…)やがて西域、とくに西トルキスタン諸国との、はなやかな東西交易が開花してゆくのである。」
現在、張騫は切手になり、世界遺産シルクロードの起点に銅像が立っているそうだ。
シルクロード史は中国史の補完になる ― 2022年02月21日
『張騫とシルクロード』に続いて、同じ著者の次の本を読んだ。
『シルクロードの文化と日本』(長澤和俊/雄山閣/1983.12)
約40年前の1980年代初頭からNHKが放映した大型番組『シルクロード』はシルクロード・ブームを引き起こした。長澤和俊(2019年没、享年90歳)はこの番組の委員を務めたシルクロード研究者だ。本書はテレビ番組がきっかけで執筆したそうだ。
タイトルが示しているように、シルクロードが日本文化にどのような影響を与えているかを概説した書だが、シルクロード全般の解説が叙述のメインである。それをふまえて日本文化への影響を考察している。
シルクロードを大きく捉えると「草原の道」「オアシスの道」「海上の道」となり、それが栄えた時代は概ねこの順番になる。本書はそのすべてを概説しているが、最も詳細に述べているのは「オアシスの道」であり、それは西域史でもある。
直前に読んだ『張騫とシルクロード』が漢の時代までの西域史だったが、本書は魏晋南北朝から隋唐に至る時代の西域をかなり詳しく解説していて、中国史の補完になる。
イスラムの台頭によるササン朝の滅亡が、長安の西域ブームに大きく寄与しているとの指摘に、世界史のダイナミズムを感じた。本書ではソグド商人をかなり詳しく取り上げている。私がソグド人を知ったのは比較的最近だが、40年近く前の一般向け概説書に明解な解説があったのだ。あらてめて自分が勉強不足だったと感じた。
日本文化へのシルクロードの影響というテーマは茫漠としていて大きい。著者は、江上波夫の「日本古代王朝=騎馬民族説」の検討をふまえて、天皇家による古代日本国家の成立こそが、シルクロード(草原の道)が日本文化におよぼした最初の文化的影響だと述べている。壮大な影響であり、シルクロードが歴史そのものに思えてくる。
『シルクロードの文化と日本』(長澤和俊/雄山閣/1983.12)
約40年前の1980年代初頭からNHKが放映した大型番組『シルクロード』はシルクロード・ブームを引き起こした。長澤和俊(2019年没、享年90歳)はこの番組の委員を務めたシルクロード研究者だ。本書はテレビ番組がきっかけで執筆したそうだ。
タイトルが示しているように、シルクロードが日本文化にどのような影響を与えているかを概説した書だが、シルクロード全般の解説が叙述のメインである。それをふまえて日本文化への影響を考察している。
シルクロードを大きく捉えると「草原の道」「オアシスの道」「海上の道」となり、それが栄えた時代は概ねこの順番になる。本書はそのすべてを概説しているが、最も詳細に述べているのは「オアシスの道」であり、それは西域史でもある。
直前に読んだ『張騫とシルクロード』が漢の時代までの西域史だったが、本書は魏晋南北朝から隋唐に至る時代の西域をかなり詳しく解説していて、中国史の補完になる。
イスラムの台頭によるササン朝の滅亡が、長安の西域ブームに大きく寄与しているとの指摘に、世界史のダイナミズムを感じた。本書ではソグド商人をかなり詳しく取り上げている。私がソグド人を知ったのは比較的最近だが、40年近く前の一般向け概説書に明解な解説があったのだ。あらてめて自分が勉強不足だったと感じた。
日本文化へのシルクロードの影響というテーマは茫漠としていて大きい。著者は、江上波夫の「日本古代王朝=騎馬民族説」の検討をふまえて、天皇家による古代日本国家の成立こそが、シルクロード(草原の道)が日本文化におよぼした最初の文化的影響だと述べている。壮大な影響であり、シルクロードが歴史そのものに思えてくる。
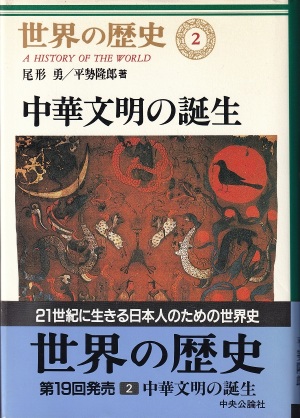
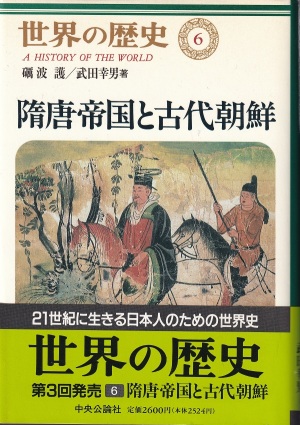
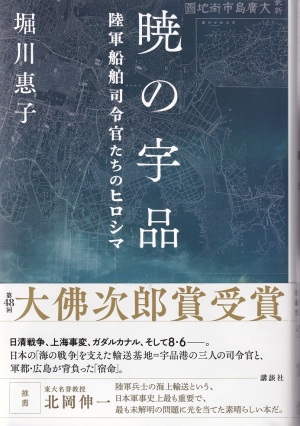


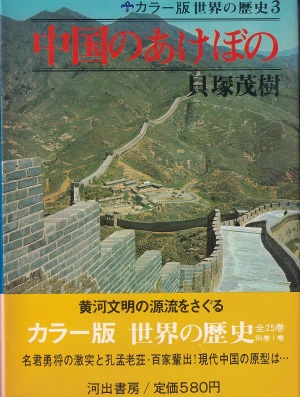
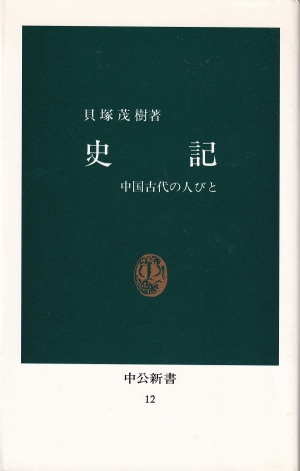

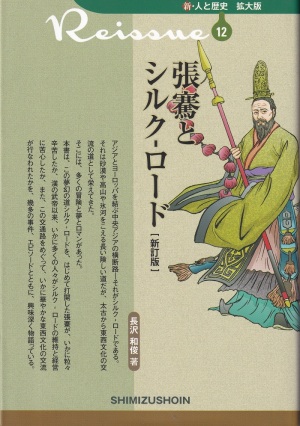
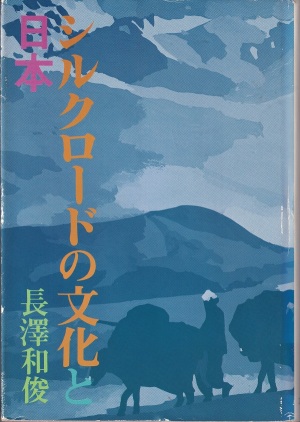
最近のコメント