面白いけどややこしい『人類の起源』 ― 2022年12月10日
今年のノーベル生理学・医学賞は「古ゲノム学」という新たな学問分野を切り開いたスバンテ・ペーボ博士が選ばれた。ノーベル賞発表の半年以上前に出た本書は「古ゲノム学」の最新の成果を紹介している。ノーベル賞効果もあり、よく売れているらしい。
『人類の起源:古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』(篠田謙一/中公新書)
本書は最新の知見に基づいた人類の起源の概説書だが、それ以上に最近のさまざまな古代ゲノム解析の結果を紹介する報告書である。著者自身が研究の当事者なので、研究の最前線の様子が伝わってきて興味深い。ただし、その内容はかなりややこしくて一読では十分に理解できない。
本書で私が初めて知ったのは、DNAを高速で解読できる「次世代シークエンサ」なる新技術である。2006年頃から実用化され、これによって研究が飛躍的に進展したそうだ。
発掘された古代人のDNA(サンプルに含まれるすべてのDNA)の解読が可能になり、2010年にはネアンデルタール人の持つすべてのDNAが解読できた。世界各地で発掘された多くの化石のDNAを解読すれば、さまざまな集団の移動・混合・置換え・消滅などが明らかになる。いま、まさにそんな研究が活況を呈しているそうだ。と言っても、研究にはいろいろな制約や困難があるようだ。
古代人だけでなく現代人のDNAも研究対象である。私が十分に理解できているわけではないが、DNAには過去から現在までの変異が刻印されているのだ。生物の不思議を感じる。
十分の咀嚼できていない本書で私が感じたのは、人類の起源と進化の歴史は単純ではないということである。猿人→原人→旧人→新人という進化はわかりやすい。大筋で間違いではないかもしれないが、その実態はかなりややこしいようだ。限られた材料をベースに推測している段階では、すっきりしたわかりやすいモデルが構築可能である。しかし、材料が増えてくるとシンプルなモデルでは捉えられない事象が出てくる。おそらく、この世界の実相はとても複雑なのだと思う。複雑な事象の説明を試みると難解になりやすい。
古代ゲノム学は、そんな状況なあるのだろうという感想を抱いた。
『人類の起源:古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』(篠田謙一/中公新書)
本書は最新の知見に基づいた人類の起源の概説書だが、それ以上に最近のさまざまな古代ゲノム解析の結果を紹介する報告書である。著者自身が研究の当事者なので、研究の最前線の様子が伝わってきて興味深い。ただし、その内容はかなりややこしくて一読では十分に理解できない。
本書で私が初めて知ったのは、DNAを高速で解読できる「次世代シークエンサ」なる新技術である。2006年頃から実用化され、これによって研究が飛躍的に進展したそうだ。
発掘された古代人のDNA(サンプルに含まれるすべてのDNA)の解読が可能になり、2010年にはネアンデルタール人の持つすべてのDNAが解読できた。世界各地で発掘された多くの化石のDNAを解読すれば、さまざまな集団の移動・混合・置換え・消滅などが明らかになる。いま、まさにそんな研究が活況を呈しているそうだ。と言っても、研究にはいろいろな制約や困難があるようだ。
古代人だけでなく現代人のDNAも研究対象である。私が十分に理解できているわけではないが、DNAには過去から現在までの変異が刻印されているのだ。生物の不思議を感じる。
十分の咀嚼できていない本書で私が感じたのは、人類の起源と進化の歴史は単純ではないということである。猿人→原人→旧人→新人という進化はわかりやすい。大筋で間違いではないかもしれないが、その実態はかなりややこしいようだ。限られた材料をベースに推測している段階では、すっきりしたわかりやすいモデルが構築可能である。しかし、材料が増えてくるとシンプルなモデルでは捉えられない事象が出てくる。おそらく、この世界の実相はとても複雑なのだと思う。複雑な事象の説明を試みると難解になりやすい。
古代ゲノム学は、そんな状況なあるのだろうという感想を抱いた。
生きるのが面倒くさい人が増えているらしい ― 2022年11月13日
精神科医が書いた次の新書を読んだ。
『生きるのが面倒くさい人:回避性パーソナル障害』(岡田尊司/朝日新書/朝日新聞出版)
生きるのが面倒になったから読んだわけではない。というか、すでに七十余年という十分な時間を生きてしまった私には縁遠い話題で、いまさら「面倒くさい」と言える立場でもない。
本書を読もうと思ったのは、半年前に読んだ『星新一の思想』(浅羽通明)で紹介されていて興味を抱いたからである。星新一をアスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)と見なしている浅羽通明氏は次のように述べている。
「精神科医岡田尊司は『生きるのが面倒くさい人』第7章の16頁分を、星新一のパトグラフィに充てました。岡田の診断によると星新一はアスペルガーよりも回避性人格のようです。」
本書のメインテーマである「回避性パーソナル障害」を十分に理解できたわけではないが、「生きるのが面倒くさい」「人生の選択を先のばしにする」「自己評価が低い」「無気力」「ひきこもり」などの性向のようだ。
本書では、そんな傾向が見られる著名人として、星新一の他に井上靖、サマセット・モーム、藤子・F・不二雄、村上春樹、森鴎外などの事例を紹介している。そして、精神科医である著者自身が回避性パーソナル障害だったとし、自分自身も分析対象にしている。勤務医だった著者は、現在は自分のクリニックを開業し、ひきこもり患者の社会復帰などを手助けしているそうだ。
回避性パーソナル障害の原因は、遺伝的要素もあるが、家庭環境を含めた社会的要因が大きく、時代とともに世界レべルで増加傾向にあるらしい。村上春樹ではないが「やれやれ」という気分になる。
本書の後半は、回避性パーソナル障害の若者たちが社会に出て行くための具体的アドバイスである。年寄りの私は、いまの若者たちは大変だなあと同情しつつも、しっかり生きてくれと期待するしかない。
『生きるのが面倒くさい人:回避性パーソナル障害』(岡田尊司/朝日新書/朝日新聞出版)
生きるのが面倒になったから読んだわけではない。というか、すでに七十余年という十分な時間を生きてしまった私には縁遠い話題で、いまさら「面倒くさい」と言える立場でもない。
本書を読もうと思ったのは、半年前に読んだ『星新一の思想』(浅羽通明)で紹介されていて興味を抱いたからである。星新一をアスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)と見なしている浅羽通明氏は次のように述べている。
「精神科医岡田尊司は『生きるのが面倒くさい人』第7章の16頁分を、星新一のパトグラフィに充てました。岡田の診断によると星新一はアスペルガーよりも回避性人格のようです。」
本書のメインテーマである「回避性パーソナル障害」を十分に理解できたわけではないが、「生きるのが面倒くさい」「人生の選択を先のばしにする」「自己評価が低い」「無気力」「ひきこもり」などの性向のようだ。
本書では、そんな傾向が見られる著名人として、星新一の他に井上靖、サマセット・モーム、藤子・F・不二雄、村上春樹、森鴎外などの事例を紹介している。そして、精神科医である著者自身が回避性パーソナル障害だったとし、自分自身も分析対象にしている。勤務医だった著者は、現在は自分のクリニックを開業し、ひきこもり患者の社会復帰などを手助けしているそうだ。
回避性パーソナル障害の原因は、遺伝的要素もあるが、家庭環境を含めた社会的要因が大きく、時代とともに世界レべルで増加傾向にあるらしい。村上春樹ではないが「やれやれ」という気分になる。
本書の後半は、回避性パーソナル障害の若者たちが社会に出て行くための具体的アドバイスである。年寄りの私は、いまの若者たちは大変だなあと同情しつつも、しっかり生きてくれと期待するしかない。
『選択と誘導の認知科学』を読むと自由意思を信じられなくなる ― 2022年10月29日
タイトルにある「誘導」という言葉に惹かれて次の本を読んだ。
『選択と誘導の認知科学』(山田歩/新曜社)
日本認知科学会監修『「認知科学のススメ」シリーズ』という叢書の1冊である。認知科学とは多様な分野にまたがる学問だそうだ。私には心理学と脳科学の要素が大きいように見える。
本書冒頭では、ファーストフード店が長時間滞在を減らすために椅子の形状や固さを工夫している話、電車の座席に凸凹をつけてマナー違反の座り方を減らしている話など、物理的環境で人の行動を誘導する例を紹介している。続いて、人々の意思や考えを確認するための質問において、選択肢を少し工夫するだけで結果が大きく異なる事例を紹介している。確かに「誘導の科学」である。
興味深い事例に惹かれて読み進めるうちに次第に「アタリマエのこと」をくり返し述べているように思えてきた。著者に文句をつけているのではない。自分自身を含めて人間とは、さほど考えずに行動するのが「アタリマエ」に思えてきたのである。
例えば、異性を選ぶときに「外見」「中身」のどちらを重視するかと聞かれても、常に同じ回答をするとは限らない。聞かれるまでは、そんな割り切った基準は頭のなかになく、曖昧模糊としていて、要は何も考えていなのである。選択肢の工夫によって回答がぶれるのは当然のように思われる。
脳科学の本で、人は必ずしも「意識→行動」というプロセスをとっているのではなく、行動の後追いで意識が発生するという話を読んだ記憶がある。
本書を読んで人間の「自由意思」があやふやであることを再認識した。考えているように見えて、実はさほど考えていないから容易に誘導されるのである。
また、理由があって行動するのではなく、行動してから理由を後付けしているにもかかわらず、自分では「理由→行動」と思い込んでいるという話もよくわかる。自分自身のことも含めて、そんな事例は多いと思う。
何も考えていないのに、何かを考えていると思い込んでいる、それが人間である、と考えることは何ともむなしい。「考える」の実相に迫るのが非常に難しいということかもしれないが……。
『選択と誘導の認知科学』(山田歩/新曜社)
日本認知科学会監修『「認知科学のススメ」シリーズ』という叢書の1冊である。認知科学とは多様な分野にまたがる学問だそうだ。私には心理学と脳科学の要素が大きいように見える。
本書冒頭では、ファーストフード店が長時間滞在を減らすために椅子の形状や固さを工夫している話、電車の座席に凸凹をつけてマナー違反の座り方を減らしている話など、物理的環境で人の行動を誘導する例を紹介している。続いて、人々の意思や考えを確認するための質問において、選択肢を少し工夫するだけで結果が大きく異なる事例を紹介している。確かに「誘導の科学」である。
興味深い事例に惹かれて読み進めるうちに次第に「アタリマエのこと」をくり返し述べているように思えてきた。著者に文句をつけているのではない。自分自身を含めて人間とは、さほど考えずに行動するのが「アタリマエ」に思えてきたのである。
例えば、異性を選ぶときに「外見」「中身」のどちらを重視するかと聞かれても、常に同じ回答をするとは限らない。聞かれるまでは、そんな割り切った基準は頭のなかになく、曖昧模糊としていて、要は何も考えていなのである。選択肢の工夫によって回答がぶれるのは当然のように思われる。
脳科学の本で、人は必ずしも「意識→行動」というプロセスをとっているのではなく、行動の後追いで意識が発生するという話を読んだ記憶がある。
本書を読んで人間の「自由意思」があやふやであることを再認識した。考えているように見えて、実はさほど考えていないから容易に誘導されるのである。
また、理由があって行動するのではなく、行動してから理由を後付けしているにもかかわらず、自分では「理由→行動」と思い込んでいるという話もよくわかる。自分自身のことも含めて、そんな事例は多いと思う。
何も考えていないのに、何かを考えていると思い込んでいる、それが人間である、と考えることは何ともむなしい。「考える」の実相に迫るのが非常に難しいということかもしれないが……。
医学者が書いた『皮膚、人間のすべてを語る』は広範な考察の書 ― 2022年07月18日
約1カ月前(2022年6月19日)の朝日新聞と日経新聞の書評欄が同じ本を取り上げていて、面白そうな本だと興味を抱いた。次の本である。
『皮膚、人間のすべてを語る:万能の臓器と巡る10章』(モンティ・ライアン/塩崎香織訳/みすず書房)
皮膚を研究する医学者が「皮膚とは何か」を多面的に全10章で解説・考察している。冒頭は皮膚に関する医学的・生物学的な話である。やがて脳科学がからんでくる。さらには心理学・社会学・宗教学にまで論点が広がっていく。面白い本だ。これまで皮膚について考えたことがほとんどなかったので、皮膚を巡る考察がこんなにも広がるのかと驚いた。
本書では、著者が医師として接してきたさまざまな皮膚病の事例を紹介している。そんな恐ろしげな症状を読んでいるだけで体がムズムズする。たしかに皮膚とは不可思議で身近な「臓器」である。
人類(先住民)の多様な皮膚の色(メラミンの量)の分布は地球に降り注ぐ紫外線の量の分布と重なるそうだ。きわめて当然の話である。しかし、かつては長い時間をかけて移動した人類がいまでは短時間で移動できるようになった。そのため、皮膚の色と紫外線量に齟齬が発生し、それが皮膚がんの発生やビタミンD欠乏につながっている。わかりやすい説明であり、文明のパラドックスを感じざるをえない。
本書後半の次のような指摘が印象に残った。
「おそらく脳を除けば、皮膚以上に人間が聖なるものとして大きな意味をもたせる臓器はない。皮膚は神学者を夢中にさせ、哲学者を虜にしてきた。また、私たちの日常的な考え方に意外なかたちで作用するものである。」
「皮膚は肉体と森羅万象とを分かつバリアとして機能していながら、肉的な欲望に身を任せる私たちのきわめて重要な一部でもある。皮膚は感覚器官であり、ありてにいえば、欲望と罪と恥が入り混じるスリルと興奮に満ちた最大の生殖器だ。」
本書を読んでいて安部公房の『他人の顔』を思い出した。事故で顔面がケロイドになった技術者が精巧な仮面を作る話である。著者は文学の領域までには踏み込んでいないが、皮膚を巡る文学もいろいろありそうに思える。
『皮膚、人間のすべてを語る:万能の臓器と巡る10章』(モンティ・ライアン/塩崎香織訳/みすず書房)
皮膚を研究する医学者が「皮膚とは何か」を多面的に全10章で解説・考察している。冒頭は皮膚に関する医学的・生物学的な話である。やがて脳科学がからんでくる。さらには心理学・社会学・宗教学にまで論点が広がっていく。面白い本だ。これまで皮膚について考えたことがほとんどなかったので、皮膚を巡る考察がこんなにも広がるのかと驚いた。
本書では、著者が医師として接してきたさまざまな皮膚病の事例を紹介している。そんな恐ろしげな症状を読んでいるだけで体がムズムズする。たしかに皮膚とは不可思議で身近な「臓器」である。
人類(先住民)の多様な皮膚の色(メラミンの量)の分布は地球に降り注ぐ紫外線の量の分布と重なるそうだ。きわめて当然の話である。しかし、かつては長い時間をかけて移動した人類がいまでは短時間で移動できるようになった。そのため、皮膚の色と紫外線量に齟齬が発生し、それが皮膚がんの発生やビタミンD欠乏につながっている。わかりやすい説明であり、文明のパラドックスを感じざるをえない。
本書後半の次のような指摘が印象に残った。
「おそらく脳を除けば、皮膚以上に人間が聖なるものとして大きな意味をもたせる臓器はない。皮膚は神学者を夢中にさせ、哲学者を虜にしてきた。また、私たちの日常的な考え方に意外なかたちで作用するものである。」
「皮膚は肉体と森羅万象とを分かつバリアとして機能していながら、肉的な欲望に身を任せる私たちのきわめて重要な一部でもある。皮膚は感覚器官であり、ありてにいえば、欲望と罪と恥が入り混じるスリルと興奮に満ちた最大の生殖器だ。」
本書を読んでいて安部公房の『他人の顔』を思い出した。事故で顔面がケロイドになった技術者が精巧な仮面を作る話である。著者は文学の領域までには踏み込んでいないが、皮膚を巡る文学もいろいろありそうに思える。
5年の長旅に同行した気分になる『ビーグル号航海記』 ― 2022年04月14日
ついに『ビーグル号航海記』を読んだ。
『ビーグル号航海記(上)(下)』(チャールズ・R・ダーウィン/荒俣宏訳/平凡社)
この本を読もうと思ったのは14年前である。その頃、私は世界一周の船旅をし、ガラパゴス島で大いに感動した。帰国したらダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思った。帰国後、ネット古書店で入手した『ビーグル号世界周航記』(ダーウィン著)という本は、『ダーウィンは何を見たか』というダイジェスト解説の翻訳本で、私が期待した航海記ではなかった。
きちんとした全訳を読まねばと思いつつ瞬く間に時は流れ、最近になって荒俣宏による新訳版(2013年刊行)が出ていると知って入手した。この大部な本を読もうとして、やはり『種の起源』を先に読んでおく方がいいと思った。
ダーウィンが『種の起源』を出版したのは50歳(1859年)の時だ。ビーグル号による世界一周は22~27歳の5年間、『ビーグル号航海記』は30歳の時の本だ。『種の起源』の内容を知ったうえで『航海記』のなかにその萌芽を探すような読書が面白いと考えたのである。で、『種の起源』を読み終えてから、この『航海記』を読んだ。
本書を読んで、まず感じたのは、これはいわゆる「航海記」ではなく「博物誌」に近いということだ。そもそも、世界一周5年間は長すぎる。ダーウィンは日本で言えば幕末の人で横井小楠と同い年(リンカーンとも同年)、緒方洪庵や佐久間象山と同世代で、ペリーよりは15歳若い。ビーグル号は帆船だが、世界一周だけなら5年はかからない。ビーグル号の任務は南米の測量・海図作成で、ダーウィンは艦長の話し相手の博物学者として自費で同乗したのである。
というわけで、最初の4年近く、ビーグル号は南米の海岸を行ったり来たりしていて、その間、ダーウィンは南米の陸地のあちこちを探検旅行している。本書の大半はその報告である。動植物に関する記録も多いが、地形や地質、化石に関する考察・記録が多い。そもそも、この本の原題の邦訳は『海軍大佐フィッロイ艦長指揮、英国海軍軍艦ビーグル号による世界周航中に訪れた諸国の自然史ならびに地質学に関する調査紀要』であって、「航海記」ではない。と言っても「航海記」部分も十分に面白い。
本書を読んで感嘆するのはダーウィンの該博な知識と広範な探究心・好奇心である。博物学者・古生物学者・地質学者・文化人類学者の目を兼ね備えている。標本を採集し、ときには解剖もする。サンゴ礁がなぜできるかについての自説を詳細に展開し、奴隷制への厳しい批判も述べている。
で、ガラパゴスである。全21章の第17章が「ガラパゴス諸島」で、下巻の中盤あたりだ。その第17章にたどり着くのを楽しみに大部な本書を読み進めた。どの章も興味深いが、やはり「第17章 ガラパゴス諸島」が面白い。
固有生物が多く生息し、各島によってそれが変化しているさまを目の当たりにしたダーウィンの高揚が伝わってくる。ダーウィンは次のように述べている。
「地質学の年代でいえばつい最近まで、このあたりは青海原に覆われていたと信じたくなる。ということはつまり、時間と空間の両次元で、あの大いなる事実――神秘の中の神秘――つまり新しい生物がこの地上に出現する現場へと、われわれはいくらか接近した、ということになるのかもしれない。」
「(…)以上のような事実を深く考えると、ついつい、自然の創造力といった言葉を使いたくなってしまう。この自然の創造力が、これだけ荒涼とした岩だらけの小島群に投下された作用の大きさには、まったく驚かされるものがある。」
〈種の起源〉を探究する好奇心は20代の「航海」のなかに確かに息づいている。眼前の興味深い事象を観察しながら、悠久の時間を考察しているのだ。
この大部な『ビーグル号航海記』を読み終えたとき、長年の宿題を果たしたと感じると同時に、ダーウィンの5年にわたる長旅につきあって、共に故国に帰航した気になった。感無量の気分である。
〔蛇足〕
『ビーグル号航海記』を読んでいて、今回のウクライナ侵攻を想起するシーンに出くわした。ブラジルの将軍とインディオの戦闘に関して、インディオに同情的なダーウィンは、脱出に成功したインディオ父子の姿から「バイロンが描く英雄マゼッパ」を連想している。マゼッパは、つい最近読んだ『物語ウクライナの歴史』にも登場する17世紀のウクライナ独立闘争の英雄で、現在はウクライナの紙幣にもなっている。
『ビーグル号航海記(上)(下)』(チャールズ・R・ダーウィン/荒俣宏訳/平凡社)
この本を読もうと思ったのは14年前である。その頃、私は世界一周の船旅をし、ガラパゴス島で大いに感動した。帰国したらダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思った。帰国後、ネット古書店で入手した『ビーグル号世界周航記』(ダーウィン著)という本は、『ダーウィンは何を見たか』というダイジェスト解説の翻訳本で、私が期待した航海記ではなかった。
きちんとした全訳を読まねばと思いつつ瞬く間に時は流れ、最近になって荒俣宏による新訳版(2013年刊行)が出ていると知って入手した。この大部な本を読もうとして、やはり『種の起源』を先に読んでおく方がいいと思った。
ダーウィンが『種の起源』を出版したのは50歳(1859年)の時だ。ビーグル号による世界一周は22~27歳の5年間、『ビーグル号航海記』は30歳の時の本だ。『種の起源』の内容を知ったうえで『航海記』のなかにその萌芽を探すような読書が面白いと考えたのである。で、『種の起源』を読み終えてから、この『航海記』を読んだ。
本書を読んで、まず感じたのは、これはいわゆる「航海記」ではなく「博物誌」に近いということだ。そもそも、世界一周5年間は長すぎる。ダーウィンは日本で言えば幕末の人で横井小楠と同い年(リンカーンとも同年)、緒方洪庵や佐久間象山と同世代で、ペリーよりは15歳若い。ビーグル号は帆船だが、世界一周だけなら5年はかからない。ビーグル号の任務は南米の測量・海図作成で、ダーウィンは艦長の話し相手の博物学者として自費で同乗したのである。
というわけで、最初の4年近く、ビーグル号は南米の海岸を行ったり来たりしていて、その間、ダーウィンは南米の陸地のあちこちを探検旅行している。本書の大半はその報告である。動植物に関する記録も多いが、地形や地質、化石に関する考察・記録が多い。そもそも、この本の原題の邦訳は『海軍大佐フィッロイ艦長指揮、英国海軍軍艦ビーグル号による世界周航中に訪れた諸国の自然史ならびに地質学に関する調査紀要』であって、「航海記」ではない。と言っても「航海記」部分も十分に面白い。
本書を読んで感嘆するのはダーウィンの該博な知識と広範な探究心・好奇心である。博物学者・古生物学者・地質学者・文化人類学者の目を兼ね備えている。標本を採集し、ときには解剖もする。サンゴ礁がなぜできるかについての自説を詳細に展開し、奴隷制への厳しい批判も述べている。
で、ガラパゴスである。全21章の第17章が「ガラパゴス諸島」で、下巻の中盤あたりだ。その第17章にたどり着くのを楽しみに大部な本書を読み進めた。どの章も興味深いが、やはり「第17章 ガラパゴス諸島」が面白い。
固有生物が多く生息し、各島によってそれが変化しているさまを目の当たりにしたダーウィンの高揚が伝わってくる。ダーウィンは次のように述べている。
「地質学の年代でいえばつい最近まで、このあたりは青海原に覆われていたと信じたくなる。ということはつまり、時間と空間の両次元で、あの大いなる事実――神秘の中の神秘――つまり新しい生物がこの地上に出現する現場へと、われわれはいくらか接近した、ということになるのかもしれない。」
「(…)以上のような事実を深く考えると、ついつい、自然の創造力といった言葉を使いたくなってしまう。この自然の創造力が、これだけ荒涼とした岩だらけの小島群に投下された作用の大きさには、まったく驚かされるものがある。」
〈種の起源〉を探究する好奇心は20代の「航海」のなかに確かに息づいている。眼前の興味深い事象を観察しながら、悠久の時間を考察しているのだ。
この大部な『ビーグル号航海記』を読み終えたとき、長年の宿題を果たしたと感じると同時に、ダーウィンの5年にわたる長旅につきあって、共に故国に帰航した気になった。感無量の気分である。
〔蛇足〕
『ビーグル号航海記』を読んでいて、今回のウクライナ侵攻を想起するシーンに出くわした。ブラジルの将軍とインディオの戦闘に関して、インディオに同情的なダーウィンは、脱出に成功したインディオ父子の姿から「バイロンが描く英雄マゼッパ」を連想している。マゼッパは、つい最近読んだ『物語ウクライナの歴史』にも登場する17世紀のウクライナ独立闘争の英雄で、現在はウクライナの紙幣にもなっている。
『種の起源』はやはり名著だ ― 2022年04月01日
私は14年前にガラパゴス諸島に行ったことがあり、現地のダーウィン研究所も見学した。そのとき、ダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思ったが、うかうかと年月が経ち、最近になって荒俣宏による新訳を入手した。だが、書店で光文社古典新訳文庫の『種の起源』を手にしたとき、『ビーグル号航海記』の前に『種の起源』を読むべきだと感じた。この高名な書でダーウインの思想を把握したうえで航海記を読む方がよさそうに思えたのである。で、『種の起源』を読んだ。
『種の起源(上)(下)』(ダーウィン/渡辺政隆訳/光文社古典新訳文庫)
(上)(下)2冊で約800頁、かなりの分量である。ダーウインの進化論に関しては教科書や解説書などで知っているつもりだ。その概要は数頁で尽くせそうに思える。800頁も費やしていったい何を語っているのだろうと興味がわいた。「訳者まえがき」によれば、この書は構想中の大著の「要約」だったそうだ。
本書を読了して、ダーウィンが本書を「要約」とした気分がわかった。本書でダーウィンは「種は、継起するわずかな変異が保存され蓄積されることで変わってきた」という「自然淘汰」を力強く主張し、「生物は創造主によって個別に創造された」という「創造説」を否定している。主旨はそれだけだ。その論拠として膨大で多様なな証拠を「要約」的に提示している。もっと語りたいという著者の気持ちが随所に垣間見える。
意外なことに「進化」や「適者生存」という言葉は出てこない。訳者解説によれば、これらの用語は社会学者スペンサーによるもので、『種の起源』の後の版には出てくるそうだ(本書は初版の翻訳)。キーワードはあくまで「自然淘汰」で、この言葉は繰り返し出てくる。
ダーウィンは本書で、栽培植物や飼育動物から世界中の野生の動植物にいたる多様な動植物を取り上げ、自然淘汰の証拠を詳細に論じている。だが、人間や類人猿への言及はない。人間の祖先が猿だとも述べていない。
半世紀以上前の学生時代、生物専攻の友人からファーブルがダーウィンに批判的だったと聞いたことがある。そのとき、現場重視のファーブルと理論重視のダーウィンという構図が浮かんだ。目の前の昆虫を地道に観察・探究するオタク的なファーブルが、頭デッカチに大風呂敷を広げるダーウィンを評価できなかったのだろうと感じた。『種の起源』を読んで、それは間違いだと気づいた。
ダーウィンもファーブルに劣らないフィールドワークの人である。ミミズ、ハト、ハチをはじめ多くの生物を自ら飼育・観察・研究している。化石も研究している。さまざまな実験も重ねている。もちろん、広範な研究者たちの成果も検討していて、ファーブルの研究成果への言及もある。
ガラパゴス諸島への言及は思ったより少ない。ダーウィンはガラパゴスのフィンチを観察して進化論を着想したと聞いたことがある。だが、本書にフィンチは登場せず、ガラパゴスの扱いもワン・オブ・ゼムに近い。訳者解説によれば「ダーウィンフィンチ」は後世につくられた伝説だそうだ。少しがっかりした。
「自然淘汰」を主張し「創造説」を否定する本書には、くどいと感じる部分も多い。だが、終章は圧巻である。慎重に論を重ねたうえで次のように踏み込んでいる。
「私は類推から出発して、地球上にかつて生息したすべての生物はおそらく、最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかない。」
遺伝学成立前の時代、透徹した視点に達しているのに驚く。次の記述も印象深い。
「さまざまな種類の植物に覆われ、灌木では小鳥が囀り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生き物ものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。」
『種の起源』は広大な自然史・自然誌を探究した名著だと思った。
『種の起源(上)(下)』(ダーウィン/渡辺政隆訳/光文社古典新訳文庫)
(上)(下)2冊で約800頁、かなりの分量である。ダーウインの進化論に関しては教科書や解説書などで知っているつもりだ。その概要は数頁で尽くせそうに思える。800頁も費やしていったい何を語っているのだろうと興味がわいた。「訳者まえがき」によれば、この書は構想中の大著の「要約」だったそうだ。
本書を読了して、ダーウィンが本書を「要約」とした気分がわかった。本書でダーウィンは「種は、継起するわずかな変異が保存され蓄積されることで変わってきた」という「自然淘汰」を力強く主張し、「生物は創造主によって個別に創造された」という「創造説」を否定している。主旨はそれだけだ。その論拠として膨大で多様なな証拠を「要約」的に提示している。もっと語りたいという著者の気持ちが随所に垣間見える。
意外なことに「進化」や「適者生存」という言葉は出てこない。訳者解説によれば、これらの用語は社会学者スペンサーによるもので、『種の起源』の後の版には出てくるそうだ(本書は初版の翻訳)。キーワードはあくまで「自然淘汰」で、この言葉は繰り返し出てくる。
ダーウィンは本書で、栽培植物や飼育動物から世界中の野生の動植物にいたる多様な動植物を取り上げ、自然淘汰の証拠を詳細に論じている。だが、人間や類人猿への言及はない。人間の祖先が猿だとも述べていない。
半世紀以上前の学生時代、生物専攻の友人からファーブルがダーウィンに批判的だったと聞いたことがある。そのとき、現場重視のファーブルと理論重視のダーウィンという構図が浮かんだ。目の前の昆虫を地道に観察・探究するオタク的なファーブルが、頭デッカチに大風呂敷を広げるダーウィンを評価できなかったのだろうと感じた。『種の起源』を読んで、それは間違いだと気づいた。
ダーウィンもファーブルに劣らないフィールドワークの人である。ミミズ、ハト、ハチをはじめ多くの生物を自ら飼育・観察・研究している。化石も研究している。さまざまな実験も重ねている。もちろん、広範な研究者たちの成果も検討していて、ファーブルの研究成果への言及もある。
ガラパゴス諸島への言及は思ったより少ない。ダーウィンはガラパゴスのフィンチを観察して進化論を着想したと聞いたことがある。だが、本書にフィンチは登場せず、ガラパゴスの扱いもワン・オブ・ゼムに近い。訳者解説によれば「ダーウィンフィンチ」は後世につくられた伝説だそうだ。少しがっかりした。
「自然淘汰」を主張し「創造説」を否定する本書には、くどいと感じる部分も多い。だが、終章は圧巻である。慎重に論を重ねたうえで次のように踏み込んでいる。
「私は類推から出発して、地球上にかつて生息したすべての生物はおそらく、最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかない。」
遺伝学成立前の時代、透徹した視点に達しているのに驚く。次の記述も印象深い。
「さまざまな種類の植物に覆われ、灌木では小鳥が囀り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生き物ものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。」
『種の起源』は広大な自然史・自然誌を探究した名著だと思った。
脳科学の知見の面白さが伝わってくる『脳はなにげに不公平』 ― 2021年07月25日
脳科学者の池谷裕二氏が『週刊朝日』に連載しているコラムを集成した文庫本を読んだ。
『脳はなにげに不公平』(池谷裕二/朝日文庫)
週刊誌1頁の『パテカトルの万能薬』と題するこのコラムは現在も連載中だが、本書は2012年~2013年のコラムから62編を厳選したもので、2016年刊行の単行本の文庫版(2019年5月刊行)である。
各コラムは脳科学周辺の最新の科学論文から得た知見をサラリと3ページで紹介するスタイルになっている。数年前に読んだ池谷氏の 『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』は歯ごたえのある解説書で頭が疲れたが、本書は小ネタ集の趣で、とても読みやすい。
最初のコラムのタイトルは「不平等な世界のほうが安定する」である。格差が拡大すると社会不安が増大し、中間層が多い方が社会は安定すると思われるので、このタイトルにドキリする。著者は、全員が1万円ずつを所持する平等社会において平等なルールに基づくランダムにトレードをくり返すと不平等社会に遷移していくシミュレーションを紹介し、次のように述べている。
《平等さを突き詰めると不平等になるのは、自然なプロセスなのです。でも、多くの人は、この至って当たり前の統計的事実に気づかずに(あるいは意図的に無視して?)、平等主義や民主主義の理想像に憧れます。》
なんだか格差社会を追認する言説のように見えるが、これは脳回路を構成するシナプスの話で、少数の強いシナプスと大多数の弱いシナプスによって安定した脳回路ができているそうだ。そのまま人間の社会に適用できる話ではない。
「上流階級ほどモラルが低い?」というコラムも興味深い。これは人間社会を対象にした実験の紹介で、社会的ステータスの高い人ほど「騙してでもいいから、自分に有利に交渉」を進め、下流層の人は率直で正直な交渉をするそうだ。また、下流層の人でも「自分は社会的地位が高い」との前提で行動選択すると非道徳的になっていくそうだ。身も蓋もない話である。
他にも「ヒトは性善説か?」「自由意思はあるか?」など面白い話題を最新科学の知見によって紹介していて、脳の刺激になる――と思ったが、本書には、脳に刺激を与えることの可否に関する話もある。
『脳はなにげに不公平』(池谷裕二/朝日文庫)
週刊誌1頁の『パテカトルの万能薬』と題するこのコラムは現在も連載中だが、本書は2012年~2013年のコラムから62編を厳選したもので、2016年刊行の単行本の文庫版(2019年5月刊行)である。
各コラムは脳科学周辺の最新の科学論文から得た知見をサラリと3ページで紹介するスタイルになっている。数年前に読んだ池谷氏の 『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』は歯ごたえのある解説書で頭が疲れたが、本書は小ネタ集の趣で、とても読みやすい。
最初のコラムのタイトルは「不平等な世界のほうが安定する」である。格差が拡大すると社会不安が増大し、中間層が多い方が社会は安定すると思われるので、このタイトルにドキリする。著者は、全員が1万円ずつを所持する平等社会において平等なルールに基づくランダムにトレードをくり返すと不平等社会に遷移していくシミュレーションを紹介し、次のように述べている。
《平等さを突き詰めると不平等になるのは、自然なプロセスなのです。でも、多くの人は、この至って当たり前の統計的事実に気づかずに(あるいは意図的に無視して?)、平等主義や民主主義の理想像に憧れます。》
なんだか格差社会を追認する言説のように見えるが、これは脳回路を構成するシナプスの話で、少数の強いシナプスと大多数の弱いシナプスによって安定した脳回路ができているそうだ。そのまま人間の社会に適用できる話ではない。
「上流階級ほどモラルが低い?」というコラムも興味深い。これは人間社会を対象にした実験の紹介で、社会的ステータスの高い人ほど「騙してでもいいから、自分に有利に交渉」を進め、下流層の人は率直で正直な交渉をするそうだ。また、下流層の人でも「自分は社会的地位が高い」との前提で行動選択すると非道徳的になっていくそうだ。身も蓋もない話である。
他にも「ヒトは性善説か?」「自由意思はあるか?」など面白い話題を最新科学の知見によって紹介していて、脳の刺激になる――と思ったが、本書には、脳に刺激を与えることの可否に関する話もある。
『物理学の原理と法則』を読み、解明できない難問を再認識 ― 2021年07月19日
高校物理の復習をする気分で次の本を読んだ。
『物理学の原理と法則:科学の基礎から「自然の論理」へ』(池内了/講談社学術文庫)
70歳を過ぎて勉強し直そうという殊勝な心境になったわけではない。毎日の暑さでぼんやりしている頭が多少でもシャンとすれば、という気まぐれで本書に手がのびた。
冒頭で物理学における「原理」「法則」「定理」などの意味を解説していて、大人向け教科書の趣である。続いて、科学史の話題をふまえながら主に力学の原理や法則の説明になり、高校物理の復習気分で頭の体操になった。
話題は高校物理の範囲を超えて特殊相対性理論、一般相対性理論、量子論にまで広がり、ボーズ粒子やフェルミ粒子のスピンの話まで出てくる。著者は宇宙物理学者なので、当然ながら宇宙論やダークマター、ダークエネルギーにまで話題は及ぶ。
と言っても、本書は現代物理学の概説書ではなく、物理学の「考え方」を追究している。最終章のタイトルは「自然の論理と人間の思考」となっていて、「自然の論理によって生み出されたもの」と「自然に対峙する人間の思考によって創出されたもの」を区別して論じている。この二つが必ずしも一致するとは限らないという問題意識が刺激的である。
次のような指摘も面白い。
「現代科学が成功したのは、解ける問題、解きやすい問題、解く方法がわかっている問題、に特化してきたためと言えるかもしれない。自然現象のうち解ける見通しがついている問題を、あたかも難問であるかのような顔をして説いて見せて、あれこれ講釈してきたと言えるかもしれない。」
この指摘に関連して、天才物理学者たちが晩年に非線形の研究に突入したことに触れ、次のように述べている。
「非線形世界に行かねば物理世界は理解できないと、科学者なら誰もが薄々感じているのだが、我々の如き凡百の人間には手は出せない。湯川やハイゼンベルクやアインシュタインは若くしてノーベル賞を受賞したような大天才で、偉大な業績を残したがために思い切った冒険ができたのだろう。結局、成果のない冒険に終わったのだが。」
まだまだ、未開の世界は大きいようだ。
『物理学の原理と法則:科学の基礎から「自然の論理」へ』(池内了/講談社学術文庫)
70歳を過ぎて勉強し直そうという殊勝な心境になったわけではない。毎日の暑さでぼんやりしている頭が多少でもシャンとすれば、という気まぐれで本書に手がのびた。
冒頭で物理学における「原理」「法則」「定理」などの意味を解説していて、大人向け教科書の趣である。続いて、科学史の話題をふまえながら主に力学の原理や法則の説明になり、高校物理の復習気分で頭の体操になった。
話題は高校物理の範囲を超えて特殊相対性理論、一般相対性理論、量子論にまで広がり、ボーズ粒子やフェルミ粒子のスピンの話まで出てくる。著者は宇宙物理学者なので、当然ながら宇宙論やダークマター、ダークエネルギーにまで話題は及ぶ。
と言っても、本書は現代物理学の概説書ではなく、物理学の「考え方」を追究している。最終章のタイトルは「自然の論理と人間の思考」となっていて、「自然の論理によって生み出されたもの」と「自然に対峙する人間の思考によって創出されたもの」を区別して論じている。この二つが必ずしも一致するとは限らないという問題意識が刺激的である。
次のような指摘も面白い。
「現代科学が成功したのは、解ける問題、解きやすい問題、解く方法がわかっている問題、に特化してきたためと言えるかもしれない。自然現象のうち解ける見通しがついている問題を、あたかも難問であるかのような顔をして説いて見せて、あれこれ講釈してきたと言えるかもしれない。」
この指摘に関連して、天才物理学者たちが晩年に非線形の研究に突入したことに触れ、次のように述べている。
「非線形世界に行かねば物理世界は理解できないと、科学者なら誰もが薄々感じているのだが、我々の如き凡百の人間には手は出せない。湯川やハイゼンベルクやアインシュタインは若くしてノーベル賞を受賞したような大天才で、偉大な業績を残したがために思い切った冒険ができたのだろう。結局、成果のない冒険に終わったのだが。」
まだまだ、未開の世界は大きいようだ。
福岡伸一『生命海流』でわが懐かしのガラパゴスを追体験 ― 2021年07月04日
『生物と無生物のあいだ』や
『動的平衡』で知られる生物学者・福岡伸一氏がガラパゴス諸島に行き、その記録を本にした。
『生命海流:GALAPAGOS』(福岡伸一/朝日出版社)
ガラパゴスは私にとって懐かしい場所だ。ピースボートの世界一周で ガラパゴスを訪れた のは13年前の2008年11月で、私は彼の地で還暦をむかえた。これまで、そこそこの数の世界各地の観光地に行ったが、再訪したいと思った場所の筆頭はガラパゴスだった。
もはや私がガラパゴスを再訪する機会はないだろうと思いつつ本書を手にした。美しいカラー写真がたくさん載っている読みやすい本である。
福岡伸一氏にとってガラパゴス訪問は長年の夢で、昨年(2020年)3月、コロナ蔓延直前に念願を果たしたそうだ。その訪問は、私のような規定の観光コースではなく、1835年にダーウィンがビーグル号で巡ったコースを小型のチャーター船でたどるという贅沢な旅である。
ガラパゴスとは関東地方くらいの範囲に大小123島が散在する群島で、13年前の私は4泊の4島巡りだった(当初は6島予定だったが諸般の事情で変更)。ビーグル号は1ヵ月あまりかけて主要な島を調査・測量している。福岡氏はそのコースを1週間で巡ったそうだ。
本書はガラパゴス紹介の本だが、半分ばかりは福岡氏の自分語りの書でもある。ガラパゴスに到着するまでのアレコレが脱線気味に長い。朝日出版社のレクチュア・ブックスに関する記述など、私には懐かしくて興味深かったが、うんざりする読者がいるかもしれない。
旅日記はガラパゴスの自然誌紹介であると同時に福岡氏の自然観の開陳である。小型船のメンバー紹介、トイレ紹介、料理紹介などからは福岡氏の高揚感が伝わってきて、自分も同乗している気分にさせられる。私には13年前の追体験のようでもあり、懐かしさに浸った。
私が本書で最も面白いと思ったのは「ダーウィンのふるさととされるガラパゴスは、実は、もっともダーウィン的ではなかったのだ」という指摘である。
それは、ガラパゴスの生物は生存の自由度と余裕を享受しているという見方である。ダーウィンに異議を唱えた今西錦司の「棲み分け」につながるように思える。福岡氏は今西進化論について「夢中になって読んだものの、話法が独特すぎてほとんどきちんと理解できなかった」と述懐している。同感である。上記の「ダーウィン的ではなかった」については「別の機会に考察を進めてみたい」としている。期待したい。
『生命海流:GALAPAGOS』(福岡伸一/朝日出版社)
ガラパゴスは私にとって懐かしい場所だ。ピースボートの世界一周で ガラパゴスを訪れた のは13年前の2008年11月で、私は彼の地で還暦をむかえた。これまで、そこそこの数の世界各地の観光地に行ったが、再訪したいと思った場所の筆頭はガラパゴスだった。
もはや私がガラパゴスを再訪する機会はないだろうと思いつつ本書を手にした。美しいカラー写真がたくさん載っている読みやすい本である。
福岡伸一氏にとってガラパゴス訪問は長年の夢で、昨年(2020年)3月、コロナ蔓延直前に念願を果たしたそうだ。その訪問は、私のような規定の観光コースではなく、1835年にダーウィンがビーグル号で巡ったコースを小型のチャーター船でたどるという贅沢な旅である。
ガラパゴスとは関東地方くらいの範囲に大小123島が散在する群島で、13年前の私は4泊の4島巡りだった(当初は6島予定だったが諸般の事情で変更)。ビーグル号は1ヵ月あまりかけて主要な島を調査・測量している。福岡氏はそのコースを1週間で巡ったそうだ。
本書はガラパゴス紹介の本だが、半分ばかりは福岡氏の自分語りの書でもある。ガラパゴスに到着するまでのアレコレが脱線気味に長い。朝日出版社のレクチュア・ブックスに関する記述など、私には懐かしくて興味深かったが、うんざりする読者がいるかもしれない。
旅日記はガラパゴスの自然誌紹介であると同時に福岡氏の自然観の開陳である。小型船のメンバー紹介、トイレ紹介、料理紹介などからは福岡氏の高揚感が伝わってきて、自分も同乗している気分にさせられる。私には13年前の追体験のようでもあり、懐かしさに浸った。
私が本書で最も面白いと思ったのは「ダーウィンのふるさととされるガラパゴスは、実は、もっともダーウィン的ではなかったのだ」という指摘である。
それは、ガラパゴスの生物は生存の自由度と余裕を享受しているという見方である。ダーウィンに異議を唱えた今西錦司の「棲み分け」につながるように思える。福岡氏は今西進化論について「夢中になって読んだものの、話法が独特すぎてほとんどきちんと理解できなかった」と述懐している。同感である。上記の「ダーウィン的ではなかった」については「別の機会に考察を進めてみたい」としている。期待したい。
『理不尽な進化』を増補新版で再読――やはり後半は難解だが面白い ― 2021年06月21日
2年前に読んで蒙を啓かれた
『理不尽な進化』(朝日出版社)
がちくま文庫の新刊で出た。「増補新版」となっている。面白いが難解な本だったので、いずれ再読せねばと思っていた。これを機に増補新版を購入して読み返すことにした。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満/ちくま文庫)
地球で発生した生物の99.9%は絶滅したという話や適者生存はトートロジーという話は面白かったが、後半は哲学的で難解だった――そんな印象が残っているので、やや身構えて本書再読に取り組んだ。
第1章と第2章は、進化の理不尽性や素人の進化論理解に関する話で、分かりやすくて面白い。第3章は研究者同士の適応主義を巡る論争の紹介と評価である。ドーキンスら主流派に対してグールドが適応主義偏重を批判し(実はもっと複雑な内容だが…)、いまでは主流派の勝ちと見なされている。著者も明快にグールドの負けと判定している。ここまでは理解しやすい。
で、「終章 理不尽にたいする態度」になる。この章が本書のメインで、論争に負けた筈のグールドが不思議な形でよみがえり、議論の時空が拡大し、自然・人間・歴史を巡る哲学的な考察の展開になる。覚悟はしていたが、やはり難解である。理解(この「理解」という用語も要注意…)したとは言い難く、雰囲気を味わっただけだ。だが、十分に刺激的で多少は頭のマッサージになった気がする。
文庫版で増補された「附録 パンとゲシュタポ」で、著者は次のように述べている。
「アートとサイエンス、どちらも込みで私たちの世界であり人生である。だが、その棲み分けはつねに完璧というわけではない。両者の識別不能ゾーンというべきものが存在し、しばしば私たちを混乱させる。/ 本書が照準を合わせたのは、この識別不能ゾーンである。」
そんなゾーンがわかりやすい筈がない。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満/ちくま文庫)
地球で発生した生物の99.9%は絶滅したという話や適者生存はトートロジーという話は面白かったが、後半は哲学的で難解だった――そんな印象が残っているので、やや身構えて本書再読に取り組んだ。
第1章と第2章は、進化の理不尽性や素人の進化論理解に関する話で、分かりやすくて面白い。第3章は研究者同士の適応主義を巡る論争の紹介と評価である。ドーキンスら主流派に対してグールドが適応主義偏重を批判し(実はもっと複雑な内容だが…)、いまでは主流派の勝ちと見なされている。著者も明快にグールドの負けと判定している。ここまでは理解しやすい。
で、「終章 理不尽にたいする態度」になる。この章が本書のメインで、論争に負けた筈のグールドが不思議な形でよみがえり、議論の時空が拡大し、自然・人間・歴史を巡る哲学的な考察の展開になる。覚悟はしていたが、やはり難解である。理解(この「理解」という用語も要注意…)したとは言い難く、雰囲気を味わっただけだ。だが、十分に刺激的で多少は頭のマッサージになった気がする。
文庫版で増補された「附録 パンとゲシュタポ」で、著者は次のように述べている。
「アートとサイエンス、どちらも込みで私たちの世界であり人生である。だが、その棲み分けはつねに完璧というわけではない。両者の識別不能ゾーンというべきものが存在し、しばしば私たちを混乱させる。/ 本書が照準を合わせたのは、この識別不能ゾーンである。」
そんなゾーンがわかりやすい筈がない。


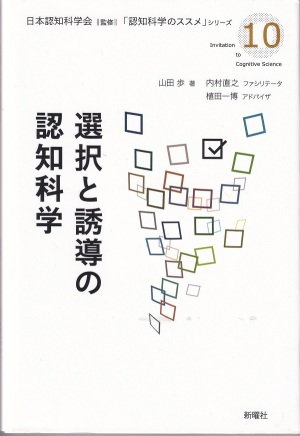





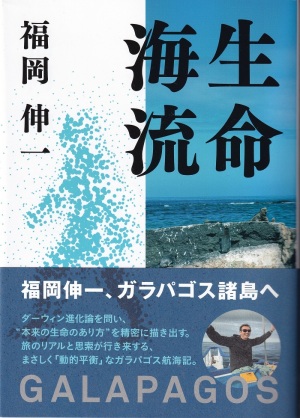
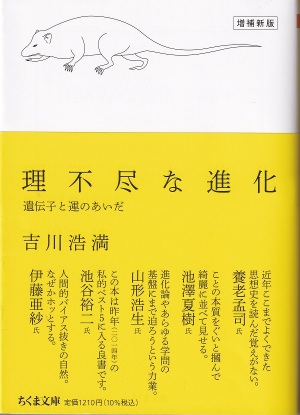
最近のコメント