ロングセラー『栽培植物と農耕の起源』はスリリングな書 ― 2021年04月10日
1966年1月の刊行後、半世紀以上読み続けられてきた次の岩波新書を読んだ。私が読んだのは、2020年12月発行の64刷改版である。
『栽培植物と農耕の起源』(中尾佐助/岩波新書)
先日読んだ『世界史との対話(上)』 で本書を名著と紹介していたので興味がわいて入手した。オビには「絶対名著」の大活字が躍っている。
イネやムギの栽培種は野生種とは大きく異なっているという話から、植物学的に農耕の起源を探っていく導入部に引き込まれ、興味深く読み進めた。だが、途中から少し難しくなる。生物学や農学の予備知識がないので、知識不足で理解しにくい事項が増えてくる。そのたびにネットや参考書で調べるのは面倒だし、もどかしくもある。わからない事はそのまま読み飛ばして強引に読了した。
だから十全に理解したとは言い難いし、自分がこの分野に未知だと自覚させられた。でも、本書の面白さは堪能できた気がする。本書は通常の啓蒙書ではなく、著者の調査研究のレポートであり、通説を再検討した自説展開の書である。一般向けに書いたスリリングな学術書のようにも思える。門外漢が研究現場の息吹を感じることができて面白いのだ。
本書に雑草と野草は違うという指摘があり、驚いた。私は10年近く前から八ヶ岳南麓で野菜作りの真似事をしていて、畑仕事とは雑草との終わりなき戦いだと感じている。年に2回は草刈り機で山小屋の庭の雑草(野草)も刈る。それを怠ると雑草(野草)に侵略されて大変なことになる。雑草も野草も同じものだと思っていた。
栽培植物は野草を元に人間が作りだしたものだ。それはよくわかる。雑草とは農耕という人間が作りだした環境に生じたもので、野草ではなく野草から進化したものだそうだ。人類は自分が作りだしたものとの終わりなき戦いをしているのだ。そう考えると何とも感慨深い。
『栽培植物と農耕の起源』(中尾佐助/岩波新書)
先日読んだ『世界史との対話(上)』 で本書を名著と紹介していたので興味がわいて入手した。オビには「絶対名著」の大活字が躍っている。
イネやムギの栽培種は野生種とは大きく異なっているという話から、植物学的に農耕の起源を探っていく導入部に引き込まれ、興味深く読み進めた。だが、途中から少し難しくなる。生物学や農学の予備知識がないので、知識不足で理解しにくい事項が増えてくる。そのたびにネットや参考書で調べるのは面倒だし、もどかしくもある。わからない事はそのまま読み飛ばして強引に読了した。
だから十全に理解したとは言い難いし、自分がこの分野に未知だと自覚させられた。でも、本書の面白さは堪能できた気がする。本書は通常の啓蒙書ではなく、著者の調査研究のレポートであり、通説を再検討した自説展開の書である。一般向けに書いたスリリングな学術書のようにも思える。門外漢が研究現場の息吹を感じることができて面白いのだ。
本書に雑草と野草は違うという指摘があり、驚いた。私は10年近く前から八ヶ岳南麓で野菜作りの真似事をしていて、畑仕事とは雑草との終わりなき戦いだと感じている。年に2回は草刈り機で山小屋の庭の雑草(野草)も刈る。それを怠ると雑草(野草)に侵略されて大変なことになる。雑草も野草も同じものだと思っていた。
栽培植物は野草を元に人間が作りだしたものだ。それはよくわかる。雑草とは農耕という人間が作りだした環境に生じたもので、野草ではなく野草から進化したものだそうだ。人類は自分が作りだしたものとの終わりなき戦いをしているのだ。そう考えると何とも感慨深い。
フォン・ノイマンの頭脳の優秀さに驚いたが… ― 2021年03月07日
半世紀以上昔、世の中に姿を現し始めたコンピュータの勉強を始め、ノイマンの名を知った。プログラム記憶方式というコンピュータの基本思想の創始者である。と言っても、その詳しい業績を知らないまま今日まできた。新刊書広告の「人間のフリをした悪魔」というサブタイトルが気になり、次の新書を読んだ。
『フォン・ノイマンの哲学:人間のフリをした悪魔』(高橋昌一郎/講談社現代新書)
ノイマンの頭脳の優秀さに驚いた。残した論文の分野は論理学・数学・物理学・化学・計算機科学・情報工学・生物学・気象学・経済学・心理学・社会学・政治学に及ぶ。理系の人に見えるが、8歳にして『世界史』全44巻を読破、ディケンズの『二都物語』を暗唱できたそうだ。
ハンガリー生まれの天才で、ヒトラー台頭の頃に米国に移住、1957年に53歳で亡くなっている。数学者ゆえにノーベル賞を逸したのではなく、早逝しなければ物理学賞はもちろん経済学賞も受賞したと言われている。
本書にはノイマン周辺の多くの学者が登場し、その多くがノーベル賞受賞者だが、彼らはノイマンの頭脳は別格だと証言している。並のノーベル賞受賞者を超えた頭脳の人だったようだ。私の凡庸な頭脳では、その凄さは理解できず、学者たちの証言で間接的に想像できるだけだ。
ノイマンの生涯を辿る本書は、原爆開発とコンピュータ黎明期の物語でもあり、科学技術史としても面白い。ノイマンはこの二つに大きく関わっていた。20世紀後半の歴史変動の要ともいえる二つのプロジェクトは同時並行的に進行していたのだ。
コンピュータ開発に関しては、サイバネティクスのウィーナー(ノイマンより9歳上)がノイマンの獲得に失敗し、ノイマンがチューリング(ノイマンより9歳下)との共同研究を望みながら果たせなかった話が興味深い。仮にこの三巨人の協働が実現していたら、現在の電脳世界の姿は変わっていただろうか。
本書のサブタイトル「人間のフリをした悪魔」には二重の意味がある。一つは人間離れした頭脳の優秀さであり、もう一つは原爆の開発・投下にためらいを見せない冷徹な超合理主義である。最小のコストで最大の利益をあげるのが人類全体の幸福につながるという考え方とも言える。
著者は本書において「ノイマンの哲学」を非難・否定も肯定もしていない。提示しているだけだ。冷徹な超合理主義を否定するのは容易ではない。優秀過ぎる頭脳はニヒリズムに近いのかもしれないが……
『フォン・ノイマンの哲学:人間のフリをした悪魔』(高橋昌一郎/講談社現代新書)
ノイマンの頭脳の優秀さに驚いた。残した論文の分野は論理学・数学・物理学・化学・計算機科学・情報工学・生物学・気象学・経済学・心理学・社会学・政治学に及ぶ。理系の人に見えるが、8歳にして『世界史』全44巻を読破、ディケンズの『二都物語』を暗唱できたそうだ。
ハンガリー生まれの天才で、ヒトラー台頭の頃に米国に移住、1957年に53歳で亡くなっている。数学者ゆえにノーベル賞を逸したのではなく、早逝しなければ物理学賞はもちろん経済学賞も受賞したと言われている。
本書にはノイマン周辺の多くの学者が登場し、その多くがノーベル賞受賞者だが、彼らはノイマンの頭脳は別格だと証言している。並のノーベル賞受賞者を超えた頭脳の人だったようだ。私の凡庸な頭脳では、その凄さは理解できず、学者たちの証言で間接的に想像できるだけだ。
ノイマンの生涯を辿る本書は、原爆開発とコンピュータ黎明期の物語でもあり、科学技術史としても面白い。ノイマンはこの二つに大きく関わっていた。20世紀後半の歴史変動の要ともいえる二つのプロジェクトは同時並行的に進行していたのだ。
コンピュータ開発に関しては、サイバネティクスのウィーナー(ノイマンより9歳上)がノイマンの獲得に失敗し、ノイマンがチューリング(ノイマンより9歳下)との共同研究を望みながら果たせなかった話が興味深い。仮にこの三巨人の協働が実現していたら、現在の電脳世界の姿は変わっていただろうか。
本書のサブタイトル「人間のフリをした悪魔」には二重の意味がある。一つは人間離れした頭脳の優秀さであり、もう一つは原爆の開発・投下にためらいを見せない冷徹な超合理主義である。最小のコストで最大の利益をあげるのが人類全体の幸福につながるという考え方とも言える。
著者は本書において「ノイマンの哲学」を非難・否定も肯定もしていない。提示しているだけだ。冷徹な超合理主義を否定するのは容易ではない。優秀過ぎる頭脳はニヒリズムに近いのかもしれないが……
『クオリアと人工意識』(茂木健一郎)は超科学の考察書 ― 2020年12月26日
書店の棚で、タイトルに「人工意識」という言葉がある本が目に入った。
『クオリアと人工意識』(茂木健一郎/講談社現代新書)
脳科学者・茂木健一郎氏の姿はテレビでよく見る。著書を読むのは初体験である。
私が「人工意識」という言葉に反応したのは、2年前に 『脳の意識 機械の意識』(渡辺正峰/中公新書) を読んだからだ。サイエンスで「意識」を捉えようとしている最近の脳科学に驚いた。その後、一般向けの脳の本を何冊か読んだが、正面から「人工意識」を扱った本には出会っていない。
『クオリアと人工意識』を、脳科学における「人工意識」研究の解説書と期待してを読み進めたが、私が想定した科学解説書ではなかった。科学に軸足を置いているが、科学・文学・哲学が混然としたエッセイに近い。解説よりは主張にウエイトがあり、刺激的で面白いが、話題が錯綜しゴチャゴチャした印象を受ける。
「クオリア」というわかりにくい概念は『脳の意識 機械の意識』の冒頭にも登場し、著者の渡辺氏は「モノを見る、音を聴く、手で触れるなどの感覚的意識体験」としている。茂木氏は、「クオリアを定義しても、それに満足する人は少ない」としたうえで、次のように述べている。
「なぜならば、クオリアは、それについての認知的な理解。すなわち「メタ認知」を持つ人にとっては、これ以上ないというくらいに「自明」なことだからだ。一方、クオリアについてのメタ認知をまだ持たない人は、それをいくら説明されてもわからない。」
クオリアの定義や説明の放棄である。だが、クオリアは本書の主要なキー概念であり、くりかえし登場する。Windows のユーザーより Mac のユーザーの方がクオリアへの感受性が高いなどの記述もあり、おかしな気分になる。「瞑想」などが登場すると、科学解説といより芸術論、宗教論に近いと感じてしまう。
脳科学や人工知能における「意識」や「知性」を考えるとき、現状の自然科学の方法での解明は困難で、新たな方法を探らなければならない、というのが茂木氏の考えのようだ。だから、本書は解説書ではなく「考察の書」であり、哲学や文学にも接近し、わかりにくくなっている。
そんな「考察」を十全に理解できたわけではないが、脳科学や人工知能の研究の現状の一端を垣間見ることはできた。次のような指摘は興味深い。
「画期的な人工知能の研究は、その研究手法や発表のやり方も新しい。その行動倫理は、「アナーキーで反権威主義的」なものだと言える。これは、いわゆる「破壊的イノベーション」(disruptive innovation)を推進するコミュニティに共通のものだが、人工知能の周辺では、その傾向が先鋭化している。」
本書のタイトルにある「人工意識」は必ずしも人工知能研究に馴染んでいるテーマではない。著者は「人工意識」を考慮しない「人工知能」に疑念を呈しているのだ。
『クオリアと人工意識』(茂木健一郎/講談社現代新書)
脳科学者・茂木健一郎氏の姿はテレビでよく見る。著書を読むのは初体験である。
私が「人工意識」という言葉に反応したのは、2年前に 『脳の意識 機械の意識』(渡辺正峰/中公新書) を読んだからだ。サイエンスで「意識」を捉えようとしている最近の脳科学に驚いた。その後、一般向けの脳の本を何冊か読んだが、正面から「人工意識」を扱った本には出会っていない。
『クオリアと人工意識』を、脳科学における「人工意識」研究の解説書と期待してを読み進めたが、私が想定した科学解説書ではなかった。科学に軸足を置いているが、科学・文学・哲学が混然としたエッセイに近い。解説よりは主張にウエイトがあり、刺激的で面白いが、話題が錯綜しゴチャゴチャした印象を受ける。
「クオリア」というわかりにくい概念は『脳の意識 機械の意識』の冒頭にも登場し、著者の渡辺氏は「モノを見る、音を聴く、手で触れるなどの感覚的意識体験」としている。茂木氏は、「クオリアを定義しても、それに満足する人は少ない」としたうえで、次のように述べている。
「なぜならば、クオリアは、それについての認知的な理解。すなわち「メタ認知」を持つ人にとっては、これ以上ないというくらいに「自明」なことだからだ。一方、クオリアについてのメタ認知をまだ持たない人は、それをいくら説明されてもわからない。」
クオリアの定義や説明の放棄である。だが、クオリアは本書の主要なキー概念であり、くりかえし登場する。Windows のユーザーより Mac のユーザーの方がクオリアへの感受性が高いなどの記述もあり、おかしな気分になる。「瞑想」などが登場すると、科学解説といより芸術論、宗教論に近いと感じてしまう。
脳科学や人工知能における「意識」や「知性」を考えるとき、現状の自然科学の方法での解明は困難で、新たな方法を探らなければならない、というのが茂木氏の考えのようだ。だから、本書は解説書ではなく「考察の書」であり、哲学や文学にも接近し、わかりにくくなっている。
そんな「考察」を十全に理解できたわけではないが、脳科学や人工知能の研究の現状の一端を垣間見ることはできた。次のような指摘は興味深い。
「画期的な人工知能の研究は、その研究手法や発表のやり方も新しい。その行動倫理は、「アナーキーで反権威主義的」なものだと言える。これは、いわゆる「破壊的イノベーション」(disruptive innovation)を推進するコミュニティに共通のものだが、人工知能の周辺では、その傾向が先鋭化している。」
本書のタイトルにある「人工意識」は必ずしも人工知能研究に馴染んでいるテーマではない。著者は「人工意識」を考慮しない「人工知能」に疑念を呈しているのだ。
『空間は実在するか』で空間と時間の不思議を再認識 ― 2020年12月10日
橋元淳一郎氏の新刊新書を新聞広告で知り、早速購入して読んだ。
『空間は実在するか』(橋元淳一郎/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)
橋元氏には「時間は物理的実在ではない」と論述した著書があり、その時間論に惹かれた経験があり、今度は「空間」かと驚き、興味がわいたのである。
橋元氏の時間論を読んだのは比較的最近のような気がしていたが、読書メモを調べると 『時間はどこで生まれるか』 を読んだのは2007年、 『時間はなぜ取り戻せないのか』『時空と生命』 を読んだのは2010年、10年以上も昔のことだ。
これらの本を十分に咀嚼できたわけではなく、その内容の大半は失念している。だが、とても面白くて刺激だったことは鮮明に憶えている。「物理的実在でない時間は生命現象によって発生した」という、私にとっては驚くべき論旨が記憶に残っている。
橋元氏の『時間はどこで生まれるか』を読んだ2007年、福岡伸一氏の『生物と無生物のあいだ』も読み、両者に通底するものを感じた。今回の『空間は実在するか』のオビには、福岡伸一氏の「この哲学にしびれた!」との惹句がある。
『空間は実在するか』は、「時間論」に対抗した驚くべき「空間論」ではなく、基本的には橋元氏の従来の時間論をわかりやすく解説した内容だった。よく考えてみれば、以前の著作でも「ヒッグス場が生じることで質量が生じた。それ以前には時間も空間もなかった」と述べていた。物質(質量)が空間を作り、生命が時間を創った――それが本書の要諦である。
ほとんど失念しているとは言え、以前に橋元氏の時間論3冊を読んでいたおかげか、比較的スムーズに本書を読み進めることができ、復習気分で実数の時間軸と虚数の空間軸からなるミンコフスキー空間の紡ぎ出すセンス・オブ・ワンダーを堪能できた。
私は安易に時空という言葉を使うことがあるが、本書を読んで、あらためて時間と空間が一体だと認識した。時間の測定より空間の測定の方が困難だとの話も意外だった。時間は原子時計があるが、空間には原子レベルでの原器を作るのが難しいそうだ。本書を機に前著も再読して橋元時間論の理解を深めたくなった。
『空間は実在するか』(橋元淳一郎/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)
橋元氏には「時間は物理的実在ではない」と論述した著書があり、その時間論に惹かれた経験があり、今度は「空間」かと驚き、興味がわいたのである。
橋元氏の時間論を読んだのは比較的最近のような気がしていたが、読書メモを調べると 『時間はどこで生まれるか』 を読んだのは2007年、 『時間はなぜ取り戻せないのか』『時空と生命』 を読んだのは2010年、10年以上も昔のことだ。
これらの本を十分に咀嚼できたわけではなく、その内容の大半は失念している。だが、とても面白くて刺激だったことは鮮明に憶えている。「物理的実在でない時間は生命現象によって発生した」という、私にとっては驚くべき論旨が記憶に残っている。
橋元氏の『時間はどこで生まれるか』を読んだ2007年、福岡伸一氏の『生物と無生物のあいだ』も読み、両者に通底するものを感じた。今回の『空間は実在するか』のオビには、福岡伸一氏の「この哲学にしびれた!」との惹句がある。
『空間は実在するか』は、「時間論」に対抗した驚くべき「空間論」ではなく、基本的には橋元氏の従来の時間論をわかりやすく解説した内容だった。よく考えてみれば、以前の著作でも「ヒッグス場が生じることで質量が生じた。それ以前には時間も空間もなかった」と述べていた。物質(質量)が空間を作り、生命が時間を創った――それが本書の要諦である。
ほとんど失念しているとは言え、以前に橋元氏の時間論3冊を読んでいたおかげか、比較的スムーズに本書を読み進めることができ、復習気分で実数の時間軸と虚数の空間軸からなるミンコフスキー空間の紡ぎ出すセンス・オブ・ワンダーを堪能できた。
私は安易に時空という言葉を使うことがあるが、本書を読んで、あらためて時間と空間が一体だと認識した。時間の測定より空間の測定の方が困難だとの話も意外だった。時間は原子時計があるが、空間には原子レベルでの原器を作るのが難しいそうだ。本書を機に前著も再読して橋元時間論の理解を深めたくなった。
感染症と文明には切っても切れない関係がある ― 2020年06月11日
感染症と文明には切っても切れない関係がある
コロナ禍で増刷された次の新書を読んだ。
『感染症と文明:共生への道』(山本太郎/岩波新書)
発行は東日本大震災直後の2011年6月、私が読んだのは2020年4月28日発行の第6刷である。
コロナ禍になって『感染症の世界史』(石弘之)、『疫病と世界史』(マクニール)、『ペスト大流行』(村上陽一郎)などを読んだ流れで本書にも手を伸ばした。一連の読書で人類史における感染症の位置づけを把握できればと思った。
本書の前半にはマクニールの『疫病と世界史』やジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』などからの引用もあり、マクロな視点で感染症が人類の文明にどのように関わってきたかを説明している。だが、著者は歴史家ではなく国際的な感染症対策に従事してきた医師である。後半になると医師らしい視点の叙述が増えてくる。
私は本書によって初めて「帝国医療」「植民地医学」という言葉を知った。列強の帝国主義による植民地支配には感染症の研究が必須であり、その「帝国医療」「植民地医学」が近代医学の礎になっているのである。そう言えば「厚生省」という役所も戦時中に軍部の要請によって設立されたと聞いたことがある。
また、戦後のWHOによる天然痘根絶計画の実態に関する記述も興味深い。紀元前から存在した天然痘は1979年に根絶が宣言されたとは知っていたが、本書によって、その背後に日本人医師団のアフリカにおける壮絶な活躍があったことを知った。
そんな活躍を紹介しながらも、著者は次のように述べている。
「例えば天然痘根絶計画についても、この計画の成功が病原体と宿主を含む生態系にどのような影響を与え、長期的に人類の健康にどのような影響をもたらすことになるのか、現時点では誰にもわからない。」
本書のサブタイトルが「共生への道」となっているように、著者は病原体根絶の危険性を指摘し、次のように述べている、
「感染症のない社会を作ろうとする努力は、努力すればするほど、破滅的な悲劇の幕開けを準備することになるのかもしれない。大惨事を保全しないためは、「共生」の考え方が必要になる。」
コロナ禍で増刷された次の新書を読んだ。
『感染症と文明:共生への道』(山本太郎/岩波新書)
発行は東日本大震災直後の2011年6月、私が読んだのは2020年4月28日発行の第6刷である。
コロナ禍になって『感染症の世界史』(石弘之)、『疫病と世界史』(マクニール)、『ペスト大流行』(村上陽一郎)などを読んだ流れで本書にも手を伸ばした。一連の読書で人類史における感染症の位置づけを把握できればと思った。
本書の前半にはマクニールの『疫病と世界史』やジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』などからの引用もあり、マクロな視点で感染症が人類の文明にどのように関わってきたかを説明している。だが、著者は歴史家ではなく国際的な感染症対策に従事してきた医師である。後半になると医師らしい視点の叙述が増えてくる。
私は本書によって初めて「帝国医療」「植民地医学」という言葉を知った。列強の帝国主義による植民地支配には感染症の研究が必須であり、その「帝国医療」「植民地医学」が近代医学の礎になっているのである。そう言えば「厚生省」という役所も戦時中に軍部の要請によって設立されたと聞いたことがある。
また、戦後のWHOによる天然痘根絶計画の実態に関する記述も興味深い。紀元前から存在した天然痘は1979年に根絶が宣言されたとは知っていたが、本書によって、その背後に日本人医師団のアフリカにおける壮絶な活躍があったことを知った。
そんな活躍を紹介しながらも、著者は次のように述べている。
「例えば天然痘根絶計画についても、この計画の成功が病原体と宿主を含む生態系にどのような影響を与え、長期的に人類の健康にどのような影響をもたらすことになるのか、現時点では誰にもわからない。」
本書のサブタイトルが「共生への道」となっているように、著者は病原体根絶の危険性を指摘し、次のように述べている、
「感染症のない社会を作ろうとする努力は、努力すればするほど、破滅的な悲劇の幕開けを準備することになるのかもしれない。大惨事を保全しないためは、「共生」の考え方が必要になる。」
感染症との戦いに終わりはないと認識 ― 2020年04月11日
新型コロナウイルスで緊急事態宣言という時節柄、書店に並んだ関連書から次の文庫本を購入して読んだ。
『感染症の世界史』(石弘之/角川ソフィア文庫)
2014年刊行の原著を2018年に文庫したもので、私が入手したのは2020年3月25日の7刷である。売れているようだ。著者は元・朝日新聞編集委員の著名な環境問題ジャーナリストで、東大教授、駐ザンビア特命全権大使、国連顧問などを歴任している。
本書は世界史の本というよりは感染症の解説書であり、その中でそれぞれの感染症の歴史にも言及している。ジャーナリストらしく、広範な話題を目配りよくまとめていて勉強になる。われわれを取り巻く感染症の多種多様に圧倒され、人類の歴史は感染症との終わりなき戦いの持続だと納得させられる。
本書で取り上げている主な感染症は、エボラ出血熱、デング熱、天然痘、マラリア、ハシカ、結核、コレラ、ハンセン病、エイズ、鳥インフルエンザ、スペインかぜ、SARS、ラッサ熱、ペスト、肺炎、チフス、西ナイル熱、ピロリ菌、ヘルペス、カポジ肉腫、風疹、T細胞白血病などである。この羅列だけで頭がクラクラしてくる。これらの感染症を引き起こすにはウイルス、細菌、原虫などの微生物である。
ウイルスや微生物の多くは、われわれ生物にとって必要不可欠な存在であり、それと共存していくことが運命づけられている。撲滅できる相手ではない。本書は、そんな基本的枠組みをおさえたうえで、さまざまな感染症の起源と推移そして現状を解説している。
人類は進化競争の生き残りだが、ウイルスや微生物はより速い世代交代で進化してきた生き残りであり、これからも効率よく進化していける。抗生物質やワクチンが効かない新型が次々に登場する。だから、人類と感染症の戦いに終わりはない。
と言っても、本書は絶望を語っているのではない。地球環境の変化、人の行動の変化、高齢化などと感染症拡大の関係を解説し、終わりなき戦いと認識したうえで成すべき事項も述べている。
それにしても文明と感染症が切っても切れない表裏一体だと認識しなければならいのは、何ともやりきれない。
『感染症の世界史』(石弘之/角川ソフィア文庫)
2014年刊行の原著を2018年に文庫したもので、私が入手したのは2020年3月25日の7刷である。売れているようだ。著者は元・朝日新聞編集委員の著名な環境問題ジャーナリストで、東大教授、駐ザンビア特命全権大使、国連顧問などを歴任している。
本書は世界史の本というよりは感染症の解説書であり、その中でそれぞれの感染症の歴史にも言及している。ジャーナリストらしく、広範な話題を目配りよくまとめていて勉強になる。われわれを取り巻く感染症の多種多様に圧倒され、人類の歴史は感染症との終わりなき戦いの持続だと納得させられる。
本書で取り上げている主な感染症は、エボラ出血熱、デング熱、天然痘、マラリア、ハシカ、結核、コレラ、ハンセン病、エイズ、鳥インフルエンザ、スペインかぜ、SARS、ラッサ熱、ペスト、肺炎、チフス、西ナイル熱、ピロリ菌、ヘルペス、カポジ肉腫、風疹、T細胞白血病などである。この羅列だけで頭がクラクラしてくる。これらの感染症を引き起こすにはウイルス、細菌、原虫などの微生物である。
ウイルスや微生物の多くは、われわれ生物にとって必要不可欠な存在であり、それと共存していくことが運命づけられている。撲滅できる相手ではない。本書は、そんな基本的枠組みをおさえたうえで、さまざまな感染症の起源と推移そして現状を解説している。
人類は進化競争の生き残りだが、ウイルスや微生物はより速い世代交代で進化してきた生き残りであり、これからも効率よく進化していける。抗生物質やワクチンが効かない新型が次々に登場する。だから、人類と感染症の戦いに終わりはない。
と言っても、本書は絶望を語っているのではない。地球環境の変化、人の行動の変化、高齢化などと感染症拡大の関係を解説し、終わりなき戦いと認識したうえで成すべき事項も述べている。
それにしても文明と感染症が切っても切れない表裏一体だと認識しなければならいのは、何ともやりきれない。
『日経サイエンス』が『三体』を特集 ― 2020年01月29日
『日経サイエンス 2020年3月号』の特集は何と「中国のSF『三体』の科学」である。昨年末にこのSFを読んだばかりなので、この特集記事を興味深く読んだ。
この特集は次の4つの記事で構成されている。
(1) SF小説『三体』に見る天文学最前線:系外惑星の先にある異星文明
(2) 『三体』に出てくる量子通信は可能か?
(3) 三体問題に進展 周期解に新たな予感
(4) 作者劉慈欣が語るSFと科学技術
この4編の中では(1)が最も面白かった。天文学者への取材をベースに記者がまとめているのでわかりやすくて読みやすい。学者が『三体』を評価して楽しんでいることが伝わってくる。
(2)も物理学者への取材をベースに記者がまとめたものだが少し難しい。そもそも、小説では「智子(ソフォン)」という架空の人工量子が出てきて、かなり荒唐無稽な設定だと思っていたが、物理学者の目には興味深いフィクションに見えるようだ。
(3)は数学者が三体問題の現状を語った記事で、私には難しくて歯が立たなかった。
(4)は来日した際の作者の講演をまとめたものだが、その内容は普通すぎてあまり面白くない。
それにしても、真面目な科学雑誌が『三体』を大きく取り上げるのは、あの奇想天外なブッ飛んだSFに現代のサイエンスのさまざまな要素が反映されているのだろう。今夏の続編出版前に『三体』を再読したくなった。
この特集は次の4つの記事で構成されている。
(1) SF小説『三体』に見る天文学最前線:系外惑星の先にある異星文明
(2) 『三体』に出てくる量子通信は可能か?
(3) 三体問題に進展 周期解に新たな予感
(4) 作者劉慈欣が語るSFと科学技術
この4編の中では(1)が最も面白かった。天文学者への取材をベースに記者がまとめているのでわかりやすくて読みやすい。学者が『三体』を評価して楽しんでいることが伝わってくる。
(2)も物理学者への取材をベースに記者がまとめたものだが少し難しい。そもそも、小説では「智子(ソフォン)」という架空の人工量子が出てきて、かなり荒唐無稽な設定だと思っていたが、物理学者の目には興味深いフィクションに見えるようだ。
(3)は数学者が三体問題の現状を語った記事で、私には難しくて歯が立たなかった。
(4)は来日した際の作者の講演をまとめたものだが、その内容は普通すぎてあまり面白くない。
それにしても、真面目な科学雑誌が『三体』を大きく取り上げるのは、あの奇想天外なブッ飛んだSFに現代のサイエンスのさまざまな要素が反映されているのだろう。今夏の続編出版前に『三体』を再読したくなった。
池谷裕二氏のデビュー作『記憶力を強くする』は刺激的な本 ― 2020年01月11日
先日(2020年1月8日)の朝日新聞夕刊の「編集者がつくった本」というコラムで次の本を取り上げていた。
『記憶力を強くする:最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方』(池谷裕二/ブルーバックス/講談社)
このコラムは書籍編集者が自分が手掛けた思い出の本を語るシリーズである。当然ながら紹介されるのは昔の本だ。今回の執筆者は講談社の篠木和久氏で、『記憶力を強くする』の刊行は2001年1月、池谷裕二氏のデビュー作である。当時、著者は30歳の助手だった。
篠木氏は20年前に若き脳研究者に本書執筆を依頼した経緯を語り、本書が20万部を超えるベストセラーになったと述べている。私は数年前に本書を購入して未読のまま積んでいた。この本がそんなベストセラーとは知らなかった。
一昨年、『脳の意識 機械の意識:脳神経科学の挑戦』(渡辺正峰 /中公新書)を面白く読んだ際に、脳科学への興味がわいて池谷裕二氏の『進化しすぎた脳』(ブルーバックス)、『単純な脳、複雑な「私」』(ブルーバックス)、『受験脳の作り方』(新潮文庫)などを読んだ。しかし『記憶力を強くする』には手が伸びなかった。タイトルがハウツー本っぽいので既読本と似た内容だろうと思ったのだ。
朝日新聞夕刊のコラムに触発されて『記憶力を強くする』を読み、その面白さに引き込まれ、自身の不明を恥じた。池谷裕二氏の本を読むなら真っ先に本書を読むべきであった。
『記憶力を強くする』は脳科学の最先端の研究状況(当時の)を現場の研究者が紹介した本で、記憶のしくみが脳科学でどこまで解明されているかを解説している。非常に興味深いテーマであり、刺激的な本である。終盤では脳科学にとって「意識」が未踏の研究分野であることにも触れている。
『記憶力を強くする』の読後感は、渡辺正峰氏のデビュー作『脳の意識 機械の意識』の読後感に似ている。『脳の意識 機械の意識』を読む前に池谷裕二の『記憶力を強くする』を読んでおけば、もっと理解が深まっただろうと悔やまれる。
『記憶力を強くする:最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方』(池谷裕二/ブルーバックス/講談社)
このコラムは書籍編集者が自分が手掛けた思い出の本を語るシリーズである。当然ながら紹介されるのは昔の本だ。今回の執筆者は講談社の篠木和久氏で、『記憶力を強くする』の刊行は2001年1月、池谷裕二氏のデビュー作である。当時、著者は30歳の助手だった。
篠木氏は20年前に若き脳研究者に本書執筆を依頼した経緯を語り、本書が20万部を超えるベストセラーになったと述べている。私は数年前に本書を購入して未読のまま積んでいた。この本がそんなベストセラーとは知らなかった。
一昨年、『脳の意識 機械の意識:脳神経科学の挑戦』(渡辺正峰 /中公新書)を面白く読んだ際に、脳科学への興味がわいて池谷裕二氏の『進化しすぎた脳』(ブルーバックス)、『単純な脳、複雑な「私」』(ブルーバックス)、『受験脳の作り方』(新潮文庫)などを読んだ。しかし『記憶力を強くする』には手が伸びなかった。タイトルがハウツー本っぽいので既読本と似た内容だろうと思ったのだ。
朝日新聞夕刊のコラムに触発されて『記憶力を強くする』を読み、その面白さに引き込まれ、自身の不明を恥じた。池谷裕二氏の本を読むなら真っ先に本書を読むべきであった。
『記憶力を強くする』は脳科学の最先端の研究状況(当時の)を現場の研究者が紹介した本で、記憶のしくみが脳科学でどこまで解明されているかを解説している。非常に興味深いテーマであり、刺激的な本である。終盤では脳科学にとって「意識」が未踏の研究分野であることにも触れている。
『記憶力を強くする』の読後感は、渡辺正峰氏のデビュー作『脳の意識 機械の意識』の読後感に似ている。『脳の意識 機械の意識』を読む前に池谷裕二の『記憶力を強くする』を読んでおけば、もっと理解が深まっただろうと悔やまれる。
『理不尽な進化』はびっくりするほど面白いが難しい ― 2019年06月26日
進化論に関するとても面白い本を読んだ。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ』(吉川博満/朝日出版社)
先日読んだ 『科学する心』(池澤夏樹) で本書を知った。池澤氏は次のように紹介していた。
「これ(絶滅)については2014年に出た吉川博満の『理不尽な進化』(朝日出版社)という本が必読。ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた。まるで新しい生物の姿を教えられた。」
進化論には関心があるので「必読」と言われれば読まないわけにはいかない。巻末の著者紹介によれば吉川博満氏は「哲学、卓球、犬猫鳥、ロック、映画、単車などに関心がある文筆業」で、科学者ではない。本書の序章は「私たちは進化論が大好きである。」というフレーズで始まる。進化論好きが高じて進化論を深く考察する本書が誕生したようだ。
文章は読みやすくユーモアに富んでいる。進化論の面白さにグイグイ引き込まれていくが、決してわかりやすい本ではない。本書によって進化論の歴史や最新の進化学説を把握できるが、本書の主目的は「人類にとって進化論とは何か」というややこしいテーマである。後半になると哲学的展開になり、かなり難解である。
池澤氏の「ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた」という感想はよくわかる。私も同じ気持ちである。わが書架には進化論に関する一般向け概説書は20冊ばかり並んでいるが、本書を読んで、自分が進化論をいかに浅薄にしかとらえていなかったかを知った。
進化が進歩とは別物だとは了解していたつもりだったが、進化の理不尽さ不条理性を明快に指摘されると、やはりびっくりする。そして、進化論が内包する「歴史性」「哲学性」の迷路にたじろいでしまう。本書の終り近くの次の一節が印象に残った。
「1957年、ときの知識人の帝王ジャン=ポール・サルトルは、「マルクス主義はわれわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と宣言した。サルトルにとって哲学とは、時代と社会を支配する理念である。近代の第一期におけるそれはデカルトとロック、第二期はカントとヘーゲル、そして第三期(当時)はマルクス主義である、というわけだ。(…)いま私は、「ダーウィニズムこそ、われわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と叫びたい気分である(もし冥途のサルトルが「やっぱりマルクス主義は取り消し」と言ったならダーウィニズムはマルクス主義と交代ということになるし、いまなお譲らなければ四つ目の王座を用意することになるだろう)。
【蛇足】 本書の終わりの方でギリシア詩人アイスキュロスの「ハリネズミと狐」に関する一節が紹介されている。私はたまたま今月初めにアイスキュロスの現存全作品(といっても文庫本1冊)を読んだばかりである。「ハリネズミと狐」は思い出すことができず、わが記憶力の頼りなさを嘆きつつ調べてみると、この一節はギリシア悲劇詩人アイスキュロスではなくギリシア詩人アルキロコスのもののようだ。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ』(吉川博満/朝日出版社)
先日読んだ 『科学する心』(池澤夏樹) で本書を知った。池澤氏は次のように紹介していた。
「これ(絶滅)については2014年に出た吉川博満の『理不尽な進化』(朝日出版社)という本が必読。ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた。まるで新しい生物の姿を教えられた。」
進化論には関心があるので「必読」と言われれば読まないわけにはいかない。巻末の著者紹介によれば吉川博満氏は「哲学、卓球、犬猫鳥、ロック、映画、単車などに関心がある文筆業」で、科学者ではない。本書の序章は「私たちは進化論が大好きである。」というフレーズで始まる。進化論好きが高じて進化論を深く考察する本書が誕生したようだ。
文章は読みやすくユーモアに富んでいる。進化論の面白さにグイグイ引き込まれていくが、決してわかりやすい本ではない。本書によって進化論の歴史や最新の進化学説を把握できるが、本書の主目的は「人類にとって進化論とは何か」というややこしいテーマである。後半になると哲学的展開になり、かなり難解である。
池澤氏の「ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた」という感想はよくわかる。私も同じ気持ちである。わが書架には進化論に関する一般向け概説書は20冊ばかり並んでいるが、本書を読んで、自分が進化論をいかに浅薄にしかとらえていなかったかを知った。
進化が進歩とは別物だとは了解していたつもりだったが、進化の理不尽さ不条理性を明快に指摘されると、やはりびっくりする。そして、進化論が内包する「歴史性」「哲学性」の迷路にたじろいでしまう。本書の終り近くの次の一節が印象に残った。
「1957年、ときの知識人の帝王ジャン=ポール・サルトルは、「マルクス主義はわれわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と宣言した。サルトルにとって哲学とは、時代と社会を支配する理念である。近代の第一期におけるそれはデカルトとロック、第二期はカントとヘーゲル、そして第三期(当時)はマルクス主義である、というわけだ。(…)いま私は、「ダーウィニズムこそ、われわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と叫びたい気分である(もし冥途のサルトルが「やっぱりマルクス主義は取り消し」と言ったならダーウィニズムはマルクス主義と交代ということになるし、いまなお譲らなければ四つ目の王座を用意することになるだろう)。
【蛇足】 本書の終わりの方でギリシア詩人アイスキュロスの「ハリネズミと狐」に関する一節が紹介されている。私はたまたま今月初めにアイスキュロスの現存全作品(といっても文庫本1冊)を読んだばかりである。「ハリネズミと狐」は思い出すことができず、わが記憶力の頼りなさを嘆きつつ調べてみると、この一節はギリシア悲劇詩人アイスキュロスではなくギリシア詩人アルキロコスのもののようだ。
池澤夏樹氏の『科学する心』は文学的科学エッセイ ― 2019年06月07日
作家で詩人の池澤夏樹氏の次の本を読んだ。
『科学する心』(池澤夏樹/集英社インターナショナル)
文学書ではなく科学エッセイである。考えてみれば、彼の単著を読むのはこれが初めてである。新聞や雑誌で池澤夏樹氏の文章を読むことは多いし、彼が編纂した沖縄関連の本を読んだことはある。だが、小説や詩は読んでいない。避けていたのではなく機会がなかったに過ぎない。
池澤夏樹氏のイメージは文学への造詣が深い「いかにも文学者らしい文学者」である。父親は福永武彦(加田怜太郎)だし、個人で世界文学全集や日本文学全集を編集している。『世界文学を読みほどく』なんていう著書もある。そんな池澤氏が大学では物理学を専攻していたと聞いたことはある。
本書を読むと池澤氏が科学への造詣も深い科学好きだとわかる。理系出身の小説家は少なくないし、科学と文学は対立するものではない。一人の人間のなかに「科学する心」と「文学する心」の両方がある方が自然だと思う。私自身も「理系」「文系」という言葉や区分けを使うことがあるが、それを人間の分類に使うのは間違いだと思う。
閑話休題。『科学する心』はまことに文学的な科学エッセイだった。自身の「科学する体験」が語られているだけでなく、自分が書いた小説や詩への言及や引用も多い。科学をテーマに自身の身体を通して人間や人類のありようを考察するというスタイルが科学好き文学者的である。
12編のエッセイの中で私好みだったのは「進化と絶滅と愛惜」「体験の物理、日常の科学」「『昆虫記』の文学性」の3編である。進化は進歩ではなく人類が今あるのは運がよかっただけという話は歴史の見方に役立つ。科学は知識ではなく五感をもって自然に向き合う姿勢という考えには納得できる。ファーブル vs ダーウィンは興味深い科学史話である。
本書では多くの科学書が紹介されていて、著者の語り口に乗せられてつい読んでみたくなる。世の中はワクワクさせてくれる本にあふれていそうだが、わが人生にそのすべてを読む時間は与えられていない。
『科学する心』(池澤夏樹/集英社インターナショナル)
文学書ではなく科学エッセイである。考えてみれば、彼の単著を読むのはこれが初めてである。新聞や雑誌で池澤夏樹氏の文章を読むことは多いし、彼が編纂した沖縄関連の本を読んだことはある。だが、小説や詩は読んでいない。避けていたのではなく機会がなかったに過ぎない。
池澤夏樹氏のイメージは文学への造詣が深い「いかにも文学者らしい文学者」である。父親は福永武彦(加田怜太郎)だし、個人で世界文学全集や日本文学全集を編集している。『世界文学を読みほどく』なんていう著書もある。そんな池澤氏が大学では物理学を専攻していたと聞いたことはある。
本書を読むと池澤氏が科学への造詣も深い科学好きだとわかる。理系出身の小説家は少なくないし、科学と文学は対立するものではない。一人の人間のなかに「科学する心」と「文学する心」の両方がある方が自然だと思う。私自身も「理系」「文系」という言葉や区分けを使うことがあるが、それを人間の分類に使うのは間違いだと思う。
閑話休題。『科学する心』はまことに文学的な科学エッセイだった。自身の「科学する体験」が語られているだけでなく、自分が書いた小説や詩への言及や引用も多い。科学をテーマに自身の身体を通して人間や人類のありようを考察するというスタイルが科学好き文学者的である。
12編のエッセイの中で私好みだったのは「進化と絶滅と愛惜」「体験の物理、日常の科学」「『昆虫記』の文学性」の3編である。進化は進歩ではなく人類が今あるのは運がよかっただけという話は歴史の見方に役立つ。科学は知識ではなく五感をもって自然に向き合う姿勢という考えには納得できる。ファーブル vs ダーウィンは興味深い科学史話である。
本書では多くの科学書が紹介されていて、著者の語り口に乗せられてつい読んでみたくなる。世の中はワクワクさせてくれる本にあふれていそうだが、わが人生にそのすべてを読む時間は与えられていない。

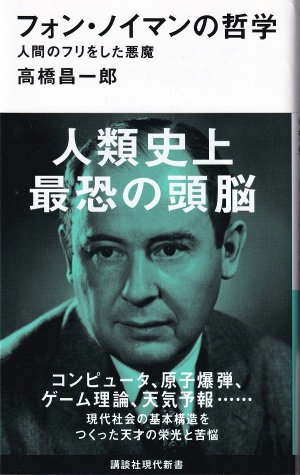



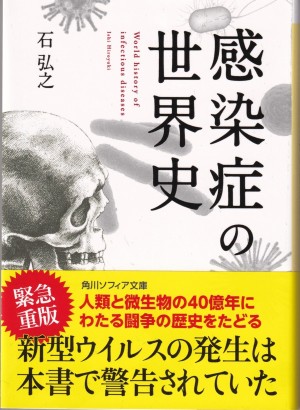




最近のコメント