『笑犬楼 VS. 偽伯爵』が醸し出す妙なる世界に陶酔 ― 2023年01月01日
『笑犬楼 VS. 偽伯爵』(筒井康隆・蓮實重彦/新潮社/2022.12)
正月を寿ぐめでたい気分にマッチした馥郁たる本である(読了したのは大晦日なのだが)。88歳の筒井康隆氏と86歳の蓮實重彦氏の対談・往復書簡からなる本書からは老大家二人の悠然奔放の香気が伝わってくる。
私は笑犬楼こと筒井康隆氏の著作はほぼ読んでいるが、偽伯爵こと蓮實重彦氏はあまり知らない。元東大総長が80歳で三島賞(新鋭を対象にした賞)を受賞して話題になった『伯爵夫人』を面白く読んだだけで、他の著書は読んでいない。新聞や雑誌で目にした文章からは、もってまわったネチっこい書き方をする面倒臭い評論家だとの印象を受けた。
書名にある「偽伯爵」は、蓮實氏の『伯爵夫人』に拠るのだろうと思ったが、古い映画に登場する偽伯爵になぞらえて淀川長治氏が蓮實氏につけた綽名だそうだ。
往復書簡には古い映画の話題が多い。大半が私の知らない映画なので、二人の盛り上がりを傍観するしかない。映画とは世代に密接に繋がった芸術だと認識し、両人の往年の感動を推しはかって羨むばかりだ。
筒井氏と蓮實氏は特に親しかったわけではない。過去には蓮實氏が筒井氏の『虚構船団』について「二ページ読んで読むのをやめた」と発言したこともあったそうだ。だが、本書では互いに相手を尊敬しあっていて、かすかな緊張感が漂う微妙なバランスが面白い。齢を重ねた老大家の恬然たる境地の妙を感じる。二人が共に高く評価するのは同世代の大江健三郎で、その作品を荒唐無稽と賞賛している。老人力の飛翔を感じる。
本書で特に心ひかれるのは、ひかえめに語りあう互いの一人息子夭折のくだりである。筒井氏は画家の一人息子を51歳で失い、蓮實氏は音楽家の一人息子を49歳で亡くしている。共に死因はがんである。そんな悲しい共通点を秘めていることが、二人の語り合いで紡ぎ出す自在な世界を陰影深くしていると思えた。
正月を寿ぐめでたい気分にマッチした馥郁たる本である(読了したのは大晦日なのだが)。88歳の筒井康隆氏と86歳の蓮實重彦氏の対談・往復書簡からなる本書からは老大家二人の悠然奔放の香気が伝わってくる。
私は笑犬楼こと筒井康隆氏の著作はほぼ読んでいるが、偽伯爵こと蓮實重彦氏はあまり知らない。元東大総長が80歳で三島賞(新鋭を対象にした賞)を受賞して話題になった『伯爵夫人』を面白く読んだだけで、他の著書は読んでいない。新聞や雑誌で目にした文章からは、もってまわったネチっこい書き方をする面倒臭い評論家だとの印象を受けた。
書名にある「偽伯爵」は、蓮實氏の『伯爵夫人』に拠るのだろうと思ったが、古い映画に登場する偽伯爵になぞらえて淀川長治氏が蓮實氏につけた綽名だそうだ。
往復書簡には古い映画の話題が多い。大半が私の知らない映画なので、二人の盛り上がりを傍観するしかない。映画とは世代に密接に繋がった芸術だと認識し、両人の往年の感動を推しはかって羨むばかりだ。
筒井氏と蓮實氏は特に親しかったわけではない。過去には蓮實氏が筒井氏の『虚構船団』について「二ページ読んで読むのをやめた」と発言したこともあったそうだ。だが、本書では互いに相手を尊敬しあっていて、かすかな緊張感が漂う微妙なバランスが面白い。齢を重ねた老大家の恬然たる境地の妙を感じる。二人が共に高く評価するのは同世代の大江健三郎で、その作品を荒唐無稽と賞賛している。老人力の飛翔を感じる。
本書で特に心ひかれるのは、ひかえめに語りあう互いの一人息子夭折のくだりである。筒井氏は画家の一人息子を51歳で失い、蓮實氏は音楽家の一人息子を49歳で亡くしている。共に死因はがんである。そんな悲しい共通点を秘めていることが、二人の語り合いで紡ぎ出す自在な世界を陰影深くしていると思えた。
2022年下半期に読んだ本のマイ・ベスト3 ― 2023年01月03日
2022年下半期に読んだ本のマイ・ベスト3を選んだ。
『アジアの歴史:東西交渉からみた前近代の世界像』(松田壽男/岩波現代文庫)
『トレブリンカ叛乱:死の収容所で起こったこと 1942-43』(サムエル・ヴィレンベルク/近藤康子訳/みすず書房)
『ビザンツ皇妃列伝:憧れの都に咲いた花』(井上浩一/筑摩書房/1996.3)
昨年後半はビザンツ史の概説書を10冊ほど読み、井上浩一氏のものがどれも面白かった。『生き残った帝国ビザンツ』と『ビザンツ皇妃列伝』のどちらにするか迷った末、エイヤで後者にした。
『アジアの歴史:東西交渉からみた前近代の世界像』(松田壽男/岩波現代文庫)
『トレブリンカ叛乱:死の収容所で起こったこと 1942-43』(サムエル・ヴィレンベルク/近藤康子訳/みすず書房)
『ビザンツ皇妃列伝:憧れの都に咲いた花』(井上浩一/筑摩書房/1996.3)
昨年後半はビザンツ史の概説書を10冊ほど読み、井上浩一氏のものがどれも面白かった。『生き残った帝国ビザンツ』と『ビザンツ皇妃列伝』のどちらにするか迷った末、エイヤで後者にした。
2022年に読んだ本のマイ・ベスト3 ― 2023年01月03日
昨年前半に読んだ本のベスト3と後半に読んだ本のベスト3から、2022年に読んだ本のベスト3を選んだ。
『暁の宇品:陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』(堀川恵子/講談社)
『異常:アノマリー』(エルヴェル・テリエ/加藤かおり訳/早川書房)
『トレブリンカ叛乱:死の収容所で起こったこと 1942-43』(サムエル・ヴィレンベルク/近藤康子訳/みすず書房)
マイ・ベスト3を選ぶのは、読んだ本の内容をどんどん忘れてしまうのが悲しいので、時おり過去の読後感を反芻し、少しでも記憶にとどめればと願うからである。無駄な抵抗だとは思うが。
《過去のベスト3》
2020年に読んだ本のベスト3
2021年に読んだ本のベスト3
『暁の宇品:陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』(堀川恵子/講談社)
『異常:アノマリー』(エルヴェル・テリエ/加藤かおり訳/早川書房)
『トレブリンカ叛乱:死の収容所で起こったこと 1942-43』(サムエル・ヴィレンベルク/近藤康子訳/みすず書房)
マイ・ベスト3を選ぶのは、読んだ本の内容をどんどん忘れてしまうのが悲しいので、時おり過去の読後感を反芻し、少しでも記憶にとどめればと願うからである。無駄な抵抗だとは思うが。
《過去のベスト3》
2020年に読んだ本のベスト3
2021年に読んだ本のベスト3
満洲を語る『李香蘭 私の半生』は面白い ― 2023年01月05日
小説『地図と拳』で満洲への関心がわいて『満洲暴走 隠された構造』を読み、カミさんの書架にあった次の自伝を思い出した。伝記の類を読みたくなる正月気分にマッチするので、さっそく読了した。
『李香蘭 私の半生』(山口淑子・藤原作弥/新潮社)
1987年に出た本である(書架にあったのは2000年の32刷)。もっと早く読んでおけばよかった思った。冒頭に平頂山事件(1932年)が出てくるからである。この事件は『地図と拳』の題材のひとつで、『満洲暴走 隠された構造』もこの事件に言及しているが、私はこの事件を知らなかった。
満洲生まれの山口淑子は11歳のとき、抗日ゲリラによる撫順炭鉱襲撃事件に遭遇し、日本軍によるゲリラ犯拷問も目撃、その生々しい記憶を綴っている。平頂山事件は炭鉱襲撃への報復として日本軍が付近の村の住民全員を虐殺した事件である。彼女が事件の全貌を知ったのは、近年(本書執筆の1987年の数年前だろう)、撫順を訪問した際だそうだ。
私が本書をスルーしていたのは、山口淑子=李香蘭に関する基本的なことは知っている気になっていたからである。皆が中国人だと思っていた女優・李香蘭が実は日本人で、終戦時には日本に協力した中国人として処刑されそうになり、危機一髪で日本人と証明されて無事に帰国した――という話は子供の頃から母(山口淑子より4歳下)に聞かされていた。また、かなり以前に読んだイサム・ノグチの伝記本にも、戦後の一時期、彼と結婚していた山口淑子に触れていた。
本書を読んで、山口淑子は私が思っていた以上に中国人になりきっていたと知った。国士風の父によって幼少期から中国語を学び、父の友人の中国人(地方政界の大物)宅にあずけられ、その娘として北京のミッションスクールに通っていたのだ。当時の北京の学校では抗日・排日の風潮が強く、学生たちの会合で各自が抗日の決意表明をする場があり、日本人であることを隠していた彼女も苦慮しつつ決意表明をしている。
また、女優になって初めて日本を訪問したとき、旅券チェックで中国人姿の彼女が日本人と気づいた警官から「チャンコロの服を着て、支那語なぞしゃべって、それで貴様、恥ずかしくないのか」と怒鳴られている。
父親はなぜ彼女を中国人の学校に入れたのだろうか。おそらく、満洲という地の国際性に惹かれていたからだ。満州人・華人・ロシア人・日本人など多様な人々が暮らす満洲には、軍部の思惑とは別の開放的なコスモポリタンの空気が流れていたのだと思う。大陸浪人や馬賊が跋扈するロマンや謀略のイメージも重なる。
彼女が所属した満映も右翼と左翼が共存する不思議な組織だ。大杉栄を虐殺した甘粕元大尉が満映総裁に就任するとき、現場では「もっとも非文化的な人間が満洲一の文化機関を支配するとは」との反発があったそうだ。しかし、総裁就任の後の甘粕元大尉は左翼系の人々からも評判がよかったらしい。ハミダシ者の新天地だったのか……。
本書で驚いたのは、終戦直前の1945年8月9日(長崎原爆の日)の上海の情景である。彼女が歌う盛大な野外コンサートが開催され、会場は中国人・欧米人・日本人が夏の涼し気なファッションを競う華やかな社交場になっていたそうだ。「あれは「真夏の白昼夢」のように思えてならない」と彼女は述べている。やはり上海は魔都だ。
本書は山口淑子の自伝(刊行時67歳)ではあるが、藤原作弥(ジャーナリスト。後の日銀総裁)との共著になっている。自伝にありがちな「記憶の捏造」避けるため、藤原氏が事実確認などの取材を担ったそうだ。好感がもてる執筆方法だと思う。
『李香蘭 私の半生』(山口淑子・藤原作弥/新潮社)
1987年に出た本である(書架にあったのは2000年の32刷)。もっと早く読んでおけばよかった思った。冒頭に平頂山事件(1932年)が出てくるからである。この事件は『地図と拳』の題材のひとつで、『満洲暴走 隠された構造』もこの事件に言及しているが、私はこの事件を知らなかった。
満洲生まれの山口淑子は11歳のとき、抗日ゲリラによる撫順炭鉱襲撃事件に遭遇し、日本軍によるゲリラ犯拷問も目撃、その生々しい記憶を綴っている。平頂山事件は炭鉱襲撃への報復として日本軍が付近の村の住民全員を虐殺した事件である。彼女が事件の全貌を知ったのは、近年(本書執筆の1987年の数年前だろう)、撫順を訪問した際だそうだ。
私が本書をスルーしていたのは、山口淑子=李香蘭に関する基本的なことは知っている気になっていたからである。皆が中国人だと思っていた女優・李香蘭が実は日本人で、終戦時には日本に協力した中国人として処刑されそうになり、危機一髪で日本人と証明されて無事に帰国した――という話は子供の頃から母(山口淑子より4歳下)に聞かされていた。また、かなり以前に読んだイサム・ノグチの伝記本にも、戦後の一時期、彼と結婚していた山口淑子に触れていた。
本書を読んで、山口淑子は私が思っていた以上に中国人になりきっていたと知った。国士風の父によって幼少期から中国語を学び、父の友人の中国人(地方政界の大物)宅にあずけられ、その娘として北京のミッションスクールに通っていたのだ。当時の北京の学校では抗日・排日の風潮が強く、学生たちの会合で各自が抗日の決意表明をする場があり、日本人であることを隠していた彼女も苦慮しつつ決意表明をしている。
また、女優になって初めて日本を訪問したとき、旅券チェックで中国人姿の彼女が日本人と気づいた警官から「チャンコロの服を着て、支那語なぞしゃべって、それで貴様、恥ずかしくないのか」と怒鳴られている。
父親はなぜ彼女を中国人の学校に入れたのだろうか。おそらく、満洲という地の国際性に惹かれていたからだ。満州人・華人・ロシア人・日本人など多様な人々が暮らす満洲には、軍部の思惑とは別の開放的なコスモポリタンの空気が流れていたのだと思う。大陸浪人や馬賊が跋扈するロマンや謀略のイメージも重なる。
彼女が所属した満映も右翼と左翼が共存する不思議な組織だ。大杉栄を虐殺した甘粕元大尉が満映総裁に就任するとき、現場では「もっとも非文化的な人間が満洲一の文化機関を支配するとは」との反発があったそうだ。しかし、総裁就任の後の甘粕元大尉は左翼系の人々からも評判がよかったらしい。ハミダシ者の新天地だったのか……。
本書で驚いたのは、終戦直前の1945年8月9日(長崎原爆の日)の上海の情景である。彼女が歌う盛大な野外コンサートが開催され、会場は中国人・欧米人・日本人が夏の涼し気なファッションを競う華やかな社交場になっていたそうだ。「あれは「真夏の白昼夢」のように思えてならない」と彼女は述べている。やはり上海は魔都だ。
本書は山口淑子の自伝(刊行時67歳)ではあるが、藤原作弥(ジャーナリスト。後の日銀総裁)との共著になっている。自伝にありがちな「記憶の捏造」避けるため、藤原氏が事実確認などの取材を担ったそうだ。好感がもてる執筆方法だと思う。
『「李香蘭」を生きて』は『李香蘭 私の半生』のダイジェスト版 ― 2023年01月06日
『李香蘭 私の半生』を読んでいるとき、ネット検索で次の本を見つけた。
『「李香蘭」を生きて:私の履歴書』(山口淑子/日本経済新聞社/2004.12)
『李香蘭 私の半生』は67歳の時点での自伝、似たタイトルの本書は84歳の時点の刊行である(山口淑子は2014年逝去。享年94歳)。新たな事実を綴った本かなと思って入手・読了したが、前著のダイジェスト版のような自伝だった。前著のようなコクはない。やや期待はずれだった。
本書は日経新聞の連載記事「私の履歴書」(2004年8月)をまとめたものである。私は新聞連載時に読んでいるはずだが、何も憶えていない。私が子供の頃に母か聞いたと思っていた李香蘭の話には、18年前に読んだ「私の履歴書」の記憶が混入していたのかもしれない。
本書の大半は『李香蘭 私の半生』と重複しているが、新たな話も少しだけある。その一つは、幼少期からの友人リュバ(ユダヤ系ロシア人)との53年ぶりの再会(1998年)である。終戦時の上海で山口淑子が裁判にかけられたとき、戸籍謄本入手を手配してくれた命の恩人である。再会したときの二人は78歳、スターリン時代を生き延びたリュバの人生にも歴史の非情が刻印されている。
もう一つ、興味深いのは、テレビ司会者になった山口淑子のパレスチナ取材である。この件、重信房子やアラファト議長を取材する写真が載っているだけで、詳しい記述はない。彼女が日本赤軍を取材したのは、かつての若者の旧満州への「海外雄飛」と重なるものを感じたからだろうか。もう少し語ってほしかった。
『「李香蘭」を生きて:私の履歴書』(山口淑子/日本経済新聞社/2004.12)
『李香蘭 私の半生』は67歳の時点での自伝、似たタイトルの本書は84歳の時点の刊行である(山口淑子は2014年逝去。享年94歳)。新たな事実を綴った本かなと思って入手・読了したが、前著のダイジェスト版のような自伝だった。前著のようなコクはない。やや期待はずれだった。
本書は日経新聞の連載記事「私の履歴書」(2004年8月)をまとめたものである。私は新聞連載時に読んでいるはずだが、何も憶えていない。私が子供の頃に母か聞いたと思っていた李香蘭の話には、18年前に読んだ「私の履歴書」の記憶が混入していたのかもしれない。
本書の大半は『李香蘭 私の半生』と重複しているが、新たな話も少しだけある。その一つは、幼少期からの友人リュバ(ユダヤ系ロシア人)との53年ぶりの再会(1998年)である。終戦時の上海で山口淑子が裁判にかけられたとき、戸籍謄本入手を手配してくれた命の恩人である。再会したときの二人は78歳、スターリン時代を生き延びたリュバの人生にも歴史の非情が刻印されている。
もう一つ、興味深いのは、テレビ司会者になった山口淑子のパレスチナ取材である。この件、重信房子やアラファト議長を取材する写真が載っているだけで、詳しい記述はない。彼女が日本赤軍を取材したのは、かつての若者の旧満州への「海外雄飛」と重なるものを感じたからだろうか。もう少し語ってほしかった。
李香蘭の自伝に続いて川島芳子の自伝を読んだ ― 2023年01月08日
先日読んだ『李香蘭 私の半生』は川島芳子との興味深い「交流」を描いていた。また、『「李香蘭」を生きて』は、巻末に十数頁にわたる「川島芳子(金璧輝)裁判記録(抜粋)」を収録している。
「男装の麗人」「東洋のマタハリ」と呼ばれた川島芳子(本名:愛新覺羅顯玗、漢名:金璧輝)は、日本の大陸浪人・川島浪速の養女として日本で教育を受けた清朝の王女である。終戦時、漢奸(日本に協力した中国人)として北京で銃殺刑になった。
『李香蘭 私の半生』によれば、山口淑子は17歳のときに天津東興楼のパーティで川島芳子出会っている。東興楼は川島芳子が経営する料亭である。二人ともヨシコなので、川島芳子は山口淑子に次のように語った。
「ボクは小さいころ“ヨコチャン”と呼ばれていたよ。だから、きみのことも“ヨコチャン”と呼ぶからな。ボクことは、“オニイチャン”と呼べよ」
当時30歳だった川島芳子は「活躍の時代」を既に終えた有名人で「頽廃的生活」をおくっていた。妹分にされた山口淑子は周辺の人から「あの人には近づかないほうがいい」と忠告されたそうだ。
山口淑子は川島芳子の「活躍」には言及していない。「東洋のマタハリ」が具体的に何をした人物か、私は知らない。ネット検索してみると、彼女の防諜活動については不明部分が多いようだ。彼女の自伝が文庫本になっていると知り、入手して読んでみた。
『動乱の蔭に:川島芳子自伝』(川島芳子/中公文庫/2021/9)
最近出た文庫本だが、原著は80年以上昔の1940年(皇紀2600年)刊行である。自伝とは言え、祐筆(伊賀上茂)による日本人向けの聞き書きの書である。この祐筆は本書冒頭の「川島芳子女士の横顔」(女史でなく女士だ)で次のように述べている。
「人前に出るには、多少の粉飾は常識である。自叙伝に於ても。化粧した姿で登場することが、咎めらるべきものでないと信ずる。従って、川島芳子女士のあり来し方を詮索するには、自叙伝以外に求めるのが賢明だいうことになる。」
祐筆が自ら粉飾と述べている通り、どこまでが事実かわからない眉唾自伝である。下手な小説のような冒険譚もある。
終章の「日本の皆様へ――歯に衣着せぬ記」は、当時の親日派中国人の日本人観の一端がうかがえて興味深い。
日本を医者、中国を患者と見たて、日本は名医だろうが患者の腹を切開して意外に重症なのに驚いているのでは、と述べている。患者の懸念である。また、日本人の中国人蔑視への苦言も呈している。中国からフランスやアメリカに留学した学生は帰国後、留学先の国を賛美するのに、日本に留学した学生は帰国後、こぞって排日運動に参加するとも指摘している。
川島芳子の生涯は中国と日本との葛藤におおわれていたのだと思う。
「男装の麗人」「東洋のマタハリ」と呼ばれた川島芳子(本名:愛新覺羅顯玗、漢名:金璧輝)は、日本の大陸浪人・川島浪速の養女として日本で教育を受けた清朝の王女である。終戦時、漢奸(日本に協力した中国人)として北京で銃殺刑になった。
『李香蘭 私の半生』によれば、山口淑子は17歳のときに天津東興楼のパーティで川島芳子出会っている。東興楼は川島芳子が経営する料亭である。二人ともヨシコなので、川島芳子は山口淑子に次のように語った。
「ボクは小さいころ“ヨコチャン”と呼ばれていたよ。だから、きみのことも“ヨコチャン”と呼ぶからな。ボクことは、“オニイチャン”と呼べよ」
当時30歳だった川島芳子は「活躍の時代」を既に終えた有名人で「頽廃的生活」をおくっていた。妹分にされた山口淑子は周辺の人から「あの人には近づかないほうがいい」と忠告されたそうだ。
山口淑子は川島芳子の「活躍」には言及していない。「東洋のマタハリ」が具体的に何をした人物か、私は知らない。ネット検索してみると、彼女の防諜活動については不明部分が多いようだ。彼女の自伝が文庫本になっていると知り、入手して読んでみた。
『動乱の蔭に:川島芳子自伝』(川島芳子/中公文庫/2021/9)
最近出た文庫本だが、原著は80年以上昔の1940年(皇紀2600年)刊行である。自伝とは言え、祐筆(伊賀上茂)による日本人向けの聞き書きの書である。この祐筆は本書冒頭の「川島芳子女士の横顔」(女史でなく女士だ)で次のように述べている。
「人前に出るには、多少の粉飾は常識である。自叙伝に於ても。化粧した姿で登場することが、咎めらるべきものでないと信ずる。従って、川島芳子女士のあり来し方を詮索するには、自叙伝以外に求めるのが賢明だいうことになる。」
祐筆が自ら粉飾と述べている通り、どこまでが事実かわからない眉唾自伝である。下手な小説のような冒険譚もある。
終章の「日本の皆様へ――歯に衣着せぬ記」は、当時の親日派中国人の日本人観の一端がうかがえて興味深い。
日本を医者、中国を患者と見たて、日本は名医だろうが患者の腹を切開して意外に重症なのに驚いているのでは、と述べている。患者の懸念である。また、日本人の中国人蔑視への苦言も呈している。中国からフランスやアメリカに留学した学生は帰国後、留学先の国を賛美するのに、日本に留学した学生は帰国後、こぞって排日運動に参加するとも指摘している。
川島芳子の生涯は中国と日本との葛藤におおわれていたのだと思う。
『君のクイズ』(小川哲)は秀逸なクイズ小説 ― 2023年01月10日
小川哲氏の新作長編を読了。一気読みだった。
『君のクイズ』(小川哲/朝日新聞出版)
事前に新聞記事などで、ゼロ文字回答を巡るクイズ小説だとは知っていた。早押しクイズは、問題の全文を読み上げる前に、問題文を推測してボタンを押すことが多い。問題文を何文字目まで読んだ時点でボタンを押せるかが勝負である。そんなクイズで、ゼロ文字つまり問題文を読む前にボタンを押して回答した人物がいた。なぜ、そんなことが可能だったのかというミステリーである。
この小説を読む前に、どうすればゼロ文字回答が可能か、いろいろ考えてみた。眉村卓の初期SF『クイズマン』のような超能力はないだろう。ITで超能力もどきを実現するのも難しそうだ。思い浮かぶのは映画『スラムドッグ$ミリオネア』で、あの映画では回答者の個人的な体験が回答に結びついていた。だが、どんな個人的体験を積めばゼロ文字回答が可能か、どう考えてもわからない。この小説自体がクイズだ。
読み終えて感服した。多少の無理を感じなくもないが、見事な論理展開である。アナウンサーが「問題です」と言った時点で、なぜ問題文を予測できたのかを説得的に解明している。
このクイズの設定は、テレビの生番組であり、クイズ強者同士の決勝の最終場面である。ボタンを押して誤答なら即敗退、正答なら優勝、絶対の自信がなければボタンは押せない。問題文を読み上げる前にボタンを押せば視聴者がヤラセと疑う可能性もある。なぜ、ゼロ文字回答になったのか。
クイズを取り巻くさまざまな状況を巧妙にストーリーに絡めているところに、この小説の面白さを感じた。
『君のクイズ』(小川哲/朝日新聞出版)
事前に新聞記事などで、ゼロ文字回答を巡るクイズ小説だとは知っていた。早押しクイズは、問題の全文を読み上げる前に、問題文を推測してボタンを押すことが多い。問題文を何文字目まで読んだ時点でボタンを押せるかが勝負である。そんなクイズで、ゼロ文字つまり問題文を読む前にボタンを押して回答した人物がいた。なぜ、そんなことが可能だったのかというミステリーである。
この小説を読む前に、どうすればゼロ文字回答が可能か、いろいろ考えてみた。眉村卓の初期SF『クイズマン』のような超能力はないだろう。ITで超能力もどきを実現するのも難しそうだ。思い浮かぶのは映画『スラムドッグ$ミリオネア』で、あの映画では回答者の個人的な体験が回答に結びついていた。だが、どんな個人的体験を積めばゼロ文字回答が可能か、どう考えてもわからない。この小説自体がクイズだ。
読み終えて感服した。多少の無理を感じなくもないが、見事な論理展開である。アナウンサーが「問題です」と言った時点で、なぜ問題文を予測できたのかを説得的に解明している。
このクイズの設定は、テレビの生番組であり、クイズ強者同士の決勝の最終場面である。ボタンを押して誤答なら即敗退、正答なら優勝、絶対の自信がなければボタンは押せない。問題文を読み上げる前にボタンを押せば視聴者がヤラセと疑う可能性もある。なぜ、ゼロ文字回答になったのか。
クイズを取り巻くさまざまな状況を巧妙にストーリーに絡めているところに、この小説の面白さを感じた。
敗戦までの昭和史は教訓に満ちているが… ― 2023年01月12日
昨年末に読んだ小説『地図と拳』(小川哲)をきっかけに満洲関連の本をいくつか読み、昭和の空気に浸った。で、いずれ読もうと積んでいた半藤一利氏の昭和史シリーズを読む気分になった。
『昭和史 1926-1945』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
語り下ろしの講義録なので、半藤氏が講談調にしゃべくる姿が目に浮かぶ(テレビで知っているだけだが)。本書は敗戦(1945年)までの20年間を語っている。
冒頭の「はじめの章」のタイトルは「昭和史の根底には“赤い夕陽の満州”があった」だ(表記が「満洲」でなく「満州」なので、以下「満州」を使う)。確かに「昭和史」という言葉を見ると、満州を知らない戦後生まれの私でも、見たことのない満州の光景を連想する。どこで刷り込まれたのだろうか。
この「はじめの章」で芥川龍之介の『支那游記』を紹介している。新聞社の特派員として訪れた中国の旅行記である。中国民衆の反日的な姿に言及している。日本人がロマンを抱いていた満州は、当初から反日感情を底流にはらんだ地だったのだ。
昭和の前半20年は、いったんは興隆した国が滅びていく時代であり、数々の失敗を積み重ねて事態が悪化していく歴史である。なぜ、こんなアホなことを……と思うことのくり返しで、ため息が出る。集団無責任体制は腹立たしい。
本書全般を通して「新聞が戦争を煽った」という指摘が多い。その通りだと思う。軍部の周到なマスコミ政策もあるだろうが、戦争になると新聞の発行部数が伸びるのである。新聞が戦争を煽り、読者が盛り上がり、それがさらに紙面に反映され、ワッショイ、ワッショイと突き進んで行く。
過去の反省をふまえれば、今後はそんなことにはならないだろう、と思いたい。だが、何とも心もとない。
日本を敗戦に導いた昭和史前半は教訓の宝庫でもある。半藤氏は本書末尾の数頁で「昭和史の20年がどういう教訓を私たちに示してくれた」を語っている。それを私なりに要約すると次の通りだ。
・国民的熱狂をつくってはいけない。
・抽象的観念論はダメ。具体的理性的方法論が大事。
・日本型タコツボ社会のエリート主義は独善に陥る。
・国際的常識を理解しなければならない。
・対症療法的短兵急な考えはダメ。大局観、複眼的思考が必要。
『昭和史 1926-1945』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
語り下ろしの講義録なので、半藤氏が講談調にしゃべくる姿が目に浮かぶ(テレビで知っているだけだが)。本書は敗戦(1945年)までの20年間を語っている。
冒頭の「はじめの章」のタイトルは「昭和史の根底には“赤い夕陽の満州”があった」だ(表記が「満洲」でなく「満州」なので、以下「満州」を使う)。確かに「昭和史」という言葉を見ると、満州を知らない戦後生まれの私でも、見たことのない満州の光景を連想する。どこで刷り込まれたのだろうか。
この「はじめの章」で芥川龍之介の『支那游記』を紹介している。新聞社の特派員として訪れた中国の旅行記である。中国民衆の反日的な姿に言及している。日本人がロマンを抱いていた満州は、当初から反日感情を底流にはらんだ地だったのだ。
昭和の前半20年は、いったんは興隆した国が滅びていく時代であり、数々の失敗を積み重ねて事態が悪化していく歴史である。なぜ、こんなアホなことを……と思うことのくり返しで、ため息が出る。集団無責任体制は腹立たしい。
本書全般を通して「新聞が戦争を煽った」という指摘が多い。その通りだと思う。軍部の周到なマスコミ政策もあるだろうが、戦争になると新聞の発行部数が伸びるのである。新聞が戦争を煽り、読者が盛り上がり、それがさらに紙面に反映され、ワッショイ、ワッショイと突き進んで行く。
過去の反省をふまえれば、今後はそんなことにはならないだろう、と思いたい。だが、何とも心もとない。
日本を敗戦に導いた昭和史前半は教訓の宝庫でもある。半藤氏は本書末尾の数頁で「昭和史の20年がどういう教訓を私たちに示してくれた」を語っている。それを私なりに要約すると次の通りだ。
・国民的熱狂をつくってはいけない。
・抽象的観念論はダメ。具体的理性的方法論が大事。
・日本型タコツボ社会のエリート主義は独善に陥る。
・国際的常識を理解しなければならない。
・対症療法的短兵急な考えはダメ。大局観、複眼的思考が必要。
昭和の戦後史はわが記憶に重なっていく ― 2023年01月14日
半藤一利氏の『昭和史 1926-1945』に続いて次の続編を読んだ。
『昭和史 戦後編 1945-1989』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
敗戦の年1945年以降の昭和史である。昭和は1989年(昭和64年)まで続くが、本書のメインは1972年の沖縄返還までの30年弱で、その後の十数年はエピローグに近い。これは1948年生まれの私の実感にマッチする。ある程度の時間が経たなければ「時代」を「歴史」として語るのは難しい。いま、歴史として語れるのが1972年まで、という見方は納得できる。
この時代の大きなテーマは「東京裁判」と「安保体制」であり、それに続く「高度経済成長」だと思う。
東京裁判をどう捉えるかはさまざまな見解がある。半藤氏は東京裁判を次のようなものと見ている。
(1) 日本の現代史を裁く
(2) 復讐の儀式
(3) 日本国民への啓蒙教化の目的
勝者が敗者を裁く戦争裁判は多分に政治的行為になる。いたしかたないことだ。本書で面白く思ったのは天皇訴追に関するくだりである。米国は天皇を訴追しないと決め、キーナン検事はそれを承知している。にもかかわらず、東条英機が天皇の責任につながりかねないことを、そうとは自覚せずに証言し、周りがあわてて証言を修正させたりしている。半藤氏は次のように述べている。
「いるのかいないのかわからないような犯罪的軍閥による戦争という「かたち」をつくるために、検事局も努力をし、弁護団も努力をし、被告も努力をしながら、裁判を進めていったわけです。敵も味方も汗を流してのまったく大変な作業であったんですね。」
安保体制は講和条約以降、現在まで継続している。その内容にさまざまな問題点はあるが、戦後日本の軽武装・経済優先路線のベースになったのは間違いない。
60年安保闘争は私が小学6年のとき、よく憶えている。「安保があると日本が米ソの戦争に巻き込まれる。だから反対しなければならない」と聞かされていた。あの頃は、石原慎太郎、江藤淳、清水幾太郎らが率先して安保反対を唱えていた。後の保守の論客だ。当時は、岸信介という元A級戦犯の傲慢な首相への反発が強かったようだ。
半藤氏は60年安保以降をザックリと次のように述べている。
「この次に出てくるのが岸内閣とはまったく方向を異にする池田内閣だったのです。それは佐藤内閣へと、すなわち吉田茂路線が長く長く続きます。そして昭和が終わったのち、その反動が来たかのように、憲法改正・再軍備の声が再び高くなってきます。自民党の本卦帰りというのかな。ま、先走って大ざっぱに言うと、そういう経過をたどって今日に至る、というわけです。」
『昭和史 戦後編 1945-1989』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
敗戦の年1945年以降の昭和史である。昭和は1989年(昭和64年)まで続くが、本書のメインは1972年の沖縄返還までの30年弱で、その後の十数年はエピローグに近い。これは1948年生まれの私の実感にマッチする。ある程度の時間が経たなければ「時代」を「歴史」として語るのは難しい。いま、歴史として語れるのが1972年まで、という見方は納得できる。
この時代の大きなテーマは「東京裁判」と「安保体制」であり、それに続く「高度経済成長」だと思う。
東京裁判をどう捉えるかはさまざまな見解がある。半藤氏は東京裁判を次のようなものと見ている。
(1) 日本の現代史を裁く
(2) 復讐の儀式
(3) 日本国民への啓蒙教化の目的
勝者が敗者を裁く戦争裁判は多分に政治的行為になる。いたしかたないことだ。本書で面白く思ったのは天皇訴追に関するくだりである。米国は天皇を訴追しないと決め、キーナン検事はそれを承知している。にもかかわらず、東条英機が天皇の責任につながりかねないことを、そうとは自覚せずに証言し、周りがあわてて証言を修正させたりしている。半藤氏は次のように述べている。
「いるのかいないのかわからないような犯罪的軍閥による戦争という「かたち」をつくるために、検事局も努力をし、弁護団も努力をし、被告も努力をしながら、裁判を進めていったわけです。敵も味方も汗を流してのまったく大変な作業であったんですね。」
安保体制は講和条約以降、現在まで継続している。その内容にさまざまな問題点はあるが、戦後日本の軽武装・経済優先路線のベースになったのは間違いない。
60年安保闘争は私が小学6年のとき、よく憶えている。「安保があると日本が米ソの戦争に巻き込まれる。だから反対しなければならない」と聞かされていた。あの頃は、石原慎太郎、江藤淳、清水幾太郎らが率先して安保反対を唱えていた。後の保守の論客だ。当時は、岸信介という元A級戦犯の傲慢な首相への反発が強かったようだ。
半藤氏は60年安保以降をザックリと次のように述べている。
「この次に出てくるのが岸内閣とはまったく方向を異にする池田内閣だったのです。それは佐藤内閣へと、すなわち吉田茂路線が長く長く続きます。そして昭和が終わったのち、その反動が来たかのように、憲法改正・再軍備の声が再び高くなってきます。自民党の本卦帰りというのかな。ま、先走って大ざっぱに言うと、そういう経過をたどって今日に至る、というわけです。」
『B面昭和史 1926-1945』は戦争の時代の民草の記録 ― 2023年01月16日
半藤一利氏の『昭和史 戦後編 1945-1989』に続いて次の「B面版」を読んだ。
『B面昭和史 1926-1945』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
政治・経済・外交などのA面でなく、世相史・文化史のB面である。1945年の敗戦までの時代を生きた民草の様子を、新聞の社会面・週刊誌風に語っている。戦後を省略したのは、前著『昭和史 戦後編』で戦後風俗にかなり言及したからだと思う。
「民草」は半藤氏が好んで使う言葉だ。「国民」や「民衆」とは微妙に使い分けている。ナショナリズムをベースに国の行方を案じて右往左往する集団が「国民」、日々の生活に追われながらもノホホンと日常を過ごす人々が「民草」、民草が集団になれば「民衆」――そんなニュアンスだろうか。
本書は、1930年生まれの半藤氏(敗戦時に15歳)の体験談を盛り込んだ歴史エッセイとも言える。半藤氏の父親が面白い。反骨の人である。戦前から「アメリカと戦争して日本が勝てるはずはない」とくり返し、山本五十六元帥戦死・アッツ島玉砕の報道に接し「総大将が戦死したり、守備隊が全滅したりする戦さに、勝利なんてない」と断言していたそうだ。
興味深い話題満載で、いちいち挙げると切りがないが、五・一五事件(1932年)のときに新聞に載った庄野潤三(当時は小学生)の作文には驚いた。世間は事件を起こした将校たちに同情的だったそうだが、庄野少年は「人殺しをしたり、けんかをしたりする世の中となったことを僕は大へん残念に思う」と綴っている。
井上清一中尉の妻の事件の記述には、もの足りなさを感じた。満州事変(1931年)以降、「招集令状→遺骨になって帰国」というケースが増えていた。井上中尉に赤紙が届いたとき、新妻は夫に心残りさせないためにみずから命を絶った。この事件は感動的に報道され、大日本国防婦人会発足のきっかけになったそうだ。本書はそこまでしか書いていない。井上中尉が満州の平頂山事件の当事者になることに触れていない(巻末の対談で澤地久枝は言及している)。当時の民草がこの事件を知るよしもなかったから、そこまで踏み込まなかったのだと思うが…
先日読んだ『李香蘭 私の半生』に出てくる「日劇七廻り半」事件も面白い。1941年の2月11日(紀元節)に日劇で開催されたショー「歌う李香蘭」に群衆が殺到し、警察が出動する騒ぎになった、というだけの話だ。『李香蘭 私の半生』を読んだとき、それほどの事件なのかと思いつつ『朝日新聞に見る日本の歩み』という新聞縮刷抄録集を調べると、この事件が収録されていた。面白いことに、その記事には李香蘭や日劇などの固有名詞は出てこない。某劇場に殺到した群衆に対する警察署長の叱責がニュースで、記者が群衆の醜態・無分別を延々と説教するヘンな記事だった。その事件を本書も採り上げている。時代を反映する出来事だったのだろうと思う。
本書で半藤氏の次のような感慨を述べている。印象に残った。
「そもそも歴史という非情にして皮肉な時の流れというものは、決してその時代に生きる民草によくわかるように素顔をそのままに見せてくれるようなことはしない。いつの世でもそうである。何か起きそうな気配すらも感ぜぬまま民草は、悠々閑々と時代の風にふかれてのんびりと、あるいはときに大きく揺れ動くだけ、そういうものなのである。」
『B面昭和史 1926-1945』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
政治・経済・外交などのA面でなく、世相史・文化史のB面である。1945年の敗戦までの時代を生きた民草の様子を、新聞の社会面・週刊誌風に語っている。戦後を省略したのは、前著『昭和史 戦後編』で戦後風俗にかなり言及したからだと思う。
「民草」は半藤氏が好んで使う言葉だ。「国民」や「民衆」とは微妙に使い分けている。ナショナリズムをベースに国の行方を案じて右往左往する集団が「国民」、日々の生活に追われながらもノホホンと日常を過ごす人々が「民草」、民草が集団になれば「民衆」――そんなニュアンスだろうか。
本書は、1930年生まれの半藤氏(敗戦時に15歳)の体験談を盛り込んだ歴史エッセイとも言える。半藤氏の父親が面白い。反骨の人である。戦前から「アメリカと戦争して日本が勝てるはずはない」とくり返し、山本五十六元帥戦死・アッツ島玉砕の報道に接し「総大将が戦死したり、守備隊が全滅したりする戦さに、勝利なんてない」と断言していたそうだ。
興味深い話題満載で、いちいち挙げると切りがないが、五・一五事件(1932年)のときに新聞に載った庄野潤三(当時は小学生)の作文には驚いた。世間は事件を起こした将校たちに同情的だったそうだが、庄野少年は「人殺しをしたり、けんかをしたりする世の中となったことを僕は大へん残念に思う」と綴っている。
井上清一中尉の妻の事件の記述には、もの足りなさを感じた。満州事変(1931年)以降、「招集令状→遺骨になって帰国」というケースが増えていた。井上中尉に赤紙が届いたとき、新妻は夫に心残りさせないためにみずから命を絶った。この事件は感動的に報道され、大日本国防婦人会発足のきっかけになったそうだ。本書はそこまでしか書いていない。井上中尉が満州の平頂山事件の当事者になることに触れていない(巻末の対談で澤地久枝は言及している)。当時の民草がこの事件を知るよしもなかったから、そこまで踏み込まなかったのだと思うが…
先日読んだ『李香蘭 私の半生』に出てくる「日劇七廻り半」事件も面白い。1941年の2月11日(紀元節)に日劇で開催されたショー「歌う李香蘭」に群衆が殺到し、警察が出動する騒ぎになった、というだけの話だ。『李香蘭 私の半生』を読んだとき、それほどの事件なのかと思いつつ『朝日新聞に見る日本の歩み』という新聞縮刷抄録集を調べると、この事件が収録されていた。面白いことに、その記事には李香蘭や日劇などの固有名詞は出てこない。某劇場に殺到した群衆に対する警察署長の叱責がニュースで、記者が群衆の醜態・無分別を延々と説教するヘンな記事だった。その事件を本書も採り上げている。時代を反映する出来事だったのだろうと思う。
本書で半藤氏の次のような感慨を述べている。印象に残った。
「そもそも歴史という非情にして皮肉な時の流れというものは、決してその時代に生きる民草によくわかるように素顔をそのままに見せてくれるようなことはしない。いつの世でもそうである。何か起きそうな気配すらも感ぜぬまま民草は、悠々閑々と時代の風にふかれてのんびりと、あるいはときに大きく揺れ動くだけ、そういうものなのである。」




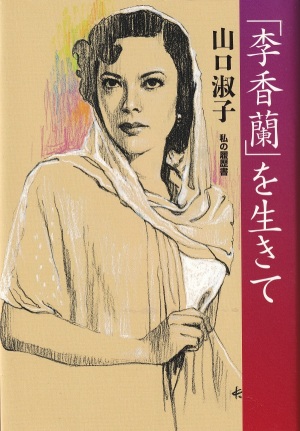
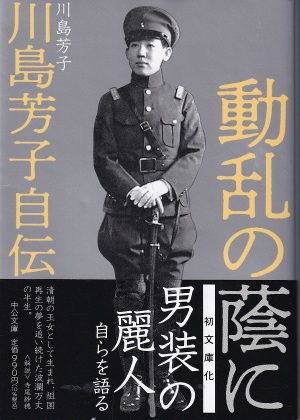

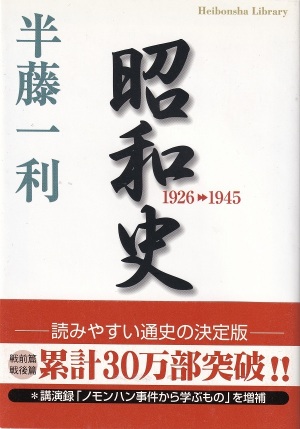
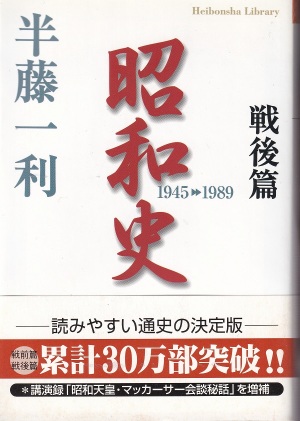

最近のコメント