『黒の試走車』を読んで星野芳郎の『マイ・カー』を想起 ― 2023年10月01日
先日読んだ梶山季之の『ルポ戦後縦断』に「産業スパイ」という記事があった。その冒頭は以下の通りだ。
「――さいきん私は、『黒の試走車』という小説を書いた。推理小説としては落第らしい。だが“企業スパイ”という、目新しい仕事を紹介したのが、どうやら読者にうけたらしく。1年たらずで発売20万部という、自分でも予想しなかったベストセラーになってしまった。」
私は『黒の試走車』を読んでいない。中学2年のときに週刊朝日連載で読んだ『夜の配当』以外に梶山作品は読んでいないと思う。急に彼の代表作『黒の試走車』が気がかりになり、岩波現代文庫版をネット古書店で入手して読んだ。
『黒の試走車』(梶山季之/岩波現代文庫/2007.7)
この小説のカッパノベルス版が出たのは1962年2月、私が田舎の中学1年生のときだ。いま読むと、戦後昭和の匂いがムンムンと伝わってくる。なぜか懐かしい。
この小説が売れたのは、産業スパイをテーマにしたからというより、車に関する情報を盛り込んでいたからだと思う。60年代初頭はマイカー時代の夜明けだった。高根の花の車への憧れは非常に強く、子供でもメーカーや車種の情報には詳しかった。車の新聞広告をうっとりと眺めていた。
本書を読みながら想起したのが星野芳郎の『マイ・カー:よい車わるい車を見破る法』である。ベストセラーになり、マイカーという言葉を定着させた。『マイ・カー』が出たのは1961年12月、『黒の試走車』の3カ月前、ほぼ同時期だ。『マイ・カー』はカッパブックス、『黒の試走車』はカッパノベル、両方ともベストセラーだ。あの頃の光文社の「カッパの本」は勢いがあった。
『マイ・カー』には「1962年の国産スポーツ・カー」という写真ページもある。『黒の試走車』の終盤、1962年型新車が自動車ショーに登場する。小説の「タイガー・スポーツセダン」のモデルになった「プリンス・スカイライン・スポーツ」の写真も『マイ・カー』で確認できる。二つの「カッパの本」は呼応している。
蛇足だが、私は1961年刊行の『マイ・カー』をリアルタイムで読んだわけではない。1960年代末期、私が大学生の頃、星野芳郎は技術論の論客として理工系学生に一定の影響力があった。1969年には『技術と人間』『日本の技術者』なども出た。古本屋で『マイ・カー』を見つけて読み、あの星野さんが昔はこんな本を書いていたのだと少々びっくりした。
「――さいきん私は、『黒の試走車』という小説を書いた。推理小説としては落第らしい。だが“企業スパイ”という、目新しい仕事を紹介したのが、どうやら読者にうけたらしく。1年たらずで発売20万部という、自分でも予想しなかったベストセラーになってしまった。」
私は『黒の試走車』を読んでいない。中学2年のときに週刊朝日連載で読んだ『夜の配当』以外に梶山作品は読んでいないと思う。急に彼の代表作『黒の試走車』が気がかりになり、岩波現代文庫版をネット古書店で入手して読んだ。
『黒の試走車』(梶山季之/岩波現代文庫/2007.7)
この小説のカッパノベルス版が出たのは1962年2月、私が田舎の中学1年生のときだ。いま読むと、戦後昭和の匂いがムンムンと伝わってくる。なぜか懐かしい。
この小説が売れたのは、産業スパイをテーマにしたからというより、車に関する情報を盛り込んでいたからだと思う。60年代初頭はマイカー時代の夜明けだった。高根の花の車への憧れは非常に強く、子供でもメーカーや車種の情報には詳しかった。車の新聞広告をうっとりと眺めていた。
本書を読みながら想起したのが星野芳郎の『マイ・カー:よい車わるい車を見破る法』である。ベストセラーになり、マイカーという言葉を定着させた。『マイ・カー』が出たのは1961年12月、『黒の試走車』の3カ月前、ほぼ同時期だ。『マイ・カー』はカッパブックス、『黒の試走車』はカッパノベル、両方ともベストセラーだ。あの頃の光文社の「カッパの本」は勢いがあった。
『マイ・カー』には「1962年の国産スポーツ・カー」という写真ページもある。『黒の試走車』の終盤、1962年型新車が自動車ショーに登場する。小説の「タイガー・スポーツセダン」のモデルになった「プリンス・スカイライン・スポーツ」の写真も『マイ・カー』で確認できる。二つの「カッパの本」は呼応している。
蛇足だが、私は1961年刊行の『マイ・カー』をリアルタイムで読んだわけではない。1960年代末期、私が大学生の頃、星野芳郎は技術論の論客として理工系学生に一定の影響力があった。1969年には『技術と人間』『日本の技術者』なども出た。古本屋で『マイ・カー』を見つけて読み、あの星野さんが昔はこんな本を書いていたのだと少々びっくりした。
世田谷パブリックシアターで舞台機構トラブル ― 2023年10月02日
本日(2023年10月2日)18時から、世田谷パブリックシアターでケムリ研究所の公演『眠くなっちゃった』(作・演出:ケラリーノ・サンドロヴィッチ)を観る予定だった。17時30分頃に劇場へ行くと、係の人が公演中止の「お知らせ」を配っていた。びっくりした。
舞台機構の深刻なトラブルで復旧に時間を要しているそうだ。今回の公演は1日から15日まで(その後、北九州、兵庫、新潟)だが、1日から7日昼までの公演は中止、7日夜以降については5日に発表とある。かなり大変な事態のようだ。
お知らせには、1日と2日の公演中止は「9月30日に発表済み」とある。コロナで芝居の公演中止が相次ぎ、劇場まで無駄足を運んだことが何度かあり、学習した私は注意してメールをチェックしている。今回の公演中止のメールは来ていない。Webでの告知だけだったようだ。
この芝居は発売してすぐ売り切れになる人気で、私は気合をいれて発売開始時刻に何とかチケットをゲットできた。新作の異色SF劇らしいと期待がふくらんでいた。観劇できなくなり、大変残念である。
舞台機構の深刻なトラブルで復旧に時間を要しているそうだ。今回の公演は1日から15日まで(その後、北九州、兵庫、新潟)だが、1日から7日昼までの公演は中止、7日夜以降については5日に発表とある。かなり大変な事態のようだ。
お知らせには、1日と2日の公演中止は「9月30日に発表済み」とある。コロナで芝居の公演中止が相次ぎ、劇場まで無駄足を運んだことが何度かあり、学習した私は注意してメールをチェックしている。今回の公演中止のメールは来ていない。Webでの告知だけだったようだ。
この芝居は発売してすぐ売り切れになる人気で、私は気合をいれて発売開始時刻に何とかチケットをゲットできた。新作の異色SF劇らしいと期待がふくらんでいた。観劇できなくなり、大変残念である。
『安倍晋三の正体』を読んで暗澹たる思い ― 2023年10月04日
『安倍晋三の正体』(適菜収/祥伝社新書)
保守の立場から安倍晋三を反日のエセ保守として徹底的に批判した新書を読んだ。この著者の本を読むのは初めてだ。著者紹介によれば、ニーチェ、小林秀雄、三島由紀夫、徒然草などに関する著書がある「作家」だそうだ。
安倍晋三については、かなり以前に読んだ『安倍三代』 (青木理)が印象に残っている。「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」と説得的に書いていた。本書が描く安倍晋三像も青木氏に近い。読売新聞記者の聞き書き『安倍晋三回顧録』を次のように評している。
「『回顧録』から見えるのは、安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ。内容も真偽不明で検証不可能な話の数々、寒々しい自慢話、酔っ払いのようなクダ、責任の押し付け、卑劣な言い訳のオンパレード。」
私は『回顧録』を読んでいない。読むまでもないと思っている。おそらく著者の指摘通りだろう。「外交の安倍」の実体が悲惨な失敗だったとの著者の指摘にも同感する。
解明すべきは、そんな安倍政権がなぜ長期にわたって続いたか、なぜ依然として安倍晋三を持ち上げる人間が多いか、である。愛想はいいが無知で軽薄なオボッチャマ政治家という人物が問題なのではなく、そんな人物を選んだ日本人の思考と行動、つまりは日本の社会の姿を省察せねばならない。難問だと思うが。
著者が己の立場としている「保守」の説明はやや難解だ。自死した西部邁に似ているかもしれない。「人間理性を懐疑する」「啓蒙主義を疑う」「進歩史観に与しない」「理想を提示しない」「漸進主義」――それが保守の立場だそうだ。そんな「本当の保守」の人は、やはり少数派だろうと思う。
「保守」と「革新」、「右翼」と「左翼」、「ナショナリズム」と「グローバリズム」などの区分け基準は人によってさまざまだ。そんな分類の有効性も疑わしい。レッテルにさほどの意味があるとは思えない。人間の集団の複雑さや単純さをどう捉えればいいのか、私にはよくわからない。わからなくても時間は流れる。思考停止することなく、考えるしかない。先送りできない判断や選択もある。
保守の立場から安倍晋三を反日のエセ保守として徹底的に批判した新書を読んだ。この著者の本を読むのは初めてだ。著者紹介によれば、ニーチェ、小林秀雄、三島由紀夫、徒然草などに関する著書がある「作家」だそうだ。
安倍晋三については、かなり以前に読んだ『安倍三代』 (青木理)が印象に残っている。「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」と説得的に書いていた。本書が描く安倍晋三像も青木氏に近い。読売新聞記者の聞き書き『安倍晋三回顧録』を次のように評している。
「『回顧録』から見えるのは、安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ。内容も真偽不明で検証不可能な話の数々、寒々しい自慢話、酔っ払いのようなクダ、責任の押し付け、卑劣な言い訳のオンパレード。」
私は『回顧録』を読んでいない。読むまでもないと思っている。おそらく著者の指摘通りだろう。「外交の安倍」の実体が悲惨な失敗だったとの著者の指摘にも同感する。
解明すべきは、そんな安倍政権がなぜ長期にわたって続いたか、なぜ依然として安倍晋三を持ち上げる人間が多いか、である。愛想はいいが無知で軽薄なオボッチャマ政治家という人物が問題なのではなく、そんな人物を選んだ日本人の思考と行動、つまりは日本の社会の姿を省察せねばならない。難問だと思うが。
著者が己の立場としている「保守」の説明はやや難解だ。自死した西部邁に似ているかもしれない。「人間理性を懐疑する」「啓蒙主義を疑う」「進歩史観に与しない」「理想を提示しない」「漸進主義」――それが保守の立場だそうだ。そんな「本当の保守」の人は、やはり少数派だろうと思う。
「保守」と「革新」、「右翼」と「左翼」、「ナショナリズム」と「グローバリズム」などの区分け基準は人によってさまざまだ。そんな分類の有効性も疑わしい。レッテルにさほどの意味があるとは思えない。人間の集団の複雑さや単純さをどう捉えればいいのか、私にはよくわからない。わからなくても時間は流れる。思考停止することなく、考えるしかない。先送りできない判断や選択もある。
大島新監督の『国葬の日』を沖縄で観た ― 2023年10月06日
いま、沖縄に来ている。気ままに過ごす日々のなか、那覇市の桜坂劇場で上映中の『国葬の日』(監督:大島新)を観た。2022年9月27日、安倍元首相国葬があった日に日本各地で取材したドキュメンタリー映画である。大島新監督の映画を観るのは2007年の『シアトリカル』以来だ。
私は、岸田首相が安倍元首相を国葬にすると決めたとき驚いた。まさか国葬はないだろうと思っていた私の認識は甘かった。世論調査では賛成4割、反対6割だった。元首相暗殺事件から2カ月後に実施された国葬の印象は薄く、その日、自分が何をしていたかも覚えていない。日記帳で確認すると、1年前の9月27日も沖縄に来ていて、のんびりした一日を過ごしていた。
この映画が2022年9月27日にキャメラをまわした場所は、国葬が行われた東京、元首相の出身地・山口、最期の地・奈良の他に京都、福島、沖縄、北海道、広島、静岡、長崎などだ。各地のさまざまな人々に国葬についてインタビューをしている。賛成の人も反対の人もいるが「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」というあいまいで無関心な人が多い。
この映画によって、映画監督の足立正生がいまだ健在なのを知り、少し驚いた。元首相暗殺事件に取材した映画を短期間で制作し、国葬の日に合わせて渋谷で上映会を開催していたのだ。足立監督に限らず国葬に強く反対を表明する人には高齢者が多い。
若い人には賛成が多いように思える。強く賛成しているというよりは時代の空気に流されて賛成しているように思えるのは、高齢者である私の偏見だろうか。「大統領やってた人だから」と国葬に賛意を表明する若者もいて、苦笑するより暗然とした。
映画のラストに流れるテロップによれば、内閣発表による献花した人数(25,889人)は、主催者発表の反対デモ参加者(16,600人)をかなり上回る。どちらもたいした数字ではないとも言えるが、献花した人が意外に多いなとも思う。
私は、岸田首相が安倍元首相を国葬にすると決めたとき驚いた。まさか国葬はないだろうと思っていた私の認識は甘かった。世論調査では賛成4割、反対6割だった。元首相暗殺事件から2カ月後に実施された国葬の印象は薄く、その日、自分が何をしていたかも覚えていない。日記帳で確認すると、1年前の9月27日も沖縄に来ていて、のんびりした一日を過ごしていた。
この映画が2022年9月27日にキャメラをまわした場所は、国葬が行われた東京、元首相の出身地・山口、最期の地・奈良の他に京都、福島、沖縄、北海道、広島、静岡、長崎などだ。各地のさまざまな人々に国葬についてインタビューをしている。賛成の人も反対の人もいるが「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」というあいまいで無関心な人が多い。
この映画によって、映画監督の足立正生がいまだ健在なのを知り、少し驚いた。元首相暗殺事件に取材した映画を短期間で制作し、国葬の日に合わせて渋谷で上映会を開催していたのだ。足立監督に限らず国葬に強く反対を表明する人には高齢者が多い。
若い人には賛成が多いように思える。強く賛成しているというよりは時代の空気に流されて賛成しているように思えるのは、高齢者である私の偏見だろうか。「大統領やってた人だから」と国葬に賛意を表明する若者もいて、苦笑するより暗然とした。
映画のラストに流れるテロップによれば、内閣発表による献花した人数(25,889人)は、主催者発表の反対デモ参加者(16,600人)をかなり上回る。どちらもたいした数字ではないとも言えるが、献花した人が意外に多いなとも思う。
台湾現代史の変動に翻弄される人生の記録 ― 2023年10月08日
『台湾の少年(1)(2)(3)(4)』(游珮芸、周見信/倉本知明訳/岩波書店)
台湾マンガである。昨年7月から今年1月にかけて翻訳版が刊行された。蔡焜霖という実在の人物の一代記に台湾現代史を反映させた大河マンガだ。読み応えがある。
蔡焜霖は1930年、日本統治下の台湾台中で生まれ、読書好きの青年となる。蒋介石政権の恐怖政治時代の1950年、20歳の時に無実の罪で逮捕され、離島の収容所で10年の刑期を過ごす。その後、紆余曲折や浮沈はあるものの、児童書出版や広告の世界で活躍し、現在は白色テロ時代の政治犯の名誉回復活動や人権教育に携わっている――そんな人の一代記マンガである。
全4巻の各巻のサブタイトルは「1 統治時代生まれ」「2 収容所島の十年」「3 戒厳令下の編集者」「4 民主化の時代へ」となっている。
私が台湾に関心を抱いたのは6年前だ。『台湾:四百年の歴史と展望』、『台湾とは何か』、『台湾海峡一九四九』をはじめ何冊かの関連書を読み、4泊の観光旅行にも行った。
複雑で波瀾に満ちた台湾現代史の概要をある程度は把握しているつもりだった。だが、本書を読むまで、蒋介石政権下の白色テロの苛烈な実態に思いを寄せることはなかった。火焼島の収容所も知らなかった。高校の読書会に参加しただけで懲役10年、少し逆らえばすぐに銃殺、軍や警察の方針は「百人を誤殺しても一人の犯人逃すな」だったという。毛沢東思想浸透への強い怖れがあったにしても、ひどい話だ。
最終巻は民主化の時代であり、主人公が晩年を迎えてのハッピーエンドという雰囲気も漂う。だが、現実の世界はそう言い切れないのが悲しい。台湾の未来は不透明だ。
主人公の以下の述懐が印象に残った。
「1989年に天安門事件が起こるまで、ぼくは中国が台湾よりも開放的な国だと思っていたんです。」「大切なのは革命そのものではなく、平和裏に行われる改革なんです。それは会社も国家も同じで、それこそが正しい道なんです。」
台湾マンガである。昨年7月から今年1月にかけて翻訳版が刊行された。蔡焜霖という実在の人物の一代記に台湾現代史を反映させた大河マンガだ。読み応えがある。
蔡焜霖は1930年、日本統治下の台湾台中で生まれ、読書好きの青年となる。蒋介石政権の恐怖政治時代の1950年、20歳の時に無実の罪で逮捕され、離島の収容所で10年の刑期を過ごす。その後、紆余曲折や浮沈はあるものの、児童書出版や広告の世界で活躍し、現在は白色テロ時代の政治犯の名誉回復活動や人権教育に携わっている――そんな人の一代記マンガである。
全4巻の各巻のサブタイトルは「1 統治時代生まれ」「2 収容所島の十年」「3 戒厳令下の編集者」「4 民主化の時代へ」となっている。
私が台湾に関心を抱いたのは6年前だ。『台湾:四百年の歴史と展望』、『台湾とは何か』、『台湾海峡一九四九』をはじめ何冊かの関連書を読み、4泊の観光旅行にも行った。
複雑で波瀾に満ちた台湾現代史の概要をある程度は把握しているつもりだった。だが、本書を読むまで、蒋介石政権下の白色テロの苛烈な実態に思いを寄せることはなかった。火焼島の収容所も知らなかった。高校の読書会に参加しただけで懲役10年、少し逆らえばすぐに銃殺、軍や警察の方針は「百人を誤殺しても一人の犯人逃すな」だったという。毛沢東思想浸透への強い怖れがあったにしても、ひどい話だ。
最終巻は民主化の時代であり、主人公が晩年を迎えてのハッピーエンドという雰囲気も漂う。だが、現実の世界はそう言い切れないのが悲しい。台湾の未来は不透明だ。
主人公の以下の述懐が印象に残った。
「1989年に天安門事件が起こるまで、ぼくは中国が台湾よりも開放的な国だと思っていたんです。」「大切なのは革命そのものではなく、平和裏に行われる改革なんです。それは会社も国家も同じで、それこそが正しい道なんです。」
台詞がデタラメでも芝居は成り立つ ― 2023年10月11日
那覇市安里の「ひめゆりピースホール」という小さな劇場で『カフウムイ:不思議の島の夜の夢』(脚本・演出:扇田拓也、出演:東谷英人、久我真希人、知花小百合、古謝渚、峯井南希、岸野健太)という芝居を観た。
このホールはひめゆり同窓会館2階にある。エレベーターはない。チラシには住所表記に加えて「栄町市場南口より突き当り」との表示があり、実際、その通りの場所にあった。風情ある路地裏だった。
この芝居はシェイクスピアの『夏の夜の夢』をガジュマルが茂る沖縄の森に置き換えたファンタジー劇である。沖縄方言で「カフウ」は果報、「ムイ」は森、「カフウムイ」は「果報の森」である。出演者6人が仮面や被り物で何役をもこなす70分の祝祭劇だ。
芝居が始まる5分前に脚本・演出の扇田拓也氏(演劇評論家の故・扇田昭彦の子息)による解説があった。なぜ解説が必要か、この芝居の台詞がジブリッシュなるデタラメ語なので、その点に関する事前の「おことわり」なのだ。だが、この解説自体がすでに芝居の始まりだったと、開幕直後に気づく仕掛けになっていた。
パントマイムのように演技だけで意思を伝えることは可能だが、ジブリッシュ芝居は黙劇ではない。役者たちは大声でしゃべり歌う。観客である私は、台詞を聞き取って解釈しようと努力する必要がないので、音楽を聴いているのに近い感覚になる。この芝居の音楽は生演奏で、演奏者(ときに歌う)も舞台上にいる。だから、音楽とデタラメ語台詞が一体化する。私には貴重は観劇体験だった。
このホールはひめゆり同窓会館2階にある。エレベーターはない。チラシには住所表記に加えて「栄町市場南口より突き当り」との表示があり、実際、その通りの場所にあった。風情ある路地裏だった。
この芝居はシェイクスピアの『夏の夜の夢』をガジュマルが茂る沖縄の森に置き換えたファンタジー劇である。沖縄方言で「カフウ」は果報、「ムイ」は森、「カフウムイ」は「果報の森」である。出演者6人が仮面や被り物で何役をもこなす70分の祝祭劇だ。
芝居が始まる5分前に脚本・演出の扇田拓也氏(演劇評論家の故・扇田昭彦の子息)による解説があった。なぜ解説が必要か、この芝居の台詞がジブリッシュなるデタラメ語なので、その点に関する事前の「おことわり」なのだ。だが、この解説自体がすでに芝居の始まりだったと、開幕直後に気づく仕掛けになっていた。
パントマイムのように演技だけで意思を伝えることは可能だが、ジブリッシュ芝居は黙劇ではない。役者たちは大声でしゃべり歌う。観客である私は、台詞を聞き取って解釈しようと努力する必要がないので、音楽を聴いているのに近い感覚になる。この芝居の音楽は生演奏で、演奏者(ときに歌う)も舞台上にいる。だから、音楽とデタラメ語台詞が一体化する。私には貴重は観劇体験だった。
37年前の島田雅彦俳優体験記を読んだ ― 2023年10月13日
ネット古書を探索して入手した次の本を読んだ。
『汗のドレス』(島田雅彦・唐十郎/河出書房新社/1986.6)
今月末、下北沢ザ・スズナリで新宿梁山泊の〈若衆公演〉『少女都市からの呼び声』(作:唐十郎、演出:金守珍)観劇を予定している。その前に本書を読みたかったのだ。島田雅彦は37年前の24歳のとき、この芝居に出演している。本書は、そのときの島田雅彦の俳優体験記であり、唐十郎のコメント・エッセイも収録している。
私は今年になって『少女都市からの呼び声』を既に2回観ている。今月末予定の観劇は3回目になる。演出はどれも金守珍だが、舞台や役者はかなり異なる。最初に観たのは花園神社境内のテント公演版である。2度目に観たのはオープンしたばかりのシアター・ミラノザでの大劇場版だ。そして次回は小劇場版になる。
『少女都市からの呼び声』は、状況劇場が1969年に紅テントで上演した『少女都市』をベースにした芝居だ。この『少女都市』が私の紅テント初体験で、強烈な印象を受け、その後、紅テントを追うことになる。今回の三連続公演を追うのも、初体験の衝撃の余波だと思う。
シアター・ミラノザでの公演パンフに島田雅彦のインタビュー記事があり、その記事で本書を知った。花園神社のテント公演を観たとき、事前に読んだ戯曲には登場しない「養老先生」「インターン」「一輪車に乗った島田雅彦」などが出てきたので、色々なバージョンがあるのだろうと思ったが、本書を読んでおよその事情がわかった。
唐十郎は編集者から島田雅彦の出演を打診され、当時刊行されていた養老孟司と島田雅彦の対談本を元に「養老先生」と「インターン」の会話などを追加したのだ。このとき、島田雅彦は一輪車で登場したわけではないが、舞台でヴァイオリンを披露している。
本書は芝居の練習から本番終了までの体験記で、内側から見た芝居つくりを窺えて興味深い。島田雅彦は俳優に転職したのではなく、体験記をまとめるという編集者の企画に乗ったわけだから、劇団内での立場は微妙だったと思う。そんな立場の克服を試みるさまも伝わってくる。
本書の末尾近くの以下の文章が、役者と作家の違いをうまく表現していると思った。
「この文章は芝居の陶酔が醒めたあとでなければ、書けなかった。(略)ぼくは大変、自虐的なことをやったといわざるを得ない。体験を言葉に翻訳することには無理がある。芝居体験は疲れた中枢のリハビリテーションになったが、そのプロセスを記述する作業はリハビリの成果を半減させてしまったようだ。」
『汗のドレス』(島田雅彦・唐十郎/河出書房新社/1986.6)
今月末、下北沢ザ・スズナリで新宿梁山泊の〈若衆公演〉『少女都市からの呼び声』(作:唐十郎、演出:金守珍)観劇を予定している。その前に本書を読みたかったのだ。島田雅彦は37年前の24歳のとき、この芝居に出演している。本書は、そのときの島田雅彦の俳優体験記であり、唐十郎のコメント・エッセイも収録している。
私は今年になって『少女都市からの呼び声』を既に2回観ている。今月末予定の観劇は3回目になる。演出はどれも金守珍だが、舞台や役者はかなり異なる。最初に観たのは花園神社境内のテント公演版である。2度目に観たのはオープンしたばかりのシアター・ミラノザでの大劇場版だ。そして次回は小劇場版になる。
『少女都市からの呼び声』は、状況劇場が1969年に紅テントで上演した『少女都市』をベースにした芝居だ。この『少女都市』が私の紅テント初体験で、強烈な印象を受け、その後、紅テントを追うことになる。今回の三連続公演を追うのも、初体験の衝撃の余波だと思う。
シアター・ミラノザでの公演パンフに島田雅彦のインタビュー記事があり、その記事で本書を知った。花園神社のテント公演を観たとき、事前に読んだ戯曲には登場しない「養老先生」「インターン」「一輪車に乗った島田雅彦」などが出てきたので、色々なバージョンがあるのだろうと思ったが、本書を読んでおよその事情がわかった。
唐十郎は編集者から島田雅彦の出演を打診され、当時刊行されていた養老孟司と島田雅彦の対談本を元に「養老先生」と「インターン」の会話などを追加したのだ。このとき、島田雅彦は一輪車で登場したわけではないが、舞台でヴァイオリンを披露している。
本書は芝居の練習から本番終了までの体験記で、内側から見た芝居つくりを窺えて興味深い。島田雅彦は俳優に転職したのではなく、体験記をまとめるという編集者の企画に乗ったわけだから、劇団内での立場は微妙だったと思う。そんな立場の克服を試みるさまも伝わってくる。
本書の末尾近くの以下の文章が、役者と作家の違いをうまく表現していると思った。
「この文章は芝居の陶酔が醒めたあとでなければ、書けなかった。(略)ぼくは大変、自虐的なことをやったといわざるを得ない。体験を言葉に翻訳することには無理がある。芝居体験は疲れた中枢のリハビリテーションになったが、そのプロセスを記述する作業はリハビリの成果を半減させてしまったようだ。」
マクニールの『世界史』は西欧の興隆分析の書 ― 2023年10月15日
いずれ読もうと思いつつ先延ばしにしていた世界史の本をやっと読了した。
『世界史(上)(下)』(W・H・マクニール/増田義郎、佐々木昭夫訳/中公文庫)
著者はカナダ出身の1917年生まれ、シカゴ大学で長く教鞭をとった歴史学者だ(2016年没)。原著の初版は1967年、その後改訂を重ね、本書は1999年の第4版の訳書である。
コロナ禍の3年前、この著者の『疫病と世界史』を面白く読んだ。本書にも疫病への言及が多い。目配りのいい比較文明史のような本である。興味深く読めた。
世界史の本は、高校の教科書から数十巻の叢書までさまざまだが、一気に読むなら一人の著者によるものに限る。分量も本書のような文庫本2冊ぐらいまでがいい。教科書は1冊だが、おびただしい固有名詞が詰まった圧縮記述なので通して読むのが難しい。
一人の著者による世界史記述は何らかのストーリーを語るスタイルになることが多く、さまざまな事象の関連をつかみやすい。そんな世界史本でザックリ読みやすいのはハラリの『サピエンス全史』だった。出口治明氏の『全世界史』も比較的読みやすかったが疲れた。予備校講師・青木裕司氏による受験生向けの『世界史B講義の実況中継』は、語り口に惹かれたが、固有名詞の奔流にぐったりした。
本書は巨視的に世界各地の文明の盛衰や交流を語っていて、固有名詞は必要最小限しか登場しない。と言っても、高校世界史程度の知識を前提にした概説で、次のような4部構成である。
第Ⅰ部 ユーラシア大文明の誕生とその成立(紀元前500年まで)
第Ⅱ部 諸文明の平衡状態(紀元前500年ー後1500年)
第Ⅲ部 西欧の優勢
第Ⅳ部 地球規模でのコスモポリタニズムのはじまり
本書は宗教への言及が多い。宗教は時代精神のようなものであり、文明を支える機能があるらしい。著者がキリスト教文明圏の人なので、宗教のウエイトが大きい世界史になっているような気もする。偏見かもしれないが。
「イスラムとナショナリズムは相容れない」との指摘には得心した。当初は西欧を圧倒していたイスラムが、近代になって西欧に追い抜かれた要因の一つである。
本書には「文明の発生→周辺蛮族の侵攻→蛮族の文明化」というパターンがしばしば登場する。それに絡んだ戦争の形態の変遷が興味深い。馬車の戦車、軽騎兵、重騎兵や歩兵、火器などの解説になるほどと思った。あらためて、人類の歴史の大半は戦争の歴史だと気づく。
本書は西欧中心の世界史ではなく、インド、中国、アフリカにも相応のページを割き、世界各地に言及している。日本も随所に登場する。とは言っても、ある意味では、やはり西欧中心の世界史記述の印象を受ける。それは、仕方ないことだとも思う。
著者が指摘しているように、人類の歴史のなかで西欧は長いあいだ後進地帯だった。いつ頃から西欧中心になったかは研究者によって見解の違いがあると思う。著者は西欧が優勢になったのは17世紀頃と見なしている。本書のメインテーマは「なぜ西欧が優勢になったか」「西欧の興隆の内実な何か」の分析・検討である。それが、世界史を語るうえでの最重要課題なの確かだ。それを西欧視点と見るのは間違いなのだろう。
本書は第Ⅲ部までが面白い。第Ⅳ部で現代に近づいてくると総花的エッセイ風になる。現代を巨視的な歴史家の眼で捉えるのは無理なのかもしれない。
『世界史(上)(下)』(W・H・マクニール/増田義郎、佐々木昭夫訳/中公文庫)
著者はカナダ出身の1917年生まれ、シカゴ大学で長く教鞭をとった歴史学者だ(2016年没)。原著の初版は1967年、その後改訂を重ね、本書は1999年の第4版の訳書である。
コロナ禍の3年前、この著者の『疫病と世界史』を面白く読んだ。本書にも疫病への言及が多い。目配りのいい比較文明史のような本である。興味深く読めた。
世界史の本は、高校の教科書から数十巻の叢書までさまざまだが、一気に読むなら一人の著者によるものに限る。分量も本書のような文庫本2冊ぐらいまでがいい。教科書は1冊だが、おびただしい固有名詞が詰まった圧縮記述なので通して読むのが難しい。
一人の著者による世界史記述は何らかのストーリーを語るスタイルになることが多く、さまざまな事象の関連をつかみやすい。そんな世界史本でザックリ読みやすいのはハラリの『サピエンス全史』だった。出口治明氏の『全世界史』も比較的読みやすかったが疲れた。予備校講師・青木裕司氏による受験生向けの『世界史B講義の実況中継』は、語り口に惹かれたが、固有名詞の奔流にぐったりした。
本書は巨視的に世界各地の文明の盛衰や交流を語っていて、固有名詞は必要最小限しか登場しない。と言っても、高校世界史程度の知識を前提にした概説で、次のような4部構成である。
第Ⅰ部 ユーラシア大文明の誕生とその成立(紀元前500年まで)
第Ⅱ部 諸文明の平衡状態(紀元前500年ー後1500年)
第Ⅲ部 西欧の優勢
第Ⅳ部 地球規模でのコスモポリタニズムのはじまり
本書は宗教への言及が多い。宗教は時代精神のようなものであり、文明を支える機能があるらしい。著者がキリスト教文明圏の人なので、宗教のウエイトが大きい世界史になっているような気もする。偏見かもしれないが。
「イスラムとナショナリズムは相容れない」との指摘には得心した。当初は西欧を圧倒していたイスラムが、近代になって西欧に追い抜かれた要因の一つである。
本書には「文明の発生→周辺蛮族の侵攻→蛮族の文明化」というパターンがしばしば登場する。それに絡んだ戦争の形態の変遷が興味深い。馬車の戦車、軽騎兵、重騎兵や歩兵、火器などの解説になるほどと思った。あらためて、人類の歴史の大半は戦争の歴史だと気づく。
本書は西欧中心の世界史ではなく、インド、中国、アフリカにも相応のページを割き、世界各地に言及している。日本も随所に登場する。とは言っても、ある意味では、やはり西欧中心の世界史記述の印象を受ける。それは、仕方ないことだとも思う。
著者が指摘しているように、人類の歴史のなかで西欧は長いあいだ後進地帯だった。いつ頃から西欧中心になったかは研究者によって見解の違いがあると思う。著者は西欧が優勢になったのは17世紀頃と見なしている。本書のメインテーマは「なぜ西欧が優勢になったか」「西欧の興隆の内実な何か」の分析・検討である。それが、世界史を語るうえでの最重要課題なの確かだ。それを西欧視点と見るのは間違いなのだろう。
本書は第Ⅲ部までが面白い。第Ⅳ部で現代に近づいてくると総花的エッセイ風になる。現代を巨視的な歴史家の眼で捉えるのは無理なのかもしれない。
『終わりよければすべてよし』と『尺には尺を』は面白いがヘン ― 2023年10月17日
新国立劇場中劇場で2023年10月19日から1カ月間、シェイクスピアの『終わりよければすべてよし』と『尺には尺を』を交互上演する。同じ役者陣が二つの作品をほぼ日替わりで演じる趣向だ。役者は大変だろうと思う。
私は、この2作を観たことがなく、戯曲も読んでいない。チラシには「こんな現代的な作品が400年前に!?」とあり、それに惹かれて2作のチケットをゲットした。今月末、観劇予定だ。観劇に先立って戯曲を入手して読んだ。
『終わりよければすべてよし』(シェイクスピア、小田島雄志訳/白水Uブックス)
『尺には尺を』(シェイクスピア、小田島雄志訳/白水Uブックス)
読了してまず感じたのは、かなりヘンな話だということだ。人物像がヘンで、現代の倫理観・道徳観からはズレている。歌舞伎も同じで、400年前の人々の考え方や感じ方が21世紀の人間とは異なるのは当然だろう。にもかかわらず、シェイクスピアや近松門左衛門がいまも上演されるのは、「ヘン」を超えた面白さがあるからだ。その面白さは原初的・普遍的な何かで、それが現代性につながるのかもしれない。
この二つの作品には似た仕掛けがある。多くのシェイクスピア作品と同様に底本があり、当時流布していた逸話や伝承に基づく底本が似ているからだと思う。ある種のお約束かもしれない。
二つに共通しているのは「身替り花嫁」である。男A、女B、女Cがいて、女Bは男Aと結婚したいのに、男Aは身勝手な事情で女Bを避けている。そして、男Aは女Cに魅せられる。女Cは男Aの誘いに乗り、ベッドを共にすることを約束するが、女Bと入れ替わる。それと知らず、男Aは女Bと交わり、結局は女Bと結婚することになる。
この話、女Bも女Cも処女で、それを強調する台詞もある。処女を尊重しているのか安売りしているのかよくわからない。男Aも共感を得にくい人格だ。面白いがヘンな話である。
この2作品はハッピーエンドの喜劇である。しかし、本当にハッピーな結末なのだろうかと、釈然としないものが残る。手抜きの雑な展開のように感じるが、それが人生の本質を反映しているようにも思えるのが面白い。2つの戯曲を読んで、これのどこが「現代的」なのだろうと思ったが、多様な読みができるのが古典である。現代視線であれこれ解釈すると、面白さが倍加するのだろうと思う。
私は、この2作を観たことがなく、戯曲も読んでいない。チラシには「こんな現代的な作品が400年前に!?」とあり、それに惹かれて2作のチケットをゲットした。今月末、観劇予定だ。観劇に先立って戯曲を入手して読んだ。
『終わりよければすべてよし』(シェイクスピア、小田島雄志訳/白水Uブックス)
『尺には尺を』(シェイクスピア、小田島雄志訳/白水Uブックス)
読了してまず感じたのは、かなりヘンな話だということだ。人物像がヘンで、現代の倫理観・道徳観からはズレている。歌舞伎も同じで、400年前の人々の考え方や感じ方が21世紀の人間とは異なるのは当然だろう。にもかかわらず、シェイクスピアや近松門左衛門がいまも上演されるのは、「ヘン」を超えた面白さがあるからだ。その面白さは原初的・普遍的な何かで、それが現代性につながるのかもしれない。
この二つの作品には似た仕掛けがある。多くのシェイクスピア作品と同様に底本があり、当時流布していた逸話や伝承に基づく底本が似ているからだと思う。ある種のお約束かもしれない。
二つに共通しているのは「身替り花嫁」である。男A、女B、女Cがいて、女Bは男Aと結婚したいのに、男Aは身勝手な事情で女Bを避けている。そして、男Aは女Cに魅せられる。女Cは男Aの誘いに乗り、ベッドを共にすることを約束するが、女Bと入れ替わる。それと知らず、男Aは女Bと交わり、結局は女Bと結婚することになる。
この話、女Bも女Cも処女で、それを強調する台詞もある。処女を尊重しているのか安売りしているのかよくわからない。男Aも共感を得にくい人格だ。面白いがヘンな話である。
この2作品はハッピーエンドの喜劇である。しかし、本当にハッピーな結末なのだろうかと、釈然としないものが残る。手抜きの雑な展開のように感じるが、それが人生の本質を反映しているようにも思えるのが面白い。2つの戯曲を読んで、これのどこが「現代的」なのだろうと思ったが、多様な読みができるのが古典である。現代視線であれこれ解釈すると、面白さが倍加するのだろうと思う。
<若衆公演>『少女都市からの呼び声』は客層も若い ― 2023年10月19日
下北沢のザ・スズナリで新宿梁山泊の<若衆公演>『少女都市からの呼び声』(作:唐十郎、演出:金守珍、出演:風間杜夫、大久保鷹、藤田佳昭、柴野航輝、矢内有紗、他)を観た。3連続公演の3弾目である。第1弾は花園神社境内のテント版、第2弾はシアター・ミラノザでの大劇場版、そして今回の小劇場版<若衆公演>である。
この芝居の元になった『少女都市』を状況劇場が紅テントで上演したのは1969年12月、私は54年前にそれを観ている。私が3連続公演すべてを観たいと思ったのは、紅テント初体験の『少女都市』が私のアングラ観劇の原点になっているからだと思う。
『少女都市』の改訂版と言える『少女都市からの呼び声』の初上演は38年前の1985年11月、テント公演ではなく、小劇場での状況劇場<若衆公演>だったそうだ。今回の小劇場版は初演の形に戻ったのかもしれない。
3公演とも演出は金守珍で、趣向や役者は異なっている(何人かは3公演ともに出演している)。今回は<若衆公演>だからメインは若い役者だが、老優も登場する。
「なんてジメジメした陽気なんだ」を繰り返す老人を演じるのは、80歳の大久保鷹、54年前の『少女都市』で主役を演じた怪優だ。今回の役では、ボケ老人を装ったアドリブで50年前のパレスチナ公演と今回のガザ攻撃に言及していた。3連続公演すべての「連隊長」役(昔は唐十郎が演じた)風間杜夫74歳も元気だ。お約束のように演歌を披露して喝采を浴びていた。
客層は圧倒的に若い人が多い。私のような高齢者は1割ぐらいだと思う。役者も客層も新陳代謝しているのは、唐十郎の演劇が普遍的で妖しい力をもっているからだろう。
この芝居、「少女都市」は夢世界で、そこからの呼び声を聞くのが「現実世界」という設定に見え、夢世界から現実世界への浸潤も描いている。と言っても、舞台上の「現実世界」が現実である筈はない。夢の多重構造が織りなすめくるめく世界が舞台に現出する。何度観ても陶酔的だ。
この芝居の元になった『少女都市』を状況劇場が紅テントで上演したのは1969年12月、私は54年前にそれを観ている。私が3連続公演すべてを観たいと思ったのは、紅テント初体験の『少女都市』が私のアングラ観劇の原点になっているからだと思う。
『少女都市』の改訂版と言える『少女都市からの呼び声』の初上演は38年前の1985年11月、テント公演ではなく、小劇場での状況劇場<若衆公演>だったそうだ。今回の小劇場版は初演の形に戻ったのかもしれない。
3公演とも演出は金守珍で、趣向や役者は異なっている(何人かは3公演ともに出演している)。今回は<若衆公演>だからメインは若い役者だが、老優も登場する。
「なんてジメジメした陽気なんだ」を繰り返す老人を演じるのは、80歳の大久保鷹、54年前の『少女都市』で主役を演じた怪優だ。今回の役では、ボケ老人を装ったアドリブで50年前のパレスチナ公演と今回のガザ攻撃に言及していた。3連続公演すべての「連隊長」役(昔は唐十郎が演じた)風間杜夫74歳も元気だ。お約束のように演歌を披露して喝采を浴びていた。
客層は圧倒的に若い人が多い。私のような高齢者は1割ぐらいだと思う。役者も客層も新陳代謝しているのは、唐十郎の演劇が普遍的で妖しい力をもっているからだろう。
この芝居、「少女都市」は夢世界で、そこからの呼び声を聞くのが「現実世界」という設定に見え、夢世界から現実世界への浸潤も描いている。と言っても、舞台上の「現実世界」が現実である筈はない。夢の多重構造が織りなすめくるめく世界が舞台に現出する。何度観ても陶酔的だ。




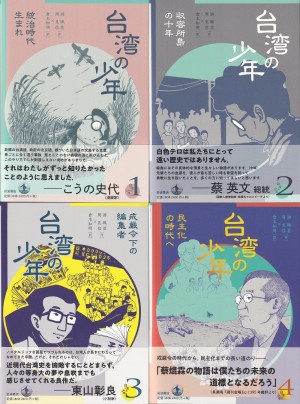

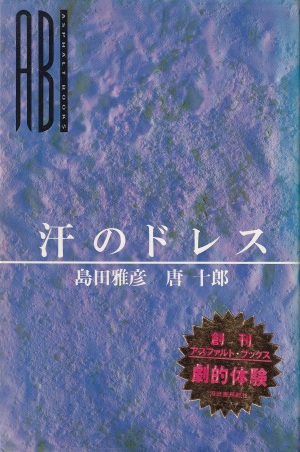

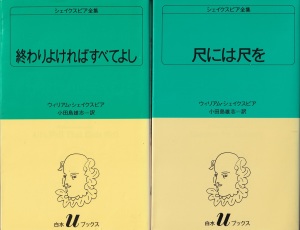

最近のコメント