脳科学の迷信・誤解を指摘する『まちがえる脳』は刺激的だ ― 2023年07月01日
『まちがえる脳』(櫻井芳雄/岩波新書/2023.4)
錯覚に関する脳科学の概説書と思って読み始めたが、私の想定を超えた興味深い内容に引き込まれた。脳科学の概説書ではあるが、わかっていないことがいかに多いかを解説している。脳科学への誤解の指摘にウエイトを置いた本である。ヘェーと驚く事柄の紹介も多い。
本書の内容を十分に理解できたわけではなく、私の誤解・曲解かもしれないが、脳科学の研究が進展しているという印象は錯覚らしい。進展しているのは「わかりつつある分野」であって、それは脳の全体像のほんの一部に過ぎないようだ。わからない部分――それこそが肝心な部分――は依然としてわからない、そんな状況らしい。
脳はニューロンとそれをつなぐシナプスで動作するイメージがあり、コンピュータの電子回路とのアナロジーで語られることがある。だが、ニューロン間の信号だけで脳を捉えるのはまったくの誤解だそうだ。脳の動作は複雑かつ可塑性に富んでいて、そのメカニズムの大半は不明なのだ。
また、右脳と左脳の使い分けや脳トレなどは迷信に近く、脳の部位ごとの機能を示す地図も固定的なものではないそうだ。私には意外だった。
昨今、生成AIが話題になっている。私もchatGTPを何度か使い、その文章力に驚いたものの知ったかぶりには呆れた。著者は、脳は単なる精密機械ではないとの認識から、「AIが脳に近づき、さらに脳を超える」ことはないと断じている。
私は5年前、『脳の意識 機械の意識』(渡辺正峰/中公新書)を読んで、人工意識の可能性に驚いた。『クオリアと人工意識』(茂木健一郎/講談社現代新書)という本も人工意識に言及していた。本書に「人工意識」という言葉は登場しないが、著者はAIが意識をもつ可能性を否定している。「人工意識」に関する脳科学者たちの議論をもっと知りたくなった。
錯覚に関する脳科学の概説書と思って読み始めたが、私の想定を超えた興味深い内容に引き込まれた。脳科学の概説書ではあるが、わかっていないことがいかに多いかを解説している。脳科学への誤解の指摘にウエイトを置いた本である。ヘェーと驚く事柄の紹介も多い。
本書の内容を十分に理解できたわけではなく、私の誤解・曲解かもしれないが、脳科学の研究が進展しているという印象は錯覚らしい。進展しているのは「わかりつつある分野」であって、それは脳の全体像のほんの一部に過ぎないようだ。わからない部分――それこそが肝心な部分――は依然としてわからない、そんな状況らしい。
脳はニューロンとそれをつなぐシナプスで動作するイメージがあり、コンピュータの電子回路とのアナロジーで語られることがある。だが、ニューロン間の信号だけで脳を捉えるのはまったくの誤解だそうだ。脳の動作は複雑かつ可塑性に富んでいて、そのメカニズムの大半は不明なのだ。
また、右脳と左脳の使い分けや脳トレなどは迷信に近く、脳の部位ごとの機能を示す地図も固定的なものではないそうだ。私には意外だった。
昨今、生成AIが話題になっている。私もchatGTPを何度か使い、その文章力に驚いたものの知ったかぶりには呆れた。著者は、脳は単なる精密機械ではないとの認識から、「AIが脳に近づき、さらに脳を超える」ことはないと断じている。
私は5年前、『脳の意識 機械の意識』(渡辺正峰/中公新書)を読んで、人工意識の可能性に驚いた。『クオリアと人工意識』(茂木健一郎/講談社現代新書)という本も人工意識に言及していた。本書に「人工意識」という言葉は登場しないが、著者はAIが意識をもつ可能性を否定している。「人工意識」に関する脳科学者たちの議論をもっと知りたくなった。
座談拝聴気分になる『オランダ紀行』(司馬遼太郎) ― 2023年07月03日
先々月、あるきっかけで『物語オランダの歴史』(中公新書)を読み、この国への親近感がわいた。司馬遼太郎の『街道をゆく』シリーズにオランダがあると知り、古書で入手して読んだ。
『オランダ紀行:街道をゆく35』(司馬遼太郎/朝日文庫)
1989年9月から10月にかけての16日間の紀行を、週刊朝日に連載(1989年12月~1990年8月)したものだ。バブル景気の時代である。好況と紀行は無関係だが、当時の明るさの反映を感じる。バブル時代とは言え、16日間の旅行記が37回連載(9カ月)とは、かなり膨らんでいる。
本書は単なる紀行文ではない。現地で出会った人々との交友録・人物評であり、広範な歴史談義である。話題は奔放に広がる。著者の楽しい座談を聴いている気分になる。
それにしても、終盤の7回にわたるゴッホ談義には驚いた。ゴッホゆかりのニューネンという町への訪問に絡めて、ゴッホの芸術や家族に関する話が延々と続く。著者は後段になって「なおも私はニューネンにいる。フィンセント・ファン・ゴッホについて、なぜこうも思案しているのか、読者に訊かれないうちに、自分に質問したいほどである。」と語っている。自覚が面白い。
著者の本領は、やはり歴史談義である。切れ味のいい見立てが秀逸だ。「司教というのは(…)十万石以上の譜代大名にやや似ている」「オランダ史は、不撓ながら百敗の歴史である。(…)百敗するのは当然で、人口がすくなすぎたのである。それに平地がほとんどで、スイスのような天嶮がないため、寡をもって衆にあたるのが不可能な国だった」などなど、炯眼に感服した。
オランダの北部(プロテスタント)と南部(カトリック)では、気質や雰囲気が違うそうだ。現地の空気が伝わってくる紀行文のおかげで、それを実感できた。
江戸初期以来、日本とオランダの関係は深い。当然に著者は日蘭交流について多く語っている。私は榎本武揚ファンなので、幕末にオランダ留学した榎本への言及を期待した。彼と共に留学した赤松則良、西周、津田真道に触れているのに、肝心の榎本は登場しない。司馬遼太郎にとって榎本武揚は関心外の人物だったのだろうか。
『オランダ紀行:街道をゆく35』(司馬遼太郎/朝日文庫)
1989年9月から10月にかけての16日間の紀行を、週刊朝日に連載(1989年12月~1990年8月)したものだ。バブル景気の時代である。好況と紀行は無関係だが、当時の明るさの反映を感じる。バブル時代とは言え、16日間の旅行記が37回連載(9カ月)とは、かなり膨らんでいる。
本書は単なる紀行文ではない。現地で出会った人々との交友録・人物評であり、広範な歴史談義である。話題は奔放に広がる。著者の楽しい座談を聴いている気分になる。
それにしても、終盤の7回にわたるゴッホ談義には驚いた。ゴッホゆかりのニューネンという町への訪問に絡めて、ゴッホの芸術や家族に関する話が延々と続く。著者は後段になって「なおも私はニューネンにいる。フィンセント・ファン・ゴッホについて、なぜこうも思案しているのか、読者に訊かれないうちに、自分に質問したいほどである。」と語っている。自覚が面白い。
著者の本領は、やはり歴史談義である。切れ味のいい見立てが秀逸だ。「司教というのは(…)十万石以上の譜代大名にやや似ている」「オランダ史は、不撓ながら百敗の歴史である。(…)百敗するのは当然で、人口がすくなすぎたのである。それに平地がほとんどで、スイスのような天嶮がないため、寡をもって衆にあたるのが不可能な国だった」などなど、炯眼に感服した。
オランダの北部(プロテスタント)と南部(カトリック)では、気質や雰囲気が違うそうだ。現地の空気が伝わってくる紀行文のおかげで、それを実感できた。
江戸初期以来、日本とオランダの関係は深い。当然に著者は日蘭交流について多く語っている。私は榎本武揚ファンなので、幕末にオランダ留学した榎本への言及を期待した。彼と共に留学した赤松則良、西周、津田真道に触れているのに、肝心の榎本は登場しない。司馬遼太郎にとって榎本武揚は関心外の人物だったのだろうか。
2023年上半期に読んだ本のマイ・ベスト3 ― 2023年07月05日
2023年前半に読んだ本のマイ・ベスト3を選んだ。
『アレクサンドロスの征服と神話(興亡の世界史)』 (森谷公俊/講談社学術文庫)
『唐:東ユーラシアの大帝国』 (森部豊/中公新書)
『まちがえる脳』 (櫻井芳雄/岩波新書)
『アレクサンドロスの征服と神話(興亡の世界史)』 (森谷公俊/講談社学術文庫)
『唐:東ユーラシアの大帝国』 (森部豊/中公新書)
『まちがえる脳』 (櫻井芳雄/岩波新書)
ナチスの妄想的人種観を分析した『ナチスと隕石仏像』 ― 2023年07月07日
ナチスやヒトラーは私の関心領域である。だが、知人に教示されるまで、6年前に出た次の新書は知らなかった。
『ナチスと隕石仏像:SSチベット探検隊とアーリア神話』(浜本隆志/集英社新書)
不思議なタイトルだ。「ナチス」「隕石」「仏像」という脈略不明の言葉に頭が混乱する。表紙の写真が「隕石仏像」である。
腹に「卍」の仏像(?)、隕石製である。かつてナチスはチベットに探検隊を派遣した。そのときにドイツに持ち帰ったものらしい。所有者の死亡によって2012年になって一般に公開され、日本の新聞にも載ったそうだ。私は見落とした。
この仏像の来歴は、公開された頃から疑問視されていた。本書は、この仏像を多面的に検討したうえで、ナチスが捏造したものとしている。説得力のある推論である。
「隕石仏像」の話は本書のマクラに過ぎない(分量は約半分だが)。後半は、アーリア人が第一とするナチスの人種観の概説と分析である。私には後半の方が面白かった。
著者はヨーロッパ文化論や比較文化論を研究するドイツ文学者である。ナチスの人種観についての概説・分析は、私には未知の事柄も多く、勉強になった。
狂信的人種主義者ヒムラーをかなり詳しく分析している。彼の神秘思想やオカルト趣味は興味深い。ヒトラーさえ彼の神秘思想とは一線を画していたそうだ。ヒムラーが設立したアーネンエルベ(ドイツ先史遺産研究所)については本書で初めて知った。この研究所が、アーリア人のルーツ探索を目的にチベット探検隊を派遣したのである。
ナチス関連の本を読み始めた頃、アーリア人とはゲルマン人を指すのかと思った。その後、印欧語族を指し、イラン系遊牧民がアーリア人を自称していたと知り、混乱した。本書を読むと多少は整理できるが、所詮、ナチスの言うアーリア人(金髪、碧眼、長身、鼻が高く細面・・・)は妄想に過ぎない。
ナチスが喧伝したアーリア人種のイメージは、ヒトラー、ゲーリング、ヒムラーなどの容貌とはかけ離れている。著者は、次のような面白い指摘をしている。
「それがナチス流プロパガンダであり、この二重構造はむしろドイツ国民にとって安心感を与えた。逆にナチスの首脳がすべてかれらのいうアーリア系の風貌をしていれば、国民はナチスを支持しなかったであろう。」
【P.S.】
本書が榎本武揚の流星号に言及しているのに感激した。まさかの、ナチスと榎本武揚の交差だ。隕石加工の話が出てきたとき、榎本武揚が隕石から刀(流星号)を作ったことを想起した。読み進めると、流星号の紹介に遭遇した。著者は「このエピソードは、隕石マニアの間では知られているが、一般にはあまりなじみがないエピソードである。」としている。私は隕石マニアではないが、榎本武揚ファンなので知っていた。『榎本武揚と東京農大』、『榎本武揚と明治維新』、『榎本武揚』、『近代日本の万能人』などに隕石から作った流星号の話が載っている。
『ナチスと隕石仏像:SSチベット探検隊とアーリア神話』(浜本隆志/集英社新書)
不思議なタイトルだ。「ナチス」「隕石」「仏像」という脈略不明の言葉に頭が混乱する。表紙の写真が「隕石仏像」である。
腹に「卍」の仏像(?)、隕石製である。かつてナチスはチベットに探検隊を派遣した。そのときにドイツに持ち帰ったものらしい。所有者の死亡によって2012年になって一般に公開され、日本の新聞にも載ったそうだ。私は見落とした。
この仏像の来歴は、公開された頃から疑問視されていた。本書は、この仏像を多面的に検討したうえで、ナチスが捏造したものとしている。説得力のある推論である。
「隕石仏像」の話は本書のマクラに過ぎない(分量は約半分だが)。後半は、アーリア人が第一とするナチスの人種観の概説と分析である。私には後半の方が面白かった。
著者はヨーロッパ文化論や比較文化論を研究するドイツ文学者である。ナチスの人種観についての概説・分析は、私には未知の事柄も多く、勉強になった。
狂信的人種主義者ヒムラーをかなり詳しく分析している。彼の神秘思想やオカルト趣味は興味深い。ヒトラーさえ彼の神秘思想とは一線を画していたそうだ。ヒムラーが設立したアーネンエルベ(ドイツ先史遺産研究所)については本書で初めて知った。この研究所が、アーリア人のルーツ探索を目的にチベット探検隊を派遣したのである。
ナチス関連の本を読み始めた頃、アーリア人とはゲルマン人を指すのかと思った。その後、印欧語族を指し、イラン系遊牧民がアーリア人を自称していたと知り、混乱した。本書を読むと多少は整理できるが、所詮、ナチスの言うアーリア人(金髪、碧眼、長身、鼻が高く細面・・・)は妄想に過ぎない。
ナチスが喧伝したアーリア人種のイメージは、ヒトラー、ゲーリング、ヒムラーなどの容貌とはかけ離れている。著者は、次のような面白い指摘をしている。
「それがナチス流プロパガンダであり、この二重構造はむしろドイツ国民にとって安心感を与えた。逆にナチスの首脳がすべてかれらのいうアーリア系の風貌をしていれば、国民はナチスを支持しなかったであろう。」
【P.S.】
本書が榎本武揚の流星号に言及しているのに感激した。まさかの、ナチスと榎本武揚の交差だ。隕石加工の話が出てきたとき、榎本武揚が隕石から刀(流星号)を作ったことを想起した。読み進めると、流星号の紹介に遭遇した。著者は「このエピソードは、隕石マニアの間では知られているが、一般にはあまりなじみがないエピソードである。」としている。私は隕石マニアではないが、榎本武揚ファンなので知っていた。『榎本武揚と東京農大』、『榎本武揚と明治維新』、『榎本武揚』、『近代日本の万能人』などに隕石から作った流星号の話が載っている。
往時のドイツ社会の空気を伝える『ナチズムの時代』 ― 2023年07月09日
『ナチズムの時代』(山本秀行/世界史リブレット/山川出版社)
久々に読んだナチス物『ナチスと隕石仏像』巻末の参考文献に本書があった。かなり以前に購入したまま未読の棚に積んでいたのを思い出した。1998年12月に出た本の13刷(2017年6月)だ。思い出したのを機に読了した。短時間で読める小冊子である。
ナチスが戦争国家を築いていく過程を「領土拡大」と「人種主義」の視点にしぼって簡潔に解説している。当時のドイツ社会の雰囲気が伝わてくる。
「ナチズムの時代」とは言え、ナチスを支持した人々の熱狂がいつまでも持続したわけではない。人間は熱しやすく冷めやすい。ヒトラー政権成立から1年後には人々の期待は幻滅に変わった。失業者は減らず、物価は上昇し、ナチ党幹部のおごりや腐敗への苦情や不満がつのる。
そんな不満をかわしたのが「ヒトラー神話」だったという分析が面白い。著者は次のように述べている。
「ナチ組織の腐敗、幹部の目にあまる増長ぶりに、国民は、そうした幹部をヒトラーが押さえつけてくれることを期待したのである。いってみればナチ党への不満が、逆にヒトラーの人気を押しあげているのである。」
オーストリア併合に関する次の記述には少し驚いた。
「オーストリアの併合も、四カ年計画の責任者ゲーリングが、資源と労働力を求めて積極的に推進したものであった。ヒトラー自身は、オーストリア併合には消極的であったといわれる。」
ヒトラーが消極的だったという説を読んだ記憶はない(読んだ本の大半の内容は失念しているが)。比較的新しい本『ヒトラー』(芝健介) と『ヒトラー(下)』(カーショー) のオーストリア併合の箇所を読み返してみたが、ヒトラーが消極的との印象は受けなかった。今後の勉強課題としたい。
久々に読んだナチス物『ナチスと隕石仏像』巻末の参考文献に本書があった。かなり以前に購入したまま未読の棚に積んでいたのを思い出した。1998年12月に出た本の13刷(2017年6月)だ。思い出したのを機に読了した。短時間で読める小冊子である。
ナチスが戦争国家を築いていく過程を「領土拡大」と「人種主義」の視点にしぼって簡潔に解説している。当時のドイツ社会の雰囲気が伝わてくる。
「ナチズムの時代」とは言え、ナチスを支持した人々の熱狂がいつまでも持続したわけではない。人間は熱しやすく冷めやすい。ヒトラー政権成立から1年後には人々の期待は幻滅に変わった。失業者は減らず、物価は上昇し、ナチ党幹部のおごりや腐敗への苦情や不満がつのる。
そんな不満をかわしたのが「ヒトラー神話」だったという分析が面白い。著者は次のように述べている。
「ナチ組織の腐敗、幹部の目にあまる増長ぶりに、国民は、そうした幹部をヒトラーが押さえつけてくれることを期待したのである。いってみればナチ党への不満が、逆にヒトラーの人気を押しあげているのである。」
オーストリア併合に関する次の記述には少し驚いた。
「オーストリアの併合も、四カ年計画の責任者ゲーリングが、資源と労働力を求めて積極的に推進したものであった。ヒトラー自身は、オーストリア併合には消極的であったといわれる。」
ヒトラーが消極的だったという説を読んだ記憶はない(読んだ本の大半の内容は失念しているが)。比較的新しい本『ヒトラー』(芝健介) と『ヒトラー(下)』(カーショー) のオーストリア併合の箇所を読み返してみたが、ヒトラーが消極的との印象は受けなかった。今後の勉強課題としたい。
これぞ、ギリシア悲劇――『オイディプス王』 ― 2023年07月11日
パルテノン多摩大ホールでソポクレスの『オイディプス王』(翻訳:河合祥一郎、演出:石丸さち子、出演:三浦涼介、大空ゆうひ、荒木宏文、他)を観た。
多摩センターにあるこの劇場に初めて行った。パルテノン(万神殿)なる名の劇場はギリシア悲劇にマッチしている。劇場のしつらえも何となくギリシア劇場風である。
2500年前に書かれたギリシア悲劇の堂々たる迫力と普遍的な面白さを堪能した。2500年という時間が溶解し、古代人も現代人も感性や理性はさほど変わらないと気づかされる。なるほど、ギリシア悲劇とはこんな舞台だったのか――そんな感慨がわいた。
私が初めて『オイディプス王』を観たのは3年前(コロナ禍前)のシアターコクーンの公演だった。その観劇にあわせて、ソポクレスの戯曲も読んだ。あの公演(翻案・演出:マシュー・ダンスター、主演:市川海老蔵)は、やや奇をてらった趣向だった。舞台は疫病禍の外界から隔離された現代(近未来?)都市、オイディプスは背広姿、使者はヘリコプターでやって来る。いま思えば、新型コロナを予感させる舞台だった。
半世紀以上昔、『オイディプス王』をベースにした映画『アポロンの地獄』(監督:パゾリーニ)や『薔薇の葬列』(監督:松本俊夫)なども観た。あまりに有名なオイディプス王の話は多様な形で記憶に刻まれている。だが、いわゆるギリシア悲劇の舞台は刻まれてなかった。今回の舞台で、初めてギリシア悲劇をイメージできた。
ギリシア悲劇にはコロス(合唱隊)が登場し、朗々と感情や情景を歌いあげる。戯曲を読んでいても、コロスの部分を具体的にイメージできなかった。3年前の舞台のコロスは舞踏中心だったので、本当のコロスとは違うのだろうと思った。
今回の舞台のコロスは16人(舞踏家と俳優が半々)だ。テーバイの市民としての集団演技に存在感があった。皆で歌うのかと思っていたが、いわゆる合唱ではなく、集団での台詞朗誦だった。朗誦は聞き取りやすく、臨場感もある。古代のコロスがどんな趣向だったかは知らないが、コロスの一形態を把むことができた。これからは、ギリシア悲劇の戯曲を読むとき、コロスの部分も具体的イメージを抱いて読めそうだ。
多摩センターにあるこの劇場に初めて行った。パルテノン(万神殿)なる名の劇場はギリシア悲劇にマッチしている。劇場のしつらえも何となくギリシア劇場風である。
2500年前に書かれたギリシア悲劇の堂々たる迫力と普遍的な面白さを堪能した。2500年という時間が溶解し、古代人も現代人も感性や理性はさほど変わらないと気づかされる。なるほど、ギリシア悲劇とはこんな舞台だったのか――そんな感慨がわいた。
私が初めて『オイディプス王』を観たのは3年前(コロナ禍前)のシアターコクーンの公演だった。その観劇にあわせて、ソポクレスの戯曲も読んだ。あの公演(翻案・演出:マシュー・ダンスター、主演:市川海老蔵)は、やや奇をてらった趣向だった。舞台は疫病禍の外界から隔離された現代(近未来?)都市、オイディプスは背広姿、使者はヘリコプターでやって来る。いま思えば、新型コロナを予感させる舞台だった。
半世紀以上昔、『オイディプス王』をベースにした映画『アポロンの地獄』(監督:パゾリーニ)や『薔薇の葬列』(監督:松本俊夫)なども観た。あまりに有名なオイディプス王の話は多様な形で記憶に刻まれている。だが、いわゆるギリシア悲劇の舞台は刻まれてなかった。今回の舞台で、初めてギリシア悲劇をイメージできた。
ギリシア悲劇にはコロス(合唱隊)が登場し、朗々と感情や情景を歌いあげる。戯曲を読んでいても、コロスの部分を具体的にイメージできなかった。3年前の舞台のコロスは舞踏中心だったので、本当のコロスとは違うのだろうと思った。
今回の舞台のコロスは16人(舞踏家と俳優が半々)だ。テーバイの市民としての集団演技に存在感があった。皆で歌うのかと思っていたが、いわゆる合唱ではなく、集団での台詞朗誦だった。朗誦は聞き取りやすく、臨場感もある。古代のコロスがどんな趣向だったかは知らないが、コロスの一形態を把むことができた。これからは、ギリシア悲劇の戯曲を読むとき、コロスの部分も具体的イメージを抱いて読めそうだ。
『ゲッベルス』で「若者」の怖さと愚かさを思う ― 2023年07月15日
ふとしたきっかけで『ナチスと隕石仏像』と『ナチズムの時代』を読んで、未読で積んだままのナチス関連本が気がかりになった。とりあえず次の新書を読了した。
『ゲッベルス:メディア時代の政治宣伝』(平井正/中公新書/1991.6)
著者は1929年生まれのドイツ文学者、30年以上前に出た新書である。ゲッベルスの日記の引用が多い。落ち込みや高揚、心情のゆらぎを綴った日記はかなり面白い。著者の日記紹介は蔑視・断罪が基調のように感じられた。もう少し引いた視線で分析的に掘り下げてもいいのではと思えた。
ゲッベルスのヒトラー観は、急成長する企業のカリスマ社長を見る取締役のようで面白い。当初はヒトラーに批判的なこともあったが、次第に心酔していく。ライバル幹部たちを気にしつつ、ヒトラーから褒められれば喜び、疎まれれば絶望する。どこにでもありそうな話だ。
ナチスは若者集団だった――あらためて、そう感じた。以前に読んだ『ヒトラーの時代』 で著者の池内紀氏がナチス幹部の若さを指摘していたのが印象に残っている。ゲッベルスの日記には「若者」という言葉が頻出する。自身を若者と位置づけ、自分たちの活動を新たな世界を切り拓く若者の運動としている。よくある思い込みである。
考えてみれば、紅衛兵も全共闘もタリバンも幕末の志士もみな若者だ。これらを同一に論ずるのは乱暴だが、「革命」と言われる歴史変動の担い手の大半は若者だった。
自分たちより上の世代を硬直した旧世代と見なした若者たちが、ある種の熱狂のなかで全能感を抱くと、手がつけられなくなる。感性・情念が理性を凌駕し、妄想と思想の区別がつかなくなる。そんな事態が時代を動かすこともある。それが吉と出るか凶と出るかはわからない。
かつて若者だった私は74歳になり、若者の愚かさが見えてきた気がする。それは人類の愚かさと同じにも思える。愚かさは克服するべきなのだが……。
『ゲッベルス:メディア時代の政治宣伝』(平井正/中公新書/1991.6)
著者は1929年生まれのドイツ文学者、30年以上前に出た新書である。ゲッベルスの日記の引用が多い。落ち込みや高揚、心情のゆらぎを綴った日記はかなり面白い。著者の日記紹介は蔑視・断罪が基調のように感じられた。もう少し引いた視線で分析的に掘り下げてもいいのではと思えた。
ゲッベルスのヒトラー観は、急成長する企業のカリスマ社長を見る取締役のようで面白い。当初はヒトラーに批判的なこともあったが、次第に心酔していく。ライバル幹部たちを気にしつつ、ヒトラーから褒められれば喜び、疎まれれば絶望する。どこにでもありそうな話だ。
ナチスは若者集団だった――あらためて、そう感じた。以前に読んだ『ヒトラーの時代』 で著者の池内紀氏がナチス幹部の若さを指摘していたのが印象に残っている。ゲッベルスの日記には「若者」という言葉が頻出する。自身を若者と位置づけ、自分たちの活動を新たな世界を切り拓く若者の運動としている。よくある思い込みである。
考えてみれば、紅衛兵も全共闘もタリバンも幕末の志士もみな若者だ。これらを同一に論ずるのは乱暴だが、「革命」と言われる歴史変動の担い手の大半は若者だった。
自分たちより上の世代を硬直した旧世代と見なした若者たちが、ある種の熱狂のなかで全能感を抱くと、手がつけられなくなる。感性・情念が理性を凌駕し、妄想と思想の区別がつかなくなる。そんな事態が時代を動かすこともある。それが吉と出るか凶と出るかはわからない。
かつて若者だった私は74歳になり、若者の愚かさが見えてきた気がする。それは人類の愚かさと同じにも思える。愚かさは克服するべきなのだが……。
『ヒトラー・ユーゲント』に戦時中の古書の引用を発見 ― 2023年07月17日
ナチス関連の未読棚に積んでいた『ゲッベルス』を読んだの機に、一緒に積んでいた同じ著者の次の本を読んだ。
『ヒトラー・ユーゲント:青年運動から戦闘組織へ』(平井正/中公新書/2001.1)
ヒトラー・ユーゲントにはワンゲルやボーイスカウトのイメージが重なる。そんな青少年の集団が、ナチ党の青少年組織となり、ヒトラー政権が成立してからはさまざまな青少年組織を統合した国家組織に拡大する。強制加入となり、画一化された集団は、最終段階では軍事化して戦闘に参加する。
ヒトラー・ユーゲントと言えば、この組織を主導したシーラッハ(本書はシーラハと表記)の名が浮かぶ。名を知っているだけだったこの人物ついて、やや詳しい事柄を本書で知った。興味深い人物だ。
シーラハは貴族出身で母はアメリカ人、ドイツ語以上に英語が達者だった。半分アメリカ人だがゲーテやシラーを尊敬、17歳のとき(1925年3月)、ヒトラーに出会って心酔する。ヒトラーの勧めでミュンヘン大学に入学、ナチ学生連盟の指導者になる。
シーラハは青年運動への思い入れが強く、理想主義者的でもあった。1932年、25歳で念願のヒトラー・ユーゲント全国指導者の地位を得る。ヒトラー政権発足後の1936年、ヒトラー・ユーゲントは国家組織になる。この組織を統括する29歳のシーラハは、学校教育が管轄の教育相と対等に渉り合う。
第二次大戦開始後、33歳になったシーラハは「ユーゲントはユーゲントによって指導されねばならない」という、彼自身が定めた原則によって、27歳のアクスマンに地位を譲る。彼はユーゲントの軍隊化に反対だったが、アクスマンの時代になるとユーゲントは戦場に送り込まれる。ユーゲント部隊が多くの犠牲者を出したとき、「私の最良の若者が無意味に殺された」と嘆いたそうだ。
本書はシーラハの戦後には言及していない。ウィキペディアによれば、ニュルンベルク裁判で禁固20年の判決を受け、1966年に刑期満了で釈放、1974年に67歳で亡くなった。孫は高名な弁護士&小説家だ。
私は3年前、戦時中に出た『ヒトラー・ユーゲント』(ヤーコプ・ザール/高橋健二)という古書を入手して読んだ。キワモノ本と思っていたが、本書はこの本に言及している。この本には、シーラハの後継者アクスマンの序文が載っている。著者は、ユーゲント軍隊化の証左として、この序文の一部を紹介している。
著者は、この古書を「ヤーコブ・ザール著、高橋健二訳」としている。これは間違いだ。高橋健二は多くの翻訳を残した高名な独文学者だが、この本に関しては訳者ではなく共著者である。
『ヒトラー・ユーゲント:青年運動から戦闘組織へ』(平井正/中公新書/2001.1)
ヒトラー・ユーゲントにはワンゲルやボーイスカウトのイメージが重なる。そんな青少年の集団が、ナチ党の青少年組織となり、ヒトラー政権が成立してからはさまざまな青少年組織を統合した国家組織に拡大する。強制加入となり、画一化された集団は、最終段階では軍事化して戦闘に参加する。
ヒトラー・ユーゲントと言えば、この組織を主導したシーラッハ(本書はシーラハと表記)の名が浮かぶ。名を知っているだけだったこの人物ついて、やや詳しい事柄を本書で知った。興味深い人物だ。
シーラハは貴族出身で母はアメリカ人、ドイツ語以上に英語が達者だった。半分アメリカ人だがゲーテやシラーを尊敬、17歳のとき(1925年3月)、ヒトラーに出会って心酔する。ヒトラーの勧めでミュンヘン大学に入学、ナチ学生連盟の指導者になる。
シーラハは青年運動への思い入れが強く、理想主義者的でもあった。1932年、25歳で念願のヒトラー・ユーゲント全国指導者の地位を得る。ヒトラー政権発足後の1936年、ヒトラー・ユーゲントは国家組織になる。この組織を統括する29歳のシーラハは、学校教育が管轄の教育相と対等に渉り合う。
第二次大戦開始後、33歳になったシーラハは「ユーゲントはユーゲントによって指導されねばならない」という、彼自身が定めた原則によって、27歳のアクスマンに地位を譲る。彼はユーゲントの軍隊化に反対だったが、アクスマンの時代になるとユーゲントは戦場に送り込まれる。ユーゲント部隊が多くの犠牲者を出したとき、「私の最良の若者が無意味に殺された」と嘆いたそうだ。
本書はシーラハの戦後には言及していない。ウィキペディアによれば、ニュルンベルク裁判で禁固20年の判決を受け、1966年に刑期満了で釈放、1974年に67歳で亡くなった。孫は高名な弁護士&小説家だ。
私は3年前、戦時中に出た『ヒトラー・ユーゲント』(ヤーコプ・ザール/高橋健二)という古書を入手して読んだ。キワモノ本と思っていたが、本書はこの本に言及している。この本には、シーラハの後継者アクスマンの序文が載っている。著者は、ユーゲント軍隊化の証左として、この序文の一部を紹介している。
著者は、この古書を「ヤーコブ・ザール著、高橋健二訳」としている。これは間違いだ。高橋健二は多くの翻訳を残した高名な独文学者だが、この本に関しては訳者ではなく共著者である。
『ナチスの戦争1918-1949』は戦後にも言及 ― 2023年07月19日
ナチス各論風の『ゲッベルス』と『ヒトラー・ユーゲント』の読後イメージが消える前に、あの時代の全体像を確認しておこうと思い、未読棚の次の本を読んだ。
『ナチスの戦争1918-1949:民族と人種の戦い』(リチャード・ベッセル/大山顕訳 中公新書/2015/9)
著者は1948年米国生まれ(私と同じだ)の研究者、原著は2004年刊行である。ナチスの戦争は「人種主義者のユートピア」を目指していたという視点で、第一次大戦終結から第二次大戦終結までを概説している。ナチスの妄想的人種観に社会全体が引き込まれ、破局に至るまでの現代史である。
多くの人命が失われる歴史を読んでいて、数年前に読んだスナイダーの『ブラッドランド』と『ブラックアース』の衝撃的な印象がよみがえった。大木毅の『独ソ戦』のイメージも重なる。本書の記述は簡潔だが、それが意味する内容は重い。
本書は戦争の最後の数カ月に着目している。著者は次のように述べている。
「ナチ・ドイツは非常に驚くべきことを成し遂げた。完全な敗北である。」
ドイツが勝つ可能性がなくなった段階でも、ヒトラーは敗戦を認めず、徹底抗戦の焦土作戦を命ずる。降伏ではなく滅亡――それが人種戦争の帰結なのだ。国民には大迷惑だが、ドイツは徹底的に破壊されて終戦を迎える。
最後の数カ月の苛酷な戦争体験がドイツ人の被害者意識を生み、ナチスの記憶を希薄化した――著者はそう見ている。
ナチスの戦争は1945年5月に終わるが、本書のタイトルは「1918-1949」になっている。最終章「第二次世界大戦の余波」で1945年から1949年までの戦後を描いているのだ。この部分が私には新鮮で興味深かった。
戦後のドイツはナチスを完全に否定した。だが、記憶や体験を消すことはできない。消せなくても捏造はできる。意識的か無意識かはわからないが。
私は1948年生まれのベビーブーマーである。戦争が終わり、大量の男が戦地から帰還して結婚し、大量の子供が生まれた。その一人が私であり、第二次世界大戦に参戦した国々に共通の事象だと思っていた。本書によって、ドイツに私と同世代のベビーブーマーがいないと知って驚いた。ドイツでは、終戦後すぐには出生数が増えていないのだ。さまざまな事情があるらしいが、世の中さまざまである。
『ナチスの戦争1918-1949:民族と人種の戦い』(リチャード・ベッセル/大山顕訳 中公新書/2015/9)
著者は1948年米国生まれ(私と同じだ)の研究者、原著は2004年刊行である。ナチスの戦争は「人種主義者のユートピア」を目指していたという視点で、第一次大戦終結から第二次大戦終結までを概説している。ナチスの妄想的人種観に社会全体が引き込まれ、破局に至るまでの現代史である。
多くの人命が失われる歴史を読んでいて、数年前に読んだスナイダーの『ブラッドランド』と『ブラックアース』の衝撃的な印象がよみがえった。大木毅の『独ソ戦』のイメージも重なる。本書の記述は簡潔だが、それが意味する内容は重い。
本書は戦争の最後の数カ月に着目している。著者は次のように述べている。
「ナチ・ドイツは非常に驚くべきことを成し遂げた。完全な敗北である。」
ドイツが勝つ可能性がなくなった段階でも、ヒトラーは敗戦を認めず、徹底抗戦の焦土作戦を命ずる。降伏ではなく滅亡――それが人種戦争の帰結なのだ。国民には大迷惑だが、ドイツは徹底的に破壊されて終戦を迎える。
最後の数カ月の苛酷な戦争体験がドイツ人の被害者意識を生み、ナチスの記憶を希薄化した――著者はそう見ている。
ナチスの戦争は1945年5月に終わるが、本書のタイトルは「1918-1949」になっている。最終章「第二次世界大戦の余波」で1945年から1949年までの戦後を描いているのだ。この部分が私には新鮮で興味深かった。
戦後のドイツはナチスを完全に否定した。だが、記憶や体験を消すことはできない。消せなくても捏造はできる。意識的か無意識かはわからないが。
私は1948年生まれのベビーブーマーである。戦争が終わり、大量の男が戦地から帰還して結婚し、大量の子供が生まれた。その一人が私であり、第二次世界大戦に参戦した国々に共通の事象だと思っていた。本書によって、ドイツに私と同世代のベビーブーマーがいないと知って驚いた。ドイツでは、終戦後すぐには出生数が増えていないのだ。さまざまな事情があるらしいが、世の中さまざまである。
シアターミラノ座の『少女都市からの呼び声』はメルヘン ― 2023年07月21日
歌舞伎町タワーのシアターミラノ座で『少女都市からの呼び声』(作:唐十郎、演出:金守珍、出演:安田章大、咲姫みゆ、三宅弘城、六平直政、風間杜夫、他)を観た。先月、花園神社境内の紫テントで新宿梁山泊の同じ芝居を観たばかりだ。どちらも金守珍演出の連続公演だが、テイストはかなり異なる。
テントと大劇場では、役者がかなり入れ替わっている。メインの安田章大(関ジャニ∞)、咲姫みゆ(元・宝塚)、三宅弘城(ナイロン100℃)は、私には未知の役者だが、新鮮な唐十郎世界を感じた。好演だった。テントで主役の六平直政は存在感ある脇を奔放に演じていた。風間杜夫はテントと同じ役でカラオケも堂々と披露した。
大劇場では演出を変えて、プロジェクション・マッピングを使うだろうと予想した。予想通りだった。プロジェクション・マッピングの効果は素晴らしい。オテナの塔やガラスの都市を視覚で捉えることができる。演劇において、この技法をどこまで使っていいものか、演出家は悩むのではないかと思う。
大劇場の舞台ではテント芝居の猥雑さが軽減する。暗黒舞踏的パフォーマンスはない。『少女都市からの呼び声』がメルヘンに感じられた。そんなバージョンも成り立つのが軽い衝撃だった。
先月のテント芝居との一番大きい違いは客層である。女性客(歌舞伎よりは若い)が圧倒的に多い。私のように両方を観ている人も少なくないだろうが、やはりそれは少数派に思えた。
公演パンフで主演・安田章大は次のように語っている。
「“現代の伝統芸能”としての唐さんの芝居を、次の世代に繋いでいけたらと思っています。今回はアングラと呼ばれる演劇をより間口の広い方たちに伝えられるチャンスだと思います」
テントと大劇場では、役者がかなり入れ替わっている。メインの安田章大(関ジャニ∞)、咲姫みゆ(元・宝塚)、三宅弘城(ナイロン100℃)は、私には未知の役者だが、新鮮な唐十郎世界を感じた。好演だった。テントで主役の六平直政は存在感ある脇を奔放に演じていた。風間杜夫はテントと同じ役でカラオケも堂々と披露した。
大劇場では演出を変えて、プロジェクション・マッピングを使うだろうと予想した。予想通りだった。プロジェクション・マッピングの効果は素晴らしい。オテナの塔やガラスの都市を視覚で捉えることができる。演劇において、この技法をどこまで使っていいものか、演出家は悩むのではないかと思う。
大劇場の舞台ではテント芝居の猥雑さが軽減する。暗黒舞踏的パフォーマンスはない。『少女都市からの呼び声』がメルヘンに感じられた。そんなバージョンも成り立つのが軽い衝撃だった。
先月のテント芝居との一番大きい違いは客層である。女性客(歌舞伎よりは若い)が圧倒的に多い。私のように両方を観ている人も少なくないだろうが、やはりそれは少数派に思えた。
公演パンフで主演・安田章大は次のように語っている。
「“現代の伝統芸能”としての唐さんの芝居を、次の世代に繋いでいけたらと思っています。今回はアングラと呼ばれる演劇をより間口の広い方たちに伝えられるチャンスだと思います」







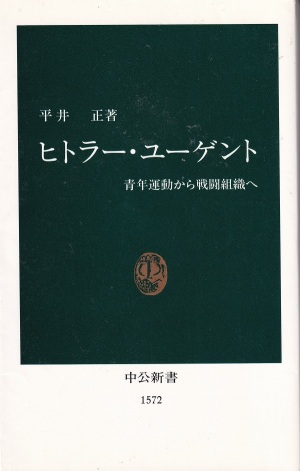


最近のコメント