敗戦までの昭和史は教訓に満ちているが… ― 2023年01月12日
昨年末に読んだ小説『地図と拳』(小川哲)をきっかけに満洲関連の本をいくつか読み、昭和の空気に浸った。で、いずれ読もうと積んでいた半藤一利氏の昭和史シリーズを読む気分になった。
『昭和史 1926-1945』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
語り下ろしの講義録なので、半藤氏が講談調にしゃべくる姿が目に浮かぶ(テレビで知っているだけだが)。本書は敗戦(1945年)までの20年間を語っている。
冒頭の「はじめの章」のタイトルは「昭和史の根底には“赤い夕陽の満州”があった」だ(表記が「満洲」でなく「満州」なので、以下「満州」を使う)。確かに「昭和史」という言葉を見ると、満州を知らない戦後生まれの私でも、見たことのない満州の光景を連想する。どこで刷り込まれたのだろうか。
この「はじめの章」で芥川龍之介の『支那游記』を紹介している。新聞社の特派員として訪れた中国の旅行記である。中国民衆の反日的な姿に言及している。日本人がロマンを抱いていた満州は、当初から反日感情を底流にはらんだ地だったのだ。
昭和の前半20年は、いったんは興隆した国が滅びていく時代であり、数々の失敗を積み重ねて事態が悪化していく歴史である。なぜ、こんなアホなことを……と思うことのくり返しで、ため息が出る。集団無責任体制は腹立たしい。
本書全般を通して「新聞が戦争を煽った」という指摘が多い。その通りだと思う。軍部の周到なマスコミ政策もあるだろうが、戦争になると新聞の発行部数が伸びるのである。新聞が戦争を煽り、読者が盛り上がり、それがさらに紙面に反映され、ワッショイ、ワッショイと突き進んで行く。
過去の反省をふまえれば、今後はそんなことにはならないだろう、と思いたい。だが、何とも心もとない。
日本を敗戦に導いた昭和史前半は教訓の宝庫でもある。半藤氏は本書末尾の数頁で「昭和史の20年がどういう教訓を私たちに示してくれた」を語っている。それを私なりに要約すると次の通りだ。
・国民的熱狂をつくってはいけない。
・抽象的観念論はダメ。具体的理性的方法論が大事。
・日本型タコツボ社会のエリート主義は独善に陥る。
・国際的常識を理解しなければならない。
・対症療法的短兵急な考えはダメ。大局観、複眼的思考が必要。
『昭和史 1926-1945』(半藤一利/平凡社ライブラリー)
語り下ろしの講義録なので、半藤氏が講談調にしゃべくる姿が目に浮かぶ(テレビで知っているだけだが)。本書は敗戦(1945年)までの20年間を語っている。
冒頭の「はじめの章」のタイトルは「昭和史の根底には“赤い夕陽の満州”があった」だ(表記が「満洲」でなく「満州」なので、以下「満州」を使う)。確かに「昭和史」という言葉を見ると、満州を知らない戦後生まれの私でも、見たことのない満州の光景を連想する。どこで刷り込まれたのだろうか。
この「はじめの章」で芥川龍之介の『支那游記』を紹介している。新聞社の特派員として訪れた中国の旅行記である。中国民衆の反日的な姿に言及している。日本人がロマンを抱いていた満州は、当初から反日感情を底流にはらんだ地だったのだ。
昭和の前半20年は、いったんは興隆した国が滅びていく時代であり、数々の失敗を積み重ねて事態が悪化していく歴史である。なぜ、こんなアホなことを……と思うことのくり返しで、ため息が出る。集団無責任体制は腹立たしい。
本書全般を通して「新聞が戦争を煽った」という指摘が多い。その通りだと思う。軍部の周到なマスコミ政策もあるだろうが、戦争になると新聞の発行部数が伸びるのである。新聞が戦争を煽り、読者が盛り上がり、それがさらに紙面に反映され、ワッショイ、ワッショイと突き進んで行く。
過去の反省をふまえれば、今後はそんなことにはならないだろう、と思いたい。だが、何とも心もとない。
日本を敗戦に導いた昭和史前半は教訓の宝庫でもある。半藤氏は本書末尾の数頁で「昭和史の20年がどういう教訓を私たちに示してくれた」を語っている。それを私なりに要約すると次の通りだ。
・国民的熱狂をつくってはいけない。
・抽象的観念論はダメ。具体的理性的方法論が大事。
・日本型タコツボ社会のエリート主義は独善に陥る。
・国際的常識を理解しなければならない。
・対症療法的短兵急な考えはダメ。大局観、複眼的思考が必要。
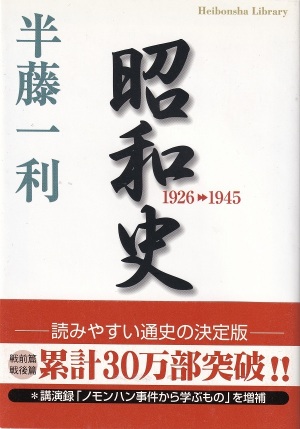
最近のコメント