『ギリシア人の物語』を面白く読んだ ― 2018年03月01日
◎塩野七生の歴史エッセイはリーダー論
塩野七生の『ギリシア人の物語』全3巻が昨年末に完結した。『ローマ人の物語』と同様に年1冊ペースの刊行で、以前から気がかりな本だった。完結を機に3冊まとめて購入し、面白く読了した。
『ギリシア人の物語Ⅰ:民主政のはじまり』(塩野七生/新潮社)
『ギリシア人の物語Ⅱ:民主政の成熟と崩壊』(塩野七生/新潮社)
『ギリシア人の物語Ⅲ:新しき力』(塩野七生/新潮社)
第1巻はペルシア戦役、第2巻はペロポネソス戦役、第3巻はアレクサンドロス(本書オビの表記は「アレクサンダー」だが本文はアレクサンドロス)を描いている。全3巻で古代ギリシアの歴史を描いているが、塩野七生の関心はあくまで人物であり、スパルタやアテネ以前のミノア文明、ミケーネ文明、線形文字解読など考古学的な話題は割愛されている。気持ちのいい割り切りである。
全3巻を読んで「小説のように面白い」と感じた。塩野七生の歴史エッセイは歴史小説とも呼ばれているからこの感想は変だ。一般的な歴史概説書よりワクワクした気分でスラスラと読めたということだ。
塩野七生の歴史エッセイは卓越した政治家や軍の司令官に焦点をあてた人物論であり、リーダー論である。それが現代にも通じる文明論にもなっているから面白い。
ペルシア戦役を扱った第1巻では、都市国家連合のギリシアのペルシアへの勝因を、ペルシアの「量」で圧倒するやり方に、ギリシアは総合的な「質」を結集して対応したこととしている。そして、次のように総括している。
「この、持てる力すべての活用を重要視する精神(スピリッツ)がペルシア戦役を機にギリシア人の心に生れ、ギリシア文明が後のヨーロッパの母胎になっていく道程を経て、ヨーロッパ精神を形成する重要な一要素になったのではないだろうか。」
ヘェーと思いつつ、何となく納得してしまう。
◎テミトクレス、アルキビアデスと悪役たち
本書には多くの人物が登場するが、著者が焦点を当てているのは第1巻ではテミトクレス、第2巻ではアルキビアデスである。前者はアテネ海軍を増強しサラミス海戦を勝利に導いた人物、後者は奔放な美貌の青年政治家で、二人ともかなり魅力的に描かれている。
そんな魅力的な人物とは対照的な悪役も登場する。スパルタの5人のエフォロス(監督官)やアテネの扇動政治家たちだ。この悪役たちの視野が狭く洞察力のない小人物ぶりに読者は苛立つしかなく、それが物語を面白くもしている。
また、名脇役のような形で歴史家のツキディディス、悲劇作家のソフォクレス、哲学者のソクラテスなどが登場するのも興味深い。彼らは軍の指揮官あるいは重装歩兵として戦役に参加しながら著作や哲学にも打ち込んでいる。そんな「文化人」たちへの著者の視線はやや醒めているように感じられる。
第1巻ではスパルタ軍を率いて活躍したパウサニアス(少年王の後見人)も魅力的に描かれている。ペルシア戦役で大勝をあげながらもエフォロス(監督官)によって死に追いやらた人物である。パウサニアスはペルシアに内通した裏切者と見なされたのだ。その冤罪が晴れて再評価されたのは、なんと20世紀になってからだそうだ。驚くしかない。パウサニアスが長期間にわたって評価されなかったのは、パウサニアスが好きでなかったツキディディスが『戦史』で中傷に近いエピソードを紹介したからだそうだ。塩野七生はツキディディスをそう非難している。
作家の学者への苛立ちのとばっちりに見えなくもない。
◎真打はアレクサンドロス大王
以上、第1巻と第2巻の登場人物たちは前座で、一番ぶ厚い第3巻のアレクサンドロスが本書の真打である。
口絵には「アレクサンドロスの東征」の地図が載っている。マケドニアを出発し、現在のトルコ、シリア、エジプト、イラク、イラン、アフガニスタン、ウズベキスタンを経てインダス川の東までを覆う「東征」を太線で辿った地図である。教科書などで見ることも多い歴史地図だが、本書の地図には、アレクサンドロスがその地に到達したときの年齢が載っている。
海峡を越えて小アジアに入ってすぐのグラニコスの会戦が21歳、大勢が決したイッソスの会戦が23歳、エジプトに赴き彼の地のアレクサンドリア建設に着手したのが24歳、バビロン入城が25歳、そこからさらに東へ北へと向かい、サマルカンドが28歳、インダス川上流が29歳、河口に下って30歳、海沿いに西に引き返しバビロンに戻り、そこで病没したのが32歳。東方世界制覇の大遠征の11年間が一望できる地図だ。
アレクサンドロスの大帝国は一代で消滅する。つまりは一代記である。塩野七生は次のように述べている。
「地勢から社会形態から困難多き中央アジアの制覇を成し遂げたヨーロッパ人は、先にも後にもこのアレクサンドロス一人になるのだ。(…)近現代になると、イギリス、ロシア、アメリカと、試みはしたのだが結局は撤退している。これに成功したアレクサンドロスの苦労を真に理解し、評価できるのは、あの地方に足を踏み入れたこともない歴史学者よりも、アフガニスタンやパキスタンで闘った経験のある、イギリスやロシアやアメリアの前線部隊長ではないか、と思ったりする。」
歴史学者を挑発しているように見えなくもない。この地は今も混迷しているが。
第3巻には不愉快な悪役は登場しない。もちろん敵役は存在するが、アレクサンドロスと愉快な仲間たちの武勇伝という趣の物語である。アレクサンドロス一行を大学探検部に例えている箇所もある。おもしろくて明るい見立てだ。
『ギリシア人の物語』で塩野七生が述べようとしたことは、都市国家がせめぎあうギリシア世界はアレクサンドロスを生み出し、他民族を取り入れていく大帝国をめざしたアレクサンドロスこそは『ローマ人の物語』の魁だった、ということだ。それは明るいビジョンとして語られている。
塩野七生の『ギリシア人の物語』全3巻が昨年末に完結した。『ローマ人の物語』と同様に年1冊ペースの刊行で、以前から気がかりな本だった。完結を機に3冊まとめて購入し、面白く読了した。
『ギリシア人の物語Ⅰ:民主政のはじまり』(塩野七生/新潮社)
『ギリシア人の物語Ⅱ:民主政の成熟と崩壊』(塩野七生/新潮社)
『ギリシア人の物語Ⅲ:新しき力』(塩野七生/新潮社)
第1巻はペルシア戦役、第2巻はペロポネソス戦役、第3巻はアレクサンドロス(本書オビの表記は「アレクサンダー」だが本文はアレクサンドロス)を描いている。全3巻で古代ギリシアの歴史を描いているが、塩野七生の関心はあくまで人物であり、スパルタやアテネ以前のミノア文明、ミケーネ文明、線形文字解読など考古学的な話題は割愛されている。気持ちのいい割り切りである。
全3巻を読んで「小説のように面白い」と感じた。塩野七生の歴史エッセイは歴史小説とも呼ばれているからこの感想は変だ。一般的な歴史概説書よりワクワクした気分でスラスラと読めたということだ。
塩野七生の歴史エッセイは卓越した政治家や軍の司令官に焦点をあてた人物論であり、リーダー論である。それが現代にも通じる文明論にもなっているから面白い。
ペルシア戦役を扱った第1巻では、都市国家連合のギリシアのペルシアへの勝因を、ペルシアの「量」で圧倒するやり方に、ギリシアは総合的な「質」を結集して対応したこととしている。そして、次のように総括している。
「この、持てる力すべての活用を重要視する精神(スピリッツ)がペルシア戦役を機にギリシア人の心に生れ、ギリシア文明が後のヨーロッパの母胎になっていく道程を経て、ヨーロッパ精神を形成する重要な一要素になったのではないだろうか。」
ヘェーと思いつつ、何となく納得してしまう。
◎テミトクレス、アルキビアデスと悪役たち
本書には多くの人物が登場するが、著者が焦点を当てているのは第1巻ではテミトクレス、第2巻ではアルキビアデスである。前者はアテネ海軍を増強しサラミス海戦を勝利に導いた人物、後者は奔放な美貌の青年政治家で、二人ともかなり魅力的に描かれている。
そんな魅力的な人物とは対照的な悪役も登場する。スパルタの5人のエフォロス(監督官)やアテネの扇動政治家たちだ。この悪役たちの視野が狭く洞察力のない小人物ぶりに読者は苛立つしかなく、それが物語を面白くもしている。
また、名脇役のような形で歴史家のツキディディス、悲劇作家のソフォクレス、哲学者のソクラテスなどが登場するのも興味深い。彼らは軍の指揮官あるいは重装歩兵として戦役に参加しながら著作や哲学にも打ち込んでいる。そんな「文化人」たちへの著者の視線はやや醒めているように感じられる。
第1巻ではスパルタ軍を率いて活躍したパウサニアス(少年王の後見人)も魅力的に描かれている。ペルシア戦役で大勝をあげながらもエフォロス(監督官)によって死に追いやらた人物である。パウサニアスはペルシアに内通した裏切者と見なされたのだ。その冤罪が晴れて再評価されたのは、なんと20世紀になってからだそうだ。驚くしかない。パウサニアスが長期間にわたって評価されなかったのは、パウサニアスが好きでなかったツキディディスが『戦史』で中傷に近いエピソードを紹介したからだそうだ。塩野七生はツキディディスをそう非難している。
作家の学者への苛立ちのとばっちりに見えなくもない。
◎真打はアレクサンドロス大王
以上、第1巻と第2巻の登場人物たちは前座で、一番ぶ厚い第3巻のアレクサンドロスが本書の真打である。
口絵には「アレクサンドロスの東征」の地図が載っている。マケドニアを出発し、現在のトルコ、シリア、エジプト、イラク、イラン、アフガニスタン、ウズベキスタンを経てインダス川の東までを覆う「東征」を太線で辿った地図である。教科書などで見ることも多い歴史地図だが、本書の地図には、アレクサンドロスがその地に到達したときの年齢が載っている。
海峡を越えて小アジアに入ってすぐのグラニコスの会戦が21歳、大勢が決したイッソスの会戦が23歳、エジプトに赴き彼の地のアレクサンドリア建設に着手したのが24歳、バビロン入城が25歳、そこからさらに東へ北へと向かい、サマルカンドが28歳、インダス川上流が29歳、河口に下って30歳、海沿いに西に引き返しバビロンに戻り、そこで病没したのが32歳。東方世界制覇の大遠征の11年間が一望できる地図だ。
アレクサンドロスの大帝国は一代で消滅する。つまりは一代記である。塩野七生は次のように述べている。
「地勢から社会形態から困難多き中央アジアの制覇を成し遂げたヨーロッパ人は、先にも後にもこのアレクサンドロス一人になるのだ。(…)近現代になると、イギリス、ロシア、アメリカと、試みはしたのだが結局は撤退している。これに成功したアレクサンドロスの苦労を真に理解し、評価できるのは、あの地方に足を踏み入れたこともない歴史学者よりも、アフガニスタンやパキスタンで闘った経験のある、イギリスやロシアやアメリアの前線部隊長ではないか、と思ったりする。」
歴史学者を挑発しているように見えなくもない。この地は今も混迷しているが。
第3巻には不愉快な悪役は登場しない。もちろん敵役は存在するが、アレクサンドロスと愉快な仲間たちの武勇伝という趣の物語である。アレクサンドロス一行を大学探検部に例えている箇所もある。おもしろくて明るい見立てだ。
『ギリシア人の物語』で塩野七生が述べようとしたことは、都市国家がせめぎあうギリシア世界はアレクサンドロスを生み出し、他民族を取り入れていく大帝国をめざしたアレクサンドロスこそは『ローマ人の物語』の魁だった、ということだ。それは明るいビジョンとして語られている。
新書大賞『バッタを倒しにアフリカへ』を読んでハッとした ― 2018年03月04日
◎研究者はエライ
新書大賞受賞の『バッタを倒しにアフリカへ』(前野ウルド浩太郎/光文社新書)を読んだ。昨年5月の刊行直後から新聞や雑誌に取り上げられていた話題の本だ。
読み始めると一気読みになった。やはり面白い。軽妙な語り口で楽しく読めて、内容は軽くはない。勤務先が限られているポスドク研究者の試練の状況を生々しく報告し、アフリカでのフィールドワークの楽しくも苛酷な様子を臨場感たっぷりに語ってる。
そして何よりも研究への情熱が伝わってくる。研究者はエライと感心してしまう。日本の研究環境ももう少し何とかならないのかとも感じる。著者がファーブルによって研究者の道を目指したように、本書を読んだ子供たちの中から次代の研究者が育っていくことを願う。研究者生活の厳しさにビビる子供が出てきては逆効果だが…
私たちの子供の頃に比べて、科学者への憧れのようなものが何となく減少しているように感じるのは私だけだろうか。
本書で驚いたのはファーブルが母国フランスでは知名度が低いという話だ。「昆虫の研究者でも10人中一人ぐらいしか知らない」そうだ。なぜ、日本とフランスで知名度が違うのだろうか。本書はその原因には言及していない。思いを巡らしているうちに、現代の日本の子供がどのくらいファーブルを知っているのか、少し気になってきた。
◎37年前に中断した読書を想起
著者の研究テーマは「神の罰」とも呼ばれるバッタの大群「飛蝗」である。本書を読んでいて、ふいに西村寿行の小説『蒼茫の大地、滅ぶ』が出てきてハッとした。飛蝗を扱ったパニック小説である。著者は学生時代に漫画で読んでいて、原作の小説版があるとは知らなかったそうだ。私は漫画化されているとは知らなかった。
私がハッとしたのは、遠い昔にこの小説を読みかけて中断したままだったことを思い出したからだ。引っ越しのたびに本を処分しているが、書架の奥を探してみると1981年5月発行の講談社文庫版の上下2冊が出てきた。37年前の本だ。上巻の100頁を過ぎたあたりに栞代わりの紙が挟まっていた。その紙の露出部分が色あせてヨレヨレになっていた。
なぜ中断したかは憶えていない。つまらない本や難しい本ではなく私好みのSFっぽいエンタメなので、普通は読み通すはずだ。当時は30代前半、仕事が多忙になり通勤電車で読書する余裕もなくなったのかもしれない。考えてみれば、この文庫本が出た時、『バッタを倒しにアフリカへ』の前野氏は生まれたばかりの1歳だ。小説の存在を知らなくて当然かもしれない。
…というわけで、37年ぶりに手にした『蒼茫の大地、滅ぶ』(上)(下)を読了した。西村寿行の動物小説ではあるが、ポリティカル・バイオレンス小説である。飛蝗パニック小説から東北独立の政治軍事小説へと移行する展開だった。西村寿行が荒唐無稽なのは当然だが、やはり昔のエンタメを読んでいる気分になる。東北地方の怨念を背景にしたこの小説を書いた西村寿行は、2011年の3.11を見ることなく2007年に76歳で没している。
若い研究者の新書がきっかけで、遠い昔の忘れ物を拾い上げた気分になった。
新書大賞受賞の『バッタを倒しにアフリカへ』(前野ウルド浩太郎/光文社新書)を読んだ。昨年5月の刊行直後から新聞や雑誌に取り上げられていた話題の本だ。
読み始めると一気読みになった。やはり面白い。軽妙な語り口で楽しく読めて、内容は軽くはない。勤務先が限られているポスドク研究者の試練の状況を生々しく報告し、アフリカでのフィールドワークの楽しくも苛酷な様子を臨場感たっぷりに語ってる。
そして何よりも研究への情熱が伝わってくる。研究者はエライと感心してしまう。日本の研究環境ももう少し何とかならないのかとも感じる。著者がファーブルによって研究者の道を目指したように、本書を読んだ子供たちの中から次代の研究者が育っていくことを願う。研究者生活の厳しさにビビる子供が出てきては逆効果だが…
私たちの子供の頃に比べて、科学者への憧れのようなものが何となく減少しているように感じるのは私だけだろうか。
本書で驚いたのはファーブルが母国フランスでは知名度が低いという話だ。「昆虫の研究者でも10人中一人ぐらいしか知らない」そうだ。なぜ、日本とフランスで知名度が違うのだろうか。本書はその原因には言及していない。思いを巡らしているうちに、現代の日本の子供がどのくらいファーブルを知っているのか、少し気になってきた。
◎37年前に中断した読書を想起
著者の研究テーマは「神の罰」とも呼ばれるバッタの大群「飛蝗」である。本書を読んでいて、ふいに西村寿行の小説『蒼茫の大地、滅ぶ』が出てきてハッとした。飛蝗を扱ったパニック小説である。著者は学生時代に漫画で読んでいて、原作の小説版があるとは知らなかったそうだ。私は漫画化されているとは知らなかった。
私がハッとしたのは、遠い昔にこの小説を読みかけて中断したままだったことを思い出したからだ。引っ越しのたびに本を処分しているが、書架の奥を探してみると1981年5月発行の講談社文庫版の上下2冊が出てきた。37年前の本だ。上巻の100頁を過ぎたあたりに栞代わりの紙が挟まっていた。その紙の露出部分が色あせてヨレヨレになっていた。
なぜ中断したかは憶えていない。つまらない本や難しい本ではなく私好みのSFっぽいエンタメなので、普通は読み通すはずだ。当時は30代前半、仕事が多忙になり通勤電車で読書する余裕もなくなったのかもしれない。考えてみれば、この文庫本が出た時、『バッタを倒しにアフリカへ』の前野氏は生まれたばかりの1歳だ。小説の存在を知らなくて当然かもしれない。
…というわけで、37年ぶりに手にした『蒼茫の大地、滅ぶ』(上)(下)を読了した。西村寿行の動物小説ではあるが、ポリティカル・バイオレンス小説である。飛蝗パニック小説から東北独立の政治軍事小説へと移行する展開だった。西村寿行が荒唐無稽なのは当然だが、やはり昔のエンタメを読んでいる気分になる。東北地方の怨念を背景にしたこの小説を書いた西村寿行は、2011年の3.11を見ることなく2007年に76歳で没している。
若い研究者の新書がきっかけで、遠い昔の忘れ物を拾い上げた気分になった。
シチリアの歴史を手軽に勉強したいと思ったが… ― 2018年03月07日
◎「文庫クセジュ」はクセモノ
ふとしたきっかけでシチリア旅行をすることになった。出発は 5月(2カ月先)、主にギリシア・ローマ時代の古跡をめぐる1週間ほどの旅行だ。シチリアは九州より小さく四国よりは大きい島だ。いまはイタリアの一部だが、かつては王国だったこともある。
ギリシア史やローマ史の本にシチリアという地名は散見する。先日読んだ『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』(塩野七生)にもでてきたが、私はこの島の歴史は断片的にしか知らない。
旅行の前にシチリアの歴史を手っ取り早く勉強しておこうと思い、次の本を読んだ。
『シチリアの歴史』(ジャン・ユレ/幸田礼雅訳/文庫クセジュ/白水社)
薄い(175頁)の新書版で手ごろな入門書と思って読み始めた。冒頭の十数頁までは普通に読み進んだが、次第にわけがわからなくなってきた。知らない地名や人名が頻出するのだ。巻頭にシチリアの地図は掲載されているが、そこにない地名もどんどん出てくる。シチリア以外の地名もたくさん出てくる。都市名か地域名か国名か判然としないことも多い。
登場人物も多い。約170頁で旧石器時代からギリシア・ローマの時代を経てムッソリーニの時代、マフィアが活動する戦後までを概説しているのだから、しかたない。
本書はフランスで刊行されている百科全書的な叢書「文庫クセジュ」の翻訳である。その点に感じた一抹の不安は的中した。ヨーロッパの地理や歴史の基本素養がある読者を前提にした、フランス教養人向けの歴史エッセイ風の通史なのだ。私のような断片的知識もおぼつかない日本人がついていくのは難しい。
それでも、何とか読み通した。何やらぼんやりとした印象が残り、周辺の基本知識を習得、整理したうえで本書を再読すれば、そのウイットを楽しみながら面白く読めるだろうと感じた。
◎シチリア王国の実態にびっくり
消化不良の読書だったので、続けて次の新書も入手して読んだ。
『中世シチリア王国』(高山博/講談社現代新書)
これは日本人研究者が書いた啓蒙書なので読みやすい。通史ではなく中世を扱った本だが、最初の章で古代から中世に至るまでを概説しているので、13世紀頃までのシチリア史の入門書にもなっている。
そして、本書のメインテーマ「シチリア王国」の説明が抜群に面白い。ひとことで言えば、北フランスのノルマンジーからやって来たノルマン人が作ったこの王国は、ローマ・カソリック文化、ビザンチン(ギリシア)文化、イスラム文化の三つがモザイクのように共存した不思議な王国であり、後のヨーロッパ世界の文化に多大な影響を及ぼしているのだ。私にとっては目から鱗のびっくり読書だった。
中世に生きた近代人と言われるフリードリッヒ二世(神聖ローマ帝国皇帝&シチリア王)は本書のエピローグに少しだけ登場する。あの皇帝の前身にこの王国があったのかと納得した。
◎周辺世界抜きには把握できないシチリア史
『シチリアの歴史』と『中世シチリア王国』を読んで、この島の歴史にはヨーロッパの歴史の多様な要素が詰まっていると認識した。九州より狭い島なのに決して一枚岩ではなく、島内の都市は多様である。それは周辺世界の反映でもある。
地理的条件から地中海周辺のいろろな国や民族の影響下にあるので、この島の歴史は周辺の事情抜きに語ることはできない。その周辺とはヨーロッパ、小アジア、北アフリカである。
ということは、シチリアの歴史を把握するには西欧史全体を把握しなけらばならない、ということになってしまう。これはタイヘンなことだ。あらためて西欧の国々の歴史はゴチャゴチャと絡み合っていることを認識した。
ふとしたきっかけでシチリア旅行をすることになった。出発は 5月(2カ月先)、主にギリシア・ローマ時代の古跡をめぐる1週間ほどの旅行だ。シチリアは九州より小さく四国よりは大きい島だ。いまはイタリアの一部だが、かつては王国だったこともある。
ギリシア史やローマ史の本にシチリアという地名は散見する。先日読んだ『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』(塩野七生)にもでてきたが、私はこの島の歴史は断片的にしか知らない。
旅行の前にシチリアの歴史を手っ取り早く勉強しておこうと思い、次の本を読んだ。
『シチリアの歴史』(ジャン・ユレ/幸田礼雅訳/文庫クセジュ/白水社)
薄い(175頁)の新書版で手ごろな入門書と思って読み始めた。冒頭の十数頁までは普通に読み進んだが、次第にわけがわからなくなってきた。知らない地名や人名が頻出するのだ。巻頭にシチリアの地図は掲載されているが、そこにない地名もどんどん出てくる。シチリア以外の地名もたくさん出てくる。都市名か地域名か国名か判然としないことも多い。
登場人物も多い。約170頁で旧石器時代からギリシア・ローマの時代を経てムッソリーニの時代、マフィアが活動する戦後までを概説しているのだから、しかたない。
本書はフランスで刊行されている百科全書的な叢書「文庫クセジュ」の翻訳である。その点に感じた一抹の不安は的中した。ヨーロッパの地理や歴史の基本素養がある読者を前提にした、フランス教養人向けの歴史エッセイ風の通史なのだ。私のような断片的知識もおぼつかない日本人がついていくのは難しい。
それでも、何とか読み通した。何やらぼんやりとした印象が残り、周辺の基本知識を習得、整理したうえで本書を再読すれば、そのウイットを楽しみながら面白く読めるだろうと感じた。
◎シチリア王国の実態にびっくり
消化不良の読書だったので、続けて次の新書も入手して読んだ。
『中世シチリア王国』(高山博/講談社現代新書)
これは日本人研究者が書いた啓蒙書なので読みやすい。通史ではなく中世を扱った本だが、最初の章で古代から中世に至るまでを概説しているので、13世紀頃までのシチリア史の入門書にもなっている。
そして、本書のメインテーマ「シチリア王国」の説明が抜群に面白い。ひとことで言えば、北フランスのノルマンジーからやって来たノルマン人が作ったこの王国は、ローマ・カソリック文化、ビザンチン(ギリシア)文化、イスラム文化の三つがモザイクのように共存した不思議な王国であり、後のヨーロッパ世界の文化に多大な影響を及ぼしているのだ。私にとっては目から鱗のびっくり読書だった。
中世に生きた近代人と言われるフリードリッヒ二世(神聖ローマ帝国皇帝&シチリア王)は本書のエピローグに少しだけ登場する。あの皇帝の前身にこの王国があったのかと納得した。
◎周辺世界抜きには把握できないシチリア史
『シチリアの歴史』と『中世シチリア王国』を読んで、この島の歴史にはヨーロッパの歴史の多様な要素が詰まっていると認識した。九州より狭い島なのに決して一枚岩ではなく、島内の都市は多様である。それは周辺世界の反映でもある。
地理的条件から地中海周辺のいろろな国や民族の影響下にあるので、この島の歴史は周辺の事情抜きに語ることはできない。その周辺とはヨーロッパ、小アジア、北アフリカである。
ということは、シチリアの歴史を把握するには西欧史全体を把握しなけらばならない、ということになってしまう。これはタイヘンなことだ。あらためて西欧の国々の歴史はゴチャゴチャと絡み合っていることを認識した。
半世紀前の概説書でギリシア史の復習 ― 2018年03月10日
◎昔も今も
先月、塩野七生の『ギリシア人の物語』全3巻を読んだ。その印象が残っている内にと思い、次のギリシア史の本を読んだ。以前から書架に眠っていた叢書の1冊だ。
『世界の歴史 4 ギリシア』(村田数之亮/河出書房新社)
『ギリシア人の物語』全3巻を読んだと言っても、その内容が時間とともにどんどん消えていくのは仕方ない。関連書を続けて読めば多少なりとも定着するものがあるのではと期待した。無駄な抵抗のような気がするが。
本書が刊行されたのは1968年、ちょうど半世紀前だ。手ごろな最近の啓蒙書もあると思うが、2000年以上昔の話なのだから50年ぐらいはたいしたことはないと考えた。
それでも、書き出しの「現代のアテネ」の記述で面食らった。「現代のアテネは、かつてのアッテカの都としてあるのではない。(…)ギリシア王国の首都であり(…)」とある。そうか、当時のギリシアは王国だったのか。調べてみると、1967年に軍事クーデターがあって反クーデターの国王は亡命、1968年から1974年までは軍事独裁政権、その後は共和政になっている。ギリシア史といえば古代のアレコレが思い浮かぶが最近半世紀もいろいろあったのだ。
◎今も昔も
本書は歴史学者による古代ギリシア史の啓蒙書で図版も多い。読みやすくてわかりやすかった。
前半の三分の一がエーゲ文明から大植民時代の話でアテネやスパルタはまだ主役ではない。
真ん中の三分の一がペルシア戦争とペロポネソス戦争の話でアテネとスパルタが主役に躍り出る。
後半の三分の一で語られるのは、ポリス社会の衰亡、アレクサンドロスの世界帝国とヘレニズム時代、そして世界帝国の解体からプトレマイオス朝エジプトの滅亡(クレオパトラの死)までである。
ここで語られているのは二千数百年に及ぶギリシア文明の勃興から衰亡に至る波乱万丈の歴史である。並行して、同じ時代に存在したアケメネス朝ペルシアの興亡も語られている。さまざまな事象が発生したダイナミックな時間の流れと空間の広がりを感じた。
紀元前の遠い昔の歴史ではあるが、それを読んでいると近現代の事象と同じだと感じることが多い。外交、同盟、国家、帝国、公共、個人、コスモポリタンなどなど人間とその集団が抱える課題は今も昔もほとんど同じに見えてきた。
もちろん、現代の目で歴史で叙述すれば、そこに現代的課題が反映されざるを得ないということはあるだろうが。
◎パウサニアスの評価は…
同じ事象であっても、塩野七生の『ギリシア人の物語』の描き方と異なる箇所がある。当然のことであり、それらをひとつ一つ確認するのも読書の楽しみである。
ただ、塩野七生がかなり力を入れて好漢として描いたスパルタの将軍パウサニアスの扱いが大きく異なっているのには驚いた。
パウサニアスはツキディディスが『戦史』で悪く描いたために評価が低いと、塩野七生がツキディディスを非難することになった人物である。塩野七生によれば、20世紀に入ってドイツの学者たちが、パウサニアス批判の根拠とされた文書(彼を裏切者であるとする文書)が偽物だと実証したそうだ。
村田数之亮は本書でパウサニアスを「ペルシアと通じて私利をむさぼった」残念な人としている。ドイツの学者たちの実証は本書刊行の後だったのかもしれないと思い、ネット検索してみたがよくわからない。ウィキペディア(日本語)でもパウサニアスは裏切者とされていて再評価の記述はない。なぜだろうか。もう少し調べてみたい。
先月、塩野七生の『ギリシア人の物語』全3巻を読んだ。その印象が残っている内にと思い、次のギリシア史の本を読んだ。以前から書架に眠っていた叢書の1冊だ。
『世界の歴史 4 ギリシア』(村田数之亮/河出書房新社)
『ギリシア人の物語』全3巻を読んだと言っても、その内容が時間とともにどんどん消えていくのは仕方ない。関連書を続けて読めば多少なりとも定着するものがあるのではと期待した。無駄な抵抗のような気がするが。
本書が刊行されたのは1968年、ちょうど半世紀前だ。手ごろな最近の啓蒙書もあると思うが、2000年以上昔の話なのだから50年ぐらいはたいしたことはないと考えた。
それでも、書き出しの「現代のアテネ」の記述で面食らった。「現代のアテネは、かつてのアッテカの都としてあるのではない。(…)ギリシア王国の首都であり(…)」とある。そうか、当時のギリシアは王国だったのか。調べてみると、1967年に軍事クーデターがあって反クーデターの国王は亡命、1968年から1974年までは軍事独裁政権、その後は共和政になっている。ギリシア史といえば古代のアレコレが思い浮かぶが最近半世紀もいろいろあったのだ。
◎今も昔も
本書は歴史学者による古代ギリシア史の啓蒙書で図版も多い。読みやすくてわかりやすかった。
前半の三分の一がエーゲ文明から大植民時代の話でアテネやスパルタはまだ主役ではない。
真ん中の三分の一がペルシア戦争とペロポネソス戦争の話でアテネとスパルタが主役に躍り出る。
後半の三分の一で語られるのは、ポリス社会の衰亡、アレクサンドロスの世界帝国とヘレニズム時代、そして世界帝国の解体からプトレマイオス朝エジプトの滅亡(クレオパトラの死)までである。
ここで語られているのは二千数百年に及ぶギリシア文明の勃興から衰亡に至る波乱万丈の歴史である。並行して、同じ時代に存在したアケメネス朝ペルシアの興亡も語られている。さまざまな事象が発生したダイナミックな時間の流れと空間の広がりを感じた。
紀元前の遠い昔の歴史ではあるが、それを読んでいると近現代の事象と同じだと感じることが多い。外交、同盟、国家、帝国、公共、個人、コスモポリタンなどなど人間とその集団が抱える課題は今も昔もほとんど同じに見えてきた。
もちろん、現代の目で歴史で叙述すれば、そこに現代的課題が反映されざるを得ないということはあるだろうが。
◎パウサニアスの評価は…
同じ事象であっても、塩野七生の『ギリシア人の物語』の描き方と異なる箇所がある。当然のことであり、それらをひとつ一つ確認するのも読書の楽しみである。
ただ、塩野七生がかなり力を入れて好漢として描いたスパルタの将軍パウサニアスの扱いが大きく異なっているのには驚いた。
パウサニアスはツキディディスが『戦史』で悪く描いたために評価が低いと、塩野七生がツキディディスを非難することになった人物である。塩野七生によれば、20世紀に入ってドイツの学者たちが、パウサニアス批判の根拠とされた文書(彼を裏切者であるとする文書)が偽物だと実証したそうだ。
村田数之亮は本書でパウサニアスを「ペルシアと通じて私利をむさぼった」残念な人としている。ドイツの学者たちの実証は本書刊行の後だったのかもしれないと思い、ネット検索してみたがよくわからない。ウィキペディア(日本語)でもパウサニアスは裏切者とされていて再評価の記述はない。なぜだろうか。もう少し調べてみたい。
早トチリで買った新書で思いがけず科学史のおさらい ― 2018年03月13日
書店の店頭に次の新刊新書が平積みされていた。
『〈どんでん返し〉の科学史:蘇る錬金術、天動説、自然発生説』(小山慶太/中公新書)
まず、タイトルに目を奪われた。オビの「まさか、錬金術が現代によみがえるとは!」にもびっくりした。手に取って目次をパラパラとめくっただけで、すぐに購入してしまった。現代科学の最前線の驚異を報告するビックリ本だと思ったのだ。
帰宅して「まえがき」読み、早トチリに気づいた。「蘇る錬金術」とは核物理学による元素変換のことであり、「蘇る天動説」とは宇宙の相対座標のことであり、「蘇る自然発生説」とは原始生命は有機高分子から発生しただろうという話である。暗黒エネルギーは21世紀のエーテルに相当するという記述もある。要は科学史の啓蒙書である。
「どんでん返し」という視点から科学史を振り返っているのが本書のミソであり、最先端のビックリ大発見の本ではなかった。目次を冷静に見れば内容はわかるのだが、本書を店頭で手にした私は妙なかん違いをしていた。トンデモ科学やエセ科学は私が最も警戒するものなのに、いったい何を期待して本書を購入したのだろうか。精神状態がおかしかったのかもしれない。
おのれの早トチリを呪いつつも本書を読み進めた。科学史関連の本を読むには久しぶりなので、学生時代の遠い記憶がよみがえってくるような新鮮で懐かしい気分になった。
本書は「蘇る錬金術」「転変をつづける宇宙像」「復活した不可秤物質」「回帰する生命の自然発生説」の4章から成り、それぞれ以下のような科学史のトピックを解説している。
・元素論、錬金術、原子構造の発見、太陽の核融合
・コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、ニュートン、アインシュタイン
・カロリック(熱素)、光子、量子力学、フォノン、重力波、ヒッグス場
・微生物の発見、進化論、DNA、生命と物質
まさにコンパクトな科学史の本である。科学史は私の興味分野の一つだ。私にとっての新たな知見もいろいろあり、面白く読了できた。想定外に科学史の本を読んでしまい、もっときちんと科学史を勉強しなければなあ、という気分になった。と言っても、残された人生の時間は限られているからなあ、とも思った。
『〈どんでん返し〉の科学史:蘇る錬金術、天動説、自然発生説』(小山慶太/中公新書)
まず、タイトルに目を奪われた。オビの「まさか、錬金術が現代によみがえるとは!」にもびっくりした。手に取って目次をパラパラとめくっただけで、すぐに購入してしまった。現代科学の最前線の驚異を報告するビックリ本だと思ったのだ。
帰宅して「まえがき」読み、早トチリに気づいた。「蘇る錬金術」とは核物理学による元素変換のことであり、「蘇る天動説」とは宇宙の相対座標のことであり、「蘇る自然発生説」とは原始生命は有機高分子から発生しただろうという話である。暗黒エネルギーは21世紀のエーテルに相当するという記述もある。要は科学史の啓蒙書である。
「どんでん返し」という視点から科学史を振り返っているのが本書のミソであり、最先端のビックリ大発見の本ではなかった。目次を冷静に見れば内容はわかるのだが、本書を店頭で手にした私は妙なかん違いをしていた。トンデモ科学やエセ科学は私が最も警戒するものなのに、いったい何を期待して本書を購入したのだろうか。精神状態がおかしかったのかもしれない。
おのれの早トチリを呪いつつも本書を読み進めた。科学史関連の本を読むには久しぶりなので、学生時代の遠い記憶がよみがえってくるような新鮮で懐かしい気分になった。
本書は「蘇る錬金術」「転変をつづける宇宙像」「復活した不可秤物質」「回帰する生命の自然発生説」の4章から成り、それぞれ以下のような科学史のトピックを解説している。
・元素論、錬金術、原子構造の発見、太陽の核融合
・コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、ニュートン、アインシュタイン
・カロリック(熱素)、光子、量子力学、フォノン、重力波、ヒッグス場
・微生物の発見、進化論、DNA、生命と物質
まさにコンパクトな科学史の本である。科学史は私の興味分野の一つだ。私にとっての新たな知見もいろいろあり、面白く読了できた。想定外に科学史の本を読んでしまい、もっときちんと科学史を勉強しなければなあ、という気分になった。と言っても、残された人生の時間は限られているからなあ、とも思った。
ゾロアスター教の面白さを発見 ― 2018年03月18日
◎ゾロアスター教に関わる二つの気がかり
『ギリシア人の物語』(塩野七生)、『世界の歴史4 ギリシア』(村田数之亮) など古代ギリシアの本を読んでいて、ギリシアのライバルだったペルシアがゾロアスター教の国だという記述に出会い、ゾロアスター教が少し気になった。
遠い昔のゾロアスター教という宗教について知っていることがあまりに少ないことに気づいたのだ。拝火教という妖しげな呼び名を知っているだけだ。だが、気がかりなことが二つある。
一つはニーチェの『ツァラトゥストラ』である。遠い昔の学生時代に途中まで読んで挫折し、いつかは読まねばと気になっている「世界の名著」だ。ツァラトゥストラがゾロアスターだとの知識はあるが、何故ゾロアスターを描いたのかが理解できない。
もう一つは東芝のマツダランプである。LED時代の今は生産されていないが、かつて東芝の白熱電球はマツダランプというブランド名だった。その「マツダ」は「松田」ではなくゾロアスター教の神様の名だということは小学生の頃に知った。だが、なぜ東芝の電球がそんな神様の名なのかの謎をかかえたまま69歳の高齢者になってしまった。
◎『宗祖ゾロアスター』は単なる解説本ではなかった
「拝火教」「ツァラトゥストラ」「マツダランプ」という単語以外は白紙のゾロアスター教を少しは知りたいと思い次の本を読んだ。
『宗祖ゾロアスター』(前田耕作/ちくま学芸文庫)
入門的な啓蒙書ではなくやや学術的な内容の本で、門外漢の私には難しい部分があったにもかかわらず興味深く読み進めることができた。
ゾロアスター教はユダヤ教や仏教よりも古い宗教で、宗祖ゾロアスターの生年は紀元前1000年から紀元前600年の間のどこかだそうだ。かなり大きな幅だ。ゾロアスター教の神はアフラー・マズダーで、この神による奇蹟でゾロアスターが誕生する。当初、ゾロアスターの教えは既存の宗教と対立し迫害されるが、一人の国王がゾロアスターの教えに帰依したのを契機に拡がっていく。キリストの物語に似ている。
アケメネス朝ペルシア、ササン朝ペルシアはゾロアスター教の国だったが、その後、この地域はイスラム教になりゾロアスター教は衰退する。だが、消滅したわけではなく、現在もムンバイやカラチでパールシー教という名で生き延びている。
本書はそんなゾロアスター教の歴史や教義の単なる解説書ではなかった。ヨーロッパが、遠い昔に中央アジアで生まれたこの宗教をどうとらえ、どう影響を受けてきたか、それを解明しているのが本書の眼目である。
◎ヨーロッパにとっては「東洋の叡智」
ヨーロッパ文化がゾロアスター教に影響を受けているとは思いもよらなかったので、本書によって蒙を啓かれた。
まずは、プラトンやアリストテレスがゾロアスター教をいにしえの東方の叡智としてとらえ、それを蘇らせ発展させて新たな思想を紡いだ。ヨーロッパ文化の基盤であるギリシア哲学の古層にゾロアスター教があったのだ。
キリスト教もゾロアスター教の影響を色濃く受けている。著者は「東方の三博士はゾロアスターをキリスト教と結びつける蝶番の役割を果たしたと述べている。
ゾロアスターは「叡智の人」「魔術者」「占星術者」というさまざまな姿でとらえられ、ヨーロッパの人々はかなり自由なイメージでゾロアスター像を作り上げていった。遠い昔のアジアの人物に関する史料は少なく、ゾロアスター教も時代とともに変わっていったので、その姿はかなり漠然としたものになったようだ。
ルネサンス時代にもゾロアスターへの関心は高まり、その後も18世紀のヴォルテールはローマ・カトリック批判にゾロアスターを援用し、モーツァルトはゾロアスターが登場する『魔笛』を作曲する。19世紀になるとバルザックやニーチェがゾロアスターに着目した著作を刊行する。
◎デュペロンの波乱万丈
本書の中で特に面白かったのは18世紀の香料商の息子デュペロンの波乱万丈の物語だ。デュペロンはゾロアスター教の聖典を探索するため、言語を学んだうえでインドに旅立ち、艱難辛苦の末についに聖典を入手し、それを翻訳して発表する。その様子を著者は次のように記述している。
「デュペロンの大冊刊行はヨーロッパに大きな反響を捲き起こした。誰も読むことのできなかった「ゾロアスターの著作」が初めて人びとの手に渡されたのである。大いなる驚きの次に深い失望と激しい反発、そして小さな称賛がやってきた。」
当時の知識人にとって、その内容が期待外れだったのでニセモノだとの批判が起きたのだ。その批判が的外れだとされるのは60年以上後になってからである。
聖典といってもその表現はかなり漠たるもので、解読・解釈は容易でないのだ。
◎ツァラトゥストラとマツダランプ
本書は『ツァラトゥストラ』にも踏み込んで言及していて、ニーチェのゾロアスターへの関心が了解できた。
マツダランプへの言及は本書にはない。だが、東芝のホームページに以下の説明があった、
〔「マツダ」の名称は、ゾロアスター教の光の神である「アウラ・マツダ」に由来している。これは、1910年GE社をはじめ世界各国の代表的な電球会社がタングステン・フィラメントの改良研究を目的に会合した際、今後各国で製作する一流のタングステン電球には「マツダランプ」としようと決められたからであった。〕
GEをはじめとする世界の電球会社が「マツダ」を選んだのは、ヨーロッパ文明の背景にゾロアスター教があることの証だろう。本書を読むとよくわかる。
ゾロアスター教は古代の中国にも伝わっているし、仏教にも影響を与えている。東芝が「マツダ」を受け容れるのは当然だったのだろう。
『ギリシア人の物語』(塩野七生)、『世界の歴史4 ギリシア』(村田数之亮) など古代ギリシアの本を読んでいて、ギリシアのライバルだったペルシアがゾロアスター教の国だという記述に出会い、ゾロアスター教が少し気になった。
遠い昔のゾロアスター教という宗教について知っていることがあまりに少ないことに気づいたのだ。拝火教という妖しげな呼び名を知っているだけだ。だが、気がかりなことが二つある。
一つはニーチェの『ツァラトゥストラ』である。遠い昔の学生時代に途中まで読んで挫折し、いつかは読まねばと気になっている「世界の名著」だ。ツァラトゥストラがゾロアスターだとの知識はあるが、何故ゾロアスターを描いたのかが理解できない。
もう一つは東芝のマツダランプである。LED時代の今は生産されていないが、かつて東芝の白熱電球はマツダランプというブランド名だった。その「マツダ」は「松田」ではなくゾロアスター教の神様の名だということは小学生の頃に知った。だが、なぜ東芝の電球がそんな神様の名なのかの謎をかかえたまま69歳の高齢者になってしまった。
◎『宗祖ゾロアスター』は単なる解説本ではなかった
「拝火教」「ツァラトゥストラ」「マツダランプ」という単語以外は白紙のゾロアスター教を少しは知りたいと思い次の本を読んだ。
『宗祖ゾロアスター』(前田耕作/ちくま学芸文庫)
入門的な啓蒙書ではなくやや学術的な内容の本で、門外漢の私には難しい部分があったにもかかわらず興味深く読み進めることができた。
ゾロアスター教はユダヤ教や仏教よりも古い宗教で、宗祖ゾロアスターの生年は紀元前1000年から紀元前600年の間のどこかだそうだ。かなり大きな幅だ。ゾロアスター教の神はアフラー・マズダーで、この神による奇蹟でゾロアスターが誕生する。当初、ゾロアスターの教えは既存の宗教と対立し迫害されるが、一人の国王がゾロアスターの教えに帰依したのを契機に拡がっていく。キリストの物語に似ている。
アケメネス朝ペルシア、ササン朝ペルシアはゾロアスター教の国だったが、その後、この地域はイスラム教になりゾロアスター教は衰退する。だが、消滅したわけではなく、現在もムンバイやカラチでパールシー教という名で生き延びている。
本書はそんなゾロアスター教の歴史や教義の単なる解説書ではなかった。ヨーロッパが、遠い昔に中央アジアで生まれたこの宗教をどうとらえ、どう影響を受けてきたか、それを解明しているのが本書の眼目である。
◎ヨーロッパにとっては「東洋の叡智」
ヨーロッパ文化がゾロアスター教に影響を受けているとは思いもよらなかったので、本書によって蒙を啓かれた。
まずは、プラトンやアリストテレスがゾロアスター教をいにしえの東方の叡智としてとらえ、それを蘇らせ発展させて新たな思想を紡いだ。ヨーロッパ文化の基盤であるギリシア哲学の古層にゾロアスター教があったのだ。
キリスト教もゾロアスター教の影響を色濃く受けている。著者は「東方の三博士はゾロアスターをキリスト教と結びつける蝶番の役割を果たしたと述べている。
ゾロアスターは「叡智の人」「魔術者」「占星術者」というさまざまな姿でとらえられ、ヨーロッパの人々はかなり自由なイメージでゾロアスター像を作り上げていった。遠い昔のアジアの人物に関する史料は少なく、ゾロアスター教も時代とともに変わっていったので、その姿はかなり漠然としたものになったようだ。
ルネサンス時代にもゾロアスターへの関心は高まり、その後も18世紀のヴォルテールはローマ・カトリック批判にゾロアスターを援用し、モーツァルトはゾロアスターが登場する『魔笛』を作曲する。19世紀になるとバルザックやニーチェがゾロアスターに着目した著作を刊行する。
◎デュペロンの波乱万丈
本書の中で特に面白かったのは18世紀の香料商の息子デュペロンの波乱万丈の物語だ。デュペロンはゾロアスター教の聖典を探索するため、言語を学んだうえでインドに旅立ち、艱難辛苦の末についに聖典を入手し、それを翻訳して発表する。その様子を著者は次のように記述している。
「デュペロンの大冊刊行はヨーロッパに大きな反響を捲き起こした。誰も読むことのできなかった「ゾロアスターの著作」が初めて人びとの手に渡されたのである。大いなる驚きの次に深い失望と激しい反発、そして小さな称賛がやってきた。」
当時の知識人にとって、その内容が期待外れだったのでニセモノだとの批判が起きたのだ。その批判が的外れだとされるのは60年以上後になってからである。
聖典といってもその表現はかなり漠たるもので、解読・解釈は容易でないのだ。
◎ツァラトゥストラとマツダランプ
本書は『ツァラトゥストラ』にも踏み込んで言及していて、ニーチェのゾロアスターへの関心が了解できた。
マツダランプへの言及は本書にはない。だが、東芝のホームページに以下の説明があった、
〔「マツダ」の名称は、ゾロアスター教の光の神である「アウラ・マツダ」に由来している。これは、1910年GE社をはじめ世界各国の代表的な電球会社がタングステン・フィラメントの改良研究を目的に会合した際、今後各国で製作する一流のタングステン電球には「マツダランプ」としようと決められたからであった。〕
GEをはじめとする世界の電球会社が「マツダ」を選んだのは、ヨーロッパ文明の背景にゾロアスター教があることの証だろう。本書を読むとよくわかる。
ゾロアスター教は古代の中国にも伝わっているし、仏教にも影響を与えている。東芝が「マツダ」を受け容れるのは当然だったのだろう。
歌舞伎座で唐十郎、野田秀樹想起の時間旅行 ― 2018年03月23日
◎祝祭気分になれる場所
歌舞伎座の「三月大歌舞伎」昼の部、夜の部を通しで観劇、午前11時から約10時間かけて次の六つの演目を観た。
1. 国性爺合戦(愛之助、扇雀、芝翫、秀太郎、他)
2. 男女道成寺(雀右衛門、松緑、他)
3. 芝浜革財布(芝翫、孝太郎、他)
4. 於染久松色読販(玉三郎、仁左衛門、他)
5. 神田祭(玉三郎、仁左衛門)
6. 滝の白糸(壱太郎、松也、他)
『芝浜革財布』ので市川中車主演をテレビ中継で観た以外はすべて初見だ。
『芝浜革財布』の元は著名な古典落語で、歌舞伎版ではハッピーエンドのラストシーンで落語とは異なり政五郎が三年ぶりに酒を飲む。ここで飲んではまたアル中に逆戻りするのではと心配になるが、そこが歌舞伎のおおらかさであり、この芝居を祝祭的にしている。
歌舞伎には時事ネタや楽屋オチが挿入されることも多い。今回は『国性爺合戦』と『神田祭』にカーリング姿や「そだねー」が出てきた。祝祭気分になる。
◎『国性爺合戦』と『滝の白糸』に惹かれた
「三月大歌舞伎」の目当ては昼一番の『国性爺合戦』と夜ラストの『滝の白糸』である。どちらも著名な演目なので、生きているうちに一度は観ておくべきだろうと思ってチケットを手配した。
チケットをゲットした後でふいに気づいた。『国性爺合戦』と『滝の白糸』に惹かれたのは記憶の深層のせいだ。これらの芝居のパロディというか別バージョンを若い日に観ていたことをぼんやりと思い出したのだ。古い記録を探索し、次の観劇記録が判明した。
※1975年3月上演『唐版滝の白糸』(作:唐十郎、演出:蜷川幸雄。主演:沢田研二・李礼仙)
※1989年11月上演『野田版国性爺合戦』(作・演出:野田秀樹、主演:桜田淳子・池畑慎之介)
前者は43年前、後者は29年前の芝居だ。観たという記憶がかすかにあるだけで内容は失念している。上演当時、沢田研二は28歳、桜田淳子は31歳。私は沢田研二より1歳下、桜田淳子より10歳上だ。みんな若かった。
上演内容を失念しているので断言はできないが、「唐版」や「野田版」の芝居を観たときにオリジナルを観たいとは思わなかった。前衛的な「唐版」「野田版」で十分に堪能し、オリジナルへの関心はわかなかったのだ。
にもかかわらず、今回の観劇には未見のオリジナルに触れたいという深層心理がはたらいたような気がする。『国性爺合戦』も『滝の白糸』もわかりやすくて面白い芝居なので十分に楽しむことができた。そこには深層心理の安堵感もいくぶんあったかもしれない。
◎孝・玉コンビ健在
目当ての『国性爺合戦』『滝の白糸』以上に堪能できたのは、片岡仁左衛門と坂東玉三郎の姿が美しい『於染久松色読販』『神田祭』だった。
私が初めて歌舞伎座で観劇したのは32年前(1986年)の『仮名手本忠臣蔵』で、片岡孝夫と坂東玉三郎の美しさに感動し「これがあの孝夫・玉三郎」かと納得した。
今回の舞台で、その美しいコンビの姿がいまだに健在であることを確認できた。観客である当方は高齢者になっても、同じ年月を経た筈の役者たちが容色を保って一層輝いていることに芝居の世界の不思議を感じる。
歌舞伎座の「三月大歌舞伎」昼の部、夜の部を通しで観劇、午前11時から約10時間かけて次の六つの演目を観た。
1. 国性爺合戦(愛之助、扇雀、芝翫、秀太郎、他)
2. 男女道成寺(雀右衛門、松緑、他)
3. 芝浜革財布(芝翫、孝太郎、他)
4. 於染久松色読販(玉三郎、仁左衛門、他)
5. 神田祭(玉三郎、仁左衛門)
6. 滝の白糸(壱太郎、松也、他)
『芝浜革財布』ので市川中車主演をテレビ中継で観た以外はすべて初見だ。
『芝浜革財布』の元は著名な古典落語で、歌舞伎版ではハッピーエンドのラストシーンで落語とは異なり政五郎が三年ぶりに酒を飲む。ここで飲んではまたアル中に逆戻りするのではと心配になるが、そこが歌舞伎のおおらかさであり、この芝居を祝祭的にしている。
歌舞伎には時事ネタや楽屋オチが挿入されることも多い。今回は『国性爺合戦』と『神田祭』にカーリング姿や「そだねー」が出てきた。祝祭気分になる。
◎『国性爺合戦』と『滝の白糸』に惹かれた
「三月大歌舞伎」の目当ては昼一番の『国性爺合戦』と夜ラストの『滝の白糸』である。どちらも著名な演目なので、生きているうちに一度は観ておくべきだろうと思ってチケットを手配した。
チケットをゲットした後でふいに気づいた。『国性爺合戦』と『滝の白糸』に惹かれたのは記憶の深層のせいだ。これらの芝居のパロディというか別バージョンを若い日に観ていたことをぼんやりと思い出したのだ。古い記録を探索し、次の観劇記録が判明した。
※1975年3月上演『唐版滝の白糸』(作:唐十郎、演出:蜷川幸雄。主演:沢田研二・李礼仙)
※1989年11月上演『野田版国性爺合戦』(作・演出:野田秀樹、主演:桜田淳子・池畑慎之介)
前者は43年前、後者は29年前の芝居だ。観たという記憶がかすかにあるだけで内容は失念している。上演当時、沢田研二は28歳、桜田淳子は31歳。私は沢田研二より1歳下、桜田淳子より10歳上だ。みんな若かった。
上演内容を失念しているので断言はできないが、「唐版」や「野田版」の芝居を観たときにオリジナルを観たいとは思わなかった。前衛的な「唐版」「野田版」で十分に堪能し、オリジナルへの関心はわかなかったのだ。
にもかかわらず、今回の観劇には未見のオリジナルに触れたいという深層心理がはたらいたような気がする。『国性爺合戦』も『滝の白糸』もわかりやすくて面白い芝居なので十分に楽しむことができた。そこには深層心理の安堵感もいくぶんあったかもしれない。
◎孝・玉コンビ健在
目当ての『国性爺合戦』『滝の白糸』以上に堪能できたのは、片岡仁左衛門と坂東玉三郎の姿が美しい『於染久松色読販』『神田祭』だった。
私が初めて歌舞伎座で観劇したのは32年前(1986年)の『仮名手本忠臣蔵』で、片岡孝夫と坂東玉三郎の美しさに感動し「これがあの孝夫・玉三郎」かと納得した。
今回の舞台で、その美しいコンビの姿がいまだに健在であることを確認できた。観客である当方は高齢者になっても、同じ年月を経た筈の役者たちが容色を保って一層輝いていることに芝居の世界の不思議を感じる。
ヘロドトスもトゥキュディデスも意外に読みやすくて面白い ― 2018年03月25日
◎古代の歴史家への関心
へロドトス、トゥキュディデスという古代の歴史家は、高校の世界史で名前を暗記しただけの存在だった。「ヘロドトスは歴史の父」と憶えて終わりだった。
それが少し変わったのは、2年前に『世界の歴史⑤ ギリシアとローマ』(本村凌二・桜井万里子/中央公論社)を読んだ時だ。この概説書で桜井万里子氏が述べているヘロドトスとトゥキュディデスの比較が面白かった。
ヘロドトスは神話や伝承を取り込んで奇想天外、トゥキュディデスは厳密で真摯。歴史研究者としてはトゥキュディデスに敬意を抱く。だが、歴史の実相に迫るには伝説や神話の援用も有効で、その意味ではヘロドトスの方が重要になる。そんな主旨の比較論で、歴史研究の場でのこの二人評価の違いを知り興味をもった。
そして最近、『ギリシア人の物語』(塩野七生)、『世界の歴史4 ギリシア』(村田数之亮) などを読んで古代ギリシアが少し身近になり、これらの本で言及されているへロドトスとトゥキュディデスへの関心が高まった。へロドトスはペルシア戦役を叙述し、トゥキュディデスはペロポネソス戦役を叙述した。そのおかげで後世の史家はギリシア史を語れるのだ。
◎『世界の名著』版は手ごろ
へロドトスとトゥキュディデスへの興味はわいたが、その大部の著書を読もうという気にまではなれなかった。そんな時に次の本の存在を知った。
『世界の名著⑤ へロドトス、トゥキュディデス』(責任編集:村川堅太郎/中央公論社)
これは1冊にへロドトスの『歴史』、トゥキュディデスの『戦史』の二つが収録されている。両方とも抄録だ(全編だとどちらも岩波文庫で3冊)。抄録なら何とか読めるかなと思いネットで入手した。1970年刊行の古書だ。
2段組で500ページ強、抄録でもコンパクトとは言い難い。冒頭60ページは『歴史叙述の誕生』と題する村川堅太郎の解説で、へロドトスとトゥキュディデスの違いの説明が勉強になった。半世紀近く昔のこの解説にも「ヘロドトスについての評価は近年高まった」とある。
◎ヘロドトスは自由奔放
『歴史(抄)』(ヘロドトス/松平千秋訳)
ヘロドトスを読み始めて、意外に読みやすいのに驚いた。訳者のおかげだろうが、紀元前の古典という感じがしない。内容も面白い。村川堅太郎が「素朴で話し好きな老人の筆」と表現しているのも了解できた。
と言っても、未知の地名や人名が頻出すると興味が削がれる。ペルシア戦役に関しては関連本を読んだばかりだし、『ギリシア・ローマ歴史地図』(原書房)という地図帳も座右にある。ところが、本書ではなかなかペルシア戦役が始まらない。前半はペルシアやエジプトの歴史や地誌である。紀元前5世紀の本だから、当然ながら遠い昔の中近東の話であり、私にとっては白紙の世界だ。それでも、地名や人名をネットで検索しながら何とか読み進めた。
後年、アリストテレスから「たわ言」と評されたトンデモ逸話(ライオンの分娩の話。訳注でアリストテレスの言説を紹介)なども挿入されていて、大昔の人がもっと昔の人の著作を批判する姿をほほえましく感じたりもした。
後半のテルモピュライの戦いやサラミス海戦のくだりは当然ながら興味深く読んだ。そして、この「抄録」を読了してヘロドトスの自由奔放な書きっぷりに惹かれ、やはり全編を読みたいと思った。
◎トゥキュディデスは謹厳実直
『戦史(抄)』(トゥキュディデス/久保正彰訳)
トゥキュディデスはヘロドトスに較べると謹厳実直で記述も手堅い。しかし、思ったほど読みにくくはない。自らも参戦した同時代のペロポネソス戦役の記録なのに、歴史を見る視点が感じられる。事象の原因を分析し、人々の言動を批判的にとらえている。
シチリア遠征において、ニキアスが月蝕によって撤退を延期して時期を逸した件でも「かれは神託予言などの類をやや偏重すしすぎる性質であった」と書いている。その後何世紀経っても神託予言を偏重する人は後を絶たないが、紀元前5世紀の時点にこんな冷静な記述があったことに驚いた。人類はさほど進歩したわけではないと思えてくる。
トゥキュディデスの圧巻は演説の紹介である。演説の正確な記録は困難なので著者は事前に次のように述べている。
「政見の記録は、事実表明された政見の全体としての主旨を、できうるかぎり忠実に、筆者の目でたどりながら、おのおのの発言者がその場で直面した事態について、もっとも適切と判断して述べたにちがいない、と思われる論旨をもってこれをつづった。」
そんな方法で、論争の場での政治家たちの演説や、戦闘を前にした将軍たちの演説がつづられている。いずれも長大であり、壮大な舞台の歴史劇を観ている気分になる。
◎古典の力
ペルシア戦役は紀元前500年~前449年、ペロポネス戦役は紀元前431年~前404年、いずれも遠い昔の出来事だ。それを同時代の歴史家がつづった著作を読み、2500年をタイムスリップして古代の情景を目の当たりにしている気分になれた。古典の力だろう。
へロドトスやトゥキュディデスがこんなに面白いなら、もっと早く読んでおけばよかったと思う。こういう古典は若いうちに読んでおいて、年取ってからは再読を楽しむ読み方がいい。もちろん、抄録ではなく全編を楽しむべきだ。悲しいかな、私は若いときに関心を抱けなかったので、そんな楽しみは享受できない。仕方ないことである。
だが、いつの日か全編をのんびり読んでみたいとは思う。そのときには、それなりに詳細な地図、人名表、年表の準備が必要だ。その準備だけでも大変そうだ。
へロドトス、トゥキュディデスという古代の歴史家は、高校の世界史で名前を暗記しただけの存在だった。「ヘロドトスは歴史の父」と憶えて終わりだった。
それが少し変わったのは、2年前に『世界の歴史⑤ ギリシアとローマ』(本村凌二・桜井万里子/中央公論社)を読んだ時だ。この概説書で桜井万里子氏が述べているヘロドトスとトゥキュディデスの比較が面白かった。
ヘロドトスは神話や伝承を取り込んで奇想天外、トゥキュディデスは厳密で真摯。歴史研究者としてはトゥキュディデスに敬意を抱く。だが、歴史の実相に迫るには伝説や神話の援用も有効で、その意味ではヘロドトスの方が重要になる。そんな主旨の比較論で、歴史研究の場でのこの二人評価の違いを知り興味をもった。
そして最近、『ギリシア人の物語』(塩野七生)、『世界の歴史4 ギリシア』(村田数之亮) などを読んで古代ギリシアが少し身近になり、これらの本で言及されているへロドトスとトゥキュディデスへの関心が高まった。へロドトスはペルシア戦役を叙述し、トゥキュディデスはペロポネソス戦役を叙述した。そのおかげで後世の史家はギリシア史を語れるのだ。
◎『世界の名著』版は手ごろ
へロドトスとトゥキュディデスへの興味はわいたが、その大部の著書を読もうという気にまではなれなかった。そんな時に次の本の存在を知った。
『世界の名著⑤ へロドトス、トゥキュディデス』(責任編集:村川堅太郎/中央公論社)
これは1冊にへロドトスの『歴史』、トゥキュディデスの『戦史』の二つが収録されている。両方とも抄録だ(全編だとどちらも岩波文庫で3冊)。抄録なら何とか読めるかなと思いネットで入手した。1970年刊行の古書だ。
2段組で500ページ強、抄録でもコンパクトとは言い難い。冒頭60ページは『歴史叙述の誕生』と題する村川堅太郎の解説で、へロドトスとトゥキュディデスの違いの説明が勉強になった。半世紀近く昔のこの解説にも「ヘロドトスについての評価は近年高まった」とある。
◎ヘロドトスは自由奔放
『歴史(抄)』(ヘロドトス/松平千秋訳)
ヘロドトスを読み始めて、意外に読みやすいのに驚いた。訳者のおかげだろうが、紀元前の古典という感じがしない。内容も面白い。村川堅太郎が「素朴で話し好きな老人の筆」と表現しているのも了解できた。
と言っても、未知の地名や人名が頻出すると興味が削がれる。ペルシア戦役に関しては関連本を読んだばかりだし、『ギリシア・ローマ歴史地図』(原書房)という地図帳も座右にある。ところが、本書ではなかなかペルシア戦役が始まらない。前半はペルシアやエジプトの歴史や地誌である。紀元前5世紀の本だから、当然ながら遠い昔の中近東の話であり、私にとっては白紙の世界だ。それでも、地名や人名をネットで検索しながら何とか読み進めた。
後年、アリストテレスから「たわ言」と評されたトンデモ逸話(ライオンの分娩の話。訳注でアリストテレスの言説を紹介)なども挿入されていて、大昔の人がもっと昔の人の著作を批判する姿をほほえましく感じたりもした。
後半のテルモピュライの戦いやサラミス海戦のくだりは当然ながら興味深く読んだ。そして、この「抄録」を読了してヘロドトスの自由奔放な書きっぷりに惹かれ、やはり全編を読みたいと思った。
◎トゥキュディデスは謹厳実直
『戦史(抄)』(トゥキュディデス/久保正彰訳)
トゥキュディデスはヘロドトスに較べると謹厳実直で記述も手堅い。しかし、思ったほど読みにくくはない。自らも参戦した同時代のペロポネソス戦役の記録なのに、歴史を見る視点が感じられる。事象の原因を分析し、人々の言動を批判的にとらえている。
シチリア遠征において、ニキアスが月蝕によって撤退を延期して時期を逸した件でも「かれは神託予言などの類をやや偏重すしすぎる性質であった」と書いている。その後何世紀経っても神託予言を偏重する人は後を絶たないが、紀元前5世紀の時点にこんな冷静な記述があったことに驚いた。人類はさほど進歩したわけではないと思えてくる。
トゥキュディデスの圧巻は演説の紹介である。演説の正確な記録は困難なので著者は事前に次のように述べている。
「政見の記録は、事実表明された政見の全体としての主旨を、できうるかぎり忠実に、筆者の目でたどりながら、おのおのの発言者がその場で直面した事態について、もっとも適切と判断して述べたにちがいない、と思われる論旨をもってこれをつづった。」
そんな方法で、論争の場での政治家たちの演説や、戦闘を前にした将軍たちの演説がつづられている。いずれも長大であり、壮大な舞台の歴史劇を観ている気分になる。
◎古典の力
ペルシア戦役は紀元前500年~前449年、ペロポネス戦役は紀元前431年~前404年、いずれも遠い昔の出来事だ。それを同時代の歴史家がつづった著作を読み、2500年をタイムスリップして古代の情景を目の当たりにしている気分になれた。古典の力だろう。
へロドトスやトゥキュディデスがこんなに面白いなら、もっと早く読んでおけばよかったと思う。こういう古典は若いうちに読んでおいて、年取ってからは再読を楽しむ読み方がいい。もちろん、抄録ではなく全編を楽しむべきだ。悲しいかな、私は若いときに関心を抱けなかったので、そんな楽しみは享受できない。仕方ないことである。
だが、いつの日か全編をのんびり読んでみたいとは思う。そのときには、それなりに詳細な地図、人名表、年表の準備が必要だ。その準備だけでも大変そうだ。
200年前の奴隷の逃亡劇が遠未来に重なる『地下鉄道』 ― 2018年03月27日
◎『地下鉄道』はどんなSFか
『地下鉄道』という翻訳小説を読んだ。2016年刊行の米国の小説で、ピュリッツア賞、全米図書賞など数多くの文学賞を受賞、日本語版の刊行は昨年(2017年)12月だ。
『地下鉄道』(コルソン・ホワイトヘッド/谷崎由衣訳/早川書房)
南北戦争以前の米国の奴隷を描いた小説と知り、現代小説にしては変わった題材だと思った。この小説を読もうと思ったきっかけはアーサー・C・クラーク賞も受賞していると知ったからだ。あの高名なSF作家の名を冠した賞があるとは知らなかったが、調べてみると「イギリスで最も名誉あるSF賞」だそうだ。『地下鉄道』という小説がどんなSFなのか興味がわいた。
◎これは米国の「時代小説」か
この小説は農園から逃亡した奴隷とそれを追跡する奴隷狩りの話だった。緊迫感のある展開で息をつかせない。歴史的事実に基づいたフィクションの趣があり、米国の歴史に不案内な私には、どこからが虚構なのかはよくわからない。日本でいえば江戸末期を描いた時代小説だ。
多くの黒人の死体が木に吊るされているシーンはビリー・ホリデイの『奇妙な果実』を思い出させる。奇妙な謎の地下鉄道を逃亡に利用するシーンでは、さすがにこれは虚構だと思った。この地下鉄道が出てくるから「広義のSF」と見なされたようだ。
地下鉄道に関しては「訳者あとがき」に説明があった。当時、奴隷州から自由州への奴隷の逃亡を援助する組織があり、その暗号名が「地下鉄道」だったそうだ。逃亡奴隷を匿う小屋は「駅」、逃亡奴隷の輸送を援助する人を「車掌」と呼んだそうだ。
作家はこの符牒をそのままの実体として小説にしている。面白い発想だ。実際の地下鉄道が登場することによって、その象徴的な存在に多様なものが反映され、奥行きのある不思議な物語になっている。
登場人物の人名(コーラ、シーザーなど)も何らかの意味を反映しているのかなと感じたが、私にはよくわからない。
◎『都市と星』と重なる
アーサー・C・クラーク賞の受賞理由は知らないが、この小説を読んでクラークの『銀河帝国の崩壊』『都市と星』を連想した。この二つはほぼ同じ内容で、前者を改稿したのが後者だ。私はかなり昔に二つとも読んだ。内容の詳細は失念したが、今でも印象深く残っているのは、遠い未来の喪われた都市の地下に眠っていた地下鉄が動き出すシーンだ。主人公はこの地下鉄に乗って未知の世界への旅を始める。
19世紀初頭の野蛮な米国南部の逃亡奴隷の姿と遠い未来のSF世界が、謎の地下鉄という鮮烈なイメージによって重なって見える。不思議な感覚だ。アーサー・C・クラーク賞の選考者も『地下鉄道』に『都市と星』と共通するものを感じ、通常のSFとは言い難いこの小説をSFと見なしたのではと妄想した。
それにしても、19世紀初頭の苛酷な黒人差別を扱った『地下鉄道』が21世紀の米国で注目を浴びていることに、いささか暗然とする。人類は進歩していないとの思いがわく。
『地下鉄道』という翻訳小説を読んだ。2016年刊行の米国の小説で、ピュリッツア賞、全米図書賞など数多くの文学賞を受賞、日本語版の刊行は昨年(2017年)12月だ。
『地下鉄道』(コルソン・ホワイトヘッド/谷崎由衣訳/早川書房)
南北戦争以前の米国の奴隷を描いた小説と知り、現代小説にしては変わった題材だと思った。この小説を読もうと思ったきっかけはアーサー・C・クラーク賞も受賞していると知ったからだ。あの高名なSF作家の名を冠した賞があるとは知らなかったが、調べてみると「イギリスで最も名誉あるSF賞」だそうだ。『地下鉄道』という小説がどんなSFなのか興味がわいた。
◎これは米国の「時代小説」か
この小説は農園から逃亡した奴隷とそれを追跡する奴隷狩りの話だった。緊迫感のある展開で息をつかせない。歴史的事実に基づいたフィクションの趣があり、米国の歴史に不案内な私には、どこからが虚構なのかはよくわからない。日本でいえば江戸末期を描いた時代小説だ。
多くの黒人の死体が木に吊るされているシーンはビリー・ホリデイの『奇妙な果実』を思い出させる。奇妙な謎の地下鉄道を逃亡に利用するシーンでは、さすがにこれは虚構だと思った。この地下鉄道が出てくるから「広義のSF」と見なされたようだ。
地下鉄道に関しては「訳者あとがき」に説明があった。当時、奴隷州から自由州への奴隷の逃亡を援助する組織があり、その暗号名が「地下鉄道」だったそうだ。逃亡奴隷を匿う小屋は「駅」、逃亡奴隷の輸送を援助する人を「車掌」と呼んだそうだ。
作家はこの符牒をそのままの実体として小説にしている。面白い発想だ。実際の地下鉄道が登場することによって、その象徴的な存在に多様なものが反映され、奥行きのある不思議な物語になっている。
登場人物の人名(コーラ、シーザーなど)も何らかの意味を反映しているのかなと感じたが、私にはよくわからない。
◎『都市と星』と重なる
アーサー・C・クラーク賞の受賞理由は知らないが、この小説を読んでクラークの『銀河帝国の崩壊』『都市と星』を連想した。この二つはほぼ同じ内容で、前者を改稿したのが後者だ。私はかなり昔に二つとも読んだ。内容の詳細は失念したが、今でも印象深く残っているのは、遠い未来の喪われた都市の地下に眠っていた地下鉄が動き出すシーンだ。主人公はこの地下鉄に乗って未知の世界への旅を始める。
19世紀初頭の野蛮な米国南部の逃亡奴隷の姿と遠い未来のSF世界が、謎の地下鉄という鮮烈なイメージによって重なって見える。不思議な感覚だ。アーサー・C・クラーク賞の選考者も『地下鉄道』に『都市と星』と共通するものを感じ、通常のSFとは言い難いこの小説をSFと見なしたのではと妄想した。
それにしても、19世紀初頭の苛酷な黒人差別を扱った『地下鉄道』が21世紀の米国で注目を浴びていることに、いささか暗然とする。人類は進歩していないとの思いがわく。


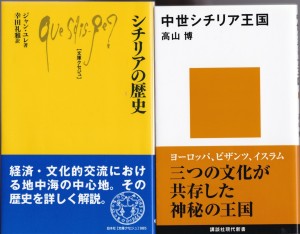




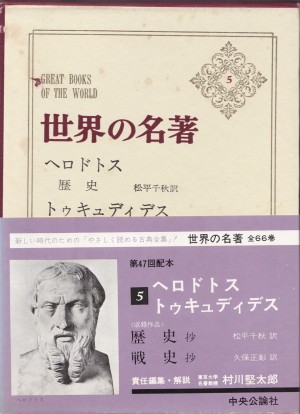
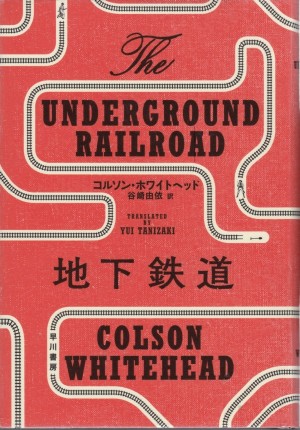
最近のコメント