ヘロドトスに取り組まねばとの気分が高まる本 ― 2018年04月01日
中公版『世界の名著 5』のヘロドトスの『歴史(抄)』が意外に読みやすくて面白かったのでヘロドトスへの興味が高まり、次の本を読んだ。
『アジアの原像:歴史はヘロドトスとともに』(前田耕作/NHKブックス)
サブタイトルに「歴史はヘロドトスとともに」とあるのに惹かれたのだ。一般向けの歴史紀行的な啓蒙書だと思って読み始めたが、やや専門的で予備知識のない門外漢には少し難しい。だが、『歴史(抄)』を読んだ直後だったので何とかついて行けて、興味深く読了した。
本書はヘロドトスを手掛かりにリュディア王国の形成から滅亡までを描いている。と言っても、そもそもリュディア王国って何だ? 高校の世界史には出てこない。ヘロドトスの『歴史(抄)』の前半にリュディアという地名やリュディア王という人物が出てきて、私は初めてこの王国の名を知った(他の本にも出てきたかもしれないが失念している)。本書によって、これまでぼんやりしたイメージしかなかったリュディアが多少明確になった。
リュディア王国とは紀元前7世紀から前6世紀まで小アジア西端にあった王国で、紀元前547年にアケメネス朝ペルシアに滅ぼされる。リュディアというのは元来は地名のようで、王国滅亡後もリュディアという地名は使われている。
ギリシアとペルシアの戦争を描いた史書だと思って読んだヘロドトスの『歴史(抄)』は、ペルシア戦役の記述は後半だけで前半はペルシアやエジプトの話だった。この前半部分に関して、私にはほとんど予備知識がなかったのだが、本書によって事後的に多少の知識を得ることができた。
『歴史(抄)』の冒頭は、妻の容色が自慢の王が側近の部下に妻の裸体を盗み見させ、盗み見されたことを察知した妻は、その部下に王の殺害をそそのかすという印象深い物語だった。面白いけれどヘンテコな話だなあと思ったが、本書によってこれが王朝交代の重要な史実にまつわる話だと認識した。やはり、周辺知識や解説は重要だ。
本書には、ヘロドトスの『歴史』に関する興味深い知見が散りばめれていて、抄録ではなく全編に取り組まねばという気分が高まった。それにはもう少し準備(地図、人名表、年表)も必要で、当面の読書計画には入れていないが…。
『アジアの原像:歴史はヘロドトスとともに』(前田耕作/NHKブックス)
サブタイトルに「歴史はヘロドトスとともに」とあるのに惹かれたのだ。一般向けの歴史紀行的な啓蒙書だと思って読み始めたが、やや専門的で予備知識のない門外漢には少し難しい。だが、『歴史(抄)』を読んだ直後だったので何とかついて行けて、興味深く読了した。
本書はヘロドトスを手掛かりにリュディア王国の形成から滅亡までを描いている。と言っても、そもそもリュディア王国って何だ? 高校の世界史には出てこない。ヘロドトスの『歴史(抄)』の前半にリュディアという地名やリュディア王という人物が出てきて、私は初めてこの王国の名を知った(他の本にも出てきたかもしれないが失念している)。本書によって、これまでぼんやりしたイメージしかなかったリュディアが多少明確になった。
リュディア王国とは紀元前7世紀から前6世紀まで小アジア西端にあった王国で、紀元前547年にアケメネス朝ペルシアに滅ぼされる。リュディアというのは元来は地名のようで、王国滅亡後もリュディアという地名は使われている。
ギリシアとペルシアの戦争を描いた史書だと思って読んだヘロドトスの『歴史(抄)』は、ペルシア戦役の記述は後半だけで前半はペルシアやエジプトの話だった。この前半部分に関して、私にはほとんど予備知識がなかったのだが、本書によって事後的に多少の知識を得ることができた。
『歴史(抄)』の冒頭は、妻の容色が自慢の王が側近の部下に妻の裸体を盗み見させ、盗み見されたことを察知した妻は、その部下に王の殺害をそそのかすという印象深い物語だった。面白いけれどヘンテコな話だなあと思ったが、本書によってこれが王朝交代の重要な史実にまつわる話だと認識した。やはり、周辺知識や解説は重要だ。
本書には、ヘロドトスの『歴史』に関する興味深い知見が散りばめれていて、抄録ではなく全編に取り組まねばという気分が高まった。それにはもう少し準備(地図、人名表、年表)も必要で、当面の読書計画には入れていないが…。
仲代達矢・85歳、まだまだ元気だ ― 2018年04月03日
世田谷パブリックシアターで無名塾の公演『肝っ玉おっ母と子供たち』を観た。主演の「おっ母」は85歳の仲代達矢が演じている。ほとんど出ずっぱりの長丁場で、歌ったり踊ったりもする。科白もよく通る。その元気な姿に感銘した。
私はブレヒトのこの高名な芝居を観るのは初めてだ。観ていなくても内容は何となく知っていて、特に観たいとは思わなかった。『三文オペラ』や『ガリレオの生涯』ほどに興味をもてなかったのは、タイトルと粗筋だけで内容が透けて見え、あえて観なくても舞台で展開される世界が想像できる気になっていたからだ。
今回、観劇しようと思ったのは高齢の仲代達矢が主演と知ったからだ。失礼ながら、これが仲代達也を舞台で観る最後のチャンスかもしれないと考えたのだ。その演目が未見の『肝っ玉おっ母と子供たち』なのも宿題をこなすいい機会に思えた。
仲代達矢が女性を演ずるのに少し驚いた。上演パンフで知ったが、この舞台の初演は30年前の1988年で、そのときも仲代達也が「おっ母」を演じている。演出は隆巴(宮崎恭子:仲代達矢の妻)で、彼女はその8年後に亡くなる。今回の公演も演出は隆巴となっている。30年前の初演を踏襲しているのだろう。
名優が何でも演じられるのは当然で、仲代達矢の老婆役に違和感はまったくなかった。また、観なくてもわかった気になっていた芝居も、実際に舞台で観ると引きこまれ、ブレヒトの代表作と言われるのもむべなるかなと思った。
17世紀の三十年戦争の世界の12年間を行商の幌車を引いて戦場を巡り歩く「肝っ玉おっ母」の姿で描く方法は、やはり秀逸だ。戦争と庶民の普遍的な様を抽出しているのは確かで、ブレヒトの才を感じさせられた。
私はブレヒトのこの高名な芝居を観るのは初めてだ。観ていなくても内容は何となく知っていて、特に観たいとは思わなかった。『三文オペラ』や『ガリレオの生涯』ほどに興味をもてなかったのは、タイトルと粗筋だけで内容が透けて見え、あえて観なくても舞台で展開される世界が想像できる気になっていたからだ。
今回、観劇しようと思ったのは高齢の仲代達矢が主演と知ったからだ。失礼ながら、これが仲代達也を舞台で観る最後のチャンスかもしれないと考えたのだ。その演目が未見の『肝っ玉おっ母と子供たち』なのも宿題をこなすいい機会に思えた。
仲代達矢が女性を演ずるのに少し驚いた。上演パンフで知ったが、この舞台の初演は30年前の1988年で、そのときも仲代達也が「おっ母」を演じている。演出は隆巴(宮崎恭子:仲代達矢の妻)で、彼女はその8年後に亡くなる。今回の公演も演出は隆巴となっている。30年前の初演を踏襲しているのだろう。
名優が何でも演じられるのは当然で、仲代達矢の老婆役に違和感はまったくなかった。また、観なくてもわかった気になっていた芝居も、実際に舞台で観ると引きこまれ、ブレヒトの代表作と言われるのもむべなるかなと思った。
17世紀の三十年戦争の世界の12年間を行商の幌車を引いて戦場を巡り歩く「肝っ玉おっ母」の姿で描く方法は、やはり秀逸だ。戦争と庶民の普遍的な様を抽出しているのは確かで、ブレヒトの才を感じさせられた。
私は『馬の首風雲録』でブレヒト世界のイメージを紡いだ ― 2018年04月05日
先日、ブレヒトの『肝っ玉おっ母と子供たち』観劇の感想を書いた。この芝居に関しては以前から「あえて観なくても舞台で展開される世界が想像できる気になっていた」と書いた。
と言っても、この戯曲を昔に読んでいたわけではない。戯曲を読んだのはほんの1カ月ほど前、チケットをゲットした後だ。だが、この戯曲の雰囲気や内容はずいぶん昔から知っているような気がした。初読なのに既視感があった。
なぜだろうと考えてみた。高名な芝居なので、遠い昔に雑誌や新聞などの紹介記事や劇評、あるいは舞台写真などに接していたせいだろうか。
そんなことを考えているうちに筒井康隆氏の『馬の首風雲録』に思い当たった。氏の長編2作目で『SFマガジン』の1966年9月号から1967年2月号に連載された。この小説のイメージが『肝っ玉おっ母』に重なっているのだ。
この小説の連載が始まった1966年は私が高校を卒業した年だ。当時は『SFマガジン』を数カ月遅れの古本で購入していたので(その方がはるかに安い)、数か月遅れのタイムラグで私はこの連載小説を読んだ。
その後に出た単行本(早川書房の「日本SFシリーズ 13」)も持っているのは、著者による解説風の「あとがき」という付加価値があるからだ。小説そのものは雑誌連載で読んだだけで、その後は読み返していない。
でも、その印象は強く残っていて、最後のセンテンスも憶えている。遠い未来の宇宙の彼方の星で犬に似た異星人が繰り広げる戦争の話で、地球人は背景としてほんの少ししか登場しない。この小説はベトナム戦争とブレヒトをベースにしていると私は感じた。
小説連載時はベトナム戦争の真っ最中であり、小説のラストセンテンス「戦争はまだまだ」終わりそうもなく、それは今や泥沼の様相を呈しはじめていた」は当時のベトナム戦争そのものだ。ベトナム戦争の影を感じるのは当然として、読んだこともないブレヒトの世界を『馬の首風雲録』に感じたのは何故だろうか。おそらく、同じ時期に接した『肝っ玉おっ母と子供たち』の情報と共鳴したのだろう。
単行本の「あとがき」で筒井康隆氏は次のように書いている。
『これは『戦争』というテーマの、一種のコラージュです。(…)この長編の中には過去のさまざまな文学作品、芸術作品がデフォルメした形で貼りあわせてあります。田河水泡『のらくろ』、ブレヒトの戦争テーマの一連の戯曲、その他ヘミングウェイ、岡本喜八の戦争喜劇映画、野間宏、メイラー、カフカ。大岡昇平まで出てきます。』
事後に読んだこの「あとがき」が記憶に何らかの作用をしている可能性もある。いずれにしても『馬の首風雲録』を読んでから約半世紀の間、私の頭の中にあったブレヒトの『肝っ玉おっ母と子供たち』のイメージの内実は『馬の首風雲録』のイメージだったのだ。
そう気づいて、『肝っ玉おっ母と子供たち』観劇後、半世紀ぶりに『馬の首風雲録』を再読した。そして、私が『馬の首風雲録』によってブレヒトをイメージしていたのは的外れではなかったことを確認した。本体を読まずしてイメージを紡げた不思議を感じる。
と言っても、この戯曲を昔に読んでいたわけではない。戯曲を読んだのはほんの1カ月ほど前、チケットをゲットした後だ。だが、この戯曲の雰囲気や内容はずいぶん昔から知っているような気がした。初読なのに既視感があった。
なぜだろうと考えてみた。高名な芝居なので、遠い昔に雑誌や新聞などの紹介記事や劇評、あるいは舞台写真などに接していたせいだろうか。
そんなことを考えているうちに筒井康隆氏の『馬の首風雲録』に思い当たった。氏の長編2作目で『SFマガジン』の1966年9月号から1967年2月号に連載された。この小説のイメージが『肝っ玉おっ母』に重なっているのだ。
この小説の連載が始まった1966年は私が高校を卒業した年だ。当時は『SFマガジン』を数カ月遅れの古本で購入していたので(その方がはるかに安い)、数か月遅れのタイムラグで私はこの連載小説を読んだ。
その後に出た単行本(早川書房の「日本SFシリーズ 13」)も持っているのは、著者による解説風の「あとがき」という付加価値があるからだ。小説そのものは雑誌連載で読んだだけで、その後は読み返していない。
でも、その印象は強く残っていて、最後のセンテンスも憶えている。遠い未来の宇宙の彼方の星で犬に似た異星人が繰り広げる戦争の話で、地球人は背景としてほんの少ししか登場しない。この小説はベトナム戦争とブレヒトをベースにしていると私は感じた。
小説連載時はベトナム戦争の真っ最中であり、小説のラストセンテンス「戦争はまだまだ」終わりそうもなく、それは今や泥沼の様相を呈しはじめていた」は当時のベトナム戦争そのものだ。ベトナム戦争の影を感じるのは当然として、読んだこともないブレヒトの世界を『馬の首風雲録』に感じたのは何故だろうか。おそらく、同じ時期に接した『肝っ玉おっ母と子供たち』の情報と共鳴したのだろう。
単行本の「あとがき」で筒井康隆氏は次のように書いている。
『これは『戦争』というテーマの、一種のコラージュです。(…)この長編の中には過去のさまざまな文学作品、芸術作品がデフォルメした形で貼りあわせてあります。田河水泡『のらくろ』、ブレヒトの戦争テーマの一連の戯曲、その他ヘミングウェイ、岡本喜八の戦争喜劇映画、野間宏、メイラー、カフカ。大岡昇平まで出てきます。』
事後に読んだこの「あとがき」が記憶に何らかの作用をしている可能性もある。いずれにしても『馬の首風雲録』を読んでから約半世紀の間、私の頭の中にあったブレヒトの『肝っ玉おっ母と子供たち』のイメージの内実は『馬の首風雲録』のイメージだったのだ。
そう気づいて、『肝っ玉おっ母と子供たち』観劇後、半世紀ぶりに『馬の首風雲録』を再読した。そして、私が『馬の首風雲録』によってブレヒトをイメージしていたのは的外れではなかったことを確認した。本体を読まずしてイメージを紡げた不思議を感じる。
『歴史学ってなんだ?』は拾いモノの新書 ― 2018年04月14日
◎私の素朴な疑問に応えてくれた本
歴史関係の本を読みながら漠然と抱いていた疑問は、歴史書と歴史小説の境目はどこらにあるかということだ。そんな素朴な課題をわかりやすく解説している本に出会った。
『歴史学ってなんだ?』(小田中直樹/PHP新書)
コンパクトで読みやすく勉強になった。大学で社会経済史を教える著者が、歴史学の「れ」の字も知らない読者を想定して書いた歴史学の入門書である。
◎ある教授の苛立ち
年を取ると歴史への興味が増大する。若い頃は同時代や近未来のアレコレへの関心が高く、煩雑膨大な年表の固まりのような歴史は敬遠気味だった。齢を重ねると、人々の現在の営みや行く末を考えるには人類が経験してきた過去の事跡を振り返ねばと思い至り、歴史関連の書籍に手が伸びる。
学者の書いたものもいいが、司馬遼太郎や塩野七生の歴史小説が読みやすくて面白い。これらの歴史小説は、完全なフィクションというより、歴史の見方のひとつを提示した歴史エッセイとして楽しめる。歴史学者がそんな歴史小説をどう評価しているのかに興味がある。何となく折り合い悪いのではないかという気がする。
また過日の宴席で私より少し若い歴史哲学の教授がいきまいていた言説も気がかりだった。彼は「歴史も小説も同じだと言う歴史学者がいる。そんなことなら何でもありになってしまう。とんでもない話だ。」と怒っていた。
◎わかった気になった
本書は「史実はわかるか」「過去を知ることは社会の役にたつか」という問題意識をベースに、歴史学の動向と現状を解説したうえで、「歴史学は、やはり科学であり、社会の役に立つ」という著者の見解を述べている。
結論は常識的だ。完全に説得されたとは言えないが、そこに至る歴史学の動向が興味深い。「大きな物語の終わり」「マルクス主義歴史学」「経済的基底還元論」「構造主義」「記号論」「史観」「社会史学」などの要領よい解説で、歴史学のかかえる課題がわかった気がする。司馬遼太郎や塩野七生の歴史小説に対する歴史学者の眼差しも推測でき、かの歴史哲学教授の苛立ちも了解できた。
また、高校の歴史教科書が面白くない理由まで納得できた。拾いモノの新書だ。
歴史関係の本を読みながら漠然と抱いていた疑問は、歴史書と歴史小説の境目はどこらにあるかということだ。そんな素朴な課題をわかりやすく解説している本に出会った。
『歴史学ってなんだ?』(小田中直樹/PHP新書)
コンパクトで読みやすく勉強になった。大学で社会経済史を教える著者が、歴史学の「れ」の字も知らない読者を想定して書いた歴史学の入門書である。
◎ある教授の苛立ち
年を取ると歴史への興味が増大する。若い頃は同時代や近未来のアレコレへの関心が高く、煩雑膨大な年表の固まりのような歴史は敬遠気味だった。齢を重ねると、人々の現在の営みや行く末を考えるには人類が経験してきた過去の事跡を振り返ねばと思い至り、歴史関連の書籍に手が伸びる。
学者の書いたものもいいが、司馬遼太郎や塩野七生の歴史小説が読みやすくて面白い。これらの歴史小説は、完全なフィクションというより、歴史の見方のひとつを提示した歴史エッセイとして楽しめる。歴史学者がそんな歴史小説をどう評価しているのかに興味がある。何となく折り合い悪いのではないかという気がする。
また過日の宴席で私より少し若い歴史哲学の教授がいきまいていた言説も気がかりだった。彼は「歴史も小説も同じだと言う歴史学者がいる。そんなことなら何でもありになってしまう。とんでもない話だ。」と怒っていた。
◎わかった気になった
本書は「史実はわかるか」「過去を知ることは社会の役にたつか」という問題意識をベースに、歴史学の動向と現状を解説したうえで、「歴史学は、やはり科学であり、社会の役に立つ」という著者の見解を述べている。
結論は常識的だ。完全に説得されたとは言えないが、そこに至る歴史学の動向が興味深い。「大きな物語の終わり」「マルクス主義歴史学」「経済的基底還元論」「構造主義」「記号論」「史観」「社会史学」などの要領よい解説で、歴史学のかかえる課題がわかった気がする。司馬遼太郎や塩野七生の歴史小説に対する歴史学者の眼差しも推測でき、かの歴史哲学教授の苛立ちも了解できた。
また、高校の歴史教科書が面白くない理由まで納得できた。拾いモノの新書だ。
ゲーテ初読の『イタリア紀行』でその愛嬌に惹かれた ― 2018年04月25日
◎シチリア旅行がきっかけ
来月、シチリア旅行を予定している。その準備の一環としてゲーテの『イタリア紀行(上・中・下)』(相良守峯訳/岩波文庫)を読んだ。
ゲーテと言えば晩年に至るまで恋愛をし「もっと光を!」という最期の言葉で生涯を終えた向日的な文豪というイメージがある。その作品をまともに読んだことはない。数年前に文庫本で『ファウスト』を購入したものの積んだままだ。その未読の『ファウスト』を差し置いて、ネット古書店で入手した『イタリア紀行』を読むことになってしまった。
きっかけはシチリア旅行に備えて読んだ『シチリア歴史紀行』(小森谷慶子/白水社)という本で次の一節の接したからだ。
「やや聞き飽きた感のあるゲーテの名言をもじりたくはないのだが、私もやはり次のように感じずにはいられない。シチリアという世界の鍵を開けることなしには、イタリアのことはもちろん、地中海世界のことなど何も理解できはしないのだ、と。」
ゲーテの名言は知らないが、この一節でゲーテに『イタリア紀行』なる書があることを思い出し、旅行記なら読みやすかろうと興味がわいたのだ。
◎上巻と中巻が面白い
ゲーテは25歳で発表した『若きウェルテルの悩み』で有名になり、32歳でヴァイマル公国の宰相になるも、37歳の時に休暇を願い出てイタリアへ旅立つ(1786年9月)。帰国するのは2年後だ。その2年間に故国の知人・友人あてに書いた報告書風の書簡をまとめたのが『イタリア紀行』だ。
ゲーテが長期滞在したのはローマで、ナポリやシチリアも訪ねている。訳本の上巻は故国を出てからローマに至るまでの報告だ。途中、ヴェネチアには16日間滞在しているがフィレンツエには3時間しか滞在していない。中巻はナポリとシチリアの報告だ。ナポリ滞在中のゲーテはシチリア旅行を逡巡していて、結局行く決断をし、1787年3月29日にナポリ出港、5月17日に帰港している。約1カ月半のシチリア旅行だ。
この上巻と中巻は初めての風物に触れる新鮮な体験や興味深いエピソードが綴れていて面白い。
下巻はローマに戻ってからの約10カ月間の滞在記で、美術品鑑賞や自身の創作活動の報告が中心でやや退屈である。
◎イタリアという地域概念
ゲーテがイタリア旅行をした18世紀。イタリアという統一国家は存在しない。ヴェネチアはヴェネチア共和国、フィレンツエはトスカーナ大公国、ローマは教皇領、ナポリとシチリアはスペイン・ブルボン家の王国だった。
本書にはそんなややこしい状態を反映した記述も多少はある。しかし、むしろ当時の欧州人にとってイタリアという地域概念はすでに明確だったように感じられた。
ヨーロッパを把握するには国という概念だけでなく、地域、民族、さらには◎◎家という汎国家的な王家のからみ具合を捉えねばならないと再認識した。ややこしいことである。
◎ゲーテは自然科学が好き
意外に思ったのはゲーテの関心が芸術作品や遺跡だけでなく岩石や植物などの自然科学の領域に及んでいることだ。後者のウエイトの方が大きいようにさえ感じられる。
噴火中のヴェスヴィオ火山に登った話には驚いた。ゲーテはポンペイ遺跡よりは熔岩や火口への関心が高い。降り注ぐ噴石の合間を縫って熔岩を観察し火口を覗こうとさえしている。一歩間違えれば遭難していたはずだ。
シチリア旅行においてはシラクサ訪問をパスした経緯も面白い。パレルモを出発して古代遺跡などを巡りながらメッシーナを目指していたゲーテは、シチリアはイタリアの穀倉といわれているのにそれらしい風景に出会わないのを不思議に思いガイドに質問する。ガイドは「それを得心なさるにはシラクサを通らず、斜にこの国を横切って行かなければなりません。そうすれば小麦のたくさん産する地方を御覧になれましょう」と答える。
そこでゲーテはシラクサ行きの中止を決める。古代ギリシア・ローマ時代に高名だった町を訪ねるよりは、現代の穀倉地帯を見る方が重要だと判断したわけだ。現世への関心の高さに感心する。さすがゲーテだ。
◎ゲーテに世俗人の愛嬌あり
ゲーテの旅行は変名を使った「おしのび」の旅行だった。しかし、随所で「ウェルテル」の作者とバレて、それなりの楽しそうに振舞っている。また、故国に送り続けていた報告書によってローマへの憧れを喚起された友人・知人たちが大挙してローマに来ようとしているのを知り、あせってそれを阻止しているのも面白い。せっかくの「人払い」が無駄になってしまうからだ。自業自得だと思うが、愛嬌を感じる。
『イタリア紀行』を読んでいると、ゲーテが「文豪」ではなく世俗に生きる等身大の人物に見えてくる。それが収穫だった。
◎ゲーテの名言
なお、本書を読みながら、『シチリア歴史紀行』で言及されていた「聞き飽きたゲーテの名言」探索も試みた。それは次の一節のようだ。
「シチリアなしのイタリアというものは、われわれの心中に何らの表象をも作らない。シチリアにこそすべてに対する鍵があるのだ。」
◎蛇足
『イタリア紀行』を読みながら密かに期待していたのはギボンの『ローマ帝国衰亡史』への言及だ。ギボンはゲーテよリ12歳年長の英国人だ。ゲーテは英語も読解できたので(本書にそれを裏付けるエピソードもある)、刊行時から評判だった『ローマ帝国衰亡史』を読んでいた可能性は高い。しかしギボンへの言及はなかった。古代ローマの遺跡を巡りつつも、文明の滅亡という陰気な物語よりは現世の陽光を楽しんでいたようだ。
来月、シチリア旅行を予定している。その準備の一環としてゲーテの『イタリア紀行(上・中・下)』(相良守峯訳/岩波文庫)を読んだ。
ゲーテと言えば晩年に至るまで恋愛をし「もっと光を!」という最期の言葉で生涯を終えた向日的な文豪というイメージがある。その作品をまともに読んだことはない。数年前に文庫本で『ファウスト』を購入したものの積んだままだ。その未読の『ファウスト』を差し置いて、ネット古書店で入手した『イタリア紀行』を読むことになってしまった。
きっかけはシチリア旅行に備えて読んだ『シチリア歴史紀行』(小森谷慶子/白水社)という本で次の一節の接したからだ。
「やや聞き飽きた感のあるゲーテの名言をもじりたくはないのだが、私もやはり次のように感じずにはいられない。シチリアという世界の鍵を開けることなしには、イタリアのことはもちろん、地中海世界のことなど何も理解できはしないのだ、と。」
ゲーテの名言は知らないが、この一節でゲーテに『イタリア紀行』なる書があることを思い出し、旅行記なら読みやすかろうと興味がわいたのだ。
◎上巻と中巻が面白い
ゲーテは25歳で発表した『若きウェルテルの悩み』で有名になり、32歳でヴァイマル公国の宰相になるも、37歳の時に休暇を願い出てイタリアへ旅立つ(1786年9月)。帰国するのは2年後だ。その2年間に故国の知人・友人あてに書いた報告書風の書簡をまとめたのが『イタリア紀行』だ。
ゲーテが長期滞在したのはローマで、ナポリやシチリアも訪ねている。訳本の上巻は故国を出てからローマに至るまでの報告だ。途中、ヴェネチアには16日間滞在しているがフィレンツエには3時間しか滞在していない。中巻はナポリとシチリアの報告だ。ナポリ滞在中のゲーテはシチリア旅行を逡巡していて、結局行く決断をし、1787年3月29日にナポリ出港、5月17日に帰港している。約1カ月半のシチリア旅行だ。
この上巻と中巻は初めての風物に触れる新鮮な体験や興味深いエピソードが綴れていて面白い。
下巻はローマに戻ってからの約10カ月間の滞在記で、美術品鑑賞や自身の創作活動の報告が中心でやや退屈である。
◎イタリアという地域概念
ゲーテがイタリア旅行をした18世紀。イタリアという統一国家は存在しない。ヴェネチアはヴェネチア共和国、フィレンツエはトスカーナ大公国、ローマは教皇領、ナポリとシチリアはスペイン・ブルボン家の王国だった。
本書にはそんなややこしい状態を反映した記述も多少はある。しかし、むしろ当時の欧州人にとってイタリアという地域概念はすでに明確だったように感じられた。
ヨーロッパを把握するには国という概念だけでなく、地域、民族、さらには◎◎家という汎国家的な王家のからみ具合を捉えねばならないと再認識した。ややこしいことである。
◎ゲーテは自然科学が好き
意外に思ったのはゲーテの関心が芸術作品や遺跡だけでなく岩石や植物などの自然科学の領域に及んでいることだ。後者のウエイトの方が大きいようにさえ感じられる。
噴火中のヴェスヴィオ火山に登った話には驚いた。ゲーテはポンペイ遺跡よりは熔岩や火口への関心が高い。降り注ぐ噴石の合間を縫って熔岩を観察し火口を覗こうとさえしている。一歩間違えれば遭難していたはずだ。
シチリア旅行においてはシラクサ訪問をパスした経緯も面白い。パレルモを出発して古代遺跡などを巡りながらメッシーナを目指していたゲーテは、シチリアはイタリアの穀倉といわれているのにそれらしい風景に出会わないのを不思議に思いガイドに質問する。ガイドは「それを得心なさるにはシラクサを通らず、斜にこの国を横切って行かなければなりません。そうすれば小麦のたくさん産する地方を御覧になれましょう」と答える。
そこでゲーテはシラクサ行きの中止を決める。古代ギリシア・ローマ時代に高名だった町を訪ねるよりは、現代の穀倉地帯を見る方が重要だと判断したわけだ。現世への関心の高さに感心する。さすがゲーテだ。
◎ゲーテに世俗人の愛嬌あり
ゲーテの旅行は変名を使った「おしのび」の旅行だった。しかし、随所で「ウェルテル」の作者とバレて、それなりの楽しそうに振舞っている。また、故国に送り続けていた報告書によってローマへの憧れを喚起された友人・知人たちが大挙してローマに来ようとしているのを知り、あせってそれを阻止しているのも面白い。せっかくの「人払い」が無駄になってしまうからだ。自業自得だと思うが、愛嬌を感じる。
『イタリア紀行』を読んでいると、ゲーテが「文豪」ではなく世俗に生きる等身大の人物に見えてくる。それが収穫だった。
◎ゲーテの名言
なお、本書を読みながら、『シチリア歴史紀行』で言及されていた「聞き飽きたゲーテの名言」探索も試みた。それは次の一節のようだ。
「シチリアなしのイタリアというものは、われわれの心中に何らの表象をも作らない。シチリアにこそすべてに対する鍵があるのだ。」
◎蛇足
『イタリア紀行』を読みながら密かに期待していたのはギボンの『ローマ帝国衰亡史』への言及だ。ギボンはゲーテよリ12歳年長の英国人だ。ゲーテは英語も読解できたので(本書にそれを裏付けるエピソードもある)、刊行時から評判だった『ローマ帝国衰亡史』を読んでいた可能性は高い。しかしギボンへの言及はなかった。古代ローマの遺跡を巡りつつも、文明の滅亡という陰気な物語よりは現世の陽光を楽しんでいたようだ。
オーウェルの『1984』が芝居になった ― 2018年04月29日
◎幻の大杉漣
新国立劇場主劇場で『1984』を観た。オーウェルが描いたあの逆ユートピア世界がどんな舞台になるのか興味があった。
主演は井上芳雄、数カ月前にチケットを購入した時点では私には未知の俳優だった。先月のNHKの『LIFE』というコント番組にゲスト出演していたのを見て好感を抱き、急に既知の俳優になった。藝大声楽家出身の若手ミュージカルスターだ。ただし、今回の舞台は科白のみで歌はなかった。
チケット購入時のチラシには出演者に大杉漣の名があった。急逝のため代役になり、新たなチラシからは名前が消えている。大杉漣が演じる予定だったオブライエンは主人公に対峙する重要な役で、代役(横すべり)の神農直隆は好演だった。でも、舞台を眺めながらその姿の向こうに大杉漣の亡霊がチラチラする感覚にとらわれた。
◎半世紀前の未来はもはや遠い過去
私が『1984年』という小説の存在を知ったのは高校生の頃で1960年代だ。この「未来小説」を読みたいと思ったが当時は入手困難で、1968年に刊行された早川書房の『世界SF全集』第1回配本『ハックスリィ、オーウェル』でやっと読むことができた。
当時、1984年は十数年先の未来だった。周知のようにオーウェルがこの小説を発表したのは1948年(私の生まれた年だ)で、西暦下2桁を入れ替えて 『1984年』にした。現状のある社会体制をおし進めたときにあり得るかもしれない監視社会という「もう一つの世界」を提示した小説で、必ずしも未来予測小説ではない。
にもかかわらず、現実に1984年を経過した時には「ついに1984年を越えてしまった」という不思議な感覚におそわれた。私たちは『1984年』を未来小説の感覚で読んだが、1984年以降の読者はどんな感覚で読むのだろうかとも思った。
その後、村上春樹が近過去小説と銘打って『1Q84』を発表したときには、内容はともかくそのタイトルのつけ方に「こんなテがあったのか」と感心した。
◎『1984』は普遍的な物語
今回、『1984』の舞台を観て、かつての「未来小説」は現実の1984年を経過して21世紀を迎え、より普遍的な物語になったのだと認識した。かつて名付けられた「逆ユートピア小説」という呼称はもはやふさわしくない。そんなノンビリした世界ではなく、近未来や近過去を超えたより切実な隣接世界を描いているように思える。
上演パンフによれば、オーウェルの『1984年』には「付録」があり、そこには2050年という年代が言及されているそうだ。半世紀前に読んだ『1984年』の詳細は失念していても、あの世界の雰囲気と主人公の運命は憶えている、だが、「付録」の存在は記憶にない。
観劇から帰宅し、本棚の奥の『世界SF全集10 ハックスリィ、オーウェル』を確認してみると小説の末尾に『付録 ニュースピークの諸原理』という十数ページの評論風の文章があった。私の記憶からはまったく抜け落ちていた。いつものことながら、わが記憶の頼りなさに愕然とする。目を通してみると、確かに2050年が射程に入っている。この付録をベースに舞台を構想した脚本家(ロバート・アイク、ダンカン・マクミラン)の着眼に感服した。
新国立劇場主劇場で『1984』を観た。オーウェルが描いたあの逆ユートピア世界がどんな舞台になるのか興味があった。
主演は井上芳雄、数カ月前にチケットを購入した時点では私には未知の俳優だった。先月のNHKの『LIFE』というコント番組にゲスト出演していたのを見て好感を抱き、急に既知の俳優になった。藝大声楽家出身の若手ミュージカルスターだ。ただし、今回の舞台は科白のみで歌はなかった。
チケット購入時のチラシには出演者に大杉漣の名があった。急逝のため代役になり、新たなチラシからは名前が消えている。大杉漣が演じる予定だったオブライエンは主人公に対峙する重要な役で、代役(横すべり)の神農直隆は好演だった。でも、舞台を眺めながらその姿の向こうに大杉漣の亡霊がチラチラする感覚にとらわれた。
◎半世紀前の未来はもはや遠い過去
私が『1984年』という小説の存在を知ったのは高校生の頃で1960年代だ。この「未来小説」を読みたいと思ったが当時は入手困難で、1968年に刊行された早川書房の『世界SF全集』第1回配本『ハックスリィ、オーウェル』でやっと読むことができた。
当時、1984年は十数年先の未来だった。周知のようにオーウェルがこの小説を発表したのは1948年(私の生まれた年だ)で、西暦下2桁を入れ替えて 『1984年』にした。現状のある社会体制をおし進めたときにあり得るかもしれない監視社会という「もう一つの世界」を提示した小説で、必ずしも未来予測小説ではない。
にもかかわらず、現実に1984年を経過した時には「ついに1984年を越えてしまった」という不思議な感覚におそわれた。私たちは『1984年』を未来小説の感覚で読んだが、1984年以降の読者はどんな感覚で読むのだろうかとも思った。
その後、村上春樹が近過去小説と銘打って『1Q84』を発表したときには、内容はともかくそのタイトルのつけ方に「こんなテがあったのか」と感心した。
◎『1984』は普遍的な物語
今回、『1984』の舞台を観て、かつての「未来小説」は現実の1984年を経過して21世紀を迎え、より普遍的な物語になったのだと認識した。かつて名付けられた「逆ユートピア小説」という呼称はもはやふさわしくない。そんなノンビリした世界ではなく、近未来や近過去を超えたより切実な隣接世界を描いているように思える。
上演パンフによれば、オーウェルの『1984年』には「付録」があり、そこには2050年という年代が言及されているそうだ。半世紀前に読んだ『1984年』の詳細は失念していても、あの世界の雰囲気と主人公の運命は憶えている、だが、「付録」の存在は記憶にない。
観劇から帰宅し、本棚の奥の『世界SF全集10 ハックスリィ、オーウェル』を確認してみると小説の末尾に『付録 ニュースピークの諸原理』という十数ページの評論風の文章があった。私の記憶からはまったく抜け落ちていた。いつものことながら、わが記憶の頼りなさに愕然とする。目を通してみると、確かに2050年が射程に入っている。この付録をベースに舞台を構想した脚本家(ロバート・アイク、ダンカン・マクミラン)の着眼に感服した。
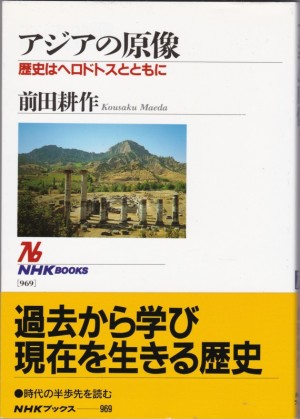

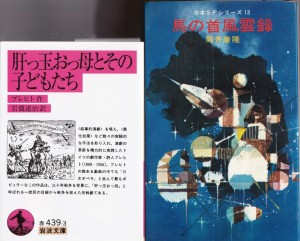
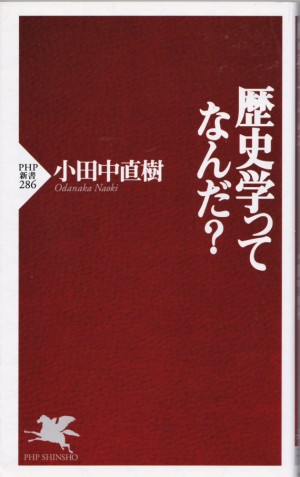


最近のコメント