21年前に出たイランの概説書を読んだ ― 2026年01月07日
来月(2026年2月)末からイラン旅行を予定している。にわか勉強のため、21年前に出版された次の本を古書で入手して読んだ。
『イランを知るための65章』(岡田恵美子、北原圭一、鈴木珠里編著/明石書房/2004年9月)
手軽に読めそうな本と思ったが意外に手強かった。50人以上のイラン研究者がそれぞれの研究対象を紹介するエッセイ集に近く、話題は多岐にわたる。文学、芸術、宗教、歴史から政治、経済、社会、地理、生活にいたるまでの広範なテーマに接し、多様なイメージが目まぐるしく脳内を去来した。頭がクラクラしてくる。読了には思いの他の時間を要した。
本書から得た知見は多い。まずは、イランという文明圏が歴史的にも地理的にも多層で複雑だと再認識した。イラン系、アラブ系、トルコ系という大雑把なくくりでは捉えきれない多様な民族は複雑だ。ゾロアスター教にイスラームのアレコレが重なった宗教的な心性も複雑だ。
本書には小学生時代をイランで過ごした日本人研究者の報告もある。イランの小学校では「書取」「作文」「算数」「幾何」の4教科に重点を置いており、筆者は「作文」だけはどうしてもイラン人にかなわなかったそうだ。イラン人は小さいときから家庭での詩のやりとりに慣れていて美文調の文章が巧みだそうだ。本書に『シャー・ナーメ(王書)』などの叙事詩がくり返し登場する理由が少しわかった気がした。
本書が出た2004年、まだ日本との直行便が就航していた(2010年まで)。大統領は改革派のハータミー(第1期は1997~2001、第2期は2001~2005)だった。先日読んだ『物語イランの歴史』(宮田律/2002.9)と同じように、本書もまたイランの改革路線が進展していくだろうと見ているように思える。だが、その後の20年の歴史はそう単純ではなく紆余曲折を重ねている。
本書には2003年のノーベル平和賞を受賞したイラン人女性弁護士シーリーン・エバーディを紹介するコラムもあり、彼女が大統領選に出馬すれば一波乱あるだろうと期待を寄せている。ネットで調べると、2009年には貸金庫に保管していたノーベル平和賞のメダルと賞状が当局に押収され、エバーディはイギリスに亡命したそうだ。
『イランを知るための65章』(岡田恵美子、北原圭一、鈴木珠里編著/明石書房/2004年9月)
手軽に読めそうな本と思ったが意外に手強かった。50人以上のイラン研究者がそれぞれの研究対象を紹介するエッセイ集に近く、話題は多岐にわたる。文学、芸術、宗教、歴史から政治、経済、社会、地理、生活にいたるまでの広範なテーマに接し、多様なイメージが目まぐるしく脳内を去来した。頭がクラクラしてくる。読了には思いの他の時間を要した。
本書から得た知見は多い。まずは、イランという文明圏が歴史的にも地理的にも多層で複雑だと再認識した。イラン系、アラブ系、トルコ系という大雑把なくくりでは捉えきれない多様な民族は複雑だ。ゾロアスター教にイスラームのアレコレが重なった宗教的な心性も複雑だ。
本書には小学生時代をイランで過ごした日本人研究者の報告もある。イランの小学校では「書取」「作文」「算数」「幾何」の4教科に重点を置いており、筆者は「作文」だけはどうしてもイラン人にかなわなかったそうだ。イラン人は小さいときから家庭での詩のやりとりに慣れていて美文調の文章が巧みだそうだ。本書に『シャー・ナーメ(王書)』などの叙事詩がくり返し登場する理由が少しわかった気がした。
本書が出た2004年、まだ日本との直行便が就航していた(2010年まで)。大統領は改革派のハータミー(第1期は1997~2001、第2期は2001~2005)だった。先日読んだ『物語イランの歴史』(宮田律/2002.9)と同じように、本書もまたイランの改革路線が進展していくだろうと見ているように思える。だが、その後の20年の歴史はそう単純ではなく紆余曲折を重ねている。
本書には2003年のノーベル平和賞を受賞したイラン人女性弁護士シーリーン・エバーディを紹介するコラムもあり、彼女が大統領選に出馬すれば一波乱あるだろうと期待を寄せている。ネットで調べると、2009年には貸金庫に保管していたノーベル平和賞のメダルと賞状が当局に押収され、エバーディはイギリスに亡命したそうだ。
挫折した巨大プロジェクトの現場の空気を感じた ― 2025年12月31日
『イラン現代史』と『物語イランの歴史』に触発されて、次の小説を古書で入手して読んだ。
『バンダルの塔』(高杉良/講談社文庫/1984.3)
IJPC(イラン・ジャパン石油化学)を題材にした小説である。1979年のイラン革命の直後、新聞の見出しでIJPCという文字を何度も見た。三井物産を中心に日本の化学メーカー(東洋曹達、三井東圧、三井石油化学、日本合成ゴム)がイランに石油化学コンビナートを建設する壮大なプロジェクトだった。イラン革命の勃発で暗雲が立ち込め、巨額の損失を出してIJPCは清算される。
この小説の単行本が出たのはイラン革命から2年後の1981年、きわものに近い小説だ。文庫版が出たのはイラン革命後のイラン・イラク戦争中、1984年だ。文庫版の解説で、佐高信は「新しい形で、日本はイランに協力することになって、現在、百名を超える日本人が現地に行き、数回に及ぶ爆撃による被害の調査を行なっている。」と希望的見解を述べている。しかし、文庫版が出た5年後の1989年、三井物産はIJPCの清算を発表する。6000億円以上をつぎ込んだプロジェクトは潰えた。
77歳の私には久々の高杉良の経済小説だった。現役時代、企業の現場を生々しく描く高杉良の企業人小説に身につまされる思いをしたこともある。この小説を読んで、昔のそんな気分が甦った。
この小説、企業名は実名だが、主人公らの登場人物は複数のモデルを合成したフィクションらしい。パーレビ体制の安定を疑う人はほとんどいなかったが、巨大プロジェクト推進のリスクを懸念する人はいた。さまざまな困難をひとつずつ乗り越えて奮闘する姿は感動的でもある。日本の高度成長末期の企業現場の元気な雰囲気が伝わってくる。
イランに赴任して一年八カ月の日本人がイラン人について「狡猾で、狡知にたけてるが、自分のことしか考えない人種です」と述懐する場面が印象に残った。一部の人間から全体を論じるのは乱暴だとは思うが、文化や考え方の違いを克服する困難を感じた。
イラン革命勃発時、コンビナートは完成目前だった。工事現場で約5千人が働いていた。日本人は3千人以上いた。だが、イラン側のトップがいち早く海外へ脱出するなど事態は急展開する。総引きあげとなった現場の無念に思いを馳せた。
P.S.
実は、私は来年2月下旬からイラン観光旅行をすることになった。『イラン現代史』や『物語イランの歴史』を読んだときは、まだ旅行検討中だった。これから、イランについて情報収集せねばと思い、その一環でこの小説を読んだ。
『バンダルの塔』(高杉良/講談社文庫/1984.3)
IJPC(イラン・ジャパン石油化学)を題材にした小説である。1979年のイラン革命の直後、新聞の見出しでIJPCという文字を何度も見た。三井物産を中心に日本の化学メーカー(東洋曹達、三井東圧、三井石油化学、日本合成ゴム)がイランに石油化学コンビナートを建設する壮大なプロジェクトだった。イラン革命の勃発で暗雲が立ち込め、巨額の損失を出してIJPCは清算される。
この小説の単行本が出たのはイラン革命から2年後の1981年、きわものに近い小説だ。文庫版が出たのはイラン革命後のイラン・イラク戦争中、1984年だ。文庫版の解説で、佐高信は「新しい形で、日本はイランに協力することになって、現在、百名を超える日本人が現地に行き、数回に及ぶ爆撃による被害の調査を行なっている。」と希望的見解を述べている。しかし、文庫版が出た5年後の1989年、三井物産はIJPCの清算を発表する。6000億円以上をつぎ込んだプロジェクトは潰えた。
77歳の私には久々の高杉良の経済小説だった。現役時代、企業の現場を生々しく描く高杉良の企業人小説に身につまされる思いをしたこともある。この小説を読んで、昔のそんな気分が甦った。
この小説、企業名は実名だが、主人公らの登場人物は複数のモデルを合成したフィクションらしい。パーレビ体制の安定を疑う人はほとんどいなかったが、巨大プロジェクト推進のリスクを懸念する人はいた。さまざまな困難をひとつずつ乗り越えて奮闘する姿は感動的でもある。日本の高度成長末期の企業現場の元気な雰囲気が伝わってくる。
イランに赴任して一年八カ月の日本人がイラン人について「狡猾で、狡知にたけてるが、自分のことしか考えない人種です」と述懐する場面が印象に残った。一部の人間から全体を論じるのは乱暴だとは思うが、文化や考え方の違いを克服する困難を感じた。
イラン革命勃発時、コンビナートは完成目前だった。工事現場で約5千人が働いていた。日本人は3千人以上いた。だが、イラン側のトップがいち早く海外へ脱出するなど事態は急展開する。総引きあげとなった現場の無念に思いを馳せた。
P.S.
実は、私は来年2月下旬からイラン観光旅行をすることになった。『イラン現代史』や『物語イランの歴史』を読んだときは、まだ旅行検討中だった。これから、イランについて情報収集せねばと思い、その一環でこの小説を読んだ。
江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』を読んだ ― 2025年12月29日
中公文庫の『カラマーゾフの兄弟』は池田健太郎訳だと思っていたが、すでに絶版になっていて、今年の夏、江川卓(1927-2001)訳で『カラマーゾフの兄弟』が刊行された。すぐに入手した。江川卓訳にこだわった経緯は、先日再々読した『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』(江川卓)の読後感に書いた。年末になり、その文庫本をやっと読了した。
『カラマーゾフの兄弟(1)(2)(3)(4)』(ドストエフスキー/江川卓訳/中公文庫)
それなりの読書時間が確保できると目論んで読み始めたが、読了に9日を要した。この長編を読むのは4回目で、訳者はすべて違う。20歳頃に初めて読んだのは米川正夫訳、13年前に読んだのは亀山郁夫訳、昨年の夏に読んだのは原卓也訳だった。
やはり『カラマーゾフの兄弟』を読むと疲れる。登場人物たちの異常に過剰な迫力と熱量に圧倒され、ぐったりする。
この長編は、殺人事件→裁判という展開の犯罪小説・心理小説的なストーリーをベースに、劇中劇のような宗教的・哲学的な議論や物語がふんだんに上乗せされている。この多重構造は有機的に絡み合っているので、現実世界を超えた異次元世界を旅している気分になる。
江川卓訳の中公文庫版は1979年の集英社版世界文学全集が底本で、訳者によるかなり詳しい注解と後記がついている。『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』が出たのは訳書より10年程後の1991年だが、この注解と後記は『謎とき』に重なっている。注解を参照しつつ小説を読むと『謎とき』の復習になる。小説に登場する事項のシンボル性や聖書との関連に「へぇー」と思いながら読み進めた。
この小説には「私」という語り手がいる。私は昨年の再々読時に、語り手は13年後のアリョーシャではないかと思って読んだ。今回、この「私」を気にしながら読み、アリョーシャを語り手と見なすには無理があると思った。
『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』のなかに「ここで作者自身(語り手でない)が突然顔を出し(…)」という部分があり、江川卓は作者と語り手が別だと述べているのだと思った。だが、それは私の早とちりだったようだ。この小説は全編「私」という語り手が記述した物語であり、「私」は作者ドストエフスキイの分身だと思う。
「私」は神様の視点で登場人物たちの行動や心理を語るのではない。「私」は自分の感想や印象を述べるし、詠嘆したり興奮したりする。まるで登場人物である。作者自身が物語世界に引きずり込まれている不思議な「語り」に思える。江川卓の指摘は、作者の分身である語り手が、ときに分身であることを忘れて作者自身になっていると述べているのだと思う。
4回目の『カラマーゾフの兄弟』であらためて感じたのはアリョーシャという人物の不可解性である。妙な自己確信と予言力があり、神を信じていないフシもある。イノセントな教祖風でもあり、自らを好色で衝動的なカラマーゾフの一人と認識している。「第7編 4 ガリラヤのカナ」終盤の次の記述が印象的だ。
「彼が大地に身を投げたときは、まだ弱々しい少年にすぎなかったが、ふたたび立ちあがったとき、彼はすでに生涯を通じて、変わらぬ不屈の闘士となっていた。」
この不可解なアリョシャ像は、幻の第二部から照射しなければ明確なイメージを結ばない。その第二部はエピローグの「カラマーゾフ万歳」で予告されている。アリョーシャに心酔している少年コーリャは「ああ、ぼくもいつか正義のために自分を犠牲にできたらなあ」と述べる。13年後のテロリストを予感させる台詞だ。皇帝暗殺の黒幕はアリョーシャ、実行犯はコーリャ――そんスリリングな将来がぼんやり浮かぶ。
『カラマーゾフの兄弟(1)(2)(3)(4)』(ドストエフスキー/江川卓訳/中公文庫)
それなりの読書時間が確保できると目論んで読み始めたが、読了に9日を要した。この長編を読むのは4回目で、訳者はすべて違う。20歳頃に初めて読んだのは米川正夫訳、13年前に読んだのは亀山郁夫訳、昨年の夏に読んだのは原卓也訳だった。
やはり『カラマーゾフの兄弟』を読むと疲れる。登場人物たちの異常に過剰な迫力と熱量に圧倒され、ぐったりする。
この長編は、殺人事件→裁判という展開の犯罪小説・心理小説的なストーリーをベースに、劇中劇のような宗教的・哲学的な議論や物語がふんだんに上乗せされている。この多重構造は有機的に絡み合っているので、現実世界を超えた異次元世界を旅している気分になる。
江川卓訳の中公文庫版は1979年の集英社版世界文学全集が底本で、訳者によるかなり詳しい注解と後記がついている。『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』が出たのは訳書より10年程後の1991年だが、この注解と後記は『謎とき』に重なっている。注解を参照しつつ小説を読むと『謎とき』の復習になる。小説に登場する事項のシンボル性や聖書との関連に「へぇー」と思いながら読み進めた。
この小説には「私」という語り手がいる。私は昨年の再々読時に、語り手は13年後のアリョーシャではないかと思って読んだ。今回、この「私」を気にしながら読み、アリョーシャを語り手と見なすには無理があると思った。
『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』のなかに「ここで作者自身(語り手でない)が突然顔を出し(…)」という部分があり、江川卓は作者と語り手が別だと述べているのだと思った。だが、それは私の早とちりだったようだ。この小説は全編「私」という語り手が記述した物語であり、「私」は作者ドストエフスキイの分身だと思う。
「私」は神様の視点で登場人物たちの行動や心理を語るのではない。「私」は自分の感想や印象を述べるし、詠嘆したり興奮したりする。まるで登場人物である。作者自身が物語世界に引きずり込まれている不思議な「語り」に思える。江川卓の指摘は、作者の分身である語り手が、ときに分身であることを忘れて作者自身になっていると述べているのだと思う。
4回目の『カラマーゾフの兄弟』であらためて感じたのはアリョーシャという人物の不可解性である。妙な自己確信と予言力があり、神を信じていないフシもある。イノセントな教祖風でもあり、自らを好色で衝動的なカラマーゾフの一人と認識している。「第7編 4 ガリラヤのカナ」終盤の次の記述が印象的だ。
「彼が大地に身を投げたときは、まだ弱々しい少年にすぎなかったが、ふたたび立ちあがったとき、彼はすでに生涯を通じて、変わらぬ不屈の闘士となっていた。」
この不可解なアリョシャ像は、幻の第二部から照射しなければ明確なイメージを結ばない。その第二部はエピローグの「カラマーゾフ万歳」で予告されている。アリョーシャに心酔している少年コーリャは「ああ、ぼくもいつか正義のために自分を犠牲にできたらなあ」と述べる。13年後のテロリストを予感させる台詞だ。皇帝暗殺の黒幕はアリョーシャ、実行犯はコーリャ――そんスリリングな将来がぼんやり浮かぶ。
19世紀のロシアの牡蠣 ― 2025年12月27日
昨日(2025.12.26)の日経新聞の春秋がチェーホフの「牡蠣」という小説に触れていた。短篇だと思うが、私はこの小説を読んでいない。いつか読んでみたいと思った。
このコラムによると、19世紀のロシアで牡蠣は西欧から輸入する高級珍味だったそうだ。ナルホドと思った。
現在、私は江川卓訳の『カラマーゾフの兄弟』を読書中である。この長編を読むのは4回目だ。「第8編 ミーチャ」の「5 突然の決心」に牡蠣が登場する。長男ドミートリイが散財を決意し、モークロエへの出発準備中の場面である。
「旦那さま方、牡蠣はいかがでございます、入荷しましたばかりの最上等の牡蠣でございますが」と店の者がすすめた。
この場面を読んだ直後に日経のコラムを読み、19世紀ロシアの牡蠣の事情を知った。コラムが私の読書の後押しをしてくれている気分になった。
このコラムによると、19世紀のロシアで牡蠣は西欧から輸入する高級珍味だったそうだ。ナルホドと思った。
現在、私は江川卓訳の『カラマーゾフの兄弟』を読書中である。この長編を読むのは4回目だ。「第8編 ミーチャ」の「5 突然の決心」に牡蠣が登場する。長男ドミートリイが散財を決意し、モークロエへの出発準備中の場面である。
「旦那さま方、牡蠣はいかがでございます、入荷しましたばかりの最上等の牡蠣でございますが」と店の者がすすめた。
この場面を読んだ直後に日経のコラムを読み、19世紀ロシアの牡蠣の事情を知った。コラムが私の読書の後押しをしてくれている気分になった。
アリョーシャは「現代のキリスト」という見立て ― 2025年12月25日
江川卓の『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』を再々読した。
『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』(江川卓/新潮選書/1991.6)
最初に読んだのは、30年以上昔の刊行時だと思う。2回目に読んだのは13年前、亀山郁夫の新訳で『カラマーゾフの兄弟』を再読したときだ(最初は、学生時代に米川正夫訳で読んだ)。江川卓の論考でぼんやり記憶に残っている事項もあるが大半は失念している。
だが、はっきり憶えている点がある。13年前に本書を読了したとき、今度は『カラマーゾフの兄弟』を江川卓訳で読もうと思ったのだ。
江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』は集英社の世界文学全集に収録されている。ネット古書店で容易に入手できるだろうと思った。だが、それが困難だった。ほとんど出品されていない。数少ない古書は異常に高価だ。なぜ江川卓訳の文庫版がないのか不思議だった。
昨年の夏、『カラマーゾフの兄弟』をベースにした野田秀樹の『正三角関係』を観劇する際は、新潮文庫の原卓也訳でこの長編を再々読した。
そして今年の夏、待望の江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』が中公文庫(全4巻)で刊行された。刊行と同時に入手したが、すぐに読んだわけではない。『カラマーゾフの兄弟』はくり返し読みたくなる小説だが、読み始めるには多少の心の準備と覚悟が必要だ。
年末が迫り、この夏に入手した江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』を年内に読もうと覚悟した。年を越すといつ挑戦できるかわからない。
この長編を読む前に『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』を再々読するのが筋だと考え、本書を読んだのである。
本書の読者の大半はすでに『カラマーゾフの兄弟』を読んでいるだろうが、本書を読み終えると、あらためて江川卓訳で『カラマーゾフの兄弟』を読み返したいと思うはずだ。著者の指摘を小説の本文で確認したくなるのだ。
本書は、アリョーシャを「現代のキリスト」としている。それは「黒いキリスト」である。それに対してスメルジャコフは「白いキリスト」だが、それは「白いキリスト」の僭称者であり、実は「臆病なユダ」だという見立てである。
本書が解き明かすカラマーゾフの世界は13年後の「幻の第二部」に照射されている。第一部終盤の「カラマーゾフ万歳!」という12人の少年たちの叫びは唐突だが、これは13年後の第二部に呼応している。13年後、キリストの没年と同じ33歳になったアリョーシャは皇帝暗殺事件の黒幕「黒いキリスト」として処刑される。暗殺の実行犯は元少年の12使徒のなかの一人である。
『カラマーゾフの兄弟』は現存の「第一部」だけで十分に傑作だろうが、「幻の第二部」を視野に入れて読み解く方がはるかに面白い。
江川卓はこの小説の「語り手」と「作者」は別だとしているようだが、その点については詳しく論じていない。次に『カラマーゾフの兄弟』を読むときは、その点も気にしながら読み進めたい。
『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』(江川卓/新潮選書/1991.6)
最初に読んだのは、30年以上昔の刊行時だと思う。2回目に読んだのは13年前、亀山郁夫の新訳で『カラマーゾフの兄弟』を再読したときだ(最初は、学生時代に米川正夫訳で読んだ)。江川卓の論考でぼんやり記憶に残っている事項もあるが大半は失念している。
だが、はっきり憶えている点がある。13年前に本書を読了したとき、今度は『カラマーゾフの兄弟』を江川卓訳で読もうと思ったのだ。
江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』は集英社の世界文学全集に収録されている。ネット古書店で容易に入手できるだろうと思った。だが、それが困難だった。ほとんど出品されていない。数少ない古書は異常に高価だ。なぜ江川卓訳の文庫版がないのか不思議だった。
昨年の夏、『カラマーゾフの兄弟』をベースにした野田秀樹の『正三角関係』を観劇する際は、新潮文庫の原卓也訳でこの長編を再々読した。
そして今年の夏、待望の江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』が中公文庫(全4巻)で刊行された。刊行と同時に入手したが、すぐに読んだわけではない。『カラマーゾフの兄弟』はくり返し読みたくなる小説だが、読み始めるには多少の心の準備と覚悟が必要だ。
年末が迫り、この夏に入手した江川卓訳『カラマーゾフの兄弟』を年内に読もうと覚悟した。年を越すといつ挑戦できるかわからない。
この長編を読む前に『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』を再々読するのが筋だと考え、本書を読んだのである。
本書の読者の大半はすでに『カラマーゾフの兄弟』を読んでいるだろうが、本書を読み終えると、あらためて江川卓訳で『カラマーゾフの兄弟』を読み返したいと思うはずだ。著者の指摘を小説の本文で確認したくなるのだ。
本書は、アリョーシャを「現代のキリスト」としている。それは「黒いキリスト」である。それに対してスメルジャコフは「白いキリスト」だが、それは「白いキリスト」の僭称者であり、実は「臆病なユダ」だという見立てである。
本書が解き明かすカラマーゾフの世界は13年後の「幻の第二部」に照射されている。第一部終盤の「カラマーゾフ万歳!」という12人の少年たちの叫びは唐突だが、これは13年後の第二部に呼応している。13年後、キリストの没年と同じ33歳になったアリョーシャは皇帝暗殺事件の黒幕「黒いキリスト」として処刑される。暗殺の実行犯は元少年の12使徒のなかの一人である。
『カラマーゾフの兄弟』は現存の「第一部」だけで十分に傑作だろうが、「幻の第二部」を視野に入れて読み解く方がはるかに面白い。
江川卓はこの小説の「語り手」と「作者」は別だとしているようだが、その点については詳しく論じていない。次に『カラマーゾフの兄弟』を読むときは、その点も気にしながら読み進めたい。
眉村卓の老境作品に老人力を感じた ― 2025年12月07日
眉村卓の生前最後の短篇集とエッセイ集を読んだ。『筒井康隆自伝』を契機に日本SF第1世代へ思いを馳せ、読みたくなったのだ。
『夕焼けのかなた』(眉村卓/双葉文庫/2017.12)
『歳月パラパラ』(眉村卓/出版芸術社/2014.7)
眉村卓は2019年11月3日、84歳で逝った。その日私は彼の長編『カルタゴの運命』を読了した。フシギな暗合に慄然とした。逝去後に遺作長編『その果てを知らず』が出版されたが、生前に出た最後の本が上記2冊だと思う。前者が短篇集、後者はエッセイ集だが、両者の印象は混ざり合う。
晩年の眉村卓の小説はエッセイのようであり、小説はエッセイのようだ。自分の脳内に浮かぶ世界のアレコレをのびのびと描く老人力を感じる。コレデイイノダという気ままな脱力という形の力量である。
この二冊には懐旧の空気が色濃く流れている。旧友や駅が多く登場する。それは現実の旧友や駅ではなく、ひとときの異世界に誘う扉である。幻の旧友と幻の駅は老境の景色にマッチする。
短篇小説では「峠」、エッセイでは「『燃える傾斜』を書いた頃」が印象に残った。
「峠」は、80歳の老作家が会社員時代に短期間過ごした町を訪ねる追憶譚である。追憶に、あり得たかもしれない別の自分が重なる。齢を重ねた誰もが抱く心境である。
「『燃える傾斜』を書いた頃」を読んでいると、私が『燃える傾斜』を読んだ60年ほど前(高校時代だ)の記憶がよみがえり、追憶を共有しているような気分になった。『燃える傾斜』は、眉村卓が会社員時代に発表したデビュー作である。このエッセイでは、SFマガジン編集長の福島正実がこの作品について「彼はまだまだ、うんとまだまだですよ」と語った、と述べている。
福島正実のコメントは私も憶えている。エッセイには「PR雑誌か何か」とあるが、正確には「別冊宝石」(1964年3月)の座談会での発言である。石川喬司が「眉村卓が去年『燃える傾斜』という力作を出しました。」と述べ、それに応えた福島正実は「眉村氏の場合は、つまり作品の完成度としてまだまだ、たいへんにまだまだだと思うのです。(…)あの作品はまだまだSFマニアのものであっても、SFというジャーナリズムに受けいれられたジャンルの小説ではない、と。そういう感じが僕はするわけなんですがね。」と発言している。
私が『燃える傾斜』を読んだのは「別冊宝石」を読んだ後だった。福島発言を追認する気分で読んだように思う。しかし、記憶に残る作品になった。
『夕焼けのかなた』(眉村卓/双葉文庫/2017.12)
『歳月パラパラ』(眉村卓/出版芸術社/2014.7)
眉村卓は2019年11月3日、84歳で逝った。その日私は彼の長編『カルタゴの運命』を読了した。フシギな暗合に慄然とした。逝去後に遺作長編『その果てを知らず』が出版されたが、生前に出た最後の本が上記2冊だと思う。前者が短篇集、後者はエッセイ集だが、両者の印象は混ざり合う。
晩年の眉村卓の小説はエッセイのようであり、小説はエッセイのようだ。自分の脳内に浮かぶ世界のアレコレをのびのびと描く老人力を感じる。コレデイイノダという気ままな脱力という形の力量である。
この二冊には懐旧の空気が色濃く流れている。旧友や駅が多く登場する。それは現実の旧友や駅ではなく、ひとときの異世界に誘う扉である。幻の旧友と幻の駅は老境の景色にマッチする。
短篇小説では「峠」、エッセイでは「『燃える傾斜』を書いた頃」が印象に残った。
「峠」は、80歳の老作家が会社員時代に短期間過ごした町を訪ねる追憶譚である。追憶に、あり得たかもしれない別の自分が重なる。齢を重ねた誰もが抱く心境である。
「『燃える傾斜』を書いた頃」を読んでいると、私が『燃える傾斜』を読んだ60年ほど前(高校時代だ)の記憶がよみがえり、追憶を共有しているような気分になった。『燃える傾斜』は、眉村卓が会社員時代に発表したデビュー作である。このエッセイでは、SFマガジン編集長の福島正実がこの作品について「彼はまだまだ、うんとまだまだですよ」と語った、と述べている。
福島正実のコメントは私も憶えている。エッセイには「PR雑誌か何か」とあるが、正確には「別冊宝石」(1964年3月)の座談会での発言である。石川喬司が「眉村卓が去年『燃える傾斜』という力作を出しました。」と述べ、それに応えた福島正実は「眉村氏の場合は、つまり作品の完成度としてまだまだ、たいへんにまだまだだと思うのです。(…)あの作品はまだまだSFマニアのものであっても、SFというジャーナリズムに受けいれられたジャンルの小説ではない、と。そういう感じが僕はするわけなんですがね。」と発言している。
私が『燃える傾斜』を読んだのは「別冊宝石」を読んだ後だった。福島発言を追認する気分で読んだように思う。しかし、記憶に残る作品になった。
観る前に読んだ『火星の女王』は物足りなかった ― 2025年11月28日
小川哲の新作SFを読んだ。
『火星の女王』(小川哲/早川書房/2025.10)
5年前この作家の『ゲームの王国』に圧倒されて以来、『ユートロニカのこちら側』、『地図と拳』、『君のクイズ』、『君が手にするはずだった黄金について』をどれも面白く読んだ。だが、書店の店頭に積まれている『火星の女王』を手にしたとき、露骨なSFタイトルに少し躊躇した。タイトルから連想するようなスペース・オペラではなく、近未来の火星と地球を舞台にしたリアルな物語のようだ。いずれ読むにしても後回しでいいやと思って平積み棚に戻した。
後日、この小説がNHKのTVドラマで年末に放映されると知った。ドラマを観てから読むより読んでから観る方がいいので、あわてて入手して読んだ。小説を映像化した作品の面白さが小説を超えることはあまりない。特にSF場合、ドラマや映画の映像を小説の「挿絵」のひとつとして楽しむのがいいと私は感じている。だから、映像を観る前に小説を読んでおくのがいい。「SFは絵だねぇ」という言葉もある。
『火星の女王』は面白いSFだったが、物足りなさを感じた。いままでどこかで読んだSFの寄せ集めのようにも思え、やや期待外れだった。
この小説を読み進めながら私が連想した小説は『さよならジュピター』(小松左京)、『あとは野となれ大和撫子』(宮内悠介)、『三体』(劉慈欣)、『ユートロニカのこちら側』(小川哲)などだ。と言っても、もちろん独自性はあり、100年後の世界の日常がリアルに感じられる。火星と地球との間の通信において発生する5分以上のタイムラグの描き方は巧みだ。このタイムラグは小説全体のテーマに関わっている。
この小説には、火星のコロニーを運営する会社のCEOであるルーク・マディソンという人物が登場する。地球でも指折りの大富豪だったが、ある日突然火星に移住してきた変わり者である。イーロン・マスクを連想させるようにも見えるが、よくわからない人物だ。私は最後までルークの人物像をイメージできなかった。それが不満である。私の読解力の問題もある。だが、ルーク・マディソンという奇妙な人物をより深く造型すれば、この小説はもっと面白くなったと思う。
『火星の女王』(小川哲/早川書房/2025.10)
5年前この作家の『ゲームの王国』に圧倒されて以来、『ユートロニカのこちら側』、『地図と拳』、『君のクイズ』、『君が手にするはずだった黄金について』をどれも面白く読んだ。だが、書店の店頭に積まれている『火星の女王』を手にしたとき、露骨なSFタイトルに少し躊躇した。タイトルから連想するようなスペース・オペラではなく、近未来の火星と地球を舞台にしたリアルな物語のようだ。いずれ読むにしても後回しでいいやと思って平積み棚に戻した。
後日、この小説がNHKのTVドラマで年末に放映されると知った。ドラマを観てから読むより読んでから観る方がいいので、あわてて入手して読んだ。小説を映像化した作品の面白さが小説を超えることはあまりない。特にSF場合、ドラマや映画の映像を小説の「挿絵」のひとつとして楽しむのがいいと私は感じている。だから、映像を観る前に小説を読んでおくのがいい。「SFは絵だねぇ」という言葉もある。
『火星の女王』は面白いSFだったが、物足りなさを感じた。いままでどこかで読んだSFの寄せ集めのようにも思え、やや期待外れだった。
この小説を読み進めながら私が連想した小説は『さよならジュピター』(小松左京)、『あとは野となれ大和撫子』(宮内悠介)、『三体』(劉慈欣)、『ユートロニカのこちら側』(小川哲)などだ。と言っても、もちろん独自性はあり、100年後の世界の日常がリアルに感じられる。火星と地球との間の通信において発生する5分以上のタイムラグの描き方は巧みだ。このタイムラグは小説全体のテーマに関わっている。
この小説には、火星のコロニーを運営する会社のCEOであるルーク・マディソンという人物が登場する。地球でも指折りの大富豪だったが、ある日突然火星に移住してきた変わり者である。イーロン・マスクを連想させるようにも見えるが、よくわからない人物だ。私は最後までルークの人物像をイメージできなかった。それが不満である。私の読解力の問題もある。だが、ルーク・マディソンという奇妙な人物をより深く造型すれば、この小説はもっと面白くなったと思う。
45年前のユーモア小説アンソロジーが心地よい ― 2025年11月22日
『筒井康隆自伝』がきっかけで『盗まれた街』を読んだのに続いて、次のアンソロジーを読んだ。
『12のアップルパイ:ユーモア小説フェスティバル』(筒井康隆・編/立風書房/1980.8)
かなり以前に古書で入手し、そのままになっていた本だ。『筒井康隆自伝』は本書について次のように述べている。
「『12のアップルパイ』というのは、その前に出した『異形の白昼』という恐怖小説のアンソロジーが好評だったので、次こそはわが本来の笑いのアンソロジーでと意気込んで出したものだったが、さほど評判にならなかった。やはり日本文学はユーモアやギャグと相容れないらしい。」
12人の現役(刊行当時)作家のアンソロジーである。作者と作品名は以下の通りだ。
遠藤周作「初春夢の宝船」
星新一「はだかの部屋」
田辺聖子「びっくりハウス」
五木寛之「美しきスオミの夏に」
北杜夫「友情」
吉行淳之介「悩ましき土地」
新田次郎「新婚山行」
生島治郎「最後の客」
豊田有恒「地震がいっぱい」
野坂昭如「ああ水中大回天」
筒井康隆「トラブル」
小松左京「本邦東西朝縁起覚書」
76歳の私にとっては懐かしき面子だ。SF作家4人(星、豊田、筒井、小松)の作品は記憶にある。他の8人も私が若い頃の同時代作家なので、その作品のいくつかは読んでいるが、本書収録作は初読だと思う。
12作品を続けて読み、それぞれの作家の多様な個性を感じた。私が一番面白いと思ったのは筒井康隆「トラブル」であり、二番目は小松左京「本邦東西朝縁起覚書」だ。どちらも雑誌(SFマガジン)で読んだときの強烈な印象が残っている。前者は、昼下がりの日比谷公園で突如勃発したサラリーマン族とTV業界族の人体パイ投げバトルを描いたシュールで突き抜けた作品だ。後者は、南朝が時空を超えて現代に蘇り、ついには東西朝時代に移行するという話で、果敢な天皇制ジョークに唖然とする。
その他で面白いのが五木寛之「美しきスオミの夏に」だ。あの頃の五木寛之的なカッコよさを維持しつつ、何ともおかしな展開になる。作家とは本来的に諧謔の人種だと思う。
このアンソロジーの異色は新田次郎「新婚山行」だろう。新田次郎の山岳小説の一つであり、彼はユーモア作家ではない。そんな作家の作品にユーモアを見出す筒井氏の鑑識眼に感心した。
このアンソロジーに往時のオールスター戦を観るような懐かしさと心地よさを感じるのは、私が年を取ったせいだろうと思う。
『12のアップルパイ:ユーモア小説フェスティバル』(筒井康隆・編/立風書房/1980.8)
かなり以前に古書で入手し、そのままになっていた本だ。『筒井康隆自伝』は本書について次のように述べている。
「『12のアップルパイ』というのは、その前に出した『異形の白昼』という恐怖小説のアンソロジーが好評だったので、次こそはわが本来の笑いのアンソロジーでと意気込んで出したものだったが、さほど評判にならなかった。やはり日本文学はユーモアやギャグと相容れないらしい。」
12人の現役(刊行当時)作家のアンソロジーである。作者と作品名は以下の通りだ。
遠藤周作「初春夢の宝船」
星新一「はだかの部屋」
田辺聖子「びっくりハウス」
五木寛之「美しきスオミの夏に」
北杜夫「友情」
吉行淳之介「悩ましき土地」
新田次郎「新婚山行」
生島治郎「最後の客」
豊田有恒「地震がいっぱい」
野坂昭如「ああ水中大回天」
筒井康隆「トラブル」
小松左京「本邦東西朝縁起覚書」
76歳の私にとっては懐かしき面子だ。SF作家4人(星、豊田、筒井、小松)の作品は記憶にある。他の8人も私が若い頃の同時代作家なので、その作品のいくつかは読んでいるが、本書収録作は初読だと思う。
12作品を続けて読み、それぞれの作家の多様な個性を感じた。私が一番面白いと思ったのは筒井康隆「トラブル」であり、二番目は小松左京「本邦東西朝縁起覚書」だ。どちらも雑誌(SFマガジン)で読んだときの強烈な印象が残っている。前者は、昼下がりの日比谷公園で突如勃発したサラリーマン族とTV業界族の人体パイ投げバトルを描いたシュールで突き抜けた作品だ。後者は、南朝が時空を超えて現代に蘇り、ついには東西朝時代に移行するという話で、果敢な天皇制ジョークに唖然とする。
その他で面白いのが五木寛之「美しきスオミの夏に」だ。あの頃の五木寛之的なカッコよさを維持しつつ、何ともおかしな展開になる。作家とは本来的に諧謔の人種だと思う。
このアンソロジーの異色は新田次郎「新婚山行」だろう。新田次郎の山岳小説の一つであり、彼はユーモア作家ではない。そんな作家の作品にユーモアを見出す筒井氏の鑑識眼に感心した。
このアンソロジーに往時のオールスター戦を観るような懐かしさと心地よさを感じるのは、私が年を取ったせいだろうと思う。

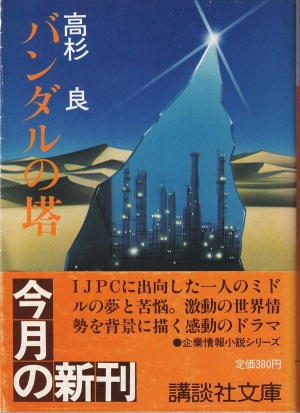


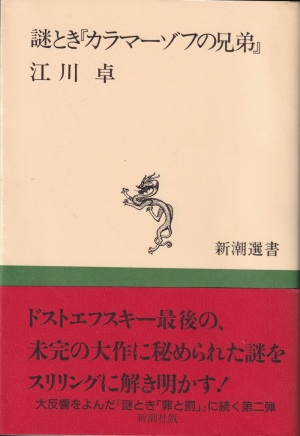



最近のコメント