戦争をリアリズムで考える「地政学」は苦い ― 2026年01月18日
地政学には前世紀の遺物のウロンな「学問」というイメージがある。だが、書店に地政学コーナーができていて、いくつかの本が並んでいた。そのなかの次の1冊に興味がわいた。
『日本人のための地政学原論』(橋爪大三郎/ビジネス社/2026.1)
私と同世代(団塊世代)の社会学者・橋爪大三郎の著書は『はじめての構造主義』、『世界は四大文明でできている』など何冊か読んでいる。本書と関連するのは『戦争の社会学』だろう。印象に残っているのは、橋爪氏が編者の『小室直樹の世界』収録の対談での橋爪氏の次の発言だ。
「どうも私は、自分のノーマルな部分に退屈しているので、ちょっと危ない知性にひかれる傾向があるみたいです。」
そんな橋爪氏が、ちょっと危ない感じががする「地政学」を概説したのが本書である。巻末の「おわりに」では次のようの述べている。
「最近ビジネスかいわいで「地政学」が話題だという。何冊か見たがピンと来ない。それなら自分で教科書を書こう。そう決めて、2025年9月に原稿を書き始めた。(…)勤務先の大学院大学至善館では野田智義学長はじめ、いろいろな皆さんからいつもビジネス現場の熱気を伝えていただいている。この環境がなかったら、本書は書けなかったろう。」
橋爪氏は東工大教授を退任した後、大学院大学至善館の教授になっている。この学校については、知り合いの若いビジネスマンから面白いビジネススクールだと聞いたことがある。彼は勤務先の企業から派遣されて、業務のかたわらこの大学院大学に通っていた。単なる米国風のMBA養成ではなく、アジアの文化、哲学、思想などリベラルアーツにもウエイト置いているそうだ。竹田青嗣、西研、平田オリザなども教授に名を連ねている。
本書は、そんなビジネススクールの教材の一つかもしれない。学者の著作というよりは教育者の著作である。
地政学とは「戦争が起こったらどうなるか」をリアリズムで考えることであり、地理学、軍事学、国際関係論などを土台にしている。ちゃんとした学問とは言えないが、土台となる諸学を踏まえなければ、地政学を理解することも、使いこなすこともできない。戦争の気配が近づくと地政学がブームになる。
戦争はイヤだが、無視すれば済むものではない。地政学も無視すればいいというものではない。本書を読んで、国家とは戦争をするものだという苦いリアリズムの認識を得た。
地政学を習得したからと言って、世界への対処方法の正解が得られるとは限らない。本書にも「……悩ましい問題である」「……今後に注目したい」「……読み切れない」などの述懐がある。
と言っても、さまざまな知見をベースに合理的な正解を追究する営為は必要だ。19世紀以降のさまざまな戦争を検討している本書は、地政学を十分に理解していなかった故に過去の指導者たちが犯した判断ミスをいろいろ指摘している。
太平洋戦争の開戦において、日本には政略も軍略もなく、最後通牒と言われたハルノートを読解できず、戦争に突入してしまったとの指摘にナルホドと思った。中国のナショナリズムは日本が育んだとの見解も、社会学的で面白い。
『日本人のための地政学原論』(橋爪大三郎/ビジネス社/2026.1)
私と同世代(団塊世代)の社会学者・橋爪大三郎の著書は『はじめての構造主義』、『世界は四大文明でできている』など何冊か読んでいる。本書と関連するのは『戦争の社会学』だろう。印象に残っているのは、橋爪氏が編者の『小室直樹の世界』収録の対談での橋爪氏の次の発言だ。
「どうも私は、自分のノーマルな部分に退屈しているので、ちょっと危ない知性にひかれる傾向があるみたいです。」
そんな橋爪氏が、ちょっと危ない感じががする「地政学」を概説したのが本書である。巻末の「おわりに」では次のようの述べている。
「最近ビジネスかいわいで「地政学」が話題だという。何冊か見たがピンと来ない。それなら自分で教科書を書こう。そう決めて、2025年9月に原稿を書き始めた。(…)勤務先の大学院大学至善館では野田智義学長はじめ、いろいろな皆さんからいつもビジネス現場の熱気を伝えていただいている。この環境がなかったら、本書は書けなかったろう。」
橋爪氏は東工大教授を退任した後、大学院大学至善館の教授になっている。この学校については、知り合いの若いビジネスマンから面白いビジネススクールだと聞いたことがある。彼は勤務先の企業から派遣されて、業務のかたわらこの大学院大学に通っていた。単なる米国風のMBA養成ではなく、アジアの文化、哲学、思想などリベラルアーツにもウエイト置いているそうだ。竹田青嗣、西研、平田オリザなども教授に名を連ねている。
本書は、そんなビジネススクールの教材の一つかもしれない。学者の著作というよりは教育者の著作である。
地政学とは「戦争が起こったらどうなるか」をリアリズムで考えることであり、地理学、軍事学、国際関係論などを土台にしている。ちゃんとした学問とは言えないが、土台となる諸学を踏まえなければ、地政学を理解することも、使いこなすこともできない。戦争の気配が近づくと地政学がブームになる。
戦争はイヤだが、無視すれば済むものではない。地政学も無視すればいいというものではない。本書を読んで、国家とは戦争をするものだという苦いリアリズムの認識を得た。
地政学を習得したからと言って、世界への対処方法の正解が得られるとは限らない。本書にも「……悩ましい問題である」「……今後に注目したい」「……読み切れない」などの述懐がある。
と言っても、さまざまな知見をベースに合理的な正解を追究する営為は必要だ。19世紀以降のさまざまな戦争を検討している本書は、地政学を十分に理解していなかった故に過去の指導者たちが犯した判断ミスをいろいろ指摘している。
太平洋戦争の開戦において、日本には政略も軍略もなく、最後通牒と言われたハルノートを読解できず、戦争に突入してしまったとの指摘にナルホドと思った。中国のナショナリズムは日本が育んだとの見解も、社会学的で面白い。
21年前に出たイランの概説書を読んだ ― 2026年01月07日
来月(2026年2月)末からイラン旅行を予定している。にわか勉強のため、21年前に出版された次の本を古書で入手して読んだ。
『イランを知るための65章』(岡田恵美子、北原圭一、鈴木珠里編著/明石書房/2004年9月)
手軽に読めそうな本と思ったが意外に手強かった。50人以上のイラン研究者がそれぞれの研究対象を紹介するエッセイ集に近く、話題は多岐にわたる。文学、芸術、宗教、歴史から政治、経済、社会、地理、生活にいたるまでの広範なテーマに接し、多様なイメージが目まぐるしく脳内を去来した。頭がクラクラしてくる。読了には思いの他の時間を要した。
本書から得た知見は多い。まずは、イランという文明圏が歴史的にも地理的にも多層で複雑だと再認識した。イラン系、アラブ系、トルコ系という大雑把なくくりでは捉えきれない多様な民族は複雑だ。ゾロアスター教にイスラームのアレコレが重なった宗教的な心性も複雑だ。
本書には小学生時代をイランで過ごした日本人研究者の報告もある。イランの小学校では「書取」「作文」「算数」「幾何」の4教科に重点を置いており、筆者は「作文」だけはどうしてもイラン人にかなわなかったそうだ。イラン人は小さいときから家庭での詩のやりとりに慣れていて美文調の文章が巧みだそうだ。本書に『シャー・ナーメ(王書)』などの叙事詩がくり返し登場する理由が少しわかった気がした。
本書が出た2004年、まだ日本との直行便が就航していた(2010年まで)。大統領は改革派のハータミー(第1期は1997~2001、第2期は2001~2005)だった。先日読んだ『物語イランの歴史』(宮田律/2002.9)と同じように、本書もまたイランの改革路線が進展していくだろうと見ているように思える。だが、その後の20年の歴史はそう単純ではなく紆余曲折を重ねている。
本書には2003年のノーベル平和賞を受賞したイラン人女性弁護士シーリーン・エバーディを紹介するコラムもあり、彼女が大統領選に出馬すれば一波乱あるだろうと期待を寄せている。ネットで調べると、2009年には貸金庫に保管していたノーベル平和賞のメダルと賞状が当局に押収され、エバーディはイギリスに亡命したそうだ。
『イランを知るための65章』(岡田恵美子、北原圭一、鈴木珠里編著/明石書房/2004年9月)
手軽に読めそうな本と思ったが意外に手強かった。50人以上のイラン研究者がそれぞれの研究対象を紹介するエッセイ集に近く、話題は多岐にわたる。文学、芸術、宗教、歴史から政治、経済、社会、地理、生活にいたるまでの広範なテーマに接し、多様なイメージが目まぐるしく脳内を去来した。頭がクラクラしてくる。読了には思いの他の時間を要した。
本書から得た知見は多い。まずは、イランという文明圏が歴史的にも地理的にも多層で複雑だと再認識した。イラン系、アラブ系、トルコ系という大雑把なくくりでは捉えきれない多様な民族は複雑だ。ゾロアスター教にイスラームのアレコレが重なった宗教的な心性も複雑だ。
本書には小学生時代をイランで過ごした日本人研究者の報告もある。イランの小学校では「書取」「作文」「算数」「幾何」の4教科に重点を置いており、筆者は「作文」だけはどうしてもイラン人にかなわなかったそうだ。イラン人は小さいときから家庭での詩のやりとりに慣れていて美文調の文章が巧みだそうだ。本書に『シャー・ナーメ(王書)』などの叙事詩がくり返し登場する理由が少しわかった気がした。
本書が出た2004年、まだ日本との直行便が就航していた(2010年まで)。大統領は改革派のハータミー(第1期は1997~2001、第2期は2001~2005)だった。先日読んだ『物語イランの歴史』(宮田律/2002.9)と同じように、本書もまたイランの改革路線が進展していくだろうと見ているように思える。だが、その後の20年の歴史はそう単純ではなく紆余曲折を重ねている。
本書には2003年のノーベル平和賞を受賞したイラン人女性弁護士シーリーン・エバーディを紹介するコラムもあり、彼女が大統領選に出馬すれば一波乱あるだろうと期待を寄せている。ネットで調べると、2009年には貸金庫に保管していたノーベル平和賞のメダルと賞状が当局に押収され、エバーディはイギリスに亡命したそうだ。
挫折した巨大プロジェクトの現場の空気を感じた ― 2025年12月31日
『イラン現代史』と『物語イランの歴史』に触発されて、次の小説を古書で入手して読んだ。
『バンダルの塔』(高杉良/講談社文庫/1984.3)
IJPC(イラン・ジャパン石油化学)を題材にした小説である。1979年のイラン革命の直後、新聞の見出しでIJPCという文字を何度も見た。三井物産を中心に日本の化学メーカー(東洋曹達、三井東圧、三井石油化学、日本合成ゴム)がイランに石油化学コンビナートを建設する壮大なプロジェクトだった。イラン革命の勃発で暗雲が立ち込め、巨額の損失を出してIJPCは清算される。
この小説の単行本が出たのはイラン革命から2年後の1981年、きわものに近い小説だ。文庫版が出たのはイラン革命後のイラン・イラク戦争中、1984年だ。文庫版の解説で、佐高信は「新しい形で、日本はイランに協力することになって、現在、百名を超える日本人が現地に行き、数回に及ぶ爆撃による被害の調査を行なっている。」と希望的見解を述べている。しかし、文庫版が出た5年後の1989年、三井物産はIJPCの清算を発表する。6000億円以上をつぎ込んだプロジェクトは潰えた。
77歳の私には久々の高杉良の経済小説だった。現役時代、企業の現場を生々しく描く高杉良の企業人小説に身につまされる思いをしたこともある。この小説を読んで、昔のそんな気分が甦った。
この小説、企業名は実名だが、主人公らの登場人物は複数のモデルを合成したフィクションらしい。パーレビ体制の安定を疑う人はほとんどいなかったが、巨大プロジェクト推進のリスクを懸念する人はいた。さまざまな困難をひとつずつ乗り越えて奮闘する姿は感動的でもある。日本の高度成長末期の企業現場の元気な雰囲気が伝わってくる。
イランに赴任して一年八カ月の日本人がイラン人について「狡猾で、狡知にたけてるが、自分のことしか考えない人種です」と述懐する場面が印象に残った。一部の人間から全体を論じるのは乱暴だとは思うが、文化や考え方の違いを克服する困難を感じた。
イラン革命勃発時、コンビナートは完成目前だった。工事現場で約5千人が働いていた。日本人は3千人以上いた。だが、イラン側のトップがいち早く海外へ脱出するなど事態は急展開する。総引きあげとなった現場の無念に思いを馳せた。
P.S.
実は、私は来年2月下旬からイラン観光旅行をすることになった。『イラン現代史』や『物語イランの歴史』を読んだときは、まだ旅行検討中だった。これから、イランについて情報収集せねばと思い、その一環でこの小説を読んだ。
『バンダルの塔』(高杉良/講談社文庫/1984.3)
IJPC(イラン・ジャパン石油化学)を題材にした小説である。1979年のイラン革命の直後、新聞の見出しでIJPCという文字を何度も見た。三井物産を中心に日本の化学メーカー(東洋曹達、三井東圧、三井石油化学、日本合成ゴム)がイランに石油化学コンビナートを建設する壮大なプロジェクトだった。イラン革命の勃発で暗雲が立ち込め、巨額の損失を出してIJPCは清算される。
この小説の単行本が出たのはイラン革命から2年後の1981年、きわものに近い小説だ。文庫版が出たのはイラン革命後のイラン・イラク戦争中、1984年だ。文庫版の解説で、佐高信は「新しい形で、日本はイランに協力することになって、現在、百名を超える日本人が現地に行き、数回に及ぶ爆撃による被害の調査を行なっている。」と希望的見解を述べている。しかし、文庫版が出た5年後の1989年、三井物産はIJPCの清算を発表する。6000億円以上をつぎ込んだプロジェクトは潰えた。
77歳の私には久々の高杉良の経済小説だった。現役時代、企業の現場を生々しく描く高杉良の企業人小説に身につまされる思いをしたこともある。この小説を読んで、昔のそんな気分が甦った。
この小説、企業名は実名だが、主人公らの登場人物は複数のモデルを合成したフィクションらしい。パーレビ体制の安定を疑う人はほとんどいなかったが、巨大プロジェクト推進のリスクを懸念する人はいた。さまざまな困難をひとつずつ乗り越えて奮闘する姿は感動的でもある。日本の高度成長末期の企業現場の元気な雰囲気が伝わってくる。
イランに赴任して一年八カ月の日本人がイラン人について「狡猾で、狡知にたけてるが、自分のことしか考えない人種です」と述懐する場面が印象に残った。一部の人間から全体を論じるのは乱暴だとは思うが、文化や考え方の違いを克服する困難を感じた。
イラン革命勃発時、コンビナートは完成目前だった。工事現場で約5千人が働いていた。日本人は3千人以上いた。だが、イラン側のトップがいち早く海外へ脱出するなど事態は急展開する。総引きあげとなった現場の無念に思いを馳せた。
P.S.
実は、私は来年2月下旬からイラン観光旅行をすることになった。『イラン現代史』や『物語イランの歴史』を読んだときは、まだ旅行検討中だった。これから、イランについて情報収集せねばと思い、その一環でこの小説を読んだ。
6年前のトランプ時代に出た『真実の終わり』を今になって読んだ ― 2025年02月16日
先日読んだ朝日新聞のコラム(2025.2.2『日曜に想う』)に、次の記述があった。
「10年近く前、ポスト・トゥルース(真実後)という新語が注目された。意味するところは、事実や真実が重視されない時代の到来である。最近耳にしなくなったのは、当たり前の風景になったからだろうか。」
この一節を読んで、6年前に買ったまま未読だった次の本を思い出し、あわてて読了した。
『真実の終わり』(ミチコ・カクタニ/岡崎玲子訳/集英社/2019.6)
原著の出版は2018年、トランプ大統領誕生の翌年だ。トランプがもたらした時代風潮を批判的に探究し、真実が無視される事態に警鐘を鳴らした本である。
百数十ページの薄い本である。短時間で読めるだろうと目近の書架に積んだまま6年の時間が流れた。いつしか、トランプ時代からバイデン時代に移り、時評的な本書への関心が薄れていった。そして、再びトランプ時代となり、新聞コラムに促され、本書を手にする次第となった。
著者はニューヨーク・タイムズで活躍した高名な文芸批評家だそうだ。本書は、虚偽に満ちたトランプの言動を厳しく批判すると同時に、真実探求の関心を失った現代社会の情況を多面的に考察している。簡略に言えば、ポストモダン思想による物事の相対化がニヒリズムにつながり、トランプを生み出す土壌になったという指摘である。
著者の指摘は概ね納得できる。この10年ほどの間に見聞きしてきたさまざまな言説をあらためて復習した気分になる。カウンター・カルチャー的左翼的思潮が既存メディア否定のポピュリズム的右翼思潮に連結していく皮肉なダイナミズムに暗然とする。
本書に出てくる「羅生門的」「羅生門効果」という言葉に驚いた。一般的な用語かは不明だが、ナルホドと思った。著者は日系2世だそうだ。
脱構築の哲学者ポール・ド・マンという人物を本書で初めて知った。死後にナチスのユダヤ人迫害を支持する言説が発見されてスキャンダルになったそうだ。評価のゆらぎが興味深い。
ブーアスティンの『幻影の時代』への言及には心躍った。半世紀以上昔の学生時代に面白く読んだ本だ。筒井康隆氏の疑似イベント小説のネタ本だと知って読んだのだ。あの本がトランプ時代を胚胎していたとすれば「真実の終わり」の起源は根深い。文明論的な考察が必要だと思える。
それにしても、厚顔無恥の大音量が成功する社会がいいとは思わない。成功か失敗かの評価は歴史の時間軸で異なってくるだろうが。私は、寛容性を失うと文明は衰退すると思っている。
2018年に出た本書がどの程度の読者を得たかは知らない。トランプ時代が再来したのだから、本書にさほどに影響力はなかったと思わざるを得ない。故・西部邁ならトランプの出現は民主主義の必然と言うかもしれない。だが、リアルの世界を生きる私は、それをよしとするわけにはいかない。
「10年近く前、ポスト・トゥルース(真実後)という新語が注目された。意味するところは、事実や真実が重視されない時代の到来である。最近耳にしなくなったのは、当たり前の風景になったからだろうか。」
この一節を読んで、6年前に買ったまま未読だった次の本を思い出し、あわてて読了した。
『真実の終わり』(ミチコ・カクタニ/岡崎玲子訳/集英社/2019.6)
原著の出版は2018年、トランプ大統領誕生の翌年だ。トランプがもたらした時代風潮を批判的に探究し、真実が無視される事態に警鐘を鳴らした本である。
百数十ページの薄い本である。短時間で読めるだろうと目近の書架に積んだまま6年の時間が流れた。いつしか、トランプ時代からバイデン時代に移り、時評的な本書への関心が薄れていった。そして、再びトランプ時代となり、新聞コラムに促され、本書を手にする次第となった。
著者はニューヨーク・タイムズで活躍した高名な文芸批評家だそうだ。本書は、虚偽に満ちたトランプの言動を厳しく批判すると同時に、真実探求の関心を失った現代社会の情況を多面的に考察している。簡略に言えば、ポストモダン思想による物事の相対化がニヒリズムにつながり、トランプを生み出す土壌になったという指摘である。
著者の指摘は概ね納得できる。この10年ほどの間に見聞きしてきたさまざまな言説をあらためて復習した気分になる。カウンター・カルチャー的左翼的思潮が既存メディア否定のポピュリズム的右翼思潮に連結していく皮肉なダイナミズムに暗然とする。
本書に出てくる「羅生門的」「羅生門効果」という言葉に驚いた。一般的な用語かは不明だが、ナルホドと思った。著者は日系2世だそうだ。
脱構築の哲学者ポール・ド・マンという人物を本書で初めて知った。死後にナチスのユダヤ人迫害を支持する言説が発見されてスキャンダルになったそうだ。評価のゆらぎが興味深い。
ブーアスティンの『幻影の時代』への言及には心躍った。半世紀以上昔の学生時代に面白く読んだ本だ。筒井康隆氏の疑似イベント小説のネタ本だと知って読んだのだ。あの本がトランプ時代を胚胎していたとすれば「真実の終わり」の起源は根深い。文明論的な考察が必要だと思える。
それにしても、厚顔無恥の大音量が成功する社会がいいとは思わない。成功か失敗かの評価は歴史の時間軸で異なってくるだろうが。私は、寛容性を失うと文明は衰退すると思っている。
2018年に出た本書がどの程度の読者を得たかは知らない。トランプ時代が再来したのだから、本書にさほどに影響力はなかったと思わざるを得ない。故・西部邁ならトランプの出現は民主主義の必然と言うかもしれない。だが、リアルの世界を生きる私は、それをよしとするわけにはいかない。
西部邁の最後の書を読んだ ― 2025年01月18日
西部邁が自死したのは2~3年前のように感じていたが、調べてみると2018年1月21日、7年前だった。齢を重ねると日々の流れが速くなる。
西部邁の自死1カ月前に出た『保守の真髄』を死の直後に読み、その本が最後の書だと思っていた。だが、その後にさらに1冊出していると知り、入手して読んだ。
『保守の遺言:JAP.COM衰微の状況』(西部邁/平凡社新書/2018.2.27)
本書の「あとがき」の日付は2018年1月15日、自死の6日前である。刊行は自死から約1カ月後だ。序文には「僕はこれが最後の著作と銘打ちつつすでに二つの書物を出版してしまった。だから、何事も三度めなので、もう嘘はないとことわりつつ…」とある。
先日読んだ『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル』で本書を知った。安倍晋三が保守系言論人からも批判された事例として本書からの引用が載っていた。著者は安倍首相をプラグマティストではなくプラクティカリスト(実際主義者)としている。それはオポチュニスト(状況適応主義)、オケージョナリスト(機会に反応するのを旨とするやり方)の別名であり、「現在に関する視界が狭い」「未来に関する視野が短い」という特徴があるそうだ。
本書にはカタカナ語が頻出し、しばしばその語源解説に及ぶ。訳語の不適切の指摘も多い。著者の芸風である。マスを「大衆」と呼ぶのは間違いで「大量人」と呼ぶべきといった言説である。コモディテイ(商品)を論じる際、古代ローマ皇帝コモドゥスを思い起こすべきだとしているのには驚いた。コモデゥスが愚帝とは承知しているが、私には了解不能で、やり過ぎではないかと感じた。
衒学的で粘っこいニシベ節には辟易することも多いが、独特の魅力も感じる。共感と反発がないまぜになる。この新書を通読した読後感は、共感3割、反感3割、理解困難4割といったところだ。悩ましい本である。著者が持論を述べた部分を引用する。
「僕の持論をここで繰り返させてもらうと、自由と秩序のあいだの平衡としての「活力」、平等と格差のあいだの平衡としての「公正」、博愛と競合のあいだの平衡としての「節度」そして合理と感情のあいだの平衡としての「良識」、この四副対の規範の(現下の状況における)具体的な姿、それがクライテリオン(複数でクライテリア)ということなのだ。」
遺言と銘打った本書のトーンは諦観である。「明るく諦観しているにすぎない」という言葉が印象深い。
西部邁の自死1カ月前に出た『保守の真髄』を死の直後に読み、その本が最後の書だと思っていた。だが、その後にさらに1冊出していると知り、入手して読んだ。
『保守の遺言:JAP.COM衰微の状況』(西部邁/平凡社新書/2018.2.27)
本書の「あとがき」の日付は2018年1月15日、自死の6日前である。刊行は自死から約1カ月後だ。序文には「僕はこれが最後の著作と銘打ちつつすでに二つの書物を出版してしまった。だから、何事も三度めなので、もう嘘はないとことわりつつ…」とある。
先日読んだ『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル』で本書を知った。安倍晋三が保守系言論人からも批判された事例として本書からの引用が載っていた。著者は安倍首相をプラグマティストではなくプラクティカリスト(実際主義者)としている。それはオポチュニスト(状況適応主義)、オケージョナリスト(機会に反応するのを旨とするやり方)の別名であり、「現在に関する視界が狭い」「未来に関する視野が短い」という特徴があるそうだ。
本書にはカタカナ語が頻出し、しばしばその語源解説に及ぶ。訳語の不適切の指摘も多い。著者の芸風である。マスを「大衆」と呼ぶのは間違いで「大量人」と呼ぶべきといった言説である。コモディテイ(商品)を論じる際、古代ローマ皇帝コモドゥスを思い起こすべきだとしているのには驚いた。コモデゥスが愚帝とは承知しているが、私には了解不能で、やり過ぎではないかと感じた。
衒学的で粘っこいニシベ節には辟易することも多いが、独特の魅力も感じる。共感と反発がないまぜになる。この新書を通読した読後感は、共感3割、反感3割、理解困難4割といったところだ。悩ましい本である。著者が持論を述べた部分を引用する。
「僕の持論をここで繰り返させてもらうと、自由と秩序のあいだの平衡としての「活力」、平等と格差のあいだの平衡としての「公正」、博愛と競合のあいだの平衡としての「節度」そして合理と感情のあいだの平衡としての「良識」、この四副対の規範の(現下の状況における)具体的な姿、それがクライテリオン(複数でクライテリア)ということなのだ。」
遺言と銘打った本書のトーンは諦観である。「明るく諦観しているにすぎない」という言葉が印象深い。
『シニア右翼』を読んでネットの歴史をふりかえった ― 2025年01月11日
約2年前に出た次の新書をネット書店で購入して読んだ。
『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)
2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。
著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。
最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。
著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。
本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。
著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。ここで言う「彼ら」の世代は、著者の親にあたる私たちベビーブーマーになるようだ。
後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私はギクリとさせられる。近現代史は常に目前の課題である。
前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。
『シニア右翼:日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(古谷経衡/中公新書ラクレ/2023.3)
2年前、本屋の店頭で本書を手にした気がするが、そのときはスルーした。今頃になって読もうと思ったのは、たまたま聞いていたラジオで著者が話していて、私には未知のこの人物に関心がわいたからである。
著者は1982年生まれの作家・評論家。私(1948年生まれ)のセガレの世代だ。本書の冒頭で自身の来歴を語っている。長く右翼業界に居を構え、雑誌やネット配信番組で若手評論家として活躍してきたそうだ。著書も多い。だが、33歳頃に右翼業界に幻滅し、右翼に批判的な立場になったそうだ。この体験談がとても面白い。
最近の若者は右傾化していると言われことが多い。しかし、著者はシニアこそが右傾化していると指摘している。若者の著者が体験した右翼の世界はシニアばかりだったそうだ。
著者も述べているが「右翼」や「保守」という言葉が何を指すかは曖昧で、人によってまちまちである。「あれは本当の右翼でない」「あれは本当の保守でない」という応酬もよく耳にする。
本書のテーマ「シニア右翼」とはいわゆる「ネット右翼」である。著者によれば、それは「保守系言論人」「右派系言論人」の言説を無批判に受容し拡大再生産する存在だそうだ。彼らはその言説を本や雑誌で受容するのではない。ネット動画のみで受容しているのだ。あらためてネット動画の威力を認識した。
著者はシニア右翼が生まれた要因を二つ指摘している。ひとつは、彼らがネットの波に遅れて乗ってきたため、ネット情報のリスクへの耐性がなく、ネット動画を無批判に受け容れたということである。もうひとつは、彼らが体得してきたと思われる戦後民主主義の脆弱性である。ここで言う「彼ら」の世代は、著者の親にあたる私たちベビーブーマーになるようだ。
後者の要因に関して、著者は「戦前と戦後の日本は、憲法という看板のかけ替えが起こっただけで何も変わっていない」としている。戦後民主主義は未完であるとする論考には力が入っている。特に目新しい指摘ではないかもしれにが、若い評論家の現代史への取り組みにシニアの私はギクリとさせられる。近現代史は常に目前の課題である。
前者の要因に関しては、そんなものかなと感じるだけだ。私は初期のパソコン通信時代を知っているので、本書の主旨とは無関係に、著者のネット史の解説を懐かしく読んだ。筒井康隆氏がパソコン通信での応酬を取り入れた新聞連載小説『朝のガスパール』(1991年)に言及しているのには驚いた。著者9歳のときの出来事だ。「このとき筒井は57歳である。応酬した読者の側は筒井より若い場合もあったが、総じて中年層だった。このような高感度の人々は、後に大量に登場するシニア右翼とは完全に別物である」と解説している。
『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル』は記述が細かい ― 2025年01月06日
1カ月以上前に読み始めた次の本を、年明けになってやっと読み終えた。
『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル(上)(下)』(船橋洋一/文藝春秋)
著者は本書を「調査報道であり、ノンフィクションである」と述べている。第2次安倍政権(2012年12月~2020年9月)の思考と行動を、おびただしい人数の関係者へのインタビューをベースに描いている。安倍晋三本人にも、退陣後2年弱のあいだに19回インタビューしたそうだ。労作である。
安倍晋三に関しては、以前に『安倍三代』(青木理)や『安倍晋三の正体』(適菜収)などを読んだ。いずれも安倍晋三に批判的な内容であり、私はこれらの著作に共感している。安倍政権を評価する気にはなれない。
にもかかわらず本書を読もうと思ったのは、著者が元・朝日新聞社主筆の船橋洋一氏だからである。船橋氏の著作は以前にいくつか読んだことがある。安倍政権に批判的だった朝日新聞の元・主筆が安倍政権をどのように描いているのかに興味がわいたのだ。
上下巻で約1200頁の本書は、「アベノミクス」「戦後70年首相談話」「プーチン」「トランプ」など約20のテーマごとに、政権中枢がどんな動きをしてきたかを細かく描いている。細かい話になると頭がついて行くのが難しくなり、読むのに時間を要した。何とか読了できたのは、やはり面白いからである。「へぇー」と感じる興味深い話がいろいろ出てくる。
本書は関係者の証言に基づいた事実を坦々と描写しているが、取材対象の多くは政権に関わった人物である。だから功罪の「罪」よりは「功」にウエイトがかかり、全体としては安倍政権をかなり評価している印象を受ける。
最終章の「戦後終章」は著者による安倍政権総括である。著者は次のように述べている。
「この政権は、国のあるべき構想を明確にし、そのための政治課題を設定し、それを能動的に遂行しようとするきわめて理念的かつ行動的な政治において際立っていた。」
「安倍時代、日本の政治は欧米民主国家の多くで起こったような「極端な党派性のポピュリスト的罠」に嵌ることはなかった。」
「この政権は、第1次政権の失敗の歴史からよく学んだ。その本質は、このリアリズムの政治のありようということだったかもしれない。そして、それが憲政史上最長の政権をつくった最大の秘訣だっただろう。」
船橋氏が描出した安倍晋三は、信念と使命を追究しつつも柔軟性をもったリアリズムの政治家である。青木理氏は『安倍三代』で安倍晋三を「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」としていた。適菜収氏は『安倍晋三回顧録』から見えるものは「安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ」と書いていた。これら批判的な安部晋三像と船橋氏が本書で描いた安倍晋三像は矛盾するだろうか。私は、必ずしも矛盾しないと思う。
本書のタイトル「宿命の子」は安倍晋三の母親・洋子(岸信介の娘。安倍晋太郎の妻)が息子について語った言葉である。岸信介の孫、安倍晋太郎の息子として生まれた凡庸で空疎なオボッチャマが、後天的に無理やりに「信念」や「使命」を自身に注入した――それが「宿命の子」だと思える。元が空疎だから可塑性はある。育ちのよさには、先天的な人たらしの魅力(愛嬌)があったのかもしれない。言葉が軽く、饒舌で、雑談の名手だったそうだ。
コロナ禍の頃に関する次の記述が印象に残った。
「萩生田は、コロナ危機の中で、安倍の体力と気力の弱まりを感じた。海外にも行けない。ゴルフもできない。みんなでワイワワイガヤガヤできない。」
外交やゴルフ、ワイワイガヤガヤが政権維持の気力の源泉だとすると、人間味を感じる。
『宿命の子:安倍晋三政権クロニクル(上)(下)』(船橋洋一/文藝春秋)
著者は本書を「調査報道であり、ノンフィクションである」と述べている。第2次安倍政権(2012年12月~2020年9月)の思考と行動を、おびただしい人数の関係者へのインタビューをベースに描いている。安倍晋三本人にも、退陣後2年弱のあいだに19回インタビューしたそうだ。労作である。
安倍晋三に関しては、以前に『安倍三代』(青木理)や『安倍晋三の正体』(適菜収)などを読んだ。いずれも安倍晋三に批判的な内容であり、私はこれらの著作に共感している。安倍政権を評価する気にはなれない。
にもかかわらず本書を読もうと思ったのは、著者が元・朝日新聞社主筆の船橋洋一氏だからである。船橋氏の著作は以前にいくつか読んだことがある。安倍政権に批判的だった朝日新聞の元・主筆が安倍政権をどのように描いているのかに興味がわいたのだ。
上下巻で約1200頁の本書は、「アベノミクス」「戦後70年首相談話」「プーチン」「トランプ」など約20のテーマごとに、政権中枢がどんな動きをしてきたかを細かく描いている。細かい話になると頭がついて行くのが難しくなり、読むのに時間を要した。何とか読了できたのは、やはり面白いからである。「へぇー」と感じる興味深い話がいろいろ出てくる。
本書は関係者の証言に基づいた事実を坦々と描写しているが、取材対象の多くは政権に関わった人物である。だから功罪の「罪」よりは「功」にウエイトがかかり、全体としては安倍政権をかなり評価している印象を受ける。
最終章の「戦後終章」は著者による安倍政権総括である。著者は次のように述べている。
「この政権は、国のあるべき構想を明確にし、そのための政治課題を設定し、それを能動的に遂行しようとするきわめて理念的かつ行動的な政治において際立っていた。」
「安倍時代、日本の政治は欧米民主国家の多くで起こったような「極端な党派性のポピュリスト的罠」に嵌ることはなかった。」
「この政権は、第1次政権の失敗の歴史からよく学んだ。その本質は、このリアリズムの政治のありようということだったかもしれない。そして、それが憲政史上最長の政権をつくった最大の秘訣だっただろう。」
船橋氏が描出した安倍晋三は、信念と使命を追究しつつも柔軟性をもったリアリズムの政治家である。青木理氏は『安倍三代』で安倍晋三を「悲しいまでに凡庸で、何の変哲もない人間」「空虚で空疎な人間」としていた。適菜収氏は『安倍晋三回顧録』から見えるものは「安倍という男の絶望的な幼さ、自己中心的な思考、地頭の悪さだ」と書いていた。これら批判的な安部晋三像と船橋氏が本書で描いた安倍晋三像は矛盾するだろうか。私は、必ずしも矛盾しないと思う。
本書のタイトル「宿命の子」は安倍晋三の母親・洋子(岸信介の娘。安倍晋太郎の妻)が息子について語った言葉である。岸信介の孫、安倍晋太郎の息子として生まれた凡庸で空疎なオボッチャマが、後天的に無理やりに「信念」や「使命」を自身に注入した――それが「宿命の子」だと思える。元が空疎だから可塑性はある。育ちのよさには、先天的な人たらしの魅力(愛嬌)があったのかもしれない。言葉が軽く、饒舌で、雑談の名手だったそうだ。
コロナ禍の頃に関する次の記述が印象に残った。
「萩生田は、コロナ危機の中で、安倍の体力と気力の弱まりを感じた。海外にも行けない。ゴルフもできない。みんなでワイワワイガヤガヤできない。」
外交やゴルフ、ワイワイガヤガヤが政権維持の気力の源泉だとすると、人間味を感じる。
森永卓郎氏の『ザイム真理教』『書いてはいけない』は陰謀論か? ― 2024年10月27日
森永卓郎氏の次の本を続けて読んだ。
『ザイム真理教』(森永卓郎/三五館シンシャ/2023.6)
『書いてはいけない:日本経済墜落の真相』(森永卓郎/三五館シンシャ/2024.3)
数日前(2024.10.24)の新聞(朝日と日経)に、新刊の『投資依存症』と並んで上記2書を並べた三五館シンシャの広告が載っていた。その広告によれば『ザイム真理教』は19万部、『書いてはいけない』は27万部売れているそうだ。本が売れない時代、ご同慶の至りである。
三五館シンシャという出版社を私は2年前に知り、興味を抱いた。きっかけは備中松山藩の山田方谷である。私はこの人物に関心がある。『財政の巨人:幕末の陽明学者・山田方谷』(林田明大/三五館)という本を読んだとき、その本の出版社を検索し、三五館がすでに倒産し、社員の一人が三五館シンシャという別会社を立ち上げていると知った。その経緯を綴った文章がとても面白く、強く印象に残った。
だから、森永卓郎氏の『ザイム真理教』が三五館シンシャから刊行されたと知ったとき、あの出版社が有名な著者の本を出したのかと驚いた。この本の「あとがき」によれば、知り合いの大手出版社数社から出版を断られ、三五館シンシャに持ち込み、ようやく出版にこぎつけたそうだ。
なぜ、大手出版社は断ったのか。財務省を批判した本だからである。そんなことで自主規制するのかと思うが、財務省の心象を害した会社には税務調査が入る可能性が高く、面倒なことになるリスクがあるのだ。陰謀論めいた話に思えるかもしれないが、私は納得できる。税務調査には恣意性があり、企業にとっては災難以外の何物でもない。
『ザイム真理教』は財政収支の均衡を目指す財務省をカルト教団に近いと批判している。緊縮財政から積極財政に転換し、消費税減税(あるは廃止)をしなければ日本経済は成長しないと主張し、日銀が国債をどんどん引き受けてもハイパーインフレにはならないと解説している。その根拠も述べている。私は、この主張の当否を今のところ判断できない。森永氏によれば、日本人の7割がザイム真理教に洗脳されているそうだ。私も洗脳されているのかもしれない。
だが、森永氏の財務省批判には首肯できる点も多い。高級官僚の天下り、金融ムラの癒着、露骨な洗脳活動(与党、野党、メディア、芸能界から子供まで)、恣意的な税務調査などが問題なのは確かだ。
森永氏が主張するように大多数の日本人が洗脳されているとすれば、その洗脳を解くのは容易でないと思う。私は、どこにでも付く膏薬のような経済学の理屈をなかなか信用できない。だが、本書をベースに少しは勉強してみようかという気になった。
『書いてはいけない』は三つのタブーを語っている。「ジャニーズ性加害」「財務省のカルト的財政緊縮主義」「日本航空123便の墜落事件」の三つであり、森永氏によれば、これらはメディアでは触れることができないテーマだそうだ。
ジャニーズ問題はBBCの報道を契機にタブーでなくなりつつあるが、それ以前にテレビ出演者の一人として見聞したアレコレを述べていて、興味深い。この本がジャニーズ問題を取り上げているのは、他のタブーも同じ構造だと主張するためである。
『書いてはいけない』の読後感を書くのは『ザイム真理教』以上に難しい。森永氏は否定するだろうが、陰謀論に近いからである。
29年前の日航機墜落事故は、訓練中の自衛隊による尾翼への誤射がひきがねで、最終的には自衛隊のミサイルによる右エンジン攻撃で墜落、その現場は特殊部隊が焼き払った――という説を紹介し、森永氏は9割は正しいだろうと述べている。さらに、墜落原因をボーイング社におしつけたことが日本の米国への借りとなり、後日のプラザ合意に影響し、その後の日本経済墜落の要因になったとしている。
日航機墜落事故にいくつかの謎があるとしても、にわかには信じがたい説である。事実だとしたら天地がひっくり返るような大騒動になるだろう。
仮に事実なら、それを知る関係者は少なくないはずである。その全員が何も語らず何も残さずにこの世から消えていくということがあるだろうか。何らかの記録が出てくれば面白いとは思うが。
『ザイム真理教』(森永卓郎/三五館シンシャ/2023.6)
『書いてはいけない:日本経済墜落の真相』(森永卓郎/三五館シンシャ/2024.3)
数日前(2024.10.24)の新聞(朝日と日経)に、新刊の『投資依存症』と並んで上記2書を並べた三五館シンシャの広告が載っていた。その広告によれば『ザイム真理教』は19万部、『書いてはいけない』は27万部売れているそうだ。本が売れない時代、ご同慶の至りである。
三五館シンシャという出版社を私は2年前に知り、興味を抱いた。きっかけは備中松山藩の山田方谷である。私はこの人物に関心がある。『財政の巨人:幕末の陽明学者・山田方谷』(林田明大/三五館)という本を読んだとき、その本の出版社を検索し、三五館がすでに倒産し、社員の一人が三五館シンシャという別会社を立ち上げていると知った。その経緯を綴った文章がとても面白く、強く印象に残った。
だから、森永卓郎氏の『ザイム真理教』が三五館シンシャから刊行されたと知ったとき、あの出版社が有名な著者の本を出したのかと驚いた。この本の「あとがき」によれば、知り合いの大手出版社数社から出版を断られ、三五館シンシャに持ち込み、ようやく出版にこぎつけたそうだ。
なぜ、大手出版社は断ったのか。財務省を批判した本だからである。そんなことで自主規制するのかと思うが、財務省の心象を害した会社には税務調査が入る可能性が高く、面倒なことになるリスクがあるのだ。陰謀論めいた話に思えるかもしれないが、私は納得できる。税務調査には恣意性があり、企業にとっては災難以外の何物でもない。
『ザイム真理教』は財政収支の均衡を目指す財務省をカルト教団に近いと批判している。緊縮財政から積極財政に転換し、消費税減税(あるは廃止)をしなければ日本経済は成長しないと主張し、日銀が国債をどんどん引き受けてもハイパーインフレにはならないと解説している。その根拠も述べている。私は、この主張の当否を今のところ判断できない。森永氏によれば、日本人の7割がザイム真理教に洗脳されているそうだ。私も洗脳されているのかもしれない。
だが、森永氏の財務省批判には首肯できる点も多い。高級官僚の天下り、金融ムラの癒着、露骨な洗脳活動(与党、野党、メディア、芸能界から子供まで)、恣意的な税務調査などが問題なのは確かだ。
森永氏が主張するように大多数の日本人が洗脳されているとすれば、その洗脳を解くのは容易でないと思う。私は、どこにでも付く膏薬のような経済学の理屈をなかなか信用できない。だが、本書をベースに少しは勉強してみようかという気になった。
『書いてはいけない』は三つのタブーを語っている。「ジャニーズ性加害」「財務省のカルト的財政緊縮主義」「日本航空123便の墜落事件」の三つであり、森永氏によれば、これらはメディアでは触れることができないテーマだそうだ。
ジャニーズ問題はBBCの報道を契機にタブーでなくなりつつあるが、それ以前にテレビ出演者の一人として見聞したアレコレを述べていて、興味深い。この本がジャニーズ問題を取り上げているのは、他のタブーも同じ構造だと主張するためである。
『書いてはいけない』の読後感を書くのは『ザイム真理教』以上に難しい。森永氏は否定するだろうが、陰謀論に近いからである。
29年前の日航機墜落事故は、訓練中の自衛隊による尾翼への誤射がひきがねで、最終的には自衛隊のミサイルによる右エンジン攻撃で墜落、その現場は特殊部隊が焼き払った――という説を紹介し、森永氏は9割は正しいだろうと述べている。さらに、墜落原因をボーイング社におしつけたことが日本の米国への借りとなり、後日のプラザ合意に影響し、その後の日本経済墜落の要因になったとしている。
日航機墜落事故にいくつかの謎があるとしても、にわかには信じがたい説である。事実だとしたら天地がひっくり返るような大騒動になるだろう。
仮に事実なら、それを知る関係者は少なくないはずである。その全員が何も語らず何も残さずにこの世から消えていくということがあるだろうか。何らかの記録が出てくれば面白いとは思うが。


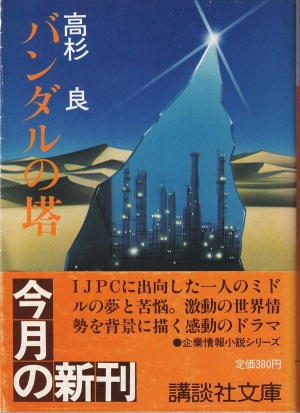


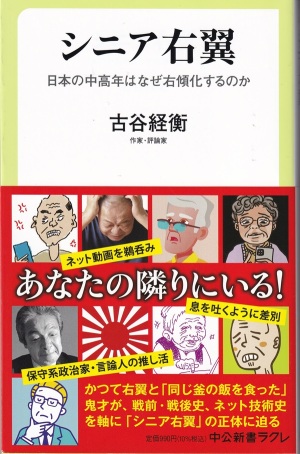


最近のコメント