『アジアの歴史』(松田壽男)は歴史を大きく把握できる本 ― 2022年08月02日
河合塾の『わたしが選んだこの一冊 2022』という冊子を入手した。34人の識者が34冊の本を推薦した読書案内で、おそらく高校生向けだと思うが、私のような高齢者にも興味深い。この冊子で歴史学者・森安孝夫氏が推薦している次の本を読んだ。
『アジアの歴史:東西交渉からみた前近代の世界像』(松田壽男/岩波現代文庫)
松田壽男は「絹馬交易」という歴史用語を生み出した東洋史学者で、1982年に78歳で亡くなっている。本書の元版は1971年刊行である。松田壽男の名は森安孝夫氏の『シルクロード世界史』などで知った。その著書を読むのは初めてである。
本書のタイトルは『アジアの歴史』だが、内容は前近代“世界史”概説に近い。著者は地中海やエジプトあたりまでも「前近代のアジア」に含めていて、ギリシアやローマへの言及もある。本書の眼目は西欧中心の歴史観の否定である。西欧という一元世界では世界史を捉えることはできない。前近代を知るということはアジア(地中海から中国まで)の歴史と地理を多元世界として把握することだ――著者はそう主張している。
多元世界と言っても地域ごとのバラバラな事象の紹介ではなく、相互の関連(交渉)にウエイトをおいて図解的に歴史と地理を概説している。図解とは文字通り著者が作成した多様な独自の概念図であり、これが非常にわかりやすい。世界を大きく把握した気分になる。
本書は先日読んだ『ヨーロッパ覇権以前』に似たグローバル・ヒストリーの書と言える。だが、よりマクロでスケールが大きい。ユーラシア大陸を湿潤地帯(季節風地帯)、乾燥地帯(砂漠地帯)、亜湿潤地帯(森林地帯)に分ける「三風土帯説」の紹介に始まり、文明発生の時代から15世紀頃までの人間の活動や交流を概説している。
私が興味深く読んだのは「トルコ=イスラーム」の動きである。トルコ系の人々の西への拡がりとイスラームの東への拡がりをダイナミックにわかりやすく描いている。突厥帝国を「古代トルコ帝国」、セルチュック(サルジューク)帝国を「中世トルコ帝国」、オスマン帝国を「近世トルコ帝国」と表現しているのが明解だ。「トルコ人はマムルークと呼ばれた一種の軍人奴隷の形をとって、イスラーム勢力そのもののなかに潜入をはじめる」という表現も秀逸である。
また、十字軍運動によってアジアからヨーロッパへの商路が変わり、それがいろいろな動きに波及していく話も興味深い。
教科書的に再読・三読したくなる本である。
『アジアの歴史:東西交渉からみた前近代の世界像』(松田壽男/岩波現代文庫)
松田壽男は「絹馬交易」という歴史用語を生み出した東洋史学者で、1982年に78歳で亡くなっている。本書の元版は1971年刊行である。松田壽男の名は森安孝夫氏の『シルクロード世界史』などで知った。その著書を読むのは初めてである。
本書のタイトルは『アジアの歴史』だが、内容は前近代“世界史”概説に近い。著者は地中海やエジプトあたりまでも「前近代のアジア」に含めていて、ギリシアやローマへの言及もある。本書の眼目は西欧中心の歴史観の否定である。西欧という一元世界では世界史を捉えることはできない。前近代を知るということはアジア(地中海から中国まで)の歴史と地理を多元世界として把握することだ――著者はそう主張している。
多元世界と言っても地域ごとのバラバラな事象の紹介ではなく、相互の関連(交渉)にウエイトをおいて図解的に歴史と地理を概説している。図解とは文字通り著者が作成した多様な独自の概念図であり、これが非常にわかりやすい。世界を大きく把握した気分になる。
本書は先日読んだ『ヨーロッパ覇権以前』に似たグローバル・ヒストリーの書と言える。だが、よりマクロでスケールが大きい。ユーラシア大陸を湿潤地帯(季節風地帯)、乾燥地帯(砂漠地帯)、亜湿潤地帯(森林地帯)に分ける「三風土帯説」の紹介に始まり、文明発生の時代から15世紀頃までの人間の活動や交流を概説している。
私が興味深く読んだのは「トルコ=イスラーム」の動きである。トルコ系の人々の西への拡がりとイスラームの東への拡がりをダイナミックにわかりやすく描いている。突厥帝国を「古代トルコ帝国」、セルチュック(サルジューク)帝国を「中世トルコ帝国」、オスマン帝国を「近世トルコ帝国」と表現しているのが明解だ。「トルコ人はマムルークと呼ばれた一種の軍人奴隷の形をとって、イスラーム勢力そのもののなかに潜入をはじめる」という表現も秀逸である。
また、十字軍運動によってアジアからヨーロッパへの商路が変わり、それがいろいろな動きに波及していく話も興味深い。
教科書的に再読・三読したくなる本である。
イスラーム社会で奴隷がはたした役割 ― 2022年08月09日
イスラーム史の概説書を読んでいるとマムルークと呼ばれる軍人奴隷が頻出する。奴隷といっても王になって王朝を作ったりもするのだから、虐げられた哀れな存在のイメージとはかなり異なる。イスラーム世界の奴隷についてもっと知りたいと思い、次の冊子を読んだ。
『イスラーム史のなかの奴隷』(清水和裕/世界史リブレット/山川出版社)
私が期待したマムルークに関する記述はさほど多くなかった。イスラーム世界には軍人以外にも多様な奴隷が多く存在したということである。もちろん、ギリシア、ローマや中国にも多くの奴隷がいた。近代世界にも奴隷は存在したが、古代世界の奴隷は近代の類型的イメージとはかなり違った存在だったようだ。
本書によって、イスラーム世界においては奴隷と自由人の境がグラデーションになっていることを知った。解放される奴隷が多く、自由人のなかには多くの元奴隷が存在し、父母や祖父母が奴隷だった人は数え切れないほどいたのだ。
イスラーム社会はコーランやハディーズ(伝承)に基づいたイスラーム法という規範をベースにしているとの知識はあったが、本書によってその具体的イメージが垣間見えた。奴隷の扱い、奴隷が自由人になるための規定が、こまかくイスラーム法に定めれているのだ。イスラーム法の具体例をいくつか知り、なるほどと思った。
イスラーム世界では女性奴隷が主人の子供を産むことは普通だったようだ。アッバース朝のカリフは二人の例外を除いてみな、母親は奴隷女性だった。
では、カリフの宮廷には何人ぐらいの奴隷がいたか。本書によれば、10世紀初頭のカリフ(ムクタディル)の宮廷には次のような人々がいたといわれている。
黒人宦官 7000人
白人宦官 4000人
自由身分もしくは奴隷身分の女性 4000人
奴隷少年(グラーム) 数千人
警備要員 6000人以上
驚くべき数である。著者は「数字そのものの信頼性は別として、かなりの数であることは間違いない。」とコメントしている。
著者は本書末尾で、イスラーム社会において奴隷制度が果たした役割を次のように述べている。
「(イスラーム社会の奴隷制度が)、異郷からの他者を長い時間をかけて社会に同化させ、社会の多様性を生み出していく、そのような役割をもはたしていたのである。」
『イスラーム史のなかの奴隷』(清水和裕/世界史リブレット/山川出版社)
私が期待したマムルークに関する記述はさほど多くなかった。イスラーム世界には軍人以外にも多様な奴隷が多く存在したということである。もちろん、ギリシア、ローマや中国にも多くの奴隷がいた。近代世界にも奴隷は存在したが、古代世界の奴隷は近代の類型的イメージとはかなり違った存在だったようだ。
本書によって、イスラーム世界においては奴隷と自由人の境がグラデーションになっていることを知った。解放される奴隷が多く、自由人のなかには多くの元奴隷が存在し、父母や祖父母が奴隷だった人は数え切れないほどいたのだ。
イスラーム社会はコーランやハディーズ(伝承)に基づいたイスラーム法という規範をベースにしているとの知識はあったが、本書によってその具体的イメージが垣間見えた。奴隷の扱い、奴隷が自由人になるための規定が、こまかくイスラーム法に定めれているのだ。イスラーム法の具体例をいくつか知り、なるほどと思った。
イスラーム世界では女性奴隷が主人の子供を産むことは普通だったようだ。アッバース朝のカリフは二人の例外を除いてみな、母親は奴隷女性だった。
では、カリフの宮廷には何人ぐらいの奴隷がいたか。本書によれば、10世紀初頭のカリフ(ムクタディル)の宮廷には次のような人々がいたといわれている。
黒人宦官 7000人
白人宦官 4000人
自由身分もしくは奴隷身分の女性 4000人
奴隷少年(グラーム) 数千人
警備要員 6000人以上
驚くべき数である。著者は「数字そのものの信頼性は別として、かなりの数であることは間違いない。」とコメントしている。
著者は本書末尾で、イスラーム社会において奴隷制度が果たした役割を次のように述べている。
「(イスラーム社会の奴隷制度が)、異郷からの他者を長い時間をかけて社会に同化させ、社会の多様性を生み出していく、そのような役割をもはたしていたのである。」
山の日(8月11日)にNADA・MAP公演『Q』を観て、得した気分 ― 2022年08月11日
NADA・MAP公演『Q:A Night At Kabuki』(作・演出:野田秀樹、音楽:QUEEN、出演:松たか子、上川隆也、広瀬すず、志尊淳、竹中直人、他)を観た。7月末に観劇予定だったがコロナで初日が延期になった芝居である。観劇を諦めていたが、追加公演(昼の部だけの日に夜の部も追加)のチケット(8月11日の夜の部)を入手できた。
2019年初演の芝居の再演、私は初見である。『Q』を収録した戯曲集が先月発売されたので購入した。古典的な有名演劇は観劇前に戯曲を読んでおくことが多いが、同時代演劇はそうでもない。戯曲が入手しにくいし、観劇の後で戯曲を読んだ方が情景を反芻できて楽しめたりもする。
今回、観劇前に戯曲を読むかどうか少し迷い、観劇前に半分だけ読んだ。舞台で新鮮な驚きを感じるため、後半は観劇後に読むことにした。
この芝居のタイトル『Q』はロック・バンドQUEENのQで、随所にQUEENの曲が流れる。テーマソングは Love Of My Life で、『ロミオとジュリエット』をベースにした若いカップルの話である。
と言っても野田版だからかなり歌舞いている。舞台は源平の時代で、ロミオは平氏、ジュリエットは源氏、栄華を誇る平氏の都にはベルリンの壁のような壁があり、その向こうは源氏の自治区である。若いロミオとジュリエットとは別に約三十年後のロミオとジュリエットも登場し、舞台上の時間が溶解している。
ザックリ言ってしまえば、恋と戦争の物語である。恋と戦争はいつの時代をも貫く普遍的なテーマである、そこから無数のバリエーションが生まれる――華やかな舞台を眺めつつ、現在進行形の戦争を連想しながら、そんなことを考えた。後半になってシベリアの収容所に送られた戦争捕虜の話になったのには驚いた。
事前に戯曲を読んでいるとき「山の日って何祝えばいいんだよ!……でも休むけど」という科白に出会い、「山の日」がよくわからなかった。ウカツにも私は「山の日」という休日を知らなかったのだ。今朝、カレンダーを見て本日(8月11日)が「山の日」だと知り、びっくりした。
舞台上で野田秀樹演ずる乳母が「山の日」のギャグをしゃべるのを聞きながら不思議な気がした。戯曲を読んでいない観客は、このギャグを本日限りのアドリブと思ったに違いない。コロナで観劇日がズレて少し得した気分である。
2019年初演の芝居の再演、私は初見である。『Q』を収録した戯曲集が先月発売されたので購入した。古典的な有名演劇は観劇前に戯曲を読んでおくことが多いが、同時代演劇はそうでもない。戯曲が入手しにくいし、観劇の後で戯曲を読んだ方が情景を反芻できて楽しめたりもする。
今回、観劇前に戯曲を読むかどうか少し迷い、観劇前に半分だけ読んだ。舞台で新鮮な驚きを感じるため、後半は観劇後に読むことにした。
この芝居のタイトル『Q』はロック・バンドQUEENのQで、随所にQUEENの曲が流れる。テーマソングは Love Of My Life で、『ロミオとジュリエット』をベースにした若いカップルの話である。
と言っても野田版だからかなり歌舞いている。舞台は源平の時代で、ロミオは平氏、ジュリエットは源氏、栄華を誇る平氏の都にはベルリンの壁のような壁があり、その向こうは源氏の自治区である。若いロミオとジュリエットとは別に約三十年後のロミオとジュリエットも登場し、舞台上の時間が溶解している。
ザックリ言ってしまえば、恋と戦争の物語である。恋と戦争はいつの時代をも貫く普遍的なテーマである、そこから無数のバリエーションが生まれる――華やかな舞台を眺めつつ、現在進行形の戦争を連想しながら、そんなことを考えた。後半になってシベリアの収容所に送られた戦争捕虜の話になったのには驚いた。
事前に戯曲を読んでいるとき「山の日って何祝えばいいんだよ!……でも休むけど」という科白に出会い、「山の日」がよくわからなかった。ウカツにも私は「山の日」という休日を知らなかったのだ。今朝、カレンダーを見て本日(8月11日)が「山の日」だと知り、びっくりした。
舞台上で野田秀樹演ずる乳母が「山の日」のギャグをしゃべるのを聞きながら不思議な気がした。戯曲を読んでいない観客は、このギャグを本日限りのアドリブと思ったに違いない。コロナで観劇日がズレて少し得した気分である。
『世界は笑う』は、私には懐かしい昭和30年代の物語 ― 2022年08月13日
シアターコクーンでケラリーノ・サンドロヴィッチ作・演出の『世界は笑う』を観た。この公演も、先日観た『Q』と同じようにコロナで開幕延期(8月7~11日の公演中止)になり、8月12日が初日だった。私は13日のチケットなので払い戻しをまぬがれた。
多彩な役者が出演している(チラシ参照)。誰が主演とは言えない群像劇である。上演時間は3時間45分(20分休憩を含む)。かなり長いが退屈はしない。
喜劇を上演する新宿の三角座(劇団&劇場)をめぐる昭和32年から昭和34年までの物語である。三角座は架空の劇団だが、実在の喜劇役者に言及する科白もあり、何故か川端康成が実名で登場する。当時の喜劇役者たちの世界に詳しい作者が、実在の喜劇役者を架空の登場人物に反映させたと思われる芝居である。
タイトルや題材から、この芝居はコメディだろうと予感していた。確かにコメディの要素もあるが、コメディの世界をややシニカルに描いたストレートプレイである。喜劇役者の実像は舞台上の姿とは異なり気難しくて怒りっぽかったりもする。そんな当然の姿を昭和レトロの世界で繰り広げる舞台である。
昭和32年と言えば私は田舎の小学3年生、ほとんど記憶はない。昭和34年頃になるとテレビ番組の記憶がかなり残っている。この芝居が描く昭和32~34年の世界にはひしひしと懐かしさを感じる。芝居の冒頭で、通行人が電気屋の白黒テレビに映っている脱線トリオをに見入って「こいつら面白いな。もうエノケン・ロッパじゃないな」とつぶやく。この感覚もかろうじてわかる。
それにしても、私より15歳若いケラリーノ・サンドロヴィッチ(1963年生まれ)が、昭和30年代初期に詳しいのには感心する。
多彩な役者が出演している(チラシ参照)。誰が主演とは言えない群像劇である。上演時間は3時間45分(20分休憩を含む)。かなり長いが退屈はしない。
喜劇を上演する新宿の三角座(劇団&劇場)をめぐる昭和32年から昭和34年までの物語である。三角座は架空の劇団だが、実在の喜劇役者に言及する科白もあり、何故か川端康成が実名で登場する。当時の喜劇役者たちの世界に詳しい作者が、実在の喜劇役者を架空の登場人物に反映させたと思われる芝居である。
タイトルや題材から、この芝居はコメディだろうと予感していた。確かにコメディの要素もあるが、コメディの世界をややシニカルに描いたストレートプレイである。喜劇役者の実像は舞台上の姿とは異なり気難しくて怒りっぽかったりもする。そんな当然の姿を昭和レトロの世界で繰り広げる舞台である。
昭和32年と言えば私は田舎の小学3年生、ほとんど記憶はない。昭和34年頃になるとテレビ番組の記憶がかなり残っている。この芝居が描く昭和32~34年の世界にはひしひしと懐かしさを感じる。芝居の冒頭で、通行人が電気屋の白黒テレビに映っている脱線トリオをに見入って「こいつら面白いな。もうエノケン・ロッパじゃないな」とつぶやく。この感覚もかろうじてわかる。
それにしても、私より15歳若いケラリーノ・サンドロヴィッチ(1963年生まれ)が、昭和30年代初期に詳しいのには感心する。
俵万智さんの19年前の小説を読んで「勁さ」を感じた ― 2022年08月15日
俵万智さんの初期の歌集やエッセイは何冊か読んだが、その後は、沖縄への関心から数年前に『旅の人、島の人』を読んだぐらいだ。これは石垣島での子育て生活を中心に綴ったエッセイ集だった。
この夏、新聞で俵万智さんの名を目にすることが多い気がする。7月6日には、「本日はサラダ記念日」という記事がいくつか見かけ、書架の『サラダ記念日』を引っ張り出して読み返したりもした。で、ネット検索をしていて、彼女が小説を1編だけ書いていたと知り、古書で入手して読んだ。
『トリアングル』(俵万智/中公文庫/2006年9月)
2003年に新聞連載し、2004年に単行本になった小説の文庫版である。主人公は33歳の女性フリーライター。妻子ある12歳年上のカメラマンと恋人関係にあり、七つ年下のフリーター(ミュージシャン志望)とも付き合い始める――そんな人間模様を主人公の一人称で綴った小説で、随所に主人公の折々の心情を表す短歌が挿入されている。
この小説を読んで、少し驚いた。フィクションではあろうが主人公に作者が色濃く反映されていると感じざるを得ないのだ。憶測を呼びそうな内容を赤裸々に描いている。赤裸々と言っても全然ドロドロしていなくて、メルヘンのような印象を受けるのが不思議である。
この小説を新聞連載した2003年、俵万智さんは男児を出産しシングルマザーになっている。当時、その件がどのように報じられたか、私にはほとんど記憶がない。この小説のことも知らなかった。2006年には『TANNKA 短歌』というタイトルで映画化もされたそうだが、それも知らなかった。
19年前の小説を読んで、俵万智さんが男児出産に際して堂々と率直に小説の形で「シングルマザー決意表明」をしていたと知った。あらためて「天然系のしなやかさ」「自然体の勁さ」のようなものを感じた。
この夏、新聞で俵万智さんの名を目にすることが多い気がする。7月6日には、「本日はサラダ記念日」という記事がいくつか見かけ、書架の『サラダ記念日』を引っ張り出して読み返したりもした。で、ネット検索をしていて、彼女が小説を1編だけ書いていたと知り、古書で入手して読んだ。
『トリアングル』(俵万智/中公文庫/2006年9月)
2003年に新聞連載し、2004年に単行本になった小説の文庫版である。主人公は33歳の女性フリーライター。妻子ある12歳年上のカメラマンと恋人関係にあり、七つ年下のフリーター(ミュージシャン志望)とも付き合い始める――そんな人間模様を主人公の一人称で綴った小説で、随所に主人公の折々の心情を表す短歌が挿入されている。
この小説を読んで、少し驚いた。フィクションではあろうが主人公に作者が色濃く反映されていると感じざるを得ないのだ。憶測を呼びそうな内容を赤裸々に描いている。赤裸々と言っても全然ドロドロしていなくて、メルヘンのような印象を受けるのが不思議である。
この小説を新聞連載した2003年、俵万智さんは男児を出産しシングルマザーになっている。当時、その件がどのように報じられたか、私にはほとんど記憶がない。この小説のことも知らなかった。2006年には『TANNKA 短歌』というタイトルで映画化もされたそうだが、それも知らなかった。
19年前の小説を読んで、俵万智さんが男児出産に際して堂々と率直に小説の形で「シングルマザー決意表明」をしていたと知った。あらためて「天然系のしなやかさ」「自然体の勁さ」のようなものを感じた。
『東京四次元紀行』は、ちょっと切ない掌篇小説集 ― 2022年08月17日
コラムニスト・小田嶋隆の最初で最後の小説集を読んだ。
『東京四次元紀行』(小田嶋隆/イースト・プレス)
発行日は2022年6月5日、その19日後の6月24日に作者は病死(享年65歳)。「あとがき」の日付は5月吉日、そこで次のように語っている。
「自分で書いてみると、小説は、読むことよりも書くことの方が断然楽しいジャンルの文章だと思うようになった。(…)今では、小説こそ素人が書くべきジャンルの文芸である、と考えるようになった(もっと早い時期に書いていればよかったなあ)。」
この( )内は、死期を悟った著者の無念のつぶやきに思えてしまう。
本書は32篇の短篇を収録している。内23篇は東京23区に対応していて「残骸――新宿区」「地元――江戸川区」のようなタイトルになっている。他の9篇は必ずしも特定の地域に対応しているわけではない。『東京四次元紀行』は本書全体を包む表題で、収録短篇のタイトルではない。東京に棲息する人々の空間と時間の点描を集積した掌篇集である。
『東京四次元紀行』と謳いながら23区だけなのは、三多摩地区在住の私としては取り残された気分で少々残念である。最後の作品「月日は百代の過客にして」の舞台が国立なので、とりあえずよしとする(この小説は他の31篇とはテイストが少し異なる)。私は調布市在住だが……。
それぞれが独立した話のなかには連作風の数篇もある。時間が自在に飛ぶ話が多く、追憶の風景と現代の光景が重なり合って、ちらりと「四次元」を感じさせたりもする。登場人物は、まっとうな人もいるが、不器用な人物や変人が多く、アル中も何人かいる。彼らの織りなす切ない状況を切り取っていて、不思議な余韻がある。どれも読みやすくて面白い。
著者への予断のせいかもしれないが、コラム一歩前の風情を湛えた小説だと感じた。
『東京四次元紀行』(小田嶋隆/イースト・プレス)
発行日は2022年6月5日、その19日後の6月24日に作者は病死(享年65歳)。「あとがき」の日付は5月吉日、そこで次のように語っている。
「自分で書いてみると、小説は、読むことよりも書くことの方が断然楽しいジャンルの文章だと思うようになった。(…)今では、小説こそ素人が書くべきジャンルの文芸である、と考えるようになった(もっと早い時期に書いていればよかったなあ)。」
この( )内は、死期を悟った著者の無念のつぶやきに思えてしまう。
本書は32篇の短篇を収録している。内23篇は東京23区に対応していて「残骸――新宿区」「地元――江戸川区」のようなタイトルになっている。他の9篇は必ずしも特定の地域に対応しているわけではない。『東京四次元紀行』は本書全体を包む表題で、収録短篇のタイトルではない。東京に棲息する人々の空間と時間の点描を集積した掌篇集である。
『東京四次元紀行』と謳いながら23区だけなのは、三多摩地区在住の私としては取り残された気分で少々残念である。最後の作品「月日は百代の過客にして」の舞台が国立なので、とりあえずよしとする(この小説は他の31篇とはテイストが少し異なる)。私は調布市在住だが……。
それぞれが独立した話のなかには連作風の数篇もある。時間が自在に飛ぶ話が多く、追憶の風景と現代の光景が重なり合って、ちらりと「四次元」を感じさせたりもする。登場人物は、まっとうな人もいるが、不器用な人物や変人が多く、アル中も何人かいる。彼らの織りなす切ない状況を切り取っていて、不思議な余韻がある。どれも読みやすくて面白い。
著者への予断のせいかもしれないが、コラム一歩前の風情を湛えた小説だと感じた。
昔の新書『都市の文明イスラーム』は刺激的 ― 2022年08月19日
何冊かイスラーム史の概説書を読み、もう少しアプローチしたくなり、次の新書を読んだ。
『都市の文明イスラーム(新書イスラームの世界史①)』(佐藤次高+鈴木董・編/ 講談社現代新書/1993.9)
30年近く昔に出た「新書イスラームの世界史(全3巻)」の第1巻である。「都市の文明」というタイトルでイスラーム史の成り立ちを捉えているのが目を引く。5人の研究者(佐藤次高、後藤明、清水宏祐、長谷部史彦、私市正年)の分担執筆で、7世紀から16世紀初頭までの約900年を概説している。イスラーム文明が世界の先端で輝いていた時代である。
本書全体のトーンは、西欧に対するイスラームの先進性の確認であり、巻頭の「序言」には次のような記述がある。
「西ヨーロッパが封建制の時代をむかえて、統一国家をつくるべくもなかった時代に、イスラーム世界では広大な地域(オリエント世界と地中海世界)を統合する巨大国家が建設され、その保護のもとで高度に洗練された都市文明を生み出したことが、世界史の展開をリードする要因となった。」
ルネサンス以前の西欧がイスラーム世界から多くを学んださまを、明治日本になぞらえたりもしている。
「明治以降の日本人が近代ヨーロッパを手本にしたように、中世ヨーロッパ人は、コルドバやグラナダに留学してイスラーム文化を学ぶことに、強いあこがれの気持を抱き続けた。」
そんな西欧が、結局はイスラームから十分には学び得なかった。それが、現在の西欧の姿だ、という指摘には驚いた。次のような見解はユニークだと思う。
「文化的には後進地域であったヨーロッパが、先進地域の中東世界と接触し、多くのことを学ぶことができた。(…)ただし、人や物のモビリティーの高さというイスラーム世界の特質そのものを、彼らが理解することはついになかった。「市民権」という名のもとに外国人を締め出そうとする現代の動きも、物の流通を考えなかった社会主義が崩壊したのも、その根は古く、この時代あたりまでさかのぼれるともいえそうだ。」
「十字軍国家の時代にフランクは、シリア・エジプトの高度な貨幣経済や文字文化から多くのことを得た。しかし、その後の歴史が教えているように、多様な諸個人の共生を前提とする中東民衆の豊かな生活文化からは、結局あまりよく学べなかったようである。」
先進的だったイスラーム世界もやがて変容していく。そのさまは「寛容」から「非寛容」への移行に対応している。興隆と寛容、衰退と非寛容は、どちらがニワトリか卵かはわからないが深く関連しているようだ。普遍的な教訓だと思う。
本書ではトルコ民族の西進(突厥帝国からアナトリアへ)について次のように述べている。興味深い指摘だ。
「ある意味では現在でも、アナトリアのトルコ化は完成していないともいえるかもしれない。東部アナトリアにはクルド系の人々が多いし、南部にはアラブ系の住民もいるからである。」
「世界史の流れをみれば、トルコ民族の西方移動はいまも続いており、ドイツにおける出稼ぎ労働者問題も、その流れで理解すべきであるかもしれない。」
30年近く昔の新書から新鮮な刺激をいくつか得ることができた。
『都市の文明イスラーム(新書イスラームの世界史①)』(佐藤次高+鈴木董・編/ 講談社現代新書/1993.9)
30年近く昔に出た「新書イスラームの世界史(全3巻)」の第1巻である。「都市の文明」というタイトルでイスラーム史の成り立ちを捉えているのが目を引く。5人の研究者(佐藤次高、後藤明、清水宏祐、長谷部史彦、私市正年)の分担執筆で、7世紀から16世紀初頭までの約900年を概説している。イスラーム文明が世界の先端で輝いていた時代である。
本書全体のトーンは、西欧に対するイスラームの先進性の確認であり、巻頭の「序言」には次のような記述がある。
「西ヨーロッパが封建制の時代をむかえて、統一国家をつくるべくもなかった時代に、イスラーム世界では広大な地域(オリエント世界と地中海世界)を統合する巨大国家が建設され、その保護のもとで高度に洗練された都市文明を生み出したことが、世界史の展開をリードする要因となった。」
ルネサンス以前の西欧がイスラーム世界から多くを学んださまを、明治日本になぞらえたりもしている。
「明治以降の日本人が近代ヨーロッパを手本にしたように、中世ヨーロッパ人は、コルドバやグラナダに留学してイスラーム文化を学ぶことに、強いあこがれの気持を抱き続けた。」
そんな西欧が、結局はイスラームから十分には学び得なかった。それが、現在の西欧の姿だ、という指摘には驚いた。次のような見解はユニークだと思う。
「文化的には後進地域であったヨーロッパが、先進地域の中東世界と接触し、多くのことを学ぶことができた。(…)ただし、人や物のモビリティーの高さというイスラーム世界の特質そのものを、彼らが理解することはついになかった。「市民権」という名のもとに外国人を締め出そうとする現代の動きも、物の流通を考えなかった社会主義が崩壊したのも、その根は古く、この時代あたりまでさかのぼれるともいえそうだ。」
「十字軍国家の時代にフランクは、シリア・エジプトの高度な貨幣経済や文字文化から多くのことを得た。しかし、その後の歴史が教えているように、多様な諸個人の共生を前提とする中東民衆の豊かな生活文化からは、結局あまりよく学べなかったようである。」
先進的だったイスラーム世界もやがて変容していく。そのさまは「寛容」から「非寛容」への移行に対応している。興隆と寛容、衰退と非寛容は、どちらがニワトリか卵かはわからないが深く関連しているようだ。普遍的な教訓だと思う。
本書ではトルコ民族の西進(突厥帝国からアナトリアへ)について次のように述べている。興味深い指摘だ。
「ある意味では現在でも、アナトリアのトルコ化は完成していないともいえるかもしれない。東部アナトリアにはクルド系の人々が多いし、南部にはアラブ系の住民もいるからである。」
「世界史の流れをみれば、トルコ民族の西方移動はいまも続いており、ドイツにおける出稼ぎ労働者問題も、その流れで理解すべきであるかもしれない。」
30年近く昔の新書から新鮮な刺激をいくつか得ることができた。
23年ぶりに『頭痛肩こり樋口一葉』を観た ― 2022年08月21日
紀伊國屋サザンシアターでこまつ座公演『頭痛肩こり樋口一葉』(作:井上ひさし、演出:栗山民也、出演:貫地谷しほり、増子倭文江、熊谷真実、香寿たつき、瀬戸さおり、若村麻由美)を観た。
こまつ座旗揚げ公演(38年前の1984年)の演目で、その後何度も上演されている。私は1999年の公演(演出:木村光一、出演:有森也実、安奈淳、岩崎加根子、風間舞子、新橋耐子、渡辺梓)を同じサザンシアターで観ている。そのとき、戯曲も読んだ。しかし、23年前の記憶は霞んでいる。ぼんやりした雰囲気がかすかに浮かぶだけだ。
観劇に先だって戯曲の前半だけ読んだが、記憶は甦らず初読とあまり変わらない。後半は読まず、観劇中のデジャブを期待した。だが、記憶の底にかすかに残るシーンを待っていても、ついにそれは現れない。この芝居と他の芝居の記憶が混ざり合っていたようだ。
23年ぶりに観た『頭痛肩こり樋口一葉』は、やはりうまくできた芝居である。秀逸なタイトルが内容を的確に表している。貧乏のなか、24歳で夭折した樋口一葉(貫地谷しほり)の姿を、演劇でしか表現できない手法で描出している。
舞台は一葉の住む借家、部屋には大きな仏壇がある。この空間で、明治23年から明治30年までの盂蘭盆や新盆のシーンが年替わりで演じられる。樋口一葉19歳のときから死後までの「お盆」シーンであり、樋口一葉にしか見えない幽霊・花蛍(若村麻由美)が毎回のお盆に登場する。最後は一葉も幽霊姿での登場になる。
舞台を縦横に動き回る花蛍の役どころが抜群に面白い。花蛍の存在によって仏壇のある小さな借家に社会や世界が色濃く投影される仕掛けになっている。
女性6人の芝居で、6人それぞれが過不足なく典型的な役割を担っているのにも感心した。
観劇後、しばらくして気づいた。23年前に観た芝居の内容はほとんど失念していたが、私の頭の中にある樋口一葉のイメージは、この芝居によって作られた部分がかなり大きいようだ。
こまつ座旗揚げ公演(38年前の1984年)の演目で、その後何度も上演されている。私は1999年の公演(演出:木村光一、出演:有森也実、安奈淳、岩崎加根子、風間舞子、新橋耐子、渡辺梓)を同じサザンシアターで観ている。そのとき、戯曲も読んだ。しかし、23年前の記憶は霞んでいる。ぼんやりした雰囲気がかすかに浮かぶだけだ。
観劇に先だって戯曲の前半だけ読んだが、記憶は甦らず初読とあまり変わらない。後半は読まず、観劇中のデジャブを期待した。だが、記憶の底にかすかに残るシーンを待っていても、ついにそれは現れない。この芝居と他の芝居の記憶が混ざり合っていたようだ。
23年ぶりに観た『頭痛肩こり樋口一葉』は、やはりうまくできた芝居である。秀逸なタイトルが内容を的確に表している。貧乏のなか、24歳で夭折した樋口一葉(貫地谷しほり)の姿を、演劇でしか表現できない手法で描出している。
舞台は一葉の住む借家、部屋には大きな仏壇がある。この空間で、明治23年から明治30年までの盂蘭盆や新盆のシーンが年替わりで演じられる。樋口一葉19歳のときから死後までの「お盆」シーンであり、樋口一葉にしか見えない幽霊・花蛍(若村麻由美)が毎回のお盆に登場する。最後は一葉も幽霊姿での登場になる。
舞台を縦横に動き回る花蛍の役どころが抜群に面白い。花蛍の存在によって仏壇のある小さな借家に社会や世界が色濃く投影される仕掛けになっている。
女性6人の芝居で、6人それぞれが過不足なく典型的な役割を担っているのにも感心した。
観劇後、しばらくして気づいた。23年前に観た芝居の内容はほとんど失念していたが、私の頭の中にある樋口一葉のイメージは、この芝居によって作られた部分がかなり大きいようだ。
『イスラムの陰に』(前嶋信次)はユニークな史書 ― 2022年08月23日
先日読んだ『都市の文明イスラーム』に両目をつぶされたカリフの話が出てくる。カリフが大アミール(大将軍)の傀儡となったブワイフ朝(932-1062)の頃である。この件についてもう少し詳しく知りたく、ネット検索で見つけた次の本を読んだ。
『イスラムの陰に(生活の世界歴史7)』(前嶋信次/河出文庫/1991.10)
原版は1970年刊行、かなり古い本だ。前嶋信次(1903-1983)は日本のイスラム史研究の泰斗である。私は昨年1月、この著者の『イスラム世界(世界の歴史8)』を読み、講談調とも言える独特の語り口にしびれた。本書も前嶋先生のマイペース気味の談義が魅力的である。
約半世紀前に河出書房から「生活の世界歴史」(全10巻)という叢書の1冊で、10世紀頃のイスラム世界の社会や文化を、次の六つのタイトルに分けて描いている。
帝王譜――カリフのいきざま
翰墨譜――教育と文学
都城譜――ある法官の茶飲み話
コルドバ図巻――市街と住民
田園図巻――コルドバ歳時記
愛恋図巻――鳩の首輪
何ともユニークな命名の章立てである。翰墨(かんぼく)という難しい言葉は辞書を引いて「筆と墨。広く、文学に関すること」と知った。
イスラム世界には、当時の社会や、そこで生活する人々の姿を表した多様な史料が残っている。本書は、そんな史料のエッセンスを著者が洒脱な語り口で紹介する形になっている。ときに、やや脱線気味に研究史談義になったりするのも楽しい。
私の目当てだった「目をつぶされたカリフ」の話は冒頭の「帝王譜――カリフのいきざま」に出てくる。目をつぶされたカリフは3人いたが、その後は、悲惨な末路をとげることなく長寿を保ったカリフが続く。著者はそれを「徒に強いものにあらがうことなく、長いものには巻かれろという保身の術がうまくなったためであろう」と述べている。
哀れなカリフだけでなく、とんでもない奇行のカリフの紹介もあって面白い。
『イスラムの陰に(生活の世界歴史7)』(前嶋信次/河出文庫/1991.10)
原版は1970年刊行、かなり古い本だ。前嶋信次(1903-1983)は日本のイスラム史研究の泰斗である。私は昨年1月、この著者の『イスラム世界(世界の歴史8)』を読み、講談調とも言える独特の語り口にしびれた。本書も前嶋先生のマイペース気味の談義が魅力的である。
約半世紀前に河出書房から「生活の世界歴史」(全10巻)という叢書の1冊で、10世紀頃のイスラム世界の社会や文化を、次の六つのタイトルに分けて描いている。
帝王譜――カリフのいきざま
翰墨譜――教育と文学
都城譜――ある法官の茶飲み話
コルドバ図巻――市街と住民
田園図巻――コルドバ歳時記
愛恋図巻――鳩の首輪
何ともユニークな命名の章立てである。翰墨(かんぼく)という難しい言葉は辞書を引いて「筆と墨。広く、文学に関すること」と知った。
イスラム世界には、当時の社会や、そこで生活する人々の姿を表した多様な史料が残っている。本書は、そんな史料のエッセンスを著者が洒脱な語り口で紹介する形になっている。ときに、やや脱線気味に研究史談義になったりするのも楽しい。
私の目当てだった「目をつぶされたカリフ」の話は冒頭の「帝王譜――カリフのいきざま」に出てくる。目をつぶされたカリフは3人いたが、その後は、悲惨な末路をとげることなく長寿を保ったカリフが続く。著者はそれを「徒に強いものにあらがうことなく、長いものには巻かれろという保身の術がうまくなったためであろう」と述べている。
哀れなカリフだけでなく、とんでもない奇行のカリフの紹介もあって面白い。
道化師の人生に20世紀の100年を重ねた加藤健一の一人芝居 ― 2022年08月25日
本多劇場で加藤健一の一人芝居『スカラムーシュ・ジョーンズあるいは七つの白い仮面』(作:ジャスティン・ブッチャー、演出:鵜山仁)を観た。
加藤健一事務所は1980年に一人芝居『審判』を上演するために立ち上げたそうだ(私は彼の倅による『審判』を2カ月前に観た)。一人芝居は得意なのかとも思うが、パンフレットでは「演者には、足がすくむほどの重圧がのしかかってきます」とある。
1999年12月31日の夜、道化師スカラムーシュが人生を振り返る独白劇である。この道化師の誕生日は1899年12月31日、百歳を迎えて己の人生に反映された20世紀を物語る仕掛けになっている。上演時間は1時間40分、舞台上には小道具・大道具が賑やかに配置され、スクリーン投影も活用して時代の変遷や空間の移動を表現している。
スカラムーシュはトリニダード・トバゴで褐色の肌のジプシー娼婦から生まれるが、その肌は抜けるように白い。その後、孤児となり奴隷となり、西アフリカのセネガルに渡り、エチオピアやエジプトを経て、ムソリーニ政権下のヴェニスに至る。そして、ミラノを経てクラクフ(ポーランド)へ行き、ついには強制収容所に入れられる。
この強制収容所のシーンが印象深い。収容所に入れられたものの、その身分は保留となり、犠牲者たちを埋める墓掘りの仕事に従事する。そこで、殺されていく子供たちのために道化師としてパントマイムを披露する。銃殺された犠牲者が天使になって昇天するパントマイムである。
戦争が終わり捕らえられたスカラムーシュは戦争裁判にかけられるも釈放され、ロンドンにたどり着く。時は1951年、つまりスカラーシュは51歳である。人生を振りかえる道化師の1999年大晦日の独白はここで終わり、道化師として過ごしたその後の50年は語られない。語られない50年が余韻として響く芝居である。
加藤健一事務所は1980年に一人芝居『審判』を上演するために立ち上げたそうだ(私は彼の倅による『審判』を2カ月前に観た)。一人芝居は得意なのかとも思うが、パンフレットでは「演者には、足がすくむほどの重圧がのしかかってきます」とある。
1999年12月31日の夜、道化師スカラムーシュが人生を振り返る独白劇である。この道化師の誕生日は1899年12月31日、百歳を迎えて己の人生に反映された20世紀を物語る仕掛けになっている。上演時間は1時間40分、舞台上には小道具・大道具が賑やかに配置され、スクリーン投影も活用して時代の変遷や空間の移動を表現している。
スカラムーシュはトリニダード・トバゴで褐色の肌のジプシー娼婦から生まれるが、その肌は抜けるように白い。その後、孤児となり奴隷となり、西アフリカのセネガルに渡り、エチオピアやエジプトを経て、ムソリーニ政権下のヴェニスに至る。そして、ミラノを経てクラクフ(ポーランド)へ行き、ついには強制収容所に入れられる。
この強制収容所のシーンが印象深い。収容所に入れられたものの、その身分は保留となり、犠牲者たちを埋める墓掘りの仕事に従事する。そこで、殺されていく子供たちのために道化師としてパントマイムを披露する。銃殺された犠牲者が天使になって昇天するパントマイムである。
戦争が終わり捕らえられたスカラムーシュは戦争裁判にかけられるも釈放され、ロンドンにたどり着く。時は1951年、つまりスカラーシュは51歳である。人生を振りかえる道化師の1999年大晦日の独白はここで終わり、道化師として過ごしたその後の50年は語られない。語られない50年が余韻として響く芝居である。





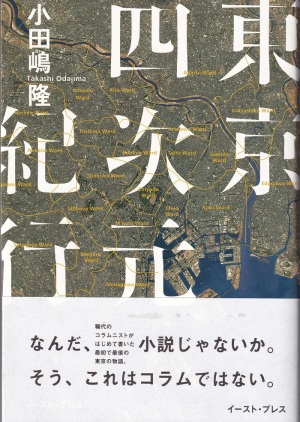
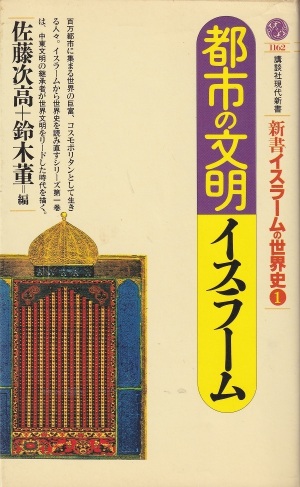



最近のコメント