2022年上半期に読んだ本のマイ・ベスト3 ― 2022年07月01日
2022年もはや半年が過ぎた。今年前半に読んだ本のマイ・ベスト3を選んだ。
『ヒュパティア:後期ローマ帝国の女性知識人』(エドワード・J・ワッソ/中西恭子訳/白水社)
『暁の宇品:陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』(堀川恵子/講談社)
『異常:アノマリー』(エルヴェル・テリエ/加藤かおり訳/早川書房)
『ヒュパティア:後期ローマ帝国の女性知識人』(エドワード・J・ワッソ/中西恭子訳/白水社)
『暁の宇品:陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』(堀川恵子/講談社)
『異常:アノマリー』(エルヴェル・テリエ/加藤かおり訳/早川書房)
小田嶋隆の訃報に接し、昔の本を読み返した ― 2022年07月03日
先日(2022.6.25)の朝刊にコラムニスト小田嶋隆の訃報が載っていた。享年65歳、私より8歳若い。熱心な読者とは言えないが、若い頃からその異才に注目し、最近もラジオなどのコメントに接していた。早すぎる死に暗然とする。わが書架にある彼の著書2冊を追悼気分で読み返した。
『我が心はICにあらず』(小田嶋隆/BNN/1988.3)
『超・反知性主義入門』(小田嶋隆/日経BP社/2015.9)
小田嶋隆の文章に初めて接したのがいつかは定かでない。『Bug News 創刊号』(1985.8)かもしれない。『我が心はICにあらず』は1984年から1987年までに『Bug News』などに掲載した文章をまとめたものだ。私が本書を書店の店頭で見つけてすぐに購入したのは、そのタイトルに惹かれたからである。
『我が心はICにあらず』はもちろん高橋和巳の『我が心は石にあらず』(原典は詩経・邶風)のもじりである。パソコン関連の文集にこんな屈折したタイトルを付けるとは「若いのに変な奴だ」と筆者に興味を抱いた。当時、私は39歳、小田嶋隆は31歳、私から見れば十分に若い世代のライターだった。
『我が心はICにあらず』はパソコンが普及し始めた時代のハッカー(オタク?)やパソコン業界の話題を、巧みな比喩を交えた辛辣でウイットに富んだ文書で綴っている。三十数年ぶりに読み返して、あの時代のパソコンを取り巻く世界の活気を懐かしく思い返した。
本書の後も小田嶋隆の文章には雑誌などで折に触れて接していた。いまも鮮明に記憶しているのは、2000年を迎えるとコンピュータ・システムのエラーが続出して大変な事態になるというY2K問題(2000年問題)への小田嶋隆の発言だ。彼は「心配する必要はない。大丈夫だ」と断言していた。彼のような意見を述べる人は少なかったと思う。結果は彼の言う通りだった。
テクニカル・ライターとして出発した小田嶋隆は辛辣なコラムニストになり、政治や社会へ切り込んでいく。7年前に出た『超・反知性主義入門』は、「日経ビジネスオンライン」に掲載したコラムを編集したもので、森本あんり(ICU副学長・小田島隆の小中高時代の同級生)との対談も収録している。この対談で、自身がアルコール中毒を克服した経緯を語っているのが興味深い。
彼がアル中になったのは、罵詈雑言気味になってきた自身の文章が自分にも返ってきて酒に逃げるようになったからだそうだ。コラムニストとして生きていく大変さがわかる。『超・反知性主義入門』に収録されているコラムでは、本音指向・非情指向・功利指向などへの疑義を提示し、環境問題は神学論争になると論じている。共感できる指摘である。
世の中にエッセイストや文筆家と呼ばれる人は多いが、芯が通ったコラムニストと呼ばれる人はさほどはいないような気がする。惜しい人が逝ったと思う。
『我が心はICにあらず』(小田嶋隆/BNN/1988.3)
『超・反知性主義入門』(小田嶋隆/日経BP社/2015.9)
小田嶋隆の文章に初めて接したのがいつかは定かでない。『Bug News 創刊号』(1985.8)かもしれない。『我が心はICにあらず』は1984年から1987年までに『Bug News』などに掲載した文章をまとめたものだ。私が本書を書店の店頭で見つけてすぐに購入したのは、そのタイトルに惹かれたからである。
『我が心はICにあらず』はもちろん高橋和巳の『我が心は石にあらず』(原典は詩経・邶風)のもじりである。パソコン関連の文集にこんな屈折したタイトルを付けるとは「若いのに変な奴だ」と筆者に興味を抱いた。当時、私は39歳、小田嶋隆は31歳、私から見れば十分に若い世代のライターだった。
『我が心はICにあらず』はパソコンが普及し始めた時代のハッカー(オタク?)やパソコン業界の話題を、巧みな比喩を交えた辛辣でウイットに富んだ文書で綴っている。三十数年ぶりに読み返して、あの時代のパソコンを取り巻く世界の活気を懐かしく思い返した。
本書の後も小田嶋隆の文章には雑誌などで折に触れて接していた。いまも鮮明に記憶しているのは、2000年を迎えるとコンピュータ・システムのエラーが続出して大変な事態になるというY2K問題(2000年問題)への小田嶋隆の発言だ。彼は「心配する必要はない。大丈夫だ」と断言していた。彼のような意見を述べる人は少なかったと思う。結果は彼の言う通りだった。
テクニカル・ライターとして出発した小田嶋隆は辛辣なコラムニストになり、政治や社会へ切り込んでいく。7年前に出た『超・反知性主義入門』は、「日経ビジネスオンライン」に掲載したコラムを編集したもので、森本あんり(ICU副学長・小田島隆の小中高時代の同級生)との対談も収録している。この対談で、自身がアルコール中毒を克服した経緯を語っているのが興味深い。
彼がアル中になったのは、罵詈雑言気味になってきた自身の文章が自分にも返ってきて酒に逃げるようになったからだそうだ。コラムニストとして生きていく大変さがわかる。『超・反知性主義入門』に収録されているコラムでは、本音指向・非情指向・功利指向などへの疑義を提示し、環境問題は神学論争になると論じている。共感できる指摘である。
世の中にエッセイストや文筆家と呼ばれる人は多いが、芯が通ったコラムニストと呼ばれる人はさほどはいないような気がする。惜しい人が逝ったと思う。
渡辺えり作・演出『私の恋人』は3人30役の音楽劇 ― 2022年07月05日
本多劇場で『私の恋人 beyond』(原作:上田岳弘、作・演出:渡辺えり、出演:渡辺えり、小日向文世、のん、他)を観た。渡辺えりの舞台を観るのは初めてだ……と言いたいが、40年前(1982年)にパルコ劇場の『少女仮面』に主演したのを観ている(当時は渡辺えり子)。だが、劇団3〇〇の舞台は観ていないし、彼女の作・演出の芝居がどんなものかを知らずに今日まできた。だから、気分としては渡辺えりの舞台初体験である。
67歳になった渡辺えりは元気溌剌だった。『私の恋人 beyond』はかなり入り組んだ音楽劇で、目まぐるしい展開に目を奪われた。想像していた以上に複雑な構成で、わかりやすくはない。
この芝居の原作は上田岳弘の小説(三島賞受賞作)である。私はその小説を読んでいない。小説を読んでいればもう少しわかったかもしれないが、渡辺えりの創作が8割だそうだ。この芝居は初演が3年前で、再演に際して「beyond」を付加したようだ。観劇後、ロビーで販売していた台本を購入した。いまひとつ掴み難い芝居だったので、台本で内容を確認したくなったのだ。観たばかりの舞台を反芻しながら台本を読むと、多少は見晴らしがよくなった。
この芝居は3人の主役が30の役を演ずる。一人十役である。休憩なしの1時間50分の間、舞台上でめまぐるしく役が変化していく。
現代に生きるフリーターが、自分の前世は「私の恋人」を追い求めるクロマニョン人やアウシュヴィッツのユダヤ人だと信じている……そんな設定だから、舞台上の時間は10万年を行き来し、一人の役者にさまざまな人物が憑依する。火星人の漬物まで登場する。何とも不思議な舞台である。
67歳になった渡辺えりは元気溌剌だった。『私の恋人 beyond』はかなり入り組んだ音楽劇で、目まぐるしい展開に目を奪われた。想像していた以上に複雑な構成で、わかりやすくはない。
この芝居の原作は上田岳弘の小説(三島賞受賞作)である。私はその小説を読んでいない。小説を読んでいればもう少しわかったかもしれないが、渡辺えりの創作が8割だそうだ。この芝居は初演が3年前で、再演に際して「beyond」を付加したようだ。観劇後、ロビーで販売していた台本を購入した。いまひとつ掴み難い芝居だったので、台本で内容を確認したくなったのだ。観たばかりの舞台を反芻しながら台本を読むと、多少は見晴らしがよくなった。
この芝居は3人の主役が30の役を演ずる。一人十役である。休憩なしの1時間50分の間、舞台上でめまぐるしく役が変化していく。
現代に生きるフリーターが、自分の前世は「私の恋人」を追い求めるクロマニョン人やアウシュヴィッツのユダヤ人だと信じている……そんな設定だから、舞台上の時間は10万年を行き来し、一人の役者にさまざまな人物が憑依する。火星人の漬物まで登場する。何とも不思議な舞台である。
当事者が語る『朝日新聞政治部』は告発と再生祈念の書 ― 2022年07月07日
元・朝日新聞政治部記者が書いた次の本が、新聞広告で「驚きの反響 発売即3刷」と大きく宣伝されていた。
『朝日新聞政治部』(鮫島浩/講談社)
書店の店頭に平積みされているだろうと思い、中規模書店に入って平積みの本を捜したがなかなか見つからない。目立たない場所に積まれているのをやっと見つけて購入した。新聞社の政治部に関する暴露本への一般読者の関心ランキングは高くないのだと感じた。増刷を重ねているようだが…
2014年に朝日新聞で発生した「池上コラム掲載拒否」「吉田調書問題」「慰安婦記事取り消し」を巡って、当事者の一人でもあった元・政治部記者が実情を語った本である。これら一連の「事件」に関する記述は本書の後半で、前半は著者が朝日新聞入社してから政治部デスクになるまでの体験記になっている。
このような構成になっているのは、本書が単なる「事件」告発の書ではなく、著者が27年間の記者生活で体験した大新聞というメディアの体質と現状に警鐘を鳴らす書だからである。
本書が指摘しているのは大新聞に棲息する人々の傲慢性、自己保身性、官僚制などである。「この会社は頭から順々に腐ってしまった」という表現もある。本書に著者の自己正当化がないとは言えないだろうが、著者の無念が伝わってくる。概ね共感できる内容だった。
部数減少の趨勢にある大新聞の厳しさはわかるが、このまま消滅していいとは思わない。新たなジャーナリズムの姿を見出して再生してほしいと思う。
『朝日新聞政治部』(鮫島浩/講談社)
書店の店頭に平積みされているだろうと思い、中規模書店に入って平積みの本を捜したがなかなか見つからない。目立たない場所に積まれているのをやっと見つけて購入した。新聞社の政治部に関する暴露本への一般読者の関心ランキングは高くないのだと感じた。増刷を重ねているようだが…
2014年に朝日新聞で発生した「池上コラム掲載拒否」「吉田調書問題」「慰安婦記事取り消し」を巡って、当事者の一人でもあった元・政治部記者が実情を語った本である。これら一連の「事件」に関する記述は本書の後半で、前半は著者が朝日新聞入社してから政治部デスクになるまでの体験記になっている。
このような構成になっているのは、本書が単なる「事件」告発の書ではなく、著者が27年間の記者生活で体験した大新聞というメディアの体質と現状に警鐘を鳴らす書だからである。
本書が指摘しているのは大新聞に棲息する人々の傲慢性、自己保身性、官僚制などである。「この会社は頭から順々に腐ってしまった」という表現もある。本書に著者の自己正当化がないとは言えないだろうが、著者の無念が伝わってくる。概ね共感できる内容だった。
部数減少の趨勢にある大新聞の厳しさはわかるが、このまま消滅していいとは思わない。新たなジャーナリズムの姿を見出して再生してほしいと思う。
前近代を知らずに近代は語れない――『ヨーロッパ覇権以前』 ― 2022年07月10日
西欧が興隆する以前の前近代世界システムを論じた次の本を読んだ。
『ヨーロッパ覇権以前:もうひとつの世界システム(上)(下)』(アブー=ルゴド/佐藤次高・斯波義信・高山博・三浦徹訳/岩波現代文庫)
オビに「グローバル・ヒストリーの古典的名著 待望の文庫化!」と謳っている。原著が出たのは33年前の1989年、翻訳が出たのは2001年、それが今年(2022年)4月に岩波現代文庫になった。
著者(女性)は都市社会学者だそうだ。13世紀の国際交易網を8つの回路からなる「世界システム」として描いている(画像参照)。これらの回路の結節点にあるのが都市であり、それぞれの都市の位置づけや消長を通して前近代の交易を論じている。
かなり専門的な内容で、未知の研究者の論考が頻出する。私には少々難しかったが何とか読了した。桑原隲蔵の蒲寿庚(南宋末から元初期のムスリム商人・軍人)に関する論考の紹介が出てきたときは、日本人研究者の国際性を感じて少しうれしかった。
私はウォーラーステインの『近代世界システム』を読んでいないし、読む気力もない。「世界システム」とは何かもよくわかっていない。それでも、本書を読むと13世紀の世界システムの姿がおぼろに浮かびあがる。また、それが西欧覇権の近代世界システムに置き換わったことの不思議と偶然に歴史の妙を感じる。
本書は西欧中心史観を転換する書である。西欧的視点を感じる箇所もあるが、16世紀以降の西欧が海外進出によって発展し、近代資本主義が誕生した、という短絡的な見方に批判的で、西欧が見落としていた前近代の広大な世界に着目している。西欧が興隆する以前の中国・中央アジア・東南アジア・インド・中東はグローバルな経済社会を構築していて、西欧はその周縁のひとつに過ぎなかった。
本書が論じる13世紀の世界システムは、「海運・航海の技術」「生産・売買の社会組織」「協業・資本蓄積のメカニズム」「貨幣鋳造・交換の技術」などにおいて、後の西欧覇権の時代に匹敵するものを既にもっていた。アジアや中東にウエイトがあったグローバル経済が、数世紀後にはなぜ西欧覇権の世界に転換したのか。西欧が中東・アジアを打ち負かしたのではない。13世紀世界システムが退化・衰退し、その空白に西欧が進出したのだ……それが著者の見解である。
十分に理解できたわけではないが興味深い見方である。旧システムが新システムに転換する際に「ルールの変化」があり、旧システムは新システムのルールに対応できなかったという見方も面白い。旧システムは連携・共存と相互忍耐から利益を引き出す対等関係の世界だった。しかし、新システムは略奪と覇権の世界だった。退化しつつあった旧システムは新システムに対して無防備だったのだ。ナルホドと思ってしまう。前近代を知らずに近代史だけを学ぶのは危険だと感じる。
本書巻末の「もうひとつの世界システム――岩波現代文庫によせて」では、訳者の一人である三浦徹氏が、本書をめぐるその後の論調を要領よく紹介している。グローバル・ヒストリーへの興味が喚起される。
『ヨーロッパ覇権以前:もうひとつの世界システム(上)(下)』(アブー=ルゴド/佐藤次高・斯波義信・高山博・三浦徹訳/岩波現代文庫)
オビに「グローバル・ヒストリーの古典的名著 待望の文庫化!」と謳っている。原著が出たのは33年前の1989年、翻訳が出たのは2001年、それが今年(2022年)4月に岩波現代文庫になった。
著者(女性)は都市社会学者だそうだ。13世紀の国際交易網を8つの回路からなる「世界システム」として描いている(画像参照)。これらの回路の結節点にあるのが都市であり、それぞれの都市の位置づけや消長を通して前近代の交易を論じている。
かなり専門的な内容で、未知の研究者の論考が頻出する。私には少々難しかったが何とか読了した。桑原隲蔵の蒲寿庚(南宋末から元初期のムスリム商人・軍人)に関する論考の紹介が出てきたときは、日本人研究者の国際性を感じて少しうれしかった。
私はウォーラーステインの『近代世界システム』を読んでいないし、読む気力もない。「世界システム」とは何かもよくわかっていない。それでも、本書を読むと13世紀の世界システムの姿がおぼろに浮かびあがる。また、それが西欧覇権の近代世界システムに置き換わったことの不思議と偶然に歴史の妙を感じる。
本書は西欧中心史観を転換する書である。西欧的視点を感じる箇所もあるが、16世紀以降の西欧が海外進出によって発展し、近代資本主義が誕生した、という短絡的な見方に批判的で、西欧が見落としていた前近代の広大な世界に着目している。西欧が興隆する以前の中国・中央アジア・東南アジア・インド・中東はグローバルな経済社会を構築していて、西欧はその周縁のひとつに過ぎなかった。
本書が論じる13世紀の世界システムは、「海運・航海の技術」「生産・売買の社会組織」「協業・資本蓄積のメカニズム」「貨幣鋳造・交換の技術」などにおいて、後の西欧覇権の時代に匹敵するものを既にもっていた。アジアや中東にウエイトがあったグローバル経済が、数世紀後にはなぜ西欧覇権の世界に転換したのか。西欧が中東・アジアを打ち負かしたのではない。13世紀世界システムが退化・衰退し、その空白に西欧が進出したのだ……それが著者の見解である。
十分に理解できたわけではないが興味深い見方である。旧システムが新システムに転換する際に「ルールの変化」があり、旧システムは新システムのルールに対応できなかったという見方も面白い。旧システムは連携・共存と相互忍耐から利益を引き出す対等関係の世界だった。しかし、新システムは略奪と覇権の世界だった。退化しつつあった旧システムは新システムに対して無防備だったのだ。ナルホドと思ってしまう。前近代を知らずに近代史だけを学ぶのは危険だと感じる。
本書巻末の「もうひとつの世界システム――岩波現代文庫によせて」では、訳者の一人である三浦徹氏が、本書をめぐるその後の論調を要領よく紹介している。グローバル・ヒストリーへの興味が喚起される。
医学者が書いた『皮膚、人間のすべてを語る』は広範な考察の書 ― 2022年07月18日
約1カ月前(2022年6月19日)の朝日新聞と日経新聞の書評欄が同じ本を取り上げていて、面白そうな本だと興味を抱いた。次の本である。
『皮膚、人間のすべてを語る:万能の臓器と巡る10章』(モンティ・ライアン/塩崎香織訳/みすず書房)
皮膚を研究する医学者が「皮膚とは何か」を多面的に全10章で解説・考察している。冒頭は皮膚に関する医学的・生物学的な話である。やがて脳科学がからんでくる。さらには心理学・社会学・宗教学にまで論点が広がっていく。面白い本だ。これまで皮膚について考えたことがほとんどなかったので、皮膚を巡る考察がこんなにも広がるのかと驚いた。
本書では、著者が医師として接してきたさまざまな皮膚病の事例を紹介している。そんな恐ろしげな症状を読んでいるだけで体がムズムズする。たしかに皮膚とは不可思議で身近な「臓器」である。
人類(先住民)の多様な皮膚の色(メラミンの量)の分布は地球に降り注ぐ紫外線の量の分布と重なるそうだ。きわめて当然の話である。しかし、かつては長い時間をかけて移動した人類がいまでは短時間で移動できるようになった。そのため、皮膚の色と紫外線量に齟齬が発生し、それが皮膚がんの発生やビタミンD欠乏につながっている。わかりやすい説明であり、文明のパラドックスを感じざるをえない。
本書後半の次のような指摘が印象に残った。
「おそらく脳を除けば、皮膚以上に人間が聖なるものとして大きな意味をもたせる臓器はない。皮膚は神学者を夢中にさせ、哲学者を虜にしてきた。また、私たちの日常的な考え方に意外なかたちで作用するものである。」
「皮膚は肉体と森羅万象とを分かつバリアとして機能していながら、肉的な欲望に身を任せる私たちのきわめて重要な一部でもある。皮膚は感覚器官であり、ありてにいえば、欲望と罪と恥が入り混じるスリルと興奮に満ちた最大の生殖器だ。」
本書を読んでいて安部公房の『他人の顔』を思い出した。事故で顔面がケロイドになった技術者が精巧な仮面を作る話である。著者は文学の領域までには踏み込んでいないが、皮膚を巡る文学もいろいろありそうに思える。
『皮膚、人間のすべてを語る:万能の臓器と巡る10章』(モンティ・ライアン/塩崎香織訳/みすず書房)
皮膚を研究する医学者が「皮膚とは何か」を多面的に全10章で解説・考察している。冒頭は皮膚に関する医学的・生物学的な話である。やがて脳科学がからんでくる。さらには心理学・社会学・宗教学にまで論点が広がっていく。面白い本だ。これまで皮膚について考えたことがほとんどなかったので、皮膚を巡る考察がこんなにも広がるのかと驚いた。
本書では、著者が医師として接してきたさまざまな皮膚病の事例を紹介している。そんな恐ろしげな症状を読んでいるだけで体がムズムズする。たしかに皮膚とは不可思議で身近な「臓器」である。
人類(先住民)の多様な皮膚の色(メラミンの量)の分布は地球に降り注ぐ紫外線の量の分布と重なるそうだ。きわめて当然の話である。しかし、かつては長い時間をかけて移動した人類がいまでは短時間で移動できるようになった。そのため、皮膚の色と紫外線量に齟齬が発生し、それが皮膚がんの発生やビタミンD欠乏につながっている。わかりやすい説明であり、文明のパラドックスを感じざるをえない。
本書後半の次のような指摘が印象に残った。
「おそらく脳を除けば、皮膚以上に人間が聖なるものとして大きな意味をもたせる臓器はない。皮膚は神学者を夢中にさせ、哲学者を虜にしてきた。また、私たちの日常的な考え方に意外なかたちで作用するものである。」
「皮膚は肉体と森羅万象とを分かつバリアとして機能していながら、肉的な欲望に身を任せる私たちのきわめて重要な一部でもある。皮膚は感覚器官であり、ありてにいえば、欲望と罪と恥が入り混じるスリルと興奮に満ちた最大の生殖器だ。」
本書を読んでいて安部公房の『他人の顔』を思い出した。事故で顔面がケロイドになった技術者が精巧な仮面を作る話である。著者は文学の領域までには踏み込んでいないが、皮膚を巡る文学もいろいろありそうに思える。
ビザンツ帝国はいつ滅亡したのか? ― 2022年07月23日
私はローマ帝国を継承したビザンツ帝国(東ローマ帝国)の歴史をよく把握していない。頭の中で不鮮明に霞んでいる。ローマ史関連の本をかなり読んできたので、西ローマ帝国滅亡(476年)までの歴史の流れは多少はイメージできる。だが、西ローマ帝国滅亡の後1000年も持続したビザンツ帝国の歴史がイメージできないのだ(コンスタンティノープル陥落は1453年)。で、ビザンツ帝国の歴史の概要を把握しようと思い、次の新書を読んだ。
『ビザンツ帝国:千年の興亡と皇帝たち』(中谷功治/中公新書/2020.6)
本書は一般向け概説書だが教科書的な通史ではない。いくつかのテーマを中心に年代を進めながらビザンツ帝国の様子を語っている。また、従来の研究成果や最新の研究動向を紹介しつつ著者の見解も表明している。私には馴染みの薄い分野の研究者たちの世界を垣間見た気がして面白かった。
ビザンツ史には「マケドニア・ルネサンス」という言葉があるそうだ。9世紀中頃から10世紀までの文芸復興を指すが、最近では「ルネサンス」という派手な表現に慎重な動きが出ているそうだ。研究者たちが何でも「ルネサンス」と称する「使いたい放題」への反省らしい。「社会的流動」という言葉も使われ過ぎらしい。研究者には、自分の研究している時代が活気のない閉塞的な社会だと認めたくない傾向があるそうだ。面白い指摘である。
著者はビザンツ皇帝の嚆矢をコンスタンティヌス1世(大帝:在324-337)としている。西ローマ帝国滅亡の150年前にビザンツ帝国はスタートし、1000年以上存続したわけだ。この間の皇帝の数は約90名で、本書はそのすべてのリストを分割して掲載している。このリストでは簒奪帝に*を付している。数えてみると簒奪帝は30人だ。かなりの頻度の政変に思える。
私は特に根拠なく、ビザンツ皇帝を文弱で狡猾な専制君主のようにイメージしていた。本書を読んで、ビザンツ皇帝の大半が軍人で自ら遠征を指揮した皇帝も多いのが意外だった。
ビザンツ皇帝は自身を「ローマ皇帝」としていたが、7世紀には公用語がギリシア語になる。実質は多民族の帝国だったようだ。本書で興味深く感じたのは、ビザンツ帝国の知識人フォティオスがヘロドトスの『歴史』をペルシア人の「王(バシレウス)」たちの物語として読んでいたという話である。当時の世界の中心が東方寄りだったのだと思われる。
本書の著者はビザンツ帝国は1204年に消滅したと見なしている。この年、第4回十字軍の攻撃でコンスタンティノープルが陥落し、ラテン帝国が成立する。ラテン帝国はすぐに滅亡し、ミカエル8世パライオロゴスがビザンツ皇帝となり、パライオロゴス朝が発足し、1453年まで続く。200年以上続いたこの王朝は群雄のひとつにすぎず、すでに「帝国」ではなかった――それが著者の見解である。オスマン帝国によるコンスタンティノープル陥落以前に「帝国」は縮小・消滅していたのだ。
本書によってビザンツ帝国に関する新たな知見を得ることができた。しかし、その1000年の歴史は私の頭の中では依然としてぼんやりしている。あらためて、把みがたい帝国だと思う。
『ビザンツ帝国:千年の興亡と皇帝たち』(中谷功治/中公新書/2020.6)
本書は一般向け概説書だが教科書的な通史ではない。いくつかのテーマを中心に年代を進めながらビザンツ帝国の様子を語っている。また、従来の研究成果や最新の研究動向を紹介しつつ著者の見解も表明している。私には馴染みの薄い分野の研究者たちの世界を垣間見た気がして面白かった。
ビザンツ史には「マケドニア・ルネサンス」という言葉があるそうだ。9世紀中頃から10世紀までの文芸復興を指すが、最近では「ルネサンス」という派手な表現に慎重な動きが出ているそうだ。研究者たちが何でも「ルネサンス」と称する「使いたい放題」への反省らしい。「社会的流動」という言葉も使われ過ぎらしい。研究者には、自分の研究している時代が活気のない閉塞的な社会だと認めたくない傾向があるそうだ。面白い指摘である。
著者はビザンツ皇帝の嚆矢をコンスタンティヌス1世(大帝:在324-337)としている。西ローマ帝国滅亡の150年前にビザンツ帝国はスタートし、1000年以上存続したわけだ。この間の皇帝の数は約90名で、本書はそのすべてのリストを分割して掲載している。このリストでは簒奪帝に*を付している。数えてみると簒奪帝は30人だ。かなりの頻度の政変に思える。
私は特に根拠なく、ビザンツ皇帝を文弱で狡猾な専制君主のようにイメージしていた。本書を読んで、ビザンツ皇帝の大半が軍人で自ら遠征を指揮した皇帝も多いのが意外だった。
ビザンツ皇帝は自身を「ローマ皇帝」としていたが、7世紀には公用語がギリシア語になる。実質は多民族の帝国だったようだ。本書で興味深く感じたのは、ビザンツ帝国の知識人フォティオスがヘロドトスの『歴史』をペルシア人の「王(バシレウス)」たちの物語として読んでいたという話である。当時の世界の中心が東方寄りだったのだと思われる。
本書の著者はビザンツ帝国は1204年に消滅したと見なしている。この年、第4回十字軍の攻撃でコンスタンティノープルが陥落し、ラテン帝国が成立する。ラテン帝国はすぐに滅亡し、ミカエル8世パライオロゴスがビザンツ皇帝となり、パライオロゴス朝が発足し、1453年まで続く。200年以上続いたこの王朝は群雄のひとつにすぎず、すでに「帝国」ではなかった――それが著者の見解である。オスマン帝国によるコンスタンティノープル陥落以前に「帝国」は縮小・消滅していたのだ。
本書によってビザンツ帝国に関する新たな知見を得ることができた。しかし、その1000年の歴史は私の頭の中では依然としてぼんやりしている。あらためて、把みがたい帝国だと思う。
碩学のガイドで遺跡巡りをした気分 ― 2022年07月26日
ビザンツ帝国に関する次の本を読んだ。
『図説ビザンツ帝国:刻印された千年の記憶』(根津由喜夫/ふくろうの本/河出書房新社)
各ページのほぼ半分が写真である。眺めて楽しい本だ。著者はビザンツ帝国史の研究者で、美術史家ではない。ビザンツの芸術作品や建築を技法や様式といった視点で紹介するのではなく、歴史学の視点で解説している。
本書は全9章で、それぞれの章が特定の都市や地域の遺跡や遺物(建物や壁画など)の紹介になっている。だが、旅行ガイドではない。千年の時間を章ごとにたどる歴史概説である。第1章は「4~6世紀」で舞台はコンスタンティノープル、最終章(第9章)は「14~15世紀」で舞台はトレビゾンド――といった具合である。
それぞれの時代解説が特定の地域の遺物紹介とうまくマッチするのだろうかと思うが、時間の流れと空間の移動がよく工夫されている。コンスタンティノープルなどは複数の章(第1章、第5章、第8章)の舞台になっている。本書が辿る場所は、コンスタンティノープル、ラヴェンナ、テサロニキ、カッパドキアからアトラス山へ、バチコヴォとフェライ、キプロス、トレビゾンドの7カ所である。
掲載されている写真(風景、建物、壁画)の大半は著者自身が現地で撮影したものである。だから、遺跡や遺物を巡って歴史を語る口調に臨場感があり、自ずと熱を帯びてくる。碩学のガイドで、歴史概説や考察に耳を傾けながら遺跡巡りをしている気分になる。充実した旅を追体験するような本である。
『図説ビザンツ帝国:刻印された千年の記憶』(根津由喜夫/ふくろうの本/河出書房新社)
各ページのほぼ半分が写真である。眺めて楽しい本だ。著者はビザンツ帝国史の研究者で、美術史家ではない。ビザンツの芸術作品や建築を技法や様式といった視点で紹介するのではなく、歴史学の視点で解説している。
本書は全9章で、それぞれの章が特定の都市や地域の遺跡や遺物(建物や壁画など)の紹介になっている。だが、旅行ガイドではない。千年の時間を章ごとにたどる歴史概説である。第1章は「4~6世紀」で舞台はコンスタンティノープル、最終章(第9章)は「14~15世紀」で舞台はトレビゾンド――といった具合である。
それぞれの時代解説が特定の地域の遺物紹介とうまくマッチするのだろうかと思うが、時間の流れと空間の移動がよく工夫されている。コンスタンティノープルなどは複数の章(第1章、第5章、第8章)の舞台になっている。本書が辿る場所は、コンスタンティノープル、ラヴェンナ、テサロニキ、カッパドキアからアトラス山へ、バチコヴォとフェライ、キプロス、トレビゾンドの7カ所である。
掲載されている写真(風景、建物、壁画)の大半は著者自身が現地で撮影したものである。だから、遺跡や遺物を巡って歴史を語る口調に臨場感があり、自ずと熱を帯びてくる。碩学のガイドで、歴史概説や考察に耳を傾けながら遺跡巡りをしている気分になる。充実した旅を追体験するような本である。
『火星の人』の作者の新作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を読んだ ― 2022年07月29日
火星に一人取り残された宇宙飛行士のサバイバルを描いた『火星の人』は、独特の語り口の秀逸なSF小説だった。同じ作家の新作と聞いて次のSF長編を読んだ。
『プロジェクト・ヘイル・メアリー(上)(下)』(アンディ・ウィアー/小野田和子訳/早川書房)
「ヘイル・メアリー」はラテン語の「アヴェ・マリア」で、アメリカン・フットボールでのイチかバチかの神頼みのロングパスを意味するそうだ。
この小説の軽妙な語り口は『火星の人』に似ている。オタク的とも言える科学談義も面白い。飽きさせない展開で一気に読める。物語のスケールは『火星の人』を大きく上回るが、緊迫が続くハラハラドキドキ感の面白さは『火星の人』の方が上だと感じた。
「ここはどこ? 私は誰?」で始まる物語で、話の内容に立ち入るとネタバレになる。だから詳しい紹介は控える。粗筋を3行で紹介すれば、バカバカしいほどにありふれた破滅テーマ宇宙SFと見なされるかもしれない。そんなプリミティブな話でもリアリティのあるディティールで紡ぎあげれば斬新で感動的な物語になる。
記憶を失った主人公が周辺の状況をサイエンス思考で探りながら次第に記憶を取り戻し、自分が何者であるか、どんなミッションを負っているかを少しづつ認識していく前半が面白い。科学談義の部分は学生向けの科学副読本にしたくなるような内容だ。中盤で記憶喪失になった真の原因が明かされる。これは少々意外な展開だった。
中盤を過ぎてからは先が見えた気がした。この先もいくつかの困難と克服を繰り返しながら成功にたどり着くのだろうと思った。しかし結末は私の予想とは違った。いい終わり方である。感心した。
『プロジェクト・ヘイル・メアリー(上)(下)』(アンディ・ウィアー/小野田和子訳/早川書房)
「ヘイル・メアリー」はラテン語の「アヴェ・マリア」で、アメリカン・フットボールでのイチかバチかの神頼みのロングパスを意味するそうだ。
この小説の軽妙な語り口は『火星の人』に似ている。オタク的とも言える科学談義も面白い。飽きさせない展開で一気に読める。物語のスケールは『火星の人』を大きく上回るが、緊迫が続くハラハラドキドキ感の面白さは『火星の人』の方が上だと感じた。
「ここはどこ? 私は誰?」で始まる物語で、話の内容に立ち入るとネタバレになる。だから詳しい紹介は控える。粗筋を3行で紹介すれば、バカバカしいほどにありふれた破滅テーマ宇宙SFと見なされるかもしれない。そんなプリミティブな話でもリアリティのあるディティールで紡ぎあげれば斬新で感動的な物語になる。
記憶を失った主人公が周辺の状況をサイエンス思考で探りながら次第に記憶を取り戻し、自分が何者であるか、どんなミッションを負っているかを少しづつ認識していく前半が面白い。科学談義の部分は学生向けの科学副読本にしたくなるような内容だ。中盤で記憶喪失になった真の原因が明かされる。これは少々意外な展開だった。
中盤を過ぎてからは先が見えた気がした。この先もいくつかの困難と克服を繰り返しながら成功にたどり着くのだろうと思った。しかし結末は私の予想とは違った。いい終わり方である。感心した。
先週も今週もコロナで観劇できなかった ― 2022年07月31日
本日(2022年7月31日)、NODA・MAP公演 『Q:A Night At The Kabuki』(東京芸術劇場プレイハウス)を観る予定だったが、「公演関係者コロナ感染」で中止になった。7月29日の開幕を8月2日に延期するそうだ。何度も抽選を外れてやっと入手したチケットだったので残念である。
先週は、タカハ劇団公演 『ヒトラーを画家にする話』を観るために劇場(東京芸術劇場シアターイースト)まで出向き、「出演者コロナ感染のため中止」の貼り紙を見てスゴスゴと帰宅した。
最近、コロナによる公演中止が相次いでいる。「コロナ 公演中止」で検索すると山ほど出てくる。2年前にも公演が総崩れになり、数枚のチケットの払い戻し手続きをした。あのときは皆が閉門蟄居状態だったので息をひそめているしかなかった。だが、今回の公演中止はランダムな銃撃を浴びている気分で、運がよければ観劇できるのだ。客も落ち着かないが、出演者たちのストレスは大変だろうと同情する。
先週は、タカハ劇団公演 『ヒトラーを画家にする話』を観るために劇場(東京芸術劇場シアターイースト)まで出向き、「出演者コロナ感染のため中止」の貼り紙を見てスゴスゴと帰宅した。
最近、コロナによる公演中止が相次いでいる。「コロナ 公演中止」で検索すると山ほど出てくる。2年前にも公演が総崩れになり、数枚のチケットの払い戻し手続きをした。あのときは皆が閉門蟄居状態だったので息をひそめているしかなかった。だが、今回の公演中止はランダムな銃撃を浴びている気分で、運がよければ観劇できるのだ。客も落ち着かないが、出演者たちのストレスは大変だろうと同情する。



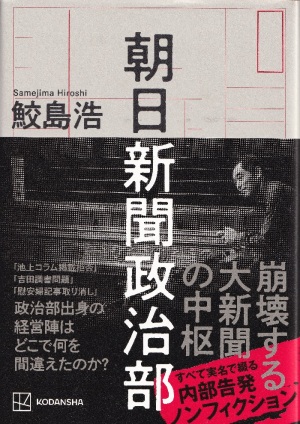


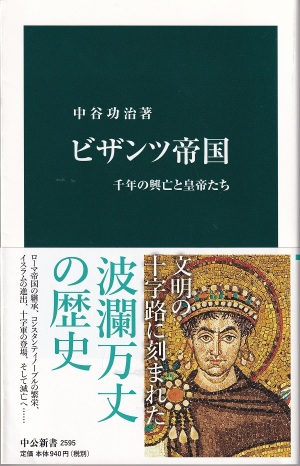



最近のコメント