『ヒトラーランド』は人々を惹きつける不気味で不思議な場所 ― 2015年04月11日
『ヒトラーランド:ナチの台頭を目撃した人々』(アンドリュー・ナゴルスキ/北村京子訳/作品社)は期待した以上に面白い本だった。
ナチス台頭の時代にベルリンに駐在していたジャーナリストや外交官たちが、同時代のヒトラーやナチスをどう見ていたかを、彼らが残した当時の記事・レポート・日記などで構成したノンフィクションである。そう聞くと、読む前からおよその内容が予測できる気がする。
あの時代、ナチスを肯定的に見る人から否定的に見る人までいろいろいただろうとは容易に推測できる。ハイデッカーのような知の巨人さえもナチスを支持していた時代だから、知性のレベルとナチスへの対応は関連なさそうだ。後世のわれわれが知っているナチスの行く末を予期した人もいれば、まったく予期できなかった人もいた。そんな内容の本だろうと思いながら本書を読み始めた。結末を知っているミステリーを楽しむ気分である。
結論から言えば、私を含めて多くの読者が予測したとおり、ナチスの台頭を目撃したジャーナリストや外交官たちのの中には、ナチスを過小評価した人もいれば、その危険性をかなり的確に予見していた人もいた、という内容の本である。もちろん、状況の進展によって人々の見解は変化していくわけで、個々のディティールが意外に面白い。
ただし、私が本書を期待以上に面白いと思ったのは、当時の人々が残した多様な見解が興味深いというより、それら全体から「歴史変動を目撃する高揚感」が伝わってくる点にある。
本書は、ナチス台頭の目撃者をアメリカ人だけに絞っている。それが本書の最大の特徴である。ドイツ人が自ら体験した同時代をどう見ていたかを知ることはもちろん重要だが、部外者の視点の方が同時代の事象を歴史の一コマとしてとらえやすいのかもしれない。間近でしか見えないものもあるが、少し離れなければ見えてこないものもある。ナチス台頭期におけるドイツとアメリカの微妙な関係と距離が、当時のアメリカ人たちを最も的確なナチスの観察者にしていると思われる。
本書は1923年のミュンヘン一揆の頃から1941年の真珠湾攻撃でアメリカが大戦に参戦するまでの期間を扱っている。ミュンヘン一揆以前には、ヒトラーに注目するジャーナリストや外交官はほとんどいなかったし、アメリカがドイツの敵国になってからは、彼らはドイツから退去させられたからだ。この間の約20年、アメリカはドイツやヨーロッパに対しては当事者ではなく中立的第三者に近かった。第一次大戦後のベルリンは政治の混乱と文化の躍動・爛熟のさなかにあり、アメリカの若者たちにとって、そこは最もホットで魅力的な場所だったらしい。
本書では次のような証言が引用されている。
「第一次大戦後、インテリ層や最先端の文化人は、パリでもロンドンでもニューヨークでもなく、ベルリンに集まっていた」「ベルリンはヨーロッパの真の首都だった。ヨーロッパの都市を走るすべての線路は、ベルリンに続いていた」(アメリカ人ミュージシャン)(P25)
「(ベルリンの街で起きていることは)まさしく文化的な暴動であり、パリやロンドンではいまだに大きな存在感を放つ堅苦しい伝統がない分、その奔放さはきわだっている」(アメリカ人記者)(P77)
当時のベルリンは1960年代末の新宿のような熱気に包まれた場所だったのだろうかと、戦後生まれ団塊世代の私は想像する。あの頃の日本は高度成長期だったが、1923年(ミュンヘン一揆の年)以降のドイツにもそれに似た情況があった。第一次大戦で疲弊したドイツはこの時期、アメリカからの投資によって一時的な繁栄を経験している。その頃に刊行された『わが闘争』はほとんど売れず、ナチス低迷の兆しも見られた。しかし、繁栄は1929年の暗黒の木曜日(世界大恐慌)によって終息し、ヒトラーの時代が始まる。
ミュンヘン一揆から開戦までのドイツは政治も文化もハチャメチャの時代で、そこに引き寄せられて集まってきたアメリカ人たちの見聞録が『ヒトラーランド』である。「ヒトラーランド」という言葉は1934年頃にアメリカ人記者の一人が使い始めたそうだ。「風変わりで、ますます不気味さを増しつつあるいっぽうで、人を惹きつけてやまない場所」(P256)の呼び名としては、異世界の趣があって秀逸だ。
「ヒトラーランド」となったドイツは、世界の人々が来訪するヨーロッパの中心地であると同時に、現代の北朝鮮や「イスラム国」、文化大革命期の中国などに似た要素をもつ不思議な場所だったようだ。その場所で、まさに歴史が大きく変動するのである。時代の渦中にあったアメリカ人のジャーナリストや外交官たちが、必ずしも変動の大きさを的確にとらえていたわけではないが、急速に変化していく情況の中で彼らが高揚していたことは確かだ。
本書の結びの一節は以下の通りだ。
「彼らは幸運だった。近代における恐怖の時代のはじまりを、その目で直接見ることができたからだ。そしてさらに幸運なことに、彼らはアメリカ人だった。だからこそ安全な特等席に座ったまま、そのすべてを眺めることができたのだ。彼らはまさしく特別な権利を享受した歴史の目撃者であった。」
その希有な体験をうらやましく思うのは、私だけではないだろう。
ナチス台頭の時代にベルリンに駐在していたジャーナリストや外交官たちが、同時代のヒトラーやナチスをどう見ていたかを、彼らが残した当時の記事・レポート・日記などで構成したノンフィクションである。そう聞くと、読む前からおよその内容が予測できる気がする。
あの時代、ナチスを肯定的に見る人から否定的に見る人までいろいろいただろうとは容易に推測できる。ハイデッカーのような知の巨人さえもナチスを支持していた時代だから、知性のレベルとナチスへの対応は関連なさそうだ。後世のわれわれが知っているナチスの行く末を予期した人もいれば、まったく予期できなかった人もいた。そんな内容の本だろうと思いながら本書を読み始めた。結末を知っているミステリーを楽しむ気分である。
結論から言えば、私を含めて多くの読者が予測したとおり、ナチスの台頭を目撃したジャーナリストや外交官たちのの中には、ナチスを過小評価した人もいれば、その危険性をかなり的確に予見していた人もいた、という内容の本である。もちろん、状況の進展によって人々の見解は変化していくわけで、個々のディティールが意外に面白い。
ただし、私が本書を期待以上に面白いと思ったのは、当時の人々が残した多様な見解が興味深いというより、それら全体から「歴史変動を目撃する高揚感」が伝わってくる点にある。
本書は、ナチス台頭の目撃者をアメリカ人だけに絞っている。それが本書の最大の特徴である。ドイツ人が自ら体験した同時代をどう見ていたかを知ることはもちろん重要だが、部外者の視点の方が同時代の事象を歴史の一コマとしてとらえやすいのかもしれない。間近でしか見えないものもあるが、少し離れなければ見えてこないものもある。ナチス台頭期におけるドイツとアメリカの微妙な関係と距離が、当時のアメリカ人たちを最も的確なナチスの観察者にしていると思われる。
本書は1923年のミュンヘン一揆の頃から1941年の真珠湾攻撃でアメリカが大戦に参戦するまでの期間を扱っている。ミュンヘン一揆以前には、ヒトラーに注目するジャーナリストや外交官はほとんどいなかったし、アメリカがドイツの敵国になってからは、彼らはドイツから退去させられたからだ。この間の約20年、アメリカはドイツやヨーロッパに対しては当事者ではなく中立的第三者に近かった。第一次大戦後のベルリンは政治の混乱と文化の躍動・爛熟のさなかにあり、アメリカの若者たちにとって、そこは最もホットで魅力的な場所だったらしい。
本書では次のような証言が引用されている。
「第一次大戦後、インテリ層や最先端の文化人は、パリでもロンドンでもニューヨークでもなく、ベルリンに集まっていた」「ベルリンはヨーロッパの真の首都だった。ヨーロッパの都市を走るすべての線路は、ベルリンに続いていた」(アメリカ人ミュージシャン)(P25)
「(ベルリンの街で起きていることは)まさしく文化的な暴動であり、パリやロンドンではいまだに大きな存在感を放つ堅苦しい伝統がない分、その奔放さはきわだっている」(アメリカ人記者)(P77)
当時のベルリンは1960年代末の新宿のような熱気に包まれた場所だったのだろうかと、戦後生まれ団塊世代の私は想像する。あの頃の日本は高度成長期だったが、1923年(ミュンヘン一揆の年)以降のドイツにもそれに似た情況があった。第一次大戦で疲弊したドイツはこの時期、アメリカからの投資によって一時的な繁栄を経験している。その頃に刊行された『わが闘争』はほとんど売れず、ナチス低迷の兆しも見られた。しかし、繁栄は1929年の暗黒の木曜日(世界大恐慌)によって終息し、ヒトラーの時代が始まる。
ミュンヘン一揆から開戦までのドイツは政治も文化もハチャメチャの時代で、そこに引き寄せられて集まってきたアメリカ人たちの見聞録が『ヒトラーランド』である。「ヒトラーランド」という言葉は1934年頃にアメリカ人記者の一人が使い始めたそうだ。「風変わりで、ますます不気味さを増しつつあるいっぽうで、人を惹きつけてやまない場所」(P256)の呼び名としては、異世界の趣があって秀逸だ。
「ヒトラーランド」となったドイツは、世界の人々が来訪するヨーロッパの中心地であると同時に、現代の北朝鮮や「イスラム国」、文化大革命期の中国などに似た要素をもつ不思議な場所だったようだ。その場所で、まさに歴史が大きく変動するのである。時代の渦中にあったアメリカ人のジャーナリストや外交官たちが、必ずしも変動の大きさを的確にとらえていたわけではないが、急速に変化していく情況の中で彼らが高揚していたことは確かだ。
本書の結びの一節は以下の通りだ。
「彼らは幸運だった。近代における恐怖の時代のはじまりを、その目で直接見ることができたからだ。そしてさらに幸運なことに、彼らはアメリカ人だった。だからこそ安全な特等席に座ったまま、そのすべてを眺めることができたのだ。彼らはまさしく特別な権利を享受した歴史の目撃者であった。」
その希有な体験をうらやましく思うのは、私だけではないだろう。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2015/04/11/7609118/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
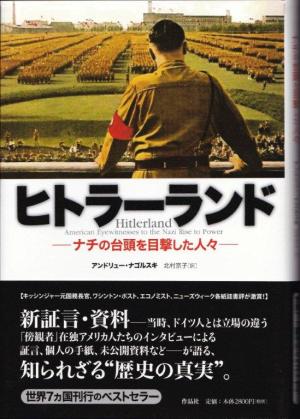
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。