『ダーウィンの進化論はどこまで正しいのか?』は難しかった ― 2025年11月25日
先日読んだ『進化論はいかに進化したか』(更科功)が面白く、もう少し進化論を勉強してみようと思い、昨年出た次の新書を読んだ。
『ダーウィンの進化論はどこまで正しいのか?:進化の仕組みを基礎から学ぶ』(河田雅圭/光文社新書)
著者は東北大名誉教授の進化学者である。研究者の現場報告の趣がある『進化という迷宮』(千葉聡)には、本書の著者・河田雅圭氏の名が何度か登場する。
サブタイトルに「進化の仕組みを基礎から学ぶ」とあり、最新の研究成果をふまえた一般向きの解説書だろう思って読み始めた。読み進めるに従って頭がついて行けなくなった。分子遺伝学のゴチャゴチャした話が私には難しいのだ。大学の専門課程の講義のようにも感じられた。もちろん、大学の講義内容を私が知っているわけではないが…。
本書にはアレルという用語が頻出する。本書冒頭の用語解説には「ゲノム上の同じ位置にある、変異を構成する配列。DNAの1塩基の変異によるアレルはSNPアレル、同一遺伝子の複数のタイプの1つであるアレルは対立遺伝子である」とある。何のコッチャという気分になる。わかりにくい所を読み飛ばしつつ何とか読了した。
著者は生真面目な研究者だと思う。用語の意味を厳密に検討するし、さまざまな事例に基づいた推論を紹介したうえで「不確かだ」「今後の研究が期待される」と表現することも多い。研究者としては当然の姿勢だろうが、読者は森の中の迷路を彷徨っている気分にもなる。
本書は4章から成る。「第1章 進化とは何か」「第2章 変異・多様性とは何か」「第3章 自然選択とは何か」「第4章 種・大進化とは何か」という構成だ。各章末には簡潔な「まとめ」があり、迷路を抜けて「まとめ」に辿り着くとホッとする。この「まとめ」をあらかじめ読んだうえで、本文をじっくり時間をかけてパズルを解くように再読すれば、多少はわかった気分になるかもしれない。
各章末の「まとめ」から、私が興味深く思った事柄は以下の通りだ。
・遺伝的多様性は、集団や種を存続させるために、維持されているわけではない。
・「種を存続」させるように自然選択などの進化プロセスが作用することはない。
・ドーキンス流の利己的遺伝子の見方は進化のプロセスを正しく表していない。
・小進化の機構を理解することなく、大進化は説明できない。進化機構には、依然として未解明なことも多く、今後の研究が期待される。
著者は、今西進化論や福岡伸一の「動的平衡」には、サイエンスの立場から批判的である。次の指摘が興味深い。
「現在、今西進化論を信奉する進化学者はいない。しかし、細胞が入れ替わっても個体は維持されるという「動的平衡」の考えを種に当てはめ「種の保存こそが生命にとって最大の目的」とする福岡伸一氏の思想は、西田哲学や今西進化論が形を変えて継承されているといえる。」
『ダーウィンの進化論はどこまで正しいのか?:進化の仕組みを基礎から学ぶ』(河田雅圭/光文社新書)
著者は東北大名誉教授の進化学者である。研究者の現場報告の趣がある『進化という迷宮』(千葉聡)には、本書の著者・河田雅圭氏の名が何度か登場する。
サブタイトルに「進化の仕組みを基礎から学ぶ」とあり、最新の研究成果をふまえた一般向きの解説書だろう思って読み始めた。読み進めるに従って頭がついて行けなくなった。分子遺伝学のゴチャゴチャした話が私には難しいのだ。大学の専門課程の講義のようにも感じられた。もちろん、大学の講義内容を私が知っているわけではないが…。
本書にはアレルという用語が頻出する。本書冒頭の用語解説には「ゲノム上の同じ位置にある、変異を構成する配列。DNAの1塩基の変異によるアレルはSNPアレル、同一遺伝子の複数のタイプの1つであるアレルは対立遺伝子である」とある。何のコッチャという気分になる。わかりにくい所を読み飛ばしつつ何とか読了した。
著者は生真面目な研究者だと思う。用語の意味を厳密に検討するし、さまざまな事例に基づいた推論を紹介したうえで「不確かだ」「今後の研究が期待される」と表現することも多い。研究者としては当然の姿勢だろうが、読者は森の中の迷路を彷徨っている気分にもなる。
本書は4章から成る。「第1章 進化とは何か」「第2章 変異・多様性とは何か」「第3章 自然選択とは何か」「第4章 種・大進化とは何か」という構成だ。各章末には簡潔な「まとめ」があり、迷路を抜けて「まとめ」に辿り着くとホッとする。この「まとめ」をあらかじめ読んだうえで、本文をじっくり時間をかけてパズルを解くように再読すれば、多少はわかった気分になるかもしれない。
各章末の「まとめ」から、私が興味深く思った事柄は以下の通りだ。
・遺伝的多様性は、集団や種を存続させるために、維持されているわけではない。
・「種を存続」させるように自然選択などの進化プロセスが作用することはない。
・ドーキンス流の利己的遺伝子の見方は進化のプロセスを正しく表していない。
・小進化の機構を理解することなく、大進化は説明できない。進化機構には、依然として未解明なことも多く、今後の研究が期待される。
著者は、今西進化論や福岡伸一の「動的平衡」には、サイエンスの立場から批判的である。次の指摘が興味深い。
「現在、今西進化論を信奉する進化学者はいない。しかし、細胞が入れ替わっても個体は維持されるという「動的平衡」の考えを種に当てはめ「種の保存こそが生命にとって最大の目的」とする福岡伸一氏の思想は、西田哲学や今西進化論が形を変えて継承されているといえる。」
『進化論はいかに進化したか』はわかりやすくて面白い ― 2025年11月14日
『進化という迷宮』(千葉聡)を読了して、未読棚の次の本が気がかりになったので読了した。
『進化論はいかに進化したか』(更科功/新潮選書/2019.1)
本書第1部「ダーウィンと進化学」の冒頭に次の述懐がある。
「進化学という分野は、何十年にもわたって同じような誤解やとんでもない説が、繰り返し主張されつづけている分野であり、現在でもその勢いは衰えていない。これは、物理や化学は生物の他の分野などには、あまり見られない特徴と言えるだろう。」
というわけで、現代の進化学を概説しつつ、ダーウィンの言説を現代の視点で検討している。わかりやすくて面白い。
ダーウィンは『種の起源』を何度も改訂し、そのたびに主張が微妙に変化している。だから、ダーウィンの言説をまとめるのは容易ではない。著者は、そんな事情を概説したうえで要領よく簡潔にダーウィン説を整理している。
生物が進化すること示したダーウインは、進化のメカニズムとして「自然選択」を提唱し、進化のプロセスとして「分岐進化」を提唱した。また、進化は連続的にゆっくり進むと考えていた。進化の漸進説である。
現在、「自然選択」には「安定化選択」と「方向性進化」があると考えられている。また、進化のメカニズムは「遺伝子浮動」「自然選択」「遺伝子交流」「突然変異」の4つとされている。これらの考えに基づいて推論すると「進化は進んだり止まったりの繰り返し」になる。形態がほとんど変化しない時期と急速に変化する時期が繰り返すのである。漸進ではないのだ。
本書で勉強になったのは木村資生の「中立説」の解説である。生物は自然選択よりも遺伝子浮動によって進化する場合が多いという。自然選択より偶然の方が重要だそうだ。興味深い話である。
また、今西進化論について1章を費やして解説しているのもうれしい。科学的な理論ではなく思想というべきもの――と見なしているようだ。
本書第2部「生物の歩んできた道」も非常に面白い。
「なぜ生物には車輪がないのか」という謎の検討も面白い。石原藤夫の傑作SF『ハイウェイ惑星』への言及を期待したが、それはなかった。
人類の直立二足歩行の進化を一夫一婦制に関連付けているのには驚いた。10年前に読んだ『家族進化論』(山極寿一)を連想した。
『進化論はいかに進化したか』(更科功/新潮選書/2019.1)
本書第1部「ダーウィンと進化学」の冒頭に次の述懐がある。
「進化学という分野は、何十年にもわたって同じような誤解やとんでもない説が、繰り返し主張されつづけている分野であり、現在でもその勢いは衰えていない。これは、物理や化学は生物の他の分野などには、あまり見られない特徴と言えるだろう。」
というわけで、現代の進化学を概説しつつ、ダーウィンの言説を現代の視点で検討している。わかりやすくて面白い。
ダーウィンは『種の起源』を何度も改訂し、そのたびに主張が微妙に変化している。だから、ダーウィンの言説をまとめるのは容易ではない。著者は、そんな事情を概説したうえで要領よく簡潔にダーウィン説を整理している。
生物が進化すること示したダーウインは、進化のメカニズムとして「自然選択」を提唱し、進化のプロセスとして「分岐進化」を提唱した。また、進化は連続的にゆっくり進むと考えていた。進化の漸進説である。
現在、「自然選択」には「安定化選択」と「方向性進化」があると考えられている。また、進化のメカニズムは「遺伝子浮動」「自然選択」「遺伝子交流」「突然変異」の4つとされている。これらの考えに基づいて推論すると「進化は進んだり止まったりの繰り返し」になる。形態がほとんど変化しない時期と急速に変化する時期が繰り返すのである。漸進ではないのだ。
本書で勉強になったのは木村資生の「中立説」の解説である。生物は自然選択よりも遺伝子浮動によって進化する場合が多いという。自然選択より偶然の方が重要だそうだ。興味深い話である。
また、今西進化論について1章を費やして解説しているのもうれしい。科学的な理論ではなく思想というべきもの――と見なしているようだ。
本書第2部「生物の歩んできた道」も非常に面白い。
「なぜ生物には車輪がないのか」という謎の検討も面白い。石原藤夫の傑作SF『ハイウェイ惑星』への言及を期待したが、それはなかった。
人類の直立二足歩行の進化を一夫一婦制に関連付けているのには驚いた。10年前に読んだ『家族進化論』(山極寿一)を連想した。
『進化という迷宮』は難しいが面白い ― 2025年10月23日
進化論は私の関心分野である。一般書を何冊か読み、『種の起源』も読んだ。だが、進化論をきちんと把握したとは思えない。わかったような気がしても、何かがするりと抜け落ちて釈然としない。そんな私の気分を表すようなタイトルの次の新書を読んだ。
『進化という迷宮:隠れた「調律者」を追え』(千葉聡/講談社現代新書)
著者は進化生物学と生態学の研究者である。私がこの著者の本を読むのは『ダーウィンの呪い』に次いで2冊目だ。
進化論の現状に関する解説書だろうと思って読み始めた。確かに解説書だが、探究の過程を語る書である。また、研究者としての著者の告白的体験談が随所に織り込まれていて、その部分がとても面白い。著者の周辺のさまざまな研究者の成果報告書でもある。
私には、本書が紹介する研究内容を理解するのは容易でなかった。咀嚼できたとは言えない。本書の内容を適切にまとめることができない。だが、興味深い本である。大進化は小進化の積み重ねで説明できるのか、進化は偶然の結果なのか必然の要因がはたらいているのか――といったことを探求している。
本書全般に登場する研究者は高名なグールド(1941-2002)である。著者の師匠の友人でもあり、著者自身も直接議論を交わしている。私はグールドの著書を読んだことはないが、以前に読んだ『理不尽な進化』でその名を知った。本書を読む限り、グールドはかなりわかりにくい研究者だ。考え方は変転している。でも、偉大な研究者だったようだ。
本書の冒頭、グールドの「時を遡る思考実験」を紹介している。進化の歴史を巻き戻して再生すると、同じような大進化は二度と起こらないという主張である。偶発性によって、進化の動画を巻き戻して再生するたびに以前とは似ても似つかぬ生物の世界になり、人類のような知的生命体は現れないという。
この思考実験に対して、何度再生しても人類や人類に似た知的生命体が進化するという反論が提示される。著者は、この反論に与していて、そこには偶発性を無力化する「調律者」がいるはずだと考える。本書は、その「調律者」の正体を追究する物語である、最終的にはその正体を暴いて幕を閉じる。何となくわかったような気もするが、やはり、本書を読み終えても依然として「進化という迷宮」をさまよっている気分である。
本書の主役はカタツムリのように思える。化石から現生種までさまざまなカタツムリが登場する。進化生物学研究におけるカタツムリの役割の大きさを知ると共に、フィールド・ワークの苛酷と研究者たちタフな肉体に圧倒された。研究現場の熱気が伝わってくる。
本書における著者はかなり饒舌である。SFやマンガへの言及も多い。『三体』(劉慈欣)、『継ぐのは誰だ』(小松左京)、『雷のような音』(ブラッドベリ)、『日の名残り』(カズオ・イスグロ)など私の記憶に残る作品も登場し、うれしくなった。手塚治虫の博士論文にまで言及しているのには驚いた。
『進化という迷宮:隠れた「調律者」を追え』(千葉聡/講談社現代新書)
著者は進化生物学と生態学の研究者である。私がこの著者の本を読むのは『ダーウィンの呪い』に次いで2冊目だ。
進化論の現状に関する解説書だろうと思って読み始めた。確かに解説書だが、探究の過程を語る書である。また、研究者としての著者の告白的体験談が随所に織り込まれていて、その部分がとても面白い。著者の周辺のさまざまな研究者の成果報告書でもある。
私には、本書が紹介する研究内容を理解するのは容易でなかった。咀嚼できたとは言えない。本書の内容を適切にまとめることができない。だが、興味深い本である。大進化は小進化の積み重ねで説明できるのか、進化は偶然の結果なのか必然の要因がはたらいているのか――といったことを探求している。
本書全般に登場する研究者は高名なグールド(1941-2002)である。著者の師匠の友人でもあり、著者自身も直接議論を交わしている。私はグールドの著書を読んだことはないが、以前に読んだ『理不尽な進化』でその名を知った。本書を読む限り、グールドはかなりわかりにくい研究者だ。考え方は変転している。でも、偉大な研究者だったようだ。
本書の冒頭、グールドの「時を遡る思考実験」を紹介している。進化の歴史を巻き戻して再生すると、同じような大進化は二度と起こらないという主張である。偶発性によって、進化の動画を巻き戻して再生するたびに以前とは似ても似つかぬ生物の世界になり、人類のような知的生命体は現れないという。
この思考実験に対して、何度再生しても人類や人類に似た知的生命体が進化するという反論が提示される。著者は、この反論に与していて、そこには偶発性を無力化する「調律者」がいるはずだと考える。本書は、その「調律者」の正体を追究する物語である、最終的にはその正体を暴いて幕を閉じる。何となくわかったような気もするが、やはり、本書を読み終えても依然として「進化という迷宮」をさまよっている気分である。
本書の主役はカタツムリのように思える。化石から現生種までさまざまなカタツムリが登場する。進化生物学研究におけるカタツムリの役割の大きさを知ると共に、フィールド・ワークの苛酷と研究者たちタフな肉体に圧倒された。研究現場の熱気が伝わってくる。
本書における著者はかなり饒舌である。SFやマンガへの言及も多い。『三体』(劉慈欣)、『継ぐのは誰だ』(小松左京)、『雷のような音』(ブラッドベリ)、『日の名残り』(カズオ・イスグロ)など私の記憶に残る作品も登場し、うれしくなった。手塚治虫の博士論文にまで言及しているのには驚いた。
自分のエッシャー鑑賞がいかにずさんだったかを知った ― 2025年03月06日
日経新聞(2025.1.25)や朝日新聞(2025.2.22)の書評が取り上げていた次の本を読んだ。
『エッシャー完全解読:なぜ不可能が可能に見えるのか』(近藤滋/みすず書房)
エッシャーの「不可能建築」と呼ばれる『物見の塔』『上昇と下降』『滝』などについて、視覚をごまかすためにどんな仕掛けが施されているかを読み解いた本である。とても面白い。著者は発生学・理論生物学の研究者である。本書の論考は著者の専門領域とも一部重なり合っている。
私は約半世紀前にエッシャーの画集を入手した。それなりにエッシャーの版画に親しんできたつもりだ。本書は、その画集をめくりながら読み進めた。私が気づいていなかった指摘が次々に出てきて、自分がいかに観ていなかったかを認識した。同時に、エッシャー鑑賞の新たな醍醐味を知った。
エッシャーの「不可能建築」は錯視を利用したトリック画である。錯視は面白い。私は、ペンローズの三角形(エッシャーは、これを『滝』に応用)の模型をペーパークラフトで作ったこともある。だが、エッシャーのトリック画を観て、フムフム面白いなと思うだけでそれ以上踏み込んで考えたことはなかった。
著者は、単なる錯視トリックではエッシャーの作品のようなリアリティは得られないと指摘し、エッシャーが仕掛けたさまざまな仕掛けを解き明かしている。
本書によって認識を新たにしたのは、錯視と遠近法の関係である。作品をリアルに表現するには遠近法が有効である。エッシャーの作品も遠近法を多用している。だが、遠近法を強調すると錯視効果が減衰する。錯視には遠近感のごまかしが関連しているのだ。私は、ペンローズの三角形の模型を作ったにもかかわらず、本書を読むまでその点に考えが及ばなかった。
本書の最大のポイントは、遠近法と錯視を両立させるためにエッシャーが仕掛けた工夫の解明である。ナルホドと感心した。
だが、私が最も驚いたのは『画廊』という作品が再帰的なドロステ画だとの指摘である。画面が極端に歪んでいくこの作品を、私は半世紀前に画集で観て、単純に「面白いな」と感じただけだった。これが再帰的な作品だとは昔から知られていたそうだ。あらためて画集の作品解説を読むと、ちゃんと書いてあった。検索すると、分かりやすい動画もあった。私は半世紀の年月を経て初めて気づいた。情けないが仕方ない。
著者が指摘するように、内側の世界と外側の世界を融合させるために螺旋構造を用いるというアイデアは秀逸である。著者は、螺旋を描いて成長する結晶がヒントになったのではと推測している。サイエンスの世界である。
『エッシャー完全解読:なぜ不可能が可能に見えるのか』(近藤滋/みすず書房)
エッシャーの「不可能建築」と呼ばれる『物見の塔』『上昇と下降』『滝』などについて、視覚をごまかすためにどんな仕掛けが施されているかを読み解いた本である。とても面白い。著者は発生学・理論生物学の研究者である。本書の論考は著者の専門領域とも一部重なり合っている。
私は約半世紀前にエッシャーの画集を入手した。それなりにエッシャーの版画に親しんできたつもりだ。本書は、その画集をめくりながら読み進めた。私が気づいていなかった指摘が次々に出てきて、自分がいかに観ていなかったかを認識した。同時に、エッシャー鑑賞の新たな醍醐味を知った。
エッシャーの「不可能建築」は錯視を利用したトリック画である。錯視は面白い。私は、ペンローズの三角形(エッシャーは、これを『滝』に応用)の模型をペーパークラフトで作ったこともある。だが、エッシャーのトリック画を観て、フムフム面白いなと思うだけでそれ以上踏み込んで考えたことはなかった。
著者は、単なる錯視トリックではエッシャーの作品のようなリアリティは得られないと指摘し、エッシャーが仕掛けたさまざまな仕掛けを解き明かしている。
本書によって認識を新たにしたのは、錯視と遠近法の関係である。作品をリアルに表現するには遠近法が有効である。エッシャーの作品も遠近法を多用している。だが、遠近法を強調すると錯視効果が減衰する。錯視には遠近感のごまかしが関連しているのだ。私は、ペンローズの三角形の模型を作ったにもかかわらず、本書を読むまでその点に考えが及ばなかった。
本書の最大のポイントは、遠近法と錯視を両立させるためにエッシャーが仕掛けた工夫の解明である。ナルホドと感心した。
だが、私が最も驚いたのは『画廊』という作品が再帰的なドロステ画だとの指摘である。画面が極端に歪んでいくこの作品を、私は半世紀前に画集で観て、単純に「面白いな」と感じただけだった。これが再帰的な作品だとは昔から知られていたそうだ。あらためて画集の作品解説を読むと、ちゃんと書いてあった。検索すると、分かりやすい動画もあった。私は半世紀の年月を経て初めて気づいた。情けないが仕方ない。
著者が指摘するように、内側の世界と外側の世界を融合させるために螺旋構造を用いるというアイデアは秀逸である。著者は、螺旋を描いて成長する結晶がヒントになったのではと推測している。サイエンスの世界である。
橋元時間論の集大成『光速・時空・生命』の最終章は壮大なSF ― 2025年01月20日
書店の棚で本書を見つけ、すぐに購入した。昨年(2024年)10月に出た新書だ。
『光速・時空・生命:秒速30万キロから見た世界』(橋元淳一郎/インタナショナル新書・集英社インターナショナル)
私はこれまでに橋元氏の時間に関する本を何冊か読んでいる。『時間はどこで生まれるか』、『時間はなぜ取り戻せないのか』、『時空と生命』、『空間は実在するか』などである。時間は生命現象によって発生したとする橋元時間論にはセンス・オブ・ワンダーがあり、魅せられた。
と言っても、私が橋元氏の言説を十分に理解できているわけではない。いつの日か、ゆっくり読み返して理解を深めたいと思っていた。だから、書店で新刊を発見したとき、橋本時間論を復習して多少なりとも理解を深める機会だと感じたのである。
本書は相対論の解説をメインに光速の不思議を解説し、速度とは何かの検討を通して時間と生命を考察している。後半はかなりSFに近くなる。
昔読んだ橋元時間論の内容の大半は失念しているので、あらためて「ヘェー」と感じながら本書を読み進めた。フワーッとしか理解できない広遠な思考実験を再体験し、遠い世界を旅した気分になった。
物理学における「時間」とわれわれが感じている「時間」は、似て非なるものである。物理の時間には「流れ」がない。時間の流れを創るのは生命である、というのが本書のテーマだと思う。「速度」や「動く」という現象への考察も面白い。これらは物理現象というよりは生命が創り出すものだそうだ。光速はモノの動く速さではなく、この宇宙の壁だという指摘にナルホドと感じた。もちろん、十分に咀嚼できたわけではないが。
著者は、本書の目論見は新たな科学的真理の構築などではなく、SF思考実験だとしている。そして、最終章は「百兆年の旅路」と題するSF的思考実験空想譚になっている。ユニバースではなくマルチバースの宇宙を旅する壮大なSFだ。
『光速・時空・生命:秒速30万キロから見た世界』(橋元淳一郎/インタナショナル新書・集英社インターナショナル)
私はこれまでに橋元氏の時間に関する本を何冊か読んでいる。『時間はどこで生まれるか』、『時間はなぜ取り戻せないのか』、『時空と生命』、『空間は実在するか』などである。時間は生命現象によって発生したとする橋元時間論にはセンス・オブ・ワンダーがあり、魅せられた。
と言っても、私が橋元氏の言説を十分に理解できているわけではない。いつの日か、ゆっくり読み返して理解を深めたいと思っていた。だから、書店で新刊を発見したとき、橋本時間論を復習して多少なりとも理解を深める機会だと感じたのである。
本書は相対論の解説をメインに光速の不思議を解説し、速度とは何かの検討を通して時間と生命を考察している。後半はかなりSFに近くなる。
昔読んだ橋元時間論の内容の大半は失念しているので、あらためて「ヘェー」と感じながら本書を読み進めた。フワーッとしか理解できない広遠な思考実験を再体験し、遠い世界を旅した気分になった。
物理学における「時間」とわれわれが感じている「時間」は、似て非なるものである。物理の時間には「流れ」がない。時間の流れを創るのは生命である、というのが本書のテーマだと思う。「速度」や「動く」という現象への考察も面白い。これらは物理現象というよりは生命が創り出すものだそうだ。光速はモノの動く速さではなく、この宇宙の壁だという指摘にナルホドと感じた。もちろん、十分に咀嚼できたわけではないが。
著者は、本書の目論見は新たな科学的真理の構築などではなく、SF思考実験だとしている。そして、最終章は「百兆年の旅路」と題するSF的思考実験空想譚になっている。ユニバースではなくマルチバースの宇宙を旅する壮大なSFだ。
半世紀経って『悲しき熱帯』をやっと読了 ― 2024年11月14日
先月、レヴィ=ストロースの『野生の思考』を読み、消化不良だったので構造主義の入門書に目を通した。そして、やはり『悲しき熱帯』から読むべきだったと反省した。
『悲しき熱帯』を収録した中央公論の『世界の名著 59』が出たのは1967年7月だ。そのころ大学生だった私は、当時よく耳にした「構造主義」を知るための必読書だろうと思って本書を入手した。だが、冒頭で挫折した。
それから半世紀以上も本棚の奥に眠っていた本書を、ついに読了した。
『悲しき熱帯』(レヴィ=ストロース/川田順造訳/世界の名著 59/中央公論社)
本書は抄訳である。全9部のうちの5部だけを訳している。川田順造氏による全訳が出るのは、本書刊行の10年後である。
抄訳ではあるが、本書巻頭にはレヴィ=ストロースが寄せた「日本の読者へのメッセージ」が載っている。日本への関心が深く、後年、何度も来日にすることになるレヴィ=ストロースは、このメッセージの時点ではまだ来日を果たしていない。
ブラジルでの調査旅行の記録でもある本書の書き出しは「私は旅と探検家がきらいだ。」である。著者の屈折した心情が伝わってくる。本書は報告書というよりは回想録に近い。
レヴィ=ストロースがブラジル奥地の現地調査をしたのは1930年代後半である。その後、フランスに帰国するが、1940年にナチスがパリを占領しヴィシー政権になる。ユダヤ人のレヴィ=ストロースはマルセイユから脱出して米国に亡命する。その時の様子を冒頭に記述した本書の刊行は1955年である。十数年前の事柄を鳥の眼と虫の眼で叙述した著作だ。
第1部のタイトルは「旅の終わり」、第2部のタイトルは「旅の断章」である。この冒頭部分は文学的かつ省察的である。味わい深いとも言える。半世紀前の学生の私は、それを消化できずに挫折したのだと思う。
『悲しき熱帯』というタイトルが何を意味しているかは、本書を読み終えれば自ずと見えてくる。
著者の研究対象である先住民族インディオは、白人がもたらした伝染病で多くが死に絶え、集団の縮小と新たにもたらされた文物によって、その文化は変貌しつつある。
コーヒー農園などは肥沃な土地を荒廃させながら移動していく。そのさまを著者は、強奪に似た農業が土地を凌辱・破壊すると表現している。先日読んだばかりの『砂糖の世界史』や『コーヒーが廻り世界史が廻る』を想起した。
文学的表現に長けた著者は、眼前の光景を絵画に例えたりする。それがアンリ・ルソーやイヴ・タンギーの絵画なのが面白い。ルソーは素朴な想像力で異国の異様な景色を描いた画家であり、イヴ・タンギーはシュルレアリスム絵画だ。現実の情景を眺めながら、そこに非現実的・超現実的な幻想絵画を重ねる著者の知力は尋常ではない。構造主義の奥義を垣間見たような気がした。
本書における著者の眼差しと探究心は魅力的である。この抄訳を読了した私は、全訳を読むべきか否か迷っている。
『悲しき熱帯』を収録した中央公論の『世界の名著 59』が出たのは1967年7月だ。そのころ大学生だった私は、当時よく耳にした「構造主義」を知るための必読書だろうと思って本書を入手した。だが、冒頭で挫折した。
それから半世紀以上も本棚の奥に眠っていた本書を、ついに読了した。
『悲しき熱帯』(レヴィ=ストロース/川田順造訳/世界の名著 59/中央公論社)
本書は抄訳である。全9部のうちの5部だけを訳している。川田順造氏による全訳が出るのは、本書刊行の10年後である。
抄訳ではあるが、本書巻頭にはレヴィ=ストロースが寄せた「日本の読者へのメッセージ」が載っている。日本への関心が深く、後年、何度も来日にすることになるレヴィ=ストロースは、このメッセージの時点ではまだ来日を果たしていない。
ブラジルでの調査旅行の記録でもある本書の書き出しは「私は旅と探検家がきらいだ。」である。著者の屈折した心情が伝わってくる。本書は報告書というよりは回想録に近い。
レヴィ=ストロースがブラジル奥地の現地調査をしたのは1930年代後半である。その後、フランスに帰国するが、1940年にナチスがパリを占領しヴィシー政権になる。ユダヤ人のレヴィ=ストロースはマルセイユから脱出して米国に亡命する。その時の様子を冒頭に記述した本書の刊行は1955年である。十数年前の事柄を鳥の眼と虫の眼で叙述した著作だ。
第1部のタイトルは「旅の終わり」、第2部のタイトルは「旅の断章」である。この冒頭部分は文学的かつ省察的である。味わい深いとも言える。半世紀前の学生の私は、それを消化できずに挫折したのだと思う。
『悲しき熱帯』というタイトルが何を意味しているかは、本書を読み終えれば自ずと見えてくる。
著者の研究対象である先住民族インディオは、白人がもたらした伝染病で多くが死に絶え、集団の縮小と新たにもたらされた文物によって、その文化は変貌しつつある。
コーヒー農園などは肥沃な土地を荒廃させながら移動していく。そのさまを著者は、強奪に似た農業が土地を凌辱・破壊すると表現している。先日読んだばかりの『砂糖の世界史』や『コーヒーが廻り世界史が廻る』を想起した。
文学的表現に長けた著者は、眼前の光景を絵画に例えたりする。それがアンリ・ルソーやイヴ・タンギーの絵画なのが面白い。ルソーは素朴な想像力で異国の異様な景色を描いた画家であり、イヴ・タンギーはシュルレアリスム絵画だ。現実の情景を眺めながら、そこに非現実的・超現実的な幻想絵画を重ねる著者の知力は尋常ではない。構造主義の奥義を垣間見たような気がした。
本書における著者の眼差しと探究心は魅力的である。この抄訳を読了した私は、全訳を読むべきか否か迷っている。
構造主義に関する36年前と56年前の新書を読んだ ― 2024年10月21日
『野生の思考』(レヴィ=ストロース)に目を通し、『100分de名著』のテキストを読んでも、頭の中にはモヤがかかったままだ。多少は理解を深めたいと思い、次の新書2冊を続けて読んだ。いずれもかなり昔の講談社現代新書である。
『はじめての構造主義』(橋爪大三郎/講談社現代新書/1988.5発行/2023.11=62刷)
『構造主義』(北沢方邦/講談社現代新書/1968.12発行/1970.1=3刷)
手頃な解説書をネット検索していて見つけたのが『はじめての構造主義』(以下、橋爪本)である。ネット書店で入手し、奥付を見ると発行は36年前だった。入手したのは2023年刊行の62刷。驚異のロングセラーだ。
橋爪本を読み始めると、半世紀以上昔の大学生時代に入手した『構造主義』(以下、北沢本)を思い出した。書棚の奥から見つけ出した古い新書の発行日は56年前だった。パラパラめくると、傍線や稚拙な書き込みがある。読了しているようだが、内容はまったく憶えていない。
北沢本はいったん脇におき、まず、橋爪本を読んだ。「はしがき」には「ちょっと進んだ高校生、かなりおませな中学生」にも読めるように書いたとある。確かにわかりやすい。ロングセラーになる所以がわかる。
橋爪本の冒頭、著者が大学生になったばかりの頃の「構造主義ブーム」を語っている。1960年代後半の話だ。橋爪氏と同年代の私は、この件りを読んで、わが学生時代に入手した北沢本の記憶がかすかによみがえったのだ。同じ時代の空気を呼吸していたとは言え、超一流大学の知性あふれる学生・橋爪氏と凡庸な私を較べるのは僭越である。齢を重ねて進歩のない私には、同年代の橋爪氏の中高生向けの手ほどきが有難い。
構造主義にもいろいろあるらしいが、橋爪本はレヴィ=ストロースの構造主義を解説している。「構造」とは何かは、レヴィ=ストロースを繰り返し読んでもピンとこない、と書いている。少し安心した。「構造」という抽象概念を把握するには数学を援用するのがいいとし、射影幾何学や抽象代数学を用いて「構造」を解説している。説明がやさしいので、わかった気になる。
橋爪本を読んだ後、北沢本を読んだ。半世紀ぶりの再読のはずだが、何も憶えていないので初読と変わらない。「あとがき」によれば1968年10月からの2カ月足らずで執筆したそうだ。発行は1968年12月である。
北沢本からは1968年の熱い息吹が伝わってくる。1968年はフランスの五月革命の年である。日本では全共闘時代、中国は文革時代、世界の至るところでスチューデント・パワーが高揚していた。当時、北沢氏は桐朋学園大学助教授として音楽社会学などの分野で活動していた。
オビには「構造主義は日本の思想界にも爆発的な登場をした。なぜこの思想が迎えられたのか。いかなる方法によって何をめざすものなのか。単なる解説書にとどまらぬ大胆犀利な問題提起」とある。
オビが語る通り、構造主義の解説書ではない。著者の言葉を借りれば「弁証法的構造主義の立場から「全体知」を開発するこころみ」の書である。入門書のつもりで繙くととまどってしまう。
北沢本もレヴィ=ストロースに相当のページを割いているが、『悲しき熱帯』以外の主著はまだ翻訳されていない時代である。『野生の時代』は『パンセ・ソヴァージュ』という原題で紹介している。レヴィ=ストロースがサルトルの『弁証法的理性批判』を批判したことには触れていない。北沢氏はサルトルに共感し、救出しようとしているようにも思われる。
北沢本には「構造としての人間」「人間の全体性」という言葉が頻出する。これらはほぼ同じ意味に思える。「構造としての人間=人間の全体性」を科学的に追究していくのが構造主義だとしているようだ。記述はかなり難解である。そのトーンは高い。アジ演説のように熱い。半世紀前に本書を読んだ私は「構造主義ってわけがわからん」と感じたのだと思う。何も覚えていないのだから…。
さほど意味のあることではないが、20年の時間差がある橋爪本と北沢本は、両書とも著者39歳のときの著書である。
『はじめての構造主義』(橋爪大三郎/講談社現代新書/1988.5発行/2023.11=62刷)
『構造主義』(北沢方邦/講談社現代新書/1968.12発行/1970.1=3刷)
手頃な解説書をネット検索していて見つけたのが『はじめての構造主義』(以下、橋爪本)である。ネット書店で入手し、奥付を見ると発行は36年前だった。入手したのは2023年刊行の62刷。驚異のロングセラーだ。
橋爪本を読み始めると、半世紀以上昔の大学生時代に入手した『構造主義』(以下、北沢本)を思い出した。書棚の奥から見つけ出した古い新書の発行日は56年前だった。パラパラめくると、傍線や稚拙な書き込みがある。読了しているようだが、内容はまったく憶えていない。
北沢本はいったん脇におき、まず、橋爪本を読んだ。「はしがき」には「ちょっと進んだ高校生、かなりおませな中学生」にも読めるように書いたとある。確かにわかりやすい。ロングセラーになる所以がわかる。
橋爪本の冒頭、著者が大学生になったばかりの頃の「構造主義ブーム」を語っている。1960年代後半の話だ。橋爪氏と同年代の私は、この件りを読んで、わが学生時代に入手した北沢本の記憶がかすかによみがえったのだ。同じ時代の空気を呼吸していたとは言え、超一流大学の知性あふれる学生・橋爪氏と凡庸な私を較べるのは僭越である。齢を重ねて進歩のない私には、同年代の橋爪氏の中高生向けの手ほどきが有難い。
構造主義にもいろいろあるらしいが、橋爪本はレヴィ=ストロースの構造主義を解説している。「構造」とは何かは、レヴィ=ストロースを繰り返し読んでもピンとこない、と書いている。少し安心した。「構造」という抽象概念を把握するには数学を援用するのがいいとし、射影幾何学や抽象代数学を用いて「構造」を解説している。説明がやさしいので、わかった気になる。
橋爪本を読んだ後、北沢本を読んだ。半世紀ぶりの再読のはずだが、何も憶えていないので初読と変わらない。「あとがき」によれば1968年10月からの2カ月足らずで執筆したそうだ。発行は1968年12月である。
北沢本からは1968年の熱い息吹が伝わってくる。1968年はフランスの五月革命の年である。日本では全共闘時代、中国は文革時代、世界の至るところでスチューデント・パワーが高揚していた。当時、北沢氏は桐朋学園大学助教授として音楽社会学などの分野で活動していた。
オビには「構造主義は日本の思想界にも爆発的な登場をした。なぜこの思想が迎えられたのか。いかなる方法によって何をめざすものなのか。単なる解説書にとどまらぬ大胆犀利な問題提起」とある。
オビが語る通り、構造主義の解説書ではない。著者の言葉を借りれば「弁証法的構造主義の立場から「全体知」を開発するこころみ」の書である。入門書のつもりで繙くととまどってしまう。
北沢本もレヴィ=ストロースに相当のページを割いているが、『悲しき熱帯』以外の主著はまだ翻訳されていない時代である。『野生の時代』は『パンセ・ソヴァージュ』という原題で紹介している。レヴィ=ストロースがサルトルの『弁証法的理性批判』を批判したことには触れていない。北沢氏はサルトルに共感し、救出しようとしているようにも思われる。
北沢本には「構造としての人間」「人間の全体性」という言葉が頻出する。これらはほぼ同じ意味に思える。「構造としての人間=人間の全体性」を科学的に追究していくのが構造主義だとしているようだ。記述はかなり難解である。そのトーンは高い。アジ演説のように熱い。半世紀前に本書を読んだ私は「構造主義ってわけがわからん」と感じたのだと思う。何も覚えていないのだから…。
さほど意味のあることではないが、20年の時間差がある橋爪本と北沢本は、両書とも著者39歳のときの著書である。
中沢新一氏の熱気にあふれた『100分de名著 野生の思考』 ― 2024年10月19日
『野生の思考』に目を通したものの消化不良なので関連書を検索した。100分de名著のテキストを見つけ、ネット書店で購入した。
『100分de名著 野生の思考』(中沢新一/NHK出版)
2016年12月号とある。8年前に放映された番組のテキストだ。8年前のテキストをまだ新本で販売しているのに驚いた。100ページ強の分量だから短時間で読了できた。
このテキストを通読し、『野生の思考』読解のための解説本というよりは派生本に近いと感じた。もちろん、読解の手助けにはなる。
100分de名著は25分4回の番組である。本書は次のような構成になっている。
第1回 「構造主義」の誕生
第2回 野生の知財と「ブリコラージュ」
第3回 神話の論理へ
第4回 「野生の思考」は日本に生きている
第1回は『野生の思考』を読む準備としてのレヴィ=ストロースの紹介である。事前に、この程度のことは把握しておくべきだったと悟った。
第4回は『野生の思考』刊行後にレヴィ=ストロースが何度も来日した話の紹介が中心で、『野生の思考』が提示した思想の新たな展開を論じている。
というわけで、『野生の思考』の内容にに即した解説は第2回と第3回である。第3回の後半は『野生の思考』とは別の論文『火あぶりにされたサンタクロース』に関する話になっている。
『野生の思考』に目を通した直後にこのテキストを読んだので、本文に直結した読解的な部分が意外に少ないと感じた。期待した解説本とはややズレているが、『野生の思考』を最大級に評価する中沢新一氏の熱気は伝わってくる。
このテキストの「はじめに」で、中沢氏は19世紀の『資本論』に匹敵する起爆力をもった20世紀の本が『野生の思考』だとし、次のように述べている。
「この本は、いまだ完全には読み解かれていない、これから新しく読み解かれるべき内容をはらんだ21世紀の書物です。」
また、テキストの末尾では次のように語っている。
「一筋縄ではいかない、強靭な知性によって書かれたとても難しい本ですが、そこには、日本人がこれからどうやって自分たちの世界をつくっていったらよいかを考えるためのたくさんのヒントが埋め込まれたいます。」
たかだか100分で読み解けるような本ではない、ということである。
『100分de名著 野生の思考』(中沢新一/NHK出版)
2016年12月号とある。8年前に放映された番組のテキストだ。8年前のテキストをまだ新本で販売しているのに驚いた。100ページ強の分量だから短時間で読了できた。
このテキストを通読し、『野生の思考』読解のための解説本というよりは派生本に近いと感じた。もちろん、読解の手助けにはなる。
100分de名著は25分4回の番組である。本書は次のような構成になっている。
第1回 「構造主義」の誕生
第2回 野生の知財と「ブリコラージュ」
第3回 神話の論理へ
第4回 「野生の思考」は日本に生きている
第1回は『野生の思考』を読む準備としてのレヴィ=ストロースの紹介である。事前に、この程度のことは把握しておくべきだったと悟った。
第4回は『野生の思考』刊行後にレヴィ=ストロースが何度も来日した話の紹介が中心で、『野生の思考』が提示した思想の新たな展開を論じている。
というわけで、『野生の思考』の内容にに即した解説は第2回と第3回である。第3回の後半は『野生の思考』とは別の論文『火あぶりにされたサンタクロース』に関する話になっている。
『野生の思考』に目を通した直後にこのテキストを読んだので、本文に直結した読解的な部分が意外に少ないと感じた。期待した解説本とはややズレているが、『野生の思考』を最大級に評価する中沢新一氏の熱気は伝わってくる。
このテキストの「はじめに」で、中沢氏は19世紀の『資本論』に匹敵する起爆力をもった20世紀の本が『野生の思考』だとし、次のように述べている。
「この本は、いまだ完全には読み解かれていない、これから新しく読み解かれるべき内容をはらんだ21世紀の書物です。」
また、テキストの末尾では次のように語っている。
「一筋縄ではいかない、強靭な知性によって書かれたとても難しい本ですが、そこには、日本人がこれからどうやって自分たちの世界をつくっていったらよいかを考えるためのたくさんのヒントが埋め込まれたいます。」
たかだか100分で読み解けるような本ではない、ということである。


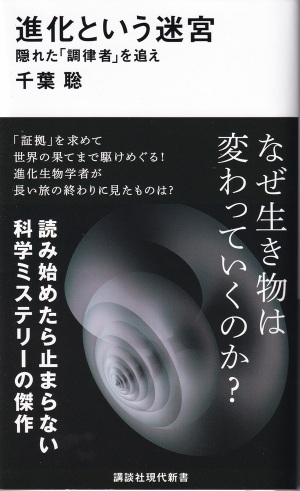





最近のコメント