『図説十字軍』は想定とやや違う内容だった… ― 2025年05月14日
『アラブが見た十字軍』で当時のイスラム世界の様子を概観し、西欧視点の十字軍についてもザーッと再確認しておこうと思い、次の本を読んだ。
『図説十字軍』(櫻井康人/ふくろうの本/河出書房新社)
著者は十字軍研究の歴史学者である。図版を多用した入門書のつもりで読み始めたが、少し勝手が違った。本書は、現在のおける十字軍史研究をふまえた概説書である。現在、十字軍は次のように定義されているそうだ。
「十字軍とはキリスト教会のために戦うことで贖罪を得ることであり、それは1095年からナポレオンによるマルタの占領(1798年)までの約700年間、いたる所で展開された。」
この定義は、私たちが普通に考える「第1回十字軍(1096-1099)から約200年間のエルサレム奪回軍事遠征」よりかなり広い。本書はこの広い定義に基づいて、約700年間のさまざまな十字軍を概説している。少々面食らったが勉強になった。
歴史家ピレンヌ(1862-1935)は、ヨーロッパの成立に関して「マホメットなくしてシャルルマーニュなし」というピレンヌ・テーゼを提唱した。本書冒頭、このテーゼは現在では否定されているとしている。驚いた。カロリング朝時代のイスラムの地中海進出が地中海貿易を途絶させ、ヨーロッパの貨幣経済は衰退し、自給自足的農業基盤生活となり、中世の封建社会が形成された、という説の否定である。現在では、イスラムの地中海進出によって地中海交易は活性化したと考えられているそうだ。
また、イベリア半島に侵入したイスラム勢力をフランク王国が押しとどめたトゥール・ポアティエ間の戦い(732年)の際、フランクは相手をイスラムとは認識せず、異教徒の蛮族と見ていたらしい。ヨーロッパがイスラムを本格的に認識したのは第1回十字軍の後だそうだ。ヘェーと思った。
十字軍に関しても「パレスチナの地に財産を求めて行った」「十字軍の参加者は家督を継げない次男・三男だった」という説を否定している。参加者の多くは、後に十字軍家系と呼ばれる特定の家系の者たちだったそうだ。その家系に属する者にとって、十字軍への参加は一種の通過儀礼であり、参加によって当該家系が多くの財産を失うことを承知で参加したという。認識を新たにする見解だ。
本書はフリードリヒ2世がアイユーブ朝のアル・カーミルとの交渉でエルサレムを回復した「東方遠征」について、フリードリヒが破門状態だったため「彼の東方遠征は贖罪価値を伴う十字軍ではなかった」としている。フリードリヒの遠征を「第6回十字軍」とする見方も多いと思うが、現在の定義では十字軍にあたらないらしい。本書はルイ9世の1回目の十字軍を「第6回十字軍」としている。
意外に感じたのは英仏百年戦争(1337~1453年)が十字軍戦争だとの指摘である。当時、教皇位が分裂し、ローマとアヴィニヨンに教皇が並立していた。それぞれの教皇が贖罪を得る十字軍特権を授けたため、百年戦争は互いに対する十字軍になったそうだ。
ややリゴリズムとも感じられる本書だが、聖地巡礼の黄金期に関する指摘は興味深い。パレスチナの十字軍国家が消滅した後の14~15世紀が聖地巡礼の黄金期だった。十字軍国家が存在していた時期の巡礼は危険で、パレスチナがイスラム世界になってはじめて安全な巡礼ができるようになったのだ。歴史の皮肉である。
『図説十字軍』(櫻井康人/ふくろうの本/河出書房新社)
著者は十字軍研究の歴史学者である。図版を多用した入門書のつもりで読み始めたが、少し勝手が違った。本書は、現在のおける十字軍史研究をふまえた概説書である。現在、十字軍は次のように定義されているそうだ。
「十字軍とはキリスト教会のために戦うことで贖罪を得ることであり、それは1095年からナポレオンによるマルタの占領(1798年)までの約700年間、いたる所で展開された。」
この定義は、私たちが普通に考える「第1回十字軍(1096-1099)から約200年間のエルサレム奪回軍事遠征」よりかなり広い。本書はこの広い定義に基づいて、約700年間のさまざまな十字軍を概説している。少々面食らったが勉強になった。
歴史家ピレンヌ(1862-1935)は、ヨーロッパの成立に関して「マホメットなくしてシャルルマーニュなし」というピレンヌ・テーゼを提唱した。本書冒頭、このテーゼは現在では否定されているとしている。驚いた。カロリング朝時代のイスラムの地中海進出が地中海貿易を途絶させ、ヨーロッパの貨幣経済は衰退し、自給自足的農業基盤生活となり、中世の封建社会が形成された、という説の否定である。現在では、イスラムの地中海進出によって地中海交易は活性化したと考えられているそうだ。
また、イベリア半島に侵入したイスラム勢力をフランク王国が押しとどめたトゥール・ポアティエ間の戦い(732年)の際、フランクは相手をイスラムとは認識せず、異教徒の蛮族と見ていたらしい。ヨーロッパがイスラムを本格的に認識したのは第1回十字軍の後だそうだ。ヘェーと思った。
十字軍に関しても「パレスチナの地に財産を求めて行った」「十字軍の参加者は家督を継げない次男・三男だった」という説を否定している。参加者の多くは、後に十字軍家系と呼ばれる特定の家系の者たちだったそうだ。その家系に属する者にとって、十字軍への参加は一種の通過儀礼であり、参加によって当該家系が多くの財産を失うことを承知で参加したという。認識を新たにする見解だ。
本書はフリードリヒ2世がアイユーブ朝のアル・カーミルとの交渉でエルサレムを回復した「東方遠征」について、フリードリヒが破門状態だったため「彼の東方遠征は贖罪価値を伴う十字軍ではなかった」としている。フリードリヒの遠征を「第6回十字軍」とする見方も多いと思うが、現在の定義では十字軍にあたらないらしい。本書はルイ9世の1回目の十字軍を「第6回十字軍」としている。
意外に感じたのは英仏百年戦争(1337~1453年)が十字軍戦争だとの指摘である。当時、教皇位が分裂し、ローマとアヴィニヨンに教皇が並立していた。それぞれの教皇が贖罪を得る十字軍特権を授けたため、百年戦争は互いに対する十字軍になったそうだ。
ややリゴリズムとも感じられる本書だが、聖地巡礼の黄金期に関する指摘は興味深い。パレスチナの十字軍国家が消滅した後の14~15世紀が聖地巡礼の黄金期だった。十字軍国家が存在していた時期の巡礼は危険で、パレスチナがイスラム世界になってはじめて安全な巡礼ができるようになったのだ。歴史の皮肉である。
『アラブが見た十字軍』はイスラム世界のドタバタ劇か? ― 2025年05月11日
『中世ヨーロッパ』(堀米庸三)、『ヨーロパ中世』(鯖田豊之)の2冊を続けて読んで頭が 中世モードになり、未読棚の次の本を引っ張り出して読んだ。
『アラブが見た十字軍』(アミン・マアルーフ/牟田口義郎、新川雅子訳/ちくま学芸文庫)
著者は1949年レバノン生まれのジャーナリスト。私より1歳若い。原書はフランス語、1983年の刊行だ。タイトル通り、アラブ視点で十字軍襲来を描いている。
十字軍はヨーロッパ視点で語られることが多い。そもそも「十字軍」という概念や用語がヨーロッパ視点である。私は4年前に塩野七生の『十字軍物語』を読んだ。あの歴史小説も基本的にはヨーロッパ視点だが、イスラム側から見た十字軍の野蛮な後進性にも言及していた。
本書のタイトルから、西方から襲来する蛮族の侵略行為を描いた本だろうと思った。だが、少し違っていた。もちろん、フランク(ヨーロッパから来た十字軍をイスラム側はフランクと呼ぶ)の蛮行も描いているが、フランク襲来の時代のイスラム世界の混迷ぶりの描写がメインである。混迷の後にサラディンらによる統一と反撃があるのだが、全般に不条理なドタバタ劇の印象が強い。
最初の十字軍が小アジアに現れた1096年頃、セルジューク朝はすでに全盛期を過ぎ、分離傾向が強くなっていた。小アジアで最初に十字軍に対応したのは、バグダードから分離独立したルーム=セルジューク朝のスルタンである。
第一回十字軍がエルサレム占拠に成功し、いくつかの十字軍国家が成立したのは、十字軍に対応するイスラム世界がバラバラだったせいだとは聞いていた。その実態を本書で知り、少々驚き、あきれた。
本書の舞台となるイスラム世界は元来はアラブ人の土地で、セルジューク朝はトルコ系である。そんなところにもバラバラの要因があるだろうが、トルコ系の領主同士も相争っている。
割拠する領主たちは兄弟であっても敵なのである。領主同士の合従連衡はあるが、いつ裏切られかわからない。フランクと戦っている領主への支援に駆け付け、手のひら返しで戦わずに引き返したりもする。フランクの勝利が自身に有利と判断したのである。相手を倒すためには、フランクと組むこともいとわない。
バグダッドではセルジューク朝のスルタンが傀儡のカリフ(アッバース朝)を戴いている。このカリフが傀儡であることに不満で、支援者を糾合してスルタンに戦いを挑んだりもする。
ビザンツとフランクの関係も複雑だ。共にキリスト教なのに、フランクはギリシア正教の村を略奪する。ビザンツがイスラムと組んでフランクに対峙することもある。
イスラム世界には、ビザンツで弾圧された非カトリックのキリスト教徒(ヤコブ派、東方キリスト諸派)も住んでいる。イスラムは異教徒に寛容だからだ。彼らはフランクではなくイスラムを支援する。
フランクも団結しているわけでなく、フランク同士の争いもある。そんな争いの一方にイスラム側が加担することもある。
また、同じイスラムでもスンニ派のセルジューク朝とシーア派のファーティマ朝(エジプト)は敵対することが多い。そこに過激なシーア派の暗殺教団が絡み、スンニ派の要人を暗殺する。暗殺教団とフランクが組むこともある。
マクロに見れば、キリスト教世界の十字軍とイスラム世界の争いなのだが、ミクロに見ると敵と味方が入り乱れて何でもありのゴチャゴチャした世界だ。人間の集団は宗教という理念で動くのではなく、己の利害や感情で動くことが多く、それが自然だろうとの思いにかられる。不条理なドタバタ劇は歴史の常態に近いのかもしれない。
本書は面白いのだが、馴染みのない人名の頻出に難儀した。イスラムの似たような人名の識別が難しくて混乱するのだ。人名索引もない。仕方なく、主な登場人物をメモしながら読み進めた。読了後に数えるとイスラム側の人名だけで58人になった。そのうちの11名は、本書の記述のベースになった歴史家や年代記作家である。あらためて、当時のイスラム世界の文化レベルの高さを感じた。
『アラブが見た十字軍』(アミン・マアルーフ/牟田口義郎、新川雅子訳/ちくま学芸文庫)
著者は1949年レバノン生まれのジャーナリスト。私より1歳若い。原書はフランス語、1983年の刊行だ。タイトル通り、アラブ視点で十字軍襲来を描いている。
十字軍はヨーロッパ視点で語られることが多い。そもそも「十字軍」という概念や用語がヨーロッパ視点である。私は4年前に塩野七生の『十字軍物語』を読んだ。あの歴史小説も基本的にはヨーロッパ視点だが、イスラム側から見た十字軍の野蛮な後進性にも言及していた。
本書のタイトルから、西方から襲来する蛮族の侵略行為を描いた本だろうと思った。だが、少し違っていた。もちろん、フランク(ヨーロッパから来た十字軍をイスラム側はフランクと呼ぶ)の蛮行も描いているが、フランク襲来の時代のイスラム世界の混迷ぶりの描写がメインである。混迷の後にサラディンらによる統一と反撃があるのだが、全般に不条理なドタバタ劇の印象が強い。
最初の十字軍が小アジアに現れた1096年頃、セルジューク朝はすでに全盛期を過ぎ、分離傾向が強くなっていた。小アジアで最初に十字軍に対応したのは、バグダードから分離独立したルーム=セルジューク朝のスルタンである。
第一回十字軍がエルサレム占拠に成功し、いくつかの十字軍国家が成立したのは、十字軍に対応するイスラム世界がバラバラだったせいだとは聞いていた。その実態を本書で知り、少々驚き、あきれた。
本書の舞台となるイスラム世界は元来はアラブ人の土地で、セルジューク朝はトルコ系である。そんなところにもバラバラの要因があるだろうが、トルコ系の領主同士も相争っている。
割拠する領主たちは兄弟であっても敵なのである。領主同士の合従連衡はあるが、いつ裏切られかわからない。フランクと戦っている領主への支援に駆け付け、手のひら返しで戦わずに引き返したりもする。フランクの勝利が自身に有利と判断したのである。相手を倒すためには、フランクと組むこともいとわない。
バグダッドではセルジューク朝のスルタンが傀儡のカリフ(アッバース朝)を戴いている。このカリフが傀儡であることに不満で、支援者を糾合してスルタンに戦いを挑んだりもする。
ビザンツとフランクの関係も複雑だ。共にキリスト教なのに、フランクはギリシア正教の村を略奪する。ビザンツがイスラムと組んでフランクに対峙することもある。
イスラム世界には、ビザンツで弾圧された非カトリックのキリスト教徒(ヤコブ派、東方キリスト諸派)も住んでいる。イスラムは異教徒に寛容だからだ。彼らはフランクではなくイスラムを支援する。
フランクも団結しているわけでなく、フランク同士の争いもある。そんな争いの一方にイスラム側が加担することもある。
また、同じイスラムでもスンニ派のセルジューク朝とシーア派のファーティマ朝(エジプト)は敵対することが多い。そこに過激なシーア派の暗殺教団が絡み、スンニ派の要人を暗殺する。暗殺教団とフランクが組むこともある。
マクロに見れば、キリスト教世界の十字軍とイスラム世界の争いなのだが、ミクロに見ると敵と味方が入り乱れて何でもありのゴチャゴチャした世界だ。人間の集団は宗教という理念で動くのではなく、己の利害や感情で動くことが多く、それが自然だろうとの思いにかられる。不条理なドタバタ劇は歴史の常態に近いのかもしれない。
本書は面白いのだが、馴染みのない人名の頻出に難儀した。イスラムの似たような人名の識別が難しくて混乱するのだ。人名索引もない。仕方なく、主な登場人物をメモしながら読み進めた。読了後に数えるとイスラム側の人名だけで58人になった。そのうちの11名は、本書の記述のベースになった歴史家や年代記作家である。あらためて、当時のイスラム世界の文化レベルの高さを感じた。
ロングセラー『肉食の思想』は刺激的な本だった ― 2025年05月03日
56年前に出た『ヨーロパ中世(世界の歴史9)』(鯖田豊之)を読了し、この著者に次の話題書があると知った。古い本だがネット書店で注文できた。
『肉食の思想:ヨーロッパ精神の再発見』(鯖田豊之/中公新書)
1966年1月初版の中公新書である。私が入手したのは半年前の2024年10月に出た62版。初版以来58年間、改訂もせずに刊行が続いているようだ。驚きのロングセラーだ。1926年生まれの著者は2001年に亡くなっている。
本書のタイトルに懐かしさを感じた。本書が出た1966年頃、高校生の私は『〇〇の思想』という表題の本が流行していると思った。
『〇〇の思想』はありふれたタイトルかもしれないが、当時読んだ小松左京の「槍とヒョウタン――思想の流行について」(1966年9月刊行『未来図の世界』収録)というエッセイの印象が強いのだ。何冊もの『〇〇の思想』という本(『地図の思想』『戦後を拓く思想』『恥部の思想』『砂漠の思想』『饒舌の思想』『哄笑の思想』『テレビの思想』『核を創る思想』など)を取り上げたうえで、「思想の逆なでシリーズ」の続刊を提起し、「高橋和巳などの場合、『孤立無援の思想』より『思想の孤立無援』の方が、何やら彼のイメージがうかぶような気がします」と述べていた。
あの時代に『肉食の思想』が刊行されたのかと思うと感慨深い。
閑話休題。本書はとても面白かった。西洋中世史・比較史が専門の著者が、日本人とヨーロッパ人の考え方や感じ方の違いの由縁をマクロな視角で明解に論じている。目から鱗が落ちるようなスリリングな読書体験だった。ロングセラーなのも納得できる。
ヨーロッパ人は肉食、日本人は穀物食、その違いには地理的歴史的な理由があり、その違いが両者の精神構造の違いを形成している――というのが本書の骨子だ。食生活の違いから社会意識の違いを論じる手際は華麗なアクロバットのようでもある。読者である私は、あっけにとられて感心するばかりだ。
ヨーロッパは農業&牧畜、日本は農業のみ。その違いは気候にある。日本は温暖湿潤、それに比べてヨーロッパは寒冷だ。ヨーロッパと言えば三圃制だが日本に三圃制はないと思う。三圃制は春耕地、秋耕地、休耕地の3年周期であり、休耕地は牛などが草を食む牧畜地である。牧畜地は広い方が効率がいい。だからから耕地は集約されていく。
三圃制は連作障害を避ける手段である。だが、水田には連作障害はない。また、日本の気候では夏の雑草の繁茂が激しくて牧畜の餌にならない。ゆえに、日本は米という穀物が主食の文化になる。
日本に比べて牧畜のコストが低いヨーロッパでは農業と牧畜の併存が常態である。主食という概念もない。肉も乳も小麦も、入手可能なものは何でも食べる。小麦はそのままでは美味しくないので、粉にしてパンにして食べる。
牧畜が身近な肉食文化が、人間と動物を峻別し、人間だけが特別な存在だとする独善的な人間中心主義を生み出す。ナルホドと思った。結婚や愛情表現に関する指摘も面白い。牧畜が身近だと子供の頃から動物の性交渉を日常的に目にすることになり、それがおおっぴらな愛情表現につながるとともに、「結婚」を「キリスト教の秘蹟」として公認しコントロールする考えが生まれたそうだ。
そんな「人間中心主義のキリスト教」がヨーロッパの階層意識や社会意識を形成してきたと本書は説いている。人間中心主義は結構かもしれないが、その「人間」を「キリスト教徒のヨーロッパ人」だけと見なしているようなのだ。これはやっかいな問題である。
本書が展開する議論は非常に面白い。推論の積み重ねなので、その妥当性は私にはわからない。本書がどう評価されているかも知らない。しかし、ヨーロッパ社会と日本社会を比較検討するうえでの刺激的な材料になるのは確かだと思えた。
『肉食の思想:ヨーロッパ精神の再発見』(鯖田豊之/中公新書)
1966年1月初版の中公新書である。私が入手したのは半年前の2024年10月に出た62版。初版以来58年間、改訂もせずに刊行が続いているようだ。驚きのロングセラーだ。1926年生まれの著者は2001年に亡くなっている。
本書のタイトルに懐かしさを感じた。本書が出た1966年頃、高校生の私は『〇〇の思想』という表題の本が流行していると思った。
『〇〇の思想』はありふれたタイトルかもしれないが、当時読んだ小松左京の「槍とヒョウタン――思想の流行について」(1966年9月刊行『未来図の世界』収録)というエッセイの印象が強いのだ。何冊もの『〇〇の思想』という本(『地図の思想』『戦後を拓く思想』『恥部の思想』『砂漠の思想』『饒舌の思想』『哄笑の思想』『テレビの思想』『核を創る思想』など)を取り上げたうえで、「思想の逆なでシリーズ」の続刊を提起し、「高橋和巳などの場合、『孤立無援の思想』より『思想の孤立無援』の方が、何やら彼のイメージがうかぶような気がします」と述べていた。
あの時代に『肉食の思想』が刊行されたのかと思うと感慨深い。
閑話休題。本書はとても面白かった。西洋中世史・比較史が専門の著者が、日本人とヨーロッパ人の考え方や感じ方の違いの由縁をマクロな視角で明解に論じている。目から鱗が落ちるようなスリリングな読書体験だった。ロングセラーなのも納得できる。
ヨーロッパ人は肉食、日本人は穀物食、その違いには地理的歴史的な理由があり、その違いが両者の精神構造の違いを形成している――というのが本書の骨子だ。食生活の違いから社会意識の違いを論じる手際は華麗なアクロバットのようでもある。読者である私は、あっけにとられて感心するばかりだ。
ヨーロッパは農業&牧畜、日本は農業のみ。その違いは気候にある。日本は温暖湿潤、それに比べてヨーロッパは寒冷だ。ヨーロッパと言えば三圃制だが日本に三圃制はないと思う。三圃制は春耕地、秋耕地、休耕地の3年周期であり、休耕地は牛などが草を食む牧畜地である。牧畜地は広い方が効率がいい。だからから耕地は集約されていく。
三圃制は連作障害を避ける手段である。だが、水田には連作障害はない。また、日本の気候では夏の雑草の繁茂が激しくて牧畜の餌にならない。ゆえに、日本は米という穀物が主食の文化になる。
日本に比べて牧畜のコストが低いヨーロッパでは農業と牧畜の併存が常態である。主食という概念もない。肉も乳も小麦も、入手可能なものは何でも食べる。小麦はそのままでは美味しくないので、粉にしてパンにして食べる。
牧畜が身近な肉食文化が、人間と動物を峻別し、人間だけが特別な存在だとする独善的な人間中心主義を生み出す。ナルホドと思った。結婚や愛情表現に関する指摘も面白い。牧畜が身近だと子供の頃から動物の性交渉を日常的に目にすることになり、それがおおっぴらな愛情表現につながるとともに、「結婚」を「キリスト教の秘蹟」として公認しコントロールする考えが生まれたそうだ。
そんな「人間中心主義のキリスト教」がヨーロッパの階層意識や社会意識を形成してきたと本書は説いている。人間中心主義は結構かもしれないが、その「人間」を「キリスト教徒のヨーロッパ人」だけと見なしているようなのだ。これはやっかいな問題である。
本書が展開する議論は非常に面白い。推論の積み重ねなので、その妥当性は私にはわからない。本書がどう評価されているかも知らない。しかし、ヨーロッパ社会と日本社会を比較検討するうえでの刺激的な材料になるのは確かだと思えた。
『中世ヨーロッパ』に続いて『ヨーロパ中世』を読んだ ― 2025年04月27日
中央公論版「世界の歴史(旧版)」の『中世ヨーロッパ』に続いて、数十年も書架に眠っていた河出書房版「世界の歴史」の似たタイトルの巻を読んだ。
『ヨーロパ中世(世界の歴史9)』(鯖田豊之/河出書房新社/1969.1)
先日読んだ『中世ヨーロッパ』は1962年の本だった。本書の刊行は1969年1月。これも古い。挟み込み「月報」の「編集部だより」には、大学紛争のさなか執筆者との連絡が大変だったとある。私が学生の頃に出た本だ。時代を感じる。
同じ題材の本を読んだ直後なので、本書は比較的すらすらと読めた。
本書冒頭の導入部はシャーロック・ホームズの『赤髪連盟』の話だ。ヨーロッパでは髪の色、眼の色、鼻の形などの違う人が共存している。混血が進んでいるのだ。それゆえに、生まれてくる自分の子供の髪の色などを両親があらかじめ正確に知るのは難しいそうだ。混血のヨーロッ人にとってインターナショナルな関係は身近である。だが、その関係はヨーロッパ世界の内部にしかおよばない。そんなヨーロッパ世界はどのように形成されてきたか。その探究が本書のテーマである。
まずはゲルマン民族の大移動である。ゲルマン人は、東ゴート、西ゴート、ヴァンダル、ブルグンド、ランゴバルド、スゥェビ、フランク、アングル、サクソンなど多様である。彼らが先住のケルト人やローマ人と混ざり合ってヨーロッパができていく。
本書でヘェーと思ったのは、フランク人のカトリック化が早かった理由である。ゲルマン人の多くはキリスト教アリウス派だったとは知っていたが、フランクは遅れた部族だったのでアリウス派ではなく古ゲルマンの多神教世界だったそうだ。そのため、カトリックへ改宗が容易だった。フランク人の王クローヴィスがカトリックに改宗したため、彼の征服戦争は異端のアリウス派を倒す「聖戦」となり、支配領域が拡大した。と言っても、「遅れた部族」の改宗が生活態度にどれほどの影響をあたえたは、はなはだ疑わしいと著者は述べている。
本書は随所で日本との比較をまじえてヨーロッパを語っている。仏教伝来とキリスト教化、武士道と騎士道などなどである。共通点もあれば違いもあり、ヨーロッパの姿がより鮮明に浮かび上がってくる。
王族の血統に関する日本とヨーロッパとの比較も興味深い。ヨーロッパには血統権原理だけでなく選挙原理もあり、二つの原理の拮抗関係のなかで次期の王が決まってきたそうだ。豪族たちによる国王選挙が血統権をつきくずすこともあった。日本は血統権が万能だが、ヨーロッパはそうではない。
ヨーロッパにおいても、国王に息子がいれば世襲相続は容易である。だが、直系の子孫が絶えた場合、何等かの血のつながりがある人物が当然に王になれるわけではない。当然に世襲相続できるのは直系の息子だけである。血統権原理の日本ならば、血のつながりがあれば直系でなくても世襲相続できる。
本書は、イギリスにおけるノルマン朝からプランタジネット朝への移行を例に説明している。ノルマン朝のイギリス国王ヘンリー1世に息子がなく、娘のマチルダしかいなかった。マチルダとアンジュー伯ジョフロアの息子がイギリス国王ヘンリー2世となる。ヘンリー2世はプランタジネット朝(アンジュー家)の開祖となる。この件について、著者は次のように述べている。
「日本的観念からすれば、イギリス国王になると同時に、ノルマン家の相続人になってもよさそうなものである。ところが、実際はそうでなかった。イギリス国王になったにもかかわらず、新しい王家の創始者になった。」
この箇所を読んで、かすかな違和感をおぼえた。血統権原理の日本なら、血のつながりがあるのだから息子が母親の実家を相続できるという話だと思う。一般的には、息子がいなければ娘に婿をとり、その子が相続するというのはよくある話だ。だが、日本の喫緊の課題である天皇家に関して、現状では当てはまらない。男系男子に拘泥し、女系は認めていない。だから、上記の「日本的観念」にアレッと感じたのだ。1969年当時と現在で「日本的観念」が変わったとも考えにくい。
日本が万世一系にこだわっているのに対して、インターナショナルで、かつ直系子孫のみを重視するヨーロッパは万世一系という考えが乏しく、王朝交代がフツーだったように見える。日本の万世一系は明治になって登場した概念にすぎないらしいが。
『ヨーロパ中世(世界の歴史9)』(鯖田豊之/河出書房新社/1969.1)
先日読んだ『中世ヨーロッパ』は1962年の本だった。本書の刊行は1969年1月。これも古い。挟み込み「月報」の「編集部だより」には、大学紛争のさなか執筆者との連絡が大変だったとある。私が学生の頃に出た本だ。時代を感じる。
同じ題材の本を読んだ直後なので、本書は比較的すらすらと読めた。
本書冒頭の導入部はシャーロック・ホームズの『赤髪連盟』の話だ。ヨーロッパでは髪の色、眼の色、鼻の形などの違う人が共存している。混血が進んでいるのだ。それゆえに、生まれてくる自分の子供の髪の色などを両親があらかじめ正確に知るのは難しいそうだ。混血のヨーロッ人にとってインターナショナルな関係は身近である。だが、その関係はヨーロッパ世界の内部にしかおよばない。そんなヨーロッパ世界はどのように形成されてきたか。その探究が本書のテーマである。
まずはゲルマン民族の大移動である。ゲルマン人は、東ゴート、西ゴート、ヴァンダル、ブルグンド、ランゴバルド、スゥェビ、フランク、アングル、サクソンなど多様である。彼らが先住のケルト人やローマ人と混ざり合ってヨーロッパができていく。
本書でヘェーと思ったのは、フランク人のカトリック化が早かった理由である。ゲルマン人の多くはキリスト教アリウス派だったとは知っていたが、フランクは遅れた部族だったのでアリウス派ではなく古ゲルマンの多神教世界だったそうだ。そのため、カトリックへ改宗が容易だった。フランク人の王クローヴィスがカトリックに改宗したため、彼の征服戦争は異端のアリウス派を倒す「聖戦」となり、支配領域が拡大した。と言っても、「遅れた部族」の改宗が生活態度にどれほどの影響をあたえたは、はなはだ疑わしいと著者は述べている。
本書は随所で日本との比較をまじえてヨーロッパを語っている。仏教伝来とキリスト教化、武士道と騎士道などなどである。共通点もあれば違いもあり、ヨーロッパの姿がより鮮明に浮かび上がってくる。
王族の血統に関する日本とヨーロッパとの比較も興味深い。ヨーロッパには血統権原理だけでなく選挙原理もあり、二つの原理の拮抗関係のなかで次期の王が決まってきたそうだ。豪族たちによる国王選挙が血統権をつきくずすこともあった。日本は血統権が万能だが、ヨーロッパはそうではない。
ヨーロッパにおいても、国王に息子がいれば世襲相続は容易である。だが、直系の子孫が絶えた場合、何等かの血のつながりがある人物が当然に王になれるわけではない。当然に世襲相続できるのは直系の息子だけである。血統権原理の日本ならば、血のつながりがあれば直系でなくても世襲相続できる。
本書は、イギリスにおけるノルマン朝からプランタジネット朝への移行を例に説明している。ノルマン朝のイギリス国王ヘンリー1世に息子がなく、娘のマチルダしかいなかった。マチルダとアンジュー伯ジョフロアの息子がイギリス国王ヘンリー2世となる。ヘンリー2世はプランタジネット朝(アンジュー家)の開祖となる。この件について、著者は次のように述べている。
「日本的観念からすれば、イギリス国王になると同時に、ノルマン家の相続人になってもよさそうなものである。ところが、実際はそうでなかった。イギリス国王になったにもかかわらず、新しい王家の創始者になった。」
この箇所を読んで、かすかな違和感をおぼえた。血統権原理の日本なら、血のつながりがあるのだから息子が母親の実家を相続できるという話だと思う。一般的には、息子がいなければ娘に婿をとり、その子が相続するというのはよくある話だ。だが、日本の喫緊の課題である天皇家に関して、現状では当てはまらない。男系男子に拘泥し、女系は認めていない。だから、上記の「日本的観念」にアレッと感じたのだ。1969年当時と現在で「日本的観念」が変わったとも考えにくい。
日本が万世一系にこだわっているのに対して、インターナショナルで、かつ直系子孫のみを重視するヨーロッパは万世一系という考えが乏しく、王朝交代がフツーだったように見える。日本の万世一系は明治になって登場した概念にすぎないらしいが。
ビザンツの扱いが気になって昔の歴史概説書を読んだ ― 2025年04月24日
中央公論社のシリーズ本『世界の歴史』は旧版(全16巻:1960年刊行開始)と新版(全30巻:1996年刊行開始)がある。その旧版第3巻の文庫版を古書で入手して読んだ。
『中世ヨーロッパ(世界の歴史3)』(責任編集:堀米庸三/中公文庫)
本書の原版の刊行は1961年2月。こんな古い本を読もうと思ったのは、ビザンツ史への関心がきっかけだ。ビザンツ史の概説書には、コンスタンティノープルの見聞記を残したクレモナ司教リュートプランドがよく登場する。この人物をウィキペディアで検索すると次の記述がある。
「堀米庸三は、彼に匹敵するギリシア通が後世に現れなかったため、彼の東ローマに対する偏見が後世まで影響を及ぼしたと述べている。(『世界の歴史3 中世ヨーロッパ』)」
半世紀以上昔、碩学・堀米庸三はビザンツ史が偏見で語られがちだと指摘していたようだ。彼がビザンツ史をどのように語っているかに興味がわき、本書を読んだ。
読み終えて、小さな失望と大きな満足を得た。ビザンツ史に関しては、私が期待したような記述はなかった。だが、本書を読み進めながら中世ヨーロッパ史の多様な面白さを堪能できた。読みごたえのある歴史書だった。
本書は前半四分の三を堀米庸三、残りの四分の一を弟子の木村尚三郎が執筆している。ウィキペディアが紹介している指摘の正確な引用は以下の通りだ。
「リュートプランド以後には、彼に匹敵するギリシア通の使節はもはやあらわれず、かえって彼のビザンツに対する偏見があとあとまで影響した。」
リュートプランドの複数回にわたるコンスタンティノープル訪問について、本書は約3ページを費やして記述している。全般的にリュープランドに同情的であり、ビザンツへの偏見をことさら話題にしているわけではない。
本書は基本的に「ビザンツ」ではなく「東ローマ」という用語を使用している。この二つは同じだと思うが、あえて使い分けるなら、東ローマのギリシア化(7世紀頃)以降をビザンツと呼ぶこともあるようだ。本書はそんな使い分けはせず、東ローマで一貫しているが、以下のような文脈でビザンツという言葉が出てくる。
「西方との接触がうすれていけば、それだけ東ローマは専制的な東洋風、ビザンツ風になっていく。」
「サラセンの地中海制覇以来、東ローマが西方との関係を次第に薄くし、東方化、ビザンツ化を深めたことは否定できない。こういった理由から私は、東ローマをビザンツ世界としてヨーロッパから区別する。」
「ビザンツ風」「ビザンツ化」「ビザンツ世界」とは何かの説明はない。読者には自明ということなのだろう。東ローマは「中世ヨーロッパ」と題する本書の対象外としているのである。東ローマから離脱することによってヨーロッパが成立したと見なしているようだ。だから、東ローマに関する記述はさほど多くない。
と言っても、ヨーロッパの成立を語るには東ローマに言及せざるを得ない場面はいろいろある。あのアンナ・コムネナも「きこえた才媛」と紹介し、その著書の記述をかなり引用している。
本書には、ビザンツ関連以外にも興味をひかれる話題が多い。私は9年前、『大聖堂』(ケン・フォレット)という小説を読んで中世ヨーロッパへの関心がわき、概説書を2冊読んだことがある。その1冊は堀米庸三の著作だった。だが、9年前に読んだ概説書の内容はほとんど蒸発していて、頭の中は白紙に近い。本書を読み進めながら、初めて中世ヨーロッパ史の概説書に取り組んでいるような新鮮な気分を味わった。
例えば、カノッサの屈辱で知られるハインリヒ4世とグレゴリー7世の波乱に富んだ物語は、中世ヨーロッパのさまざまな事情が反映されていて、とても面白い。二人とも失意の最期をむかえるのも小説のようだ。あらためて、この時代への興味がわいた。
いずれ、ゆっくり再読したい本である。
『中世ヨーロッパ(世界の歴史3)』(責任編集:堀米庸三/中公文庫)
本書の原版の刊行は1961年2月。こんな古い本を読もうと思ったのは、ビザンツ史への関心がきっかけだ。ビザンツ史の概説書には、コンスタンティノープルの見聞記を残したクレモナ司教リュートプランドがよく登場する。この人物をウィキペディアで検索すると次の記述がある。
「堀米庸三は、彼に匹敵するギリシア通が後世に現れなかったため、彼の東ローマに対する偏見が後世まで影響を及ぼしたと述べている。(『世界の歴史3 中世ヨーロッパ』)」
半世紀以上昔、碩学・堀米庸三はビザンツ史が偏見で語られがちだと指摘していたようだ。彼がビザンツ史をどのように語っているかに興味がわき、本書を読んだ。
読み終えて、小さな失望と大きな満足を得た。ビザンツ史に関しては、私が期待したような記述はなかった。だが、本書を読み進めながら中世ヨーロッパ史の多様な面白さを堪能できた。読みごたえのある歴史書だった。
本書は前半四分の三を堀米庸三、残りの四分の一を弟子の木村尚三郎が執筆している。ウィキペディアが紹介している指摘の正確な引用は以下の通りだ。
「リュートプランド以後には、彼に匹敵するギリシア通の使節はもはやあらわれず、かえって彼のビザンツに対する偏見があとあとまで影響した。」
リュートプランドの複数回にわたるコンスタンティノープル訪問について、本書は約3ページを費やして記述している。全般的にリュープランドに同情的であり、ビザンツへの偏見をことさら話題にしているわけではない。
本書は基本的に「ビザンツ」ではなく「東ローマ」という用語を使用している。この二つは同じだと思うが、あえて使い分けるなら、東ローマのギリシア化(7世紀頃)以降をビザンツと呼ぶこともあるようだ。本書はそんな使い分けはせず、東ローマで一貫しているが、以下のような文脈でビザンツという言葉が出てくる。
「西方との接触がうすれていけば、それだけ東ローマは専制的な東洋風、ビザンツ風になっていく。」
「サラセンの地中海制覇以来、東ローマが西方との関係を次第に薄くし、東方化、ビザンツ化を深めたことは否定できない。こういった理由から私は、東ローマをビザンツ世界としてヨーロッパから区別する。」
「ビザンツ風」「ビザンツ化」「ビザンツ世界」とは何かの説明はない。読者には自明ということなのだろう。東ローマは「中世ヨーロッパ」と題する本書の対象外としているのである。東ローマから離脱することによってヨーロッパが成立したと見なしているようだ。だから、東ローマに関する記述はさほど多くない。
と言っても、ヨーロッパの成立を語るには東ローマに言及せざるを得ない場面はいろいろある。あのアンナ・コムネナも「きこえた才媛」と紹介し、その著書の記述をかなり引用している。
本書には、ビザンツ関連以外にも興味をひかれる話題が多い。私は9年前、『大聖堂』(ケン・フォレット)という小説を読んで中世ヨーロッパへの関心がわき、概説書を2冊読んだことがある。その1冊は堀米庸三の著作だった。だが、9年前に読んだ概説書の内容はほとんど蒸発していて、頭の中は白紙に近い。本書を読み進めながら、初めて中世ヨーロッパ史の概説書に取り組んでいるような新鮮な気分を味わった。
例えば、カノッサの屈辱で知られるハインリヒ4世とグレゴリー7世の波乱に富んだ物語は、中世ヨーロッパのさまざまな事情が反映されていて、とても面白い。二人とも失意の最期をむかえるのも小説のようだ。あらためて、この時代への興味がわいた。
いずれ、ゆっくり再読したい本である。
司馬遼太郎と林家辰三郎の歴史対談本は面白い ― 2025年04月21日
次の歴史対談本を読んだ。
『歴史の夜咄』(司馬遼太郎・林家辰三郎/小学館文庫)
司馬遼太郎と歴史学者・林家辰三郎の対談8編を収録している。1972年から1980年にかけての対談で、雑誌や新聞に掲載されたものがメインだ。
この古い対談集を読んだきっかけは、昨年読んだ『日本に古代はあったのか』(井上章一)である。これはとても面白い本で、私が昨年(2024年)読んだ本のベスト3に入る。井上章一氏によれば、司馬遼太郎は関東史観、林家辰三郎はそうではない。後者に与する井上氏は、二人の対談本を次のように紹介している。
「対談じたいは、なごやかにすすんでいる(…)
だが、私にはこれがプロレスの試合めいて、見えなくもない。たがいの得意技に、見せ場をじゅうぶんにあたえたうえで、全体をはこんでいく。そんなゲーム、よくできた応酬を、おがませてもらったような気もする。
京都の学統をうけつぐ碩学が、関東史観の国民作家を、どうむかえうつか。その醍醐味が、この対談ではあじわえた。歴史好きには一読をすすめたい。けっこうはらはらさせられることを、うけおう。」
この文章に釣られて本書を読んだのである。井上氏のコメントは、本書2編目の対談「日本人はいかに形成されたか」に関するものだ。で、この対談を読んだ私が「はらはらさせれた」かと言うと、そうでもない。「ヘェー」と感心しながら読んだだけである。私の未熟な知識や洞察力は「はらはら」を感じるレベルにないと認識した。
「はらはら」はしないが、新たな知見に接して大いに刺激になった。「日本の律令体制は中国を真似ていながら、実は日本向きの骨抜きだった」「“天皇”という用語は大いなる独創」「中国からの返書に“倭王”とあるのを、役人が“王”の上に“白”を足して“倭皇”として記録した」など、面白い話がたくさん出てくる。二人の見解の違いは、日本人の心性の原型が形成された時期を、司馬遼太郎は鎌倉時代ごろ、林家辰三郎は東山時代ごろと考えているということのようだ。
全編を通して、読みやすくて面白い対談だった。司馬遼太郎は関東と関西の比較論が好きなのだなあと思った。関東は父系、関西は母系だそうだ。時代とともにゴチャゴチャになるだろうとは思うが…。
本書には山陽新聞(岡山県の地方紙)に載った対談が2つある。「花開いた古代吉備」と「中世瀬戸内の風景」である。私は岡山県出身なので興味深く読んだ。私の知らないことばかりだった。「古代の吉備は日本全体を支配しようという意図をもっていた」「津山は魏志倭人伝の投馬国」という林家説には驚いた。
『歴史の夜咄』(司馬遼太郎・林家辰三郎/小学館文庫)
司馬遼太郎と歴史学者・林家辰三郎の対談8編を収録している。1972年から1980年にかけての対談で、雑誌や新聞に掲載されたものがメインだ。
この古い対談集を読んだきっかけは、昨年読んだ『日本に古代はあったのか』(井上章一)である。これはとても面白い本で、私が昨年(2024年)読んだ本のベスト3に入る。井上章一氏によれば、司馬遼太郎は関東史観、林家辰三郎はそうではない。後者に与する井上氏は、二人の対談本を次のように紹介している。
「対談じたいは、なごやかにすすんでいる(…)
だが、私にはこれがプロレスの試合めいて、見えなくもない。たがいの得意技に、見せ場をじゅうぶんにあたえたうえで、全体をはこんでいく。そんなゲーム、よくできた応酬を、おがませてもらったような気もする。
京都の学統をうけつぐ碩学が、関東史観の国民作家を、どうむかえうつか。その醍醐味が、この対談ではあじわえた。歴史好きには一読をすすめたい。けっこうはらはらさせられることを、うけおう。」
この文章に釣られて本書を読んだのである。井上氏のコメントは、本書2編目の対談「日本人はいかに形成されたか」に関するものだ。で、この対談を読んだ私が「はらはらさせれた」かと言うと、そうでもない。「ヘェー」と感心しながら読んだだけである。私の未熟な知識や洞察力は「はらはら」を感じるレベルにないと認識した。
「はらはら」はしないが、新たな知見に接して大いに刺激になった。「日本の律令体制は中国を真似ていながら、実は日本向きの骨抜きだった」「“天皇”という用語は大いなる独創」「中国からの返書に“倭王”とあるのを、役人が“王”の上に“白”を足して“倭皇”として記録した」など、面白い話がたくさん出てくる。二人の見解の違いは、日本人の心性の原型が形成された時期を、司馬遼太郎は鎌倉時代ごろ、林家辰三郎は東山時代ごろと考えているということのようだ。
全編を通して、読みやすくて面白い対談だった。司馬遼太郎は関東と関西の比較論が好きなのだなあと思った。関東は父系、関西は母系だそうだ。時代とともにゴチャゴチャになるだろうとは思うが…。
本書には山陽新聞(岡山県の地方紙)に載った対談が2つある。「花開いた古代吉備」と「中世瀬戸内の風景」である。私は岡山県出身なので興味深く読んだ。私の知らないことばかりだった。「古代の吉備は日本全体を支配しようという意図をもっていた」「津山は魏志倭人伝の投馬国」という林家説には驚いた。
ポリスの誕生から衰亡までを分析した『白熱する人間たちの都市』 ― 2025年04月11日
ローマ史家・本村凌二氏がオリエント史からローマ史に至る4000年の文明史を語る『地中海世界の歴史(全8巻)』。その第3巻を読んだ。
『白熱する人間たちの都市:エーゲ海とギリシアの文明(地中海世界の歴史3)』(本村凌二/講談社選書メチエ)
このシリーズの第1巻『神々のささやく世界』はオリエント文明の発祥からアッシリア帝国以前のBC1000年頃まで、第2巻『沈黙する神々の帝国』はアッシリア帝国とアケメネス朝ペルシアが盛衰するBC1000年頃からBC300年頃までを語っていた。
それに続く本書『白熱する人間たちの都市』はエーゲ文明に始まるギリシア文明の話である。時代はBC2000年頃からBC300頃までと長い。時間的には第1巻、第2巻に重なる。第1巻、第2巻で、メソポタミアを中心にイラン、アナトリア、シリア、エジプトなどに及ぶオリエント世界の歴史を眺め、それを踏まえてオリエント文明の西の辺境とも言えるギリシア文明を第3巻で語るという趣向である。
ギリシアから見ればオリエント世界は圧倒的な先進地帯だった。ギリシアがオリエント世界から影響を受けているのは確かだが、ギリシア文明を自分たちのルーツと見なす西欧人はギリシア文明の独自性にウエイトを置く傾向があるようだ。
「オリエントの優越性や先進性は古代ギリシア人には周知だった」と指摘した『ブラック・アテナ』(M・バナール)に言及した著者は、バナール説は日本人には理解しやすいと指摘している。古代のオリエントを中国、ギリシアを日本と見れば納得できるというのである。そのうえで、オリエントの影響とギリシアの独自性のどちらに重きをおくかは識者によって千差万別だとしている。
ペルシア・ギリシア戦争の頃のギリシアについては「ペルシアの優越性が、どれほどギリシア人の庶民生活のなかで感知されたいたかとなると、はなはだ心もとない気がする」と述べているので、必ずしもバナール説を支持しているわけではなさそうだ。
第1巻、第2巻と同じように、本書はいわゆる通史ではない。古代世界に生きた人々の心性の推移を探る心性史である。ギリシア文明の心性を探るこの巻は、ギリシアの心性の独自性に着目している。
ホメロスが書いたと言われる『イリアス』と『オデュセイア』の分析が面白い。『イリアス』から『オデュセイア』に至る過程で神のふるまいに変化があり、それは人間の感性の変化を映しているとの指摘である。オデュセウスは、目標達成のためには知力のかぎりを尽くし、策略を平然と実行する。それが、新しいタイプの人間の出現だとの指摘に、ナルホドと思った。先日読んだ『アンナ・コムネナ』で、アンナが父アレクシウス1世をオデュセウスに例えているのを想起した。
著者は、ギリシアにおけるポリスの誕生から衰退までを心性史の視点で描いている。それは「自由人」という自意識の誕生に始まり「傲慢(ヒュブリス)」から「報い(ネメシス)」に至るダイナミックなギリシア悲劇である。とても面白い。
民主政につての多面的な分析も面白い。平等の徹底という意味では軍事大国スパルタこそが民主主義を実現した国制だとの指摘に驚いた。
また、奴隷への言及も興味深い。プラトンやアリストテレスなどの哲人も「自然による奴隷」「生まれながらの奴隷」の存在を当然とてしていた。奴隷を「劣等な異民族」と見なしていたらしい。著者は「ギリシア人の心性と文明は奴隷制の上に成り立っていた」としたうえで「第二次世界大戦以前の近代史にあっても、国民国家の宗主国と植民地帝国の異民族支配が表裏一体をなしていたことに気づく」と述べている。古代史の課題が近代史でも克服できていなかったのである。
『地中海世界の歴史』はすでに第6巻が刊行されたようだ。今すぐ続きの巻を読む元気はない。マイペースでボチボチ読んでいこうと思う。
『白熱する人間たちの都市:エーゲ海とギリシアの文明(地中海世界の歴史3)』(本村凌二/講談社選書メチエ)
このシリーズの第1巻『神々のささやく世界』はオリエント文明の発祥からアッシリア帝国以前のBC1000年頃まで、第2巻『沈黙する神々の帝国』はアッシリア帝国とアケメネス朝ペルシアが盛衰するBC1000年頃からBC300年頃までを語っていた。
それに続く本書『白熱する人間たちの都市』はエーゲ文明に始まるギリシア文明の話である。時代はBC2000年頃からBC300頃までと長い。時間的には第1巻、第2巻に重なる。第1巻、第2巻で、メソポタミアを中心にイラン、アナトリア、シリア、エジプトなどに及ぶオリエント世界の歴史を眺め、それを踏まえてオリエント文明の西の辺境とも言えるギリシア文明を第3巻で語るという趣向である。
ギリシアから見ればオリエント世界は圧倒的な先進地帯だった。ギリシアがオリエント世界から影響を受けているのは確かだが、ギリシア文明を自分たちのルーツと見なす西欧人はギリシア文明の独自性にウエイトを置く傾向があるようだ。
「オリエントの優越性や先進性は古代ギリシア人には周知だった」と指摘した『ブラック・アテナ』(M・バナール)に言及した著者は、バナール説は日本人には理解しやすいと指摘している。古代のオリエントを中国、ギリシアを日本と見れば納得できるというのである。そのうえで、オリエントの影響とギリシアの独自性のどちらに重きをおくかは識者によって千差万別だとしている。
ペルシア・ギリシア戦争の頃のギリシアについては「ペルシアの優越性が、どれほどギリシア人の庶民生活のなかで感知されたいたかとなると、はなはだ心もとない気がする」と述べているので、必ずしもバナール説を支持しているわけではなさそうだ。
第1巻、第2巻と同じように、本書はいわゆる通史ではない。古代世界に生きた人々の心性の推移を探る心性史である。ギリシア文明の心性を探るこの巻は、ギリシアの心性の独自性に着目している。
ホメロスが書いたと言われる『イリアス』と『オデュセイア』の分析が面白い。『イリアス』から『オデュセイア』に至る過程で神のふるまいに変化があり、それは人間の感性の変化を映しているとの指摘である。オデュセウスは、目標達成のためには知力のかぎりを尽くし、策略を平然と実行する。それが、新しいタイプの人間の出現だとの指摘に、ナルホドと思った。先日読んだ『アンナ・コムネナ』で、アンナが父アレクシウス1世をオデュセウスに例えているのを想起した。
著者は、ギリシアにおけるポリスの誕生から衰退までを心性史の視点で描いている。それは「自由人」という自意識の誕生に始まり「傲慢(ヒュブリス)」から「報い(ネメシス)」に至るダイナミックなギリシア悲劇である。とても面白い。
民主政につての多面的な分析も面白い。平等の徹底という意味では軍事大国スパルタこそが民主主義を実現した国制だとの指摘に驚いた。
また、奴隷への言及も興味深い。プラトンやアリストテレスなどの哲人も「自然による奴隷」「生まれながらの奴隷」の存在を当然とてしていた。奴隷を「劣等な異民族」と見なしていたらしい。著者は「ギリシア人の心性と文明は奴隷制の上に成り立っていた」としたうえで「第二次世界大戦以前の近代史にあっても、国民国家の宗主国と植民地帝国の異民族支配が表裏一体をなしていたことに気づく」と述べている。古代史の課題が近代史でも克服できていなかったのである。
『地中海世界の歴史』はすでに第6巻が刊行されたようだ。今すぐ続きの巻を読む元気はない。マイペースでボチボチ読んでいこうと思う。
ディープな歴史コミック『アンナ・コムネナ』に驚愕 ― 2025年04月08日
先月(2025年3月17日)の朝日新聞で、コミック『アンナ・コムネナ』完結の記事に遭遇したときは驚いた。数年前から気がかりなコミックだったのだ。「アンナ・コムネナ」を検索するとこのコミックが出てくる。アマゾンの「サンプル読み」で第1巻の冒頭部分を読み、マイナーな歴史を少女マンガの語り口で大胆かつマニアックに記述するアンバランスに驚いた。購入しようかなと思いつつも、あまりに少女マンガなので、後期高齢男性の私は躊躇していた。
新聞記事によれば、2021年に第1巻が出た『アンナ・コムネナ』が今年2月に完結したそうだ。作者の佐藤二葉氏はギリシア悲劇を大学院で専攻した人で、アンナ・コムネナが著した史書『アレクシアス』の邦訳が2019年に出たのをきっかけに、このコミックを執筆したという。ビザンツ史家の井上浩一氏も時代考証の相談に乗っているそうだ。そんなコミックなら読むしかない。
私が先日、井上氏の『歴史学の慰め:アンナ・コムネナの生涯と作品』を読んだのは、実はこの記事がきっかけである。アンナ・コムネナに関しては断片的な知識しかないので、コミックを読む前に評伝を読もうと思ったのだ。この評伝に続いて、いよいよコミック全6巻を読んだ。
『アンナ・コムネナ(1)~(6)』(佐藤二葉/星海社COMICS/星海社)
ディープな歴史を扱った少女マンガである。ビザンツ史に関心のある私には、とても面白かった。歴史書で目にする人名や地名が具体的な姿で現前するのに感動した。もちろんフィクションの部分もあるだろうが、歴史の現場をイメージできて楽しい。
この歴史絵巻コミックは、ギャグ、ラブコメ、フェミニズムなどの要素を盛り込んだ宮廷ホームドラマであり、成長物語である。姉・弟(アンナとヨハネス)の確執と夫婦愛(アンナとニケフォロス・ブリュエンニオス)を軸に物語が進行する。史実と思われる事項をベースに奔放な想像力で物語を紡いでいく作者の力量に感服した。なるほど、そういう解釈もあり得るのかと感心する箇所もいくつかあった。
こんなテーマのコミックが存在することに、日本のコミック恐るべしの感を新たにした。本書を読むと、『アレクシアス』にも取り組まねばという気になってくる。2019年に邦訳が出た『アレクシアス』は、かねてから気がかりな本だが、その価格(8000円)とボリュームにたじろいでいるのだが…。
新聞記事によれば、2021年に第1巻が出た『アンナ・コムネナ』が今年2月に完結したそうだ。作者の佐藤二葉氏はギリシア悲劇を大学院で専攻した人で、アンナ・コムネナが著した史書『アレクシアス』の邦訳が2019年に出たのをきっかけに、このコミックを執筆したという。ビザンツ史家の井上浩一氏も時代考証の相談に乗っているそうだ。そんなコミックなら読むしかない。
私が先日、井上氏の『歴史学の慰め:アンナ・コムネナの生涯と作品』を読んだのは、実はこの記事がきっかけである。アンナ・コムネナに関しては断片的な知識しかないので、コミックを読む前に評伝を読もうと思ったのだ。この評伝に続いて、いよいよコミック全6巻を読んだ。
『アンナ・コムネナ(1)~(6)』(佐藤二葉/星海社COMICS/星海社)
ディープな歴史を扱った少女マンガである。ビザンツ史に関心のある私には、とても面白かった。歴史書で目にする人名や地名が具体的な姿で現前するのに感動した。もちろんフィクションの部分もあるだろうが、歴史の現場をイメージできて楽しい。
この歴史絵巻コミックは、ギャグ、ラブコメ、フェミニズムなどの要素を盛り込んだ宮廷ホームドラマであり、成長物語である。姉・弟(アンナとヨハネス)の確執と夫婦愛(アンナとニケフォロス・ブリュエンニオス)を軸に物語が進行する。史実と思われる事項をベースに奔放な想像力で物語を紡いでいく作者の力量に感服した。なるほど、そういう解釈もあり得るのかと感心する箇所もいくつかあった。
こんなテーマのコミックが存在することに、日本のコミック恐るべしの感を新たにした。本書を読むと、『アレクシアス』にも取り組まねばという気になってくる。2019年に邦訳が出た『アレクシアス』は、かねてから気がかりな本だが、その価格(8000円)とボリュームにたじろいでいるのだが…。
『アンナ・コムネナの生涯と作品』は歴史学への愛の書 ― 2025年04月04日
ビザンツ帝国のコムネノス朝初代皇帝アレクシオス1世の長女、アンナ・コムネナ(1083-1153/4頃)は興味深い人物である。私はギボンの『ローマ帝国衰亡史』をボチボチと再読中で、それに関連してビザンツ史の一般書を、この数年で何冊か読んできた。そこでしばしば遭遇するのが、皇女アンナ・コムネナである。
皇帝の娘であるアンナは自分こそが次期皇帝にふさわしいと考えていた。自分が無理なら夫を皇帝にしたいと思った。しかし、アレクシオス1世を継いで皇帝になったのは弟のヨハネス2世だった。アンナはヨハネスと対立し、政争に敗れ、後半生は歴史家に転身し、父の業績を綴った史書『アレクシアス』を書き上げる。ギボンをはじめビザンツ史を語る史書の多くは『アレクシアス』を引用している。
そのアンナ・コムネナの伝記をビザンツ史家の井上浩一氏が書いていると知った。
『歴史学の慰め:アンナ・コムネナの生涯と作品』(井上浩一/白水社/2020.7)
井上氏の著書は、これまでに『ビザンツとスラブ』(世界の歴史11)、『生き残った帝国ビザンティン』(講談社学術文庫)、『ビザンツ皇妃列伝』を読んだ。どれも面白かった。文章が洒脱で読みやすい。本書も面白いだろうと予感して読み始めた。予感した以上に面白い歴史書だった。感動した。
本書は「第1部 生涯」「第2部 作品」から成る。第1部はアンナの伝記、第2部は彼女の著書『アレクシアス』の検討と評価である。井上氏は「あとがき」で、「楽しい歴史の旅へと誘ってくださったアンナ・コムネナさんに本書を捧げたいと思います」と述べたうえで、次のように語っている。
〔第1部「生涯」の冒頭を読んだだけで、アンナさんはこうおっしゃるかもしれません。「井上さん、違いますよ。そんなつもりではありません。」私のお答えはふたことです。「いえいえ、アンナさん、自分のことはわからないものです。どうか、最後まで読んでください。〕
アンナ贔屓と明言する著者のアンナへの思い入れが伝わってくる。『アレクシアス』はさまざまに評価されてきた歴史書である。敬愛する父親への称賛や自身の感情吐露があり、歴史書らしからぬ部分が批判されたりもする。著者は、そんな批判を歴史家の眼で検討したうえで、アンナの生涯の多様な場面を印象深く推測し、その作品を名著と高く評価している。
『アレクシアス』はアンナの自分語りをまじえた歴史書である。それ故に歴史書らしくない歴史書になっている。著者はそれを「越境する歴史学」ととらえている。そして本書には、アンナにならって著者の自分語りが随所に登場する。「このあたり、アンナの文を正確に訳す自信は私にはない」「私にはその勇気はないが、歴史学に限らず、どんな分野でも新たな可能性は越境行為にあるのではないか」などの言説に、書斎派を自認する歴史学者の矜持と自信を感じた。
アンナが皇帝あるいは皇后をめざして策動したか否かは不明である。『アレクシアス』の本文中で、アンナは繰り返し泣き、自分の不幸を嘆いているそうだ。だが、この歴史書を書くことで自分の不幸は慰められ、生きる力を得た、と著者は見ている。本書における著者のアンナへの眼差しに、歴史学者が歴史学者を観る慈愛を感じた。
皇帝の娘であるアンナは自分こそが次期皇帝にふさわしいと考えていた。自分が無理なら夫を皇帝にしたいと思った。しかし、アレクシオス1世を継いで皇帝になったのは弟のヨハネス2世だった。アンナはヨハネスと対立し、政争に敗れ、後半生は歴史家に転身し、父の業績を綴った史書『アレクシアス』を書き上げる。ギボンをはじめビザンツ史を語る史書の多くは『アレクシアス』を引用している。
そのアンナ・コムネナの伝記をビザンツ史家の井上浩一氏が書いていると知った。
『歴史学の慰め:アンナ・コムネナの生涯と作品』(井上浩一/白水社/2020.7)
井上氏の著書は、これまでに『ビザンツとスラブ』(世界の歴史11)、『生き残った帝国ビザンティン』(講談社学術文庫)、『ビザンツ皇妃列伝』を読んだ。どれも面白かった。文章が洒脱で読みやすい。本書も面白いだろうと予感して読み始めた。予感した以上に面白い歴史書だった。感動した。
本書は「第1部 生涯」「第2部 作品」から成る。第1部はアンナの伝記、第2部は彼女の著書『アレクシアス』の検討と評価である。井上氏は「あとがき」で、「楽しい歴史の旅へと誘ってくださったアンナ・コムネナさんに本書を捧げたいと思います」と述べたうえで、次のように語っている。
〔第1部「生涯」の冒頭を読んだだけで、アンナさんはこうおっしゃるかもしれません。「井上さん、違いますよ。そんなつもりではありません。」私のお答えはふたことです。「いえいえ、アンナさん、自分のことはわからないものです。どうか、最後まで読んでください。〕
アンナ贔屓と明言する著者のアンナへの思い入れが伝わってくる。『アレクシアス』はさまざまに評価されてきた歴史書である。敬愛する父親への称賛や自身の感情吐露があり、歴史書らしからぬ部分が批判されたりもする。著者は、そんな批判を歴史家の眼で検討したうえで、アンナの生涯の多様な場面を印象深く推測し、その作品を名著と高く評価している。
『アレクシアス』はアンナの自分語りをまじえた歴史書である。それ故に歴史書らしくない歴史書になっている。著者はそれを「越境する歴史学」ととらえている。そして本書には、アンナにならって著者の自分語りが随所に登場する。「このあたり、アンナの文を正確に訳す自信は私にはない」「私にはその勇気はないが、歴史学に限らず、どんな分野でも新たな可能性は越境行為にあるのではないか」などの言説に、書斎派を自認する歴史学者の矜持と自信を感じた。
アンナが皇帝あるいは皇后をめざして策動したか否かは不明である。『アレクシアス』の本文中で、アンナは繰り返し泣き、自分の不幸を嘆いているそうだ。だが、この歴史書を書くことで自分の不幸は慰められ、生きる力を得た、と著者は見ている。本書における著者のアンナへの眼差しに、歴史学者が歴史学者を観る慈愛を感じた。
ミトラ教研究の大家キュモンの定説崩壊にビックリ ― 2025年03月29日
ローマ史家・井上文則氏がミトラス教を語った新刊書を読んだ。
『異教のローマ:ミトラス教とその時代』(井上文則/講談社選書メチエ)
井上氏の本を読むのは『シルクロードとローマ帝国の興亡』(文春新書)、『軍と兵士のローマ帝国』(岩波新書)に続いて3冊目だ。前の2冊も斬新で面白かったが、本書はそれ以上に驚きの書だった。
ペルシアではミスラ神、インドではミトラ神、ローマではミトラス神と呼ばれた太陽神を祀るこの宗教(ミスラ教、ミトラ教、ミトラス教)に、私は多少の関心がある。牡牛を屠るミトラ神の彫像は印象的だ。ローマ史の本には時おりミトラ教が登場する。『ローマ帝国の神々』(小川英雄)、『ミトラの密儀』(フランツ・キュモン)なども読んだ。しかし、この宗教のぼんやりしたイメージしかつかめていない。
本書の序章では、高校世界史の教科書の以下の説明を引用している。
「ミトラ教は、インド・イランのミトラ神に起源をもち、小アジアで宗教として成立した。ミトラ神は太陽と同一視された。ローマ時代には皇帝・軍人に信者が多く、さかんに牛を屠る密儀が行われた」
私のミトラ教のイメージはこれに近い。この説明はミトラ教研究の大家フランツ・キュモン(1868-1947)の学説を踏まえているそうだ。本書の序章はキュモンの業績を紹介したうえで、その学説を大幅に相対化し、「定説の崩壊」として、キュモン以後の研究に言及している。著者の見解では、教科書の上記の記述は適切ではない。門外漢の私には驚きの序章だった。
ゾロアスター教とも関連が深いペルシアのミスラ神が、西に伝わってローマのミトラス教となり、東に伝わって弥勒になった――私はそんな壮大なイメージを抱いていた。だが、著者はそのような直接的な伝達には否定的である。
西方(ローマ帝国)への伝達については「現在ではミトラ神とミトラス神の連続性を前提とするキュモン説は批判され、両者の関係を否定する見方すら出てきている」と述べている。
東方に関しては、バーミヤンの東大仏の頭上に描かれた太陽神ミトラを例に、ミトラ神がペルシアからバーミアンを経て日本にまで伝わったと述べている。しかし、ミトラが弥勒菩薩になったという説は論拠が乏しいとしている。
ローマのミトラス教に関しては、考古学的な遺跡はあるものの文書史料が少なく、不明な点が多い。したがって諸説あるらしい。多面的な検討を踏まえたうえで著者が展開する見解は、私には驚きだった。
著者の見解では、ミトラス教は紀元70年頃、ローマで一人の教祖によって始まり、短期間でローマ世界に広まった。その教祖は、小アジアのコンマゲネ王国からローマに連れて来られた知識人の解放奴隷だった。その教祖は自らの宗教の創始者をゾロアスターとしていたので、ミトラス教徒も自らの宗教の起源をペルシアのゾロアスターと考えていた。教祖は教義を文書化していたと思われるが、それは失われた。
キリスト教の興隆によって消滅したミトラス教の成立は、キリスト教より新しかったというのである。どの宗教も初めは新興宗教だが、ミトラス教はキリスト教より新しい新興宗教で、1世紀後半から4世紀にかけて拡大し、その後、急速に消滅する。やはり、謎の新興宗教である。
キュモンは、ミトラス教などがローマの伝統宗教を破壊してキリスト教が広まる地均しをしたと考えたそうだ。著者は、キリスト教とミトラス教の流布地域のズレからキュモン説を否定し、キリスト教普及には皇帝の上からの力が大きかったとしている。興味深い見解だ。皇帝によるキリスト教支援がなければ、ミトラス教が世界宗教になった可能性はあったかもしれない。
著者はユリアヌス帝にも言及し、彼がミトラス教徒だったことは疑いないとしている。私は9年前に辻邦生の『背教者ユリアヌス』を面白く読み、その頃、ユリアヌス関連書にも目を通したが、ユリアヌスがミトラス教徒だとは認識していなかった。あらてめて確認したくなった。
『異教のローマ:ミトラス教とその時代』(井上文則/講談社選書メチエ)
井上氏の本を読むのは『シルクロードとローマ帝国の興亡』(文春新書)、『軍と兵士のローマ帝国』(岩波新書)に続いて3冊目だ。前の2冊も斬新で面白かったが、本書はそれ以上に驚きの書だった。
ペルシアではミスラ神、インドではミトラ神、ローマではミトラス神と呼ばれた太陽神を祀るこの宗教(ミスラ教、ミトラ教、ミトラス教)に、私は多少の関心がある。牡牛を屠るミトラ神の彫像は印象的だ。ローマ史の本には時おりミトラ教が登場する。『ローマ帝国の神々』(小川英雄)、『ミトラの密儀』(フランツ・キュモン)なども読んだ。しかし、この宗教のぼんやりしたイメージしかつかめていない。
本書の序章では、高校世界史の教科書の以下の説明を引用している。
「ミトラ教は、インド・イランのミトラ神に起源をもち、小アジアで宗教として成立した。ミトラ神は太陽と同一視された。ローマ時代には皇帝・軍人に信者が多く、さかんに牛を屠る密儀が行われた」
私のミトラ教のイメージはこれに近い。この説明はミトラ教研究の大家フランツ・キュモン(1868-1947)の学説を踏まえているそうだ。本書の序章はキュモンの業績を紹介したうえで、その学説を大幅に相対化し、「定説の崩壊」として、キュモン以後の研究に言及している。著者の見解では、教科書の上記の記述は適切ではない。門外漢の私には驚きの序章だった。
ゾロアスター教とも関連が深いペルシアのミスラ神が、西に伝わってローマのミトラス教となり、東に伝わって弥勒になった――私はそんな壮大なイメージを抱いていた。だが、著者はそのような直接的な伝達には否定的である。
西方(ローマ帝国)への伝達については「現在ではミトラ神とミトラス神の連続性を前提とするキュモン説は批判され、両者の関係を否定する見方すら出てきている」と述べている。
東方に関しては、バーミヤンの東大仏の頭上に描かれた太陽神ミトラを例に、ミトラ神がペルシアからバーミアンを経て日本にまで伝わったと述べている。しかし、ミトラが弥勒菩薩になったという説は論拠が乏しいとしている。
ローマのミトラス教に関しては、考古学的な遺跡はあるものの文書史料が少なく、不明な点が多い。したがって諸説あるらしい。多面的な検討を踏まえたうえで著者が展開する見解は、私には驚きだった。
著者の見解では、ミトラス教は紀元70年頃、ローマで一人の教祖によって始まり、短期間でローマ世界に広まった。その教祖は、小アジアのコンマゲネ王国からローマに連れて来られた知識人の解放奴隷だった。その教祖は自らの宗教の創始者をゾロアスターとしていたので、ミトラス教徒も自らの宗教の起源をペルシアのゾロアスターと考えていた。教祖は教義を文書化していたと思われるが、それは失われた。
キリスト教の興隆によって消滅したミトラス教の成立は、キリスト教より新しかったというのである。どの宗教も初めは新興宗教だが、ミトラス教はキリスト教より新しい新興宗教で、1世紀後半から4世紀にかけて拡大し、その後、急速に消滅する。やはり、謎の新興宗教である。
キュモンは、ミトラス教などがローマの伝統宗教を破壊してキリスト教が広まる地均しをしたと考えたそうだ。著者は、キリスト教とミトラス教の流布地域のズレからキュモン説を否定し、キリスト教普及には皇帝の上からの力が大きかったとしている。興味深い見解だ。皇帝によるキリスト教支援がなければ、ミトラス教が世界宗教になった可能性はあったかもしれない。
著者はユリアヌス帝にも言及し、彼がミトラス教徒だったことは疑いないとしている。私は9年前に辻邦生の『背教者ユリアヌス』を面白く読み、その頃、ユリアヌス関連書にも目を通したが、ユリアヌスがミトラス教徒だとは認識していなかった。あらてめて確認したくなった。
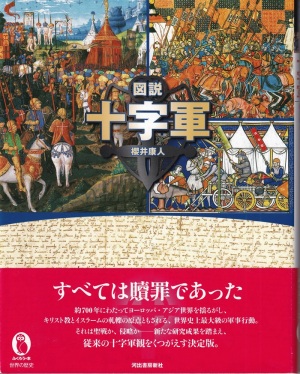









最近のコメント