KERAの新作『骨と軽蔑』は不気味なコメディ ― 2024年03月20日
日比谷のシアタークリエで『骨と軽蔑』(作・演出:ケラリーノ・サンドロヴィッチッチ、出演:宮沢りえ、鈴木杏、犬山イヌコ、堀内敬子、水川あさみ、峯村リエ、小池栄子)を観た。ケラリーノ・サンドロヴィッチッチ書下ろしの、女優7人による辛辣コメディである。
パンフレット掲載のSTORY冒頭は以下の通りだ。
「東西に分かれて内戦が続く、とある国の田舎町。作家の姉マーゴとその妹ドミー、母のグルカ、長年この家に仕えてきた家政婦のネネは、町の人から「お城」と呼ばれる巨大な邸宅に暮らしている。」
舞台台装置が、邸宅と前庭が混合したしつらえになっているのが面白い工夫だ。役者が室内にいるのか庭にいるのかは、役者の演技を観ている観客が判断するのだ。
「とある国」はおとぎ話のなかの国のようでありながら、21世紀世界の戦火の国を連想せざるを得ない。邸宅の背後からは常に砲撃の音が響いている。戦っている兵士は女性と子供である。男たちの大半はすでに戦死し、女子供を徴兵しているのだ。そんな悲惨な状況だが、舞台上の世界はどこかのんびりしていて、内戦は日常の背景に霞んでいる。戦争が日常になっている世界のコメディはやはりブラックコメディだ。
7人の女優たちが演じる役は、姉(作家)、妹、母、父の秘書で愛人、姉(作家)の担当編集者、姉(作家)の熱烈な読者、家政婦の7つである。芸達者な女優たちの多彩な会話劇に魅了された。姉(宮沢りえ)と妹(鈴木杏)の果てしなくエスカレートする口喧嘩が面白い。母、秘書、編集者が変貌していく姿も面白い。現実を映した非現実世界が不気味である。
パンフレット掲載のSTORY冒頭は以下の通りだ。
「東西に分かれて内戦が続く、とある国の田舎町。作家の姉マーゴとその妹ドミー、母のグルカ、長年この家に仕えてきた家政婦のネネは、町の人から「お城」と呼ばれる巨大な邸宅に暮らしている。」
舞台台装置が、邸宅と前庭が混合したしつらえになっているのが面白い工夫だ。役者が室内にいるのか庭にいるのかは、役者の演技を観ている観客が判断するのだ。
「とある国」はおとぎ話のなかの国のようでありながら、21世紀世界の戦火の国を連想せざるを得ない。邸宅の背後からは常に砲撃の音が響いている。戦っている兵士は女性と子供である。男たちの大半はすでに戦死し、女子供を徴兵しているのだ。そんな悲惨な状況だが、舞台上の世界はどこかのんびりしていて、内戦は日常の背景に霞んでいる。戦争が日常になっている世界のコメディはやはりブラックコメディだ。
7人の女優たちが演じる役は、姉(作家)、妹、母、父の秘書で愛人、姉(作家)の担当編集者、姉(作家)の熱烈な読者、家政婦の7つである。芸達者な女優たちの多彩な会話劇に魅了された。姉(宮沢りえ)と妹(鈴木杏)の果てしなくエスカレートする口喧嘩が面白い。母、秘書、編集者が変貌していく姿も面白い。現実を映した非現実世界が不気味である。
同時代小説は時代とともに変転する ― 2024年03月26日
『日本の同時代小説』(斎藤美奈子/岩波新書/2018.11)
6年前に出た新書を読んだ。1960年代から2010年代までの60年間の同時代小説(エンタメ、ノンフィクションも含む)を紹介した「入門書」である。斎藤美奈子の書評やエッセイには、意外な切り口でスルドク対象に迫る面白さがあり、ワクワク気分で本書を読み始めた。
本書の前半三分の一ぐらいまでは快調に読み進めることができた。だが、後半になって読書速度が急速に低下し、予想外の時間を要して何とか読了した。理由は簡単だ。団塊世代である私が同時代意識で小説を読んだのは1960年代、1970年代までで、それ以降の小説や作家にさほど馴染みがなく、読み進めるのが難儀だったからである。
作家中心ではなく作品中心に記述を進める本書は、10年ごとに章を区切り、それぞれの年代に次のようなタイトルを付けている。
1960年代 知識人の凋落
1970年代 記録文学の時代
1980年代 遊園地化する純文学
1990年代 女性作家の台頭
2000年代 戦争と格差社会
2010年代 ディストピアを超えて
こう並べると、ナルホドという気になり、たかだか10年でも時代相は変転し、それを反映した「同時代」小説が次々に生み出されてきたとわかる。団塊世代老人の私は、1960年代・1970年代の同時代意識がすでの時代遅れだと認識せざる得ないが、せわしなく「同時代」を追いかけても仕方ないという気分にもなる。
斎藤美奈子流のスルドイ指摘は本書にも随所にある。
村上龍の『希望の国のエクソダス』や丸谷才一の『女ざかり』をオッチョコチョイな小説と評しているのが面白い。これらの小説を面白く読んだ私もオッチョコチョイかもしれない。
純文学のDNAを「ヘタレな知識人」「ヤワなインテリ」と喝破し、純文学と大衆文学の違いを解説した桑原武夫の『文学入門』を「現役をとうに退いた骨董品」と切り捨てているのもすがすがしい。私は、高校一年の夏休みに読んだ『文学入門』で桑原武夫ファンになったが、斎藤美奈子の言説にも納得させられてしまう。
斎藤美奈子のガイドブックで、私の知らない「同時代小説」が続々と生み出されている現状に触れることができたのが収穫だった。
6年前に出た新書を読んだ。1960年代から2010年代までの60年間の同時代小説(エンタメ、ノンフィクションも含む)を紹介した「入門書」である。斎藤美奈子の書評やエッセイには、意外な切り口でスルドク対象に迫る面白さがあり、ワクワク気分で本書を読み始めた。
本書の前半三分の一ぐらいまでは快調に読み進めることができた。だが、後半になって読書速度が急速に低下し、予想外の時間を要して何とか読了した。理由は簡単だ。団塊世代である私が同時代意識で小説を読んだのは1960年代、1970年代までで、それ以降の小説や作家にさほど馴染みがなく、読み進めるのが難儀だったからである。
作家中心ではなく作品中心に記述を進める本書は、10年ごとに章を区切り、それぞれの年代に次のようなタイトルを付けている。
1960年代 知識人の凋落
1970年代 記録文学の時代
1980年代 遊園地化する純文学
1990年代 女性作家の台頭
2000年代 戦争と格差社会
2010年代 ディストピアを超えて
こう並べると、ナルホドという気になり、たかだか10年でも時代相は変転し、それを反映した「同時代」小説が次々に生み出されてきたとわかる。団塊世代老人の私は、1960年代・1970年代の同時代意識がすでの時代遅れだと認識せざる得ないが、せわしなく「同時代」を追いかけても仕方ないという気分にもなる。
斎藤美奈子流のスルドイ指摘は本書にも随所にある。
村上龍の『希望の国のエクソダス』や丸谷才一の『女ざかり』をオッチョコチョイな小説と評しているのが面白い。これらの小説を面白く読んだ私もオッチョコチョイかもしれない。
純文学のDNAを「ヘタレな知識人」「ヤワなインテリ」と喝破し、純文学と大衆文学の違いを解説した桑原武夫の『文学入門』を「現役をとうに退いた骨董品」と切り捨てているのもすがすがしい。私は、高校一年の夏休みに読んだ『文学入門』で桑原武夫ファンになったが、斎藤美奈子の言説にも納得させられてしまう。
斎藤美奈子のガイドブックで、私の知らない「同時代小説」が続々と生み出されている現状に触れることができたのが収穫だった。
『ヨーロッパ史』は、やや抽象的な歴史エッセイ ― 2024年03月31日
『ヨーロッパ史:拡大と統合の力学』(大月康弘/岩波新書)
朝日新聞(2024.3.23)の書評で、ビザンツ史の専門家が書いた本書を「西欧中心の歴史観に異議を唱える」と紹介していた。それを読んで、すぐに購入した。
私は一昨年からビザンツ史の本を何冊か読み、よく知らなかったこの「帝国」の面白さに魅せられている。また、西欧中心歴史観の見直しは、高齢の私が歴史書を読む際のテーマの一つだ。だから、大きな期待を抱いて本書を読み始めた。だが、思った以上の難物だった。
本書は「ヨーロッパ史とは何か」というやや抽象的な課題を論じていて、キー概念は「キリスト教ローマ帝国」である。ビザンツ帝国が自らを「ローマ帝国」と自認していたことをベースに、古代末期から中世・近代・現代に至るヨーロッパを支えてきた観念を「キリスト教ローマ帝国」という捉え方で論じている。
「時代精神」「キリスト教的時間意識」「終末意識」などの抽象概念や「当為」といった哲学用語が多く、すらすらとは読めない。私の知らない歴史研究者たちの言説紹介も多い。かなり専門的でやや難解な歴史エッセイである。断片的には面白い話も多いが全体像をつかみ難い。いずれ、覚悟して再読すれば理解が深まるかもしれない。
本書が描くヨーロッパの原点は「キリスト教ローマ帝国」としてのビザンツ帝国であり、それとフランク王国の登場やアラブ・イスラムの侵入が絡んで「キリスト教ローマ帝国」たるヨーロッパ史が始まるというストーリーになっている。
著者は「おわりに」で次のように述べている。
「ヨーロッパといえば、イギリス、フランス、ドイツと三つの国を挙げる人は多い。これにイタリアを加え、あるいはスペインを含めたいと思うことだろう。私であれば、すでに第3章で述べたように、東欧、ギリシア、トルコ、またキプロスなども当然ながらキリスト教世界としての基層を共有する「ヨーロッパ」だ、としたいところである。」
1453年、コンスタンティノープルを陥したオスマン帝国のメフメト2世は、帝都侵入後「ルーム・カエサル」と称したそうだ。本書でそれを知って驚いた。
朝日新聞(2024.3.23)の書評で、ビザンツ史の専門家が書いた本書を「西欧中心の歴史観に異議を唱える」と紹介していた。それを読んで、すぐに購入した。
私は一昨年からビザンツ史の本を何冊か読み、よく知らなかったこの「帝国」の面白さに魅せられている。また、西欧中心歴史観の見直しは、高齢の私が歴史書を読む際のテーマの一つだ。だから、大きな期待を抱いて本書を読み始めた。だが、思った以上の難物だった。
本書は「ヨーロッパ史とは何か」というやや抽象的な課題を論じていて、キー概念は「キリスト教ローマ帝国」である。ビザンツ帝国が自らを「ローマ帝国」と自認していたことをベースに、古代末期から中世・近代・現代に至るヨーロッパを支えてきた観念を「キリスト教ローマ帝国」という捉え方で論じている。
「時代精神」「キリスト教的時間意識」「終末意識」などの抽象概念や「当為」といった哲学用語が多く、すらすらとは読めない。私の知らない歴史研究者たちの言説紹介も多い。かなり専門的でやや難解な歴史エッセイである。断片的には面白い話も多いが全体像をつかみ難い。いずれ、覚悟して再読すれば理解が深まるかもしれない。
本書が描くヨーロッパの原点は「キリスト教ローマ帝国」としてのビザンツ帝国であり、それとフランク王国の登場やアラブ・イスラムの侵入が絡んで「キリスト教ローマ帝国」たるヨーロッパ史が始まるというストーリーになっている。
著者は「おわりに」で次のように述べている。
「ヨーロッパといえば、イギリス、フランス、ドイツと三つの国を挙げる人は多い。これにイタリアを加え、あるいはスペインを含めたいと思うことだろう。私であれば、すでに第3章で述べたように、東欧、ギリシア、トルコ、またキプロスなども当然ながらキリスト教世界としての基層を共有する「ヨーロッパ」だ、としたいところである。」
1453年、コンスタンティノープルを陥したオスマン帝国のメフメト2世は、帝都侵入後「ルーム・カエサル」と称したそうだ。本書でそれを知って驚いた。


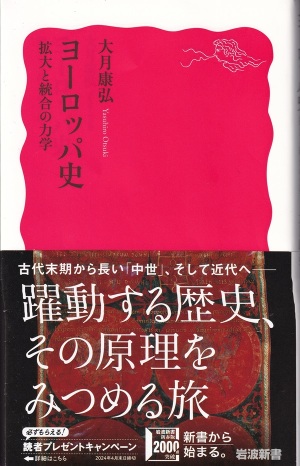
最近のコメント