夏の雑草はスゴイ ― 2022年09月03日
3週間半ぶりに八ヶ岳南麓の山小屋へ行くと、前庭が雑草に覆われていた。入口の階段にもツル草が伸びている。前回はインゲンを収穫した。そのインゲンを植えた箇所まで(約3メートル)も長く伸びた雑草に覆われていて近づけない。
あいにくの雨天だったが、夕方になって雨が上がったので、急いで草刈り機を始動させて作業を始めた。やがて、また雨が降り出したので、小屋周辺の草刈りだけで中断した。この春以来3回目の草刈り作業である。
昨年の記録を調べると、同じ頃に3週間ぶりに山小屋に行き、雑草の繁茂に圧倒されて草刈り作業をしている。あのとき、7月下旬か8月上旬には草刈りをしなければと思ったのだが、1年経つとすっかり忘れて、同じようなことを繰り返している。
あいにくの雨天だったが、夕方になって雨が上がったので、急いで草刈り機を始動させて作業を始めた。やがて、また雨が降り出したので、小屋周辺の草刈りだけで中断した。この春以来3回目の草刈り作業である。
昨年の記録を調べると、同じ頃に3週間ぶりに山小屋に行き、雑草の繁茂に圧倒されて草刈り作業をしている。あのとき、7月下旬か8月上旬には草刈りをしなければと思ったのだが、1年経つとすっかり忘れて、同じようなことを繰り返している。
奇妙な帝国ビザンティンには独特の魅力がある ― 2022年09月05日
このところビザンティン史モノを何冊か読んでいる。『ビザンツとスラブ(中公版「世界の歴史 11」』に続いて同じ著者の次の本を読んだ。
『生き残った帝国ビザンティン』(井上浩一/講談社学術文庫)
先に読んだ本の巻末の参考文献で本書を「講談社現代新書」と紹介していたので、大型書店の棚で探したが見つからず、目録からも消えていた。よく調べると、学術文庫に格上げ(?)されていた。とても読みやすく、私が最近読んだビザンティン史本数冊のなかで一番面白かった。ビザンティンの位置づけ、特徴、内実などを要領よく解説していて、わかりやすい。
本書をわかりやすいと感じたのは、既読の数冊でビザンティン史に関する基礎知識が多少なりとも蓄積されていたせいだと思う。歴史書とは、何冊かの類書をくり返し読んで、はじめて面白く感じるものかもしれない。やっかいなことである。
ビザンティンは「ローマ人の帝国」という建前を守る保守性と、現実に対応する柔軟性を併せもって中世を生き延びた奇妙なキリスト教帝国である。そこには独特の魅力もある。
ローマ帝国がなぜキリスト教を受け容れたか、に関する著者の見解が興味深い。次のように述べている。
「ローマ帝国とキリスト教が結びついたことは、私には当然のことのように思える。むしろ支配者にとってこれほど都合のよい教えは、他にさがすのがむずかしいとすらいえる。」
つまり、「神に由来した権威=皇帝」すれば支配が容易になるということである。キリスト者からは反論もあるだろうが、面白い見解だ。「異端とは聖書に忠実な人」という皮肉な指摘も首肯できる。
また、キリスト教が普及したのは、オリエント型の神とギリシア型の神を折衷させた「受肉」という「奇蹟」によるという見方も面白い。なるほどと思った。
本書のエピローグで著者は次のように述べている。
「外見にだまされて、ビザンティン帝国を、ひたすら建前を維持し、伝統を墨守するだけで生き延びていった国家とみなすべきではない。ビザンティン帝国一千年の歴史のかなめは、状況に応じて生まれ変わっていったところにある、と私は考える。」
ビザンティン帝国にはしたたかさの魅力がある。水木しげるのねずみ男を連想した。
『生き残った帝国ビザンティン』(井上浩一/講談社学術文庫)
先に読んだ本の巻末の参考文献で本書を「講談社現代新書」と紹介していたので、大型書店の棚で探したが見つからず、目録からも消えていた。よく調べると、学術文庫に格上げ(?)されていた。とても読みやすく、私が最近読んだビザンティン史本数冊のなかで一番面白かった。ビザンティンの位置づけ、特徴、内実などを要領よく解説していて、わかりやすい。
本書をわかりやすいと感じたのは、既読の数冊でビザンティン史に関する基礎知識が多少なりとも蓄積されていたせいだと思う。歴史書とは、何冊かの類書をくり返し読んで、はじめて面白く感じるものかもしれない。やっかいなことである。
ビザンティンは「ローマ人の帝国」という建前を守る保守性と、現実に対応する柔軟性を併せもって中世を生き延びた奇妙なキリスト教帝国である。そこには独特の魅力もある。
ローマ帝国がなぜキリスト教を受け容れたか、に関する著者の見解が興味深い。次のように述べている。
「ローマ帝国とキリスト教が結びついたことは、私には当然のことのように思える。むしろ支配者にとってこれほど都合のよい教えは、他にさがすのがむずかしいとすらいえる。」
つまり、「神に由来した権威=皇帝」すれば支配が容易になるということである。キリスト者からは反論もあるだろうが、面白い見解だ。「異端とは聖書に忠実な人」という皮肉な指摘も首肯できる。
また、キリスト教が普及したのは、オリエント型の神とギリシア型の神を折衷させた「受肉」という「奇蹟」によるという見方も面白い。なるほどと思った。
本書のエピローグで著者は次のように述べている。
「外見にだまされて、ビザンティン帝国を、ひたすら建前を維持し、伝統を墨守するだけで生き延びていった国家とみなすべきではない。ビザンティン帝国一千年の歴史のかなめは、状況に応じて生まれ変わっていったところにある、と私は考える。」
ビザンティン帝国にはしたたかさの魅力がある。水木しげるのねずみ男を連想した。
往年の井上ひさしの姿を綴った古書を読んだ ― 2022年09月07日
先月、こまつ座公演『頭痛肩こり樋口一葉』を23年ぶりに観た。その折に23年前の公演パンフを探し出し、今回の公演パンフと読み比べていて、こまつ座の代表が井上都から井上麻矢に変わっているのに気づいた。
38年前、井上ひさしが当時の妻・好子と共に立ち上げたのがこまつ座で、社長として活躍する井上好子の名はメディアでよく目にした。数年後の1986年、二人の離婚がテレビや週刊誌で大きく報じられた。あのとき妻は劇団を去り、娘がこまつ座社長になったと聞いていた。それが現在まで継続していると思っていたが、その後、別の娘に交代したようだ。
ネット検索してみると、2009年に長女から三女に社長が代り、翌2010年に井上ひさしは逝去している。そのとき、井上ひさしは長女・次女とは絶縁状態で彼女らは葬儀にも参列できなかったそうだ。「なにがあったのだ」とのミーハー的野次馬精神で、元妻と三女の次の本を古書で入手して読んだ。
『表裏井上ひさし協奏曲』(西館好子/牧野出版/2011.9)
『激突家族:井上家に生まれて』(石川麻矢/中央公論社/1998.6)
元妻による『表裏…』は井上ひさし逝去翌年の本で、逝去前後の娘たちの経緯にも簡単に触れている。三女による『激突…』は彼女がこまつ座に関わる以前の本なので、劇団への言及はあまりない。
この二冊を読むと井上ひさしという作家を中心に展開する異様な情景が伝わってきて、びっくりする。こまつ座の社長交代などへの関心は薄れ、作家という生き方の壮絶さに圧倒される。
娘の本より元妻の『表裏…』の方がはるかに面白い。作家への距離が最も近い人の回想記だから生々しい。「協奏曲」というよりは「狂騒曲」である。巻末には長女・井上都による「おわりもはじまり 父と母、そして私」という文章も収録している。三女の回想記『激突…』は、過激で過剰な両親に呆然としつつも、自身の道をしたたかたに生きていく様を綴っている。
このテの本には自己肯定バイアスがかかりやすいとは思うが、作家・井上ひさしが身内に見せた姿が興味深い。どんな人間にも外面と内面があるのは当然である。元妻も娘たちも、作家の身勝手に振り回されつつも、結局は元夫・父である「作家」を高く評価しているように見える。
『表裏…』には、不倫中の著者が講談社、新潮社、文藝春秋の重役に招かれた慰労会シーンがある。「離婚はダメ。悪妻に徹して作家を支えてくれ」と懇願されるのである。「作家は生活者ではない。その精神の一部はまるで幼児」「作家の場合は狂気なほど世の中が忘れない」などの発言もある。また、スキャンダルを起こしても三社から出版される本や雑誌が二人(作家と妻)を悪く書くことはない、という保証までしている。30年ほど昔の話である。
かつて、作家は出版社の収益を生み出すスターだった。いまは、どうなのだろうか。
38年前、井上ひさしが当時の妻・好子と共に立ち上げたのがこまつ座で、社長として活躍する井上好子の名はメディアでよく目にした。数年後の1986年、二人の離婚がテレビや週刊誌で大きく報じられた。あのとき妻は劇団を去り、娘がこまつ座社長になったと聞いていた。それが現在まで継続していると思っていたが、その後、別の娘に交代したようだ。
ネット検索してみると、2009年に長女から三女に社長が代り、翌2010年に井上ひさしは逝去している。そのとき、井上ひさしは長女・次女とは絶縁状態で彼女らは葬儀にも参列できなかったそうだ。「なにがあったのだ」とのミーハー的野次馬精神で、元妻と三女の次の本を古書で入手して読んだ。
『表裏井上ひさし協奏曲』(西館好子/牧野出版/2011.9)
『激突家族:井上家に生まれて』(石川麻矢/中央公論社/1998.6)
元妻による『表裏…』は井上ひさし逝去翌年の本で、逝去前後の娘たちの経緯にも簡単に触れている。三女による『激突…』は彼女がこまつ座に関わる以前の本なので、劇団への言及はあまりない。
この二冊を読むと井上ひさしという作家を中心に展開する異様な情景が伝わってきて、びっくりする。こまつ座の社長交代などへの関心は薄れ、作家という生き方の壮絶さに圧倒される。
娘の本より元妻の『表裏…』の方がはるかに面白い。作家への距離が最も近い人の回想記だから生々しい。「協奏曲」というよりは「狂騒曲」である。巻末には長女・井上都による「おわりもはじまり 父と母、そして私」という文章も収録している。三女の回想記『激突…』は、過激で過剰な両親に呆然としつつも、自身の道をしたたかたに生きていく様を綴っている。
このテの本には自己肯定バイアスがかかりやすいとは思うが、作家・井上ひさしが身内に見せた姿が興味深い。どんな人間にも外面と内面があるのは当然である。元妻も娘たちも、作家の身勝手に振り回されつつも、結局は元夫・父である「作家」を高く評価しているように見える。
『表裏…』には、不倫中の著者が講談社、新潮社、文藝春秋の重役に招かれた慰労会シーンがある。「離婚はダメ。悪妻に徹して作家を支えてくれ」と懇願されるのである。「作家は生活者ではない。その精神の一部はまるで幼児」「作家の場合は狂気なほど世の中が忘れない」などの発言もある。また、スキャンダルを起こしても三社から出版される本や雑誌が二人(作家と妻)を悪く書くことはない、という保証までしている。30年ほど昔の話である。
かつて、作家は出版社の収益を生み出すスターだった。いまは、どうなのだろうか。
寺山修司の『青ひげ公の城』は夢幻の見世物芝居 ― 2022年09月15日
下北沢ザ・スズナリでProject Nyx公演『青ひげ公の城』(作:寺山修司、構成:水嶋カンナ、演出:金守珍、出演:水嶋カンナ、のぐち和美、今川宇宙、他)を観た。
半世紀以上昔のアングラの時代、私は唐十郎の状況劇場はよく観たが、寺山修司の天井桟敷の芝居は観ていない。当時、寺山修司はすでにビッグすぎて敬遠したくなる存在だった。あれから長い年月が経過し、寺山修司の芝居が上演されると知り、どんな舞台なのか、あらためて観たくなった。
寺山修司の芝居を観るのは、何年か前に観た『毛皮のマリー』以来2回目だと思う。『青ひげ公の城』の初演は1979年、西武劇場だそうだ。今回の公演は女性だけによる美女劇と謳っている。その通り20数名の女優がきらびやかな衣装で夢幻的な舞台を紡ぎ出す。
しかし、一人だけ男性が登場する。奇術師の渋谷駿である。開演前に舞台に現れ「スマホの電源を切ってください」などの観劇の注意を述べ、いきなり観客を巻き込んだ奇術を披露する。彼が舞台回しとのことだが、芝居が進行していくなかで何度も鮮やかな奇術を披露し、目を見張らされた。
実は私の席は最前列で、最初の奇術に巻き込まれた観客の一人が私だった。観劇前から奇術のトリックに引き込まれたのである。奇術にタネやシカケがあるのは当然だ。目を凝らして目の前でくり広げられる奇術のタネやシカケを見極めようとした。しかし、奇術師の手腕に感服させられるだけだった。
この芝居の戯曲は未読なので、奇術師の登場が今回の公演独自の試みかどうかはわからない。元から「魔術師」という登場人物があるそうだが、それが次々と奇術を披露したかは不明だ。
この芝居、一応の設定とストーリーがあり、現実と舞台が溶解していく展開だが、基本的には寺山修司らしい「見世物芝居」である。おどろおどろしくも蠱惑的な舞台装置のなかで奇抜な衣装の役者たりが幻想絵画のような情景を見せてくれる。それは、本来は不思議な奇術が日常光景のような摩訶不思議な世界である。
半世紀以上昔のアングラの時代、私は唐十郎の状況劇場はよく観たが、寺山修司の天井桟敷の芝居は観ていない。当時、寺山修司はすでにビッグすぎて敬遠したくなる存在だった。あれから長い年月が経過し、寺山修司の芝居が上演されると知り、どんな舞台なのか、あらためて観たくなった。
寺山修司の芝居を観るのは、何年か前に観た『毛皮のマリー』以来2回目だと思う。『青ひげ公の城』の初演は1979年、西武劇場だそうだ。今回の公演は女性だけによる美女劇と謳っている。その通り20数名の女優がきらびやかな衣装で夢幻的な舞台を紡ぎ出す。
しかし、一人だけ男性が登場する。奇術師の渋谷駿である。開演前に舞台に現れ「スマホの電源を切ってください」などの観劇の注意を述べ、いきなり観客を巻き込んだ奇術を披露する。彼が舞台回しとのことだが、芝居が進行していくなかで何度も鮮やかな奇術を披露し、目を見張らされた。
実は私の席は最前列で、最初の奇術に巻き込まれた観客の一人が私だった。観劇前から奇術のトリックに引き込まれたのである。奇術にタネやシカケがあるのは当然だ。目を凝らして目の前でくり広げられる奇術のタネやシカケを見極めようとした。しかし、奇術師の手腕に感服させられるだけだった。
この芝居の戯曲は未読なので、奇術師の登場が今回の公演独自の試みかどうかはわからない。元から「魔術師」という登場人物があるそうだが、それが次々と奇術を披露したかは不明だ。
この芝居、一応の設定とストーリーがあり、現実と舞台が溶解していく展開だが、基本的には寺山修司らしい「見世物芝居」である。おどろおどろしくも蠱惑的な舞台装置のなかで奇抜な衣装の役者たりが幻想絵画のような情景を見せてくれる。それは、本来は不思議な奇術が日常光景のような摩訶不思議な世界である。
ビザンツ帝国の概説書をさらに2冊読んだ ― 2022年09月17日
ビザンツ帝国史の概説書を何冊か読み、クセになってさらに2冊の概説書を読んだ。
『ビザンツの国家と社会』(根津由喜夫/世界史リブレット/山川出版社)
『ビザンツ帝国史』(ポール・ルメルル/西村六郎訳/文庫クセジュ/白水社)
前者は小冊子、後者はページ数の少ない新書版である。気力減退気味の最近の私でも、手軽に読み進めることができた。
『ビザンツの国家と社会』には、私の知らない固有名詞が頻出する。概説書数冊でビザンツ史が把握できるものではないと再認識した。
本書で印象に残った指摘は、各地で力をつけたテマ(軍管区)が西欧の封建領主のような分権化に進まなかった理由である。著者は次のように述べている。
「7世紀末から9世紀初頭にかけて強大なテマ軍は中央政府にたいしてしばしば反乱の兵をあげたが、それらがテマの分離独立という形態をとらず、つねに首都に攻め上がって政権の奪取をめざすものとなったのも、中央政府が富の巨大な再分配機構としての機能を保ちつづけていたためにほかならかった。」
ビザンツ帝国で簒奪帝が多い一因がわかった気がする。
『ビザンツ帝国史』の著者は、訳者の解説によれば、フランスを代表する20世紀の国際的ビザンツ学者の一人だそうだ。
その著者の「はしがき」が私には興味深かった。ビザンツ学は17世紀フランスの碩学たちが築き、18世紀の啓蒙思想家たちはビザンツを「絶対君主政治」「宗教国家」と見なして激しく非難した。それは、フランス革命前夜の思潮を反映した偏見に近い。その偏見が現在にまで続いているそうだ。「ビザンツ」という言葉に「権謀術数」「曲学阿世」「些末主義」「お追従者」「迷宮」など否定的な意味があると聞いていたが、その淵源が見えた気がする。
『ビザンツ帝国史』は教科書的な解説書である。特にキリスト教の正統と異端の事情や東教会と西教会の関係を簡潔にわかりやすく解説している。キリスト教関連の話はゴチャゴチャしていて部外者の私にはわかりにくいので、知識整理の一助になる。
ビザンツ史千年を1冊の新書本で教科書的に概説すると、駆け足になるのは仕方ない。一回通読しただけでは把握した気がしない。
『ビザンツの国家と社会』(根津由喜夫/世界史リブレット/山川出版社)
『ビザンツ帝国史』(ポール・ルメルル/西村六郎訳/文庫クセジュ/白水社)
前者は小冊子、後者はページ数の少ない新書版である。気力減退気味の最近の私でも、手軽に読み進めることができた。
『ビザンツの国家と社会』には、私の知らない固有名詞が頻出する。概説書数冊でビザンツ史が把握できるものではないと再認識した。
本書で印象に残った指摘は、各地で力をつけたテマ(軍管区)が西欧の封建領主のような分権化に進まなかった理由である。著者は次のように述べている。
「7世紀末から9世紀初頭にかけて強大なテマ軍は中央政府にたいしてしばしば反乱の兵をあげたが、それらがテマの分離独立という形態をとらず、つねに首都に攻め上がって政権の奪取をめざすものとなったのも、中央政府が富の巨大な再分配機構としての機能を保ちつづけていたためにほかならかった。」
ビザンツ帝国で簒奪帝が多い一因がわかった気がする。
『ビザンツ帝国史』の著者は、訳者の解説によれば、フランスを代表する20世紀の国際的ビザンツ学者の一人だそうだ。
その著者の「はしがき」が私には興味深かった。ビザンツ学は17世紀フランスの碩学たちが築き、18世紀の啓蒙思想家たちはビザンツを「絶対君主政治」「宗教国家」と見なして激しく非難した。それは、フランス革命前夜の思潮を反映した偏見に近い。その偏見が現在にまで続いているそうだ。「ビザンツ」という言葉に「権謀術数」「曲学阿世」「些末主義」「お追従者」「迷宮」など否定的な意味があると聞いていたが、その淵源が見えた気がする。
『ビザンツ帝国史』は教科書的な解説書である。特にキリスト教の正統と異端の事情や東教会と西教会の関係を簡潔にわかりやすく解説している。キリスト教関連の話はゴチャゴチャしていて部外者の私にはわかりにくいので、知識整理の一助になる。
ビザンツ史千年を1冊の新書本で教科書的に概説すると、駆け足になるのは仕方ない。一回通読しただけでは把握した気がしない。
沖縄の離島の戦後史を凝縮した『豚と真珠湾―幻の八重山共和国』 ― 2022年09月19日
紀伊國屋サザンシアターで青年劇場公演『豚と真珠湾―幻の八重山共和国』(作:斎藤憐、演出:大谷賢治郎)を観た。
斎藤憐の芝居を観るのは初めてである。1970年に観た『翼を燃やす天使たちの舞踏』(演劇センター68/70)の作者4人の1人が彼だったが、あの黒テント芝居は佐藤信のイメージが強い。『豚と真珠湾』は2007年の作品である。斎藤憐は2011年に70歳で亡くなったそうだ。
チラシに「戦後から5年間のこの島(石垣島)でたくましく生きる人々の物語」とあり、基地問題が継続している沖縄を描いたシリアスな芝居だろうと思った。サブタイトルに「幻の八重山共和国」とあるので、何か超現実的な世界が浮かびあがってくる舞台かなとも予感した。だが、そんなことはなく、戦後のひとときに島民が想起した「幻の八重山共和国」をリアルに描いていた。「幻」はまさに幻である。
舞台は終戦直後の石垣島の料亭――とは言っても、孤児たちを養っている飲み屋の風情だ。その料亭を舞台にした戦後の5年間を描いた群像劇である。料亭の女主人をはじめ、さまざまな島民、台湾出身の密貿易人、糸満出身の女密貿易人、沖縄出身ハワイ移民2世の進駐軍通訳など、さまざまな人物が登場する。沖縄の戦後史を図解するような人間模様であり、うまく工夫していると感心した。ハワイから沖縄への豚の移送は朝ドラ『ちむどんどん』にも出てきた。伝説の英雄アカハチへの言及もある。
この芝居には、石垣島で新聞発行を始める青年が登場する。それを観て、かつて石垣島に行ったときに八重山の新聞について考えたことを思い出した。また、舞台を眺めながら、かつて読んだ『ナツコ 沖縄密貿易の女王』(奥野修司)や『台湾海峡一九四九』(龍應台)が浮かんできた。沖縄の離島の戦後史のあれやこれやの情報と情況を詰め込んだ舞台である。
斎藤憐の芝居を観るのは初めてである。1970年に観た『翼を燃やす天使たちの舞踏』(演劇センター68/70)の作者4人の1人が彼だったが、あの黒テント芝居は佐藤信のイメージが強い。『豚と真珠湾』は2007年の作品である。斎藤憐は2011年に70歳で亡くなったそうだ。
チラシに「戦後から5年間のこの島(石垣島)でたくましく生きる人々の物語」とあり、基地問題が継続している沖縄を描いたシリアスな芝居だろうと思った。サブタイトルに「幻の八重山共和国」とあるので、何か超現実的な世界が浮かびあがってくる舞台かなとも予感した。だが、そんなことはなく、戦後のひとときに島民が想起した「幻の八重山共和国」をリアルに描いていた。「幻」はまさに幻である。
舞台は終戦直後の石垣島の料亭――とは言っても、孤児たちを養っている飲み屋の風情だ。その料亭を舞台にした戦後の5年間を描いた群像劇である。料亭の女主人をはじめ、さまざまな島民、台湾出身の密貿易人、糸満出身の女密貿易人、沖縄出身ハワイ移民2世の進駐軍通訳など、さまざまな人物が登場する。沖縄の戦後史を図解するような人間模様であり、うまく工夫していると感心した。ハワイから沖縄への豚の移送は朝ドラ『ちむどんどん』にも出てきた。伝説の英雄アカハチへの言及もある。
この芝居には、石垣島で新聞発行を始める青年が登場する。それを観て、かつて石垣島に行ったときに八重山の新聞について考えたことを思い出した。また、舞台を眺めながら、かつて読んだ『ナツコ 沖縄密貿易の女王』(奥野修司)や『台湾海峡一九四九』(龍應台)が浮かんできた。沖縄の離島の戦後史のあれやこれやの情報と情況を詰め込んだ舞台である。
『北条氏の時代』(本郷和人)で鎌倉時代の面白さを知った ― 2022年09月23日
先日、本郷和人氏の『歴史学者という病』を面白く読み、この著者の他の本にも興味がわき、次の新書を読んだ。
『北条氏の時代』(本郷和人/文春新書)
期待にたがわぬ面白い本である。大河ドラマ『鎌倉殿の十三人』に当て込んだ新書だろうが、日本の中世史に不案内は私には大いに勉強になった。著者は「あとがき」で次のように述懐してる。
「長年の研究生成果を詰め込んで。独自のものをまとめることができたと自負しています(自惚れが過ぎるかな)。」
北条氏を中心にした鎌倉時代150年を概説し、随所に著者の見解表明がある。単なる出来事の羅列ではなく、時代の趨勢のなかでの出来事の位置づけを的確に解説している。北条氏の興亡に歴史の面白さと教訓を感じた。どの地域のどんな時代でも、その歴史を深く探究すれば独自の面白さを発見できるのだとは思うが、本書によって鎌倉時代が興味深い時代だと認識した。
本書はタイトル通り、北条氏の歴史を描いている。全6章のタイトルは以下の通りだ。この章題が150年の歴史のあらましを語っている。
第1章 北条時政――敵をつくらない陰謀家
第2章 北条義時――「世論」を味方に朝廷を破る
第3章 北条泰時――「先進」京都に学んだ式目制定
第4章 北条時頼――民を視野に入れた統治力
第5章 北条時宗、北条貞時――強すぎた世襲権力の弊害
第6章 北条高時――得宗一人勝ち体制が滅びた理由
上記7人の「時〇」「〇時」たちは執権であり得宗(北条本家の当主)でもある。第2章まで、つまり義時までの50年弱で本書の約半分である。
本書前半は今回の大河ドラマに重なる時代になり、読み進めながら、あの大河ドラマが思った以上に史実をふまえていると知った。ドラマでは人物像を美化・戯画化しているが、三浦義村は本書とドラマのイメージが重なる。多くの重要事件や陰謀にかかわったキーパーソンであり、いわば曲者である。
本書で意外に感じたのは実朝像である。実朝といえば太宰治の『右大臣実朝』や吉本隆明の『源実朝』の印象が強く、政治から距離を置いた歌人のイメージがある。しかし、著者は実朝を「自ら多くの政治的決断を行った」とし、和歌作りも政治的行動の一環と見なしている。そして、実朝暗殺に関して次のように述べている。
「私は、この事件は御家人たちの総意であり、それをくみ取った義時によって起こされたと考えています。理由は再三述べてきた通り、実朝が将軍の存在意義を忘れてしまい、御家人の利益代表でなくなったことに尽きます。」
本書後半の約100年は、私にとってはほとんど未知の時代で、著者の慧眼に蒙を啓かれた。貨幣経済の発展にともない、鎌倉幕府内に「御家人ファースト派」対「統治派」のオセロゲームのようなせめぎ合いがあったという指摘が興味深い。
鎌倉時代とは、地方の無名の一族に過ぎなかった北条氏が勢力を拡大し、将軍や天皇を決める力をもつ実質的な「日本国王」にまで登りつめて行く歴史である。そして、その勢力の拡大こそが滅亡の要因になったという顛末も面白い。北条氏150年の興亡史に歴史のダイナミズムを感じる。同時に、いつの時代でも人間の集団の扱いはやっかいで難しいと思うしかない。
『北条氏の時代』(本郷和人/文春新書)
期待にたがわぬ面白い本である。大河ドラマ『鎌倉殿の十三人』に当て込んだ新書だろうが、日本の中世史に不案内は私には大いに勉強になった。著者は「あとがき」で次のように述懐してる。
「長年の研究生成果を詰め込んで。独自のものをまとめることができたと自負しています(自惚れが過ぎるかな)。」
北条氏を中心にした鎌倉時代150年を概説し、随所に著者の見解表明がある。単なる出来事の羅列ではなく、時代の趨勢のなかでの出来事の位置づけを的確に解説している。北条氏の興亡に歴史の面白さと教訓を感じた。どの地域のどんな時代でも、その歴史を深く探究すれば独自の面白さを発見できるのだとは思うが、本書によって鎌倉時代が興味深い時代だと認識した。
本書はタイトル通り、北条氏の歴史を描いている。全6章のタイトルは以下の通りだ。この章題が150年の歴史のあらましを語っている。
第1章 北条時政――敵をつくらない陰謀家
第2章 北条義時――「世論」を味方に朝廷を破る
第3章 北条泰時――「先進」京都に学んだ式目制定
第4章 北条時頼――民を視野に入れた統治力
第5章 北条時宗、北条貞時――強すぎた世襲権力の弊害
第6章 北条高時――得宗一人勝ち体制が滅びた理由
上記7人の「時〇」「〇時」たちは執権であり得宗(北条本家の当主)でもある。第2章まで、つまり義時までの50年弱で本書の約半分である。
本書前半は今回の大河ドラマに重なる時代になり、読み進めながら、あの大河ドラマが思った以上に史実をふまえていると知った。ドラマでは人物像を美化・戯画化しているが、三浦義村は本書とドラマのイメージが重なる。多くの重要事件や陰謀にかかわったキーパーソンであり、いわば曲者である。
本書で意外に感じたのは実朝像である。実朝といえば太宰治の『右大臣実朝』や吉本隆明の『源実朝』の印象が強く、政治から距離を置いた歌人のイメージがある。しかし、著者は実朝を「自ら多くの政治的決断を行った」とし、和歌作りも政治的行動の一環と見なしている。そして、実朝暗殺に関して次のように述べている。
「私は、この事件は御家人たちの総意であり、それをくみ取った義時によって起こされたと考えています。理由は再三述べてきた通り、実朝が将軍の存在意義を忘れてしまい、御家人の利益代表でなくなったことに尽きます。」
本書後半の約100年は、私にとってはほとんど未知の時代で、著者の慧眼に蒙を啓かれた。貨幣経済の発展にともない、鎌倉幕府内に「御家人ファースト派」対「統治派」のオセロゲームのようなせめぎ合いがあったという指摘が興味深い。
鎌倉時代とは、地方の無名の一族に過ぎなかった北条氏が勢力を拡大し、将軍や天皇を決める力をもつ実質的な「日本国王」にまで登りつめて行く歴史である。そして、その勢力の拡大こそが滅亡の要因になったという顛末も面白い。北条氏150年の興亡史に歴史のダイナミズムを感じる。同時に、いつの時代でも人間の集団の扱いはやっかいで難しいと思うしかない。
『夜を賭けて』は戦後史小説 ― 2022年09月25日
25年前に新刊で購入し、未読のままページが黄ばんでいた次の文庫本を読んだ。
『夜を賭けて』(梁石日/幻冬舎文庫)
戦後の混乱期に大阪造兵廠跡地に出没した屑鉄泥棒集団「アパッチ」を描いた小説である。私は十代の頃(半世紀以上昔)『日本アパッチ族』(小松左京)や『日本三文オペラ』(開高健)を読んでアパッチに興味を抱いた。『夜を賭けて』の作者はアパッチの一人で、その体験をふまえて書いたアパッチ小説の決定版と知り、この文庫本を迷わず購入した。だが、いずれ読もうと思いつつ、うかうかと25年が経過した。
数か月前、ブレヒトの『三文オペラ』を翻案した『てなもんや三文オペラ』を観劇した。原作の盗賊団が大阪の屑鉄泥棒アパッチになっていたのを観て未読の『夜を賭けて』を思い出したのである。
この小説は第一部と第二部の構成で、第一部ではアパッチと警察との攻防を生々しく描いている。第二部になると小説の趣はガラリと変わり、長崎の大村収容所の話になる。
本書であらためて知ったのは、大阪造兵廠の規模の大きさ(6万8千人が従事)とと、アパッチが在日朝鮮人だったということである。
大空襲で廃墟になった造兵廠跡地は戦後十数年たっても放置されていた。アパッチが大々的に屑鉄泥棒(廃墟の屑鉄は国有資産)を始めるのは1958年のはじめ、警察との8カ月間の攻防のすえ、1958年10月には壊滅させられる。本書第一部は、その8カ月間の在日朝鮮人たちの生命力あふれる強烈な世界を描いている。息苦しいほどに濃厚な空気が伝わってくる群像劇である。
第二部は群像劇ではなく主人公が若い二人の男女に絞られる。大村収容所に収容された男と、それを救出しようとする女の物語になり、戦後史の暗く重い情況もストレートに描いている。朝鮮戦争後、南北に分かれた祖国の情勢を背景にした民団と総連の対立や帰国運動など、いまでも身につまされる話である。『凍土の共和国』を思い出した。大村収容所についても、その悲惨で非情な実態を本書ではじめて認識した。
最終章では時間が35年とんで、1993年(本書発表時の現代)になる。造兵廠跡の廃墟は大阪城公園になっている。主人公の一人は「何やしらんけど、SFの世界に迷い込んだみたいや」とつぶやく。読者の私も、その感慨に共鳴する。もちろん本書はSFではない。しかし、私には戦後史とSFが二重写しになったように感じられる小説である。
『夜を賭けて』(梁石日/幻冬舎文庫)
戦後の混乱期に大阪造兵廠跡地に出没した屑鉄泥棒集団「アパッチ」を描いた小説である。私は十代の頃(半世紀以上昔)『日本アパッチ族』(小松左京)や『日本三文オペラ』(開高健)を読んでアパッチに興味を抱いた。『夜を賭けて』の作者はアパッチの一人で、その体験をふまえて書いたアパッチ小説の決定版と知り、この文庫本を迷わず購入した。だが、いずれ読もうと思いつつ、うかうかと25年が経過した。
数か月前、ブレヒトの『三文オペラ』を翻案した『てなもんや三文オペラ』を観劇した。原作の盗賊団が大阪の屑鉄泥棒アパッチになっていたのを観て未読の『夜を賭けて』を思い出したのである。
この小説は第一部と第二部の構成で、第一部ではアパッチと警察との攻防を生々しく描いている。第二部になると小説の趣はガラリと変わり、長崎の大村収容所の話になる。
本書であらためて知ったのは、大阪造兵廠の規模の大きさ(6万8千人が従事)とと、アパッチが在日朝鮮人だったということである。
大空襲で廃墟になった造兵廠跡地は戦後十数年たっても放置されていた。アパッチが大々的に屑鉄泥棒(廃墟の屑鉄は国有資産)を始めるのは1958年のはじめ、警察との8カ月間の攻防のすえ、1958年10月には壊滅させられる。本書第一部は、その8カ月間の在日朝鮮人たちの生命力あふれる強烈な世界を描いている。息苦しいほどに濃厚な空気が伝わってくる群像劇である。
第二部は群像劇ではなく主人公が若い二人の男女に絞られる。大村収容所に収容された男と、それを救出しようとする女の物語になり、戦後史の暗く重い情況もストレートに描いている。朝鮮戦争後、南北に分かれた祖国の情勢を背景にした民団と総連の対立や帰国運動など、いまでも身につまされる話である。『凍土の共和国』を思い出した。大村収容所についても、その悲惨で非情な実態を本書ではじめて認識した。
最終章では時間が35年とんで、1993年(本書発表時の現代)になる。造兵廠跡の廃墟は大阪城公園になっている。主人公の一人は「何やしらんけど、SFの世界に迷い込んだみたいや」とつぶやく。読者の私も、その感慨に共鳴する。もちろん本書はSFではない。しかし、私には戦後史とSFが二重写しになったように感じられる小説である。






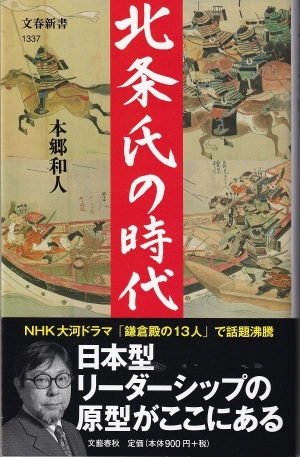
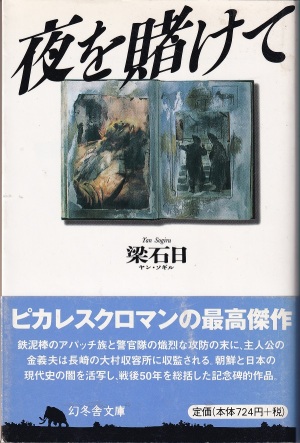
最近のコメント