『進化という迷宮』は難しいが面白い ― 2025年10月23日
進化論は私の関心分野である。一般書を何冊か読み、『種の起源』も読んだ。だが、進化論をきちんと把握したとは思えない。わかったような気がしても、何かがするりと抜け落ちて釈然としない。そんな私の気分を表すようなタイトルの次の新書を読んだ。
『進化という迷宮:隠れた「調律者」を追え』(千葉聡/講談社現代新書)
著者は進化生物学と生態学の研究者である。私がこの著者の本を読むのは『ダーウィンの呪い』に次いで2冊目だ。
進化論の現状に関する解説書だろうと思って読み始めた。確かに解説書だが、探究の過程を語る書である。また、研究者としての著者の告白的体験談が随所に織り込まれていて、その部分がとても面白い。著者の周辺のさまざまな研究者の成果報告書でもある。
私には、本書が紹介する研究内容を理解するのは容易でなかった。咀嚼できたとは言えない。本書の内容を適切にまとめることができない。だが、興味深い本である。大進化は小進化の積み重ねで説明できるのか、進化は偶然の結果なのか必然の要因がはたらいているのか――といったことを探求している。
本書全般に登場する研究者は高名なグールド(1941-2002)である。著者の師匠の友人でもあり、著者自身も直接議論を交わしている。私はグールドの著書を読んだことはないが、以前に読んだ『理不尽な進化』でその名を知った。本書を読む限り、グールドはかなりわかりにくい研究者だ。考え方は変転している。でも、偉大な研究者だったようだ。
本書の冒頭、グールドの「時を遡る思考実験」を紹介している。進化の歴史を巻き戻して再生すると、同じような大進化は二度と起こらないという主張である。偶発性によって、進化の動画を巻き戻して再生するたびに以前とは似ても似つかぬ生物の世界になり、人類のような知的生命体は現れないという。
この思考実験に対して、何度再生しても人類や人類に似た知的生命体が進化するという反論が提示される。著者は、この反論に与していて、そこには偶発性を無力化する「調律者」がいるはずだと考える。本書は、その「調律者」の正体を追究する物語である、最終的にはその正体を暴いて幕を閉じる。何となくわかったような気もするが、やはり、本書を読み終えても依然として「進化という迷宮」をさまよっている気分である。
本書の主役はカタツムリのように思える。化石から現生種までさまざまなカタツムリが登場する。進化生物学研究におけるカタツムリの役割の大きさを知ると共に、フィールド・ワークの苛酷と研究者たちタフな肉体に圧倒された。研究現場の熱気が伝わってくる。
本書における著者はかなり饒舌である。SFやマンガへの言及も多い。『三体』(劉慈欣)、『継ぐのは誰だ』(小松左京)、『雷のような音』(ブラッドベリ)、『日の名残り』(カズオ・イスグロ)など私の記憶に残る作品も登場し、うれしくなった。手塚治虫の博士論文にまで言及しているのには驚いた。
『進化という迷宮:隠れた「調律者」を追え』(千葉聡/講談社現代新書)
著者は進化生物学と生態学の研究者である。私がこの著者の本を読むのは『ダーウィンの呪い』に次いで2冊目だ。
進化論の現状に関する解説書だろうと思って読み始めた。確かに解説書だが、探究の過程を語る書である。また、研究者としての著者の告白的体験談が随所に織り込まれていて、その部分がとても面白い。著者の周辺のさまざまな研究者の成果報告書でもある。
私には、本書が紹介する研究内容を理解するのは容易でなかった。咀嚼できたとは言えない。本書の内容を適切にまとめることができない。だが、興味深い本である。大進化は小進化の積み重ねで説明できるのか、進化は偶然の結果なのか必然の要因がはたらいているのか――といったことを探求している。
本書全般に登場する研究者は高名なグールド(1941-2002)である。著者の師匠の友人でもあり、著者自身も直接議論を交わしている。私はグールドの著書を読んだことはないが、以前に読んだ『理不尽な進化』でその名を知った。本書を読む限り、グールドはかなりわかりにくい研究者だ。考え方は変転している。でも、偉大な研究者だったようだ。
本書の冒頭、グールドの「時を遡る思考実験」を紹介している。進化の歴史を巻き戻して再生すると、同じような大進化は二度と起こらないという主張である。偶発性によって、進化の動画を巻き戻して再生するたびに以前とは似ても似つかぬ生物の世界になり、人類のような知的生命体は現れないという。
この思考実験に対して、何度再生しても人類や人類に似た知的生命体が進化するという反論が提示される。著者は、この反論に与していて、そこには偶発性を無力化する「調律者」がいるはずだと考える。本書は、その「調律者」の正体を追究する物語である、最終的にはその正体を暴いて幕を閉じる。何となくわかったような気もするが、やはり、本書を読み終えても依然として「進化という迷宮」をさまよっている気分である。
本書の主役はカタツムリのように思える。化石から現生種までさまざまなカタツムリが登場する。進化生物学研究におけるカタツムリの役割の大きさを知ると共に、フィールド・ワークの苛酷と研究者たちタフな肉体に圧倒された。研究現場の熱気が伝わってくる。
本書における著者はかなり饒舌である。SFやマンガへの言及も多い。『三体』(劉慈欣)、『継ぐのは誰だ』(小松左京)、『雷のような音』(ブラッドベリ)、『日の名残り』(カズオ・イスグロ)など私の記憶に残る作品も登場し、うれしくなった。手塚治虫の博士論文にまで言及しているのには驚いた。
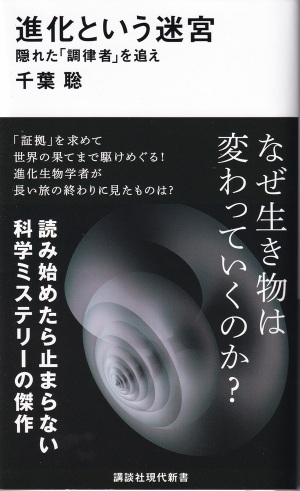
最近のコメント