国民国家成立前の時代を描いた『オスマン帝国500年の平和』 ― 2021年04月26日
オスマン帝国にはエキゾチックな敵役というイメージがある。コンスタンティノープル陥落やウィーン包囲の印象が強く、スルタンとハレムのトプカピ宮殿の姿が思い浮かび、自分のなかの西欧中心史観を自覚する。
先日読んだ『世界史との対話(中)』の「第36講 オスマン帝国の栄光と黄昏」には、私の知らないオスマン帝国の姿が描かれていて、次の指摘があった。
《昔の世界史教科書は「オスマン・トルコ」と呼んでいました。でも彼らはトルコ人の国であるという自覚はなかったので、この呼び方は間違っています。》
まさに私は、オスマン・トルコと覚えた世代である。西欧史の敵役、イスラム史の脇役といった、ぼんやりした断片的イメージしかないオスマン帝国の姿を少しクリアにしようと思い、次の本を読んだ。
『オスマン帝国500年の平和 (興亡の世界史)』(林佳世子/講談社学術文庫)
本書は私にとって非常に新鮮だった。トルコ人の国、イスラムの国という見方がいかに間違っているかがわかった。他の宗教に寛容だったイスラム教とキリスト教(ギリシア正教、アルメニア教会など)などとの関係が具体的に見えてきた。また、この帝国は多様な「民族」から構成されていたこともわかった。著者はオスマン帝国を「何人(なにじん)の国でもなかった」と表現している。
オスマン帝国(当初はオスマン侯国)は14世紀前半に誕生し、滅亡したのは第一次世界大戦後の1922年である。約600年続いた帝国だが、本書のタイトル「500年の平和」は14世紀から18世紀までを指し、それが本書の主な対象であり、19世紀以降の近代100年は簡略に触れているだけだ。
オスマン帝国の領土は現在のトルコよりはるかに広く、バルカン半島からシリア、エジプトまでを含んでいる。そんな帝国の命脈が続いたのは18世紀までであり、それ以降は国の姿や体制が大きく変化している。
本書の冒頭で著者は、なぜトルコ人だけが「何人(なにじん)の国でもなかった」オスマン帝国の末裔とされたか、その経緯を述べている。バルカンやアラブの人々は、歴史のある段階でオスマン帝国と敵対して建国したので自らをオスマン帝国の末裔と位置づけることを拒否した。事情はトルコ共和国も同じで「トルコ人の国」ではなかったオスマン帝国の否定からスタートしている。と言うものの、近代の帝国末期には「トルコ人の国」のような形に縮小していたので、トルコ共和国がオスマン帝国の末裔役を引き受けることになったそうだ。
こんな事情は、近代が国民国家なるものを生み出したせいである。国民国家の課題を考えるにはオスマン帝国は興味深い研究対象だと知った。私には、それが本書の大きな収穫だった。
本日(2021年4月26日)の朝刊に、バイデン米大統領の声明にトルコのエルドアン大統領が反発したとのニュースが載っていた。オスマン帝国末期に起きたアルメニア人迫害を、米国が「ジェノサイド」と認定したことへの反発である。トルコ共和国がオスマン帝国の末裔を引き受けていることをあらためて認識した。近代が生み出した国民国家と民族問題は21世紀の大問題である。
先日読んだ『世界史との対話(中)』の「第36講 オスマン帝国の栄光と黄昏」には、私の知らないオスマン帝国の姿が描かれていて、次の指摘があった。
《昔の世界史教科書は「オスマン・トルコ」と呼んでいました。でも彼らはトルコ人の国であるという自覚はなかったので、この呼び方は間違っています。》
まさに私は、オスマン・トルコと覚えた世代である。西欧史の敵役、イスラム史の脇役といった、ぼんやりした断片的イメージしかないオスマン帝国の姿を少しクリアにしようと思い、次の本を読んだ。
『オスマン帝国500年の平和 (興亡の世界史)』(林佳世子/講談社学術文庫)
本書は私にとって非常に新鮮だった。トルコ人の国、イスラムの国という見方がいかに間違っているかがわかった。他の宗教に寛容だったイスラム教とキリスト教(ギリシア正教、アルメニア教会など)などとの関係が具体的に見えてきた。また、この帝国は多様な「民族」から構成されていたこともわかった。著者はオスマン帝国を「何人(なにじん)の国でもなかった」と表現している。
オスマン帝国(当初はオスマン侯国)は14世紀前半に誕生し、滅亡したのは第一次世界大戦後の1922年である。約600年続いた帝国だが、本書のタイトル「500年の平和」は14世紀から18世紀までを指し、それが本書の主な対象であり、19世紀以降の近代100年は簡略に触れているだけだ。
オスマン帝国の領土は現在のトルコよりはるかに広く、バルカン半島からシリア、エジプトまでを含んでいる。そんな帝国の命脈が続いたのは18世紀までであり、それ以降は国の姿や体制が大きく変化している。
本書の冒頭で著者は、なぜトルコ人だけが「何人(なにじん)の国でもなかった」オスマン帝国の末裔とされたか、その経緯を述べている。バルカンやアラブの人々は、歴史のある段階でオスマン帝国と敵対して建国したので自らをオスマン帝国の末裔と位置づけることを拒否した。事情はトルコ共和国も同じで「トルコ人の国」ではなかったオスマン帝国の否定からスタートしている。と言うものの、近代の帝国末期には「トルコ人の国」のような形に縮小していたので、トルコ共和国がオスマン帝国の末裔役を引き受けることになったそうだ。
こんな事情は、近代が国民国家なるものを生み出したせいである。国民国家の課題を考えるにはオスマン帝国は興味深い研究対象だと知った。私には、それが本書の大きな収穫だった。
本日(2021年4月26日)の朝刊に、バイデン米大統領の声明にトルコのエルドアン大統領が反発したとのニュースが載っていた。オスマン帝国末期に起きたアルメニア人迫害を、米国が「ジェノサイド」と認定したことへの反発である。トルコ共和国がオスマン帝国の末裔を引き受けていることをあらためて認識した。近代が生み出した国民国家と民族問題は21世紀の大問題である。
壮大な歴史絵本のような映画『クレオパトラ』 ― 2021年04月16日
1963年公開の映画『クレオパトラ』をブルーレイで観た。私が中学生の頃に公開された大作映画で、当時いろいろ話題になっていたのは憶えている。エリザベス・テーラーやリチャード・バートンという俳優名もその頃に知った。だが、歴史やクレオパトラにさほどの関心がなかったので、映画を観たいとは思わなかった。
中学生の頃に関心がなかった映画を70歳を過ぎて初めて観たのは、年を取って歴史への関心がわいたからである。いつかは観ようと思いつつ、ずるずると半世紀以上の時間が経過したとも言える。
この10年ばかりで古代ローマ史関連の本をいくつか読んできたので、カエサルやクレオパトラに関する知識も多少は増え、そのイメージの定着に資するだろうと思って映画を観た。
壮大な失敗作との評判を知ったうえで4時間を超えるこの映画を観て、失敗作と言われる由縁が理解できた気がした。長時間の映画にもかかわらず歴史のダイジェストを眺めている感じで、何とも平板な印象の物語なのだ。
しかし、映像には圧倒された。CGのない時代に壮大なセット、華麗な衣装、膨大なエキストラを使って作り上げた情景には感心する。大規模な絵本を眺めている気分になる。20世紀フォックスの経営を傾かせるほどの製作費を費やしたということが納得できる。
もちろん、映画の画像が歴史の実景だとは思わない。あくまでハリウッド的な古代ローマ時代の情景である。歴史の情景は、これまでさまざまな絵画で表現されてきた。同様に映画でも表現されてきた。それがフィクションであっても、歴史のあれこれを自分の頭の中に定着させるには有効だと思う。史実とおぼしき史料をベースに、画家や映画製作者が想像し創造した情景を借用してイメージを紡がなければ、歴史を知った気にはなれない。
中学生の頃に関心がなかった映画を70歳を過ぎて初めて観たのは、年を取って歴史への関心がわいたからである。いつかは観ようと思いつつ、ずるずると半世紀以上の時間が経過したとも言える。
この10年ばかりで古代ローマ史関連の本をいくつか読んできたので、カエサルやクレオパトラに関する知識も多少は増え、そのイメージの定着に資するだろうと思って映画を観た。
壮大な失敗作との評判を知ったうえで4時間を超えるこの映画を観て、失敗作と言われる由縁が理解できた気がした。長時間の映画にもかかわらず歴史のダイジェストを眺めている感じで、何とも平板な印象の物語なのだ。
しかし、映像には圧倒された。CGのない時代に壮大なセット、華麗な衣装、膨大なエキストラを使って作り上げた情景には感心する。大規模な絵本を眺めている気分になる。20世紀フォックスの経営を傾かせるほどの製作費を費やしたということが納得できる。
もちろん、映画の画像が歴史の実景だとは思わない。あくまでハリウッド的な古代ローマ時代の情景である。歴史の情景は、これまでさまざまな絵画で表現されてきた。同様に映画でも表現されてきた。それがフィクションであっても、歴史のあれこれを自分の頭の中に定着させるには有効だと思う。史実とおぼしき史料をベースに、画家や映画製作者が想像し創造した情景を借用してイメージを紡がなければ、歴史を知った気にはなれない。
ロングセラー『栽培植物と農耕の起源』はスリリングな書 ― 2021年04月10日
1966年1月の刊行後、半世紀以上読み続けられてきた次の岩波新書を読んだ。私が読んだのは、2020年12月発行の64刷改版である。
『栽培植物と農耕の起源』(中尾佐助/岩波新書)
先日読んだ『世界史との対話(上)』 で本書を名著と紹介していたので興味がわいて入手した。オビには「絶対名著」の大活字が躍っている。
イネやムギの栽培種は野生種とは大きく異なっているという話から、植物学的に農耕の起源を探っていく導入部に引き込まれ、興味深く読み進めた。だが、途中から少し難しくなる。生物学や農学の予備知識がないので、知識不足で理解しにくい事項が増えてくる。そのたびにネットや参考書で調べるのは面倒だし、もどかしくもある。わからない事はそのまま読み飛ばして強引に読了した。
だから十全に理解したとは言い難いし、自分がこの分野に未知だと自覚させられた。でも、本書の面白さは堪能できた気がする。本書は通常の啓蒙書ではなく、著者の調査研究のレポートであり、通説を再検討した自説展開の書である。一般向けに書いたスリリングな学術書のようにも思える。門外漢が研究現場の息吹を感じることができて面白いのだ。
本書に雑草と野草は違うという指摘があり、驚いた。私は10年近く前から八ヶ岳南麓で野菜作りの真似事をしていて、畑仕事とは雑草との終わりなき戦いだと感じている。年に2回は草刈り機で山小屋の庭の雑草(野草)も刈る。それを怠ると雑草(野草)に侵略されて大変なことになる。雑草も野草も同じものだと思っていた。
栽培植物は野草を元に人間が作りだしたものだ。それはよくわかる。雑草とは農耕という人間が作りだした環境に生じたもので、野草ではなく野草から進化したものだそうだ。人類は自分が作りだしたものとの終わりなき戦いをしているのだ。そう考えると何とも感慨深い。
『栽培植物と農耕の起源』(中尾佐助/岩波新書)
先日読んだ『世界史との対話(上)』 で本書を名著と紹介していたので興味がわいて入手した。オビには「絶対名著」の大活字が躍っている。
イネやムギの栽培種は野生種とは大きく異なっているという話から、植物学的に農耕の起源を探っていく導入部に引き込まれ、興味深く読み進めた。だが、途中から少し難しくなる。生物学や農学の予備知識がないので、知識不足で理解しにくい事項が増えてくる。そのたびにネットや参考書で調べるのは面倒だし、もどかしくもある。わからない事はそのまま読み飛ばして強引に読了した。
だから十全に理解したとは言い難いし、自分がこの分野に未知だと自覚させられた。でも、本書の面白さは堪能できた気がする。本書は通常の啓蒙書ではなく、著者の調査研究のレポートであり、通説を再検討した自説展開の書である。一般向けに書いたスリリングな学術書のようにも思える。門外漢が研究現場の息吹を感じることができて面白いのだ。
本書に雑草と野草は違うという指摘があり、驚いた。私は10年近く前から八ヶ岳南麓で野菜作りの真似事をしていて、畑仕事とは雑草との終わりなき戦いだと感じている。年に2回は草刈り機で山小屋の庭の雑草(野草)も刈る。それを怠ると雑草(野草)に侵略されて大変なことになる。雑草も野草も同じものだと思っていた。
栽培植物は野草を元に人間が作りだしたものだ。それはよくわかる。雑草とは農耕という人間が作りだした環境に生じたもので、野草ではなく野草から進化したものだそうだ。人類は自分が作りだしたものとの終わりなき戦いをしているのだ。そう考えると何とも感慨深い。
重い世界史講義全70回を読了、頭が疲れた ― 2021年04月08日
『世界史との対話:70時間の歴史批評(下)』(小川幸司/地歴社)
ようやく『世界史との対話(下)』を読み終えた。高校で週2回の授業なら年70回になるそうだ。高校教師による本書は70回の講義を上・中・下の3冊にまとめている。 上巻 が24回分、 中巻 が23回分、下巻が23回分と均等配分なのに巻を追うごとに厚くなる(上巻334頁、中巻382頁、下巻474頁)。近現代を語る下巻は上巻(古代・中世)の1.4倍の厚さである。
下巻が厚いのは近現代になるに従って講義に熱が入ってきて、現代社会を歴史を通して考えるということが深化されていくからである。国民国家とナショナリズム、格差の拡大など現代の課題の淵源が世界史から浮かび上がってくる講義で、著者の熱い思いが伝わってくる。
下巻冒頭の第48講はドーデの『最後の授業』とアルザスの話で、とても面白い。小学生の頃に読んで感銘を受けた『最後の授業』が、実はいろいろ問題がある作品だとは仄聞していたが、アルザスという地の二転三転の顛末には驚いた。『「国民国家」がかくも人々を翻弄するものかということに愕然とせざるをえません』という著者の感慨が印象深い。
ナチス台頭のドイツや太平洋戦争に突き進んだ日本などを例に、状況追随的な思考を積み重ねていくうちに引き返せない事態になるとの指摘は、まさに歴史から学ぶべき重要事項だろう。他にも、興味深い考察満載の講義である。
下巻最後の第70講のタイトルは「トリニティからチェルノブイリとフクシマへ」である。トリニティはマンハッタン計画における史上初の原爆実験場「トリニティ・サイト」のことである。トリニティ(三位一体)などと名付けたとは知らなかった。著者は、作家・林京子(長崎の被爆者)がトリニティ・サイトを訪れたときの文章を引いて、人類史・地球史に立ち返った上で現代社会に生きる我々の課題を提示している。
頭が疲れる重い世界史講義全70回だった。
ようやく『世界史との対話(下)』を読み終えた。高校で週2回の授業なら年70回になるそうだ。高校教師による本書は70回の講義を上・中・下の3冊にまとめている。 上巻 が24回分、 中巻 が23回分、下巻が23回分と均等配分なのに巻を追うごとに厚くなる(上巻334頁、中巻382頁、下巻474頁)。近現代を語る下巻は上巻(古代・中世)の1.4倍の厚さである。
下巻が厚いのは近現代になるに従って講義に熱が入ってきて、現代社会を歴史を通して考えるということが深化されていくからである。国民国家とナショナリズム、格差の拡大など現代の課題の淵源が世界史から浮かび上がってくる講義で、著者の熱い思いが伝わってくる。
下巻冒頭の第48講はドーデの『最後の授業』とアルザスの話で、とても面白い。小学生の頃に読んで感銘を受けた『最後の授業』が、実はいろいろ問題がある作品だとは仄聞していたが、アルザスという地の二転三転の顛末には驚いた。『「国民国家」がかくも人々を翻弄するものかということに愕然とせざるをえません』という著者の感慨が印象深い。
ナチス台頭のドイツや太平洋戦争に突き進んだ日本などを例に、状況追随的な思考を積み重ねていくうちに引き返せない事態になるとの指摘は、まさに歴史から学ぶべき重要事項だろう。他にも、興味深い考察満載の講義である。
下巻最後の第70講のタイトルは「トリニティからチェルノブイリとフクシマへ」である。トリニティはマンハッタン計画における史上初の原爆実験場「トリニティ・サイト」のことである。トリニティ(三位一体)などと名付けたとは知らなかった。著者は、作家・林京子(長崎の被爆者)がトリニティ・サイトを訪れたときの文章を引いて、人類史・地球史に立ち返った上で現代社会に生きる我々の課題を提示している。
頭が疲れる重い世界史講義全70回だった。
『騙し絵の牙』が想定通り大泉洋主演で映画化 ― 2021年04月05日
先週から公開中の映画『騙し絵の牙』(監督:吉田大八)を観た。
原作の小説
を読んだのは3年以上前で、構造不況の出版業界を描いた面白い話だと思った。この小説で驚いたのは、主人公を俳優・大泉洋にアテガキしていることだった。表紙には大泉洋が主人公に扮した写真が載っていた。役者をアテガキする戯曲はあるが小説は珍しい。
この小説が刊行された頃、大泉洋がどこかで「この小説が映画化されるとき、ぼくが主人公じゃなかったら騙しですよね」と語っていた。小説が売れないことをネタにしたこの小説がどれほど売れたかは知らないが、無事、大泉洋主演で映画化されたのはご同慶の至りである。
映画の展開は小説とは少し異なっている。大手文芸出版社という舞台設定は同じだ。雑誌、特に文芸雑誌が売れなくなってきた時代への対応を迫られている出版社の話は興味深い。小説で描かれていたパチンコ業界やゲーム業界との絡みは映画では省かれている。そのかわり、というのも変だが、町の本屋の苦境が取り上げられている。
映画は小説以上に「騙し合い」をメインにしたエンタメになっていて、それなりに楽しめた。出版不況への対応策を提示しているわけではないが、現代の問題を提示しているのは確かだ。
どうせなら「小説の映画化」というプロジェクトそのものを映画化して、メタフィクション風に映画業界を相対化して観せる映画にしても面白かったのではと思った。
この小説が刊行された頃、大泉洋がどこかで「この小説が映画化されるとき、ぼくが主人公じゃなかったら騙しですよね」と語っていた。小説が売れないことをネタにしたこの小説がどれほど売れたかは知らないが、無事、大泉洋主演で映画化されたのはご同慶の至りである。
映画の展開は小説とは少し異なっている。大手文芸出版社という舞台設定は同じだ。雑誌、特に文芸雑誌が売れなくなってきた時代への対応を迫られている出版社の話は興味深い。小説で描かれていたパチンコ業界やゲーム業界との絡みは映画では省かれている。そのかわり、というのも変だが、町の本屋の苦境が取り上げられている。
映画は小説以上に「騙し合い」をメインにしたエンタメになっていて、それなりに楽しめた。出版不況への対応策を提示しているわけではないが、現代の問題を提示しているのは確かだ。
どうせなら「小説の映画化」というプロジェクトそのものを映画化して、メタフィクション風に映画業界を相対化して観せる映画にしても面白かったのではと思った。
『世界史との対話(中)』は深くて読み応えがある ― 2021年03月29日
『世界史との対話(上)』に続く中巻をやっと読み終えた。
『世界史との対話:70時間の歴史批評(中)』(小川幸司/地歴社)
長年、高校や市民講座で世界史を教えてきた高校教師の講義録という体裁だが、テーマを絞って人物、生活、社会などにこだわった濃い講義で読み応えがある。全3冊で70回(週2回で1年分)のうち23講義を本書に収録している。
冒頭の第25講のタイトルは「ジュリエットとスコラ哲学」で、オッカムという哲学者の文章が紹介される。その引用文があまりに難解で困惑したが、引用の直後に「これでは理解不能と思われる方も多いでしょう。私も最初はそうでした」とあり、ホッとした。それにしてもジュリエットなんて哲学者がいたかなあと思いつつ読み進めると、これは『ロミオとジュリエット』のジュリエットだった。『薔薇の名前』も出てくる。関係なさそうなものが見事に絡みあって歴史の講義になっていく展開に引き込まれた。
著者の講義は哲学や文学を援用して世界史を語る形が多い。本書末尾の第47講は美貌の皇妃エリザベートを題材にした「宮廷生活を嫌ったオーストリア皇后」で、この講義ではカフカの『変身』を引用している。「存在と記憶の抹殺」という世界史の問題をこの小説に重ねているのだ。もちろんカフカ自身も歴史の登場人物の一人である。なるほどと唸ってしまう。
本書全般の大きなテーマは、従来の西欧中心史観の見直しである。いわゆる「大航海時代」を東南アジアの視点で捉え直した説明が興味深い。大英帝国の「覇権」を冷静に再検討しているのも私には新鮮だった。教えられることが満載の講義である。
全3巻の本書には各巻ごとに「まえがき」と「あとがき」がついていて、それがまた面白い。世界史教育の課題がわかるだけでなく、高校教師の悲哀と喜びが伝わってくる。本文にも著者の自分語りの箇所があり、親しみがわく。
『世界史との対話:70時間の歴史批評(中)』(小川幸司/地歴社)
長年、高校や市民講座で世界史を教えてきた高校教師の講義録という体裁だが、テーマを絞って人物、生活、社会などにこだわった濃い講義で読み応えがある。全3冊で70回(週2回で1年分)のうち23講義を本書に収録している。
冒頭の第25講のタイトルは「ジュリエットとスコラ哲学」で、オッカムという哲学者の文章が紹介される。その引用文があまりに難解で困惑したが、引用の直後に「これでは理解不能と思われる方も多いでしょう。私も最初はそうでした」とあり、ホッとした。それにしてもジュリエットなんて哲学者がいたかなあと思いつつ読み進めると、これは『ロミオとジュリエット』のジュリエットだった。『薔薇の名前』も出てくる。関係なさそうなものが見事に絡みあって歴史の講義になっていく展開に引き込まれた。
著者の講義は哲学や文学を援用して世界史を語る形が多い。本書末尾の第47講は美貌の皇妃エリザベートを題材にした「宮廷生活を嫌ったオーストリア皇后」で、この講義ではカフカの『変身』を引用している。「存在と記憶の抹殺」という世界史の問題をこの小説に重ねているのだ。もちろんカフカ自身も歴史の登場人物の一人である。なるほどと唸ってしまう。
本書全般の大きなテーマは、従来の西欧中心史観の見直しである。いわゆる「大航海時代」を東南アジアの視点で捉え直した説明が興味深い。大英帝国の「覇権」を冷静に再検討しているのも私には新鮮だった。教えられることが満載の講義である。
全3巻の本書には各巻ごとに「まえがき」と「あとがき」がついていて、それがまた面白い。世界史教育の課題がわかるだけでなく、高校教師の悲哀と喜びが伝わってくる。本文にも著者の自分語りの箇所があり、親しみがわく。
青山墓地で満開の桜と星新一の墓を見た ― 2021年03月27日
私は年に数回、六本木から外苑前まで、青山墓地の中央を縦断して歩く。普段は人通りの少ない並木道である。青山墓地には著名人の墓も多いと聞いているので、それを探索してみるのも一興と思いつつ、いつも墓を素通りしている。
普段は人通りの少ない青山墓地の縦断道も、桜の季節になると散歩する人が増える。昨日の午後、外苑前で所用を終えた後、気まぐれで青山墓地に足を踏み入れた。桜は満開で人も多い。桜並木を散策しながら、星新一の墓がここにあると聞いたことを突然に思い出した。
スマホで「星新一 青山墓地」と検索すると、墓のアドレスが出てきた。墓地の随所には地図看板がある。何ともわかりやすく、検索して数分後には「星家の墓」の前に立っていた。墓石の左側面には星一(星新一の父、星製薬創業者)の墓誌があり、右側面には星親一(星新一の本名)の墓誌があった。
満開の桜の下でショートショートの神様の墓の前に立ち、浮世を一瞬だけ離脱した浩然の気に浸った。「気まぐれ…」というタイトルの多い作家への気まぐれ墓参であった。
普段は人通りの少ない青山墓地の縦断道も、桜の季節になると散歩する人が増える。昨日の午後、外苑前で所用を終えた後、気まぐれで青山墓地に足を踏み入れた。桜は満開で人も多い。桜並木を散策しながら、星新一の墓がここにあると聞いたことを突然に思い出した。
スマホで「星新一 青山墓地」と検索すると、墓のアドレスが出てきた。墓地の随所には地図看板がある。何ともわかりやすく、検索して数分後には「星家の墓」の前に立っていた。墓石の左側面には星一(星新一の父、星製薬創業者)の墓誌があり、右側面には星親一(星新一の本名)の墓誌があった。
満開の桜の下でショートショートの神様の墓の前に立ち、浮世を一瞬だけ離脱した浩然の気に浸った。「気まぐれ…」というタイトルの多い作家への気まぐれ墓参であった。
井上ひさしの初期作品『日本人のへそ』を観た ― 2021年03月25日
紀伊国屋サザンシアターでこまつ座の井上ひさし芝居『日本人のへそ』(演出:栗山民也、出演:井上芳雄、小池栄子、山西惇、朝海ひかる、他)を観た。
戯曲は読んでいるが舞台を観るのは初めてである。2時間弱の第一幕と1時間弱の第二幕という構成で、第一幕は合唱が多い音楽劇で突然の事件で幕となる。第二幕に合唱はないがギャグが頻発し、事件の解決編という趣からどんでん返しを繰り返す。
当然ながら、舞台を観ると戯曲を読んだだけではわからない面白さを感得できる。この芝居には、井上ひさしが抱いていたさまざまな「想い」と「仕掛け」が過剰に詰め込まれている。「騙す」や「演ずる」を多層化・相対化して「真実」と等価と思わせてしまうエネルギーを感じた。真実を明らかにするためのどんでん返しではなく、どんでん返しを自己目的化してもいいではないかという居直りも感じる。
『日本人のへそ』の初演は1969年2月、あの『表裏源内蛙合戦』より早い。当時大学生だった私は、唐十郎の状況劇場に魅せられ、紅テントに通いながらアングラ系の芝居を観ていた。『表裏源内蛙合戦』という新劇ともアングラとも違う芝居が登場したと聞き、戯曲は読んだもののさほど食指は動かず、舞台を観たのは後年である。
1969年当時、大学生の私が『日本人のへそ』を観ていたらどう感じただろうと想像してみた。多少の違和感を抱きつつも、面白いとは思っただろう。共感したか反発したか黙殺したか、70歳を過ぎたいまでは何ともわからない。この芝居に1969年頃のアレコレが反映されているのは確かだが…
戯曲は読んでいるが舞台を観るのは初めてである。2時間弱の第一幕と1時間弱の第二幕という構成で、第一幕は合唱が多い音楽劇で突然の事件で幕となる。第二幕に合唱はないがギャグが頻発し、事件の解決編という趣からどんでん返しを繰り返す。
当然ながら、舞台を観ると戯曲を読んだだけではわからない面白さを感得できる。この芝居には、井上ひさしが抱いていたさまざまな「想い」と「仕掛け」が過剰に詰め込まれている。「騙す」や「演ずる」を多層化・相対化して「真実」と等価と思わせてしまうエネルギーを感じた。真実を明らかにするためのどんでん返しではなく、どんでん返しを自己目的化してもいいではないかという居直りも感じる。
『日本人のへそ』の初演は1969年2月、あの『表裏源内蛙合戦』より早い。当時大学生だった私は、唐十郎の状況劇場に魅せられ、紅テントに通いながらアングラ系の芝居を観ていた。『表裏源内蛙合戦』という新劇ともアングラとも違う芝居が登場したと聞き、戯曲は読んだもののさほど食指は動かず、舞台を観たのは後年である。
1969年当時、大学生の私が『日本人のへそ』を観ていたらどう感じただろうと想像してみた。多少の違和感を抱きつつも、面白いとは思っただろう。共感したか反発したか黙殺したか、70歳を過ぎたいまでは何ともわからない。この芝居に1969年頃のアレコレが反映されているのは確かだが…
ハッジ(大巡礼)の迫力に圧倒される写真集『メッカ:聖地の素顔』 ― 2021年03月23日
先日読んだ
『世界史との対話(上)』
(中巻は現在読書途中)で紹介されていた次の本に興味がわき、入手して読んだ。
『カラー版 メッカ:聖地の素顔』(野町和嘉/岩波新書)
メッカ巡礼の写真がメインで、文章はさほど多くない。どの写真も迫力がある。文章も面白い。
イスラム教徒が生涯に一度は巡礼したいと願うメッカとメディナは、ムスリム以外は入れない聖地である。観光で行ける場所ではない。なぜ、著者はこんな写真を撮影できたのか。本書の冒頭でその経緯が語られている。
1946年生まれの野町氏は、アフリカ、中東、チベットなどを撮るカメラマンとして国際的に知られていた。1994年、ムハンマドの直系子孫にあたる人物から野町氏に、メディナのモスク竣工記念写真集のための撮影依頼が来る。イスラム教徒でなくても撮影できるよう特別許可を出すという。
野町氏はメディナだけでなくメッカの写真も撮りたいと希望するが、それは異教徒には無理だと言われる。そのとき、なんと野町氏はイスラムに入信する決断をする。東京のイスラミック・センターで宣誓し、ムスリム証明書を受け取るとき、「メッカの撮影が終わったらムスリムをやめるというんではダメですよ」とクギをさされる。
ムスリムになった野町氏は1995年から2000年まで毎年メッカ、メディナを取材し、5回のハッジ(大巡礼)を体験する。その体験の記録が本書である。初めての巡礼体験の新鮮な驚きが伝わってきて読者も興奮させられる。
本書冒頭の見開き写真は、カーバ神殿を回る大群衆の写真である。この写真には見覚えがあった。2年前に酔狂で購入した高校世界史の教科書(山川出版社)の巻頭グラビアページにこの写真があり、「これは何じゃ」と驚いた。パラパラと拾い読みしただけの「山川世界史」で印象に残っているのはこの写真だけだ。その印象強烈な写真は、日本人カメラマンが撮影した貴重なものだったのだ。
イスラム史の重要都市として知っているだけのメッカとメディナのイメージが本書によって鮮明になった。歴史の蓄積と近代が混合した大迫力の「巡礼都市」というの不思議なイメージである。
『カラー版 メッカ:聖地の素顔』(野町和嘉/岩波新書)
メッカ巡礼の写真がメインで、文章はさほど多くない。どの写真も迫力がある。文章も面白い。
イスラム教徒が生涯に一度は巡礼したいと願うメッカとメディナは、ムスリム以外は入れない聖地である。観光で行ける場所ではない。なぜ、著者はこんな写真を撮影できたのか。本書の冒頭でその経緯が語られている。
1946年生まれの野町氏は、アフリカ、中東、チベットなどを撮るカメラマンとして国際的に知られていた。1994年、ムハンマドの直系子孫にあたる人物から野町氏に、メディナのモスク竣工記念写真集のための撮影依頼が来る。イスラム教徒でなくても撮影できるよう特別許可を出すという。
野町氏はメディナだけでなくメッカの写真も撮りたいと希望するが、それは異教徒には無理だと言われる。そのとき、なんと野町氏はイスラムに入信する決断をする。東京のイスラミック・センターで宣誓し、ムスリム証明書を受け取るとき、「メッカの撮影が終わったらムスリムをやめるというんではダメですよ」とクギをさされる。
ムスリムになった野町氏は1995年から2000年まで毎年メッカ、メディナを取材し、5回のハッジ(大巡礼)を体験する。その体験の記録が本書である。初めての巡礼体験の新鮮な驚きが伝わってきて読者も興奮させられる。
本書冒頭の見開き写真は、カーバ神殿を回る大群衆の写真である。この写真には見覚えがあった。2年前に酔狂で購入した高校世界史の教科書(山川出版社)の巻頭グラビアページにこの写真があり、「これは何じゃ」と驚いた。パラパラと拾い読みしただけの「山川世界史」で印象に残っているのはこの写真だけだ。その印象強烈な写真は、日本人カメラマンが撮影した貴重なものだったのだ。
イスラム史の重要都市として知っているだけのメッカとメディナのイメージが本書によって鮮明になった。歴史の蓄積と近代が混合した大迫力の「巡礼都市」というの不思議なイメージである。
ガルブレイスは懐メロ昭和歌謡…… ― 2021年03月21日
ガルブレイスは懐かしい名前だが、最近はほとんど目にしない。忘れられた経済学者だと思っていたので、本屋の店頭に次の新書が積まれいるのを見つけて驚いた。
『今こそ読みたいガルブレイス』(根井雅弘/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)
近頃は『資本論』を再評価する本が目につく。そんな流れの本かなと思いつつ購入して読んだ。短時間で読了できる読みやすい本である。
約40年前、社会人になって数年目の頃、何人かでサムエルソンの『経済学』(当時の標準的教科書)の輪講読書会をした。並行してガルブレイスの『ゆたかな社会』と『新しい産業国家』を興味深く読んだ。正統的なサムエルソン(新古典派総合)に対する異端のガルブレイスという構図だった。別の異端であるシカゴ学派のフリードマンに手を伸ばす気はせず、この学派が他を駆逐して後の正統になるとは思いもしなかった。
本書の著者はガルブレイスの主著を『ゆたかな社会』『新しい産業国家』『経済学と公共目的』とし、読み継がれるのは『ゆたかな社会』だと見なしている。私は『経済学と公共目的』は未読で、他に読んだのは『不確実性の時代』だけで、そもそも読んだ内容の大半は失念しているので、何を読み継ぐべきかの評価はできない。
と言うものの、本書を読んでいて昔の読書の記憶がまだらに浮かびあがり、ガルブレイスの名文に魅せられた記憶がよみがえってきた。変なたとえだが、本書を読みながら懐メロの昭和歌謡にうっとり浸っている気分になった。そして、ガルブレイスは経済学者というよりは社会学者、文明論の人だったと思えてきた。
著者が指摘しているように、現時点で見ればガルブレイスの見解に誤りは多い。にもかかわらず「今こそ読みたい」と言いたくなる気持はわかる。大きな問題を抱えた現代、骨太な叡智を感じる論客が見当たらないのが問題なのだ。
『今こそ読みたいガルブレイス』(根井雅弘/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)
近頃は『資本論』を再評価する本が目につく。そんな流れの本かなと思いつつ購入して読んだ。短時間で読了できる読みやすい本である。
約40年前、社会人になって数年目の頃、何人かでサムエルソンの『経済学』(当時の標準的教科書)の輪講読書会をした。並行してガルブレイスの『ゆたかな社会』と『新しい産業国家』を興味深く読んだ。正統的なサムエルソン(新古典派総合)に対する異端のガルブレイスという構図だった。別の異端であるシカゴ学派のフリードマンに手を伸ばす気はせず、この学派が他を駆逐して後の正統になるとは思いもしなかった。
本書の著者はガルブレイスの主著を『ゆたかな社会』『新しい産業国家』『経済学と公共目的』とし、読み継がれるのは『ゆたかな社会』だと見なしている。私は『経済学と公共目的』は未読で、他に読んだのは『不確実性の時代』だけで、そもそも読んだ内容の大半は失念しているので、何を読み継ぐべきかの評価はできない。
と言うものの、本書を読んでいて昔の読書の記憶がまだらに浮かびあがり、ガルブレイスの名文に魅せられた記憶がよみがえってきた。変なたとえだが、本書を読みながら懐メロの昭和歌謡にうっとり浸っている気分になった。そして、ガルブレイスは経済学者というよりは社会学者、文明論の人だったと思えてきた。
著者が指摘しているように、現時点で見ればガルブレイスの見解に誤りは多い。にもかかわらず「今こそ読みたい」と言いたくなる気持はわかる。大きな問題を抱えた現代、骨太な叡智を感じる論客が見当たらないのが問題なのだ。


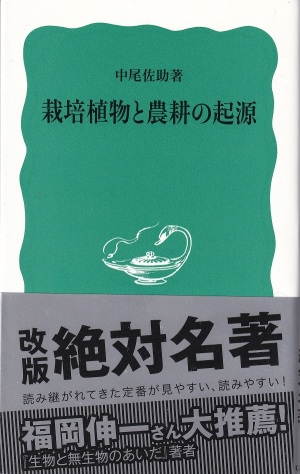




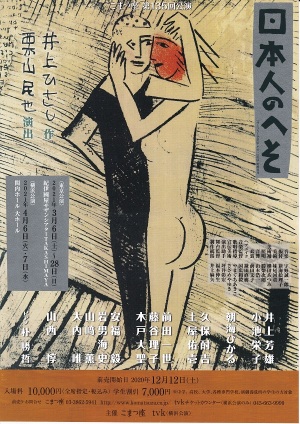


最近のコメント