シェイクスピアの『お気に召すまま』を観た ― 2019年08月04日
池袋の東京芸術劇場プレイハウスでシェイクスピアの『お気に召すまま』(演出:熊林弘高、出演:満島ひかり、坂口健太郎、他)を観た。
観客は比較的若い女性が多く、華やかな雰囲気だった。『お気に召すまま』は大団円で終わるやや祝祭的で軽妙な恋愛喜劇というイメージがある。とは言え400年以上昔の古典だから、現代人にはピンと来ない展開やわかりにくいセリフもある。にもかかわらず、21世紀の若い観客を引き寄せることができるエンターテインメントに仕上がっているのに感心した。
この芝居の要は、男性に扮した娘ロザリンド(満島ひかり)が恋人のオーランド(坂口健太郎)と絡み合う場面の面白さにある。オーランドが相手を男と思い込み、自分の恋人と気づかないのを不自然と考えるのは野暮であり、芝居を成り立たせる約束ごととしてそのまま受けいれるしかない。
満島ひかりはテレビドラマで明智小五郎を怪演していたので、彼女が女性と男装女性をどう演じ分けるか興味があった。公演のホームページに付け髭姿で語る動画があったので、男装のときには付け髭になるのだろうと思っていた。
ところが、男装の場面になっても衣装が変わるだけで髭はなかった。どう見てもロザリンドそのままで、それにオーランドが気づかないのが不思議に見えてくる。女性と男性をあいまいにしてしまうところに演出意図があるようだ。「男性と女性」だけでなく「男性と男性」「女性と女性」もありという雰囲気を醸し出しているような舞台だった。
なお、この芝居には「この世界はすべてこれ一つの舞台、人間は男女を問わずすべてこれ役者にすぎぬ」という名セリフがあり、これを舞台で聞けて嬉しかった。上記の引用は手元の小田島雄志訳で、今回の公演は早船歌江子の新訳なので、多少違っているかもしれないが、聞いたときの印象は小田島訳とさほど違ってはなかった。
観客は比較的若い女性が多く、華やかな雰囲気だった。『お気に召すまま』は大団円で終わるやや祝祭的で軽妙な恋愛喜劇というイメージがある。とは言え400年以上昔の古典だから、現代人にはピンと来ない展開やわかりにくいセリフもある。にもかかわらず、21世紀の若い観客を引き寄せることができるエンターテインメントに仕上がっているのに感心した。
この芝居の要は、男性に扮した娘ロザリンド(満島ひかり)が恋人のオーランド(坂口健太郎)と絡み合う場面の面白さにある。オーランドが相手を男と思い込み、自分の恋人と気づかないのを不自然と考えるのは野暮であり、芝居を成り立たせる約束ごととしてそのまま受けいれるしかない。
満島ひかりはテレビドラマで明智小五郎を怪演していたので、彼女が女性と男装女性をどう演じ分けるか興味があった。公演のホームページに付け髭姿で語る動画があったので、男装のときには付け髭になるのだろうと思っていた。
ところが、男装の場面になっても衣装が変わるだけで髭はなかった。どう見てもロザリンドそのままで、それにオーランドが気づかないのが不思議に見えてくる。女性と男性をあいまいにしてしまうところに演出意図があるようだ。「男性と女性」だけでなく「男性と男性」「女性と女性」もありという雰囲気を醸し出しているような舞台だった。
なお、この芝居には「この世界はすべてこれ一つの舞台、人間は男女を問わずすべてこれ役者にすぎぬ」という名セリフがあり、これを舞台で聞けて嬉しかった。上記の引用は手元の小田島雄志訳で、今回の公演は早船歌江子の新訳なので、多少違っているかもしれないが、聞いたときの印象は小田島訳とさほど違ってはなかった。
ムガル帝国の創設者バーブルは文学者 ― 2019年08月05日
「世界史リブレット人」の『ティムール』を読んだ行きがかりで、その子孫のバーブルも読んだ。
『バーブル:ムガル帝国の創設者』(間野英二/世界史リブレット人/山川出版社)
バーブルはムガル帝国の創設者であり、文学者でもある。ムガル帝国と言えばあの壮大華麗なタージ・マハルが思い浮かぶ。私は約10年前にタージ・マハルを訪れ、写真や画像の印象を超えた美しさに圧倒された記憶がある。この墓廟を建てたのは第5代皇帝だから、バーブルよりかなり後の時代になる。ムガル帝国の実質的な建設者はバーブルの孫の第3代皇帝で、バーブルの時代は混沌の揺籃期である。
バーブルの父はティムール朝の創設者ティムールから数えて5代目の子孫、母はチンギス・ハンの次男チャガタイ・ハン(チャガタイ・ハン国の始祖)から数えて10代目の子孫である。バーブルはトルコ化・イスラム化したモンゴルで、彼が生まれた時代、ティムール朝は分裂した衰退期に入っていた。
分裂したティムール朝の一領国の若き君主バーブルはサマルカンドを中心とした中央アジアの覇権を目指すが、それがならず南下してアフガニスタンに移動する。その後、さらに南下してインドに王朝をひらく。こ経路は玄奘三蔵が辿った道に重なる。家臣と共に戦を重ねながらさすらって行く王朝の姿は、まさにチンギス・ハンの血を受け継ぐ遊牧国家である。
チャガタイ・ハンとティムールの年齢差は約150年、ティムールとバーブルの年齢差も約150年、3世紀を経て様変わりしたことは多い。だが、変わっていないものもあるように見えるのが面白い。
バーブルはトルコ文学の傑作と言われる『バーブル・ナーマ』という回想録を残している。この書の研究者・翻訳者でもある著者は文人としてのバーブルの魅力を強調している。
私にはバーブルが文学好きの経営者に見えた。斜陽の名門大企業の御曹司が、その企業の立て直しに奮闘するも挫折し、新たな分野での創業者へと変貌し、その新たな企業の成長を夢見ながら疾風怒涛の時代に果てていく…そんな姿を連想した。
『バーブル:ムガル帝国の創設者』(間野英二/世界史リブレット人/山川出版社)
バーブルはムガル帝国の創設者であり、文学者でもある。ムガル帝国と言えばあの壮大華麗なタージ・マハルが思い浮かぶ。私は約10年前にタージ・マハルを訪れ、写真や画像の印象を超えた美しさに圧倒された記憶がある。この墓廟を建てたのは第5代皇帝だから、バーブルよりかなり後の時代になる。ムガル帝国の実質的な建設者はバーブルの孫の第3代皇帝で、バーブルの時代は混沌の揺籃期である。
バーブルの父はティムール朝の創設者ティムールから数えて5代目の子孫、母はチンギス・ハンの次男チャガタイ・ハン(チャガタイ・ハン国の始祖)から数えて10代目の子孫である。バーブルはトルコ化・イスラム化したモンゴルで、彼が生まれた時代、ティムール朝は分裂した衰退期に入っていた。
分裂したティムール朝の一領国の若き君主バーブルはサマルカンドを中心とした中央アジアの覇権を目指すが、それがならず南下してアフガニスタンに移動する。その後、さらに南下してインドに王朝をひらく。こ経路は玄奘三蔵が辿った道に重なる。家臣と共に戦を重ねながらさすらって行く王朝の姿は、まさにチンギス・ハンの血を受け継ぐ遊牧国家である。
チャガタイ・ハンとティムールの年齢差は約150年、ティムールとバーブルの年齢差も約150年、3世紀を経て様変わりしたことは多い。だが、変わっていないものもあるように見えるのが面白い。
バーブルはトルコ文学の傑作と言われる『バーブル・ナーマ』という回想録を残している。この書の研究者・翻訳者でもある著者は文人としてのバーブルの魅力を強調している。
私にはバーブルが文学好きの経営者に見えた。斜陽の名門大企業の御曹司が、その企業の立て直しに奮闘するも挫折し、新たな分野での創業者へと変貌し、その新たな企業の成長を夢見ながら疾風怒涛の時代に果てていく…そんな姿を連想した。
畑荒らしの犯人は動物ではなく人間 ― 2019年08月07日
八ヶ岳の山小屋の庭でささやかな野菜作りを始めて10年になる。最近は訪問の頻度も減り、畑を縮小しつつある。今年はダイコンとインゲンだけを植えた。
7月中旬にはインゲンを収穫した。ダイコンの根はまだ4センチぐらいだったので収穫は次回に持ち越した。
少し時間が経ち過ぎたが昨日(8月6日)、日帰りで収穫に行った。おどろいたことに20本(2畝)植えたダイコンは、発育不全の2本を残してすべて抜かれていた。ダイコンが動物に齧られたことはあるが、これは明らかに人間の仕業である。暗然とした。
野菜とは別にブルーベリーを7本植えているが、これも人間にやられたようだ。7月は上旬と中旬の2回山小屋に行った。上旬のときはブルーベリーの果実はまだ青く、わずかに20粒ほどを試食しただけだった。7月中旬にブルーベリー収穫を期待して行ったとき、一粒も収穫できず不思議な気がした。動物被害にしては周辺が散らかっていないので、かすかに人間を疑った。今回のダイコンでブルーベリーも人間の仕業だと確信した。ブルーベリーの収穫は今回もゼロである。
おそらく、インゲンもやられている。前回のインゲン収穫の際、そこそこに収穫できたものの、大きくなり過ぎたものがなく収穫量も思ったほどではなかった。天候不順のせいと思っていたが、盗まれていたに違いない。
野菜作りを始めて10年、数多の動物被害にあってきたが、人間にやられたのは初めてである。相手が動物と人間では腹の立ちようがまったく異なる。動物に対しては多少のファイトもわくが、人間に盗まれたとなると、怒りが倍化すると同時に気分が沈んでしまう。
7月中旬にはインゲンを収穫した。ダイコンの根はまだ4センチぐらいだったので収穫は次回に持ち越した。
少し時間が経ち過ぎたが昨日(8月6日)、日帰りで収穫に行った。おどろいたことに20本(2畝)植えたダイコンは、発育不全の2本を残してすべて抜かれていた。ダイコンが動物に齧られたことはあるが、これは明らかに人間の仕業である。暗然とした。
野菜とは別にブルーベリーを7本植えているが、これも人間にやられたようだ。7月は上旬と中旬の2回山小屋に行った。上旬のときはブルーベリーの果実はまだ青く、わずかに20粒ほどを試食しただけだった。7月中旬にブルーベリー収穫を期待して行ったとき、一粒も収穫できず不思議な気がした。動物被害にしては周辺が散らかっていないので、かすかに人間を疑った。今回のダイコンでブルーベリーも人間の仕業だと確信した。ブルーベリーの収穫は今回もゼロである。
おそらく、インゲンもやられている。前回のインゲン収穫の際、そこそこに収穫できたものの、大きくなり過ぎたものがなく収穫量も思ったほどではなかった。天候不順のせいと思っていたが、盗まれていたに違いない。
野菜作りを始めて10年、数多の動物被害にあってきたが、人間にやられたのは初めてである。相手が動物と人間では腹の立ちようがまったく異なる。動物に対しては多少のファイトもわくが、人間に盗まれたとなると、怒りが倍化すると同時に気分が沈んでしまう。
中央アジアに残るトルコ系とイラン系……タジキスタン紀行記(1) ― 2019年08月21日
8月中旬、「幻のソグディアナ タジキスタン紀行8日間」というツァーに参加した。最近のわが関心事が「ソグド商人」で、「ソグディアナ」という言葉に反応して参加を決めた。
タジキスタンがメインのツァーだが、日本からの往復にはタシケント空港(ウズベキスタン)を利用する。だから、ウズベキスタンも少し周遊できた。ウズベキスタンもタジキスタンも以前はソ連の一部で、ソ連崩壊によって独立した国である。これら中央アジアの国への旅行は私には初体験である。
ウズベキスタンはトルコ系のウズベク人の国、タジキスタンはイラン系のタジク人の国である。だが、ウズベキスタンのサマルカンドやブハラにはタジク人も多く住んでいる。そんな事前知識はあったが、現地を訪れて国、民族、言語が絡んだ状況を少し実感できた。
民族の定義は難しい。タジク語を話す人がタジク人、ウズベキ語を話す人がウズベク人と見なすのがわかりやすい。タジク語は印欧語系、ウズベキ語はアルタイ語系で、まったく異なる言語である。
現地での日本語ガイドは日本留学の経験があるウズベキスタン人だった。彼はウズベキスタンに住むタジク人で、ウズベク語もタジク語も話せる。学校ではウズベク語、家庭ではタジク語という環境で育ち、どちらも同等に話せる完全なバイリンガルである。かつてはソ連の一部だったのでロシア語もわかるし、もちろん日本語も堪能である。
その日本語ガイドは全行程に同道したが、タジキスタンではタジキスタン人の英語ガイド(米国留学経験者)が加わった。タジキスタン各地では彼がタジク語で説明し、それを聞いたウズベキスタン人のガイドが日本語に翻訳する。タジキスタンには日本語ガイドが少ないのでこんな形になったのだと思う。ウズベキスタンのタジク人はタジキスタン人のタジク語を完全に理解できるわけではなく、一部意味不明のこともあるそうだ。
タジキスタンもウズベキスタンも旧ソ連である。ソ連時代には主要な町の中央にレーニン像が建っていたが、独立後レーニン像は撤去された。それに替わって建てられたのはウズベキスタンではティムール(トルコ系)像、タジキスタンではサーマーニー(イラン系)像である。現在のウズベキスタンにレーニン像はないそうだ。タジキスタンでは町の中央から郊外に移設されたレーニン像が残っている所もあり、観光資源になっている。
独立後に返り咲いたティムールもサーマーニーもかなり昔の人物だ。14、15世紀に栄えたティムール帝国はトルコ化したモンゴル人のイスラム王朝である。サーマーニーが創始者とされるサーマーン朝は9、10世紀のイラン系イスラム王朝で、首都はブハラ(現在はウズベキスタン)だった。
中央アジアに残るトルコ系、イラン系の姿が少し見えてくるような気がした。
タジキスタン紀行記 (1) (2) (3)
タジキスタンがメインのツァーだが、日本からの往復にはタシケント空港(ウズベキスタン)を利用する。だから、ウズベキスタンも少し周遊できた。ウズベキスタンもタジキスタンも以前はソ連の一部で、ソ連崩壊によって独立した国である。これら中央アジアの国への旅行は私には初体験である。
ウズベキスタンはトルコ系のウズベク人の国、タジキスタンはイラン系のタジク人の国である。だが、ウズベキスタンのサマルカンドやブハラにはタジク人も多く住んでいる。そんな事前知識はあったが、現地を訪れて国、民族、言語が絡んだ状況を少し実感できた。
民族の定義は難しい。タジク語を話す人がタジク人、ウズベキ語を話す人がウズベク人と見なすのがわかりやすい。タジク語は印欧語系、ウズベキ語はアルタイ語系で、まったく異なる言語である。
現地での日本語ガイドは日本留学の経験があるウズベキスタン人だった。彼はウズベキスタンに住むタジク人で、ウズベク語もタジク語も話せる。学校ではウズベク語、家庭ではタジク語という環境で育ち、どちらも同等に話せる完全なバイリンガルである。かつてはソ連の一部だったのでロシア語もわかるし、もちろん日本語も堪能である。
その日本語ガイドは全行程に同道したが、タジキスタンではタジキスタン人の英語ガイド(米国留学経験者)が加わった。タジキスタン各地では彼がタジク語で説明し、それを聞いたウズベキスタン人のガイドが日本語に翻訳する。タジキスタンには日本語ガイドが少ないのでこんな形になったのだと思う。ウズベキスタンのタジク人はタジキスタン人のタジク語を完全に理解できるわけではなく、一部意味不明のこともあるそうだ。
タジキスタンもウズベキスタンも旧ソ連である。ソ連時代には主要な町の中央にレーニン像が建っていたが、独立後レーニン像は撤去された。それに替わって建てられたのはウズベキスタンではティムール(トルコ系)像、タジキスタンではサーマーニー(イラン系)像である。現在のウズベキスタンにレーニン像はないそうだ。タジキスタンでは町の中央から郊外に移設されたレーニン像が残っている所もあり、観光資源になっている。
独立後に返り咲いたティムールもサーマーニーもかなり昔の人物だ。14、15世紀に栄えたティムール帝国はトルコ化したモンゴル人のイスラム王朝である。サーマーニーが創始者とされるサーマーン朝は9、10世紀のイラン系イスラム王朝で、首都はブハラ(現在はウズベキスタン)だった。
中央アジアに残るトルコ系、イラン系の姿が少し見えてくるような気がした。
タジキスタン紀行記 (1) (2) (3)
タジキスタンは山岳の国……タジキスタン紀行記(2) ― 2019年08月22日
紀元前4世紀のアレクサンダー大遠征の最遠地『アレクサンドリア・エスカテ(最果てのアレクサンドリア)』が現在のホジャンド(タジキスタン第2の町)である。国境を越えた最初の訪問地がホジャンドで、ここから首都ドゥシャンベまでは二つの山脈(トルキスタン山脈とヒッサール山脈)を越える山岳道路である。峠の標高は3000メートルを越える。
事前に旅行会社から配布された書類には次の記述があった。
「ホジャンド~ドゥシャンベ、ドゥシャンベ~ペンジケントなどは険しい山岳道路です。小型バスまたはバンに分乗してのご案内となり、添乗員が同乗しない車両がございます」
13年前に刊行された『週刊シルクロード紀行』という雑誌には、この山岳道路を「尻が5センチも浮き上がる衝撃が続く悪路」と綴った紀行文があった。だから覚悟はしていた。
しかし、この山岳道路は思いのほか快適で、窓外に広がる息をのむ山岳風景を満喫できた。道路はすべて舗装されてる。ガードレールはほとんどない。総勢13人(参加者9人、添乗員、ガイド2人、運転手)には贅沢すぎる普通のバスで走行でき、小型バスに分乗することはなかった。
近年、この道路は中国によって舗装され、トンネルも掘られたそうだ。タジキスタンと中国は国境を接している。この道路整備も「シルクロード経済ベルト」を目指す一帯一路構想の一環だろうか。世界各地で増大する中国の存在感が不気味でもある。
標高3000メートルを越えるこの山岳道路は冬季も通行可能だそうだ。驚きである。ガイドは「有料道路なので冬も整備しています」と言っていた。
タジキスタンは山岳の国である。地形図を見れば明らかなように、われわれが旅行した西側はまだ標高が低い地域で、国の東側は7000メートルを越える高山が連なるパミール高原になる。その山岳地域にもかなりの数の人々が暮らしているそうだ。
ドゥシャンベのホテルの部屋には「MOUNTAINS ARE CALLING」と書いたチラシや冊子を置いてあった。パミールの山岳地帯を目指すワイルドないで立ちの宿泊客も見かけた。
ガイドの話によれば、パミールに行くツアーも多くあり、パミールから国境を越えてアフガニスタンに入ることもできるそうだ。そこはアフガニスタンでも比較的安全な地域で、日本人観光客も何人か案内したと言っていた。これにはびっくりした。日本の外務省はアフガニスタンを危険レベル最高のレベル4(退避してください。渡航は止めてください)に指定している。
なお、日本のパミール中央アジア研究会は、日本の地図帳の「パミール高原」という記載を「パミール」に訂正すべきだと提言している。この地域は「高原」という言葉で連想されるのどかな場所ではない。険しい大山岳地帯なのである。
タジキスタン紀行記 (1) (2) (3)
事前に旅行会社から配布された書類には次の記述があった。
「ホジャンド~ドゥシャンベ、ドゥシャンベ~ペンジケントなどは険しい山岳道路です。小型バスまたはバンに分乗してのご案内となり、添乗員が同乗しない車両がございます」
13年前に刊行された『週刊シルクロード紀行』という雑誌には、この山岳道路を「尻が5センチも浮き上がる衝撃が続く悪路」と綴った紀行文があった。だから覚悟はしていた。
しかし、この山岳道路は思いのほか快適で、窓外に広がる息をのむ山岳風景を満喫できた。道路はすべて舗装されてる。ガードレールはほとんどない。総勢13人(参加者9人、添乗員、ガイド2人、運転手)には贅沢すぎる普通のバスで走行でき、小型バスに分乗することはなかった。
近年、この道路は中国によって舗装され、トンネルも掘られたそうだ。タジキスタンと中国は国境を接している。この道路整備も「シルクロード経済ベルト」を目指す一帯一路構想の一環だろうか。世界各地で増大する中国の存在感が不気味でもある。
標高3000メートルを越えるこの山岳道路は冬季も通行可能だそうだ。驚きである。ガイドは「有料道路なので冬も整備しています」と言っていた。
タジキスタンは山岳の国である。地形図を見れば明らかなように、われわれが旅行した西側はまだ標高が低い地域で、国の東側は7000メートルを越える高山が連なるパミール高原になる。その山岳地域にもかなりの数の人々が暮らしているそうだ。
ドゥシャンベのホテルの部屋には「MOUNTAINS ARE CALLING」と書いたチラシや冊子を置いてあった。パミールの山岳地帯を目指すワイルドないで立ちの宿泊客も見かけた。
ガイドの話によれば、パミールに行くツアーも多くあり、パミールから国境を越えてアフガニスタンに入ることもできるそうだ。そこはアフガニスタンでも比較的安全な地域で、日本人観光客も何人か案内したと言っていた。これにはびっくりした。日本の外務省はアフガニスタンを危険レベル最高のレベル4(退避してください。渡航は止めてください)に指定している。
なお、日本のパミール中央アジア研究会は、日本の地図帳の「パミール高原」という記載を「パミール」に訂正すべきだと提言している。この地域は「高原」という言葉で連想されるのどかな場所ではない。険しい大山岳地帯なのである。
タジキスタン紀行記 (1) (2) (3)
ペンジケント遺跡に立つ……タジキスタン紀行記(3) ― 2019年08月23日
ソグド商人への関心から「ソグディアナ」という言葉に惹かれてツアーに参加した私にとって、メインの訪問地はペンジケント遺跡である。ただし事前に「ほとんど何も残っていない場所ですよ」と聞いていたので、現場の雰囲気を感じるだけでいいと覚悟していた。
ペンジケントは5~8世紀のソグド人の都市遺跡である。ここをマーイムルグ(米国)と比定する吉田豊説が有力だそうだ( 森安孝夫『シルクロードと唐帝国』による。吉田豊氏はソグド語が解読できる日本でただ一人の学者)。シルクロードの支配者とされるソグド商人の故地ソグディアナは、多くのオアシス都市で構成されていた。それは都市国家の緩やかな連合体であり、ソグド人は統一国家を作ることはなかった。ペンジケントはそんな都市国家の一つである。
ペンジケント遺跡は中央アジアで発掘が最も進んでいる遺跡である。歴史学者ドゥ・ラ・ヴェシエールは「最盛期におけるソグディアナの経済的・社会的情報は、ザラフシャン川の渓谷に深く入りくんだまちであるペンジケントにおいてのみ知られている」と 『ソグド商人の歴史』で述べている。中央アジアの歴史概説書のいくつかには、ペンジケント遺跡の図面や発掘された壁画の写真が載っている。
日本から約6000Km、はるばるたどり着いたペンジケント遺跡の入口付近には案内板が3つ立っていた。それだけで、門や囲いはなく管理人などもいない。丘陵への階段を登っていくと踏み跡のような道につながり、周囲に日干しレンガの構築物の残骸らしきものが見えてくる。住居や寺院の跡のようだがよくわからない。廃墟というより荒野に近い。われわれ以外には誰もいない。
この遺跡に立って千数百年前のオアシス都市の姿を偲ぶには心の眼で眺めるしかない。現場に立ったという昂揚感で、時間の彼方から吹いてくるシルクロードの風をかすかに感じた気がした。
遺跡内に説明看板は一つもない。来場者に対してもう少し親切に整備するべきではと思った。だが、空気を感じるには何もない方がいいのかもしれない。
この遺跡は住居跡から多くの壁画が発掘されたことで有名である。ソ連時代に発掘された壁画の多くはエルミタージュ美術館に運ばれた。ドゥシャンベの国立古代博物館に展示されている壁画もあり、それは昨日観てきた。
壁画で有名なペンジケント遺跡だが、現場は抜け殻である。それは仕方のないことではあるが、遺跡のどこにどんな壁画があったのかは知りたいと思った。
タジキスタン紀行記 (1) (2) (3)
ペンジケントは5~8世紀のソグド人の都市遺跡である。ここをマーイムルグ(米国)と比定する吉田豊説が有力だそうだ( 森安孝夫『シルクロードと唐帝国』による。吉田豊氏はソグド語が解読できる日本でただ一人の学者)。シルクロードの支配者とされるソグド商人の故地ソグディアナは、多くのオアシス都市で構成されていた。それは都市国家の緩やかな連合体であり、ソグド人は統一国家を作ることはなかった。ペンジケントはそんな都市国家の一つである。
ペンジケント遺跡は中央アジアで発掘が最も進んでいる遺跡である。歴史学者ドゥ・ラ・ヴェシエールは「最盛期におけるソグディアナの経済的・社会的情報は、ザラフシャン川の渓谷に深く入りくんだまちであるペンジケントにおいてのみ知られている」と 『ソグド商人の歴史』で述べている。中央アジアの歴史概説書のいくつかには、ペンジケント遺跡の図面や発掘された壁画の写真が載っている。
日本から約6000Km、はるばるたどり着いたペンジケント遺跡の入口付近には案内板が3つ立っていた。それだけで、門や囲いはなく管理人などもいない。丘陵への階段を登っていくと踏み跡のような道につながり、周囲に日干しレンガの構築物の残骸らしきものが見えてくる。住居や寺院の跡のようだがよくわからない。廃墟というより荒野に近い。われわれ以外には誰もいない。
この遺跡に立って千数百年前のオアシス都市の姿を偲ぶには心の眼で眺めるしかない。現場に立ったという昂揚感で、時間の彼方から吹いてくるシルクロードの風をかすかに感じた気がした。
遺跡内に説明看板は一つもない。来場者に対してもう少し親切に整備するべきではと思った。だが、空気を感じるには何もない方がいいのかもしれない。
この遺跡は住居跡から多くの壁画が発掘されたことで有名である。ソ連時代に発掘された壁画の多くはエルミタージュ美術館に運ばれた。ドゥシャンベの国立古代博物館に展示されている壁画もあり、それは昨日観てきた。
壁画で有名なペンジケント遺跡だが、現場は抜け殻である。それは仕方のないことではあるが、遺跡のどこにどんな壁画があったのかは知りたいと思った。
タジキスタン紀行記 (1) (2) (3)
中央アジアの通史は複雑で読むのが大変 ― 2019年08月29日
『文明の十字路=中央アジアの歴史』(岩村忍/講談社学術文庫)
300ページほどの文庫本だが読了に思いのほかの時日を要した。タジキスタン旅行の前に読み始め、航空機の中での読書に手頃だと思い機内に持参した。往復の機内で多少は読み進めたが、当然ながら居眠りetcで中断が多く半分ぐらいまでしか読めなかった。
帰国後も細切れ読書ばかりで1週間以上かけてやっと読み終えた。時間がかかったのは読書環境のせいだけではなく、本書の扱っている時間と地域のせいである。時間は膨大、地域は限定されているからである。
本書は1977年に講談社から刊行された『世界の歴史12 中央アジアの遊牧民族』を文庫化したものである。私は講談社のこの歴史全集をバラで3冊だけ持っている。著者はこの全集の5人の企画委員の一人で、各巻のオビには次の惹句がある。
「第三世界にも焦点をあて、人類全史を新視点で体系化した日本で初めての世界歴史全集」
従来の歴史全集との差別化を謳っているのだ。そんな気合のせいか、本書はユニークな歴史書である。
扱っている地域は東トルキスタン(中国の新疆ウイグル自治区)と西トルキスタン(カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン)で、かなり限定されている。その歴史記述は紀元前5000年から1950年代までと長い。東西トルキスタンの石器時代から現代までを描いた通史なのである。
この長い時間を一気に読むにはかなりの気力がいる。地域を限定していても周辺の国々との多様な関係によって歴史は進行する。中国、ロシア(ソ連)、中近東、ヨーロッパの出来事や人物が頻出する。基本的な世界史が頭に入っていないとわけがわからなくなる。だから、人名辞典・用語集・参考書などを参照しながらの読書になってしまう。
前半の「第4章 シルクロード」あたりまでは私の現在の関心領域なので興味深く読み進められた。「第5章 イスラム勢力の展開」から19世紀、20世紀と時代が進んでくると消化不良になった。私にとって未知の事項が多いからである。勉強にはなった。
著者の岩村忍氏は1905年生まれ、1988年に没した歴史学者である。遊牧民への否定的イメージの払しょくを主張する歴史学者・杉山正明氏(1952年生まれ)とは世代がかなり隔たっている。本書を読んでいると杉山氏の指摘する「否定的イメージ」を感じる箇所が確かにある。歴史学の変遷という視点であらためて比較検討してみたいと感じた。
なお、この文庫本で気になったのは「旧ソ連」という言葉である(P29)。著者はソ連崩壊以前に亡くなっているので、文庫化にあたって編集者が書き換えたと思われるが、編集者が手を入れたという記述はどこにもない。本書はあくまで1970年代視点の現代史に連なる歴史を描いているのだから「旧ソ連」はおかしい。他にも後世視点で手を入れている部分があるのではと勘ぐりたくなる。
300ページほどの文庫本だが読了に思いのほかの時日を要した。タジキスタン旅行の前に読み始め、航空機の中での読書に手頃だと思い機内に持参した。往復の機内で多少は読み進めたが、当然ながら居眠りetcで中断が多く半分ぐらいまでしか読めなかった。
帰国後も細切れ読書ばかりで1週間以上かけてやっと読み終えた。時間がかかったのは読書環境のせいだけではなく、本書の扱っている時間と地域のせいである。時間は膨大、地域は限定されているからである。
本書は1977年に講談社から刊行された『世界の歴史12 中央アジアの遊牧民族』を文庫化したものである。私は講談社のこの歴史全集をバラで3冊だけ持っている。著者はこの全集の5人の企画委員の一人で、各巻のオビには次の惹句がある。
「第三世界にも焦点をあて、人類全史を新視点で体系化した日本で初めての世界歴史全集」
従来の歴史全集との差別化を謳っているのだ。そんな気合のせいか、本書はユニークな歴史書である。
扱っている地域は東トルキスタン(中国の新疆ウイグル自治区)と西トルキスタン(カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン)で、かなり限定されている。その歴史記述は紀元前5000年から1950年代までと長い。東西トルキスタンの石器時代から現代までを描いた通史なのである。
この長い時間を一気に読むにはかなりの気力がいる。地域を限定していても周辺の国々との多様な関係によって歴史は進行する。中国、ロシア(ソ連)、中近東、ヨーロッパの出来事や人物が頻出する。基本的な世界史が頭に入っていないとわけがわからなくなる。だから、人名辞典・用語集・参考書などを参照しながらの読書になってしまう。
前半の「第4章 シルクロード」あたりまでは私の現在の関心領域なので興味深く読み進められた。「第5章 イスラム勢力の展開」から19世紀、20世紀と時代が進んでくると消化不良になった。私にとって未知の事項が多いからである。勉強にはなった。
著者の岩村忍氏は1905年生まれ、1988年に没した歴史学者である。遊牧民への否定的イメージの払しょくを主張する歴史学者・杉山正明氏(1952年生まれ)とは世代がかなり隔たっている。本書を読んでいると杉山氏の指摘する「否定的イメージ」を感じる箇所が確かにある。歴史学の変遷という視点であらためて比較検討してみたいと感じた。
なお、この文庫本で気になったのは「旧ソ連」という言葉である(P29)。著者はソ連崩壊以前に亡くなっているので、文庫化にあたって編集者が書き換えたと思われるが、編集者が手を入れたという記述はどこにもない。本書はあくまで1970年代視点の現代史に連なる歴史を描いているのだから「旧ソ連」はおかしい。他にも後世視点で手を入れている部分があるのではと勘ぐりたくなる。
『ヒトラーの時代』は文学者視点の歴史エッセイ ― 2019年08月31日
カフカの伝記なども書いているドイツ文学者・池内紀氏がヒトラーに関する新書を出した。
『ヒトラーの時代:ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか』(池内紀/中公新書)
文学的な話題も多い歴史エッセイで読みやすい。池内氏は「あとがき」で本書執筆の動機を述べている。「ドイツ文学者」として自分なりに「ヒトラーの時代」が何であったかの答えを出すのは生涯の課題であり、「自分の能力の有効期間が尽きかけている。もう猶予はできない。」と気づいて執筆したそうだ。
本書はいろいろな切り口から「ヒトラーの時代」を考察したエッセイで、興味深いエピソードも多く盛り込まれている。著者が長年考えてきたアレコレを縦横に語るコラム集成のような本で、時間が行ったり来たりする。それは仕方ないのだが、繰り返しが多いのが気になった。年寄りの長話を拝聴している気分になる。私も年寄りなので他人のことは言えないが…
本書の指摘であらためて認識したのは、ナチ政権成立時の幹部たちの「若さ」である。ヒトラー43歳、ゲーリング40歳、ゲッベルス35歳、ヘス38歳、ヒムラー32歳、まさに暴走する青年達の政権である。当時の年配者たちが抱いたであろう危惧と期待の混ざった困惑が想像できる。
本書の二十数編のエッセイ、どれも面白いが、特に「歓喜力行」と「亡命ハンドブック」が興味深かった。
労働者の休暇を組織化し、音楽会、映画会、スポーツ、旅行などを安価に斡旋した「歓喜力行」については他書でも読んでいたが、その規模の大きさに驚く。海外クルーズや健康志向に、やはり奇妙な帝国だと思ってしまう。
「亡命ハンドブック」については本書で初めて知った。ユダヤ人の出版社がユダヤ人のために出版したハンドブックで、かなり実用的な本だったらしい。この本が発禁にはならなかったのが面白い。執筆者は複数いて、その一人はギリギリまでドイツに残って亡命に失敗し、アウシュヴィッツで死んだそうだ。それが「ヒトラーの時代」である。
「ジュタリーン文字」の話はよくわからなかった。ドイツ文字を改良した書体らしいがドイツ文字との違いがわからず、ネットで検索したがやはりわからない。
『ヒトラーの時代:ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか』(池内紀/中公新書)
文学的な話題も多い歴史エッセイで読みやすい。池内氏は「あとがき」で本書執筆の動機を述べている。「ドイツ文学者」として自分なりに「ヒトラーの時代」が何であったかの答えを出すのは生涯の課題であり、「自分の能力の有効期間が尽きかけている。もう猶予はできない。」と気づいて執筆したそうだ。
本書はいろいろな切り口から「ヒトラーの時代」を考察したエッセイで、興味深いエピソードも多く盛り込まれている。著者が長年考えてきたアレコレを縦横に語るコラム集成のような本で、時間が行ったり来たりする。それは仕方ないのだが、繰り返しが多いのが気になった。年寄りの長話を拝聴している気分になる。私も年寄りなので他人のことは言えないが…
本書の指摘であらためて認識したのは、ナチ政権成立時の幹部たちの「若さ」である。ヒトラー43歳、ゲーリング40歳、ゲッベルス35歳、ヘス38歳、ヒムラー32歳、まさに暴走する青年達の政権である。当時の年配者たちが抱いたであろう危惧と期待の混ざった困惑が想像できる。
本書の二十数編のエッセイ、どれも面白いが、特に「歓喜力行」と「亡命ハンドブック」が興味深かった。
労働者の休暇を組織化し、音楽会、映画会、スポーツ、旅行などを安価に斡旋した「歓喜力行」については他書でも読んでいたが、その規模の大きさに驚く。海外クルーズや健康志向に、やはり奇妙な帝国だと思ってしまう。
「亡命ハンドブック」については本書で初めて知った。ユダヤ人の出版社がユダヤ人のために出版したハンドブックで、かなり実用的な本だったらしい。この本が発禁にはならなかったのが面白い。執筆者は複数いて、その一人はギリギリまでドイツに残って亡命に失敗し、アウシュヴィッツで死んだそうだ。それが「ヒトラーの時代」である。
「ジュタリーン文字」の話はよくわからなかった。ドイツ文字を改良した書体らしいがドイツ文字との違いがわからず、ネットで検索したがやはりわからない。

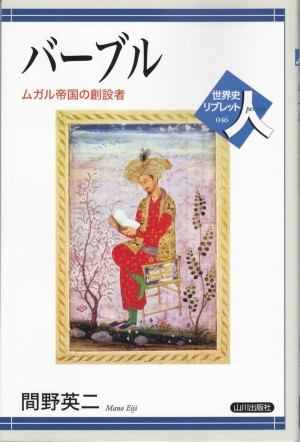






最近のコメント