「大学はジャングルだ」を誤解していた ― 2021年12月03日
京大の前総長、ゴリラ学者・山極寿一氏の新刊をタイトルに惹かれて読んだ。
『京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこと』(山極寿一/朝日新書/朝日新聞出版)
大学をジャングルに見立てたタイトルで連想したのは、数年前に読んだ『最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常』である。妻が藝大生の作家が、藝大という秘境に棲む怪人たちの生態をレポートした本だった。
『京大という…』は、総長という立場から解放されたゴリラ学者が、大学という密林に生息する類人猿もどきの怪しい大学人たちの生態を冷徹な学者の目であばき出す本だろうと予想した。未知の世界を覗き見する野次馬気分で読み始めたが、予想とは違う内容だった。大学教育のあるべき姿を模索する真面目でまっとうな新書である。
大学の事情や課題の提示がメインで、総長として体験した話に加えて研究者時代のフィールドワークの報告も盛り込まれている。総長時代の話も興味深いが、やはり研究者としての体験談の方が面白い。私は6年前に山極氏の 著書2冊を読んでいて、その研究概要の一端のサワリに触れたことはあったが、あらためて霊長類研究が人類の「教育」の考察につながることを知り、学問の深遠を認識した。
「教育」とは人類独特のものらしい。ゴリラには1頭のオスと複数のメスからなる家族のような集団しかなく、チンパンジーには複数のオスとメスからなる共同体しかない。人間には家族があり、さらに複数の家族が集まった共同体がある。こんな二重構造の社会は人間にしかなく、そこには高い「共感能力」「同化意識」が必要であり、そんな「社会力」が人類進化の源泉だった。「教育」とは家族と共同体の二重構造の社会に生れた共感力の賜物なのである。なるほどと思った。
大学をジャングルに見立てたのを、魑魅魍魎が生息する未開の暗闇のように思ったのは私の大きな誤解だった。ジャングルは多様な生物が共生する地であり、「大学はジャングルと同じように多様性と総合知によって成り立つコモンズ」という肯定的なたとえなのである。
『京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこと』(山極寿一/朝日新書/朝日新聞出版)
大学をジャングルに見立てたタイトルで連想したのは、数年前に読んだ『最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常』である。妻が藝大生の作家が、藝大という秘境に棲む怪人たちの生態をレポートした本だった。
『京大という…』は、総長という立場から解放されたゴリラ学者が、大学という密林に生息する類人猿もどきの怪しい大学人たちの生態を冷徹な学者の目であばき出す本だろうと予想した。未知の世界を覗き見する野次馬気分で読み始めたが、予想とは違う内容だった。大学教育のあるべき姿を模索する真面目でまっとうな新書である。
大学の事情や課題の提示がメインで、総長として体験した話に加えて研究者時代のフィールドワークの報告も盛り込まれている。総長時代の話も興味深いが、やはり研究者としての体験談の方が面白い。私は6年前に山極氏の 著書2冊を読んでいて、その研究概要の一端のサワリに触れたことはあったが、あらためて霊長類研究が人類の「教育」の考察につながることを知り、学問の深遠を認識した。
「教育」とは人類独特のものらしい。ゴリラには1頭のオスと複数のメスからなる家族のような集団しかなく、チンパンジーには複数のオスとメスからなる共同体しかない。人間には家族があり、さらに複数の家族が集まった共同体がある。こんな二重構造の社会は人間にしかなく、そこには高い「共感能力」「同化意識」が必要であり、そんな「社会力」が人類進化の源泉だった。「教育」とは家族と共同体の二重構造の社会に生れた共感力の賜物なのである。なるほどと思った。
大学をジャングルに見立てたのを、魑魅魍魎が生息する未開の暗闇のように思ったのは私の大きな誤解だった。ジャングルは多様な生物が共生する地であり、「大学はジャングルと同じように多様性と総合知によって成り立つコモンズ」という肯定的なたとえなのである。
ハラリ氏の『21 Lessons』は自分語りの書でもある ― 2021年12月05日
『21 Lessons:21世紀の人類のための21の思考』(ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田裕之訳/河出文庫)
原著は2018年刊行、翻訳の単行本が出たのが2年前の2019年11月だった。あの頃、本屋の店頭に山積みになっている本書(単行本)をパラパラとめくり、敬遠した。先月その文庫版が出て、購入した。
4年前、 『サピエンス全史』を読んだとき、明晰で俯瞰的な切れ味に感動した。だが、次の著作『ホモ・デウス』には感動しなかった。このブログに読後感も書かなかったので記憶が霞んでいるが、テクノロジーによって人間が神になるという話が陳腐に思え、あたりまえの話のくり返しに退屈した気がする。
2年前、本書の単行本を手にしたとき、『ホモ・デウス』のテクノロジー譚を現代に敷衍しただけの本に思えて敬遠した。その文庫版を読む気になったのは、私の考えが変わったからである。この世は私が思っている以上に陳腐かつ不可解・不合理で、とんでもない未来社会に突入しそうな気がしてきて、濃霧の未来を考えるにはハラリ氏の割り切りのいい見解が有効かもしれないと思うようになったのだ。
本書は「今日の世界で何が起こっているのか、そして、さまざま出来事の持つ深い意味合いは何か」を検討している。論理は明晰で、秀逸なレトリックと面白いアナロジーに魅了される。ユーモアもある。著者が展開する見解の大部分は自明で常識的なものに思える。問題は現実の世界が自明で常識的な論理では動いていないということである。
人はドグマに陥ってはダメであり、寛容でなければならない。自分の周囲だけでなく、より広い世界(地球、宇宙)を視野に考えなければならない、自身の無知を知らなければならない。その通りであり、すべての人類がそうなればいいのだが、それが難しい。著者は次のように述べている。
「人間の愚かさは、決して過小評価するべきでない。人間は個人のレベルでも集団のレベルでも、自滅的なことをやりがちだから。」
著者は本書で自身について率直に語っていて、その部分も興味深い。ユダヤ人であること、宗教に懐疑的であること、同性愛者であることなどの自分語りを通して世界を洞察している箇所も多い。しかし、私には最後の2レッスン「20. 意味:人生は物語でない」「21. 瞑想:ひたすら観察せよ」は難解で、ついて行けなかった。
原著は2018年刊行、翻訳の単行本が出たのが2年前の2019年11月だった。あの頃、本屋の店頭に山積みになっている本書(単行本)をパラパラとめくり、敬遠した。先月その文庫版が出て、購入した。
4年前、 『サピエンス全史』を読んだとき、明晰で俯瞰的な切れ味に感動した。だが、次の著作『ホモ・デウス』には感動しなかった。このブログに読後感も書かなかったので記憶が霞んでいるが、テクノロジーによって人間が神になるという話が陳腐に思え、あたりまえの話のくり返しに退屈した気がする。
2年前、本書の単行本を手にしたとき、『ホモ・デウス』のテクノロジー譚を現代に敷衍しただけの本に思えて敬遠した。その文庫版を読む気になったのは、私の考えが変わったからである。この世は私が思っている以上に陳腐かつ不可解・不合理で、とんでもない未来社会に突入しそうな気がしてきて、濃霧の未来を考えるにはハラリ氏の割り切りのいい見解が有効かもしれないと思うようになったのだ。
本書は「今日の世界で何が起こっているのか、そして、さまざま出来事の持つ深い意味合いは何か」を検討している。論理は明晰で、秀逸なレトリックと面白いアナロジーに魅了される。ユーモアもある。著者が展開する見解の大部分は自明で常識的なものに思える。問題は現実の世界が自明で常識的な論理では動いていないということである。
人はドグマに陥ってはダメであり、寛容でなければならない。自分の周囲だけでなく、より広い世界(地球、宇宙)を視野に考えなければならない、自身の無知を知らなければならない。その通りであり、すべての人類がそうなればいいのだが、それが難しい。著者は次のように述べている。
「人間の愚かさは、決して過小評価するべきでない。人間は個人のレベルでも集団のレベルでも、自滅的なことをやりがちだから。」
著者は本書で自身について率直に語っていて、その部分も興味深い。ユダヤ人であること、宗教に懐疑的であること、同性愛者であることなどの自分語りを通して世界を洞察している箇所も多い。しかし、私には最後の2レッスン「20. 意味:人生は物語でない」「21. 瞑想:ひたすら観察せよ」は難解で、ついて行けなかった。
ナンセンス・コメディ『イモンドの勝負』は東京五輪の賜物? ― 2021年12月08日
本多劇場でナイロン100℃の『イモンドの勝負』(作・演出:ケラリーノ・サンドロヴィッチ、出演:大倉孝二・他)を観た。ケラリーノ・サンドロヴィッチ(ケラ)主宰のナイロン100℃の舞台は初体験である。
3カ月前にケラ演出の『砂の女』を観て、初めてこの鬼才を知った。『イモンドの勝負』は『砂の女』とはまったく異なるナンセンス・コメディで、こちらがケラ氏の本領のようだ。休憩を含めて3時間を超える舞台は、絢爛なイルージョンと醒めたナンセンスが織りなす不思議な世界だった。
『砂の女』では垂直方向に拡がる舞台装置と壮大なプロジェクションマッピングに魅せられた。『イモンドの勝負』も舞台は垂直方向に拡がる街になっていて、プロジェクションマッピングも華麗だ。垂直舞台で不可思議な勝負の世界が展開される。
冒頭のベンチのシーンは別役実を思わせるが、不条理というよりはブラックユーモアのナンセンスな展開になる。ベンチに横たわって死んでしまった主人公(大倉孝二)の幽体離脱シーンには驚いた。その後の展開でも、登場人物たちが生きているのか死んでいるのかよくわからない。ゾンビをバンビと呼ぶナンセンスが楽しい。
7000人の孤児を抱えると誇示しながら実は2人の孤児しかいない孤児院の助成金獲得運動が、ナンセンス・コメディのなかで妙にリアルに感じられる。人間を食べる怪獣のような動物はペットのようでもあり、妖しい電波で人間をコントロールする宇宙人も登場する。この舞台を観ながら倉橋由美子の『スミヤキストQの冒険』を連想した。荒唐無稽のなかに辛辣なものを感じる。
この舞台の背後には「オリンピック」がある。東京五輪に批判的だったケラ氏はパラリンピック開会式の演出を引き受けるものの、開催延期にともなって降板する。近々開催予定のまま、いつ開催されるか、あるいはすでに開催されたのも不分明なまま忘れられようとしている国際的(あるいは宇宙的)な競技大会――この設定にケラ氏の実体験がどの程度反映されているかはわからない。とても面白いテーマだと思う。
3カ月前にケラ演出の『砂の女』を観て、初めてこの鬼才を知った。『イモンドの勝負』は『砂の女』とはまったく異なるナンセンス・コメディで、こちらがケラ氏の本領のようだ。休憩を含めて3時間を超える舞台は、絢爛なイルージョンと醒めたナンセンスが織りなす不思議な世界だった。
『砂の女』では垂直方向に拡がる舞台装置と壮大なプロジェクションマッピングに魅せられた。『イモンドの勝負』も舞台は垂直方向に拡がる街になっていて、プロジェクションマッピングも華麗だ。垂直舞台で不可思議な勝負の世界が展開される。
冒頭のベンチのシーンは別役実を思わせるが、不条理というよりはブラックユーモアのナンセンスな展開になる。ベンチに横たわって死んでしまった主人公(大倉孝二)の幽体離脱シーンには驚いた。その後の展開でも、登場人物たちが生きているのか死んでいるのかよくわからない。ゾンビをバンビと呼ぶナンセンスが楽しい。
7000人の孤児を抱えると誇示しながら実は2人の孤児しかいない孤児院の助成金獲得運動が、ナンセンス・コメディのなかで妙にリアルに感じられる。人間を食べる怪獣のような動物はペットのようでもあり、妖しい電波で人間をコントロールする宇宙人も登場する。この舞台を観ながら倉橋由美子の『スミヤキストQの冒険』を連想した。荒唐無稽のなかに辛辣なものを感じる。
この舞台の背後には「オリンピック」がある。東京五輪に批判的だったケラ氏はパラリンピック開会式の演出を引き受けるものの、開催延期にともなって降板する。近々開催予定のまま、いつ開催されるか、あるいはすでに開催されたのも不分明なまま忘れられようとしている国際的(あるいは宇宙的)な競技大会――この設定にケラ氏の実体験がどの程度反映されているかはわからない。とても面白いテーマだと思う。
1992年のTV番組『大モンゴル』の書籍を入手 ― 2021年12月10日
杉山正明氏は
『大モンゴルの世界』
の文庫版あとがきで、NHKとBBS共同制作の番組『大モンゴル』にかかわった思い出を語っている。自信作らしいが、私はこの番組を見ていない。1992年に5回にわたって放映、その
第1回の冒頭部分はウェブで視聴できるが、NHKオンデマンドには入ってない。いつの日かの再放送を待つしかない。
ネット検索でこの番組を書籍化したものを見つけ、古書で入手した。ムック風の大判全4冊で、第4巻は写真集だった。第1~3巻に5回の番組内容を収録している。その第1巻は、番組の第2集『蒼き狼チンギス・ハーン』である。
『大モンゴル1:蒼き狼チンギス・ハーン』(NHK取材班編/角川書店)
番組に対応した本文とは別に、作家や学者の文章8編を収録している。それぞれの見解と番組内容に多少のズレがあるのが興味深い。歴史の面白さである。
チンギス・ハーンの生涯を追った番組の取材先はモンゴル、中国、ウズベキスタンなどだ。番組の取材は1990年から1991年にかけてで、ソ連崩壊の時期に重なる。モンゴルが「モンゴル人民共和国」から「モンゴル国」に改称したのは1992年であり、ウズベキスタン独立は1991年である。変動の時代の雰囲気が取材記の行間から伝わってくる。
ソ連の影響力が強かった時代、モンゴルではチンギス・ハーンは「禁じられた英雄」だった。だが1990年には復活し、チンギス・ハーン像も建てられた。番組はその除幕式の様子を伝えている。ソ連崩壊という現代史の転換期だから『大モンゴル』という番組を企画したのかもしれない。
この巻で興味深いのは、チンギス・ハーンの参謀だった契丹人・耶律阿海に注目している点である。有名な耶律楚材とはまったくの別人で、楚材よりずっと以前からテムジン(後のチンギス・ハーン)に仕え、楚材よりはるかに高い地位についた人物である。
人材登用に積極的だったモンゴルは、契丹人の耶律阿海をはじめ多様な人種で成り立ち、高度な情報収集力をもっていた。チンギス・ハーンの「侵略」は周到な事前調査調査に基づいたものだった。そんな指摘が新鮮に感じられた。
ネット検索でこの番組を書籍化したものを見つけ、古書で入手した。ムック風の大判全4冊で、第4巻は写真集だった。第1~3巻に5回の番組内容を収録している。その第1巻は、番組の第2集『蒼き狼チンギス・ハーン』である。
『大モンゴル1:蒼き狼チンギス・ハーン』(NHK取材班編/角川書店)
番組に対応した本文とは別に、作家や学者の文章8編を収録している。それぞれの見解と番組内容に多少のズレがあるのが興味深い。歴史の面白さである。
チンギス・ハーンの生涯を追った番組の取材先はモンゴル、中国、ウズベキスタンなどだ。番組の取材は1990年から1991年にかけてで、ソ連崩壊の時期に重なる。モンゴルが「モンゴル人民共和国」から「モンゴル国」に改称したのは1992年であり、ウズベキスタン独立は1991年である。変動の時代の雰囲気が取材記の行間から伝わってくる。
ソ連の影響力が強かった時代、モンゴルではチンギス・ハーンは「禁じられた英雄」だった。だが1990年には復活し、チンギス・ハーン像も建てられた。番組はその除幕式の様子を伝えている。ソ連崩壊という現代史の転換期だから『大モンゴル』という番組を企画したのかもしれない。
この巻で興味深いのは、チンギス・ハーンの参謀だった契丹人・耶律阿海に注目している点である。有名な耶律楚材とはまったくの別人で、楚材よりずっと以前からテムジン(後のチンギス・ハーン)に仕え、楚材よりはるかに高い地位についた人物である。
人材登用に積極的だったモンゴルは、契丹人の耶律阿海をはじめ多様な人種で成り立ち、高度な情報収集力をもっていた。チンギス・ハーンの「侵略」は周到な事前調査調査に基づいたものだった。そんな指摘が新鮮に感じられた。
「ネスリウス派の今」にびっくりしたが… ― 2021年12月11日
1992年放映のNHKスペシャル『大モンゴル』書籍版の第2巻である。
『大モンゴル2:幻の王プレスタージョン/世界征服への道』(NHK取材班編/角川書店)
この巻は次の2回分の番組内容を収録している。
第1集『幻の王プレスター・ジョン』
第3集『世界征服への道』
書籍はチンギス・ハーンに始まる時系列構成だが、テレビ番組の第1回は『幻の王プレスター・ジョン』である。シリーズ冒頭に衝撃的なツカミとしてプレスター・ジョンをもってきた番組制作者の意図は、いまも視聴できる 第1集の冒頭部分を見れば理解できる。
はるか東方にキリスト教を信じるプレスター・ジョンという王がいて、イスラム教徒を駆逐している。そんな伝説が十字軍時代のヨーロッパにあり、東方の王の来援を期待していた。しかし、東方から現れたのはモンゴル軍だった――思わず引き込まれる話である。
キリスト教の東方へ伝播を追った第1集ではネストリウス派を取り上げている。そこで、私には非常に興味深い記述に出会った。
シルクロードで唐にまで伝わったキリスト教はネストリウス派で、唐では景教と呼ばれた。大昔に消えた宗派だと私は思っていたが、最近、そのネストリウス派が現代まで続いていると知って驚いた。アッシリア東方教会というのが現代のネストリウス派で、この教会はネストリウス派を蔑称と感じているので、いまはネストリウス派という名称を使わないようにしようという流れがあるそうだ。
そんな話を聞いた直後に、30年前の本書で「ネストリウス派の今」に関する記述に接した。驚いたことに、アッシリア東方教会の総本山はアメリカのイリノイ州にあるそうだ。取材班は総本山に連絡をとり「私たちの本部は、中世以来長い間バグダードにありましたが、今世紀(20世紀)に入って総司教がアメリカに移住し、本部も移したのです」との情報を得ている。
ヘェーと思いながらウィキペディアで 「アッシリア東方教会」 を検索すると、確かに「総主教庁はアメリア・イリノイ州にある」と記述している。念のためにウィキペディア英語版で "Assyrian Church of the East" を検索すると、日本語版の数倍の情報量だった。ザーッと眺めたところ、この英文ページには、信者は米国に多くいてイリノイ州やカリフォルニア州に教区があるとは書いているが「総主教庁はイリノイ州」の記述はない。Headquarters の欄は "Ankawa, Erbil, Iraq"となっている。ウィキペディアの信憑性は自分で判断するしかない。
私が推測するに、30年前にNHKが報じた「総本山はイリノイ州」は、当時そう自称する団体があったというだけの話で、誤報ではなかろうか。日本語のウィキペディアに「総主教庁はイリノイ州」とあるのは、この番組が何らかの影響を及ぼしているのかもしれない。
『大モンゴル2:幻の王プレスタージョン/世界征服への道』(NHK取材班編/角川書店)
この巻は次の2回分の番組内容を収録している。
第1集『幻の王プレスター・ジョン』
第3集『世界征服への道』
書籍はチンギス・ハーンに始まる時系列構成だが、テレビ番組の第1回は『幻の王プレスター・ジョン』である。シリーズ冒頭に衝撃的なツカミとしてプレスター・ジョンをもってきた番組制作者の意図は、いまも視聴できる 第1集の冒頭部分を見れば理解できる。
はるか東方にキリスト教を信じるプレスター・ジョンという王がいて、イスラム教徒を駆逐している。そんな伝説が十字軍時代のヨーロッパにあり、東方の王の来援を期待していた。しかし、東方から現れたのはモンゴル軍だった――思わず引き込まれる話である。
キリスト教の東方へ伝播を追った第1集ではネストリウス派を取り上げている。そこで、私には非常に興味深い記述に出会った。
シルクロードで唐にまで伝わったキリスト教はネストリウス派で、唐では景教と呼ばれた。大昔に消えた宗派だと私は思っていたが、最近、そのネストリウス派が現代まで続いていると知って驚いた。アッシリア東方教会というのが現代のネストリウス派で、この教会はネストリウス派を蔑称と感じているので、いまはネストリウス派という名称を使わないようにしようという流れがあるそうだ。
そんな話を聞いた直後に、30年前の本書で「ネストリウス派の今」に関する記述に接した。驚いたことに、アッシリア東方教会の総本山はアメリカのイリノイ州にあるそうだ。取材班は総本山に連絡をとり「私たちの本部は、中世以来長い間バグダードにありましたが、今世紀(20世紀)に入って総司教がアメリカに移住し、本部も移したのです」との情報を得ている。
ヘェーと思いながらウィキペディアで 「アッシリア東方教会」 を検索すると、確かに「総主教庁はアメリア・イリノイ州にある」と記述している。念のためにウィキペディア英語版で "Assyrian Church of the East" を検索すると、日本語版の数倍の情報量だった。ザーッと眺めたところ、この英文ページには、信者は米国に多くいてイリノイ州やカリフォルニア州に教区があるとは書いているが「総主教庁はイリノイ州」の記述はない。Headquarters の欄は "Ankawa, Erbil, Iraq"となっている。ウィキペディアの信憑性は自分で判断するしかない。
私が推測するに、30年前にNHKが報じた「総本山はイリノイ州」は、当時そう自称する団体があったというだけの話で、誤報ではなかろうか。日本語のウィキペディアに「総主教庁はイリノイ州」とあるのは、この番組が何らかの影響を及ぼしているのかもしれない。
『大モンゴル』最終回はクリミア・タタール人の現在 ― 2021年12月12日
1992年放映のNHKスペシャル『大モンゴル』書籍版の第3巻である。
『大モンゴル3:大いなる都/巨大国家の遺産』(NHK取材班編/角川書店)
この巻は次の2回分の番組内容を収録している。
第4集『大いなる都』
第5集『巨大国家の遺産』
「大いなる都」とは、フビライが築いた計画都市・大都(北京)である。大都は運河で海に直結する都として建設された。クビライは南宋を接収する以前から、海運の拠点である江南と大都を直結させた海運国家を構想していたらしい。
この番組ではフビライの時代の大都をCGで再現している。本書はそのCG画像を何点か掲載していて、これが興味深い。大運河の俯瞰や運河を往来する目線の画像もあり、海に直結する往時の都の様子を実感できる。
最終回『巨大国家の遺産』はモンゴル後継国家の話である。18世紀まで存続し、最後のモンゴル帝国とされるクリム・ハーン国の話が面白い。現代史に直結しているのだ。
クリミア半島にあったクリム・ハーン国がロシアに併合されて滅亡したのは1783年、エカテリーナ2世の時代である。それ以前のクリム・ハーン国はかなり存在感のある国だった。キプチャク・ハーン国の中からモスクワ国(ロシア)が台頭したのは、モンゴルに取り入ったからであり、ロシアとモンゴルの王室の間でにはかなりの血の交流があった。16世紀に活躍したイワン雷帝は一時期、キプチャク・ハーン国のハーン直系子孫に帝位を譲っている。この不思議な譲位は、ロシアがクリム・ハーン国からの攻撃を牽制するためだったのでは、と言われているそうだ。
クリム・ハーン国がロシアに併合されてからもクリミアにはタタール人が住んでいた。だが独ソ戦さなかの1944年、スターリンはクリミア・タタール人全員を中央アジアに強制移住させた。彼らはその後、クリミアへの帰還運動を繰り広げている。番組放映の前年の1991年2月、クリミア自治共和国が復活したが、クリミア・タタール人はロシア人主導のこの自治共和国を認めていない。
番組は、クリム・ハーン国をシンボルに独立国家建設運動を続けているクリミア・タタール人をレポートしている。
本書刊行から30年、ウクライナとロシアのはざまのクリミアは依然として紛糾の地である。
『大モンゴル3:大いなる都/巨大国家の遺産』(NHK取材班編/角川書店)
この巻は次の2回分の番組内容を収録している。
第4集『大いなる都』
第5集『巨大国家の遺産』
「大いなる都」とは、フビライが築いた計画都市・大都(北京)である。大都は運河で海に直結する都として建設された。クビライは南宋を接収する以前から、海運の拠点である江南と大都を直結させた海運国家を構想していたらしい。
この番組ではフビライの時代の大都をCGで再現している。本書はそのCG画像を何点か掲載していて、これが興味深い。大運河の俯瞰や運河を往来する目線の画像もあり、海に直結する往時の都の様子を実感できる。
最終回『巨大国家の遺産』はモンゴル後継国家の話である。18世紀まで存続し、最後のモンゴル帝国とされるクリム・ハーン国の話が面白い。現代史に直結しているのだ。
クリミア半島にあったクリム・ハーン国がロシアに併合されて滅亡したのは1783年、エカテリーナ2世の時代である。それ以前のクリム・ハーン国はかなり存在感のある国だった。キプチャク・ハーン国の中からモスクワ国(ロシア)が台頭したのは、モンゴルに取り入ったからであり、ロシアとモンゴルの王室の間でにはかなりの血の交流があった。16世紀に活躍したイワン雷帝は一時期、キプチャク・ハーン国のハーン直系子孫に帝位を譲っている。この不思議な譲位は、ロシアがクリム・ハーン国からの攻撃を牽制するためだったのでは、と言われているそうだ。
クリム・ハーン国がロシアに併合されてからもクリミアにはタタール人が住んでいた。だが独ソ戦さなかの1944年、スターリンはクリミア・タタール人全員を中央アジアに強制移住させた。彼らはその後、クリミアへの帰還運動を繰り広げている。番組放映の前年の1991年2月、クリミア自治共和国が復活したが、クリミア・タタール人はロシア人主導のこの自治共和国を認めていない。
番組は、クリム・ハーン国をシンボルに独立国家建設運動を続けているクリミア・タタール人をレポートしている。
本書刊行から30年、ウクライナとロシアのはざまのクリミアは依然として紛糾の地である。
「小市民」生活の奇妙な場面を積み上げる静謐な不条理劇 ― 2021年12月14日
新国立劇場小劇場で『あーぶくたった、にいたった』(作:別役実、演出:西沢栄治)を観た。「小市民」を描いた別役実の静謐な不条理劇である。
舞台には例によって電信柱が1本、上手のレトロな郵便ポストは何故か傾いたまま半分埋まっている。電信柱に万国旗がかかっているのがかえって寂しげである。開演前からロビーにも舞台にも三波春夫のメドレーが流れている。「1970年のこんにちわ~」と歌い終わった時点で開幕になった。
第1場はムシロの上の金屏風を背にした新郎と新婦の会話。まだ存在していない娘や息子の運命に関する妄想がエスカレートしていく。第2場も似たような婚礼場面で、新婦と新婦の両親が新郎を待っているが、新郎は来ない。新郎が来ないことはあらかじめわかっていたようでもある……そんなささやかな不条理シーンが電信柱の下で繰り返される。
タイトルの「あーぶくたった、にいたった」は「あぶく立った、煮え立った」という意味のわらべ唄で、この劇のシーン転換のたびに、子供の声で「あーぶく立った、煮い立った。煮えたかどうだか、食べてみよ。ムシャ、ムシャ、ムシャ。まだ煮えない」という唄がくり返し流れる。
また、舞台装置や役者の配置を指示する「ト書き」までが音声で流れる。私は戯曲を読んでいないので、これが作者の仕掛けなのか演出家の工夫なのかはわからない。「男1」「女1」「男2」「女2」などの役名があからさまに耳に入ると、舞台上の異世界の象徴性が高まる効果がある。
各シーンの男女は同一の人物の時間経過を追っているようにも、少しズレた分身のようにも見え、人の半生が長いようにも一瞬のようにも感じられる。婚礼から老いて死を迎えるまでの時間は、豆が煮える時間にも満たない。邯鄲の夢だ。
舞台には例によって電信柱が1本、上手のレトロな郵便ポストは何故か傾いたまま半分埋まっている。電信柱に万国旗がかかっているのがかえって寂しげである。開演前からロビーにも舞台にも三波春夫のメドレーが流れている。「1970年のこんにちわ~」と歌い終わった時点で開幕になった。
第1場はムシロの上の金屏風を背にした新郎と新婦の会話。まだ存在していない娘や息子の運命に関する妄想がエスカレートしていく。第2場も似たような婚礼場面で、新婦と新婦の両親が新郎を待っているが、新郎は来ない。新郎が来ないことはあらかじめわかっていたようでもある……そんなささやかな不条理シーンが電信柱の下で繰り返される。
タイトルの「あーぶくたった、にいたった」は「あぶく立った、煮え立った」という意味のわらべ唄で、この劇のシーン転換のたびに、子供の声で「あーぶく立った、煮い立った。煮えたかどうだか、食べてみよ。ムシャ、ムシャ、ムシャ。まだ煮えない」という唄がくり返し流れる。
また、舞台装置や役者の配置を指示する「ト書き」までが音声で流れる。私は戯曲を読んでいないので、これが作者の仕掛けなのか演出家の工夫なのかはわからない。「男1」「女1」「男2」「女2」などの役名があからさまに耳に入ると、舞台上の異世界の象徴性が高まる効果がある。
各シーンの男女は同一の人物の時間経過を追っているようにも、少しズレた分身のようにも見え、人の半生が長いようにも一瞬のようにも感じられる。婚礼から老いて死を迎えるまでの時間は、豆が煮える時間にも満たない。邯鄲の夢だ。
唐十郎の『泥人魚』をシアターコクーンで観た ― 2021年12月16日
シアターコクーンで『泥人魚』(作:唐十郎、演出:金守珍、出演:宮沢りえ、風間杜夫、他)を観た。2003年に劇団唐組で初演した芝居で、唐十郎の作品としては比較的最近のものだ。私は今回が初見である。戯曲は読売文学賞や鶴屋南北戯曲賞を受賞したそうだが、いまでは入手できず、読んでいない。
諫早湾干拓のギロチン堤防をモチーフに摩訶不思議な唐ワールドが繰り広げられる。冒頭、あのギロチンが轟音をたてながら次々と落とされて行く映像が流れる。そのシーンで、舞台が外界から遮断された異世界に転換した気分になる。
その異世界は、ブリキの湯たんぽが山ほどぶら下がっている「ブリキ加工店」だ。奇抜な設定に期待が高まる。そこに店主の風間杜夫が大きなブリキ板を頭上に抱えて登場する。この店主、まだらボケで、午後6時になると詩人・伊藤静雄(伊東ではない)に変身する。風間杜夫の怪演が快調である。
風間杜夫が唐作品に出演するのは 『唐版 風の又三郎』(シアターコクーン)、 『ベンガルの虎』(新宿梁山泊)に続いて3作目だそうだ。本人は「齢72にしてアングラデビュー」と語っているが、水を得た魚のような存在感がある。齢を重ねて怖いものがなくなるパワーだろうか。同世代として頼もしい限りである。
唐十郎の世界は脈略が錯綜し、さまざまなモノやイメージが乱舞する。今回は伊東静雄、島尾敏雄、天草四郎、かくれキリシタン、人間魚雷、ガラスの義眼、さくら貝の鱗、ブリキの鱗……などなどである。そして、宮沢りえの人魚姿へと収斂していく。
うかつにも私は知らなかったが、宮沢りえはこれまでに数多くの唐作品に出演してきたそうだ。すでに女座長のような風格が出ている。頼もしい限りである。
大劇場のシートに身をうずめ、文化功労者・唐十郎の芝居を重鎮や若手が大舞台で演ずる姿を観ていて、半世紀以上昔のギューギュー詰め紅テントの観客には想像できなかった未来だと思った。21世紀になって、くり返し上演される唐作品は、すでの伝統芸能のようでもある。
諫早湾干拓のギロチン堤防をモチーフに摩訶不思議な唐ワールドが繰り広げられる。冒頭、あのギロチンが轟音をたてながら次々と落とされて行く映像が流れる。そのシーンで、舞台が外界から遮断された異世界に転換した気分になる。
その異世界は、ブリキの湯たんぽが山ほどぶら下がっている「ブリキ加工店」だ。奇抜な設定に期待が高まる。そこに店主の風間杜夫が大きなブリキ板を頭上に抱えて登場する。この店主、まだらボケで、午後6時になると詩人・伊藤静雄(伊東ではない)に変身する。風間杜夫の怪演が快調である。
風間杜夫が唐作品に出演するのは 『唐版 風の又三郎』(シアターコクーン)、 『ベンガルの虎』(新宿梁山泊)に続いて3作目だそうだ。本人は「齢72にしてアングラデビュー」と語っているが、水を得た魚のような存在感がある。齢を重ねて怖いものがなくなるパワーだろうか。同世代として頼もしい限りである。
唐十郎の世界は脈略が錯綜し、さまざまなモノやイメージが乱舞する。今回は伊東静雄、島尾敏雄、天草四郎、かくれキリシタン、人間魚雷、ガラスの義眼、さくら貝の鱗、ブリキの鱗……などなどである。そして、宮沢りえの人魚姿へと収斂していく。
うかつにも私は知らなかったが、宮沢りえはこれまでに数多くの唐作品に出演してきたそうだ。すでに女座長のような風格が出ている。頼もしい限りである。
大劇場のシートに身をうずめ、文化功労者・唐十郎の芝居を重鎮や若手が大舞台で演ずる姿を観ていて、半世紀以上昔のギューギュー詰め紅テントの観客には想像できなかった未来だと思った。21世紀になって、くり返し上演される唐作品は、すでの伝統芸能のようでもある。
イブン・バットゥータは中国に行ったか? ― 2021年12月19日
14世紀の大旅行家イブン・バットゥータは、生地モロッコを旅立ち、中東、中央アジア、インド、中国などを訪れ、帰国後さらにサハラ砂漠を縦断してマーッリー王国にまで行った。その旅行記は貴重な史料で、高校世界史の教科書にも載っている。
私がこの人を知ったのは数年前である。私の高校時代(半世紀以上昔)の教科書に載っていたかどうかは不明だ。そのバットゥータに関する次の新書を読んだ。
『イブン・バットゥータの世界大旅行:14世紀イスラームの時空を生きる』(家島彦一/平凡社新書)
イブン・バットゥータの『大旅行記』は日本語に翻訳すると400字詰原稿用紙3000枚の大部なもので、従来は抄訳で紹介されていた。著者の家島彦一氏はその全訳(東洋文庫の『大旅行記』全8巻)を2002年に刊行した研究者である。
全訳刊行の翌年に出た本書は大旅行の概要を紹介すると同時に、14世紀の国際交易ネットワークを解説している。大旅行を可能にした背景がよくわかる。
13・14世紀はモンゴルが陸と海の世界帝国を築いた時代であり、イスラムが世界に拡大した時代でもある。メッカへの巡礼路が整備され、イスラム商人が地中海からインド洋、東シナ海に及ぶ海域で活躍する時代だった。
イブン・バットゥータは21歳のとき(1326年)モロッコを出発、中東、中央アジア、インド、中国を巡り、帰郷したときには46歳だった。その後、ジブラルタル海峡を渡ってグラナダを訪問、さらにサハラ砂漠縦断の旅に出発し、2年後に帰還する。
旅の目的は一義的にはメッカ巡礼であり、各地のイスラムの聖者や学者を訪ねて教えを乞うことだった。彼は法学者でもあり、インド旅行の目的は仕官だった。デリーには8年間滞在し、法官職を務めている。とはいえ、基本的には好奇心旺盛な旅行好きだったと思われる。
本書だけでは細かいことは不明だが、彼には旅が生活だっったようだ。旅の過程で何人かの妻を得ているし、何人かかの子供も生まれている。同道したケースも各地に滞在させたケースもあるようだが、よくわからない。危険な目には何度も遭遇している。
イブン・バットゥータの『大旅行記』は自筆ではない。彼の大旅行に興味をもったスルタンが文学者イブン・ジュザイイに命じて口述筆記させたものである。旅行終えた後に過去数十年の記憶を語ったものだから、記憶違いや話を盛った可能性もあるようだ。筆記した文学者も既存の各種旅行記を参照して記述を装飾しているらしい。
そんな事情もあり、彼がインドまで行ったのは確かだが、その先の中国は怪しいと見る研究者が少なくないそうだ。著者の家長氏も中国には行っていないと推定している。とは言え、中国の様子を報告できる資料がこの時代には存在していたのである。
山川出版社の教科書『世界史B』(2019年)を見ると、イブン・バットゥータの訪れた都市名・地名(中国を含む)を羅列した箇所に、小活字の註で「実際にベンガル以東を訪れたかどうかは不明」とあった。
私がこの人を知ったのは数年前である。私の高校時代(半世紀以上昔)の教科書に載っていたかどうかは不明だ。そのバットゥータに関する次の新書を読んだ。
『イブン・バットゥータの世界大旅行:14世紀イスラームの時空を生きる』(家島彦一/平凡社新書)
イブン・バットゥータの『大旅行記』は日本語に翻訳すると400字詰原稿用紙3000枚の大部なもので、従来は抄訳で紹介されていた。著者の家島彦一氏はその全訳(東洋文庫の『大旅行記』全8巻)を2002年に刊行した研究者である。
全訳刊行の翌年に出た本書は大旅行の概要を紹介すると同時に、14世紀の国際交易ネットワークを解説している。大旅行を可能にした背景がよくわかる。
13・14世紀はモンゴルが陸と海の世界帝国を築いた時代であり、イスラムが世界に拡大した時代でもある。メッカへの巡礼路が整備され、イスラム商人が地中海からインド洋、東シナ海に及ぶ海域で活躍する時代だった。
イブン・バットゥータは21歳のとき(1326年)モロッコを出発、中東、中央アジア、インド、中国を巡り、帰郷したときには46歳だった。その後、ジブラルタル海峡を渡ってグラナダを訪問、さらにサハラ砂漠縦断の旅に出発し、2年後に帰還する。
旅の目的は一義的にはメッカ巡礼であり、各地のイスラムの聖者や学者を訪ねて教えを乞うことだった。彼は法学者でもあり、インド旅行の目的は仕官だった。デリーには8年間滞在し、法官職を務めている。とはいえ、基本的には好奇心旺盛な旅行好きだったと思われる。
本書だけでは細かいことは不明だが、彼には旅が生活だっったようだ。旅の過程で何人かの妻を得ているし、何人かかの子供も生まれている。同道したケースも各地に滞在させたケースもあるようだが、よくわからない。危険な目には何度も遭遇している。
イブン・バットゥータの『大旅行記』は自筆ではない。彼の大旅行に興味をもったスルタンが文学者イブン・ジュザイイに命じて口述筆記させたものである。旅行終えた後に過去数十年の記憶を語ったものだから、記憶違いや話を盛った可能性もあるようだ。筆記した文学者も既存の各種旅行記を参照して記述を装飾しているらしい。
そんな事情もあり、彼がインドまで行ったのは確かだが、その先の中国は怪しいと見る研究者が少なくないそうだ。著者の家長氏も中国には行っていないと推定している。とは言え、中国の様子を報告できる資料がこの時代には存在していたのである。
山川出版社の教科書『世界史B』(2019年)を見ると、イブン・バットゥータの訪れた都市名・地名(中国を含む)を羅列した箇所に、小活字の註で「実際にベンガル以東を訪れたかどうかは不明」とあった。
マグリブの巡礼紀行文学(リフラ)研究を紹介した小冊子 ― 2021年12月20日
『イブン・バットゥータの世界大旅行』(平凡社新書)に続いて同じ著者の次の小冊子を読んだ。
『イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ:イスラーム世界の交通と旅』(家島彦一/世界史リブレット人/山川出版社)
復習気分で読みはじめたが、想定した以上に歯ごたえのある専門的な内容だった。この冊子はイブン・ジュバイルとイブン・バットゥータの人物像や旅行の概説書ではなく、サブタイトルの「イスラーム世界の交通と旅」が主テーマである。
メッカ巡礼が重要だったイスラーム世界では、巡礼の旅に関する情報を記録した旅行記「リフラ(巡礼紀行文学)」が多く書かれた。イブン・バットゥータの『大旅行記』もリフラの一つである。
代表的なリフラは、イブン・バットゥータより180年前に生れたイブン・ジュバイルの『メッカ巡礼記』で、リフラの手本とされてきた。イブン・バットゥータもイブン・ジュバイルのリフラ持参で旅行し、その『大旅行記』にはイブン・ジュバイルからの引用が多いそうだ。
著者はリフラの研究家で、12世紀後半から19世紀末までに書かれた64種類のリフラの変遷を比較・検討・分析している。門外漢には少し遠い世界である。
マグリブとマシュリクの違いの解説は興味深かった。エジプトより西の北アフリカ地中海岸の一帯をマグリブ(西方)と呼ぶと知ったのは、一昨年チュニジア旅行をした頃だった。エジプトより東はマシュリク(東方)である。こんな呼び方があるのは、二つの地域の間に何らかの違いがあるからだろうが、あまり深く考えなかった。
本書を読んで、マグリブの人のマシュリクに対する複雑な思いの一端を知った。イブン・ジュバイルもイブン・バットゥータもマグリブの人であり、リフラはマグリブ人たちによるメッカ巡礼記として特殊な発展をとげたそうだ。アレクサンドリアやメッカのあるマシュリクはマグリブ人にとっては先進的な理想郷だった。しかし、マグリブの巡礼者が実見したマシュリクは政治・社会・文化の堕落したイスラームの姿だった。そして、本来の正しいイスラムームはマグリブにしかない、というマグリブ人意識が高揚したらしい。面白い話である。
著者は本書で、イブン・バットゥータが中国に行ってないかもしれないとは述べていない。少し不思議である。ただし、神秘主義に傾いたイブン・バットゥータを次のよう描いている。
「(…)得意満面に弁をふるっているうちに、彼自らが旅した実地体験の記憶と、他人から伝え聞いた情報がいりまじり、しだいに現実と空想の世界とが混然一体となって、彼の旅行談は誇大化していったのであり、それは旅人としての彼の心象や思考が吐露したものとであると考えられるのである。」
『イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ:イスラーム世界の交通と旅』(家島彦一/世界史リブレット人/山川出版社)
復習気分で読みはじめたが、想定した以上に歯ごたえのある専門的な内容だった。この冊子はイブン・ジュバイルとイブン・バットゥータの人物像や旅行の概説書ではなく、サブタイトルの「イスラーム世界の交通と旅」が主テーマである。
メッカ巡礼が重要だったイスラーム世界では、巡礼の旅に関する情報を記録した旅行記「リフラ(巡礼紀行文学)」が多く書かれた。イブン・バットゥータの『大旅行記』もリフラの一つである。
代表的なリフラは、イブン・バットゥータより180年前に生れたイブン・ジュバイルの『メッカ巡礼記』で、リフラの手本とされてきた。イブン・バットゥータもイブン・ジュバイルのリフラ持参で旅行し、その『大旅行記』にはイブン・ジュバイルからの引用が多いそうだ。
著者はリフラの研究家で、12世紀後半から19世紀末までに書かれた64種類のリフラの変遷を比較・検討・分析している。門外漢には少し遠い世界である。
マグリブとマシュリクの違いの解説は興味深かった。エジプトより西の北アフリカ地中海岸の一帯をマグリブ(西方)と呼ぶと知ったのは、一昨年チュニジア旅行をした頃だった。エジプトより東はマシュリク(東方)である。こんな呼び方があるのは、二つの地域の間に何らかの違いがあるからだろうが、あまり深く考えなかった。
本書を読んで、マグリブの人のマシュリクに対する複雑な思いの一端を知った。イブン・ジュバイルもイブン・バットゥータもマグリブの人であり、リフラはマグリブ人たちによるメッカ巡礼記として特殊な発展をとげたそうだ。アレクサンドリアやメッカのあるマシュリクはマグリブ人にとっては先進的な理想郷だった。しかし、マグリブの巡礼者が実見したマシュリクは政治・社会・文化の堕落したイスラームの姿だった。そして、本来の正しいイスラムームはマグリブにしかない、というマグリブ人意識が高揚したらしい。面白い話である。
著者は本書で、イブン・バットゥータが中国に行ってないかもしれないとは述べていない。少し不思議である。ただし、神秘主義に傾いたイブン・バットゥータを次のよう描いている。
「(…)得意満面に弁をふるっているうちに、彼自らが旅した実地体験の記憶と、他人から伝え聞いた情報がいりまじり、しだいに現実と空想の世界とが混然一体となって、彼の旅行談は誇大化していったのであり、それは旅人としての彼の心象や思考が吐露したものとであると考えられるのである。」
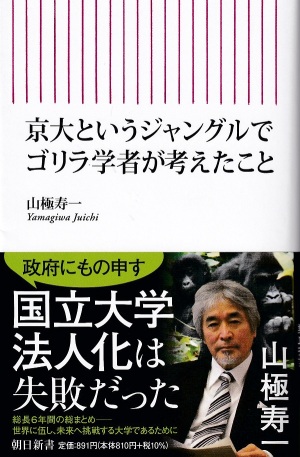


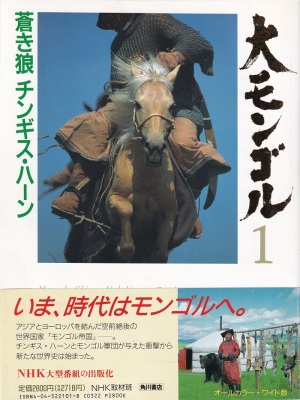
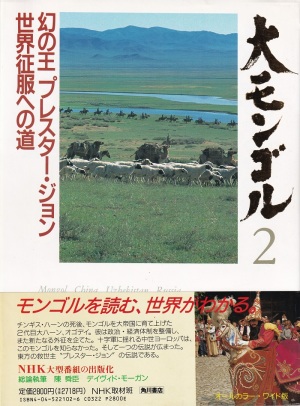
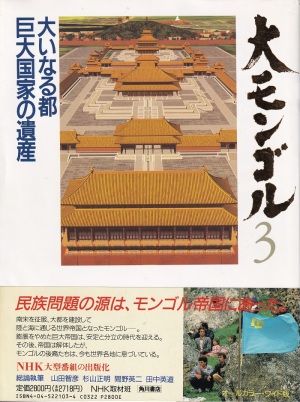




最近のコメント