『多神教と一神教』『ローマ人の愛と性』をセット読み ― 2019年02月25日
◎古代人の心性に着目した社会史
歴史学者・本村凌二氏の次の新書を続けて読んだ。
『多神教と一神教:古代地中海世界の宗教ドラマ』(本村凌二/岩波新書)
『ローマ人の愛と性』(本村凌二/講談社現代新書)
『多神教と一神教』は2005年、『ローマ人の愛と性』は1999年の刊行で、この2冊のテーマは絡み合っていてワンセットの論考として読める。ローマ帝国やミスラ教などに多少の関心のある私にはとても面白い内容だった。蒙を啓かれた。
どちらも社会史的アプローチで古代の人々の心性の変遷をさぐっている。前者は文明発生の紀元前3000年代から2世紀のローマ帝政期までの地中海世界、後者は時間と地域を狭めて紀元前1世紀半ばから2世紀半ばまでの約200年のローマの社会を対象にしている(書かれたのは後者が先)。
◎多神教から一神教への移行は必然か?
著者の見解を大雑把に言えば、文明発生期の社会は森羅万象の背後に神を見出す多神教の社会であったが、時代が進むに従って神々の習合(宗教融合:シンクレティズム)なども起こり、やがて一神教が発生し、個人の救済に関わる一神教の浸透によって多神教の社会は一神教の社会へと変異したということである。
パクス・ロマーナを現出させたローマ帝国は寛容な多神教の社会だったが、不寛容な一神教であるキリスト教の浸透とともにローマ帝国は衰退した --- 私にはそんな認識があった。しかし、歴史はそう単純に把握できるものではなさそうだ。
本書を読んでいると、一神教の浸透は文明の発展にともなう必然の流れに見えてくる。アルファベットという簡略化された文字の使用を一神教の浸透に関連付ける考察には驚き、感心した。
著者は人類の心性の変化が一神教を生み出すメカニズムを説いているだけで、一神教が優れていると主張しているのではない。一神教に問題があるのは確かだ。やっかいなことである。
◎馬鹿な歴史家もどき??
この2冊のあとがきが面白い。
『多神教と一神教』の「あとがき」で著者は自身を「ローマ帝国の社会史を研究する者の一人」としたうえで、次のように述べている。
「地中海世界の古層といえるシュメール人から古代末期にいたる筋道を描くなどとは、専門研究者なら馬鹿としか思えないだろう。でも、馬鹿の一人になってもいいかという気分で書いたつもりである。それでも、決して余興ではなく、本気でやったつもりである。」
『ローマ人の愛と性』の「あとがき」では、著者は小説家と歴史家の違いを述べた塩野七生氏の言説を紹介して塩野七生氏を「ローマの天下国家を描く歴史家のごとき作家」としたうえで、次のように述べている。
「でも、天下国家を論じることが苦手な作家のごとき歴史家もいます。さしずめ私はそんな類の歴史家でしょう。というよりも、歴史家もどきといったほうがいいかもしれません。」
本村凌二氏の魅力が伝わってくる。
歴史学者・本村凌二氏の次の新書を続けて読んだ。
『多神教と一神教:古代地中海世界の宗教ドラマ』(本村凌二/岩波新書)
『ローマ人の愛と性』(本村凌二/講談社現代新書)
『多神教と一神教』は2005年、『ローマ人の愛と性』は1999年の刊行で、この2冊のテーマは絡み合っていてワンセットの論考として読める。ローマ帝国やミスラ教などに多少の関心のある私にはとても面白い内容だった。蒙を啓かれた。
どちらも社会史的アプローチで古代の人々の心性の変遷をさぐっている。前者は文明発生の紀元前3000年代から2世紀のローマ帝政期までの地中海世界、後者は時間と地域を狭めて紀元前1世紀半ばから2世紀半ばまでの約200年のローマの社会を対象にしている(書かれたのは後者が先)。
◎多神教から一神教への移行は必然か?
著者の見解を大雑把に言えば、文明発生期の社会は森羅万象の背後に神を見出す多神教の社会であったが、時代が進むに従って神々の習合(宗教融合:シンクレティズム)なども起こり、やがて一神教が発生し、個人の救済に関わる一神教の浸透によって多神教の社会は一神教の社会へと変異したということである。
パクス・ロマーナを現出させたローマ帝国は寛容な多神教の社会だったが、不寛容な一神教であるキリスト教の浸透とともにローマ帝国は衰退した --- 私にはそんな認識があった。しかし、歴史はそう単純に把握できるものではなさそうだ。
本書を読んでいると、一神教の浸透は文明の発展にともなう必然の流れに見えてくる。アルファベットという簡略化された文字の使用を一神教の浸透に関連付ける考察には驚き、感心した。
著者は人類の心性の変化が一神教を生み出すメカニズムを説いているだけで、一神教が優れていると主張しているのではない。一神教に問題があるのは確かだ。やっかいなことである。
◎馬鹿な歴史家もどき??
この2冊のあとがきが面白い。
『多神教と一神教』の「あとがき」で著者は自身を「ローマ帝国の社会史を研究する者の一人」としたうえで、次のように述べている。
「地中海世界の古層といえるシュメール人から古代末期にいたる筋道を描くなどとは、専門研究者なら馬鹿としか思えないだろう。でも、馬鹿の一人になってもいいかという気分で書いたつもりである。それでも、決して余興ではなく、本気でやったつもりである。」
『ローマ人の愛と性』の「あとがき」では、著者は小説家と歴史家の違いを述べた塩野七生氏の言説を紹介して塩野七生氏を「ローマの天下国家を描く歴史家のごとき作家」としたうえで、次のように述べている。
「でも、天下国家を論じることが苦手な作家のごとき歴史家もいます。さしずめ私はそんな類の歴史家でしょう。というよりも、歴史家もどきといったほうがいいかもしれません。」
本村凌二氏の魅力が伝わってくる。
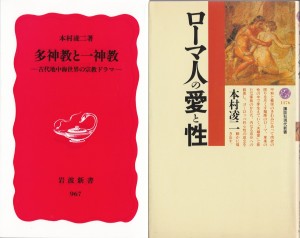
最近のコメント