時空一望の野望を抱きたくなる『全世界史』 ― 2019年02月01日
◎気宇壮大な「全世界史」概念
ビジネスマンから大学学長に転じた出口治明氏が著した世界史の概説書を読んだ。
『全世界史(上)(下)』出口治明/新潮文庫
『「全世界史」講義』という表題で2016年に刊行された単行本の文庫版(2018/7)だが、「全世界史」とは気宇壮大なタイトルである。著者は歴史学者ではない。大学には世界史学科はなく専門の研究者もいない。一人の学者が読みこめる史料の限界からおのずと研究領域が限定されると聞いたことがある。
地球上のすべての地域で発生した有史以来のあらゆる出来事を知り、それを整理解釈するのが困難だとはだれでもわかる。だが、歴史を知らずに自分たちが生きている社会を把握することはできない。
私は高校時代には「世界史」が苦手だった。年を経て、自分の興味のある分野(「ナチ・ドイツ史」「古代ローマ史」など)の本は多少読んできたが、つまみ食いの知識はイビツで、頭の中に明快な世界史をイメージすることはできない。だから、本書は有益で面白かった。
◎第一千年紀から第五千年紀まで
著者は文字資料が残っているおよそ五千年前から説き起こし、第一千年紀から第五千年紀までの千年単位に分けて「全世界史」を描いている。第三千年紀までが紀元前で、紀元後は第四、第五千年紀になる。千年単位という巨視的な大づかみによって歴史の見晴らしがよくなるような気分になる。
五部構成だから各部が千年紀に対応していればキレイだが、近い過去と遠い過去には精粗がある。第一部で第一、第二千年紀の2000年を描き、第五千年紀は前半・後半の500年ずつに分けて記述している。
目次は以下の通りである。この目次を眺めるだけで、時間と空間を巨視的につかむ視点が伝わってくる。
-------------------------------------------------
第一部 第一千年紀 ― 第二千年紀
第一章 文字の誕生と最初の文明
第二章 チャリオットによる軍事革命
第三章 黄河文明の登場とBC1200年のカタストロフィ
第二部 第三千年紀
第一章 世界帝国の時代
第二章 知の爆発の時代
第三部 第四千年紀
第一章 漢とローマ帝国から拓跋帝国とフランク王国へ
第二章 一神教革命の成就
第三章 ムハンマドなくしてシャルルマーニュなし
第四章 イスラムの大翻訳運動とヴァイキングの活躍
第五章 唐宋革命とイスラム帝国の分裂
第四部 第五千年紀前半
第一章 ユーラシアの温暖化と商業の隆盛
第二章 中世の春
第三章 パクス・モンゴリア
第四章 寒冷化とペストの時代
第五章 クアトロチェント
第五部 第五千年紀後半
第一章 アジアの四大帝国と宗教改革、そして新大陸の時代
第二章 アジアの四大帝国が極大化、ヨーロッパにはルイ14世が君臨
第三章 産業革命とフランス革命の世紀
第四章 ヨーロッパは初めて世界の覇権を握る
第五章 二つの世界大戦
第六章 冷戦の時代
終章 どしゃぶりの雨で始まった第六千年紀
-------------------------------------------------
◎的確でユニークなおしゃべりに蒙を啓かれる
本書カバーの紹介文には「歴史書一万冊を読んできた著者ならではの切り口で文字の誕生から混迷の現代までを縦横無尽に語る」とある。著者は幼少の頃からの活字中毒で膨大な本を読んできたと聞いたことがある。一万冊は誇張でないだろう。本書は上下2冊で約850ページなので、ざっくりと本書1ページにつき10冊以上、1行につき1冊近い書籍の裏付けがある計算になる。
確かにそんな背景が本書から伝わってくる。著者は、話したいことの十分の一も語れていないようだ。850ページは「全世界史」を語るには少なすぎる。めまぐるしく地域を変えつつも関連付けながら記述しているのが本書の特徴である。時に出来事の駆け足羅列になるが、無味乾燥ではない。
本書の面白いのは「おしゃべり部分」であり、時間と空間を見渡す的確でユニークな解説が随所にあり、蒙を啓かれる。
著者は私と同じ1948年生まれなので、中学・高校では同じような教科書を使っていたはずである。そんな高校生止まりの古い知識の修正を指摘する箇所も多く、大いに勉強になった。
◎いつか集中して再読したい
私は本書2冊を4日ほどで読み、5000年の時空間に散在するアレヤコレヤで頭がボーッとなった。そして、いつか再読したいと思った。
再読するならば、歴史地図、年表、人名表などで多少の知識整理をし、十分なウォーミングアップをしたうえで、できれば集中して1日で2冊を読了したい。そうすれば、5000年間に地球上で人類が繰り広げてきた「全世界史」を一つの明快なイメージとしてつかんだ気になれるかもしれない。
ビジネスマンから大学学長に転じた出口治明氏が著した世界史の概説書を読んだ。
『全世界史(上)(下)』出口治明/新潮文庫
『「全世界史」講義』という表題で2016年に刊行された単行本の文庫版(2018/7)だが、「全世界史」とは気宇壮大なタイトルである。著者は歴史学者ではない。大学には世界史学科はなく専門の研究者もいない。一人の学者が読みこめる史料の限界からおのずと研究領域が限定されると聞いたことがある。
地球上のすべての地域で発生した有史以来のあらゆる出来事を知り、それを整理解釈するのが困難だとはだれでもわかる。だが、歴史を知らずに自分たちが生きている社会を把握することはできない。
私は高校時代には「世界史」が苦手だった。年を経て、自分の興味のある分野(「ナチ・ドイツ史」「古代ローマ史」など)の本は多少読んできたが、つまみ食いの知識はイビツで、頭の中に明快な世界史をイメージすることはできない。だから、本書は有益で面白かった。
◎第一千年紀から第五千年紀まで
著者は文字資料が残っているおよそ五千年前から説き起こし、第一千年紀から第五千年紀までの千年単位に分けて「全世界史」を描いている。第三千年紀までが紀元前で、紀元後は第四、第五千年紀になる。千年単位という巨視的な大づかみによって歴史の見晴らしがよくなるような気分になる。
五部構成だから各部が千年紀に対応していればキレイだが、近い過去と遠い過去には精粗がある。第一部で第一、第二千年紀の2000年を描き、第五千年紀は前半・後半の500年ずつに分けて記述している。
目次は以下の通りである。この目次を眺めるだけで、時間と空間を巨視的につかむ視点が伝わってくる。
-------------------------------------------------
第一部 第一千年紀 ― 第二千年紀
第一章 文字の誕生と最初の文明
第二章 チャリオットによる軍事革命
第三章 黄河文明の登場とBC1200年のカタストロフィ
第二部 第三千年紀
第一章 世界帝国の時代
第二章 知の爆発の時代
第三部 第四千年紀
第一章 漢とローマ帝国から拓跋帝国とフランク王国へ
第二章 一神教革命の成就
第三章 ムハンマドなくしてシャルルマーニュなし
第四章 イスラムの大翻訳運動とヴァイキングの活躍
第五章 唐宋革命とイスラム帝国の分裂
第四部 第五千年紀前半
第一章 ユーラシアの温暖化と商業の隆盛
第二章 中世の春
第三章 パクス・モンゴリア
第四章 寒冷化とペストの時代
第五章 クアトロチェント
第五部 第五千年紀後半
第一章 アジアの四大帝国と宗教改革、そして新大陸の時代
第二章 アジアの四大帝国が極大化、ヨーロッパにはルイ14世が君臨
第三章 産業革命とフランス革命の世紀
第四章 ヨーロッパは初めて世界の覇権を握る
第五章 二つの世界大戦
第六章 冷戦の時代
終章 どしゃぶりの雨で始まった第六千年紀
-------------------------------------------------
◎的確でユニークなおしゃべりに蒙を啓かれる
本書カバーの紹介文には「歴史書一万冊を読んできた著者ならではの切り口で文字の誕生から混迷の現代までを縦横無尽に語る」とある。著者は幼少の頃からの活字中毒で膨大な本を読んできたと聞いたことがある。一万冊は誇張でないだろう。本書は上下2冊で約850ページなので、ざっくりと本書1ページにつき10冊以上、1行につき1冊近い書籍の裏付けがある計算になる。
確かにそんな背景が本書から伝わってくる。著者は、話したいことの十分の一も語れていないようだ。850ページは「全世界史」を語るには少なすぎる。めまぐるしく地域を変えつつも関連付けながら記述しているのが本書の特徴である。時に出来事の駆け足羅列になるが、無味乾燥ではない。
本書の面白いのは「おしゃべり部分」であり、時間と空間を見渡す的確でユニークな解説が随所にあり、蒙を啓かれる。
著者は私と同じ1948年生まれなので、中学・高校では同じような教科書を使っていたはずである。そんな高校生止まりの古い知識の修正を指摘する箇所も多く、大いに勉強になった。
◎いつか集中して再読したい
私は本書2冊を4日ほどで読み、5000年の時空間に散在するアレヤコレヤで頭がボーッとなった。そして、いつか再読したいと思った。
再読するならば、歴史地図、年表、人名表などで多少の知識整理をし、十分なウォーミングアップをしたうえで、できれば集中して1日で2冊を読了したい。そうすれば、5000年間に地球上で人類が繰り広げてきた「全世界史」を一つの明快なイメージとしてつかんだ気になれるかもしれない。
半世紀ぶりに安部公房の『榎本武揚』を再読して気づいたこと ― 2019年02月03日
この3カ月ほどで榎本武揚に関する小説や評伝を10冊ほど読んだ。私が初めて読んだ榎本関連本は安部公房の小説『榎本武揚』で、約半世紀前の学生時代だ。榎本武揚関連本を続けて読んだのを機に安部公房の小説『榎本武揚』と戯曲『榎本武揚』を再読した。
『榎本武揚』(安部公房/中央公論社)
『戯曲 友達・榎本武揚』(安部公房/河出書房新社)
私は安部公房ファンで、その著作をほとんど読んでいる。榎本武揚が気がかりな存在になったのは、安部公房の小説を読んだせいかもしれない。とは言え、『榎本武揚』は安部作品としては異色である。今回、小説と戯曲を再読して、位置づけの難しい宙ぶらりんな作品だと再確認した。
小説『榎本武揚』は評伝ではない。現代の人間が史料(その一部は作者の創作と思われる)を元に榎本武揚とは何者だったを探る少々入り組んだ構造になってる。
榎本武揚が箱館戦争に踏み切った動機は何か、明治政府高官への転身は変節か、自分の生きた時代への忠誠を裁く基準はあるのか、などを追求する内容で、作者自身はこの小説に関連して「忠誠でもなく、裏切りでもない、第三の道というものはありえないのだろうか」と語っている。
そんな作者の意図に沿って考察するなら、変遷する時代の風圧にさらされる個人の生き方を素材に転向論を追求した小説ということになり、戦後日本の知識人の思想と行動の軌跡の幾ばくかが反映されているようにも思えてくる。
だが、そんな図解的な読み方はつまらない。その図解からはみ出る部分にこの小説の面白さがあると思える。単純に言えば、安部公房が榎本武揚のどこに魅かれているかを読み解ければいいのである。
また、再読で気づいたのだが、小説『榎本武揚』もまた失踪小説である。失踪する福地旅館の主人は『砂の女』の主人公に重なる。さらに言えば、榎本武揚も「内なる辺境」に亡命した失踪者の一人にも思えてくる。
『榎本武揚』(安部公房/中央公論社)
『戯曲 友達・榎本武揚』(安部公房/河出書房新社)
私は安部公房ファンで、その著作をほとんど読んでいる。榎本武揚が気がかりな存在になったのは、安部公房の小説を読んだせいかもしれない。とは言え、『榎本武揚』は安部作品としては異色である。今回、小説と戯曲を再読して、位置づけの難しい宙ぶらりんな作品だと再確認した。
小説『榎本武揚』は評伝ではない。現代の人間が史料(その一部は作者の創作と思われる)を元に榎本武揚とは何者だったを探る少々入り組んだ構造になってる。
榎本武揚が箱館戦争に踏み切った動機は何か、明治政府高官への転身は変節か、自分の生きた時代への忠誠を裁く基準はあるのか、などを追求する内容で、作者自身はこの小説に関連して「忠誠でもなく、裏切りでもない、第三の道というものはありえないのだろうか」と語っている。
そんな作者の意図に沿って考察するなら、変遷する時代の風圧にさらされる個人の生き方を素材に転向論を追求した小説ということになり、戦後日本の知識人の思想と行動の軌跡の幾ばくかが反映されているようにも思えてくる。
だが、そんな図解的な読み方はつまらない。その図解からはみ出る部分にこの小説の面白さがあると思える。単純に言えば、安部公房が榎本武揚のどこに魅かれているかを読み解ければいいのである。
また、再読で気づいたのだが、小説『榎本武揚』もまた失踪小説である。失踪する福地旅館の主人は『砂の女』の主人公に重なる。さらに言えば、榎本武揚も「内なる辺境」に亡命した失踪者の一人にも思えてくる。
『日本の近代とは何であったか』は目から鱗が落ちる本 ― 2019年02月05日
◎後半が面白い
友人から薦められて次の新書を読んだ。
『日本の近代とは何であったか:問題史的考察』(三谷太一郎/岩波新書)
学者がじっくりと書いた新書で歯ごたえがある。素人にはどうでもいいと思われるやや抽象的で退屈な解説から始まり、最初のうちは読みづらかったが途中から面白くなった。
本書は次の4つの視点で日本の近代(幕末維新以降)を論じている。
(1) なぜ日本に政党政治が成立したか
(2) なぜ日本に資本主義が形成されたか
(3) 日本はなぜ、いかにして植民地帝国となったか
(4) 日本の近代にとって天皇制とは何であったか
この4つの中の後半2つが面白かった。私にとっては新鮮で目から鱗が落ちる指摘が多かったからである。
◎植民地経営の難しさを知った
私は朝鮮や台湾が日本の植民地だった時代を体験していないが、台湾で生まれた母親から当時の「よかった時代」の様子聞をいた記憶はある。そんな話などから、朝鮮に比べて台湾の植民地経営はうまくいっていたという漠然とした印象をもったこともある。
しかし、よく考えてみれば植民地経営は生易しいものではない。ナショナリズムの胎動で植民地支配の破綻が見え始めてきた時代に、欧米から遅れて植民地支配に乗り出したのだから、日本の植民地支配には無理があったのだ。
本書によって朝鮮総督が台湾総督より上位だったことを知り、植民地における法律の制定や教育政策の困難が了解できた。また、「民族主義」を超える「地域主義」なる概念が導入されたという話は興味深かった。
植民地の時代が終わっても、あの時代に露呈した課題はグローバリズムの現代において参照すべきものが多いように思える。
◎天皇神格化と教育勅語の特殊性
私は天皇制について深く考えたことはなく、関心も薄い。江戸時代には「お飾り」に近かった天皇を明治以降に神格化したのはアホなことで、それが軍国主義を推進したと思っている。
本書によって、明治憲法による日本の立憲君主制がヨーロッパのものとかなり違うことを知った。天皇の神格化はアホな元勲によって推進されたのではなく、元から「機能」として意図されていたのである。
明治憲法の制定者はキリスト教の伝統があるヨーロッパの憲法を日本に移植するにあたって、キリスト教に替わる「国家の基軸」を天皇とした。それで天皇は「神」になってしまい、不可解な国の形につながったようだ。
本書は教育勅語制定の経緯を詳しく述べている。教育勅語が大臣の副署がない極めて特殊なものだということを本書で初めて知り、教育勅語が担った役割の大きさに驚いた。そんなに大したものとは驚きである。
いまは象徴天皇制だが、国、国民と天皇の関係は依然としてわかりにくい課題である。そんなことも本書は提示している。
友人から薦められて次の新書を読んだ。
『日本の近代とは何であったか:問題史的考察』(三谷太一郎/岩波新書)
学者がじっくりと書いた新書で歯ごたえがある。素人にはどうでもいいと思われるやや抽象的で退屈な解説から始まり、最初のうちは読みづらかったが途中から面白くなった。
本書は次の4つの視点で日本の近代(幕末維新以降)を論じている。
(1) なぜ日本に政党政治が成立したか
(2) なぜ日本に資本主義が形成されたか
(3) 日本はなぜ、いかにして植民地帝国となったか
(4) 日本の近代にとって天皇制とは何であったか
この4つの中の後半2つが面白かった。私にとっては新鮮で目から鱗が落ちる指摘が多かったからである。
◎植民地経営の難しさを知った
私は朝鮮や台湾が日本の植民地だった時代を体験していないが、台湾で生まれた母親から当時の「よかった時代」の様子聞をいた記憶はある。そんな話などから、朝鮮に比べて台湾の植民地経営はうまくいっていたという漠然とした印象をもったこともある。
しかし、よく考えてみれば植民地経営は生易しいものではない。ナショナリズムの胎動で植民地支配の破綻が見え始めてきた時代に、欧米から遅れて植民地支配に乗り出したのだから、日本の植民地支配には無理があったのだ。
本書によって朝鮮総督が台湾総督より上位だったことを知り、植民地における法律の制定や教育政策の困難が了解できた。また、「民族主義」を超える「地域主義」なる概念が導入されたという話は興味深かった。
植民地の時代が終わっても、あの時代に露呈した課題はグローバリズムの現代において参照すべきものが多いように思える。
◎天皇神格化と教育勅語の特殊性
私は天皇制について深く考えたことはなく、関心も薄い。江戸時代には「お飾り」に近かった天皇を明治以降に神格化したのはアホなことで、それが軍国主義を推進したと思っている。
本書によって、明治憲法による日本の立憲君主制がヨーロッパのものとかなり違うことを知った。天皇の神格化はアホな元勲によって推進されたのではなく、元から「機能」として意図されていたのである。
明治憲法の制定者はキリスト教の伝統があるヨーロッパの憲法を日本に移植するにあたって、キリスト教に替わる「国家の基軸」を天皇とした。それで天皇は「神」になってしまい、不可解な国の形につながったようだ。
本書は教育勅語制定の経緯を詳しく述べている。教育勅語が大臣の副署がない極めて特殊なものだということを本書で初めて知り、教育勅語が担った役割の大きさに驚いた。そんなに大したものとは驚きである。
いまは象徴天皇制だが、国、国民と天皇の関係は依然としてわかりにくい課題である。そんなことも本書は提示している。
シアターコクーンの『唐版 風の又三郎』は盛況だった ― 2019年02月10日
シアターコクーンで『唐版 風の又三郎』(演出:金守珍)を観た。最近、往年の状況劇場の芝居が上演されることが多く、つい観たくなるのは、あの「わけのわからない」芝居をもう一度観れば、多少は「わけのわからなさ」が減少するのではとのかすかな期待のせいかもしれない。だが今回の観劇で、そんな期待は無意味で、芝居は解読するものではなく体験・体感するものだと再認識した。
シアターコクーンはかなり大きな劇場だが、満席で立ち見チケットまで販売していた。若い女性の観客が多いのに驚いた。ロートルがノスタルジーで観劇しているだけではなく、若い主演俳優目当てにファンが押しかけているように思えた。
私は1974年の『唐版 風の又三郎』初演(「夢の島」「忍ばずの池」のどっちだったかは失念)を観ている。だから、この芝居を観ながら役者の背後に往年の紅テントの怪優たちを重ねてしまう。
窪田正孝(初演時は根津甚八)
柚希礼音(初演時は李礼仙)
北村有起哉(初演時は大久保鷹)
丸山智己(初演時は小林薫)
六平直政(初演時は不破万作)
風間杜夫(初演時は唐十郎)
もちろん、今回の大劇場での公演は紅テントの舞台とは演出も仕掛けも異なっている。猥雑さは減少し華麗である。美術が宇野亜喜良には驚いた。85歳で現役もすごいが、天井桟敷のイメージが強く、唐十郎世界とは無縁の人と感じていた。宇野亜喜良の甘美・妖艶な世界と唐十郎の怪しさがミックスした夢幻世界が舞台に展開しているのは新鮮である。
この「わけのわからない」華麗な舞台が、往年の紅テントを知らない若い観客たちに何を刻印したのか興味深い。解けても解けない謎々は世代を超えて繰り返し再生されていくだろうか。
シアターコクーンはかなり大きな劇場だが、満席で立ち見チケットまで販売していた。若い女性の観客が多いのに驚いた。ロートルがノスタルジーで観劇しているだけではなく、若い主演俳優目当てにファンが押しかけているように思えた。
私は1974年の『唐版 風の又三郎』初演(「夢の島」「忍ばずの池」のどっちだったかは失念)を観ている。だから、この芝居を観ながら役者の背後に往年の紅テントの怪優たちを重ねてしまう。
窪田正孝(初演時は根津甚八)
柚希礼音(初演時は李礼仙)
北村有起哉(初演時は大久保鷹)
丸山智己(初演時は小林薫)
六平直政(初演時は不破万作)
風間杜夫(初演時は唐十郎)
もちろん、今回の大劇場での公演は紅テントの舞台とは演出も仕掛けも異なっている。猥雑さは減少し華麗である。美術が宇野亜喜良には驚いた。85歳で現役もすごいが、天井桟敷のイメージが強く、唐十郎世界とは無縁の人と感じていた。宇野亜喜良の甘美・妖艶な世界と唐十郎の怪しさがミックスした夢幻世界が舞台に展開しているのは新鮮である。
この「わけのわからない」華麗な舞台が、往年の紅テントを知らない若い観客たちに何を刻印したのか興味深い。解けても解けない謎々は世代を超えて繰り返し再生されていくだろうか。
13世紀の世界連邦を描出した『クビライの挑戦』 ― 2019年02月12日
出口治明氏の『全世界史(上)(下)』(新潮文庫))をきっかけに読んだ次の本が面白かった。
『クビライの挑戦:モンゴルによる世界史の大転回』(杉山正明/講談社学術文庫)
『全世界史』の巻末には500点以上の参考文献が載っていて、たとえばその1点が「『世界の名著』中央公論社 全81巻」だったりするから冊数は膨大だ。中でも異様なのが「塩野七生 全著作」「杉山正明 全著作」である。存命の人の全著作を参考文献に挙げるのはよほどの贔屓だ。
塩野七生氏の著作(歴史小説)は何点か読んでいるので、出口氏の思いはわかる。杉山正明氏の著作を読んだことがなく、にわかにこの著者が気がかりになった。全著作は無理でも1冊ぐらいは読んでみようと思った。
杉山正明氏は1952年生まれ(私より4歳若い)の歴史学者で『クビライの挑戦:モンゴルによる世界史の大転回』は1995年の著作(そのときのサブタイトルは「モンゴル海上帝国への道」)を2010年に文庫化したものだ。
出口治明氏の『全世界史』で目から鱗だったのは、モンゴルやイスラム諸国が世界史のなかで果たした業績を大きく評価していることだった。私にとってはモヤの中のようだったモンゴルやイスラムにイメージがくっきりしてきた。
『クビライの挑戦』は、「モンゴル帝国」の実態は漢民族の怨念や西欧の無知によって歪められてきたとし、その再評価と世界史の中での正当な位置づけを迫っている。著者の気迫が伝わってくる本である。
ユーラシア大陸の大半を統治していた13世紀の「モンゴル帝国」は実は人種や宗教に寛容で、重商主義と自由経済に重点をおく通商帝国だったそうだ。さまざまな人種・言語・文化・宗教がほとんど国家から規制をうけずに併存・共生する平和で文化的な世界は、近代的とも言える「世界連邦」だったのである。
南宋を併合したモンゴルは海洋航路を開発し海上国家になりつつあった。「モンゴル帝国」が順調に発展していれば「大航海時代」は西欧ではなくアジアを起点に展開されていった可能性もあったのだ。出口氏の『全世界史』によれば「大航海時代」以前の明の鄭和の航海こそが「大航海」であり、西欧のそれは「小航海」と呼ぶ方がふさわしいそうだ。鄭和の大航海はモンゴル海上帝国の遺産をベースにしている。
そんなモンゴルによる「世界連邦」がなぜ挫折し未完に終わったのか。本書ではその点についても解説している。だが、私にとっては十分に納得できるものではなく、やはり謎である。
『クビライの挑戦:モンゴルによる世界史の大転回』(杉山正明/講談社学術文庫)
『全世界史』の巻末には500点以上の参考文献が載っていて、たとえばその1点が「『世界の名著』中央公論社 全81巻」だったりするから冊数は膨大だ。中でも異様なのが「塩野七生 全著作」「杉山正明 全著作」である。存命の人の全著作を参考文献に挙げるのはよほどの贔屓だ。
塩野七生氏の著作(歴史小説)は何点か読んでいるので、出口氏の思いはわかる。杉山正明氏の著作を読んだことがなく、にわかにこの著者が気がかりになった。全著作は無理でも1冊ぐらいは読んでみようと思った。
杉山正明氏は1952年生まれ(私より4歳若い)の歴史学者で『クビライの挑戦:モンゴルによる世界史の大転回』は1995年の著作(そのときのサブタイトルは「モンゴル海上帝国への道」)を2010年に文庫化したものだ。
出口治明氏の『全世界史』で目から鱗だったのは、モンゴルやイスラム諸国が世界史のなかで果たした業績を大きく評価していることだった。私にとってはモヤの中のようだったモンゴルやイスラムにイメージがくっきりしてきた。
『クビライの挑戦』は、「モンゴル帝国」の実態は漢民族の怨念や西欧の無知によって歪められてきたとし、その再評価と世界史の中での正当な位置づけを迫っている。著者の気迫が伝わってくる本である。
ユーラシア大陸の大半を統治していた13世紀の「モンゴル帝国」は実は人種や宗教に寛容で、重商主義と自由経済に重点をおく通商帝国だったそうだ。さまざまな人種・言語・文化・宗教がほとんど国家から規制をうけずに併存・共生する平和で文化的な世界は、近代的とも言える「世界連邦」だったのである。
南宋を併合したモンゴルは海洋航路を開発し海上国家になりつつあった。「モンゴル帝国」が順調に発展していれば「大航海時代」は西欧ではなくアジアを起点に展開されていった可能性もあったのだ。出口氏の『全世界史』によれば「大航海時代」以前の明の鄭和の航海こそが「大航海」であり、西欧のそれは「小航海」と呼ぶ方がふさわしいそうだ。鄭和の大航海はモンゴル海上帝国の遺産をベースにしている。
そんなモンゴルによる「世界連邦」がなぜ挫折し未完に終わったのか。本書ではその点についても解説している。だが、私にとっては十分に納得できるものではなく、やはり謎である。
『始祖鳥記』の空飛ぶ表具屋は、わが故郷の人だった ― 2019年02月14日
私が岡山県出身と知っている友人から次の小説を紹介された。
『始祖鳥記』(飯嶋和一/小学館文庫)
鳥人幸吉の話だという。江戸時代の岡山に羽根をつけて橋の上から飛んだ幸吉という人物がいたと子供の頃に聞いたことはある。詳しいことは知らない。筒井康隆氏に『空飛ぶ表具屋』という短編があるが、羽根をつけて橋から飛んだ男の話が長編になるのだろうかといぶかしく思いながら読み始めた。
読み始めてびっくりした。私が生まれ育った地域のマイナーな地名が次々に出てくるのだ。
私は岡山県玉野市の日比という地区で生まれ、中学卒業までそこで過ごした。玉野市は造船所と精錬所の企業城下町で、父は後者に勤務していて、わが家は社宅住まいだった。私が中学卒業の頃に父が東京に転勤になり、玉野市は遠い存在になった。
本書には八浜、宇野、日比、田井、金甲山などの地名が出てくる。いずれも私が子供の頃になれ親しんでいた玉野市内の地名である。成人してからはほとんど耳にすることがなかった地名に小説の中で遭遇し、遠い記憶が蘇る不思議な気分になった。本書の重要人物である船頭が、わが日比を拠点に活躍しているのがうれしくなり、幸吉が身近な人物に思えてきた。
飯嶋和一氏の小説はかなり以前に『出星前夜』を読んでいるが、私にはあまり馴染みのない小説家である。『始祖鳥記』は2000年に書き下ろし単行本で出たそうだ。
飯嶋氏はディティールを濃厚に書き込む作風でやや重い。細かなエピソードを重ねた分厚い織物のようでありながら、話はあちこちに飛躍する。表具屋が空を飛ぶ話が急に行徳の塩問屋の情景になり、塩の製法や流通に関する話が続いて面くらう。さらには兵庫の港に停泊している弁財船の場面に移り、鳥人幸吉はどこに行ったのだと気にかかる。
作者は悠々と輻輳した物語を展開させ、登場人物たちを絡めて、大飢饉で有名な天明から寛政の世の経済と社会を描出する。その中で「おれはこんな所でこんなことをしていていいのだろうか」という普遍的な血の騒ぎの物語を奏でている。
出生地が玉野市日比でなくても面白く読める小説である。
この小説を読み終えたとき、ふと加藤登紀子の「この空を飛べたら…」と「時代遅れの酒場」のメロディーと歌詞が浮かんだ。歌と小説のテイストはまったく違うのだが…
『始祖鳥記』(飯嶋和一/小学館文庫)
鳥人幸吉の話だという。江戸時代の岡山に羽根をつけて橋の上から飛んだ幸吉という人物がいたと子供の頃に聞いたことはある。詳しいことは知らない。筒井康隆氏に『空飛ぶ表具屋』という短編があるが、羽根をつけて橋から飛んだ男の話が長編になるのだろうかといぶかしく思いながら読み始めた。
読み始めてびっくりした。私が生まれ育った地域のマイナーな地名が次々に出てくるのだ。
私は岡山県玉野市の日比という地区で生まれ、中学卒業までそこで過ごした。玉野市は造船所と精錬所の企業城下町で、父は後者に勤務していて、わが家は社宅住まいだった。私が中学卒業の頃に父が東京に転勤になり、玉野市は遠い存在になった。
本書には八浜、宇野、日比、田井、金甲山などの地名が出てくる。いずれも私が子供の頃になれ親しんでいた玉野市内の地名である。成人してからはほとんど耳にすることがなかった地名に小説の中で遭遇し、遠い記憶が蘇る不思議な気分になった。本書の重要人物である船頭が、わが日比を拠点に活躍しているのがうれしくなり、幸吉が身近な人物に思えてきた。
飯嶋和一氏の小説はかなり以前に『出星前夜』を読んでいるが、私にはあまり馴染みのない小説家である。『始祖鳥記』は2000年に書き下ろし単行本で出たそうだ。
飯嶋氏はディティールを濃厚に書き込む作風でやや重い。細かなエピソードを重ねた分厚い織物のようでありながら、話はあちこちに飛躍する。表具屋が空を飛ぶ話が急に行徳の塩問屋の情景になり、塩の製法や流通に関する話が続いて面くらう。さらには兵庫の港に停泊している弁財船の場面に移り、鳥人幸吉はどこに行ったのだと気にかかる。
作者は悠々と輻輳した物語を展開させ、登場人物たちを絡めて、大飢饉で有名な天明から寛政の世の経済と社会を描出する。その中で「おれはこんな所でこんなことをしていていいのだろうか」という普遍的な血の騒ぎの物語を奏でている。
出生地が玉野市日比でなくても面白く読める小説である。
この小説を読み終えたとき、ふと加藤登紀子の「この空を飛べたら…」と「時代遅れの酒場」のメロディーと歌詞が浮かんだ。歌と小説のテイストはまったく違うのだが…
『峠の群像』は「忠臣蔵」を相対化した忠臣蔵 ― 2019年02月20日
◎塩田つながりで手を出した
堺屋太一氏の告別式を報じるTVニュースを観ていて、本棚の奥で未読のまま眠っている『峠の群像』を思い出し、つい読み始めて、全3巻を一気に読んでしまった。予感していた以上に面白かった。
『峠の群像(上)(中)(下)』(堺屋太一/日本放送出版協会)
『峠の群像』は忠臣蔵の物語で1982年(37年前!)のNHK大河ドラマの原作である。私はこのドラマを見ていない。松の廊下の刃傷の原因を製塩業をめぐる確執としていると聞いたことはあった。
「松の廊下の刃傷は原因不明」が歴史学者の共通認識のようだが、製塩が刃傷の原因にはなり得ないという見解(赤穂と吉良の製塩は競合しない)を読んで納得したことがある。そんなこともあり『峠の群像』に食指が動かなかった。
それを読む気になったのは、つい最近読んだ『始祖鳥記』(飯嶋和一)で江戸時代の製塩業の世界に接し、塩田つながりで頭のアンテナが反応したのかもしれない。
◎元禄の転換期を描出した経済小説
『始祖鳥記』の舞台でもある岡山県の塩田は私の原風景のひとつである。私が小学校(玉野市の第二日比小学校)に入学した頃(1954年)、校庭の先は入浜式の塩田だった。それが流下式の塩田に替わり、いつの間にか塩田はなくなり埋め立て地になった。「入浜式」から「硫下式」への外形的な変化は子供の目に印象的だった。
だから『峠の群像』で次の記述に出会って、遠い昔の風景がよみがえった。
「入浜塩田の最初のものは、正保三年浅野長直によって造成された赤穂御崎新浜であったとされている。(…)それ以降三百年間、昭和二十年代末に流下式が普及するまで日本の塩田は基本的に変わっていない。」
『峠の群像』は忠臣蔵物語ではあるが、製塩業に焦点をあてた江戸経済小説でもある。
全3巻の小説で、松の廊下の刃傷が発生するのは3巻目になってからで、1、2巻では松の廊下に至る8年間の元禄の社会を政治と経済の目で描いている。芭蕉、其角、近松門左衛門なども登場する。江戸と赤穂だけでなく大阪も主要な舞台になっている。
幕藩体制の基本である米の経済が崩れ、藩の財政は悪化し、困窮する武士が増加する一方で、貨幣経済への移行・商業景気によって富裕な商人が台頭してくる。そんな転換期の社会を多様な登場人物によって描き出している。
◎クライマックスを盛り上げない忠臣蔵
この小説では吉良上野介も大野九郎兵衛も悪意の人物ではなく、それぞれが自分が正しいと思う行動をしている。塩田に関する話が大きなウエイトを占めているが、刃傷の原因を製塩に関する競合とはしていない。思惑のすれ違いや誤解のエスカレートが刃傷という悲劇を招いたという話にしている。
元来、忠臣蔵物語の面白さは「刃傷」「討ち入り」という二つのクライマックスに話を盛り上げていくところにあるが、この小説はそういう構造にはなっていない。
「刃傷」や「討ち入り」を坦々と描いている。それでも面白いのは、商人や劇作家(近松)を含めた多様な視点を取り入れたうえで、作者が時代を俯瞰しているからである。
◎「不義士」たちの運命
また、この小説の面白さは、討ち入りに参加しなかった「不義士」たちの運命を描くことによって「忠臣蔵」を相対化している点にもある。井上ひさしの『不忠臣蔵』に通じる苦さでもあるが、産業振興にまい進して失業武士の救済を図ったテクノクラートが「不義士」として斥けられる皮肉は堺屋太一氏ならではだ。
忠臣蔵とは歴史上の事件をタネに際限なく膨れ上がる共同幻想の世界であり、それをどう摑まえるかは千差万別で、そこに忠臣蔵の面白さがある。
堺屋太一氏の告別式を報じるTVニュースを観ていて、本棚の奥で未読のまま眠っている『峠の群像』を思い出し、つい読み始めて、全3巻を一気に読んでしまった。予感していた以上に面白かった。
『峠の群像(上)(中)(下)』(堺屋太一/日本放送出版協会)
『峠の群像』は忠臣蔵の物語で1982年(37年前!)のNHK大河ドラマの原作である。私はこのドラマを見ていない。松の廊下の刃傷の原因を製塩業をめぐる確執としていると聞いたことはあった。
「松の廊下の刃傷は原因不明」が歴史学者の共通認識のようだが、製塩が刃傷の原因にはなり得ないという見解(赤穂と吉良の製塩は競合しない)を読んで納得したことがある。そんなこともあり『峠の群像』に食指が動かなかった。
それを読む気になったのは、つい最近読んだ『始祖鳥記』(飯嶋和一)で江戸時代の製塩業の世界に接し、塩田つながりで頭のアンテナが反応したのかもしれない。
◎元禄の転換期を描出した経済小説
『始祖鳥記』の舞台でもある岡山県の塩田は私の原風景のひとつである。私が小学校(玉野市の第二日比小学校)に入学した頃(1954年)、校庭の先は入浜式の塩田だった。それが流下式の塩田に替わり、いつの間にか塩田はなくなり埋め立て地になった。「入浜式」から「硫下式」への外形的な変化は子供の目に印象的だった。
だから『峠の群像』で次の記述に出会って、遠い昔の風景がよみがえった。
「入浜塩田の最初のものは、正保三年浅野長直によって造成された赤穂御崎新浜であったとされている。(…)それ以降三百年間、昭和二十年代末に流下式が普及するまで日本の塩田は基本的に変わっていない。」
『峠の群像』は忠臣蔵物語ではあるが、製塩業に焦点をあてた江戸経済小説でもある。
全3巻の小説で、松の廊下の刃傷が発生するのは3巻目になってからで、1、2巻では松の廊下に至る8年間の元禄の社会を政治と経済の目で描いている。芭蕉、其角、近松門左衛門なども登場する。江戸と赤穂だけでなく大阪も主要な舞台になっている。
幕藩体制の基本である米の経済が崩れ、藩の財政は悪化し、困窮する武士が増加する一方で、貨幣経済への移行・商業景気によって富裕な商人が台頭してくる。そんな転換期の社会を多様な登場人物によって描き出している。
◎クライマックスを盛り上げない忠臣蔵
この小説では吉良上野介も大野九郎兵衛も悪意の人物ではなく、それぞれが自分が正しいと思う行動をしている。塩田に関する話が大きなウエイトを占めているが、刃傷の原因を製塩に関する競合とはしていない。思惑のすれ違いや誤解のエスカレートが刃傷という悲劇を招いたという話にしている。
元来、忠臣蔵物語の面白さは「刃傷」「討ち入り」という二つのクライマックスに話を盛り上げていくところにあるが、この小説はそういう構造にはなっていない。
「刃傷」や「討ち入り」を坦々と描いている。それでも面白いのは、商人や劇作家(近松)を含めた多様な視点を取り入れたうえで、作者が時代を俯瞰しているからである。
◎「不義士」たちの運命
また、この小説の面白さは、討ち入りに参加しなかった「不義士」たちの運命を描くことによって「忠臣蔵」を相対化している点にもある。井上ひさしの『不忠臣蔵』に通じる苦さでもあるが、産業振興にまい進して失業武士の救済を図ったテクノクラートが「不義士」として斥けられる皮肉は堺屋太一氏ならではだ。
忠臣蔵とは歴史上の事件をタネに際限なく膨れ上がる共同幻想の世界であり、それをどう摑まえるかは千差万別で、そこに忠臣蔵の面白さがある。
歌舞伎では生首は日常的な小道具 ― 2019年02月23日
二月大歌舞伎の昼の部・夜の部を通しで観た。演目は以下の通り。
昼の部
(1)義経千本桜・すし屋
(2)暗闇の丑松
(3)団子売
夜の部
(1)熊谷陣屋
(2)富年祝春駒
(3)名月八幡祭
メインディッシュは定番の「義経千本桜・すし屋」(いがみの権太:松緑)と「熊谷陣屋」(熊谷次郎直実・吉右衛門)で、いかにも歌舞伎だなあという気分で鑑賞した。両方とも生首が大きな役割を果たしている。生首を小道具として日常的に扱う歌舞伎は、やはりヘンテコな芝居かもしれない。
舞踊演目には少し退屈することもあるが、今回の「団子売」と「富年祝春駒」はどちらも祝祭的な華やかさを堪能できて面白かった。
二月大歌舞伎は33年前に40歳で亡くなった尾上辰之助の追善狂言で、息子の松緑、孫の左近が出演している。私は尾上辰之助の舞台を観たことはない。
「名月八幡祭」は、かつて尾上辰之助が孝夫(現・仁左衛門)、玉三郎と共演したものを三十数年ぶりに仁左衛門、玉三郎は同役、辰之助に替わって松緑で演じたものだそうだ。昔の舞台は知らないが、仁左衛門、玉三郎には三十数年前を彷彿させる色気があり、年齢を超越する歌舞伎役者の凄さを再認識した。
昼の部
(1)義経千本桜・すし屋
(2)暗闇の丑松
(3)団子売
夜の部
(1)熊谷陣屋
(2)富年祝春駒
(3)名月八幡祭
メインディッシュは定番の「義経千本桜・すし屋」(いがみの権太:松緑)と「熊谷陣屋」(熊谷次郎直実・吉右衛門)で、いかにも歌舞伎だなあという気分で鑑賞した。両方とも生首が大きな役割を果たしている。生首を小道具として日常的に扱う歌舞伎は、やはりヘンテコな芝居かもしれない。
舞踊演目には少し退屈することもあるが、今回の「団子売」と「富年祝春駒」はどちらも祝祭的な華やかさを堪能できて面白かった。
二月大歌舞伎は33年前に40歳で亡くなった尾上辰之助の追善狂言で、息子の松緑、孫の左近が出演している。私は尾上辰之助の舞台を観たことはない。
「名月八幡祭」は、かつて尾上辰之助が孝夫(現・仁左衛門)、玉三郎と共演したものを三十数年ぶりに仁左衛門、玉三郎は同役、辰之助に替わって松緑で演じたものだそうだ。昔の舞台は知らないが、仁左衛門、玉三郎には三十数年前を彷彿させる色気があり、年齢を超越する歌舞伎役者の凄さを再認識した。
『多神教と一神教』『ローマ人の愛と性』をセット読み ― 2019年02月25日
◎古代人の心性に着目した社会史
歴史学者・本村凌二氏の次の新書を続けて読んだ。
『多神教と一神教:古代地中海世界の宗教ドラマ』(本村凌二/岩波新書)
『ローマ人の愛と性』(本村凌二/講談社現代新書)
『多神教と一神教』は2005年、『ローマ人の愛と性』は1999年の刊行で、この2冊のテーマは絡み合っていてワンセットの論考として読める。ローマ帝国やミスラ教などに多少の関心のある私にはとても面白い内容だった。蒙を啓かれた。
どちらも社会史的アプローチで古代の人々の心性の変遷をさぐっている。前者は文明発生の紀元前3000年代から2世紀のローマ帝政期までの地中海世界、後者は時間と地域を狭めて紀元前1世紀半ばから2世紀半ばまでの約200年のローマの社会を対象にしている(書かれたのは後者が先)。
◎多神教から一神教への移行は必然か?
著者の見解を大雑把に言えば、文明発生期の社会は森羅万象の背後に神を見出す多神教の社会であったが、時代が進むに従って神々の習合(宗教融合:シンクレティズム)なども起こり、やがて一神教が発生し、個人の救済に関わる一神教の浸透によって多神教の社会は一神教の社会へと変異したということである。
パクス・ロマーナを現出させたローマ帝国は寛容な多神教の社会だったが、不寛容な一神教であるキリスト教の浸透とともにローマ帝国は衰退した --- 私にはそんな認識があった。しかし、歴史はそう単純に把握できるものではなさそうだ。
本書を読んでいると、一神教の浸透は文明の発展にともなう必然の流れに見えてくる。アルファベットという簡略化された文字の使用を一神教の浸透に関連付ける考察には驚き、感心した。
著者は人類の心性の変化が一神教を生み出すメカニズムを説いているだけで、一神教が優れていると主張しているのではない。一神教に問題があるのは確かだ。やっかいなことである。
◎馬鹿な歴史家もどき??
この2冊のあとがきが面白い。
『多神教と一神教』の「あとがき」で著者は自身を「ローマ帝国の社会史を研究する者の一人」としたうえで、次のように述べている。
「地中海世界の古層といえるシュメール人から古代末期にいたる筋道を描くなどとは、専門研究者なら馬鹿としか思えないだろう。でも、馬鹿の一人になってもいいかという気分で書いたつもりである。それでも、決して余興ではなく、本気でやったつもりである。」
『ローマ人の愛と性』の「あとがき」では、著者は小説家と歴史家の違いを述べた塩野七生氏の言説を紹介して塩野七生氏を「ローマの天下国家を描く歴史家のごとき作家」としたうえで、次のように述べている。
「でも、天下国家を論じることが苦手な作家のごとき歴史家もいます。さしずめ私はそんな類の歴史家でしょう。というよりも、歴史家もどきといったほうがいいかもしれません。」
本村凌二氏の魅力が伝わってくる。
歴史学者・本村凌二氏の次の新書を続けて読んだ。
『多神教と一神教:古代地中海世界の宗教ドラマ』(本村凌二/岩波新書)
『ローマ人の愛と性』(本村凌二/講談社現代新書)
『多神教と一神教』は2005年、『ローマ人の愛と性』は1999年の刊行で、この2冊のテーマは絡み合っていてワンセットの論考として読める。ローマ帝国やミスラ教などに多少の関心のある私にはとても面白い内容だった。蒙を啓かれた。
どちらも社会史的アプローチで古代の人々の心性の変遷をさぐっている。前者は文明発生の紀元前3000年代から2世紀のローマ帝政期までの地中海世界、後者は時間と地域を狭めて紀元前1世紀半ばから2世紀半ばまでの約200年のローマの社会を対象にしている(書かれたのは後者が先)。
◎多神教から一神教への移行は必然か?
著者の見解を大雑把に言えば、文明発生期の社会は森羅万象の背後に神を見出す多神教の社会であったが、時代が進むに従って神々の習合(宗教融合:シンクレティズム)なども起こり、やがて一神教が発生し、個人の救済に関わる一神教の浸透によって多神教の社会は一神教の社会へと変異したということである。
パクス・ロマーナを現出させたローマ帝国は寛容な多神教の社会だったが、不寛容な一神教であるキリスト教の浸透とともにローマ帝国は衰退した --- 私にはそんな認識があった。しかし、歴史はそう単純に把握できるものではなさそうだ。
本書を読んでいると、一神教の浸透は文明の発展にともなう必然の流れに見えてくる。アルファベットという簡略化された文字の使用を一神教の浸透に関連付ける考察には驚き、感心した。
著者は人類の心性の変化が一神教を生み出すメカニズムを説いているだけで、一神教が優れていると主張しているのではない。一神教に問題があるのは確かだ。やっかいなことである。
◎馬鹿な歴史家もどき??
この2冊のあとがきが面白い。
『多神教と一神教』の「あとがき」で著者は自身を「ローマ帝国の社会史を研究する者の一人」としたうえで、次のように述べている。
「地中海世界の古層といえるシュメール人から古代末期にいたる筋道を描くなどとは、専門研究者なら馬鹿としか思えないだろう。でも、馬鹿の一人になってもいいかという気分で書いたつもりである。それでも、決して余興ではなく、本気でやったつもりである。」
『ローマ人の愛と性』の「あとがき」では、著者は小説家と歴史家の違いを述べた塩野七生氏の言説を紹介して塩野七生氏を「ローマの天下国家を描く歴史家のごとき作家」としたうえで、次のように述べている。
「でも、天下国家を論じることが苦手な作家のごとき歴史家もいます。さしずめ私はそんな類の歴史家でしょう。というよりも、歴史家もどきといったほうがいいかもしれません。」
本村凌二氏の魅力が伝わってくる。
映画『カンゾー先生』で大煙突の記憶が蘇る ― 2019年02月27日
私が15歳までを過ごした岡山県玉野市の日比が登場する小説『始祖鳥記』(飯嶋和一) の読後感をブログに書いたところ、それを読んでくださった方から、日比が舞台の映画『カンゾー先生』を紹介された。
この映画が日比を舞台にしていると、かなり以前に聞いていたが、観る機会を逸したまま忘れていた。ブログにコメントをいただいたのを機に、中古DVDを入手して『カンゾー先生』(原作:坂口安吾、監督:今村昌平)を観た。31年前の映画である。
主演は柄本明で、麻生久美子、松坂慶子、唐十郎、世良公則などが出演している。当然ながら、いま観ると役者がみな若い。舞台は終戦直前の日比、開業医「カンゾー先生」の話である。滑稽譚と思っていたが、滑稽譚を超えた味わい深い映画だった。
原作の舞台は伊東、それを映画では日比に変えている。だが、ロケ地は日比ではなく牛窓(瀬戸内市)である。さほど有名でもない日比を映画の舞台にした理由はよくわからない。
映画の冒頭は米軍の空襲パイロットのシーンである。大煙突がある日比の精錬所の上空に来るが、連合軍捕虜が精錬所で働かされているとの情報があって空襲は断念する。上空から見た大煙突や精錬所の映像に引き込まれた。
私は大煙突を毎日眺めながら幼少期を過ごした。精錬所は私の父の職場だった。だから、映画の冒頭シーンに懐かしさを感じた。映画は戦時中の話で、私が知っているのは戦後復興期の情景だから時間差がある。それにしても、よく眺めると、映画の情景は私の知っている大煙突や精錬所ではない。ロケ地が日比でないのだから当然なのだが…。
日比の大煙突は山頂にあり、東洋一の煙突だと聞かされていた(私の幼少期には「東洋一」という表現が多かった)。子供の頃は煙突山に登って大煙突を真下から見上げたものだ。大煙突の周辺は遊び場のひとつだった。山麓の精錬所と山頂の大煙突の間には大蛇のような煙道があったが、映画ではそれがない。だから、映画の大煙突は私の知っている大煙突とは別物に見えた。
十数年前、故郷に行ったとき、まだ大煙突は山頂にあったが煙は出てなかった。少し離れた脇に赤白模様のやや近代的でスマートな煙突が建っていた。あの赤白煙突のせいで大煙突が映画のロケに使われなかったのだろうか。
この映画が日比を舞台にしていると、かなり以前に聞いていたが、観る機会を逸したまま忘れていた。ブログにコメントをいただいたのを機に、中古DVDを入手して『カンゾー先生』(原作:坂口安吾、監督:今村昌平)を観た。31年前の映画である。
主演は柄本明で、麻生久美子、松坂慶子、唐十郎、世良公則などが出演している。当然ながら、いま観ると役者がみな若い。舞台は終戦直前の日比、開業医「カンゾー先生」の話である。滑稽譚と思っていたが、滑稽譚を超えた味わい深い映画だった。
原作の舞台は伊東、それを映画では日比に変えている。だが、ロケ地は日比ではなく牛窓(瀬戸内市)である。さほど有名でもない日比を映画の舞台にした理由はよくわからない。
映画の冒頭は米軍の空襲パイロットのシーンである。大煙突がある日比の精錬所の上空に来るが、連合軍捕虜が精錬所で働かされているとの情報があって空襲は断念する。上空から見た大煙突や精錬所の映像に引き込まれた。
私は大煙突を毎日眺めながら幼少期を過ごした。精錬所は私の父の職場だった。だから、映画の冒頭シーンに懐かしさを感じた。映画は戦時中の話で、私が知っているのは戦後復興期の情景だから時間差がある。それにしても、よく眺めると、映画の情景は私の知っている大煙突や精錬所ではない。ロケ地が日比でないのだから当然なのだが…。
日比の大煙突は山頂にあり、東洋一の煙突だと聞かされていた(私の幼少期には「東洋一」という表現が多かった)。子供の頃は煙突山に登って大煙突を真下から見上げたものだ。大煙突の周辺は遊び場のひとつだった。山麓の精錬所と山頂の大煙突の間には大蛇のような煙道があったが、映画ではそれがない。だから、映画の大煙突は私の知っている大煙突とは別物に見えた。
十数年前、故郷に行ったとき、まだ大煙突は山頂にあったが煙は出てなかった。少し離れた脇に赤白模様のやや近代的でスマートな煙突が建っていた。あの赤白煙突のせいで大煙突が映画のロケに使われなかったのだろうか。




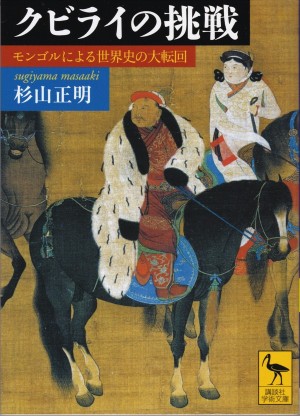



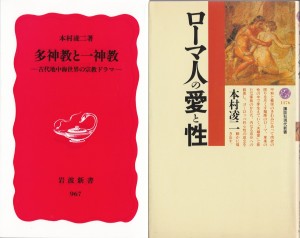

最近のコメント