80年を通観した『日本近代史』は頭が疲れる本 ― 2018年11月06日
『日本近代史』(坂野潤治/ちくま新書)
1857年(安政4年)から1937年(昭和12年)までの80年を通観した史書である。新書としてはやや分厚い約450ページで、安政の大獄の頃から盧溝橋事件までの歴史を分析的に記述している。
この新書を読了するにはかなり時間がかかった。途中で何冊か他の本の割り込みもあったが、読み通すのに骨が折れるのは分厚さのせいではない。日本が大きく変貌したこの80年間のさまざまな出来事や時代の動きに翻弄され、頭が疲労困憊するからである。
80年という時間は歴史を見る目からはさほど長くはない。私だって70年近く生きているから、その間の世の中の変遷を眺め、体験してきた。しかし、幕末から昭和の開戦前夜までの80年の歴史には、人間一人の一生では消化しきれない濃密さがあり、その流れについて行くのは大変である。
坂野潤治氏は私が先月読んだ『西郷隆盛と明治維新』(講談社現代新書)の著者で、その中で「西郷を尊敬する」と明言し、西郷を高く評価していた。もちろん、その見方は本書でも同じである(本書の刊行は『西郷隆盛と明治維新』の前年)。
著者はこの80年を以下の6段階にわけて分析している。
(1) 改革の時代(1857-1863)公武合体
(2) 革命の時代(1863-1871)尊王討幕
(3) 建設の時代(1871-1880)殖産興業
(4) 運用の時代(1880-1893)明治立憲制
(5) 再編の時代(1894-1924)大正デモクラシー
(6) 危機の時代(1925-1937)昭和ファシズム
概ね納得できる区分だが、明治維新を「革命」と見ているのが本書の特徴だろう。公武合体論を保守、尊王討幕を革新と見る立場である。明治維新を「革命」と見るか否かは歴史学者の間でも議論があり、そもそも「革命とは何か」から明らかにする必要があり、私ごときには何とも評価できない。
本書で面白く思ったのは、日露戦争後の日比谷焼き討ち事件などの講和反対運動を1960年の日米安保反対運動と重ねて見ている点である。世界の現実を理解できない蒙昧な大衆運動とも見えるし、体制への反発・抵抗の発露と見ることもできる。多面的な切り口で分析すべきテーマである。歴史的出来事と思っていた日比谷焼き討ち事件が、60年安保を知っている身に身近な課題に感じられた。
私が最も興味深く読んだのは後半の大正から昭和初期の歴史である。この時代への漠然とした理解が覆されるような指摘が多く、勉強になった。原敬や浜口雄幸などをめぐる政党の話は、評価軸が複雑に入り組んでいて面白い。美濃部達吉の軍部に批判的な「正論」を著者が批判的に見ているのも興味深い。
本書最終章の「危機の時代」の次には「崩壊の時代」がやって来る。危機の時代において、崩壊の時代を未然に防ぐことができたか、著者はそれについて若干の考察をしている。タラレバではあるが、より深く広く考えるべき歴史の課題だと思う。
1857年(安政4年)から1937年(昭和12年)までの80年を通観した史書である。新書としてはやや分厚い約450ページで、安政の大獄の頃から盧溝橋事件までの歴史を分析的に記述している。
この新書を読了するにはかなり時間がかかった。途中で何冊か他の本の割り込みもあったが、読み通すのに骨が折れるのは分厚さのせいではない。日本が大きく変貌したこの80年間のさまざまな出来事や時代の動きに翻弄され、頭が疲労困憊するからである。
80年という時間は歴史を見る目からはさほど長くはない。私だって70年近く生きているから、その間の世の中の変遷を眺め、体験してきた。しかし、幕末から昭和の開戦前夜までの80年の歴史には、人間一人の一生では消化しきれない濃密さがあり、その流れについて行くのは大変である。
坂野潤治氏は私が先月読んだ『西郷隆盛と明治維新』(講談社現代新書)の著者で、その中で「西郷を尊敬する」と明言し、西郷を高く評価していた。もちろん、その見方は本書でも同じである(本書の刊行は『西郷隆盛と明治維新』の前年)。
著者はこの80年を以下の6段階にわけて分析している。
(1) 改革の時代(1857-1863)公武合体
(2) 革命の時代(1863-1871)尊王討幕
(3) 建設の時代(1871-1880)殖産興業
(4) 運用の時代(1880-1893)明治立憲制
(5) 再編の時代(1894-1924)大正デモクラシー
(6) 危機の時代(1925-1937)昭和ファシズム
概ね納得できる区分だが、明治維新を「革命」と見ているのが本書の特徴だろう。公武合体論を保守、尊王討幕を革新と見る立場である。明治維新を「革命」と見るか否かは歴史学者の間でも議論があり、そもそも「革命とは何か」から明らかにする必要があり、私ごときには何とも評価できない。
本書で面白く思ったのは、日露戦争後の日比谷焼き討ち事件などの講和反対運動を1960年の日米安保反対運動と重ねて見ている点である。世界の現実を理解できない蒙昧な大衆運動とも見えるし、体制への反発・抵抗の発露と見ることもできる。多面的な切り口で分析すべきテーマである。歴史的出来事と思っていた日比谷焼き討ち事件が、60年安保を知っている身に身近な課題に感じられた。
私が最も興味深く読んだのは後半の大正から昭和初期の歴史である。この時代への漠然とした理解が覆されるような指摘が多く、勉強になった。原敬や浜口雄幸などをめぐる政党の話は、評価軸が複雑に入り組んでいて面白い。美濃部達吉の軍部に批判的な「正論」を著者が批判的に見ているのも興味深い。
本書最終章の「危機の時代」の次には「崩壊の時代」がやって来る。危機の時代において、崩壊の時代を未然に防ぐことができたか、著者はそれについて若干の考察をしている。タラレバではあるが、より深く広く考えるべき歴史の課題だと思う。
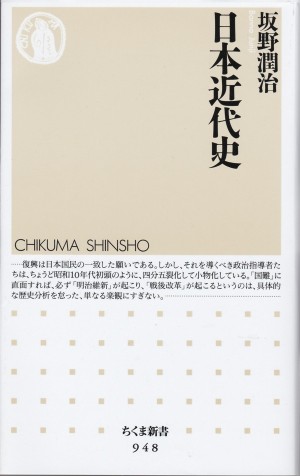
最近のコメント