古代ローマではキリスト教に拮抗していたミトラ教 ― 2018年11月04日
『ローマ帝国の神々』(小川英雄/中公新書)を読んだのは半年前で、読後感をブログに書いたにもかかわらず、その内容は頭の中でおぼろになりつつある。その著者の小川英雄氏が翻訳した『ミトラの密儀』が先月、文庫版で出版された。
『ミトラの密儀』(フランツ・キュモン/小川英雄訳/ちくま学芸文庫)
著者のキュモンはミトラ研究の第一人者で、原書が出たのは1899年である。翻訳版は1世紀後の1993年に平凡社から刊行され、15年経ってちくま学芸文庫に収録された。
半年前に『ローマ帝国の神々』を読んだのは、古代ローマ史に見え隠れする謎のミトラ教につい知りたいと思ったからである。すでに頭の中で薄れつつある読書記憶の更新になればと本書を購入した。
読み始めてすぐに、門外漢の私には難しい本だと気づいた。未知の固有名詞(地名、用語など)が多く、一般書というより学術書に近い。難儀なことだと思ったが、全300ページの後半100ページは「註」や「目録」で本文は200ページ、文庫本で200ページなら何とか突っ走ろうと覚悟して読み進めた。
ミトラ教は古代イランを起源とする古い宗教で、ゾロアスター教など多様な信仰との融合で形成されている。教典などが残っているわけではなく、その内容は明確にはわかっていない。ただし、この宗教がローマ帝国に伝播し拡大していたことはさまざまな痕跡から明らかになっている。
本書はミトラ教がローマ帝国でどのように拡大したか、その教義や典礼はどんなものであったかを、いろいろな手がかりを元に丁寧に解説している。
途中までは読み進めるのがしんどかったが、最終章の「ミトラとローマ帝国の諸宗教」でがぜん面白くなった。ミトラ教とキリスト教の世界制覇をかけた抗争を描いているからである。
キリスト教に制覇されるまでのローマ帝国は伝統的な多神教の世界だと思っていたが、そのローマ帝国で一大勢力を築いていたミトラ教はキリスト教と同じ一神教である。キリスト教とミトラ教との共通点も多い。というか、ミトラ教に勝利したキリスト教はミトラ教からさまざまなものを取り入れたのである。キリスト教が何らかの事情で挫折していれば、ミトラ教が世界宗教になったかもしれないとも言われているそうだ。
キュモンはミトラ教がキリスト教に敗れた要因をいくつか分析している。その一つは、ミトラ教がローマ帝国の多神教に寛容だったのに対し、キリスト教は多神教を認めなかった点である。キリスト教の非妥協的で反抗的な姿勢が、結局は勝利につながったというのである。興味深い見方だと思った。
現在、ミトラ教が「謎の宗教」なのは、非妥協的なキリスト教の勝利によってその痕跡の多くが消されたせいだと思われる。
本書の最終章は次のセンテンスで終わっている。
「このように更新されていったミトラの教義は何世紀もの間あらゆる迫害に耐え、中世の間に新しいかたちの下に再興し、新たに古くからのローマ世界を揺るがせることになるのである」
私には、これが何を意味しているのかわからない。もう少し勉強する必要がある。
『ミトラの密儀』(フランツ・キュモン/小川英雄訳/ちくま学芸文庫)
著者のキュモンはミトラ研究の第一人者で、原書が出たのは1899年である。翻訳版は1世紀後の1993年に平凡社から刊行され、15年経ってちくま学芸文庫に収録された。
半年前に『ローマ帝国の神々』を読んだのは、古代ローマ史に見え隠れする謎のミトラ教につい知りたいと思ったからである。すでに頭の中で薄れつつある読書記憶の更新になればと本書を購入した。
読み始めてすぐに、門外漢の私には難しい本だと気づいた。未知の固有名詞(地名、用語など)が多く、一般書というより学術書に近い。難儀なことだと思ったが、全300ページの後半100ページは「註」や「目録」で本文は200ページ、文庫本で200ページなら何とか突っ走ろうと覚悟して読み進めた。
ミトラ教は古代イランを起源とする古い宗教で、ゾロアスター教など多様な信仰との融合で形成されている。教典などが残っているわけではなく、その内容は明確にはわかっていない。ただし、この宗教がローマ帝国に伝播し拡大していたことはさまざまな痕跡から明らかになっている。
本書はミトラ教がローマ帝国でどのように拡大したか、その教義や典礼はどんなものであったかを、いろいろな手がかりを元に丁寧に解説している。
途中までは読み進めるのがしんどかったが、最終章の「ミトラとローマ帝国の諸宗教」でがぜん面白くなった。ミトラ教とキリスト教の世界制覇をかけた抗争を描いているからである。
キリスト教に制覇されるまでのローマ帝国は伝統的な多神教の世界だと思っていたが、そのローマ帝国で一大勢力を築いていたミトラ教はキリスト教と同じ一神教である。キリスト教とミトラ教との共通点も多い。というか、ミトラ教に勝利したキリスト教はミトラ教からさまざまなものを取り入れたのである。キリスト教が何らかの事情で挫折していれば、ミトラ教が世界宗教になったかもしれないとも言われているそうだ。
キュモンはミトラ教がキリスト教に敗れた要因をいくつか分析している。その一つは、ミトラ教がローマ帝国の多神教に寛容だったのに対し、キリスト教は多神教を認めなかった点である。キリスト教の非妥協的で反抗的な姿勢が、結局は勝利につながったというのである。興味深い見方だと思った。
現在、ミトラ教が「謎の宗教」なのは、非妥協的なキリスト教の勝利によってその痕跡の多くが消されたせいだと思われる。
本書の最終章は次のセンテンスで終わっている。
「このように更新されていったミトラの教義は何世紀もの間あらゆる迫害に耐え、中世の間に新しいかたちの下に再興し、新たに古くからのローマ世界を揺るがせることになるのである」
私には、これが何を意味しているのかわからない。もう少し勉強する必要がある。
80年を通観した『日本近代史』は頭が疲れる本 ― 2018年11月06日
『日本近代史』(坂野潤治/ちくま新書)
1857年(安政4年)から1937年(昭和12年)までの80年を通観した史書である。新書としてはやや分厚い約450ページで、安政の大獄の頃から盧溝橋事件までの歴史を分析的に記述している。
この新書を読了するにはかなり時間がかかった。途中で何冊か他の本の割り込みもあったが、読み通すのに骨が折れるのは分厚さのせいではない。日本が大きく変貌したこの80年間のさまざまな出来事や時代の動きに翻弄され、頭が疲労困憊するからである。
80年という時間は歴史を見る目からはさほど長くはない。私だって70年近く生きているから、その間の世の中の変遷を眺め、体験してきた。しかし、幕末から昭和の開戦前夜までの80年の歴史には、人間一人の一生では消化しきれない濃密さがあり、その流れについて行くのは大変である。
坂野潤治氏は私が先月読んだ『西郷隆盛と明治維新』(講談社現代新書)の著者で、その中で「西郷を尊敬する」と明言し、西郷を高く評価していた。もちろん、その見方は本書でも同じである(本書の刊行は『西郷隆盛と明治維新』の前年)。
著者はこの80年を以下の6段階にわけて分析している。
(1) 改革の時代(1857-1863)公武合体
(2) 革命の時代(1863-1871)尊王討幕
(3) 建設の時代(1871-1880)殖産興業
(4) 運用の時代(1880-1893)明治立憲制
(5) 再編の時代(1894-1924)大正デモクラシー
(6) 危機の時代(1925-1937)昭和ファシズム
概ね納得できる区分だが、明治維新を「革命」と見ているのが本書の特徴だろう。公武合体論を保守、尊王討幕を革新と見る立場である。明治維新を「革命」と見るか否かは歴史学者の間でも議論があり、そもそも「革命とは何か」から明らかにする必要があり、私ごときには何とも評価できない。
本書で面白く思ったのは、日露戦争後の日比谷焼き討ち事件などの講和反対運動を1960年の日米安保反対運動と重ねて見ている点である。世界の現実を理解できない蒙昧な大衆運動とも見えるし、体制への反発・抵抗の発露と見ることもできる。多面的な切り口で分析すべきテーマである。歴史的出来事と思っていた日比谷焼き討ち事件が、60年安保を知っている身に身近な課題に感じられた。
私が最も興味深く読んだのは後半の大正から昭和初期の歴史である。この時代への漠然とした理解が覆されるような指摘が多く、勉強になった。原敬や浜口雄幸などをめぐる政党の話は、評価軸が複雑に入り組んでいて面白い。美濃部達吉の軍部に批判的な「正論」を著者が批判的に見ているのも興味深い。
本書最終章の「危機の時代」の次には「崩壊の時代」がやって来る。危機の時代において、崩壊の時代を未然に防ぐことができたか、著者はそれについて若干の考察をしている。タラレバではあるが、より深く広く考えるべき歴史の課題だと思う。
1857年(安政4年)から1937年(昭和12年)までの80年を通観した史書である。新書としてはやや分厚い約450ページで、安政の大獄の頃から盧溝橋事件までの歴史を分析的に記述している。
この新書を読了するにはかなり時間がかかった。途中で何冊か他の本の割り込みもあったが、読み通すのに骨が折れるのは分厚さのせいではない。日本が大きく変貌したこの80年間のさまざまな出来事や時代の動きに翻弄され、頭が疲労困憊するからである。
80年という時間は歴史を見る目からはさほど長くはない。私だって70年近く生きているから、その間の世の中の変遷を眺め、体験してきた。しかし、幕末から昭和の開戦前夜までの80年の歴史には、人間一人の一生では消化しきれない濃密さがあり、その流れについて行くのは大変である。
坂野潤治氏は私が先月読んだ『西郷隆盛と明治維新』(講談社現代新書)の著者で、その中で「西郷を尊敬する」と明言し、西郷を高く評価していた。もちろん、その見方は本書でも同じである(本書の刊行は『西郷隆盛と明治維新』の前年)。
著者はこの80年を以下の6段階にわけて分析している。
(1) 改革の時代(1857-1863)公武合体
(2) 革命の時代(1863-1871)尊王討幕
(3) 建設の時代(1871-1880)殖産興業
(4) 運用の時代(1880-1893)明治立憲制
(5) 再編の時代(1894-1924)大正デモクラシー
(6) 危機の時代(1925-1937)昭和ファシズム
概ね納得できる区分だが、明治維新を「革命」と見ているのが本書の特徴だろう。公武合体論を保守、尊王討幕を革新と見る立場である。明治維新を「革命」と見るか否かは歴史学者の間でも議論があり、そもそも「革命とは何か」から明らかにする必要があり、私ごときには何とも評価できない。
本書で面白く思ったのは、日露戦争後の日比谷焼き討ち事件などの講和反対運動を1960年の日米安保反対運動と重ねて見ている点である。世界の現実を理解できない蒙昧な大衆運動とも見えるし、体制への反発・抵抗の発露と見ることもできる。多面的な切り口で分析すべきテーマである。歴史的出来事と思っていた日比谷焼き討ち事件が、60年安保を知っている身に身近な課題に感じられた。
私が最も興味深く読んだのは後半の大正から昭和初期の歴史である。この時代への漠然とした理解が覆されるような指摘が多く、勉強になった。原敬や浜口雄幸などをめぐる政党の話は、評価軸が複雑に入り組んでいて面白い。美濃部達吉の軍部に批判的な「正論」を著者が批判的に見ているのも興味深い。
本書最終章の「危機の時代」の次には「崩壊の時代」がやって来る。危機の時代において、崩壊の時代を未然に防ぐことができたか、著者はそれについて若干の考察をしている。タラレバではあるが、より深く広く考えるべき歴史の課題だと思う。
テント芝居小屋「平成中村座」初体験 ― 2018年11月08日
浅草寺の境内で平成中村座の十一月大歌舞伎・昼の部を観た。「十八世中村勘三郎七回忌追善」と銘打った公演である。10月の歌舞伎座も「十八世中村勘三郎七回忌追善」だったから2カ月続けての追善公演である。
平成中村座の歌舞伎は初体験だ。勘三郎が江戸の芝居小屋を再現した仮設劇場「平成中村座」を旗揚げし、日本各地だけでなくニューヨークにまでその芝居小屋を持ち込んで公演したという話は新聞や雑誌で知っていて、関心はあった。だが、観たいと思いつつ機会を逸し、勘三郎没後7年が経過した。
観劇の動機は「平成中村座」という芝居小屋がどんな所だろうという興味である。テントだというが、写真では普通の立派な芝居小屋に見える。
その芝居小屋は、仲見世通りを抜けて浅草寺を回った裏手に建っていた。遠くから見ると大きな倉庫のようにも見える。近づいてよく見ると、垂直の壁は確かにテントだ。紅テントや黒テントとは規模が違う。芝居小屋の前には屋台風の売店も並び、華やかな風情である。
昼の部の演目は「実盛物語」「近江のお兼」「狐狸狐狸ばなし」の3本、もちろん勘九郎と七之助の見せ場もあり、歌舞伎はエンタメだと了解できる舞台だった。勘九郎の5歳の次男長三郎が科白の多い役を可愛く立派にこなしているのに感心し、歌舞伎の家に生まれた子供の優位と宿命を再認識した。
遮音性が低いテント小屋なので、芝居の最中に上空を飛ぶヘリコプターの爆音が聞こえてくることがあった。うるさいと思うより、一過性の芝居を観ているという臨場感に浸る気分になった。
平成中村座の歌舞伎は初体験だ。勘三郎が江戸の芝居小屋を再現した仮設劇場「平成中村座」を旗揚げし、日本各地だけでなくニューヨークにまでその芝居小屋を持ち込んで公演したという話は新聞や雑誌で知っていて、関心はあった。だが、観たいと思いつつ機会を逸し、勘三郎没後7年が経過した。
観劇の動機は「平成中村座」という芝居小屋がどんな所だろうという興味である。テントだというが、写真では普通の立派な芝居小屋に見える。
その芝居小屋は、仲見世通りを抜けて浅草寺を回った裏手に建っていた。遠くから見ると大きな倉庫のようにも見える。近づいてよく見ると、垂直の壁は確かにテントだ。紅テントや黒テントとは規模が違う。芝居小屋の前には屋台風の売店も並び、華やかな風情である。
昼の部の演目は「実盛物語」「近江のお兼」「狐狸狐狸ばなし」の3本、もちろん勘九郎と七之助の見せ場もあり、歌舞伎はエンタメだと了解できる舞台だった。勘九郎の5歳の次男長三郎が科白の多い役を可愛く立派にこなしているのに感心し、歌舞伎の家に生まれた子供の優位と宿命を再認識した。
遮音性が低いテント小屋なので、芝居の最中に上空を飛ぶヘリコプターの爆音が聞こえてくることがあった。うるさいと思うより、一過性の芝居を観ているという臨場感に浸る気分になった。
榎本武揚を魅力的に描いた『武揚伝』の陰の主人公は勝海舟 ― 2018年11月11日
私は幕末維新の人物では榎本武揚に好感を抱いている。「蝦夷共和国」という夢のある大きな構想を実現させようとした国際法に明るい軍人政治家である。合理的思考ができる理系人間で、幅広い知識を習得した有能な技術者でもある。そんな人物が魅力的なのは当然だと思う。
と言っても榎本武揚に関する断片的な知識があるだけで、半世紀昔の学生時代に安部公房の『榎本武揚』を読んだ以外まとまったものを読んだ記憶はない。いずれ、いろいろ読もうと思いつつ月日が経った。そして、70歳を目前にして次の歴史小説を読んだ。
『武揚伝 決定版(上)(中)(下)』(佐々木譲/中公文庫)
全3冊だが長さを感じさせない面白さがあり、一気に読める。フィクションを織り込んだ小説だから主人公を魅力的に描いているのは当然だが、科学技術志向の聡明な軍人が人望あるリーダーへと成長していく物語になっているのがいい。
この小説のタイトルに「決定版」とあるのは、2001年に刊行した小説を2015年に改稿しているからである。著者の「あとがき」には「この十数年のあいだに榎本武揚研究が進み、新史料もさまざま出てきた。(…)新史料、新しい研究成果を付加して書き直した」とある。フィクションとは言え、史実の大筋を反映していると思われる。
この小説で面白いのは勝海舟を悪役に仕立ててるところだ。オランダ語ができるだけで軍事の実学ができない艦長失格の口舌の徒、自分を売り込むことに長けた薩摩・幕府の二股膏薬の政治屋と描いている。
ただし、江戸開城後の薩摩軍の狼藉に挫折を感じる勝海舟も描いていて、その勝海舟を「世の先行きを見通すことのできる知性と、激情に流されぬだけの分別と、大きな戦略を描くことのできる想像力の光を有していた」と評価する箇所もある。
そして、「蝦夷共和国」を立ち上げた榎本武揚に対して勝海舟は「そんな自治州ができた暁には、新しい世はずたずたになる。たえず政変と内乱の火種を抱えることになる」と嫉妬に近い強烈な反発を吐露する。幕末維新の大立者、ホラ吹きの勝つぁんが武揚の引き立て役になっているのだ。この小説の陰の主人公は勝海舟のように思えてくる。
榎本武揚が箱館戦争で敗退するのは34歳の時である。その後、彼は明治政府の有能な高官として活躍して73歳で没する。しかし「武揚伝」と題するこの小説は、箱館戦争後の半生は1頁半の概説で終わっている。後半生にドラマは乏しいかもしれないが、後半生の葛藤にも踏み込んでほしかった。
と言っても榎本武揚に関する断片的な知識があるだけで、半世紀昔の学生時代に安部公房の『榎本武揚』を読んだ以外まとまったものを読んだ記憶はない。いずれ、いろいろ読もうと思いつつ月日が経った。そして、70歳を目前にして次の歴史小説を読んだ。
『武揚伝 決定版(上)(中)(下)』(佐々木譲/中公文庫)
全3冊だが長さを感じさせない面白さがあり、一気に読める。フィクションを織り込んだ小説だから主人公を魅力的に描いているのは当然だが、科学技術志向の聡明な軍人が人望あるリーダーへと成長していく物語になっているのがいい。
この小説のタイトルに「決定版」とあるのは、2001年に刊行した小説を2015年に改稿しているからである。著者の「あとがき」には「この十数年のあいだに榎本武揚研究が進み、新史料もさまざま出てきた。(…)新史料、新しい研究成果を付加して書き直した」とある。フィクションとは言え、史実の大筋を反映していると思われる。
この小説で面白いのは勝海舟を悪役に仕立ててるところだ。オランダ語ができるだけで軍事の実学ができない艦長失格の口舌の徒、自分を売り込むことに長けた薩摩・幕府の二股膏薬の政治屋と描いている。
ただし、江戸開城後の薩摩軍の狼藉に挫折を感じる勝海舟も描いていて、その勝海舟を「世の先行きを見通すことのできる知性と、激情に流されぬだけの分別と、大きな戦略を描くことのできる想像力の光を有していた」と評価する箇所もある。
そして、「蝦夷共和国」を立ち上げた榎本武揚に対して勝海舟は「そんな自治州ができた暁には、新しい世はずたずたになる。たえず政変と内乱の火種を抱えることになる」と嫉妬に近い強烈な反発を吐露する。幕末維新の大立者、ホラ吹きの勝つぁんが武揚の引き立て役になっているのだ。この小説の陰の主人公は勝海舟のように思えてくる。
榎本武揚が箱館戦争で敗退するのは34歳の時である。その後、彼は明治政府の有能な高官として活躍して73歳で没する。しかし「武揚伝」と題するこの小説は、箱館戦争後の半生は1頁半の概説で終わっている。後半生にドラマは乏しいかもしれないが、後半生の葛藤にも踏み込んでほしかった。
アーサー・ミラーの『セールスマンの死』で今の米国を連想 ― 2018年11月15日
神奈川芸術劇場で『セールスマンの死』(演出:長塚圭史/出演:風間杜夫、片平なぎさ、他)を観た。アーサー・ミラーの高名なこの戯曲を知ったのは高校生の頃だと思う。戯曲は読んだが、舞台を観るのは初めてである。
約3時間の舞台は緊張感が持続する観劇時間だった。やはり名作だと思う。テネシー・ウイリアムズの『ガラスの動物園』や『欲望という名の電車』と似たテイストのやるせない世界を提示している。第二次世界大戦の直後、戦勝国アメリカでこんなに暗い名作劇が続いて生まれたことに不思議を感じる。
『セールスマンの死』はタイトルだけで、疲れ果てたセールスマンが追い詰められて死ぬ話だろうと推測でき、実際の内容もその推測から大きく離れているわけではない。ネタバレのようなタイトルなのに観客を引き込むことができるのは、単純な推測を超えた秀逸な仕掛けが組み込まれているからである。
この芝居は肥大した自己幻想がもたらす悲劇を描いている。半世紀以上昔のアメリカの大都市に住む家族というレトロな世界の物語だが、テーマは普遍的である。アメリカン・ドリームという概念が今も持続しているかどうかは知らないが、それに似た憧れと希望は形は変わってもいつの時代にもあるように思える。
大多数の人々にとってアメリカン・ドリームは見果てぬ夢であり、夢見る自身との折り合いのつけ方が人生の課題になる。
この舞台を観ていて、主人公の老セールスマンがトランプ大統領を支持するラストベルト地帯の白人労働者の姿と重なって見える気がした。と言って、何等かの解決策や出口が見えたわけではない。
約3時間の舞台は緊張感が持続する観劇時間だった。やはり名作だと思う。テネシー・ウイリアムズの『ガラスの動物園』や『欲望という名の電車』と似たテイストのやるせない世界を提示している。第二次世界大戦の直後、戦勝国アメリカでこんなに暗い名作劇が続いて生まれたことに不思議を感じる。
『セールスマンの死』はタイトルだけで、疲れ果てたセールスマンが追い詰められて死ぬ話だろうと推測でき、実際の内容もその推測から大きく離れているわけではない。ネタバレのようなタイトルなのに観客を引き込むことができるのは、単純な推測を超えた秀逸な仕掛けが組み込まれているからである。
この芝居は肥大した自己幻想がもたらす悲劇を描いている。半世紀以上昔のアメリカの大都市に住む家族というレトロな世界の物語だが、テーマは普遍的である。アメリカン・ドリームという概念が今も持続しているかどうかは知らないが、それに似た憧れと希望は形は変わってもいつの時代にもあるように思える。
大多数の人々にとってアメリカン・ドリームは見果てぬ夢であり、夢見る自身との折り合いのつけ方が人生の課題になる。
この舞台を観ていて、主人公の老セールスマンがトランプ大統領を支持するラストベルト地帯の白人労働者の姿と重なって見える気がした。と言って、何等かの解決策や出口が見えたわけではない。
ピンターの『誰もいない国』の「わからなさ」の面白さ ― 2018年11月17日
新国立劇場小劇場でハロルド・ピンターの『誰もいない国』(演出:寺十吾/出演:柄本明、石倉三郎、他)を観た。ピンターの芝居は初体験である。半世紀前の学生時代に友人からピンターの『ダム・ウェイター』がスゴイと聞いた記憶があるが、どうスゴイのかはわからなかった。
その後、ピンターの芝居を観ることも戯曲を読むこともなかった。2005年にノーベル文学賞を受賞したピンターはすでに物故者だ。私に『ダム・ウェイター』がスゴイと言った友人も数年前に亡くなった。
『誰もいない国』は事前に戯曲を読まずに観劇した。戯曲の入手が難しかったからである。ウワサに違わず、わけのわからない芝居だった。事前に戯曲を読んでいたとしても、この「わからなさ」は同じだろう。
4人の登場人物のカミあっているのかカミあってないのか曖昧な会話で不思議な状況が進行する。わからないなりにユーモラスな会話や状況が随所に折り込まれていて笑える場面は多い。柄本明と石倉三郎がウィスキー、ウォッカ、シャンパンなどをやたらに飲むので、酔いが伝染して当方の頭もぼんやりしてきそうになる。
食堂と寝室の間に大きな水たまりがあり、ジャブジャブと足を濡らしながら行き来しなければならないのは、夢の中のシーンのようだ。唐突に上方から幾筋かの水が落ちて来たりもする。会話に登場する「誰もいない国(NO MAN'S LAND)」という言葉には魅力的なひびきがある。
こういう芝居を観ていると、芝居にとって「わかる」ということはさほど重要でないかもしれないという気分になる。役者だって科白の内容や意味を十全にわかってしゃべっているわけはない。全身で演じてひとつの世界を現出させようとしているのだと思う。その世界を体験したと観客が思い込むことができれば、それでいい。
その後、ピンターの芝居を観ることも戯曲を読むこともなかった。2005年にノーベル文学賞を受賞したピンターはすでに物故者だ。私に『ダム・ウェイター』がスゴイと言った友人も数年前に亡くなった。
『誰もいない国』は事前に戯曲を読まずに観劇した。戯曲の入手が難しかったからである。ウワサに違わず、わけのわからない芝居だった。事前に戯曲を読んでいたとしても、この「わからなさ」は同じだろう。
4人の登場人物のカミあっているのかカミあってないのか曖昧な会話で不思議な状況が進行する。わからないなりにユーモラスな会話や状況が随所に折り込まれていて笑える場面は多い。柄本明と石倉三郎がウィスキー、ウォッカ、シャンパンなどをやたらに飲むので、酔いが伝染して当方の頭もぼんやりしてきそうになる。
食堂と寝室の間に大きな水たまりがあり、ジャブジャブと足を濡らしながら行き来しなければならないのは、夢の中のシーンのようだ。唐突に上方から幾筋かの水が落ちて来たりもする。会話に登場する「誰もいない国(NO MAN'S LAND)」という言葉には魅力的なひびきがある。
こういう芝居を観ていると、芝居にとって「わかる」ということはさほど重要でないかもしれないという気分になる。役者だって科白の内容や意味を十全にわかってしゃべっているわけはない。全身で演じてひとつの世界を現出させようとしているのだと思う。その世界を体験したと観客が思い込むことができれば、それでいい。
戦前に出た『日支事變と次に來るもの』を読んでみた ― 2018年11月19日
◎戦争の悲惨を予測した本?!
1937年(昭和12年)発行の次の古本をネットで入手して読んだ。
『日支事變と次に來るもの』(武藤貞一/新潮社)
こんな本を読もうと思ったのは、先日読んだ『日本近代史』(坂野潤治/ちくま新書)で次のように紹介しているのが気になったからである。
『盧溝橋事件の勃発からわずか二か月後に、武藤貞一の『日支事変と次に来るもの』という本が新潮社から刊行された。(…)著者の武藤は朝日新聞の論説委員ながら、対中、対英戦争への国民的覚悟を煽った軍事評論家として有名であった。(…)典型的な行け行けドンドンのジャーナリストであったらしい。(…)この好戦的で合理的な軍事評論家が1937年9月7日に発行したこの本には、驚くべき予測が並んでいる』
真珠湾攻撃の4年前に出た本書は、日本が敗戦に至るまでに体験した悲惨な状況(食糧などの物資不足、金属製品の挑発、焼夷弾に備えたモンペ姿の婦人、などなど)を、来るべき大戦の予測として描き出しているそうだ。
坂野潤治氏は次のようにも述べている。
『日米戦争を覚悟し、その結果としての焼野原をも覚悟して日中戦争を戦おうと思っていた好戦論者だけが、1937年の時点で、1945年の地獄絵を描くことができたのである』
こんな紹介を読んで、武藤という軍事評論家は本書でどんな未来図を描いたのか興味がわいた。
◎当時のベストセラー
ネット古書店で検索すると、この本は何冊か出ていた。私が入手した本書の奥付には次のように記載されていた。
昭和12年9月 7日発行
昭和12年9月13日三刷
初版五萬部
再刷二萬部
三刷三萬部
発行から1週間で2回増刷して10万部、ベストセラーだったようだ。本書巻末には同じ著者による『世界戰争は、もう始まってゐる』という書籍の1頁大の広告が載っていて「既に六萬部賈切・更に一萬部出來」とある。前著も刺激的なタイトルで売れていたようだ。
著者の武藤貞一について調べてみた。1892年生まれで、1936年に大阪朝日新聞の論説委員になり、「天声人語」も交代執筆している。1939年には報知新聞の主筆に転じ、戦後も評論活動を続け1983年に91歳で亡くなっている。
◎中国との戦いが全面戦争になるという見通し
本書は張り扇の講談のような語り口で読みやすい。論説というより床屋政談に近い。来るべき世界大戦の状況をどの程度リアルに見通していたのだろうと期待して読んだが、坂野氏が『日本近代史』で引用紹介した部分が透徹した見解のすべてで、それ以上の未来図はなかった。
武藤氏は国民に対して挙国一致で総力戦に備えよと鼓吹しているが、日中戦争の次に米英との大戦が始まるとは述べていない。中国はソ連の支援を受けていて、欧米も中国に近代兵器を供給しているので日中戦争は拡大・長期化すると述べている。ソ連参戦の可能性も検討している。
本書では敵国中国を、日本の友邦たる本来の中国ではなく、ソ連共産党に操られた「妖魔」と描いている。次のような調子である。
「よく歌舞伎芝居を觀ると、死人に化物が取憑いて踊り出すのがある。本人はくたばつてしまつてゐる、踊つてゐるのは本人でなく、本人の死體を借りものとした妖魔なのだ。支那は現に息絶えてゐる死屍だ。これに容共抗日の妖魔が乗り移つて、その抗日の毒手を全支に揮つてゐるのではないか。(…)もう一つ悲傪にも死人を踊らしてゐるものは歐米強國である。彼は粹興にも、支那人に近代武器をあてがふことを發見した。」
当時の日本人の多くがこんな見解に共感したのかもしれない。
◎ユダヤ人にも言及
現代の目から見て本書にツッコミ所が多いのは当然だが、ユダヤ人に関してヒトラーとほとんど同じユダヤ人観を展開しているのには少し驚いた。日本人にとってユダヤ人は遠い存在で関心も薄かったと思っていたし、満州ではユダヤ難民を受け入れる計画があったとも聞いていたからである。
武藤氏はソ連共産党も米国資本主義もユダヤ人が背後で操っていると述べ、欧州大戦(第一次大戦)を始めたのも終わらせたのもユダヤ人の指揮によるとしている。ユダヤ人は「戦争を起こさせる運動」と「反戦運動」の両方を操って利益を上げているという雑駁なユダヤ陰謀論である。
本書がユダヤ人問題を重視しているのは、極東ハバロフスク近傍でユダヤ人国家の建設が進んでいるからだそうだ。パレスチナではアラブ人の反発が大きく、極東でユダヤ人国家が出現することを警戒しているのである。
私には初耳の話で驚いた。調べてみると、根拠のない話ではなく、スターリンは極東にユダヤ自治州を作ったそうだ。現在、そこにユダヤ人はほとんど住んでいない。
本書が当時の日本国民にどの程度の影響力があったのかはわからないが、戦前の空気の一端に触れた気分になった。それは、始めた戦争は勝たねばならぬという、どうしようもない好戦の空気である。気をつけねばならない。
1937年(昭和12年)発行の次の古本をネットで入手して読んだ。
『日支事變と次に來るもの』(武藤貞一/新潮社)
こんな本を読もうと思ったのは、先日読んだ『日本近代史』(坂野潤治/ちくま新書)で次のように紹介しているのが気になったからである。
『盧溝橋事件の勃発からわずか二か月後に、武藤貞一の『日支事変と次に来るもの』という本が新潮社から刊行された。(…)著者の武藤は朝日新聞の論説委員ながら、対中、対英戦争への国民的覚悟を煽った軍事評論家として有名であった。(…)典型的な行け行けドンドンのジャーナリストであったらしい。(…)この好戦的で合理的な軍事評論家が1937年9月7日に発行したこの本には、驚くべき予測が並んでいる』
真珠湾攻撃の4年前に出た本書は、日本が敗戦に至るまでに体験した悲惨な状況(食糧などの物資不足、金属製品の挑発、焼夷弾に備えたモンペ姿の婦人、などなど)を、来るべき大戦の予測として描き出しているそうだ。
坂野潤治氏は次のようにも述べている。
『日米戦争を覚悟し、その結果としての焼野原をも覚悟して日中戦争を戦おうと思っていた好戦論者だけが、1937年の時点で、1945年の地獄絵を描くことができたのである』
こんな紹介を読んで、武藤という軍事評論家は本書でどんな未来図を描いたのか興味がわいた。
◎当時のベストセラー
ネット古書店で検索すると、この本は何冊か出ていた。私が入手した本書の奥付には次のように記載されていた。
昭和12年9月 7日発行
昭和12年9月13日三刷
初版五萬部
再刷二萬部
三刷三萬部
発行から1週間で2回増刷して10万部、ベストセラーだったようだ。本書巻末には同じ著者による『世界戰争は、もう始まってゐる』という書籍の1頁大の広告が載っていて「既に六萬部賈切・更に一萬部出來」とある。前著も刺激的なタイトルで売れていたようだ。
著者の武藤貞一について調べてみた。1892年生まれで、1936年に大阪朝日新聞の論説委員になり、「天声人語」も交代執筆している。1939年には報知新聞の主筆に転じ、戦後も評論活動を続け1983年に91歳で亡くなっている。
◎中国との戦いが全面戦争になるという見通し
本書は張り扇の講談のような語り口で読みやすい。論説というより床屋政談に近い。来るべき世界大戦の状況をどの程度リアルに見通していたのだろうと期待して読んだが、坂野氏が『日本近代史』で引用紹介した部分が透徹した見解のすべてで、それ以上の未来図はなかった。
武藤氏は国民に対して挙国一致で総力戦に備えよと鼓吹しているが、日中戦争の次に米英との大戦が始まるとは述べていない。中国はソ連の支援を受けていて、欧米も中国に近代兵器を供給しているので日中戦争は拡大・長期化すると述べている。ソ連参戦の可能性も検討している。
本書では敵国中国を、日本の友邦たる本来の中国ではなく、ソ連共産党に操られた「妖魔」と描いている。次のような調子である。
「よく歌舞伎芝居を觀ると、死人に化物が取憑いて踊り出すのがある。本人はくたばつてしまつてゐる、踊つてゐるのは本人でなく、本人の死體を借りものとした妖魔なのだ。支那は現に息絶えてゐる死屍だ。これに容共抗日の妖魔が乗り移つて、その抗日の毒手を全支に揮つてゐるのではないか。(…)もう一つ悲傪にも死人を踊らしてゐるものは歐米強國である。彼は粹興にも、支那人に近代武器をあてがふことを發見した。」
当時の日本人の多くがこんな見解に共感したのかもしれない。
◎ユダヤ人にも言及
現代の目から見て本書にツッコミ所が多いのは当然だが、ユダヤ人に関してヒトラーとほとんど同じユダヤ人観を展開しているのには少し驚いた。日本人にとってユダヤ人は遠い存在で関心も薄かったと思っていたし、満州ではユダヤ難民を受け入れる計画があったとも聞いていたからである。
武藤氏はソ連共産党も米国資本主義もユダヤ人が背後で操っていると述べ、欧州大戦(第一次大戦)を始めたのも終わらせたのもユダヤ人の指揮によるとしている。ユダヤ人は「戦争を起こさせる運動」と「反戦運動」の両方を操って利益を上げているという雑駁なユダヤ陰謀論である。
本書がユダヤ人問題を重視しているのは、極東ハバロフスク近傍でユダヤ人国家の建設が進んでいるからだそうだ。パレスチナではアラブ人の反発が大きく、極東でユダヤ人国家が出現することを警戒しているのである。
私には初耳の話で驚いた。調べてみると、根拠のない話ではなく、スターリンは極東にユダヤ自治州を作ったそうだ。現在、そこにユダヤ人はほとんど住んでいない。
本書が当時の日本国民にどの程度の影響力があったのかはわからないが、戦前の空気の一端に触れた気分になった。それは、始めた戦争は勝たねばならぬという、どうしようもない好戦の空気である。気をつけねばならない。
榎本武揚の評伝でその魅力を再認識 ― 2018年11月24日
◎榎本武揚の評伝は少ない
佐々木譲の小説『武揚伝(上)(中)(下)』(中公文庫)を読んだのを契機に榎本武揚に関するものを読みたくなり、次の評伝を読んだ。
『榎本武揚』(加茂儀一/中公文庫)
元版は1960年刊行、中公文庫になったのが1988年、いずれも古書でしか入手できない。現在入手できる榎本武揚の評伝はこの本ぐらいしかない。
著者の加茂儀一氏は小樽商大の学長を勤めた技術史家である。「まえがき」によれば、小樽商大学長時代に榎本武揚に関心を抱いた加茂氏は、榎本の全体像を伝える伝記が皆無だと知って本書を執筆したそうだ。
榎本の死後52年目の1960年刊行の本書は「榎本の伝記としては先駆的な意義をもつ著作」(綱淵謙錠の文庫版解説より)とされている。本書刊行から半世紀以上経過しているが、他に榎本の評伝がほとんど出ていないのが意外である。やはり不人気な人物なのか。
◎全開運転の前半生、韜晦抑制の後半生
榎本武揚の生涯は箱館戦争終結までの前半生(34歳まで)と獄中生活を経て政府高官として活躍する後半生(34歳~73歳)に分かれる。小説『武揚伝』は前半生だけの物語だったが、文庫本で約600頁のこの評伝は前半生と後半生がほぼ半分ずつの分量でバランスはいい。
とは言っても、オランダ留学から箱館戦争に至る前半生が波乱に富んでいて面白いのに対し、後半生はさまざまな局面におけるピンチヒッター的活躍の積み重ねで印象がやや散漫になる。前半生がおのれの意思で突き進む全開運転だったのに対し、薩長藩閥政権の中で元幕臣として生きる後半生はおのれの業績に口をつぐむ自己韜晦の抑制運転のように見える。
◎「共和国」という言葉は出てこない
加茂氏は薩長による幕末の討幕運動に肯定的で、幕藩体制という封建制度を突き崩すための必然と見ている。薩長に反発した榎本の評伝だからといって著者が反薩長なのではない。
戊辰戦争における榎本たちの抵抗を「感情的」とみなし、勝海舟と榎本武揚の比較では勝の方を高く評価している。勝が幕府を超えて大局的に時代を見る理性の人物だったのに対し、榎本は幕臣という意識が強すぎる感情の人物だったとしている。
箱館を制覇したとき、榎本が選挙で総裁に選ばれたことを述べてはいるが、この評伝には「蝦夷共和国」とか「共和国」という言葉は登場しない。「朝廷からは国賊と呼ばれていたのに反して、外国からは一政府としての礼遇を受け、決して謀反人として扱われなかった。榎本軍にとっては誠に光栄の至りであると同時に、わが国史上においても特筆すべき事柄である。」との記述はある。
幕末維新の変動を必然的な近代化と見なす加茂氏の見解は1960年頃にはスタンダードな考えだったのかもしれない。私は幕府対薩長をもっと相対的に評価していいのではと思っている。
◎榎本の福沢諭吉評価
本書で面白く思ったのは榎本の福沢諭吉評価である。福沢諭吉は晩年、『痩我慢の説』において勝と榎本の「変節」を厳しく糾弾し、それが今日までの榎本の低評価につながっているとも言われている。だが、榎本が獄中にいたとき、福沢は榎本の助命活動をし、榎本の求めに応じて書籍の差し入れなどもしている。
このとき、差し入れられた書籍の内容に失望した榎本が家族に宛てた手紙に次の一節がある。
「実は此方一同福沢の不見識には驚き入申候、もそつと学問のある人物と思ひしところ存外なりとて半ば歎息致候、是位の見識の学者にても百人余の弟子ありとは、我邦未だ開化文明の届かぬ事知るべし」
榎本の学問のレベルが当時の日本の標準を超えていたのだろうが、なかなかの言いようである。晩年の福沢の榎本批判の根がこんなところにあったのかもしれない。
◎榎本は全能人
この評伝の骨子は、榎本の生涯にわたる事跡を掘り起こし、同時代人には見過ごされてきた事柄を高く評価している点にある。榎本は語学の天才(オランダ語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、英語、蒙古語、ラテン語ができた)であり、化学や鉱物学をはじめ多様な科学技術への造詣が深く、国際法に通暁した外交官であり、実証的なヒューマニストでもあった。著者が箱館戦争に至る榎本を「感情の人」と見なしているのは、豪胆なヒューマニストとして評価しているのかもしれない。
著者は「世界史における大きな変革期はつねに全能な人間を生み出す」と述べ、榎本を明治維新という変革期に出現した全能人としている。
全能人を一般人が正当に評価するのは容易ではないが、やはり榎本は興味尽きない人物である。
佐々木譲の小説『武揚伝(上)(中)(下)』(中公文庫)を読んだのを契機に榎本武揚に関するものを読みたくなり、次の評伝を読んだ。
『榎本武揚』(加茂儀一/中公文庫)
元版は1960年刊行、中公文庫になったのが1988年、いずれも古書でしか入手できない。現在入手できる榎本武揚の評伝はこの本ぐらいしかない。
著者の加茂儀一氏は小樽商大の学長を勤めた技術史家である。「まえがき」によれば、小樽商大学長時代に榎本武揚に関心を抱いた加茂氏は、榎本の全体像を伝える伝記が皆無だと知って本書を執筆したそうだ。
榎本の死後52年目の1960年刊行の本書は「榎本の伝記としては先駆的な意義をもつ著作」(綱淵謙錠の文庫版解説より)とされている。本書刊行から半世紀以上経過しているが、他に榎本の評伝がほとんど出ていないのが意外である。やはり不人気な人物なのか。
◎全開運転の前半生、韜晦抑制の後半生
榎本武揚の生涯は箱館戦争終結までの前半生(34歳まで)と獄中生活を経て政府高官として活躍する後半生(34歳~73歳)に分かれる。小説『武揚伝』は前半生だけの物語だったが、文庫本で約600頁のこの評伝は前半生と後半生がほぼ半分ずつの分量でバランスはいい。
とは言っても、オランダ留学から箱館戦争に至る前半生が波乱に富んでいて面白いのに対し、後半生はさまざまな局面におけるピンチヒッター的活躍の積み重ねで印象がやや散漫になる。前半生がおのれの意思で突き進む全開運転だったのに対し、薩長藩閥政権の中で元幕臣として生きる後半生はおのれの業績に口をつぐむ自己韜晦の抑制運転のように見える。
◎「共和国」という言葉は出てこない
加茂氏は薩長による幕末の討幕運動に肯定的で、幕藩体制という封建制度を突き崩すための必然と見ている。薩長に反発した榎本の評伝だからといって著者が反薩長なのではない。
戊辰戦争における榎本たちの抵抗を「感情的」とみなし、勝海舟と榎本武揚の比較では勝の方を高く評価している。勝が幕府を超えて大局的に時代を見る理性の人物だったのに対し、榎本は幕臣という意識が強すぎる感情の人物だったとしている。
箱館を制覇したとき、榎本が選挙で総裁に選ばれたことを述べてはいるが、この評伝には「蝦夷共和国」とか「共和国」という言葉は登場しない。「朝廷からは国賊と呼ばれていたのに反して、外国からは一政府としての礼遇を受け、決して謀反人として扱われなかった。榎本軍にとっては誠に光栄の至りであると同時に、わが国史上においても特筆すべき事柄である。」との記述はある。
幕末維新の変動を必然的な近代化と見なす加茂氏の見解は1960年頃にはスタンダードな考えだったのかもしれない。私は幕府対薩長をもっと相対的に評価していいのではと思っている。
◎榎本の福沢諭吉評価
本書で面白く思ったのは榎本の福沢諭吉評価である。福沢諭吉は晩年、『痩我慢の説』において勝と榎本の「変節」を厳しく糾弾し、それが今日までの榎本の低評価につながっているとも言われている。だが、榎本が獄中にいたとき、福沢は榎本の助命活動をし、榎本の求めに応じて書籍の差し入れなどもしている。
このとき、差し入れられた書籍の内容に失望した榎本が家族に宛てた手紙に次の一節がある。
「実は此方一同福沢の不見識には驚き入申候、もそつと学問のある人物と思ひしところ存外なりとて半ば歎息致候、是位の見識の学者にても百人余の弟子ありとは、我邦未だ開化文明の届かぬ事知るべし」
榎本の学問のレベルが当時の日本の標準を超えていたのだろうが、なかなかの言いようである。晩年の福沢の榎本批判の根がこんなところにあったのかもしれない。
◎榎本は全能人
この評伝の骨子は、榎本の生涯にわたる事跡を掘り起こし、同時代人には見過ごされてきた事柄を高く評価している点にある。榎本は語学の天才(オランダ語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、英語、蒙古語、ラテン語ができた)であり、化学や鉱物学をはじめ多様な科学技術への造詣が深く、国際法に通暁した外交官であり、実証的なヒューマニストでもあった。著者が箱館戦争に至る榎本を「感情の人」と見なしているのは、豪胆なヒューマニストとして評価しているのかもしれない。
著者は「世界史における大きな変革期はつねに全能な人間を生み出す」と述べ、榎本を明治維新という変革期に出現した全能人としている。
全能人を一般人が正当に評価するのは容易ではないが、やはり榎本は興味尽きない人物である。
榎本武揚は科学技術のマイナス面にも直面していた ― 2018年11月26日
『榎本武揚と明治維新:旧幕臣の描いた近代化』(黒瀧秀久/岩波ジュニア新書)
2017年12月に出版された榎本武揚に関するコンパクトな概説書である。榎本武揚は東京農業大学の創始者であり、著者はその縁で榎本への関心を深めた東京農業大学の教授である。
本書には次のような一節がある。
「2016年に行われた日経ホールでの榎本シンポジウム後、「蝦夷共和国」に加わった子孫で北海道在住の人々は、榎本のことを語り継ぐに際し、未だに“総裁”の名称を敬愛を込めて呼ぶと語られたことに驚きと歴史の重みを改めて感じざるをえなかった」
これを読んで2年前に残念な思いをした記憶がよみがえった。ある日、新聞を広げると「東京農業大学創立125周年記念シンポジウム:創設者 榎本武揚を再評価する」という広告が目に飛び込んできた。榎本武揚がテーマとは珍しく、ぜひとも参加したい思った。しかし、日程が私の長期旅行と重なっていて参加申し込みを断念した。
そんな個人的記憶再生もあり、本書を興味深く読了した。榎本の業績紹介をメインにした内容で、箱館戦争以降の業績に多くの頁を割いている。獄中で書き綴った“実践的ハウ・ツー集成”『開成雑俎』の紹介も面白い。その中の一例として「鶏や家鴨の卵を孵化させる方法」の記述を具体的に取り上げていて、農大関係者らしい着眼だと思った。
コンパクトなジュニア新書ではあるが、加茂儀一の『榎本武揚』が触れていない事項もいくつか取り上げている。なかでも驚いたのは足尾鉱毒事件との関わりである。
足尾鉱毒事件は榎本が農商務大臣の時の事件であり、榎本はその責任を痛感して農商務大臣を辞任した後、一切の公職から手を引いたそうだ。著者の黒瀬氏は、榎本がこの事件をどのように認識していたかについて考察している。西欧の科学技術に通暁した優れた技術者であった榎本は、科学技術がもたらすマイナス面にも直面せざるを得なかったのである。
榎本武揚の生涯には歴史変動の時代の多様な課題が反映されている。
2017年12月に出版された榎本武揚に関するコンパクトな概説書である。榎本武揚は東京農業大学の創始者であり、著者はその縁で榎本への関心を深めた東京農業大学の教授である。
本書には次のような一節がある。
「2016年に行われた日経ホールでの榎本シンポジウム後、「蝦夷共和国」に加わった子孫で北海道在住の人々は、榎本のことを語り継ぐに際し、未だに“総裁”の名称を敬愛を込めて呼ぶと語られたことに驚きと歴史の重みを改めて感じざるをえなかった」
これを読んで2年前に残念な思いをした記憶がよみがえった。ある日、新聞を広げると「東京農業大学創立125周年記念シンポジウム:創設者 榎本武揚を再評価する」という広告が目に飛び込んできた。榎本武揚がテーマとは珍しく、ぜひとも参加したい思った。しかし、日程が私の長期旅行と重なっていて参加申し込みを断念した。
そんな個人的記憶再生もあり、本書を興味深く読了した。榎本の業績紹介をメインにした内容で、箱館戦争以降の業績に多くの頁を割いている。獄中で書き綴った“実践的ハウ・ツー集成”『開成雑俎』の紹介も面白い。その中の一例として「鶏や家鴨の卵を孵化させる方法」の記述を具体的に取り上げていて、農大関係者らしい着眼だと思った。
コンパクトなジュニア新書ではあるが、加茂儀一の『榎本武揚』が触れていない事項もいくつか取り上げている。なかでも驚いたのは足尾鉱毒事件との関わりである。
足尾鉱毒事件は榎本が農商務大臣の時の事件であり、榎本はその責任を痛感して農商務大臣を辞任した後、一切の公職から手を引いたそうだ。著者の黒瀬氏は、榎本がこの事件をどのように認識していたかについて考察している。西欧の科学技術に通暁した優れた技術者であった榎本は、科学技術がもたらすマイナス面にも直面せざるを得なかったのである。
榎本武揚の生涯には歴史変動の時代の多様な課題が反映されている。
榎本武揚の生涯とグローバルな世界史との関連を解読 ― 2018年11月28日
榎本武揚という名がタイトルに付されている次の新書を読んだ。
『榎本武揚から世界史が見える』(臼井隆一郎/PHP新書)
著者はドイツ・ヨーロッパ文化論の学者で、本書は榎本武揚をネタに世界史のアレコレを縦横に語る歴史エッセイである。私の知らない人物や事項がふんだんに盛り込まれていて、やや衒学的かつ文学的なところもあり、消化するのに少々骨が折れた。強引なこじつけに思える見解もあるが刺激的で面白い本である。
本書冒頭の「北溟有魚」と題する章は、極東における欧米の捕鯨とオホーツク海にまで波及したクリミア戦争を絡めた話になっている。18歳の榎本は幕府海防掛目付・堀利熈の部下として蝦夷・樺太に赴く。長崎で幕府に交渉を迫ったロシアのプチャーチンは、交渉場所を樺太のコルサロフに指定される。樺太での交渉担当者は堀利熈だったが、プチャーチンはそこに現れない。クリミア戦争の敵国イギリスがオホーツク海の制海権を握っていたからである。そんな逸話とメルヴィルの『白鯨』を織り込んだ鯨油文明の話が絡んでいて気宇壮大である。
著者は、榎本の生涯は「クリミア戦争で始まり、日露戦争戦争で終わった」とし、世界史的な事象に榎本の生涯がどう絡んでいるかを語っている。クリミア戦争はヨーロッパの国民国家形成時代の幕開けを告げる世界戦争であり、日露戦争終結の時点で世界は第一次世界大戦への陣形整備を完了する。つまり、榎本の生きた時代とは国民国家が領土国家として成立し、領土の確定と取り合いに終始した時代だった。それが著者の見方である。
19世紀から20世紀初頭にかけての国民国家成立の物語を主旋律としたこの歴史エッセイは、欧米、ロシア、日本、中国、朝鮮から南米の事情にまで言及している。その中で特にドイツに焦点をあてている。統一ドイツが存在しない状態からプロイセンを中心にした国民国家が形成され、それが大きな力をつけていく過程が日本の近代化と照応しているからである。
本書の舞台回しは榎本とは別にもう一人いる。マックス・フォン・ブラントというプロイセンの軍人外交官である。榎本と直接の関わりは少ないが、日本との関わりは深い。著者は次のように紹介している。
「ブラントは1835年生まれ。1836年生まれの榎本武揚とはほぼ同年齢である。プロセン人ブラントと旧幕臣・榎本武揚とは、幕末から戊辰戦争を越えて朝鮮をめぐる日清・日露戦争に至るまで、対照的な軌跡を描いていくことになる。」
榎本やブラントをはじめ多様な人物を配した逸話を語りながら、その個別で具体的な事象を世界史的・地球的なマクロな視点で解読しているのが本書の面白さである。
『榎本武揚から世界史が見える』(臼井隆一郎/PHP新書)
著者はドイツ・ヨーロッパ文化論の学者で、本書は榎本武揚をネタに世界史のアレコレを縦横に語る歴史エッセイである。私の知らない人物や事項がふんだんに盛り込まれていて、やや衒学的かつ文学的なところもあり、消化するのに少々骨が折れた。強引なこじつけに思える見解もあるが刺激的で面白い本である。
本書冒頭の「北溟有魚」と題する章は、極東における欧米の捕鯨とオホーツク海にまで波及したクリミア戦争を絡めた話になっている。18歳の榎本は幕府海防掛目付・堀利熈の部下として蝦夷・樺太に赴く。長崎で幕府に交渉を迫ったロシアのプチャーチンは、交渉場所を樺太のコルサロフに指定される。樺太での交渉担当者は堀利熈だったが、プチャーチンはそこに現れない。クリミア戦争の敵国イギリスがオホーツク海の制海権を握っていたからである。そんな逸話とメルヴィルの『白鯨』を織り込んだ鯨油文明の話が絡んでいて気宇壮大である。
著者は、榎本の生涯は「クリミア戦争で始まり、日露戦争戦争で終わった」とし、世界史的な事象に榎本の生涯がどう絡んでいるかを語っている。クリミア戦争はヨーロッパの国民国家形成時代の幕開けを告げる世界戦争であり、日露戦争終結の時点で世界は第一次世界大戦への陣形整備を完了する。つまり、榎本の生きた時代とは国民国家が領土国家として成立し、領土の確定と取り合いに終始した時代だった。それが著者の見方である。
19世紀から20世紀初頭にかけての国民国家成立の物語を主旋律としたこの歴史エッセイは、欧米、ロシア、日本、中国、朝鮮から南米の事情にまで言及している。その中で特にドイツに焦点をあてている。統一ドイツが存在しない状態からプロイセンを中心にした国民国家が形成され、それが大きな力をつけていく過程が日本の近代化と照応しているからである。
本書の舞台回しは榎本とは別にもう一人いる。マックス・フォン・ブラントというプロイセンの軍人外交官である。榎本と直接の関わりは少ないが、日本との関わりは深い。著者は次のように紹介している。
「ブラントは1835年生まれ。1836年生まれの榎本武揚とはほぼ同年齢である。プロセン人ブラントと旧幕臣・榎本武揚とは、幕末から戊辰戦争を越えて朝鮮をめぐる日清・日露戦争に至るまで、対照的な軌跡を描いていくことになる。」
榎本やブラントをはじめ多様な人物を配した逸話を語りながら、その個別で具体的な事象を世界史的・地球的なマクロな視点で解読しているのが本書の面白さである。

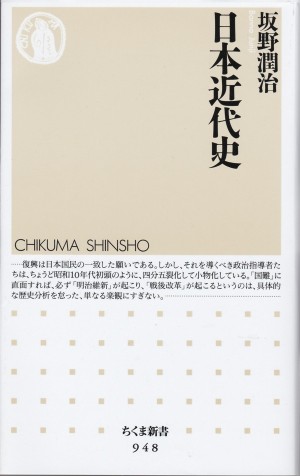






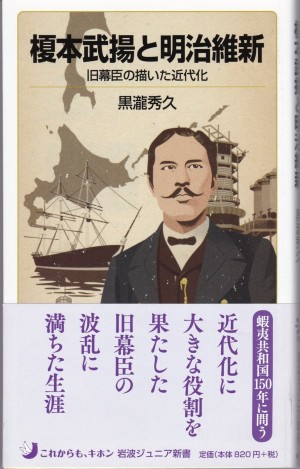

最近のコメント