山田風太郎の奇怪な忠臣蔵を読んだ ― 2024年12月30日
『元禄忠臣蔵』に続いて『うろんなり助左衛門』を読み、未読の忠臣蔵本が気がかりになり、本棚に眠っていた次の2冊を読んだ。
『妖説忠臣蔵』(山田風太郎/集英社文庫)
『忍法忠臣蔵』(山田風太郎/講談社)
2冊とも奇想の作家・山田風太郎のかなり古いエンタメ小説である。
短編集『妖説忠臣蔵』には「赤穂飛脚」「殺人蔵」「蟲臣蔵」「俺も四十七士」「生きている上野介」の5編を収録している。どれも、それぞれに面白い。
ドンデン返しミステリーの「生きている上野介」は討入り後に世間から蔑まれる脱盟者らの鬱屈を表現して秀逸だ。「俺も四十七士」は四十七士でありながら無名に近い人物の哀感に焦点をあてた皮肉小説である。
長編『忍法忠臣蔵』は山田風太郎忍法全集の1冊である。荒唐無稽な忍法に頭がクラクラしてくる。風太郎の独壇場だ。上杉の家老千坂兵部が、赤穂浪士を女色に溺れさせて仇討ちを骨抜きにしようと、女忍者たちを放つ話である。闊達なエロ・グロ・ナンセンンスの奇怪な世界が繰り広げられる。「忠義が嫌い」とうそぶく伊賀忍者を主人公にしている所に作者の反骨を感じる。
『妖説忠臣蔵』(山田風太郎/集英社文庫)
『忍法忠臣蔵』(山田風太郎/講談社)
2冊とも奇想の作家・山田風太郎のかなり古いエンタメ小説である。
短編集『妖説忠臣蔵』には「赤穂飛脚」「殺人蔵」「蟲臣蔵」「俺も四十七士」「生きている上野介」の5編を収録している。どれも、それぞれに面白い。
ドンデン返しミステリーの「生きている上野介」は討入り後に世間から蔑まれる脱盟者らの鬱屈を表現して秀逸だ。「俺も四十七士」は四十七士でありながら無名に近い人物の哀感に焦点をあてた皮肉小説である。
長編『忍法忠臣蔵』は山田風太郎忍法全集の1冊である。荒唐無稽な忍法に頭がクラクラしてくる。風太郎の独壇場だ。上杉の家老千坂兵部が、赤穂浪士を女色に溺れさせて仇討ちを骨抜きにしようと、女忍者たちを放つ話である。闊達なエロ・グロ・ナンセンンスの奇怪な世界が繰り広げられる。「忠義が嫌い」とうそぶく伊賀忍者を主人公にしている所に作者の反骨を感じる。
末裔が書いた『うろんなり助左衛門』は面白い ― 2024年12月27日
『元禄忠臣蔵』を読んで、にわかに気がかりになったのが次の本である。約20年間書架で眠っていたのを引っ張り出し、一気に読了した。
『うろんなり助左衛門:ある赤穂浪士とその末裔』(冨森叡児/草思社/2002.12)
四十七士の一人・冨森助右衛門の名はいろいろな忠臣蔵モノで目にする。あまりクローズアップされる人物ではなく、印象は希薄である。だが、『元禄忠臣蔵』の白眉「御浜御殿綱豊卿」は冨森助右衛門が主役だった。で、助右衛門の末裔が書いた本書を思い出した。
著者の冨森叡児(1928-2018)は、朝日新聞の政治部長、編集局長、常務取締役だった新聞人である。自分が赤穂義士の末裔と知ったのは著者が小学生の頃だそうだ。両親とも筋金入りのクリスチャン(父は同志社大学神学科教授)で、ご先祖の赤穂義士については、あまり語らなかったらしい。
本書は著者のルーツ探しの報告書であり、助右衛門はどんな人物だったかを探求した本である。
ルーツ探しは部外者の関心を惹く話ではないが、探究のアレコレはスリリングだった。冨森家は助右衛門の数代後に断絶していて、かなりの年月が経過した幕末になって養子を立てて再興したそうだ。四十七士のなかで今日まで直系血脈を保っているのは大石、原の両家だけらしい。家系とは断絶するのが普通のようだ。
著者が提示した助右衛門像は面白い。助右衛門は江戸詰めの有能な武士官僚で、マイホーム主義だった。しかも金持ちだった。資産家の商人が縁戚にいたらしい。したがって、周囲からは「うろんな奴」と見られ、討ち入りに参加するとは思われていなっかったようだ。
著者は、助右衛門が討ち入りに参加した理由を、当時の時代情況に絡めて推理している。ジャーナリストらしい見方が興味深い。
史実の探究とは別に、忠臣蔵モノの小説で助右衛門がどう扱われているかにも言及している。『赤穂浪士』(大佛次郎)、『新編忠臣蔵』(吉川英治)、『新・忠臣蔵』(船橋聖一)、『忠臣蔵』(森村誠一)などに登場する助右衛門は、さほど重要な役割は担っていない。主役を担っているのは『御浜御殿綱豊卿』(真山青果『元禄忠臣蔵』)である。『四十七人の刺客』(池宮彰一郎)でも助右衛門が活躍する。
私は上記の小説を読んでいるが、その内容はかなり失念している。『四十七人の刺客』の助右衛門も忘れていた。
『うろんなり助左衛門:ある赤穂浪士とその末裔』(冨森叡児/草思社/2002.12)
四十七士の一人・冨森助右衛門の名はいろいろな忠臣蔵モノで目にする。あまりクローズアップされる人物ではなく、印象は希薄である。だが、『元禄忠臣蔵』の白眉「御浜御殿綱豊卿」は冨森助右衛門が主役だった。で、助右衛門の末裔が書いた本書を思い出した。
著者の冨森叡児(1928-2018)は、朝日新聞の政治部長、編集局長、常務取締役だった新聞人である。自分が赤穂義士の末裔と知ったのは著者が小学生の頃だそうだ。両親とも筋金入りのクリスチャン(父は同志社大学神学科教授)で、ご先祖の赤穂義士については、あまり語らなかったらしい。
本書は著者のルーツ探しの報告書であり、助右衛門はどんな人物だったかを探求した本である。
ルーツ探しは部外者の関心を惹く話ではないが、探究のアレコレはスリリングだった。冨森家は助右衛門の数代後に断絶していて、かなりの年月が経過した幕末になって養子を立てて再興したそうだ。四十七士のなかで今日まで直系血脈を保っているのは大石、原の両家だけらしい。家系とは断絶するのが普通のようだ。
著者が提示した助右衛門像は面白い。助右衛門は江戸詰めの有能な武士官僚で、マイホーム主義だった。しかも金持ちだった。資産家の商人が縁戚にいたらしい。したがって、周囲からは「うろんな奴」と見られ、討ち入りに参加するとは思われていなっかったようだ。
著者は、助右衛門が討ち入りに参加した理由を、当時の時代情況に絡めて推理している。ジャーナリストらしい見方が興味深い。
史実の探究とは別に、忠臣蔵モノの小説で助右衛門がどう扱われているかにも言及している。『赤穂浪士』(大佛次郎)、『新編忠臣蔵』(吉川英治)、『新・忠臣蔵』(船橋聖一)、『忠臣蔵』(森村誠一)などに登場する助右衛門は、さほど重要な役割は担っていない。主役を担っているのは『御浜御殿綱豊卿』(真山青果『元禄忠臣蔵』)である。『四十七人の刺客』(池宮彰一郎)でも助右衛門が活躍する。
私は上記の小説を読んでいるが、その内容はかなり失念している。『四十七人の刺客』の助右衛門も忘れていた。
『元禄忠臣蔵』はエピソードの戯曲集 ― 2024年12月26日
年末である。忠臣蔵を読みたくなった。私は、かなり以前に忠臣蔵にハマった時期があり、かなりの忠臣蔵モノを読んだ。と言っても、この10年ほどはほとんど読んでいない。書店で忠臣蔵モノを見つけるとつい購入することが多かったので、未読本も少なくない。気がかりだった次の忠臣蔵を読んだ。
『元禄忠臣蔵(上)(下)』(真山青果/岩波文庫)
本書は高名な戯曲である。上下2巻と長いので、赤穂事件の全貌を描いた大河ドラマのような作品だと思っていた。だが、少し違っていた。
昭和初期に発表された本書は新歌舞伎の戯曲集である。10編の連作であり、それぞれが独立して上演されたようだ。エピソード集に近い。全10編のタイトルは以下の通りである。
(1) 江戸城の刃傷
(2) 第二の使者
(3) 最後の大評定
(4) 伏見撞木町
(5) 御浜御殿綱豊卿
(6) 南部坂雪の別れ
(7) 吉良屋敷裏門
(8) 泉岳寺
(9) 仙石屋敷
(10) 大石最後の一日
この並びは出来事の時系列だが、(7)と(8)は時間が多少重なっている。(8)は(7)の末尾から少し時間が遡った時点から始まる。10編の戯曲は、1934年(昭和9年)から1940年(昭和15年)にかけて雑誌(『日の出』『キング』)に掲載された。最初の作品は「(10) 大石最後の一日」、最後の作品は「(5) 御浜御殿綱豊卿」だから、発表は時系列ではない。
各作品のト書き部分は、史伝エッセイの趣もある。著者は史書に基づいた歴史小説のつもりでこの戯曲を書いたのかもしれない。
本書に討ち入りのシーンはなく、全体として討ち入り後の話にウエイトがある。「(8) 泉岳寺」は、討ち入り後に泉岳寺に駆け付けた高田群兵衛(脱盟者)の件りが面白い。
全10編のなかで私が一番惹かれたのは「(5) 御浜御殿綱豊卿」である。甲府家当主綱豊(綱吉の次に将軍になる家宣)と冨森助右衛門の話である。綱豊のお浜御殿(いまの浜離宮)での催しに吉良上野介が来ると知った助右衛門は、忍び込んで上野介の顔を確認しようと画策する。赤穂浪士の討ち入りを期待している綱豊は助右衛門と面談しようとする――という展開である。
私はこのエピソードを知らなかった。どこかで読んでいたとしても失念している。だから興味深く読んだ。韜晦する綱豊と、それを見抜く助右衛門の緊張感をはらんだやり取りが面白い。
『元禄忠臣蔵(上)(下)』(真山青果/岩波文庫)
本書は高名な戯曲である。上下2巻と長いので、赤穂事件の全貌を描いた大河ドラマのような作品だと思っていた。だが、少し違っていた。
昭和初期に発表された本書は新歌舞伎の戯曲集である。10編の連作であり、それぞれが独立して上演されたようだ。エピソード集に近い。全10編のタイトルは以下の通りである。
(1) 江戸城の刃傷
(2) 第二の使者
(3) 最後の大評定
(4) 伏見撞木町
(5) 御浜御殿綱豊卿
(6) 南部坂雪の別れ
(7) 吉良屋敷裏門
(8) 泉岳寺
(9) 仙石屋敷
(10) 大石最後の一日
この並びは出来事の時系列だが、(7)と(8)は時間が多少重なっている。(8)は(7)の末尾から少し時間が遡った時点から始まる。10編の戯曲は、1934年(昭和9年)から1940年(昭和15年)にかけて雑誌(『日の出』『キング』)に掲載された。最初の作品は「(10) 大石最後の一日」、最後の作品は「(5) 御浜御殿綱豊卿」だから、発表は時系列ではない。
各作品のト書き部分は、史伝エッセイの趣もある。著者は史書に基づいた歴史小説のつもりでこの戯曲を書いたのかもしれない。
本書に討ち入りのシーンはなく、全体として討ち入り後の話にウエイトがある。「(8) 泉岳寺」は、討ち入り後に泉岳寺に駆け付けた高田群兵衛(脱盟者)の件りが面白い。
全10編のなかで私が一番惹かれたのは「(5) 御浜御殿綱豊卿」である。甲府家当主綱豊(綱吉の次に将軍になる家宣)と冨森助右衛門の話である。綱豊のお浜御殿(いまの浜離宮)での催しに吉良上野介が来ると知った助右衛門は、忍び込んで上野介の顔を確認しようと画策する。赤穂浪士の討ち入りを期待している綱豊は助右衛門と面談しようとする――という展開である。
私はこのエピソードを知らなかった。どこかで読んでいたとしても失念している。だから興味深く読んだ。韜晦する綱豊と、それを見抜く助右衛門の緊張感をはらんだやり取りが面白い。
舞台『しゃぼん玉』の原作小説で四国・九州問題を解明 ― 2024年12月23日
先日観た劇団文化座の芝居『しゃぼん玉』の原作小説を読んだ。
『しゃぼん玉』(乃南アサ/新潮文庫)
芝居の冒頭シーンは深夜の山道である。トラックから降ろされて置き去りにされた主人公の若者が、去って行くトラックに悪態をつく。なぜ、そんな事態になったのかは、やがて判明する。トラックをヒッチハイクした主人公は、運転手をナイフで脅してトラック・ジャックしていたのだ。だが、うかつにも居眠りをしたために山の中に置き去りにされたのである。
夜が明け、老婆に出会い、山村に迷い込んだ主人公は、ここが九州の山奥だと知って驚く。本人は四国の山奥だと思っていたのだ。何の予備知識もなしに観劇していた私は、四国と九州がワープする異空間の山村の物語なのだろうかと想像してしまった。だが、その後の展開は超現実とは無縁だった。簡単に言えば、犯罪に走った若者が更生する物語である。いい話だった。
それにしても、四国と思った場所がなぜ九州だったのかがわからない。それを確認するために原作の文庫本を入手して読んだ。
原作を読んで、私の疑問は氷塊した。大学を中退した落ちこぼれの主人公は地理に無知だったのだ。行くあてのない主人公は、宮崎に行くというトラックをヒッチハイクし、宮崎は四国にあると思い込んでいたのである。それだけである。
文化座代表の佐々木愛はこの小説を読んだとき、すぐに舞台化したいと思ったそうだ。この小説は2016年に映画化されている(出演:林遣都、市原悦子、他)。芝居の初演(2017年)の準備をしているとき、すでに映画化されていることを知ったが、迷うことなく舞台化を進めたという。それだけ、原作に魅力があったのだろう。
舞台で内容を知っている私が原作を読もうと思ったのも、単に「四国・九州問題」確認のためだけではなかったかもしれない。芝居の内容を原作で追体験したかったのだ。読んだ人を映画化・舞台化に駆り立てる原作の魅力を確認したかったのだと思う。
『しゃぼん玉』は粗筋だけでは陳腐に思える物語である。しかし、小説家の筆力によって独特の世界を紡ぎあげている。読み始めるとグイグイ引き込まれてしまった。
『しゃぼん玉』(乃南アサ/新潮文庫)
芝居の冒頭シーンは深夜の山道である。トラックから降ろされて置き去りにされた主人公の若者が、去って行くトラックに悪態をつく。なぜ、そんな事態になったのかは、やがて判明する。トラックをヒッチハイクした主人公は、運転手をナイフで脅してトラック・ジャックしていたのだ。だが、うかつにも居眠りをしたために山の中に置き去りにされたのである。
夜が明け、老婆に出会い、山村に迷い込んだ主人公は、ここが九州の山奥だと知って驚く。本人は四国の山奥だと思っていたのだ。何の予備知識もなしに観劇していた私は、四国と九州がワープする異空間の山村の物語なのだろうかと想像してしまった。だが、その後の展開は超現実とは無縁だった。簡単に言えば、犯罪に走った若者が更生する物語である。いい話だった。
それにしても、四国と思った場所がなぜ九州だったのかがわからない。それを確認するために原作の文庫本を入手して読んだ。
原作を読んで、私の疑問は氷塊した。大学を中退した落ちこぼれの主人公は地理に無知だったのだ。行くあてのない主人公は、宮崎に行くというトラックをヒッチハイクし、宮崎は四国にあると思い込んでいたのである。それだけである。
文化座代表の佐々木愛はこの小説を読んだとき、すぐに舞台化したいと思ったそうだ。この小説は2016年に映画化されている(出演:林遣都、市原悦子、他)。芝居の初演(2017年)の準備をしているとき、すでに映画化されていることを知ったが、迷うことなく舞台化を進めたという。それだけ、原作に魅力があったのだろう。
舞台で内容を知っている私が原作を読もうと思ったのも、単に「四国・九州問題」確認のためだけではなかったかもしれない。芝居の内容を原作で追体験したかったのだ。読んだ人を映画化・舞台化に駆り立てる原作の魅力を確認したかったのだと思う。
『しゃぼん玉』は粗筋だけでは陳腐に思える物語である。しかし、小説家の筆力によって独特の世界を紡ぎあげている。読み始めるとグイグイ引き込まれてしまった。
中世を舞台にした『バウドリーノ』は奇怪な小説 ― 2024年12月19日
あの『薔薇の名前』のウンベルト・エーコに十字軍を扱った小説があると知り、読みたくなった。ビザンツ史や神聖ローマ皇帝フェデリコ2世は私の関心領域なので、どんな話か興味がわいたのである。
『バウドリーノ(上)(下)』(ウンベルト・エーコ/堤康徳訳/岩波文庫)
この小説はさほど衒学的ではなく難解でもない。エンタメに近いと思う。読み始めてしばらくは、サラサラと読了できそうな気がした。だが、思った以上に時間を要した。頭がゴチャゴチャすることも多かった。10年前の私なら途中で投げていたと思う。西欧中世史やビザンツ史に関する多少の知識がないと、この小説の世界には入り込みにくい。私はこの10年で多少は歴史の本に親しんできたので、何とか読み進めることができた。
上巻のカバー裏には次の惹句がある。
「時は中世、十字軍の時代――。神聖ローマ皇帝フリードリヒ・バルバロッサに気に入られて養子となった農民の子バウドリーノが語りだす数奇な生涯とは……。言語の才に恵まれ、語る嘘がことごとく真実となってしまうバウドリーノの、西洋と東洋をまたにかけた大冒険がはじまる。」
確かにこの惹句通りの内容だが、歴史小説や冒険小説とは呼び難い。面妖で奇怪な小説である。前半と後半で雰囲気が異なる。前半は、中世の史実をベースに想像力をふくらませたフィクションの趣だが、後半になるとプリニウスが描くような怪人が登場し、妖怪小説になる。ゲゲゲの鬼太郎のような展開に面食らった。終盤はシャーロック・ホームズである。波長が合えば楽しめるが、波長がずれると「何じゃこれは」という気分になる。私は、波長を合わせる努力をしながら読み進めた。
特異な才をもつ農民の子バウドリーノは、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(1122年~1190年)に拾われ、側近として皇帝が没するまで仕える。その後、第4回十字軍がコンスタンティノープルを攻撃したとき(1204年)、バウドリーノはビザンツの歴史家ニケタス(実在の人物)を救出する。
この小説の大部分は、バウドリーノがニケタスに語る自身の半生の物語である。バウドリーノは、自分には嘘を語る才があると述べている。だから、彼が語る物語(この小説の大部分)のどこまでが事実かが不明という趣向になっている。
虚実の混じった物語ではあるが、私が歴史書で興味を抱いた人物への言及に出会うとうれしくなった。アレクサンドリアの女性学者ヒュパティアが出てきたのには驚いた。彼女は古代末期の人だから、登場するのはその末裔のヒュパティア一族である。キリスト教を批判するヒュパティアの神談義も興味深い。理解できたわけではないが…。
『バウドリーノ(上)(下)』(ウンベルト・エーコ/堤康徳訳/岩波文庫)
この小説はさほど衒学的ではなく難解でもない。エンタメに近いと思う。読み始めてしばらくは、サラサラと読了できそうな気がした。だが、思った以上に時間を要した。頭がゴチャゴチャすることも多かった。10年前の私なら途中で投げていたと思う。西欧中世史やビザンツ史に関する多少の知識がないと、この小説の世界には入り込みにくい。私はこの10年で多少は歴史の本に親しんできたので、何とか読み進めることができた。
上巻のカバー裏には次の惹句がある。
「時は中世、十字軍の時代――。神聖ローマ皇帝フリードリヒ・バルバロッサに気に入られて養子となった農民の子バウドリーノが語りだす数奇な生涯とは……。言語の才に恵まれ、語る嘘がことごとく真実となってしまうバウドリーノの、西洋と東洋をまたにかけた大冒険がはじまる。」
確かにこの惹句通りの内容だが、歴史小説や冒険小説とは呼び難い。面妖で奇怪な小説である。前半と後半で雰囲気が異なる。前半は、中世の史実をベースに想像力をふくらませたフィクションの趣だが、後半になるとプリニウスが描くような怪人が登場し、妖怪小説になる。ゲゲゲの鬼太郎のような展開に面食らった。終盤はシャーロック・ホームズである。波長が合えば楽しめるが、波長がずれると「何じゃこれは」という気分になる。私は、波長を合わせる努力をしながら読み進めた。
特異な才をもつ農民の子バウドリーノは、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(1122年~1190年)に拾われ、側近として皇帝が没するまで仕える。その後、第4回十字軍がコンスタンティノープルを攻撃したとき(1204年)、バウドリーノはビザンツの歴史家ニケタス(実在の人物)を救出する。
この小説の大部分は、バウドリーノがニケタスに語る自身の半生の物語である。バウドリーノは、自分には嘘を語る才があると述べている。だから、彼が語る物語(この小説の大部分)のどこまでが事実かが不明という趣向になっている。
虚実の混じった物語ではあるが、私が歴史書で興味を抱いた人物への言及に出会うとうれしくなった。アレクサンドリアの女性学者ヒュパティアが出てきたのには驚いた。彼女は古代末期の人だから、登場するのはその末裔のヒュパティア一族である。キリスト教を批判するヒュパティアの神談義も興味深い。理解できたわけではないが…。
光州事件を描いた『少年が来る』は生々しい ― 2024年12月04日
今年のノーベル文学賞受賞者ハン・ガンの『菜食主義者』に続いて『少年が来る』を読んだ。これも慄然とする小説だった。
『少年が来る』(ハン・ガン/井出俊作訳/クオン)
光州事件を扱った小説だとは聞いていたが、想定以上に生々しい内容だった。そして、沈沈たる空気をたたえた文学作品だった。
光州事件とは、軍事政権下で民主化を求める学生・市民を軍が武力で制圧した事件である。武器を携えた学生・市民もいて、多数の死傷者が出た。死者の数は170人と発表されたが、その数倍とも言われている。この小説にも多くの死体が登場する。死者が主人公とも言える。先日観た映画『シヴィル・ウォー』を連想した。
この小説は記録に基づいているのだと思う。登場人物にモデルがいるのかもしれない。エピローグには、著者を思わせる「私」が登場人物の縁者から執筆の許可を得る場面もある。だが、この小説は記録文学というよりは内面の物語である。
本書からは、軍事政権から民主化へ転換してきた韓国現代史の壮絶な面が伝わってくる。安保闘争や全共闘の日本の戦後史がヤワに見えてしまう。壮絶な同時代史の当事者がその体験を文学に昇華するのは容易でない。語り得ぬこと、伝え難きことの一人称での言語化は難しい。
光州事件が起きたのは1980年5月、著者が10歳のときである。10歳の「私」の見聞も語られているが、著者は当事者ではない。同時代の空気を知っている「後世の人」だ。本書の「5章 夜の瞳」は、当時の体験の証言を求められた当事者が何度も拒絶しつつ逡巡する話である。死を賭した闘争・革命・熱狂・熱情の後の虚脱・諦観に人の世の酷薄を感じる。光州事件の現場と当事者のその後を描いた『少年が来る』は二人称を多用している。作者が「後世の人」だからこそ描き得た物語に思える。
本書のエピローグの印象に残った一節を引用する。
「その経験は放射能被曝と似ています、と語る拷問を受けた生存者のインタビュー読んだ。骨と筋肉に付着した放射性物質が数十年間、体内にとどまって染色体を変形させる。細胞をがんにして生命を攻撃する。」
P.S.
この読後感をポストするとき、「韓国で戒厳令発令」のニュースが流れ、目を疑った。タイムスリップ感覚だった。すぐに解除されたようだが。
『少年が来る』(ハン・ガン/井出俊作訳/クオン)
光州事件を扱った小説だとは聞いていたが、想定以上に生々しい内容だった。そして、沈沈たる空気をたたえた文学作品だった。
光州事件とは、軍事政権下で民主化を求める学生・市民を軍が武力で制圧した事件である。武器を携えた学生・市民もいて、多数の死傷者が出た。死者の数は170人と発表されたが、その数倍とも言われている。この小説にも多くの死体が登場する。死者が主人公とも言える。先日観た映画『シヴィル・ウォー』を連想した。
この小説は記録に基づいているのだと思う。登場人物にモデルがいるのかもしれない。エピローグには、著者を思わせる「私」が登場人物の縁者から執筆の許可を得る場面もある。だが、この小説は記録文学というよりは内面の物語である。
本書からは、軍事政権から民主化へ転換してきた韓国現代史の壮絶な面が伝わってくる。安保闘争や全共闘の日本の戦後史がヤワに見えてしまう。壮絶な同時代史の当事者がその体験を文学に昇華するのは容易でない。語り得ぬこと、伝え難きことの一人称での言語化は難しい。
光州事件が起きたのは1980年5月、著者が10歳のときである。10歳の「私」の見聞も語られているが、著者は当事者ではない。同時代の空気を知っている「後世の人」だ。本書の「5章 夜の瞳」は、当時の体験の証言を求められた当事者が何度も拒絶しつつ逡巡する話である。死を賭した闘争・革命・熱狂・熱情の後の虚脱・諦観に人の世の酷薄を感じる。光州事件の現場と当事者のその後を描いた『少年が来る』は二人称を多用している。作者が「後世の人」だからこそ描き得た物語に思える。
本書のエピローグの印象に残った一節を引用する。
「その経験は放射能被曝と似ています、と語る拷問を受けた生存者のインタビュー読んだ。骨と筋肉に付着した放射性物質が数十年間、体内にとどまって染色体を変形させる。細胞をがんにして生命を攻撃する。」
P.S.
この読後感をポストするとき、「韓国で戒厳令発令」のニュースが流れ、目を疑った。タイムスリップ感覚だった。すぐに解除されたようだが。
『大いなる遺産』に格差社会のアレコレを感じた ― 2024年12月02日
ディケンズの『大いなる遺産』を読んだ。今年の年頭、『20の古典で読み解く世界史』を読んだとき、そこで紹介していたこの長編を読みたくなり、すぐに購入した。だが、読み始めるのは年末になってしまった。
『大いなる遺産(上)(下)』(ディケンズ/加賀山卓朗訳/新潮文庫)
ディケンズは、子供の頃にジュニア版の『クリスマス・キャロル』を読んだだけだ。この高名な作家についてほとんど何も知らなかったが、本書を読了して「やはり、英国人作家だ」と感じた。フランス、ドイツ、ロシアなどの作家とは異なる独特の英国風イメージをまとっている。
ディケンズは19世紀の作家である。9年前、21世紀は19世紀になるかもしれないというピケティの『21世紀の資本』の指摘に接し、19世紀西欧文学が表出する社会・経済への関心が高まった。『大いなる遺産』からも19世紀世界を窺うことができる。
この小説から得たイメージは「格差社会」のアレコレである。労働者社会と資産家社会を行き来する主人公の心境や視線の変遷が、19世紀英国の格差社会を見事に描き出している。20世紀には前時代的に見えたものが、21世紀になると同時代的に思えるとすれば暗然とする。私は、この小説は前時代のクラシックなものと捉えているのだが…。
『大いなる遺産』は、やや不自然でご都合主義に感じる設定はあるものの、プロットの芯は秀逸で、面白い物語になっている。アレコレの伏線の回収や因果めいた展開が造りものめいていても、そこにクラシックな歌舞伎のような雰囲気を感じた。
この小説の主人公がどの程度まで読者の共感を得られるか、私にはよくわからない。だが、ラストシーンの余韻に深みを感じた。
『大いなる遺産(上)(下)』(ディケンズ/加賀山卓朗訳/新潮文庫)
ディケンズは、子供の頃にジュニア版の『クリスマス・キャロル』を読んだだけだ。この高名な作家についてほとんど何も知らなかったが、本書を読了して「やはり、英国人作家だ」と感じた。フランス、ドイツ、ロシアなどの作家とは異なる独特の英国風イメージをまとっている。
ディケンズは19世紀の作家である。9年前、21世紀は19世紀になるかもしれないというピケティの『21世紀の資本』の指摘に接し、19世紀西欧文学が表出する社会・経済への関心が高まった。『大いなる遺産』からも19世紀世界を窺うことができる。
この小説から得たイメージは「格差社会」のアレコレである。労働者社会と資産家社会を行き来する主人公の心境や視線の変遷が、19世紀英国の格差社会を見事に描き出している。20世紀には前時代的に見えたものが、21世紀になると同時代的に思えるとすれば暗然とする。私は、この小説は前時代のクラシックなものと捉えているのだが…。
『大いなる遺産』は、やや不自然でご都合主義に感じる設定はあるものの、プロットの芯は秀逸で、面白い物語になっている。アレコレの伏線の回収や因果めいた展開が造りものめいていても、そこにクラシックな歌舞伎のような雰囲気を感じた。
この小説の主人公がどの程度まで読者の共感を得られるか、私にはよくわからない。だが、ラストシーンの余韻に深みを感じた。
『ロボット(R.U.R.)』を半世紀ぶりに再読した ― 2024年11月19日
今週末『ロボット』という芝居を観る予定だ。チャペックの有名作『RUR』の上演である。ロボットという言葉は、チェコ語のrobota(賦役)が語源で、1920年に発表されたこの作品から生まれた。
私は半世紀以上昔、この戯曲を『SFマガジン』で読んでいる。内容はほとんど失念している。ロボットの反乱の話だとの記憶はある。この作品が戯曲という珍しい形式だったことが強く印象に残っている。
観劇前に岩波文庫版を入手して再読した。
『ロボット(R.U.R.)』(チャペック/千野栄一訳/岩波文庫)
この文庫を読んだ後、念のために本棚の奥底の古いSFマガジンを探索した。処分した号も多いのだが『RUR』が載った1964年8月臨時増刊号(60年前だ)は残っていた。「名作古典」と紹介されている。深町真理子訳なので重訳かもしれない。岩波文庫版と突き合わせてみて、多少の食い違いに気づいた。SFマガジン版が簡略化されている箇所があり、その逆のケースもある。戯曲は上演のたびに変化することもある。いくつかの版があるのだと思う。
チャペックの元祖ロボットは機械人形ではなく合成人間である。その工場は薬品などを駆使する化学工場だ。昔読んだときは、フランケンシュタインに近いクラシックで古臭い設定だとの印象を受けた。だが、生命工学が発展しつつある現在では、合成人間製造の生化学工場の方が機機械工場より新しいと感じる。
この戯曲を読みながら、半世紀以上昔の初読のときの印象が少しよみがえってきた。私はロボットを労働者の寓意だととらえ、この作品は寓話SFだと思った。『RUR』が発表されたのはロシア革命の数年後だった。
今回の再読で、単純な寓話とは言えないと感じた。ロボットの反乱によって、ただ一人を除いてすべての人間が殺されてしまう。しかし、ロボットたちは自身の再生産の手段を知らず、ロボットも絶滅の危機を迎える。そしてラストシーンで、ロボットのアダムとイブが人間として再生すると予感させる。寓話というよりは神話である。
このやや不自然な設定の物語は、小説ではなく舞台でなければ表現しにくいだろうと思えた。観劇予定の『ロボット』のチラシには「2024年に生きる人々に向けて、シニカルかつ不条理なドラマとして転換し、現代の物語としてお届けします。」とある。百年前の戯曲をどう料理するのか楽しみである。
私は半世紀以上昔、この戯曲を『SFマガジン』で読んでいる。内容はほとんど失念している。ロボットの反乱の話だとの記憶はある。この作品が戯曲という珍しい形式だったことが強く印象に残っている。
観劇前に岩波文庫版を入手して再読した。
『ロボット(R.U.R.)』(チャペック/千野栄一訳/岩波文庫)
この文庫を読んだ後、念のために本棚の奥底の古いSFマガジンを探索した。処分した号も多いのだが『RUR』が載った1964年8月臨時増刊号(60年前だ)は残っていた。「名作古典」と紹介されている。深町真理子訳なので重訳かもしれない。岩波文庫版と突き合わせてみて、多少の食い違いに気づいた。SFマガジン版が簡略化されている箇所があり、その逆のケースもある。戯曲は上演のたびに変化することもある。いくつかの版があるのだと思う。
チャペックの元祖ロボットは機械人形ではなく合成人間である。その工場は薬品などを駆使する化学工場だ。昔読んだときは、フランケンシュタインに近いクラシックで古臭い設定だとの印象を受けた。だが、生命工学が発展しつつある現在では、合成人間製造の生化学工場の方が機機械工場より新しいと感じる。
この戯曲を読みながら、半世紀以上昔の初読のときの印象が少しよみがえってきた。私はロボットを労働者の寓意だととらえ、この作品は寓話SFだと思った。『RUR』が発表されたのはロシア革命の数年後だった。
今回の再読で、単純な寓話とは言えないと感じた。ロボットの反乱によって、ただ一人を除いてすべての人間が殺されてしまう。しかし、ロボットたちは自身の再生産の手段を知らず、ロボットも絶滅の危機を迎える。そしてラストシーンで、ロボットのアダムとイブが人間として再生すると予感させる。寓話というよりは神話である。
このやや不自然な設定の物語は、小説ではなく舞台でなければ表現しにくいだろうと思えた。観劇予定の『ロボット』のチラシには「2024年に生きる人々に向けて、シニカルかつ不条理なドラマとして転換し、現代の物語としてお届けします。」とある。百年前の戯曲をどう料理するのか楽しみである。
ノーベル文学賞の『菜食主義者』に慄然とした ― 2024年11月17日
今年のノーベル文学賞を受賞したハン・ガンの小説を読んだ。
『菜食主義者』(ハン・ガン/きむ ふな訳/クオン)
ノーベル文学賞のニュースに接するまで、この作家の名も作品名も知らなかった。本書は13年前に「新しい韓国の文学」というシリーズの第1作目として翻訳出版されている。慧眼の士にはよく知られた作家だったようだ。
私の場合は典型的な付和雷同読書である。書店に平積みされた本書をパラパラとめくり、読みやすそうな小説だなと思い、発作的に購入した。韓国の小説家の作品を読むのは初めてだと思う。
確かに読みやすい。しかし、わかりやすくはない。読み始めると不可思議な作品世界に引き込まれ、一気に読了した。
この小説は「菜食主義者」「蒙古斑」「木の花火」という三作品から成る連作長編である。三編の話はつながっていて登場人物も共通だが、叙述の視点が変化する。それぞれが慄然たる余韻で終わる中編小説である。そして、全体で一つの長編になっている。
突然、一人の女性が菜食主義者になり、ついには自分を樹木と思い込んでいく話である。その女性の夫の視点で始まり、姉の夫の視点、姉の視点へと展開しながら事態は拡大していく。現代韓国の家族をめぐる話であり、物語の背景に韓流ドラマ世界の雰囲気をチラリと感じたりもする。もちろんエンタメではない。日常の深奥に潜んでいる非日常的な悲しみや美意識が浮かびあがってくる。現代的な小難しい思索や技巧を超えた強靭さを感じさせる小説である。
『菜食主義者』は、この世の生きにくさを表現した小説だと思う。小説家は炭鉱のカナリアにたとえられことがある。この小説は、21世紀世界がはらむ病理を予告・反映してるのかもしれない。
『菜食主義者』(ハン・ガン/きむ ふな訳/クオン)
ノーベル文学賞のニュースに接するまで、この作家の名も作品名も知らなかった。本書は13年前に「新しい韓国の文学」というシリーズの第1作目として翻訳出版されている。慧眼の士にはよく知られた作家だったようだ。
私の場合は典型的な付和雷同読書である。書店に平積みされた本書をパラパラとめくり、読みやすそうな小説だなと思い、発作的に購入した。韓国の小説家の作品を読むのは初めてだと思う。
確かに読みやすい。しかし、わかりやすくはない。読み始めると不可思議な作品世界に引き込まれ、一気に読了した。
この小説は「菜食主義者」「蒙古斑」「木の花火」という三作品から成る連作長編である。三編の話はつながっていて登場人物も共通だが、叙述の視点が変化する。それぞれが慄然たる余韻で終わる中編小説である。そして、全体で一つの長編になっている。
突然、一人の女性が菜食主義者になり、ついには自分を樹木と思い込んでいく話である。その女性の夫の視点で始まり、姉の夫の視点、姉の視点へと展開しながら事態は拡大していく。現代韓国の家族をめぐる話であり、物語の背景に韓流ドラマ世界の雰囲気をチラリと感じたりもする。もちろんエンタメではない。日常の深奥に潜んでいる非日常的な悲しみや美意識が浮かびあがってくる。現代的な小難しい思索や技巧を超えた強靭さを感じさせる小説である。
『菜食主義者』は、この世の生きにくさを表現した小説だと思う。小説家は炭鉱のカナリアにたとえられことがある。この小説は、21世紀世界がはらむ病理を予告・反映してるのかもしれない。
『安部公房展』は盛況だった ― 2024年11月05日
県立神奈川近代文学館で開催中の『安部公房展:21世紀文学の基軸』に行った。会場での記念対談『安部公房と戦後の政治・芸術運動 苅部直(政治学者)鳥羽耕史(文学研究者)』も聴講した。
安部公房展は11年前に世田谷文学館でも開催された。私はそれも観ている。前回は没後10年記念、今回は生誕100年記念である。11年前の安部公房展の記憶はかなり薄れているが、今回の方が盛況のような気がした。安部公房が忘れられた作家になる心配なさそうだ。新しい世代の読者が広がっているのだと思う。
今回は成城高校在学中の数学のノートまで展示していた。微分や積分の端正なノートを見て、安部公房は真面目にきちんと数学の勉強もしていたのだと、少し感動した。
「夜の会」「世紀の会」「下丸子文化集団」など、若い頃の芸術運動や政治活動に関する歴史的な資料の展示も興味深い。
会場では、安部公房スタジオの最後の公演『仔象は死んだ』のビデオを小さなデイスプレイで流していた。私はこの公演を観ていないが、ビデオを観て、この公演への辛口批評が納得できる気がした。映像パフォーマンスとしては面白いかもしれないが、役者の魅力は殺がれているように感じられた。
苅部直氏と鳥羽耕史氏の対談も面白かった。両氏とも1960年代生まれの研究者だから、安部公房より40歳ぐらい若い。対談を聞きながら、私のような団塊世代には同時代作家に感じられる安部公房が、すでに歴史上の人物になったと思えた。
苅部氏が『S・カルマ氏の犯罪』のパロディが筒井康隆の『脱走と追跡のサンバ』だと指摘したのには驚いた。『脱走と追跡のサンバ』を読んだ直後に『S・カルマ氏の犯罪』を読んだので、『S・カルマ氏の犯罪』を面白いと思えなかったそうだ。
私は半世紀以上昔に『S・カルマ氏の犯罪』を角川文庫の古本(桂川寛のオリジナル挿絵が入った珍品)で読み、その後に『脱走と追跡のサンバ』をリアルタイムで読んだ。あのとき、パロディとは気づかなかった。いずれ、読み返して確認してみたい。
安部公房展は11年前に世田谷文学館でも開催された。私はそれも観ている。前回は没後10年記念、今回は生誕100年記念である。11年前の安部公房展の記憶はかなり薄れているが、今回の方が盛況のような気がした。安部公房が忘れられた作家になる心配なさそうだ。新しい世代の読者が広がっているのだと思う。
今回は成城高校在学中の数学のノートまで展示していた。微分や積分の端正なノートを見て、安部公房は真面目にきちんと数学の勉強もしていたのだと、少し感動した。
「夜の会」「世紀の会」「下丸子文化集団」など、若い頃の芸術運動や政治活動に関する歴史的な資料の展示も興味深い。
会場では、安部公房スタジオの最後の公演『仔象は死んだ』のビデオを小さなデイスプレイで流していた。私はこの公演を観ていないが、ビデオを観て、この公演への辛口批評が納得できる気がした。映像パフォーマンスとしては面白いかもしれないが、役者の魅力は殺がれているように感じられた。
苅部直氏と鳥羽耕史氏の対談も面白かった。両氏とも1960年代生まれの研究者だから、安部公房より40歳ぐらい若い。対談を聞きながら、私のような団塊世代には同時代作家に感じられる安部公房が、すでに歴史上の人物になったと思えた。
苅部氏が『S・カルマ氏の犯罪』のパロディが筒井康隆の『脱走と追跡のサンバ』だと指摘したのには驚いた。『脱走と追跡のサンバ』を読んだ直後に『S・カルマ氏の犯罪』を読んだので、『S・カルマ氏の犯罪』を面白いと思えなかったそうだ。
私は半世紀以上昔に『S・カルマ氏の犯罪』を角川文庫の古本(桂川寛のオリジナル挿絵が入った珍品)で読み、その後に『脱走と追跡のサンバ』をリアルタイムで読んだ。あのとき、パロディとは気づかなかった。いずれ、読み返して確認してみたい。


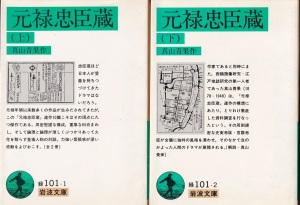



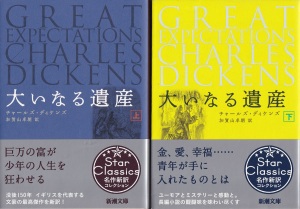

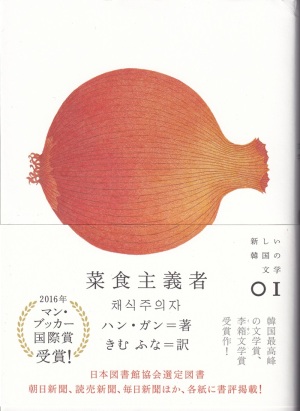

最近のコメント