何度読んでも謎が残るチェーホフの戯曲 ― 2023年08月18日
先日、パルコ劇場で『桜の園』を観たのを契機に戯曲を再読した。
『桜の園・三人姉妹』(チェーホフ、神西清訳/新潮文庫)
半世紀以上昔の学生時代、チェーホフ四大劇(『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』)を読み、虚しさを嚙みしめるようなチェーホフの世界に魅せられた。当時アイドルだったドストエフスキイを補完する存在だった。
4年前、『かもめ』観劇の際に『かもめ・ワーニャ伯父さん』を再読した。今回は『桜の園・三人姉妹』の再読、何度読んでも釈然としない謎が残るのがチェーホフだ。
『桜の園・三人姉妹』を再読した直接の動機は、今回の『桜の園』観劇のときに「…ギボンの『ローマ帝国衰亡史』…」という台詞を耳にしたからである。この数年、私はギボン再読に取り組んでいるので、ギボンという言葉に反応する。『桜の園』にギボンへの言及があっただろうかと気になった。
神西清訳を再読しても、ギボンへの言及を確認できなかった。今回の上演台本は現代的な英訳版からの重訳である。謎が残った。
『桜の園・三人姉妹』を再読してあらためて気づいたのは、二作品ともハッピーと言えない結婚を扱っている点だ。
チェーホフが描いている「結婚」には、解放・桎梏・方便・打算などの多面的要素が盛り込まれている。当然ながら、結婚=ハッピーエンドという単純さはない。チェーホフ劇の「結婚」は、一般的イメージの結婚とは別物の何かを表しているようにも思える。それは、乗り越えていくべき何かである。
『桜の園・三人姉妹』(チェーホフ、神西清訳/新潮文庫)
半世紀以上昔の学生時代、チェーホフ四大劇(『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』)を読み、虚しさを嚙みしめるようなチェーホフの世界に魅せられた。当時アイドルだったドストエフスキイを補完する存在だった。
4年前、『かもめ』観劇の際に『かもめ・ワーニャ伯父さん』を再読した。今回は『桜の園・三人姉妹』の再読、何度読んでも釈然としない謎が残るのがチェーホフだ。
『桜の園・三人姉妹』を再読した直接の動機は、今回の『桜の園』観劇のときに「…ギボンの『ローマ帝国衰亡史』…」という台詞を耳にしたからである。この数年、私はギボン再読に取り組んでいるので、ギボンという言葉に反応する。『桜の園』にギボンへの言及があっただろうかと気になった。
神西清訳を再読しても、ギボンへの言及を確認できなかった。今回の上演台本は現代的な英訳版からの重訳である。謎が残った。
『桜の園・三人姉妹』を再読してあらためて気づいたのは、二作品ともハッピーと言えない結婚を扱っている点だ。
チェーホフが描いている「結婚」には、解放・桎梏・方便・打算などの多面的要素が盛り込まれている。当然ながら、結婚=ハッピーエンドという単純さはない。チェーホフ劇の「結婚」は、一般的イメージの結婚とは別物の何かを表しているようにも思える。それは、乗り越えていくべき何かである。
キーウ・クラシック・バレエ団の『白鳥の湖』を観た ― 2023年08月20日
調布市グリーンホールでキーウ・クラシック・バレエ団の『白鳥の湖』を観た。私はバレエはほとんど観ないが、今年は5月に観た『蝶々夫人』に続いて2回目、稀有なことだ。
あまりに有名な『白鳥の湖』である。チャイコフスキーの名曲は馴染み深いし、4羽の白鳥が手をつないで踊るシーンも頭に浮かぶ。あらすじも何となく憶えている。そんなバレエだから門外漢でも十分に楽しむことができた。
チラシには「4歳以上入場可」とあり、「本プログラムは小さなお子様も飽きずに楽しめるよう、全2幕(約2時間/休憩1回)構成となっております」の表記もある。バレエの敷居を低くした公演のようだ。私のような人間には有難い配慮である。月並みな感想だが、ダンサーたちの身体能力に圧倒された。
キーウ・クラシック・バレエ団のダンサー達はロシアのウクライナ侵攻後、避難を余儀なくされ、日本を含む10以上の国で活動を続けているそうだ。
公演パンフの最終ページには8月から10月までの日本各地でのスケジュールが載っている。日替わりで各地を転々とする過密スケジュールに驚いた。全国を回る公演はどれも似たようなものかもしれないが、舞台装置の解体・移動・設営やリハーサルなどを想像するだけで眩暈がしそうになる。
あまりに有名な『白鳥の湖』である。チャイコフスキーの名曲は馴染み深いし、4羽の白鳥が手をつないで踊るシーンも頭に浮かぶ。あらすじも何となく憶えている。そんなバレエだから門外漢でも十分に楽しむことができた。
チラシには「4歳以上入場可」とあり、「本プログラムは小さなお子様も飽きずに楽しめるよう、全2幕(約2時間/休憩1回)構成となっております」の表記もある。バレエの敷居を低くした公演のようだ。私のような人間には有難い配慮である。月並みな感想だが、ダンサーたちの身体能力に圧倒された。
キーウ・クラシック・バレエ団のダンサー達はロシアのウクライナ侵攻後、避難を余儀なくされ、日本を含む10以上の国で活動を続けているそうだ。
公演パンフの最終ページには8月から10月までの日本各地でのスケジュールが載っている。日替わりで各地を転々とする過密スケジュールに驚いた。全国を回る公演はどれも似たようなものかもしれないが、舞台装置の解体・移動・設営やリハーサルなどを想像するだけで眩暈がしそうになる。
『ドン・キホーテ』は物語内物語満載のメタフィクション ― 2023年08月22日
ジュニア版しか読んでいないドン・キホーテの原作が岩波文庫で全6冊と知って、その長大さに驚いた。この物語は前篇と後篇に分かれている。1605年発表の前篇が評判になり、10年後に後篇を出したようだ。前篇・後篇というよりは正篇・続篇に近い。とりあえず。前篇の3冊を読んだ。
『ドン・キホーテ 前篇(1)(2)(3)』(セルバンテス、牛島信明訳/岩波文庫)
騎士物語を読み過ぎて頭がおかしくなったドン・キホーテがサンチョ・パンサを従者に遍歴の旅に出て、奇行を繰り返す。同郷の司祭と床屋がその二人を探しに行き、何とか連れ戻す――要約すればそれだけの話である。それが、なぜ文庫本3冊の長さになるのか。ドン・キホーテ行状記の中に別の物語がいくつも挿入されているからである。
ドタバタ劇や絵に描いたような偶然の頻出に呆れるが、次々に美女が登場する展開で飽きさせない。不撓不屈のドン・キホーテに感心する。読みやすい古典である。
作者のセルバンテスはレパントの海戦(1571年)で負傷した戦士で、その後、イスラムの海賊に拉致され、アルジェで5年間の虜囚生活の後、身代金で解放された。そんな体験も物語に反映されている。
『ドン・キホーテ(前篇)』が出版されたのはセルバンテス58歳の時だった。生年は1547年、信長の弟の茶人・織田有楽斎と同じ、没年は1616年(享年68歳)、シェイクスピア(享年51歳)や徳川家康(享年73歳)と同じ――そんな時代の人だ。
この小説で驚くのはドン・キホーテのハチャメチャ奇行ではなく、脱線の連続のような物語内物語の繰り返しである。唐突に登場して自分の物語を延々と披露する人物が次々に登場する。ドン・キホーテは遠景にかすみ、読者は「いま私は何の物語を読んでいるのだろうか」と途方に暮れる。重層的な不思議な読書時間である。
また、騎士物語論や読書論のようなメタフィクション的な記述もある。次のような人を食った記述には笑うしかない。
「(…)ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャを世に送り出した時代は、何と幸福な喜ばしい時代であったことか。(…)心をなごませるような楽しみの少ないこの時代に、ドン・キホーテの伝記の得もいわれぬ面白さのみならず、その伝記のなかに収められた数々の短い物語や挿話をも楽しむことができるからである。」
セルバンテスは確信犯的に物語内物語を押し売りしているのだ。
============================
【後日追記リンク】
『ドン・キホーテ 後篇』
『ドン・キホーテ 前篇(1)(2)(3)』(セルバンテス、牛島信明訳/岩波文庫)
騎士物語を読み過ぎて頭がおかしくなったドン・キホーテがサンチョ・パンサを従者に遍歴の旅に出て、奇行を繰り返す。同郷の司祭と床屋がその二人を探しに行き、何とか連れ戻す――要約すればそれだけの話である。それが、なぜ文庫本3冊の長さになるのか。ドン・キホーテ行状記の中に別の物語がいくつも挿入されているからである。
ドタバタ劇や絵に描いたような偶然の頻出に呆れるが、次々に美女が登場する展開で飽きさせない。不撓不屈のドン・キホーテに感心する。読みやすい古典である。
作者のセルバンテスはレパントの海戦(1571年)で負傷した戦士で、その後、イスラムの海賊に拉致され、アルジェで5年間の虜囚生活の後、身代金で解放された。そんな体験も物語に反映されている。
『ドン・キホーテ(前篇)』が出版されたのはセルバンテス58歳の時だった。生年は1547年、信長の弟の茶人・織田有楽斎と同じ、没年は1616年(享年68歳)、シェイクスピア(享年51歳)や徳川家康(享年73歳)と同じ――そんな時代の人だ。
この小説で驚くのはドン・キホーテのハチャメチャ奇行ではなく、脱線の連続のような物語内物語の繰り返しである。唐突に登場して自分の物語を延々と披露する人物が次々に登場する。ドン・キホーテは遠景にかすみ、読者は「いま私は何の物語を読んでいるのだろうか」と途方に暮れる。重層的な不思議な読書時間である。
また、騎士物語論や読書論のようなメタフィクション的な記述もある。次のような人を食った記述には笑うしかない。
「(…)ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャを世に送り出した時代は、何と幸福な喜ばしい時代であったことか。(…)心をなごませるような楽しみの少ないこの時代に、ドン・キホーテの伝記の得もいわれぬ面白さのみならず、その伝記のなかに収められた数々の短い物語や挿話をも楽しむことができるからである。」
セルバンテスは確信犯的に物語内物語を押し売りしているのだ。
============================
【後日追記リンク】
『ドン・キホーテ 後篇』
サグラダ・ファミリアの進捗状況に驚いた ― 2023年08月24日
東京国立近代美術館で『ガイディとサグラダファミリア展』を観た。ガウディの建築物はいくつか見ているが、ガウディ本人についてはほとんど知らなかった。ガウディの伝記的な展示によって、普通に建築学を習得して建築家としてスタートした人だと知った。もっとエキセントリックな人物を想像していた。
サグラダ・ファミリアの起工は1882年、141年前だ。ガウディはその翌年に就任した2代目の建築家だった。就任したときは31歳、1914年(62歳)以降は他の仕事から手を引いてサグラダ・ファミリアに専念、1926年(73歳)に交通事故で死去する。
私は15年前の2008年にサグラダ・ファミリアを訪れた。あわただしい観光で、エレベータで上まで行って階段で降りてきたのを憶えている。工事中の教会という印象が強かった。
寄付金を集めながら100年以上にわたって工事中のサグラダ・ファミリアを観て、完成予想図を知ったとき、完成までにはさらに何十年もかかるだろうと思った。
今回の展示で現在の状況を知り、その進捗ぶりに驚いた。チラシに載っている写真が現在の姿だ。中央部分の巨大な「イエスの塔」が姿を表しつつある。この塔は2026年完成予定だそうだ。
サグラダ・ファミリアには永遠に工事中という独特の魅力があると感じていたが、この状況だと、私の存命中に竣工する可能性もある。目出度いような残念なような、複雑な気分である。
サグラダ・ファミリアの起工は1882年、141年前だ。ガウディはその翌年に就任した2代目の建築家だった。就任したときは31歳、1914年(62歳)以降は他の仕事から手を引いてサグラダ・ファミリアに専念、1926年(73歳)に交通事故で死去する。
私は15年前の2008年にサグラダ・ファミリアを訪れた。あわただしい観光で、エレベータで上まで行って階段で降りてきたのを憶えている。工事中の教会という印象が強かった。
寄付金を集めながら100年以上にわたって工事中のサグラダ・ファミリアを観て、完成予想図を知ったとき、完成までにはさらに何十年もかかるだろうと思った。
今回の展示で現在の状況を知り、その進捗ぶりに驚いた。チラシに載っている写真が現在の姿だ。中央部分の巨大な「イエスの塔」が姿を表しつつある。この塔は2026年完成予定だそうだ。
サグラダ・ファミリアには永遠に工事中という独特の魅力があると感じていたが、この状況だと、私の存命中に竣工する可能性もある。目出度いような残念なような、複雑な気分である。
『ドン・キホーテ 後篇』は前篇以上にメタフィクション ― 2023年08月26日
『ドン・キホーテ 前篇』に続いて『後篇』全3冊を読んだ。
『ドン・キホーテ 後篇(1)(2)(3)』(セルバンテス、牛島信明訳/岩波文庫)
『後篇』の出版は『前篇』の10年後(1615年)だが、物語内の時間は連続している。『前篇』は、約2カ月にわたる遍歴からドン・キホーテが帰郷して終わっている。『後篇』では、帰郷したドン・キホーテが、約1カ月の休養の後、再びサンチョ・パンサを従えて旅立つ。遍歴は約3カ月にわたる。
『後篇』は時間的には『前篇』と連続した物語だが、『後篇』の世界は『前篇』と大きく異なる。『ドン・キホーテ 前篇』が出版された後の世界になっているのだ。
『後篇』の登場人物の何人かは評判の『ドン・キホーテ 前篇』をすでに読んでいる。ドン・キホーテ自身は、知人から自分の伝記が出版されていると聞いているだけで、読んではいない。騎士道物語を山ほど読んできたドン・キホーテは、自分の伝記が新たな騎士道物語として流布しているのは当然と了解している。
『ドン・キホーテ 前篇』が評判になった頃、セルバンテスではない人物が書いた『ドン・キホーテ 続篇』が出版されたそうだ。『続編』という名の贋作である。『後篇』には、この『続編』に対する辛辣な批判も盛り込まれている。ドン・キホーテが印刷工場で『続編』を目撃したり、旅籠で『続編』の登場人物に遭遇して『続編』の誤謬を指摘したりもする。
こんな形で『前篇』や『続篇』(贋作)を取り入れた『後篇』は『前篇』以上にメタフィクションである。17世紀初めにこんなメタフィクションが存在したことに驚くと同時に、メタフィクションは文学の原初的要素かもしれないと思った。
『前篇』を読んでドン・キホーテの狂気を知っている人々が、この狂人を愚弄して楽しむために「高名な遍歴の騎士」として遇する――そんな悪ふざけの繰り返しが『後篇』のパターンである。手の込んだ愚弄がしつこいので、悪ふざけに邁進する人々の愚かさまでもが露呈される。
『後篇』で目立つのがサンチョ・パンサの能弁と有能だ。ことわざを連射する饒舌も面白く、『前篇』以上に生彩がある。
この物語は、最終的に傷心のドン・キホーテが自分の意思で帰郷、その後、正気に戻って静かに息を引き取るまでを描いている。長い物語なのにさほど長さを感じないが、長大な饒舌につきあった気分にはなる。退屈させない饒舌である。
訳文はとても読みやすく、訳注も充実している。「遅かりし由良助よ!」なんて訳文にはシビれた。忠臣蔵は『ドン・キホーテ』から約1世紀後だが…。
この物語を読む前、「前篇・後篇」よりは「正篇・続篇」の方が適切なのでは思った。しかし、文庫本全6冊を読み終えると、「正篇・続篇」ではなく「前篇・後篇」が適切だとわかった。『前篇』だけではドン・キホーテの面白さは半分しか伝わらない。『後篇』によって物語世界が大きくふくらむのだ。レコンキスタ後の17世紀初頭のスペインにおける改宗モーロ人(キリスト教に改宗したムーア人)の状況などを垣間見ることもできる。
『ドン・キホーテ 後篇(1)(2)(3)』(セルバンテス、牛島信明訳/岩波文庫)
『後篇』の出版は『前篇』の10年後(1615年)だが、物語内の時間は連続している。『前篇』は、約2カ月にわたる遍歴からドン・キホーテが帰郷して終わっている。『後篇』では、帰郷したドン・キホーテが、約1カ月の休養の後、再びサンチョ・パンサを従えて旅立つ。遍歴は約3カ月にわたる。
『後篇』は時間的には『前篇』と連続した物語だが、『後篇』の世界は『前篇』と大きく異なる。『ドン・キホーテ 前篇』が出版された後の世界になっているのだ。
『後篇』の登場人物の何人かは評判の『ドン・キホーテ 前篇』をすでに読んでいる。ドン・キホーテ自身は、知人から自分の伝記が出版されていると聞いているだけで、読んではいない。騎士道物語を山ほど読んできたドン・キホーテは、自分の伝記が新たな騎士道物語として流布しているのは当然と了解している。
『ドン・キホーテ 前篇』が評判になった頃、セルバンテスではない人物が書いた『ドン・キホーテ 続篇』が出版されたそうだ。『続編』という名の贋作である。『後篇』には、この『続編』に対する辛辣な批判も盛り込まれている。ドン・キホーテが印刷工場で『続編』を目撃したり、旅籠で『続編』の登場人物に遭遇して『続編』の誤謬を指摘したりもする。
こんな形で『前篇』や『続篇』(贋作)を取り入れた『後篇』は『前篇』以上にメタフィクションである。17世紀初めにこんなメタフィクションが存在したことに驚くと同時に、メタフィクションは文学の原初的要素かもしれないと思った。
『前篇』を読んでドン・キホーテの狂気を知っている人々が、この狂人を愚弄して楽しむために「高名な遍歴の騎士」として遇する――そんな悪ふざけの繰り返しが『後篇』のパターンである。手の込んだ愚弄がしつこいので、悪ふざけに邁進する人々の愚かさまでもが露呈される。
『後篇』で目立つのがサンチョ・パンサの能弁と有能だ。ことわざを連射する饒舌も面白く、『前篇』以上に生彩がある。
この物語は、最終的に傷心のドン・キホーテが自分の意思で帰郷、その後、正気に戻って静かに息を引き取るまでを描いている。長い物語なのにさほど長さを感じないが、長大な饒舌につきあった気分にはなる。退屈させない饒舌である。
訳文はとても読みやすく、訳注も充実している。「遅かりし由良助よ!」なんて訳文にはシビれた。忠臣蔵は『ドン・キホーテ』から約1世紀後だが…。
この物語を読む前、「前篇・後篇」よりは「正篇・続篇」の方が適切なのでは思った。しかし、文庫本全6冊を読み終えると、「正篇・続篇」ではなく「前篇・後篇」が適切だとわかった。『前篇』だけではドン・キホーテの面白さは半分しか伝わらない。『後篇』によって物語世界が大きくふくらむのだ。レコンキスタ後の17世紀初頭のスペインにおける改宗モーロ人(キリスト教に改宗したムーア人)の状況などを垣間見ることもできる。
『ファウスト』を初めて読んだが…… ― 2023年08月28日
ふとした気まぐれでゲーテの『ファウスト』を読んだ。10年ほど前に購入して積んでいた文庫本である。
『ファウスト(1)(2)』(ゲーテ/高橋義孝訳/新潮文庫)
ゲーテの高名な代表作だから頑張って最後まで読んだが、読了した気分になれない。目を通しただけで咀嚼はできていないのだ。
戯曲形式の大作で原文は韻文である。韻文の翻訳なので改行が多く、欄外に行番号を振っている。活字量はさほど多くはないが詩のような台詞が続くので、イメージを紡ぐのが難儀である。韻文の翻訳は大変だと思うが、不思議な訳文を読むのも疲れる。まったくの散文で訳すと原文の雰囲気が失われるのだろうが…。
『ファウスト』はファウスト伝説に基づいた戯曲で、ゲーテのオリジナルではない。学問を究めたファウスト博士が悪魔メフィストーフェレスと契約を結び、メフィストーフェレスを従え、この世の知識と快楽を求めて遍歴する――そんな伝説の詳細に不案内な私には、この戯曲はわかりにくい。伝説を知らない人には不親切である。
合唱のような詩的台詞や婉曲な表現が延々と続いていると思って油断していると、事態が急展開したりする。初めてこの作品に接する読者はとまどってしまう。
ファウストが美女(グレートヒェン)を口説いていると思っていたら、いつの間にかその女性が嬰児殺しで牢獄にいる。私の読み落としのせいだが、びっくりする。また、ファウストが別の美女(ヘレネー)に出会ったと思えば、すぐに子供が出来ていて、アッという間に子供が成長し、あっけなく死んでしまう。
キリスト教やギリシア神話の知識がなければわからない表現や情景が多く、同時代のアレコレを風刺した場面もある。註を参照しながら読み進めなければ、意味不明の語句に溺れてしまう。
歌舞伎などの古典芸能と同じように、戯曲を精読したうえで、役者たちが演じる舞台をイヤホンガイドを聞きながら鑑賞すれば楽しめるのだろうと夢想した。
ゲーテの著作は、数年前に『イタリア紀行』 を面白く読んだが、本書はお手上げに近い。上っ面を撫でただけで咀嚼できていない作品について軽々に読後感を述べることはできない。何度か繰り返し読まなければ、面白いか否かも判断できそうにない。
『ファウスト(1)(2)』(ゲーテ/高橋義孝訳/新潮文庫)
ゲーテの高名な代表作だから頑張って最後まで読んだが、読了した気分になれない。目を通しただけで咀嚼はできていないのだ。
戯曲形式の大作で原文は韻文である。韻文の翻訳なので改行が多く、欄外に行番号を振っている。活字量はさほど多くはないが詩のような台詞が続くので、イメージを紡ぐのが難儀である。韻文の翻訳は大変だと思うが、不思議な訳文を読むのも疲れる。まったくの散文で訳すと原文の雰囲気が失われるのだろうが…。
『ファウスト』はファウスト伝説に基づいた戯曲で、ゲーテのオリジナルではない。学問を究めたファウスト博士が悪魔メフィストーフェレスと契約を結び、メフィストーフェレスを従え、この世の知識と快楽を求めて遍歴する――そんな伝説の詳細に不案内な私には、この戯曲はわかりにくい。伝説を知らない人には不親切である。
合唱のような詩的台詞や婉曲な表現が延々と続いていると思って油断していると、事態が急展開したりする。初めてこの作品に接する読者はとまどってしまう。
ファウストが美女(グレートヒェン)を口説いていると思っていたら、いつの間にかその女性が嬰児殺しで牢獄にいる。私の読み落としのせいだが、びっくりする。また、ファウストが別の美女(ヘレネー)に出会ったと思えば、すぐに子供が出来ていて、アッという間に子供が成長し、あっけなく死んでしまう。
キリスト教やギリシア神話の知識がなければわからない表現や情景が多く、同時代のアレコレを風刺した場面もある。註を参照しながら読み進めなければ、意味不明の語句に溺れてしまう。
歌舞伎などの古典芸能と同じように、戯曲を精読したうえで、役者たちが演じる舞台をイヤホンガイドを聞きながら鑑賞すれば楽しめるのだろうと夢想した。
ゲーテの著作は、数年前に『イタリア紀行』 を面白く読んだが、本書はお手上げに近い。上っ面を撫でただけで咀嚼できていない作品について軽々に読後感を述べることはできない。何度か繰り返し読まなければ、面白いか否かも判断できそうにない。
大昔に入手した『ハムレットとドン キホーテ』を読んだ ― 2023年08月31日
『ドン・キホーテ』(前篇
、後篇
)全6冊を読了したとき、ツルゲーネフの『ハムレットとドンキホーテ』を想起、半世紀以上昔の学生時代に入手した薄い岩波文庫を書架の奥から探し出した。
『ハムレットとドン キホーテ』(ツルゲーネフ、河野与一・柴田治三郎訳/岩波文庫)
黄ばんだ本書を開き、「ハムレットとドン・キホーテ」だけでない評論集だったと思い出した。「ハムレットとドン・キホーテ」「プーシュキン論」「ファウスト論」の3編を収録している。前2編は講演録だから短い。学生時代に1編目を全部読んだか途中で投げたか定かでない。後2編は未読だと思う。
『ドン・キホーテ』を読了したので「ハムレットとドン・キホーテ」を読む気になったが、他の2編も気になる。プーシュキンは多少読んだがファウストは未読だ。これを機に、いつか読もうと積んでいた『ファウスト』を読んでから本書を読もうと思った。という事情で『ドン・キホーテ』に続いて『ファウスト』 を読んだのである。
閑話休題。3編のなかでは、やはり「ハムレットとドン・キホーテ」が面白い。読みやすくはないが、かなり単純なことを述べているように思えた。
ハムレットとドン・キホーテが人間の本性の相反する二つの典型だとの指摘は炯眼で納得できる。この2作品が同じ年(1605年)に出たことに不思議な因縁を感じる。主人公二人の比較に着目したのがツルゲーネフの手柄だと思う。彼以前に二人を論じた人がいたかどうかは知らないが…。
ハムレットは自分自身のために生きるエゴイスト、ドン・キホーテは理想に献身する人――それがツルゲーネフの基本的な見立てである。全体を通してハムレットには批判的、ドン・キホーテには同情的に感じられる。
私が昨年読んだ『謎解き『ハムレット』』 では、ハムレットを優柔不断な哲学青年と見なす従来のロマン主義的解釈を批判していた。ハムレットも行動者であり、ドンキホーテ的要素をもっていたかもしれない。
解釈は多様でかまわない。ツルゲーネフの解釈に基づいたこの比較論は、ツルゲーネフの心象の反映でもある。自身のなかにあるハムレット的なものを克服し、ドン・キホーテ的なものを追究したいという思いが表れている。
「プーシュキン論」はプーシュキン銅像除幕式の際の演説で、プーシュキンをロシア最初の詩人・芸術家と位置付けた礼讃である。
「ファウスト論」は面白いが十分には理解できなかった。「ゲーテは詩人としては匹敵する者をもたない。しかし今日必要なのは詩人だけなのではない。」と述べるところにロシア人作家の自恃を感じた。この評論のかなりの部分が、出たばかりのロシア語翻訳の批評である。「私はヴェロンチェンコ氏の訳に詩句を見出せない」との指摘に、韻文の翻訳はどの言語でも難しいのだと思った。
『ハムレットとドン キホーテ』(ツルゲーネフ、河野与一・柴田治三郎訳/岩波文庫)
黄ばんだ本書を開き、「ハムレットとドン・キホーテ」だけでない評論集だったと思い出した。「ハムレットとドン・キホーテ」「プーシュキン論」「ファウスト論」の3編を収録している。前2編は講演録だから短い。学生時代に1編目を全部読んだか途中で投げたか定かでない。後2編は未読だと思う。
『ドン・キホーテ』を読了したので「ハムレットとドン・キホーテ」を読む気になったが、他の2編も気になる。プーシュキンは多少読んだがファウストは未読だ。これを機に、いつか読もうと積んでいた『ファウスト』を読んでから本書を読もうと思った。という事情で『ドン・キホーテ』に続いて『ファウスト』 を読んだのである。
閑話休題。3編のなかでは、やはり「ハムレットとドン・キホーテ」が面白い。読みやすくはないが、かなり単純なことを述べているように思えた。
ハムレットとドン・キホーテが人間の本性の相反する二つの典型だとの指摘は炯眼で納得できる。この2作品が同じ年(1605年)に出たことに不思議な因縁を感じる。主人公二人の比較に着目したのがツルゲーネフの手柄だと思う。彼以前に二人を論じた人がいたかどうかは知らないが…。
ハムレットは自分自身のために生きるエゴイスト、ドン・キホーテは理想に献身する人――それがツルゲーネフの基本的な見立てである。全体を通してハムレットには批判的、ドン・キホーテには同情的に感じられる。
私が昨年読んだ『謎解き『ハムレット』』 では、ハムレットを優柔不断な哲学青年と見なす従来のロマン主義的解釈を批判していた。ハムレットも行動者であり、ドンキホーテ的要素をもっていたかもしれない。
解釈は多様でかまわない。ツルゲーネフの解釈に基づいたこの比較論は、ツルゲーネフの心象の反映でもある。自身のなかにあるハムレット的なものを克服し、ドン・キホーテ的なものを追究したいという思いが表れている。
「プーシュキン論」はプーシュキン銅像除幕式の際の演説で、プーシュキンをロシア最初の詩人・芸術家と位置付けた礼讃である。
「ファウスト論」は面白いが十分には理解できなかった。「ゲーテは詩人としては匹敵する者をもたない。しかし今日必要なのは詩人だけなのではない。」と述べるところにロシア人作家の自恃を感じた。この評論のかなりの部分が、出たばかりのロシア語翻訳の批評である。「私はヴェロンチェンコ氏の訳に詩句を見出せない」との指摘に、韻文の翻訳はどの言語でも難しいのだと思った。
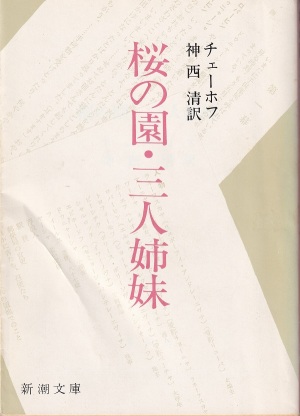






最近のコメント