学問の面白さと厳しさ伝わってくる『モンゴルが世界史を覆す』 ― 2021年12月22日
先月、杉山正明氏の著書を2冊(『疾駆する草原の征服者』、『大モンゴルの世界』)続けて読み、NHK取材班の『大モンゴル』も読んだ。その流れで杉山氏の次の本を読んだ。
『モンゴルが世界史を覆す』(杉山正明/日経ビジネス文庫/日本経済新聞社)
2002年刊行の『逆説のユーラシア史――モンゴルからのまなざし』の文庫版(2006年刊行)で、文庫化の際に改題した。雑誌などに発表した文章を編集したもので、気軽に読めるエッセイ集と思っていたが、私にとっては重量級の筋の通った史書だった。
教えられた箇所は多いが『第4章 人類史における「帝国」』が特に勉強になった。東西の歴史を読んでいると、皇帝・天皇・王などの概念が国や時代によってかなり異なっているように感じられる。そんなぼんやりした疑念が、この章を読んで少しすっきりした。杉山氏は世界史の広大な時間と地域の広がりをふまえて「帝国」とは何かを検討・整理している。帝国と自称しても帝国とは限らないし、自ら帝国と名乗っていない帝国も多い。歴史家の目で、どの時代のどこを帝国と見なすかを検討するには、時空を見渡すことが前提になるのだ。
第1章-5の「マルコ・ポーロはいなかった?」も面白い。私は3年前に気まぐれで 『東方見聞録』を読んだことがあり、「マルコ・ポーロは実在しなかった」という説を承知はしている。それでも、何となく実在人物のような気がしていた。杉山氏は歴史家の冷徹な目でマルコ・ポーロが形作られてきた事情と過程を分析している。それこそが歴史の面白さだと感じた。
本書には、杉山氏が自身の学究生活の一端を吐露している文章もあり、あらためて学問の厳しさを知った。モンゴル史を研究するには漢文、ペルシア語、アラビア語、トルコ語をはじめ多くの言語で原典・原物にあたる必要がある。大変なことだと思う。モンゴルのパクパ文字について、講演で次のように語っているのには感心した。
「パクパ文字は、それほど難しくありません。(…)わたしは1時間で覚えました。別に自慢をしているのではなく、逃げ腰にならずにやりさえすれば、誰にでもすぐにわかります。(…)事典などで「パクパ文字」を引くと、よく「非常にむずかしい文字なので普及しなかった」という説明書きがあります。(…)書いた人は、本当はパクパ文字にトライしたことがないのでしょう。」
『モンゴルが世界史を覆す』(杉山正明/日経ビジネス文庫/日本経済新聞社)
2002年刊行の『逆説のユーラシア史――モンゴルからのまなざし』の文庫版(2006年刊行)で、文庫化の際に改題した。雑誌などに発表した文章を編集したもので、気軽に読めるエッセイ集と思っていたが、私にとっては重量級の筋の通った史書だった。
教えられた箇所は多いが『第4章 人類史における「帝国」』が特に勉強になった。東西の歴史を読んでいると、皇帝・天皇・王などの概念が国や時代によってかなり異なっているように感じられる。そんなぼんやりした疑念が、この章を読んで少しすっきりした。杉山氏は世界史の広大な時間と地域の広がりをふまえて「帝国」とは何かを検討・整理している。帝国と自称しても帝国とは限らないし、自ら帝国と名乗っていない帝国も多い。歴史家の目で、どの時代のどこを帝国と見なすかを検討するには、時空を見渡すことが前提になるのだ。
第1章-5の「マルコ・ポーロはいなかった?」も面白い。私は3年前に気まぐれで 『東方見聞録』を読んだことがあり、「マルコ・ポーロは実在しなかった」という説を承知はしている。それでも、何となく実在人物のような気がしていた。杉山氏は歴史家の冷徹な目でマルコ・ポーロが形作られてきた事情と過程を分析している。それこそが歴史の面白さだと感じた。
本書には、杉山氏が自身の学究生活の一端を吐露している文章もあり、あらためて学問の厳しさを知った。モンゴル史を研究するには漢文、ペルシア語、アラビア語、トルコ語をはじめ多くの言語で原典・原物にあたる必要がある。大変なことだと思う。モンゴルのパクパ文字について、講演で次のように語っているのには感心した。
「パクパ文字は、それほど難しくありません。(…)わたしは1時間で覚えました。別に自慢をしているのではなく、逃げ腰にならずにやりさえすれば、誰にでもすぐにわかります。(…)事典などで「パクパ文字」を引くと、よく「非常にむずかしい文字なので普及しなかった」という説明書きがあります。(…)書いた人は、本当はパクパ文字にトライしたことがないのでしょう。」
モンゴル史研究家・杉山正明氏はギボンを評価していた ― 2021年12月25日
杉山正明氏の『モンゴルが世界史を覆す』に続いて次の本を読んだ。
『世界史を変貌させたモンゴル』(杉山正明/角川叢書/2000.12)
全3章の本書は次の3点に関する専門的な論考である。
(1) 世界地図「混一疆理歴代国都之図」などの地図
(2) カラ・コルムと大都
(3) モンゴル時代史研究の過去・現在・未来
大元ウルス(元朝)時代の世界地図をベースに李朝朝鮮で1402年に作成され世界地図「混一疆理歴代国都之図」に関しては、『モンゴルが世界史を覆す』でも言及していたが、それをより詳細に検討している。ヴァスコ・ダ・ガマの「インド航路開拓」より1世紀以上前のモンゴル時代に作られた地図には「海に囲繞されたアフリカ」が描かれている。この時代にアフロ・ユーラシア(アフリカ大陸+ユーラシア大陸)という世界認識があったのだ。実に興味深い。
(2)の大都に関する論考は私には専門的すぎて難しかった。あとがきには、大学の研究報告に収録したものに手をくわえたとある。素人には難しくて当然かもしれない。
モンゴル研究の状況をレポートした(3)には、門外漢の私が知らない研究者の固有名詞が頻出する。だが、外野スタンドから研究者たちの奮闘を眺める面白さがある。ギボンとペリオへの言及が印象に残った。
私はギボンの『ローマ帝国衰亡史』をとりあえずは読了しボチボチ再読中であり、今年1月には 『ギボン自伝』も読だ。要はギボン・ファンである。西欧中心史観の転換を提唱する杉山氏は、18世紀の啓蒙歴史家ギボンには好意的で、次のように述べている。
「イギリスでは、かのエドワード・ギボンが『ローマ帝国衰亡史』のなかでチンギス・カンにはじまるモンゴル帝国の歴史に、なみなみならぬ造詣を披歴している。とりわけ、モンゴル帝国についてのギボンの発言は、いまの眼でも肯くところが多々あり、歴史家としての彼の力量・センスがやはり尋常でなかったことを十分にしのばせてくれる。」
私は『ローマ帝国衰亡史』を読んでいて、ギボンが「元寇」にまで言及しているのに驚いた記憶があり、杉山氏の評価を読んで少しうれしくなった。
ペリオはシルクロード関連の本でよく目にするフランスの研究者だ。漢文を読解できたので、敦煌文書発見の際には価値のあるものを選出して持ち帰った(一応、合法に)という話を読んだことがある。モンゴル研究にはポリグロト(多言語に通じた人)であることが求められ、ペリオもポリグロトだった。だが、杉山氏はペリオには辛辣で、次のように述べている。
「ペリオの仕事は、考証のための考証といった域を永遠に出ないところがある。(…)歴史の大勢や全体像にかかわるような仕事は、ペリオはするつもりもなかったし、あるいは多分できなかった。そういう類の人であった。」
本書を読むと、モンゴル時代史の研究とは「歴史の大勢や全体像」にかかわる研究だとわかる。
『世界史を変貌させたモンゴル』(杉山正明/角川叢書/2000.12)
全3章の本書は次の3点に関する専門的な論考である。
(1) 世界地図「混一疆理歴代国都之図」などの地図
(2) カラ・コルムと大都
(3) モンゴル時代史研究の過去・現在・未来
大元ウルス(元朝)時代の世界地図をベースに李朝朝鮮で1402年に作成され世界地図「混一疆理歴代国都之図」に関しては、『モンゴルが世界史を覆す』でも言及していたが、それをより詳細に検討している。ヴァスコ・ダ・ガマの「インド航路開拓」より1世紀以上前のモンゴル時代に作られた地図には「海に囲繞されたアフリカ」が描かれている。この時代にアフロ・ユーラシア(アフリカ大陸+ユーラシア大陸)という世界認識があったのだ。実に興味深い。
(2)の大都に関する論考は私には専門的すぎて難しかった。あとがきには、大学の研究報告に収録したものに手をくわえたとある。素人には難しくて当然かもしれない。
モンゴル研究の状況をレポートした(3)には、門外漢の私が知らない研究者の固有名詞が頻出する。だが、外野スタンドから研究者たちの奮闘を眺める面白さがある。ギボンとペリオへの言及が印象に残った。
私はギボンの『ローマ帝国衰亡史』をとりあえずは読了しボチボチ再読中であり、今年1月には 『ギボン自伝』も読だ。要はギボン・ファンである。西欧中心史観の転換を提唱する杉山氏は、18世紀の啓蒙歴史家ギボンには好意的で、次のように述べている。
「イギリスでは、かのエドワード・ギボンが『ローマ帝国衰亡史』のなかでチンギス・カンにはじまるモンゴル帝国の歴史に、なみなみならぬ造詣を披歴している。とりわけ、モンゴル帝国についてのギボンの発言は、いまの眼でも肯くところが多々あり、歴史家としての彼の力量・センスがやはり尋常でなかったことを十分にしのばせてくれる。」
私は『ローマ帝国衰亡史』を読んでいて、ギボンが「元寇」にまで言及しているのに驚いた記憶があり、杉山氏の評価を読んで少しうれしくなった。
ペリオはシルクロード関連の本でよく目にするフランスの研究者だ。漢文を読解できたので、敦煌文書発見の際には価値のあるものを選出して持ち帰った(一応、合法に)という話を読んだことがある。モンゴル研究にはポリグロト(多言語に通じた人)であることが求められ、ペリオもポリグロトだった。だが、杉山氏はペリオには辛辣で、次のように述べている。
「ペリオの仕事は、考証のための考証といった域を永遠に出ないところがある。(…)歴史の大勢や全体像にかかわるような仕事は、ペリオはするつもりもなかったし、あるいは多分できなかった。そういう類の人であった。」
本書を読むと、モンゴル時代史の研究とは「歴史の大勢や全体像」にかかわる研究だとわかる。
『モンゴル帝国:NHKスペシャル 文明の道5』の世界地図がいい ― 2021年12月27日
杉山正明氏が関わったテレビ番組を元にした次の本を読んだ。
『モンゴル帝国:NHKスペシャル 文明の道5』(杉山正明・他/日本放送出版協会/2004.2)
『NHKスペシャル 文明の道』は2003年5月から12月まで8回にわたって放映され、その第8集「クビライの挑戦 ユーラシア帝国の完成」を書籍化したものである。私はこのテレビ番組は観ていない。本書を読んで面白そうな番組だと思い、NHKオンデマンドを検索してみた。『文明の道』の第1集から第7集まではオンデマンドで視聴可能(有料)だが、何故か第8集は提供されていない。
本書はテレビ番組ベースの本にしては活字頁が多い。その半分は杉山正明氏によるモンゴル帝国史の概説である。私には知識の整理・復習になり有益だった。ヨーロッパや中華王朝が「世界」を意識する何百年も前の14世紀、モンゴル帝国では世界地図が作られ世界史が編纂(『集史』)されていたのは、やはり興味深い。
本書の冒頭には世界地図「混一疆理歴代国都之図」が見開き写真で紹介されている。びっしり書き込まれた地名を写真から読み取るのは難しいが、この図版の欄外には主な20の地名の解説があり、地図のどの位置かを線で示している。フランスのマルセイユから日本の京都までが一望できる。地中海が海の色に塗りつぶされていないのは、原図から複写するときのミスなのだろうか。あらためて、この地図を堪能できた。
『モンゴル帝国:NHKスペシャル 文明の道5』(杉山正明・他/日本放送出版協会/2004.2)
『NHKスペシャル 文明の道』は2003年5月から12月まで8回にわたって放映され、その第8集「クビライの挑戦 ユーラシア帝国の完成」を書籍化したものである。私はこのテレビ番組は観ていない。本書を読んで面白そうな番組だと思い、NHKオンデマンドを検索してみた。『文明の道』の第1集から第7集まではオンデマンドで視聴可能(有料)だが、何故か第8集は提供されていない。
本書はテレビ番組ベースの本にしては活字頁が多い。その半分は杉山正明氏によるモンゴル帝国史の概説である。私には知識の整理・復習になり有益だった。ヨーロッパや中華王朝が「世界」を意識する何百年も前の14世紀、モンゴル帝国では世界地図が作られ世界史が編纂(『集史』)されていたのは、やはり興味深い。
本書の冒頭には世界地図「混一疆理歴代国都之図」が見開き写真で紹介されている。びっしり書き込まれた地名を写真から読み取るのは難しいが、この図版の欄外には主な20の地名の解説があり、地図のどの位置かを線で示している。フランスのマルセイユから日本の京都までが一望できる。地中海が海の色に塗りつぶされていないのは、原図から複写するときのミスなのだろうか。あらためて、この地図を堪能できた。
堺屋太一氏のチンギス・ハン伝記にはビジネス書の面白さがある ― 2021年12月29日
杉山正明氏の本を何冊か読み、頭がモンゴル史モードになっているので、次の小説を読んだ。
『世界を創った男チンギス・ハン(上)(中)(下)』(堺屋太一/日経ビジネス文庫/日本経済新聞社)
15年前、日経新聞に1年半連載(2006年2月~2007年8月)した小説である。堺屋太一氏はわれわれ「団塊の世代」の名付け親だ。その小説をいくつか読んでいるが、元通産官僚で経済企画庁長官も務めた多才多弁な経済評論家のイメージが強い。
新聞連載開始の2006年はチンギス・ハンがモンゴル諸族を統一してカハンの位についた1206年から800周年で、モンゴル国では祝賀行事が開催された。子供の頃からチンギス・ハンのファンで研究を続けていた堺屋氏は、そんなイベントに関わると同時にこの新聞連載を始めたそうだ。
チンギス・ハンの前半生は謎に包まれている。史料(『元史』『元朝秘史』『集史』など)の内容があまりに虚実入り混じり、伝説か創作か史実か区別がつかず、史料間の整合性もない。杉山正明氏によれば、史実と見なせるのは1203年にオン・カン(トオリル・ハン)を倒して1206年にカハンの位についてからであり、それ以前について「真剣にあれこれ論じても、しょせん小説と大きく変わらない」そうだ。
チンギス・ハンの没年1227年は確かだが生年には諸説ある。堺屋氏は生年1162年説(モンゴル政府もこの説)を採用し、44歳(1206年)でカハンに就位し、65歳で亡くなったとしている。全3巻のこの小説で、チンギス・ハンが44歳でカハンになるのは3巻目の中頃だから、3巻目半ばまでは杉山氏のいう「しょせん小説」ということになる。堺屋氏は次のように述べている。
《本作において「史的事実については誤りなく採り入れる(嘘や間違いなない)が、不明な部分は周辺情況やあとの事態などとの整合性を持つ範囲で推測想定する」という歴史小説の厳格な条件を守る方針である。》
虚実不明でも史料に基づいて記述し、史料間の食い違いを注釈しながら書き進めるという姿勢である。この小説には多くの注があり、地図もたくさん載っている。注には、かなり長い解説文や図表もある。さらに、小説の随所に「歴史小説のロビーで」というエッセイが挿入されている。小説本文の中にも解説的な記述が散りばめられている。
チンギス・ハンの一代記ではあるが、蘊蓄が主で物語が従だ。物知り旦那の解説座談付き歴史紙芝居の趣があり、それなりに面白く読めた。巨視的に時代を語る「図解歴史小説」である。
ざっくりと言えば、旧体制から新体制へ転換する物語で、世界観の対立を絵解きしている。旧体制とは氏族長連合封建体制を堅持する守旧派であり、新体制とは「人間(じんかん)に差別なし、地上に境界なし」を標榜するチンギス・ハンの絶対王朝体制であり、グローバリズムの競争社会でもある。割り切りが明解な見方だ。
この歴史小説は経済・経営小説でもある。零細家内企業が世界企業に発展していく起業家物語であり、堺屋氏独特の見立ての頻出が楽しい。テムジン(後のチンギス・ハン)が15歳のとき、父が急死する場面を「大学を卒業して外国留学中に父の急死で呼び戻された青年」にたとえ、次のように描いている。
『父親は(…)名門ながら傍流、ようやく従業員千人程度の中堅企業を育てた感じだろう。その父親が50歳代前半で急死した。気丈な母親は専務取締役の勧めた銀行派遣の経営陣による管理を拒んだが、いろんな人物が暗躍、資金と販路が閉ざされた。』
チンギス・ハンを起業家と見なし、その事業には「明確なビジョン(理念)」「それを形にする概念(コンセプト)」「実現するための筋道(ストーリー)」があったとしている。まるでビジネス書だが、そんな目で歴史を観るのもアリだと思える。
この小説に登場するイスラム商人や旅芸人たちが関西弁なのが面白いし、遊牧民たちの移動距離のスケールにも驚く。ちょっとした使い走りでも往復1週間である。本書を読んで、歴史小説には歴史を疑似体験する楽しさがあるとあらためて感じた。
『世界を創った男チンギス・ハン(上)(中)(下)』(堺屋太一/日経ビジネス文庫/日本経済新聞社)
15年前、日経新聞に1年半連載(2006年2月~2007年8月)した小説である。堺屋太一氏はわれわれ「団塊の世代」の名付け親だ。その小説をいくつか読んでいるが、元通産官僚で経済企画庁長官も務めた多才多弁な経済評論家のイメージが強い。
新聞連載開始の2006年はチンギス・ハンがモンゴル諸族を統一してカハンの位についた1206年から800周年で、モンゴル国では祝賀行事が開催された。子供の頃からチンギス・ハンのファンで研究を続けていた堺屋氏は、そんなイベントに関わると同時にこの新聞連載を始めたそうだ。
チンギス・ハンの前半生は謎に包まれている。史料(『元史』『元朝秘史』『集史』など)の内容があまりに虚実入り混じり、伝説か創作か史実か区別がつかず、史料間の整合性もない。杉山正明氏によれば、史実と見なせるのは1203年にオン・カン(トオリル・ハン)を倒して1206年にカハンの位についてからであり、それ以前について「真剣にあれこれ論じても、しょせん小説と大きく変わらない」そうだ。
チンギス・ハンの没年1227年は確かだが生年には諸説ある。堺屋氏は生年1162年説(モンゴル政府もこの説)を採用し、44歳(1206年)でカハンに就位し、65歳で亡くなったとしている。全3巻のこの小説で、チンギス・ハンが44歳でカハンになるのは3巻目の中頃だから、3巻目半ばまでは杉山氏のいう「しょせん小説」ということになる。堺屋氏は次のように述べている。
《本作において「史的事実については誤りなく採り入れる(嘘や間違いなない)が、不明な部分は周辺情況やあとの事態などとの整合性を持つ範囲で推測想定する」という歴史小説の厳格な条件を守る方針である。》
虚実不明でも史料に基づいて記述し、史料間の食い違いを注釈しながら書き進めるという姿勢である。この小説には多くの注があり、地図もたくさん載っている。注には、かなり長い解説文や図表もある。さらに、小説の随所に「歴史小説のロビーで」というエッセイが挿入されている。小説本文の中にも解説的な記述が散りばめられている。
チンギス・ハンの一代記ではあるが、蘊蓄が主で物語が従だ。物知り旦那の解説座談付き歴史紙芝居の趣があり、それなりに面白く読めた。巨視的に時代を語る「図解歴史小説」である。
ざっくりと言えば、旧体制から新体制へ転換する物語で、世界観の対立を絵解きしている。旧体制とは氏族長連合封建体制を堅持する守旧派であり、新体制とは「人間(じんかん)に差別なし、地上に境界なし」を標榜するチンギス・ハンの絶対王朝体制であり、グローバリズムの競争社会でもある。割り切りが明解な見方だ。
この歴史小説は経済・経営小説でもある。零細家内企業が世界企業に発展していく起業家物語であり、堺屋氏独特の見立ての頻出が楽しい。テムジン(後のチンギス・ハン)が15歳のとき、父が急死する場面を「大学を卒業して外国留学中に父の急死で呼び戻された青年」にたとえ、次のように描いている。
『父親は(…)名門ながら傍流、ようやく従業員千人程度の中堅企業を育てた感じだろう。その父親が50歳代前半で急死した。気丈な母親は専務取締役の勧めた銀行派遣の経営陣による管理を拒んだが、いろんな人物が暗躍、資金と販路が閉ざされた。』
チンギス・ハンを起業家と見なし、その事業には「明確なビジョン(理念)」「それを形にする概念(コンセプト)」「実現するための筋道(ストーリー)」があったとしている。まるでビジネス書だが、そんな目で歴史を観るのもアリだと思える。
この小説に登場するイスラム商人や旅芸人たちが関西弁なのが面白いし、遊牧民たちの移動距離のスケールにも驚く。ちょっとした使い走りでも往復1週間である。本書を読んで、歴史小説には歴史を疑似体験する楽しさがあるとあらためて感じた。
57年前の文庫本『蒼き狼』を再読していて虫の死骸に遭遇 ― 2021年12月31日
堺屋太一のチンギス・ハン伝を読み終え、井上靖の『蒼き狼』を読み返そうと思った。成吉思汗の生涯を描いた高名なこの小説を、私は半世紀以上昔に読んでいる。その内容はほとんど失念しているので、どんな話だったか確認したくなったのである。書架の奥に往時の文庫本がまだ残っていた。
『蒼き狼』(井上靖/新潮文庫/1964.6)
本書の巻末に汚い字のメモがあり、読んだ時期が判明した。57年前(1964年)、高校1年の夏休みである。昔の小さい活字に耐えて再読していると、黄ばんだ頁に挟まった虫(蚊?)の死骸に遭遇した。半世紀以上昔に生きていた虫だと思うと感慨深い。
この小説は坦々とした記述で進行し、ケレン味がない。馴染みのうすいカタカナの人名・部族名・地名が頻出するが、現在の私には多少のモンゴル史の知識があるので興味深く読了できた。無知な高校1年生には少々厄介で退屈な小説だったかもしれない。
草原の幕舎での成吉思汗出生のシーンに始まり、老いた成吉思汗が戦地の幕舎で息を引き取るシーンで終わる物語である。シーンの背景には、漆黒の夜空に散りばめられた無数の星や、ごうごうと森を揺らす風があり、かなりロマンチックである。ケレンはなくても、終章はやや芝居がかっているように思えた。
頁に挟まれて化石のようになった虫に例えては失礼だが、この小説を読んでいて所々に化石に近い古さを感じた。特に女性の描き方が気になる。現代のフェミニストから糾弾されそうな表現もある。私は遊牧民の女性は強いというイメージをもっているが、登場する女性の多くはあまり強くない。
この小説の肝は、成吉思汗と長男ジョチが二代にわたって「自分は本当に父の子か?」という内心の疑念に悩み、それが征服行動の原動力になったという点である。部族間での女性略奪が普通の時代ゆえの状況で、面白い見方だとは思う。
小説を読み終えてしばらくして、ふと思い出した。遠い昔に『蒼き狼』を巡って「歴史小説論争」なるものがあったと聞いた記憶がある。学生時代、「論争」には関心があったが「歴史小説」に興味がなかったので、「歴史小説論争」の内容はまったく知らない。ネット検索するといくつか資料が出てきた。論争の発端になった「『蒼き狼』は歴史小説か」(大岡昇平)という文章と、それへの反論「自作『蒼き狼』について」(井上靖)という文章も読むことができた。
大岡昇平の口調はキツいが、いまひとつピンとこない論争である。「歴史小説とは何か」という論点は、私にはどうでもいい話に思える。この小説に関する大岡昇平の批判と井上靖の反論のどちらにも納得できる部分がある。大岡昇平の歴史小説観はリゴリズムに思えるが、『蒼き狼』への違和感には共感できる部分もある。次のような指摘が面白い。
「モンゴルの男は狼だが、女は鹿だという幻想は、井上氏の主人公に奇妙な女性蔑視の観念を持たせる。(…)女性不信は井上氏の他の小説にもよく繰り返されるモチーフだが、成吉思汗に適用してまったく根拠がない。」
『蒼き狼』(井上靖/新潮文庫/1964.6)
本書の巻末に汚い字のメモがあり、読んだ時期が判明した。57年前(1964年)、高校1年の夏休みである。昔の小さい活字に耐えて再読していると、黄ばんだ頁に挟まった虫(蚊?)の死骸に遭遇した。半世紀以上昔に生きていた虫だと思うと感慨深い。
この小説は坦々とした記述で進行し、ケレン味がない。馴染みのうすいカタカナの人名・部族名・地名が頻出するが、現在の私には多少のモンゴル史の知識があるので興味深く読了できた。無知な高校1年生には少々厄介で退屈な小説だったかもしれない。
草原の幕舎での成吉思汗出生のシーンに始まり、老いた成吉思汗が戦地の幕舎で息を引き取るシーンで終わる物語である。シーンの背景には、漆黒の夜空に散りばめられた無数の星や、ごうごうと森を揺らす風があり、かなりロマンチックである。ケレンはなくても、終章はやや芝居がかっているように思えた。
頁に挟まれて化石のようになった虫に例えては失礼だが、この小説を読んでいて所々に化石に近い古さを感じた。特に女性の描き方が気になる。現代のフェミニストから糾弾されそうな表現もある。私は遊牧民の女性は強いというイメージをもっているが、登場する女性の多くはあまり強くない。
この小説の肝は、成吉思汗と長男ジョチが二代にわたって「自分は本当に父の子か?」という内心の疑念に悩み、それが征服行動の原動力になったという点である。部族間での女性略奪が普通の時代ゆえの状況で、面白い見方だとは思う。
小説を読み終えてしばらくして、ふと思い出した。遠い昔に『蒼き狼』を巡って「歴史小説論争」なるものがあったと聞いた記憶がある。学生時代、「論争」には関心があったが「歴史小説」に興味がなかったので、「歴史小説論争」の内容はまったく知らない。ネット検索するといくつか資料が出てきた。論争の発端になった「『蒼き狼』は歴史小説か」(大岡昇平)という文章と、それへの反論「自作『蒼き狼』について」(井上靖)という文章も読むことができた。
大岡昇平の口調はキツいが、いまひとつピンとこない論争である。「歴史小説とは何か」という論点は、私にはどうでもいい話に思える。この小説に関する大岡昇平の批判と井上靖の反論のどちらにも納得できる部分がある。大岡昇平の歴史小説観はリゴリズムに思えるが、『蒼き狼』への違和感には共感できる部分もある。次のような指摘が面白い。
「モンゴルの男は狼だが、女は鹿だという幻想は、井上氏の主人公に奇妙な女性蔑視の観念を持たせる。(…)女性不信は井上氏の他の小説にもよく繰り返されるモチーフだが、成吉思汗に適用してまったく根拠がない。」

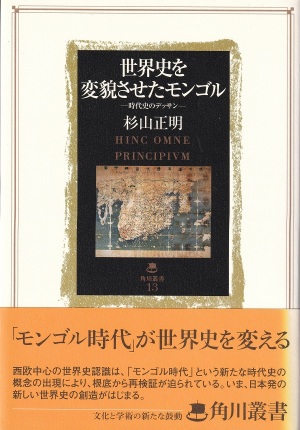



最近のコメント