カフカは近代産業の内幕を把握した有能な官吏だった ― 2011年02月28日
8年前、ネット句会でこんな句を作ったことがある。
短日のカフカの街の子犬かな
題詠の題が「子犬」で、苦しみまぎれにエイヤっと作った句だ。「道に迷ってさまよう子犬」を想像し、それがカフカのイメージに重なった。プラハに行ったことはなかったが、頭の中で未知のプラハを幻視していた。以来、いつかはプラハに行きたいと思っていた。
来月、中欧観光旅行でプラハを訪れる予定だ。それを機会に『カフカの生涯』(池内紀/白水社)を読んだ。面白い評伝だった。評伝が引き金になって『失踪者』(カフカ/池内紀訳/カフカ小説全集1/白水社)も読んだ。
カフカを読んだのはかなり昔だ。『変身』『審判』『城』などの代表作は読んだが、長編『アメリカ』は未読だった。『カフカの生涯』を読んで、『アメリカ』も読もうと思った。かつて『アメリカ』というタイトルだった長編は、現在は『失踪者』というタイトルで出版されていた。
生前は無名作家だったカフカは3つの長編を残した。『審判』『城』『アメリカ→失踪者』である。3作とも未完で、カフカの死後、友人のブロートが原稿ノートを整理して出版した。『アメリカ』が『失踪者』に変わったのは、1968年にブロートが亡くなってカフカのノートが「解禁」になり、カフカの手稿の研究が進んだせいだそうだ。
ブロートが亡くなった1968年と言えば、私がカフカを読んでいた頃だ。私にとって、カフカは「二十世紀の古典」のような存在で、「世界名作」の範疇に入る作家だった。しかし、カフカの評伝を読んで、思っていた以上に私たちと年代の近い作家だと気付いた。
カフカと同年齢(1983年生まれ)の著名人を調べると、志賀直哉、北一輝、ムッソリーニ、ユトリロなどが出てくる。意外に最近の人だと再認識した。カフカは1924年に40歳で亡くなっている。カフカが生き延びていれば、私が生まれた1948年には65歳。私から見れば祖父の世代だったのだ。
カフカが死んだ1924年はヒトラーのミュンヘン一揆の翌年である。カフカはナチスの台頭や第二次世界大戦を見ることなく生涯を終えている。若くして死んでいるから、昔の人のような気がしていたのだ。カフカがもっと生きていれば、その家族たちのようにアウシュビッツで命を落としていたかもしれない。そうなっていれば、作家カフカのイメージも多少違ってきただろう。
『カフカの生涯』の「はじめに -- カフカの肖像」は、わずか3頁でカフカという人物の奇妙な魅力をざっくりと印象的に描写している。この作家の生涯をたどりたくなる気分を盛り上げてくれる秀逸なプロローグだ。
本編はこのプロローグの敷衍である。本書を読み終えて感じたのは、カフカのあの奇妙な作品群は、結局は彼の境涯を綴った「私小説」だったのではないかという想いだ。これは、カフカ小説全集の翻訳者でもある池内紀氏が、彼自身の作品解釈をふまえてこの評伝を書いているからに他ならない。カフカの超現実的で奇妙な世界が現実の生活を反映している、というのは考えてみれば当然のことかもしれない。説得力のある読み解きだと思った。
半官半民の労働者障害保険協会の職員としての仕事の合間に小説を書いていたカフカにとって、小説を書くことは決して余技ではなかった。彼は小説を書くことを生活のメインにしていた。となると、職場では鬱屈しているサラリーマンのようにも見えるが、実はなかなか有能な職員だったようだ。それなりに出世もしている。
池内紀氏は、職場での業績も残しているカフカについて次のように述べている。
「カフカは数多くの出張を通して近代産業の内幕というものをよく知っていた。その点、二十世紀の作家たちのなかで、ただ一人の例外だった。」
「(大工場経営者たちが)いかなる素姓の者であり、どのような労働条件のもとに短期間で財をなしたか、カフカはよく知っていた。やがて「プロレタリア作家」とよばれて登場した者たちよりも、よリひろく、よりくわしく知っていた。(略)ただ彼は小説を書くにあたり、ついぞプロレタリア作家のようなリアリズムのスタイルはとらなかった。」
カフカの世界には、専業小説家(?!)では捉えることができなかった近代産業の実態があるという指摘は、カフカという作家の特異性と普遍性を裏付けるものだろう。
かつて、ある先輩が「カフカばりの小説なんて誰にでもすぐに書ける。ぼくが書きたいのは、人情味のある話だ」と語るのを聞いて、人情話はともかく、前段の指摘にはうなづける気がしたことがある。寓話の一つや二つは、だれでもひねり出せそうな気がする。しかし、多くの読者をそんな気にさせるところが、じつはカフカの普遍性なのだ。その世界には、リアリズム作家以上に切実でリアルな現実世界の把握という裏付けがあり、それは頭の中だけで獲得できるものではなかったようだ。
そんなところに、カフカが大きな影響力をもつ作家になった秘密のひとつがあるのだろう。
また、『カフカの生涯』によって、二十世紀ヨーロッパにおける「ユダヤ人」についての認識が少し深まった。日本に住む私たちには実感しにくい問題だが、「ユダヤ人」という存在は当のユダヤ人たちにとっても、やっかいで奇妙な問題だったようだ。
カフカの死後、カフカを世に広めた友人ブロートは、プラハ大学で1年後輩のユダヤ人で、シオニストだった。カフカより早く世に出て売れっ子作家になったブロートは後にイスラエルに移住する。カフカ自身はシオニズムとは一定の距離をとっていたらしい。
ブロートが編集した『アメリカ』が、手稿版の『失踪者』に改訂されるにあたって、物語の終わり方が異なっている。というか、元々は未完のノートなので、残された断片をどのような形で発表するかという問題である。
池内紀氏の解説によると、ブロートは「新大陸で行きくれた主人公が、最後には救済を見つける」形にしたのだ。「熱烈なシオニストであり、みずからもいち早く『約束の地』イスラエルへ移り、また友人カフカに一人のメシアを見ようとしたブロートには、物語は救済で終わらなくてはならない。」という考えがあった。
そのようなブロートのフィルターを除いて、ノートのままの形にしたのが『失踪者』である。
いずれにしても、カフカ自身が途中で放棄した小説なので、宙ぶらりんなのはいたしかたない。やはり『審判』や『城』の方が面白いと思えた。
『カフカの生涯』には、1967年に著者が留学中のウィーン大学の講演会で、イスラエルから来たブロートを目撃した話が出てくる。この目撃談は印象的だ。少し引用してみる。
「八十四歳で死んだとき、ブロートの著作は八十三冊に達していた。(略)にもかかわらず『カフカの作品の編集者』が、そのすべてを忘れさせた。マックス・ブロートの名は、ひとえにカフカの名と結びついて後世にのこった。(略)死の前年、ウィーンで見かけた老人に、どこかしら受難者めいた面影があったのは、自分が引き受けた役回りに殉じたせいだったかもしれない。」
カフカには孤独で内向的な受難者のような面影が感じられるが、実は、かけがいのない友人や女性たちに恵まれ、ひたすら小説と手紙を書き続けることができた、やや身勝手で幸福な人だったようにも思える。
久々にカフカの小説を読みながら感じたのは、物語を読んでる気分ではなく他人の思弁的な日記帳を読んでいる気分だった。断片だけを味わいながら読み進めることができた、とも言える。こんな気分になるのは『カフカの生涯』読了直後に小説を読んだからかもしれないが。
アメリカを見ることなく新大陸を放浪する青年を描いたカフカ、その作家が暮らした街プラハへ、プラハを見ることなく駄句を詠んだ私が赴こうとしている。カフカの小説のように、いつまで経っても到達できな場所ではないだろう。
短日のカフカの街の子犬かな
題詠の題が「子犬」で、苦しみまぎれにエイヤっと作った句だ。「道に迷ってさまよう子犬」を想像し、それがカフカのイメージに重なった。プラハに行ったことはなかったが、頭の中で未知のプラハを幻視していた。以来、いつかはプラハに行きたいと思っていた。
来月、中欧観光旅行でプラハを訪れる予定だ。それを機会に『カフカの生涯』(池内紀/白水社)を読んだ。面白い評伝だった。評伝が引き金になって『失踪者』(カフカ/池内紀訳/カフカ小説全集1/白水社)も読んだ。
カフカを読んだのはかなり昔だ。『変身』『審判』『城』などの代表作は読んだが、長編『アメリカ』は未読だった。『カフカの生涯』を読んで、『アメリカ』も読もうと思った。かつて『アメリカ』というタイトルだった長編は、現在は『失踪者』というタイトルで出版されていた。
生前は無名作家だったカフカは3つの長編を残した。『審判』『城』『アメリカ→失踪者』である。3作とも未完で、カフカの死後、友人のブロートが原稿ノートを整理して出版した。『アメリカ』が『失踪者』に変わったのは、1968年にブロートが亡くなってカフカのノートが「解禁」になり、カフカの手稿の研究が進んだせいだそうだ。
ブロートが亡くなった1968年と言えば、私がカフカを読んでいた頃だ。私にとって、カフカは「二十世紀の古典」のような存在で、「世界名作」の範疇に入る作家だった。しかし、カフカの評伝を読んで、思っていた以上に私たちと年代の近い作家だと気付いた。
カフカと同年齢(1983年生まれ)の著名人を調べると、志賀直哉、北一輝、ムッソリーニ、ユトリロなどが出てくる。意外に最近の人だと再認識した。カフカは1924年に40歳で亡くなっている。カフカが生き延びていれば、私が生まれた1948年には65歳。私から見れば祖父の世代だったのだ。
カフカが死んだ1924年はヒトラーのミュンヘン一揆の翌年である。カフカはナチスの台頭や第二次世界大戦を見ることなく生涯を終えている。若くして死んでいるから、昔の人のような気がしていたのだ。カフカがもっと生きていれば、その家族たちのようにアウシュビッツで命を落としていたかもしれない。そうなっていれば、作家カフカのイメージも多少違ってきただろう。
『カフカの生涯』の「はじめに -- カフカの肖像」は、わずか3頁でカフカという人物の奇妙な魅力をざっくりと印象的に描写している。この作家の生涯をたどりたくなる気分を盛り上げてくれる秀逸なプロローグだ。
本編はこのプロローグの敷衍である。本書を読み終えて感じたのは、カフカのあの奇妙な作品群は、結局は彼の境涯を綴った「私小説」だったのではないかという想いだ。これは、カフカ小説全集の翻訳者でもある池内紀氏が、彼自身の作品解釈をふまえてこの評伝を書いているからに他ならない。カフカの超現実的で奇妙な世界が現実の生活を反映している、というのは考えてみれば当然のことかもしれない。説得力のある読み解きだと思った。
半官半民の労働者障害保険協会の職員としての仕事の合間に小説を書いていたカフカにとって、小説を書くことは決して余技ではなかった。彼は小説を書くことを生活のメインにしていた。となると、職場では鬱屈しているサラリーマンのようにも見えるが、実はなかなか有能な職員だったようだ。それなりに出世もしている。
池内紀氏は、職場での業績も残しているカフカについて次のように述べている。
「カフカは数多くの出張を通して近代産業の内幕というものをよく知っていた。その点、二十世紀の作家たちのなかで、ただ一人の例外だった。」
「(大工場経営者たちが)いかなる素姓の者であり、どのような労働条件のもとに短期間で財をなしたか、カフカはよく知っていた。やがて「プロレタリア作家」とよばれて登場した者たちよりも、よリひろく、よりくわしく知っていた。(略)ただ彼は小説を書くにあたり、ついぞプロレタリア作家のようなリアリズムのスタイルはとらなかった。」
カフカの世界には、専業小説家(?!)では捉えることができなかった近代産業の実態があるという指摘は、カフカという作家の特異性と普遍性を裏付けるものだろう。
かつて、ある先輩が「カフカばりの小説なんて誰にでもすぐに書ける。ぼくが書きたいのは、人情味のある話だ」と語るのを聞いて、人情話はともかく、前段の指摘にはうなづける気がしたことがある。寓話の一つや二つは、だれでもひねり出せそうな気がする。しかし、多くの読者をそんな気にさせるところが、じつはカフカの普遍性なのだ。その世界には、リアリズム作家以上に切実でリアルな現実世界の把握という裏付けがあり、それは頭の中だけで獲得できるものではなかったようだ。
そんなところに、カフカが大きな影響力をもつ作家になった秘密のひとつがあるのだろう。
また、『カフカの生涯』によって、二十世紀ヨーロッパにおける「ユダヤ人」についての認識が少し深まった。日本に住む私たちには実感しにくい問題だが、「ユダヤ人」という存在は当のユダヤ人たちにとっても、やっかいで奇妙な問題だったようだ。
カフカの死後、カフカを世に広めた友人ブロートは、プラハ大学で1年後輩のユダヤ人で、シオニストだった。カフカより早く世に出て売れっ子作家になったブロートは後にイスラエルに移住する。カフカ自身はシオニズムとは一定の距離をとっていたらしい。
ブロートが編集した『アメリカ』が、手稿版の『失踪者』に改訂されるにあたって、物語の終わり方が異なっている。というか、元々は未完のノートなので、残された断片をどのような形で発表するかという問題である。
池内紀氏の解説によると、ブロートは「新大陸で行きくれた主人公が、最後には救済を見つける」形にしたのだ。「熱烈なシオニストであり、みずからもいち早く『約束の地』イスラエルへ移り、また友人カフカに一人のメシアを見ようとしたブロートには、物語は救済で終わらなくてはならない。」という考えがあった。
そのようなブロートのフィルターを除いて、ノートのままの形にしたのが『失踪者』である。
いずれにしても、カフカ自身が途中で放棄した小説なので、宙ぶらりんなのはいたしかたない。やはり『審判』や『城』の方が面白いと思えた。
『カフカの生涯』には、1967年に著者が留学中のウィーン大学の講演会で、イスラエルから来たブロートを目撃した話が出てくる。この目撃談は印象的だ。少し引用してみる。
「八十四歳で死んだとき、ブロートの著作は八十三冊に達していた。(略)にもかかわらず『カフカの作品の編集者』が、そのすべてを忘れさせた。マックス・ブロートの名は、ひとえにカフカの名と結びついて後世にのこった。(略)死の前年、ウィーンで見かけた老人に、どこかしら受難者めいた面影があったのは、自分が引き受けた役回りに殉じたせいだったかもしれない。」
カフカには孤独で内向的な受難者のような面影が感じられるが、実は、かけがいのない友人や女性たちに恵まれ、ひたすら小説と手紙を書き続けることができた、やや身勝手で幸福な人だったようにも思える。
久々にカフカの小説を読みながら感じたのは、物語を読んでる気分ではなく他人の思弁的な日記帳を読んでいる気分だった。断片だけを味わいながら読み進めることができた、とも言える。こんな気分になるのは『カフカの生涯』読了直後に小説を読んだからかもしれないが。
アメリカを見ることなく新大陸を放浪する青年を描いたカフカ、その作家が暮らした街プラハへ、プラハを見ることなく駄句を詠んだ私が赴こうとしている。カフカの小説のように、いつまで経っても到達できな場所ではないだろう。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://dark.asablo.jp/blog/2011/02/28/5711376/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
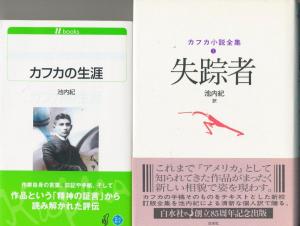
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。