台湾から与那国島への「3万年前の航海」報告会見を聞いた ― 2019年07月18日
日本記者クラブで「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」報告会見があった。プロジェクト代表の海部陽介・国立科学博物館人類史研究グループ長と二人の漕ぎ手(原康司キャプテンと田中道子さん)が会見した。
旧石器時代にわれわれの先祖が大陸から海を渡って来たことを「沖縄ルート」で実証するプロジェクトで、今月上旬、手漕ぎの丸木舟による台湾から与那国島への航海が成功した。
私は1年前、このプロジェクトの「漕ぎ手募集説明会」のチラシを図書館で見かけた時から興味を抱いていた。だから、成功のニュースにはひときわ感動した。
今回の会見で航海の詳細を聞き、あらためてこのプロジェクトの意義を理解し、3万年前の技術だけによる公開の難しさを知った。航海時間は30時間から40時間の見込みだったが実際には45時間かかったそうだ。
3万年前、台湾は大陸の一部だった。当時も今も黒潮が流れていて、昔の潮流も推測でき、漂流では台湾から沖縄の諸島に流れ着くことができないと実証されている。だから、太古の人は己の意思で海を渡ったと推測される。
与那国島と台湾の距離は100キロ、天候がよければ与那国島から台湾は見える。台湾の標高は与那国島に比べてはるかに高い。台湾から与那国島は見えないとも言われていたが、海部氏は現地調査し、海岸からは見えなくても高い山からは与那国島が見えることを確認したそうだ。
与那国島は台湾の東方100キロにあるが、今回の航海の距離は225キロである。黒潮の流れを想定して南方から北東に向かう航海になるからである。それは地図を観て理解していたが、漕ぎ手たちは北東ではなく東南東に向かって漕いだと知って驚いた。潮の流れとの格闘であり、潮に乗る制御なのである。
地球は丸いから海上から与那国島が見えるのは50キロ圏内に入ってからである。当然、出発地から島は見えない。それでも3万年前の人類は島を目指して海に漕ぎ出して行ったのである。その動機が何だったのはわからないが、探求心だったと思いたい。
旧石器時代にわれわれの先祖が大陸から海を渡って来たことを「沖縄ルート」で実証するプロジェクトで、今月上旬、手漕ぎの丸木舟による台湾から与那国島への航海が成功した。
私は1年前、このプロジェクトの「漕ぎ手募集説明会」のチラシを図書館で見かけた時から興味を抱いていた。だから、成功のニュースにはひときわ感動した。
今回の会見で航海の詳細を聞き、あらためてこのプロジェクトの意義を理解し、3万年前の技術だけによる公開の難しさを知った。航海時間は30時間から40時間の見込みだったが実際には45時間かかったそうだ。
3万年前、台湾は大陸の一部だった。当時も今も黒潮が流れていて、昔の潮流も推測でき、漂流では台湾から沖縄の諸島に流れ着くことができないと実証されている。だから、太古の人は己の意思で海を渡ったと推測される。
与那国島と台湾の距離は100キロ、天候がよければ与那国島から台湾は見える。台湾の標高は与那国島に比べてはるかに高い。台湾から与那国島は見えないとも言われていたが、海部氏は現地調査し、海岸からは見えなくても高い山からは与那国島が見えることを確認したそうだ。
与那国島は台湾の東方100キロにあるが、今回の航海の距離は225キロである。黒潮の流れを想定して南方から北東に向かう航海になるからである。それは地図を観て理解していたが、漕ぎ手たちは北東ではなく東南東に向かって漕いだと知って驚いた。潮の流れとの格闘であり、潮に乗る制御なのである。
地球は丸いから海上から与那国島が見えるのは50キロ圏内に入ってからである。当然、出発地から島は見えない。それでも3万年前の人類は島を目指して海に漕ぎ出して行ったのである。その動機が何だったのはわからないが、探求心だったと思いたい。
中央ユーラシア史の観点で「安史の乱」を解説 ― 2019年07月16日
山川書店の「世界史リブレット」シリーズはワンテーマを100頁弱で解説した読みやす冊子である。その「安禄山」を読んだ。
『安禄山:「安史の乱」を起こしたソグド人』(森部豊/世界史リブレット人/山川出版社)
高校世界史の教科書だと安禄山や安史の乱に関する記述は1ページに満たない。それを薄い冊子で解説するのだから、かなりの詳細がわかる。サブタイトルが示しているようにソグド人としての安禄山に焦点をあてた記述になっている。
最近読んだ『シルクロードと唐帝国』(森安孝夫)や『ソグド商人の歴史』(E・ドゥ・ラ・ヴェシエール)でもソグド人としての安禄山に言及していて、それがきっかけで安禄山への興味がわき、本書を読んだ。
755年の「安史の乱」は唐衰退の契機となる8年にわたる大乱である。反乱を起こした安禄山が息子に殺害され、反乱を引き継いだ史思明も息子に殺害されるという訳のわからない展開だと感じていたが、本書でおよその経緯はつかめた。そして、思った以上に大規模な事変だと知った。
本書では「反乱」の理由として、安禄山 vs 宰相・楊国忠の権力闘争とは別に複雑な地域間対立を指摘している。それは中央ユーラシア史という広い観点から「安史の乱」をとらえる見方である。
安禄山の父はソグド人、母は突厥人である。「反乱」の資財はソグド商人のネットワークから得ていたそうだ。
唐帝国の世界には多様な種族(「民族」と表現するのは適切ではない)がいて、その種族がそれぞれの思惑で入り混じって戦ったのが「安史の乱」である。唐は建国のときには突厥からの援助を受けたが「安史の乱」ではウイグルの援助を受けている。突厥復興を夢みる突厥遺民は安禄山側で参戦している。唐の側にはアッバース朝から弾圧されたアラブの軍勢までがパミール高原をこえて参戦している。
著者は、「安史の乱」は7世紀以来のユーラシア全体の歴史変動を視野に入れなければ理解できないと述べている。その歴史変動とは、突厥第一可汗国の崩壊、薛延陀の滅亡、西突厥の衰亡、奚・契丹と唐の攻防、ウマイヤ朝からアッバース朝への交代などなどである。実にややこしい。
『安禄山:「安史の乱」を起こしたソグド人』(森部豊/世界史リブレット人/山川出版社)
高校世界史の教科書だと安禄山や安史の乱に関する記述は1ページに満たない。それを薄い冊子で解説するのだから、かなりの詳細がわかる。サブタイトルが示しているようにソグド人としての安禄山に焦点をあてた記述になっている。
最近読んだ『シルクロードと唐帝国』(森安孝夫)や『ソグド商人の歴史』(E・ドゥ・ラ・ヴェシエール)でもソグド人としての安禄山に言及していて、それがきっかけで安禄山への興味がわき、本書を読んだ。
755年の「安史の乱」は唐衰退の契機となる8年にわたる大乱である。反乱を起こした安禄山が息子に殺害され、反乱を引き継いだ史思明も息子に殺害されるという訳のわからない展開だと感じていたが、本書でおよその経緯はつかめた。そして、思った以上に大規模な事変だと知った。
本書では「反乱」の理由として、安禄山 vs 宰相・楊国忠の権力闘争とは別に複雑な地域間対立を指摘している。それは中央ユーラシア史という広い観点から「安史の乱」をとらえる見方である。
安禄山の父はソグド人、母は突厥人である。「反乱」の資財はソグド商人のネットワークから得ていたそうだ。
唐帝国の世界には多様な種族(「民族」と表現するのは適切ではない)がいて、その種族がそれぞれの思惑で入り混じって戦ったのが「安史の乱」である。唐は建国のときには突厥からの援助を受けたが「安史の乱」ではウイグルの援助を受けている。突厥復興を夢みる突厥遺民は安禄山側で参戦している。唐の側にはアッバース朝から弾圧されたアラブの軍勢までがパミール高原をこえて参戦している。
著者は、「安史の乱」は7世紀以来のユーラシア全体の歴史変動を視野に入れなければ理解できないと述べている。その歴史変動とは、突厥第一可汗国の崩壊、薛延陀の滅亡、西突厥の衰亡、奚・契丹と唐の攻防、ウマイヤ朝からアッバース朝への交代などなどである。実にややこしい。
ソグド人への関心で読んだ『西域』 ― 2019年07月13日
◎急にツアー参加を決めて…
旅行会社のパンフで「幻のソグディアナ タジキスタン紀行8日間」というツアーを発見して惹きつけられた。『シルクロードと唐帝国』(森安孝夫)や『ソグド商人の歴史』(E・ドゥ・ラ・ヴェシエール)で興味を抱いたソグディアナという地名が目に飛び込び、思い切ってこのツアーを申し込んだ。出発までに約1カ月しかない。
という事情で、中央アジアのにわか勉強の一環で次の本を読んだ。
『西域(世界の歴史10)』(羽田明/河出書房新社)
河出書房の『世界の歴史(全24巻)』は数十年前に安価な古書で入手したが、この巻は未読だった。刊行は1969年2月、かなり昔の本である。
◎西域のロマン
「西域」という言葉には遥かなる遠方の辺境を思わせる独特の魅力がある。「君に勧む更に尽せ一杯の酒/西のかた陽関を出ずれば故人無からん」という王維の詩句が浮かび、シルクロードのロマンに重なる。
西域とはタリム盆地(タクラマカン砂漠)からカスピ海に至る広大な地域で、本書は先史時代から19世紀までのこの地域の長い歴史を概説している。と言ってもメインの記述は、この地域がシルクロードの中枢として繁栄し西域と呼ばれていた時代である。
西域の歴史を読めば、そこで活動していた多様な人々や多くのオアシス都市の様子がわかり、この地域を辺境ロマンの目で眺めるのは偏見で、文明の十字路と見るべきだとあらためて認識した。また、人間の集団とは西や東への大移動をくりかえすものだと知った。島国日本では体感しにくい事象である。
◎ソグド商人は文化の伝達者
本書を読む動機のひとつはソグド人への関心である。ただし、1970年代以降にソグド人の墓や墓誌があいつで発見され、それからソグド研究が盛んになったと聞いたことがあるので、1969年発行の本書にはさほど詳しい記述はないのではと思っていた。
予断に反して、本書はソグド人やソグド商人の活動をかなりのページを割いて記述している。ソグドが単なる商業民族ではなく、遊牧民族との共生関係を築いて軍事的にも強かったと指摘している。また、ソグド語が国際語として広く使われていたことを述べ、文化の伝達者としてのソグド人にも着目している。
◎ソグドの古代都市遺跡
ソグド人の古代都市ペンジケント(ピャンジケント)遺跡を図解入りで詳しく説明しているのもうれしかった。来月予定のツアーではタジキスタンにあるこの遺跡が訪問先のひとつだが、ガイドブックにはほんの簡単な記述しかなかったのである。正倉院の御物にこの遺跡で発見された壁画を連想させるものがあるという興味深い指摘もある。
本書のソグド人に関する記述を読み、日本の東洋史学の底力の一端に触れた気分になった。
◎蛇足
本書の著者・羽田明氏(京大教授)は高名な東洋史家・羽田亨(京大総長、京大にはその功績を顕彰した羽田記念館がある)の長男で、親子二代の西域研究者である。「あとがき」によれば、本書全体の構想をたてたのは羽田明氏だが、約半分は別の研究者(山田信夫、間野英二、小谷仲男)が執筆したそうだ。
本書付録の月報の「編集部だより」の次の一節が面白かった。
「本巻執筆中に羽田先生が京大教養部長に就任されたため、執筆時間を学園紛争にとられたことや当社が経営上の躓きを経験したことから、きわめて厳しいスケジュールを先生に課す結果となった。」
本書の発行日は1969年2月15日、全共闘まっさかりの時期で私は大学生だった。そんな頃、河出書房倒産のニュースを耳にしたと思う。本書の奥付を確認すると発行者は「河出書房新社」、1968年11月発行の『世界の歴史7 大唐帝国』までの発行者は「河出書房」、8巻以降は「新社」になっている。1960年代末の熱気と混迷を感じた。
旅行会社のパンフで「幻のソグディアナ タジキスタン紀行8日間」というツアーを発見して惹きつけられた。『シルクロードと唐帝国』(森安孝夫)や『ソグド商人の歴史』(E・ドゥ・ラ・ヴェシエール)で興味を抱いたソグディアナという地名が目に飛び込び、思い切ってこのツアーを申し込んだ。出発までに約1カ月しかない。
という事情で、中央アジアのにわか勉強の一環で次の本を読んだ。
『西域(世界の歴史10)』(羽田明/河出書房新社)
河出書房の『世界の歴史(全24巻)』は数十年前に安価な古書で入手したが、この巻は未読だった。刊行は1969年2月、かなり昔の本である。
◎西域のロマン
「西域」という言葉には遥かなる遠方の辺境を思わせる独特の魅力がある。「君に勧む更に尽せ一杯の酒/西のかた陽関を出ずれば故人無からん」という王維の詩句が浮かび、シルクロードのロマンに重なる。
西域とはタリム盆地(タクラマカン砂漠)からカスピ海に至る広大な地域で、本書は先史時代から19世紀までのこの地域の長い歴史を概説している。と言ってもメインの記述は、この地域がシルクロードの中枢として繁栄し西域と呼ばれていた時代である。
西域の歴史を読めば、そこで活動していた多様な人々や多くのオアシス都市の様子がわかり、この地域を辺境ロマンの目で眺めるのは偏見で、文明の十字路と見るべきだとあらためて認識した。また、人間の集団とは西や東への大移動をくりかえすものだと知った。島国日本では体感しにくい事象である。
◎ソグド商人は文化の伝達者
本書を読む動機のひとつはソグド人への関心である。ただし、1970年代以降にソグド人の墓や墓誌があいつで発見され、それからソグド研究が盛んになったと聞いたことがあるので、1969年発行の本書にはさほど詳しい記述はないのではと思っていた。
予断に反して、本書はソグド人やソグド商人の活動をかなりのページを割いて記述している。ソグドが単なる商業民族ではなく、遊牧民族との共生関係を築いて軍事的にも強かったと指摘している。また、ソグド語が国際語として広く使われていたことを述べ、文化の伝達者としてのソグド人にも着目している。
◎ソグドの古代都市遺跡
ソグド人の古代都市ペンジケント(ピャンジケント)遺跡を図解入りで詳しく説明しているのもうれしかった。来月予定のツアーではタジキスタンにあるこの遺跡が訪問先のひとつだが、ガイドブックにはほんの簡単な記述しかなかったのである。正倉院の御物にこの遺跡で発見された壁画を連想させるものがあるという興味深い指摘もある。
本書のソグド人に関する記述を読み、日本の東洋史学の底力の一端に触れた気分になった。
◎蛇足
本書の著者・羽田明氏(京大教授)は高名な東洋史家・羽田亨(京大総長、京大にはその功績を顕彰した羽田記念館がある)の長男で、親子二代の西域研究者である。「あとがき」によれば、本書全体の構想をたてたのは羽田明氏だが、約半分は別の研究者(山田信夫、間野英二、小谷仲男)が執筆したそうだ。
本書付録の月報の「編集部だより」の次の一節が面白かった。
「本巻執筆中に羽田先生が京大教養部長に就任されたため、執筆時間を学園紛争にとられたことや当社が経営上の躓きを経験したことから、きわめて厳しいスケジュールを先生に課す結果となった。」
本書の発行日は1969年2月15日、全共闘まっさかりの時期で私は大学生だった。そんな頃、河出書房倒産のニュースを耳にしたと思う。本書の奥付を確認すると発行者は「河出書房新社」、1968年11月発行の『世界の歴史7 大唐帝国』までの発行者は「河出書房」、8巻以降は「新社」になっている。1960年代末の熱気と混迷を感じた。
歴博の第1展示室(先史・古代)の人形は異様にリアル ― 2019年07月12日
千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館に行った。じっくり見るならとても一日では回り切れない。膨大な展示物に圧倒された。展示室は次の6つである。
第1展示室 先史・古代
第2展示室 中世
第3展示室 近世
第4展示室 民俗
第5展示室 近代
第6展示室 現代
現物展示もあるが、模型やジオラマも多い。巨大な歴史図鑑である。それぞれの展示物の説明を読みながら歩いていると一つの展示室だけで疲労困憊してしまう。だから、大半の展示物はザーッと見ただけだ。
中世の展示室で写経生の姿(右下の写真)に接したのには感動した。最近読んだ『天平の時代』 (栄原永遠男/集英社版日本の歴史4)に描かれていた写経生の生活が印象深く、彼らに感情移入していたからである。写経生の人形の背景には「待遇改善要求」の説明漫画も掲示されている。歴史概説書で抱いたイメージが眼前に現出したので驚いた。
ただし、この写経生のマネキン風人形は顔も手も黒で表情がない。それでも雰囲気は伝わってくるが、もっと踏み込んでリアルな様を演出してほしいと思った。
と言うのは、今年3月にリニューアルした第1展示室「先史・古代」の人形が異様にリアルで(左下の写真)、その迫真性に惹きつけられたからである。人形が生身の人物に見え、縄文時代の集落に迷い込んだ気分になり縄文の空気が肌で感じられる。
この手の展示物の人形の出来栄えなどあまり気にしていなかったが、精緻でリアルな人形に独特の効果があると実感した。だから、中世の写経生の人形に生身の人間の表情があれば、中世の下級ホワイトカラーの生活がより身につまされて伝わると思った。それが、歴史のねつ造につながるかどうかはよくわからないが。
第1展示室 先史・古代
第2展示室 中世
第3展示室 近世
第4展示室 民俗
第5展示室 近代
第6展示室 現代
現物展示もあるが、模型やジオラマも多い。巨大な歴史図鑑である。それぞれの展示物の説明を読みながら歩いていると一つの展示室だけで疲労困憊してしまう。だから、大半の展示物はザーッと見ただけだ。
中世の展示室で写経生の姿(右下の写真)に接したのには感動した。最近読んだ『天平の時代』 (栄原永遠男/集英社版日本の歴史4)に描かれていた写経生の生活が印象深く、彼らに感情移入していたからである。写経生の人形の背景には「待遇改善要求」の説明漫画も掲示されている。歴史概説書で抱いたイメージが眼前に現出したので驚いた。
ただし、この写経生のマネキン風人形は顔も手も黒で表情がない。それでも雰囲気は伝わってくるが、もっと踏み込んでリアルな様を演出してほしいと思った。
と言うのは、今年3月にリニューアルした第1展示室「先史・古代」の人形が異様にリアルで(左下の写真)、その迫真性に惹きつけられたからである。人形が生身の人物に見え、縄文時代の集落に迷い込んだ気分になり縄文の空気が肌で感じられる。
この手の展示物の人形の出来栄えなどあまり気にしていなかったが、精緻でリアルな人形に独特の効果があると実感した。だから、中世の写経生の人形に生身の人間の表情があれば、中世の下級ホワイトカラーの生活がより身につまされて伝わると思った。それが、歴史のねつ造につながるかどうかはよくわからないが。
小説と歴史概説書で天平のイメージを少しつかめた ― 2019年07月06日
光明皇后を主人公にした次の小説を面白く読んだ。
『緋の天空』(葉室麟/集英社文庫)
この小説を読み終えて、その時代背景を確認しようと次の歴史概説書を読んだ。
『天平の時代』 (栄原永遠男/集英社版日本の歴史4)
これは1991年刊行の日本史叢書の1冊で、ほとんど全てのページに多彩なカラー図版があり、文章も読みやすい。
『緋の天空』は藤原不比等の娘として生まれた安宿媛(あすかべひめ・後の光明皇后)の少女時代から没するまでを点描した小説である。主な登場人物は首皇子(おびとのみこ・後の聖武天皇)、膳夫(かしわで・長屋王の息子)、清人(きよと・後の道鏡)などで、彼らの成長していく様を皇位継承の経緯とからめて描いている。
この小説の主な事件は「長屋王の変」や「大仏開眼」だが、印象に残るのは持統・元明・元正・孝謙など女性天皇の姿であり、頼りない聖武天皇をリードする光明皇后の姿である。タイトルの「緋の天空」は「女帝が治める世を蓋う天空の色」を表している。
あらためて、奈良時代とは女帝の時代だと認識した。女帝即位にはそれぞれ事情があったが、女帝たちは傀儡だったわけではなく、主体的に動いているように見える。
小説がどこまで史実を反映しているか私にはわからない。基本的なことは知っておこうと、歴史学者の書いた『天平の時代』を読んだ。この概説書は、貴族や天皇の政争から経済や社会の様子、国際情勢までをバランスよく描いている。近年になって大量に発掘された木簡の話など研究現場の話題紹介も多い。
『天平の時代』は長屋王邸を図解や写真を交えて詳しく解説している。この屋敷は小説の主要な舞台の一つなのでイメージがふくらんだ。小説にはほとんど登場しない下級の人々の様子も活写されている。写経所で写経という仕事に従事している経師たちの生活は近代の安サラリーマンそのもので、遠い古代社会が身近に感じられた。
私は日本古代史に関しておぼろな知識しかないが、この2冊によって光明皇后や聖武天皇のイメージが具体的になり、長屋王の変の様相も把め、平城京の空気を多少は感じることができた。
『緋の天空』(葉室麟/集英社文庫)
この小説を読み終えて、その時代背景を確認しようと次の歴史概説書を読んだ。
『天平の時代』 (栄原永遠男/集英社版日本の歴史4)
これは1991年刊行の日本史叢書の1冊で、ほとんど全てのページに多彩なカラー図版があり、文章も読みやすい。
『緋の天空』は藤原不比等の娘として生まれた安宿媛(あすかべひめ・後の光明皇后)の少女時代から没するまでを点描した小説である。主な登場人物は首皇子(おびとのみこ・後の聖武天皇)、膳夫(かしわで・長屋王の息子)、清人(きよと・後の道鏡)などで、彼らの成長していく様を皇位継承の経緯とからめて描いている。
この小説の主な事件は「長屋王の変」や「大仏開眼」だが、印象に残るのは持統・元明・元正・孝謙など女性天皇の姿であり、頼りない聖武天皇をリードする光明皇后の姿である。タイトルの「緋の天空」は「女帝が治める世を蓋う天空の色」を表している。
あらためて、奈良時代とは女帝の時代だと認識した。女帝即位にはそれぞれ事情があったが、女帝たちは傀儡だったわけではなく、主体的に動いているように見える。
小説がどこまで史実を反映しているか私にはわからない。基本的なことは知っておこうと、歴史学者の書いた『天平の時代』を読んだ。この概説書は、貴族や天皇の政争から経済や社会の様子、国際情勢までをバランスよく描いている。近年になって大量に発掘された木簡の話など研究現場の話題紹介も多い。
『天平の時代』は長屋王邸を図解や写真を交えて詳しく解説している。この屋敷は小説の主要な舞台の一つなのでイメージがふくらんだ。小説にはほとんど登場しない下級の人々の様子も活写されている。写経所で写経という仕事に従事している経師たちの生活は近代の安サラリーマンそのもので、遠い古代社会が身近に感じられた。
私は日本古代史に関しておぼろな知識しかないが、この2冊によって光明皇后や聖武天皇のイメージが具体的になり、長屋王の変の様相も把め、平城京の空気を多少は感じることができた。
懐かしき映画『新宿泥棒日記』……そして『由比正雪』を ― 2019年06月30日
Space早稲田で流山児事務所公演の『由比正雪』(作:唐十郎、演出:流山児祥)を観た。1968年に状況劇場が紅テントで上演した芝居の再演である。
私が状況劇場の芝居を観始めたのは1969年12月の『少女都市』からなので『由比正雪』は観ていない。戯曲は当時ゾッキ本で古本屋に積まれていた『ジョン・シルバー』(唐十郎作、横尾忠則絵/天声出版)に収録されているので読んでいる。
観ていないこの芝居に懐かしさを感じるのは、私の状況劇場初体験が大島渚の映画『新宿泥棒日記』だからである。横尾忠則主演のこの迷宮映画の影の主演が唐十郎で、花園神社の紅テントの芝居が映画の中に色濃く混入している。混入している芝居は『由比正雪』である。
映画『新宿泥棒日記』で唐十郎に幻惑され、大学祭での状況劇場の歌謡ショーに圧倒され、紅テントに通うことになった。すべて半世紀前の1969年、私が二十歳の頃の事象である。
今回の『由比正雪』では、流山児祥が「朝は海の中 昼は丘 夜は川の中 それは誰?」という唄を少しアレンジして披露したのがうれしかった。この歌は『由比正雪』の戯曲には出てこない(おそらく、それ以前の『アリババ』の挿入歌)が、『新宿泥棒日記』の牽引歌である。『由比正雪』でこの歌は聞けないだろうと思っていたので感激した。
21世紀になって観た『由比正雪』は、半世紀前の舞台とはかなり違っているだろうと推察できる。「剣にとって美とはなにか」というセリフは今と昔ではウケが違うし、「由比正雪」に革命騒乱を重ねる趣向も60年代的だと思う。にもかかわらず、2019年の若い役者たちがこの芝居を演じていることに感動し、不思議な感覚におそわれる。唐十郎ファンだった私は、その芝居の射程がこれほど長いとは思っていなかった。
考えてみれば、この1年半で私は唐十郎の芝居6本観ていて、その上演主体がすべて違っている(以下のリスト参照)。スゴイことだと思う。この先の半世紀も唐十郎の芝居は受容されていき、古典になるのだろうか。
2018年1月『秘密の花園』(東京芸術劇場/演出:福原充則)
2018年5月『吸血姫』(劇団唐組/演出:久保井研+唐十郎)
2018年12月『腰巻お仙 振袖火事の巻』(日本の演劇人を育てるプロジェクト/演出:小林七緒)
2019年2月『唐版風の又三郎』(シアターコクーン/演出:金守珍)
2019年6月『蛇姫様』(新宿梁山泊/演出:金守珍)
2019年6月『由比正雪』(流山児事務所/演出:流山児祥)
私が状況劇場の芝居を観始めたのは1969年12月の『少女都市』からなので『由比正雪』は観ていない。戯曲は当時ゾッキ本で古本屋に積まれていた『ジョン・シルバー』(唐十郎作、横尾忠則絵/天声出版)に収録されているので読んでいる。
観ていないこの芝居に懐かしさを感じるのは、私の状況劇場初体験が大島渚の映画『新宿泥棒日記』だからである。横尾忠則主演のこの迷宮映画の影の主演が唐十郎で、花園神社の紅テントの芝居が映画の中に色濃く混入している。混入している芝居は『由比正雪』である。
映画『新宿泥棒日記』で唐十郎に幻惑され、大学祭での状況劇場の歌謡ショーに圧倒され、紅テントに通うことになった。すべて半世紀前の1969年、私が二十歳の頃の事象である。
今回の『由比正雪』では、流山児祥が「朝は海の中 昼は丘 夜は川の中 それは誰?」という唄を少しアレンジして披露したのがうれしかった。この歌は『由比正雪』の戯曲には出てこない(おそらく、それ以前の『アリババ』の挿入歌)が、『新宿泥棒日記』の牽引歌である。『由比正雪』でこの歌は聞けないだろうと思っていたので感激した。
21世紀になって観た『由比正雪』は、半世紀前の舞台とはかなり違っているだろうと推察できる。「剣にとって美とはなにか」というセリフは今と昔ではウケが違うし、「由比正雪」に革命騒乱を重ねる趣向も60年代的だと思う。にもかかわらず、2019年の若い役者たちがこの芝居を演じていることに感動し、不思議な感覚におそわれる。唐十郎ファンだった私は、その芝居の射程がこれほど長いとは思っていなかった。
考えてみれば、この1年半で私は唐十郎の芝居6本観ていて、その上演主体がすべて違っている(以下のリスト参照)。スゴイことだと思う。この先の半世紀も唐十郎の芝居は受容されていき、古典になるのだろうか。
2018年1月『秘密の花園』(東京芸術劇場/演出:福原充則)
2018年5月『吸血姫』(劇団唐組/演出:久保井研+唐十郎)
2018年12月『腰巻お仙 振袖火事の巻』(日本の演劇人を育てるプロジェクト/演出:小林七緒)
2019年2月『唐版風の又三郎』(シアターコクーン/演出:金守珍)
2019年6月『蛇姫様』(新宿梁山泊/演出:金守珍)
2019年6月『由比正雪』(流山児事務所/演出:流山児祥)
謎解きエンタメを超えた香港ミステリー『13・67』 ― 2019年06月28日
最近の香港情勢のニュースに接して、昨年、ある人から香港関連の面白いミステリーがあると薦められたのを思い出した。それが次の本である。
『13・67』(陳浩基/天野健太郎訳/文藝春秋)
このタイトルは2013年と1967年を表している。オビには「雨傘革命前夜の2013年から反英暴動が勃発した1967年ヘ、逆年代記で語られる名刑事の事件簿から見えてくる香港現代史の闇とは!」とある。
この惹句を読んで香港現代史を背景にした重厚なハードボルド風ミステリーを予感した。香港現代史の勉強気分でこのミステリーを読もうと思った。2段組み480ページ、そこそこの分量である。
第1章を読み終えて、大きな勘違いに気づいた。長編のつもりで読み始めたが、これは短編集ではないか。第1章と思ったのは私の早とちりで、単に「1」とあるだけだった。
冒頭の短編は荒唐無稽スレスレの名探偵謎解きミステリーで、ドンデン返しに近いあざやかな終盤に驚き、面白いとは思った。しかし、私が予感したテイストとはかなり違う。2013年の香港が舞台なのに雨傘運動を予感させる社会背景はあまり感じられず、器用な作家のエンタメ謎解き小説に思えた。
あらためて目次を確認すると、本書は6編の連作小説で第1編が2013年の話、1編ごとに時代を遡り、最後が1967年の話になっているらしい。期待したような長編ではないので中断しようと思いながらも、もう一つぐらいは読もうと2編目を読んだ。
2編目の舞台は10年遡って2003年、同じ名探偵(香港警察の刑事)が登場する。これも驚きの謎解きミステリーで、うっちゃりをくらった気分になった。次は騙されないぞと3編目も読み……ということを繰り返して最後の6編目まで読み、毎回うっちゃりをくらった。
エンタメ謎解きの面白さに引っぱられての読了たが、読み進めるごとに香港社会の時代背景が見えてくる。6編の連作が見事にからみあっていて、全編を読み終えると香港半世紀の社会変動の時代を生き抜いた刑事の半生に立ち会った気分になる。謎解きに驚いた後にジワリと時代と社会が浮かびあがる。そして半世紀という時間への感慨がわく。まさに本書は、私が予感し期待していたような長編だったのである。
最終編の1967年は文化大革命の頃で、その影響を受けた香港の若者は祖国復帰の理念のもとに反植民地・反英国の武装闘争に走る。それから半世紀、香港の若者は中国支配への抗議運動をしている。これが歴史である。このエンタメ謎解きミステリーには、そんな歴史背景が確かに投影されている。
『13・67』(陳浩基/天野健太郎訳/文藝春秋)
このタイトルは2013年と1967年を表している。オビには「雨傘革命前夜の2013年から反英暴動が勃発した1967年ヘ、逆年代記で語られる名刑事の事件簿から見えてくる香港現代史の闇とは!」とある。
この惹句を読んで香港現代史を背景にした重厚なハードボルド風ミステリーを予感した。香港現代史の勉強気分でこのミステリーを読もうと思った。2段組み480ページ、そこそこの分量である。
第1章を読み終えて、大きな勘違いに気づいた。長編のつもりで読み始めたが、これは短編集ではないか。第1章と思ったのは私の早とちりで、単に「1」とあるだけだった。
冒頭の短編は荒唐無稽スレスレの名探偵謎解きミステリーで、ドンデン返しに近いあざやかな終盤に驚き、面白いとは思った。しかし、私が予感したテイストとはかなり違う。2013年の香港が舞台なのに雨傘運動を予感させる社会背景はあまり感じられず、器用な作家のエンタメ謎解き小説に思えた。
あらためて目次を確認すると、本書は6編の連作小説で第1編が2013年の話、1編ごとに時代を遡り、最後が1967年の話になっているらしい。期待したような長編ではないので中断しようと思いながらも、もう一つぐらいは読もうと2編目を読んだ。
2編目の舞台は10年遡って2003年、同じ名探偵(香港警察の刑事)が登場する。これも驚きの謎解きミステリーで、うっちゃりをくらった気分になった。次は騙されないぞと3編目も読み……ということを繰り返して最後の6編目まで読み、毎回うっちゃりをくらった。
エンタメ謎解きの面白さに引っぱられての読了たが、読み進めるごとに香港社会の時代背景が見えてくる。6編の連作が見事にからみあっていて、全編を読み終えると香港半世紀の社会変動の時代を生き抜いた刑事の半生に立ち会った気分になる。謎解きに驚いた後にジワリと時代と社会が浮かびあがる。そして半世紀という時間への感慨がわく。まさに本書は、私が予感し期待していたような長編だったのである。
最終編の1967年は文化大革命の頃で、その影響を受けた香港の若者は祖国復帰の理念のもとに反植民地・反英国の武装闘争に走る。それから半世紀、香港の若者は中国支配への抗議運動をしている。これが歴史である。このエンタメ謎解きミステリーには、そんな歴史背景が確かに投影されている。
『理不尽な進化』はびっくりするほど面白いが難しい ― 2019年06月26日
進化論に関するとても面白い本を読んだ。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ』(吉川博満/朝日出版社)
先日読んだ 『科学する心』(池澤夏樹) で本書を知った。池澤氏は次のように紹介していた。
「これ(絶滅)については2014年に出た吉川博満の『理不尽な進化』(朝日出版社)という本が必読。ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた。まるで新しい生物の姿を教えられた。」
進化論には関心があるので「必読」と言われれば読まないわけにはいかない。巻末の著者紹介によれば吉川博満氏は「哲学、卓球、犬猫鳥、ロック、映画、単車などに関心がある文筆業」で、科学者ではない。本書の序章は「私たちは進化論が大好きである。」というフレーズで始まる。進化論好きが高じて進化論を深く考察する本書が誕生したようだ。
文章は読みやすくユーモアに富んでいる。進化論の面白さにグイグイ引き込まれていくが、決してわかりやすい本ではない。本書によって進化論の歴史や最新の進化学説を把握できるが、本書の主目的は「人類にとって進化論とは何か」というややこしいテーマである。後半になると哲学的展開になり、かなり難解である。
池澤氏の「ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた」という感想はよくわかる。私も同じ気持ちである。わが書架には進化論に関する一般向け概説書は20冊ばかり並んでいるが、本書を読んで、自分が進化論をいかに浅薄にしかとらえていなかったかを知った。
進化が進歩とは別物だとは了解していたつもりだったが、進化の理不尽さ不条理性を明快に指摘されると、やはりびっくりする。そして、進化論が内包する「歴史性」「哲学性」の迷路にたじろいでしまう。本書の終り近くの次の一節が印象に残った。
「1957年、ときの知識人の帝王ジャン=ポール・サルトルは、「マルクス主義はわれわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と宣言した。サルトルにとって哲学とは、時代と社会を支配する理念である。近代の第一期におけるそれはデカルトとロック、第二期はカントとヘーゲル、そして第三期(当時)はマルクス主義である、というわけだ。(…)いま私は、「ダーウィニズムこそ、われわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と叫びたい気分である(もし冥途のサルトルが「やっぱりマルクス主義は取り消し」と言ったならダーウィニズムはマルクス主義と交代ということになるし、いまなお譲らなければ四つ目の王座を用意することになるだろう)。
【蛇足】 本書の終わりの方でギリシア詩人アイスキュロスの「ハリネズミと狐」に関する一節が紹介されている。私はたまたま今月初めにアイスキュロスの現存全作品(といっても文庫本1冊)を読んだばかりである。「ハリネズミと狐」は思い出すことができず、わが記憶力の頼りなさを嘆きつつ調べてみると、この一節はギリシア悲劇詩人アイスキュロスではなくギリシア詩人アルキロコスのもののようだ。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ』(吉川博満/朝日出版社)
先日読んだ 『科学する心』(池澤夏樹) で本書を知った。池澤氏は次のように紹介していた。
「これ(絶滅)については2014年に出た吉川博満の『理不尽な進化』(朝日出版社)という本が必読。ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた。まるで新しい生物の姿を教えられた。」
進化論には関心があるので「必読」と言われれば読まないわけにはいかない。巻末の著者紹介によれば吉川博満氏は「哲学、卓球、犬猫鳥、ロック、映画、単車などに関心がある文筆業」で、科学者ではない。本書の序章は「私たちは進化論が大好きである。」というフレーズで始まる。進化論好きが高じて進化論を深く考察する本書が誕生したようだ。
文章は読みやすくユーモアに富んでいる。進化論の面白さにグイグイ引き込まれていくが、決してわかりやすい本ではない。本書によって進化論の歴史や最新の進化学説を把握できるが、本書の主目的は「人類にとって進化論とは何か」というややこしいテーマである。後半になると哲学的展開になり、かなり難解である。
池澤氏の「ぼくはこの本によって文字通り蒙を啓かれた」という感想はよくわかる。私も同じ気持ちである。わが書架には進化論に関する一般向け概説書は20冊ばかり並んでいるが、本書を読んで、自分が進化論をいかに浅薄にしかとらえていなかったかを知った。
進化が進歩とは別物だとは了解していたつもりだったが、進化の理不尽さ不条理性を明快に指摘されると、やはりびっくりする。そして、進化論が内包する「歴史性」「哲学性」の迷路にたじろいでしまう。本書の終り近くの次の一節が印象に残った。
「1957年、ときの知識人の帝王ジャン=ポール・サルトルは、「マルクス主義はわれわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と宣言した。サルトルにとって哲学とは、時代と社会を支配する理念である。近代の第一期におけるそれはデカルトとロック、第二期はカントとヘーゲル、そして第三期(当時)はマルクス主義である、というわけだ。(…)いま私は、「ダーウィニズムこそ、われわれの時代の乗り超え不可能な哲学である」と叫びたい気分である(もし冥途のサルトルが「やっぱりマルクス主義は取り消し」と言ったならダーウィニズムはマルクス主義と交代ということになるし、いまなお譲らなければ四つ目の王座を用意することになるだろう)。
【蛇足】 本書の終わりの方でギリシア詩人アイスキュロスの「ハリネズミと狐」に関する一節が紹介されている。私はたまたま今月初めにアイスキュロスの現存全作品(といっても文庫本1冊)を読んだばかりである。「ハリネズミと狐」は思い出すことができず、わが記憶力の頼りなさを嘆きつつ調べてみると、この一節はギリシア悲劇詩人アイスキュロスではなくギリシア詩人アルキロコスのもののようだ。
大黒屋光太夫を描いた「三谷かぶき」を観た ― 2019年06月22日
歌舞伎座で6月大歌舞伎の昼の部、夜の部を観た。演目は以下の通り。
昼の部
寿式三番叟
女車引
梶原平三誉石切(鶴ケ岡八幡社頭の場)
恋飛脚大和往来(封印切)
夜の部
月光露針路日本(つきあかりめざすにほん)
昼の部と夜の部ではガラリと趣が変わる。いかにも歌舞伎らしい歌舞伎と三谷幸喜作・演出の「三谷かぶき」の両方を楽しめた。
昼の部は目出たくて華やかな舞踊劇に続いて中村吉右衛門&播磨屋一門の「石切梶原」と片岡仁左衛門&松嶋屋一門の「封印切」という歌舞伎らしい見せ場芝居である。両方とも300両(約2000万円)という金銭がらみの話で、どちらも「石」や「金包みの封印」を「切る」という場面がクライマックスになっているのが面白い。吉右衛門の貫禄、仁左衛門の色気と姿の良さを感じた。
夜の部『月光露針路日本』は大黒屋光太夫が主人公である。2年前に『おろしや国酔夢譚』(井上靖)と『大黒屋光太夫』(吉村昭/新潮文庫)を読んだので、大黒屋光太夫への関心はある。ロシアに漂着し、サンクトペテルブルグで女帝エカテリーナ2世に謁見して帰国を果たした人物である。
『月光露針路日本』の原作は『風雲児たち』(みなもと太郎)という長編漫画だそうだ。私はこの漫画は読んでいない(みなもと太郎は懐かしい名前だ。ギャク漫画『ホモホモ7』はスゴかった)。
光太夫を演ずるのは松本幸四郎で、市川猿之助や片岡愛之助などの他に幸四郎の父(白鸚)と子(染五郎)も出演する。
市川高麗蔵(61歳)が可憐なロシア娘・アグリッピーナに扮して染五郎(14歳)の恋人を演じたのは驚いた。不気味・滑稽を通り越して何でも演じてしまう歌舞伎役者のスゴさを感じた。
「三谷かぶき」は面白くてわかりやすい。義太夫節で「イルクーツク!」などと朗々と張り上げるので、私でも容易に聞き取れる。江戸時代の人にとっての歌舞伎や義太夫は、かくもわかりやすくて面白いものだったのであろうと想像した。
『月光露針路日本』の舞台は船上とロシアの地で日本は登場しない。日本が見えてきた所で終幕になる。いい終わり方だと思う。だが、日本に帰還して江戸で取り調べを受けるあたりまでを舞台で観たいとも思った。
光太夫が江戸に到達したのは寛政5年(1673年)、松平定信の寛政の改革の頃である。その前年には海国兵談の林子平が処罰され、翌年には写楽の大首絵が売り出される。仮に当時の情報流通事情がよく、オカミの統制も緩かったとすれば、光太夫の物語は絶好の同時代演劇の材料になっただろうと空想する。
昼の部
寿式三番叟
女車引
梶原平三誉石切(鶴ケ岡八幡社頭の場)
恋飛脚大和往来(封印切)
夜の部
月光露針路日本(つきあかりめざすにほん)
昼の部と夜の部ではガラリと趣が変わる。いかにも歌舞伎らしい歌舞伎と三谷幸喜作・演出の「三谷かぶき」の両方を楽しめた。
昼の部は目出たくて華やかな舞踊劇に続いて中村吉右衛門&播磨屋一門の「石切梶原」と片岡仁左衛門&松嶋屋一門の「封印切」という歌舞伎らしい見せ場芝居である。両方とも300両(約2000万円)という金銭がらみの話で、どちらも「石」や「金包みの封印」を「切る」という場面がクライマックスになっているのが面白い。吉右衛門の貫禄、仁左衛門の色気と姿の良さを感じた。
夜の部『月光露針路日本』は大黒屋光太夫が主人公である。2年前に『おろしや国酔夢譚』(井上靖)と『大黒屋光太夫』(吉村昭/新潮文庫)を読んだので、大黒屋光太夫への関心はある。ロシアに漂着し、サンクトペテルブルグで女帝エカテリーナ2世に謁見して帰国を果たした人物である。
『月光露針路日本』の原作は『風雲児たち』(みなもと太郎)という長編漫画だそうだ。私はこの漫画は読んでいない(みなもと太郎は懐かしい名前だ。ギャク漫画『ホモホモ7』はスゴかった)。
光太夫を演ずるのは松本幸四郎で、市川猿之助や片岡愛之助などの他に幸四郎の父(白鸚)と子(染五郎)も出演する。
市川高麗蔵(61歳)が可憐なロシア娘・アグリッピーナに扮して染五郎(14歳)の恋人を演じたのは驚いた。不気味・滑稽を通り越して何でも演じてしまう歌舞伎役者のスゴさを感じた。
「三谷かぶき」は面白くてわかりやすい。義太夫節で「イルクーツク!」などと朗々と張り上げるので、私でも容易に聞き取れる。江戸時代の人にとっての歌舞伎や義太夫は、かくもわかりやすくて面白いものだったのであろうと想像した。
『月光露針路日本』の舞台は船上とロシアの地で日本は登場しない。日本が見えてきた所で終幕になる。いい終わり方だと思う。だが、日本に帰還して江戸で取り調べを受けるあたりまでを舞台で観たいとも思った。
光太夫が江戸に到達したのは寛政5年(1673年)、松平定信の寛政の改革の頃である。その前年には海国兵談の林子平が処罰され、翌年には写楽の大首絵が売り出される。仮に当時の情報流通事情がよく、オカミの統制も緩かったとすれば、光太夫の物語は絶好の同時代演劇の材料になっただろうと空想する。
神奈川芸術劇場で『ゴドーを待ちながら』を観た ― 2019年06月20日
神奈川芸術劇場で『ゴドーを待ちながら』(演出:多田淳之介)を観た。20世紀を代表するあまりに高名な芝居である。ベケットがノーベル文学賞を受賞したのは1969年、川端康成受賞の翌年で私が大学生の頃だ。
学生の頃に戯曲を読み舞台写真も眺め、それだけで芝居の印象は刻印された。これまで私はこの芝居を観る機会がなかったが、観ていなくてもすでに観た気分になっていた。
今回の神奈川芸術劇場での公演は「昭和平成版」と「令和版」の二つのバージョンを交互に上演すると知り、よくわからないながらも面白そうだと思いチケットを手配した。
私は早とちりで「交互」の意味を勘違いしていた。1回の公演で「場」ごとに「昭和平成版」「令和版」を繰り返しながら上演するのだろうと思い、1回で2パターンを観劇できるのはお得だと感じたのである。
チケット入手後、「昭和平成版」と「令和版」の公演を交互に上演するのだと気づいた。私のチケットは「昭和平成版」だった。上演時間を考えてみれば一度に2つのバージョンをやるのは難しいと気づくはずだった。しかし、この芝居は少しずつズレながらのくり返しの趣があるので、「昭和平成版」「令和版」を混ぜてくり返すという方法も面白いと思う。
『ゴドーを待ちながら』(昭和平成版)の舞台は十分に楽しめた。円形舞台の4方向に客席があり、客席部分に舞台装置がくいこんでいる仕掛けが面白い。わかりやすさとわかりにくさが混在した20世紀の古典民話のような世界だと感じた。
実は、今月末『由比正雪』(作:唐十郎、演出:流山児祥)という唐十郎の初期作品の再演を観る予定があり、そのことも今回の観劇の動機だった。『由比正雪』のチラシに「虚実入り混じった唐版「ゴドーを待ちながら」が始まる」とあり、ナンジャと思っているときにゴドー上演を知り、そのチケットも手配したのである。『由比正雪』を観たら、あらためてゴドーを考えてみたい。
学生の頃に戯曲を読み舞台写真も眺め、それだけで芝居の印象は刻印された。これまで私はこの芝居を観る機会がなかったが、観ていなくてもすでに観た気分になっていた。
今回の神奈川芸術劇場での公演は「昭和平成版」と「令和版」の二つのバージョンを交互に上演すると知り、よくわからないながらも面白そうだと思いチケットを手配した。
私は早とちりで「交互」の意味を勘違いしていた。1回の公演で「場」ごとに「昭和平成版」「令和版」を繰り返しながら上演するのだろうと思い、1回で2パターンを観劇できるのはお得だと感じたのである。
チケット入手後、「昭和平成版」と「令和版」の公演を交互に上演するのだと気づいた。私のチケットは「昭和平成版」だった。上演時間を考えてみれば一度に2つのバージョンをやるのは難しいと気づくはずだった。しかし、この芝居は少しずつズレながらのくり返しの趣があるので、「昭和平成版」「令和版」を混ぜてくり返すという方法も面白いと思う。
『ゴドーを待ちながら』(昭和平成版)の舞台は十分に楽しめた。円形舞台の4方向に客席があり、客席部分に舞台装置がくいこんでいる仕掛けが面白い。わかりやすさとわかりにくさが混在した20世紀の古典民話のような世界だと感じた。
実は、今月末『由比正雪』(作:唐十郎、演出:流山児祥)という唐十郎の初期作品の再演を観る予定があり、そのことも今回の観劇の動機だった。『由比正雪』のチラシに「虚実入り混じった唐版「ゴドーを待ちながら」が始まる」とあり、ナンジャと思っているときにゴドー上演を知り、そのチケットも手配したのである。『由比正雪』を観たら、あらためてゴドーを考えてみたい。

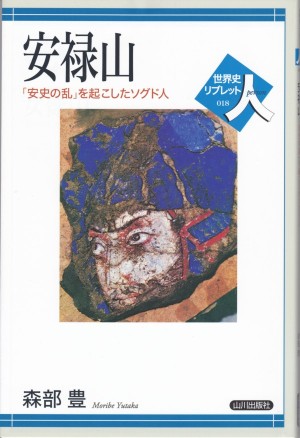








最近のコメント