NHK「クローズアップ現代」で偶然の発生を体験した ― 2010年12月13日
本日の夕刻、出来心で何冊かの本を買った。そして、夕食を摂りながら、テレビを見ながら、夕刊の見出しを眺めながら、買ってきた本をパラパラと拾い読みをしていた(どれかに集中しろ)。
入手したばかりの本の拾い読みは「まえがき」や「目次」にザーっと目を通して本文をパラパラめくることになる。電子書籍では体感しにくい至福のひとときである。
本日買った本の一つが竹内薫著「ゼロから学ぶ量子力学」だった。この著者の本を買ったのは初めてだと思う。量子力学の入門書や専門書は何冊か本棚の奥にあるが、ちょっとしたきっかけがあって、つい本書に手が伸びた。
この本の「まえがき」は少々ふざけている。筆者は著者でなく飼い猫だ。「吾輩の名はエルヴィン。すでに名がある。ご主人様の名前は竹内薫と言って、ぐうたらで、いつも寝てばかりいる」と書き出している。かの「シュレディンガーの猫」のようだ。この猫が飼い主について「大学と大学院では理論物理をやっていたらしいが、なぜか、就職せずに、大学の講師などをやっている。売れない作家だというが、取材と称しては飲み歩いているようにしか見えない」などと述べている。
・・・と拾い読みをした直後に、テレビ画面に竹内薫氏本人が現れた。NHKの「クローズアップ現代」でイグ・ノーベル賞を取り上げ、その解説者が竹内薫氏だったのだ。テレビではサイエンス作家と紹介されていたように記憶している。いま読んでいる文章の著者が目の前のテレビに登場したのには驚いた。その風貌が文章にマッチしているのに納得したりもした。
竹内薫氏がどの程度テレビに登場している方なのかは知らないが、私にとっては書籍でもテレビでも初めての方だったので、驚きもひとしおだった。
竹内薫氏の著書を読みながら本日の「クローズアップ現代」を観ていた人は日本中で何人いたのだろうか。この確率を計算するのは難しい。
入手したばかりの本の拾い読みは「まえがき」や「目次」にザーっと目を通して本文をパラパラめくることになる。電子書籍では体感しにくい至福のひとときである。
本日買った本の一つが竹内薫著「ゼロから学ぶ量子力学」だった。この著者の本を買ったのは初めてだと思う。量子力学の入門書や専門書は何冊か本棚の奥にあるが、ちょっとしたきっかけがあって、つい本書に手が伸びた。
この本の「まえがき」は少々ふざけている。筆者は著者でなく飼い猫だ。「吾輩の名はエルヴィン。すでに名がある。ご主人様の名前は竹内薫と言って、ぐうたらで、いつも寝てばかりいる」と書き出している。かの「シュレディンガーの猫」のようだ。この猫が飼い主について「大学と大学院では理論物理をやっていたらしいが、なぜか、就職せずに、大学の講師などをやっている。売れない作家だというが、取材と称しては飲み歩いているようにしか見えない」などと述べている。
・・・と拾い読みをした直後に、テレビ画面に竹内薫氏本人が現れた。NHKの「クローズアップ現代」でイグ・ノーベル賞を取り上げ、その解説者が竹内薫氏だったのだ。テレビではサイエンス作家と紹介されていたように記憶している。いま読んでいる文章の著者が目の前のテレビに登場したのには驚いた。その風貌が文章にマッチしているのに納得したりもした。
竹内薫氏がどの程度テレビに登場している方なのかは知らないが、私にとっては書籍でもテレビでも初めての方だったので、驚きもひとしおだった。
竹内薫氏の著書を読みながら本日の「クローズアップ現代」を観ていた人は日本中で何人いたのだろうか。この確率を計算するのは難しい。
万能人の洞察か、妄想愉快犯の哲学講談か――『量子の社会哲学』は奇書 ― 2010年12月15日
新聞の書評で『量子の社会哲学:革命は過去を救うと猫が言う』(大澤真幸/講談社)という本を知り、読みたくなった。朝日新聞(2010年11月21日)では柄谷行人氏が「読者は、本書を楽しみつつ読むうちに、自ずと世界が違って見えてくることを感じるだろう」と推奨し、日経新聞(2010年10月31日)では金森修氏が「率直に言って破たんギリギリ。だが、それでも一読に値する」と紹介している。
著者は社会学者だ。「まえがき」で次のように宣言している。
「私は、本書で、量子力学が、現代社会を理解し、未来社会を構想するための基本的な指針を与えるような、政治的・倫理的な含意を宿していることを示してみよう」
納得できるか否かは別として、まさにその通りの内容だった。20世紀初頭に登場した量子力学は、一般常識では受け容れ難いさまざま不思議な事象を提示した。著者はその不思議な事象を、量子力学と同時代に発生した別分野(美術、探偵小説、精神分析、革命理論etc)の様々な事項に関連づけて論じている。何とも奇妙な本である。
私は科学史には興味がある。だから、あまり抵抗なく本書を読み始めることができた。しかし、読み進めるにつれて「これは、何じゃ!」という感慨に何度もおそわれた。それでも、途中で投げ出さずに比較的短時間で読了できたのだから、本書は「面白い」と言うことになるだろう。著者の主張がよく理解できたわけではないが。
本書には多様な素材が登場する。冒頭で登場するのはA.C.クラークの短編『神の九〇億の御名』だ。大昔に『SFマガジン』で読んだ作品だったので、それだけで本書の世界に引き込まれてしまった。SF小説としては、ハインラインの『夏への扉』やウィリアム・テンの短編も出てくる。
絵画への言及も多い。ベラスケス、ゴヤ、ティチアーノ、エル・グレコ、モネ、ターナー、セザンヌ、ピカソ、ジャコメッティなどなどだ。
映画はヒッチコックの『裏窓』『鳥』と黒沢明の『羅生門』だ。コナン・ドイルやチェスタトンやアガサ・クリスティらの探偵小説も出てくる。
もちろん、社会科学関係の素材も多い。フロイトの精神分析理論、ヴェーバーの著作、ナチスを理論的に正当化した政治学者カール・シュミットの著作などに続いて、レーニンやローザ・ルクセンブルグが登場してきたのにはいささか驚いた。
これらが量子力学とどう絡んでいるのか、不審に思う人も多いだろうが、著者は自信たっぷりな包丁さばきで、この多様な素材から量子力学との対応を引き出してくる。
著者は、探偵小説の登場を「相対性理論」の登場に対応づけ、フロイト理論や『羅生門』やセザンヌの絵画の解釈を「相対性理論」から「量子力学」への発展に対応させる。牽強付会とも思える強引さである。
レーニンに至っては本書の準主役級の役割を担わされている。ロシア革命とその後のスターリニズムも量子力学で読み解かれている。
自然科学、社会科学、哲学、文学、美術などの分野を自由に駆け巡るさまはルネサンス人的だが、量子力学の研究者が本書をどう読むか、興味深い。俗流解釈だとして切り捨てるかもしれない。しかし、量子力学などの認識論が哲学に隣接しているのは確かであり、本書を荒唐無稽と言い切るのも困難かもしれない。
物理学者の並木美喜雄氏は『量子力学入門』(岩波新書/1992.1)において次のように述べている。
「物理学などの自然科学研究の背景にも科学者自身の社会観や哲学がある。思想的背景といってもよい。平素はあまり表面に出ないが、科学が未知の新しい領域に突入しようとするとき、科学者自身の哲学的志向が科学研究の具体面に現れることがある」
量子力学が登場して発展した20世紀において、同時代的に生起したさまざまな分野の現象が何らかの意味で互いに呼応していたと観るのは、あながち間違いではないかもしれない。
私自身は、本書を読みながら、この百年の文化・社会・政治のダイナミズムを再認識することができた。そして、私たちが生きている現代社会の基盤を垣間見たような気分になった。
なお、本書の第Ⅷ部(最終部)のタイトルは「時間の発生」である。ここではマクタガードの「時間は実在しない」という時間論をふまえて、それを否定する形で「時間は社会的現象だ」という考察をしている。
「時間とは何か」は面白いテーマなので興味深く読めた。著者の考察に説得されたわけではないが、拾い物をしたような「お得感」を得た。
著者は社会学者だ。「まえがき」で次のように宣言している。
「私は、本書で、量子力学が、現代社会を理解し、未来社会を構想するための基本的な指針を与えるような、政治的・倫理的な含意を宿していることを示してみよう」
納得できるか否かは別として、まさにその通りの内容だった。20世紀初頭に登場した量子力学は、一般常識では受け容れ難いさまざま不思議な事象を提示した。著者はその不思議な事象を、量子力学と同時代に発生した別分野(美術、探偵小説、精神分析、革命理論etc)の様々な事項に関連づけて論じている。何とも奇妙な本である。
私は科学史には興味がある。だから、あまり抵抗なく本書を読み始めることができた。しかし、読み進めるにつれて「これは、何じゃ!」という感慨に何度もおそわれた。それでも、途中で投げ出さずに比較的短時間で読了できたのだから、本書は「面白い」と言うことになるだろう。著者の主張がよく理解できたわけではないが。
本書には多様な素材が登場する。冒頭で登場するのはA.C.クラークの短編『神の九〇億の御名』だ。大昔に『SFマガジン』で読んだ作品だったので、それだけで本書の世界に引き込まれてしまった。SF小説としては、ハインラインの『夏への扉』やウィリアム・テンの短編も出てくる。
絵画への言及も多い。ベラスケス、ゴヤ、ティチアーノ、エル・グレコ、モネ、ターナー、セザンヌ、ピカソ、ジャコメッティなどなどだ。
映画はヒッチコックの『裏窓』『鳥』と黒沢明の『羅生門』だ。コナン・ドイルやチェスタトンやアガサ・クリスティらの探偵小説も出てくる。
もちろん、社会科学関係の素材も多い。フロイトの精神分析理論、ヴェーバーの著作、ナチスを理論的に正当化した政治学者カール・シュミットの著作などに続いて、レーニンやローザ・ルクセンブルグが登場してきたのにはいささか驚いた。
これらが量子力学とどう絡んでいるのか、不審に思う人も多いだろうが、著者は自信たっぷりな包丁さばきで、この多様な素材から量子力学との対応を引き出してくる。
著者は、探偵小説の登場を「相対性理論」の登場に対応づけ、フロイト理論や『羅生門』やセザンヌの絵画の解釈を「相対性理論」から「量子力学」への発展に対応させる。牽強付会とも思える強引さである。
レーニンに至っては本書の準主役級の役割を担わされている。ロシア革命とその後のスターリニズムも量子力学で読み解かれている。
自然科学、社会科学、哲学、文学、美術などの分野を自由に駆け巡るさまはルネサンス人的だが、量子力学の研究者が本書をどう読むか、興味深い。俗流解釈だとして切り捨てるかもしれない。しかし、量子力学などの認識論が哲学に隣接しているのは確かであり、本書を荒唐無稽と言い切るのも困難かもしれない。
物理学者の並木美喜雄氏は『量子力学入門』(岩波新書/1992.1)において次のように述べている。
「物理学などの自然科学研究の背景にも科学者自身の社会観や哲学がある。思想的背景といってもよい。平素はあまり表面に出ないが、科学が未知の新しい領域に突入しようとするとき、科学者自身の哲学的志向が科学研究の具体面に現れることがある」
量子力学が登場して発展した20世紀において、同時代的に生起したさまざまな分野の現象が何らかの意味で互いに呼応していたと観るのは、あながち間違いではないかもしれない。
私自身は、本書を読みながら、この百年の文化・社会・政治のダイナミズムを再認識することができた。そして、私たちが生きている現代社会の基盤を垣間見たような気分になった。
なお、本書の第Ⅷ部(最終部)のタイトルは「時間の発生」である。ここではマクタガードの「時間は実在しない」という時間論をふまえて、それを否定する形で「時間は社会的現象だ」という考察をしている。
「時間とは何か」は面白いテーマなので興味深く読めた。著者の考察に説得されたわけではないが、拾い物をしたような「お得感」を得た。
歴史の勉強の難しさと面白さが伝わってくる『学校で習わない日本の近代史』 ― 2010年12月21日
『学校で習わない日本の近代史:なぜ戦争は起こるのか』(横内則之/文芸社/2010.8.15)を読んだ。「あとがき」で著者は「私は、専門家ではなく、浅学菲才の一介の歴史好きにすぎない」と述べている。これは謙遜で、該博な知識と知見に基づいた読みでのある本だった。
巻末の著者プロフィールによれば、横内氏は1945年生まれ、トヨタ自動車に長く奉職し、トヨタ紡績の専務取締役、常勤監査役を歴任し2008年6月に退任している。
そして、退任の3カ月後の2008年9月から4カ月間「地球1周の船旅」に参加している。実は私もこの船旅、つまり「第63回ピースボート地球一周の船旅」に参加した。ついでに言えば、私は著者より2歳下だが、著者と同じように2008年6月に仕事をやめ、その3カ月後に乗船した。
そんなわけで、乗船中に著者の顔と名前は存知あげていたが、お話しをする機会はなかった。乗船中に知り合った別の人からのメールで、横内氏が本書を上梓したことを知った。
著者が「はじめに」に書いているように、本書はピースボートの船内で著者が開設した自主企画講座『日本の近代(明治維新から東京裁判まで)』で12回にわたって話した内容を元にしている。
ピースボート(著者は本書において「ピースボート」という言葉を使わず「地球1周の船旅」で通している)の乗客の約半数は20~30歳代の若者(あとの半分は中高年)で、この自主講座は「日本史をきちんと学んでいないであろう若者たち」を対象に開いたようだ。
私は、船内で『日本の近代』という自主講座が開かれていることは知っていたが、一度も参加しなかった。今から思えば、残念なことをしたと悔やんでいる。
この自主講座に参加しなかった理由の一つは、ピースボート・シンパによる進歩的文化人的・戦後民主主義擁護的な内容だろうと思って敬遠したのだ。やがて、参加した人の話から、そういう内容ではないということが分かった。ラバウル寄港の前に船上で開催された「戦没者慰霊祭」の仕掛け人が横内氏であることも聞いていた。しかし、船上で「お勉強」するのが億劫なこともあり、この講座に参加することはなかった。
この講座の最終回のタイトルは「なぜ戦争は起こるのか」だった。参加した知人に「で、結論はどうだったんですか」と尋ねると「戦争はなくならない、という話だった」という答えが返ってきた。「戦争をなくそう」という理念をもっていると思われるピースボートの船内の自主講座でそんな結論を話すとは面白いなと思った。
その知人は同時に「横内さんは、何であんなによく知っているのだろう。歴史資料にもずいぶん詳しい」と感心していた。
……そんな、ささやかな体験をふまえて本書を読んだ。
明治維新からサンフランシスコ講和条約に至るまでの歴史をていねいに解説すると同時に、さまざまな歴史事項への著者の評価も織り込まれている。私の知人が著者の該博な知識と知見に感心したのも納得できる。また、今回の船旅も含めて、著者が歴史的な場所を訪れたときの感想や、著者のビジネスマンとしての見聞に基づいた感想なども挿入されていて興味深い。
本書は10章で構成されている。各章末に「まとめ」というタイトルの箇条書きの要約が載っているのが親切でうれしい。
第4章「第一次世界大戦と大正デモクラシー」の末尾には以下のような一節もある。
「これ(社会主義思想、国家改造論、軍部主導の国家総動員体制の準備などの風潮)に対し、政治が本来の役割を果さず、無為無策を続ける内に、国民に政治不信がつのり、昭和の動乱の芽が育まれていった。平成の今日と、どこか似通ったところの多い時代であった。」
私にとって、本書によって蒙を啓かれた気分になった事象がたくさんあった。いちいち挙げると煩雑になるので個別事象の紹介はしない。歴史的事象の背景にはさまざまな力学がはたらいていて、歴史を知るということは一筋縄ではいかないということを、本書のさまざまな事例からあらためて認識した。
歴史とは常に勝者の視点で語られるものだから、歴史の実相を捉えるのは簡単ではない、ということは分かっているつもりだったが、本書を読みながら「歴史の勉強の難しさと面白さ」を感じることができた。
私たちが過去の歴史を振り返るとき、すでにその後の展開を知っているので結果論から眺めることができる。日中戦争や太平洋戦争も、敗戦で終わることを知ったうえで、当時の事項を眺めることになる。だが、結果を知っているからと言って歴史を正しく評価できるわけではない。
歴史上の人々の言動や行動についても、だれが正しくてだれが間違っているかの評価は人によって異なるだろう。「歴史が評価してくれる」という言葉もあるが、時間が経過したからと言って、評価が簡単に定まるわけではない。
結局のところ、歴史を勉強するということは、歴史を掘り下げていくことによって歴史の見方を更新し、現代につながるさまざまな事象への自分なりの捉え方を構築していくことになるのだと思う。より多くの国民が「歴史好き」にならなければ、国も社会も危うくなるだろう。
本書には、そんなことを考えさせてくれる教育的な効果もあり、それが表題の「学校で習わない・・・」につながっているように思えた。
巻末の著者プロフィールによれば、横内氏は1945年生まれ、トヨタ自動車に長く奉職し、トヨタ紡績の専務取締役、常勤監査役を歴任し2008年6月に退任している。
そして、退任の3カ月後の2008年9月から4カ月間「地球1周の船旅」に参加している。実は私もこの船旅、つまり「第63回ピースボート地球一周の船旅」に参加した。ついでに言えば、私は著者より2歳下だが、著者と同じように2008年6月に仕事をやめ、その3カ月後に乗船した。
そんなわけで、乗船中に著者の顔と名前は存知あげていたが、お話しをする機会はなかった。乗船中に知り合った別の人からのメールで、横内氏が本書を上梓したことを知った。
著者が「はじめに」に書いているように、本書はピースボートの船内で著者が開設した自主企画講座『日本の近代(明治維新から東京裁判まで)』で12回にわたって話した内容を元にしている。
ピースボート(著者は本書において「ピースボート」という言葉を使わず「地球1周の船旅」で通している)の乗客の約半数は20~30歳代の若者(あとの半分は中高年)で、この自主講座は「日本史をきちんと学んでいないであろう若者たち」を対象に開いたようだ。
私は、船内で『日本の近代』という自主講座が開かれていることは知っていたが、一度も参加しなかった。今から思えば、残念なことをしたと悔やんでいる。
この自主講座に参加しなかった理由の一つは、ピースボート・シンパによる進歩的文化人的・戦後民主主義擁護的な内容だろうと思って敬遠したのだ。やがて、参加した人の話から、そういう内容ではないということが分かった。ラバウル寄港の前に船上で開催された「戦没者慰霊祭」の仕掛け人が横内氏であることも聞いていた。しかし、船上で「お勉強」するのが億劫なこともあり、この講座に参加することはなかった。
この講座の最終回のタイトルは「なぜ戦争は起こるのか」だった。参加した知人に「で、結論はどうだったんですか」と尋ねると「戦争はなくならない、という話だった」という答えが返ってきた。「戦争をなくそう」という理念をもっていると思われるピースボートの船内の自主講座でそんな結論を話すとは面白いなと思った。
その知人は同時に「横内さんは、何であんなによく知っているのだろう。歴史資料にもずいぶん詳しい」と感心していた。
……そんな、ささやかな体験をふまえて本書を読んだ。
明治維新からサンフランシスコ講和条約に至るまでの歴史をていねいに解説すると同時に、さまざまな歴史事項への著者の評価も織り込まれている。私の知人が著者の該博な知識と知見に感心したのも納得できる。また、今回の船旅も含めて、著者が歴史的な場所を訪れたときの感想や、著者のビジネスマンとしての見聞に基づいた感想なども挿入されていて興味深い。
本書は10章で構成されている。各章末に「まとめ」というタイトルの箇条書きの要約が載っているのが親切でうれしい。
第4章「第一次世界大戦と大正デモクラシー」の末尾には以下のような一節もある。
「これ(社会主義思想、国家改造論、軍部主導の国家総動員体制の準備などの風潮)に対し、政治が本来の役割を果さず、無為無策を続ける内に、国民に政治不信がつのり、昭和の動乱の芽が育まれていった。平成の今日と、どこか似通ったところの多い時代であった。」
私にとって、本書によって蒙を啓かれた気分になった事象がたくさんあった。いちいち挙げると煩雑になるので個別事象の紹介はしない。歴史的事象の背景にはさまざまな力学がはたらいていて、歴史を知るということは一筋縄ではいかないということを、本書のさまざまな事例からあらためて認識した。
歴史とは常に勝者の視点で語られるものだから、歴史の実相を捉えるのは簡単ではない、ということは分かっているつもりだったが、本書を読みながら「歴史の勉強の難しさと面白さ」を感じることができた。
私たちが過去の歴史を振り返るとき、すでにその後の展開を知っているので結果論から眺めることができる。日中戦争や太平洋戦争も、敗戦で終わることを知ったうえで、当時の事項を眺めることになる。だが、結果を知っているからと言って歴史を正しく評価できるわけではない。
歴史上の人々の言動や行動についても、だれが正しくてだれが間違っているかの評価は人によって異なるだろう。「歴史が評価してくれる」という言葉もあるが、時間が経過したからと言って、評価が簡単に定まるわけではない。
結局のところ、歴史を勉強するということは、歴史を掘り下げていくことによって歴史の見方を更新し、現代につながるさまざまな事象への自分なりの捉え方を構築していくことになるのだと思う。より多くの国民が「歴史好き」にならなければ、国も社会も危うくなるだろう。
本書には、そんなことを考えさせてくれる教育的な効果もあり、それが表題の「学校で習わない・・・」につながっているように思えた。
「忠臣蔵」は武士の窮状を反映している ― 2010年12月30日
やはり、年末は忠臣蔵だ。
十数年前、忠臣蔵がマイブームになり、忠臣蔵の本や映像に熱中したことがあった。今でも忠臣蔵は好きである。
河出文庫で三田村鳶魚の『赤穂義士 忠臣蔵の真相』という本が出た(2010年12月20日発行)。さっそく読んでみた。久々に忠臣蔵関連の本を読んだが、やはり忠臣蔵は面白い。
三田村鳶魚の著作を読んだのは初めてだ。本書は昭和5年に発行された『横から見た赤穂義士』を改題した本だそうだ。忠臣蔵の史実を考察した80年前の文章だが、洒脱な語り口と冷静な分析が魅力的である。
世の中に忠臣蔵関連の本は山ほどあるが、おおむね次のように分類できるだろう。
(1) 忠臣蔵のドラマを正統的に描いたフィクション
(大仏次郎『赤穂浪士』、船橋聖一『新編忠臣蔵』etc)
(2) 忠臣蔵の外伝や別視点で描いたフィクション
(井上ひさし『不忠臣蔵』、清水義範『上野介の忠臣蔵』etc)
(3) 忠臣蔵の史実を考察した本
(海音寺潮五郎『赤穂義士』、野口武彦『忠臣蔵』etc)
(4) 忠臣蔵の史実と『仮名手本忠臣蔵』を考察した本
(渡辺保『忠臣蔵』、丸谷才一『忠臣蔵とは何か』etc)
これらのどのジャンルの本もそれぞれに楽しむことができる。本書は(3)のジャンルの本だ。
本書を読んであらためて認識したのは、当時の武士の窮状だ。戦争がなくなった江戸時代において、生産活動に従事していない武士階級を社会が養っていくのは容易でなかったようだ。「水戸の光圀なども、永年仕えている家来の事を考えてみるのに、持高がきまっている上に、家来の子供はずんずん殖えるので、何とも手当の仕様がない、といって嘆息しております」という記述もある。
いったん浪人になると仕官するのは容易ではなく、「浪人問題というものは、その頃大変な問題だった」のだ。
武士と言えば、代々にわたって一つの大名家に仕えているイメージが強いが「武士は渡りもの」とも言われ、いろいろな事情から主君を渡り歩いていく事例も多かったようだ。赤穂の浅野家は分家で、長矩はその三代目である。比較的歴史の浅い大名家なので、赤穂義士の中にも二君に仕えることになった新参者がかなりいたそうだ。
また、その当時から、武士といえども軍学や武芸ではなく「算勘」の達者な者が重用されるようになってきていた。映画『武士の家計簿』は幕末の武士を描いているが、元禄の頃から算盤は重要だったのだ。
考えてみれば当たり前の話で、大名とは現在で言えば県知事や市長のようなものだから、領地の経営や生産活動向上ができるスタッフが必要だったのだ。だから、浅野家でも算盤高い大野九郎兵衛の方が大石内蔵助より重用されていたのだ。
本書によれば浅野長矩という人は勘定高い当世風の大名であり、つまりは倹約を奨励する吝嗇な人で、無能な人ではなく実務にも口出しする人だったようだ。それが松の廊下につながってしまったのだ。
武芸より算盤が重要な時代になっていたからこそ、赤穂義士の討ち入りは当時でも「時代錯誤」ととらえられ、それだけに事件の衝撃は大きかったのだ。
彼らの処分をめぐって「儒者が入り乱れての論戦」の果てに切腹と決まった背景にも、浪人問題をかかえた当時の社会情勢があったようだ。彼らの行動を「忠義の見本」とする理念を通すには、切腹しかなかったのだ。生き永らえて浪人になって晩節を汚すようなことをしでかしてもらってはマズいし、他家に士官したのでは討ち入りが仕官目的のように見えてしまうからだ。
忠臣蔵は娯楽としても面白い上に、多様な解釈ができる材料をたくさん内包していて、現代社会に通じる教訓を引き出すこともできる。それが忠臣蔵の世界の魅力だ。
十数年前、忠臣蔵がマイブームになり、忠臣蔵の本や映像に熱中したことがあった。今でも忠臣蔵は好きである。
河出文庫で三田村鳶魚の『赤穂義士 忠臣蔵の真相』という本が出た(2010年12月20日発行)。さっそく読んでみた。久々に忠臣蔵関連の本を読んだが、やはり忠臣蔵は面白い。
三田村鳶魚の著作を読んだのは初めてだ。本書は昭和5年に発行された『横から見た赤穂義士』を改題した本だそうだ。忠臣蔵の史実を考察した80年前の文章だが、洒脱な語り口と冷静な分析が魅力的である。
世の中に忠臣蔵関連の本は山ほどあるが、おおむね次のように分類できるだろう。
(1) 忠臣蔵のドラマを正統的に描いたフィクション
(大仏次郎『赤穂浪士』、船橋聖一『新編忠臣蔵』etc)
(2) 忠臣蔵の外伝や別視点で描いたフィクション
(井上ひさし『不忠臣蔵』、清水義範『上野介の忠臣蔵』etc)
(3) 忠臣蔵の史実を考察した本
(海音寺潮五郎『赤穂義士』、野口武彦『忠臣蔵』etc)
(4) 忠臣蔵の史実と『仮名手本忠臣蔵』を考察した本
(渡辺保『忠臣蔵』、丸谷才一『忠臣蔵とは何か』etc)
これらのどのジャンルの本もそれぞれに楽しむことができる。本書は(3)のジャンルの本だ。
本書を読んであらためて認識したのは、当時の武士の窮状だ。戦争がなくなった江戸時代において、生産活動に従事していない武士階級を社会が養っていくのは容易でなかったようだ。「水戸の光圀なども、永年仕えている家来の事を考えてみるのに、持高がきまっている上に、家来の子供はずんずん殖えるので、何とも手当の仕様がない、といって嘆息しております」という記述もある。
いったん浪人になると仕官するのは容易ではなく、「浪人問題というものは、その頃大変な問題だった」のだ。
武士と言えば、代々にわたって一つの大名家に仕えているイメージが強いが「武士は渡りもの」とも言われ、いろいろな事情から主君を渡り歩いていく事例も多かったようだ。赤穂の浅野家は分家で、長矩はその三代目である。比較的歴史の浅い大名家なので、赤穂義士の中にも二君に仕えることになった新参者がかなりいたそうだ。
また、その当時から、武士といえども軍学や武芸ではなく「算勘」の達者な者が重用されるようになってきていた。映画『武士の家計簿』は幕末の武士を描いているが、元禄の頃から算盤は重要だったのだ。
考えてみれば当たり前の話で、大名とは現在で言えば県知事や市長のようなものだから、領地の経営や生産活動向上ができるスタッフが必要だったのだ。だから、浅野家でも算盤高い大野九郎兵衛の方が大石内蔵助より重用されていたのだ。
本書によれば浅野長矩という人は勘定高い当世風の大名であり、つまりは倹約を奨励する吝嗇な人で、無能な人ではなく実務にも口出しする人だったようだ。それが松の廊下につながってしまったのだ。
武芸より算盤が重要な時代になっていたからこそ、赤穂義士の討ち入りは当時でも「時代錯誤」ととらえられ、それだけに事件の衝撃は大きかったのだ。
彼らの処分をめぐって「儒者が入り乱れての論戦」の果てに切腹と決まった背景にも、浪人問題をかかえた当時の社会情勢があったようだ。彼らの行動を「忠義の見本」とする理念を通すには、切腹しかなかったのだ。生き永らえて浪人になって晩節を汚すようなことをしでかしてもらってはマズいし、他家に士官したのでは討ち入りが仕官目的のように見えてしまうからだ。
忠臣蔵は娯楽としても面白い上に、多様な解釈ができる材料をたくさん内包していて、現代社会に通じる教訓を引き出すこともできる。それが忠臣蔵の世界の魅力だ。
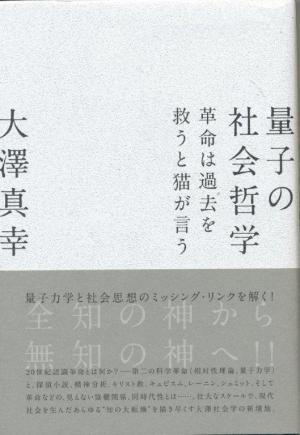


最近のコメント