西欧中心の見方を否定した『イスラーム歴史物語』 ― 2022年06月15日
昨年1月、イスラーム史の概説書を4冊続けて読んだ。その記憶がかなり薄れてきているので、復習気分で次の本を読んだ。
『ビジュアル版 イスラーム歴史物語』(後藤明/講談社/2001.11)
1年半前に読んだ『イスラーム帝国のジハード』(小杉泰/講談社学術文庫)巻末の参考文献で本書を「ビジュアル版で、文章も非常に読みやすい。著者の専門は初期イスラームであるが、日本でイスラーム史全体を俯瞰できる数少ない一人。」と紹介していた。それが目に止まり、本書を古書で入手した。
確かに俯瞰的な歴史物語である。文明の始まりから20世紀末までを100話(1話3ページ)で語っている。全体は6章に分かれていて、各章の冒頭の「総説」で章全体を概観しているので頭に入りやすい。
第1話では「イスラム教」でなく「イスラーム」と表記した理由を述べている。アラビア語の原音に近いということもあるが、イスラームはふつうの意味での「宗教」をこえているからである。国家や社会がどうあるべきかという理念を含む用語として「イスラーム」としたそうだ。確かに、歴史を俯瞰するとき「イスラーム世界」という概念を使うとわかりやすくなるように思える。
本書の特徴は西欧中心的な歴史の見方から脱却している点にある。イスラームの歴史なら、ムハンマド登場の7世紀から始まると思うが、本書はそのはるか以前の古代オリエント文明から書き起こしている。イスラームの起源がそこにある、としているからである。少し面食らうが、本書を読むと納得できた。
西欧が自身の歴史の起源をギリシアとする考え方は短絡的で、かつギリシアを一面的にしか捉えていない。文明の起源はオリエント文明にあり、ギリシアはその一部にすぎない。そんな視点から、著者は古代オリエントの文明を承継したのはイスラームであるとしている。
ローマ帝国の時代において、ローマは政治の中心だっただけで経済・文化の中心は以前と同じように東方にあったという見解にも驚いた。視点をずらせば、そのようにも見えてくる気がする。著者は5世紀の「西ローマ帝国滅亡」を「滅亡」としたのは19世紀の西欧史家の誤謬だとし、次のように述べている。
「ローマ帝国は、476年のあとも繁栄をつづけました。そして7世紀に、イスラームはローマ帝国の主要な領土であるシリア、エジプト、北アフリカを継承します。そののち、長い時間をかけて、イスラーム世界はローマ帝国を飲み込んでいきます。それは、1453年にオスマン帝国がコンスタンティノープルを征服したときに完了します。イスラーム世界とは、まさしくローマ帝国の継承者でもあるわけです。」
かなりの期間、歴史の主役をつとめていたイスラームが傾き始めるのは14~15世紀頃からであり、コンスタンティノープル征服の頃は最盛期を過ぎていたことになる。18世紀にはイスラームは西欧やロシアに逆転され、19~20世紀にはイスラーム地域の大部分が西欧の植民地になってしまう。本書は、そんな大きな流れの物語である。
以下、私が本書で興味深く感じた事柄を列挙する。
・西欧文明の実質的故郷はイスラム文明のイベリア半島だ。
・ソグド商人は時代とともにムスリム商人になった。
・ポルトガル人が日本に伝えた鉄砲はオスマン帝国製か?
・喜望峰を東に廻って北上し、ムスリム商人が活躍する海域(アラビア海)に出たポルトガルは、港市を襲撃して交易を妨害した。
・インド洋の交易に参入した西欧はアジアに売る商品をもっていなかった。アメリカから調達した銀だけが西欧の「商品」だった。
・西欧は、アメリカから到来した銀とジャガイモによって発展した。
・西欧支配下にあった中東のイスラームは、日露戦争での日本の勝利に沸き返った。
〔P.S.〕
本書を半ばまで読んだ時点で、著者への興味から他の著書を検索し、『イスラーム世界史』(角川ソフィア文庫)という本を見つけ、ネット書店で注文した。届いた文庫本は本書を文庫化したものだった。
『ビジュアル版 イスラーム歴史物語』(後藤明/講談社/2001.11)
1年半前に読んだ『イスラーム帝国のジハード』(小杉泰/講談社学術文庫)巻末の参考文献で本書を「ビジュアル版で、文章も非常に読みやすい。著者の専門は初期イスラームであるが、日本でイスラーム史全体を俯瞰できる数少ない一人。」と紹介していた。それが目に止まり、本書を古書で入手した。
確かに俯瞰的な歴史物語である。文明の始まりから20世紀末までを100話(1話3ページ)で語っている。全体は6章に分かれていて、各章の冒頭の「総説」で章全体を概観しているので頭に入りやすい。
第1話では「イスラム教」でなく「イスラーム」と表記した理由を述べている。アラビア語の原音に近いということもあるが、イスラームはふつうの意味での「宗教」をこえているからである。国家や社会がどうあるべきかという理念を含む用語として「イスラーム」としたそうだ。確かに、歴史を俯瞰するとき「イスラーム世界」という概念を使うとわかりやすくなるように思える。
本書の特徴は西欧中心的な歴史の見方から脱却している点にある。イスラームの歴史なら、ムハンマド登場の7世紀から始まると思うが、本書はそのはるか以前の古代オリエント文明から書き起こしている。イスラームの起源がそこにある、としているからである。少し面食らうが、本書を読むと納得できた。
西欧が自身の歴史の起源をギリシアとする考え方は短絡的で、かつギリシアを一面的にしか捉えていない。文明の起源はオリエント文明にあり、ギリシアはその一部にすぎない。そんな視点から、著者は古代オリエントの文明を承継したのはイスラームであるとしている。
ローマ帝国の時代において、ローマは政治の中心だっただけで経済・文化の中心は以前と同じように東方にあったという見解にも驚いた。視点をずらせば、そのようにも見えてくる気がする。著者は5世紀の「西ローマ帝国滅亡」を「滅亡」としたのは19世紀の西欧史家の誤謬だとし、次のように述べている。
「ローマ帝国は、476年のあとも繁栄をつづけました。そして7世紀に、イスラームはローマ帝国の主要な領土であるシリア、エジプト、北アフリカを継承します。そののち、長い時間をかけて、イスラーム世界はローマ帝国を飲み込んでいきます。それは、1453年にオスマン帝国がコンスタンティノープルを征服したときに完了します。イスラーム世界とは、まさしくローマ帝国の継承者でもあるわけです。」
かなりの期間、歴史の主役をつとめていたイスラームが傾き始めるのは14~15世紀頃からであり、コンスタンティノープル征服の頃は最盛期を過ぎていたことになる。18世紀にはイスラームは西欧やロシアに逆転され、19~20世紀にはイスラーム地域の大部分が西欧の植民地になってしまう。本書は、そんな大きな流れの物語である。
以下、私が本書で興味深く感じた事柄を列挙する。
・西欧文明の実質的故郷はイスラム文明のイベリア半島だ。
・ソグド商人は時代とともにムスリム商人になった。
・ポルトガル人が日本に伝えた鉄砲はオスマン帝国製か?
・喜望峰を東に廻って北上し、ムスリム商人が活躍する海域(アラビア海)に出たポルトガルは、港市を襲撃して交易を妨害した。
・インド洋の交易に参入した西欧はアジアに売る商品をもっていなかった。アメリカから調達した銀だけが西欧の「商品」だった。
・西欧は、アメリカから到来した銀とジャガイモによって発展した。
・西欧支配下にあった中東のイスラームは、日露戦争での日本の勝利に沸き返った。
〔P.S.〕
本書を半ばまで読んだ時点で、著者への興味から他の著書を検索し、『イスラーム世界史』(角川ソフィア文庫)という本を見つけ、ネット書店で注文した。届いた文庫本は本書を文庫化したものだった。
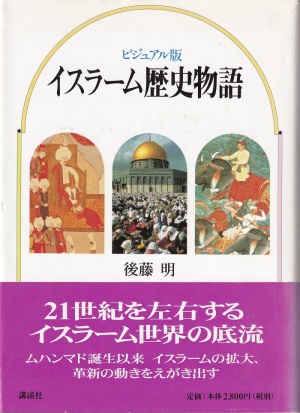
最近のコメント