5年の長旅に同行した気分になる『ビーグル号航海記』 ― 2022年04月14日
ついに『ビーグル号航海記』を読んだ。
『ビーグル号航海記(上)(下)』(チャールズ・R・ダーウィン/荒俣宏訳/平凡社)
この本を読もうと思ったのは14年前である。その頃、私は世界一周の船旅をし、ガラパゴス島で大いに感動した。帰国したらダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思った。帰国後、ネット古書店で入手した『ビーグル号世界周航記』(ダーウィン著)という本は、『ダーウィンは何を見たか』というダイジェスト解説の翻訳本で、私が期待した航海記ではなかった。
きちんとした全訳を読まねばと思いつつ瞬く間に時は流れ、最近になって荒俣宏による新訳版(2013年刊行)が出ていると知って入手した。この大部な本を読もうとして、やはり『種の起源』を先に読んでおく方がいいと思った。
ダーウィンが『種の起源』を出版したのは50歳(1859年)の時だ。ビーグル号による世界一周は22~27歳の5年間、『ビーグル号航海記』は30歳の時の本だ。『種の起源』の内容を知ったうえで『航海記』のなかにその萌芽を探すような読書が面白いと考えたのである。で、『種の起源』を読み終えてから、この『航海記』を読んだ。
本書を読んで、まず感じたのは、これはいわゆる「航海記」ではなく「博物誌」に近いということだ。そもそも、世界一周5年間は長すぎる。ダーウィンは日本で言えば幕末の人で横井小楠と同い年(リンカーンとも同年)、緒方洪庵や佐久間象山と同世代で、ペリーよりは15歳若い。ビーグル号は帆船だが、世界一周だけなら5年はかからない。ビーグル号の任務は南米の測量・海図作成で、ダーウィンは艦長の話し相手の博物学者として自費で同乗したのである。
というわけで、最初の4年近く、ビーグル号は南米の海岸を行ったり来たりしていて、その間、ダーウィンは南米の陸地のあちこちを探検旅行している。本書の大半はその報告である。動植物に関する記録も多いが、地形や地質、化石に関する考察・記録が多い。そもそも、この本の原題の邦訳は『海軍大佐フィッロイ艦長指揮、英国海軍軍艦ビーグル号による世界周航中に訪れた諸国の自然史ならびに地質学に関する調査紀要』であって、「航海記」ではない。と言っても「航海記」部分も十分に面白い。
本書を読んで感嘆するのはダーウィンの該博な知識と広範な探究心・好奇心である。博物学者・古生物学者・地質学者・文化人類学者の目を兼ね備えている。標本を採集し、ときには解剖もする。サンゴ礁がなぜできるかについての自説を詳細に展開し、奴隷制への厳しい批判も述べている。
で、ガラパゴスである。全21章の第17章が「ガラパゴス諸島」で、下巻の中盤あたりだ。その第17章にたどり着くのを楽しみに大部な本書を読み進めた。どの章も興味深いが、やはり「第17章 ガラパゴス諸島」が面白い。
固有生物が多く生息し、各島によってそれが変化しているさまを目の当たりにしたダーウィンの高揚が伝わってくる。ダーウィンは次のように述べている。
「地質学の年代でいえばつい最近まで、このあたりは青海原に覆われていたと信じたくなる。ということはつまり、時間と空間の両次元で、あの大いなる事実――神秘の中の神秘――つまり新しい生物がこの地上に出現する現場へと、われわれはいくらか接近した、ということになるのかもしれない。」
「(…)以上のような事実を深く考えると、ついつい、自然の創造力といった言葉を使いたくなってしまう。この自然の創造力が、これだけ荒涼とした岩だらけの小島群に投下された作用の大きさには、まったく驚かされるものがある。」
〈種の起源〉を探究する好奇心は20代の「航海」のなかに確かに息づいている。眼前の興味深い事象を観察しながら、悠久の時間を考察しているのだ。
この大部な『ビーグル号航海記』を読み終えたとき、長年の宿題を果たしたと感じると同時に、ダーウィンの5年にわたる長旅につきあって、共に故国に帰航した気になった。感無量の気分である。
〔蛇足〕
『ビーグル号航海記』を読んでいて、今回のウクライナ侵攻を想起するシーンに出くわした。ブラジルの将軍とインディオの戦闘に関して、インディオに同情的なダーウィンは、脱出に成功したインディオ父子の姿から「バイロンが描く英雄マゼッパ」を連想している。マゼッパは、つい最近読んだ『物語ウクライナの歴史』にも登場する17世紀のウクライナ独立闘争の英雄で、現在はウクライナの紙幣にもなっている。
『ビーグル号航海記(上)(下)』(チャールズ・R・ダーウィン/荒俣宏訳/平凡社)
この本を読もうと思ったのは14年前である。その頃、私は世界一周の船旅をし、ガラパゴス島で大いに感動した。帰国したらダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思った。帰国後、ネット古書店で入手した『ビーグル号世界周航記』(ダーウィン著)という本は、『ダーウィンは何を見たか』というダイジェスト解説の翻訳本で、私が期待した航海記ではなかった。
きちんとした全訳を読まねばと思いつつ瞬く間に時は流れ、最近になって荒俣宏による新訳版(2013年刊行)が出ていると知って入手した。この大部な本を読もうとして、やはり『種の起源』を先に読んでおく方がいいと思った。
ダーウィンが『種の起源』を出版したのは50歳(1859年)の時だ。ビーグル号による世界一周は22~27歳の5年間、『ビーグル号航海記』は30歳の時の本だ。『種の起源』の内容を知ったうえで『航海記』のなかにその萌芽を探すような読書が面白いと考えたのである。で、『種の起源』を読み終えてから、この『航海記』を読んだ。
本書を読んで、まず感じたのは、これはいわゆる「航海記」ではなく「博物誌」に近いということだ。そもそも、世界一周5年間は長すぎる。ダーウィンは日本で言えば幕末の人で横井小楠と同い年(リンカーンとも同年)、緒方洪庵や佐久間象山と同世代で、ペリーよりは15歳若い。ビーグル号は帆船だが、世界一周だけなら5年はかからない。ビーグル号の任務は南米の測量・海図作成で、ダーウィンは艦長の話し相手の博物学者として自費で同乗したのである。
というわけで、最初の4年近く、ビーグル号は南米の海岸を行ったり来たりしていて、その間、ダーウィンは南米の陸地のあちこちを探検旅行している。本書の大半はその報告である。動植物に関する記録も多いが、地形や地質、化石に関する考察・記録が多い。そもそも、この本の原題の邦訳は『海軍大佐フィッロイ艦長指揮、英国海軍軍艦ビーグル号による世界周航中に訪れた諸国の自然史ならびに地質学に関する調査紀要』であって、「航海記」ではない。と言っても「航海記」部分も十分に面白い。
本書を読んで感嘆するのはダーウィンの該博な知識と広範な探究心・好奇心である。博物学者・古生物学者・地質学者・文化人類学者の目を兼ね備えている。標本を採集し、ときには解剖もする。サンゴ礁がなぜできるかについての自説を詳細に展開し、奴隷制への厳しい批判も述べている。
で、ガラパゴスである。全21章の第17章が「ガラパゴス諸島」で、下巻の中盤あたりだ。その第17章にたどり着くのを楽しみに大部な本書を読み進めた。どの章も興味深いが、やはり「第17章 ガラパゴス諸島」が面白い。
固有生物が多く生息し、各島によってそれが変化しているさまを目の当たりにしたダーウィンの高揚が伝わってくる。ダーウィンは次のように述べている。
「地質学の年代でいえばつい最近まで、このあたりは青海原に覆われていたと信じたくなる。ということはつまり、時間と空間の両次元で、あの大いなる事実――神秘の中の神秘――つまり新しい生物がこの地上に出現する現場へと、われわれはいくらか接近した、ということになるのかもしれない。」
「(…)以上のような事実を深く考えると、ついつい、自然の創造力といった言葉を使いたくなってしまう。この自然の創造力が、これだけ荒涼とした岩だらけの小島群に投下された作用の大きさには、まったく驚かされるものがある。」
〈種の起源〉を探究する好奇心は20代の「航海」のなかに確かに息づいている。眼前の興味深い事象を観察しながら、悠久の時間を考察しているのだ。
この大部な『ビーグル号航海記』を読み終えたとき、長年の宿題を果たしたと感じると同時に、ダーウィンの5年にわたる長旅につきあって、共に故国に帰航した気になった。感無量の気分である。
〔蛇足〕
『ビーグル号航海記』を読んでいて、今回のウクライナ侵攻を想起するシーンに出くわした。ブラジルの将軍とインディオの戦闘に関して、インディオに同情的なダーウィンは、脱出に成功したインディオ父子の姿から「バイロンが描く英雄マゼッパ」を連想している。マゼッパは、つい最近読んだ『物語ウクライナの歴史』にも登場する17世紀のウクライナ独立闘争の英雄で、現在はウクライナの紙幣にもなっている。
『種の起源』はやはり名著だ ― 2022年04月01日
私は14年前にガラパゴス諸島に行ったことがあり、現地のダーウィン研究所も見学した。そのとき、ダーウィンの『ビーグル号航海記』を読もうと思ったが、うかうかと年月が経ち、最近になって荒俣宏による新訳を入手した。だが、書店で光文社古典新訳文庫の『種の起源』を手にしたとき、『ビーグル号航海記』の前に『種の起源』を読むべきだと感じた。この高名な書でダーウインの思想を把握したうえで航海記を読む方がよさそうに思えたのである。で、『種の起源』を読んだ。
『種の起源(上)(下)』(ダーウィン/渡辺政隆訳/光文社古典新訳文庫)
(上)(下)2冊で約800頁、かなりの分量である。ダーウインの進化論に関しては教科書や解説書などで知っているつもりだ。その概要は数頁で尽くせそうに思える。800頁も費やしていったい何を語っているのだろうと興味がわいた。「訳者まえがき」によれば、この書は構想中の大著の「要約」だったそうだ。
本書を読了して、ダーウィンが本書を「要約」とした気分がわかった。本書でダーウィンは「種は、継起するわずかな変異が保存され蓄積されることで変わってきた」という「自然淘汰」を力強く主張し、「生物は創造主によって個別に創造された」という「創造説」を否定している。主旨はそれだけだ。その論拠として膨大で多様なな証拠を「要約」的に提示している。もっと語りたいという著者の気持ちが随所に垣間見える。
意外なことに「進化」や「適者生存」という言葉は出てこない。訳者解説によれば、これらの用語は社会学者スペンサーによるもので、『種の起源』の後の版には出てくるそうだ(本書は初版の翻訳)。キーワードはあくまで「自然淘汰」で、この言葉は繰り返し出てくる。
ダーウィンは本書で、栽培植物や飼育動物から世界中の野生の動植物にいたる多様な動植物を取り上げ、自然淘汰の証拠を詳細に論じている。だが、人間や類人猿への言及はない。人間の祖先が猿だとも述べていない。
半世紀以上前の学生時代、生物専攻の友人からファーブルがダーウィンに批判的だったと聞いたことがある。そのとき、現場重視のファーブルと理論重視のダーウィンという構図が浮かんだ。目の前の昆虫を地道に観察・探究するオタク的なファーブルが、頭デッカチに大風呂敷を広げるダーウィンを評価できなかったのだろうと感じた。『種の起源』を読んで、それは間違いだと気づいた。
ダーウィンもファーブルに劣らないフィールドワークの人である。ミミズ、ハト、ハチをはじめ多くの生物を自ら飼育・観察・研究している。化石も研究している。さまざまな実験も重ねている。もちろん、広範な研究者たちの成果も検討していて、ファーブルの研究成果への言及もある。
ガラパゴス諸島への言及は思ったより少ない。ダーウィンはガラパゴスのフィンチを観察して進化論を着想したと聞いたことがある。だが、本書にフィンチは登場せず、ガラパゴスの扱いもワン・オブ・ゼムに近い。訳者解説によれば「ダーウィンフィンチ」は後世につくられた伝説だそうだ。少しがっかりした。
「自然淘汰」を主張し「創造説」を否定する本書には、くどいと感じる部分も多い。だが、終章は圧巻である。慎重に論を重ねたうえで次のように踏み込んでいる。
「私は類推から出発して、地球上にかつて生息したすべての生物はおそらく、最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかない。」
遺伝学成立前の時代、透徹した視点に達しているのに驚く。次の記述も印象深い。
「さまざまな種類の植物に覆われ、灌木では小鳥が囀り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生き物ものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。」
『種の起源』は広大な自然史・自然誌を探究した名著だと思った。
『種の起源(上)(下)』(ダーウィン/渡辺政隆訳/光文社古典新訳文庫)
(上)(下)2冊で約800頁、かなりの分量である。ダーウインの進化論に関しては教科書や解説書などで知っているつもりだ。その概要は数頁で尽くせそうに思える。800頁も費やしていったい何を語っているのだろうと興味がわいた。「訳者まえがき」によれば、この書は構想中の大著の「要約」だったそうだ。
本書を読了して、ダーウィンが本書を「要約」とした気分がわかった。本書でダーウィンは「種は、継起するわずかな変異が保存され蓄積されることで変わってきた」という「自然淘汰」を力強く主張し、「生物は創造主によって個別に創造された」という「創造説」を否定している。主旨はそれだけだ。その論拠として膨大で多様なな証拠を「要約」的に提示している。もっと語りたいという著者の気持ちが随所に垣間見える。
意外なことに「進化」や「適者生存」という言葉は出てこない。訳者解説によれば、これらの用語は社会学者スペンサーによるもので、『種の起源』の後の版には出てくるそうだ(本書は初版の翻訳)。キーワードはあくまで「自然淘汰」で、この言葉は繰り返し出てくる。
ダーウィンは本書で、栽培植物や飼育動物から世界中の野生の動植物にいたる多様な動植物を取り上げ、自然淘汰の証拠を詳細に論じている。だが、人間や類人猿への言及はない。人間の祖先が猿だとも述べていない。
半世紀以上前の学生時代、生物専攻の友人からファーブルがダーウィンに批判的だったと聞いたことがある。そのとき、現場重視のファーブルと理論重視のダーウィンという構図が浮かんだ。目の前の昆虫を地道に観察・探究するオタク的なファーブルが、頭デッカチに大風呂敷を広げるダーウィンを評価できなかったのだろうと感じた。『種の起源』を読んで、それは間違いだと気づいた。
ダーウィンもファーブルに劣らないフィールドワークの人である。ミミズ、ハト、ハチをはじめ多くの生物を自ら飼育・観察・研究している。化石も研究している。さまざまな実験も重ねている。もちろん、広範な研究者たちの成果も検討していて、ファーブルの研究成果への言及もある。
ガラパゴス諸島への言及は思ったより少ない。ダーウィンはガラパゴスのフィンチを観察して進化論を着想したと聞いたことがある。だが、本書にフィンチは登場せず、ガラパゴスの扱いもワン・オブ・ゼムに近い。訳者解説によれば「ダーウィンフィンチ」は後世につくられた伝説だそうだ。少しがっかりした。
「自然淘汰」を主張し「創造説」を否定する本書には、くどいと感じる部分も多い。だが、終章は圧巻である。慎重に論を重ねたうえで次のように踏み込んでいる。
「私は類推から出発して、地球上にかつて生息したすべての生物はおそらく、最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかない。」
遺伝学成立前の時代、透徹した視点に達しているのに驚く。次の記述も印象深い。
「さまざまな種類の植物に覆われ、灌木では小鳥が囀り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生き物ものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。」
『種の起源』は広大な自然史・自然誌を探究した名著だと思った。
脳科学の知見の面白さが伝わってくる『脳はなにげに不公平』 ― 2021年07月25日
脳科学者の池谷裕二氏が『週刊朝日』に連載しているコラムを集成した文庫本を読んだ。
『脳はなにげに不公平』(池谷裕二/朝日文庫)
週刊誌1頁の『パテカトルの万能薬』と題するこのコラムは現在も連載中だが、本書は2012年~2013年のコラムから62編を厳選したもので、2016年刊行の単行本の文庫版(2019年5月刊行)である。
各コラムは脳科学周辺の最新の科学論文から得た知見をサラリと3ページで紹介するスタイルになっている。数年前に読んだ池谷氏の 『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』は歯ごたえのある解説書で頭が疲れたが、本書は小ネタ集の趣で、とても読みやすい。
最初のコラムのタイトルは「不平等な世界のほうが安定する」である。格差が拡大すると社会不安が増大し、中間層が多い方が社会は安定すると思われるので、このタイトルにドキリする。著者は、全員が1万円ずつを所持する平等社会において平等なルールに基づくランダムにトレードをくり返すと不平等社会に遷移していくシミュレーションを紹介し、次のように述べている。
《平等さを突き詰めると不平等になるのは、自然なプロセスなのです。でも、多くの人は、この至って当たり前の統計的事実に気づかずに(あるいは意図的に無視して?)、平等主義や民主主義の理想像に憧れます。》
なんだか格差社会を追認する言説のように見えるが、これは脳回路を構成するシナプスの話で、少数の強いシナプスと大多数の弱いシナプスによって安定した脳回路ができているそうだ。そのまま人間の社会に適用できる話ではない。
「上流階級ほどモラルが低い?」というコラムも興味深い。これは人間社会を対象にした実験の紹介で、社会的ステータスの高い人ほど「騙してでもいいから、自分に有利に交渉」を進め、下流層の人は率直で正直な交渉をするそうだ。また、下流層の人でも「自分は社会的地位が高い」との前提で行動選択すると非道徳的になっていくそうだ。身も蓋もない話である。
他にも「ヒトは性善説か?」「自由意思はあるか?」など面白い話題を最新科学の知見によって紹介していて、脳の刺激になる――と思ったが、本書には、脳に刺激を与えることの可否に関する話もある。
『脳はなにげに不公平』(池谷裕二/朝日文庫)
週刊誌1頁の『パテカトルの万能薬』と題するこのコラムは現在も連載中だが、本書は2012年~2013年のコラムから62編を厳選したもので、2016年刊行の単行本の文庫版(2019年5月刊行)である。
各コラムは脳科学周辺の最新の科学論文から得た知見をサラリと3ページで紹介するスタイルになっている。数年前に読んだ池谷氏の 『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』は歯ごたえのある解説書で頭が疲れたが、本書は小ネタ集の趣で、とても読みやすい。
最初のコラムのタイトルは「不平等な世界のほうが安定する」である。格差が拡大すると社会不安が増大し、中間層が多い方が社会は安定すると思われるので、このタイトルにドキリする。著者は、全員が1万円ずつを所持する平等社会において平等なルールに基づくランダムにトレードをくり返すと不平等社会に遷移していくシミュレーションを紹介し、次のように述べている。
《平等さを突き詰めると不平等になるのは、自然なプロセスなのです。でも、多くの人は、この至って当たり前の統計的事実に気づかずに(あるいは意図的に無視して?)、平等主義や民主主義の理想像に憧れます。》
なんだか格差社会を追認する言説のように見えるが、これは脳回路を構成するシナプスの話で、少数の強いシナプスと大多数の弱いシナプスによって安定した脳回路ができているそうだ。そのまま人間の社会に適用できる話ではない。
「上流階級ほどモラルが低い?」というコラムも興味深い。これは人間社会を対象にした実験の紹介で、社会的ステータスの高い人ほど「騙してでもいいから、自分に有利に交渉」を進め、下流層の人は率直で正直な交渉をするそうだ。また、下流層の人でも「自分は社会的地位が高い」との前提で行動選択すると非道徳的になっていくそうだ。身も蓋もない話である。
他にも「ヒトは性善説か?」「自由意思はあるか?」など面白い話題を最新科学の知見によって紹介していて、脳の刺激になる――と思ったが、本書には、脳に刺激を与えることの可否に関する話もある。
『物理学の原理と法則』を読み、解明できない難問を再認識 ― 2021年07月19日
高校物理の復習をする気分で次の本を読んだ。
『物理学の原理と法則:科学の基礎から「自然の論理」へ』(池内了/講談社学術文庫)
70歳を過ぎて勉強し直そうという殊勝な心境になったわけではない。毎日の暑さでぼんやりしている頭が多少でもシャンとすれば、という気まぐれで本書に手がのびた。
冒頭で物理学における「原理」「法則」「定理」などの意味を解説していて、大人向け教科書の趣である。続いて、科学史の話題をふまえながら主に力学の原理や法則の説明になり、高校物理の復習気分で頭の体操になった。
話題は高校物理の範囲を超えて特殊相対性理論、一般相対性理論、量子論にまで広がり、ボーズ粒子やフェルミ粒子のスピンの話まで出てくる。著者は宇宙物理学者なので、当然ながら宇宙論やダークマター、ダークエネルギーにまで話題は及ぶ。
と言っても、本書は現代物理学の概説書ではなく、物理学の「考え方」を追究している。最終章のタイトルは「自然の論理と人間の思考」となっていて、「自然の論理によって生み出されたもの」と「自然に対峙する人間の思考によって創出されたもの」を区別して論じている。この二つが必ずしも一致するとは限らないという問題意識が刺激的である。
次のような指摘も面白い。
「現代科学が成功したのは、解ける問題、解きやすい問題、解く方法がわかっている問題、に特化してきたためと言えるかもしれない。自然現象のうち解ける見通しがついている問題を、あたかも難問であるかのような顔をして説いて見せて、あれこれ講釈してきたと言えるかもしれない。」
この指摘に関連して、天才物理学者たちが晩年に非線形の研究に突入したことに触れ、次のように述べている。
「非線形世界に行かねば物理世界は理解できないと、科学者なら誰もが薄々感じているのだが、我々の如き凡百の人間には手は出せない。湯川やハイゼンベルクやアインシュタインは若くしてノーベル賞を受賞したような大天才で、偉大な業績を残したがために思い切った冒険ができたのだろう。結局、成果のない冒険に終わったのだが。」
まだまだ、未開の世界は大きいようだ。
『物理学の原理と法則:科学の基礎から「自然の論理」へ』(池内了/講談社学術文庫)
70歳を過ぎて勉強し直そうという殊勝な心境になったわけではない。毎日の暑さでぼんやりしている頭が多少でもシャンとすれば、という気まぐれで本書に手がのびた。
冒頭で物理学における「原理」「法則」「定理」などの意味を解説していて、大人向け教科書の趣である。続いて、科学史の話題をふまえながら主に力学の原理や法則の説明になり、高校物理の復習気分で頭の体操になった。
話題は高校物理の範囲を超えて特殊相対性理論、一般相対性理論、量子論にまで広がり、ボーズ粒子やフェルミ粒子のスピンの話まで出てくる。著者は宇宙物理学者なので、当然ながら宇宙論やダークマター、ダークエネルギーにまで話題は及ぶ。
と言っても、本書は現代物理学の概説書ではなく、物理学の「考え方」を追究している。最終章のタイトルは「自然の論理と人間の思考」となっていて、「自然の論理によって生み出されたもの」と「自然に対峙する人間の思考によって創出されたもの」を区別して論じている。この二つが必ずしも一致するとは限らないという問題意識が刺激的である。
次のような指摘も面白い。
「現代科学が成功したのは、解ける問題、解きやすい問題、解く方法がわかっている問題、に特化してきたためと言えるかもしれない。自然現象のうち解ける見通しがついている問題を、あたかも難問であるかのような顔をして説いて見せて、あれこれ講釈してきたと言えるかもしれない。」
この指摘に関連して、天才物理学者たちが晩年に非線形の研究に突入したことに触れ、次のように述べている。
「非線形世界に行かねば物理世界は理解できないと、科学者なら誰もが薄々感じているのだが、我々の如き凡百の人間には手は出せない。湯川やハイゼンベルクやアインシュタインは若くしてノーベル賞を受賞したような大天才で、偉大な業績を残したがために思い切った冒険ができたのだろう。結局、成果のない冒険に終わったのだが。」
まだまだ、未開の世界は大きいようだ。
福岡伸一『生命海流』でわが懐かしのガラパゴスを追体験 ― 2021年07月04日
『生物と無生物のあいだ』や
『動的平衡』で知られる生物学者・福岡伸一氏がガラパゴス諸島に行き、その記録を本にした。
『生命海流:GALAPAGOS』(福岡伸一/朝日出版社)
ガラパゴスは私にとって懐かしい場所だ。ピースボートの世界一周で ガラパゴスを訪れた のは13年前の2008年11月で、私は彼の地で還暦をむかえた。これまで、そこそこの数の世界各地の観光地に行ったが、再訪したいと思った場所の筆頭はガラパゴスだった。
もはや私がガラパゴスを再訪する機会はないだろうと思いつつ本書を手にした。美しいカラー写真がたくさん載っている読みやすい本である。
福岡伸一氏にとってガラパゴス訪問は長年の夢で、昨年(2020年)3月、コロナ蔓延直前に念願を果たしたそうだ。その訪問は、私のような規定の観光コースではなく、1835年にダーウィンがビーグル号で巡ったコースを小型のチャーター船でたどるという贅沢な旅である。
ガラパゴスとは関東地方くらいの範囲に大小123島が散在する群島で、13年前の私は4泊の4島巡りだった(当初は6島予定だったが諸般の事情で変更)。ビーグル号は1ヵ月あまりかけて主要な島を調査・測量している。福岡氏はそのコースを1週間で巡ったそうだ。
本書はガラパゴス紹介の本だが、半分ばかりは福岡氏の自分語りの書でもある。ガラパゴスに到着するまでのアレコレが脱線気味に長い。朝日出版社のレクチュア・ブックスに関する記述など、私には懐かしくて興味深かったが、うんざりする読者がいるかもしれない。
旅日記はガラパゴスの自然誌紹介であると同時に福岡氏の自然観の開陳である。小型船のメンバー紹介、トイレ紹介、料理紹介などからは福岡氏の高揚感が伝わってきて、自分も同乗している気分にさせられる。私には13年前の追体験のようでもあり、懐かしさに浸った。
私が本書で最も面白いと思ったのは「ダーウィンのふるさととされるガラパゴスは、実は、もっともダーウィン的ではなかったのだ」という指摘である。
それは、ガラパゴスの生物は生存の自由度と余裕を享受しているという見方である。ダーウィンに異議を唱えた今西錦司の「棲み分け」につながるように思える。福岡氏は今西進化論について「夢中になって読んだものの、話法が独特すぎてほとんどきちんと理解できなかった」と述懐している。同感である。上記の「ダーウィン的ではなかった」については「別の機会に考察を進めてみたい」としている。期待したい。
『生命海流:GALAPAGOS』(福岡伸一/朝日出版社)
ガラパゴスは私にとって懐かしい場所だ。ピースボートの世界一周で ガラパゴスを訪れた のは13年前の2008年11月で、私は彼の地で還暦をむかえた。これまで、そこそこの数の世界各地の観光地に行ったが、再訪したいと思った場所の筆頭はガラパゴスだった。
もはや私がガラパゴスを再訪する機会はないだろうと思いつつ本書を手にした。美しいカラー写真がたくさん載っている読みやすい本である。
福岡伸一氏にとってガラパゴス訪問は長年の夢で、昨年(2020年)3月、コロナ蔓延直前に念願を果たしたそうだ。その訪問は、私のような規定の観光コースではなく、1835年にダーウィンがビーグル号で巡ったコースを小型のチャーター船でたどるという贅沢な旅である。
ガラパゴスとは関東地方くらいの範囲に大小123島が散在する群島で、13年前の私は4泊の4島巡りだった(当初は6島予定だったが諸般の事情で変更)。ビーグル号は1ヵ月あまりかけて主要な島を調査・測量している。福岡氏はそのコースを1週間で巡ったそうだ。
本書はガラパゴス紹介の本だが、半分ばかりは福岡氏の自分語りの書でもある。ガラパゴスに到着するまでのアレコレが脱線気味に長い。朝日出版社のレクチュア・ブックスに関する記述など、私には懐かしくて興味深かったが、うんざりする読者がいるかもしれない。
旅日記はガラパゴスの自然誌紹介であると同時に福岡氏の自然観の開陳である。小型船のメンバー紹介、トイレ紹介、料理紹介などからは福岡氏の高揚感が伝わってきて、自分も同乗している気分にさせられる。私には13年前の追体験のようでもあり、懐かしさに浸った。
私が本書で最も面白いと思ったのは「ダーウィンのふるさととされるガラパゴスは、実は、もっともダーウィン的ではなかったのだ」という指摘である。
それは、ガラパゴスの生物は生存の自由度と余裕を享受しているという見方である。ダーウィンに異議を唱えた今西錦司の「棲み分け」につながるように思える。福岡氏は今西進化論について「夢中になって読んだものの、話法が独特すぎてほとんどきちんと理解できなかった」と述懐している。同感である。上記の「ダーウィン的ではなかった」については「別の機会に考察を進めてみたい」としている。期待したい。
『理不尽な進化』を増補新版で再読――やはり後半は難解だが面白い ― 2021年06月21日
2年前に読んで蒙を啓かれた
『理不尽な進化』(朝日出版社)
がちくま文庫の新刊で出た。「増補新版」となっている。面白いが難解な本だったので、いずれ再読せねばと思っていた。これを機に増補新版を購入して読み返すことにした。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満/ちくま文庫)
地球で発生した生物の99.9%は絶滅したという話や適者生存はトートロジーという話は面白かったが、後半は哲学的で難解だった――そんな印象が残っているので、やや身構えて本書再読に取り組んだ。
第1章と第2章は、進化の理不尽性や素人の進化論理解に関する話で、分かりやすくて面白い。第3章は研究者同士の適応主義を巡る論争の紹介と評価である。ドーキンスら主流派に対してグールドが適応主義偏重を批判し(実はもっと複雑な内容だが…)、いまでは主流派の勝ちと見なされている。著者も明快にグールドの負けと判定している。ここまでは理解しやすい。
で、「終章 理不尽にたいする態度」になる。この章が本書のメインで、論争に負けた筈のグールドが不思議な形でよみがえり、議論の時空が拡大し、自然・人間・歴史を巡る哲学的な考察の展開になる。覚悟はしていたが、やはり難解である。理解(この「理解」という用語も要注意…)したとは言い難く、雰囲気を味わっただけだ。だが、十分に刺激的で多少は頭のマッサージになった気がする。
文庫版で増補された「附録 パンとゲシュタポ」で、著者は次のように述べている。
「アートとサイエンス、どちらも込みで私たちの世界であり人生である。だが、その棲み分けはつねに完璧というわけではない。両者の識別不能ゾーンというべきものが存在し、しばしば私たちを混乱させる。/ 本書が照準を合わせたのは、この識別不能ゾーンである。」
そんなゾーンがわかりやすい筈がない。
『理不尽な進化:遺伝子と運のあいだ(増補新版)』(吉川博満/ちくま文庫)
地球で発生した生物の99.9%は絶滅したという話や適者生存はトートロジーという話は面白かったが、後半は哲学的で難解だった――そんな印象が残っているので、やや身構えて本書再読に取り組んだ。
第1章と第2章は、進化の理不尽性や素人の進化論理解に関する話で、分かりやすくて面白い。第3章は研究者同士の適応主義を巡る論争の紹介と評価である。ドーキンスら主流派に対してグールドが適応主義偏重を批判し(実はもっと複雑な内容だが…)、いまでは主流派の勝ちと見なされている。著者も明快にグールドの負けと判定している。ここまでは理解しやすい。
で、「終章 理不尽にたいする態度」になる。この章が本書のメインで、論争に負けた筈のグールドが不思議な形でよみがえり、議論の時空が拡大し、自然・人間・歴史を巡る哲学的な考察の展開になる。覚悟はしていたが、やはり難解である。理解(この「理解」という用語も要注意…)したとは言い難く、雰囲気を味わっただけだ。だが、十分に刺激的で多少は頭のマッサージになった気がする。
文庫版で増補された「附録 パンとゲシュタポ」で、著者は次のように述べている。
「アートとサイエンス、どちらも込みで私たちの世界であり人生である。だが、その棲み分けはつねに完璧というわけではない。両者の識別不能ゾーンというべきものが存在し、しばしば私たちを混乱させる。/ 本書が照準を合わせたのは、この識別不能ゾーンである。」
そんなゾーンがわかりやすい筈がない。
物理学者の頭の中と数学者の頭の中はどう違うのか? ― 2021年06月06日
超ひも理論という難解な素粒子論を研究している物理学者の日常の頭の中を公開したオモシロ・エッセイを読んだ。
『物理学者のすごい思考法』(橋本幸士/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)
『小説すばる』に連載した短いエッセイをまとめたもので、関西人らしいウケねらいもあり、面白く読めた。
本書で面白いと思ったのは、高校の科目と大学の専攻のズレの指摘である。高校時代に数学が得意だった著者は大学理学部に進学し、大学の数学を面白く感じなくなったことからズレに気づいたそうだ。著者によれば「高校の数学→大学の物理」「高校の物理→大学の化学」「高校の化学→大学の生物」と対応するという。なんとなく納得できる。
では、大学の数学に対応する高校の科目はないのだろうか。著者は「ひょっとしたら『小論文』が一番近いかもしれない」と述べている。意外な指摘だが、以前に読んだ 『反オカルト論』 に載っていた数学専攻大学院生の告白的文章を想起した。以下に引用する。
《数学科に進学するということは人生の多くのものをあきらめるということである。(…)人間的な余裕も諦めなけらばならない。数学の抽象度は日ごとに増し、数学科生は日夜数学のことを考えながら生きていくことを強いられる。(…)そのような生活の果てにあるのは疲れ切った頭脳と荒廃した精神のみである。》
この文章が数学へ誘う「進学ガイド」に載っているのが面白い。学問の世界に無縁で凡庸な私には数学者と物理学者の頭の中がどれほど違うのか(あるいは似ているのか)わからないが、それが凡人とかけ離れているのだろうとは想像できる。
『物理学者のすごい思考法』(橋本幸士/インターナショナル新書/集英社インターナショナル)
『小説すばる』に連載した短いエッセイをまとめたもので、関西人らしいウケねらいもあり、面白く読めた。
本書で面白いと思ったのは、高校の科目と大学の専攻のズレの指摘である。高校時代に数学が得意だった著者は大学理学部に進学し、大学の数学を面白く感じなくなったことからズレに気づいたそうだ。著者によれば「高校の数学→大学の物理」「高校の物理→大学の化学」「高校の化学→大学の生物」と対応するという。なんとなく納得できる。
では、大学の数学に対応する高校の科目はないのだろうか。著者は「ひょっとしたら『小論文』が一番近いかもしれない」と述べている。意外な指摘だが、以前に読んだ 『反オカルト論』 に載っていた数学専攻大学院生の告白的文章を想起した。以下に引用する。
《数学科に進学するということは人生の多くのものをあきらめるということである。(…)人間的な余裕も諦めなけらばならない。数学の抽象度は日ごとに増し、数学科生は日夜数学のことを考えながら生きていくことを強いられる。(…)そのような生活の果てにあるのは疲れ切った頭脳と荒廃した精神のみである。》
この文章が数学へ誘う「進学ガイド」に載っているのが面白い。学問の世界に無縁で凡庸な私には数学者と物理学者の頭の中がどれほど違うのか(あるいは似ているのか)わからないが、それが凡人とかけ離れているのだろうとは想像できる。
『20世紀論争史』は論点のサワリを俯瞰する書 ― 2021年05月25日
先日読んだ
『反オカルト論』や
『フォン・ノイマンの哲学』の著者の新刊新書が本屋の店頭に積んであった。
『20世紀論争史:現代思想の源泉』(高橋昌一郎/光文社新書)
教授と助手の対話という手軽に読めそうな体裁に惹かれて購入した。『小説宝石』の連載をまとめた新書で、雑誌のコラムを読む気分で読了した。
全30章、つまり30の論争を紹介している。「カミュ vs サルトル論争」のようにメディア上で実際に展開された論争もあるが、見解の異なる論者たちの論点整理・紹介が多い。その論点は数学・哲学・物理学・生物学・科学論・技術論と多岐にわたる。私の知らない学者も多く登場し、勉強になった。と言っても論点のサワリをサラリと紹介する本なので、きちんと理解できたわけでない。
著者紹介によれば高橋昌一郎氏の専門は論理学・科学哲学だそうだ。『反オカルト論』は理系の教授と女性助手の対話という形だったが、本書は文系の教授と女性助手の対話である。各章の冒頭1~2頁はコーヒー談義で、全編で30種のコーヒー蘊蓄を聞かされる。
理解できないながらもゲーデルの「不完全性定理」はやはり衝撃である。また、民主主義を完全に満足させる社会的決定は不可能と証明したアローの「不可能性定理」も興味深い。論理の限界、社会集団の難しさを感じる。
物理学者ホイルの話も面白い。定常宇宙論を唱えビッグバンを否定したホイルはSF作家としても有名で、私も『暗黒星雲』『10月1日では遅すぎる』などを大昔に読んだ。学者としては異端の人だと思っていたが、ノーベル物理学賞の可能性がある業績がありながらも主流理論を批判し続けたので受賞を逸したと言われているそうだ。
本書で20世紀を俯瞰すると、この世には識者たちが侃々諤々を続ける「わからないこと」があふれているとわかる。
『20世紀論争史:現代思想の源泉』(高橋昌一郎/光文社新書)
教授と助手の対話という手軽に読めそうな体裁に惹かれて購入した。『小説宝石』の連載をまとめた新書で、雑誌のコラムを読む気分で読了した。
全30章、つまり30の論争を紹介している。「カミュ vs サルトル論争」のようにメディア上で実際に展開された論争もあるが、見解の異なる論者たちの論点整理・紹介が多い。その論点は数学・哲学・物理学・生物学・科学論・技術論と多岐にわたる。私の知らない学者も多く登場し、勉強になった。と言っても論点のサワリをサラリと紹介する本なので、きちんと理解できたわけでない。
著者紹介によれば高橋昌一郎氏の専門は論理学・科学哲学だそうだ。『反オカルト論』は理系の教授と女性助手の対話という形だったが、本書は文系の教授と女性助手の対話である。各章の冒頭1~2頁はコーヒー談義で、全編で30種のコーヒー蘊蓄を聞かされる。
理解できないながらもゲーデルの「不完全性定理」はやはり衝撃である。また、民主主義を完全に満足させる社会的決定は不可能と証明したアローの「不可能性定理」も興味深い。論理の限界、社会集団の難しさを感じる。
物理学者ホイルの話も面白い。定常宇宙論を唱えビッグバンを否定したホイルはSF作家としても有名で、私も『暗黒星雲』『10月1日では遅すぎる』などを大昔に読んだ。学者としては異端の人だと思っていたが、ノーベル物理学賞の可能性がある業績がありながらも主流理論を批判し続けたので受賞を逸したと言われているそうだ。
本書で20世紀を俯瞰すると、この世には識者たちが侃々諤々を続ける「わからないこと」があふれているとわかる。
STAP事件批判の告発本『反オカルト論』は説得力がある ― 2021年05月09日
私はオカルトに懐疑的で、超能力や超常現象はトリックか脳内現象だと思っている。先日読んだ
『フォン・ノイマンの哲学』
の著者・高橋昌一郎氏にオカルト批判の新書があると知り、入手して読んだ。
『反オカルト論』(高橋昌一郎/光文社新書)
週刊新潮に連載したコラムをベースにした2016年刊行の新書で、教授と助手(理系女性研究者)の会話という読みやすい形式だ。気軽な雑談風とは言え、全8章それぞれの末尾に「解説」に加えて読者に問う「課題」があり、教科書のようである。この問いに真面目に対応して答案を作るのは大変だと思った。それはオカルトに騙されない判断力を涵養するための課題になっている。
オビに「STAP事件は現代のオカルト!」とあり、あれが何故オカルトなのかピンとこなかったが、本書を読み終えて納得した。STAP事件をめぐる学界やメディアの対応への告発こそが本書のメインテーマのようにも思える。
第1章はスピリチュアリズムの起源から始まる。それは、19世紀のフォスター姉妹(14歳と11歳)のイタズラによる「怪奇現象」であり、イタズラが大人たちの思惑によって社会現象にエスカレートしていくさまを紹介している。また、妖艶なミナ夫人の「霊能力」に優秀な科学者たちが容易に騙されていく話も描いている。
続いてSTAP事件に話題が移っていく。著者は小保方晴子氏をミナ夫人らのような欺瞞の人と見なしている。欺瞞には自己欺瞞もあり、著者は彼女をコミュニケーション能力にに長けた「抜群に世渡りの上手な人物」とし、彼女を中心に関係者の思惑が現代科学の最先端の場でオカルトを発生させたという見解である。
本書全体のおよそ三分の二が、スピリチュアリズムの解明とSTAP事件の分析に当てられている。「なぜ騙されるのか」「なぜ妄信するのか」「なぜ不正を行うのか」「なぜ自己欺瞞に陥るのか」「なぜ嘘をつくのか」という視点から、STAP事件がスピリチュアリズムと同様のオカルトだと追究していく展開に迫力がある。辛辣な小保方晴子氏批判、学界批判であり、私は納得・賛同できた。
『反オカルト論』(高橋昌一郎/光文社新書)
週刊新潮に連載したコラムをベースにした2016年刊行の新書で、教授と助手(理系女性研究者)の会話という読みやすい形式だ。気軽な雑談風とは言え、全8章それぞれの末尾に「解説」に加えて読者に問う「課題」があり、教科書のようである。この問いに真面目に対応して答案を作るのは大変だと思った。それはオカルトに騙されない判断力を涵養するための課題になっている。
オビに「STAP事件は現代のオカルト!」とあり、あれが何故オカルトなのかピンとこなかったが、本書を読み終えて納得した。STAP事件をめぐる学界やメディアの対応への告発こそが本書のメインテーマのようにも思える。
第1章はスピリチュアリズムの起源から始まる。それは、19世紀のフォスター姉妹(14歳と11歳)のイタズラによる「怪奇現象」であり、イタズラが大人たちの思惑によって社会現象にエスカレートしていくさまを紹介している。また、妖艶なミナ夫人の「霊能力」に優秀な科学者たちが容易に騙されていく話も描いている。
続いてSTAP事件に話題が移っていく。著者は小保方晴子氏をミナ夫人らのような欺瞞の人と見なしている。欺瞞には自己欺瞞もあり、著者は彼女をコミュニケーション能力にに長けた「抜群に世渡りの上手な人物」とし、彼女を中心に関係者の思惑が現代科学の最先端の場でオカルトを発生させたという見解である。
本書全体のおよそ三分の二が、スピリチュアリズムの解明とSTAP事件の分析に当てられている。「なぜ騙されるのか」「なぜ妄信するのか」「なぜ不正を行うのか」「なぜ自己欺瞞に陥るのか」「なぜ嘘をつくのか」という視点から、STAP事件がスピリチュアリズムと同様のオカルトだと追究していく展開に迫力がある。辛辣な小保方晴子氏批判、学界批判であり、私は納得・賛同できた。
『環境問題の嘘 令和版』(池田清彦)はCO2温暖化説を否定しているが… ― 2021年05月01日
生物学者の池田清彦氏の次の新書本を読んだ。
『環境問題の嘘 令和版』(池田清彦/Mdn新書/エムディーエヌコーポレーション)
この新書は、ご隠居さんの奔放なおしゃべりを文字にした座談の趣があり、読みやすくて面白い。緻密な議論の書とは言い難いところもあり、著者の主張を検討するには関連資料を精査するべきだろう感じた。
話題は多岐にわたり、メインはCO2温暖化説の否定である。CO2温暖化否定の本を読むのは久しぶりだ。5年前の 『地球はもう温暖化していない』(深井有) 以来だと思う。最近の新聞は「脱炭素」関連の記事であふれ、CO2温暖化はすでの世界の常識になったように見える。科学の問題ではなく政治・経済・社会の問題として走り出しているので、止めようがないのだ。著者は次のように述べている。
《人為的地球温暖化論を推進しているのは、エコという正義の御旗を梃子にCO2削減のためのさまざまなシステムを構築して金もうけを企んでいる巨大企業と、それを後押しする政治権力で、反対しているのは何の利権もなく、データに立脚して物事を考える科学者なんだよね。》
本書全般における著者の批判対象はグローバル資本主義である。それに対抗する道として、物々交換のローカリズムを提唱し、次の見解を提示している。
《中産階級以下の人が優雅に生きようとするならば、短期的に利潤だけを追求するラットレースから降りて、貨幣に全面依存しないで生きられるような定常システムを構築して、ダンバー数(互いに密接な関係を築ける集団構成員数の上限)以下の信頼できるコミュニティの中で生活するのが一番いいと思う。》
やや現実離れした夢物語に思えるのが、隠居の放談らしさかもしれない。最近、これと似た印象のビジョンに接した。『人新世の「資本論」』(斎藤幸平)である。斎藤幸平氏はCO2温暖化を全面的に肯定し、それを論拠としていた。地球温暖化に関しては真逆の立場の池田清彦氏と斎藤幸平氏のビジョンが似ているのが面白い。
『環境問題の嘘 令和版』(池田清彦/Mdn新書/エムディーエヌコーポレーション)
この新書は、ご隠居さんの奔放なおしゃべりを文字にした座談の趣があり、読みやすくて面白い。緻密な議論の書とは言い難いところもあり、著者の主張を検討するには関連資料を精査するべきだろう感じた。
話題は多岐にわたり、メインはCO2温暖化説の否定である。CO2温暖化否定の本を読むのは久しぶりだ。5年前の 『地球はもう温暖化していない』(深井有) 以来だと思う。最近の新聞は「脱炭素」関連の記事であふれ、CO2温暖化はすでの世界の常識になったように見える。科学の問題ではなく政治・経済・社会の問題として走り出しているので、止めようがないのだ。著者は次のように述べている。
《人為的地球温暖化論を推進しているのは、エコという正義の御旗を梃子にCO2削減のためのさまざまなシステムを構築して金もうけを企んでいる巨大企業と、それを後押しする政治権力で、反対しているのは何の利権もなく、データに立脚して物事を考える科学者なんだよね。》
本書全般における著者の批判対象はグローバル資本主義である。それに対抗する道として、物々交換のローカリズムを提唱し、次の見解を提示している。
《中産階級以下の人が優雅に生きようとするならば、短期的に利潤だけを追求するラットレースから降りて、貨幣に全面依存しないで生きられるような定常システムを構築して、ダンバー数(互いに密接な関係を築ける集団構成員数の上限)以下の信頼できるコミュニティの中で生活するのが一番いいと思う。》
やや現実離れした夢物語に思えるのが、隠居の放談らしさかもしれない。最近、これと似た印象のビジョンに接した。『人新世の「資本論」』(斎藤幸平)である。斎藤幸平氏はCO2温暖化を全面的に肯定し、それを論拠としていた。地球温暖化に関しては真逆の立場の池田清彦氏と斎藤幸平氏のビジョンが似ているのが面白い。




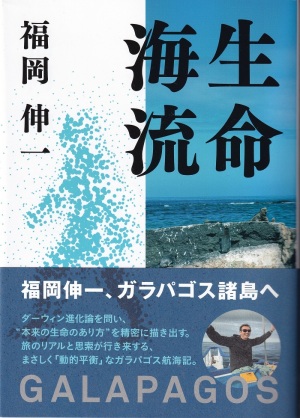
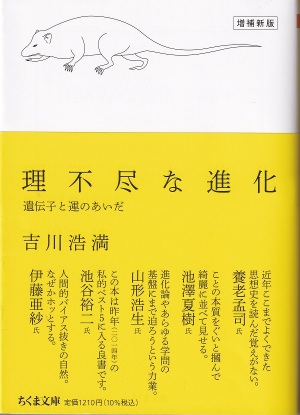



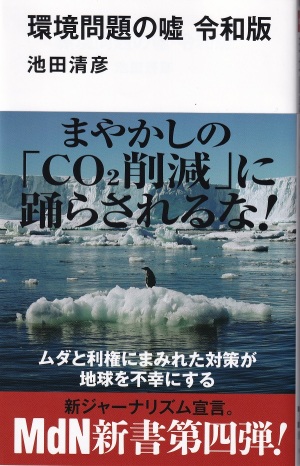
最近のコメント