科学で解明できない「神」を科学者はなぜ信じるのか ― 2018年08月02日
三田一郎氏は素粒子物理学者であると同時にカトリックの聖職者である。2008年にノーベル物理学賞を受賞した「小林・益川理論」の実証に貢献した世界的な物理学者だ。私は9年前に三田氏の講演会で少しお話をさせていただいたことがあり、そのときの感想は以前のブログに書いた。
その三田氏の次の新著を新聞広告で知り、さっさく購入して読んだ。
『科学者はなぜ神を信じるのか:コペルニクスからホーキングまで』(三田一郎/ブルーバックス/講談社)
私は無宗教で神を信じていない。私よりはるかに頭脳明晰な物理学者がなぜ神を信じているのか、その不思議が解明できるかと思って本書を読んだ。読み終えて、科学者が神をどのようにとらえているかの理解は少し深まった。
本書は基本的には地動説から現代宇宙論に至るまでの科学史概説であり、それは「神業」の領域がどんどん狭められてきた歴史である。マクロな宇宙の構造や起源からミクロな素粒子までが徐々に解明されていく物語にはワクワクさせられる。
著者によれば、神の領域を狭めてきた偉大な科学者の多くは神の存在を感じていたそうだ。無神論とみなされている学者(アインシュタイン、ディラック、ホーキングなど)も神を意識していたはずだというのが著者の見解だ。
カトリック教会はガリレオを断罪したが、1992年になって教皇ヨハネ・パウロ2世はガリレオに謝罪する。ほんの26年前だ。三田氏は、この謝罪がなければ自分も教会から離れただろうと述べている。部外者には推し量りがたい心境だ。倫理ではなく自然科学的「真理探究」に宗教が関わることへの違和感はある。
最終章の「最後に言っておきたいこと --- 私にとっての神」では、素粒子研究者である自分が神を信じるに至った経緯を述べている。「積極的無宗教」を標榜する益川敏英氏への反論が面白い。神を信じることは思考停止ではなく、「もう神は必要ない」と探求の「無限のいたちごっこ」をやめてしまうことこそが思考停止だとの見解だ。説得されたわけではないが何となく納得させられてしまう。だが、モヤモヤしたものは残る。
その三田氏の次の新著を新聞広告で知り、さっさく購入して読んだ。
『科学者はなぜ神を信じるのか:コペルニクスからホーキングまで』(三田一郎/ブルーバックス/講談社)
私は無宗教で神を信じていない。私よりはるかに頭脳明晰な物理学者がなぜ神を信じているのか、その不思議が解明できるかと思って本書を読んだ。読み終えて、科学者が神をどのようにとらえているかの理解は少し深まった。
本書は基本的には地動説から現代宇宙論に至るまでの科学史概説であり、それは「神業」の領域がどんどん狭められてきた歴史である。マクロな宇宙の構造や起源からミクロな素粒子までが徐々に解明されていく物語にはワクワクさせられる。
著者によれば、神の領域を狭めてきた偉大な科学者の多くは神の存在を感じていたそうだ。無神論とみなされている学者(アインシュタイン、ディラック、ホーキングなど)も神を意識していたはずだというのが著者の見解だ。
カトリック教会はガリレオを断罪したが、1992年になって教皇ヨハネ・パウロ2世はガリレオに謝罪する。ほんの26年前だ。三田氏は、この謝罪がなければ自分も教会から離れただろうと述べている。部外者には推し量りがたい心境だ。倫理ではなく自然科学的「真理探究」に宗教が関わることへの違和感はある。
最終章の「最後に言っておきたいこと --- 私にとっての神」では、素粒子研究者である自分が神を信じるに至った経緯を述べている。「積極的無宗教」を標榜する益川敏英氏への反論が面白い。神を信じることは思考停止ではなく、「もう神は必要ない」と探求の「無限のいたちごっこ」をやめてしまうことこそが思考停止だとの見解だ。説得されたわけではないが何となく納得させられてしまう。だが、モヤモヤしたものは残る。
「知らない」ということを知ったつもりになるという錯覚 ― 2018年08月04日
タイトルに惹かれて次の本を読んだ。
『知ってるつもり:無知の科学』(スティーブン・スローマン、フィリップ・ファーンバック/土方奈美訳/早川書房)
著者の二人は米国の認知科学者だ。本書に接するまで「認知科学」という言葉に馴染みがなかった。人間の知性の働きを研究する学問だそうだ。本書を読んだ印象では、心理学や脳科学などをベースに自然科学と社会科学のまじわる領域を研究する学問のようだ。
人間はおのれが自覚している以上に無知であり、物事を知っていると思っているのは錯覚である、というのが本書の指摘である。人間が存外無知であるにもかかわらず人類は複雑な装置や仕組みを作り出してきた。人間は認知的分業する動物で、人類が数々の偉業を達成できたのは「コミュニティの知」の力によるそうだ。言われてみれば、そんな気がする。
人間の知性の働きにコミュニティが大きくかかわっているという指摘は興味深い。人間の考えは所属するコミュニティの影響を大きく受けているので、個人の考えを変えるのは容易ではない。考えを変えるということはコミュニティからの離脱につながる重大事になりかねない。これはかなり大きな課題だ。
コミュニティの知にはプラスもマイナスもあり、「グループシンク(集団浅慮)」という現象も紹介されている。ネットの共鳴箱効果もその一例で、これも現代的な課題だ。
本書は自分が無知であることを認識せよと主張しているようだが、無知である人間が「知ってるつもり」の錯覚におちいるのは、そもそも人間がそのようにできているからであり、それが進化の結果だとも述べている。無知であることを自覚しつつ錯覚に自身をゆだねる---結構ややこしい生き方になりそうである。
『知ってるつもり:無知の科学』(スティーブン・スローマン、フィリップ・ファーンバック/土方奈美訳/早川書房)
著者の二人は米国の認知科学者だ。本書に接するまで「認知科学」という言葉に馴染みがなかった。人間の知性の働きを研究する学問だそうだ。本書を読んだ印象では、心理学や脳科学などをベースに自然科学と社会科学のまじわる領域を研究する学問のようだ。
人間はおのれが自覚している以上に無知であり、物事を知っていると思っているのは錯覚である、というのが本書の指摘である。人間が存外無知であるにもかかわらず人類は複雑な装置や仕組みを作り出してきた。人間は認知的分業する動物で、人類が数々の偉業を達成できたのは「コミュニティの知」の力によるそうだ。言われてみれば、そんな気がする。
人間の知性の働きにコミュニティが大きくかかわっているという指摘は興味深い。人間の考えは所属するコミュニティの影響を大きく受けているので、個人の考えを変えるのは容易ではない。考えを変えるということはコミュニティからの離脱につながる重大事になりかねない。これはかなり大きな課題だ。
コミュニティの知にはプラスもマイナスもあり、「グループシンク(集団浅慮)」という現象も紹介されている。ネットの共鳴箱効果もその一例で、これも現代的な課題だ。
本書は自分が無知であることを認識せよと主張しているようだが、無知である人間が「知ってるつもり」の錯覚におちいるのは、そもそも人間がそのようにできているからであり、それが進化の結果だとも述べている。無知であることを自覚しつつ錯覚に自身をゆだねる---結構ややこしい生き方になりそうである。
「ウナギ博士」塚本勝巳氏の会見に参加 ― 2018年08月12日
「ウナギ博士」塚本勝巳氏の「ウナギの未来と日本」という会見が日本記者クラブであった。塚本氏は日本ウナギの産卵場所が西マリアナ海嶺であることをつきとめ、世界で初めて天然ウナギ卵を採取した世界的な海洋生物学者である。
冒頭、塚本氏は「ウナギ博士」と呼ばれることに抵抗があったとユーモラスに語った。ウナギだけを研究してきたわけでなく、他の魚も含めて主に魚の回遊を研究してきたからである。だが、今ではあきらめて「ウナギ博士」を受け容れているそうだ。
何年か前に読んだ塚本氏の『ウナギ大回遊の謎』(PHPワールドサイエンス新書)でもアユの回遊に関する興味深い話が紹介されていた。とは言え、生物学的にはともかく食文化におけるウナギの存在感は圧倒的に大きく、「ウナギ博士」という語感には広がりがある。塚本氏の会見も多岐にわたる面白い内容だった。
ウナギ研究には「生態」「養殖」「資源」「保全」などの分野があり、「生態」「養殖」では日本は世界のトップ、それも30年ぐらい水をあけたダントツだそうだ。頼もしい限りである。とは言え「資源」「保全」の研究はまだまだらしい。将来にわたってウナギを食べ続けられるよう、この分野にも若い頭脳が挑戦してほしい…と手前勝手に願望した。
冒頭、塚本氏は「ウナギ博士」と呼ばれることに抵抗があったとユーモラスに語った。ウナギだけを研究してきたわけでなく、他の魚も含めて主に魚の回遊を研究してきたからである。だが、今ではあきらめて「ウナギ博士」を受け容れているそうだ。
何年か前に読んだ塚本氏の『ウナギ大回遊の謎』(PHPワールドサイエンス新書)でもアユの回遊に関する興味深い話が紹介されていた。とは言え、生物学的にはともかく食文化におけるウナギの存在感は圧倒的に大きく、「ウナギ博士」という語感には広がりがある。塚本氏の会見も多岐にわたる面白い内容だった。
ウナギ研究には「生態」「養殖」「資源」「保全」などの分野があり、「生態」「養殖」では日本は世界のトップ、それも30年ぐらい水をあけたダントツだそうだ。頼もしい限りである。とは言え「資源」「保全」の研究はまだまだらしい。将来にわたってウナギを食べ続けられるよう、この分野にも若い頭脳が挑戦してほしい…と手前勝手に願望した。
大著『ヒトラー』の上巻を読了、脳科学を連想 ― 2018年08月14日
書店の棚で『ヒトラー』(上)(下)を見たとき、その分厚さにたじろいだ。上下2冊重ねると『広辞苑』よりかなり厚い。著者は1943年生まれの英国の歴史家で、原書の上巻は1998年、下巻は2000年に刊行されている。翻訳版の刊行は2016年、オビには「白水社創立百周年記念出版」という気合の入った惹句がある。長い逡巡を経て本書を購入し、その上巻を読了した。
『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』(イアン・カーショー/川喜多敦子訳/石田勇治監修/白水社)
上巻読了時点で読後メモを書くのは、上巻より厚い下巻を読み終える頃には上巻の内容が蒸発しているおそれがあるからだ。上下それぞれに独自のタイトルが付され、序文も両方にあり、上下を独立した書とみなしていいかとも思った。
上巻の『傲慢(HUBRIS)』、下巻の『天罰(NEMESIS)』という大仰なギリシア語源のサブタイトルは因果応報物語の雰囲気を感じさせるが、本書はまっとうな歴史書である。著者のイアン・カーショーは社会史を重視する研究者で一人の人物に焦点をあてる伝記的記述には興味がなかったそうだ。そんな研究者が大著『ヒトラー』を書いたのは、ヒトラー出現をもたらした時代情況の分析が重要と考えたからである。
『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』はヒトラーの生誕からドイツのラインラント進駐までの47年を描いている。学も教養もない怠惰な落伍者だった男が、弁舌の才と過剰な自意識だけで20世紀西欧の文明国の独裁者に登りつめていく物語である。太閤記的な面白さもあるが、人間の集団の判断と行動の頼りなさがあばかれる苦い物語でもある。「傲慢(HUBRIS)」という言葉は、ラインラント進駐によってヒトラーが己の無謬性を確信した状態を表している。
著者は、大げさな感情表出で自己中心的に振る舞うヒトラーをプリマドンナに例えている。ヒトラーは「意思の力」で成り上がったのではなく、空気を読まない過剰な自意識と感情で行動しただけである。ヒトラーを忌避する要人が多かったにもかかわらず、彼を取り巻く情況と思惑の絡み合いが彼を押し上げて独裁者を作り上げた。著者はそんな分析を展開している。歴史の力学の不思議を感じる。
本書を読んでいて、「すぐに錯覚する脳」の頼りなさを指摘した脳科学の本を連想した。また、トランプ現象、ポピュリズム、反知性主義などに象徴される現代においてヒトラーとナチズムの再検証は意義深いと思った。陳腐な感想だが仕方ない。
『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』(イアン・カーショー/川喜多敦子訳/石田勇治監修/白水社)
上巻読了時点で読後メモを書くのは、上巻より厚い下巻を読み終える頃には上巻の内容が蒸発しているおそれがあるからだ。上下それぞれに独自のタイトルが付され、序文も両方にあり、上下を独立した書とみなしていいかとも思った。
上巻の『傲慢(HUBRIS)』、下巻の『天罰(NEMESIS)』という大仰なギリシア語源のサブタイトルは因果応報物語の雰囲気を感じさせるが、本書はまっとうな歴史書である。著者のイアン・カーショーは社会史を重視する研究者で一人の人物に焦点をあてる伝記的記述には興味がなかったそうだ。そんな研究者が大著『ヒトラー』を書いたのは、ヒトラー出現をもたらした時代情況の分析が重要と考えたからである。
『ヒトラー(上)1889-1936 傲慢』はヒトラーの生誕からドイツのラインラント進駐までの47年を描いている。学も教養もない怠惰な落伍者だった男が、弁舌の才と過剰な自意識だけで20世紀西欧の文明国の独裁者に登りつめていく物語である。太閤記的な面白さもあるが、人間の集団の判断と行動の頼りなさがあばかれる苦い物語でもある。「傲慢(HUBRIS)」という言葉は、ラインラント進駐によってヒトラーが己の無謬性を確信した状態を表している。
著者は、大げさな感情表出で自己中心的に振る舞うヒトラーをプリマドンナに例えている。ヒトラーは「意思の力」で成り上がったのではなく、空気を読まない過剰な自意識と感情で行動しただけである。ヒトラーを忌避する要人が多かったにもかかわらず、彼を取り巻く情況と思惑の絡み合いが彼を押し上げて独裁者を作り上げた。著者はそんな分析を展開している。歴史の力学の不思議を感じる。
本書を読んでいて、「すぐに錯覚する脳」の頼りなさを指摘した脳科学の本を連想した。また、トランプ現象、ポピュリズム、反知性主義などに象徴される現代においてヒトラーとナチズムの再検証は意義深いと思った。陳腐な感想だが仕方ない。
『天声人語』書き写しという夏休みの宿題 ― 2018年08月20日
中学3年の孫娘が塾の先生から夏休みに『天声人語』の書き写しをするように言われたと聞き、次の2冊を読んだ。
『深代惇郎の天声人語』(深代惇郎/朝日文庫)
『竹内政明の「編集手帳」傑作選』(竹内政明/中公新書ラクレ)
書き写すのは日々の新聞のコラムなので、過去のコラムを集めたこの2冊と宿題に直接の関係はない。これらのコラム集に、中学生の文章教材にしたいコラムが何編ぐらいあるか、確めたくなったのである。
『深代惇郎の天声人語』は早世した朝日新聞の名文記者深代惇郎氏の1973年から1975年のコラムの選集である。近年は読売新聞の竹内政明氏のコラムの評判が高い。『竹内政明の「編集手帳」傑作選』は2004年から2014年のコラムの傑作選である。
過去の新聞1面コラムをまとめて読んで、まず感じたのは1面コラムはナマモノであり、時日が経過すると率直には味わえないということだ。歴史文書としての面白さはあっても、文章のお手本になり得る普遍的面白さがあるのは1割以下だと思えた。
とは言っても、やはり1面コラムは読みやすくて、つい引き込まれてしまう。中学生の国語教材に適切か否かなどを念頭におかなければ、興味深く楽しめるものが多い。笑ったりうなったりもする。
かなり以前に読んだ『大人のための文章教室』(講談社現代新書)で、著者の清水義範氏が素人は新聞1面コラムの真似をするなと指摘していたのを思い出した。読み返してみると次のように書いてある。
「あれは実はアクロバット的な文章で、へたすると爺さんの世迷言のようになる。歳時記と、偉人のエピソードと、枯淡の心境とをシャッフルして、十行ごとに話が変わっていき、仙人の独白にたどりつくという文章なのだ。(…)あんな大技に、一般人は挑戦しないほうがいいと思う。」
至言であり、同感である。新聞1面コラムは興味深く読めて楽しめばそれで十分である。『天声人語』書き写しが新聞を楽しく読む習慣につながればいいと思う。
『深代惇郎の天声人語』(深代惇郎/朝日文庫)
『竹内政明の「編集手帳」傑作選』(竹内政明/中公新書ラクレ)
書き写すのは日々の新聞のコラムなので、過去のコラムを集めたこの2冊と宿題に直接の関係はない。これらのコラム集に、中学生の文章教材にしたいコラムが何編ぐらいあるか、確めたくなったのである。
『深代惇郎の天声人語』は早世した朝日新聞の名文記者深代惇郎氏の1973年から1975年のコラムの選集である。近年は読売新聞の竹内政明氏のコラムの評判が高い。『竹内政明の「編集手帳」傑作選』は2004年から2014年のコラムの傑作選である。
過去の新聞1面コラムをまとめて読んで、まず感じたのは1面コラムはナマモノであり、時日が経過すると率直には味わえないということだ。歴史文書としての面白さはあっても、文章のお手本になり得る普遍的面白さがあるのは1割以下だと思えた。
とは言っても、やはり1面コラムは読みやすくて、つい引き込まれてしまう。中学生の国語教材に適切か否かなどを念頭におかなければ、興味深く楽しめるものが多い。笑ったりうなったりもする。
かなり以前に読んだ『大人のための文章教室』(講談社現代新書)で、著者の清水義範氏が素人は新聞1面コラムの真似をするなと指摘していたのを思い出した。読み返してみると次のように書いてある。
「あれは実はアクロバット的な文章で、へたすると爺さんの世迷言のようになる。歳時記と、偉人のエピソードと、枯淡の心境とをシャッフルして、十行ごとに話が変わっていき、仙人の独白にたどりつくという文章なのだ。(…)あんな大技に、一般人は挑戦しないほうがいいと思う。」
至言であり、同感である。新聞1面コラムは興味深く読めて楽しめばそれで十分である。『天声人語』書き写しが新聞を楽しく読む習慣につながればいいと思う。
『ヒトラー(下)1936-1945 天罰』で第2次大戦の世界に没入 ― 2018年08月25日
『ヒトラー(下)1936-1945 天罰』(イアン・カーショー/福永美和子訳/石田勇治監修/白水社)
上巻『傲慢(HUBRIS)』に続く下巻『天罰(NEMESIS)』を読了した。ラインラント進駐によって己の無謬性を確信する「傲慢(HUBRIS)」状態になったヒトラーが、オーストリア、チェコ、ポーランドへの侵攻、パリ占拠、独ソ戦を経て最終的には「天罰(NEMESIS)」と言うべき戦火のベルリン首相官邸地下壕で自決するまでの9年間の歴史である。2段組870ページの本文(別に注釈など270ページ)によって波乱万丈の第2次大戦の世界に没入していると頭がボーッとしてくる。
下巻はヒトラーの伝記というよりは、ナチス体制における意思決定の分析をまじえた戦史である。ソ連崩壊の頃から全貌が明らかになったゲッベルス日記による記述が多く、ゲッベルスの視点でヒトラーや党組織を眺めている気分にもなる。各部署がヒトラーの決定権だけに依存した「カリスマ支配」の非効率に分断された組織は、規模の違いはあっても現代の経営組織にも当てはまりそうに思える。ナチス幹部の人間関係の軋轢も興味深い。
本書は、国防軍内にかなり以前からあった反ヒトラーの動きを詳しく記述している。第2次大戦勃発以前の1938年のミュンヘン会談の頃のクーデター計画、1939年の建具屋エルザーによる時限爆弾、大戦末期の1944年7月20日のシュタウフェンベルク大佐による爆殺未遂などいろいろあるが、いずれも失敗に帰する。歴史のタラレバは無意味ではあるが、第2次大戦勃発以前にヒトラーが暗殺されていれば、歴史教科書に偉人の一人として載ったかもしれない。1944年の暗殺が成功していても歴史の大勢は変わらなかったように思える。
それにしても、自身が示したヴィジョンが達成できないなら国や国民は滅びてしまう方がいいと考えていたヒトラーは常軌を逸した人物である。そんなヘンな人は世の中には何割かいて、中には芸術家として大成する人もいるかもしれない。だが、そんな人が政治権力を掌握したら大きな悲劇になる。
上巻『傲慢(HUBRIS)』に続く下巻『天罰(NEMESIS)』を読了した。ラインラント進駐によって己の無謬性を確信する「傲慢(HUBRIS)」状態になったヒトラーが、オーストリア、チェコ、ポーランドへの侵攻、パリ占拠、独ソ戦を経て最終的には「天罰(NEMESIS)」と言うべき戦火のベルリン首相官邸地下壕で自決するまでの9年間の歴史である。2段組870ページの本文(別に注釈など270ページ)によって波乱万丈の第2次大戦の世界に没入していると頭がボーッとしてくる。
下巻はヒトラーの伝記というよりは、ナチス体制における意思決定の分析をまじえた戦史である。ソ連崩壊の頃から全貌が明らかになったゲッベルス日記による記述が多く、ゲッベルスの視点でヒトラーや党組織を眺めている気分にもなる。各部署がヒトラーの決定権だけに依存した「カリスマ支配」の非効率に分断された組織は、規模の違いはあっても現代の経営組織にも当てはまりそうに思える。ナチス幹部の人間関係の軋轢も興味深い。
本書は、国防軍内にかなり以前からあった反ヒトラーの動きを詳しく記述している。第2次大戦勃発以前の1938年のミュンヘン会談の頃のクーデター計画、1939年の建具屋エルザーによる時限爆弾、大戦末期の1944年7月20日のシュタウフェンベルク大佐による爆殺未遂などいろいろあるが、いずれも失敗に帰する。歴史のタラレバは無意味ではあるが、第2次大戦勃発以前にヒトラーが暗殺されていれば、歴史教科書に偉人の一人として載ったかもしれない。1944年の暗殺が成功していても歴史の大勢は変わらなかったように思える。
それにしても、自身が示したヴィジョンが達成できないなら国や国民は滅びてしまう方がいいと考えていたヒトラーは常軌を逸した人物である。そんなヘンな人は世の中には何割かいて、中には芸術家として大成する人もいるかもしれない。だが、そんな人が政治権力を掌握したら大きな悲劇になる。
大著『ヒトラー(上)(下)』の後に新書の『ヒトラーとナチ・ドイツ』 ― 2018年08月27日
大著『ヒトラー(上)(下)』(イアン・カーショー/石田勇治監修)読了の余韻があるうちに、おさらい気分で次の新書を一気読みした。
『ヒトラーとナチ・ドイツ』(石田勇治/講談社現代新書)
著者の石田勇治氏は1957年生まれのドイツ近現代史の研究者で、上記カーショーの翻訳版の監修者である。この新書は大著読了で疲れた頭のクールダウンになった。
本書はヒトラーの生涯とナチ・ドイツの歴史をコンパクトのまとめている。と言っても、早わかり解説本ではなく、史実の背景分析にウエイトが置かれている。
ヒトラー政権成立時に副首相に就任した元首相パーペンは「ヒトラーを雇い入れる」「用が済めば放り出せばよい」と考えていたが、その思惑は外れる。著者の石田氏は次のように記述している。
「この日(ヒトラー政権成立の1933年1月30日)から、ヒトラーが首相と大統領の地位と権限をあわせもつ絶対の「指導者」(総統)に就任する三四年八月二日までは、振り返ると実に恐ろしい一年半だ。あれよあれよというまに、さまざまなことが決まり、もはや民主主義国家に戻ることのできない不可逆地点を越えた。結果的にホロコーストへとつながる最初の一歩も、すでにこの時期に踏み出していた。」
時代が動くときには時間が極端に速く流れる。歴史にはそんな局面がしばしば現われる。よく知っておくべきことだと思う。
本書はユダヤ人迫害とホロコーストの背景と過程を丁寧に分析している。遺伝病患者や心身障害者への「安楽死殺害政策」とホロコーストの関連、ユダヤ人国外退去政策が絶滅政策に転換していった経緯が明解に分析されている。
最新の研究成果が反映されいるのも本書の特色だ。『わが闘争』はヒトラーの口述をヘスが筆記したとされていたが、ヒトラー本人がタイプライターで書いたらしい。また、ヒトラーが反ユダヤ思想を抱いたのはウィーンでの浮草暮らし時代ではなく第一次大戦後らしい。歴史の見方は更新されていくから面白い。
『ヒトラーとナチ・ドイツ』(石田勇治/講談社現代新書)
著者の石田勇治氏は1957年生まれのドイツ近現代史の研究者で、上記カーショーの翻訳版の監修者である。この新書は大著読了で疲れた頭のクールダウンになった。
本書はヒトラーの生涯とナチ・ドイツの歴史をコンパクトのまとめている。と言っても、早わかり解説本ではなく、史実の背景分析にウエイトが置かれている。
ヒトラー政権成立時に副首相に就任した元首相パーペンは「ヒトラーを雇い入れる」「用が済めば放り出せばよい」と考えていたが、その思惑は外れる。著者の石田氏は次のように記述している。
「この日(ヒトラー政権成立の1933年1月30日)から、ヒトラーが首相と大統領の地位と権限をあわせもつ絶対の「指導者」(総統)に就任する三四年八月二日までは、振り返ると実に恐ろしい一年半だ。あれよあれよというまに、さまざまなことが決まり、もはや民主主義国家に戻ることのできない不可逆地点を越えた。結果的にホロコーストへとつながる最初の一歩も、すでにこの時期に踏み出していた。」
時代が動くときには時間が極端に速く流れる。歴史にはそんな局面がしばしば現われる。よく知っておくべきことだと思う。
本書はユダヤ人迫害とホロコーストの背景と過程を丁寧に分析している。遺伝病患者や心身障害者への「安楽死殺害政策」とホロコーストの関連、ユダヤ人国外退去政策が絶滅政策に転換していった経緯が明解に分析されている。
最新の研究成果が反映されいるのも本書の特色だ。『わが闘争』はヒトラーの口述をヘスが筆記したとされていたが、ヒトラー本人がタイプライターで書いたらしい。また、ヒトラーが反ユダヤ思想を抱いたのはウィーンでの浮草暮らし時代ではなく第一次大戦後らしい。歴史の見方は更新されていくから面白い。
サルトルの『出口なし』は芝居らしい芝居 ― 2018年08月30日
サルトルの『出口なし』(演出:小川絵梨子)を新国立劇場小劇場で観た。出演は大竹しのぶ、多部未華子、段田安則である。
かの実存主義のサルトルである。私の世代にとっては避けて通るのが難しい知識人代表選手のような存在だったが、私はろくに読んでいない。もはや忘れられた過去の哲学者・文学者と思っていた。
そのサルトルの名が大竹しのぶ、多部未華子という名と並んでいる取り合わせに軽い衝撃を受け、劇場に足を運んだ。サルトルの芝居は約半世紀前に『汚れた手』(劇団民芸)を観ただけだ。今回の観劇を機に古書で入手した戯曲『出口なし』には事前に目を通した。
不思議な一部屋に閉じ込められた三人の会話で終始する芝居である。三人の役者が好演する舞台を観終えて、いかにも芝居らしい芝居を観たなあという、懐かしさに似た感慨がわいた。
三人の登場人物は死んだばかりの死者であり、みな自分が死んだことを知っている。しかも自分たちが天国ではなく地獄におとされたことも自覚している。ただし、地獄がどんな所かは知らない。そんな三人の会話劇である。いろいろな展開が想定される面白い設定だ。
『出口なし』は現代人のおかれた状況を地獄に見立てた芝居で、救いを見出しにくい話ではあるが、多少のユーモアもある。キメ科白は「地獄とは他人のことだ」である。これは残る。出口が開いても誰も出て行けない。他人なしに自身が存在できないのだ。
観劇の後、唐十郎の紅テント『状況劇場』という名はサルトルの「シチュアシオン」(Situations)に由来すると聞いたような気がすると思い出し、サルトルの舞台が少しだけ身近に思えてきた。
かの実存主義のサルトルである。私の世代にとっては避けて通るのが難しい知識人代表選手のような存在だったが、私はろくに読んでいない。もはや忘れられた過去の哲学者・文学者と思っていた。
そのサルトルの名が大竹しのぶ、多部未華子という名と並んでいる取り合わせに軽い衝撃を受け、劇場に足を運んだ。サルトルの芝居は約半世紀前に『汚れた手』(劇団民芸)を観ただけだ。今回の観劇を機に古書で入手した戯曲『出口なし』には事前に目を通した。
不思議な一部屋に閉じ込められた三人の会話で終始する芝居である。三人の役者が好演する舞台を観終えて、いかにも芝居らしい芝居を観たなあという、懐かしさに似た感慨がわいた。
三人の登場人物は死んだばかりの死者であり、みな自分が死んだことを知っている。しかも自分たちが天国ではなく地獄におとされたことも自覚している。ただし、地獄がどんな所かは知らない。そんな三人の会話劇である。いろいろな展開が想定される面白い設定だ。
『出口なし』は現代人のおかれた状況を地獄に見立てた芝居で、救いを見出しにくい話ではあるが、多少のユーモアもある。キメ科白は「地獄とは他人のことだ」である。これは残る。出口が開いても誰も出て行けない。他人なしに自身が存在できないのだ。
観劇の後、唐十郎の紅テント『状況劇場』という名はサルトルの「シチュアシオン」(Situations)に由来すると聞いたような気がすると思い出し、サルトルの舞台が少しだけ身近に思えてきた。



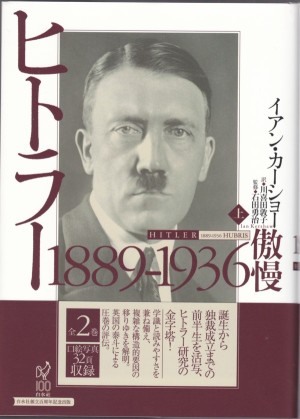


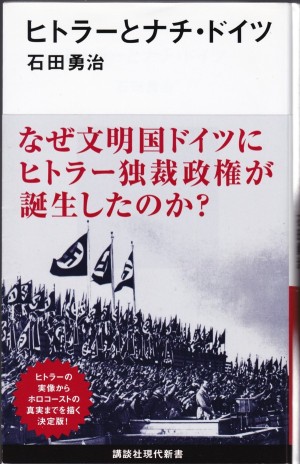

最近のコメント