スタンダール『パルムの僧院』に押し切られた ― 2018年06月12日
◎19世紀フランス小説を読む理由
3年前から19世紀フランスの小説をボチボチ読んでいる。ピケティが『21世紀の資本』でバルザックなどを引用して「21世紀は19世紀の再来になるかもしれない」と指摘していたのがきっかけの一つだ。
若い頃はロシア文学に魅せられていてフランス文学は素通りし、今頃になってフランス文学の面白さを認識したということもある。
年を取ったせいか、同時代の現代小説より19世紀の小説の方が面白く読めるのも確かだ。世捨て人になったわけではないが…。
そんなわけでバルザック、ユゴー、デュマ、ゾラなどの小説をいくつか読んできた。19世紀の作家と言っても世代はさまざまだ。1799年生まれのバルザックと1840年生まれゾラは親子以上に離れていて、現代に近いゾラの方が生々しい。ユゴーとデュマは1802年生まれの同い年でバルザックとほぼ同世代だ…などと考えていて、彼らより一回り年長のスタンダール(1783年~1842年)も読まなくては、という気分になった。
◎『パルムの僧院』は天保の時代小説
スタンダールの『赤と黒』は半世紀近く昔の学生時代に読んだが内容はほとんど失念している。『赤と黒』の再読も考えたが未読の『パルムの僧院』を読むことにした。書架の古い文学全集の生島遼一訳は活字が小さくて辛いので、やや活字の大きい次の文庫本にした。
『パルムの僧院(上)(下)』(スタンダール/大岡昇平訳/新潮文庫)
この小説の舞台は19世紀始めの北イタリアで、主人公を含む大半の登場人物はイタリア人だ。ただし語り手(スタンダール?)はフランス人という設定で、当時のフランス人とイタリア人の気質や考え方の違いをいろいろ述べている。現代の日本人の私にはその機微がわからない。
前半は小説にイマイチ入り込めず、やや退屈だった。ワーテルローの戦いを背景にしたイタリア貴族の恋愛模様を描いているが、あまりに時代小説的でリアリティを感じることができない。日本なら江戸時代(文政・天保)の話だから時代小説めくのは致し方ない。
だが、興味深い描写もいくつかあった。フランス革命からナポレオンに至る時代の西欧貴族たちのさまざまな立場や気分が感得できるのは面白い。イタリア統一以前のいろいろな公国や王国が分立している北イタリア地方の状況や雰囲気をうかがい知ることができたのも収穫だ。
◎やはり面白い
小説後半に入ると次第に面白くなってきた。率直には感情移入しがたい登場人物たちに呆れつつも魅力を感じるようになり、19世紀的とも言える作者の力業に圧倒され、押し切られるような形で小説世界に引きずり込まれてしまった。やはり、19世紀の古典はあなどれない。
『パルムの僧院』は僧院の話でも宗教者の話でもない。主人公は侯爵の次男のファブリスという若い貴族で、その叔母である伯爵夫人(ジーナ)との恋愛感情を軸に、他の若い娘(クレリア)との恋愛も絡まり、貴族の経済や宮廷政治を背景に、殺人・投獄・脱獄などの波乱もある人間模様を描いた物語である。
主人公のファブリスは一応は魅力的に描かれているが、感情過多の軽薄な人物にも見えてしまう。むしろ伯爵夫人の方が魅力的で、実質的には彼女が主人公のように見える。若い娘・クレリアも十分に魅力的である。この二人の女性によって物語は盛り上がる。
そして、盛り上がった物語は最後の数ページでバタバタと駆け足で終幕を迎える。これには唖然とした。作者が力尽きて最後は粗筋で手抜きしたようにも見える。だが、最終段階で時間を圧縮して坦々と記述するのは、人生の真実を語る秀逸な手法かもしれない。臨終の人が人生をふり返るとき、その一生は均一の時間ではなく、ある一時期が圧倒的なウエイトを占めるはずだ。それを反映した小説手法に思える。
「パルムの僧院」という言葉は、この長大な小説の最終ページに初めて出てくる。それは、この小説で語られた波乱の青春期の後、主人公ファブリスが残りの人生(わずか1年)を過ごした場所の名である。人生のパノラマ視の象徴のようなタイトルだ。
◎蛇足
『パルムの僧院』を読んでいて、小さな発見がいくつかあった。一つは、貴族の立場で使われる「ブルジョア」という言葉が、過剰な贅沢を排したつましい生活を表していることだ。時代背景からして当然だと得心しつつも、19世紀と20世紀の語感の違いを知った。この点は、21世紀に19世紀が復活するとは思えない。
もう一つは、貴族が余暇を過ごす趣味の一つが遺跡発掘だという点だ。つい先月も、シチリアでそんな痕跡を観たばかりで、篤志な金持ちの事業と感心していたが、もっと軽いノリの趣味の発掘も多かったのではと思えてきた。
3年前から19世紀フランスの小説をボチボチ読んでいる。ピケティが『21世紀の資本』でバルザックなどを引用して「21世紀は19世紀の再来になるかもしれない」と指摘していたのがきっかけの一つだ。
若い頃はロシア文学に魅せられていてフランス文学は素通りし、今頃になってフランス文学の面白さを認識したということもある。
年を取ったせいか、同時代の現代小説より19世紀の小説の方が面白く読めるのも確かだ。世捨て人になったわけではないが…。
そんなわけでバルザック、ユゴー、デュマ、ゾラなどの小説をいくつか読んできた。19世紀の作家と言っても世代はさまざまだ。1799年生まれのバルザックと1840年生まれゾラは親子以上に離れていて、現代に近いゾラの方が生々しい。ユゴーとデュマは1802年生まれの同い年でバルザックとほぼ同世代だ…などと考えていて、彼らより一回り年長のスタンダール(1783年~1842年)も読まなくては、という気分になった。
◎『パルムの僧院』は天保の時代小説
スタンダールの『赤と黒』は半世紀近く昔の学生時代に読んだが内容はほとんど失念している。『赤と黒』の再読も考えたが未読の『パルムの僧院』を読むことにした。書架の古い文学全集の生島遼一訳は活字が小さくて辛いので、やや活字の大きい次の文庫本にした。
『パルムの僧院(上)(下)』(スタンダール/大岡昇平訳/新潮文庫)
この小説の舞台は19世紀始めの北イタリアで、主人公を含む大半の登場人物はイタリア人だ。ただし語り手(スタンダール?)はフランス人という設定で、当時のフランス人とイタリア人の気質や考え方の違いをいろいろ述べている。現代の日本人の私にはその機微がわからない。
前半は小説にイマイチ入り込めず、やや退屈だった。ワーテルローの戦いを背景にしたイタリア貴族の恋愛模様を描いているが、あまりに時代小説的でリアリティを感じることができない。日本なら江戸時代(文政・天保)の話だから時代小説めくのは致し方ない。
だが、興味深い描写もいくつかあった。フランス革命からナポレオンに至る時代の西欧貴族たちのさまざまな立場や気分が感得できるのは面白い。イタリア統一以前のいろいろな公国や王国が分立している北イタリア地方の状況や雰囲気をうかがい知ることができたのも収穫だ。
◎やはり面白い
小説後半に入ると次第に面白くなってきた。率直には感情移入しがたい登場人物たちに呆れつつも魅力を感じるようになり、19世紀的とも言える作者の力業に圧倒され、押し切られるような形で小説世界に引きずり込まれてしまった。やはり、19世紀の古典はあなどれない。
『パルムの僧院』は僧院の話でも宗教者の話でもない。主人公は侯爵の次男のファブリスという若い貴族で、その叔母である伯爵夫人(ジーナ)との恋愛感情を軸に、他の若い娘(クレリア)との恋愛も絡まり、貴族の経済や宮廷政治を背景に、殺人・投獄・脱獄などの波乱もある人間模様を描いた物語である。
主人公のファブリスは一応は魅力的に描かれているが、感情過多の軽薄な人物にも見えてしまう。むしろ伯爵夫人の方が魅力的で、実質的には彼女が主人公のように見える。若い娘・クレリアも十分に魅力的である。この二人の女性によって物語は盛り上がる。
そして、盛り上がった物語は最後の数ページでバタバタと駆け足で終幕を迎える。これには唖然とした。作者が力尽きて最後は粗筋で手抜きしたようにも見える。だが、最終段階で時間を圧縮して坦々と記述するのは、人生の真実を語る秀逸な手法かもしれない。臨終の人が人生をふり返るとき、その一生は均一の時間ではなく、ある一時期が圧倒的なウエイトを占めるはずだ。それを反映した小説手法に思える。
「パルムの僧院」という言葉は、この長大な小説の最終ページに初めて出てくる。それは、この小説で語られた波乱の青春期の後、主人公ファブリスが残りの人生(わずか1年)を過ごした場所の名である。人生のパノラマ視の象徴のようなタイトルだ。
◎蛇足
『パルムの僧院』を読んでいて、小さな発見がいくつかあった。一つは、貴族の立場で使われる「ブルジョア」という言葉が、過剰な贅沢を排したつましい生活を表していることだ。時代背景からして当然だと得心しつつも、19世紀と20世紀の語感の違いを知った。この点は、21世紀に19世紀が復活するとは思えない。
もう一つは、貴族が余暇を過ごす趣味の一つが遺跡発掘だという点だ。つい先月も、シチリアでそんな痕跡を観たばかりで、篤志な金持ちの事業と感心していたが、もっと軽いノリの趣味の発掘も多かったのではと思えてきた。
『ローマ帝国の神々』で「多神教」の実態が少し見えた ― 2018年06月18日
◎複雑な宗教事情
ローマ帝国はその衰退期にキリスト教を容認し国教にする。キリスト教の神の力による帝国の再興は成らず、キリスト教を受け容れた帝国はやがて滅亡する。キリスト教という一神教を受け容れる以前のローマは多神教の国だった。
私はゴリゴリの一神教よりは多神教の方が寛容そうで好ましいとの気分をもっているものの、その多神教の神々についてさほどの関心があるわけない。多神教の神とはギリシア・ローマ神話に登場するユピテルやアポロなどの神々だろうと漠然と考えていただけだ。
古代ローマ史に興味があってもその宗教への関心が薄いのは、ローマ帝国の人々が天界や精神世界よりは現世への関心の方が高かったように勝手に思っているからだ。だが、巨大な神殿の遺跡などに接すと、やはり宗教の力をあなどってはいけないと思えてくる。
で、おのれの無知を多少は補うつもりで次の本を読んだ。
『ローマ帝国の神々:光はオリエントより』(小川英雄/中公新書)
本書によって古代ローマの複雑で多様な宗教事情を知り、私の知らない世界を垣間見ることができた。なかなか興味深い世界だ。
◎ギリシアの神々では物足りなかった
本書はギリシア・ローマ神話の神々について書いたものではない。サブタイトルに「光はオリエントより」とあるように、ペルシア、シリア、エジプト、小アジアなどの地域からローマ帝国に伝わってきた多様な神々を扱っている。
「まえがき」には次のようなフレーズがある。
「ギリシア文化とともにローマ世界に入ってきたギリシアの神々はあまりに人間的であり、信仰の対象としては不十分であった。」
納得できる指摘だ。目から鱗が落ちた気分になる。あの神話世界の面白くもやや威厳に欠け軽率でさえある神々を「宗教」の視点でとらえるのは無理があるのだ。だから、東方のさまざまな宗教が入ってきたのだ。
と言っても、どんな宗教も荒唐無稽に見える神話を背景にした神を戴いているし、文明の誕生とともにさまざまな場所でそれぞれの宗教が誕生する。それが、人々の交流によって混合・変質・淘汰されていく。
ギリシアの神々もそのような文明のうねりの中の素材のひとつだったと思われる。本書を読むと、宗教とは時代ととも混合・変質していくものだとわかる。
◎キリスト教の標的になったミトラ教
古代ローマの本には「ミトラ教」というやや怪しげな宗教が出てくることがある。本書を読もうと思ったきっかけのひとつは、このミトラ教について知りたいと思ったからだ。
本書には「ミトラス教 --- イラン起源の神」という章があり、この宗教の概要を知ることができた。
この宗教の神名は元々はミスラで、ギリシア人はミトラスと呼び、ローマ人はミトラと呼んだそうだ。この宗教の起源は非常に古く明確でない。複雑で曖昧だ。ゾロアスター教にもミスラがあり、中国や日本では弥勒菩薩になったらしい。広大無辺でつかみどころがない。
ローマ帝国にはかなり多くのミトラス神殿があったそうだ。だが、4世紀にはキリスト教の標的になって神殿を破壊されオリエント系「異教」の中ではいち早く姿を消したそうだ。
◎取り込んで淘汰する
オリエントからローマ帝国に拡がってきた宗教の真打はキリスト教であり、本書はキリスト教の正統派(アナタシウス派)が「異教」や「異端」を淘汰していく物語にもなっている。
キリスト教は、その形成過程において他の宗教の儀式をはじめいろいろな要素を取り込み、それ故に他の宗教を迫害してきたのだ。それだけでなくギリシア哲学も取り込んでいるところが巧みだ。
著者はキリスト教成功の要因をいくつか挙げているが、注目すべきは次の指摘だ。
「キリスト教の信者たちは非妥協的であるのに対して、他宗派の人々はお互いの神々に寛容であった。」
「寛容」が「非妥協」に敗北して、キリスト教世界が広まったのである。「寛容」の世界の方が「非妥協」の世界より住みよいと思うので、普遍的真実とは思いたくないが、歴史の現実である。別の視点もあり得るかもしれないが…。
ローマ帝国はその衰退期にキリスト教を容認し国教にする。キリスト教の神の力による帝国の再興は成らず、キリスト教を受け容れた帝国はやがて滅亡する。キリスト教という一神教を受け容れる以前のローマは多神教の国だった。
私はゴリゴリの一神教よりは多神教の方が寛容そうで好ましいとの気分をもっているものの、その多神教の神々についてさほどの関心があるわけない。多神教の神とはギリシア・ローマ神話に登場するユピテルやアポロなどの神々だろうと漠然と考えていただけだ。
古代ローマ史に興味があってもその宗教への関心が薄いのは、ローマ帝国の人々が天界や精神世界よりは現世への関心の方が高かったように勝手に思っているからだ。だが、巨大な神殿の遺跡などに接すと、やはり宗教の力をあなどってはいけないと思えてくる。
で、おのれの無知を多少は補うつもりで次の本を読んだ。
『ローマ帝国の神々:光はオリエントより』(小川英雄/中公新書)
本書によって古代ローマの複雑で多様な宗教事情を知り、私の知らない世界を垣間見ることができた。なかなか興味深い世界だ。
◎ギリシアの神々では物足りなかった
本書はギリシア・ローマ神話の神々について書いたものではない。サブタイトルに「光はオリエントより」とあるように、ペルシア、シリア、エジプト、小アジアなどの地域からローマ帝国に伝わってきた多様な神々を扱っている。
「まえがき」には次のようなフレーズがある。
「ギリシア文化とともにローマ世界に入ってきたギリシアの神々はあまりに人間的であり、信仰の対象としては不十分であった。」
納得できる指摘だ。目から鱗が落ちた気分になる。あの神話世界の面白くもやや威厳に欠け軽率でさえある神々を「宗教」の視点でとらえるのは無理があるのだ。だから、東方のさまざまな宗教が入ってきたのだ。
と言っても、どんな宗教も荒唐無稽に見える神話を背景にした神を戴いているし、文明の誕生とともにさまざまな場所でそれぞれの宗教が誕生する。それが、人々の交流によって混合・変質・淘汰されていく。
ギリシアの神々もそのような文明のうねりの中の素材のひとつだったと思われる。本書を読むと、宗教とは時代ととも混合・変質していくものだとわかる。
◎キリスト教の標的になったミトラ教
古代ローマの本には「ミトラ教」というやや怪しげな宗教が出てくることがある。本書を読もうと思ったきっかけのひとつは、このミトラ教について知りたいと思ったからだ。
本書には「ミトラス教 --- イラン起源の神」という章があり、この宗教の概要を知ることができた。
この宗教の神名は元々はミスラで、ギリシア人はミトラスと呼び、ローマ人はミトラと呼んだそうだ。この宗教の起源は非常に古く明確でない。複雑で曖昧だ。ゾロアスター教にもミスラがあり、中国や日本では弥勒菩薩になったらしい。広大無辺でつかみどころがない。
ローマ帝国にはかなり多くのミトラス神殿があったそうだ。だが、4世紀にはキリスト教の標的になって神殿を破壊されオリエント系「異教」の中ではいち早く姿を消したそうだ。
◎取り込んで淘汰する
オリエントからローマ帝国に拡がってきた宗教の真打はキリスト教であり、本書はキリスト教の正統派(アナタシウス派)が「異教」や「異端」を淘汰していく物語にもなっている。
キリスト教は、その形成過程において他の宗教の儀式をはじめいろいろな要素を取り込み、それ故に他の宗教を迫害してきたのだ。それだけでなくギリシア哲学も取り込んでいるところが巧みだ。
著者はキリスト教成功の要因をいくつか挙げているが、注目すべきは次の指摘だ。
「キリスト教の信者たちは非妥協的であるのに対して、他宗派の人々はお互いの神々に寛容であった。」
「寛容」が「非妥協」に敗北して、キリスト教世界が広まったのである。「寛容」の世界の方が「非妥協」の世界より住みよいと思うので、普遍的真実とは思いたくないが、歴史の現実である。別の視点もあり得るかもしれないが…。
17年前に購入した『日本文学盛衰史』を読んだ ― 2018年06月26日
◎劇評記事で原作小説を想起
日経新聞(2018.6.15夕刊)と朝日新聞(2018.6.18夕刊)で『日本文学盛衰史』という芝居の劇評に接し、面白そうなので早速チケットを手配した。
同時に、この芝居の原作である高橋源一郎の小説が未読のまま本棚の奥に眠っているのを思い出した。
『日本文学盛衰史』(高橋源一郎/講談社)
購入したのは17年前の2001年。購入のきっかけは明確だ。当時、高橋源一郎が『週刊朝日』に連載していたコラムで2週に渡ってこの自著を宣伝し、その紹介文に惹かれたからだ。そんな昔の経緯を憶えているわけではない。この本にコラムの切り抜きが挟まっていたので記憶がよみがえったのだ。
何故未読のまま放置したかは定かでない。箱入りハードカバー約600頁という分厚さにたじろいで後回しにしているうちに失念したのだろう。
観劇前に小説を読んでおかねばと繙くと面白さに引き込まれて一気に読了できた。奇天烈なエッセイ風パロディ小説である。
◎舞台は明治だが、20世紀末でもある
この小説は『群像』(1997年5月号~2000年11月号)に連載され、2001年5月に刊行されている。刊行直前の著者の自己宣伝コラムには次のように書いてある。
「舞台は明治、登場人物は夏目漱石、森鴎外、石川啄木、二葉亭四迷たち明治の作家---(略)書き進めながら、『日本文学盛衰史』は明治でも現代でもあるような、小説でも批評でも詩でも歴史でもマンガでもポルノでもあるような不思議で長大な作品になっていった。」
著者が述べているように舞台は明治であり、登場人物は当時の文学者たちだ。しかし、漱石と鴎外が「たまごっち」を話題にし、啄木がブルセラショップの店長になり、『蒲団』の田山花袋がアダルトビデオの監督になったりと、連載当時の1990年代後期の風俗が明治に浸潤している。タカハシ・ゲンイチロウも登場人物や話者として顔を出し、その胃カメラ写真がカラーで引用されている。まことに奔放である。
物語の中盤まではパロディ風だが後半はエッセイ味が強くなってくる。後半までパロディ世界を徹底させればもっと面白かったのにと思う。
エッセイ風の部分がつまらないわけではない。特にに後段の「謎解き『こころ』(漱石)」と言える部分には引き込まれた。普通の評論としても成り立つ題材だが、それを評論にするのは無粋だからフィクションにしたのだと思う。だとすれば、フィクションとしてもっとはじけてもいいのにと感じた。
◎わからくても楽しめた
著者は小説執筆にあたって明治の文学にどっぷり浸ったそうで、この小説には多くの明治の文学者が登場する。その大半は、私にとっては名前を聞いたことがあっても作品に接したことのない未知の文学者である。それでも、この小説を楽しむことはできた。
もちろん、北村透谷、山田美妙、川上眉山、横瀬夜雨、伊良子清白などなど私が読んでいない文学者たちの作品を読めば、もっと楽しめるのだろうが、そこまで深入りする気にはなれない。
また、この小説はパロディにあふれている。島崎藤村が『破戒』を書きながら「勝利だよ、勝利だよ」とつぶやくのは、吉本隆明の『言語にとって美となにか』の「あとがき」の引用だろう。何故、藤村が隆明だとの疑念を抱くも思わず笑ってしまう。「されど我らが日々」と「そしていつの日にか」の対句は柴田翔へのオマージュなのか揶揄なのか…。
そんな、私でも原典が推測できるものもあるが、大半は私にはわからない。それがわかればもっと笑えるだろうと残念に思うが仕方ない。
◎奇妙な時間感覚
刊行から17年を経てこの小説を読んだことによって、刊行直後に読んだなら感じなかったであろう時間感覚を抱いた。
この小説に登場する「たまごっち」「伝言ダイヤル」「パソコン通信」などなど1990年代後半(つまりは20世紀末)の事象は、現在(2018年)から見ればもはや懐かしい遺物だ。
明治が遠くになったのは当然として、本書発表時の20世紀末も「遠くなりにけり」である。
新聞の劇評によれば、現在上演中の芝居『日本文学盛衰史』は平田オリザ作・演出で、原作小説への「返歌」になっているそうだ。どんな舞台なのか、今週末の観劇が楽しみだ。
日経新聞(2018.6.15夕刊)と朝日新聞(2018.6.18夕刊)で『日本文学盛衰史』という芝居の劇評に接し、面白そうなので早速チケットを手配した。
同時に、この芝居の原作である高橋源一郎の小説が未読のまま本棚の奥に眠っているのを思い出した。
『日本文学盛衰史』(高橋源一郎/講談社)
購入したのは17年前の2001年。購入のきっかけは明確だ。当時、高橋源一郎が『週刊朝日』に連載していたコラムで2週に渡ってこの自著を宣伝し、その紹介文に惹かれたからだ。そんな昔の経緯を憶えているわけではない。この本にコラムの切り抜きが挟まっていたので記憶がよみがえったのだ。
何故未読のまま放置したかは定かでない。箱入りハードカバー約600頁という分厚さにたじろいで後回しにしているうちに失念したのだろう。
観劇前に小説を読んでおかねばと繙くと面白さに引き込まれて一気に読了できた。奇天烈なエッセイ風パロディ小説である。
◎舞台は明治だが、20世紀末でもある
この小説は『群像』(1997年5月号~2000年11月号)に連載され、2001年5月に刊行されている。刊行直前の著者の自己宣伝コラムには次のように書いてある。
「舞台は明治、登場人物は夏目漱石、森鴎外、石川啄木、二葉亭四迷たち明治の作家---(略)書き進めながら、『日本文学盛衰史』は明治でも現代でもあるような、小説でも批評でも詩でも歴史でもマンガでもポルノでもあるような不思議で長大な作品になっていった。」
著者が述べているように舞台は明治であり、登場人物は当時の文学者たちだ。しかし、漱石と鴎外が「たまごっち」を話題にし、啄木がブルセラショップの店長になり、『蒲団』の田山花袋がアダルトビデオの監督になったりと、連載当時の1990年代後期の風俗が明治に浸潤している。タカハシ・ゲンイチロウも登場人物や話者として顔を出し、その胃カメラ写真がカラーで引用されている。まことに奔放である。
物語の中盤まではパロディ風だが後半はエッセイ味が強くなってくる。後半までパロディ世界を徹底させればもっと面白かったのにと思う。
エッセイ風の部分がつまらないわけではない。特にに後段の「謎解き『こころ』(漱石)」と言える部分には引き込まれた。普通の評論としても成り立つ題材だが、それを評論にするのは無粋だからフィクションにしたのだと思う。だとすれば、フィクションとしてもっとはじけてもいいのにと感じた。
◎わからくても楽しめた
著者は小説執筆にあたって明治の文学にどっぷり浸ったそうで、この小説には多くの明治の文学者が登場する。その大半は、私にとっては名前を聞いたことがあっても作品に接したことのない未知の文学者である。それでも、この小説を楽しむことはできた。
もちろん、北村透谷、山田美妙、川上眉山、横瀬夜雨、伊良子清白などなど私が読んでいない文学者たちの作品を読めば、もっと楽しめるのだろうが、そこまで深入りする気にはなれない。
また、この小説はパロディにあふれている。島崎藤村が『破戒』を書きながら「勝利だよ、勝利だよ」とつぶやくのは、吉本隆明の『言語にとって美となにか』の「あとがき」の引用だろう。何故、藤村が隆明だとの疑念を抱くも思わず笑ってしまう。「されど我らが日々」と「そしていつの日にか」の対句は柴田翔へのオマージュなのか揶揄なのか…。
そんな、私でも原典が推測できるものもあるが、大半は私にはわからない。それがわかればもっと笑えるだろうと残念に思うが仕方ない。
◎奇妙な時間感覚
刊行から17年を経てこの小説を読んだことによって、刊行直後に読んだなら感じなかったであろう時間感覚を抱いた。
この小説に登場する「たまごっち」「伝言ダイヤル」「パソコン通信」などなど1990年代後半(つまりは20世紀末)の事象は、現在(2018年)から見ればもはや懐かしい遺物だ。
明治が遠くになったのは当然として、本書発表時の20世紀末も「遠くなりにけり」である。
新聞の劇評によれば、現在上演中の芝居『日本文学盛衰史』は平田オリザ作・演出で、原作小説への「返歌」になっているそうだ。どんな舞台なのか、今週末の観劇が楽しみだ。
平田オリザの『日本文学盛衰史』を観た ― 2018年06月30日
吉祥寺シアターで『日本文学盛衰史』(作・演出:平田オリザ、青年団第79回公演)を観た。平田オリザの芝居を観るのは初めてだ。
休憩なしの2時間20分、舞台は一貫して葬儀(通夜)の宴席である。同じ装置のまま4場に転換し、次の4つの通夜が演じられる。
第1場 北村透谷の葬儀 1894年(明治27年)
第2場 正岡子規の葬儀 1902年(明治35年)
第3場 二葉亭四迷の葬儀 1909年(明治42年)
第4場 夏目漱石の葬儀 1916年(大正5年)
高橋源一郎の原作には多くの文学者が登場するが、芝居ではより多彩な文学者たちが時代を越えて出没する。その舞台回しは島崎藤村と田山花袋で、このコンビが軽くて面白い。原作同様に花袋はAVの監督もやっている。加計学園、和歌山のドンファンなどのギャグも飛び出す。
観劇直前に原作の小説を読んでいたので、明治の青年群像に現代の風俗が浸透する奇天烈な世界には容易に入り込めた。原作の「たまごっち」や「伝言ダイヤル」に代わってLINEやツイッターが登場する。舞台装置や人物の服装は明治の趣なので、そんな彼ら彼女らが奇天烈な世界で熱く語り合い狂騒する姿を眺めると、あらためて明治の青年もわれらと同時代人だと感じる。
同時に「誰もが昔は若かった」という当たり前の感慨を抱いた。原作には出てこない野上弥生子(結婚前なので姓は小手川)が若い姿で現われたのには感動した。登場人物の中で唯一、私が実物を見たことがある文学者だ。私は高校生の頃(半世紀以上昔)、当時80歳位の野上弥生子の講演を聞いたことがある。舞台を眺めながら明治が地続きに感じられた。
やや意外なのは森鴎外の科白が多いことだ。藤村や花袋のような舞台回しではないのに4つすべての葬儀に参列し、かなりの存在感を発揮している。陸軍軍医総監だった鴎外に、文学者とは別に「国家」の代弁者という役が与えられているからだ。
この芝居は、現代日本語を生み出そうとしている人々の物語であると同時に、思想表現を通じた国家論も射程に入っている。だから「国家」の代弁者も必要なのだ。
その鴎外が何の脈略もなく、突然に「脚気は、脚気菌が原因である」と絶叫し、その後「失礼しました。大人げないところを見せてしまいました」と冷静に返る。このシーンには笑うと同時に感心した。平田オリザは鴎外批判の勘所をおさえていると思った。
高橋源一郎の『日本文学盛衰史』は、そのタイトルが示すように、一時は盛り上がった「文学」の衰退を予感させている。と言っても文学の命運を明示しているわけではない。
平田オリザの舞台は文学の「盛衰」や「命運」をより明示しようと試みている。ラスト近くの狂騒に近づくシーンでは「作家は長者番付の常連になります。20世紀の終わりまでは」という科白が飛び出し、「やがて、小説はだんだんと読まれなくなります」と続く。
20世紀末に書かれた『日本文学盛衰史』は衰退に入る直前、つまりは最盛期最後の小説だったのだ。芝居の方がよりシビアな現実を表現していることになる。文学と直接には関連しないかもしれないが、芝居では新聞の衰退にも触れていて、かなり辛辣だ。
だが、原作小説より芝居の方が明るくて楽観的に感じられた。何故だろうか。最後にみんなが踊りだすからではない、と思う。小説よりは芝居の方が原初的なものだからだろうか。
休憩なしの2時間20分、舞台は一貫して葬儀(通夜)の宴席である。同じ装置のまま4場に転換し、次の4つの通夜が演じられる。
第1場 北村透谷の葬儀 1894年(明治27年)
第2場 正岡子規の葬儀 1902年(明治35年)
第3場 二葉亭四迷の葬儀 1909年(明治42年)
第4場 夏目漱石の葬儀 1916年(大正5年)
高橋源一郎の原作には多くの文学者が登場するが、芝居ではより多彩な文学者たちが時代を越えて出没する。その舞台回しは島崎藤村と田山花袋で、このコンビが軽くて面白い。原作同様に花袋はAVの監督もやっている。加計学園、和歌山のドンファンなどのギャグも飛び出す。
観劇直前に原作の小説を読んでいたので、明治の青年群像に現代の風俗が浸透する奇天烈な世界には容易に入り込めた。原作の「たまごっち」や「伝言ダイヤル」に代わってLINEやツイッターが登場する。舞台装置や人物の服装は明治の趣なので、そんな彼ら彼女らが奇天烈な世界で熱く語り合い狂騒する姿を眺めると、あらためて明治の青年もわれらと同時代人だと感じる。
同時に「誰もが昔は若かった」という当たり前の感慨を抱いた。原作には出てこない野上弥生子(結婚前なので姓は小手川)が若い姿で現われたのには感動した。登場人物の中で唯一、私が実物を見たことがある文学者だ。私は高校生の頃(半世紀以上昔)、当時80歳位の野上弥生子の講演を聞いたことがある。舞台を眺めながら明治が地続きに感じられた。
やや意外なのは森鴎外の科白が多いことだ。藤村や花袋のような舞台回しではないのに4つすべての葬儀に参列し、かなりの存在感を発揮している。陸軍軍医総監だった鴎外に、文学者とは別に「国家」の代弁者という役が与えられているからだ。
この芝居は、現代日本語を生み出そうとしている人々の物語であると同時に、思想表現を通じた国家論も射程に入っている。だから「国家」の代弁者も必要なのだ。
その鴎外が何の脈略もなく、突然に「脚気は、脚気菌が原因である」と絶叫し、その後「失礼しました。大人げないところを見せてしまいました」と冷静に返る。このシーンには笑うと同時に感心した。平田オリザは鴎外批判の勘所をおさえていると思った。
高橋源一郎の『日本文学盛衰史』は、そのタイトルが示すように、一時は盛り上がった「文学」の衰退を予感させている。と言っても文学の命運を明示しているわけではない。
平田オリザの舞台は文学の「盛衰」や「命運」をより明示しようと試みている。ラスト近くの狂騒に近づくシーンでは「作家は長者番付の常連になります。20世紀の終わりまでは」という科白が飛び出し、「やがて、小説はだんだんと読まれなくなります」と続く。
20世紀末に書かれた『日本文学盛衰史』は衰退に入る直前、つまりは最盛期最後の小説だったのだ。芝居の方がよりシビアな現実を表現していることになる。文学と直接には関連しないかもしれないが、芝居では新聞の衰退にも触れていて、かなり辛辣だ。
だが、原作小説より芝居の方が明るくて楽観的に感じられた。何故だろうか。最後にみんなが踊りだすからではない、と思う。小説よりは芝居の方が原初的なものだからだろうか。

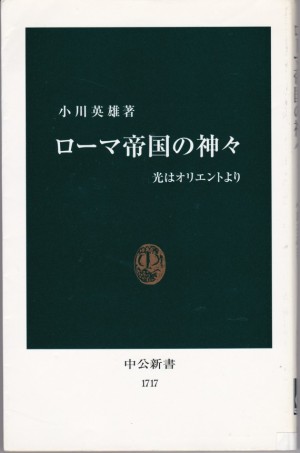


最近のコメント