ヨーロッパ中世の概説書で『大聖堂』の世界を検証 ― 2016年04月03日
◎ヨーロッパ中世の概説書を読む
書架に並べてある世界史シリーズ本の中からヨーロッパ中世を扱った次の2冊を引っ張り出して読んだ。
『中世の光と影(大世界史 7)』(堀米庸三/文藝春秋/1966.12)
『西ヨーロッパ世界の形成(世界の歴史 10)』(佐藤彰一、池上俊一/中央公論社/1997.5)
前者は約50年前、後者は約20年前の本だ。元来、私はヨーロッパ中世には無知で、さほど関心もなかった。なのに上記の本を読んだのは、ケン・フォレットのエンタメ大長編『大聖堂』『大聖堂 ― 果てしなき世界』(以下『大聖堂・続編』)を読んで、この小説の舞台になった時代の概要を知りたいと思ったからだ。
『大聖堂』の舞台は12世紀イギリスの架空の町、『大聖堂・続編』は同じ町の14世紀の物語だ。職人、商人、修道士、騎士などが活躍する壮大なフィクションだが、歴史上の人物も多少は登場する。前者ではイングランド王のヘンリー1世、スティーブン1世、ヘンリー2世、カンタベリー大司教のトマス・ベケットなど、後者ではエドワード3世、プリンス・オブ・ウェールズなどだ。いずれも高校の世界史には出てこない人々だ。高校世界史よりは多少詳しい概説書を読んで史実を把握しておこうと思った。
◎ヨーロッパ中世千年史に既視感
『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』のいずれにも巻末に年表があり、そこには4世紀から15世紀までの約千年の出来事が記載されている。ヨーロッパの中世は千年も続いたのかと、あらためてその長さに驚いた。
『中世の光と影』を読み進めていて、かすかな既視感がわいた。ヨーロッパ中世史の本など読んだことがないはずだがと思いつつ記憶を探り、約1年前に読了したギボンの『ローマ帝国衰亡史』と重なっていることに気づいた。あの長大な史書の後半5巻は西ローマ帝国滅亡の5世紀からコンスタンティノポリス陥落の1453年までの約千年を扱っていた。考えてみれば『ローマ帝国衰亡史』は古代史+中世史の本だった。
にもかかわらず、私は『大聖堂』『大聖堂・続編』を読みながらギボンを想起することはなく、自分にとってヨーロッパ中世史は暗闇のようなものだと感じていた。要は読書しても何も残っていないということで、悲しいことではある。とは言え、18世紀英国の啓蒙家ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において自分の国イギリスの中世にはあまり言及していない。かつてのローマ帝国の中心だった地中海世界から見ればイギリスは辺境だったからだろうか。いずれにしても、私はギボンの世界に重なりあいを感じることなく『大聖堂』『大聖堂・続編』を読んだのだ。
◎教科書的な概説書ではなかった
では、『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』を読んで、『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界をより深く知ることができたか。答えはノーでもありイエスでもある。
『中世の光と影』も『西ヨーロッパ世界の形成』も歴史年表を詳述するような教科書的な概説書ではなかった。史実の羅列ではなく著者が中世史をどのように捉えているかを述べた本で、『大聖堂』『大聖堂・続編』に登場する実在の国王などに関する記述はほとんどなかった。
『大聖堂』は12世紀半ばの約50年、『大聖堂・続編』は14世紀半ばの約30年の物語で、千年の中世史の中のわずかな時間に過ぎない。また、小説の舞台イギリスはヨーロッパ中世史の中心地域からはやや外れている。1冊で千年を語る概説書の記述から漏れ落ちるのは仕方ない。小説に登場する実在の人物に関する史実を確認したいという目的は果たされなかった。
ただし、トマス・ベケット大司教の暗殺は『中世の光と影』で言及されていた。フィクションの主要人物を暗殺者に仕立て、小説に史実を巧みに組み込んでいることがわかり、拾いものだった。
『中世の光と影』は、紀行文を随所に挿入した歴史エッセイ風の本で、法王と皇帝とのせめぎあいでヨーロッパが作られていくさまが描かれていて、中世という時代の様子が俯瞰できた。また、教会建築がロマネスク様式からゴシック様式に転換していく様子はかなり詳しく書かれている。尖頭アーチ、肋骨式横断アーチ、交叉穹窿などの建築技術が図解入りで解説されているので、『大聖堂』の世界の追体験になった。
◎やはり史実を確認できた
『西ヨーロッパ世界の形成』は予想外の概説書だった。教科書的な史実の解説などほとんどない。読者が基本的な史実を把握していることを前提にした本のようだ。
社会史あるいは民衆史とも言える内容で、少々まごついたが、意外にこれが面白い。都市、農村、森、修道院などについてかなり細かく書かれている。付録の月報は著者二人と日本中世史の大家・網野善彦氏との座談会で、網野氏は「新しい中世史像を知ることができて大きな収穫がありました」と持ち上げている。
『大聖堂』『大聖堂・続編』には実在した国王や大司教も登場するが、主な登場人物は石工、羊毛商人、大工、機織り屋、農民、修道士、修道院長、托鉢修道士、司教、騎士、領主など多様は人々だ。また、主な舞台は修道院、その周辺の町、定期的に開催される市、森、農村などである。『西ヨーロッパ世界の形成』は、このような多様な人々や場所についてかなり詳しく記述している。
私は「縮絨(しゅくじゅう)」という言葉を『大聖堂』で初めて知った。毛織物を仕上げる工程の一つで、かなりの重労働だそうだ。小説では、主人公が縮絨を容易にするため水車を使う方法を「発明」するシーンがある。『西ヨーロッパ世界の形成』で、12世紀頃には水車が縮絨に使われるようになったとの記述に接し、虚実の遭遇に軽い感動を覚えた。また、『大聖堂・続編』では染色に工夫する印象的なシーンがあり、『西ヨーロッパ世界の形成』には、当時の染色職人や染色技術に関する興味深い記述がある。小説との暗合を感じた。
数えあげればきりがないが、『西ヨーロッパ世界の形成』には『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界のディティールに関連した記述が多い。歴史上の人物などとは別次元で、小説世界に展開されたあれこれに史実の裏付けがあることを『西ヨーロッパ世界の形成』で確認できたのは想定外の収穫だった。つまりは、ケン・フォレットが最新(執筆当時)の歴史学や考古学の成果をふまえて小説を書いたことが確認できたのである。
書架に並べてある世界史シリーズ本の中からヨーロッパ中世を扱った次の2冊を引っ張り出して読んだ。
『中世の光と影(大世界史 7)』(堀米庸三/文藝春秋/1966.12)
『西ヨーロッパ世界の形成(世界の歴史 10)』(佐藤彰一、池上俊一/中央公論社/1997.5)
前者は約50年前、後者は約20年前の本だ。元来、私はヨーロッパ中世には無知で、さほど関心もなかった。なのに上記の本を読んだのは、ケン・フォレットのエンタメ大長編『大聖堂』『大聖堂 ― 果てしなき世界』(以下『大聖堂・続編』)を読んで、この小説の舞台になった時代の概要を知りたいと思ったからだ。
『大聖堂』の舞台は12世紀イギリスの架空の町、『大聖堂・続編』は同じ町の14世紀の物語だ。職人、商人、修道士、騎士などが活躍する壮大なフィクションだが、歴史上の人物も多少は登場する。前者ではイングランド王のヘンリー1世、スティーブン1世、ヘンリー2世、カンタベリー大司教のトマス・ベケットなど、後者ではエドワード3世、プリンス・オブ・ウェールズなどだ。いずれも高校の世界史には出てこない人々だ。高校世界史よりは多少詳しい概説書を読んで史実を把握しておこうと思った。
◎ヨーロッパ中世千年史に既視感
『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』のいずれにも巻末に年表があり、そこには4世紀から15世紀までの約千年の出来事が記載されている。ヨーロッパの中世は千年も続いたのかと、あらためてその長さに驚いた。
『中世の光と影』を読み進めていて、かすかな既視感がわいた。ヨーロッパ中世史の本など読んだことがないはずだがと思いつつ記憶を探り、約1年前に読了したギボンの『ローマ帝国衰亡史』と重なっていることに気づいた。あの長大な史書の後半5巻は西ローマ帝国滅亡の5世紀からコンスタンティノポリス陥落の1453年までの約千年を扱っていた。考えてみれば『ローマ帝国衰亡史』は古代史+中世史の本だった。
にもかかわらず、私は『大聖堂』『大聖堂・続編』を読みながらギボンを想起することはなく、自分にとってヨーロッパ中世史は暗闇のようなものだと感じていた。要は読書しても何も残っていないということで、悲しいことではある。とは言え、18世紀英国の啓蒙家ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において自分の国イギリスの中世にはあまり言及していない。かつてのローマ帝国の中心だった地中海世界から見ればイギリスは辺境だったからだろうか。いずれにしても、私はギボンの世界に重なりあいを感じることなく『大聖堂』『大聖堂・続編』を読んだのだ。
◎教科書的な概説書ではなかった
では、『中世の光と影』『西ヨーロッパ世界の形成』を読んで、『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界をより深く知ることができたか。答えはノーでもありイエスでもある。
『中世の光と影』も『西ヨーロッパ世界の形成』も歴史年表を詳述するような教科書的な概説書ではなかった。史実の羅列ではなく著者が中世史をどのように捉えているかを述べた本で、『大聖堂』『大聖堂・続編』に登場する実在の国王などに関する記述はほとんどなかった。
『大聖堂』は12世紀半ばの約50年、『大聖堂・続編』は14世紀半ばの約30年の物語で、千年の中世史の中のわずかな時間に過ぎない。また、小説の舞台イギリスはヨーロッパ中世史の中心地域からはやや外れている。1冊で千年を語る概説書の記述から漏れ落ちるのは仕方ない。小説に登場する実在の人物に関する史実を確認したいという目的は果たされなかった。
ただし、トマス・ベケット大司教の暗殺は『中世の光と影』で言及されていた。フィクションの主要人物を暗殺者に仕立て、小説に史実を巧みに組み込んでいることがわかり、拾いものだった。
『中世の光と影』は、紀行文を随所に挿入した歴史エッセイ風の本で、法王と皇帝とのせめぎあいでヨーロッパが作られていくさまが描かれていて、中世という時代の様子が俯瞰できた。また、教会建築がロマネスク様式からゴシック様式に転換していく様子はかなり詳しく書かれている。尖頭アーチ、肋骨式横断アーチ、交叉穹窿などの建築技術が図解入りで解説されているので、『大聖堂』の世界の追体験になった。
◎やはり史実を確認できた
『西ヨーロッパ世界の形成』は予想外の概説書だった。教科書的な史実の解説などほとんどない。読者が基本的な史実を把握していることを前提にした本のようだ。
社会史あるいは民衆史とも言える内容で、少々まごついたが、意外にこれが面白い。都市、農村、森、修道院などについてかなり細かく書かれている。付録の月報は著者二人と日本中世史の大家・網野善彦氏との座談会で、網野氏は「新しい中世史像を知ることができて大きな収穫がありました」と持ち上げている。
『大聖堂』『大聖堂・続編』には実在した国王や大司教も登場するが、主な登場人物は石工、羊毛商人、大工、機織り屋、農民、修道士、修道院長、托鉢修道士、司教、騎士、領主など多様は人々だ。また、主な舞台は修道院、その周辺の町、定期的に開催される市、森、農村などである。『西ヨーロッパ世界の形成』は、このような多様な人々や場所についてかなり詳しく記述している。
私は「縮絨(しゅくじゅう)」という言葉を『大聖堂』で初めて知った。毛織物を仕上げる工程の一つで、かなりの重労働だそうだ。小説では、主人公が縮絨を容易にするため水車を使う方法を「発明」するシーンがある。『西ヨーロッパ世界の形成』で、12世紀頃には水車が縮絨に使われるようになったとの記述に接し、虚実の遭遇に軽い感動を覚えた。また、『大聖堂・続編』では染色に工夫する印象的なシーンがあり、『西ヨーロッパ世界の形成』には、当時の染色職人や染色技術に関する興味深い記述がある。小説との暗合を感じた。
数えあげればきりがないが、『西ヨーロッパ世界の形成』には『大聖堂』『大聖堂・続編』の世界のディティールに関連した記述が多い。歴史上の人物などとは別次元で、小説世界に展開されたあれこれに史実の裏付けがあることを『西ヨーロッパ世界の形成』で確認できたのは想定外の収穫だった。つまりは、ケン・フォレットが最新(執筆当時)の歴史学や考古学の成果をふまえて小説を書いたことが確認できたのである。
猥雑妖艶な『毛皮のマリー』を観て歌舞伎を連想 ― 2016年04月09日
新国立劇場(中劇場)で『毛皮のマリー』(作・寺山修司、主演・美輪明宏)を観た。1967年初演の高名なこのアングラ芝居は、その後何度も再演されている。私は今回初めて観た。
半世紀近く昔の学生時代、私はアングラ芝居をかなり観たが、寺山修司主宰の『天井桟敷』の芝居は観ていない。当時の私には『天井桟敷』は<本当のアングラではない>と思えていた。寺山修司は私が高校生の頃から若き文学スターだった。だから、大学生になった頃には彼がすでに<権威>に見えていた。『天井桟敷』が『民芸』や『俳優座』と違うのは確かだが、アングラをウリにするうさんくささを感じていたのだ。
だから、『状況劇場』の役者たちが『天井桟敷』に殴りこんだ乱闘事件のニュースに接したとき、内心で快哉をあげた。後になって、唐十郎が寺山修司への敬意を表していることを知り「なんだかなあ~」という気にもなった。当時、寺山修司は30代前半、唐十郎は20代後半、みんな若かった。いまから思えば、そんな若造たちの世界に<権威>などを嗅ぎとるのは幼さのあらわれで、何も見えていなかったのだ。
その後も寺山修司の作品をきちんと読んだわけではないが、短歌や俳句などを読み返して才能を感じた。あの、煌めきに満ちた懐かしき1960年代を象徴する人物の一人が寺山修司だったのは間違いない。
そんな気分で今回の『毛皮のマリー』公演に行ったのだが、もちろん美輪明宏のバケモノめいた妖しさを観たいという動機もあった。1967年初演の『毛皮のマリー』は、寺山修司が役者・美輪明宏(当時は丸山明宏・32歳)を当て込んで書いた芝居だ。あの頃の丸山明宏はゾッとするほどに妖艶だった。『毛皮のマリー』は一応のストーリーはあるものの、丸山明宏の妖艶さに拠って猥雑な見世物小屋的異世界空間を紡ぎ出す仕掛けの、丸山明宏抜きでは成り立ち難い芝居である。
そんな芝居が、初演後約半世紀ものあいだ同じ主演俳優によって継続的に上演されてきたのは驚異である。この芝居の初演を新宿アートシアターで観た観客の中に、半世紀後に80歳を過ぎた丸山(美輪)明宏によって「国立」の立派な劇場でこの芝居が上演されると想像した人がいたとは思えない。
81歳になったはずの美輪明宏の妖艶な肢体に圧倒されつつ、1960年代の狂騒を彷彿させるサイケで猥雑な活人画のような舞台をノスタルジックな感慨で眺めながら、私は遠い昔から現代にまで継承されてきた歌舞伎を連想した。江戸時代の人が歌舞伎に接するときのカブいた気分を追体験したような気分になったのだ。
遠い将来、第○世美輪明宏と名乗る役者が歌舞伎座のような大舞台でこの猥雑な芝居を演じているかもしれない…などと妄想した。
半世紀近く昔の学生時代、私はアングラ芝居をかなり観たが、寺山修司主宰の『天井桟敷』の芝居は観ていない。当時の私には『天井桟敷』は<本当のアングラではない>と思えていた。寺山修司は私が高校生の頃から若き文学スターだった。だから、大学生になった頃には彼がすでに<権威>に見えていた。『天井桟敷』が『民芸』や『俳優座』と違うのは確かだが、アングラをウリにするうさんくささを感じていたのだ。
だから、『状況劇場』の役者たちが『天井桟敷』に殴りこんだ乱闘事件のニュースに接したとき、内心で快哉をあげた。後になって、唐十郎が寺山修司への敬意を表していることを知り「なんだかなあ~」という気にもなった。当時、寺山修司は30代前半、唐十郎は20代後半、みんな若かった。いまから思えば、そんな若造たちの世界に<権威>などを嗅ぎとるのは幼さのあらわれで、何も見えていなかったのだ。
その後も寺山修司の作品をきちんと読んだわけではないが、短歌や俳句などを読み返して才能を感じた。あの、煌めきに満ちた懐かしき1960年代を象徴する人物の一人が寺山修司だったのは間違いない。
そんな気分で今回の『毛皮のマリー』公演に行ったのだが、もちろん美輪明宏のバケモノめいた妖しさを観たいという動機もあった。1967年初演の『毛皮のマリー』は、寺山修司が役者・美輪明宏(当時は丸山明宏・32歳)を当て込んで書いた芝居だ。あの頃の丸山明宏はゾッとするほどに妖艶だった。『毛皮のマリー』は一応のストーリーはあるものの、丸山明宏の妖艶さに拠って猥雑な見世物小屋的異世界空間を紡ぎ出す仕掛けの、丸山明宏抜きでは成り立ち難い芝居である。
そんな芝居が、初演後約半世紀ものあいだ同じ主演俳優によって継続的に上演されてきたのは驚異である。この芝居の初演を新宿アートシアターで観た観客の中に、半世紀後に80歳を過ぎた丸山(美輪)明宏によって「国立」の立派な劇場でこの芝居が上演されると想像した人がいたとは思えない。
81歳になったはずの美輪明宏の妖艶な肢体に圧倒されつつ、1960年代の狂騒を彷彿させるサイケで猥雑な活人画のような舞台をノスタルジックな感慨で眺めながら、私は遠い昔から現代にまで継承されてきた歌舞伎を連想した。江戸時代の人が歌舞伎に接するときのカブいた気分を追体験したような気分になったのだ。
遠い将来、第○世美輪明宏と名乗る役者が歌舞伎座のような大舞台でこの猥雑な芝居を演じているかもしれない…などと妄想した。
辻邦生の『背教者ユリアヌス』を読んで60年代を想う ― 2016年04月10日
◎読み始めると面白くて一気読み
いずれ読もうと古書店で購入したまま書架に眠っていた『背教者ユリアヌス』(辻邦生/中央公論社)をついに読んだ。二重函入り二段組み720ページ(二千枚)の大著で、読み始めるには気合が必要だったが、導入部から物語の世界にひきずりこまれ、ほぼ一気に読み終えた。
この本を購入したのは5年前、塩野七生の『ローマ人の物語』(薄い文庫本で43冊)を読了した直後だった。読み始める機を逸し、その後、ギボンの『ローマ帝国衰亡史』に取りかかったので、辻邦生は後回しになった。
『背教者ユリアヌス』の刊行は1972年10月、連合赤軍あさま山荘事件や日本赤軍テルアビブ空港乱射事件があった年で、私の大学生活最後の年だった。その頃、この分厚い本を書店で手にしたが、購入しようとは思わなかった。古代ローマ史には暗くユリアヌスは未知の人だったし、辻邦生という理知的なイメージの作家にもさほどの関心はなかった。この直方体の箱のような本に接して「何とも浮き世離れした小説のようだなあ」との感慨を抱いた。
この小説が記憶に刻印されたのは「背教者」という異様な修飾語のせいである。このタイトルに接して以降、ユリアヌスは気がかりな人物の一人になった。そして、『ローマ人の物語』や『ローマ帝国衰亡史』を読んでからは、私にとってユリアヌスは「気がかりな人物」から「魅力的で興味深い人物」へ転換した。
◎哲学青年から皇帝になって夭折
ユリアヌスは数奇な運命をたどり、32歳で戦死したローマ皇帝である。キリスト教を公認したコンスタンティヌス大帝の甥として生まれ、幼少の頃に親族が粛清され、幽閉生活の中で成長する。ホメロスやプラトンなどを愛読する勉学好きの哲学青年で、政治への野心はなかった。しかし、はからずも副帝に任命されると、さほど期待されていなかった軍事的才覚を発揮、ついには皇帝にまで登りつめる。だが、在位1年半で夭折する。
当時のローマ帝国では公認のキリスト教が一大勢力となり、古来の多神教は廃れかけていた。ギリシア哲学の徒だったユリアヌスは、皇帝になるとローマ帝国古来の宗教の復活に着手する。キリスト教を弾圧したわけではなく、ワン・オブ・ゼムの宗教と見なし、キリスト教批判も展開する。それが「背教者(アポスタタ)」と呼ばれる所以だ。キリスト教から見た蔑称が今日に至るまでユリアヌスの修飾語になったのだ。
辻邦生の『背教者ユリアヌス』では、ユリアヌスは感性豊かな理性の人と描かれていて、キリスト教者の多くは頑迷で打算的で蒙昧な人々と描かれている。コンスタンティヌス大帝がキリスト教を公認した情況の中では、身すぎ世すぎでキリスト教に改宗した人も多かったし、皇帝権力に接近して権謀術数でキリスト教の勢力拡張を図る司教もいた。だから、小説とはいえ、辻邦生の見方は当時の宗教情況を巧みに描いているように私には思えた。キリスト教の信者には受け容れ難い見方かもしれないが…。
◎ギボンの見方
キリスト教徒だったギボンはユリアヌスをどう見ているか。18世紀の啓蒙家ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において辛辣なキリスト教批判を開陳している。刊行当時、蜂の巣をつついたような騒ぎを起こしたそうだ。そんなギボンだから、ユリアヌスの勇気、知能、努力を高く評価し、十分に魅力的に描いている。ただし、辻邦生の小説のように、ユリアヌスを理性の人、キリスト教者を蒙昧な人ととらえているのではない。ユリアヌスが古代の神々の復活に執心したことを妄想的信仰と見なして批判している。さすが、啓蒙思想の人である。
◎塩野七生の評価
排他的な一神教に批判的な塩野七生はユリアヌスをどう見ているか。『ローマ人の物語』でユリアヌスはかなり魅力的に描かれてはいるが、やや突き離しているような印象も受ける。反キリスト教「改革」の稚拙さに関して「ユリアヌスには、ローマ文明がわかっていたのかと疑ってしまう。」とも述べている。
しかし、ユリアヌスに関する章の末尾部分では以下のように評価している。
「ユリアヌスについて深くも考えていなかった頃の私は、この若き皇帝を、アナクロニズムの代表のように見ていたのである。(略)思慮の浅い人物だろうと思いこんでいたのだった。」「しかし、今はそのようには見ていない。それどころか、もしも彼の治世が、十九ヵ月ではなくて十九年であったとしたら、その後のローマ帝国はどうなっていたのだろう、と考えてしまうのである。」「宗教が現世をも支配することに反対の声をあげたユリアヌスは、古代ではおそらく唯一人、一神教のもたらす弊害に気づいた人ではなかったか、と思う。」
一神教のもたらす弊害は現代にいたるまで克服されず、21世紀になってますます顕在化している。そう考えると、『背教者ユリアヌス』はきわめて今日的な課題を秘めた小説に見えてくる。
◎やはり同時代小説
そんな感想を抱いて、この小説が刊行された1972年頃のことを思い起こすと、この小説に「何とも浮き世離れした小説のようだなあ」と感じたのは見当はずれだったと思えてくる。そんなノンキな小説ではなく、1960年代の狂騒と残照を反映した物語のように見えるのだ。ラストシーンは1960年代を見送る挽歌のようでもある。この小説の数年前に刊行された似たような長さの長編小説『邪宗門』(高橋和巳)に通底するものも感じる。
挫折した革命(世直し)物語ととらえるのは安易すぎるし、キリスト教にマルクス主義を重ねて見るのはうがちすぎだが、古代ローマの叙事詩に1960年代の空気がひそやかに流れているように感じてしまうのだ。
いずれ読もうと古書店で購入したまま書架に眠っていた『背教者ユリアヌス』(辻邦生/中央公論社)をついに読んだ。二重函入り二段組み720ページ(二千枚)の大著で、読み始めるには気合が必要だったが、導入部から物語の世界にひきずりこまれ、ほぼ一気に読み終えた。
この本を購入したのは5年前、塩野七生の『ローマ人の物語』(薄い文庫本で43冊)を読了した直後だった。読み始める機を逸し、その後、ギボンの『ローマ帝国衰亡史』に取りかかったので、辻邦生は後回しになった。
『背教者ユリアヌス』の刊行は1972年10月、連合赤軍あさま山荘事件や日本赤軍テルアビブ空港乱射事件があった年で、私の大学生活最後の年だった。その頃、この分厚い本を書店で手にしたが、購入しようとは思わなかった。古代ローマ史には暗くユリアヌスは未知の人だったし、辻邦生という理知的なイメージの作家にもさほどの関心はなかった。この直方体の箱のような本に接して「何とも浮き世離れした小説のようだなあ」との感慨を抱いた。
この小説が記憶に刻印されたのは「背教者」という異様な修飾語のせいである。このタイトルに接して以降、ユリアヌスは気がかりな人物の一人になった。そして、『ローマ人の物語』や『ローマ帝国衰亡史』を読んでからは、私にとってユリアヌスは「気がかりな人物」から「魅力的で興味深い人物」へ転換した。
◎哲学青年から皇帝になって夭折
ユリアヌスは数奇な運命をたどり、32歳で戦死したローマ皇帝である。キリスト教を公認したコンスタンティヌス大帝の甥として生まれ、幼少の頃に親族が粛清され、幽閉生活の中で成長する。ホメロスやプラトンなどを愛読する勉学好きの哲学青年で、政治への野心はなかった。しかし、はからずも副帝に任命されると、さほど期待されていなかった軍事的才覚を発揮、ついには皇帝にまで登りつめる。だが、在位1年半で夭折する。
当時のローマ帝国では公認のキリスト教が一大勢力となり、古来の多神教は廃れかけていた。ギリシア哲学の徒だったユリアヌスは、皇帝になるとローマ帝国古来の宗教の復活に着手する。キリスト教を弾圧したわけではなく、ワン・オブ・ゼムの宗教と見なし、キリスト教批判も展開する。それが「背教者(アポスタタ)」と呼ばれる所以だ。キリスト教から見た蔑称が今日に至るまでユリアヌスの修飾語になったのだ。
辻邦生の『背教者ユリアヌス』では、ユリアヌスは感性豊かな理性の人と描かれていて、キリスト教者の多くは頑迷で打算的で蒙昧な人々と描かれている。コンスタンティヌス大帝がキリスト教を公認した情況の中では、身すぎ世すぎでキリスト教に改宗した人も多かったし、皇帝権力に接近して権謀術数でキリスト教の勢力拡張を図る司教もいた。だから、小説とはいえ、辻邦生の見方は当時の宗教情況を巧みに描いているように私には思えた。キリスト教の信者には受け容れ難い見方かもしれないが…。
◎ギボンの見方
キリスト教徒だったギボンはユリアヌスをどう見ているか。18世紀の啓蒙家ギボンは『ローマ帝国衰亡史』において辛辣なキリスト教批判を開陳している。刊行当時、蜂の巣をつついたような騒ぎを起こしたそうだ。そんなギボンだから、ユリアヌスの勇気、知能、努力を高く評価し、十分に魅力的に描いている。ただし、辻邦生の小説のように、ユリアヌスを理性の人、キリスト教者を蒙昧な人ととらえているのではない。ユリアヌスが古代の神々の復活に執心したことを妄想的信仰と見なして批判している。さすが、啓蒙思想の人である。
◎塩野七生の評価
排他的な一神教に批判的な塩野七生はユリアヌスをどう見ているか。『ローマ人の物語』でユリアヌスはかなり魅力的に描かれてはいるが、やや突き離しているような印象も受ける。反キリスト教「改革」の稚拙さに関して「ユリアヌスには、ローマ文明がわかっていたのかと疑ってしまう。」とも述べている。
しかし、ユリアヌスに関する章の末尾部分では以下のように評価している。
「ユリアヌスについて深くも考えていなかった頃の私は、この若き皇帝を、アナクロニズムの代表のように見ていたのである。(略)思慮の浅い人物だろうと思いこんでいたのだった。」「しかし、今はそのようには見ていない。それどころか、もしも彼の治世が、十九ヵ月ではなくて十九年であったとしたら、その後のローマ帝国はどうなっていたのだろう、と考えてしまうのである。」「宗教が現世をも支配することに反対の声をあげたユリアヌスは、古代ではおそらく唯一人、一神教のもたらす弊害に気づいた人ではなかったか、と思う。」
一神教のもたらす弊害は現代にいたるまで克服されず、21世紀になってますます顕在化している。そう考えると、『背教者ユリアヌス』はきわめて今日的な課題を秘めた小説に見えてくる。
◎やはり同時代小説
そんな感想を抱いて、この小説が刊行された1972年頃のことを思い起こすと、この小説に「何とも浮き世離れした小説のようだなあ」と感じたのは見当はずれだったと思えてくる。そんなノンキな小説ではなく、1960年代の狂騒と残照を反映した物語のように見えるのだ。ラストシーンは1960年代を見送る挽歌のようでもある。この小説の数年前に刊行された似たような長さの長編小説『邪宗門』(高橋和巳)に通底するものも感じる。
挫折した革命(世直し)物語ととらえるのは安易すぎるし、キリスト教にマルクス主義を重ねて見るのはうがちすぎだが、古代ローマの叙事詩に1960年代の空気がひそやかに流れているように感じてしまうのだ。
久々の畑仕事 ― 2016年04月26日
4月22日から24日まで八ヶ岳南麓の山小屋で農作業をしてきた。久々に行ったので、畑には雑草がかなり生えてきていて、その除去作業が大変だった。
昨年はジャガイモがイノシシに掘り返され、トウモロコシはハクビシンに齧られた。これら動物被害への適切な対策も思いつかぬまま、昨年と同じような野菜作りをすることにした。無為無策の成り行きまかせだ。
今回の農作業では、ジガイモを植え付け、インゲンとトウモトシは半分だけ(それぞれ1畝ずつ)種を植えた。残りの半分は5月上旬に植える予定だ。その方が長い期間にわたって収穫できると考えたからである。
昨年ジガイモを植えたのは4月上旬だったが、今年はウカウカしていて植え付ける時期が少し遅くなった。寒冷地だから問題はないと思う。連作障害を避けるため、ジャガイモの植え付け場所は山小屋側にした。昨年は山小屋から遠いフェンス側に植えたジャガイモがイノシシにやられた。今年は山小屋側なのでイノシシが遠慮してくれるのではないかと、根拠の薄い期待を抱いている。
昨年はジャガイモがイノシシに掘り返され、トウモロコシはハクビシンに齧られた。これら動物被害への適切な対策も思いつかぬまま、昨年と同じような野菜作りをすることにした。無為無策の成り行きまかせだ。
今回の農作業では、ジガイモを植え付け、インゲンとトウモトシは半分だけ(それぞれ1畝ずつ)種を植えた。残りの半分は5月上旬に植える予定だ。その方が長い期間にわたって収穫できると考えたからである。
昨年ジガイモを植えたのは4月上旬だったが、今年はウカウカしていて植え付ける時期が少し遅くなった。寒冷地だから問題はないと思う。連作障害を避けるため、ジャガイモの植え付け場所は山小屋側にした。昨年は山小屋から遠いフェンス側に植えたジャガイモがイノシシにやられた。今年は山小屋側なのでイノシシが遠慮してくれるのではないかと、根拠の薄い期待を抱いている。
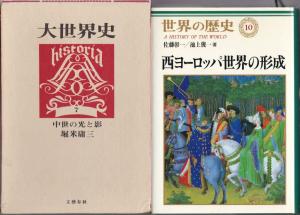



最近のコメント