『ライ王のテラス』を観て三島由紀夫自決をあらためて考えた ― 2016年03月09日
◎『癩王のテラス』から『ライ王のテラス』へ
三島由紀夫の最後の戯曲『癩王のテラス』が、宮本亜門演出『ライ王のテラス』としてで上演されると知ったのは数カ月前で、早速チケットを予約し、昨日赤坂ACTシアターでの公演を観た。
この芝居の初演は1969年7月(帝国劇場)で、三島由紀夫自決のおよそ1年前、主演は北大路欣也(当時26歳)だった。当時、私は大学生で芝居に関心があったが、観るのはアングラが主でこの初演は観ていない。だが、劇評などの印象は残っていて、観てもいないのに、いまだに北大路欣也というと『癩王のテラス』を連想してしまう。こんなに印象深いのは「癩王のテラス」という異様なタイトルのせいだ。
7年前、アンコール・ワット観光に行ったとき「癩王のテラス」という遺跡に遭遇し、それが現存していることに少し驚いた。三島由紀夫がアンコール・トムのバイヨン寺院遺跡に着想を得て書いたという戯曲『癩王のテラス』を私が読んだのは、遺跡「癩王のテラス」を観た後である。
◎三島由紀夫の自決に考えがおよんでしまう
そして今回、ついに『ライ王のテラス』の舞台を観ることができた。三島由紀夫らしい華麗な舞台を観ながら、つい考えてしまう。この戯曲を書いたとき、三島由紀夫は自決を決意していたのだろうかと。戯曲の脱稿は自決の1年前であり、戯曲の内容から推測しても自決を決意していたように思える。しかし、アンコール・トムで着想を得たのは自決の5年前であり、そのときから自決を決意していたとは思えない。着想から脱稿までの4年間に、戯曲の形が固まっていくのと並行して自決の意志も固まり、あの演劇的自決劇の構想が浮かび上がってきたのではないだろうか。
本来、作家の残した作品はその内容において評価されるものであり、作家の死に方とは無関係なはずだが、なかなかそうは行かない。三島由紀夫は「成功した自殺を演出した」という点だけでも希有な人だった。『ライ王のテラス』のラストでは突然に王の精神と肉体が分裂して論争を始める。この異様なラストシーンには1970年11月25日の自決が色濃く反映されているとしか見えない。精神の蒙昧を排除して肉体を生かすには肉体を殺すしかない --- それが青春のパラドックスだ、というわかりにくい論理は、三島由紀夫自決のわかりにくさを反映している。
◎奇妙な暗合
芝居の本筋とは関係ないが、今回の観劇で私個人は不思議な感覚に襲われた。先日読んだケン・フォレットの大長編エンタメ小説『大聖堂』『大聖堂 ― 果てしなき世界)』との暗合に驚いたのだ。『ライ王のテラス』はバイヨン寺院建設という壮大な事業と王の癩病の進行という病魔の蔓延を対比させた舞台である。ケン・フォレットの小説は正編が大聖堂建設、続編がペスト蔓延を基調にした物語である。たまたま私が直近に読んだ小説と直近に観た芝居の間に「寺院建設」「病魔の蔓延」という共通部分があることに気づき、世界の狭さを感じてしまったのだ。
寺院建設や病魔蔓延などは、どこにでもころがっている珍しくもないテーマということなのだろうか。あるいは、作家や読者がいやおうなしに引き寄せられてしまう普遍的モチーフなのだろうか。
三島由紀夫の最後の戯曲『癩王のテラス』が、宮本亜門演出『ライ王のテラス』としてで上演されると知ったのは数カ月前で、早速チケットを予約し、昨日赤坂ACTシアターでの公演を観た。
この芝居の初演は1969年7月(帝国劇場)で、三島由紀夫自決のおよそ1年前、主演は北大路欣也(当時26歳)だった。当時、私は大学生で芝居に関心があったが、観るのはアングラが主でこの初演は観ていない。だが、劇評などの印象は残っていて、観てもいないのに、いまだに北大路欣也というと『癩王のテラス』を連想してしまう。こんなに印象深いのは「癩王のテラス」という異様なタイトルのせいだ。
7年前、アンコール・ワット観光に行ったとき「癩王のテラス」という遺跡に遭遇し、それが現存していることに少し驚いた。三島由紀夫がアンコール・トムのバイヨン寺院遺跡に着想を得て書いたという戯曲『癩王のテラス』を私が読んだのは、遺跡「癩王のテラス」を観た後である。
◎三島由紀夫の自決に考えがおよんでしまう
そして今回、ついに『ライ王のテラス』の舞台を観ることができた。三島由紀夫らしい華麗な舞台を観ながら、つい考えてしまう。この戯曲を書いたとき、三島由紀夫は自決を決意していたのだろうかと。戯曲の脱稿は自決の1年前であり、戯曲の内容から推測しても自決を決意していたように思える。しかし、アンコール・トムで着想を得たのは自決の5年前であり、そのときから自決を決意していたとは思えない。着想から脱稿までの4年間に、戯曲の形が固まっていくのと並行して自決の意志も固まり、あの演劇的自決劇の構想が浮かび上がってきたのではないだろうか。
本来、作家の残した作品はその内容において評価されるものであり、作家の死に方とは無関係なはずだが、なかなかそうは行かない。三島由紀夫は「成功した自殺を演出した」という点だけでも希有な人だった。『ライ王のテラス』のラストでは突然に王の精神と肉体が分裂して論争を始める。この異様なラストシーンには1970年11月25日の自決が色濃く反映されているとしか見えない。精神の蒙昧を排除して肉体を生かすには肉体を殺すしかない --- それが青春のパラドックスだ、というわかりにくい論理は、三島由紀夫自決のわかりにくさを反映している。
◎奇妙な暗合
芝居の本筋とは関係ないが、今回の観劇で私個人は不思議な感覚に襲われた。先日読んだケン・フォレットの大長編エンタメ小説『大聖堂』『大聖堂 ― 果てしなき世界)』との暗合に驚いたのだ。『ライ王のテラス』はバイヨン寺院建設という壮大な事業と王の癩病の進行という病魔の蔓延を対比させた舞台である。ケン・フォレットの小説は正編が大聖堂建設、続編がペスト蔓延を基調にした物語である。たまたま私が直近に読んだ小説と直近に観た芝居の間に「寺院建設」「病魔の蔓延」という共通部分があることに気づき、世界の狭さを感じてしまったのだ。
寺院建設や病魔蔓延などは、どこにでもころがっている珍しくもないテーマということなのだろうか。あるいは、作家や読者がいやおうなしに引き寄せられてしまう普遍的モチーフなのだろうか。
『岩波講座日本歴史』最終巻(2016.2発行)には「トランプ現象」も出てくる ― 2016年03月24日
『岩波講座 日本歴史』全22巻が先月完結し、最終巻の『第22巻 歴史学の現在』が手元に届いた。私は学問の世界とは縁のない人間で、特に史学に関心があるわけでもない。だが、晩年の消閑の具になるかとの衝動的短慮で、置き場所も考えずに全巻予約したのだ。
これまでに届いた二十数巻はパラパラとめくってみただけで、まともに読んだ論文はない。ところが、最終巻『歴史学の現在』をパラパラとめくっていると急に興味が湧いてきた。「トランプ現象」などの言葉が目に飛び込み同時代性に驚いたのだ。ページをめくる速度が遅くなり、知らない業界の内部事情をのぞき見しているようなミーハー気分が刺激された。そして、この最終巻だけは通読してしまった。
『第22巻 歴史学の現在』には12編の論文が収録されている。だが、その中の2編は『第21巻 史料論』に収録されるべきものが最終巻に掲載されたものだった。それに気づかずに読み進めてシュールな違和感を抱いた私は愚かだった。「歴史学の現在」のテーマに沿って書かれた論文は次の10編だ。
1 文明史からみた日本史:福沢諭吉『文明論之概略』を超えて 宮嶋博史
2 東アジア世界論と日本史 李成市
3 近世論から見たグローバルヒストリー 永井和
4 植民地と歴史学 吉井秀夫
5 マルクス主義と戦後日本史学 戸邉秀明
6 社会史の成果と課題 山本幸司
7 女性史/ジェンダー史:近現代日本の領域を軸に 成田龍一
8 国民国家論と「日本史」 今西一
9 国境を越える歴史認識:比較史の発見的効用 三谷博
10 教科書訴訟・教科書問題と現代歴史学 大串潤児
本書の序論によれば、日本史の岩波講座の刊行は20年ぶりで、この20年間の日本史研究で主題として顕在化してきた問題群から10の論点を選び出したそうだ。
私は門外漢だから、この20年はおろか歴史学が発生してから今日まで歴史学者たちが何をテーマに研究を進めてきたかを知らない。本書の筆者たちについても知らないし、それらの論文で引用されている学者たちの大半も知らない人たちだ。しかし、この10編の論文を興味深く読むことができた。十分に理解して読んだとは言い難いが、現代の歴史学者たちが抱えている課題を垣間見たように思えた。
この10編の中で、特に興味深かったのは「マルクス主義と戦後日本史学」「社会史の成果と課題」「国民国家論と「日本史」」の3編だ。歴史を発展段階の過程と見る唯物史観が一世を風靡したことは私も分かっているが、その魅力が色褪せた現在、「史観」はどういうことになっているのかはよく分からない。これらの論文を読んで、過去の経緯と現状は何となく分かった。いろいろ大変だなあということは見えてきたが、すっきりとした見通しが得られたわけではない。
ただし、「国民国家」という概念を初めて知り、その刺激性に関心がわいた。「国民は解放の観念であると同時に抑圧の観念である」「国民はのり越えられるべき歴史的概念である」(西川長夫)などの引用に惹かれ、少し勉強してみたくなった。
『歴史学の現在』を通読して得た印象は、学者たちの苛立ちである。たとえば「歴史意識の変貌を前にして、すべての歴史的想像力は等価であるとうたうならば、既成のイデオロギーへの従属に過ぎない」(戸邉秀明)、「現代は「保守革命」の時代である」(今西一)、「九〇年代以降の、歴史の「相対主義」にどのようにむきあうのか」(大串潤児)といったフレーズにそれは反映されている。「歴史学の現在」ではなく「史料論」のテーマで書かれた論文にも「人文社会系の学問が軽視され、古典研究の未来に暗雲が漂い、その学問の継承に危機が迫る現在(…)」といった表現がある。
この苛立ちが「歴史学の現在」のように思える。
これまでに届いた二十数巻はパラパラとめくってみただけで、まともに読んだ論文はない。ところが、最終巻『歴史学の現在』をパラパラとめくっていると急に興味が湧いてきた。「トランプ現象」などの言葉が目に飛び込み同時代性に驚いたのだ。ページをめくる速度が遅くなり、知らない業界の内部事情をのぞき見しているようなミーハー気分が刺激された。そして、この最終巻だけは通読してしまった。
『第22巻 歴史学の現在』には12編の論文が収録されている。だが、その中の2編は『第21巻 史料論』に収録されるべきものが最終巻に掲載されたものだった。それに気づかずに読み進めてシュールな違和感を抱いた私は愚かだった。「歴史学の現在」のテーマに沿って書かれた論文は次の10編だ。
1 文明史からみた日本史:福沢諭吉『文明論之概略』を超えて 宮嶋博史
2 東アジア世界論と日本史 李成市
3 近世論から見たグローバルヒストリー 永井和
4 植民地と歴史学 吉井秀夫
5 マルクス主義と戦後日本史学 戸邉秀明
6 社会史の成果と課題 山本幸司
7 女性史/ジェンダー史:近現代日本の領域を軸に 成田龍一
8 国民国家論と「日本史」 今西一
9 国境を越える歴史認識:比較史の発見的効用 三谷博
10 教科書訴訟・教科書問題と現代歴史学 大串潤児
本書の序論によれば、日本史の岩波講座の刊行は20年ぶりで、この20年間の日本史研究で主題として顕在化してきた問題群から10の論点を選び出したそうだ。
私は門外漢だから、この20年はおろか歴史学が発生してから今日まで歴史学者たちが何をテーマに研究を進めてきたかを知らない。本書の筆者たちについても知らないし、それらの論文で引用されている学者たちの大半も知らない人たちだ。しかし、この10編の論文を興味深く読むことができた。十分に理解して読んだとは言い難いが、現代の歴史学者たちが抱えている課題を垣間見たように思えた。
この10編の中で、特に興味深かったのは「マルクス主義と戦後日本史学」「社会史の成果と課題」「国民国家論と「日本史」」の3編だ。歴史を発展段階の過程と見る唯物史観が一世を風靡したことは私も分かっているが、その魅力が色褪せた現在、「史観」はどういうことになっているのかはよく分からない。これらの論文を読んで、過去の経緯と現状は何となく分かった。いろいろ大変だなあということは見えてきたが、すっきりとした見通しが得られたわけではない。
ただし、「国民国家」という概念を初めて知り、その刺激性に関心がわいた。「国民は解放の観念であると同時に抑圧の観念である」「国民はのり越えられるべき歴史的概念である」(西川長夫)などの引用に惹かれ、少し勉強してみたくなった。
『歴史学の現在』を通読して得た印象は、学者たちの苛立ちである。たとえば「歴史意識の変貌を前にして、すべての歴史的想像力は等価であるとうたうならば、既成のイデオロギーへの従属に過ぎない」(戸邉秀明)、「現代は「保守革命」の時代である」(今西一)、「九〇年代以降の、歴史の「相対主義」にどのようにむきあうのか」(大串潤児)といったフレーズにそれは反映されている。「歴史学の現在」ではなく「史料論」のテーマで書かれた論文にも「人文社会系の学問が軽視され、古典研究の未来に暗雲が漂い、その学問の継承に危機が迫る現在(…)」といった表現がある。
この苛立ちが「歴史学の現在」のように思える。

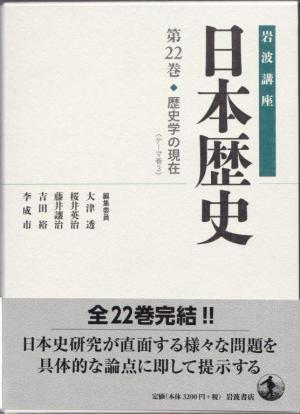
最近のコメント